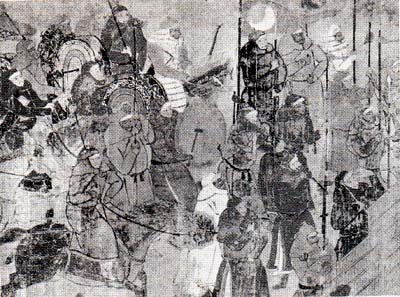|
****************************************
Index その一 その二 その三
二 蒙古襲来と北条時宗(その二)
五 日蓮の高笑い
1 おそろしいモンゴルの皇帝
2 モンゴル使者趙良弼
3 奇跡をよぶ日蓮
六 元軍の侵略はいつ?
1 御家人竹畸五郎の仕事
2 モンゴルから「元」へ
3 朝鮮の山は赤はだか |
七 文永の役−博多の浜の決戦
1 日蓮、鎌倉を去る
2 元、ついに、対馬をせめる
3 五郎季長の出陣
4 日本軍の苦戦
5 季長、先陣
6 海から消えた元軍
7 写経する時宗 |
五 日蓮の高笑い top
1 恐ろしいモンゴルの皇帝
文永六(一二六九)年。
時宗は、供を一人つれて、巨福呂(こぶくろ)坂(鎌倉市雪ノ下)をのぼっていった。坂の上には建長寺がある。
建長寺は、いまはなき父の時頼が、宋の国から渡来した蘭渓道隆(らんけいどうゆう)をむかえるため、三年の年月をついやしてたてた禅寺である。
時宗は、建長寺の前をとおり、そのさきの最明寺(さいみょうじ)の山門(寺の門)をくぐった。
最明寺は、父時頼が執権職をしりぞいたあと、僧となってこもった寺である。
本堂で、時宗は座禅をくんだ。
――上に立つ者に迷いがあってはいけない。こうだと思ったときには、ただちに実行しなければならない。
それだからこそ座禅をくみ、心の迷いをはらおうとする。
しかし、時宗はそれでも迷わずにはいられない。
――モンゴルは攻めて来るだろうか。
――せめてきたとき、日本の力でこれをよく防げるであろうか。
――父上、父上だったらどうなさいますか。
最明寺での座禅がおわると、建長寺の蘭渓道隆をたずねた。
「禅師、そもそもモンゴルの皇帝、フビライとは、どのような男なのですか。」
「わが宋の国をほろぼしつつある敵の大将ですが、その祖、チンギス・ハンゆずりの英傑であります。」
「して、モンゴルの戦いの仕方は?」
「モンゴル兵は小がらではありますが、脚の強い馬にのって強い弓を引きます。」
「鎌倉武士によくにていますな。」
「ちがうのは、馬の数が多いことです。一人の兵が、五、六頭の馬をもち、水、食料、衣類、武器を充分に用意しているので、遠くまで攻め込むことができます。」
道隆は、さらに説明をつづける。
「フビライは、西のトルコやペルシア(イラン)ともまじわっています。
そうしてよその国の宗教を取入れるなど、心の広い一面もありますが、やはり恐ろしい王です。
たとえば城をせめるにあたって、一日さからえば人民の三分の一を、二日さからえば二分の一を、三日さからえば全部ころす、というやりかたです。」
「しかし、禅師のお国は、唐の昔から、すぐれた文明をもった国でしだのに、どうして異国の蛮族(ばんぞく=文明のひらけていない種族)などにほろぼされたのでしょうか。」
「それは、政治を行う者の決断がなかったからです。
それで、意見が三つにも四つにもわれて、一つにまとまらないうちに、攻め込まれたからです。」
「ううむ……。」
「時宗どの、本当の敵は、敵ではなく味方です。一つにならない味方は、敵よりも恐ろしいのです。」
「ては、一つにするのにはどうすれば……。」
「上に立つ者の決断がかんじんです。」
と、このとき、山門をくぐりぬけて走ってきた数騎の武者がいた。時宗の弟宗政たちであった。
宗政が、兄の前にひざまずいていった。
「モンゴルの使者が、再び対馬(つしま=長崎県北西部の島)をおとずれたとのことにございます。
たったいま、大宰府より使者が到着いたしました。」
時宗は、ただちに政所にもどった。
大宰府の使者の知らせは、つぎのようなものであった。
訪れだのは、モンゴル皇帝フビライにつかえる黒的(こくてき)という武将で、七十人余りの部下をつれてきたという。
黒的は、対馬の守護代(しゅごだい=御家人を統率する役職の代官)宗助国(そうすけくに)に申入れた。
「去年、高麗の使者をとおしてさしあげた、わが皇帝の手紙にたいする、日本の返事をもらいにきた。
ただちに我々を、大宰府につれていきなさい。」 |

二度の元寇(げんこう=蒙古襲来)にあった対馬(つしま)
|
宗助国は、年をとってはいたが、すでに鎌倉幕府の決定を知っていた。
「お断わりする。無礼な手紙には返事をしないのが、この国のやりかたなのだ。」
しかし黒的は、船のいかりをおろしたまま、たちさらなかった。
半月たっても返事をもらえないのに怒った黒的は、対馬の漁民、塔二郎、弥三郎の二人を捕えて、モンゴルにつれさっていったが、これは、二人に、モンゴルの国が、いかに栄えているかをみせつけるためであった。
九月になると、この二人はモンゴルと高麗の使者におくられて対馬へ帰された。
「話にきく極楽とは、あのようなところをいうのでしょうか。」
と、二人は宗助国に、モンゴルのようすを話した。
こうして、モンゴルと高麗の使者は、モンゴル皇帝フビライの二度めの手紙をもって大宰府にきたのだった。
しかし時宗は、このたびも、返事を出す必要はない、ときっぱりいった。
2 モンゴル使者趙良弼 top
翌年の文永七(一二七〇)年。
なぜか、モンゴルの使者はこなかった。
「フビライは、あきらめたのかもしれませんな。」
いまは連署(れんしょ=執権をたすける役職)として時宗をたすける政村がいった。
「いや、まだわかりません。もし本気でせめる気なら、たくさんの船がいります。
あるいはその準備をしているのかもしれません。」
中国から渡来してきた人々の話によって、時宗はモンゴル軍の中心は騎兵であることを知っていた。
とすると、たくさんの馬を運ぶためにも想像をこえる数の船がいるはずだ。
時宗は、九州沿岸の武士たちにたいし、合戦の準備、絶対におこたりのないようにと、厳しく命じさせた。
はたして、翌文永八(一二七一)年の九月、またまたモンゴル船が九州に姿をみせた。
船は対馬によらずに、大宰府にいくつもりとみえて、博多に近い今津(福岡県福岡市西区)の浜に船をつけた。
百人をこえる人々をつれた使者であり、その長は、フビライに長年つかえている趙良弼(ちょうりょうひつ)という外交にだけだ男であった。
趙(ちょう)は、大宰府(だざいふ)を守る鎮西(ちんぜい)奉行の少弐資能(しょうにすけよし)にいった。
「二度まで国書をさしあげたのに返事がない。このうえは、私がみずから京へのぼって朝廷に国書を渡します。」
「それは困る。はじめの国書が届いたとき、わが国の態度はきまったのです。」
「それはおかしい。あなたは、みかど(天皇)でも、大臣でもないのに、どうしてそんなことがいえるのか。」
「すべては、この国の政治をあずかる鎌倉幕府の命令てござる。」
「とにかく、私がきたことを、鎌倉と京へお知らせください。」
こんな押し問答がいく日かつづいたが、結局、趙良弼は船に引上げていった。
3 奇跡をよぶ日蓮 top
同じころ、鎌倉では、日蓮の辻説法が、いよいよ激しくなっていった。
「よいか、みなの衆。この日蓮には、よく見えるのじゃ。
いま、執権時宗さまのお父ぎみ最明寺入道時頼さまや、そのご一族の極楽寺入道重時さまのお二人が……。」
といって、日蓮は鎌倉山のかなたを指さした。
「……お二人が、地獄で苦しんでおられるのだ。
それというのも、生前、この日蓮の言葉をお取上げにならず、禅宗をひいきになされたからじゃ。」
役人からこの言葉を聞いて、さすがに心の広い時宗も怒った。
それでも時宗は、自分自身でたしかめようと、日蓮を捕えさせた。
だが、日蓮はひるまなかった。
「確かに申上げました。正しい教えに耳を傾けない者はかならず、み仏の罰をうけるのです。」
「ては、おまえのいうことが、どうしてこの世でただ一つ正しいといいきれるのだ。」
すると日蓮は、黒く太いまゆを、ぴくっとさせていった。
「お疑いなら、ほかの宗派の人たちと、この場において論争してみせましょう。
さ、すぐここへおよびください。」
「そのようなかっては許されぬ。」
「それならば、私を島流しにするなり、打ち首にされるがよい。
さすれば、たちどころに大きなわざわいが、この国にふりかかってくるでありましょう。
いや、すでに海のむこうから、モンゴルが攻め寄せようとしておりますぞ。」
時宗は、いよいよ決断しなければならなくなった。
日蓮をこのまま野ばなしにしておいたら、人々の心は不安になるだけであり、宗教の世界は混乱し、争いが生ずるであろう。
ただちに評定衆が集り話しあったすえ、ついに死刑ときまった。
九月十二日、日蓮は捕えられ、その夜、ひそかに松明をかざした数人の役人が、日蓮をひきたてて鎌倉幕府の門を出た。
やがて、日蓮は竜の口(神奈川県藤沢市片瀬)につくられた刑場にすわらされた。 |

国難をとく日蓮
|

日蓮が奇蹟を呼んだ竜の口刑場あと
|
「これより執権(しっけん)どのの命令により、首をはねる。」
と、さきほどまで明るい月夜だと思っていたのに、いつのまにかすっかり雲にかくされていた。
そうして、ピューと黒い風がふいてきて、武士たちの手にした松明の火が消えそうになった。
「あ、いけない!」
あわてて風をさえぎろうとしたとき、ポツリ! ポツリ! と大粒の雨がおちてきた。
と思うと、ザアッーと大雨になり、たちまち松明の火が消えた。
ゴロ、ゴロー ピカッー
稲妻とともに、激しく雷の落ちる音がとどろいた。
火が消えたうえに、ひどい吹き降り、しかも、激しい雷光で、これでは日蓮の首をはねるどころではなくなってきた。
「やむをえぬ。中止じゃ。おのおの、引きかえせ。」
役人のかしらがいった。
すると、まっ暗やみの中から、
「はっはっはっはっ……。」と、高笑いがとどろいた。
「はっはっはっはっ……おのおの、おわかりか!
この日蓮を罰しようものなら、天は、このように怒りたまうぞよ。はっはっはっはっ……。」
日蓮の笑い声は、鎌倉のやみ夜に、高くぶきみにこだましていった。
六 元軍の侵略はいつ? top
1 御家人竹崎五郎の仕事
文永九二二七三年。
阿蘇の山が、秋空に、美しい紫の山はだをみせていた。
ふもとの竹崎五郎季長の家からは、
トンカラ、トントン! トンカラ……。
布をおる「おさ」の音がきこえてくる。
その庭先の柿の木に、二人の子供がのぼって、赤くうれはじめた実を、もぎとろうとしていた。
「あっ! 父上じゃ。」
上の枝にのっていた兄の熊丸が、川のむこうの道を指さしてさけんだ。
すると、下の枝にのぼっていた妹も、
「ち、ち、う、えー。」
と叫んで、片手をふった。
「これ、手をはなしたら、あぶないぞよ。」
下の畑で、そばをかっていた作人の弥二郎が、子供たちをしかったが、自分も、鎌(かま)をおいて道に出ていった。
家の中の、トントン! トンカラ……、と、布をおっていた音もやんで、長い髪を結んで後ろにたらしていた五郎の妻小菊も庭におりたった。そのふところに、この春生まれた赤子が抱かれている。
小菊は熊丸の声で、夫が帰ってきたのだと知ると、小(こ)しばがき(雑木でつくった垣根)の門をあけて外へ出た。
博多へつづく道のかなたに騎馬武者のかげが見える。竹崎五郎季長だ。
五郎は、わが家のほとりで手をふる家族の姿に気づいたのだろうか。むちをふって馬を走らせた。
妻や子にむかえられた五郎は、馬の手綱を弥二郎にわたすと、妻の手から乳のみ子をだきとって家の中にはいった。
三間しかないおくの間には、病気の母かふせていた。
「母上、大宰府より、ただいま戻ってまいりました。」
「お役目ごくろうさまでした。どうですか、ムクリ(当時のモンゴルの日本での呼び方)が押し寄せてくる気配は……。」
「はい、いまのところ、そのきざしはありませぬが、油断なく一同つとめております。」
鎌倉幕府は、九州の御家人たちに命じて、一月交代で、筑前(ちくぜん=福岡県北部)と肥前(ひぜん=佐賀県・長崎県)の沿岸のそなえをかためさせていた。これを異国警固番役(いこくけいごばんやく)といった。
竹崎五郎季長も、先月からこの役にふりあてられて、大宰府につめていたのであった。
母に挨拶すると、五郎は狩衣(かりぎぬ=鎌倉時代の武士の礼服)をぬぎすてて、まつわりつく子供たちをあやしながら、野良着にかえて庭に出た。
「今夜は月夜だな。」
農具小屋から、稲刈りがまをとりだして弥二郎にいった。
背戸(せど=裏口)の先には、竹崎家の田がひろがっている。
稲の穂がすっかり黄ばんでいるし、よい天気もつづきそうなので刈り取りにはいい日だ。
「お役目からお帰りのきょう一日くらいはお休みなされませ。」
と、弥二郎がいったが、五郎は首をふった。
「いやいや、明日にもムクリが押し寄せてこないともかぎらぬ。
そうなればただちに出陣で、稲刈りどころではなくなる。仕事は、できるときにやっておかねばのう。」
「それはそうですが……。」
「それに、今夜は月が出そうじゃ。夜刈りをしようぞ。おまえばかりを働かせているわけにはいかん。」
「何を水くさいことをおおせられます。」
主従は、いたわりあいながら、背戸の稲田におりていった。
「ちょっと気がかりなことは……。」
と、弥二郎がいいよどんだ。
「この冬のかいばがたりぬか?」
「おさっしのとおりで……。」
かいばとは馬のえさとなる草である。
夏のうちにたくさん刈り取り、ほしておいて冬にそなえるのだが、竹崎家の草かり場は少ないので、どうしても、二頭の馬のかいばにはたりない。
もともと、竹崎家ほどのまずしい武士が、二頭の馬をかっているのは贅沢、といわれてもしかたがないところなのだ。
しかし、竹崎家は代々武勇のほまれ高く、食うものは食わなくても、馬、弓矢の用にはことかかさないようにしていた。
その夜は、月明かりをたよりにして、すっかり二枚の田の稲刈りをすませた。
家にかえると、五郎にはもう一つ日課がまっている。
裏山の神社にかけのぼって、大くすのきに、百、二百、三百と木太刀を打ちこむのだ。
2 モンゴルから「元」 へ top
つぎの日、姉のむこの三井資長がたずねてきた。
「異国警固番役のつとめ、ごくろうでござった。」
と、資長は、みやげの米一袋と、子供たちへは柿を渡しながらいった。
「五郎どの、その後、ムクリのようすはいかがか?」
「海の上は、いまのところ、かわったことはござらぬが。」
「脅しだけで、本当に攻めて来る気はないのじゃろう。」
「いえいえ、私にはそうは思えませぬ。」
モンゴル軍がいつくるか、いつくるかで、もう四年もたっている。
いまでは、九州の国々の親が、子をしかるときに、
「はやくねないと、ムクリがきて連れていってしまうよ。」という言葉まで、はやったほどであった。
一年前の一二七一年、モンゴルは国名を“元(げん)”とあらためた。
元という字は人間の首を表わす文字で、すべてのもののなかで一番、上のもの、大事なものという意味である。 |

ペルシア(イラン)を攻めるモンゴル軍(左)
|
その年、モンゴルから趙良弼という使者がきて返事をするよううながした。
しかし、執権時宗の決心はかわらない。
趙良弼はいったん帰国したが、今年、またやってきた。
趙良弼は、モンゴル政府につかえる、地位のある外交官だ。
趙はまだまだ国書を鎌倉へ届けるように大宰府に申入れた。
しかし、趙は、鎌倉からの返事などまるであてにしていないかのように、大宰府の近くの町や浜を毎日ぶらぶら歩きまわっていたという。
「たまたま、わたしの警固役の日、その男の見はりを命ぜられました。」
「何か、おかしなことでも……。」
「いや、楽しそうに異国の海辺を歩く、といったようすではありましたが、よくよく気をつけてみると、歩く歩幅が同じなのです。
これは、地形や距離をはかっているにちがいないと思いました。」
「油断のならぬやつめよ。」
「やがて、鎌倉からの返事がとどきました。返書ではなく、ただちに国外退去させよと、鎮西奉行とのへの命令でした。」
「それで、趙良弼(ちょうりょうひつ)とやらは、あきらめたか。」
「ところが、かぜをひいているの、せっかくだから美しい日本の風景を見ておこう、などと申して、一日のばしにのばしています。」
やっと子をねつかせた妻の小菊も炉ばたにすわった。
「ムクリは攻めては、とつくに(外国)の家を焼き、女、子供でも容赦なく殺してしまうとか……。」
この阿蘇の山すそにも、大宰府あたりのうわさがはいってくるので、女、子供が恐がるのもむりはなかった。
3 朝鮮の山は赤はだか top
趙良弼(ちょうりょうひつ)は、翌年の春むなしく帰国したかのようであったが、そうではなかった。
じつは、ひそかに日本をせめるための準備をしていたのであった。
対馬(つしま)の守護代(しゅごだい)宗助国(そうすけくに)が、朝鮮半島に密使をだしてようすを調べさせたところ、そうとわかったのだ。
朝鮮の高麗王朝は、いまや全く元(モンゴル)の奴隷のようにいいなりにされているということであった。
まず、モンゴル皇帝の命令で、たくさんの船をつくらなければならなかった。
それも五十艘や百艘ではない。一千艘に近いらしいとのことであった。
「朝鮮半島の木という木は切りたおされ、山々は赤はだかでございましたそうなこと、宗助国の密使は報告した。
高麗と日本とはまじわりがふかい。とりわけ対馬の島民は親しい。
それで日本に同情する高麗人も多い。
また、モンゴルから追い出された中国の役人や僧なども多いので、日本にようすを知らせてくれる者もいる。
これらのさまざまな情報を集めて考えるに、国難は確実におとずれようとしているのだ。
七 文永(ぶんえい)の役、博多の浜の決戦
top
1 日蓮、鎌倉を去る
文永十一(一二七四)年二月。 突然、時宗は役人をよびだした。
「日蓮はいかがしているか。」
「はい、佐渡島であいかわらず法華経(ほけきょう)を信ずべしと唱えて、守護代を困らせているそうにございます。」
三年前、あの暴風雨にさえぎられ、危うく処刑をまぬがれた日蓮は、時宗によって助命され、佐渡に流されていた。
時宗は佐渡の守護にたいし、日蓮がほかの宗派の信者によって暗殺されるようなことのないようにと、ひそかに命じて守らせていた。
「あの男には、はかりしれない強い意志があって、それが神の加護(かご=たすけ、守ること)をよぶのであろう。
よし、日蓮を鎌倉へよびかえせ。」
一月後、日蓮は鎌倉にもどり、やがて、時宗の前によびだされた。
[モンゴルは、いつ攻めて来るか]
「今年じゅうに……。」
日蓮は、黒く太いまゆをぴくっとさせていった。
「モンゴルを防げるか。」
時宗のかたわらにいた評定衆の平頼綱がたずねた。
「このままでは、日本はほろびますぞ。日本をすくう道は一つしかありませぬ。」
「申してみよ。」
「この日蓮におまかせくださることです。この日蓮の調伏(ちょうふく=仏に祈り、敵をしずめること)によって、かならずやモンゴルを屈服させてみせましょう。ただし、条件がございます。」
「いかなることか?」
と、平頼綱がたずねたが、時宗はそっぽをむいた。日蓮のいうことはわかっている。はたして日蓮はいった。
「よその宗派の僧の調伏(ちょうふく)をいっさい禁止してください。
この日蓮ただ一人が、この日本国をすくう調伏をいたします。」
時宗が、じっと日蓮の目を見すえた。
「それはならぬ。たびたび申したとおりじゃ。」
「ならばやむをえません。昔の賢人(けんじん=かしこい人、徳のある人)の言葉に、三たび意見を申上げて聞き入れられないときは、その身、退くといいます。」
「いずこへいくぞ。」
「よこしまな(正しくない)宗派の行われない、清らかな山の中にかくれすみます。」
こういって日蓮は鎌倉をはなれ、富士山の西側を流れる富士川ぞい、甲斐(かい=山梨県)の身延山(みのぶさん=山梨県南巨摩郡身延町)にひっこんで小さな寺をたてた。
これが、現在も日蓮宗の総本山として栄えている久遠寺(くおんじ)である。
2 元、ついに対馬をせめる top
文永十一(一二七四)年、十月五日の午後四時ごろ。
対馬の国府(役所のあるところ)の八幡宮が、突然白い煙につつまれ、やがて社殿がまっ赤な火をふいた。
おどろいて島の人々がかけつけると、これは一体どうしたことか、煙も火も幻(まぼろし)のように消えていた。
「これは、何か恐ろしいことの起こる前ぶれではないか……。」
と、人々は脅えて顔を見あわせた。
島の人のいった「何か恐ろしいこと」は、あまりにも早くおとずれた。
その日の夕方から夜にかけて、対馬の沖に、おびただしい船の帆柱が見えたのだ。
「ムクリがきたぞ!」
浜の漁師が見つけてさけんだ。この知らせは、すぐに国府に届いた。
くるものがとうとうきたのだ――と、守護代(しゅごだい)の宗助国(そうすけくに)は覚悟した。
この数年間、モンゴルからの使者は、かならず対馬へやってくる。対馬は日本の門のようなものである。
だからモンゴルが攻めて来るとすると、まず対馬をおそうにちがいないのだ。
対馬じゅうの寺や神社の鐘がうち鳴らされた。
「老人、女、子供を山のおくにかくせ。武士はただちに弓矢をとって浜に集れ。」
宗助国(そうすけくに)の命令がくだされた。しかし、島じゅうの武士を集めても百騎にもたりない。
すでに夜になっていた。
宗助国は、八十余騎をしたがえて夜の浜にかけつけだ。
真夜中だが、沖には、おびただしい船のかがり火が明るくかがやいている。
やがて、しらじらと夜が明けると、大きな軍船から、つぎからつぎへと小舟がおろされはじめた。対馬への上陸準備だ。
「真継男!」
と、宗助国は、高麗語を話せる家来をよんだ。
どうしても戦いはさけたい。ここは話し合いで、ことをすませたい。と考えたのだ。
だが、通訳の真継男が、浜へ出て高麗語で話しても、相手はこたえず、いきなりバラバラッと矢の雨をあびせてきた。
宗助国は、このとき六十八歳だった。こうなってはしようがない。戦いがあるのみだ。
自分はここで討ち死にしてもくいはない。しかし若い者を死の道づれにすることはなんとしてもさけたい。
しかし孤島で、逃げるすべがない。
「みなの者、日本国のためじゃ、いさぎよく命をすててくれ……。」
武士たちは、一人として、臆する(気おくれする)者はいなかった。いっせいに太刀をぬき、
「えい! えい! おう!」
と、ときの声をあげた。
「それがし、初矢つかまつりましょう。」
宗助国の子馬次郎が、波うちぎわにかけよって、きりきりと弓をひき、やっ! とはなった。
矢はあやまたず、浜に上陸して、馬上にまたがったばかりの敵将の胸にふかぶかとつきささった。
それを合図のように、「文永の役」の対馬合戦の火ぶたがきっておとされた。
敵は討っても討っても、次々に小舟をよせて上陸してくる。
助国が、しばらくたたかって、丘の上に引上げてくると、いつしか十数騎ばかりになっていた。
その武者たちも、みな、全身はりねずみのように矢がつきささっている。
「小太郎、兵衛次郎!」
助国は、生残った二人の若武者をよんだ。
「そなたたちは、島をぬけだして、大宰府にこのさまを知らせよ。」
「何をおおせられます。死なばもろともです。」
小太郎は、涙をうかべていった。
「おろかな! いまは、ただただ日本国を守ることが第一ぞ。」
二人は涙をおしぬぐって、島影から小舟をひきだし、ひそかに博多の海辺にむかってこぎだした。
3 五郎季長の出陣 top
「とうとう、きたか!」
五郎季長のところにも知らせがきた。
弥二郎は、馬小屋から、あお(黒馬)をひきだし、
「主従二騎、では、すこし心細すぎる。里の若い者をさがしてつれていこうかのう。」
といった。
あるじの出陣を、すこしでも立派なものにしたいし、手柄をたてるためには強い家来が必要だとおもうからだ。
五郎は神棚から竹のつつをおろした。
「武士の出陣じゃ、あるいはこれが、親子、今生のわかれかもしれぬ。」
といいながら、五郎は竹づつの中から、三枚の紙をとりだした。
紙には姿絵がえがかれてあった。
「寺の和尚に絵筆をかりて、えがいておいたのだ。」
一枚は自分の似顔絵、一枚は妻の、一枚はわが子の姿絵であった。
一時(約二時間)ほどたって、弥二郎が戻ってきた。 |

「蒙古襲来絵詞」に描かれた竹崎季長(先頭の武士)
|
「若い者などはとっくにおらん。みな菊池さまの手勢にくわわって、もう出陣してしまったようじゃ。」
「しかたない。なあに弥二郎、そなたがいれば十人の兵をひきつれたよりも心強い。」
五郎は、妻の絵だけをたたんでふところにいれて、よろいを着した。
大宰府につづく道のとちゅう、姉むこ三井資長(すけなが)主従の三人とも一緒になった。
これで小さな武士団が成立した。
大宰府につくと、九州各地から集った大勢の武士たちの、のぼりや旗さしものが、まるで林のように立っていた。
本陣の中央に、黒糸おどし(黒糸でよろいの部分をつづること)のよろいをつけた老人がゆうぜんとすわっていた。
鎮西奉行の少弐資能(すけよし)入道だ。七十七歳ながら、その目は博多沖を見すえて、こうこうと光っていた。
その横にすわっていた紫おどしのよろいをつけた若い武将が、すっくと立ちあがった。
「父にかわって、いくさの奉行を、この少弐経資がつとめる。
副将は豊後(ぶんご=大分県)の大友頼泰どのにお願いする。」
五郎季長は、おもに肥後(ひご=熊本県)の武士団と一緒にたたかうことになった。
いざ出陣というとき、浜のほうから、一人の血だらけの武士が、両わきをかかえられてやってきた。
「壱岐(いき=長崎県北西部の島)の守護代平景隆(たいらのかげたか)どののご使者!」
と、ささえていた武士がいうと、息もたえだえの武士が顔をあげた。
「無念ながら、平景隆(たいらのかげたか)どのをはじめ、百余騎、ことごとく討ち死つかまつりました。」
対馬(つしま)、壱岐(いき)の両島は、完全に元軍に占領されたのだ。
つづいてまた一騎、馬をとはして伝令がかけつけだ。
「申上げます。」
伝令によると、壱岐をおとしいれた元軍は、さらに肥前(長崎県)の松浦(まつら)地方(長崎県北部・佐賀県北西部、現在はまつうらと読む)をせめた。
水軍で名高い松浦党は必死でたたかったが、何千という大軍の前に次々に討ち死に、平戸島(長崎県北西部にある島)と鷹島(たかじま=長崎県伊万里湾内の島)では数十人の女、子供が捕えられ、なわで数珠つなぎに束ねられ、敵船につれさられたという。
「あの松浦党までうたれるとは、容易ならぬ敵じゃのう。」
「はい、多勢のうえに、毒矢まで使い、かすっただけでも深傷となりますそうで……。」
と、伝令は話した。
元軍の主力は、二手にわかれていた。一手はモンゴル軍(元・宋軍)、もう一手は、高麗(こうらい)軍。
五郎季長(すえなが)の属する肥後軍は、総大将少弐経資(しょうにつねすけ)の弟、景資(かげすけ)にひきいられて博多の浜(福岡県福岡市博多区)に陣をかまえた。
十月十九日、敵軍は博多沖に姿を現した。 |

|
沖には、水面いっぱいに敵船がならび、赤、青、黄などの旗を、潮風になびかせている。
「よし、弥二郎いくぞ!」
五郎季長は、やなぐい(矢をいれて背おう道具)から黒羽の矢をひきぬいた。
まわりの武士たちも、いっせいに矢をつがえた。
しかし、敵船は、それ以上近づいてこようとはしない。
そのまま夜となった。
4 日本軍の苦戦 top
|

モンゴル軍の兵士に向かって突っ込もうとする竹崎季長。しかし馬が「てっぽう」に驚く。
|
翌十月二十日の朝方になって、ようやく敵船の一部がうごきはじめた。
伝令が走ってきた。
「申上げます。敵は今津のみさき、あるいは百道原(ももじばる=福岡市早良区北部)に上陸するかと思われます。」
百道原は、博多の西、松原つづきの長い海岸線である。
日本軍も、一部をのこして主力は百道原にむかった。
「はなれるなよ、五郎どの。」
姉婿の三井資長(すけなが)がいった。
「おう、死なばもろともしや。」
五郎季長(すえなが)も、あおにむちをくれていった。
百道原(ももじばる)の松原につくと、すでに敵兵は何十艘という小舟を砂浜にこぎよせて、続々と上陸しはじめていた。
見なれない服装のモンゴル兵が、わけのわからない声をあげて浜を走ってくる。
すると、日本軍の中から、白馬にまたがった、目のさめるように美しい若武者が、しずしずと陣の先にすすんだ。
「やあやあ! モンゴルの方々、よくききたまえ、われこそは日本軍の総大将、少弐経資(しょうにつねすけ)の一子小太郎資時(すけとき)、当年とって十二歳!」
ろうろうとした声で名のると、弓にかぶら矢(音をたてて飛ぶように工夫された矢)をつがえた。
「おお、あれは少弐どのの若とのか。」
五郎も三井資長も、美しくもりりしい若武者にみとれた。
若武者のはなった矢が、ヒュルン、ヒュルンー と音をたてながら空をきってとんだ。
国内の合戦だと、先方からも同じようなかぶら矢を射てくる。
「矢合わせ」といって、合戦始まりの挨拶である。
おたがいに矢を射た敵を、「おみごと」とか「あっぱれ」といってほめあってから合戦がはじまるのである。
しかし、相手はことばの通じない外敵である。
この優雅なかぶら矢の挨拶をどっと笑い、どら(銅鑼=かね)、太鼓を打ち鳴らし、ときの声をあげ、日本軍めがけて突進してきた。
よし、それならば、と五郎季長も、馬にむちをくれて真一文字に敵につっこんでいった。その横を、
「筑前(福岡県)の国の住人、朝倉の八郎吉直!」
と名のって、追いぬいていった武者があった。
モンゴル兵が、さっとひいた。
逃げる敵兵を追って、なおもつっこんでいくと、突然、どら、太鼓が鳴った。
すると逃げたはずの敵兵が、くるりと輪をつくるようにして、すっぽりと朝倉八郎をとりかこみ、あっさりと討ち取ってしまった。
「おのれ、モンゴル兵めが!
怒った五郎季長は弓をすて、太刀をぬき、敵陣につっこもうとした。
「あぶないっ! 一騎うちは敵の思うつぼじゃ。」
弥二郎があわてて、五郎のあおのくつわ(手綱をつけるため馬の口にはめる金具)をおさえた。
「一騎がけはあぶない。
ひとかたまりになっておしだせっ!」
五郎たちは、菊池党の武者たちのくるのをまって、馬の首をならべて敵兵につっこんだ。
と、その時、何か黒いかたまりがとんできて、
バァーン!
とてつもない大きな音をだして爆発し、火をふいた。
それと同時に、敵兵は、どらや太鼓などをいっせいに鳴らした。
ヒ、ヒ、ヒーン!
あおがおどろいてさお立ちになり、危うく五郎は落馬しそうになった。
日本軍の馬は、みな大きな音におどろき、武者たちは自分の馬をしずめるのにせいいっぱいとなった。
みだれた日本軍に、モンゴル兵はいっせいに矢をはなち、ひるむところへ、ほこ(鉾=長い柄の先に、両刃の剣をつけた武器)をかまえた歩兵が、わあっ! と、喚声をあげて攻め込んできた。
「引け! 引けい!」
誰かがさけん、でいる。一度さかって、陣をたてなおさなければならない。
五郎は、ほこをつきあげてくるモンゴル兵をなぎはらいながら、命からがら本陣に引上げた。
5 季長、先陣 top
モンゴル軍の戦法は、鉄砲(火薬のはいった鉄の玉)を飛ばして敵をおどろかし、毒矢を射、どら、太鼓を鳴らして、敵の馬をおどろかせて混乱させ、そこへよりぬきの騎兵が、長いほこをならべてつっこんでくるのである。
この戦法によって、南はインド、西は遠く、ロシア、ハンガリーまで攻め込んで支配したのである。
日本軍の主力は、大宰府の北にある博多の町を守っていた。
一陣、二陣とそなえていたが、元の大軍は、その陣を突破して博多の町に火をはなちはじめた。
五郎らは、博多までしりぞいてきたが、ここで一息つくと、本陣を守るために馬を走らせた。
すると、紫のよろい、赤い母衣(よろいの背しつけ、流れ矢をふせぐ布)をつけた立派な武将が、百騎ばかりをひきつれてかけつけて、本陣にせまったモンゴル兵をやぶった。
こうしてモンゴル兵がくずれはじめ、ぎゃくに日本軍が追うかたちになった。
「深追いはあぶない。かたまっていけ!」
五郎が、さきほどの失敗にこりて、さけんだ。
だが、みすみす手柄を渡してはならない。
五郎もまた弥二郎、三井資長らともども、敵を追ったが、味方の大将少弐景資(しょうにかげすえ)の旗じるしを見つけると、馬をとめ、声をはりあげた。
「少弐どの! 竹崎の五郎季長、これよりモンゴル軍へ先陣つかまつる。」
「おぬしを見届けたこと、わしが生き長らえれば、確かに伝えようぞ。」
景資はこういって季長をはげました。
逃げるモンゴル兵を追っていくと、むこうから敵兵の首を、太刀やなぎなたの先につらぬいて、引上げてくる武士団がやってきた。
「あっぱれな武者ぶり! どなたの手勢でござるか。」
五郎が声をかけると、先頭の紫のよろい武者が、「菊池次郎武房!」と名のった。
「さては、同じ肥後の御大将どのか。それがしは、阿蘇竹崎の住人、五郎季長、当年二十九歳でござる。
これよりもう一いくさ、先がけてみるつもりでござる。どうぞ、のちのちの証人になってくだされ!」
丘を一つこえると、その下にはモンゴル兵が待機しているのが見えた。
五郎を追ってきた弥二郎が、ふとうしろをふりむいた。丘の木立にさえぎられて味方が見えない。
すると三井資長もそれに気づいて、うしろから五郎に声をかけた。
「五郎どの、せくな! 味方が見ていないところで先がけしてもむだじゃ。証人の味方がくるまで、しばしまて!」 |

日本の大将少弐景資(しょうにかげすえ)
|
「いや、味方をまっていては、先がけの功を人に奪われるやもしれぬ。とりあえず、攻め込みましょう!」
五郎は、敵陣にせまると、やなぐいから矢を引きぬき、引きぬき、さんざんに射た。
一の矢、二の矢……と、次々にモンゴル兵がたおれるのが見えた。
しかし、日本軍がわずか五人と気づくと、モンゴル兵たちは、五郎らを包囲しようと動きはじめた。
モンゴル軍はあくまで集団戦法だ。
いつしか取り囲まれた五郎は苦戦におちいり、あげく左手にしびれる痛みを感じ、と同時に馬が前脚を射られ、さお立ちになったので、ドッと地上にころげ落ちてしまった。
弥二郎は必死に五郎を守って太刀をふりまわしたが、太ももにほこをつきさされて、ひざからくずれた。
五郎は必死で立ちあがる。かぶとにも矢が命中し、ざんばらがみ、血だらけになりながらも、右手一本で太刀をふるう。 |
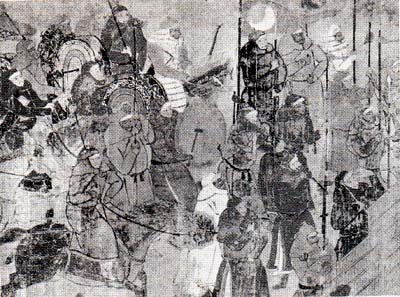
待機するモンゴル軍の兵士たち。中央にドラが見える。
|
あわや、というときモンゴル兵がバタバタとたおれた。
「白石六郎通泰! 助勢もうす。」
大勢のよろい武者たちが五郎らの苦戦に気づいて、矢を射かけてきた。
モンゴル兵がひるむとみるや、弓をすて太刀をぬいて突進してきたので、五郎たちは危うく一命をとりとめたのだった。
戦いは夕方までつづいたが、モンゴル兵の大軍は、じわじわと日本軍をおしてきた。
そうして、ぱっ! と、夕やみに火の手があがった。とうとう博多の町に火がはなたれたのだ。
火は九州武士たちが、あつく信仰している筥崎(はこざき)八幡宮にももえうつった。
「おのれ、ムクリめが!」
武士たちは、討ち死に覚悟でかけたそうとしたが、総大将少弐経資(しょうにつねすけ)がとめた。
これ以上犠牲がでれば、明日の合戦はおぼつかない。
夜のやみが、日本軍に味方した。
モンゴル兵は、勝手のわからない土地での夜戦をおそれ、船に引上げた。
元軍も博多攻撃軍の勇将劉復亨(りゅうふくこう)を討たれている。
五郎季長の傷は、さいわい浅い傷だった。むしろ、弥二郎の太ももの傷のほうがふかかった。
五郎は、弥二郎の傷口をあらい、うまないように一晩じゅう冷やしつづけた。
「との、明日も大いくさ、私にかまわずお休みください。」
「けが人は、よけいな気づかいをするな。」
と、五郎はしかったが、それでも合戦のつかれで、いつしか眠りこんでしまった。
ビューツー ザザザアーツ……。
真夜中、強い雨、激しい風、打ちよせる波の音で、五郎はふと目ざめたが、それも一瞬で、再び深い眠りにおちた。
6 海から消えた元軍 top
カッ! カッ! カッ! カッ! ヒ、ヒーン!
ひづめの音と馬のいななきで、五郎も弥二郎も目ざめた。
明るい。雨はやんだらしい。しかし岸をうつ大海のどとう(あれくるう大波)の音が、とどろくばかりに高い。
「敵が! ……ムクリがおらんぞ!」
誰かが叫んでいる。その声で、武士たちが外へとび出していくようすだ。
「本当じゃ!」
「船も見えんぞ!」
五郎も目をこすって外へ出た。
黒くやけおちた町のむこうに、海が大きくうねっているが、モンゴル船は全く影も形もない。
一体、これはどうしたことじゃ! と五郎は、まわりの武士たちと、狐につままれたように顔を見あわせた。
少弐経資も浜に出てきて、けげんそうに目をしばたたいた。
つぎからつぎに早馬がかけてきて、少弐経資の前にかたひざついて報告する。
「箱崎(福岡市東区)の海にも、ムクリの船は見えませぬ。」
「町のいずこにも、ムクリ兵かおりませぬ。」
「げせぬことよ。よし、わしが見とどけよう。」
経資が馬にむちをくれて、博多の浜から今津までかけて見届ける。
そのうち、合戦をさけてかくれていた漁師や町びとが、続々姿をみせた。
「昨夜、ムクリの兵たちは、日がくれると船に引上げていきました。」 と、老いた漁師がいった。
「なにやら、大将同士が、大声でいいあらそっていた気配でございました。」
海辺の船底で息をひそめていたという若い男がいった。
その時、また一騎、志賀島(福岡県博多湾にある島)からの物見(見はり)が馬を走らせてきた。
「申上げます。みさきの浜に、こわれた敵の船、旗にまじって、たくさんのムクリの死体がうちあげられました。」
同じような報告が、あちらの浜、こちらの島からとどいてきた。
「昨夜の大風のすさまじさで、ムクリの大船でも転覆してしまったとみえる。」
「さよう、入り江であればまだしも、波のあらい沖ではのう。」
漁師たちの話で、元軍の船が、昨夜の“しけ”ですべて難船したらしい、ということがわかった。
7 写経する時宗 top
時は、すこし前へ戻る。
鎌倉の時宗は座禅のときをすごすと、居間に戻って墨をすり、白い紙をひろげ、筆をとって経文を写しはじめた。写経である。
鎌倉山の紅葉がまっ赤である。鶴岡八幡宮の大いちょうが、秋風にふかれて、黄色い小鳥のように美しい葉をちらす。
こんなにここは静かなのに、西の果てでは国の運命をかけた大いくさがはじまっているのだ。
対馬がモンゴルに襲われた、という知らせが、みやこ(京都)に届いたのは十月十七日のことであった。
「博多も、大宰府もムクリに奪われたそうな。」
「九州の女、子供は、皆殺しにされたそうな。」
町びとも、公家(貴族)も、みなおそれおののいた。
自分たちを守ってくれるものは神仏しかない、とみな思っている時代である。
亀山上皇(天皇が退位すると上皇になる。実際は天皇より権力が強かった。)は、大昔、朝鮮半島に出兵したという神功(じんこう)皇后の御陵(ごりょう=墓)をはじめ八つの御陵に、じきじきに「敵国退散」祈願の書をたてまつった。
あちらこちらの神社の祈檮(神仏にいのること)には「不動明王」の絵がささげられた。
これは、海ぞいの岸壁に立つ不動明王の図で、右の目はつりあがって海のかなたをにらみ、左の目は足もとの波しぶきを見おろしている。
元軍の船が全滅した、との報が京についたのは十一月六日のことであった。
亀山上皇は、石(いわ)清水八幡宮(京都府八幡市にある神社)や、賀茂(かも)神社(京都市北区・左京区にある神社)、北野天満宮(京都市上京区にある神社)にお礼まいりした。
「神風がふいたのじゃ。」
「そうじゃ、日本は神国じゃ。」
一時は、ムクリが京まで攻めて来る、とのうわさでふるえあかっていただけに、京のみやこびとの喜びようといったらなかった。
数日おくれて、鎌倉にも勝利の知らせが届いた。
時宗は、連署、評定衆など重職についている者たちをあつめた。
「まさしく神風がふきましたのう。」
一人が言葉をはずませた。すると、時宗の目が、ぎょろっと光った。
「モンゴルは降伏したわけではない。嵐に襲われて失敗しただけじゃ。モンゴルは再び攻めて来るであろう。
それをやぶれるのは、いかなることにも動しない鎌倉武士の心のみじゃ。」
評定衆が帰ると、時宗は建長寺にむかい、その石段を静かにのぼっていった。
top
**************************************** |