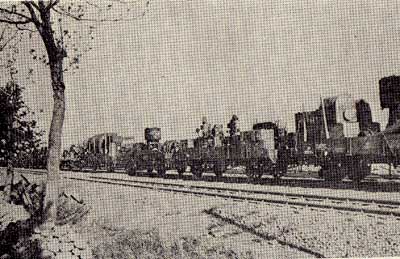|
****************************************
Index 内戦参加 ノモンハン 独軍侵入
第一〇章 独軍侵入――社会主義の祖国が危機にひんしている!
|

|
一九四一年六月二二日に入ろうとする深夜、参謀本部と国防人民委員部の全勤務員に対して職場に居残るようにという指令が出された。
一刻も早く各軍管区に対して、国境警備部隊を戦闘配置につかせるよう伝達する必要があったのである。
そのときは、私自身ばかりでなく国防人民委員部もきりきり舞をしていた。
というのは、軍管区司令官やそこの参謀たちが、国境警備隊、さらにその前線の警備兵からくる情報に基いて国境のこちら側のあわただしい情勢をひっきりなしに報告してきており、我々は彼らにいちいち応対してやらねばならなかったからである。
すべての報告が、刻一刻とドイツ軍が国境に近づいてきていることを伝えていた。
このことについて、深夜零時半に我々はスターリンに報告した。
スターリンは、軍管区に指令を出したかどうかとたずねたので、私は処置ずみであることを回答した。
スターリンの死後、六月二二日早朝に若干の司令官や参謀部員は、何も知らず気楽に眠っていたとか、呑気にはしやいでいた、といったような説が伝えられた。
しかし、それは全く実情にそわない。最後の平和の夜は、それどころではなかった。
すでに述べたように、我々と国防人民委員部スタッフは、クレムリンから帰った後も、前線の軍管区司令官や参謀長などと緊急電話線を通じて何度か連絡をとっていた。
六月二二日の朝、チモシェンコとワトゥーチンと私は、国防人民委員部の執務室に集った。
午前三時一七分に、黒海艦隊司令官のオクチャブリスキー大将から緊急電話で私に呼出しがかかった。
オクチャブリスキーの報告は次のようなものだった。
「艦隊の空中偵察班からの報告によると、海上の各方面から所属不明のおびただしい数の飛行機が接近中です。
艦隊は完全な戦闘態勢に入りました。指示をこう」
私は、オクチャブリスキー大将にたずねた。「あなたの考えは?」
「手段は一つです。艦隊の対空機能をあげて飛行機を迎えうつことです」。
チモシェンコ元帥と打合せると、私はオクチャブリスキーに答えた。
「直ちにその処置をとり、その旨を所属人民委員部に報告してほしい」
三時三〇分には、西方軍管区参謀長タリモフスキフ大将から、白ロシアの諸都市の上空にドイツ軍の飛行機が飛来してきていることを報告してきた。
さらに三分ほどして、キエフ軍管区参謀長プルカーエフ大将がウクライナの諸都市にも飛行機がとんできていることをつげた。
三時四〇分になると、沿バルト軍管区司令クズネツォフ大将も、カウナスその他の都市に敵機が飛来していることを電話でつげてきた。
国防人民委員は、私(参謀本部長=スターリンの軍事の側近)に、スターリンに電話するように命じた。
すぐに電話したが、誰も出てこなかった。
何度も受話器をならしているとやっと警備の宿直の将官の眠そうな声が受話器に伝わってきた。
私は、スターリンにとりつぐように頼んだ。
三分ほどしてスターリンが受話器を取上げた。
私は状況を報告し、すぐに戦闘行為に入るよう決定を下してほしいと頷んだ。
受話器を通してスターリンの息づかいだけが聞えていた。
「お分りになりましたか?」それでも返事はなかった。やっとスターリンがたずねた。
「国防人民委員はどこかね?」
「緊急電話でキエフ軍管区と通話中です」
「チモシェンコ(国防人民委員)と一緒にすぐにクレムリンに来てほしい。
それから、ポスクレブイシェフに、政治局員全部に電話するように伝えてくれたまえ」
四時に私は、もう一度オクチャブリスキーと話をした。
彼は落着いた調子で次のように報告した。
「敵機は撃退しました。艦隊壊滅の敵の試みは成功していません。ただ、市街には破壊個所が出ています」
私はオクチャブリスキー大将に、組織的な敵の攻撃をうけたのは黒海艦隊が最初だということを強調したいと思った。
四時一〇分には、西方と沿バルトの両軍管区から、地上陣地に対してもドイツ軍の攻撃が開始されたことを報告してきた午前四時半には政治局員全員が集合した。
私と国防人民委員も閣議室に通された。
スターリンは青ざめていて、タバコのつまったパイプをもって椅子にかけて言った。
「すぐにドイツ大使館に電話する必要がある」
大使館の回答は、フォン・シューレンブルク大使の方で緊急報告するために面会を求めている、というものであった。
大使の接見はモロトフにまかされた。
そうするうちにも、参謀本部第一代理のワトゥーチン大将は、北西および西方一帯の軍管区に対して、ドイツ軍歩兵隊が猛烈な砲撃を行なった後進撃に移りつつあると報告してきていた。
しばらくすると閣議室にモロトフが足早に入ってきていった。
「ドイツ政府は、我々に宣戦を布告しました」
スターリンはイスに深く身をしずめ、ジッと考えこんだ。
長い、苦しい沈黙がつづいた。私は、あえてこの沈黙を破った。
そして、国境の各軍管区は、全力をあげて敵の崩れそうな部分に集中攻撃をかけ、その態勢を崩さないように維持し続けるようすぐ命令することを提案した。
「維持するだけではない、敵を壊滅するのだ」とチモシェンコが強調した。
「指令を出したまえ」とスターリンがいった。
六月二二日午前七時一五分、国防人民委員部の指令第二号は各軍管区に伝えられた。
しかし、この指令は、両軍の力関係や複雑な情勢を無視したもので非現実的で、実行には移されなかった。 |
すぐその後で判明したのだが、二二日の夜明け前に、もう西部国境の各軍管区では、部隊間の通信網は切断されており、軍管区参謀部と部隊との間には迅速に指令を伝える方法はなかったのである。
ドイツ軍によって予めわが領土内に送りこまれたスパイや撹乱部隊は、通信網を破壊し、わが方の通信兵を射殺し、戦闘の不安に興奮してしまっている部隊長などを攻撃していたのである。
すでに述べたように、ほとんどの国境軍管区の部隊は、無線手段によっても連絡はつかなかった。
軍管区の参謀部には、いろんな方面からお互いに矛盾した情報がどんどん入ってきた。
その中には、しばしば挑発的な内容をもったものもあった。
ところが参謀本部の方には、軍管区参謀部からも通信部隊からも何一つ連絡はなかった。
いうまでもないことだが、総司令部や参謀本部が、こういう孤立した状態におち入ることは、一瞬たりともあってはならないことだった。
二二日の午前八時頃になって参謀本部にはやっと次のような状態が分ってきた。
「白ロシア、キエフ、沿バルト各軍管区の沢山の飛行場が敵爆撃機の激しい空襲に見舞われ、そこにあった飛行機は、飛びたつことも格納庫の外へ出て散開することも間にあわずに手ひどい打撃を受けた」
「沿バルト地方、白ロシア、ウクライナ各地の沢山の都市、鉄道集中点、セバストポールと沿バルト地方の海軍根拠地などが空襲を受けた」
「西部国境全域にわたって歩兵部隊どうしの激しい戦闘があった。そして各所でドイツ軍はもう、赤軍の前線と交戦状態に入っていた」
「最先端陣地の攻撃部隊は、戦闘行為の激しさにおびえて、火蓋はきったものの陣地を守りとおすことぱできなかった」
「レニングラード軍管区方面は静かで、敵は全然姿を現わさなかった」
チモシエンコ元帥はスターリンに電話して「クレムリンに訪ねて、お目にかかりたい」と頼んだ。
その目的は、動員令の発布と、最高軍司令部の構成について最高会議幹部会の法案をつくること、その他の問題で打合わせる必要があったからだった。
九時に我々は、国防人民委員とともにクレムリンに着いた。
スターリンが我々を引見したのはそれから三〇分後だった。
情報報告を聞いた後で、スターリンは言った。
「一二時には、モロトフがラジオに出るだろう」
スターリンは参謀本部で作成していた動員令の法案をよみあげるのを聞いていて、しばしば冗漫な表現を削って、それをポスクレブイシェフに渡し、最高会議幹部会で確認を受けるように命じた。
中央アジア、ザバイカル、極東の三軍管区を除き一四の地域にわたって、一九〇五〜一九一八年の間に生れた兵役義務者の総動員に関する布告は六月二三日付で出され、同時に欧州地域における戦争状態が公表された。
この結果、国防関係、社会秩序維持、国家の安全保障などに関する国家権力の全部の機能は、軍事機関に移った。
国防上の目的にそって、国民を動員し、運搬手段を徴発し、また最重要の軍需要ないしは国民経済維持のための物資を確保する、などの全権隕が軍事機関の手に移されたのである。
最高軍司令部の構成についての仕上げを、スターリンは、後で政治局で検討するからといって、自分の仕事として残した。この最高軍司令部の構成に関する布告は、我々が最初につくった案が、いくらか手直しされて、六月二三日に布告された。
この手直しの問題で、国防人民委員と意見の相違が生じたのだが、我々は最初に、最高軍司令官にはスターリンを想定しており、その通りにすべきだったのである。
現在の秩序の下では、いずれにしても万事を決定するのはスターリンで、チモシェンコが自主的に主要な決定を下すことなどできはしなかったのだ。
結局、二人の最高軍司令官がおかれることになった。
一人は国防人民委員チモシェンコで、法制的な面での最高軍司令官、そして一方、指令に関してはスターリンが行うことになり、こちらが実質的な最高軍司令官ということになった。
この事実は、戦争遂行上の事務を煩雑にし、決定を下す場合などにムダな時間をくうことはさけられなかった。
我々はまた、最高軍司令部の構成メンバーに、参謀本部第一代理ワトゥーチソを加えるように提案したのだが、スターリンは賛成しなかった。
結局、ソ連共産党中央委員会および人民委員会議の法令として、最高軍司令部のスタッフとして次のような顔ぶれが発表された。
国防人民委員チモシェンコ(長官)、スターリン、モロトフ、ウォロシロフ元帥、ブジョンヌイ元帥、海軍人民委員クズネツォフ提督。
六月二二日には、沿バルト、西方およびキエフの三軍管区は、北西および西方、それに南西の三方面軍とよぶようになった。
二二日の午後一時頃、スターリンは私に電話をかけてきて、次のように命じた。
「我々の統轄している戦線には、戦闘指導に十分な経験をもったものがいない。
おそらく、それが相次ぐ敗退の原因になっているのだ。
そこで政治局は、あなたを最高軍司令部の代表者という身分で、南西方面軍に派遣することを決定した。
西部方面軍には、シャポーシニコフ、クーリクの両元帥を送ることにした。
シャポーシニコフとクーリクには、私がよび出して直接指令を与える。
あなたは、いま直ぐキエフへ飛んで、そこからすぐにフルシチョフと共同行動をとり、テルノーピリの戦線を指揮してほしい」
私はたずねた。
「それでは、こんな緊急の事態に、参謀本部の指揮はだれがとるのですか?」
これに対してスターリンはいった。
「ワトゥーチンにまかせるよ」そして、いくらかいらいらした調子で次のように付け加えた。
「時間をムダにするな、後は我々で何とかやっていくよ」
私は家に電話して、自分をまたないようにつげると、四〇分後にはすでに機上の人となっていた。
そこで初めて、私は昨日から何もたべていないことに気がついた。
飛行士が熱い紅茶とパンをごちそうしてくれたので、やっと人心地がついた。
夕方には私は、キエフに着きウクライナ共産党中央委員部に顔を出した。そこではフルシチョフが待っていた。フルシチョフは、これから先は飛行機は危ないといった。ドイツ軍の飛行機が、ソ連軍の輸送機を狙っているというのである。
緊急電話線を使って、ワトゥーチンから一番新しい全般的な事情を知らせてもらい、我々はテルノーポリに赴いた。
そこには、南西方面軍司令部があり、キルパノース大将が指揮をとっていた。
夕方おそく司令部につくと、またすぐ緊急電話線でワトゥーチンと話をした。
ワトゥーチンは私に次のように説明した。
「積極的に各種手段が講ぜられたにもかかわらず、六月二二日の夕方には、参謀本部ではもう前線からも、その他の部隊や航空部隊方面からもわが軍や敵の行動についての正確な報告は何一つ入って来なくなってしまいました。
敵がソ連領内のどの辺まで侵入しているかについての情報は、全くてんでんばらばらです。
空軍や地上軍に関する損害の度合いも、正確なところは分っていません。
ただ、白ロシフ軍管区の空軍が、手ひどい攻撃を受けたことだけははっきりしています。
参謀本部も国防人民委員部も、前線の司令官であるクズネツォフ、あるいはパウロフといった将軍連と連絡することができないでいます。
これらの将軍連は、国防人民委員部へ連絡もなくどこかの部隊へ行ってしまっているのです。
前線の参謀部は、いまの段階では、自分の指揮下に入っているのがどの部隊であるかさえ分らないでいます。
現在指揮下にある偵察機の連絡では、戦闘は、わが軍の固めていた国境の各所で行われていて、国内への侵入の深さはしばしば一五ないし二〇キロにもわたっているということです。
各方面軍の参謀部は、前線部隊と連絡をつけようとしていますが成功していません。
こんな具合なので、ほとんどの軍団、個々の部隊は有線、無線にかかわらず通信手段を失っています」
さらにワトゥーチンは「スターリンが、国防人民委員部の第三号指令を承認したので、私に署名するように命じました」と告げた。
「それは、どういう指令だったかね?」と私はたずねた。
「主要戦線で、敵軍壊滅のために、わが軍を反撃にうつらせ、できればそれに敵の領土内まで侵入させようというものです」。
私は反論した。
「我々にはまだ、敵がどのくらいの勢力で攻撃をしかけてきているのかも正確には分っていない。
ともかく、明朝までに戦線の模様を調べてみて、その後で必要な決定を行うことが得策じゃないかと思う」
「私もあなたと同意見ですが、この指令はもうきめられてしまったのです」
「よろしい、署名しよう」とつげた。 |
この指令は、南西方面軍には夜の一二時頃にとどいた。
私の予期した通り、この方面軍のプルカーエフ参謀長は激しく反対した。
彼は、方面軍としては、この指令を実行に移すための兵力も手段も全くないと判断していたのである。
複雑な状況は、方面軍の軍事会議で、詳細に検討された。
私はキルパノースに対して「すぐ機械化部隊を集結させるように命令を出したらどうか」と提案した。
そして、この機械化部隊で、ソーカリ地区で突破されている「南」の主要部隊と一緒になって反撃に移らせようというものだった。
反撃のために、前線の全空軍力と最高軍司令部直属の長距離爆撃機の一部とを集結することが必要とされた。
最高軍司令部と方面軍参謀部は、命令要旨を準備して、それを軍団および部隊に伝達した。
プルカーエフ方面軍参謀長とバグラーミャン参謀部作戦部長が、戦争第一日の困難な状況下に、早くも偉大な統率力と、なみなみでない組織能力とを発揮していることを強調しておく必要がある。
我々は、六月二三日午前九時、リャブイシェフ中将の指揮する第八機械化部隊の司令部に到着した。
私はリャブイシェフを、キエフ特殊軍管区でよく知っていた。
軍管区司令官や参謀部員の顔つきを見ただけで、我々には、彼らの当面している仕事の困難さはすぐ分った。
彼らは、ドロゴブイチ地方から大急ぎでブローダに到着したばかりで、部隊の士気は高揚していた。
リャブイシェフと参謀部スタッフに接したとき、私はすぐに、名誉ある第一一戦車旅団を思い出した。
そして、その旅団長だった勇敢なヤコブレフ将軍を。
そしてまた、この人たちが一九三九年、ハルヒン・ゴールのバイン・ツァガンの山で、いかに勇敢に敵軍を破砕したかを。
「この人たちはよく戦うだろう」と私は思った。
「ただ願わくば、攻撃の時期を失してくれるな」
リャブイシェフは地図を示し、どこにどう部隊を展開させようとしているかを説明した。
彼は、自分の部隊の状況について手短に報告した。
「必要資材および予備資材などを配置し、部隊が完全に集結を終るためには一昼夜が必要です。その間に、戦闘地帯の偵察も部隊配置もすませます。従って、二四日朝には、全勢力を傾注して攻撃にうつることができます」
「よろしい。もちろん、第九、一九、二二各機械化兵団と同時に反撃を開始することが望ましい。
しかし、残念ながら彼らは出発地を出るのが遅れている。現在の状況では、完全な集結をまっていることは許されない。
第八機械化兵団の攻撃に対しては、敵は、強力な戦車ないしは対戦車砲でこれを迎えうつことだろう。
こういう状況も考慮に入れて、地形や敵勢力を綿密に偵察してかかる必要がある」
リャブイシェフが私に何かいいかけようとしたとき「空襲!」という警報が伝わった。
「全く当てはずれの聖ユリー(注)の日だ」ジャブイシェフは靜かにつぷやいた。
(注=むかしの帝制ロシアでは旧暦一一月二六日を聖ユリーの日としてその日の前後には農奴の自由移転が許された)
「我々はまだ、防空壕さえ掘りおえていないんですよ。それでも閣下、条件としては防空壕の中にいるのと同じですから」 「リャプイシェフ、君は何か提案したいんじゃないのかい?」
「そうなんですよ。軽く食べようと思うのですが、どうですか?」
「結構だね。私の車の中に何かあったよ」
天幕の中に、兵団の参謀長やそのスタッフがソロソロと入って来た。
彼らは、自己紹介もそこそこに、ドイツ爆撃機の錐もみ下降しての爆撃や爆破の状況などを話した。
私は、ジャブイシェフやいま入ってきた司令官連中を見回した。
皆、普通の事務的な緊張以上を出ていなかった。
まるで演習にでも参加しているようにみえた。
「立派なもんだ。これなら、戦争に負けないだろう」と私には思われた。
軍団の司令官だちとの基本的な問題についての交渉をおえ、夕方、テルノーポリの方面軍司令部に戻った。
帰ると、方面軍参謀長プルカーエフ中将と方面軍司令官キルパノース大将は次のように報告した。
「戦闘は現在、方面軍の全地域にわたって展開されている。特に、ブローダ、ドゥブノ、ウラジーミル・ボリンスク地域の戦闘が激戦になっている。第九、第一九機械化兵団は、六月二五日にはロブノ地方で森林地帯を抜ける。我々は、完全な兵団の集結を待つことなく二四日には、クレバニとドゥブノ地帯で反撃に出ることを決定した。第五軍司令部には第二二機械化兵団の他、第九、第一九機械化兵団の行動を統轄させ、必要な援助を与えさせる」
この決定は、ねられたあげくのもので、私は方面軍の指令に賛成した。
ただ、機械化兵団と方面軍の空軍との間の相互連絡をたたないように気をつけるようにと付け加えた。
リャブイシェフ指揮下の第八機械化兵団は、攻撃の方向をベレスチェーチコ方面に移した。我々は、この部隊の活躍に大きな期待をかけていた。
というのは、彼らは最新式戦車戦闘の訓練を受けており、しかもそれをよくマスターしていたからである。
カルペソ大将指揮下の第二五機械化兵団は、ラジェホフから南の方面に攻撃をしかけた。
これら兵団の攻撃、特に第八機械化兵団の巧みな攻撃は、すぐにドイツ軍に衝撃を与えた。
特に、クレイストの第四八自動車部隊の右翼を援護していた第五七歩兵師団の壊滅の後、それはさらに広がった。
第四八ドイツ軍自動車部隊にとって、この日は苦難の日だった。
ヒトラー軍は、我々の側からの反撃にあって、全滅をさけるために飛行機をすてて退却しなければならなかった。
こういうソ連側の反撃にあって、敵はさらに第四四兵団となお若干の部隊を引き下がらせなければならなかった。
この日の状況について、ドイツ軍陸軍参謀長ハリデル大将は陣中日誌に次のように書いている。
「敵は我々の戦車陣地に対して、陣地深くから次々に新しい部隊を繰出してきた。予定したところだったが、敵は第一戦車部隊の南翼に、おびただしい戦車の大部隊をもって攻撃をしかけてきた。局部的には陣地の後退を余儀なくされた」
このように南西方面軍による反撃は、第一回目は成功だった。
しかし、もし彼らに、機械化兵団との相互連絡のための強力な空軍力があり、さらに望むとすれば、一〜二の歩兵兵団がその指揮下にあったとすれば、その実力はもっともっと効果的に発揮できたのだった。
南西方面軍の司令部にあった我々は、ウクライナ地方の戦闘の中心になっていたドゥベンスク方面の戦闘に一番注意をはらっていた。
第六軍団司令官のムズイチェンコ大将および第二六軍団司令官コスチェンコ大将との電話連絡で、私には、ドイツ軍の第一七軍団は、リウォフ方面に主とした攻撃をしかけてきていることが分った。
ドイツ軍捕虜の情報によると、この部隊は、ラバ・ルースキーを占領して、第一四自動車部隊と合流することを予定していた。
ラバ・ルースキー要塞地帯は、戦争開始以来、第三五および第一四○独立機関銃大隊とマールイ少佐の率いる国境守備隊とによって防衛されていた。
間もなくそこヘミクーシェフ少将の率いる第四一歩兵師団が赴いた。
第一七ドイツ軍の司令部は、この方面に対して歩兵五個師団を差向けてきた。
強力な砲撃と空爆、それに執拗な攻撃にもかかわらず、ドイツ軍は、ラバ・ルースキー要塞地帯を占領し続けることはできなかった。
第四一歩兵師団の抵抗に耐えきれなかったのである。
六月二二日の午後には、第四一師団は、二個連隊の砲兵部隊の他に、一五二ミリ砲を装備した第二〇九兵団の砲兵連隊をもその統轄下に収めることができた。この日の攻撃で、敵は大損害を受け、しかも目的を達せずに終った。
ペレムイシュリ要塞は、第五二および第一五〇独立砲兵大隊と、第九二国境守伽隊とによって守られていた。
要塞地帯の一部は、六月二二日の午前六時頃には、わが軍が支配していた。
そして部隊とともにいた国境住民や労働者、サラリーマンなどの武装部隊が、初めて敵の砲火と攻撃を受けたのである。
都市を守っていたこれらの勇敢な人たちは、兵力においてはるかに優勢な敵の攻撃を、数時間にわたって食い止めていた。
しかし、間もなく第九二国境守備隊長の指令に従って都市から撤退したので、そこは再び敵の手に落ちることになった。
そこで、デミェンチェフ大佐の率いる第九九歩兵師団はペレムイシュリ奪回にまわり、国境警備隊の独立部隊と協力して反撃に移り、二三日には市をファシストの手から奪回した。
六月二三日、ドイツ軍は攻撃を再開したが、特にラバ・ルースキー方面に強い攻撃を加えてきた。
そして敵の一部は、四一師団の防衛陣地にどうにか楔(くさび)を打ちこむことに成功したが、ミクーシェフ大将の指揮下部隊の頑強な抵抗のおかげで敵の反撃は結局はじめの線まで押戻された。
しかし、この日の夕刻になってドイツ軍はわが軍の手薄の部分を見つけ出した。
それは、ラバ・ルースキーとペレムイシュリ地帯との接点の部分で、ここに強力な攻撃を加え始めた。
そこには、第九七および第一五九歩兵師団が守備についていた。
この一五九師団は、兵員のかなりの部分が訓練をへない予備部隊から集められてきたもので、しかも戦線への展開も終っていなかった。
そんな状況だったから、敵の攻撃をささえきれず退却をはじめ、隣接部隊に深刻な危険を与え始めたのである。
ムズイチェンコ大将によって率いられた第六兵団による反攻も事態を回復するまでにはいたらず、二四日の夕刻には防衛線の崩壊は、この方面で四〇キロにわたった。
ラバ・ルースキーとペレムイシュリの両地帯では、わが方の攻撃はますます強化され、引続き敵は後退し続けた。
第九九師団は、敵に大損害を与える一方、味方陣地は一メートルも失うことはなかった。
この師団は、勇敢な行動によって赤旗勲章を授けられた。
第四一歩兵師団もまた、巧みな戦局展開を行なっていた。
しかし、敵のかなりの部隊が、第一五九師団の防衛線で楔を打ちこむのに成功したことから、要塞地帯を迂回される危険が出てきたために、方面軍司令部は六月二七日の夜、国境線から後退したのである。
第九歩兵師団はどうかというと、この部隊は、六月二三日から二八日にかけて、ヘレムイシュリを守り続けたのだが、二九日の朝になって司令部の命令で都市を撤退している。
六月二五、二六日は、戦闘行為が一番激しい形で展開された時期だった。
敵はこのとき、大量の戦闘機を失っている。
空中で地上で、死にもの狂いの陣地争奪戦が行われ、敵も味方もともにひどい打撃を受けた。
ドイツ航空部隊はしばしばわが方の飛行士の大胆な攻撃を支えきれず、飛行場へ逃げ帰っていった。
ドゥブノ地帯に、敵の最前線が突出してきたため、リャブイシェフ大将は、そこへ指揮下の第八兵団を向けるようにという命令を受けた。
第一五機械化兵団もベレスチェーチコの辺り一帯に兵力を展開し、さらにドゥブノ到達を目指すことになった。
第三六歩兵兵団と第一九機械化兵団もまたその地帯に近づきつつあったので、ドゥブノ到達が目標となった。
ドゥブノ地帯争奪のための激しい戦闘は、六月二七日に始った。
敵もすぐに第五五兵団をドゥブノに向けたため、かろうじて彼らは全滅はまぬがれた。
しかし、敵は大きな損害を被り、他の方面から兵力をさいてドゥブノに回すというようなことをしなければならなかった。
しかし、わが方もまた敵兵力を完全に打ち崩すことはできず、攻撃を食い止めるだけに留まったが、主な目的は達せられた。
ウクライナの首都キエフに向って進撃を続けていた敵の前線部隊は、ブロドイ〜ドゥブノの線でくい止められ、しかも弱体になっていた。
六月二四日午後五時『ボド・ライン』(訳注―秘密通信線)を通じて私は第五軍司令官ポタポフ大将と話合った。
対話内容について述べる前に、ポタポフ大将を紹介すると、彼は非常に経験のある将軍で、ハルヒン・ゴールの戦闘ではよい実戦経験をもっていた。
大胆で、しかも頭のきれる司令官だったので、ドイツの司令官も一度ならず痛い目にあわされ、第五軍の実力は敵方にも知れわたっていたのである。
この対話は、戦争の開始期の模様を特徴的に説明しているので、要点を書くと次のようである。
ジューコフ:状況を説明してくれたまえ。
ポタポフ:ブラドフ〜ウスチルグの戦線では、歩兵部隊約五個師団と戦車約二〇〇〇が戦っています(戦車の数は非常に誇大になっていた)。
敵戦車の主要部隊は、ドペンカ〜ゴロドフの戦線に展開しています。
ウスチルグからソーカリまでには、第一四装甲師団とともに歩兵約六個師が配置されています。
この装甲師団の主要な前進目標は、ウラジーミル・ボリンスク〜ルーツクの線です。
第五軍と第六軍との接する辺りには、兵力は極秘となっている機械化部隊が配置してあります。
敵は、主要な攻撃をウラジーミル・ポリンスクからルーツクの線に集中し、ブレスト・リトースクからコーペリにかけた線を補助攻撃するという形をとっています。
一九四一年六月二四日、午後二時二〇分現在のわが軍の状況を報告します。
フェジュニンスキーは、プレメッツ〜クスニーシチ〜ビシニェフ〜ニキーチッチにわたる戦線を守っています。
彼の率いる第八七歩兵師団のうち二個連隊はウスチルグの要塞地帯を守っていますが、敵に包囲されており、弾丸が不足しています。
第二一四師団については、昨日以来連絡がたたれています。
第四一戦車師団はマツェユフ〜セント・コシャルイの間を守っていますが、戦闘の後で現在資材の整備に当っています。
第一三五師団は、第一九戦車連隊および第八七歩兵師団に属する一連隊と協力してウラジーミル・ボリンスクの線を攻撃していますが、この戦闘には第一対戦車旅団と砲兵兵団の全部も参加しています。
ルーツクは現在のところ各方面ともに防衛されています。
しかし、その防衛線はまばらで、特に私の心配しているのは、南方からの敵戦車の攻撃です。
これは、二つの戦線にわたって危機を与えることになるでしょう。
現在私の指揮下には、南方からの攻撃を食い止めるにたる兵力は一兵も残っていません。
爆撃機の強力な援助によって、ドベンカ〜ゴロドロの線を敵戦車が突破するのを妨げてもらうと同時に、ブレスト・リトースク方面からの戦車の進出も食止めてもらいたいと思います。
さらに、地上軍および航空部隊の協力で、ウフジーミル・ボリンスク地帯にいる敵部隊を壊滅してもらいたいのです。
予備の部隊は全部出払ってしまいました。
第九機械化兵団は、旧型戦車二〇〇台までを、二日以内にオルイリの地帯に集結することはできます。
電話線はいたるところで断ち切られています。
いくら修理しても、じきにまた敵飛行機の爆撃でやられてしまうのです。
歩兵部隊との無線連絡手段は確保しています。
今後の行動について指示をお願いします。
ジューコフ:
一、あなたの隣接部隊は、プルジャヌイ〜ゴロジェッツの地帯で戦闘を続けている。
敵軍は、ブレストからコーベリに向って進出してきたが、これは、コロプコフの不用意な戦闘の結果によるものである。
あなたは、ブレスト・リトースク方面に部隊の主翼を向け、敵のコーベリヘの接近を阻止してほしい。
二、カミオンク〜ストルミーロフ〜ラバ・ルースキーの北の一帯、およびさらに遠く国境にそった辺りの戦闘は、ムズイチェンコによって成功裏に遂行されている。
しかし、敵はおびただしい戦車隊を繰出して、第五、第六軍の開の防衛線を破り、いまブロドイを占領しようとしている。
三、カルペゾとリャブイシェフの二地点では次の方向に対して反撃を行なっている。
カルペゾは、ブロドイをこえて北西へ。
そのため、この地帯の主要な戦闘は、おそらく、ブロドイの北西一五キロほどの地点で行われているはずである。
リャブイシェフでは、左翼、つまり北方への進出が目指されており、ここの戦闘は、あなたのところの戦闘を助ける結果になるでしょう。
反撃の目的は、ブロドイ〜クルイストイノ〜ピリからさらに北方にかけての辺りの敵をせん滅し、そうすることによって、あなたに部隊を集結し、強力な戦線を建直す余裕を与えようというものです。
ルーツク地区、さらにそこから北方および南方にかけては、第一九、第九両機械化兵団と歩兵二個兵団とが、あなたの部隊を強化するために配置されるでしょう。航空部隊についても、処置がとられています。
あなたからの無線連絡は、当方では全然受信されていない。またそちらでも読解がなされていない。
無線発信と読解に関して、技術的な誤認をなくすために、専門家を飛行機でそちらへ差向けます。
繰返す。
北方からのコーベリヘの敵の接近を断固はねのけること。戦車なしで歩兵部隊を反撃行動に繰出さないこと。
これは、全然効果がない。砲、弾薬を第八七歩兵師団に必ず提供してやってほしい。
夜間、この部隊を敵の包囲から抜け出させることは可能かどうか?
あなたのところのKV型その他の戦車の活動状況はどうか。敵の兵器を破壊する能力はどうか?
あなたの戦線で、敵は大体どのくらいの戦車を失っているだろうか?
ポタポフ:現在私は、指揮下に、飛行機四一台(今朝現在)をもつ第一四空軍師団を配属されています。
方面軍からの命令によると、我々は、さらに第六二、第一八の両爆撃師団も配属されていることになっているのですが、この両部隊については、私は、何の連絡も受けていないし、どこにいるのか。
当方からの連絡の手段もありません。戦車は大型KV三〇台をもっています。
しかし、一五二ミリ砲用の弾薬を受取っていません。
さらに、T26型とBT型、それに旧型のもの若干ですが、その中には二重砲塔のものも含まれています。
敵戦車は、約一〇〇台を破壊しました。
命令はよく分りました。しかし、その完遂の保証はできません。
ともかく、フェジュニンスキーの右翼戦線をまげて、北からの敵の接近を阻むために全力をつくしてみましょう。
敵戦車はいまのところラトノ地区におります。
私としては、命令遂行のために、早速行動に移ります。
ジューコフ:KV型戦車の一五二ミリ砲は、09〜30グラム弾を用いる。
それ故、09〜30グラム弾として至急発注し活動を開始してくれたまえ。
そして、総力をあげて敵戦車をたたきつぶしてほしい。
その他の援助は、私がアレンジします。
私は、特にあなたとニキシェフに期待をかけています。
今夜か明日には、そちらへ行きます。さようなら。 |
ドイツ軍としては、キエフ方面の戦線の攻勢を持続するためには、相当な兵員と数百台の戦車を乗組員ともども予備部隊からフォン・クレイストの部隊に補充してやらねばならなかった。
従って、もし、南西戦線の部隊で、空陸両方面での偵察活動がよりよく組織されており、相互の連絡や部隊統率がもっとうまくいっていたら、わが方の反撃の成果はずっと効果的だったろう。
これらの戦闘で、一番目ざましい働きを示したのは、コンドルーセフ少将指揮下の第二二機械化兵団とリャブイシェフ指揮下の第五方面軍所属第二七歩兵兵団と第八機械化兵団とだった。
カルペゾ大将指揮下の第一五機械化兵団は与えられた任務は遂行したが、残念ながら総力を完全に出しきれなかった。
ドイツ軍の第三戦車隊司令官ホット大将が、その回想録の中に書いているこの頃の戦闘の評価は、なかなか興味がある。
それには次のようにのべられている。
「一番苦しい戦いに当面したのは『南』の部隊だった。
北翼の軍の前に立ちはだかった敵軍は、初めのうちこそ国境から退却したが、すぐにその打撃から回復し、予備軍や後方から繰出してきた戦車隊と合体してドイツ軍の進撃を食い止めた。
第六軍に所属した第一戦車隊の進撃は、六月二八日までは開始されなかった。
ドイツ軍の進撃の道には、敵の強力な攻撃が待っていた」
その頃、モスクワのワトゥーチン大将との電話連絡を通じて、私には次のような事情が分った。
西方と北西両方面軍においては、司令官や参謀たちがまだ、所属各軍司令官だちとしっかりした連絡関係をとりつけていない、ということだった。
師団や兵団の司令部は、隣接部隊との協力も、空軍の支援も、上級からの適切な命令もなく、孤立した戦いを続行していたのである。
ワトゥーチンの報告から、西方と北西両方面軍で特に事態が深刻になってきていることが分った。
それにまた、スターリンがいらいらして、西部方面軍の司令官や参謀たちが無責任すぎるとし、特にクーリク元帥の無策を非難していることも分った。
西部方面軍参謀部に配属されていたシャポーシニコフ元帥の知らせによると、クーリク元帥は、六月二三日の朝は第三軍の参謀部にいたはずだったが、連絡は全然とだえていた。
しかし、しばらくして参謀本部は、各方面の情報を総合して敵の機甲部隊と機械化部隊の大編隊が、西部方面軍の各所を破壊して白ロシアから沿バルト国境辺にかけて急進撃を続けていることがやっと判明した。
ソ連国民にとって、きびしい事態が始っていたのである。
最近では参謀本部は、なぜ国内の主力部隊を動員して国境に配置し、敵を撃退しなかったのだという非難が普通になっている。
しかし、私は今でも、たとえそういうことをやってみたところで、それがよかったか悪かったか断言することはできない。
わが軍は、対戦車、対空両方面で敵に対抗するだけの実力はなかったし、また機動性にもとぼしく、せきを切ってなだれこんでくる強力な敵装甲部隊の進撃を支えられ得るものではなかった。
国境警備の部隊がどんな苦しい破目におち入っていたか想像はついていた。
しかし、もし主力部隊を国境に移してしまっていたら、その後、モスクワやレニングラード、南方で、事態はどう進展していたか?
六月二六日早朝、ワトゥーチン大将は、テルノーピリの司令部にいた私に次のように伝えてきた。
「沿バルトと白ロシアの状態が、極端に悪化してきた。そのため北西方面軍の第八軍をジガに差向け、第一一軍もポロック方向に転回さしてもらいたい。後の補強には、モスクワ軍管区から第一二機械化部隊が差向けられる」
スターリンは、予備方面軍の構成を命じ、それをスーシチェボ〜ニェーベリ〜ビチェプスク〜モギレフ〜ジュロービン〜ゴメリ〜チェルニゴフ〜デスナ川〜ドニェプル川の線に配置することを命じた。
この予備方面軍は、第一九、二〇、二一、二二軍によって構成されていた。
実をいうとこの戦線は、この年の五月に、チモシェンコ元帥をはじめとする国防人民委員部と我々参謀本部のものと一緒に下検分をすませていたところだった。
方面軍司令部や参謀本部のメンバーも、最高軍司令部のスタッフでさえも、この当時まだ、わが国境線に展開していた敵軍について、総体的な完全な情報はとらえていなかった。
戦車、空軍、機械化などの敵の各部隊について、最高軍司令官が戦線から入手した情報は、明らかに誇張されていた。
戦争の初期の段階のこの辺の事情については、その後いくつかの文章や本が書かれているが、概して一定の意図をもって書かれたものが多く、公正な専門的な判断にかけている。
一七〇のソ連師団は、戦争の直前、バレン卜海から黒海にのびる四五〇〇キロにわたる国境戦線に深さ四〇〇キロをもって全般に配置されていた。
しかし、ここで注意しておく必要のあることは、この四五〇〇キロの間は、陸の国境線は五つの方面軍によって守られていたが、海岸線は、沿岸警備隊や海軍の守備範囲になっていた、ということである。
しかも、レニングラードからタリンにわたる海岸線は、全然防備がなかった。
それ故、現実には、一七〇個師の守っていたのは、三三七五キロにしかわたっていなかったのである。
しかし、防衛線の深度は、場所によってかなり違っていたのである。
北部方面軍(レニングラード軍管区)についていえば、その守備範囲は一二七五キロで、そこに二一個師と一歩兵旅団が配置されており、一個師団の守備範囲は約六一キロになっていた。
沿バルト、西部、キエフ、オデッサ各軍管区の陸地防衛地区は、長さ一二〇〇キロで、ここに一四九個師と一旅団が展開していた。
この最重要な地点で一個師団として、平均一四キロが割当てられていたのである。
こういう配置が、戦争直前には次のような構成になっていた。
沿バルト軍管区――二五個師、一歩兵旅団。この旅団は四戦車、二機械化各師団をもつ。西特別軍管区――二四歩兵師団、一二戦車、六機械化、二騎兵各師団。オデッサ軍管区――一三歩兵、四戦車、二機械化、三騎兵各師団。
このようにわが軍編成上の最強の構成は、南西方面に向けられていたのである。
そこには、歩兵師団四五、戦車師団二〇、機械化師団一〇、騎兵師団五が集中されていたわけになる。
この西方四方面軍に属する一四九師団と一旅団のうちで、四七個師団が、先ず第一線部隊として国境線から一〇ないし一五キロにわたって展開されていた。
国境軍管区の最強部隊は、国境線から八〇ないし三〇〇キロ入った辺りに展開されていた。
沿岸地帯は、海軍によって防衛され、海岸線は主として砲兵部隊によって守られていた。
国境線の直接の警戒は、内務人民委員部の国境部の管轄だった。
軍の指導者はだれでも、上からの命令は、たとえそれが問違った行動と知っていても、その行動の責任は自分が負わねばならなかったし、その間違いを上級の責任に帰する、というようなことはできなかった。
軍隊とその司令官は、常にその責任範囲で軍務を遂行できる態勢にあらねばならなかった。
そんな関係で六月二二日の夜にも、国境に展開していた。
編隊、編成の若干の指擇官たちは、すでに国境の彼方からキャタピラの響きやエンジンの音が伝わってきていても、最後まで上からの命令を待ち、必要な軍事行動の開始を抑えていたのである。
このような状態の下にドイツ軍一五三個師は、またたく間に行動に移り、そのうち、二九個師が沿バルト地区に、五〇個師が西部特別軍管区に、三三個師がキエフ特別軍管区にほこ先を向けてきたのである。
さらに二四個師が予備隊として、主要戦線の後方から進軍していた。
一五ないし一六個師が、わが南方戦線の第九、第一八軍に向けられ、約五個師がフィンランド戦線に配置されていた。
戦争初期のこうしたデータは、主として、捕虜の口から、ないしは分取った各種文書から知り得たものである。
当時、スターリンも国防人民委員部当局も、また参謀本部も、わが方の情報に基いて、ヒトラーの司令部は、西欧、その他の占領地域に、その陸上部隊、航空部隊の少なくとも半分の勢力はクギづけにしておかないわけにはいくまい、とみていた。
しかし現実にはドイツ軍は、その方向には三分の一たらず、しかも二軍的な能力のものを残しただけだったし、その数もその後どんどん削減していったのである。
敵の編成は「北」「中央」「南」となっていて、三七一二台の戦車と爆撃兵器とを駆使していた。
地上部隊は、四〇五〇台の飛行機によってその活動を援助されていた。
砲はわが方のほとんど二倍をもち、しかもそれらの運搬手段は、ほとんど機械化されていたのである。
こういう大軍が、予め戦略的重要地点に全部展開ずみになっていて、いっせいに攻撃を仕かけてきたわけで、我々としては敵の第一撃の能力を総体的に予め知り得る立場になかった。
国防人民委員部も私も、先任のシャポーシニコフもメレツコフやその他参謀本部の指導部も、敵の機械化、装甲部隊が集中編成され、戦闘開始のその日にわが戦線に楔を打ちこむ目的で配置ずみになっていようとは全く考えていなかった。
おまけに、ちょうど開戦直前に、西部軍管区の第一〇軍と若干の部隊が、敵に背を向けた位置にあるベロストックの突出部に展開していたのである。
第一〇軍は、一番都合の悪い状態にあった。
こういう不利な態勢は、敵に、グロドノ、プレスト方面のわが軍を、翼を広げたような形で深く、広く包囲してしまう可能性を与えたのである。
一方でまた、わが軍のこの方面の勢力は、敵の楔を打ちくだいて、ベロストックの部隊と手をつなぎ得るほど強力ではなかった。
敵の主力が、グロドノ、ブレストの地域で包囲の網をしめっけ始めたとき、第一〇軍とその翼にのびた第三、第四軍は、速やかに包囲状態を抜け出し、後方に撤退して、最も脅威を受けている部分の防衛に当るようにすべきだった。
そうすれば、そこで抵抗していた味方部隊の反撃力を強めるのに大いに役立ったはずである。
しかし、こういう作戦は行われなかった。同じような作戦の間違いは、南西方面軍についてもみられており、そこでも撤退が遅れている。
最高軍司令部と参謀本部のおかしたもう一つの間違いについてもふれておく必要がある。
この問題は前にもふれているのだが、それは、一九四一年六月二二日付の反撃に関する第三号指令に関するものである。
反撃問題の討議に当って、最高軍司令部当局には、六月二二日に起った現実の事態が少しもつかめていなかった。
戦線の司令官もまた事態が分っていなかった。
最高軍司令部は、現実の情勢や基礎的事実の分析によらずに、戦闘の危険な段階では特にさけられねばならない、直感や希望的観測に基いて決定を行なったのである。
六月二二日の夕方の混乱した状態の下では、楔を打ちこんでくる敵の装甲部隊の鼻先に、味方の機械化部隊をぶっつける以外に手はなかった。
ところが、反撃手段はほとんどが生半(なまはん)かで、目指す目的を達することはできなかった。
戦争の当初の欠陥はまだある。
一部の司令官たちは、自分の指令すべき正しい位置から適切な指揮を行うかわりに、また隣接部隊や戦線本部と連絡をつけるようなこともせずに、他の部隊の情勢におかまいなしにやたらに指令を与えていた。
そのために、各部隊の指揮者は、とまどってしまうだけだった。
上級司令部とのしっかりした結びつきもなく、自分が適切と思う方法で行動を余儀なくされ、しばしば隣接部隊に損害を与えていたのである。
たとえば、グロドノから第三軍が、ブレストから第四軍が勝手に撤退してしまったために、ゴルペフ少将の指揮下にあった第一〇軍の情勢は急激に悪化した。
幸い第一〇軍は、オソベッツ要塞地帯にたてこもっていたので、そう敵に圧倒されることもなく戦闘は続行していた。
西部方面軍副司令官ボルジン少将がその方面の救助に向い、第六、第一一機械化兵団と第六騎兵部隊とを合わせて騎兵、機械化合同部隊を編成しようとした。
そして、六月二三日に、スバルキ突出部から、敵の出鼻に反撃をしかけたのである。
これは失敗に終った。
ポルジン少将は、反撃のための全部隊の集結に成功しなかったのである。
原因は、指揮系統がバラバラだったということで、敵は、わが軍の主導権を抑えてしまったのだ。
六月二四日には、クロドノ地域で激戦が展開された。ここでは敵は、空軍力でまさっていたにもかかわらず苦しい戦いを行わねばならなかった。
敵「中央」軍集団の司令部は、さらにここに二個軍団と第三戦車兵団の一部とを投入することを余儀なくされている。
流血の戦闘は二五日一杯続いたが、反撃のための適切な物資、技術の供給がなく、どうしてもうまく効果的な打撃を相手に与えることができなかった。
この戦闘で、敵は大きな損害をこうむり、後退し始めた。敵の戦車部隊は燃料の不足から、沢山の物資を後に置去りにしていった。
この戦闘で、ハツキレビッチ兵団長が戦死した。
彼は優れた司令官で、勇気のある人だった。
この人と私のつき合いは古く、三〇年代二人がまだ騎兵部隊にいたときからのものである。
さらにニキーチン大将もここで死んだ。彼も騎兵部隊の司令官として、賢明で大胆という評判が高かった。
西方の戦略地帯で、なんといっても、敵が、歩兵、空軍の最強力部隊をぶつけてきたのはモスクワに向けてだった。
西部方面軍に対しては、敵は「中央」軍集団を当て、その構成は、合同編成になる第四、第九両軍と、第二、第三の二戦車兵団からなっていた。
さらに「中央」軍は、第二空軍部隊の支援を受けていたが、この部隊は垂直下降爆撃機だけでできた兵団だった。
また「中央」軍集団は、砲、機械、技術、建設の各部門にわたる部隊をもち、十分な物資の補給も受けていた。
ともかくこの戦線では、ドイツ軍は攻撃手段のあらゆる面で、ソ連軍の五ないし六倍の優勢を誇っていた。
ほとんどの部隊の活動は、ちゃんと空軍の援助の下に行われていた。
ブレスト地域の戦闘は、ますます苦しくなっていた。
それでも敵は、ブレスト要塞守備軍の抵抗を完全に打ちくだくことはできず、包囲された英雄たちは、貴重な損害を相手に与えていた。
ドイツ軍にとって、ブレスト要塞のソ連将兵の英雄詩は、全く予期していなかったものだった。
グーデリアンの装甲戦車部隊と第四野戦部隊は、遂にこの土地をバイパスすることを余儀なくされたのだった。
コロプコフ少将指揮下の第四軍も、グロドノ地区のクズネツォフ少将指揮下の第三軍と同様敵の攻撃を受けていた。
この第四軍は、英雄的なブレストの部隊をその指揮下に入れていたのだし、そう遠くなく、第三二戦車師団、第六、四二、四九、七五各歩兵師団が展開していたのだから、もっとずっと効果的な戦いが遂行できたはずなのである。
残念ながらそういうことは、第一四機械化兵団がそこへ配置されても、なお実現をみることはなかった。
それでは当時、このミンスクに近いあたりでは、事態はどうなっていたのだろう?
この方面軍の司令官はパウロフ軍大将だったが、彼は、第三、第一〇、第四各兵団の状況を知らず、また、楔を打ちこもうとする敵装甲戦車部隊の攻撃についても何の見通しももたず、まるで事態にそぐわない命令を再三にわたって下していたのである。
最高軍司令部の指示に従って、パウロフ大将は、第三および第一〇軍に対して、東方に撤退してジダ〜スロニム〜ピンスクの線の防衛に当るように命令している。
しかし、この命令はとても遂行できるものではなかった。
というのは、これらの部隊は半ば敵の包囲状態にあり、すでに勢力を消耗し、敵空軍と裝甲戦車部隊のひっきりなしの攻撃の下にやっと生残っている、という状態におかれていたのだった。
六月二六日には、敵の第三九機械化部隊が、ミンスクの防衛をつき破るべく接近してきた。
そこで彼らは、ユシュケビッチ大将指揮下の第四四歩兵兵団と衝突することになる。
さらに、ミンスクの防衛強化の目的で、北西モロデチノ方面から第二歩兵団が急きょ進撃していた。
この部隊は、エルマコフ少将の指揮の下にあり、第一〇〇および第一六一歩兵師団からなっていた。
この第一〇〇師団は、レーニン勲章を受けており、司令官はルシャノフ少将だった。
私が第四コサック師団の司令官としてスルックにいたとき、彼は、ドイツ・プロレタリアートという名前の第四歩兵師団の連隊長として評判がよかった。
野戦に関する訓練においても戦闘行動においても、ルシャノフ連隊は、戦術的に優秀で、訓練と秩序がい際立っていた。
今度この編成部隊が、ミンスク近くで敵第三戦車部隊と遭遇し、彼らに甚大な打撃を与えることになったわけである。
ところが、敵のグーデリアン戦車部隊の第四七機械化兵団がミンスクの南西に接近してきた頃、味方防衛軍の状況は、極度に悪化していた。敵は先ず、ミンスクを盲爆した。
市全体が炎に包まれた。数千人の非戦闘員が死んだ。
何の罪もない人々は、死に当って、野獣化したファシストの飛行士をのろった。
敵がミンスクに近づくにつれて、戦闘は激しいものになっていった。
特に、第六四、第一〇〇、第一六一歩兵師団の将兵たちはよく戦った。
彼らは、数百台の敵戦車を破壊し、数千のファシストを殺した。
ちょうどそんなころ、六月二六日だったが、テルノーピリの南西方面軍司令部にいた私に、スターリンから電話がかかってきた。
スターリンは私に次のように話した。
「西部方面軍で、事態が急迫してきた。敵はミンスクに近づいている。
パウロフのところで何が起っているのか全く連絡がない。
クーリク元帥もどこにいるのか不明である。
シャポーシニコフ元帥が病に倒れてしまった。
あなたには、すぐにモスクワに飛行機で帰ってきてもらえないだろうか?」
「すぐにキルパノース、プルカーエフ同志たちと事後の相談をした上で、飛行場にかけつけましょう」と私は答えた。
六月二六日の夕方遅く、私はモスクワに到着し、飛行場からまっすぐスターリンのところへかけつけだ。
スターリンの書斎には、チモシェンコ国防人民委員と私の第一代理であるワトゥーチンが直立不動の姿勢で立っていた。
二人とも青ざめ、そうそうとしており、不眠のため目は真赤だった。
スターリンも、元気というわけにはいかなかった。
ちょっと会釈して、スターリンはすぐ話し始めた。
「この緊急事態に当って、どうしたらよいのか、一緒に考え、意見をのべてほしい」
そして西部戦線の地図を机の上に投出した。
「四〇分ほど余裕をください、判断を下すために」と私はスターリンに言った。
「よろしい、四〇分後に報告してくれたまえ」
我々は隣の部屋に移り、事態の分析を行い、西部戦線での可能な手段を話合った。
その地域の状態は、まことに暗澹たるものだった。
ミンスクから西は包囲されており、第三、第一〇軍の残存部隊は、比較にもならない数の敵軍を引受けて戦っていた。
第四軍の若干の部分は、プリピャト森林地帯に後退していた。
ドクシツィ〜スモレビッチ〜スルツク〜ピンスクの線を守っていた部隊も、手ひどい損害を被ってチリヂリバラバラになって、ベレジナ川の辺りまで引下がっていた。
しかも、こうして弱った部隊に対して、強力な敵部隊の追撃は引続いて行われていた。
いくら話合ってみても、防衛線をすぐにデスナ〜ポロツク〜ビチェブスク〜オルシャーモギレフ〜モズイルの線にさげ、その防衛線に、第一三、第一九、第二〇、第二一、第二二の各兵団を当てる、という以外の考えは出てこなかった。
さらに、後方防衛線として、最高軍司令部の第二四、第二八予備部隊をセリジャロボ湖〜スモレンスク〜ロボムの線に緊急に配置するというものだった。
それにもう一つ、急きょ二ないし三兵団を新しくつくり、モスクワ守備師団とすることについても提案した。
スターリンは、これらの提案すべてを承認したので直ちにそれに必要な命令が発せられることになった。 |
我々はこれらの提案に当って、モスクワへの敵の接近につれて、防衛線をいかに深く、厚く構成するか、ということに主要な注意をそそいだ。
それは、敵を疲れさせ、防衛線の一つ一つで彼らを停滞させ、その間に反撃の態勢を整えようとするもので、そのためには、極東においても必要な兵力を構成し、新しい部隊構成を行う必要があった。しかしさて実行に移す段になると、どの辺で敵をとどめ、反撃開始のためには、どの辺りが好都合なのか、どんな部隊を編成したらよいのか、当時は何も分っていなかった。
ほんの思いつきにすぎなかったのである。
六月二七日午前一〇時五分、最高軍司令部の指令は私によって『ボド・ライン』を通じて、クリモフスキフ方面軍参謀長に伝達された。
その内容は次のようなものだった。
「ジューコフ 最高軍司令部の名において指令を伝える。
貴官の任務
第一、緊急にすべての部隊の所在をつきとめ、各司令官に連絡をつけ、彼らに戦況、敵の状態、味方の部隊の状況を知らせること。
特に、敵の機械化部隊がどこまで食いこんできているか、その場所を詳しく知らせる。
また、わが方の燃料、弾薬、食料の基地がどこにあるかを知らせて、各部隊に対して、これらの基地から戦闘に必要なものを受取らせるようにする。
各部隊に対し、戦闘の続行が可能か、森林地帯に引下がらざるを得ないかを含めさせる。
森林への撤退部隊に対しては、どの道を通って、どの部隊へ集合するか指示する。
第二、貴重な機械、特に重戦車や重砲を置きすてにしないために、必要な部隊に対しては、飛行機で燃料と弾薬を与えるむね伝え、その向きを報告させる。
第三、すべての残存部隊は、次の三方向にそって撤退する。ドクシッイ、ポロックを通って、レペリスキーおよびポロッキーの要塞地帯に集結するもの。
ミンスク辺の部隊はミンスク要塞地帯に集る。第三の方向は、グルースキー森林を抜けてボブルイスクヘ集結する。
第四、敵の第一線の機械化部隊が、歩兵部隊をはるか後方に引離してしまっている状態に注意を向けること。
この状態はいまや敵の弱点になってきている。
204
機械化部隊は歩兵から引離され、歩兵部隊は戦車なしで行進しているからである。
もし、貴官所属の司令官で、そういう敵部隊――特に機械化部隊をとらえることができたなら、これを壊滅してほしい。
第一線にのびすぎた機械化部隊でもよいし、引離されて戦車なしに行進している歩兵部隊でもよい。
さらに可能なら、先ずミンスクとボブルイスクに向って行進中の第一線機械化部隊の背後から強力な攻撃をしかけ、さらに可能な場合、転回して後続の歩兵部隊にかかってもらいたい。
この種の大胆な戦略は、西部戦線の敵のキモを冷すに十分である。
特に成功が期待されるのは、機械化部隊に対する夜間攻撃である。
第五、騎兵部隊はピンスク森林地帯に撤退すること。
そして、ピンスク、ルニニェツツを基地に、敵部隊の背後、ないしは部隊そのものに対して果敢かつ広範な攻撃をしかけること。
騎兵の散在している小部隊は、頼りになる勇敢な中級指揮官を中心に、あらゆる道路にそって展開すること」
六月二八日午後二時、私は、直接通信線を使ってクリモフスキフと話合い、命令に対する補足説明を行なった。
その会話の要点を次に引用してみよう。
ジューコフ:第三、第一〇、第四兵団について何か判明したか、ミンスク市はどちら側に属しているか、また敵はどこにいるか、これらについて知らせてほしい。
クリモフスキフ:ミンスク市は依然わが軍の手にあります。
通信が入りました。ミンスクとスモレビッチに敵の降下部隊が降りました。
しかし、ミンスクの第四四歩兵部隊の努力で、降下部隊は排除中です。
敵飛行機は、ほとんど毎日ボリソフ〜オルシャ間の道路を爆撃しております。
駅や線路施設に被害をうけています。
第三兵団との無線連絡は、まだついていません。
一番新しい報告によると、敵は要基地帯の前面まで到着しました。
ゼフノビッチ、ボブルイスク、プホビッチは、夕方まではわが軍の手にあります。
ジューコフ:クーリク、ボルジン、コロブコフ各司令官たちはどこにいるのか?
機械化部隊と騎兵部隊の所在は?
クリモフスキフ:クーリクとボルジンからは連絡はたえています。コロプコフとは連絡がついています。
彼は、ボブルイスクのさらに東の自己の司令部におります。
ハツキレビッチの部隊はバラノビッチヘ向って移動しており、アフリュースチンの部隊はストルプッツィヘ向って移動中です。
ジューコフ:ハツキレビッチとアフリュースチンの部隊はいつ移動を始めたのかね?
クリモフスキフ:この地帯の移動は、六月二六日の夕方頃から始ったものです。
昨日の午後七時頃、スペトリツィン兵団副司令官が彼らのところへ飛びました。
明日は、クズネツォフとゴルベフに命令を伝達させるために落下傘兵士を送るつもりです。
ジューコフ:第二一歩兵兵団が、モロジェチノ、ビレイカ地帯に回ってうまく放退できたかどうか知っているかね?
クリモフスキフ:第二一歩兵兵団については、彼らがモロジェチノ方面に向って撤退をはかっている、という情報は得たのですが、その後これらの情報を確認する何の手がかりもないのです。
ジューコフ:重砲はどこにあるかね?
クリモフスキフ:大部分の重砲は、味方の手にあります。第三七五、第一二〇曲射砲連隊については全く手がかりがありません。
ジューコフ:騎兵部隊はどこにいるか、また第一三、第一四、第一七機械化兵団の所在は?
クリモフスキフ:第一三機械化兵団はストルブッツィにおります。
第一四兵団については、数台の戦車が残っているだけで、ゼフノビッチにいる第一七兵団に吸収されました。
騎兵兵団の所在についての情報はありません。
コロプコフは第四二、第六、第七五師団の残存部隊を救出しました。
第四九歩兵師団もベロペリスキー森林にいるとみられる確かな根拠があります。
これを確認し、救出するために、明早朝に特別落下傘兵士を送ります。
クズネツォフの脱出は、ニェマン川の両岸にそってできると見ています。
ジューコフ:ミンスク要塞地帯の前面まで到着していた敵の機械化兵団は、今日はどんな状態にあるかね?
昨日、スルックとミンスク前面にいた敵は、いまどうしているかね?
クリモフスキフ:ミンスク要塞地帯前面の敵は、わが第六四歩兵師団と戦端を開きました。
スルックからの敵は、ボブルイスクに向って進行中です。
しかし、夕方までにボブルイスクが占領されているということはあり得ません。
ジューコフ:どうして、あり得ないのかね?
クリモフスキフ:我々も、敵はわが軍を追いかけてボブルイスクにそのまま突入して来る、とみていたのです。
ところが、そうなっていないのです。
ジューコフ:敵がミンスク要塞を北から包囲しない、ということに注意を向けたまえ。
ロゴイスク、センヒン、プレシェニッツィの方向を固めなさい。
さもないと敵は、要塞をバイパスして、あなたより早くボブルイスクに入ってしまうかもしれない。
もう話すことはない、さようなら。 |
兵士、指褌官たちの一致した英雄的行為にもかかわらず、また部隊長たちの勇敢な抵抗にもかかわらず、西部戦線の一般的状況は悪化の一途をたどった。
六月二八日夕刻、わが軍はミンスクから撤退した。
ミンスクに突入した敵軍は、野獣のように民家をこわし、火をつけ、文化的施設や国の記念物を破壊した。
最高軍司令部も参謀本部も、白ロシアの首都を敵の掌中に渡したことに深く心をいためた。
すべて我々は、東方へ撤退しおおせなかった市民たちの受けた苦難の深さを知っている。
六月二九日、スターリンは二度、国防人民委員部と最高軍司令部へやってきた。
来るたびにスターリンは、西部戦略地帯での苦しい状態についてふれ、深く悲しんだ。
六月三〇日、午前六時四五分、国防人民委員チモシェンコ元帥の命令で私は、方面軍司令官パウロフ軍大将と『ボド・ライン』を通じて会話した。
この会話でも分る通り、司令官自身戦況をはっきり把握していなかったのである。
会話の内容は次のようなものだった。
ジューコフ:ミンスク、ボブルイスク、スルックの地帯に何が起きているのか分らないので、我々は、西部戦線について何の決定もできない状態にある。
事件の実態を知らせてもらいたい。
パウロフ:ミンスク地域では、第四四歩兵兵団がモギレフスキー街道にそって南へ撤退しています。
新しい防衛線としてスタホフ〜チェベニが指示されています。
スルツク地域については、昨日の偵察飛行の報告によると、第一二〇機械化師団がシセッツィで戦闘中でした。
ポブルイスク地域では本日午前四時、敵は橋をかけ、その上を戦車一二台が行進しています。
ジューコフ:ドイツ軍がラジオで伝えているところによると、ベロストックの東方で二個兵団が敵に包囲されているということである。
察するに、これは満更のデタラメではないようだ。
なぜあなたの本部は、軍隊を探すために代表を派遣する努力を怠っているのですか?
クーリク、ボルジン、クズネツォフの所在はどこですか? 騎兵兵団の所在地は?
飛行機で騎兵の所在が探し出せないはずはないのだがね。
パウロフ:その通りのはずなのです。
我々の知り得ている限りでも、六月二五、二六日の両日は、シャーフ川の辺に味方の部隊がいて、シャーフ川の東岸を占領していた敵軍と渡河争いの戦闘が行われています。
第三軍は、シャツ川の両岸にそって撤退をしようとしていました。
第二一歩兵兵団はジダ地域にいました。
これらの兵団との無線連絡はついていたのです。
ところが昨日からは連絡がないのです。
敵が放送しているあたりで、味方の兵団が包囲から逃れようとしていることは確かです。
騎兵隊の所在は飛行機では分りません。というのは、彼らは敵の爆撃をさけて、森の中に分らないようにすっかり入りこんでいるからです。
探索のための無線設備をもったグループも派遣されています。
しかし、クーリクがどこか、わが部隊がどの辺に散在しているのか、これらの偵察グループから、これまでのところ何の情報も入ってきていないのです。
ボルジンもクズネツォフも、ゴルペフ同様、六月二六日までは部隊と一緒だったのです。
ジューコフ:あなたの基本的な任務は、できるだけ早く味方の各部隊を探し出し、彼らをベレジナ川のこちらへ撤退させる、ということです。
この仕事は、自分で直接監督し、そのために能力ある陸上、航空の司令官たちを任命し、使うことはさしつかえありません。
最高軍司令部では、最短時間に部隊を集め、彼らを適当に誘導する任務をあなたに与えています。
いかなることがあっても、敵部隊をしてボブルイスクないしはボリソフの地帯に侵入させることがあってはいけません。
オルシャ〜モギレフ〜ジュロービン〜ロガチェフの防衛線に軍隊を集結する作業は、絶対に失敗を許さない性質のものです。
自ら戦闘を指導し、ボブルイスクで何が起っているかあなた自身知るために、あなたの副官の指揮の下に、無線設備を用意した指揮者のグループを派遣してほしい。
物資は、敵の手中におちないため、直ちに撤収したまえ。情勢が判明次第、時を移さず何でも報告してほしい。
パウロフ:ボブルイスクとボリソフの防衛線維持のためには、全部隊を動員します。『学校』でさえも。 |
しかしながら、状況は少しもよくならなかった。
六月三〇日、スターリンは参謀本部の私に電話してきて、西部方面軍司令官パウロフ軍大将をモスクワに召還することを命じた。
翌日、パウロフ軍大将は到着した。危うく彼を見間違いするところだった。
パウロフ軍大将は、戦争の八日間にゲッソリやせてしまっていたのである。
その日彼は方面軍司令官の地位を奪われ、その後裁判にかけられた。
西部方面軍軍事委員会の提案に基いて、パウロフ軍大将と一緒に、参謀総長クリモフスキフ大将、方面軍通信司令官グリゴージェフ大将、砲兵司令官クリチ大将その他同方面軍の指導将官たちも裁判にかけられた。
西部方面軍司令官には新しく国防人民委員のチモシェンコ元帥が任命され、第一代理としてエリョメンコ中将が任命された。西部方面軍強化の目的で、予備方面軍もその指揮下に入ることになった。
北西方面軍でも、情勢は悪化の一途をたどっていた。
第八、第一一軍は、折角敵の包囲を脱出したものの、方面軍司令官の命令が徹底していなかったため、とんでもない方角に行ってしまい、大損害をこうむる破目におち入ってしまった。
プスコフ〜レニングラードの線を守るために、最高軍司令部は第一二機械化兵団の司令官にレリューシェンコ大将を任命した。
そして、味方の部隊をオポチカ〜イドリッツアの線から脱出させ、ダウガブリス地域まで移動させるとともに、西ドウィナ川辺への敵の集結をふせごうとしたのだった。
しかし、この目的は完全に失敗した。
敵はすでに二六日に大軍を西ドウィナ川に集結し終っており、ダウガブリスも押えてしまっていたのである。
それでも、第一二機械化兵団は、予定通り勇敢に追撃し、敵第五六機械化兵団に打撃を与え、その進出を食止めたのである。
当時の第五六兵団の司令官フォン・マンシュダイン元帥は「失われた勝利」と題する著書の中で当時の戦況を回想して次のように書いている。
「間もなく我々は、ドウィナ川の北岸で、戦車師団一個師に支援された敵の攻撃にあい、進むより自らを防衛する状態になってしまった。いくつかの地点では、事態はまさに危機にひんした」
しかし、圧倒的に優勢にある航空部隊の圧迫を受けて、わが第二一兵団は退却して守備の態勢に入り、敵の攻撃をはねのけながら、七月二日まで頑張った。その後、この第二一兵団は、ペルザリン少将指揮下の第二七兵団に吸収された。
その月の終りに、スターリンは再び軍指導部の入替えを行なった。
七月三〇日、北西方面軍参謀にワトゥーチン中将が任命され、その後任の参謀本部第一代理には、ワシレフスキーが任命された。
七月二日、第二七軍は、敵の圧迫の前に退却を始めた。
この当時は、各兵団とも広脯な戦線を受けもっており、厚い防衛戦線を固めて戦うだけの力も手段も持合わせていなかったのである。
このとき、予備隊のベジカヤ川への撤収が遅れたために、敵はプスコフを急襲して、これを占領してしまった。
その結果、北西方面軍の第八兵団は、他部隊との連絡を断ちきられ、北方へ撤退しなければならなくなった。
このようにして、北西方面軍では、戦争開始から一八日間に、リトアニアとラトビア、それにロシア共和国の一部などを失ってしまったのである。
その結果は、ルガを取られる心配を生じたばかりでなく、レニングラードヘも敵を接近させる危険が生じた。
この辺りはまだ、味方の防衛機能は全く弱体なままになっていたのだった。
この期間ずっと、参謀本部は、北西方面軍参謀部から、わが軍の状況、敵兵力、さらには敵の戦車、機械化部隊の配置状況といったことがらについて、明瞭かつ綿密な報告を一度も受けていないのである。
時たまには、事件の発展をきめてかかった直感的な報告があったが、こういうやり方は、いうまでもないことだが、どうしても間違いやすい。
西部戦線では――ビチェブスク〜オルシャンスク〜モギレフスク〜ボブルイスクの線で七月一日に激戦が開始され、敵はここに、ソ連軍をはるかにしのぐ機械化部隊、航空兵力をつぎこんできた。
ひっきりなしの戦闘に疲れきった味方の軍隊は、東方に撤退した。
しかし彼らはこのような際も、少しでも多く敵に打撃を与え、一寸でも防衛線を遠ざける努力を怠っていなかった。
南方戦線では、ドイツ・ルーマニア連合軍がルーマニア領内から繰出してきて、モギレフ〜ポドリスク〜ジュメリンカの線に強い攻撃を加えてきた。
これは、南西方面軍の第一二、第二六、第六軍の側面から背後にかけて脅威を与える形になった。
戦闘開始から六昼夜で敵は、南方方面軍の防衛線を破り、六〇キロの深さまで前進することに成功した。
南西方面軍の状態が極度に悪化した。それというのはこの頃、ドイツ軍が、ロブノ〜ドゥブノ〜クレメニェッツの防衛戦を、何回かの失敗の後で遂に突き破り、組織的な破壊作業を開始したからだった。
七月四日にはドイツ軍は、ノボグラド〜ボルインスキー要塞地帯に接近してきた。
しかしここの攻撃では、敵は大損害をこうむり撤退した。
敵の機械化、装甲戦車部隊は、まる三日攻撃をし続けたが遂にあきらめ、ホコ先きを南に転じ、七日、ベルジチェフを占領、九日にはジトミールに入った。
ベルジチェフ、ジトミールを占領したドイツ・ルーマニア連合軍は、さらに前進を続けてモギレフ〜ポドリスクの線に圧力をかけ、南西方面軍の第一二、二六、六各兵団を包囲の態勢に入ろうとした。
急進する敵から身をかわして、これらの各部隊はいち早く東方に引下がった。
しかし、撤退は包囲の危険性をますます濃くするだけのため、南西方面軍は七月九日遂にベルジチェフ奪回に立上がった。
この反撃作戦のため第一五、第四、第一六各機械化兵団が集結した。
ジトミールの北方からは、第五兵団が攻撃をしかけた。
このとき同時に南西方面軍は、コロスチェン防衛地区から敵の第一戦車部隊の側面に強力な反撃を加えた。
ベルジチェフ〜ジトミール地帯の戦闘は、七月九日に始り一六日まで続いた。
ドイツ軍部隊「南」軍集団司令部は、北側面から本部に向けられた攻撃に危険を感じ、大損害を受けてジトミール地区での前進を断念した。
この勝利はわが南西方面軍の司令部をして、第六、第二一軍に対する敵包囲の危険性を全く取払ってくれたばかりでなく、キエフの防衛強化に非常にプラスになった。
このようにして、敵は南西方面軍包囲の企てを二度とすることはなかった。
ドイツ軍は常にこのように、方面軍単位の流血の大作戦をしいられている。
フォン・クレイストの率いる装甲、機械化の大部隊も、ソ連軍の防衛線を突破り、十分作戦できる広いソ連の領土内への突破を成功させることはできなかった。
北部戦線では、敵の攻撃は六月二九日に始っている。
戦闘は局地的なもので、その影響は全般的な戦略には及んでいない。
わが海軍については、戦争の初期には、ドイツ海軍との正面きった戦いは行なっておらず、主に敵機の撃退を行なっていた。
しかし、段々バルチック艦隊が危うくなってきた。
それというのは、バルチック艦隊のすべての主力艦とその予備物資が集中的におかれた主要海軍根拠地が危険な状態におち入ってきたからだった。
タリン基地とタリン市は、北西方面軍の第八軍の作戦が不成功に終ったことから、陸上からの攻撃の脅威にさらされたのである。
このエストニア共和国の首都の防衛には、バルチック艦隊、都市労働者防衛隊のすべての力が結集された。
タリンの回りには防衛線が急いで構築され、防衛施設もつくられ、市の目標物も防衛体制をとった。
一挙に都市と海軍基地をおさえてしまおうとした敵の試みは、第八軍第一〇歩兵兵団、海軍陸戦隊、砲艦、武装市民部隊などの団結した英雄的な活動によってはね返された。
七月末からほとんど八月一杯、タリンに対する攻撃は続いた。
八月末になって、わが方の力の消耗と敵攻撃の強化とを考慮して、最高軍司令部は遂に艦隊をクロンシュタットとレニングラードとに移し、タリンを放棄する決定を下した。
北方艦隊はこの頃、北部方面軍の戦闘と相呼応して、ベトサモからニッケル鉱を運び出すドイツの輸送船に対して潜水艦攻撃をしかけていた。
黒海艦隊は、沿岸部隊への兵員、弾薬の補給を担当し、ルーマニアやブルガリアの港へのドイツ船の立寄り、連絡を妨害していた。
また黒海艦隊の船団グループは、航空隊と協力して、コンスタンツァのルーマニア艦隊基地を攻撃した。
黒海艦隊の飛行機は、継続的にルーマニアの石油工場、鉄道要地を爆撃したのである。
しかし、海軍のことは提督たちにまかせたいので詳しくはふれない。
ただ一ついっておきたいことは、もし戦争開始以前に、沿岸防備の問題と海軍基地防衛の問題が真剣に取上げられていたら、沿岸部隊と艦隊の相互協力はずっと大きな効果をあげていたろう、ということである。
残念ながら、海軍の司令官たちも国防人民委員部、それに参謀本部当局もこの問題に着手するのが遅過ぎた。 |
ファシスト・ドイツが不可侵条約を破り、わが国境をおかして軍隊を進めてから約三週間がたった。
この間にドイツ軍は、約一〇万の生命を失い、数千台の飛行機を失い、一五〇〇台からの戦車(戦争開始期に所有していたものの約半分)を破壊された。
ソ連軍隊も――特に西部方面軍は――ばく大な損害をこうむった。
それはその後に続いた戦闘に響いた。
独ソ戦線における両者の戦闘能力と物資のつり合いは、極端に敵の優勢に頷いていった。
動員計画――特に弾薬生産に関して――は早くから案がねられていて、すでに六月二三日には発動となった。
人民委員部は、戦車、兵器、飛行機、その他各種の軍用機械の増産について、指令を受けとっていた。
一週間後に政府は、すでにとりかかっていた一九四一年第三四半期の計画遂行をとり止め、国民経済の総動員を確認した。
この新しい計画によると四一年第三四半期において軍用機械の生産を四分の一以上ふやすことが見込まれた。
しかし、事態の発展は、こんなことではとても追いつけないこと示していた。
そこで、ウォズネセンスキー(国家計画委員会議議長)の下に委員会がつくられ、一九四一年第四四半期間を対象にさらに緊迫した新軍事経済計画がねられ、発動することになった。
さらに政府は、戦前に蓄積された生産ストックをもとに、ポポロージェ、ウラル、西シベリア、カザフスタン、中央アジア各地方の開発促進を目ざした四二年度計画をつくった。
全国民経済の軍事軌道への切替えに当って、これらの地域は特別重大な役割を果すことになった。
国の東部に、経済を再建し発展させるに当って、重要な役割を果したのは、党の地方委員会だった。
中でも、特に国防生産に貢献したのは、当時パトリチェフが委員長だったチェリャビンスク党支部である。
戦争の必要をみたすための工業、運輸の再建、人的、物的資源の再整理、国民経済の動員が始った。
昨日まで平和目的のための生産品をつくっていた数千の工場が、今日は弾薬や軍用機械をつくる工場に切替えられた。
機械生産や工作機械生産に当っていた工場が、いち早く戦車や飛行機生産に変り、冶金工場は装甲板や弾薬、高質鉄などの大量生産にとりかかったのである。
軍事用のモーター、ジェネレーター、地雷探知機、音波探知器、電波方向探知器などは、ラジオや電器産業の工場がつくった。
航空機用燃料、戦車や船舶用の燃料は、主として石油工業を扱っていた工場が生産した。
時計の部品工場は、爆発物の生産に当った。装甲列車の生産には鉄道技師がとりかかった。
敵は主要な経済地帯を占領し、これまでの軍管区にもとづく動員を不可能にし、数百万のソ連人、膨大な価値ある物資を自分たちの背後にかくしてしまった。 |
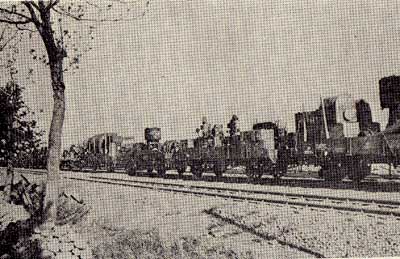
工場施設の東方移転は困難の中にも着々と進められた(1941年)
|
その率は、人間が総人口の四○パーセント、物資については国民総生産の三分の一以上に達した。
戦略物資、鋳鉄、銑鉄、鋼材、電力の生産は激減した。
しかも、新開拓の工業中心地にまで、脅威がおそいかかろうとしていた。
幸い残存している企業を危険地帯から引上げ、東部に移して、そこに現在活動している企業と合併する。
そして、この東部地帯をよりどころとして敵をたたき、進行を食止め、さらには壊滅させる。
こういう目的実現のために、相当思いきった処置をとることが必要になってきた。
こうして、歴史の上で、その規模からいっても性質からいってもかつて企てられたことのない事業が展開されることになった。
六月二四日付のソ連共産党中央委および政府の布告として、疎開委員会の創設が発表され、委員長にはシュベールニク、副委員長にはコスイギンとペルブーヒンが任命された。
人民委員会の内部に、さらに疎開に関する独立局と委員会が組織された。
一五〇〇以上の企業、特に大企業、軍事企業が、一九四一年六月から一一月という短期間に疎開され、すぐにそこで生産を営むことになった。
当時は、毎日、毎晩、軍隊や兵器をつんだ車両の流れが、西へ、南西へと移動していた。
この巨大な人と物との入替えは、おぴただしい肉体の消耗と神経の緊張を伴い、事態は大きな混乱の中で動いていた。
しかも、共産党の指導の下に、規模の上からも時間的にも着々と事業は遂行されていたのである。
私は、ソ連国民の生活の中でのこの歴史的なページが、不当に忘れさられていることを残念に思っている。
党と国民によってなされたこの偉大な経済上の努力が、正当に評価され、説明されていないのである。
あのような危機の時期に際して、危険な事態に直面して、社会主義制度の有利さと社会所有を土台とした国民経済の利点とが、非常にはっきり現わされたのである。
疎開と戦争下での生産能力開発という勤労の詩をうたいあげた国民と、それを指導した党の組織とともに、国の運命にとって、重要な戦闘の勝利にも劣らない役割を果している。
我々の党は、ソ連を単一の団結した戦闘陣地にかえたのである。
こうした党の活動は、いろんな新しい条件の起きてくる中で、すでに戦争開始の第一日目から行われていたのである。
わがソ連に死の危機が見舞ったときレーニン的な行動の基礎・規準が、戦線といわず銃後といわず、共産党員のあらゆる活動の根底にあったのだ。
一方一般国民は共産党を信頼し、新しい困難な状況の中でも、必ず彼らは解決策を見出し、ドイツ・ファシストの軍隊を壊滅することができると信じていたのである。
一九四一年六月三〇日、ソ連共産党中央委員会書記長スターリンを長とする国家防衛委員会が創設された。
この組織は、国の防衛を指導する最高機関で、あらゆる権力を集中的ににぎっていた。
国家といわず党といわず、すべてのソ連の組織は、この国家防衛委員会のあらゆる布告、あらゆる決定を遂行することを義務づけられた。
地方、州、軍事産業、主要企業、防衛委員会支部といったところには、この中央組織から監督のために代表が派遣された。
国家防衛委員会は、昼でも夜でも必要に応じていつでも開かれ、普通、クレムリンかスターリンの別荘がその会場にあてられ、国家緊急の問題が討議され決定された。
最も重要な作戦上の問題も、国家防衛委員会が党中央委、人民委員部と協議して決めることになったので、この組織の権限は、ものすごく広範なものだった。
この結果は、莫大な物資を、それを最も必要としている部門に向けて集中的に供給し続けるというような活動が、単一な戦略指導の下に、銃後の協力を得ながら、全国民の努力と軍事活動とを調和させつつ行うことができるようにしたのである。
この国家防衛委員会の審議は、非常にしばしば、するどい論争をまき起した。
そんな際、委員たちの発言はするどく、断固としていた。
普通スターリンは、議論には加わらずテーブルの辺りを行き来して、注意深く論争に聞入っていた。
スターリン自身は寡黙で、他人のおしゃべりも好きでなく、しばしば脇から「短く」とか「要点だけを」とかいって、おしゃべりの腰をおった。
スターリンはまた「開会の辞」というようなものはやらず、静かに、自由に、問題の本質だけを話した。
表現は簡潔で、正確だった。
この会議で意見のまとまりが得られないような場合は、すぐその場で対立する意見の双方から代表が出て、別に委員会ができて話合い、そこに統一意見の提出をまかせた。
またこういうこともあった。
スターリンが、自分でしっかりと意見をまとめていない場合、あるいは、スターリンが、すでに用意された決定を会議にもちこむ、というようなこと。
後者のような場合には、論議はなかった。
またスターリンが、討論者の一方の側に賛成するというようなときにも、討論はそれで終りになった。
スターリンという人物は、意志強固で、いわゆる、“腰抜け”ではなかった。
彼が、いくらかでも意気消沈してみえたのは、たった一回だけだった。
それは、一九四一年六月二二日の朝で、その時「戦争は避けられる」という彼の確信がもろくも崩れ去ったのである。この日以降、戦争の間中、ずっとスターリンは党中央委およびソ連政府とともに、しっかりと、国家を、戦争を、さらに国際的な諸問題を処理し続けたのである。
情勢の悪化にもかかわらず、党組織、ウクライナ、白ロシア、沿バルト地域のソ連機関は、よく国民を動員し、敵との果敢な戦いを続けることに成功した。
戦いを勝抜くために、一時、敵中におちた地域にも党やコムソモールの地下組織がつくられ、パルチザン部隊が編成され、それが、赤軍、司令官、包囲を脱出してきた人たちによる市民部隊などと力を合わせたのである。
ソ連領土内に突入してきた敵は、ソ連国民の、ドイツ・フアシスト占領者に対する表面に現れた憎しみ以外に、人々が地下にもぐってしまって、そのためにもたらされた目には見えない大きな損失を感じとることになった。
この当時、司令部としても、よい方法はなかった。
ただ、全戦線を守り抜く、ということ一つだった。
戦闘、特に大規模な作戦遂行に当っては、手段を講ずる、というような余裕はなかった。
戦争のためのすべての機能を組織だて、それらをよく装備し、激しい力で敵の主導権を粉砕し、攻撃態勢をこちらに奪い、ソ連領内から敵を追出す、ということだけだった。
当時の防衛戦略の最も重要な点は、次のようなものだった。
一、ファシスト軍をできるだけ長く防衛線のあちら側に抑えておく、そしてその間を利用して、国内の深い部分から戦う力を引出す、つまり新しいストックを見出し、これを最重要な地点に送り出し、活用するということ。
一、敵に少しでも損失を与え、疲れさせ、出血をしいることによって、彼我の力のアンバランスを少しでも取り戻すようにする。
一、労働者や工場を国内深く疎開するという党・政府の決定をやりやすくしてやり、戦争遂行のための企業再建に力をかしてやるということ。
一、全能力を集結し、反撃に態勢を転じ、ヒトラーの戦争計画を根本的に挫折させるということ。 |
戦争が始って五日目に、党中央委の決議に基いて、共産党員やコムソモールの戦線への動員が始った。
彼らは、政治活動家としてそこに加わることになったのである。
彼らはそこで、軍隊内の政治活動の中心となることになった。
戦前、赤軍および海軍には、六五万人以上の党員がいた。
全軍隊の三分の一は、個人的な形でコムソモールに属していた。
そして戦争開始後六ヵ月の間に、戦線には一一〇万の共産党員がいる、ということになった。
今日でも時々、外国で出されている政治的文献などで、共産党員ないし党活動者をソ連社会の“エリート”と表現しているのを見かける。
私は軍人として、そういう外国の人たちにすすめたいのである。
祖国のために献身し、英雄的に命をすて得る人々、そういう“エリート”をそちらでも持ったらどうですか、と。
私はしばしば、軍隊に新しく送りこまれてきた政治活動家たちと会話することがあった。
これらの人たちは、自分たちの勝利について、一種独特な、動かしがたい信念をもっていた。
「耐えましょう!」と彼らはいった。
この言葉について私は考えた。
これは単純な言葉ではない、思考の表現であり、これこそ本当のソビエト的愛国心なのだ、と。
これらの政治活動家たちこそ、その大胆な楽観主義によって、ともすれば心の支えを失いがちだった人々に、信念と勇気をとり戻してやったのである。
七月三日のラジオ放送で、スターリンは、党中央委の名において、戦況の悪化を説明し、国民に対して、強力で、悪賢い、しかも残忍な敵との戦いに対応するよう日常生活と国民経済とを急速に建直す必要のあることを説いた。
さらにスターリンは、党と国民に聖戦意識をたかめ、傍観主義をやめ、警戒心を旺盛にすることを求めた。
国民に向けられた、このようなスターリンの演説、党、政府の指令!
それらは力強い、壮重な警鐘として国民の耳をうった。
それはまた、レーニンの有名な次の言葉のこだまのようにも聞えた。
「社会主義の祖国が危機にひんしている!」
怒りにみちて、よびかけるこの警鐘は、最後のファシスト占領軍がわが祖国の国境を見捨てたとき、初めて国民の耳から消えた。
当時、党のスローガンとして「すべてを戦線に、すべてを勝利のために」というのがあったが、これもソ連国民をして敢えて危険に向わせる勇気を与えた。
このスローガンは、違った見解や習慣をもった兵士や一般市民、男、女、老人、子供、すべての人々を団結させた。
七月には、党中央委の決定に基いて、軍隊内部に政治活動を滲透し、党の影響力を強化する目的で、軍隊内に政治宣伝機関が再組織され、軍事委員制度もとり入れられた。
戦線で銃後で、若い男女は、ソビエト愛国心の模範を示した。彼らは、祖国の名の下に常に命を投出す用意をしていたのである。
こういう人たちは、しばしば情報収集と後方撹乱の目的で、ドイツ軍の背後に送りこまれることがあったが、そうしたコムソモールの人たちと話合う機会が何度かあった。
残念ながら私は、それらの人たちの名前を書きとめておかなかった。
しかし、当時の模様ははっきり記憶に残っている。
そのうちの一つのエピソードを知らせておきたいと思う。
七月一日のことだった。
その頃敵はミンスクを占領して、さらにベレジナ川に向っていた。
ミンスクは敵の背後になっていて、情報・撹乱部隊は、チリヂリバラバラだった。
そこへ二人の女性と二人の青年――みなコムソモールでドイツ語はペラペラだった――が送りこまれた。
私の記憶に誤りがなければ、少女たちは外国語大学の学生だった。
話をしてみて私は、この人たちがモスクワっ子だ、ということがわかった。
「敵の背後に飛ぶなんて、こわくないかね」と私がたずねると、彼らは互いに顔を見合わせながら、ニコニコして答えるのだった。
「もちろん、少しばかり恐いわね。しかし、一番心配なのは上陸しない前につかまってしまうことですね。
その時つかまりさえしなければ、万事うまくいきますよ」
この人たちは非常に若くて、美人でもあった。祖国はこういう人たちを必要とし、またこの人たちも、自らすすんで危険なむずかしい仕事にぶつかっていったのである。
もしこのグループの中の誰かが生残っていたら、その人は、一九四一年七月のある日、モスクワ、フルンゼ通りの参謀本部で私と会ったことを思い出してくれるだろう。 |
兵員や物資の莫大な損耗は、戦闘能力を弱めないために各種の組織的な手段を講ずることを求めた。
時々、兵団規模の構成を再組織しなければならないこともあった。
そんなとき、部隊を離れた幹部や通信設備などが、軍ないしは師団に再配属されるというようなこともあった。
そんな場合、普通なら“軍”の規模は、その下に九ないし一〇の師団をもっているのだが、それが六個師しかもたないということになった。
そして、最高の編成として兵団が存在すべきところが、師団の規模までしかない、というようなこともあった。
航空連隊や空軍師団の所有飛行機数は半分になった。
最高軍司令部の予備隊の編成は間にあわないほどだった。
国家防衛委員会と党中央委は、司令部や政治機関に対して、軍隊内部の規律の強化のためにあらゆる措置を講ずるよう求めた。
政治機関や国防人民委員部からこの目的のために沢山の指令が出されている。
七月になって、全戦線にわたって事態は一層深刻になってきた。
我々の防衛作戦上の主要な弱点は、資材、兵力の不足から幾重にもなる厚い防衛戦線を構築することができないということにあった。
防衛のための部隊構成は本来は縦線的な形をとるべきものなのだ。
ところが、速度も速く、四方に自由に走り出せる牽引車がないため、ソ連軍は、随時必要な場所に大砲が出没して敵戦車の攻撃を押返してくれるような幅広い砲撃作戦が展開できなかったのである。
また戦車部隊は、方面軍にも軍にもごくわずかしか残らなくなってしまった。
こういう状況下に、激しいスモレンスク争奪戦が展開されたのである。
敵の作戦計画は、先ず、わが西部方面軍を強力な大部隊の攻撃によって蹴散らし、次いでスモレンスク地域防衛の主力を包囲し、モスクワヘの道を開こうということにあった。
この古い都、スモレンスクの城壁は、ナポレオンのモスクワ進撃に際しても強固な障害となってその前に立ちはだかったのである。
この土地をめぐる激しい戦いは、一ヵ月以上続いた。
この戦闘こそ、モスクワ攻防戦の前哨戦だった。
西部方面軍の第一線陣地に、最初に攻撃をしかけてきたのは、ドイツ「中央」軍集団の第二、第三戦車部隊だった。
このうち第二戦車隊は、スモレンスクの南西を迂回して、シュクロフ地域から攻撃してきた。
その所属に入る第二四機械化兵団は、ブイフォフ地域からクリチェフ、エリニャの方向に向ってきた。
敵第三戦車隊は、第五、第六陸軍兵団と協力の下に、スモレンスクを側面から包囲すべく、南西からやってきた。
敵勢力は、おびただしくわが方より優勢だった。
すでに戦闘の当初において、彼らは、ポロック、ビチェブスクおよびモギレフの北方、南方で、わが方陣地深く食いこんできた。
わが西部方面軍の右翼は、ニェーペリに向けて退却をよぎなくされたのである。
グーデリアンの戦車隊は、モギレフに正面から突進してきた。
歩兵四個師、一戦車師団、“大ドイツ”連隊、その他いくつかのドイツ軍部隊は、市をめがけて進撃してきた。
頑強にモギレフを防衛していたわが第一三軍は、遂に包囲されてしまった。
バクーニン大将の率いる第六一兵団は、都市の周辺を円く守っていた。
特にこの戦闘で目ざましい働きをしたのは、ロマノフ少将の率いた第一七二歩兵師団だった。
約四万五〇〇〇のモギレフ市民は、防衛線構築に参加した。都市の勇敢な防衛軍は、二三日間敵の攻撃をはね返し続けた。
第一二軍の右側面にはり出した師団と協力したモギレフ南方防衛部隊は、ドイツ第二戦車隊の第四六、第二四機械化兵団をクギづけにし、彼らに大損害を与えた。
この戦いでドイツ軍は、三万人の将兵を失った。
一方敵は、ドニェプル川から東に向けても進撃してきたので、クズネツォフ大将指揮下の第二一軍が、七月一三日にドニェプル岸に急行、ロガチョフ、ジュロービンを解放し、さらにボブルイスクに向けて進撃した。
ペトロフスキー司令官の率いる第六三歩兵兵団は、敵に手ひどい損害を与えた。
しかし彼は、この戦いの後数日して、勇敢な戦死をとげた。
私は、ペトロフスキーをよく知っている。
非常に有能な、教育のある軍人だった。
もし彼がこんな早く戦死しなかったら、おそらく彼は、大規模作戦の司令官として活躍したことだったろう。
この反撃で、第二一軍は、敵の八個師をクギづけにした。
このことは、全体の作戦上大きな意味をもった。
モギレフでの第一三軍の頑強な防衛と、ボブルイスクの第一二軍の積極的な作戦は、ロスラブリ方面への敵の進撃を非常に遅らせた。
ドイツ「中央」軍集団司令部は、この第一二軍の守備地域攻撃のために他の地区から数個師をまわすことを余儀なくされたのである。
戦線の中央部では、スモレンスクへあくまで中央突破を試みようとする敵の主力部隊との間に頑強な防衛戦が戦われていた。
第二〇軍部隊は、広範な戦線で敵の攻撃をはねのけ、はねのけしたのだが、遂にドイツ第九軍の攻撃をささえることができなかった。
敵の戦車部隊は、わが軍守備線を回りこんで、スモレンスクに入りこんだ。
スモレンスクの陥落は、国家防衛委員会、特にその委員長であるスターリンにとっては、重苦しいものであった。
スターリンは、茫然自失といった状態で、我々軍指導者もまた、このスターリンの失望は身にしみてわかったのである。
しかし、スモレンスクの敗戦が決して我々の勇気をくじくようなことはなかった。
最高軍司令部は、西部方面軍を後方に引下がらせ、急きょ新防衛線を構築した。
まだ防衛戦が戦われている間の七月一四日に、第二九、第三〇、第二四、第二八、第三一諸軍の混成による予備軍で新方面軍が出来上がっていた。
この部隊の最高司令官はボグダノフ中将で、後でこの部隊の大部分は、西部方面軍に編入された。
西部方面軍は、スターラヤ・ルッサ〜オスタシコフ〜ベールイ〜エリニャ〜ブリヤンスクの線に新しく展開した。
さらに、モスクワ防衛の最外郭線として、新たにモジャイスクを中心にした防衛線も築かれた。
この防衛線の構成は、第三二、第三三、第三四の各軍によることが予定された。
また、旗色の悪くなってきた前線を補強するために、最高軍司令官は、西部方面軍司令官チモシェンコ元帥の手許にあった予備隊の第二〇歩兵師団を前線に回す決定を下した。
これらの師団は、五つの軍団に分けられ、その最高指揮官として、ロコソフスキー少将、ホメンコ少将、カリーニン中将、カチャロフ中将、マスレニコフ中将らがそれぞれ任命された。このときの最高軍司令部のチモシェンコ元帥への命令は、ベールイ〜ヤルツェポ〜ロスラブリの線から反撃を起し、スモレンスクに向って進撃し、敵戦線をつき破り、包囲されながらもなおスモレンスク地域で頑強な抵抗を続けているスモレンスク防衛基幹部隊と合流することにあった。
七月下旬のスモレンスク、さらにその東方の戦闘は、一層激しい戦いとなった。
全戦線にわたって赤軍の積極果敢な反撃と、これを迎えうつドイツ軍の死闘が展開された。
七月二三日、第二八軍団はロスラブリ地域から、二四、二五両日にかけては第三〇および第二四軍団がベールイ、ヤルツェボ地域から、それぞれスモレンスクに向って進撃を開始した。
第一六、第二〇軍はスモレンスクを通り越して北と南から包囲の態勢に移った。
敵はすぐに、スモレンスクにあった補充部隊を引上げ、わが西部方面軍の第一六、第二〇軍の包囲企図の打破にかかった。
ここでも戦闘は、激烈をきわめた。
この二軍団は、戦車部隊をもつロコソフスキー指揮の部隊の援助を得て、敵に包囲されずにヤルツェボの南からドニェプル川の東岸に出て、そこで基幹部隊に合流、スモレンスクの守備固めに入った。
三個師をもってロスラブリからスモレンスクに進撃していたカチャロフ軍団は機械化兵団一をもつ第九師団とぶつかった。 敵はすぐにロスラブリを占領し、カチャロフ軍団を包囲した。
この彼我の勢力は、お話にならなかった。苦しい戦闘の後、わずかの残存部隊が囲みを破り、自軍に合流するのに成功しただけだった。
この戦闘で、カチャロフ大将が勇敢な戦死をとげた。敵の第四六機械化兵団は、エリニャを占領し、さらにドロゴプジを攻撃し始めた。しかしこの企ては、わが予備軍の第二四軍によって阻止された。
ゴメル方面を守るために、最高軍司令部は中央方面軍を結成した。
これには、西部方面軍の第四、第一三、第二一軍も包含され、目的はセシチャ〜プロポイスクの線に圧力をかけ、さらに遠く南方ドニエプル川岸まで進撃することにあった。
スモレンスクの戦闘は、大祖国戦争の初期の段階で非常に大きな役割を果している。
最高軍司令部が予期した通りに敵軍を破砕することはできなかったが、敵の受けた打撃は大きかった。
ドイツ側の計算によっても、スモレンスク戦でヒトラー軍は、二五万の将兵を失った。七月三〇日、ヒトラー司令部は「中央」軍集団に対して防衛に転ずるよう命令を下した。
ソ連側は、ペリーキー・ルーキ〜ヤルツェボ〜クリチェフ〜ジュロービンの防衛線を固めることができた。
スモレンスク戦では、赤軍将兵、市都および近郊の住民は、強硬な抵抗ぶりを遺憾なく発揮した。
激しい戦闘が、一つ一つの防衛トーチカあるいは街路、住宅区域をめぐって展開された。敵の目ざした重要地点への攻撃ははね返され、大きな戦略的成功を収めた。
このために我々は、モスクワ防衛のための戦略的予備資材の蓄積、直接の防衛手段の実施のために十分な時間をとることができた。
スモレンスクにはソ連親衛隊が生れた。
このとき七月一四日に、オルシャの戦いでフリェロフ大佐の率いる砲兵中隊が、ロケット・モーターの有名な“カチューシャ”砲を初めて戦線で使用したのである。
チモシェンコ元帥の功績は讃えられなければならない。戦争のきわめて困難な最初の段階で、元帥はよく軍隊を指揮し、あらゆる力を効果的に動員し、防衛作戦を遂行して、敵の攻撃をはね返すことに成功している。
この結果、ヒトラー軍の戦略的統帥部から司令部、軍隊すべてが、ソ連兵士の大胆さと集団的な英雄行為に舌をまいたのである。
そして、ソ連国内へ深く入りこむほど、ドイツ軍にとって戦いが困難なものになってくることをいやでも自覚させられたのである。
七月末、ポスクレプイシェフから私に電話がかかってきた。
「チモシェンコ元帥はどこですか?」
「参謀本部で、我々と戦線のことで討議中です」
「スターリンが、あなたとチモシェンコ元帥に、すぐに別荘の方に来るようにとのことです」
我々は、スターリンがこれからの行動について、我々と相談したがっているものと思った。
ところが、呼出しの目的は違っていた。
私たち二人がスターリンの部屋に入ったとき、そこには党政治局のほとんど全員がすでに着席していた。
スターリンは着古したジャケツを着て部屋の真中辺に、火の消えたパイプを手に持って立っていた。
雰囲気は、はっきり重苦しいものだった。
スターリンが先ず口をきった。
「実はねえ、政治局でチモシェンコ元帥の西部方面軍司令官の地位について話合ったのだ。
その結果、その地位を解こう、ということに決めたのだ。
そして、後任にジューコフを任命しよう、という意見が出ている。あなた自身はどう思うかね?」
こうスターリンは、私とチモシェンコに向って話しかけてきた。
チモシェンコは黙っていた。そこで私が口をきった。
「同志スターリン、方面軍司令官の度々の更迭は、作戦の遂行に悪影響を与えます。
司令部が、所定の作戦を完全に遂行し得なかったとしても、それは、戦闘が苦しい状況の下で行われざるを得なかったからです。
チモシェンコ元帥は方面軍司令官となって、まだ四週間もたっていません。
スモレンスク戦については、軍隊自身わかっていると思いますが、彼らはよく戦いました。
チモシェンコ元帥も、司令官としてでき得る限りのことはやっています。
ほとんど一ヵ月、スモレンスク地域への敵の攻撃をささえました。
私は、誰がやっても、あれ以上のことはできなかった、と見ています。
将兵もまたチモシェンコを信頼しています。これは大事なことです。
私は、いまチモシェンコ元帥の方面軍司令官を解任するということは、正しくもないし、目的にそうものでもない、と考えます」
カリーニンがおもむろに口をきった。
「どうです、正しいんじゃないですか……」
スターリンは、ゆっくりとパイプをくゆらしながら、政治局員たちを見回した。そして言った。
「我々も、ジューコフの意見に賛成しますか?」
「その通りです、同志スターリン。チモシェンコはまだ事態を回復し得るでしょう」といくつかの声が応じた。
会議は解散となりチモシェンコ元帥は、直ちに戦線に向うよう命令された。
チモシェンコ元帥が、不当な非難に対して、心からくやしがったであろうことは想像にかたくない。 |
こういうことは、このときだけのことではない。
スターリンは、軍司令官の活動の評価に当って、必ずしもいつも公平だったとは言いがたい。
私自身も経験していることで、チモシェンコ元帥の気持はよくわかる。
しかし、このときの非難は、個人的なものではなかった。
スモレンスク地域の激戦の後、西部戦線では、しばらく戦闘の小休止が続いた。
両軍とも戦線を整理し、来たるべき次の戦闘に備えた。
ただ、エリニャ地域だけでは、依然戦闘が続いていた。
すでにドイツ軍に占領されていたエリニャ突出部は、彼らにとって、モスクワ攻撃のための極めて有利な拠点だった。
従ってドイツ軍は、何としてでも、この地点を守り抜こうと考えていたのである。
レニングラード方面でも、敵は攻撃に移っていた。
しかし、かなりの場所で、成功的に作戦を進めながらも、一挙にソ連軍の主要戦線を突破することはできず、なかなかレニングラード近くへ接近できないでいた。
スモレンスクでの激戦の間に、ドイツ「北」軍集団は、ルガを通ってレニングラードに近づこうとしていた。
七月一二日、敵の第四一機械化兵団が、レニングラード街道をルガに向って進撃を開始したが、わが軍によって阻止された。
しかし、キンギセプ〜イワノフスキーの線の防衛線が弱いのを探り出し、ドイツ第四戦車部隊はルガから急に北方に転進して来た。
そして、一部防衛線を突破したが、わが予備部隊が急きょかけつけ、その進撃をはばんだ。
また他のドイツ軍部隊は、ノブゴロドからチュドボの方面にかけてソ連領内深く入りこもうとしていたが、頑強な抵抗にあい、そこでも目的を達することができなかった。
敵の機械化兵団は、ソリツィで航空部隊に支援されたわが第一一軍部隊に不意打ちをくらい、しっぽを巻いて退却にかかった。
第一一軍は、逃げる敵に追打ちをかけ、敵に大損害を与えた。
このときの敵軍、マンシュタインの率いた第五六機械化兵団は、もし第一六軍の援助が得られなかったならば、全滅させられているところだった。
敵が補充部隊をつぎこんできたので、北西方面軍の第一二第二七軍はスターリャ・ルッサーホルムの線に後退した。
しかし、二個軍団、一戦車部隊から編成されたドイツ「北」軍集団は、ルガの防衛陣地と、ドノー地域、さらにスターラヤ・ルッサーホルムの線、キンギセプ〜シペルスキーの線などで味方の頑強な反撃にあい、大損害を被り、補充部隊の援助なしにはレニングラード攻撃を開始することができなくなっていた。
スモレンスク戦闘の開始、それにバルチック艦隊と航空部隊とに支援されたソ連軍の北部および北西方面軍の抵抗などは、ヒトラーのバルバロッサ作戦計画にかなりの支障を来たさせた。
ところで、南西方面軍が激しい防衛戦を展開しているウクライナ地帯では、戦闘はどうなっていたろうか?
ウクライナ地方の占領は、ドイツ軍にとっては特別な経済的重要性をもっていた。
彼らは、ウクライナ地帯の全面占領を急いでいた。
それは、ソ連側に対して、最大の工業地帯と農業地帯とを失わせることになると同時に、クリポイ・ローク鉄鉱、ドネツ炭田、二コポル・マンガン鉱、ウクライナの穀物などの経済的潜在力を自国の経済に併合することを可能にしたからである。
また、戦略的な面からみても、ウクライナの領有は、重要な意味をもっていた。
それは、ドイツ軍にとっての最初からの中心課題であるモスクワの占領――それを受持っていたのはドイツ「中央」軍集団だったが――を南方から支援する態勢を保障することになるからである。
戦争の当初から、ウクライナ戦線の進捗ぶりは、ヒトラーの電撃作戦が予定したようにはいっていなかった。
赤軍は、ドイツ軍の攻撃の前に退却を余儀なくされながらも、勇敢に抵抗し続けた。
ポタポフ大将指揮下の第五軍、コスチェンコ大将指揮下の第二六軍、ムズイチェンコ大将指揮下の第六軍などが、特に頑強に、巧妙に、そして大胆にドイツ軍を悩まし続けた。
もう一つ、私かすぐれた作戦を行なった部隊としてあげておきたいのは第四ドン・コサック騎兵師団である。
この部隊は私自身一九三二〜三六年に指揮したことがあったが、第一騎兵軍の中で、最も歴史の古い、伝説的な師団として有名になっている。
キエフ防衛地帯の頑強な反撃を受けた敵は、急きょ南方に向きをかえ、ペルジチェフ〜スタロコンスタンチーノフ〜プロスクーロフの線に後退して守っていた味方の第六、第二一軍の背面に回ろうとした。
一方別の部隊が、キエフの南方へ回り、わが第二六軍の防衛線にぶつかって来た。
しかし、この方面の突破は、本質的な意味はもっていなかった。
敵の「南」軍集団の主要勢力は、もっと南に移っていたのである。
そして、わが第六、第二一、第一八軍が、彼らを包囲しようと企てた敵主力部隊と激しい戦闘に入ったのである。
情勢はその後悪化し続けた。というのは、敵の第一一軍が、南部方面軍の防衛線を突破してモギレフ〜ポド〜リスキーの辺りに攻撃を加えて味方戦線の側面から背後に進出し、わが上記三個軍団を包囲しようとしたからである。
南西方面軍の軍隊は、南部方面軍と協力して反撃をかけ、敵の進撃を食止めようとしていた。
彼らは敵に大損害を与えた。
しかし、彼らを食止めることはできなかった。
ドイツ軍は、若干の部隊の再編成を行なった後、あらためて、退却しつつあったわが第六、第二一軍に襲いかかってきた。
そのため、わが軍は、たちまち苦境におち入ったのである。
南西方面軍としては、これらの軍団については、地理的にも遠く、統率指揮がむずかしいとして、その統轄を南部方面軍にまかせたいと申出てきた。
最高軍司令部もこれを了承し、第六および第二一軍は、チュレニェフ軍大将指揮下の南部方面軍の編成に入った。
この部隊が南部方面軍の統率下に移ったとき、部隊のほとんどは敵の包囲下にあった。第六軍司令官ムズイチェンコ大将は、重傷を負った後捕虜になった。
また第二一軍司令官のポニェデーリン大将も、捕虜になる運命を免れ得なかった。
このとき、南部方面軍の方も、情勢は非常に急迫していた。第九軍は、後退しながらの戦闘で、半包囲の状態にあった。
部隊は大打撃を受け、残存部隊は、イングレッツ川の線まで退却した。
敵は、ドニェプル川まで進出、ザポロジェ、ドニェプロペトロフスク、オデッサの固めを突破したので、南西戦線全体にわたってソ連軍の状況は悪化した。
しかし、この勝利は、敵にとっても高価なものについた。
彼らは、大きな損害を受け、疲労しきってしまったのである。
私が、南西方面軍からモスクワに帰還してから後のすべての描写は、参謀総長としての立場から、最高軍司令部で責任ある仕事を分担しつつ味わった戦闘の不成功の苦渋、たまにあった勝利の喜びを書きつづったものである。
次に私は、最高軍司令部そのものの活動、ないしはスターリンの活躍などについてのべてみたいと思う。
一九四一年七月、党政治局は、軍の戦略的指導組織の編成替えを行なった。
七月一〇日、最高軍司令部の名称をかえた。(訳注)
(訳注=従来は直訳すると、“主要な司令の本営”と呼んでいたのを文字通り“最高司令の本営”と呼ぶことになったので、日本訳としてはどちらも最高軍司令部とする)。
そしてこの構成員に、スターリン(議長)、モロトフ、チモシェンコ元帥、プジョンヌイ元帥、ウォロシロフ元帥、シャポーシニコフ元帥、ジューコフ大将の七人が名を列ねることになった。
七月一九日、スターリンは国防人民委員に任命され、八月八日にはソ連邦最高軍司令官にも任命された。
スターリンが最高軍司令官となり、戦争遂行の全権をにぎることになったことは、国民全般および戦線の将兵たちによっても歓迎された。
国防人民委員部も再組織され、各局の機能は専門化され、新しい部署も創設された。最高軍司令部の編成替えと同時に、方面軍と艦隊との活動を統合し、重要戦線にある軍事力の強化と統合を目ざして、三つの重要な司令部がつくられた。
しかし、これは、最高軍司令部が方面軍も海軍も、それに各部隊をも指導し得る、という体制と抵触するものではなかった。
当時、軍隊や飛行機の限られた予備勢力は、全部最高軍司令部の統率下にあり、当然のことながら各部署の司令官の独立にも影響を与え得たのである。
この頃、党中央委の支持に基いて、軍の戦闘能力強化に役立つようなもう一つの手段がとられた。
党は、戦略における兵たん部の仕事についても配慮することを忘れていなかた。
そして、方面軍および海軍に兵たん局といったものがつくられ、軍、兵団および師団にはそれぞれその下部機構ができ、各司令部の副官は、物資、技術面の補充にも責任を負わされるようになった。
わが軍のこれらの兵たん機能は、大きな戦闘の後方で、非常に重要な役割を果していたのである。
参謀本部は、最高軍司令部の唯一の執行機関だった。
最高軍司令部の各種指令、措置は、全部参謀本部を通じて発布、実施された。
それらの仕事は普通、クレムリン内のスターリンの書斎で行われた。
この書斎は広々としていて、かなり明るい部屋だった。
壁には、みがかれた樫の木がはめこまれ、部屋には緑色の布のかかった細長いテーブルが置かれていた。
壁にはまた、マルクス、エングルス、レーニンの肖像が飾ってあったし、戦争中は、ズウォーロフ、クトゥーゾフ両将軍の肖像もあった。
書斎には、本棚や本は全くなかった。
ガッシリした家具以外余計なものは一つもなかった。
隣室には巨大な地球儀が一つあり、その隣には机、壁には世界地図がかかっていた。
書斎の一番奥に、壁につけてスターリンの事務机があって、そこにはいつも書類、紙、地図などが積重なっていた。
また、無線装置の非常電話やクレムリンの内線電話もそこにあり、いつも削られた色鉛筆の固まりもおいてあった。
スターリンは通常、青色の鉛筆でメモをとり、その動作は敏速で、大胆だったが、文字はかなり読み易いものだった。
スターリンの書斎の入口には、個人秘書のポスクレブイシェフの小部屋があって、ここを通過しないでは書斎へは通れなかった。
書斎の奥には、休憩室と通信室があり、ここには通信機械や特別な『ボド・ライン』があった。
ポスクレブイシェフはこの施設を使って、スターリンと戦線の司令官や戦線派遣の最高軍司令部の代表者たちと連絡をとっていたのである。
最高軍司令部や参謀本部のスタッフは、大きな机の上に地図をひろげ、それを中心に、戦線の模様を報告したものである。
従って、報告は立つたまま行われ、時にはメモを見ながら、ということもあった。
スターリンは、大股に部屋を歩きながら、時々ふらついたりして、この報告を聞きとつた。
そして、しばしば大机の傍により、のぞきこむようにしてじっと地図に見入るのだった。
たまに自分の机の所にかえってタバコの包みを取上げ、ゆっくりとそれをパイプにつめた。 |
最高軍司令部の基本的な課題は、各部隊に戦略的な課題を説明し、伝えることで、戦略的に特に重要視される方面軍や部署に兵力や資材を割当て、陸海双方の戦闘行為を統轄し、指揮するということにあった。
こんな際に、最高軍司令部の予備隊が非常に重要な役割を果すので、司令部としては、たえずこれを補い、整備していなければならなかった。
この予備隊は、最高軍司令部の強力な武器で、重要な地域や最重要の作戦に際して、よくわが軍の力の強化に役立ったのである。
最高軍司令部の重要な戦略決定の審議は、通常、国家防衛委員会のメンバー参加の上に行われた。
さらに参謀本部員、空軍・砲兵司令官、機械化・戦車部隊長官、赤軍兵たん部長、その他国防人民委員部の重要機関の幹部なども招待された。
方面軍司令官がこの審議に加わるのは、特にその司令官の得意の専門に関連したことか、さし迫った作戦の審議のときに限られていた。まれには、飛行機、戦車、大砲の製作担当者が参加することもあった。
最高軍司令部の審議の零囲気は、普通事務的で、イライラしたような気分はなく、誰も自分の意見を述べることができた。
スターリンは、誰にも同等にしかも厳しく、どちらかというと公式的な態度だった。
彼は、専門的な知識の話でも、理解することができた。
ついでにいうと――これは私が戦時中いつも確信していたことだが――スターリンは、むずかしい質問をしかけてみて、その問題をめぐって論争したり、またいつまでも自分の見解に固執したりするようなタチではなかった。
もし誰かが、反対の見解を固執すると、単刀直入にいったものである。
「そういう見解は間違っている」と。
前にもふれたが、参謀本部は、最高軍司令部の執行機関だったから、戦争の当初、私はそのメンバーと四六時中一緒にいて、各戦線から送られてくる矛盾した情報の分析や、報告としての取りまとめなどをやっていたものである。
参謀本部の機能は、じきに複雑になり、仕事量は急激にふえていった。
組織再編は早急に進められたが、それでも我々は問題のすべてを処理しきることはできなかった。
ソ連軍や敵軍に関する各種の情報、しかもそれが昼となく夜となく時間をかまわず入ってくるものを、正否を判断し、適宜に施設や弾薬類を戦線に提供してやるよう指令を出したり、数時間内に、ときとしては数分内に、最も責任ある最高軍司令部としての指令を書くということは、全く人間業ではなかった。
さらに最高軍司令部――つまりはスターリンだが――に対する報告についていえば、自己推測に基いていたり、または誇張されたような材料を報告することはいけなかった。
スターリンは当てずっぽの報告にはたえられず、あくまで完全で明確な回答を要求し、少しでもそれに判断をつけ加えることは、自分自身で行なったのである。
またスターリンは、報告や書類の中の間違いの発見には特殊な感覚をもっていて、間違った情報はすぐにこれを観破し、するどく叱責した。
また記憶力も抜群で、言ったことや言われたことを決して忘れず、こちらが忘れたりすると容赦しなかった。
それ故、我々は、参謀本部の書類はこれ以上なしという綿密さで準備したものだが、その時分は私もそれができたのである。
しかし、戦線で苦しい状態が続いていた頃、確かにまだ生活のリズムは、そういう戦時状態にうまくなれていなかった。
しかし、参謀本部のスタッフの名誉にかけていうが、間もなく我々は、極端に緊張した条件の中で、新しい生活態度を打出し、事務的に万事を処理し得るようになったのである。
その後戦争中ずっと、私は、参謀本部スタッフと個人的にも仕事の上でも関係が絶えたことはなかった。
彼らは、大きな作戦の準備やその実現に当って、私をよく助けてくれた。
参謀本部は、よく重責にたえて、新しい部隊の育成をやり、最高軍司令部の指令草案を作成し、その指令の実施を監視し、国家防衛委員会の指令作成を助け、軍隊およびサービス部門の活動に指示を与え、最高軍司令部の重要なまた主要な諸問題についても積極的に参与した。
スターリンは、重要な問題ではいつも、最高軍司令部の代表を情勢分析のために直接戦線に送り、現地の司令官たちと相談させ、その報告を基礎に決定を行なっていた。
私がスターリンと身近に接するようになったのは、一九四〇年以降で、その時私は参謀総長になり、戦争になってからは、最高軍司令部の一員としてそばにいた。
スターリンは、すでに前に書いたように、背丈はそんなに高くなく、一見目立ない風釆だったが、相手に強い印象を与えるものをもっていた。
気どりは全くなく、ごくあっさりした態度の中に相手をひきつけるものがあった。
スターリンの自由な話しぶり、整然と自分の考えをまとめる能力、うまれつきの分析能力、博学、それに鋭い記憶力とは、話す人に、その人が相当利口な卓越した人物でも、ひそかに恐れ、用心することを余儀なくしたものである。
スターリンは、会話をするときには、座るのは好きでなく、ゆっくりと部屋の中を歩き回り、時々立止って相手に近より、真直ぐ相手の目を見つめた。
スターリンのまなざしは、明るくかつつきさすような鋭さをもっていた。彼は、一節一節はっきり区切って、静かに話した。
身ぶりはほとんどせず、手には大抵パイプをもっていた。
パイプは火のついていないこともあり、その端で、髭をこすっているのが好きだった。
話の調子には、はっきりとグルジアなまりが出ていたが、ロシア語は正確に知っていて、いろんな文学的の比喩や、たとえ話、風刺などを引用するのが好きだった。
スターリンは、めったに笑わなかった。笑ったとしても、静かな含み笑い、といった程度だった。
しかしユーモアは解していて、機知や冗談を理解することができた。視力は強く、本を読むのに昼でも夜でも眼鏡はいらなかった。
書きものは普通、タイプを使わず自分で書いた。
読書力は旺盛で、いろんな分野について、その博識ぶりを発揮した。
彼の驚嘆すべき活動能力、敏速に対象を理解する能力が、初めてスターリンをして、日々発生するあらゆる部門にわたる山ほどもの問題を検討し、処理することを可能にしたもので、こういうことは普通人のちょっとまねのできない部分だった。
スターリンの性格を、一言でいうのはむずかしい。
能力があり、多面的な性格で、月並みではない。
彼は、強い意志の持主だったが、同時に、陰険な面もあり、発作的な面さえももっていた。
普通は静かで、判断力をもっているのだが、時々、かんしゃく玉を破裂させた。そんなときは、理性を失っていて、文字通り人が変った。
顔は一層青白くなり、目つきは重苦しく残忍さをひめてくるのだった。
こういうスターリンの怒りにたえ、それをはねつけ得るような大胆な人物を、私はほとんど知らない。
スターリンの日常生活もちょっと変っていた。
彼は概して、夕方と夜働いた。一二時より前に起きることはめったになかった。
正午から午後三時頃までが一番働く時間だった。
従って当時は、党中央委も、国防人民委員部も、他の人民委員部や重要な政府機関、計画立案機関も皆、このスターリンの日課に則応して夜遅くまで活動していた。
このことは、普通一般の人を非常に疲れさせた。
いろんな政治上、軍事上その他一般の国家の諸問題が、党中央委の政治局の公式会議や書記局などで決められず、スターリンの住い、あるいは別荘などでの夕食のときなどに審議された。
こういう席には普通、政治局の一番信用ある人たちが出席した。
食事の内容はいつもきわめて粗末だったが、招待された政治局員や人民委員には、問題ごとに担当がまかされていた。
参謀総長も国防人民委員と一緒に招待を受けることがあった。
戦争が始るまでは私は、軍事問題や作戦、戦略的な問題などで、スターリンの知識の深さや能力を評価することはできなかった。
というのは、政治局やその他スターリンのいるところで(ほとんど私も居合せたが)審議され決定された問題は、組織問題や動員計画、その他資材、技術関係の問題などだったからである。
ただ、次のような点だけは繰返しいうことができる。
スターリンは常に、沢山の軍装備および軍事的技術に関した問題解決に当っていた。
彼はしばしば、飛行機、大砲、戦車の製造にも頭をつっこみ、ソ連ばかりでなく外国のものについても、細かい技術的な問題を質問していた。
彼が、軍装備の基本的な問題をよく理解していた、という点については正当に評価する必要があるだろう。
スターリンは、主要な設計士、軍事工場長を個人的に知っていて、飛行機、戦車、大砲その他の重要兵器について一定期間に製作を要求したばかりでなく、質的にも、外国の水準に劣らないもの、もしくはそれを凌駕するものをこしらえるように求めた。
スターリンの承認がないと、新しい型の兵器の採用、ないし新技術のとり入れはできなかったし、古いものを廃止することもできなかった。
これは、赤軍の装備問題処理に当っての国防人民委員のイニシアチブを圧迫した。
祖国戦争の前、特に戦中に、軍隊の創設や戦略ないし作戦にも関連した軍事科学の基礎的開発の領域で、スターリンがすぐれた役割を果したことがのべられている。
ところで実際にスターリンは、軍隊の創設や作戦、戦略的な知識の面などですぐれた軍事思想家と呼べるのだろうか?
戦争中ほとんどスターリンと一緒にいたので、私は軍人として、徹底的にスターリンを研究した。
スターリングラードの戦いまではスターリンは、戦略ないし作戦関係については、ごく一般的な立場から問題を処理していただけだったし、近代的戦線の組織、あるいは戦闘についてもそうだった。
しかしその後、スターリングラード戦が始ってからは、スターリンは、戦線の組織、、部隊の作戦などを深く研究し、完全な知識の下にそれらを指導し、重要な戦略問題を非常によく理解していた。
戦闘指揮に当っては、彼の生れつきの賢明さとすぐれた直観力が役にたった。
彼は戦略上の重要ポイントを探し出し、あそこ、ここと大きな攻撃作戦を展開して敵に打撃を与えた。
確かにスターリンは、有能な、その地位にふさわしい最高軍司令官だった。
もちろんスターリンは、個々の部隊や司令官を、正しく戦線に配列するというような細かい問題についても知識をもっていたわけではない。
そういうことはまた、スターリンには不要だったのである。
そういう問題は、最高軍司令部のメンバー、参謀本部、あるいは砲兵、戦車、空軍、海軍、兵たん、運輸といったそれぞれの担当者が意見を出していたわけである。
個人的にもスターリンは、いろんな分野で新しいやり方を工夫したといわれている。
よくいわれているのは、砲兵の攻撃方法、空域支配の手段、敵包囲の戦術、包囲中からの敵の分断、敵部隊を孤立させて行うせん滅法などについてである。
すべてこういう重要な作戦上の問題は、実戦の長い経験や、深い思索、指揮官ないしは兵隊の活動を通しての総合的な結論、そうしたものの成果として初めて会得できるものである。
スターリンの偉いところは、つまるところ、我々のようなベテランの軍事専門家の意見を聞く耳をもっていたということにある。
彼は我々の意見を理解しただけでなく、これを補充し、発展させて、すぐにそれを実際の軍事指導の中にもりこんでいったのだ。
作戦に当っての物質的、技術的な編成、予備の備え、人、物の補給の道などすべての面で、スターリンは、お世辞ぬきで、すぐれた組織者だったといえる。
もし我々がいま、こういうスターリンの偉さに対して、しかるべき尊敬を払わないとしたら、それは間違っている。
しかし、何といっても我々が、深く低頭して感謝しなければならない人、それは、わがソ連の一般市民である。
彼らこそ、自分に最も必要なもの――食べものから眠りまで――をあきらめて、共産党が敵せん滅のために彼らに課したすべての課題を、総力をあげてやりとげたのである。
戦況の悪化につれて、党は軍隊の士気に気を配るようになった。
赤軍の政治宣伝本部は、党中央委の指示に基いて、七月中旬重要な二つの指令を出した。
この内容は、共産党員とコムソモールの率先指導の体制を、戦闘遂行、司令官の命令実施に当って一層高度に実施させよう、というものであった。
政治的諸機関、党およびコムソモールの組織には部隊編成、戦闘能力の発揮などに当って特殊な重責がかけられるようになった。
この人たちは、特に困難な窮迫した事態の下で、兵士たちを指導し、恐怖やふしだらな行為をとりしまり、戦いの経験を普及し、勇気、献身、率先実行、大胆、団結などの模範を示すことが求められた。
軍隊内部のこうした政治的な活動は、日を追い月を追って拡大されていったのだが、それは効果があったし、また重要な意味ももっていた。
私は、ワシレフスキー総長代理をはじめ、他の参謀本部員たちとも情勢を検討した結果、結局次のように判断した。
敵は、わが南西方面軍の側面と背後に回るのを狙いとして、おそらく近いうちに、先ずわが中央方面軍に攻撃をしかけてくるに違いないと。
モスクワ攻撃については、敵が、自軍の「中央」軍集団に対する側面からの脅威がなくなったとき、つまりわが中央方面軍からの攻撃の可能性を断ち切ったときに初めて行動を起してくるだろう、と判断された。
北西方面の戦線については、敵は、部隊を強化して、近いうちにレニングラード攻略に出て、フィンランド軍と手をにぎろうとするだろう、とみられた。
これらの見通しを、その後さらに検討しあい、誤りないと判断した私は、これを最高軍司令部に報告し、直ちに必要な反撃手段を講じようと決心した。
七月二九日、私はスターリンに電話して、至急に報告したいことがあるから会ってほしいと頼んだ。
戦略地図、ドイツ軍の所在を示した地図、それにわが各戦線、中央にある軍隊、物資、機械などのストック状況を書いた書類の三つをもって私は、ポスクレブイシェフのいる控えの部屋へ入った。
そして、スターリンに私の来たことをつげてほしいと頼んだ。
するとポスクレブイシェフは「おかけ下さい。メフジスの来るのを待てといわれているんです」といった。
一〇分ほどして、スターリンは私をよんだ。
「さあ、報告してくれたまえ、君の考えたことを」
私は机の上に地図をひろげ、情勢を詳しく説明した。
各戦線の損害、それに対する予備隊補充の実情も数字をひいて説明した。
さらに敵軍の配置状況についても細かく説明し、予測される彼らの作戦行動についても意見を述べた。
スターリンは、注意深く聞いており、時にはちょっと地図をのぞきこんで、そこに細かく書きこまれたしるしを見たりしていた。
「ドイツ軍がそういうふうに行動するだろう、ということを君はどこから知ったのかね?」
と傍のメフジスが質問してきた。
「ドイツ軍が、現実にどう出るか、彼らのプランはわかっていません。
しかし、情報分析の結果、彼らは、こう出てくるはずだし、それ以外ではあり得ない、と結論したのです。
我々の予測は、現状の分析と、ドイツ軍の作戦行動の主柱になっている装甲および機械化各部隊の現実の配置状況に基いて行われたものです」と私は答えた。
「報告を続けたまえ」とスターリンがいった。
私は続けた。
「モスクワ防衛線に対しては、敵は近く作戦行動を起すことはないでしょう。
というのは、いま彼らは余りにも大きな損害を被ってしまっているからです。
敵には現在、『中央』軍集団の左右両翼を補強するだけの十分な作戦予備がありません。
レニングラード方面でも、戦力を補強しないでレニングラード占領作戦にはとりかかれませんし、フィンランド軍との連携もなりません。
ウクライナでは、大きな戦闘が、ドニェプロペトロフスクやクレメンチュグあたりで展開されています。
そこには敵は、『南』軍集団の装甲部隊の主要戦力を集めています。
ところでわが防衛戦線のうちで一番薄手で弱い部分は中央戦線です。
ウニエチャからゴメルにわたる線に展開しているわが軍は、数も少ないし、機械化の程度も不十分です。
おそらくドイツ軍はこの弱点を狙い、その後南西方面軍の側面と背後をつこうとするでしょう」
「そこでどうしようというのかね?」とスターリンはたずねた。
「まず中央方面軍を強化します。ここに、大砲をもった少なくとも三個軍団を補強するのです。
一軍団は西部方面軍、もう一つは南西方面軍、残りは最高軍司令部の予備部隊から送るのです。
この軍団の司令官には、経験もあり積極的な人物をもっていく必要があります。
私としては、ワトゥーチンを推薦したいと思います」
するとスターリンはいった。「何をいうのかね君は、モスクワに対する防衛を弱めてもよいという気かね?」
「いいえ、そうではありません。一二日ないし一五日もすれぱ、我々は極東から、一戦車師団を含めて強力な少なくも八個師団をよびよせることができるのです。そうすれば、モスクワ防衛線は、弱まるどころか、補強されます」
「そうして極東を日本に渡すか?」とメフジスが横から皮肉な調子で口をいれた。
私はそれに答えず、説明を続けた。
「南西方面軍は、ドユエプル川以西からは完全に撤退する必要があります。
そして、中央方面軍と南西方面軍の接点のところに、予備隊として、少なくとも五個師団を結集するのです」
「すると、キエフはどうなるかね?」とスターリンが質問してきた。
「キエフ」「放棄」という二語が、すべてのソ連国民にとって、またスターリンにとっても、どんな響きをもって聞かれるか、ということは私にもわかっていた。
しかし私は、感情におぼれることは許されなかった。
軍人として私には、現在の窮境の中で、自分がたった一つ可能だと思った決定を申し述べる義務があった。
私はさらに続けた。
「キエフは見捨てることになるでしょう。
西部戦線では、一刻も早く反撃の準備をして、エリニャに進出してきている敵を排除する必要があります。
敵は、このエリニャを、モスクワ攻撃の基地に利用します」
「そんなところで反撃だって! 冗談をいうな。キエフを敵に渡せると思っているのかね、君は!」
スターリンは怒り出した。
私もつい自分がおさえきれず、反発した。
「参謀総長が冗談しかいえない人間だと思っているのなら、もうここでは、何もやることはありません。
お願いです、参謀総長をやめさせて下さい。そして戦線に送って下さい。
戦線ならおそらく、少しはお国に役立ち得ると思います」
「興奮しちゃこまる。しかし、君が問題をそうとるなら、我々は、君なしでもやっていけるだろうよ……」
とスターリンは答えた。
それから私は、戦局については自分の見解をもっているということ、そしてそれに基いて戦争を遂行できるとも考えていることを述べた。
それだから、自分としては、私がそう考え、参謀本部スタッフも賛成したところを具申したのだ、といった。
「行きたまえ、仕事を続けてくれ。我々はここで相談するから。まとまったらまた呼ぶよ」
私は、地図をまとめて、憂うつな気持で部屋を出た。
四〇分ほどして、最高軍司令部へよばれた。そこでスターリンは、私に次のようにつげた。
「さて、我々も、いろいろ相談してみたが、結局参謀総長はやめてもらう、ということになった。
後任には、シャポーシニコフがなるだろう。
どうも彼は、体が本当ではないようだが、まあいいだろう、私たちが助けてやれる」
「私をどこへとばそうというのですか?」
「どこへ行きたいかね?」
「もちろん私は、何でもやれます。師団でも、兵団でも、軍でも、方面軍でも、どこでも指揮をとれます」
「興奮しちゃいかん、興奮しちゃいかん。そうだ、君は、エリニャの反撃について話したね。うん、この仕事を君やってくれたまえ。君を、予備方面軍司令官に任命する。いつ出発できるかね?」
「一時間後」
「参謀本部には、すぐシャポーシニコフがやってくるだろう。仕事を彼に引継いで出かけてくれたまえ。
しかし君は、最高軍司令部のスタッフという肩書は残っているのだから忘れないで」とスターリンは結んだ。
「帰ってよろしいですか?」
「まあ、かけたまえ。お茶でも飲もう、何か話そうじゃないか」
スターリンは、もう笑顔をつくっていった。
腰かけた。そして茶を飲み始めたが、話はのらなかった。
出発準備はじきに終った。シャポーシニコフが着任するまで、ワシレフスキー第一代理が総長の仕事に当った。
間もなく、最高軍司令部の代表として派遣されていた西部方面軍から、シャポーシニコフが帰ってきて就任した。
私はグジャツクに赴いた。
そこには、予備方面軍の本部がおかれていたのである。 |
top
****************************************
|