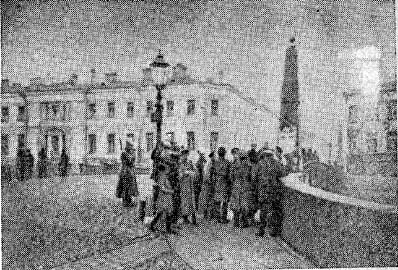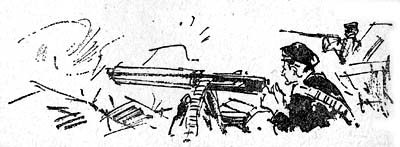|
****************************************
Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Ⅱ 暗雲低迷す
1 危機せまる top
「十一月九日、金曜日」というカレンダーを見て、私はもう二日もたってしまったのかと、いまさらのように驚いた。
時間のたつのがバカに早く感じられて、一ヵ所に数分間いると、イライラしてくる。
つまり私は何かに追いかけられ、何かを追っかけているような落着かない気持ちに、たえず攻め立てられているのだった。
思えば私はこの二日は、息せききって走り続けていたようなものである。
無我夢中で、西に東に、かけずりまわっていた。
いや、こういう間にも、私の体は、じっとしていないのだ。
私は町に出るとまず新聞を買った。
するといきなりドキンとするような記事が、目の中に跳び込んできた。
いわく、
「ノボルチェルカスクにおいて昨日、コサック軍の最高司令官カンティン隊長は、次のような声明を発表した。
“ボリシェビーキが反乱をおこし、政権をにぎろうとくわだてたことは、我々として絶対に許せないことである。
我々はボリシェビーキを、国家の犯罪人とみなす。
よって我々コサック軍のすべては、ケレンスキー内閣をたすけ、ロシアが元通りになるまで、ボリシェビーキと戦う”」 |
そうしてもう一つの新聞には、ガッチナで発表したケレンスキーの命令が、デカデカと書きたてられていた。
| 「総理大臣にしてロシア共和国全軍の最高指揮官たる余は、すべての軍隊が余の命令に従って行動することを宣言する……。」 |
|

ケレンスキー軍――仕官候補生軍と地方のコサック軍が主力であった。
|
ざっと新聞に目を通して、えらいことになったもんだと、私はつぶやいた。
これらの記事はもちろん反革命派の宣伝だけれど、全くの嘘でもはったりでもないことがわかったからである。
ガッチナという町は、ペトログラードから三十キロほど南西に離れたところにある。
そこはボリシェビーキ軍のうちのクロンシュタット水兵や、セミョノフスキー連隊、イズマイロフスキー連隊の一部が守っていた。
ところが夕べのうちに、攻め寄せたコサック兵に取り囲まれ、武器を取上げられ降伏してしまったのである。
ケレンスキーは本当にコサック軍を使って、ガッチナまで巻き返してきたのだ。
牙(きば)をむき出して、ペトログラードの奪還をねらうケレンスキーの姿が、目にみえるようであった。
きくところによるとガッチナばかりでなく、南の方の小さな町のボリシェビーキ軍がバラバラにされ、右往左往しているという。
ペトログラードにケレンスキーを近づけまいとして、ボリシェビーキ軍はあちこちの町を固めたつもりだったが、それはかえって危険を招く結果になったようだ。
ボリシェビーキの軍事革命委員会は、刻々とせまる危険な情勢にそなえて、ペトログラードの防備を固め始めた。
「それはそれとして、鉄道や電信や、郵便のほうは、どうするつもりだろう。」
と、私はつぶやいた。
鉄道の従業員はポリシェビーキに背いて仕事をせず、郵便配達員はボリシェビーキの郵便を取り扱おうとせず、こうしてボリシェビーキは、地方や外部の世界から遮断されていた。
ただ、無線電信による連絡は無事であったし、飛行機も二台あった。
といって、鉄道輸送ができないと物資や人間の動きが止まってしまう。
こうなったら、いくら無血革命を建前としているボリシェビーキだって、そうそう生ぬるいことばかりはしていられないはずだ。
ついに命令がでた。
ボリシェビーキの委員たちが相談して、すべての同志たちに“一丸となって戦うこと”を要求した命令である。
今までになく厳しい命令であった。兵士として働いていた者はもちろん、工場で仕事をしていた者、農民もできるだけ戦いに参加しろという命令なのだ。
「ケレンスキーの軍隊が、首都ペトログラードを奪還にやってくる公算は大となった。
このため市会を中心とする反革命派のやりかたも露骨になってきた。
いつも勝った方につこうとする群衆も、動揺している。
我々の同志の中にも、どっちつかずの態度をとるものが増えつつある。
むろん我々ボリシェビーキは、いたずらに流血を好む者ではないが、世の中から不合理な階級制度をなくし、真に人民大衆のための社会をつくるためには、断固として戦わねばならない。
かくて、工場で働いている同志諸君に命令する。
一、塹壕掘り、バリケード構築、鉄条網の増強のため、できるだけ多くの工場労働者は参加すること。
二、このため、工場の仕事を中止しなければならなくなっても、やむをえない。
三、使用可能の鉄線、および有刺鉄線を全部集めよ。また、塹壕掘りとバリケード構築に使う道具も、全部集めよ。
四、使える武器なら、なんでも手にもて。
五、規律は厳重に守り、決意をかためて我々にしたがえ。」 |
こういう命令のほかに、ボリシェビーキの軍事革命委員会はペトログラードの市民たちにも、断固たる態度を示した。
「市民諸君!
軍事革命委員会は、革命のための秩序を乱すような行為を、断じてゆるさない。
とくに、強盗、殺人などをくわだてたものは、容赦なく厳罰に処する。
合せて、我々の戦いの邪魔をしようとしたり、戦いのどさくさまぎれに悪事をはたらいたり、騒ぎをおこしたり、けしかけたりする者があったら、容赦なく撲滅する!」 |
ボリシェビーキがみせた迫力に、市民たちは一応おとなしくなった。
ただ、市会と反革命派の連中は相変らず、何かをくわだてているようであった。
町の様子は平穏であった。おいはぎも、強盗も、喧嘩騒ぎもなかった。
ボリシェビーキの武装巡察隊が、たえず見回っていたからである。
たまに金持ちの息子の学生が、ボリシェビーキの兵士に嫌味たっぷりな議論をふっかけたり、実業家が労働者を説き伏せようとしたりすることはあったが、大抵の市民はヒソヒソと噂話をささやきかわす程度であった。
「コサック兵は、やってくるでしょうかねえ。」
「さあ、どうかな。」
「何か新しいニュースはありませんか。」
「ペトログラードから三十一キロほどのところに、ケレンスキーがやってきたということですよ。ボリシェビーキの一部の連中は、軍艦オーロラ号へ逃げ込んだそうです…」 |
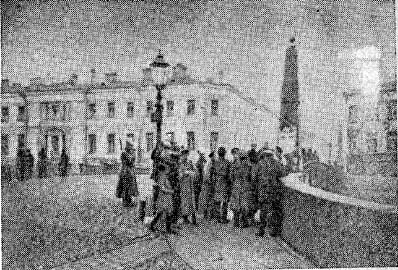
パトロールするボリシェビーキの武装巡察隊
|
ひところのように、ひどい噂話やデマがとばないのは、人民委員会議議長のレーニンが、そのような新聞の発行を取締ることにしたからであった。
レーニンは反対派の新聞が書きたてるニュースが、爆弾や機関銃と同じような威力をもつことを恐れ、しばらくのあいだ発行禁止する布告をだしたのである。
こうして、嵐の前の静けさとでもいうべき状態で、十一月九日は終った。
十一月十日、土曜日。
「いよいよ一戦(ひといくさ)が始る。」
と思うと、私はより確実な真相をつかみたくなった。
戦いがどういう成り行きになるかを知るためには、確かな情報が必要である。
私は市会へと足を運んだ。
町の様子は昨日に引続き、とくに変ったことはなかったが、市会ではみんながひどく色めきたっていた。
どこからかき集めたのか、反革命派の士官たちが、ウロウロしている。
この士官たちはケレンスキーの軍隊がなだれこんできたとき、一緒になってボリシェピーキ軍と一戦交えるつもりらしい。市長は反革命派の主な連中と、何かさかんに相談していた。
そこヘ一人の役人が、ケレンスキーの布告文を一枚もって、かけこんできた。
その布告文は、今朝ほどネフスキー通りに、低空飛行でやってきた飛行機から、何百枚もばらまかれたものであった。 |

市会に集まった反革命派の連中は、
ケレンスキーが出すビラを見て色めき立っていた。
|
もちろん、私も拾って読んだが、
「今のうちに降参しないと、あとでどんなにひどい罰をうけるかしれないぞ。
さあ、ボリシェビーキの貧乏な兵士たちよ。元のとおり武器を捨てて、ケレンスキー政府にしたがえ。
すぐに練兵場に集合して、我らの命令をまつのだ。我らはもうすぐペトログラードヘ乗込む。」 |
という、脅かしの文句を書きつらねたものであった。
私は戦いの情報を求めてやってきたのだが、どうも満足すべき答えは得られそうもなかった。
すでに私が知っていること以外は、あいもかわらぬ噂話ていどの情報なのである。
「内閣総理大臣ケレンスキーは、ツアールスコエ・セローの町を占領して、ペトログラードヘあと八キロの地点までせまった。明日にはケレンスキー軍が、堂々とここへ攻めこんでくるだろう。」
「ケレンスキーがひきいるコサック兵は、ボリシェビーキ軍を片っ端からやっつけ、ドンドン味方を増やしつつあるとのことだ。」
「この知らせにおびえた市内のボリシェビーキ軍も、次々と武器をなげすて、革命戦線からはなれている。」
「国立銀行の従業員と食糧供給委員会の者たちと電話交換手たちは、ボリシェビーキの委員たちの下で働くことを拒絶したぞ。」
「外務省の六百人の事務員、労働省の従業員たち全部も、ボリシェビーキ委員のいうことを、全くきかなくなった。」 |
私はこれらの情報を、うんざりしながら聞いていたが、そのうち、
「ボリシェビーキは、スモーリヌイ学校をすてて逃げ出したぞ。」
という言葉をきくと、さすがにハッとして市会をとびだした。
スモーリヌイ学校は、いわばボリシェビーキの本山である。
それを投げ出したということがもし本当なら、ボリシェビーキはどこへ行くのか。
「まさか……」と思いつつ息をきらして、私はスモーリヌイ学校へ駆け付けた。
なんたるデマだ。あまりにもでたらめなデマに、私は腹もたたなかった。
スモーリヌイ学校は安泰で、いっそう忙しく労働者や兵士が出入りしていたのである。
私は前よりも見張りが厳重になった入口のところで、反対派の新聞記者や中立派の新聞記者たちとでくわした。
「おい、アメリカの新聞記者さん。ボリシェビーキのやつらは、僕たちを放り出しやがった。僕たちに出て行けといったんだ。僕たちがスパイだともいった。
こんな侮辱があるもんか。まさに暴力だよ。言論は自由だぜ。新聞の発行とか、雑誌の発行とかを妨げるボリシェビーキは、自由の敵だ。
やつらは、ふたことめには自由、自由というが、これじゃあ大嘘つきだよ。ボリシェビーキは、嘘つきの暴力団だ。労働者も兵士も、いまに騙されて、きっと泣くに泣けぬようになるだろう。」 |
新聞記者たちは、ののしり、わめきちらした。
なるほど、言論の自由を束縛するような社会に、本当の自由はない。
しかし新聞記者たちの方も、少しばかり自由をひけらかしすぎるところがあった。 |

スモーリヌイ学校の入口で出会った反対派の新聞記者や、
中立派の新聞記者たちの話を聞く筆者。
|
なりよりもこの新聞記者たちは、自由自由といいながらボリシェビーキ革命の邪魔をしているのである。
ボリシェビーキが彼らを追い出したのちも、今の処、仕方ないことではないか。
私は黙って彼らの傍をすりぬけ、控室に入っていった。
彼らはあっけにとられたように、自由な振舞いをする私を見送っていた。
控室の大きなテーブルの上には、軍事革命委員会が発した命令や布告文や通達をすりこんだビラが、うず高く積んであった。
労働者や兵士がビラの束を、ウンウンいいながら次々と外の自動車に運び込んだ。
私は一枚のビラを、ひょいとつまんで読んでみた。
「ロシアの人民大衆が必死で戦いぬこうとしている今、ポリシェビーキ党や右翼社会党の連中は、昔の理想をすて労働階級を裏切った。
彼らは、ケレンスキーたち一派についたのだ。
彼らは裏切り者ケレンスキーの命令を印刷して、反革命の宣伝の片棒を担(かつ)ごうとしている。
何も知らない町の人たちを、まどわせている。
市民諸君! 嘘とでたらめで固めた噂を信じてはいけない。
いかなる虚偽の力も、革命を破ることはできないのだ。
ケレンスキーとその一派は、もはや我々の手ではりつけ台に縛(しば)られるのを待つばかりなのだ。
彼らは我々の同志、労働者、兵士、水兵、農民のすべてを、昔のように鉄の鎖でつなごうとしているが、我々は今度こそ反対に、彼らを葬(ほうむ)ってやる。
人民を裏切った者どもに、恥と呪いの罰をあたえてやる。」 |
相当激しい調子のビラの文章をよんで、私はちょっと身ぶるいを感じた。
私は軍事委員会の部屋へ上っていった。
スモーリヌイ学校の一番上の第十七号室である。
兵士がドアの前に頑張っていたが、私にはなんともいわなかった。
室内には立派な服装をした金持ちや、外国人たちがひしめいていた。
「おや? 捕えられたのかな。」
と私は思ったが、それは勘違いであった。
この人たちはペトログラードの町を捨て外国に逃げ出すために、パスポート(旅券)をもらいに来ているのだった。
金持ちたちは、
「ボリシェビーキが天下をとるようなロシアになんか、死んでも居たくない。」
といいたげな顔つきをしていた。しかしボリシェビーキの人々は、
「ああ、出て行きたければ、出て行きなさい。」
というふうに、あっさりパスポートを作ってやっていた。 |

軍事委員会の部屋では、革命ロシアを去るため、パスポートを貰いに来たブジョワがひしめいていた。 |
私はビル・シャトフとペテルスという二人の当番に、最新の報告をきかせてくれと頼んだ。
「ああ、いいとも。」
二人は仕事の手を休め、気やすく書類つづりを取上げて、読んでくれた。
「第百七十九予備連隊が、全部我々の味方になった。
プチロフ波止揚の、荷あげ労働者五千名が、我々のレーニン新政府を祝福してくれた。
労働組合中央委員会も、熱狂的に我々を支持してくれることになったよ。
レベルの守備隊と小艦隊は、新しく我々の陣営にくわわるため、軍隊をよこしてくれそうだ。……
遠くではフィンランド師団、第五、第十二師団が、我々に従うといってきた。
それから、モスクワからのニュースはあまり確実じゃないけど、我らの同志軍が重要な地点を占領しているそうだ。
クレムリン宮殿を守っていた二個中隊も、我々の方についた。
しかし、兵器廠は敵が握っているらしい……。」
「ありがとう。」
と、私は礼をいって、二人の表情をさぐるようにみつめた。
二人はニコニコしているが、どことなく不安な顔色をしていた。
ケレンスキーのコサック軍は、大砲をもって、早い速度でおそいかかりつつあるのだ。黄色い顔をした書記に、
「顔色か悪いね。」
と、声をかけると、彼は顔をゆがめ、
「やつらの兵力は一個軍団だ。しかし、やつらは決して我々を打ち負かすことはできん。」
と、あらあらしくいった。
「ひょっとすると、我々は、明日から永久に眠れることになるかもしれんな。」
と、冗談めかしていったのは、眠そうな顔をした兵士だった。すると、もう一人が横から口をはさんだ。
「敵は訓練されている。我々は寄せ集めた。」
どうも、頼りないことばかりいう人たちだが、へたに大ボラふいたり、空(から)元気をつけたりするより信用できる。
もちろんこの人たちは、どこまでもやる気にちがいなかった。
つぎに私は、ほかの部屋やホールをのぞいてまわった。
ちょうどどこの部屋でも、一つの伝達がはりだされたところであった。
その貼紙には、クラスノエーセローの町よりとして、
「わが守備隊はガッチナから退却したが、これに作戦のためである。」
というようなことが書いてあった。
「すると、ペトログラード南方や南西部の町に出ていたボリシェビーキの兵士たちは、本当にケレンスキー軍からけちらされたのだな。
ガッチナ、パウロフスク、ツァールスコエ・セローなどの守備隊は、本当にやられバラバラになり、ペトログラードヘ逃げ帰りつつあるのだな。
なにしろケレンスキーの軍隊は、十倍の戦力だというから無理もないが……」
と私は推察した。ポリシェビーキ軍の旗色は、ひどく悪いのである。
外へ出ると空の色が暗く、憂鬱(ゆううつ)な感じだった。
重苦しい 気をつんざくように、あちこちの工場の汽笛が、いらだたしい音を響かせている。
|

男も女も、あらゆる労働者、あらゆる貧乏人が
自ら勇んでイソイソと任務についていった。
|

武器をもった労働者たち
|
男も女も、あらゆる労働者、あらゆる貧乏人が、工場から町の片隅から流れだし、南方へ、南西方向へと急いでいる。
「コサックがくる。我らのペトログラードがあぶない。」
男、女、子供でさえ銃をかつぎ、鶴嘴(つるはし)を持ち、鉄線や弾薬をかかえ、ぞくぞくと流れていった。
人々の流れは、巨大な激流のようであった。
この人たちは自ら勇んでイソイソと任務についたのだ。
こん何もあらゆる人々が一斉に立ち上がったことは、どこの国の歴史にもない。
「労働者、農民の共和国の首都ペトログラードを、体当りで守る革命的大衆!」
と、私はメモに書きしるした。
流れゆく大衆労働者のそばを、ボリシェビーキの兵士の群れ、トラックなどが急流のように流れていった。
急流、激流がいりまじって奔流となったが、流れの方向は一つであった。このとき、
「そうだ。俺も行けるところまで行ってみよう。」
と、私は決心した。
2 戦線をゆく top
スモーリヌイ学校の玄関のところで、私は一台の自動車をつかまえた。
粗末な外套のポケットに両手をつっこんで、背の高い男が自動車によりかかっていた。
アントノフである。
それともう一人、澄んだ目をした髭づらで大男の水兵がいて、ピストルをもてあそんでいた。
これはドイペンコだった。
アントノフとドイペンコは、陸海軍人民委員である。
いわば、陸海軍大臣といった役目だ。
この二人が乗っていく自動車なら、きっとどこかの戦線を視察にいくのに違いない。
「乗せてもらいますよ。」
といって、私は、さっさと車に乗込んだ。
ずうずうしく振舞うのが、新聞記者の奥の手だ。
二人の人民委員はちょっと目を見張ったが、黙っていた。
運転手とアントノフとドイペンコと私と、トルシシュカという男の五人を乗せて、車は走り出した。
スボロフスキー通りにさしかかったとき、誰かが
「二、三日分の食糧を買っといた方がいいんじゃないた。」
といった。しかし、人民委員ともあろうものが、二人とも一文なしであった。
やっとトルシシュカがいくらか持っていて、通りの店からさしあたりの食べ物を買ってきた。
私はあらためて感心した。
まがりなりにもボリシェビーキは、いまペトログラードを制圧しているのである。
かってな振舞いをしようと思えば、いくらでもできる。
食糧がなければ、掠奪するのが普通の行為だろう。
革命とか内乱には、それがつきものだ。
しかしボリシェビーキの人々は、たとえ一文なしで腹をへらしていても、町の商店を襲ったり品物を強奪したりしようとはしなかった。
車がネフスキーの通りの方へまがると、今度はタイヤがパンクした。
「弱ったな。どうしよう。」
と、アントノフがいった。
「ほかの車をつかまえるほかない。」
と、ドイペンコが、ピストルを振り回した。
さっそくアントノフが、道路の真中に立ちはだかり、一人の兵士が運転している自動車を呼び止めた。
「その車を、よこせ。
「冗談じゃない。嫌だよ。」
と、兵士はどなりかえした。
「僕は人民委員のアントノフだ。このとおり、非常のときにさいして、僕は全同志軍の司令官にも任命された。
君たちは、文句なしに、ぼくの命令にしたがわなくちゃならんのだ。」
と、アントノフは、証明書と命令書をさしだしてみせた。
すると、兵士は恐縮するどころか、ひどく怒って大声を張り上げた。
「この自動車は第一機関銃隊のもんだよ。俺たちは、これで弾薬を運んでるんだ。つまり、あんたの命令どおりに、戦闘準備をしてるんだ。さあ、どいてくれ。」
アントノフは、仕方なさそうに、
「そうか。頑張ってくれ。」
というほかなかった。
ボリシェビーキの兵士たちは、相手が司令官であろうが人民委員であろうが、決してヘイコラしない。
この点も、まことにかわっていた。
そこヘ一台の自家用車がやってきた。イタリア国旗をたてているが、のっているのは、高価な毛皮のオーバーをきた金持ちのロシア人であった。よその国の旗をつけているのは、ごまかしのためである。
アントノフは、目をかがやかせて、その自家用車を徴発した。金持ちはボリシェビーキの敵である。
金持ちのものは、遠慮なくとりあげることになっているのだ。 |

ボリシェビーキ軍は自動車が不足していたが、
丁度ブルジョワの自家用車が通りがかったので、徴発した。
|
私たちはこの車に乗り移り、ペトログラード市から約十六キロほどはなれたナルブスカヤ・ザスタバに到着した。
ここではボリシェビーキ軍の指揮官の元で、数百人の労働者が塹壕(ざんごう)を掘りおえ、コサックの来襲に備えていた。
「同志。すべてうまくいってるかね?」
と、アントノフがたずねた。
「大丈夫です、同志。わが同志軍は、全員意気さかんです。しかし、弾薬がありません。」
と、指揮官は答えた。
「なに? 弾薬がない? スモーリヌイ学校に二十億発あるから、それをすぐわけてもらってくるんだ。
よし、命令書を書いておくから、これをもって行きたまえ。」
アントノフは忙しくポケットをさぐった。
命令を書く紙と鉛筆を、探したのである。
何にもなかった。
「おい、誰か紙を持っていないか。鉛筆もだ。」
驚いたことに、ドイペンコは何一つ持っていなかった。
いや、人民委員が一枚の紙も、一本の鉛筆も持っていないなんて、驚きあきれたのは私だった。
ここはこのくらいにして、私はまたペトログラード市にとんでかえり、駅にいってみた。
ツアールスコエ・セローの町まで、汽車が動いていると聞いたからだ。
駅にいく途中、私は、赤衛軍の行進をみた。
赤衛軍というのは、ボリシェビーキ軍のうちの、もっとも本式の部隊である。みんな武器をもっていた。
彼らは姿勢もただしく、冷たい泥道の中を四列縦隊でまっすぐ歩いていった。
とても若々しい兵士たちであった。彼らは、みんな死を覚悟した顔つきをしていた。
惜しいことに軍楽隊もなく太鼓もなかったが、彼らの足並みはよくそろっていた。
先頭の赤旗には「平和! 土地!」という字が、なぐりつけるように書かれていた。
町の群衆は、半分恐れ半分軽蔑したような目つきで、赤衛軍の行進をみつめていた。 |

赤衛軍の行進を見つめる市民たち
|
さて私がのった汽車は、いろんな種類の人で満員であった。
誰も彼も、革命のことケレンスキーのこと、いよいよ両軍がぶつかりあうらしいことなどを、大声でしゃべりあっていた。
「こういう一般の民衆は、自分たちの運命について、どうしてもっと真剣に考えないのだろうか。
どうにかくらしに困らない人たちは革命が成功しようとしまいと、自分たちの知った事じゃないと考えているらしい。
呑気なものだな。」
と、私はつぶやいてみた。
ボリシェビーキの人々は、労働者、農民、兵士たちを同志にして、貴族や金持ちや権力者をぶっつぶし、みんなが平等になる社会をきずこうとして革命をおこした。
一方、権力者や金持ちたちは、今まで通りの社会を維持しようとして、ボリシェビーキに立向った。
そうして、どっちつかずの一般大衆は、いくぶんボリシェビーキを憎みなながら、成り行きをみている。
この人たちは、自分たちも金持ちになりたいと思っているし、金持ちがいなくなる社会なんて嫌だと、単純に考えているのである。
簡単にいえば、このたびのロシア革命は、ブルジョア階級(上層階級)と、プロレタリア階級(下層階級)の戦いなのだが、そもそも人間の社会には、なぜブルジョアとプロレタリアができたのか、深く考えてみるとむずかしい問題であった。
お互いに人間どうし同じ国民どうしでありながら、階級があるばかりに、激しく闘争する……。
あれこれ思いをめぐらしているうちに、汽車はツアールスコエ・セロー駅についた。
ここから先は、汽車は一切、動いていないのである。
「戦闘地域にきたぞ。」
私はさすがに、身の引き締まるのを覚えた。
3 敗北の色 top
ツアールスコエ・セローの駅は、みたところ平穏無事であった。
しかし、あちこちにむらがっている兵士たちは、不安そうな様子をしていた。
彼らはボソボソと小声で話合い、時々ガランとしたガッチナ方面への道を眺めた。
私は、彼らの一同にちかずいて、
「君たちは、どっち側ですか。」
と、きいてみた。
「私たちは、事件の真相をくわしくしらないんですよ。
いくさをしかけて、ボリシェビーキを怒らせたのは、ケレンスキー側ですね。
それはわかってるんだけど、どうも私たちはロツア人同士で射ち合ったり、殺しあったりするのは、間違いだと思ってるんです。」
と、一人の兵士が、あいまいな返事をした。
どっちつかずの兵士と話をしても、頼りない気がするばかりである。
|
私は駅の司令官室にいった。
赤い腕章をつけた、大男のひげづらの普通兵士がいて、私がスモーリヌイ本部からもらった証明書をみせると、陽気に敬礼した。
この男は、ボリシェビーキの味方だったが、どうやらおいてけぼりをくったらしい。
二時間前には赤衛兵がいたんですけど、またどこかへ行っちまいましたよ。
けさ、一人の委員も来たんですけどね、すぐペトロダラードに戻りました。」
と、彼はしょげてみせた。
「コサックが攻めてきたのですね。」
と、私はいった。
「ええ。コサック兵は、朝早くやってきました。
もちろん戦闘になりました。コサックのやつらは、我々の仲間を二、三百人つかまえ、二十五人ほど殺しました。」
「で、コサックは、どこにいるのですか。」
「さあ、どこにいったのか、あっちのほうへいきましたよ。」
と、彼は、西の方を指さした。これも、頼りないことおびただしい。
「こんなことでいいのか? ボリシェビーキは、ジリジリとやられてるじゃないか。」
と、私は妙にいらだたしい気分に攻められて、舌うちした。 |

駅の指令室の兵士から
この地の様子を聞く筆者
|
私は、レストランがあるのをみつけ、ふんだんに夕食をした。
不思議なことに、この駅のレストランには立派な夕食があり、ペトログラードよりウンと安かった。
ちょうどこの時、ガッチナからやってきたフランス人の士官が、私のそばに腰をおろした。
革命戦争の見学をしているらしい。
「ガッチナは、ケレンスキーが占領しましたよ。いまは静かでした。」
と、フランス人は、私に教えてくれ、
「何という変な内乱でしょう。ロシア人のすることは、独特です。
戦争するやつは、むきになってやるが、したくないやつはケロリとして見物したり議論したりしている。」
と、あきれたようにつけくわえた。
私は町へ出かけることにしたが、駅の入口でさっきのフランス人が不思議がったような光景に出くわした。
銃剣をもった二人の兵士が、百人ほどの実業家や官吏や学生に取り囲まれて、さかんに悪口をいわれていたのである。
兵士はいたずらもしないのに叱られた子供のように、ふくれつらをしていた。
しかし目の前の人々を、射ち殺そうとは決してしなかった。
生意気な顔つきの、のっぽの学生が、一番激しく兵士をののしっていた。
「どうせ、君たちは労働者だから、よくはわからないだろうけどさ。
君たちはいわば人殺しの道具みたいなものなんだぜ。ボリシェビーキの道具さ。
君たちはわけもわからず、同じロシア人に鉄砲をむけてるんだ。」
「しかし、兄弟よ。二つの階級があってさ、プロレタリアートとブルジョアジーの二つの階級があって……」
と、兵士は、一緒う懸命口ごたえをする。
「なにいってんだ。そんなばかげた理屈なんか、とっくに知ってるよ。僕は学生だからね。
そもそも君たちのような、無知で脳なしの百姓どもは、気のきいた言葉をきくと、すぐのぼせ上っちまうんだ。
意味もロクロクわがらずに、ブルジョアとかプロレタリアとか、オウムみたいに言うんじゃないよ。」
とりかこんでいる人々が、ゲラゲラと笑った。
学生は、ますます傲慢(ごうまん)に肩をそびやかし、大声を張り上げた。
「僕はこれでも、マルクス主義を勉強した学生だぜ。レーニンさんと同じようにね。僕はチャンとわかってるんだ。
君たちが戦いとろうとしているのは、本当のボリシェビーキの社会じゃないんだ。
君たちはドイツの手先みたいなものなんだ。」 |
|

二人の銃をもった兵士が、群衆に囲まれて
革命側の悪口を言われていた。
|
「そりゃあ、おまえさんは教育のある人間だろうよ。頭がいいことはわかる。
俺たちは、教養も何もない人間にすぎん。けれども、俺たちは信じている……」
と、兵士は、汗びっしょりになって、真剣に答えようとした。
「ふん、何を信じているか、僕の方からいってやろう。
レーニンさんこそプロレタリアートの、本当の友だちだというんだろう。どうだい。」
「そうさ、そうとも!」
と、兵士は、強くいった。
「そんなら、いいこと教えてやろうか。
レーニンはドイツを通って帰ってきたとき、ドイツからこっそり金をもらったんだぜ。
つまり、スパイ料さ。どうだ、知ってるかい。」
「知るもんか。とにかく、誰がなんといおうと、レーニンのいうことは、みんなが信じてるんだ。」
「アーア、バカにつける薬はないね。君たちはだまされてるんだ。
こうみえても、僕だって二年間、革命のために働いたんだよ。
そしてよくわかったんだが、ボリシェビーキは我々のロシアを破壊し、真に自由な革命を妨げているんだ。
僕は、ボリシェビーキに絶対反対だ。」
「おまえさんが、学問した頭で何を考えようと勝手さ。
ただ、俺たちは教育なんかうけてないけど、二つの階級プロレタリアとブルジョアがあって、一方の側にいない者は別の側にいるってことだけは、チャンとわかってるんだ。」
と、兵士は、頑固にいいつづけた。
学生は歯ぎしりするように、まだ何か叫んでいたが、いいかげんで私は、そこをはなれた。
私は暗い町通りをうろついたが、歩いている人はほとんどいなかった。ぶきみな静寂が、町全体をつつんでいた。
しかし、理髪店と風呂屋には、明々とあかりがついていて、に賑やかであった。
そういえば、今日は土曜日だ。ロシア人は土曜口の晩には、風呂に入り香水をつける習慣なのである。
「ひょっとすると、コサック兵もボリシェビーキの兵士も、一緒になって風呂にはいっているのではあるまいか。」
と、私は妙なことを考えた。 |

革命騒ぎの土曜日の晩の町は、普段と変わらなかった。
|
国をあげて革命騒ぎの最中だし、しかもいつ弾丸が乱れ飛ぶかもわからない時なのに、依然として土曜日の晩のしきたりだけはやめないロシア人。全く、不思議なロシア人ではないか。
公園のほうに近づくと、人通りは全然なくなり、一人の兵士がズボンに手をつっこんだまま、ブラブラしていた。彼は、
「ボリシェビーキの連中なんて、とっくにどこかへ行っちまったよ。」
と、いった。
「どこへ行ったんです。」
「知らんね。」
とりつくしまがない。先へ歩いていくと、水兵と兵士が手をつないでやってきた。
私は、スモーリヌイ本部でもらった証明書をみせ、
「あなたたちは、ボリシェビーキ側でしょう?」
と、声をかけたが、二人はギョッとしたふうに顔を見あわせ、さっさと遠ざかってしまった。
しだいに、うす気味悪くなってきたが、ひきかえす気にはなれない。
私は、巨大なエカテリーナ宮殿のほうへ、なおもすすんだ。
宮殿のまえは、池や橋のある庭園になっていて、昼間は美しい眺めなのだろうが、今は暗く陰気な感じであった。
ふと、私は人の気配を感じて、たちすくんだ。はたして、すぐそこの草むらに、六人の武装した兵士がひそんでいた。
ここで、ひるんではいけないと思ったので、私は、
「あなたたちは、誰です。そこで何をしてるのです。」
と、せいぜい威張った声をだした。
「番兵です。」
と、一人が答えた。
「みなさんは、ケレンスキーの軍隊ですか? それとも……」
「我らは中立です。」
「僕はアメリカの新聞記者。」
と、いいすてて、私は宮殿内に入り込んだ。
中にはまた、歩哨がたっていたが、
「司令官に会いにきた。」
と声をかけ、私はかまわずに建物の内部へと歩みをすすめた。
一つの優美な部屋に、一群の士官たちが、心配そうな顔をよせあって集まっていた。
みんな寝不足らしい。顔色が青く目が赤い。彼らは議論しつづけたようであった。
私は軍服に勲章をつけた、白ひげの大佐の前にたつと、ボリシェビーキ本部でもらった証明書をみせた。
大佐は、びっくりして声をふるわせた。
「よくも殺されずに、ここへ来られましたね。その証明書は、ここでは危険ですよ。
この町では、けさ戦闘があって、ボリシェビーキの味方をする者は、ほとんどいなくなっています。
あしたも戦闘があるでしょう。ケレンスキーは、八時にこの町へはいってくるそうです。」 |
「コサックは、どの辺りにいるのですか。」
「約一キロ半ほどはなれた地点です。」
「では、大佐。あなたたちは、コサックが攻めてくるのをふせぐのですね。」 |

エカテリーナ宮殿の一室では、一群の士官たちが会議をしていた。
ケレンスキーが明日、この町へ来るための迎えの準備であった。
|
「いや、いや。我らはケレンスキー閣下のために、この町をまもっているのです。」
と、大佐は気の毒そうにいった。
「だから、ボリシェビーキの証明書をもっているあなたは、いわば敵です。
そんなものはお捨てなさい。コサックにつかまったら、命があぶない。
どうしても戦闘が見たいなら、私が新しい証明書を書いてあげるから、明日の朝七時までに、ここへおいでなさい。」
「本当に大佐は、ケレンスキー軍の味方なのですか。」
と私は、しつこく訊ねた。
「そういわれると困るが、つまり士官というものは、ケレンスキー側につくほかないのですよ。
さもなければ、軍人をやめるほかない。軍人をやめたら、食えませんしね。
兵士たちは、ケレンスキー側ではありませんが、中には、戦いたくない者も、ずいぶんいるんですよ。
とにかくこの町にいたボリシェビーキ側の兵士は、今朝の戦闘で追われて、ペトログラードへ退却してしまったんです。」
「僕も、ペトログラードへ帰りましょう。」
と、私はいった。
「それがいい。この町には、あんまり長くいないほうがいい。」
大佐はまことに親切で、兵隊をよぶと私を駅まで送らせてくれた。
私の考えでは、この町はケレンスキーの勢力下にあり、従ってもう戦鬪はないだろうと思われた。
「ボリシェビーキは、敗北しつつある。」
とも思った。
寒い暗闇の中をつつ走る汽車の窓から、私は焚火をしている兵士の群れや、装甲自動車の群れを見た。
ペトログラードへ退却しているボリシェビーキ軍にちがいなかった。
指揮者のいない兵士や赤衛軍は、混乱しさまよっているように見える。
軍事革命委員会の委員たちが、あちこちととびまわって全軍をまとめ、ペトログラードの防衛に全力をつくしているのだろうが、はたして大丈夫だろうか……。
4 首都の十字火 top
私がペトログラードに帰り着いたとき、町の雰囲気は一変していた。
何かしら、ただならぬ空気が、町中にみなぎっているのであった。
ひどく興奮して、町々にあふれた群衆は、夜ふけになっても寝ようとはしなかった。
町の群衆は、もうすぐ何かが起こることを知っていた。
町はしだいに、雑多な物音や人々の叫び声などで、煮えたぎる坩堝(るつぼ)のようになっていった。
そうして、真夜中に士官候補生の一隊が、反撃の火ぶたを切ったのである。
この一隊はたくみに変装して、電話交換局に姿を現したという。
交換局を警備していたボリシェビーキの兵士は、てっきり交替の同志がきてくれたのだと思って、怪しみも疑いもせず、彼らを迎え入れた。
士官候補生の一隊は、合言葉まで使ったのだ。
やがて、委員のアントノフが見回りにきたが、士官候補生の一隊にとらえられ、一室に閉じ込められてしまった。
かくて電話交換局を、まんまと乗っ取った彼らは、その後さらに交替にやってきたボリシェビーキの兵士に一斉射撃をあびせ、数人を射ち殺したのである。
外からはケレンスキーが攻めてくる。
内には、相当な反撃の火の手があがった。
ボリシェビーキは、ペトログラードをまもりとおせるか?
……私としては、ことの成り行きを見まもるほかない。 |

ただならぬ様子のペトルグラードの町
|
十一日、日曜日の朝がきた。
聞くところによるとこの朝早く、コサック兵はツアールスコエ・セローヘ、堂々と進軍してきたとのことであった。
ケレンスキーは意気ようようと白馬にまたがり、すこぶる上機嫌だったという。
すべての教会の鐘が高らかに鳴り響き、ケレンスキーは町はずれの丘の上から、首都ペトログラードをじっくりと眺めた。おそらく彼は、
「今にみていろ。薄汚いボリシェビーキめ。もうすぐ一挙に攻めこんで、貴様らの息の根をとめてやるからな。」
と、つぶやいたことだろう。
実際、へたをするとボリシェビーキは、反革命軍によって息の根をとめられそうな状態であった。
夜明け頃には大部隊の士官候補生軍が、軍用ホテルと電信局を占領していた。
今にも雪が降りそうな空の下で、ペトログラードは銃火の巷(ちまた)と化してしまったのである。
ボリシェビーキ軍は、本気になった。もはや血を流すことを、ためらっている場合ではない。
ボリシェビーキ軍は必死の覚悟で、軍用ホテルと電信局を奪い返したが、この戦闘でついに多くの死者がでた。
一方、水兵たちが電話局を包囲していた。
電話局も占領されているため、ボリシェビーキは、まるで連絡がとれないのである。
反革命軍はボリシェビーキ側につながる線を切り、ケレンスキーは市会や反革命派の連中との連絡だけができるようにしていた。
水兵たちは、樽とか箱とかブリキ板とか町角の建物の陰などに身をひそめ、電話局に向かって近づくものは、なんでも狙い射ちしていた。
一度、砲塔の機関銃をグルグル回転させながら、むやみやたらと弾丸の雨をふりまく装甲自動車がやってきた。
その弾丸で、罪もない町の人や少年が死んだ。
俄然(がぜん)、水兵たちは怒声とともに、装甲自動車へおどりかかっていき、銃剣を何度も銃眼の中へつっこんだ。
水兵たちは、命しらずの熊のように勇敢だった。これほど勇敢な水兵が、何故一挙に電話局を攻撃しないのか。
実は、電話局の交換手たちが女だからだ。
彼女たちを死なせてはならないという思いやりが、水兵たちの攻撃精神をにぶらせているのだった。 |

革命に参加した水兵たち
|
|

ペトログラード市内のあちこでは、ひっきりなしに戦闘が行われていた。
|
ペトログラード市内のあちこでは、ひっきりなしに士官候補生軍とボリシェビーキ軍の射ち合いや、装甲自動車どうしの戦闘が行われていた。
士官候補生軍は、
「もうすぐ、ケレンスキーの大軍がなだれこんでくる。それまで頑張れば、あとはしめたものだ。」
という希望があるせいか、意外に頑強であった。
一斉射撃、単独射撃、耳をつんざく機関銃の掃射音などが、遠く近く絶間なく聞えてきた。
うかうかしていたら、いつ流れ弾にあたるかしれない。
しかし驚いたことに、町の商店は鉄のよろい戸を下しながらも、商売をやっているのであった。
映画館も、表側のあかりをけしただけで、中では映画をやっていた。しかも満員の客なのだ。
もっとも驚くべきことは、市電が走っていることだった。
「ロシアの運命をかけて、ボリシェビーキと反革命派が、血で血をあらう死闘をつづけている最中に、一般市民は商売をしたり、映画をみたりしている。
革命とか戦争とかは、それに熱中した人たちが命がけでやるものであって、一般市民は俺の知った事かと、そっぽをむくものであろうか。どこの国でも、一般市民は何もしないものなのだろうか。」 |
私は、つくづく考えさせられた。
ふと思いついて、私は中央局へ電話をかけてみた。つうじる。
けれどもスモーリヌイ学校とか、ボリシェビーキ関係の建物には、一切通じなかった。
しばらくのあいだ、私は受話器を通して聞える射撃の音に、耳を傾けていた。
うかつに町をとび歩くこともできず、全部の戦闘状態を見て回るわけにもいかず、正直いって私は途方にくれた形だった。
しかし、ボリシェビーキ側の行動に関しては、できるだけくわしく情報を集め続けた。
初めのうち私は、反革命派の反撃にたじろいだボリシェビーキの前途に、大きな不安を感じたものだった。
けれどもしだいに様子がハッキリしてくるにつれて、私はボリシェビーキが、決してマゴマゴしているばかりではないことを知った。
反革命派の手先となった士官候補生軍が動き始めると、ボリシェビーキ軍はさっそく手厳しい行動に移っていたのである。
まずボリシェビーキの兵士、水兵たちの巡察隊は、朝の七時にウラジミール士官学校を訪れ、候補生たちに、
「武器を捨てろ。二十分間だけまってやる。」
と、命令している。
しかし、血気にはやるウラジミールの士官候補生たちは、その命令をはねつけ進撃を開始した。
こうなったら仕方がない。
ボリシェビーキ巡察隊は、門からでてくる士官候補生軍に猛射をあびせ、校内に閉じ込めてしまったのである。
また士官学校を取り囲み、大砲をうちかけ、二台の装甲自動車の機関銃で弾丸の雨をあびせた。
たまりかねた士官候補生は、電話でケレンスキーのひきいるコサツク軍に、救援をもとめたが、とても間に合いそうになかった。ボリシェビーキ軍は、さらに野砲三門で士官候補生軍をおびやかし、
「いいかげんで降伏しろ。」
と、話合いをするための使者まで出したものである。 |
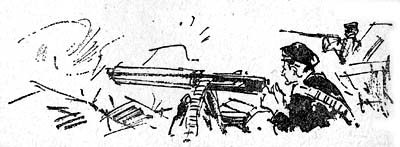
士官候補生軍に猛射をあびせるボリシェビーキ巡察隊
|
ところが、すっかり血迷った士官侯補生は、白旗を掲げて話合いにきたボリシェビーキ軍の代表者二名を、たちまち射殺したのだ。
ボリシェビーキ軍は、完全に激怒した。今までは、脅かし半分だった砲撃を、まともな猛撃にきりかえた。
学校の壁にはみるみるうちに大穴があけられ、そこから兵士たちが突撃を敢行する。
死に者狂いの士官候補生軍は、めくらめっぽうに機関銃で応戦する。
ここの戦闘と、パウロフスキー士官学校の戦闘と、ミハイロフスキー士官学校の戦闘は、凄絶をきわめたものであった。
もちろん、両軍ともに大変な死者が続出した。
なるべくなら話合いでカタをつけようとするボリシェビーキ軍が、この時ばかりは指導者の命令をきかずに、士官候補生の一部を惨殺したのである。
いかに激しい戦闘になったかは、この事からもわかるであろう。
何よりも本気で怒ったボリシェビーキ軍は、もういかなることにたいしても、なまぬるい話合いとか、遠慮気兼ねをやめたのであった。
従って午後になると、電話交換局を包囲していたボリシェビーキの水兵たちも、一斉に突撃を強行した。
士官候補生たちは、おそるべき殺意をむきだしにした水兵たちに、すっかり縮みあがってしまった。
「やつらは、僕たちを殺す。ああ、殺される。」
と、士官候補生たちは、だらしなくも悲鳴をあげ逃げまどった。
実際、水兵たちは士官候補生を皆な殺しにする勢いであった。
「貴様らは冬宮で、今後絶対武器をとらない、刃むかわないと誓ったではないか。
それで牢獄にもいれられず、釈放された。
ところが、いつのまにか誓いにそむき、我々の革命の邪魔をした。我々の仲間を殺した。」
と、水兵たちは、土官候補生たちに、怒りをぶちまけた。
とはいうものの、水兵たちは今度もまた、士官候補生たちを放免してやったのである。
何故なれば、委員のアントノフを無事に助け出さねばならなかったからだ。
水兵と労働者たちは血だらけになり疲れ果てていたが、それでも電話交換局を奪い返した喜びにふるえ、交換機室に駆け込んだ。
たくさんの美しい少女たちが、金切り声をあげ、恐怖に目をひきつらせて、部屋の片隅に逃げた。
水兵たちは困ったように、モジモジした。
これをみると少女たちは腹を立てた猿のように、目をむき歯をむきだして、言いたい放題の悪口を投げ付け始めた。
「あんたたちは、獣(けだもの)よ! 豚よ! でていってちょうだい!
ここは、あんたたちのような、汚ならしい人間の来るところじゃないわ!」
彼女たちだって、電話の交換手という労働者なのだが、彼女たち自身は、貴族にあこがれているのだった。
士官候補生は、ほとんど貴族の坊ちゃんたちである。
彼女たちは貴族の坊ちゃんたちのために、弾薬を運んだり負傷の看護をしたりすることに、少女らしい喜びを感じていたのだ。 |

電話交換局を奪い返し交換機室に駆け込んだ水兵と労働者たち。
そこには交換手の美しい少女たちがいた。
|
水兵や労働者にむかって、なおもムチャクチャな悪口をいう少女たちを、軍事革命委員のビシニャクが、おだやかな口調でなだめようとした。
「みなさん。どうか我々とともに、働いてください。
みなさんは我々と同じように、働く仲間じゃありませんか。よく考えてください。
あなたたちは、今まで、実に安い賃金で、一日十時間以上も労働していた。
我々の敵、ブルジョワ階級が、あなたたちをこきつかい、しぼりあげ、自分たちは楽々としていたのです。
我々ボリシェビーキの政府は、あなたたちの給料を引きあげ、労働時間を短くします。
あなたたちは労働者階級の一員として、幸福でなければならない。ね、そうでしょう。」
「私たちが、労働者階級の一員ですって! あんたたちの仲間ですって! とんでもない。
私たちをそんな汚ならしい人たちと、一緒にしないでよ!」
少女たちは口々に叫ぶと、われさきに部屋をでていった。
この少女たちに、いくら革命の意義を説明しても、無駄なようであった。
彼女たちにとっては革命なんかより、お化粧やおしゃれの話のほうが、よっぽど大切なのだ。
それでも六人の少女が残ってくれた。
電話は重要な連絡道具である。
六人の少女に、交換機の動かし方をおそわって、水兵や労働者たちが、けんめいに働き始めた。
六人の少女は、百人の水兵や労働者のあいだをかけずりまわり、教え、助け、しかりつけ、けなげな活躍をした。
こうして、スモーリヌイ学校、兵営、工場の電話が通じるようになった。
市会や土官学校や反革命派たちの電話は切断された。
ボリシェビーキは、見事に息を吹き返したのである。 |

残ってくれた六人の少女に教わって、
電話交換局ではたらくポリシェビーキの人たち
|
きょう一日、荒れ狂った町も、夜のとばりがおりるころには、森閑(しんかん)となった。
さすがの市会や反革命派も、ボリシェビーキのすさまじい底力には、胆(きも)をつぶしたようであった。
はるか遠くで、時々、まのびのした砲声がきこえたが、ケレンスキーもコサックも結局、来なかった。
「忌々(いまいま)しいケレンスキーめ。汚れ果てたブルジョワめ。ケレンスキーなんか、くたばっちまえ!
俺たちには奴なんかいらないんだ。俺たちに必要なのは、レーニンなんだ!」
と、大声で威勢をつけながら、兵士の一人が町に貼られた反対派のポスターを、ひきちぎっていた。
top
**************************************** |