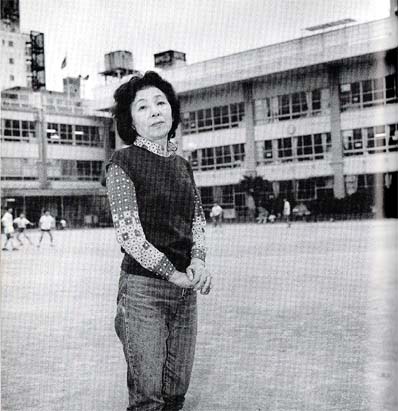|
****************************************
Index 戦災障害者の証言(その一 その二 その三)
戦災障害者の証言(その一)
1 いかだから救いの手がのびて 田崎初代――1945/3/10東京大空襲
top
|

7歳の時の七五三の記念に(弟5歳)。
顔に火傷のない最後の写真となった
|

田崎初代 本所区(現墨田区)錦糸町生まれ。
1945 (昭和20)年3月10日の空襲(江東橋上)で顔の左顎から
首の頸動脈にかけて、また両手両足に火傷を負う。当時9歳。
|
私は両親と弟の四人家族でした。
父は本所区(現墨田区)錦糸(きんし)町でガラス加工業の店を構えて、職人を雇っていました。
私は千葉のお寺に学童疎開していたのですが、帯胴(たいどう)神経痛になってしまい、両親が迎えにきて東京に戻って空襲にあいました。
その晩、家族四人で二度駅の官舎の方へ行ったのですが、あまりにも火の粉がひどいので、江東橋の方に逃げたのです。
橋の上に行ったら反対方向の緑町からも逃げてくる人でいっぱいになって、向こうにも行けない状態でした。
そこに軽油のようなものが雨が降ってきたように撒かれて、波状攻撃のようになったのだと思います。
まわりから火がついて手荷物などが燃え出しました。
誰かが「荷物は川に捨てろ!」と言うので、持っている荷物を全部、川に捨てて自分の身だけを守っていましたが、火が渦巻のような状態になって、大混乱になり私たちの家族は散りぢりになりました。
私の目の前で人がのけぞって焼け焦げていく姿をまのあたりにしました。
私も火の海の中でよろけて橋の欄干にぶつかり顎を火傷しました。
その時は無我夢中ですから熱さも何もわかりません。
私は必死で川に飛び込みました。
川は荷物や死体やら山のようになっていました。
私は何かにしがみついてました。
いかだの上にかなり多くの人が避難していて、ある女性の方が、私の手を引っ張り上げて助けてくれました。
そして、私の名前を聞き、その女性は橋の上の人たちに向かって呼びかけてくれました。
それに父がこたえて弟と三人が一緒になりました。
父と会ったとたんに私は目がみえなくなりました。
たぶん火傷と泥水のためだったと思います。
寒いのと、いかだの間に足が吸い込まれそうでしたが、明け方までじっとしていました。
一人の男性がみんなを励まし「歌を歌いましょう」と言って、みんな大きな声で歌ったのです。
あとからわかったことですが、その時、母は橋の上にいてその歌声を聞いたというのです。
母は両手両足、顔も火傷して、何とか羽田の親戚の家に一人でたどり着いた時には、防空頭巾(ぼうくうずきん)が燃えて紐だけ残っていたそうです。
やがて空襲も終わり、火の手も弱まったころ、私たちはいかだから上がりました。
父は私をおぶって弟の手を引き、とりあえず学校に避難しました。
陸軍病院からお医者がきていて「あなたの火傷は三度で、ひどいからすぐ病院に行くように」とトラックに乗せられました。
父は何とか弟も一緒にと頼み込んで姉弟で陸軍病院に入院できました。
一ヵ月くらいで、まだ傷はよくなっていませんでしたが、病院はケガ人をつぎからつぎと受入れるため、私は別の病院に移りました。
そこは、シーツも布団もないあまりにひどい病院でした。
こんな所には一晩でもいられないと言って、父は羽田の親戚を頼ることにしました。そこには、もう死んだと思っていた母が生きていました。
父は一ヵ月の間、ずっと焼け跡で母を探していましたが、みつからないのでたずね人の札を立てていたのです。
その後、私たちは父の田舎の水戸に移りましたが、そこに父だけを残して、母の実家のある前橋に行くことにしました。
終戦はそこで迎えました。母方の兄弟たちが寄り集まって大勢で暮らしておりました。
「戦争が終ってよかったね、これからは家族だけで暮らせるね」と母と話したのを覚えています。
一年半くらいたって東京に戻ったら、焼け跡には他の人がバラックを建てて暮らしていました。
私たちは、ガラス屋さん(父の仕事仲間)の倉庫の二階を借りて住み、母も父の仕事の手伝いをして生活することになりました。
あの頃は食べるものもなく、月に一度、今川焼を買ってもらったり、おそばやさんに行くのが唯一の楽しみでした。
コロッケなんてぜいたくでコッペパン一つ、外米にイモや大根などを混ぜて食べていました。
中学卒業後、父が保谷(ほうや)ガラスに勤めたので、大泉学園に引っ越し、社宅に入ることになり、やっと余裕が出てきたようでした。
私は印刷会社に勤めて、活字を拾う文選の技術を身につけました。
母の体が弱かったので結婚なんて考えていなかったのですが、母から「あんたも苦労しっぱなしできたんだから、私の目の黒いうちに幸せな顔をみたい」と言われ、親孝行と思い二九歳で見合い結婚しました。
夫は水道設備の仕事をしていました。四年目に長女を授かり、近くに住む病弱な両親の面倒をみながら暮らしてきましたが、夫がガンで、一九九二年に亡くなりました。
しばらくは途方に暮れ、無気力で何もする気がしなかったのですが、去年の七月に娘も結婚したので、今年の六月から病院の掃除一般の仕事を始めました。
自分にあった仕事を始めて、やっと生き方をみつけました。
戦争で火傷をしなかったら、もっと別の人生を歩めたのではないかと思っています。
顔に火傷をしているというはずかしさで、何でも前向きにできないのです。
娘時代は顔を隠して歩くということがありましたから、振返れば、私は優しい人と出会えて子供にも恵まれ不幸な半生ではなかっだけど、「戦争さえなかったら」という思いは残っています。
何かお役に立つことができないか、といつも思ってはいるのですが、働かなくては食べていけないし、少しでも蓄えておかなくては、と自分の生活のことで精一杯なのです。
ただ、私に言えることは、もう二度とあのような悲惨な戦争は孫の代まで、あってほしくないということです。
2 「三丁目一一〇番の鈴木です」 鈴木美津子――1945/3/10東京大空襲
top
|

50年経った今もケロイドの後遺症に苦しみ、入退院を繰返す
|

鈴木美津子 城東区(現江東区)亀戸生まれ。
1945 (昭和20)年3月10日の空襲(亀戸高架線上)で顔、
両手両足、両肩、左背から脇腹、左右上腕部を大火傷。
現在も入退院を繰返す。当時14歳。
|
亀戸(かめいど)の境(さかい)町(町内会名で現在境橋)で生まれ、被災当時もそこに住んでいました。
家族は父と母と三人姉妹で、小学校教師で学童疎開を引率していた長女と、真ん中の姉と私の五人です。
私は学徒動員で沖電機で、不良品のコイルをほどいていましたが、こんなことをしていて戦争に勝てるのかしらと思っていました。
近所に叔母さん親子がいて、私とその六歳の従妹を連れて母の実家の埼玉に疎開しようとしたのですが、私は
「みんなが疎開したら戦争に負けちゃう。田舎なんかに行くのはいやだ」と言って疎開しなかったのです。
ですから叔母と従妹が、亀戸駅方面で亡くなったと聞いて、私がわがままを言わなければとすごく責任を感じました。
いまでも三月一〇日には欠かさず東京都慰霊堂(いれいどう)へお参りしています。
三月九日に、私はその従妹を自転車に乗せて、原っぱをひとまわりしたのを覚えています。
毎晩食事がすむと家へきて、警戒警報といえばうちの防空壕へ入ったりしていたのですが、三月九日の夜にかぎって、この親子がこなかったのです。 その夜はひどい強風の日でした。
|

1938年頃姉妹と一緒に。本人左端
|

右=小学校5年生のとき、姉やいとこたちと
左から2番目の従妹は3月10日の空襲で亡くなった(本人左端)
左=女学校4年のとき、2番日の姉と
|
警戒警報なのに焼夷弾(しょういだん)が落ちはじめたのです。
私は防空壕に入って、カタカタ震えていたのですが、母たちがこないので心配になって外へ出ました。
外は風や火の粉がすごく、空は真っ赤でした。
自転車小売業をしていましたから、家の裏に倉庫があっだのですが、それに火がついて、父が水をかけていました。
母は逃げる支度をしていて、「あんたは防空壕に入ってなさい」と言われたのですが、こわくて一人で入っていられないのです。
逃げなきやダメだということになって、疎開用に事務所に積んであった荷物をリヤカーに乗せました。
私はオーバーを三枚くらい着せられて水をかぶって、リヤカーに乗せられて亀戸駅の方へ逃げたのです。
姉は一足先に逃げていたようです。
けれどもう十三間通りは火の海で通れません。
それで横道に曲がって水神通りの方から駅方面へ行ったらしいのですが、私はこわくて目をつぶっており、時々目を開けると道の両側は家も電信柱も燃えていました。
そこを通りぬけてやっと東武線の線路にたどり着きました。
そこで、どぶの中に金庫などの荷物を全部捨て、線路の土手を登ろうとした時に母が吹き飛ばされて、みんなが置いていって燃えている荷物の中に落ちてしまったのです。
母が「私を置いて逃げてください」と言うので、父は私を連れて逃げました。
やっと高架線に上がったとたんに父も私も吹き飛ばされ、親子バラバラになってしまいました。
なにしろひどい強風で線路上は人間が火だるまになって吹き飛んでくるし、みんなの捨てた風呂敷の荷物が燃えながら吹き飛んでくるのです。
まるで火の海でした。
体に火がつくと強風に煽られてパーッと燃え、「熱いよー」と叫びながら火柱になっている人もいました。
私は自分で火の粉を払いながら、立っていたらダメだと思って横になったのです。
そして気を失ってしまったのです。
無意識に、自分の体に火がつき熱くて気がついて払っていたのですが、逃げるという気力はなかったのです。
父も母ももう死んだと思い、私もここで死ぬんだと思ったりしました。
あまりの寒さに気がつき起きようと思ったけど、体が焼けて炭化状態になって動かないのです。
腕時計が残っていました。朝の六時でした。
まさか自分が丸裸になっているとは思いませんから、やっと起きてみると、まわりはみんな死んでいる人たちです。
まだ精工舎が真っ赤に燃えていました。
そして、自分が何も着ていないことに気づいたのです。
まわりの人に「寒くて仕方がないのです。何か着る物をください」と頼みましたが、私の顔は焼けて真っ黒で、成仏できなくてきたんだと思われたのでしょう、誰も相手にしません。
また別の方に行って頼んだら、男の人がこれしかないけど着なさいと、男物の浴衣と羽織をくれました。本当に助かりました。
まわりでは泣き叫ぶ声、「○○ちゃんいますかー」と家族を探す声、大勢の人たちが右往左往していました。
もしかしたら父だけは生きているかなと思って、三丁目の鈴木徳太郎はいませんかー」と大声で呼んでは、父が私を呼んでいないかと耳を澄ましました。
聞き逃していないかとしばらく耳を澄ましましたが、誰も私を呼んでいません。
そこで、どこへ行ったらいいのかと考えました。
私の祖父が小松川に住んでいたことを思い出して、線路から道路へ降りました。
喉がとても乾いていたので、水を飲もうと思って手を差し出したら、手が真っ黒に焼けて火ふくれで、飲めないのです。
びっくりして、蛇口から直接飲みました。
小松川の方向を近くの人に聞くと、「あそこのガードをくぐって行けばいいよ」と教えてくれました。
そのとおり、ガードのところに行ったら、母と姉が座っていたのです。
「お母さんじゃないの」って言ったのですが、母は私だとわからなくて、ぼけーっと顔をみているのです。
「三丁目一一〇番の鈴木美津子です」って言いましたら、母はびっくりしていました。
それから、煙で目が見えなくなっていた姉の手を母が引いて、私は後からついて、小松川へ向かったのです。
途中、どういうわけか乾燥芋が一つ落ちていて、お腹がすいてどうしようもなかった私は、母に拾って食べていいかって聞いたのですが、きっとどこかで炊き出しをしているから止めなさい、と言われました。
いまだに乾燥芋をみると、あの時のことを思い出します。
小松川橋を渡ってすぐに救所所がありました。
母は姉を連れて、私は火傷の人が並んでいる列について順番を待ちました。
やっと私の番がきても、「こりゃひどいや」と後まわしにされるのです。
仕方なく次の救護所まで行くのですが、そこでもやっぱり後まわしにされてみてもらえません。
ようやく小松川へたどり着きましたが、近所の家は何ともないのに祖父の家だけが飛び火で焼けてしまっていました。
それでも、そこに父がいたのです。はじめて父が涙を流してよろこぶのをみました。
そこに着いたのが午後四時頃だと思いますが、食べたおにぎりのおいしかったことをよく覚えています。
父のいとこが江戸川区松本町にいましたので、私たち家族はそこに行くことになりました。
翌日、すぐそばの女医さんのところで火傷の治療をしてもらったのですが、一週間ずっときてくれたそうですが、結局、
「こんな時代だからガーゼも薬もないし、助かる人に使いたい。
この人はもう心臓もだいぶ弱っているし、火傷の熱と毒素で助からないから薬も使えない」と言われたそうです。
父は、焼け残った薬屋へ行って、私の状態を話し、ガーゼと薬をわけてもらってきて、母と四〇日間、寝ずの看病だったそうです。
あまりのひどさに痛みは感じず、私はただ暑いとか寒いとか言っていました。
脱水症状で喉が乾くものですから、母はどうせ助からないのなら飲みたいものを飲ませてあげたい、と水をどんどん飲ませたのがよかったそうです。
それに遠い親戚なのに私に貴重な卵や白いおかゆを食べさせてくれたのです。
卵や米は、当時は買えない時代です。
私は八畳の床の間に寝ていたのですが、自分が臭いのなんてわかりませんでしたが、後で姉は人間が腐っていく臭いがして、とてもそこで食事などできなくて、廊下に出て食べたと言っていました。
四月にやっと小岩に家がみつかって引っ越したのですが、リヤカーでそーっと引かれていくだけでも目がまわるのです。
近所に千葉大に行っているインターンで外科を専攻していた方がいまして、その方が四月の末頃からみてくれることになったのです。
両親が治療しているので、たいしたことはないと思っていたそうですが、きてみて、よくこれだけの治療をしていたとおどろいたそうです。
教授に相談しながら引っ越す七月頃まで治療してくれました。
私が自分を臭いとわかるようになったのは六月。痛いのがわかるようになったのは五月です。
一日二回は治療した方がいいということで、昼は父が、夜はインターンの方が一回に二時間かけてやってくれました。
治療中に痛くて涙をポロポロ流して泣くと、父が「そんなに泣くと空襲の時に置いて逃げちゃうぞ」って怒るのです。
そうすると私は「こんなの痛くない」って言って。
血が流れてさわげば、「そんなの血じゃない、マーキュロだ」と、励まされていました。
暑くなる頃にはだいぶ回復してきましたが、完治まで二年半かかりました。
なにしろ腋の下は骨が出ていましたから。
七月の末に埼玉に疎開しました。一〇月頃どうしても学校に行きたくて、神田の女学校へ復学したのです。
電車は殺人的に混んで、体は擦れるし、なかなか治らなくて大変でした。
今はだいぶ小さくなりましたが、若い頃はケロイドがいやで、髪を長くして、夏でも長袖を着ていました。
頭の毛も燃えて、ケロイドは首から両肩、上腕部まで、火傷は左背脇腹や尾てい骨まであります。
ケガのために出席日数が少なくて、女学校を卒業できるかわからない状態だったのですが、一九四八年に無事卒業して文化服装学院へ行きました。
その後近所で和裁を習いましたが、病弱で大学に行けなかったのが残念でなりません。
病気をしていた父が「肩身の狹い思いをするだろうから、結婚なんかするな」と言っていましたが、やはりそうは言っても安心したのでしょうか、結納の時にはニコニコしていました。
その父も一九五七年、数えの五六歳で亡くなりました。
母は一九八四年に亡くなりました。両親とも私のことを心配しておりました。
若い時は雨の前になると肋間神経痛が起きて、よく往診を頼みました。
母が生きている時は母におんぶにだっこでした。
母がいたからこそ今日までこられたと思っています。
年をとってからケロイドの痛みがひどくなり、また全身が痛んで転げまわるほどです。
寝たり起きたりの生活ですが、寒さはことにつらく、体温調節があまりできないので風邪ばかり引き、痛みもつらくて寝ている生活が多くなります。
長い間にだんだん薬も効かなくなり、夜も眠れぬ日がつづくこともあります。
主婦でありながら動けないことで、いらいらが募ります。
一九七九年から入退院を繰返すようになり、もう十数年苦しんでいます。長い闘病生活の中で鬱(うつ)的状態になり、心療内科に通うようになりました。
病院を転々とかえ、痛みを何とか治したいと思いますが、根本的治療はないのです。精神的に頑張って生きていくほかない、と自ら言い聞かせて過ごしています。
3 「逃げなさい」と母が突き飛ばす 池田町子――1945/3/10東京大空襲
top
父母と兄と私と弟三人、妹の合計八人家族でしたが、当時、すぐ下の弟は新潟に学童疎開していましたし、一番下の弟と妹は福島に疎開していました。
それと、三月九日以前の空襲で焼け出された叔母が、うちに身を寄せていました。
私は卒業と進学の準備のために帰京してたのです。
猿江(さるえ)町の通りに面したところは材木屋などがあり、一歩路地を入ると長屋で、その一角に私たちは住んでいました。
三月九日の夜、いつものように床についたのですが、母に起こされました。
夜中なのに空は明るく、とても不気味(ぶきみ)でした。
二歳の弟を背負った母と叔母の四人で防空壕に入っていましたが、「早く出ろ」と言う父の声で外に出ました。
父は防水桶の水を私たちにかけると、地面に逃げ道を書いて「ここを真っ直ぐ逃げるんだぞ、さあ急け!」と送り出したのです。
しかし、母は父の言った方向に行かないで命を失いました。
あとから、父は「あの時から死神がついていたんだなあ」と言っていました。
父と兄は、母たちの後からその道順を逃げてケガ一つなく助かっているのです。
私たち四人は二つ三つ路地を通りぬけて電車通りへ出ると、逃げ惑う人たちが一つの群れになっていました。 |
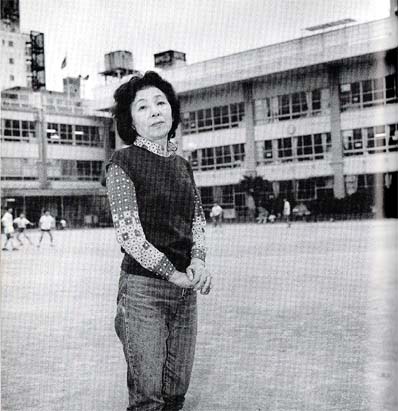
池田町子 深川区(現江東区)猿江町生まれ。
1945 (昭和20)年3月10日の空襲(東川国民学校)で
顔、手足、背などを大火傷。その時に母と弟を亡くす。
現在も皮植手術の後遺症に悩む。当時12歳。
|
線路の上を、火のついた大八車が風に飛ばされてきます。
母がいきなり私の頭をたたき、火のついた頭巾をむしりとってくれました。
「あの交差点を越えれば、恩賜(おんし)公園だから」という方をみると、交差点は火の海になっていました。
火の舞うなかで立ち往生していると、誰かが「学校に入れ、学校だ」と叫びました。
電車通りの向こう側に、私の通っている東川(とうせん)国民学校がありました。
しかし、帯のようにはっている火をくぐらなくては行かれないのです。
とまどっていると、誰かが転がるように火をくぐったので私たちもつづきました。
北門にたどり着くと、内側から鍵がかけられていて入れない人が群れていました。
誰かが塀を乗り越えて門を開けると、一斉になだれ込みました。
その人たちで廊下はいっぱいになり、「教室に入れ!」と言う声でまた先を争いました。
「火を消せ、荷物に火がついてるぞ!」「門を閉めろ、もう入れるな!」と入口に向かって叫んでいましたが、その時すでに遅く、廊下の火は教室のガラス窓を破って勢いよく吹き込んできました。
私は息苦しくなり、必死で母にしがみつきましたら、すうっと楽になりました。
家を出る時かけてくれた水が、ねんねこ半纏の袂に残っていたのです。
その時誰かが「ここにいたらみんな死ぬぞ、校庭に出ろ!」と叫びましたが、鍵が開きません。
椅子で叩き壊して開けようとしますが、引戸は三尺しか開きません。
母は私の名を呼びながら、ヤカンの水を口に含み、思いきり私に吹きかけました。
「さあ逃げなさい」と言って、私を突き飛ばしたのです。
小さかった私は、大人の間から転げるように戸口にきていました。
外に出ることができなかった人たちは、真っ黒な顔をして呻き苦しみながら、折り重なるように息絶えていきました。
校庭は私の背丈ほどある炎でいっぱいでした。
そして、炎が顔におおいかぶさってきました。
両手で顔を覆い転がり苦しんでいる時、大人が引きずるように、花壇の端に引っ張ってくれました。
人の影に隠れようとすると前に押し出されて、何度か繰返しているうちに、窪みのある大きな扉の前にきていました。
扉を背に立っていると、廊下の燃えている火が、扉の隙間からバーナーのように背中や足を吹きつけるのです。
剌すような痛さでした。
夜明けとともに火がおさまり、あたりがぼんやりみえてきました。
煙のなかに、黒いものがゴロゴロと、なかには少し動いているものもありました。
私たちの衣服はボロボロ、顔はふくれあがりましたが、それでも生きていました。
生と死をわけたのは風でした。
校庭の隅にあるプールのなかも大勢の人が死んでいましたし、講堂の四隅にも重なりあって死んでいました。
私はオバケのような手つきをした叔母に出会いました。
声をかけてもしばらくは私がわからないようでした。
叔母は焼けただれた手で私をかかえて、家に戻ろうと言うのですが、私は歩けないので、叔母は私を引きずり、数えきれないほどの死体を跨ぎながら、わが家の焼け跡に戻ったのです。
そこに父と兄がケガもなく待っていました。
私の顔は異常にふくれあがり、左の小指は白い骨が出ていました。
「寒い寒い」と言う私を抱えて途方にくれていると、通りがかった人から毛利国民学校に軍医がきていることを聞きまして、そこへ運んでもらいました。
学校の中はケガ人でいっぱいでした。
軍医は最初、私の踵に下がっているものを運動靴のゴムだと思ったようですが、下がっていたのは踵(かかと)の皮だったのです。
右の手首には、標準服の袖口のゴムが、輪のままベットリと食い込んでいました。
顔、手、足、膝、背中にかけて手のつけられない火傷です。
軍医は側にいる父に「この子はもう助からないから欲しがるものをあげなさい」と言うと、何の手当てもなくつぎの人をみていました。
私は水が欲しくて、何度言っても父は聞いてくれません。
鉄かぶとに水が入っているのをみつけて、こっそりはって顔を突っ込んで飲んだのです。
心配して訪ねてくれた親戚の人たちに運ばれて、母の実家の向島(むこうじま)に身を寄せました。
その後三日三晩うわ言がつづき、水のような重湯(おもゆ)を飲ませると、いつまでもおいしそうに飲む姿をみて、この子はこれで死んでしまうと涙して見守っていたそうです。
数日後、運よく鐘ヶ淵(かねがふち)の白髭(しらひげ)病院に入院でき、夏まで病院生活を送りました。
大工(だいく)の父は、病院のあちこちを修理することを条件に、私のベッドの傍(かたわ)らに畳一枚を敷いて、そこに寝起きしながら私の看病をしていました。
退院してからは、とにかく指を動かさなければいけないと、新小岩の洋裁研究所に行かされました。
ですから、学校は小学校までで、その卒業式も三一年後でした。二七歳で洋裁店を開いてから、結婚後の一時期を除いて、ずっと好きな洋裁をつづけてきました。
いまあの当時を思うと、母は二歳の弟を背負ったまま、校庭に出られずに息絶えたと思います。
いまだに母の遺骨はみつかっていません。
数年たってから整形手術を受けましたが、数十年過ぎた現在、火傷跡の皮膚の後遺症に悩まされています。
4 母は焦土の町を四人の子を連れ 山田茂夫――1945/3/10東京大空襲
|

福島の疎開先で母や姉とともに(1953年)
母
当時、夫は徴用(ちょうよう)で石川島造船所に通っていましたが、三月九日は当直にもかかわらず、胸騒ぎを覚えて帰宅していたのです。
子供は四人で八歳、六歳、四歳の女の子と、末の茂夫はお誕生を過ぎて、やっとヨチヨチ歩きができる頃でした。
一度は警報が解除され、寝入りばなの夜半のことでした。
敵機来襲で起こされ、子供と防空壕に入っていました。 |

山田茂夫 本所区(現墨田区)菊川生まれ。
1945 (昭和20)年3月10日の空襲(本所区菊川)で両手首を火傷。
左薬指、小指に障害が残る。同夜の空襲で父を亡くす。
当時一歳。母・きくよ当時35歳。
|
夫は役を持っていたので隣組で走りまわっていました。
夫の「早く逃げろ!」の声で防空壕から出ると、焼夷弾の炸裂と光線、地響き、突風に舞い散る火の粉と煙、真紅に焼けた夜空のなかを右往左往する人の群れと、あまりのかわりようにただごとでないことを察しました。
茂夫を背負い、三女を乳母車に乗せ、上の二人を連れて、叔母さんの家族と一緒に逃げたのです。
途中で叔母さんたちとはぐれました。上の二人の子供は叔母さんたちについて行って、私がいないのに気づき、引返してきて助かったのです。
叔母さんたちは行方不明のままですから、亡くなったと思います。
子供たちが背負ったリュックは、次々に火を吹きました。
ねんねこにも火がつき、脱ぎ捨てました。
茂夫はその時に、手に火傷を負ったのです。
どこも燃えているのです。上をみれば電柱がメラメラと燃え上がり、火の粉が降りかかってくるのです。
子供たちを守るのが精一杯でした。
飛んできたバケツをかぶり、足元のトタンで火を防ぎ、突風で飛ばされないように必死で持っていました。
熱風と煙で「もうダメ、もうダメ」と何回思ったことでしょう。
そんな時に、「もう少しの辛抱だ、がんばるんだ!」と大声で怒鳴っている人に励まされたのです。
夫は最後まで残り、逃げ切れなかったのでしょう。どこで亡くなったのか、行方不明のままです。
火もおさまり東の空か明るくなると、まわりは真っ黒に焼けた死体がゴロゴロしていました。
私たちの衣服はボロボロで、煤(すす)けた顔に目は真っ赤でした。
焦土の街を四人の子供を連れ、中和(ちゅうわ)国民学校へ向いました。
学校の中はケガ人であふれ、茂夫の火傷をみてもらうのに十時間以上待ちました。
包帯も薬もなく、カーテンを引き裂いて包帯がわりに巻くだけの処置でした。
毛布と乾パンで命をつなぎ、明かりのない教室で、人の呻き声とB29におびえながら、夫が迎えにくるのを持っていたのです。
そのうち、私の姉が横浜から訪ねてきてくれて、二ヵ月ほど姉のところにお世話になった後、福島に疎開しました。
福島の親の実家とはいえ、母は亡くなり、叔父の世話になったのです。
着の身着のまま何もなく、呉服ものなどの行商をして子供たちを養いました。
子供四人では大変だからと三女は養子に出したのですが、その子は亡くなりました。
父親がいないので、人から後ろ指をさされるようなことはしないでと、いつも言い聞かせて育てたつもりです。
子供たちは福島の学校を出てそれぞれ就職し、娘たちは結婚して、いまでは孫とひ孫がおります。
一生懸命やったかいがありました。
戦後五〇年、遠くなりましたがあの空襲は忘れられません。
不幸をもたらす戦争は、絶対にしてはいけないのです。
茂夫
当時のことはわかりませんが、小学校の時に曲がった指をひやかされた記憶はあります。
福島の中学を卒業後、横浜の木工所に三年勤め、一八歳の頃から大工の仕事をしています。
二七歳のときに自宅を買い、平屋だったのを二階建てに自分で直しました。まだ結婚はしていません。
今は母と二人で暮らしています。
5 「妹は、もう助からない」といわれ 桶井タキ子――1945/3/10東京大空襲
top
|

佐藤コヨ(故人)深川区(現江東区)自河町生まれ。
1945 (昭和20)年3月10日の空襲(深川区白河町)で、焼けた電柱が倒れかかり、頭から全身に大火傷を負う。頭、両手両足にひどいケロイドが残り、左手全指が曲がったままとなる。当時43歳。(空襲当夜。
涌J川タキ子さんか泊りに行った佐藤のおばさん)1978年死亡。
|

涌井タキ子 深川区(現江東区)白河町生まれ。
1945 (昭和20)年3月10日の空襲(白河町)で下
半身を火傷。その日の空襲で弟を亡くす。当時15歳。
|
父は製材の仕事をしていましたが、当時は軍属として南方へ行っていました。
六人兄弟のうち、一人は体か弱かったので田舎の祖母のところへ疎開し、母と姉、私、弟、妹二人の六人暮らしでした。
私は中学校を卒業後、家の近くの鋲(びょう)をつくる会社に事務の見習いで勤めていました。
一九四五(昭和二〇)年二月二五日だと記憶しているのですが、雪の降った日の空襲で家を焼かれました。
それで、たんすなどの荷物を、通りをはさんだ親戚の鈴木さん宅に運んで、そこに泊めていただいていたのです。
三月九日の晩は、近所の子供のいない佐藤コヨさん(左上)の旦那さんが留守だったもので、私が泊まりに行ってあげていたのです。
その日は、空襲警報が鳴って解除したかと思ったら、またすぐ鳴ったりしてなんだかへんでした。
そのうちにドカーンと大きな音がして、前のお風呂屋さんのところに焼夷弾が落ちました。
私は佐藤のおばさんと防空壕に入っていたものの、家族と別々なのが不安でそこを出ました。
そうしたら、向こうから母たちがやってきたのです。
母の背中のねんねこに火がついていて、妹の美子は大火傷を負っていました。
焼けた家の跡に行くど、ねじれた水道の蛇口からチョロチョロと水が出ていました。
火傷を負った美子が、熱い熱いというので水をかけてやりました。
私は朝まで美子を抱いてましたが、夜中じゅう家財が吹っ飛んできて頭にあたるわ、畳やトタンは飛んでくるわで生きた心地がしませんでした。
空には、タイヤもわかるくらいにB29が低空で飛んでいました。
朝になって、妹を連れて白河町の区役所に行き、治療を頼んだところ、「もう助からないからダメだ」と言われて……。
母が何とか頼み込んで治療してもらったそうです。
私が泊まっていた佐藤のおばさんも、リヤカーで区役所に運ばれていました。
全身包帯だらけの姿をみて、みんなもうびっくりして泣きました。
佐藤さんは、ずっと防空壕の中に入っていたが、あまりに熱くて出たところ、焼けた電柱が倒れてきて大火傷を負ったそうです。
それから明治学校に避難し、翌日、兵隊さんに上野までトラックで連れて行ってもらい、汽車で祖母たちのいる母の実家、福島へ向かいました。
食物もなくおなかが空いて、汽車のなかで、半分黒焦になった缶詰をもらったのを覚えています。
弟の喜一郎は、たまたま学校から労働に出ていた会社の寮に泊まっていて、行方がわからなかったのですが、空襲で亡くなりました。
私もいつの間にズボンに火がついていたのか、足首や左内股からお尻にかけて火傷を負っていました。
薬もなく、膿まないようにと注射をしてもらったのですが、消毒不足で傷が膿(う)んで、膿(うみ)がタラタラと流れてきてひどかったのです。
膿を出すために麻酔なしで切って、そこに長い脱脂綿をつめるのですが、もう痛くて痛くてどうしようもなかった。
包帯もなくてどこにも出られず、皮が再生するまで一年くらいかかりました。
なおってから、新聞で募集していた福島の日東紡ヘー年働き、その後、友人と一緒に東京に出てきました。
二人で新宿の裏通りをあちこちと歩いて職を探しましたが、なかなかみつからず、江東区清澄町の叔父のところにやっかいになりました。
叔父の口ききで、私は森下の下駄屋さんに住み込みで子守をしました。
子守といっても自由で、歌ばっかり歌っていました。
そこでもう一人の住み込みの人と、ズボン屋や八百屋(やおや)の店を出してもらいましたが、商売が下手で赤字出してやめました。
一九五二年、二二歳で兵隊がえりの人と結婚しました。一緒になってまもなく、鉄骨関係の仕事で北海道に行きました。
私は飯場で寒い思いをして働きどうしで、東京に帰えると会社が倒産していて、給料がもらえなくてつらい目にあいました。
夫が亡くなってからもう七年になります。本当はまだ働いていたいのですが、以前、老人のヘルパーをしていた頃に、体の調子がおかしくなってやめました。
今は吞気に暮らしています。
6 二週間前に家を焼かれ、そして 関 美子――1945/3/10東京大空襲
top
|

母と5人姉妹。前列左から長女きよ子、母、次女タキ子、4女春子。
後列左から5女町子と私(1991/7)
一九四五(昭和二〇)年、雪の降った二月二五日の空襲で家を焼け出され、私たち家族は近くの親戚の家に泊めてもらっていました。
父は軍属で南方に行っていました。兄は学校から軍需工場に働きに出ていて寮に泊まっていました。
母と私たち姉妹の五人が厄介になっていました。
三月一〇日の未明、ドカーンとものすごい音とともに、まるで地震のように戸やふすまがはずれました。
「大変だ!」。いちはやく空襲を知った母は私を背負い、すぐ上の姉を連れて逃げ出しました。
|

関美子 深川区(現江東区)白河町生まれ。
1945 (昭和20)年3月10日の空襲(深川区白河町)で右手首、右脇腹から大腿部にかけて大火傷を負い、その日の空襲で兄を亡くす。当時5歳。
|
二番目の姉のタキ子は、懇意にしていた佐藤のおばさんの家に泊まりに行っていて空襲になり、おばさんと別れて帰る途中、私たちと一緒になったのです。
通りはすごい風で、トタンやたらいが飛んでくるものですから、それを被って火を避けていました。
そのうち姉たちが「もう母ちゃん、ダメだ」と言ってバッタリ倒れました。
私はこの火の中でみんな死んでいくのかと思っていました。 私は「日本は神の国だ。
神様はどこにいるんだ!」と大きな声で叫ぶと、南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげっきょ)を唱えていました。
「美子も唱えなさい」と言われて私も唱えた記憶があります。
焼け跡の水道からわずかに水が出ていて、みんなでそれをチュウチュウすってしのいだそうです。
「熱いよ、熱いよ」と言っていた私にも、姉たちが手ですくって水をかけたらしいのですが、ひどい火傷を負いました。
「母ちゃん、美子焼け死んじゃうよ」とタキ子姉が言うと、母が背中の私を降ろしてさっさと先に行ったというのですが、そんな錯乱(さくらん)が起こってもおかしくない世界でした。
まわりにはずいぶんたくさんの人が死んでいて、私たちだけ助かったのです。奇跡でした。
冷たいなあと思って気がつくと、区役所のコンクリートの上に座らされていました。
この子はもうダメだと軍医が言うのを、田舎に連れて帰るから薬だけでもつけてくれと母が頼みこんだそうです。
そして、母は九死の私を抱えて福島の実家へ帰りました。
母の実家では、ワラ布団をつくってもらって寝かされました。
たぶん家を焼かれたのでしょう、畑の土手の穴に住んでいたお医者さんがみてくれました。
ボロ布が包帯がわりでしたが、指がくっつかないように、一本一本離したりのばしたりしてくれました。
右手の小指は骨が固まって曲がりませんが指がくっつかずにすみ感謝しています。
一九四六年頃、父は無事に帰ってきましたが、仕事らしい仕事もありませんでした。
とにかくあの頃は食物がなくて、昼はさつまいもやとうもろこしだけでした。
トゲのあるアザミまで採って母が煮ていましたが、チクチクして食べられませんでした。
母の実家を出てから、古い大きな水車小屋を借りて住んでいましたが、ある日、風で倒れてしまいました。
中学三年まで、電気も水道もないほっ立て小屋に住まざるをえませんでした。
中学を卒業してからは、住み込みで女中をしたり、あちこちを転々として働きました。
酒屋に勤めたら、朝五時に起きて冬でもスリッパもはかず、廊下をツルツルに磨くのです。
それで、しもやけがひどくなって福島の田舎に帰ったこともありました。
でも一生懸命に働き、二〇歳の時に自分で貯めたお金で、ケロイドでつれた右足のつけ根を整形手術しました。
この手術でようやく踵(かかと)が地につくようになりました。
二四歳の時、知人の紹介で、江東区で鉄鋼関係の会社に勤めていた夫と結婚しました。
翌年と翌々年に二人の息子に恵まれ、現在二人とも独立した父の工場を手伝っています。
昨年、千葉に新居を構えまして、長男家族と一緒に暮らしています。
7 素足のまま焼跡を歩いた 御幸尾静江――1945/3/10東京大空襲
top
父は本所区(現墨田区)菊川一丁目で、軍需工場の指定を受けた鉄工所を経営していました。
祖父母と母と私と妹の六人家族の他に、従業員が二〇人くらい働いていました。
通いの人も住込みの人もいました。 空襲の時は一〇人ぐらいいたと思います。
私は女学生でしたが、勤労艇身隊(ていしんたい)として川崎のディーゼル自動車に学校から派遣されて、毎日通っていました。祖父母と妹は千葉の父の実家に疎開していました。
三月一〇日の空襲の前の、二月二五日に空襲がありました。 うちの三軒先まで焼けたのです。
だから「もうここは空襲はないよ」と父は言っていました。
父は三月九日に、工場の疎開先を探すために千葉に出かけて留守でした。 家には母と私と従業員が一〇人ほど留守番がてらいたのです。
夜の一〇時頃から警戒警報が出たのですが、いつものことだと寝てしまいました。
母は父がいないこともあって、いろいろ身のまわりの支度をして、私を起こしてくれました。
母と一緒に表に出てみるといつもとちがって明るいのです。 従業員の人たちを起こして、防空壕に入りました。 |

御幸尾静恵 本所区(現墨田区)菊川生まれ。
1945 (昭和20)年3月10日の空襲(竪川の三の橋)で、
左足首の骨折と右足を火傷。当時14歳。
|
そのうち警防団の方が「ここは危ないからどこか避難してください」とふれてまわっていました。
私はリュックを背負って、みんなで錦糸(きんし)公園の方へ逃げたのですが、竪川(たてかわ)の三の橋のたもとで、公園の方はガス爆発があったとかで通行止になっているというのです。
しかたがないので戻って清澄(きよすみ)庭園の方へ行こうとしたのですが、こちらも火の手が上がっていて、もう逃げられなくなってしまいました。
行き場を失った私たちは、私の母校の中和(ちゅうわ)国民学校に入ろうとしたのですが門に鍵がかけられて入ることができません。
それでまた、三の橋まで戻ったのですが、その間に焼夷弾がどんどん落ちてきて、あっちこっちから火の手が上りまわりは火の海です。
どうせ死ぬなら、川で死ねば着物が焼けずに身元がわかるだろうと、母と相談して飛び込みました。
川にはすでに人がたくさん飛び込んでいて、私は人の頭の上に落ちたのです。
その時に左足首を骨折したようです。私は泳げなかったのですが、ちょうど電柱の支えの鉄線が川まで垂れていて、そこへ母と掴まりました。
そこに三時間……もっといたかしら、だんだん明るくなってきた時に、火事も下火になってきたので、上がろうとするのですが、足が折れているものですから一人では上がれないのです。
お尻を押してもらって上がってみると、建物はぜんぜんないのです。
中和国民学校と両国駅がぽつんとあるだけです。「ワーッどうしたの」と思わず母に聞きました。
行くあてもないので中和国民学校に行ったのですが、途中に、子供を抱いたまま焼け死んだ人や、用水桶の中で背中だけ焼けて亡くなっている人などが、あっちにもこっちにもちらばっていました。
朝方だというのに太陽が上がっているはずなのに、真っ暗という感じでした。
川から上がった時、私は、右の靴がいつの間にか脱げていました。
左足は折れてましたから、母の肩に掴まりながら、素足のまま焼け跡を歩いたのでした。
学校に着いてふと足をみると、右足は火ぶくれになっていました。
学校には軍医さんがいたのですが、薬がないので手の施しようがなかったのです。
最初から学校に逃げていた人は、カッポウ着なんか着て、みんなきれいな姿です。
外からきた人は、目に油が入っている人が多くて目が開かないのです。水道は出ないし、薬もなくて、私たちは座ったままで二日間そこにいました。
その間にも空襲がありました。焼夷弾が落ちてくるのです。
水がないものだから、みんなのお小水をバケツに溜めておいて、火事になるとそれをかけて消すという状態でした。
三日目に、やっと父が探しにきてくれて、ようやく会えました。
一〇人ほど一緒だった従業員は一人助かっただけで、ほかの人たちは、どこでどうなったかわからずしまいでした。
父も責任があるものですから、後日、亡くなった方たちの実家をまわったそうです。
それで、父と母と私と助かった従業員の四人で、父の実家の村、現在の君津市へ行くことにしました。
タイヤが焼け落ちたリヤカーに私を乗せて。
その村で、私の骨折と火傷の治療をしてもらいました。薬といっても消毒するだけなのです。
火ぶくれの皮を破って砂を取るのですが、その痛さはいまでも忘れられません。
それから、五本の指を離して、くっつかないようにガーゼを詰める、そんな治療を二年間ぐらいつづけました。
終戦の玉音放送は聞いた覚えはあります。ホッとしたというか、もうこれで警報がなくて、逃げなくていいんだという実感が痛切でした。
その後、自分で歩けるようになって、木更津の高等女学校の編入試験を受けて、そこを卒業しました。
ほんとうは東京の体育の専門学校に行きたかったのですが、父が東京に一人で出すなんてとんでもないということで、千葉の洋裁学校に二〜三年通いました。
卒業してしばらくは自宅で、いまでいうリフォームを近所の注文に応じてやっていました。
その頃、父は工場をそこにつくりました。工場といっても農家の鎌(かま)や鍬(くわ)の修理をしていたのです。
結婚は二一歳の時です。私たちの家族は、夫の実家の隠居所を借りていたのです。
終戦になって、旧制官立専門学校の学生だった夫が一時帰ってきていて、私の高等女学校への編入試験のため、家庭教師をお願いしていたのです。
勉強のことはもちろん、将来の進路なんかの相談相手になってくれた人でした。
その後、二人の娘に恵まれました。
国家公務員の夫は職業がら、各地に赴任しなければならなかったのですが、ずっと単身赴任でした。
ですから私は、娘たちと父と妹の世話をする専業主婦、そして、父の工場の従業員の賄婦(まかないふ)をかねてずっとつづけてきました。
父亡きあとの工場は、妹が継いでいます。二人の娘もかたづいて、夫も定年で帰ってきました。
今はゆっくり生活しているといったところでしょうか。
考えてみますと、私の同級生の三分の一は戦災で亡くなっています。
残った女性で結婚した方は数えるほどです。そういった意味では、亡くなった方には申しわけないのですが、戦争で疎開したことが、今の私の幸せになっているのかな、と思います。
8 兄と姉が直撃弾を受けた 山田 勉――1945/3/10東京大空襲
top
|

飾葛区立小松小学校六年生の春の遠足。
三列目左方の帽子の子が本人(1951年}
当時、父はコンパスやホックをあつかう鉄工所を経営していました。
たまに軍需品の仕事もあったようです。家族は両親と兄弟六人で、上の兄二人は出征していました。
私はもうすぐ小学校に上がるころで、空襲があると電球の傘に風呂敷をかぶせて、その下だけ明るくてまわりは真っ暗だったことをよく覚えています。 |

山田勉 城東区(現江東区)亀戸生まれ。
1945 (昭和20)年3月10日の空襲(江戸川区小松川)で爆弾によって
右足関節負傷と火傷を負い、兄と姉は直撃を受けて死亡。
右足に機能障害が残る。当時7歳。
|
三月一〇日の空襲の時、父は警防団員で消防に出て行ったので、おふくろと私と兄姉、それに前の家の女の子二人の六人で、土手に向かって逃げました。
爆弾が落ちてきてまわりは火の海で、私はおふくろの背中におぶさっていたのですが、その時のことははっきり覚えていません。
前を歩いていた女の子二人と兄と姉の四人が、爆弾の直撃を受けて死にました。
私とおふくろは爆風で飛ばされ、私は右足をやられて、どこかの縁の下で気絶していたようです。
おふくろも右手関節をケガして、私を片手で抱え、何度も滑りながら土手までたどり着いたようです。
しばらくそこに寝かされていましたが、親父がみつけたしてくれて、私を背負って関東配電に移動しました。
その時はじめて目を開けて、土手からうちの方をみると、暗いなかに真っ赤な火が燃えていたことだけは強烈に覚えています。
屋根もなにもない関東配電には、ケガ人や死んだ人がたくさん集められていましたが、薬もないし医者もいない状態でした。
そのうちに足がうんできてウジがわきだしました。
父は走りまわってトラックとガソリンを調達してきました。
それで数日後に千葉医大に入院することができました。
そこでも空襲を受けて隣の病棟が焼けましたが、私は無事に治療を受け、足を切らずにすみました。
傷が少し直った終戦後、母と私の二人で栃木県大田原の知人のところに身を寄せました。
半年くらい遅れて小学校に入りましたが、その頃はまだ一里も歩けませんでした。
しばらくして東京に帰ってきましたが、帰りの汽車は軍人や買い出しの人でぎゅうぎゅう詰めで、窓からやっと入ったのでした。
父はその後、新小岩で小さな町工場を始めて、兵隊に行っていた兄二人も無事に帰ってきました。
私は学校で、なるべく足を使うように野球や水泳をやって鍛え、家では毎日、足首に重しをつけて曲げる訓練をしました。それでようやく足が少し曲がるようにもなりました。
中学を卒業後、母の勧めで銀座三丁目の床屋で九年半修業し、葛飾区の立石に店を構えました。
二四、五歳の時です。そこで結婚し、四年半後に武蔵野市に移ってきました。
床屋は一日中立っている仕事ですから、どうしても右足をかばってしまいます。それで一五年ほど前から腰を悪くしまして、磯谷式力学療法でリハビリをつづけています。
私はこのくらいのキズですみましたが、もっと大変なケガをされた方がいるはずです。もう五〇年にもなるのですから、国がなんらかの救済の手を差しのべるべきだと思います。
9 八月一五日の手術があくる日に 小出冬子――1945/3/10東京大空襲
top
私は亀戸三丁目の香取小学校のすぐそばに住んでいました。
母は、太平洋戦争がはじまる一年前に亡くなっていました。
父と私と妹の三人家族でした。
一九四四年八月に私と妹は山形へ集団疎開し、翌年三月に中学受験のため帰京しました。
そして一〇日の夜に戦災にあったのです。妹は戻っていませんでしたから、空襲にはあっていません。
焼夷弾が投下され空襲がはじまる時、父は隣組の役員をしていたので、隣の家族にあずけられました。
おじいさん、おばあさん、お孫さん、若い娘さんもいたと思いますが、一緒に逃げましたが、途中ではぐれてしまいました。
亀戸の十三間通りは人の波で、もう身を任せてみんなとどんどん進むほかなく、十字路から亀戸駅の方へ行った人もいました。
私は亀戸天神の反対の方へ行きましたが、右往左往するだけで、どうしようもないのです。
そのうちにどんどん火が飛んできて、通りの両側は燃えてくる、熱いやらなにやらで、みんなその辺の防空壕に入ったのです。 |

小出冬子(仮名)城東区(現江東区)亀戸生まれ。
1945 (昭和20)年3月10日の空襲(城東区亀戸)で両手を火傷。
整形手術をするが、ケロイドと機能障害が残る。当時12歳。
|
私も入ってじっとしていたのですが、防空壕に火が移ってきました。
すると人々がわれ先に逃げて、私は踏み潰されたようなかたちになったのです。
ちょっと気を失っていたかもしれません。
苦しくて、気がつき、早く出なくてはと壕から体を出すと熱風がすごいのです。
地面へ伏せてもアスファルトが熱くて、火の粉が飛んできてそれが人の衣服につくとあっというまに火だるまになりました。
とにかく大勢の人たちと伏せていました。
夜明けになり、いくらか涼しい風が吹いて、「ああ、これで生きられた」という大人の声をきき、ホッとしてまわりをみると、四〜五人しかいませんでした。
あとはみんな真っ黒焦げです。一二歳の子供ですから、それが人間とは思えないのです。
丸太がゴロゴロころがっているような感じでした。
そこでピリピリ痛いので自分が火傷していることにやっと気づきました。
風があたると痛くて、とても外に立っていられないのです。
それで焼け残った防空壕にまた入りました。中には四〜五人の大人がいました。
下に汚い水が溜まっているのです。
男の人が頭に破片かなにか刺さって、ウーンウーンと唸っているのです。
そして、「お水をください。お水をください」とかすかな声。そばにいた大人が「もうこの人はダメだから、飲ませてやったらいい」と言って、その泥水をバケツで上ずみをすくい飲ませてあげましたがまもなく動かなくなってしまいました。
人の死を目のあたりにしても、それが死んでいく姿だという意識がぜんぜんなく、ただぼうぜんとしていました。
少し薄暗くなってから警防団の人がきて、日立の焼け残った工場の医務室で、手当てをしてもらいました。
それはもう一〇日の夕方です。
父は私をさんざん探してどうしてもみつからず、隣の人も全滅だったとのことで、一緒に死んだと思ったらしいのです。
私は亀戸(かめいど)の駅をうろうろしていましたが、何かあった時は行徳(ぎょうとく)の親戚の家に行くことになっていましたので、小松川橋方面へ向って歩きました。
途中で自転車の男の人がすっと寄ってきてくれたのです。その人が行徳の人で、自転車のうしろに乗せてもらい親戚の家に着きました。本当に運がよかったのです。
私を始めみんなが動転していましたから、その方の名前聞くのも忘れたのです。
いまだにその方の名前はわかりません。
それから私は寝込でしまって、ぜんぜん動けない体になりました。薬もなかったし、傷口が化膿してしまいました。
毎日熱が出て、医者へ行っても治療してもらえません。
江戸川べりに三好という軍需工場があり、その医務室で手当てしていただきました。
そこには毎日リヤカーに乗せられて行きました。
どうやら傷がいえてから、整形手術をした方がいいと言われて千葉医大へ行きました。
何度か通って、八月の一五日に手術ということになりましたが、今日は天皇陛下の放送があるというので、その放送の後からにしようということになりましたが、敗戦ということで「今日はやめた」との先生の声。
その時の田口先生の顔、看護婦さんたちのすすり泣きの情景は忘れられません。
そこで次の日に手術をしたのです。
手術は七回にわけてしました。最初おなかの肉を取って両方の手の甲に移植しました。
次は指を二回ずつにわけてしましたけれど、右手の指は踏まれたかなんかで骨折していました。
翌年の一月に退院しましたが、元のようにというわけにはいきません。どうにか親指だけは元のままです。
上野高等女学校に入学して、一年間籍を置きましだけれど、それきり二年には行きませんでした。
私は行きたかったのですけど、家事をしなければならなかったのです。
父も戦災にあって、何もかも計画がめちゃくちゃになって、生活が苦しかったのです。
私は一九五三年に結婚しました。子供は三人います。
長男五歳、長女が三歳の時、夫が病気になり、一年半入院しました。
会社から六割の給料を受けていましたので、生活にはさしさわりありませんでしたが、今後のこともあって、収入の方途として編物を習いました。私は学校でも裁縫の時間が好きでしたから。
その頃(一九五九〜六○年)は、セーター、カーディガンが好まれた時代でした。
そんなわけで家事と仕事でとても忙しい日々でした。
しかし、父がリュウマチになり床に伏した時、私は仕事をもっていて本当によかったと思いました。
父はそれまで健康で働いていましたが、戦災後はうまくいかないようでした。父の病床生活は十一年つづきました。
一九七四年に小さなマイホームに移りました。
父は日あたりのよい小部屋ですごし、七六歳の秋永眠しました。
父にはたとえ短い時間でも、私の家で死なせてあげたいと思っていましたので、五、六年ほどでしたが、願いをかなえることができました。
子供たち三人もそれぞれ独立し健康に暮らしています。
年に一回同期会があり、なつかしく楽しい集いですが、あの空襲で半数以上が亡くなりました。
生きている人たちも、それぞれ大きな苦難があったと思います。
忌わしい戦火から五〇年、いまだ病床で苦しむ被爆者の方には、本当にお慰めの言葉もありません。
私はよく働いてくれる左右の親指に感謝しつつこれからの人生を歩んでいきたいと思っています。
10 右手は木が燃えたようになる 中村みどり――1945/3/10東京大空襲
top
|

大事にしている聖書
住んでいたところは浅草の金龍山(こんりゅうざん)瓦町というところでした。
今の待乳山(まつちやま)聖天の前あたりで、言問橋(ことといばし)の近くです。
戦災にあったのは、次の日が誕生日で一五歳になる直前の時です。 |

中村みどり 江戸川区小岩生まれ。
1945 (昭和20)年3月10日の空襲(隅田公園)で、顔と手足を火傷し、
右手首を切断する。その夜の空襲で母と弟を亡くす。当時14歳。
|
それまで毎日空襲がつづいていて、銀座の方にぬける途中がぽつぽつ焼けていましたけれど、三月一〇日がひどかったのです。
上野の方から焼けてきて、荷物を持った人たちがずーっと隅田川の方に逃げてきました。
私が住んでいたところは隅田川公園のすぐ横ですから、わりに閑静なところです。
だけどその道路が荷物を持った人でいっぱいになったのです。
公園はその頃、高射砲の陣地になっていました。
鉄条網があったのですが、空襲の時は焼ける物がないからと、みんな公園に入りました。
私の母親と弟は防空壕に入ったのですけれど、私やお手伝いさんや叔母は入らなかったのです。
家に火がついて熱いから、公園の側にある焼けていない家に入ったのです。
そこには軍人さんの親子や何人か他の人も入っていて、ちょっと休んだのです。
そのうち、火が家の裏からまわってきて、軍人さんが息子さんに出ようと言って、外に出た時に、私も押されるように一緒に出たのです。
でもお手伝いさんと叔母はついてきませんでした。 ’
公園に入ったら、人と荷物がいっぱいでした。
すでに川に入っている人もいました。
私は高射砲の陣地の前の土盛(どもり)のところに行ったのです。
ものすごく風が強くなって、トタン板が舞ってくるようなカラカラという音がしたので、伏せていました。
その時、赤ちゃんを連れた女の人がとんできたのですが、その人に火がつきました。
でも消すような力が、もうないのです。目の前で焼け死んでいくのです……。
それから「南無妙法蓮華経」(なむみょうほうれんげきょう)の声がいっぱい起こってきたのですが、その声もだんだん小さくなって、結局みんな焼け死んでいくわけです。
後になって公園には、亡くなった方の真っ黒になった死体が累々(るいるい)とありました。
私は厚いウールのオーバーを着ていました。
それで火がつきにくかったのだと思います。
かぶっている防空頭巾はみんなそこで燃えて、朝になったら半ピラと紐だけついていました。
体の方は、出ている手とか足を火傷しました。自分ではそれほどひどくやられたと思っていなかったのですけれど、右手が木を燃やしたような指になってしまいました。
真っ黒で、折ったらポキンと折れそうでした。
手の甲が腫れ上がって皮がめくれて、肉がみえるような状態に両方なって、鏡はみてませんからわかりませんが、顔も真っ黒になっていたと思います。
リボンみたいなもので結っていた髪もみんな焼けてしまって……。
自分の家の焼け跡に行ったら、隣の人が救護所に連れて行ってくれるということで、そちらの方に行きかけたのですが、言問橋も渡れない状態で、裸足であっち行ったりこっち行ったりしてたのです。
浅草寺病院が焼けていないから、そこに行ったらいいというので、一軒おいた隣のおばさんが連れて行ってくれました。
そこへ行く途中、観音様も銀杏(いちょう)の木も焼けていました。
病院には、すでにケガ人が並んでいて、私は立って待っていられません。看護婦さんが気がついて、白い薬をベタベタ塗って病室に連れて行ってくれたのですが、床の上で寝るしかないのです。
その時は水道も電気もガスも使えなかったのではないでしょうか。何の手当てもしてもらえません。
それから何日くらいかわかりませんが、出張していた父が、私だけ生きているというのがわかったらしく、様子をみにきました。
でもどうすることもできなかったのですが。
それから重症の人だけ慶応病院に移されました。そこはちゃんとベッドがあり、手当もしてもらえたのです。
そのうちに、こんどは慶応病院にも爆弾が落ちたのです。
それで重症患者は豊島(としま)病院に移って、そこで肘と手首の間くらいから切ってしまわなければ、ということで切断しました。
母と弟は防空壕で亡くなりました。お隣と共同でつくったものでしたから、お隣の人は全員そこで亡くなりました。
父が後からその防空壕を掘って遺体を確認できたようですけれど、弟の胸と母のひざのところが合わさって、首なんかなかったそうです。着ている物で確認したということでした。
掘出して、ちょっとそのまま置いていたら、全部どこかへ片づけられたということです。
一緒に出たお手伝いさんや叔母もぜんぜんわからないのです。生きているのか死んだのか……。
たぶん戦災記念堂かどこかに一緒に入っていると思います。
その後も、東京では毎日のように空襲でした。
それで上野駅まで父に背負われて、福島の白河に疎開しました。
福島に行ってからも入院しました。病院にいるうちに足と顔の火傷はだいぶよくはなったのですが、栄養状態が悪いから、切ったところが化膿して、退院後もしばらくの間、通院していました。
一九五〇(昭和二五)年に東京に戻ってきました。
日本聖書神学校というキリスト教の伝道師をつくる学校が目白(めじろ)にあって、私は、そこに入りました。
神学校を卒業して、福岡市街の津屋崎という海岸があり、そこの教会で七〜八年お手伝いして、それから一九六一年に池袋西教会にきたのですが、ここはもう三三年になります。
現在、父は亡くなりましたが、父が再婚した二度目の母との間にできた義妹の家族と、大田区に一緒に暮しています。
top
****************************************
|