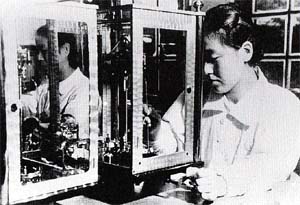|
****************************************
Index 戦災障害者の証言(その一 その二 その三)
戦災の証言(その三)
21 ふしぎに血はでませんでした 早川初子――1945/5/25東京空襲
top
母の姉が東京に住んでいました。私は、その息子のところヘ二○歳で嫁いできました。
一九四五年の二月のことです。
戦争中のことですから、結婚式も新婚旅行もしませんでした。
もんぺを履いて荷物を持って出てきたのです。
五月二五日の夜の十一時半頃だったかしら、パラパラ焼夷弾が落ちてきました。
私は東京にきたばっかりで、逃げるといっても、どう逃げていいかわからないのです。 夫は警防団で出て行ったので、伯母と一緒に逃げました。
途中で転んだかなんかして手をついたところへ、焼夷弾が落ちたのです。
一瞬に左手首がふっ飛びました。でもふしぎに血は出ませんでした。
どうしたらいいかわからなく、とにかく傷口をグッと押さえて、じっとそのままで待っていました。
朝になると夫がきて、戸板をタンカがわりにして中野駅の近くの外科病院に運んでくれました。
病院は、ケガをした人でいっぱいでした。薬などないから、赤チンを塗るだけが治療です。 |

早川初子 名古屋市生まれ。
1945 (昭和20)年5月25日の空襲(中野区城山町)で
焼夷弾の直撃を受け、左手首を失う。当時20歳。
|
そこで手術したのですが、麻酔なんかないのです。
今でも、コリコリ骨を切る音が耳に残っています。一ヵ月ほど入院していました。
家は焼け出されましたので一時は知合いの家に身を寄せていましたが、荻窪に空き家をみつけて落ち着いたのです。
大家さんも事情を知ってタダで貸してくれました。
一九四七年だったと思います。その年に娘が生まれましたから。
三つ違いで息子を産みましたが、手首がないと子育ても大変で、本当に自殺しようと考えたこともありました。
戦中、夫は会社勤めでしたが、戦後、ここに越してきてからは豆腐屋を始めたのです。
「堅い商売だから」と、夫の母が息子に習わせたのです。
それからは私が大変でした。
豆腐をつくるのに冬でも冷たい水を使うのですから、しもやけになって膿(う)んでしまうのです。
痛くて、今でも冬はつらいのです。
夫は一七年前に亡くなりましたが、息子夫婦が店を継いでくれています。
22 わざわざ疎開したその場で 石田あい子――1945/5/19東京空襲
top
|

石山さんが独自で訓練した聴導犬チトセ1歳の誕生日に、
いつも介助や連絡をしてくれる親しい友だちをよんで、
ささやかなパーティを開く(1985年)
一九四三年に二度目の父親が病死、母と私と弟と妹の四人家族の母子家庭でした。
上野の不忍(しのばず)に住んでいましたが、近くまで空襲で燃えたので、板橋の伯母の家はまわりが畑だから、まさか爆弾は降ってこないだろうということで疎開したのです。 |

石山あい子 本郷区(現文京区)生まれ。
1945 (昭和20)年6月10日の空襲(板橋区)で、
小型機の爆弾によって失聴。当時15歳。
|
一九四四年の一二月頃だったと思います。 不忍の家は焼けなかったのですが、わざわざやられるために疎開したようなものでした。
当時、母か私のどちらかが働きに出なければなりませんでした。
私が勤労動員に引っ張られますので、母が伯父の会社で働いていました。
そして、私は学校をやめて弟や妹の子守をしていました。
一九歳でした。学校に行っても畑仕事ばっかりで勉強はないのです。
それで勉強は後からでもできると思って、私が親がわりになりました。
一九四五年の六月一〇日のお昼でした。
小型機ですけど高射砲で撃たれて落ちながら爆弾をばらまいたのです。
うちのまわりだけで一三発落ちたそうです。
井戸のポンプがアメみたいにグニャグニャになっていました。
すぐそばの伯父の家では、カゼで休んでいた伯父と子供たち三人は昼の支度で家の中に入っていたのです。
伯父の三男と私たちは表にいました。そしたら、ものすごい音とともに家ごと道路を狭んだ向こうの畑へ飛んでしまいました。
家の中にいた三人ともドロンコになって即死です。
伯母の子供たちは生垣がかぶさって助かったのですが、上の子は片耳が聞こえないのです。 三男はまだ爆弾の破片が頭に入っています。
私の妹と弟は目をやられました。私は耳が聞こえなくなりました。
それも急に聞こえなくなったのでなくて、それを境に聴力が落ちてきたのです。 |

慈善団体からプレゼントされた聴導犬ロンが
加わり、散歩におおわらわ。
その後ロンはヒラリアで死亡(1988年)
|
それで、ここも危ないということで新潟に疎開しました。
そこでの住まいは、風船工場らしいところで、一つの工場に何世帯も入っていました。
私たちは土の上に板を敷いて、その上にゴザを敷いて生活していましたが、折り合いが悪くなって、まだ空襲が終らない東京に戻ってきました。
終戦は伯父の家で迎えました。
私たち姉弟三人、母と祖母、従兄弟二人の七人家族でした。
夜でも電気を堂々とつけられるようになってホッとしました。
それまでは、とにかく暗くしなければいけなかったし、夜はいつでも逃げられるように着たまま寝ていましたから。
一二月頃、朝起きたら耳が聞こえなくなっていました。
それまでは耳が少し遠いなあとは思っていましたけど……、ビックリしました。
耳のほかに神経もやられて、それで体質が変わりました。
たとえば、ペンキ屋の前は通れなくなるとか、煙がダメになってしまうし、体の重心がとれなくて酔っ払いみたいになりました。
ふしぎなことに、今までバスに酔っていたのがぜんぜん酔わなくなりました。
耳の方は病院ですいぶん治療しましたから、前に比べればよくなりましたが、耳鳴りはずっと四〇年続いています。
頭がサッパリとしたことは一日もないのです。
何のためにこんなにまでして、生きていかなければならないのかと思います。
母子家庭で母が忙しいものですから、八百屋とか魚屋にお使いを頼まれます。
でも相手の言うことがわからないものですから怖い、それで行かないと「言うことを聞かない」って母が怒るのです。
ホウキ持って追いまわされたりもしました。
ある日、新宿へ映画「断崖」をみに行った帰りですが、道端で本を売っていたのです。
厚くて綺麗な本は珍しいと思って買ったら、それは聖書だったのです。
その聖書がきっかけで、ウェンミラー環先生から、とてもよい文章のハガキをいただきました。
「いろんな花が、木々が、春にそなえて冬の間こつこつと励む時、その木にとって春は一段と喜びをもたらすでしょう」というような意味でした。
ずいぷんと心が和(なご)みました。
それから、一九四七〜四八年頃だと思いますが、グレイス・デキャンプさんという宣教師が日本へこられました。
その方とお会いして、その方は少し日本語が話せたのですが、とにかく辞書と首っ引きで話をしたわけです。
よく励ましてくださったり、面倒をみてくださって、それからずっとつき合いが続きました。
日本聾唖(ろうあ)学校も紹介していただきました。
母は反対していましたが、私が勝手に入ったのです。一七歳だったと思います。
それで読話で言葉が読めるようになると、母も認めてくれて月謝を払ってくれるようになりました。
そこでお友だちがいっぱいできて、今でもおつき合いしています。
一九五六年に結婚しましたが、相手が怠け者で暴れるものですから、子供が生まれて一歳半ぐらいの時に別れてしまいました。
結婚した当時、鶏を飼っていたのですが、猫とかの被害があって番兵がほしいと言っていたのです。
そしたら、妹からスピッツの雑種一匹を結婚祝いにもらいました。
名前はジョンでものすごく利口なのです。
卵を買うお客さんがくると、玄関の方を向いて吠えて教えてくれるのです。アラッと思いました。
鶏の世話で忙しいから、行李に赤ん坊を入れてジョンに子守させていたのですが、そのうち勝手にいろいろ教えてくれるようになったのです。
離婚後、実家に息子とジョンを連れて帰りましたら、実家でもお客さんを教えてくれるのです。
昼寝している時でも内に入れおくと、ちゃんとおでこを叩いて起こすのです。
それが聴導犬(ちょうどうけん)と呼ばれることになるのは、もっと先のことになるのですが。
一代目がジョン、二代目がタケル、三代目がチサト、四代目がチトセです。
一から一〇まで私が訓練したのです。
あの頃は労働犬(ろうどうけん)と言ってまして、意識して訓練したのがタケルなのです。
タケルは捨てられた犬でした。チサトは「動物フェスティバル」に出されたなかから選びました。
聴導犬を訓練するところは当時まだありませんでした。
私が二八年間犬を訓練してきたのです。
アメリカでヒヤリングドックとして広まって、日本小動物医師会が慳及委員会をつくろうということになって、それで一九三二年に、訓練した犬をオールドッグセンター(埼玉県にある警察犬訓練所)に渡して、聴導犬の訓練所が初めて日本に誕生しました。
アメリカはまだ九年ですし、イギリス、フランスは昨年からはじめたと聞いています。
ですから聴導犬の開発は、私が世界で最初だと思います。
それで一人でコツコツと聴導犬をひろめる運動をしてきました。
ところが、聴力障害者は犬を飼えない団地に住む人が多かったり、資金が出せないということもあって、なかなかひろがりません。
現在、私は役所に犬を飼えるようにかけあっています。
四号犬までは現在使われていて、訓練所では六号犬を訓練しているところです。 私は聴導犬をひろめる運動をずっとつづけてきましたので、残りわずかですが聴導犬の普及に生涯をかけたいと思います。 (一九八五年収録)
23 洗面器の手首に母は号泣(ごうきゅう)する 吉田陽子――1945/4/13埼玉・蕨空襲
top
|

下の娘(小学校2年生)と生まれ故郷の浦賀の海で
兄と、姉が三人で、私は五人兄弟の末っ子です。
一九四五年四月一三日に蕨(わらび)市が空襲を受けました。 私が五歳の時です。
夜の真っ暗な中を逃げたという記憶があります。 |

吉田陽子 神奈川県横須賀市浦賀町生まれ。
1945 (昭和20)年4月13日(埼玉県蕨市)の空襲で、
焼夷弾の破片が左腕にあたり切断。当時5歳。
|
今は芝園(しばぞの)団地が建っているのですが、当時は軍需工場の日本車輛だったので、それをめがけて板橋の方からきたんじゃないかと言われています。
板橋からかなりの距離をB29が焼夷弾を落としていったのです。
三学院という大きなお寺に逃げようと、隣組で決めていたのですが、当時一四歳の姉が逃げたくないと言い、私たち家族は逃げ遅れてしまったのです。
和楽備(わらび)神社の四つ角を曲がって三学院に行かなくてはならないのですが、ここは突っ切れないくらい、いっぱい荷車とか荷物を持った人がきたのです。
そして、人の流れに流されて日本車輛の方に行ってしまいました。
一緒に逃げたのは、母と二人の姉と私だけです。危ない方へ逃げて、焼夷弾を落とされたのです。
持って行った布団やお米なども焼けて防空ずきんも燃えてしまいました。
私は一四歳の姉におぶさって、母が荷物をいっぱい背負って、すぐ上の姉の手を引いていました。
母はもう少し安全な場所まで逃げるという気で、私を姉の背中から降ろさなかったのです。 |

蕨(わらび)市役所に勤める陽子さん
|
たんぽの畦道(あぜみち)みたいなところにたどり着き、母は二つ上の姉を腹の下に入れて腹ばいになってたらしいのです。
そこへ焼夷弾の破片が二つ落ちたのです。
破片といっても、丸い漬物の重しにできるくらいの石なので、おどろきました。
一つは姉の右のお尻で、私が左手をやられました。
姉の臀部(でんぶ)は肉がえぐれ、さいわいにも骨までいってなくて今は普通に歩けます。
私は着物の上から破片があたったので血は出なかったのですが、骨が全部砕けてしまって、皮膚だけになっていたと母が言っていました。
もうちょっと左だったら私は死んでいたのです。
その直後に「お手々が痛い」と言って気を失ったそうです。
母は動けなくなった姉の世話をしている間に、自分のもんぺが燃えたのに気がつかなくて、両足に大火傷を負いました。
近所の人がリヤカーを持ってきてくれて姉を乗せて、中島という大きな外科病院で、手当てをしてもらったのです。
私の手は骨が砕けて、絶対につかないということで、切断されました。
洗面器に乗せられた小さな手をみて、母は号泣したそうです。
姉のえぐれた尻の傷を中島病院では手に負えないということで、大宮の日赤病院まで連れて行かれたのは、一四日になっていました。
一日かけて一七号国道をリヤカーで運んでくれたのです。
それから私たち三人の入院生活が始まりました。
赤チンを塗るとか白い乾き薬だけで治療をしたので、完治するのに四ヵ月くらいかかりました。退院したのが八月ですから終戦と同時です。
日赤にいる間にも何度か空襲にあいました。空襲があるたびに、庭に防空壕が掘ってあったのですが、そこに看護婦さんが連れて行ってくれたのです。
母はひざから下の火傷ですから痛くて歩けなくて、這って行ったのです。
ベッドに寝ている姉たち重症患者は病室にいました。
姉の隣に寝ていた女の人は、「恐い、私も連れて行って」と泣き叫んでいました。
姉はいつまで続くかわからないこの戦争で、生きていることはないと覚悟していたようです。
ですから「連れてって」とは、言いませんでした。四ヵ月の病院生活は悲しい思い出だけでした。
一九四六年の四月に小学校に上がりました。
右手が残っていたので、義務教育には支障がないだろうということで。
父がその年の秋に病気で死に、母は、私が一九歳の時に亡くなりました。
父が死んでから母はずっと働きどおしでした。
母は私が結婚できないだろうと心配していましたが、さいわい理解してくれる夫に恵まれ、二六歳の時に結婚しました。
そして二人の娘にも恵まれました。でも子育ては大変でした。
保育園に預けるために、自転車の前と後ろに二人を乗せて、片手で運転していたのですから。
その子たちも無事に育ち、上の娘は嫁いでいきました。
下の娘ももうすぐ嫁いでいきます。
今は亡き母のあの悲しい思いを、当時の女性の人や息子、恋人たちを戦場に取られた悲しい思いを、私は娘たちにはさせてはならないと思うのです。
戦争は命の敵だから……。
24 雨のように機銃弾が降る 間宮正巳――1945/7/18千葉空襲
top
|

空襲を受ける1年前の7月、上野公園で
|

間宮正己 千葉県和田町生まれ。
1945 (昭和20)年7月18日の艦載機による空襲
(千葉県和田町)で、右手首を撃ちぬかれ切断。当時16歳。
|
当時の家族構成は、両親、祖母、兄弟が六名と、川崎から疎開してきた叔母の子供が二人いて、全部で一二人ほどいました。
私は学校を卒業して、家が農業なのでその手伝いをしていました。
七月一八日の日は、父親が家の庭先にあった防空壕を大きくつくりかえるため、私にかわりに消防団に出てくれと言うので詰所に出ていたのです。
その頃、空襲が頻繁にあって、このあたりはB29の通り道でしたから、しょっちゅう空襲讐報が鳴っていました。
私がやられた時はグラマンが三五〇機きたのです。
横浜、木更津を空襲して、そしてこの部落と。ゴウゴウとして、空が暗くなるくらいでした。
最初に飛行機が一機翼をふって、次には全機が急降下して……、
詰所の前で「きたっ!」と言った瞬間に、もう雨のような機銃掃射です。
消防小屋の隣の小さな墓地に石碑が立っていて、私はその石碑を抱いて防いでいたのです。
その時に雨のように機銃弾が降ってきました。一六歳ですから、ただ怖いっていう一心でした。
何もなければ貫通していたでしょうが、石を抱いてたからあたった瞬間に手が取れたのです。
手がジンジンとしびれて、みたらスパッと大根を切ったように切れていて、ジューと血が走るのです。
右手の下の方が、手を持ち上げたらぶらーんとしているのです。
それで「やられた!」って言ったら、仲間に「今こんなに弾丸が飛んできてるから我慢してろ」って言われて……。
しばらくして機銃が止んだので団員が駆け寄ってきて止血したものの、もうその時は血の海です。
リヤカーに乗せられて出ようとしたらまた空襲になって、飛行機がくるなかを逃げながら病院まで行ったのです。
そして、医者に「これはもう切らないとだめだ」と言われて手を切り落としたのです。
麻酔なんかありません。私はまさか手がとれるという感じはなかったのです。
その病院で「破傷風になるかもしれないから」と医者がカルテを書いてくれて、姉が東京の伝染病研究所へ薬をもらいにいったのです。
そしたら、ないと言われて。姉はもしものことがあっては困るからと、米二升持っていったらしいのですが、
「じゃあ、もうこの米は必要ないからお宅で食べてください」と言ったら、
「ちょっと待ってください。何本かあるでしょう。みてきますから」と、係の人が出してくれたそうです。
それで私は命拾いしたのです。
その後、鴨川(かもがわ)市の東条病院というところに移って四ヵ月入院していました。
院長が「この人は九分九厘もうだめだ」と言ったそうですが、やっぱり寿命があったのでしょう。
終戦はそこで聞きました。これで空襲がなくなる、怖い思いをしなくていいんだと思うとホッとしました。
そして、何とかよくなって家に帰るとそれからが大変でした。
今まで両方の手があったのにそれが片方になったから、何をやるにも全部左手と口です。歯を使って農作業をやりました。
体が疲労しないように自分で考え出して。
「踏み鍬(くわ)っていうのはこういうふうにやるもんだ」と父に教わった時も
「そんなこと言われても私は手がないから普通の人のようにはできない。自分で工夫してやるんだから」
と言って何でもやりました。
終戦後、「何だ、手がない」と人に言われたこともあります。
でも、私は病気で手を取られたわけでなく、自分か好きこのんでこうなったわけではない。
私は敵機にやられたんだ、人が何と言おうとようしみてろ、人並み以上にやってみせるからと、その時思いました。
だから今も何の仕事でもやります。
結婚は二五歳の時。子供が二人生まれ農業で暮らしていましたが、一九五八年の二月におふくろが、四月につれあいを亡くしたのです。
その時は困りました。
金には心配なかったけど、仕事を終えて暗くなって帰ってくると、下の娘は小学四年生、上は男で中学一年生でしたが、炊事場にぷら下がった裸電球の下で、二人が味噌汁の大根をきざんでいるのです。
その姿をみたら「ああ、女親がいればこんな小さな子供を、こんなように苦労させなくてもよかったものを。かわいそうになあ」と思いました。
じゃあ、自分が一生懸命やろうと、朝早く起きて子供たちに食べさせて、弁当つくって持たせてがんばりました。
人に負けるものか、人間やってやれないことはないと考えていたからです。
夜、疲れてくたくたになって帰ってくると、子供が「ひじが切れたから直してくれ」「ボタンが取れたから直してくれ」と言ってくるのです。
もうこっちは夕飯食べて、すぐにでも風呂に入って寝たいくらいの時なのに、でもこれやってやらないと、明日着ていくものがなくて困るだろう、とミシンを踏んでやりました。
その時が一番つらかったです。あとはそんなに苦しいと思ったことはありません。
農作業も機械を使いこなすのに慣れるまでは大変でしたが、自分なりに考えて工夫しながらやりました。
それから、五年間一人で子供の面倒をみていましたが、その後、姉の世話で今の女房と再婚しました。
私は戦争でこんな体になったけど、子供たちはおふくろに先立たれてもグレもせず、まっすぐ歩いて私についてきてくれました。
人に後ろ指さされるようなことや、親兄弟に迷惑をかけるようなことは、絶対してはいけないぞと言い聞かせて育ててきました。
二人とも所帯を持ってやっと親の役目がすんだなと、これからはできるだけ、この家のためにやれるだけのことをしようと思っています。
25 縁の下から飛び出したその時 鋤柄敏子――1945/5/29横浜空襲
top
|
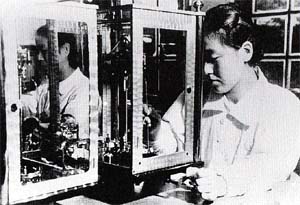
大東亜戦争一周年記念特集号を組んだ『週刊婦人朝日』の
グラビアに携載された、東京陸軍第一造兵廠での敏子さん
私の父は教師をしていました。
北海道を転々としていましたが札幌の市立の学校を最後に、勉強したいということで上京したのです。
私が小学校二年生の時です。
父は巣鴨の中学校で教鞭を執りながら、夜は日大や東洋大の夜学に通っていました。
私の下に弟と妹がいましたので生活は大変で、私は女学校を卒業すると王子の東京第一陸軍造兵廠に勤めておりました。 |

鋤柄(すきえ)敏子 北海道厚岸生まれ。
1945 (昭和20)年4月13日の空襲(豊島区駒込)で家を焼き出され、同年5月29日の空襲(横浜市港北区大曽根町)で顔・両腕を火傷。当時24歳。
|
一九四〇(昭和一五)年、父は横浜の大倉山に女学校を創立して、駒込から通っていました。
一九四五年の東京大空襲から空襲が激しくなっていましたので、家財道具を大倉山の防空壕に疎開させていました。
四月一三日の空襲の夜も、私と妹で荷物を運んでいて、母だけ一人残っていました。
家は焼失しましたが母は無事で、家財道具の半分くらいは残りましたので、以前から借りていた大倉山の駅のそばの一間におちつきました。
ところが、五月二九日の朝六時頃から警戒警報があり、勤めにも行けないのです。父は学校に飛んで行きました。
それで待機してましたら、九時過ぎ頃に空襲警報です。
それであわてて縁の下に三人で入ったのです。
そうするとゴーゴーとものすごい音が通り過ぎました。
しばらくすると横浜の中心部が真っ黒い雲で覆われていました。
一〇時頃、また戻ってきたのです。
大倉山に海軍の気象部があったのですがそこを目標にしたのか、焼夷弾をパラパラと落としたのです。
線路を狭んだこちら側にも落ちてどんどん燃えてきました。
それでまたあわてて縁の下から飛び出した途端に、母と妹と私の間に焼夷弾が落ちて炸裂して、私は火だるまになったのです。
一瞬ですから熱いも痛いも感じませんでした。
母や妹や大家さんが水をかけてくれたのですが、油脂がベッタリついているものですから、なかなか消えないのです。
どのくらいたってか、自分でひょっこり起き上がって手を見ると、左手は肉が取れて骨が見えていましたし、右手もやられていました。
顔は自分ではわかりません。
母がかわってやりたかったと泣いていましたが、とにかく一瞬の出来事でした。
それで私は農家に運ばれて、駅前の耳鼻科の先生が救急で破傷風の注射を一本だけしてくれました。
それから海軍気象部に運ばれたのです。
そこで亜鉛化軟膏をつけてもらい、今度は学校に運ばれました。
あちこちの病院に連絡をとるのですが、どこもいっぱいで入れないのです。
そこで机の上にタンカごと置かれたまま、耳鼻科の先生にきていただくことになりました。
私の勤めていた造兵廠の理科学試験室には、いろんな薬品がありましたので、そこからガーゼや必要な薬を取寄せて、学校の一教室が私の病室になったのです。
空襲になると、タンカごと防空壕に運んでもらうのですが、艦載機の低空飛行には生きた心地がしませんでした。
毎日のように空襲があったのですが、そんななかでも包帯交換は続けられました。
ところが、だんだん暑くなる時期で、ガーゼに膿がベッタリ。それを取るのが痛いのです。
それにウジがわいてくるのです。つらかったですね。
そこで終戦を知っだのですが、何のためにケガしたのか、ほんとに悲しいのです。
この頃、皮ができ始めて一時はすっかり綺麗になりました。
ところが、一番ひどいところからケロイドになってきたのです。
靴の底みたいに堅く真っ赤になってきました。
鼻は曲がってくるし、口は開かなくなってしまいました。
一年ぐらいたってから、親がこんな顔じゃかわいそうだというので、東大で整形手術をしました。
その時はベールを被って行きました。
顔は保証できないということで、ここでは左手を伸びるようにしました。
入院していた方から渋谷の日赤病院を教えていただき、一九四六年の春に入院しました。
腿の皮膚を取って植皮するのですが、一遍にはできませんので、十数回も手術したのです。
一回植皮すると一週間は動けないのです。あごのところは三度目でやっと成功しました。
一年半入院していました。
食糧もない時代で、母と妹がかわり番こにつき添ってくたのですが、医療費はみんな借金ですから大変でした。
退院して、女学校時代の担任の先生が、田園調布教会を紹介してくださって、そこで洗礼を受けました。一九四六年の一〇月でした。
それでさて、私は何をしようかと悩んだすえ、私たちと同じ境遇に会って、戦災孤児になった人のところで一緒に生活したらどうかと考えたのです。
それには資格があったほうがいいので、一九四九年に自由ヶ丘の厚生保母学園に入学しました。
そこは夜学でしたので、昼間は保育をしながら通いましたが、電車の箱が校舎になっていました。
そこを二年で、保母と幼稚園の資格を取って卒業しました。
在学中には、沢田美喜さんのエリザベス・サンダースホームや日赤子供の家、啓明学園や肢体不自由児施設などの実習や見学をしたのですが、戦災孤児がいたかどうかはわかりませんでした。
その頃は、父の女学校にも幼稚園がありました。
父は私に内緒で保育学校の先生のところへ「あんな顔でも幼稚園の先生になれるか」と相談に行ってたそうです。
私はこんな顔ですから、とてもじゃないですが普通の園児をみるのは嫌だったのですが、父は私を主任にして、そこに勤めさせたのです。
そこで十数年勤めました。父が辞めざるを得なくなった機会に私も辞めて、友だちの紹介で池袋のミッションの青空保育にお手伝いに行きました。
一九五二年に、同じ障害者で高校の教師をしていた椎野と結婚しました。
彼はてんかんの病気をもっていたのですが、私には一切隠していたのです。結婚一年後に、事故で亡くなりました。とても優しい人でした。
その後、一九五九年に鋤柄と再婚しました。
鋤柄は川崎で失業者たちの子供を集めて、“青空こども会”を開いていました。
彼は児童館をつくる運動をしていましたので、私にピッタリだと思ったのです。結婚してから、川崎の小さな家に引っ越し、無認可保育を始めました。
彼は花の咲かない川崎を、土壌改良で見事に咲かせまして“花いっぱい運動”をやりました。
地域で七夕や運動会やもちつき大会などをどんどんやるもんですから楽しかったですね。
でも私は大変でした。
彼のお母さんは寝たり起きたりの状態ですし、子供たちの世話もしなければならない、そんな生活を一四年間やってきました。
一九七一年に私の母を、翌年には彼の母親を亡くしました。
その時、私の体はガタガタになっていたのです。
私の父も八三歳でひとりぼっちになっていましたので、母の一周忌の日に、彼に内緒で父の元に帰ったのです。
父が亡くなる二年ほど前、一〇年ぶりに鋤柄に電話をして、離婚届けに判を押してもらうために会うことになりました。
もうその時は友だちみたいなものでした。「よく思い切って出てきたねえ」と言われました。
それからはちょくちょくハガキがきたりします。
私は神奈川県戦災傷害者の会の会長なのです。
最初、小暮さんが呼びかけた新聞の切り抜きを友だちが送ってくれまして、東京の傷害者の会の発会式に参加したのです。
しばらくは東京の会で一緒に活動してたのですが、神奈川でもやったらということで、一九七六年に会を発足させました。
戦災傷害者の援護と実態調査の二点を国に要請しようと、神奈川県と市に陳情と請願を繰返してきました。
神奈川県と一九市が採択してくださって国へ意見書を提出していますが、国の壁は厚くて今だに実現できないでいます。
ですから、私は休む暇がないのです。神様が私に役目をあたえてくれたのです。 (一九八九年収録)
26 玉音放送、もう少し早ければ 青木アキ――1945/8/13茅ヶ崎空襲
top
|

夫の23回忌に娘2人と孫と姉と

夫が出征するときに持たせた、寄せ書きの日章旗と千人針と慰問袋
|

青木アキ 神奈川県平塚市生まれ。
1945 (昭和20)年8月13日の艦載機による空襲
(茅ヶ崎市十間坂)で、爆弾の破片が左足膝下を貫通して切断。
同時に長女は左腿を貫通、長男は親指と小指にケガを負う。当時32歳。
|
当時、茅ヶ崎駅の卞ぐ近くに住んでいましたが、夫は五月に招集されたので、私の母にきてもらって、子供三人を抱えての生活でした。
八月一三日の朝から警報が鳴っていましたが、昼になっても静かなものですから防空壕を出てお昼ご飯を食べていると、急にバリバリとやってきたのです。
これはいけないとみんな押入の布団の中にもぐりました。
私は、腹をこわした一番下の長男を連れて便所に入っていました。
窓からみますと艦載機がプンプン旋回していて、怖くて出られないのです。
空襲の時は戸を開け放つように言われていましたから、動く姿をみられたら爆弾を落とされると思いました。
窓から機関車が動いているのがみえました。
突然機関手が機関車の下にもぐった途端にドカーンとものすごい音がしました。
機関車を目がけて落としたのだと思いますが、その一発が私の家のすぐ前に落ちたのです。
気がつくと、私の左足がやられていました。
足はついていましたが、グニャッとしていました。
でも痛いという感じはありませんでした。
押入れにもぐった長女の左足の腿もやられ、抱いていた長男の指も削られました。
そして、前のうちの奥さんは子供を抱いたまま、眉間に破片が当たって即死。
筋向かいの娘さんは手を落とし、奥さんは手に傷を負いました。
すぐに警防団の方がタンカを持ってきて病院へ運ばれましたが、その途中で、またバリバリと機銃を撃ってきました。
その時は死ぬ覚悟はできていましたから「私を置いて逃げてください」と言って、警防団の方を避難させました。
病院は廊下までケガ人でいっぱいでした。
駅の構内にも落ちたらしく、駅員の方も足をやられていましたが、しばらくして亡くなりました。
私は気をしっかりしていたつもりですが、お寺さんにピカピカ燈明みたいなものが上がっていて、みんなが待っている幻をみました。
だから危なかったのだと思います。でも自分の血液型も知っていましたからすぐ手術できました。
私は足がなくなったと思ってもいませんでした。
二〜三日して先生に「足があると思っているだろうなあ」と言われて、初めて気がつきました。
つける薬などないですから、いつまでもジュクジュクしていました。
終戦の玉音放送は病院で聞き、もう少しはやければという悔しい思いをしました。
一ヵ月ほどして退院しました。通院しなければならなかったのですが、その頃復員した夫は「なぜ防空壕に入っていなかった」と怒って病院に連れて行ってもらえませんでした。
仕方なく、弟に湯河原の温泉水を運んでもらい、毎日その水で傷口を洗って赤チンを塗って、自分でなおしたのです。
傷が治っても、はって歩くことしかできませんでした。
夫の実家でめんどうをみてくれるというので、自宅を売って同じ茅ヶ崎市の小和田へ移りました。
外の景色をみたくて、ある日、柱に掴まって、高窓からのぞいたのがきっかけで立つことを覚えました。
それから、兄が松葉杖を手に入れてきたので、それを使って庭くらいは散歩できるようになりました。
夫は働き者でしたが、復員してからは「働く気がしない」と遊んでいました。
そして浜でナガラミを取っていたりしていましたが、ある日、潮の巻き目にはまって亡くなりました。
復員してから半年後のことです。
長男は二歳を過ぎたばかりでしたので、こうしてはいられないと働き始めました。
実家が松下電器の孫請けの仕事をしていましたので、その縁で乾電池のカンを仕上げる仕事をしばらくしました。
そのうちに実家から出てくれと言われ、民生委員の方の土地を借りてそこへ移り、その方の口利きで辻堂にある電球会社の工場に松葉杖で通うようになりました。
しかしその会社もしばらくして倒産して、ビーズや裁縫などの手先でできる内職をしていました。
一九四九年に「希望荘」という障害者の施設ができたのを知り、何度か足を運んで入れてもらうことができました。
仕事もありましたし、義足もここでつくってもらいました。ここには一三年間いました。
母子家庭の子は就職口が中々なかった時代ですが、娘二人とも神奈川中央交通にバスガイドとして働いていました。
それで、一九六二年に南原の土地を買って、大工の弟に家を立ててもらって越してきたのです。
今は娘たちも嫁ぎましたので、長男夫婦と孫二人と暮らしております。
以前は足が冷えたりしますと疼(うず)いて、時々はケイレンを起こしていました。
今はいい薬がありますから、発作が起こる前に飲んでしまいます。
もうこの年齢になりますと、記憶のほうもだんだん薄らいできました。
戦場のような空襲のことは、片足になって苦労したことも、つい忘れがちになります。
でも二度とこんな戦争があってはならかいと思います。
27 本土最後の艦砲射撃で失明 松浦禮次――1945/7/29浜松空襲
top
|

軍が支給した軍服と綿の防弾チョッキ、紙でつくられた軍帽
一九四三(昭和一八)年、高等小学校を卒業して、六月頃に浜松の中部三部隊に軍属として入隊しました。
半分志願、半分強制みたいなかたちでした。
そして、富士山の山麓にある陸軍少年戦車学校に三ヵ月間訓練に行きました。
九月に浜松飛行隊に配属になって、爆撃機の整備の補助をしておりました。 |

松浦禮次 静岡県周知郡森町生まれ。
1945 (昭和20)年7月29日夜からの艦砲射撃(浜松三方ヶ原飛行場)で
右目を失明。右足踵に今も破片が残る。 当時19歳。
|
配属になった当初は重爆撃機が二〇機ぐらいはありましたが、終戦近くになるとエンジンの抜けた一機だけになりました。
飛行場には木製の飛行機に似せたものを二〜三機つくって、敵をあざむくための偽装をしていました。
終戦も真近い一九四五年七月二九日の夜、飛行機の整備をしていて、激しい艦砲射撃を受けました。
後で知りましたが、日本本土最後の艦砲射撃だったようです。
防空壕に入ろうとした時に、一〇メートルぐらい先に砲弾が落ちました。
倒れて意識のない私を友人が助け起こして防空壕に運んでくれ、衛生兵が手当てをしてくれたようです。
といっても、化膿止めと赤ちんを塗るくらいで、そのまま野宿のような感じでした。
飛行場のほかに軍需工場もけっこうありましたから、あたり一面火の海で、市内はほとんど焼けつくしました。
次の日に、民間の病院に運ばれましたが、ここも薬品がなくて、化膿止めらしき目薬をさして眼帯をするだけでした。
それでも一ヵ月は入院しておりました。
八月一五日の終戦は、病院じゅうがさわがしくて、日本が降伏したということだけ聞きました。
その時はただやっと解放される、生返ったという印象だけです。
それまでは自分であって自分ではなかったわけですから。
八月一八日頃、周知郡森町の実家に帰りましたが、近所の人の知らせが先にいってたようで、両親は私のケガにおどろかなかったようです。
近所の方の勧めで、目にいいという漢方薬ものみましたが、初期治療が悪く失明を取戻すことはできませんでした。
傷口がふさがってから農業で暮らしました。
一九五一年に結婚して、子供二人が生まれましたが、私は次男でしたので、一九五六年、家族を連れて知人を頼って東京に出てきました。
そして、マッサージの学校を出て、友人と一緒に、ずっとマッサージの仕事を続けています。
家内は三年前に亡くなりました。東京で生まれた二人を含めて、娘四人とも嫁いでいきましたので、今は一人で暮らしています。
私は古い考えを植えつけられた人間です。テレビなどで政府の要人が、中国や朝鮮にあやまる姿を見ると、正直にいってとまどいます。
しかし、自分の人生を振返ってみると、まさに青春はなかったし、その後は苦労の連続でした。失明さえなければ、と思うこともしばしばです。
もう二度とあんな時代はゴメンです。
28 麻酔なく抑えられて手術 筒井幸子――1945/7/24愛知・半田空襲
top
学徒動員で中島飛行機へ行っていました。
女子寮があって、その寮から中島飛行機まで歩いて通っていたのです。
その日はたまたま朝から警報が鳴っていたので、工場へ行くのは中止になって、私たちは寮の掃除をしたりして待機していました。
そうこうしているところに急に空襲警報になったのです。
それでみんな防空壕に入りかけたのですが、私は班長をやっていたので、みんなが入る後から入ろうとした時、上の方からシュシュシューガーって、爆弾が真上から落ちてくる音がしたのです。
防空壕に入るいとまもなく、私は地面に伏せていましたが、そのままバーンと飛ばされてしまいました。
寮ごとですし、防空壕にも落ちて友だちも二人亡くなっています。
確か十一時頃だったと思います。私は病院に連れて行かれました。
失神しながらもうっすらと覚えているのは、トラックに物を放られるように入れられたということです。
二日間くらい気を失っていたらしいのですが、気がついた時には目の前に母親がいました。 |

筒井幸子 名古屋市生まれ。
1945 (昭和20)年7月24日午前の空襲(半田市乙川の中島飛行機)で
右肩から腕にかけて負傷。同時に友人2人を亡くす。当時14歳。
|
失神しながらも覚えていることは、すごく喉が乾いて「水が欲しい、水が欲しい」と言ってたら、軍医が「この子はもう助からないから水を飲ませてあげなさい」と言って、コップで水を飲んだことです。
出血多量で布団がグジュグジュになるほどだったらしいし、爆弾の破片も右肩に入っていました。
それだけではなくて、腕をえぐられているのです。
背骨や足にも傷がたくさんありました。
助かってからが大変なのです。
すごい膿(うみ)だったのですが、窓に網戸などないから蝿が入ってきて、ウジがわくのです。
首のあたりをウジがはいずってくるのです。
それから爆弾の破片などを取除く手術をしました。
麻酔がなくて押さえつけて手術するわけですから、母親にはみせられなかったのではないですか。
「名古屋へ行って、一晩で帰ってきてください。あとの世話は生徒などがみますから」と言われて母は帰されたそうです。
両足手首全部しばられたみたいにつかまれて、私がギャーギャー言うのを押さえつけて、ジョキジョキとハサミで切っていくのです。
切ったところから、爆弾の破片が五〜六個も出てきました。
それから防空頭巾の綿と髪の毛、骨のかけら、それらが山のように入っていたそうです。
その夜は四〇度を越すようなすごい熱が出たそうです。
その時には、医者が生徒に死ぬかもしれないから、ついているように言って。
それでも峠を越えて生きのびたのです。
それから徐々に膿の出るのも減ってきて、肉がだんだん盛り上がり、少しずつよくなってきました。
そうなってくると先生が「さあ、今日も泣かせてやろうかな」と言うのです。
骨折で骨がごちゃごちゃにくっついた手を無理やり上にあげるのです。
私は病院中に響き渡るような声でうめいたものです。
先生は今は苦しいだろうけれど、ちょっとでも動かしておかないと使えなくなるからと言って。
手術する前は肩から取ってしまうと言っていたのです。
うちの母親が片手のない娘ではかわいそうだから、何とか形だけでも残してくれと頼んだらしいのです。
半年後の一二月に、伯父が温泉に入れておいしい物を食べさせて療養させるからということで、中途退院したのです。
そして「女の子だから何とか治らないか」と名古屋の病院、四〜五ヶ所に連れられて行きました。
でも、どこも「いまの日本には設備も医療もありませんから、残念ですが何もできません」と言われました。
あちこち行ったものですから、帰ってからすごい熱が出ました。
それでとうとう伯父さんは私を温泉に連れて行けなくなったのです。
その後、傷口の穴からギザギザに折れた骨が何回も出てくるのです。
それで家族に取ってもらって、赤チンなどで消毒してもらうということが半年くらいつづきました。
その骨のかけらも取っておいたのですが、私が東京にきている間になくなってしまいました。
それからはずっと家にいまして、字は書けますから、軽い事務みたいなことはしました。
復学はしませんでしたけれど、卒業証書はもらっています。
二六歳の時に、家にいるのが気まずくなって東京へ出てきました。
東京の友だちのところにしばらくいて、シビィリアンクラブという外人向けのレストランでウェイトレスをしていました。
そこでバンドマンのトランペッターの夫と知合ったのです。
一九六三年に結婚しました。それで長男が生まれたのですけど、子育ては本当に大変でした。
いまも疼くのです。えぐられたところや関節がズキズキします。
洗い物くらいはできるのですが、右手は半分までしかあがらない。
耳も半分やられていますから、人の集まりがあっても行かないのです。
若い頃の青春時代なんてありませんでした。
ショートヘアもできない、水着も着られない、娘らしいおしゃれもできません。
私の傷を知らない京都大学の学生と恋に落ちたこともありましたが、私の方から身を引きました。
戦争は痛い、苦しい、悲しいだけじゃなくて、人の人生をかえてしまいます。
戦争の本当の責任は誰にあったかと言いたいのです。
内地も戦場で、学徒動員で駆り出されたりしたのに、軍人は傷ついたら恩給というのが出ています。
でも学徒はむりやり動員されても何の補償もないのですから。
私もせっかく女学校に入りながら、天皇のために学業を捨てて働いて、一生取返しのつかない傷を負わされて、いまだに苦しんでいます。
そういう人たちに何の補償も思いやりもないのです。
戦争の罪とか責任とかをもう少し考えてはしいと思います。
どれだけ多くの人の心や体を傷つけてきたのか、私の戦争は一生終らないのです。
29 兄弟四人助かり、父母は即死 中林昭夫――1945/8/2富山空襲
top
|

景気の良かった東京オリンピックの1964年、同僚と仕事現場へ
富山というのはB29の通り道なのです。
大阪、名古屋、京都、あのへんを爆撃するのにずーっとまわってくるコースなのです。だから毎晩です。
たまたま八月二日は富山にきました。
でも毎晩のことだから、空襲警報が鳴るたびに防空壕へ走っていたのだけど、しまいには慣れっこになりました。
うちの親父は、富山の国鉄に勤めていたから、家は富山駅の近くにありました。 |

中林昭夫 富山市生まれ。
1945(昭和20)年8月2日午前8時頃の空襲で焼夷弾が自宅を直撃し、
顔と手の甲を火傷。その時に両親を亡くす。当時12歳。
|
その日は防空壕に入らず、家族六人家にいたのです。
そうしたら家に直撃弾が落ちました。
焼夷弾が落ちる時は、ちょうどブリッジ板に砂利を撒いたような、ザーッていう音がして、何だろうと思っていたら、一瞬のうちに火の海になりました。
親父もおふくろも即死でした。
その日の晩に限って、親父の妹家族がうちに遊びにきていたのですが、妹家族四人も即死しました。
ぼくはすぐに姉と弟二人連れて逃げ出しました。
だから兄弟はみんな助かりました。
一緒に逃げたのだけど、外に出たらみんなバラバラになってしまいました。
おふくろの姉さんが嫁に行った家が、富山市内のはずれにありました。
そこに逃げるように、前からおふくろに言われていたので、バラバラになったけど、みんな一応そこをめざしたわけです。
ぼくは大ケガして国道八号線のところに意識不明という感じで倒れていたらしいのです。 |

中学卒業後、最初に修業にいった高円寺の建具屋で
|
それまでは国道の下の川に、夜中の二時頃から四時間くらい夜を明かして、一晩中そうしてたから疲れて寝たのかな?
夜が明けて親類の家を目指したのですけど気を失って、気がついたら病院にいました。
他の兄弟は親戚の家に辿りついたらしいのです。
病院は富山からずっと離れた滑川(なめりかわ)っていうところですが、そこに一週開くらいいたと思います。
爆弾が落ちた瞬間に手で顔を覆ったから、顔と手の甲を火傷していました。
退院できる状態ではなかったけれど姉が迎えにきました。
親類のうちで療養して、あくる年の一九四六年に、おふくろの弟を頼って、兄弟四人で東京に出ました。
包帯はしていたけど、だいぶケガはよくなっていました。
それが小学校六年の八月。それで杉並第五小学校へ転校しました。
中学を卒業すると、高校は叔父さんに学費まで出してもらっては悪いから、新聞配達しながら通いました。
高校卒業してから建具屋に見習いに入って、もう四〇年も建具職人をやっています。
今はみんな大学出てるけど、昔は職人になる人が多く、そういう時代でした。
火傷はしてても、手は動くから、仕事にはぜんぜん問題なかったのです。
30 堤防の方から火の玉が襲う 鈴木洋子――1945/7/19福井空襲
top
|

1963年頃、足立区の靴工場の社内旅行で
父の仕事の関係であちこち転校しまして、一九四一(昭和一六)年四月、小学校四年の時に福井市へ引っ越しました。
空襲にあった時は高等科二年でした。学徒動員で昼間は軍需工場へ行っていました。
私の下に小学校五年の妹と三年生と五歳の弟がいました。
七月一九日の夜十一時頃、空襲警報が始まりました。
いつものようにすぐ解除になると思っていましたが、福井市のあちこちに照明弾が落ちて、どんどん焼夷弾が落ちてきました。 |

鈴木洋子 福井県若狭市生まれ。
1945 (昭和20)年7月19日夜の空襲(福井市内)
で焼夷弾の直撃を受け右手を切断する。当時13歳。
|
防空壕にいったん入ったのですけれど、警防団の方が防空壕は危険だから避難してくれというので、家族全員、近くの足羽川のグラウンドに逃げたのです。
平和な時は、私たちはクローバーの花を摘んだり、泳いだりして遊んだところなのですが、その頃は河原はみんな畑になっていました。
そこには市内のあちこちから避難してきた人たちがいて、
「私は福井は大丈夫だと思って大阪から疎開してきたのに、福井でまたこんな目にあうとは」と言っていた人もいました。
堤防の向こう側に激しく焼夷弾が投下され、私の家の方向は真っ赤な炎に包まれていました。
それこそただ恐ろしいというだけで、空襲が終ってほしい、これは自然災害ではなく人間がやっていることなんだ、神様があるなら助けてほしいという気持でいたのです。
突然、堤防の向こう側から、火の玉が飛んできたと思ったら私の手に当たって、手がダラーッとぶら下がったのです。
まだ意識がありました。
母がすぐに自分の被っていた防空頭巾と腰に結んでいた紐とで止血してくれたのです。
着ている洋服は燃え出し、体を川に浸して火を消しました。
その時、父は会社の当直で家にいなかったのです。近所の男の方が「ここにいても救護班はこないから堤防の上に行きましょう」と言って、私をおぶって連れて行ってくれました。
ケガ人だけ乗せてくださいと、トラックがまわってきたのは覚えているのです。
それで私一人がそれに乗せられて、福井の端にある日赤へ連れられて行きました。
その後意識がなくなって、気がついてみたらもう手が切られていたのです。
その時は肘まで手があったのですが、薬もなにもないし、ただ消毒してリバノールという、黄色い薬のついたガーゼを貼っているだけですから、だんだん化膿してきました。
痛くて痛くて眠れない日がつづいて、化膿の臭いがプーンとして、くさいのと痛いという状態で、切らないと今度は命がだめになるということで、また切られて短くなってしまいました。
母がずっと私のそばについていたのですけれど、父や妹たちは家が焼かれて行くところがないから、防空壕の生活だったのです。
私の食事は一応病院から出るのですが、母の食事は出ないから、父が食事をつくって運んでいました。
鉄道も破壊され列車が不通になっていましたが、回復を待って妹と弟たちは長野の父と母の実家に別れて疎開しました。
その後、空襲は何度かあって、民間人は空襲にあっても、自力で逃げてくださいということなのです。
母と一回、一緒に逃げたのですけれど、そのつらいこと。
母もおぶってくれるのですけれど、避難場所が遠かったのです。
いくら子供とはいえ一二歳ですから重いのです。
時々私も歩いたのですが、目がまわるフラフラの状態で、
「こんなに苫しいならもう逃げたくない。もしこの病院が焼かれて死ぬんだったらここにいるわ」と言うと、母も
「じゃあ私も一緒にここにいるからね」と。
看護婦さんは傷痍軍人の介助に忙しく、民間人には手がまわりませんでした。
八月一五日に、天皇陛下の重大放送があるから、病院の事務所の前に集まってくれということで、父が行って聞いてきたのですが、何と言っているかわからない、どうも戦争に負けたらしいということでした。
私は、当時そういう言い方は非国民なのかもしれませんが、戦争に勝っても負けてもどっちでもいい、もう終ってよかったという、ホッとした感じだったのです。
それから新聞で原爆について「七〇年不毛の地に」とか「新型爆弾」という恐ろしい記事をみたことが記憶に残っています。
退院してきた時は、市内は見渡すかぎり焼野原で、物の焼けた何ともいえない変な臭いがしていました。
城下町なのでたくさん蔵があっだのですが、屋根だけ燃えてなくなって土壁だけが残っているのです。足羽山という小高い山が一望のもとに見渡すことができました。
戦中、芦原(えばら)温泉に急遽飛行場ができたのです。
そこへ父も母も勤労動員で行ったのですけれども、戦争が終ると、今度はそこが戦災者や引揚者の開拓地になって、開拓者を募集したのです。
父は子供がたくさんいるし、食物も大変だから、食糧増産しなくてはということで、その開拓に入ったのです。兄も予科練から帰ってきて開拓に入りました。
私は十一月に退院して、一二月からしばらく地元の学校に通いました。
入院中に左手で書いたり持ったりする練習をやりましたから、学校では片手で何とかみんなについていくことができました。
その後、地元の洋裁訓練所へ通いました。そこは障害者ではなく普通の人が行くところだったのですが、そこの園長さんが受入れてくれたのです。
一年間通って、最後に卒業制作にスーツを縫いました。
ミシン縫いもありましたが、裾のまつりなど手縫いの部分もけっこうあって、そういうのは人より時間をかけてやらなければなりません。
その頃は若かったから、徹夜してでもみんなについていけたのです。
当時は洋裁ができても、いまとは障害者に対する考えが違いますから、手がないというと就職がむずかしくて、なかなか思うような職場はありません。
ですから兄弟の服をつくる程度でした。職業安定所にも行ったのですが、職員も電話の交換手ならできると思うが、公的にダメということになっていますからと言うのです。
それで、東京で何かあるかしらと思って、小平市にある身体障害者職業訓練所に入りました。
革靴の甲をつくる仕事があったので、そこの寮に一年間いて技術を習って、三〇歳頃、足立区にある靴工場に初めて就職したのです。
そこには四年ほどいました。
その間に障害者の集まりで知合った人と結婚しました。
夫は労災で障害者になったものですから、やはり手が悪いのですが、ずっと会社に勤めて四年前に定年退職しました。
私は結婚してからは、近くにあった女性の下着をつくる会社に一〇年くらい前まで勤めていたのですが、その後は主婦をやっています。
そして地域の公民館などに集まる平和を考える会や、憲法を勉強する会に入ったり、生協の委員をしたり、食品の安全性を考えたりと、とにかく人間の命が大切だと思っていますから、そういう活動をしています。
戦争は人と人との殺し合いです。
人殺しが賞賛されて英雄視される社会から、しあわせなど生まれるはずがありません。
しかし地球上から戦火はいまだに絶えません。
「二度と過ちは繰返しません」と誓った日本は、世界第二位の軍事大国に変貌。
アメリカの銃社会を持出すまでもなく、武器を持てば使ってみたくなるのが人の常。
戦争で手足をもぎとられた犠牲者や、難民の子と母の表情がテレビで放映されるたびに、病む腕をかばいながら、避難した悲しい思い出が脳裏(のうり)をよぎります。
31 異様な何かを感じたのです 君塚節子――1945/6/15大阪・池田空襲
top
|

1952年、北多摩の職業訓練所にはいる記念に、
独習でつくったスーツコートを着て
|

君塚節子 京都市上京区生まれ。
1945年6月15日の空襲(大阪・池田市の自宅)で
焼夷弾が右足を貫通し、大腿部より切断。当時18歳。
|
私が住んでいたのは大阪府池田市石橋で、隣の池田駅にある軍需工場に勤めていました。
出勤前に洗濯をしていると八時頃に警戒警報が出ました。
警戒警報から空襲になって、またたく間に頭上にB29が飛んできていました。
洗濯を途中で止め、玄関の隣にある勉強室に入って、椅子に腰かけて絵本をみていました。
母は庭の簡単な防空壕に入っていましたけど、私は母と口げんかをしたものですから。
その時、音だか何だかわからないのですが、異様な何かを感じたのです。
それで、目と鼻と耳を押さえて椅子の横に伏せました。
そこに天井を突き破って焼夷弾が落ちたのです。私の足を貫いて、床にぬけました。
私は、焼夷弾がもんぺをかすっただけだと思ったものですから、起きようとしたのですが動けないのです。
目の前は穴が開いて、モクモク煙が出てくるのです。それで腰を抜かしてしまいました。
隣の部屋にいた弟が、「何してるんだ」と手を引っ張ってくれたのですが、血が出ていて、弟がびっくりして母を呼んできたのですが、母もオロオロするばかりです。
私は引っ張り出してもらったから、気が強くなったのか、紐と棒をもらって自分で血止めしたのです。
B29が爆音をひびかせながら頭上を飛んでいる中を、母が私を背負って救急所へ行ったのです。
私は背負われながら生暖かい血がタラタラと流れていくのがわかりました。
広い通りに出たら、隣の町会の方が担架を持っていました。
そこで若者と母が私を乗せて、大阪大学病院の先生の家が、救護所になっていて、そこに連れられて行かれました。
そこで、先生に血清注射を打ってもらいました。
運がいいことに、陸軍の蛍池(ほたるがいけ)の飛行場の衛生兵の人が空襲の見回りで、救護所に寄ったのです。
それで、陸軍が使っている阪大分院が待兼山(まちかねやま)というところにあったので、そこへ行こうということで産業道路に出ました。
そこにまた都合のいいことに陸軍のトラックがきたので、それに乗ってその病院へ行きました。
病室は二人部屋で、片方には軍人さんが入っていました。
すぐに患部の手術を受けたのですが、翌日には足がきれいに白くツルツルになりました。
そして二日目にはねずみ色になって、緑色の斑点が出てきたのです。
もうこれは切らなければダメだということになりました。
瓦斯壊疽(がすえそ)という破傷風よりもっとひどい症状になっていたのです。
私はそれまでは、看護婦さんに「びっこ引かずに歩けるようになりますか」なんて聞いたり、「歩けるようになりますよ」と慰めてもらったりしていたのですが、看護婦さんは命さえ助からないと思っていたのです。
陸軍病院では手におえず、六月一八日に民間の病院へ移ったのです。
蛍池に結核の大きな病院がありました。
そこは応急の戦傷者収容所になっていて、包帯をぐるぐる巻いて目だけ開けている人など大勢いました。
この病院も一週間前に空襲を受けたのです。屋上にちゃんと赤十字の印があるのですけど。
水道は出ない、手術室だってガラスは割れています。
蝿が飛び交っているのを看護婦さんが潰したりしていました。
ひどいところで手術してもらったのです。
気がついた時は、ガリガリとハンドルを回す音がしました。
それは骨を切る音だったのです。
女医さんが「この人は心臓が丈夫だね」と言っている声が聞こえました。それでまた昏睡状態に入っていきました。
病院が高台にありました。毎朝四時頃に空襲の地響きがズズーンとするのです。
川西市の方に飛行場があり、それを目標にしたのだと思います。
毎日のようにありました。
機銃掃射があるとみんなは防空壕に隠れるのですけれど、布団を窓側に積上げて、母はベッドの下に隠れていました。
それで、終戦から三日目の一八日に、まだ完全には治っていなかったのですが、退院しました。
戦争は終ったし、家に帰ってきて安堵はじましたけれど、頭の中は真っ白でした。
二本あればバランスが取れるけれど、片足だから立つ時にも、はじめのうちはひっくり返ってしまうのです。
仕方ないからひざで歩きました。病院に入っている時に近所の方が杖をくれました。
それをつかって座敷で練習したのですが、なにしろ運動神経もよくないのでうまくいきません。
一年が経って、海軍に入って出陣しないうちに終戦を迎えた兄が帰ってきました。
戦争が始まった頃、父の生家の千葉の田舎にくるようにって、言われていたのですが、父は私が女学校三年の時に亡くなっていたのです。
私がケガをしたので千葉の家に行ったわけですが、そこには東京の被災者の方が三所帯入っていて、その方たちもやっぱり行くところがないので出られないのです。
それで私たちは本家の畳もない物置に住んでいました。
一九五二年に北多摩の職業訓練所に入りました。
半年ごとに新しい人が入ってくるのですが、私は一年いました。
所長さんが目をかけてくれて、美容院を紹介してくれました。
私にキャッシャーをやらないかということなのです。
その美容院というのがすごいところで、始終女優さんなんかがみえました。
私はまだよく歩けないし、キャッシャーなんてとんでもない、洋裁の方をやるからと断ったのですが、そのうちに「洋裁部ができた」と言うのです。
それで、それまで半年いた共同作業所を辞めて洋裁部へ入りました。
そこのデザイナーがとてもセンスのいい方で、私はその方につきましたが、美容と写真の先生の住まいの二階に洋裁の先生と私たちが住み込んで仕事をはじめたのです。
なにしろ美容の方はどんどん繁盛するのですが、洋裁の方は赤字なのです。
それで私たちが食事の用意をするのですが、多い時には一三人くらいの賄(まかな)いをしたのです。
私にとってはお風呂が大変でした。
銭湯に行くのは恥ずかしいし、お風呂をつくってくれた時は本当にうれしかったものです。
その店でいろいろあって、私は飛び出すことにしました。
友だちのつてで葛飾区柴又の小さな毛糸屋が洋裁をやっている店に入って、二畳の部屋に寝起きして働きました。
そこでもお風呂屋には行きませんでした。そのうち、四畳半一間の部屋を不動産屋にみつけてもらって、そこに入ったのです。
そこのお店の仕事もしていましたが、お客さんが直接くるようになったので看板を出しました。
初めて注文を取るようになったのです。そこには足かけ五年いました。
そうしているうちに、あのセンスのよい先生が恵比須(えびす)に家を建てたからくるように言われたのです。
私は仕事を始めたばかりで、おもしろくてしょうがないものですから返事を避けてたのですが、三度目の誘いもあって行くことにしました。
若い子を使うのは難しいものです。一人で好き勝手にやっていたものですから……。
恵比須に引っ越して一年ほどで、またそこを飛び出しました。
そして、住居を変えながらも自分の仕事も先生の仕事もやってたのですが、子宮筋腫になってしまいました。
それで日赤へ入院して、帰ってきたら、そのアパートから大家さんの都合でまた追い出されてしまいました。
アパートをみつけるにも、この体ではいろいろと条件が多く、なかなか自分に合った部屋がみつかりません。
戦傷者に都営住宅なりを優先して入れてくれれば、と切に思いました。
その頃、巷は、やれ車だ、ゴルフだと次第に景気よくなってきた頃です。
少数でしょうが戦災傷害者はただ生きることだけに精一杯きゅうきゅうとしているのにと、ぞのギャップに打ちのめされました。
その頃、弟が半分家を建てていて養生がてらくるように言われていました。
弟のところには四年いて、やっと家が建ったので、いまの住まいに移りました。
ここに移ってちょうど二〇年になります。
何度か結婚話はありましたが、結局一人できてしまいました。
古希(こき)間近な現在、自分の努力し足りなかったものの、時代も時代であり、何事にも傷害が禍(わざわ)いし悔(く)い多い人生でした。
top
****************************************
|