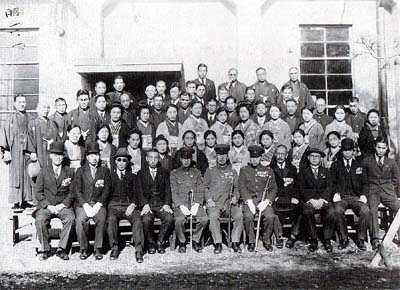|
****************************************
Index 戦災障害者の証言(その一 その二 その三)
戦災の証言(その二)
11
疎開の送別会が永久の別れに 小幡誠武――1945/3/10東京大空襲
top
|

3月10日の空襲で亡くなった家族の写真を手に(1985)
私たち家族は、瀧野川(たきのがわ)区(現北区)田端新町に住んでいましたが強制疎開にあい、一九四五(昭和二〇)年一月に、浅草区象潟(きさがた、現台東区浅草)に移りました。
私は本所区(現江東区)大平町に中島飛行機の下請け工場を持っていました。 |

小幡誠武 京橋区(現中央区)月島生まれ。
1945 (昭和20)年3月10日の空襲(浅草区の馬道のロータリー)で、
焼夷弾が目の前で炸裂し、顔一手首・足などを大火傷。
妻と子供の家族5人を一夜にして亡くす。当時33歳。
|
当時は配給ばっかりで、砂糖も日用品の石鹸にもこと欠いていた状態で、窮乏生活を強いられていましたが、軍需工場でしたから軍の援助もあって、一般の家庭に比べればかなり楽な生活でした。
それまでの空襲は大体昼間で、撃ち落とされることもなく、ゆうゆうと銀翼を光らせて飛んでいましたから、「三月一〇日の陸軍記念日には何かあるぞ」と在郷軍人の仲間内でうわさしていました。
それで、子供たちを田舎に疎開させる手はずをすませて、三月九日の晩、家族で送別会を開いたのです。お汁粉に舌鼓をうって。
十一時頃でしたか、空襲警報が鳴り出しました。
「空襲だ!」。
みんな飛び起きて、私と妻は子供たちに支度させて、外に出てみると静かです。
そのうちに空襲警報解除のサイレンが鳴ったので、また寝たのです。
そしたら今度は、警報が鳴り出す前にボンボンボンと音がするので、あれっと思って飛び起きると、もうまわりは火で真っ赤でした。
あわてて子供たちを起こし、家の裏の富士公園の防空壕に連れて行って、家の戸じまりをすませて戻ると家族がいないのです。
警防団が第一避難場所の墨田公園に連れて行ったと聞いて、それなら安心だなと思ってまた町内に戻りました。
一軒一軒、全部みてまわって、押入の中や防空壕に隠れていた女の人、四〜五人を避難させました。
町内もみてまわったし、私も墨田公園に行こうと馬道のロータリーに差しかかった時でした。
目の前にボーンと焼夷弾が落ち、一瞬、顔を棒で殴られるような痛さがあって、体が宙を飛んで地面に叩きつけられたまでは覚えています。
背中が焼けるような痛さでフッと気がつくと、手も足もコチンコチンに焼け焦(こ)げて曲げることができない、ゴロゴロ転がって体の火をもみ消しました。
顔を触ると、顔もコチンコチンでまばたきもできないのです。
それでも何とか立って、二天門の前の通りの防空壕に逃げ込みました。
防空壕には、私みたいな焼け焦げた人たちが一二〜三名いました。
みんな眠い眠いと言うので、「寝ちゃったら死んじゃうぞ。景気よく南無妙法蓮華経を怒鳴ろう!」と言って、みんなの合唱がはじまって、生きて朝を迎えられたのです。
私たちは歩いて浅草寺病院に行きましたが、ケガ人がいっぱいで医者はみてくれません。
ずいぶん長い間ほっとかれて、ようやく裸にされて薬らしきものを塗って包帯を巻かれました。
その時腹にしっかりしまっていた通帳や実印や懐中時計、鞄に入れていた重要書類などをすべて取られてしまいました。
そして「ありゃあ、もうダメだな」と医者が看護婦に話す声が聞こえました。ああそうか俺はもうダメなんだと観念しました。
家族はどうしたかなあ、死ぬ前に子供たちに会いたいなあと、冷たい地下室のコンクリートの上で、そればかり考えていました。
それからどのくらい時間がたったのか、「誠武!、小幡誠武はいませんか!」とおふくろの声がするのです。
返事をしようにも、唇も焼け落ちて声にならなくて「ウー」と唸る。
それでも返事をするものだから、母は、とうとうみつけ出してくれました。
そして、リヤカーに私を乗せて小島町の親戚の家に連れ帰りました。
そこで、医者を呼びましたが、処置できないと帰ってしまいました。
私も終(しま)いだなと思ったので、子供たちを呼んでくれと頼むと、たぶん茨城県の結城(ゆうき)の家内の実家に行ったのではないかと言うのです。
とにかく私を病院に入れなければと、私の兄の疎開先の浦和に行くことになりました。
しかし、浦和の病院も薬がないからと断られ、しかたなく私たちを管理していた軍事管理部に連絡して、交渉してもらいました。
医者は、これだけの薬を用意できるのならばやってみましょうと薬のリストを出したところ、全部ドイツの薬だったらしいのです。
やってきた将校は、牛込の陸軍病院に問い合わせてそろえさせたのです。
軍は民間には出さずに蓄えていたのです。
治療はつらかった。
毎日四〇度の熱は出るし、顔は包帯だらけで、あいているのは鼻の穴だけ、口から食物を取ることもできない状態でした。
ある日、炭化した顔の肉がポッカリ取れると、牛肉の上に目玉を乗せたようでみていられなかったそうです。
三週間目くらいで、命は大丈夫ということになりました。
この時期になっても、子供たちの安否はわからず、本当のことを教えてくれないのです。
退院してからは温泉治療を六ヵ月間ほどつづけて、もう化膿しない状態になってから東京に戻って、初めてこっそり自分の顔を鏡でみました。
これが自分の顔か……。
身近なところに鏡など置いておかなかった意味がよくわかりました。
それで子供たちのことをきつく問い詰めると、どうも子供と妻の五人とも焼死したらしいと言うではないですか。
うすうすは感づいてはいましたが、もう言葉にならなかった……。
あの時行動を一緒にしていればという後悔だけでした。
工場も焼けて、私もこのような状態だから、もう再建しませんと軍に申し立てたのですが、群馬県に工場をつくれという単の命令で、その準備の最中に終戦になりました。
買った機械を全部処分して、会社の金と合わせて従業員の退職金に当てました。
国家補償が必ずあると思っていましたから手元に残しませんでした。
私は当時の金で一九七万円ほど国に納品していましたから、当然戻ってくると信じていたのです。
ところが九月になると、軍に関係した者には、一切支払いをしてはならないというマッカーサー命令の通達が出て、私は一文なしになったのです。
温泉どころか、治療もできなくなりました。
顔がこんな状態で働くこともできないし、もうガックりきて自殺も考えました。
でも生活できませんから、一九五五年に、マスクをして山谷(さんや)でニコヨン(日雇い労働者)を始めました。
ここでも“バケモン”と呼ばれ、食事はいつも物陰でこっそりと食べていました。
でもまじめに一生懸命働き、人のめんどうをよくみました。
そのうち、“頭”(かしら)になってくれということになりました。
いまでいえば手配師です。“組”の者が入るまで九年間ここで働きました。
そして、酸素会社の寮長としてきてほしいと声がかかったのです。
これが私の社会復帰の足がかりでした。その後、家具の卸会社にも就職できました。
この頃から昔の知人に会えるようになり、その縁で鉄鋼関係の会社に部長待遇で働くことになりました。
工場を経営していたころの知識が生かされたのです。 `
この会社にいる一九六七年に、ようやく顔の整形手術ができました。
マスクをはずして退院した晞のうれしさといったらなかった。これで人並みの人間になれたという気持ちがしました。
ところがそんな時、交通事故にあって腰を悪くして、重い鋼材を持てなくなってしまい、それで陸送の業種に働く道をみつけることになったのです。
この道三〇年になります。
陸送業界で個人の一本立ちはむずかしいのですが、ずいぶん前に独立も果たしました。
二七歳のときに「マコトハガネ商会」で独立して、七〇歳を越えてまた「マコト陸送」で独立。
私の人生は波瀾万丈(はらんばんじょう)です。 (一九八四年収録)
12 神田明神前裏の蔵前通りで 柴田ロク――1945/3/10東京大空襲
top
|

外地へ送る衛生車から(1940年、陸軍衛生材料廠)
一九四二(昭和一七)年、二五歳の時に神田区末広(すえひろ)町(現千代田区外神田)に嫁いで、当時は用賀の陸軍衛生材料厰(しょう)に勤めていました。
戦争が始まってから、獣医課が立川市に独立したので、御茶ノ水から立川まで通っていたのです。
夫は兵隊で外地に行っていました。
三月一〇日の空襲の日、子供と姑は町会の指導で先に防空壕に逃げて、私と祖父と兄と妹が家を守っていましたが、危なくなって四人で逃げたのです。
神田明神の裏の蔵前通りの途中で、火の粉が飛んできて、もう逃げられなくなって、寝そべっていました。
まわりで人がゴロゴロ死んでいきました。
私は和服を六枚も着ていたのですが、全部ボロボロです。
飛んできたトタンを被っていたので髪の毛は少し燃えただけでしたが、襟首のところがひどく焼けて、ちょうど魚を焦がしたみたいになっていました。 |

柴田ロク 世田谷区生まれ。
1945 (昭和20)年3月10日の空襲(神田明神近くの蔵前通り)で
上半身を火傷。ケロイドとして残る。当時27歳。
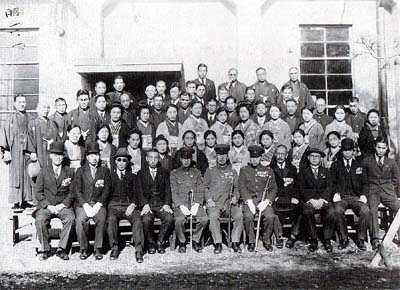
陸軍衛生材料廠の全員と記念撮影
前から3列目中央が本人(1936年1月)
|
ただ意識がはっきりしていたので、死にきれなかったのでしょう。
火災が下火になったところで、軍人さんがホースで水をかけてくれたのでホッとしました。
聖橋(ひじりばし)のところに友だちがいたので着物を一枚借りて、日大病院まで歩いて行きました。
翌日、兄が消防自動車で迎えにきてくれて、実家のそばの病院へ入院しました。
54-28
それから三日間、目がみえなくて、動くこともできずに五○日くらい入院していました。
病院には薬もなかったのですが、勤め先の衛生材料厰から、薬や包帯を持ってきてくれて助かりました。
腰のあたりがひどいケロイドが残り、五年くらいは触られると痛かったのです。
顔も焼けたのですが、何とかきれいになおりました。
退院してから兄嫁のいる福島に疎開したのですが、電灯もないし何にもないところなので、土湯(つちゆ)という温泉に療養がてら行っていたのです。
それで、お盆になるからと東京の家に帰ってきました。そして、青山の第一師団指令部に転勤になったばかりの八月、終戦を迎えました。
夫は衛生兵で満州にいたのですが、シベリアに三年間連行されていました。私は洋裁でどうにか食べていました。
子供が小学校に上がる年に夫が無事帰ってきて、半年くらいは仕事もなく遊んでいましたが、神田のラジオデパートに勤めるようになり、去年の六月まで働いていました。
13 今でも、ないはずの指が痛む 小暮タケ子――1945/4/15東京空襲
top
その頃、父と兄と私の三人で暮らしていました。
母はすでに一九三九(昭和一四)年に病死して上の兄は出征していました。
四月一五日の夜、いつものように警戒警報で目がさめたのですが、すぐに空襲になりました。
B29が、それはしつこいくらいどんどんやってきて、今日はなんて長い空襲だろうと思っていたら、誰かが「今日はちょっと危ないんじゃないか」と言うのです。
案の定、どんどん焼夷弾が落ちてきました。道路に落ちた焼夷弾は狐火(きつねび)みたいに燃えるのです。
それが家の角まで燃えてきたので、もうダメかと思ったら、急に風向きが変わって、この一角は燃えずにすみました。
私と兄は家の防空壕の入口に立っていました。
突然ものすごい音がしたのです。
あとから考えるとB29の低空飛行の音だと思います。
それで二人ともビックリして、転げ込むように防空壕に入りました。
ほとんど同時に焼夷弾が壕の入口にめり込んでバンと炸裂したのです。
気がつくと体半分が熱くて熱くて、焼けて溶けたのかと思ってみると、右手首がふっ飛んで骨が出ているのです。 |

小暮たけ子 芝区(現港区)白金台生まれ。
1945 (昭和20)年4月15日夜半から、16日にかけての空襲(目黒区祐天寺裏)で、焼夷弾の直撃を受け右手を失う。当時14歳。
|
自分でも信じられない……。これで死ぬんだと思ったとたんに、気が遠くなりました。
その時、隣のご主人が叱るように「さあ、早く出てきなさい」と手をさし出し、「もう死ぬのだからいいの」と泣き叫ぶ私を壕の中から引きずり出してくれました。
それで病院へ行くのですが、どこの病院も満員で、ようやく目黒駅の近くの個人病院に入ることができました。
電気もガスも止まっていますから、コークスの火で器具を消毒して、ロウソクの明かりのなかでの手術でした。
一ヵ月で退院して、経過も良好、通院も一ヵ月ですみました。
でも、今でも冬場は痛みます。
どこが痛いかというと、ないはずの指が痛いのです。
痒みも感じるのです。実際はないのに感覚は残っているのです。
私が通っていた女学校も焼けてしまい、心の整理もつかないうちに終戦を迎えました。
職業訓練学校や福祉施設などない時代ですので、秋になって、小学校の一部を借りて再開した学校に相談すると、「聴講生としてでもいらっしゃい」と言うので、学校に戻ることにしました。
学校に行くのがとても楽しくて、クラスメイトはみんなよくしてくれました。
若かったから左手での生活にも慣れ、無事に卒業しました。
就職は、友だちのお父さんの会社の事務、母校の事務など転職しました。
当時は、大卒でも就職難の時代でした。
障害者への思いやりなんてなかったし、給料は最低でした。
でも父と兄がいましたから、私はわりと気楽に生活できました。
一九歳の時、キリスト教の神学校に入りました。
女学校時代からバイブルクラブに入ってましたから、何となく自然にという感じです。そこを二年で卒業して、ルーテルアワーの放送の通信講座の添削の仕事についたのです。
今までの仕事のなかで一番めぐまれていました。
そこは障害者だからという差別もないし、仕事の格差もなかったし、賃金格差もありませんでした。
結婚後三年まで働いていました。
結婚は二七歳の時です。四年目に長女が生まれました。
果たして育児をやっていけるだろうか、自信はありませんでしたが、可愛さ一心で夢中で育てました。
家事から育児まで、つらい時もありましたが、左手一本で普通の主婦と変わらない仕事をこなしました。
父は一九七六年に亡くなりましたが、「いずれ国が金持ちになれば、あんたのことも補償してくれる」とよく言っていました。
上の兄が戦死して遺族年金をもらえるようになってから「今度はあんたの番だね」って。
私はそんなものをあてにしていませんでした。
ただ、軍人や軍属にはそれなりの国家補償があるのに、同じ被害を被った私たち民間人にはなぜ補償がないのかという疑問はありました。
それで一九七五年の四月に、「空襲でケガをした方はご連絡ください」と新聞に投稿したのです。
すると『毎日新聞』の記者の方が訪ねてきて「大変な問題だからぜひ取材させてほしい」ということで、五月二〇日の夕刊で取上げてくれたのです。
そしたら、今度はTBSのモーニングショーに出て話してほしいということで、もうピックリです。
新聞とテレビの効果はすぐに出ました。
反響が大きくて、仲間が次々に集まり、六月に準備会ができ、九月には「東京都戦災傷害者の会」を一〇〇人近くで発足することができました。
名古屋の戦災傷害者の会の杉山さんと連絡をとりながら、いろいろと活動しました。
政府に対しては、医療を無料で受けられるように手帳の交付と、年金の支給を要求してきました。
国会へ行ったり、大臣を訪ねたり、厚生省や東京都に足を運んだりしました。
渋谷の街頭で署名運動もやりました。もう夢中でした。
さまざまなことを経験して、私のなかで変革が起ったのです。それまでは、私たちは被害者だとばかり考えていたのですが、一方では加害者なのです。
アジアの国々に対しては……。だから“平和”というものを願っていく運動体にしていかなければならないのではないか、と思うようになりました。
今の会は正常に動けない状態になってしまいました。
高齢になって動けなくなった方もいるのですが、それよりもやはり、もう国家補償はありえない、と感じて集まらない方のほうが多いのです。
だからこれからは、後遺症を負ったもの同士が時々集まっては、なぐさめ合うようなものになるしかない、という意見もあるのです。
誰だって、悲惨な、みじめな体験は忘れてしまいたい、思い出したくないというのが本当のところです。
でも、忘れたくても忘れられないのが私たち傷害者なのです。
運動をともにしてきた人のなかには、前途に希望を持てず、自らの生命を絶ってしまった人もいます。
あの時から精神に異常をきたしたままの人や、ケロイドがガンに変質して亡くなった方もいます。
何一つ言い残すことなく、死んでいった人たちにかわって体験を語り継ぐ仕事が、私の残された人生であるように感じてなりません。 (一九八四年収録)
14 布団の中の足をそっとさわる 馬場キクエ――1945/4/15東京空襲
top
私は山形の田舎から知人の紹介で、東京の蒲田区(現大田区)へ養女にきて、養母と二人で暮らしていました。
上京してわずか一年後でした。
その日は、従兄弟の慰問(いもん)に横須賀(よこすか)に行き、戻ってきた夜でした。
何時頃か覚えていませんが、目がさめた時には、もうまわりは焼夷弾が落ちて火の海でした。
あわてて表に飛び出し、一旦は通りの防空壕へ入っだのですが、近くに牛が二頭つながれていて、火をみて暴れると危ないからと、少し離れた強制疎開跡の貯水池の傍(かたわ)らまで避難したのです。
もう大勢の人が避難していました。
その時です。とつぜん機銃掃射があって、右足に激しい痛みを感じました。
しかし、近くに時限爆弾が落ちているといううわさが流れ、そのまま養母に背負われて近くの空地まで避難しました。
そこで初めて軍医さんらしき人に傷をみてもらい、足に板をあて、血止めでしょうか小さい薬を二粒もらいました。
その時「絶対眠ってはいけないよ」と言われましたが、痛みと眠気に気が遠くなる思いで、「殺して! 殺して!」と叫んで、まわりの人を困らせたそうです。 |

馬場キクエ 山形県生まれ。
1945 (昭和20)年4月15日の空襲(現大田区七辻)で、
機銃掃射による貫通銃創を右足に負い切断。当時12歳。
|
死ぬよりつらいとは、あの時のようなことを言うのでしょうか。
夜が明けて近くのお寺に移り、さらにそこから六郷(ろくごう)小学校までリヤカーで運ばれましたが、そこでも何の治療もしてもらえず一晩明かしました。
痛みで意識朦朧(もうろう)としていた私は、枕元に置いていた炊出しのおむすびや、体にかけてあった丹前までが、いつの間にかなくなっているのも気づかなかったのです。
痛くて痛くてそれどころではなかったのです。
二日たって、ようやく「とくに傷のひどい人だけ」と、トラックに乗せられて聖路加(せいろか)病院に運ばれました。
切らずにすめばと一週間ようすをみていたのですが、その間に膝まで腐ってきて、そのいやな臭いと痛みに、毎日毎日が地獄の責めにあっているようでした。
手術の日の朝、看護婦さんに「悪いところを取るだけだから、がんばって!」と励まされて手術室に入りました。
何時間かたってふと目がさめると、今までの痛みが嘘のように楽になっていました。
自分で起きられるようになってから、布団をそうーっとめくってみましたら、膝の下がないのです。
あの時のおどろき、あの時の気持ちは、いま思い出しても、何とも言いあらわすことはできません。
二ヵ月くらいで退院できたのですが、家が焼けてしまったので、とりあえず山形の田舎に帰って、終戦になって東京に戻りました。
表に出れば「ビッコ、ビッコ」と言われ、泣き泣き家に帰ると、養母に
「そんなことで、これから先どうやって生きていくの」ときつく叱られるので、入口で涙をふいて家に入ったものです。
人に好奇な目でみられたり、言われたりされるのが嫌で、とうとう学校には行かずじまいで、養女になんかにこなければ、こんな目にち会わなかったのにと、実母をうらんでみたりもしました。
一五歳頃でしょうか、義足をつくることになり、膝の位置が中途半端なので、また手術で何センチか切断したのです。
義足で歩く練習も子供の私には大変なことでした。
一七歳になって、身体障害者職業補導所で洋服仕立てを一年間習いました。
修了後、高田馬場の洋裁店に住込みで、社会への第一歩を踏み出したとたん、私の行く末を心配していた養母が亡くなり、私はひとりっきりになりました。
まだ一九歳の時でした。わが身の不幸をなげき悲しんだものですが、人にたよることを許さなかった養母の教えを守って、歯を食いしばっての生活でした。
一九五七年、そんな私もようやく自宅で独立を果たしました。
しかし生活はそれはもう大変でした。
一九六〇年に、仕事でお世話になっていた大田区の洋服店のご主人の紹介で、結婚することができました。
七年目に長男が生まれましたが、私の体が不自由なので、果たして無事に育てることができるかどうか、心配でなりませんでした。
家の中でも抱いて歩けないので、座布団に乗せて引っ張って歩いたものです。
子供がヨチヨチと歩けるようになっても私は追いかけられないので、子供の体に紐(ひも)をつけて遊ばせたりしました。
家の中で子供をおぶっていて転び、下敷きにしてあわててやめたこともありました。
同じ年頃の子がおんぶや抱っこと甘えている時に、うちの子は許されなかったのです。
上の子が三歳くらいだったでしょうか、私のない足をふしぎそうにみて「大丈夫だよ、ぼくのをあげるから」と言うのです。
もううれしさと不憫さで涙が出てきて、思わず息子を抱きしめたことがあります。
そんな時は今までの苦労も慰められたし、これからも頑張らなくちゃと勇気づけられもしました。
一九六八年、夫が会社で大ケガをして長期入院しました。
そんな時に、妊娠しているのに気がついたのです。
精神的にも、経済的にも、苦しい試練の時でした。
それを耐えながら、翌年長女が生まれ、夫も退院できました。
長女が生まれて間もなく足の具合が悪くなり、また手術することになりました。
でも医学の進歩でしょうか、この三度目の手術で今まであったいやなシビレやウズキがなくなり、心身ともにようやく落ちつきました。
一九七七年に、前二輪後一輪の自転車があるのを知って、その自転車を買って子供たちに教わり、乗りこなせるようになってから、私はずいぶんかわりました。
買物が楽になっただけでなく、子供二人も車の前後に乗せて、今まで行くにも行けないところまで楽に行くことができるし、私の心までがパアーと明るくなりました。
いまでも自転車に乗ってると「いつも二コニコしているね」と言われます。
自分に、自信がもてるようになって、積極的に社会に出ていくようになりました。
大田区の福祉センターの関係で、一六ミリ映写機の免許を取って、子供たちの集会のお手伝いもできたし、手話の講習も受け、たくさんの人とお友だちになれて、楽しい思い出もたくさんできました。
ずいぶん苦労はじましたけど、今は幸せだと思えるのです。
足があって今の幸せがあるのかと言われてみれば、足がないから今の幸せがあるのかなという気がします。
(一九八四年収録)
15 「目があかない。見えない」と泣く 須藤杞久――1945/5/24東京空襲
top
|

自宅前で(1954年)
杞久
中延四丁目に住んでいました。 当時、父は会社を一時辞めて沖電気に徴用に行っていまして、兄は学童疎開していました。 五月二四日の夜に空襲があり、バッカーンという音とともに、一軒おいた隣の家に焼夷弾が落ちたので、どぷに沿って暗闇を逃げたのです。 |

須藤杷久 品川区中延生まれ。
1945 (昭和20)年5月24日の空襲で顔を火傷、ケロイドが残る。当時4歳。
|
母
夫は隣組だったから最後まで一人で残っていたのです。
私はこの子を背中に背負って、焼夷弾がボンボン落とされるなかを逃げたのです。
この子は防空ずきんを被っていたのですけど、それに直撃と同じような感じで落ちてきたのです。
子供は背負っているし、仏様は持っているでしょう、だから手がつけられないのです。
仕方なくどぶ川に飛び込んだんですよ。
ちょうどコンクリートの橋があったから、その下にもぐっていたのです。
杷久
夜、逃げる時に赤いのがあって、どぶに飛び込んだのしか覚えていないのです。
痛いとかそんなの覚えていませんよ。
母
でもこの子は歯軋(はぎし)りして、痛いも何も言わないの。
ただギリギリ歯軋りしてね。
明け方になって私は川から上がろうとしたんだけど、びっしょりでしょう。
子供にもいろんなもの着せてるし、背負ったその重さで上がれないの。
そうしたら町会の人がきて上げてくれて、すぐ外科に連れて行ってくれたのです。
そこに夫がきて、「こんなことじゃだめだ」って、すぐ昭和医大に連れて行って、そこに二ヵ月くらい入院しました。
病院に入ってもただギリギリ歯軋りしてね、一〇日間というもの何も食べないのです。
ただ氷水を口に充てて。そして一〇日目に「お腹がすいた」と言ってね。
隣の家の人が卵など持ってきてくれて、それを食べたら、今度は「目があかない。みえない」って言うんですよ。
びっくりしちゃってね、もし目がみえなくなったら親子で死んじゃうつもりでしたよ。
すぐ目医者にきてもらって治療してもらって。でもいいとも悪いとも言わなくて……。
病院を移されそうになったこともあったけれど、ここよりほかに行くところはありませんから置いてくださいと婦長さんにお願いしてね。
ベッドがないからと廊下に寝かされた人もいました。
なにしろ人がいっぱいで、二〜三〇センチくらいしか足の踏み場がないし、亡くなるとみんなトラックで運んで捨てるのですよ。 ガレージの中は死人の山ですもの。
杞久
左目に火の粉が入って、視力が低下してしまって。
今は両目でみるぶんにはあまり困らないけれど、右目を隠すと輪郭しかみえないんですよ。
顔のほかにも露出している部分は火傷して。
普通の火傷なら時間がたてばなおるけれど、焼夷弾は油だからケロイドが残っちゃうんですね。
顔じゃなければよかったなと思いますけれどね。
母
二〇歳の時、手術したらそれがまたダメになって。
もうノイローゼみたいになっちゃってね。
お医者さんは「男の子だからかまわないよ」って言うのです。
皮膚移植はせずに、口が曲がっていたのを治療したんでしょうね。
退院して、終戦は山梨の富士吉田で迎えたんです。
自宅は丸焼けで、病院に入っているうちにその土地も借地だったから取られちゃったの。
その後、伯父さんのつてで、今は荏原(えばら)第五中学のあるところに移りました。
畳はないけどバラックがあるからということで、一九四六年秋にそこに入れてもらったんです。六畳と三畳でね。
入る前日に夫がきれいに畳を敷いていたんですけれど、行ってみたら隙間だらけの畳になっていて。
いる人がみんな取り替えちゃうの。そこには二年以上いたかしらね、学校が建つのでそこを出て、現在のところへきたのです。
16 肉体の傷はいえても心の傷は 佐藤秀子――1945/5/24東京空襲
top
|

ドレメ本科一年(17歳)のときに、お見合いように撮影
秀子
父は一九四二(昭和一七)年に亡くなっていました。
母と弟と私の三人は目黒区下目黒に住んでいました。 |

佐藤秀子 目黒区生まれ。
1945 (昭和20)年5月24日の空襲(目黒区下目黒)で
焼夷弾の直撃を受け、顔から胸、両手両足に大火傷。
ケロイドとして残り、左手指は固まったままとなる。当時20歳。
|
当時、ドレメの師範科を卒業して、一時はドレメに残り、講師や裁縫部を手伝ったりしていましたが、戦争が逼迫(ひっぱく)してきて廃校になったのです。
遊んでますと徴用にとられますので、近くの軍需工場につとめました。
空襲がはげしかったものですから、一九四五年の五月だったと思いますが、母と弟が先に叔母の実家の新潟へ疎開しました。
私は荷物をまとめて後から送る役として残って、明日にも送れるという時だったのです。
その夜、十一時頃やすみましたところ、警戒警報からすぐ空襲警報になって、「ここにいたんでは危ないから逃げよう」と、軍需工場の上司が心配して飛んできてくれました。 そして、その方の誘導されるままに元競馬場の方に逃げました。
その途中でザーツと焼夷弾の落ちる音がしました。
警防団の方が「伏せろ!」と怒鳴ったので、上司に手を引かれていましたが、とっさに手を振切って伏せました。
ところが、焼夷弾は目の前に落ちました。
私はその焼夷弾に覆い被さる格好になったのです。
途端に焼夷弾が炸裂しまして、瞬時に炎をすい込み、気管支を焼いて声が出ません。
目は煙でやられてみえない、そして体がメラメラと燃え出しました。
もがいてももがいても火が消えない、心蔵まで燃えたら終わりだなと思いました。
まわりでは苦しんでいる声や、「お父さん死んじゃダメ」と泣き叫ぶ声は聞こえていました。
上司に火を叩き消していただいて、近くの救護所へどうにか自分で歩いて行きました。
救護所では手がつけられなくて応急処置だけです。
とにかく大きな病院に運ばなければ命が危ないと言って、タンカに乗せられて目黒駅前の水野外科病院に運ばれました。
ここもすでにケガ人がいっぱいで、外に横たわって待っている状態でした。
手がまわらないので、他の病院にまわってくれと言うのです。
それで権の助坂にある耳鼻科へ運んでもらいました。
そこへ今の夫が、どこで聞きつけたのか飛んできてくれました。
応急の注射も、針は入っても液が入っていかないのです。
そのうち吐き気がしまして、全部もどしてしまったのですが、夫はそれを手ですくってきれいにしてくれたのです。
その時、本当に申しわけなくて「バチがあたったんだ」と思いました。
夫は、私がドレメから軍隊に慰問に行った時に知り合って、兄妹のようにつき合っていた人なのです。
夫
つい三ヵ月前に、彼女の母親から結婚を断られたんだよ。
それはそれであきらめていたんだけど、こんな状態なのに本命の彼は、ただウロウロしてるだけなんだ。
そして先生に「顔は元通りになるんでしょうか」なんてバカなことを聞いているんだ。
コノヤロー、今は命が危ないのに何考えてるんだと思ったね。
先生は「後一時間です」と言うんだ。
「よし、そんなことを言うんだったら生かしてやる」と意地になったね。
ぼくは同盟通信社につとめてたから、そこの車を使って慈恵(じけい)医大に運んだのです。
ここでも待たされたんだが、通りかかった院長がぼくの腕章に気づき、「すぐ手術室に運べ」となったわけです。
手術が終った二五日の夜も空襲があって、焼夷弾が雨のごとく降って、まわりは火の海で窓から炎が入ってくるものだから、絶対安静だったんだけど、地下室に移したわけです。
その時、脈をとるとカタッ、カタッととぎれていた。
先生に「強心剤を打ってくれ」と頼んでも首を横にふるんだ。
それで胸ぐらを掴んで「打て!」と言ってね……。
彼女は体の三八%を火傷していて、体は冷たいのに「熱い熱い」と言うんだ。
隣の一般患者の氷を一かけらもらって口にふくませてね、体はぼくが肌で温めたんです。
秀子
そんなことはじめて聞くわ……。
朝になって目を開けるんですが、電球の明かりくらいしかみえないのです。
息をか細くするだけでも痛くて痛くて、こんなのだったら死んだほうがどんなに楽かと思いました。
そんな時、日頃の教育はおそろしいもので、「我慢しろ、兵隊さんのことを思え!」と、どこからか聞こえてくるのです。
夫
三〇時間くらい何も食わずに看護してたんだけど、死ぬのをみてはおれないと一旦社に帰った。
食堂で雑炊(ぞうすい)を食って、同僚らと病院へ戻ってみると、脈が正常になっていたんです。
それで電報を打って母親を呼びました。
それから、会社の食堂のオヤジに頼んで、毎日弁当運びですよ。砂糖ももらったね。
これが彼女の栄養剤だった。
医者からは左手を切断したほうがいい、と言われていたんだけど、母親は反対でね……。
秀子
私は知らなかったのです。
「親指ぐらいはもしかしたら切るかもしれないよ」と医者から言われていましたけど、母は何とか残してやりたいという気持ちがあったんでしょうね。
それで「明日切りましょう」 「もう一日待ってください」とのばしてるうちに、握ったまんま固まってしまったのです。
七月中頃、まだ退院できる時期ではなかったのですが、東京も空襲が続いていましたので、新潟医大に移りました。
終戦になってからですけど、そこで整形手術をしました。
顔は胸にくっつくようにつれていましたし、左手は棒状でしょう。
右手も直角ぐらいからのびない状態で、とにかくトイレにも困っていたのです。
それで顔を起こす手術と、右手肘をのばす手術を立て続けにやったのですが、みんな火敗でした。
そのために全身傷だらけになりました。
その傷が治るまで、松之山温泉で湯治(とうじ)しました。
夫がなかなか手に入らないサケの缶詰を持って追っかけてきてくれて、マッカーサー元師が日本に降り立った時の話をしてくれたのを覚えています。
将来の話もしましたが、こんな体で結婚なんて考えられませんので断ったのです。
そしたら「もう兄でも妹でもない、もう手紙なんか絶対書かないからな」と怒って帰ってしまったのです。
夫
これで俺の役目も終わりで、もう二度と会うこともないだろうと思ったね。
それから何度か手紙や電話でやり取りして、再び母親に会った時「今でも心はかわりありませんか」と聞かれたんだ。
そこまで言われれば、男だもの……。
秀子
晩秋に山形の温泉に移りましたが、何から何まで運ばなければならない湯治ですから、また夫に世話になったのです。
それでも、結婚なんかしても絶対うまくいかないに決まっていると、冷静に考えて断っていました。
ある日、祖母から「そんな神様みたいな人の申し出を断ってはいけない。親不孝だ」と、言われました。
ああ、これは考えなおさないといけないかなと思って、「こんな私でよかったら」とちょこっと言ったのです。
そしたら、親戚を集めてそこで仮祝言を上げてしまったのです。
東京の今の住まいに越しましたのが翌年の四月です。
当時、ここの住まいは上司の家で、若い独身の部下四人で留守番をしていました。
入稿ずみの原稿用紙をたばにしてギュッとねじって炭がわりにしてたわね。
さきに結婚した者にこの家の権利を与えるということだったらしく、私たち夫婦と母と弟、そして部下の居候との生活が始まり、二年後には長女が生まれました。
夫
ちょうどその頃だよ、ガソリンもない時代だったから、ぼくは電気自動車をつくろうと走りまわっていたんだ。
それで軍隊時代にわずらった結核が再発して、郷里の病院で手術をすることになった。
秀子
これは私が何とか頑張らなくてはと、洋裁を本格的にはじめることになるのです。
しかし、ミシンかけには自信があったのに、まっすぐ縫うこともできないのです。
こんなこともできないのかとミシンにつっぶして泣いていたの。
ふと気配を感じて後ろを向くと、母が今までみたこともないような悲しい顔をして立っていました。
それをみて、二度と泣くまいと決心したことを覚えています。
当時は、自分の衣類も縫わなければ何もない時代ですから、とにかくやりたい一心です。
電柱に同好の志を募るチラシを貼ったのが始まりですね。
それから、実益になる裁縫部をつくってほしいということで、外からの注文を受けるんですが、みんなはじめてですからヘタです。
難しいところは全部私がやらなきゃならない、それで左手のかわりに、膝を使うことをおぼえました。
やりたいという気持ちがあれば、何とか残された機能を生かして工夫できるんですね。
「あなたたち、一〇本の指を持ってるのに何してるの」と、普通では吐けない言葉も出るくらいに自信がついてきたのです。
一週間をフルに使って、昼と夜の部までつくってやりました。
しかし、こんな状態では子供たちのしつけもできないし、家庭もメチャメチャになると思いまして止める決心をしました。
その頃の夫も新しい会社で順調にいってましたから。
長女の後に九歳違いの次女も生まれまして、今は二人とも自分の好きな道へ進みました。
私はこんな体ですから、一人で生きる決心をしながらも、さいわいにも家庭を持つことができました。
しかし、つき刺さるような視線は言い切れないほどつらく、肉体の傷はいえても、心の傷は一生背負っていかなければならないのです。
以前、原爆乙女数人が植皮手術をするため、アメリカに招かれました。
原爆であろうと、焼夷弾による火傷であるうと、心の傷は同じなのに“どうして?”と、私は誰にも言えず心で泣きました。
同じ侵略をしたある国では、諸外国への謝罪、補償金などはちゃんとしていると聞いています。
私たち国民は、大なり小なりみんな被害者なのだからという曖昧(あいまい)な理由で、我慢させられているような気がします。
戦争さえ起きなかったら、こんな不幸な人生ではなかっただろうにと嘆いている人たちに、なぜ国は救いの手をさしのべないのでしょうか?
17 夢の中ではちゃんとある手 桜井 実――1945/5/24東京空襲
top
一九四五年の春、小学校六年の時に学童疎開から帰り、三月一〇日の空襲で家を焼け出されました。
父は一年ほど前に病気で亡くなり、母と二番目の姉と兄と私の四人で暮らしていました。
家が焼けてしまったので、一番上の姉の嫁ぎ先の富士市へ身を寄せましたが、私が学校へ行けないので、神田にあった東京工業学校へ入る手続きをすませて、うちの貸家があった蒲田(かまた)区(現大田区)女塚(おんなづか)へ戻ることにしました。
四月の入学式には間に合いませんでしたが、五月二二日頃に入学の準備のため、母と一番目の姉と私とで上京していて、五月二四日の切符が取れれば、荷物を取りに一度富士市へ帰ることになっていたのです。
ところが切符が取れなくて、その夜もそこに泊まることになって空襲にあったのです。
座布団を頭に被って空き地に走って向かう途中で焼夷弾の直撃を受けて、気絶してしまいました。
その後のことは痛いということ以外何も覚えてなくて、手がなくなったとわかったのは一ヵ月後でした。
大森の葛原(くずはら)病院に運ばれました。
その日に入院した三〇人のうち助かったのは二人だけということです。 |

桜井 実 荒川区西日暮里生まれ。
1945 (昭和20)年5月24日の空襲(蒲田区女塚)
で右腕に焼夷弾の直撃を受けて切断。当時12歳。
|
なにしろ薬も何もなくて、オキシドールを塗るだけでした。
五月だし、傷口が膿むのと腐るのとで大変でした。
初めは上腕まであったのですけれど、腐って、肩しか残らなかったのです。
だけどいまだに夢のなかではちゃんと手があるのです。
病院を二ヵ月で退院して、一旦焼け残った蒲田の家に戻って、それから近所の空家に住んで八月から学校に通いました。
しかし終戦になって、食物もないし、勉強するにも手がないから、製図も引けないので一年くらいでやめました。
それから日暮里の焼け跡に帰り、焼け跡の借地に杉皮でバラックを建てました。
屋根はあっても天井はないから星はみえるし、雪は布団に積もっていました。
雨が降るとボロ布を敷いたり、布団を動かしてしのいだのです。
それから亀戸の空缶工場へ勤めました。
他の人は、一日一六銭もらうのに、手のない私は七銭でした。
でも一〇〇個に二個くらい中身のある缶詰があって、食糧難の時代だから給料は安かったけど、それがあったから勤めたのです。
芋の買い出しによく行きましたが、手のない小さい子供ですから、たかがしれています。
満員でなかなか乗れない汽車も唐草模様の風呂敷をパッテンに結んで背負って、友だちにお尻を押してもらって窓から入りました。
それは手がないという以前の問題で、食わなければ生きていけない時代でしたから、人目を気にする余裕などなかったのです。
自宅の前が常磐線の線路端で、朝七時頃に進駐軍の専用列車が通るのです。
それで時々列車の窓から段ボール箱を捨てるのですが、そのなかにパンの残りとか缶詰とかタバコが入っているのです。
それが楽しみで早起きしてそこで手をふるのです。そうやって食いつないでいたのです。
一四〜五歳の時に、友人の誘いで露店(ろてん)商をはじめました。
朝の八時から夜の一二時まで勤めることになりました。
上野広小路までリヤカーで、サンズン(露店の屋根や柱)を積んで持って行って組立てて、品物を並べて売るというものです。
その露店を一八歳まで続けました。
二三歳くらいで床屋の娘と結婚して、バラックだったところに床屋を建てて独立しました。
私も床屋を手伝って、七件くらい床屋を持ったのですが、結局この店をビルにしてテナントとして貸した方がいいので、ビルのオーナーになったのです。
その後は荒川区の都会議員の見習いを三〇年くらいしました。
秘書にはなったのですが、政治家になるよりも実業家の方が身にあっていたのでしょう。
五〇歳頃に独立してクラブをやったり手広く仕事をするようになりました。
手がないのに、結婚できるかという問題、家を建てられるかという問題、勤められるかという問題、この三つがいつも頭にありました。
雇ってくださいと頼んでも、「あんたは手がない」と何度も断られ続けて、手がないんだから死んだっていいやと思っていたから、かえってやれるだけやろうと思ったのです。
18 “逃げる者は非国民である”と 三好秀子――1945/5/25東京空襲
top
|

洋裁学校に通っていた18歳の頃。
ありあわせの布で縫ったワンピース姿で
一九四五の一月に、私は軍人の三好と見合い結婚しました。 夫は甲府に勤務し、三好家の長男はすでに出征して南方におりました。 |

三好秀子 世田谷区生まれ。
1945 (昭和20)年5月25日から26日にかけての空襲
(世田谷区野沢)で身体3分の1を大火傷。
ケロイドとして残り現在も通院を続ける。当時20歳。
|
その兄は一九四一年に結婚して一週間後に招集令状がきて征(い)ってしまったそうです。
三好家は一つ家屋敷の中に長男、次男、両親の家がそれぞれありましたが、当時は物資や食料も乏しく、すべて節約をしなければ暮らせません。
兄嫁と私は、両親の家で食事や日常生活を一緒にしていました。
五月二五日の夜、また空襲が始まりました。
三軒茶屋方向の空か真っ赤です。
「今日はすごいね」と話していましたら、急にボカンボカンと、まるで花火のように、空中で焼夷弾が炸裂していました。
夜空の火は遠くのようにみえるのですが、気がつくと頭の上に雨のように降ってくるという感じでした。
家に駆け込むと屋根をつき破って落ちてきた焼夷弾があちこちでメラメラと燃えあがったのです。
もう消すどころではありません。
当時、軍管区情報がラジオから常に流れていました。
「焼夷弾が落ちたら直ちに消すこと、逃げる者は非国民である、罰せられる」などといわれ、逃げ出してはいけないという意識を植えつけられていましたから、一旦家に入ったのですが、これではダメだと気づいて飛び出しました。
生垣(いけがき)もボウボウ燃えているのです。
その中を潜りぬけるようにして逃げたのですが、防空頭巾の上に焼夷弾の油脂が、燃えながらタラタラ流れ落ちてきました。
顔にも手の甲にもです。
火のない所までもう無我夢中で逃げてきましたら、竜巻のような冷たい風が吹いて、そのとき体がヒリヒリっとしたのです。
アッ火傷したなと思い、火を消そうと地面に転がり、U字溝にはまってしまいました。
そしてそこの泥水で火を消し止めたのです。
みんな暗闇の道をぞろぞろ火の気のない方へと逃げていきます。
泣き叫び、はぐれた家族の名を呼びあいながら。
私は家族ともはぐれてしまって、助けを求めることもできません。
救護所を探したのですがみつかりません。
人にたずねてもわかりません。
やっとみつけてもどこも負傷者でいっぱいなのです。
それからフラフラになって、歩いていましたら、警防団の方がタンカに乗せて、あちこちまわってくださいました。
最後にいった所が海軍病院なのですが、やはりここもいっぱいで、タンカごと廊下に寝かされました。
その夜は喉が乾いて「水が欲しい、水が欲しい」とうわごとのように言っていました。
私の隣に、宮内庁にお勤めの方が寝かされていました。
そのうち息を引取られたのですが、そばに奥さんと三〜四歳くらいの女のお子さんがついていて「お父さま、死なないで、死なないで!」と泣き叫ぶその声が、今でも耳にこびりついています。
一週間ほどで破傷風(はしょうふう)にかかってしまいました。
体が硬直して背、手、足が反り返ってしまいます。
高熱が続いてうなされるのです。
破傷風にかかると口が開かなくなるのです。
舌をかまぬようにタオルを詰められて、おもゆなど、流しこんでもらったことをかすかに覚えています。
先生が回診の時、義母にヒソヒソとドアの外で話しているようすから、危険な状態ということは察していました。
実家の両親や兄、姉たちも呼ばれたようですが、私はぜんぜん覚えてないのです。
でも自分ではまだ死なないなという感じはありました。
六月に入るとだんだん暑くなるので、傷がジュクジュクしてきました。
自分でも鼻をつく臭さなのです。
それに網戸もないから蠅が飛んできてウジが湧き、包帯交換の看護婦さんが、「アッここにもいた、ここにもいた」と、ウジを取ってくれるようすを聞きながら、身動きできないままで、それを想像していました。
夏の間、治りかけたかと思うと、ビラン状態になるという繰返しでした。
終戦はペットの上で迎えました。まだねたきりの状態でしたから。
その日は廊下が妙にざわついていたのを記憶してます。
今まで爆撃のつらさ怖さがありましたので、これで戦争が終ったという安堵感はありました。
同時に、これだけ負傷して、これからどうして生きていけるのか、という思いがこみ上げてきて、何もいえず、じっとただ天井をみつめたままで休んでいました。
秋になって肌が乾いてきてから腿の皮膚を取って両腕に移植しました。
うまくつかなかったところは包帯交換の時、剥がれてしまうのです。
現在、白くみえるところがそうです。
まだ全治したわけではありませんが一〇月には退院させられました。
海軍病院でしたから、マッカーサの指令で軍を一掃する時期でもあったかと思います。
自宅は焼失していますから、私は夫と実家に身を寄せ、一年ほど養生をかねて住みました。
そのうち長兄の戦死の公報が入り、兄嫁は実家に戻りました。三好の家は夫だけになりましたので、両親の面倒をみることになります。
そのうちに娘がうまれました。
子育ては楽しく夢中で育てましたが、反面この体でつらいことも多く、大変でしたので、子供は一人だけにしました。
三好の両親は母六八歳、父九三歳の天寿を全うしました。もう娘は嫁いで孫もおります。夫は八年前に亡くなりました。
いま、私はボケ防止の意味で六六歳から簡単な仕事をしています。
七〇歳までは何とか頑張ろうと思います。
この先体調がよければ、無理せず何かのお役に立てるよう、生きていきたいと思っています。
19 「おばちゃん、苦しいよ」と女の子 白鳥とく――1945/5/25東京空襲
top
|

落語家月の家円鏡(現在橘家円蔵)と針娘さんたちと。
1967年、職場訪問のラジオ番組の収録のあとで
私は東京で看護婦をしていましたが、一九四三年に弟が出征し、人手不足のため一旦は千葉の田舎に帰りましたが、上京せよという看護婦会の通知で、一九四四年一〇月に東京に戻ってきました。
青山の看護婦会に下宿していましたが、看護婦会も忙しくありませんので、東京女子医専を受けてみたら受かったのです。 |

白鳥とく 千葉県香取郡多古町生まれ。
1945 (昭和20)年5月25日から26日にかけての空襲
(赤坂区青山北町)で、顔・両手・両足を火傷。
骨膜炎になり左膝下より切断。
その後局所破傷風に罹り大腿切断。当時28歳。
|
三月末頃「学校へ出てきて救護班を手伝いなさい」と通知がきました。
四月に授業がはじまった時には、学校が焼けていて、講堂で一・二年生が午前中は一緒の役業でした。
午後は毎日戦災者の包帯などの洗濯でした。
五月二四日に荏原(えばら)方面で空襲があり、義弟がいましたから、二五日にみに行き、帰ってきた時に警報が鳴り始めました。
夜の一〇時ちょっと前でした。食料等を防空壕に入れて飛び出しました。
南青山方面に焼夷弾が落らてきたと思うと、真っ暗なところにパアーッと花火みたいに開くので、きれいだなと思って見ていると、B29が低空飛行して襲ってきました。
眼鏡をかけた、真っ黒な塔乗員がみえるのです。そして機銃掃射してきました。私は倒れるように生垣にかくれました。
そのわずかの間にみんなとはぐれてしまいました。
青山通りの表参道の十字路まできて、神宮の方をみると参道の両側の家が燃えて炎が地面をなめています。
青山墓地へ行こうかとそちらをみると、道路のアスファルトが真っ青に燃えていました。 |

1942年に発行された
看護婦の証明書
|
しばらくそこに立ち往生しました。その時に、暗い方へという頭があればよかったのですが、人のいる明るい方へと行ったのです。
明るくて人がいる家に入ると、階段からみんながどんどんおりてきて、「棟(むね)、落ちちゃうよ、逃げなくちゃだめだよ」と言うのです。
ふとみると、一緒に逃げた隣の若い夫婦がうずくまっていました。
私が「逃げましょうよ、だめみたいですよ」と言っても、二人ともしゃがみ込んで動かないのです。
フッと表をみると、今そこに立っていた男の人が火の玉になって燃えあがりました。
頭の中が真っ白になりました。
外に出たらあの人のようになると思ったけれど、みんなどんどん表へ出て行くのです。
私もしかたなく、持っていた本などが入ったリュックを置いて、ドテラみたいなものを被って表に飛び出し、人の動いている向かいの家に逃げ込みました。
そこも焼け落ちるという声に、また表に飛び出すと、とたんに突風でビューッと体をもっていかれ、つかまったのが防火用水でした。青山警察の前あたりです。
なかに女の子が浸かっていました。
水があると言うので逆さまになり、乾いた防空頭巾を濡らすとあわてて体を起こし、右足を入れて濡らしましたが、女の子が「おばちゃん苦しいよ、苦しいよ」と言うので、左足を入れる気力もなく、横に倒れてしまいました。
足がボーッと熱くなって、たたいて消したのは覚えています。
だけどそのまま意識がなくなったようです。
どのくらい時間がたったのか、カタンカタンと音かし、雨の降るような音がしたような気がしました。
いま考えると青山警察が水をかけて火を消していたのです。
用水の中の女の子が「おばちゃん、出ても大丈夫?」と聞くので、「大丈夫よ、どこか人のいるところへ行きなさい」と言ったのを覚えています。
それでまた意識が薄れました。目を開けると薄明るいのです。
立上がったけれど、一歩も歩けず、また意識がなくなりました。
助けてくれたのは医専の二年生の森下さんでした。
一旦は強制疎開の跡だったと思いますが、背負われて連れて行かれました。
二度目に連れて行かれる途中、表参道の銀行の角に人がいっぱい集まっていました。
そこにトラックが三台くらい囲んで、熊手で人間を積んでいました。
それが頭に今でもこびりついています。
渋谷の日赤に連れて行かれました。もう夜でした。講堂に運ばれて、藁(わら)を敷いたベッドに寝かされました。
何日たったかわかりませんが骨膜炎(こつまくえん)になり左足膝の下から切断しました。
そしたら隣の方が破傷風(はしょうふ)になって痙攣(けいれん)を起こしました。
私は医学の知識が多少あるから「ああ、私もなるな」とその時思いました。その翌日破傷風になったのです。
その前に、三人の重症者の一本の血清を三等分して打ったらしく、その一人が私だったので、その血清のおかげか、全身破傷風ではなく局所破傷風になったわけです。
局所破傷風はとにかく痛い。あの時死んでいたらよかったと思います。
ものすごい痙攣がくるのです。
空襲警報があるたびにストレッチャーに乗せられて、地下の防空壕に運ばれるのがつらいのです。
終戦の頃は、三八度くらいの熱が上がったり下がったりしていました。
玉音放送はガーガー言っててさっぱり聞こえないのですが、でも戦争は終った、日本は負けたということはわかりました。
二、三日のうちに看護婦さんがどんどんいなくなっていくのです。
米軍が上陸してくると何かされるというので、脱走するのだと言っていました。
妹が私についてくれていて、八月一九日に、私も強引に田舎に連れて行かれました。
治療は疎開していた千葉大の医師がしてくれました。
あくる年まで田舎にいました。
そして傷がなおってから、日赤の時の主治医の先生を訪ねて仮義足をつくってもらいました。
義足の歩行をずいぶん習いましたけれど歩けないのです。
こっちの努力が足りなかったかもしれません。
そのうち、このままだと癌になるかもしれないというので、世田谷の奥沢外科で整形手術しました。
杖で歩く方が楽だから結局杖になってしまいました。
その当時は、一年後に学校に復学するつもりで月謝は払っていましたが、立ち上がった時には学校には通えないと思い、学校を断念しました。
一九五〇年に、ドレメの先生が洗足(せんぞく)に仕事場を持って教えていましたので、そこに通いました。
そこを二年で卒業して、それから和裁を習いました。
和裁は、私たちが学生時代には一通りはしないといけなかったので基礎があるわけです。
そのうえに仕立屋さんに習ったわけです。
洋裁は立ってしなければならない仮縫いがあって、これが私はダメでした。
久我山には、一九五四年に移って、「お仕立ていたします」の看板をかけたのが始まりなのです。
その頃は教え子が多い時七〜八人、少なくても三〜四人いました。
だから私がお勝手をしなくても、その針子たちがしてくれました。
六五歳頃から「やめます、やめます」と言っていましたが、ちっともやめられないのです。
これではしょうがないからと、七〇歳になった時、「あなたたちは自分で仕事を持って、だめだったらきなさい」と。
和裁の仕事が減ってきた時期でしたので、スムースに七三歳でやめられました。
結婚はしませんでした。親の言うとおり結婚していれば、戦災にあわずにすんだかもしれません。
あの時に自分の頭が正常なら、暗い方へ逃げていれば大丈夫だったかも、と今にして思えば運命の別れ道とはこうしたものかと思い、信念を持たなかったためなのだと自分をみつめています。
20 戦争は命の敵だから… 早乙女治子――1945/5/25東京空襲
top
|

左=火傷を負う前の1943年に友人と
右=母、妹、息子とともに(1960年)
三月一〇日の空襲の時は牛込区(現新宿区)払方(はらいかた)町に住んでいました。
六人兄弟の弟は海軍の航空隊に行っていて、下から二番目の妹は学童疎開で、一番下の妹がこれから学童疎開へ行くという時に焼け出されたのです。 その時は火の粉がそれほどひどくなく、火傷もしませんでした。
それで家族は御殿場(ごてんば)に疎開したのですが、私は疎開のためにやめた武田薬品に、また勧めるため東京に戻りました。 |

早乙女治子 牛込区(現新宿区)払方町生まれ。
1945 (昭和20)年5月25日の空襲(小石川区音羽通り)で
顔、両手首に火傷を負う。当時22歳。
|
矢来(やらい)町にある父の師匠の鏑木清方(つぶらぎきよかた)という日本画家が疎開して、空いている部屋を借りていました。
五月二五日に二回目の空襲にあい、被災したのです。
茨城の叔父の家へ食物をもらいに行って、帰ってきたその夜のことでした。
いつもなら夕方には東京に戻るのに、その日は土浦駅で汽車が止まって、なかなか発車しないのでへんだなと思っていたら、ノロノロ動き出して、東京に着いたのは夜の八時頃でした。
空襲はもう始まっていて、真暗な中に赤いのは火だけで、それでも国電は動いていたのでしょう、家に帰りましたから。
家に戻って、すぐに逃げればよかったのですけれど、もらってきた食料品を防空壕に入れて、隣にある別宅の留守番の人のところへ行くと、旦那さんが焼夷弾の火を消していたので逃げるのが遅れたのです。
気がついた時には火の粉がすごくなってしまっていました。
江戸川橋方面に逃げたのですが、音羽通りの両側が燃えていたので、その中を歩いただけで、私は手袋をしていなかったのと、もんぺのホックがはずれたところから火の粉が入って、火傷をしました。
焼夷弾がどんどん落ちてきていましたから、火の粉が隙間がないほど渦巻いて、熱かったということだけ覚えています。
逃げたのは音羽(おとわ)三丁目にある帝大分院(現東大)なのですが、途中でみんな火傷したのですぐに入院しました。
顔は防空頭巾を被っていたから、少し右側を火傷しだけれど、医者にチンク油という白いトロトロした薬を塗ってもらってだいぶよくなりました。
あごのあたりに残った跡も、その後の手術で目立たなくなりました。
留守番の夫婦はまだ若くて、旦那さんが生まれて間もない赤ん坊を抱いて、奥さんが三歳くらいの子供をおぶっていたのですけれど、赤ちゃんは熱気でやられたのか病院に着いて、一度大声で泣いたと思った瞬間に、もう亡くなっていたのです。
旦那さんも二〜三日後に亡くなりました。
奥さんは顔中すごい火傷をしたのです。
でもその後その家族には会っていません。
入院してから家族に連絡してもらって、父が何も言わずずっとつき添ってくれました。
母は泣いて私の顔をみようとしません。私は親不孝をしたと思いました。
水道も止まってしまって、毎朝五時になると井戸水をくむ順番を取るだけでも、大変だったようです。
食事はほとんど食べずに強心剤の注射だけだったと思います。
とにかく薬がなくて、後で医者も失敗したと言っていましたが、傷口を乾燥させるために紙を燃やしてつくった黒素を火傷に塗ったのです。
それが入墨みたいになってしまいました。
病院には一ヵ月くらいいて、完全に治ってはいませんでしたが退院して御殿場に帰り、その年いっぱい家にいました。
なにしろ腰がぬけたようになって、座ったら立ち上がれないような状態だったのです。
髪の毛もホウボウにぬけてしまいました。
それから手の甲がひきつれて手が反ってしまったので、一年後に植皮手術をしたのです。
火傷した指をのはず筋をやられしまって、もう治らないと手術前から言われていました。
一緒に入院していた人からよいと聞いて、湯河原の温泉に二〜三ヵ月くらい行っていました。
一年いればきれいに治ると言われましたけれど、湯あたりしてあまり食事もできずに痩せてきたので家に帰りました。
終戦は御殿場で迎えました。御殿場は田舎でラジオがあまり普及していなく、玉音放送があるというので、みんなどこかの家に集まって聞いたようですが、私は家で寝ていて聞きませんでした。
放送を聞いて帰ってきた母は、五月にケガして八月に終戦なんだから、もう少し東京に出て行かずにここにいたらよかったのに、と言っていました。
終戦は人伝てだったので、あまり何も感じませんでした。
ケガが治ってから、沼津の洋裁学校へ二年くらい通いました。
だけど、いまほど生地があるわけではないし、他人の気にいるようにつくるのは大変で、洋裁より事務で食べていく方が楽だったから、一九四八年に家族で東京へ出てから、しばらくして洋裁は止めてしまいました。
その頃結婚したのです。去年亡くなりましたけれど、夫はサラリーマンでした。
子供は一人います。
親離れしてくる中学生くらいの時に、私は東京銀行の株式部で、四年半くらいアルバイトをしました。
今のこんぶ問屋の事務は十一年くらい経ちます。
今年七二歳ですが、何もしないでいるとボケてしまいそうだから働いています。
top
****************************************
|