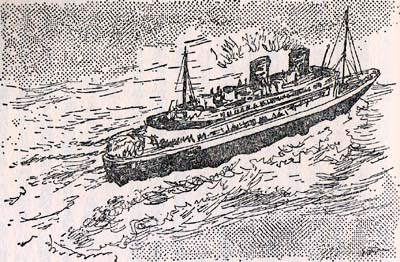|
****************************************
Home 概要 敗戦 帰国 戦後
第二部 帰国(満蒙開拓団の壊滅2)
1 満人の妻になった中島千世子――十月 方正収容所――
top
読書(よみかき)村の西尾さと、加藤きよ江は、苦難の継続としか呼びようのない収容所生活を送っていた。
満洲の秋はすでに内地の冬を思わせたが、コンクリートの部屋に火の気はなく、破れた夏服をつけた収容者は、ちぎれたゴザ、カマスなど手当たりしだいに体に巻き、身をよせ合って暖をとった。
全満いたる所に設けられた収容所は、いずれも名ばかりのものであった。
読書村はじめ樺川県の多くの開拓民が入れられた方正は、拉占(ローセン、牡丹江省)、延吉(間島省)と共に、特に惨状の甚しかった収容所の一つである。
方正県伊漢通開拓団の空屋を中心に設けられたもので、翌二十一年五月までに収容された総人員は、八千六百四十人であった。
『満洲開拓史』によれば、この人々の終末は次の通りである。
ソ連兵に拉致(らち)された者
脱走し行方不明になった者
自決または病死した者
満妻となった者
現地に残った者
ハルピンに移動した者 |
四六〇人
一二〇〇人
二三六〇人
二三〇〇人
一一二〇人
一二〇〇人 |
「ハルピンに移動した者」の大多数は、帰国者である。
西尾さとたちの周囲で、連日、人々が死んでいった。極度の粗食が続き、疫痢、発疹チフスが発生し、特に抵抗力の弱い幼児多数が倒れた。
女にはさらに耐えがたい苦痛があった。ソ連兵が公然と女を要求するのである。
若い女は肉の落ちた頬に鍋墨を塗り、髪を切って男装した。
しかしそんなことで、いつまでもだませる相手ではない。
ソ連兵は難民の部屋に踏みこみ、男装していても胸に手をさし入れて乳房をさぐった。
避難民の責任者は「今夜は何人の女を出せ」とソ連兵に命じられるたびに、苦境に立った。
日本の女性を提供するのはしのびがたいことだが、拒否すればたちまち射殺される。
しかもそれによって、女たちの貞操が救われるわけではない。
身がわりに立ってくれる水商売の女でもいればなあ――と、娘たちの悲鳴に耳を押えて、責任者はつぶやいた。
しかし、この収容所にそうした女はいない。
都会やその周辺には、水商売の女が開拓団の女の身がわりになった例がいくつかある。
嫩江(どんこう)義勇隊訓練所寮母・中込くにの日記にも、その例が記されている。
団の女性の何人かは犠牲になったが、最後まで抵抗した数人が遂にトラックに乗せられようとした時、ソ連軍司令官の許に留められていた鈴千代という女が走り出て、彼女らを助けた。
その三日後には、「女を出せ」というソ連兵の要求に困り果てた本部役員が、嫩江街(どんこうがい)の菊屋、曙という二軒の料亭の女たち二十四人に頼みこんで、娘たちの貞操を救った。
西尾さとのいる方正収容所の娘たちは、ソ連兵が来ると半狂乱で助けを求めた。
だがすがりつかれた同胞も、かばえばたちまち撃たれるので、どうすることもできない。
娘たちは、ドアに、机の脚に、椅子に、床に敷かれた泥まみれのゴザに、ありとあらゆる物にしがみついて抵抗した。
しょせんは無駄なあがきであった。
ソ連兵は泣き叫ぶ娘を軽々と抱き上げ、何かにしがみついている手をもぎとって、引揚げてゆく。
同胞たちのせめてもの心づかいは、魂もぬけた様子で帰されてくる娘たちから、目をそらすくらいのことであった。
読書村分村には、約四十人の報国農場隊員がいた。
開拓団の労働力不足をおぎなうため、毎年内地から送られてくる青年男女である。
収容所で最もソ連兵にねらわれたのは、この若い女子隊員たちであった。
ある夜、女あさりのソ連兵が踏みこんで来た時、西尾さとのそばに男装した女子隊員がいた。
顔を鍋墨と泥で汚していても、彼女の若々しい容貌はソ連兵の目を引いたらしい。
一人が彼女に近より、胸に手をかけた。
さとがはっと身を縮めるほど烈しく、女子隊員は兵の手を払いのけた。
室内は泣き叫ぶ声、救いを求める声に満ちていたが、彼女は何もいわず、再び抱きすくめようとする兵の手を払いのけて、自分から出口へ歩いていった。
抵抗がいかに無意味かを、知っている足どりであった。
さとが見上げた彼女の顔は、憤りにひきつっていた。
男の本能をむき出しにしたソ連兵への憤りであったのか。
または敗戦間近と知りながら、報国隊員を送り出した非情な祖国への憤りであったのか。
彼女たちは終戦も間近な二十年五月に、空襲下の敦賀港から船に乗せられたのである。
自分からソ連兵の許へ歩き出したこの少女は、それきり収容所に帰らなかった。
ソ連兵に暴力ではずかしめられるよりはと、多くの女が自分から満人の許へ逃れるように去っていった。
かっての支配者であった日本人の女を、満人は妻に、妾にと望んで、食料や衣類を持って収容所の周囲をうろついていた。
泰阜(やすおか)村開拓団の中島嘉代も、四人の子供と共に方正収容所にいた。十七歳の長女・千世子をソ連兵の目からかくすことに、嘉代は神経をすりへらす思いで暮らしていた。小柄で幼な顔の残る千世子は少年の姿で難をのがれていたが、嘉代の心がかりはそれだけではない。
寒さは日ましにきびしく、食糧はいよいよ乏しくなる中で、幼い子供たちの命がいつまで保てるか――。
千世子は自分からいい出して、方正郊外の農家の長男の嫁になった。
婚家の人々は千世子の家族全員を温かく迎え入れ、彼女の弟妹はまたたく間に健康をとり戻した。
一家を救おうという千世子の決意が、この結婚の動機であったろうが、彼女はしあわせな妻の座を得た。
2 死者の軍服を着こんだ健吉――十月十三日以降奉天収容所――
top
十月十三日、健吉母子のいる黒台信濃村の一団は、住みついた倉庫を追い出され、鶏寧(けいねい)駅から汽車に乗せられた。
ハルピンへ送られるのだというが、こじき同様の姿で貨車の隅にうずくまった人々は、前途に希望を託してはいない。
いいことなど、もう何一つ考えられなくなっていた。
健吉は、現地民に与えられた軍服を着ていた。
いずれ、日本兵の死体からはぎ取ったものであろうか、彼は服の出どころの詮索などはしない。
返礼にタバコのすいがら一山を届け、得意そうに着ていた。
袖口やズボンの裾をいく重にもまくり上げたダブダブの古軍服が、健吉を幼く見せていた。
途中で何度も停車させられたため、一行が林口を出たのは十六日であった。
朝から、吹雪である。貨車の小窓から見える外界は、暗い灰白色一色に塗りこめられ、それを斜めに切って、雪片が絶えず鋭い線を引いていた。
人々は膝を抱き、身をよせ合って、無感動にそれを見上げている。
間もなく牡丹江――という時、また汽車が止まった。橋が落ちたため、前進不可能だという。
三十分ほど前に出た汽車が、その橋の事故で転覆し、全員死亡したという噂が伝わった。
人々はその話をも、無感動に聞いた。自分たちは助かった――という喜びも湧かないほど、彼らは疲れていた。
幸運と呼ぶべきかどうか誰にもわからなかったが、徒歩でたどりついた牡丹江から、彼らはまた汽車に乗ることができた。 そして、ハルピンに着いた。それが十月の何日なのか、健吉は知らない。
ハルピンでは、小学校跡の難民収容所にはいった。もと教室であった四角い部屋にムシロを敷いて、溢れるほどの日本人がうごめいていた。
田畑を捨て、家・財産を失って、各地の団から命からがら逃れてきた人々である。
誰もが疲れはて、痩せさらばえ、汚れきっていた。不潔なにおいが、建物全体に満ちていた。
健吉たちは三日間ここにいただけで、新京経由、奉天送りと決まった。
早朝、出発のため中庭に集合したが、なおしばらく待だされた。
一行の中から死者が出たのを誰も気づかず、同室の難民に注意されたためである。
壁に向かって寝ていた女が、そのままの姿で息絶えていた。
細りに細った、一本の薪のような女の体が無造作にかつぎ出され、裏の空地へ運ばれてゆく。
色もなく乾いた唇から黄色い歯をのぞかせた死者の顔を見て、健吉はそれが誰であるか思い出した。
団を出て間もないころ、コーリャン畑の中で赤ン坊を生んだ女であった。
その時この女につき添っていた姑は、とっくにいなくなっていた。
生まれたての汚ない顔で健吉を失望させた赤ン坊も、もちろん消えていた。
その母親だけが出産直後の体で、その後二ヵ月余りの苛酷な生活に耐え、ハルピンまでたどりついて死んだ。
この女の名前を、誰も知らない。
停車駅で匪賊に襲われるなど、なお受難を重ねながらも、一行は奉天駅についた。
難民収容所に当てられた春日小学校へ向かう彼らの姿を、道行く人は侮蔑の目でふり返った。
こうした日本の難民を、彼らは“麻袋部隊”と呼んだ。梱包用の麻袋を身にまとっているためである。
この中で健吉だけは相変わらずダブダブの軍服をつけ、与えられた麻袋を手に持っていた。
奉天の収容所も、ハルピンのそれと大した違いはなかった。寒さは日塞しにきびしく、コンクリートの広い部屋にあるただ一個の名ばかりのストーブに、人々はゴミまでを拾い集めて燃した。
薬一つない収容所に、病人が満ちていた。深夜、人々のいびきの中で、発疹チフスの高熱にうわごとをいっていた人が、いつの間にか死んでいる。
深夜の死は、隣人にすぐ伝わる。
息絶えて、体温の消えた体を見捨てた虱(しらみ)の群が、隣人の体へ続々と移動してゆくからである。
二人分の虱を引受けた人は、当然の権利のように、死者のふとんへ手をのばす。
死さえも、ここでは悲しみで受けとられはしない。
「今夜から暖かくなるぞ」と、死者のふとんを奪った者がつぶやく。
ふとんといっても、紙のような毛布が最高級品で、多くは麻袋をつなぎ合わせたボロ布である。
健吉にはたくさんの仲間ができた。
体力のある大人は職を求めて働き、僅かながら食糧を得ていたか、少年を雇う者はない。
空腹に攻められ、彼らは働く以外の方法で食糧や薪を手に入れるようになった。
“かっぱらい”である。健吉はいつか、少年組のガキ大将になっていた。
元気のいい少年十人ばかりが一団となって、八百屋やまんとう屋の店先を襲う。
手当たり次第にさつま芋やまんとうをさらって逃げるのだが、誰かが捕まれば必ず駆け戻って救出する。
少年たちは剣道の竹刀(しない)のつばを手に入れ、そのぐるりに鋭い切りこみを入れて手のひらにかくしていた。
いざとなるとそのつばの穴に指二本を差しこんで持ち、仲間を捕えている満人の店番の顔をなぐるのである。
大きい構えの家にしのびこみ、台所で鍋の中の料理を手づかみで食うこともあった。 |

健吉母子は奉天に送られ難民生活に入る。
権吉には仲間ができ、“かっぱらい”のガキ大将となった。
|
少年たちは開拓団の学校に通っていたころ、盗みという行為を最も重い罪の一つと教えられていた。
彼らもまた、疑いもなくそう信じていたのだが、しかしそれはソ連参戦までのことである。
あの日を境にして、少年たちの生活も、ものの考え方も、根底から変わった。
今は――強い者、要領のいい者だけが生き残り、そうでないものは死ぬほかない。
教室で先生に教わった修身などを守って死んでみても“三文の値打ちもない”と、健吉には思われた。
喚声をあげて満人の店から引揚げる少年たちは、意気揚々としていた。罪の意識など、みじんもない。
健吉は盗んだ食べものの半分を、必ず母の許に持ち帰った。初めから母の分を勘定に入れて、二人分を狙った。
今は全く健吉に依存して生きているヨネは、息子がどのような手段で手に入れた食べものかを考えもせず、人影のない所へ行って、むさぼり食った。
その間も、絶えず周囲に警戒の目を向けている落ち着きのない様子は、鼠がものを食う姿に似ていた。
健吉が何も持ち帰らない日は、ひとにぎりのオカラだけが母子の命をつないだ。
誰もが飢餓(きが)にさいなまれていた。
たまに一日分以上の食糧を手に入れた者は、雑居生活の中でその保存に苦心した。
町工場で働く男が、食パンをもらって帰った。三食分くらいはある太い棒状である。
彼は考えぬいた末、それに手拭いを巻き、枕にして寝た。
翌朝、目がさめてみると、パンは彼の頭の下だけを残して、両端をむしり取られていた。
女や子供を求める満人が、収容所の周囲をうろついていた。
彼らは衣類やまんとう、魚など、難民のほしがる品を持ってきて見せびらかした。
男の子より女の子の方がほしがられ、若い女は当然いちばん誘惑が多かった。
今は健吉も、なぜ男たちが若い女を狙うのか、その理由を知っていた。
それを知らなかったばかりに、彼は仲間にあざ笑われ、ガキ大将の面目をつぶしたことがあった。
仲間は少年らしい直截なことばで、そのわけを健吉に教えた。
健吉は急に自分が大人になったように思い、鶏寧(けいねい)附近の野原でソ連兵に捉えられた女の悲鳴を思い浮かべた。
収容所の中で、抵抗力の弱い幼児の死亡率は最も高く、母親の中には「みすみす死なせるよりは」と満人に与えるものもあった。
子供を与えるからには少しでも有利にと、交換物資の交渉をする親もあった。
「満人の子になれば、たくさん食べられる」と母にいい聞かされ、痩せ細った顔に微笑を浮かべて、すすんでもらわれてゆく子供もいた。
何も収穫のなかった健吉が、日暮れの収容所に一人で帰ってきた。“かっぱらい”にも当たりはずれがある。
ふと見ると、物置のかげに一人の満人と、赤ン坊を抱いた難民の女が立っていた。
女は満人に子供を渡し、何かを手に下げてひき返した。それが繩で縛った一尾の大きな魚だと気づいて、健吉の目が輝いた。
彼はそっと女のあとをつけた。
女は人気のない裏庭へ出た。凍って、褐色の棒のようになった死体が並べられている大穴のそばである。
女は石を積み上げた一角から、薪をつかみ出した。ここが彼女のかくし場所であろう。
折りとった数本の小枝を魚につき刺し、その根元を石で囲った女は、周囲の薪に火をつけた。
やがて、ものかげから見守る健吉の鼻を、魚の焼けるにおいがくすぐり、胃袋が一時に空腹を訴えた。
魚の前にしゃがんだ女は、小枝の箸を火中の魚につき刺し、大きな肉片を口に運んだ。
小枝の箸は、魚と女の口の間を絶え間なく往復する。
噛みもせず、呑みこんでいるらしい。火が消えると、女は箸を捨て、両手で掴み上げた魚にかぶりついた。
首が右に左に、忙しく動く。ただ一度、その動きが止まった。
魚から話した口を思いきり大きく開き、片手の指で口の奥から何かをつまみ出して、捨てた。
喉にささった骨を抜いたのであろう。あとはまた、首とあごが烈しく動き、十人前はあろうと思われた魚が見る見る骨だけになった。
健吉の期待は、女が少しは肉の残った魚の残骸を捨てはしないか――というところにあったが、彼女はその骨までを音をたててしゃぶった。
収容所にひき返す女の足どりは、落ち着いていた。
飢餓に母性愛をも滅ぼされた女は、魚がわが子の代償であることなど思わず、何ヵ月ぶりかの満腹感だけを味わっていたらしい。
3 ひとり越冬する九歳の文子――十一月以降――
top
十一月になり、濃河鎮の倉庫で暮らす文子たち張家屯(ちょうかとん)の一団は、めっきり人数が減った。
多くの人が死んだだけでなく、警備隊からのすすめで何家族かが満人にひきとられていった。
あとに残ったのは、ほとんどが病弱者である。
文子の母タキは、極度に悪化した食糧事情の中でよく彼らの世話をした。
十一月十五日の早朝、タキが共同炊事から帰ると、いつもなら起きているはずの正男が、まだふとんをかぶっていた。
正男――タキが声をかけても、身動きもしない。この二、三日、疲れた様子だった。
たまには寝坊させてやろう、と枕元を通りすぎた瞬間、タキの心に不吉な影が走った。
ふとんをはねのけ、息子の体に手をかけてゆすぶったが――何の反応もない。正男は死んでいた。
「かわってやれるものなら」と、祖母は正体もなく泣いた。
文子が母の涙を見たのも、この時が初めてであった。
祖母の涙も枯れたかと思われた五日目、三歳の光男が兄のあとを追うよりに死んだ。
祖母はもう泣く力もなく、小さな遺体を抱いたタキと並んで、白髪を冬の風にさらしながら町はずれの湿地へ歩いた。
凍った土に墓穴を掘ることもできず、草原に寝かされた遺体は、祖母と母の手でかけられる枯草に埋まっていった。
満人が死体の着物をはぐと聞いた祖母は、何とかそれを防ごうと、地面に倒れ伏した枯草の葉を、いつまでもむしり続けた。
五日前、正男の遺体もまた、こうして葬られたのである。
文子と祖母と母の三人は、安藤、吉江の二家族と共に、木蘭(もくらん)の李という大百姓の家にひきとられた。
正男に死なれてからのタキは急に元気を失い、人のことば通りに動く気弱さを見せ始めた。
李の家に着くと、タキの懇願にもかかわらず、祖母は別棟に連れ去られた。
吉江一家も、子供の夜尿症をきらわれて、オンドルの部屋には入れてもらえなかった。
李の家の近くに、同じ長野県出身の富士見分村の人々が分散していることがわかったが、タキはだるそうな様子で、その話を聞き流していた。
文子はこんなに無気力な母の様子を初めて見て、子供心に不安を感じた。
翌日からタキは高熱を発して、寝ついた。
文子は、母の歯や唇が薄墨をなめたように黒ずんだのを見て、身ぶるいした。
今までに彼女は、熱病患者がこうした症状を呈して死んでゆくのを、何度も見ていた。
祖母はどこにいるのか会わせてもらえず、安藤、吉江の二家族は他の家に移されていた。
母の看病をしながら、文子は心細さに泣いた。
二日目から、タキはよくうわごとをいった。
文子に「正男、正男」と呼びかけたり、「父ちゃんが出かけるよ、奉公袋を……」と、身をもがいたりした。
正気の時のタキは、今までになく文子に向かって、夫の話をした。
父ちゃんは必ず無事に帰ってくる。三度も応召して、そのたびに無傷で帰ってきた運の強い人だから――。
三日目の夜から、タキの容体は悪化した。
昼は田畑で働き、夜は警備に立ち、赤ン坊を背負って山野を逃げ歩き、飲まず食わずで乳を与え、隣人の世話を続け、三人の男の子を次々に失いながら、最後に残った姑と文子を守ろうと努力を続けてきたタキだった。
気力一つで自分をひきずってきたのだが、体力の限界はとうに越えていた。
母の溲(し)びんの始末をするため、裏庭の外へ出た文子は、かすかに名前を呼ばれてたち止まった祖母の声である。
薄暗い納屋のむしろの間に半身を起こしている祖母は、たった四日の間に、見違えるほど小さくなっていた。
文子、今、ばば(婆)がいうことを、よくおぼえていておくれ――祖母の声はかすれて聞きとりにくかったが、文子は大きくうなずいた。
――どんなつらい目にあっても、無事に日本へ帰ってくれ。戦争に行った父のことは、もうあきらめている。男の子三人は死んだ。文子は女の子だが、お前しかこの家の血をひいている者はない。一家が満洲に渡ったために、血筋を絶やしてはご先祖様に中しわけない。何事も耐え忍んで、日本へ帰ってくれ――。 |
「ばばが頼む」と繰り返した後、祖母はふるえる手をふって、追いたてるように文子を母の許へ帰した。
祖母の唇もまた、薄墨色に変わっていた。
暮れもおしつまった十二月三十日の夕方、李の娘が文子に祖母の死を伝えた。
ほとんど意識もない状態のタキであったが、姑の死だけははっきりとわかった。
こわいほど落ちくぼんだ目を閉じたまま「困ったなあ」とかすかにいい、しばらくして「父ちゃんに申しわけない」ということばを、黒い歯の間から押し出した。
その語尾は喉にからむタンの音に消され、彼女はそのまま昏睡状態に落ちていった。
タキは姑の死亡の翌日、大晦日に息をひきとった。
タキの死を知ると、李とその妻は、朽ち木を扱うような無造作な態度で遺体に手をかけた。
すがりついた文子はつきとばされ、母は運び出された。
翌朝、李の妻は平然とタキの衣服を着て現われた。
文子は怒りに胸を熱くしたが、何をいうこともできず、怒りは憎しみとなって燃え残った。
文子は何度か、母のあとを追って死にたいと思った。
彼女がそれを実行に移さなかったのは、祖母の「ぜひとも日本へ帰ってくれ」という遺言にひきとめられたためである。
「前田の血筋をひく最後の者」といわれたことには何の実感も伴わないが、祖母との約束は果たさなければならない重みを文子の胸に残していた。
李は文子を養女にするつもりで、機嫌をとったり、おどしたりして、手なずけようとした。
何をいわれても、文子は固い表情を崩さず、日本に帰ることだけを思って暮らした。
「日本はアメリカに殺人爆弾を落とされて、人間は全部死んでしまった。草や木もなくなった」
という李のことばにも、彼女は表情を動かさなかった。文子は“強情な子”“かわいげのない子”といわれた。
春になった。文子が李の娘に連れられて摘み草に行った帰り、はかなげな雪割草が一面に咲く湿地を通った。
李の娘は湿地の一角を指して、ここに文子の祖母と母が埋められた、と告げた。
文子は満服の裾をひるがえしてその場所に駆けより、土に頬を押し当てて泣いた。
李の娘がどううながしても、彼女は動かなかった。
文子は土の下の祖母と母に、どんな辛抱でもして、必ず日本へ帰ります――と、くり返して誓った。
数日後、文子は李一家のすきをねらって、近くにいる富士見分村の人々との連絡に成功した。
帰国の時は、必ず自分も連れて行ってくれ――と、彼女は大人のようなしっかりしたことばで頼みこんだ。
石砠子(せきそし)鉱山で暮らす駅馬(えきば)開拓団の人々は、帰国の見通しもつかないままに、本格的な冬を迎えた。
衰えきった人々は、寒さに抵抗できず次々に死んでゆく。
鉱山の北方にある、もとダイナマイト置場であった丘が、墓地と定められた。
毎日のように、雪を盛り上げた新しい墓ができてゆく。
ワラを買う金もなく、よもぎの茎で編んだ苞(つと)に死体を包み、凍りきって穴も掘れない丘に横たえて、雪をかけるだけである。
どんなに厚く雪をかけても、翌日行ってみれば、死体は野犬の餌食になっていた。
飢えた野犬の群を追い払い、ひきちぎられた手足を拾い集めて、数日後には自分もこの姿になるのか――と、シャベルで雪をかける人々は、もう将来に希望をつなぐ力も失せかけていた。
やがて春になったか、団員たちの顔には、生きる限度の来たことが現われ始めた。
あせりが虚脱感に変わって、一日中放心している人もあった。
こうした人々に囲まれて、清水圭太郎団長は三反歩の菜園に、きゅうり、すいか、いんげん、ごぼうなどの種子を蒔(ま)こうとしている。
団長、こんなものを蒔いてどうするんだ。おれたちは、いつ日本に帰れるんだ――と、くってかかる者もいた。
このきゅうりを食わないで、帰れるかもしれん。
しかし、ごぽうを食いきっても、まだ帰れないかも知れん。あせっては負けだ。
落ち着いて、だが明日にも引揚げられる心構えを持ってくれ――。
団長の声は静かだった。
4 俘虜(ふりょ)収容所の加藤松三――二十年・二十一年冬――
top
シベリヤの、雪に閉ざされた俘虜収容所の廊下を、加藤松三は足をひきずるようにノロノロと歩いてゆく。
極度の粗食と過労が、彼の容貌からたくましさを消していた。
灰色の壁にかけられた額の中から、スターリンが微笑を浮かべて見下ろしている。
その下を松三は、僅かに残った体力が外にこぼれるのを恐れるように、ゆっくりと炊事場へ歩いてゆく。
ここでは日本の軍制がそのまま踏襲されていた。
ソ連軍は若い日本の将校を責任者にして、労働力を徹底的に搾取した。
俘虜たちの年齢も、体の強弱もいっさい問題にされず、栄養失調、心臓衰弱、脚気などは病気とみなされない。
三十八度以上の発熱だけが、医療室で休息できる唯一の理由となる。
俘虜は次々に倒れた。
死者は仲間の手で倉庫に運ばれ、積み上げられる。黙祷(もくとう)を捧げる者さえない。
そのような感情は、シベリヤの寒気の中で凍りついていた。
時たまトラックが倉庫の前に止まり、積み上げられた死体を運び去る。どこへ運ばれてゆくのか、誰も知らない。
満洲から汽車で運ばれてきた松三は、名も知れない二つの収容所を経て、ここに来た。
三つの収容所は、施設も、それをとりまく風物も、それぞれ異なっていたが、粗食であることと、スターリンの肖像がかけられていることだけは、どこも同じだった。
苛酷な収容所の生活を、はるか遠くで支配しているのはスターリンの微笑だと、俘虜たちは思い知らされた。
そこから、あきらめが湧いた。
松三は、初めて荒涼としたシベリヤの原野を目にした時、骨も凍る絶望感を味わった。
おれはなぜ妻子とひき離され、こんな所で働かされるのか――憤りが胸に満ちた。
たった三日、日本の軍隊の飯を食ったというだけで、なぜこれほどの罰を受けなければならないのか。
部隊にいたその三日間、軍規の乱れた中で、松三は上官から命令らしい命令を受けたこともなかった。
だか戦争が終わり、俘虜となってから、ソ連の意志で収容所内部だけに復活した日本の軍制下に、彼は“上官”の命令によって牛馬のように働かされた。
労働のノルマを上げる義務を負わされた旧日本軍の将校は、“部下”の命などかばってはいられない。
配給になる食糧さえ、“一等兵”に与えられる量は少なかった。
体力が衰えるにつれ、松三の憤りも力を失っていった。
彼は心のうちで「なぜ」と問いかけることもせず、炊事場に落ちている馬鈴薯の皮をしゃぶり、パンの盗み食いをして“上官”になぐり倒された。
脱走を計った者は例外なく捕えられ、営倉がわりの地下の野菜貯蔵所に入れられた。
数日後に生きて出てきた者も凍傷にやられ、多くは病院送りとなって手足を切断された。
松三も初めは脱走を考えたが、不可能と知ってからは、ただ体をかばうことだけを思った。
細々と燃える命の火を、両手でかこうような生き方である。
にぶい動きしか示さない松三の肉体の中にただ一ヵ所、生き生きとした部分が残っていた。
清乃の住む場所である。清乃――と、松三は一日に何度か妻に呼びかける。
そのたびに、生きぬこことする意欲は、新しく燃えた。死んではならないのである。
どのようなことにも耐えて生きぬき、清乃の許に帰らなければならない――。
5 ようやく祖国ヘ――二十一年五月以降――
top
五月十六日、奉天収容所を出た健吉母子は、他の多くの難民と共にコロ島(注)に着いた。(注=中国の渤海湾にある港町、戦後の日本人引揚げ者の乗船基地となった。)
日本を目指して、ここから乗船するのである。
相変わらず古い軍服を着た健吉は、検疫官に頭からDDTをふりかけられて、はしやいだ。
健吉は日本についてほとんど何の記憶もないのだが、大きな船で海を渡ることが、大冒険のように彼を喜ばせていた。また母親はじめ周囲の大人たちの爆発的な喜びが、少年の心をたかぶらせた。
団を出てから九ヵ月余り、健吉は十四歳になっていた。
貨物船は、収容所がそのまま引越してきたように、難民で埋まった。船員が日本人であることまでが人々に安堵を与え、話題になった。
健吉は母の膝に頭をのせ、船員に借りたナイフで歯をけずってもらった。 |
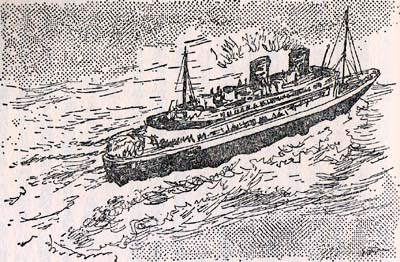
コロ島から博多へ向かう引揚げ船
|
団を出てから一度も磨いたことのない歯は、黄色い石のようなものがこびりついていた。
船に乗って以来、母のヨネは急に元気をとり戻し、健吉に向かって久しぶりに母親らしい口をきくようになった。
五月三十一日、博多に上陸。健吉母子は汽車で故郷・長野に向かった。
駅馬開拓団の清水圭太郎団長は、人々の動揺を恐れて口には出さなかったが、常に祖国帰還を計っていた。
周囲の事情を見定めて、彼が磐石県日本人居留民会をつくったのは、春の終わりころである。
牛心頂子(ニュウシンテンズ)にいる約百人の煙筒山開拓団の残留者とも連絡をとった。
その煙筒山開拓団の代表者・加部己佐雄が頭にほうたいを巻いた姿で、突然、清水団長をたずねてきた。
附近の暴民に襲われて、この始末だ。
一日も早く、どこか日本人の集まっている都会への引揚げを決行してもらいたい。
いつまでもここにいては、我々だけ満洲にとり残される危険もある――という。
清水団長も、団員の中沢孝平などから、吉林で日本人の内地送還が具体化しつつあるという情報を得ていた。
二人は吉林へ引揚げる決意をした。
思いきって腰を上げなければ、一生日本へ帰れなくなる――と語り合うにつけ、気にかかるのは石租子の東南方六十キロの黒石鎮(こくせきちん)に残っていると聞く、第九次報馬(ほうま)開拓団(群馬県群馬郡相馬村分村)の人々である。
同じ開拓民同士だ、彼らも誘わなければ――しかし黒石鎮への連絡は、なみ大ていのことではない。
匪賊の出没する地域であるばかりでなく、数日前から八路軍(毛沢東軍)のゲリラ隊と中央軍(蒋介石軍)とが激戦を続けていると噂されている。
決死の連絡行には反対もあったが、清水団長を中心に、今井指導員と県公署の地政課に勤務していた青木宗十郎とが行くことになった。
ようやくの思いで危険区域を突破し、たどりついた報馬開拓団で、三人が驚いたのは、帰国の相談に対する人々の反応のなさであった。
彼らは希望を捨ててからすでに長いためか、帰国の可能性を信じなかった。
人々の表情は、自分たちとは結びつかない遠い国の話を聞くように、ぼんやりとしていた。
しかし、翌日から次第に彼らの心に希望がよみがえり、清水団長らが帰る日には、遂に報馬開拓団も居留民会に加わり、引揚げと決まった。
駅馬、煙筒山、報馬などの団を合わせて磐石(ばんせき)を脱出する下工作は、こうして進められていった。
しかしこれだけの大人数の汽車賃など、とうてい払えるはずはない。
無賃の引揚列車を、都合してもらわなければならない。
また重病人の輸送は別に考えなければ、すし詰めの引揚列車に乗せることは、殺すようなものである。
一同の相談の結果、あり金のすべてをはたいて、重病人とそのつき添いの旅費に当て、先発させることになった。
七月十五日、清水団長は無賃輸送の交渉のため、吉林を目指して再び危険な旅に出た。
吉林市には多数の日本人難民が集まり、もとの吉林神社を事務所にして、日僑俘連絡所が日本人の本国送還事務に当たっていた。
ここの幹部として働いていた満拓の末次地方事務所長が、思いがけない清水団長の来訪を喜び迎えてくれた。
今ごろ、それほど多くの日本人が、磐石にいるとは知らなかった。
中央軍の王副官に頼んで、至急、無賃救出列車を出してもらうよう交渉する――と末次はいった。
五日目に「承諾」の返事が来た。
清水団長は体の力が一時にぬけてゆく思いに、しばらく立ち上がることもできなかった。
彼はそのまま吉林に留まって、団員やその家族の到着を待つことにした。
中央軍から石砠子の人々へ、列車手配が通知された。
敗戦以来十一ヵ月、喜びを味わったことのない駅馬開拓団の人々は、この通知に接して、とまどいさえ感じた。
本当に日本へ帰れるというのか――。だが、ぼんやりしてはいられない。出発までに二日しかなかった。
団長のるすをあずかる石井副団長の命令で、まず小屋の掃除が始められた。
満鮮人に笑われない立ちのきを――と、塹壕のように長く掘られた野天の便所も埋められた。
七月二十八日早朝。鉱山事務所前の広場に、今日の出発に緊張した五百人の痩せ衰えた顔が並んだ。
出発といっても、着がえ一枚あるわけではない。
いつもの通りのボロ服に野菜袋のリュックサックを背負ったこの集団は、こじき部隊の大移動としか見えない。
妻を失ったばかりの分隊長は、痩せこけた赤ン坊を背中にくくりつけて、人員点呼を続けている。
人々は丘の墓地に葬られた五十余人の冥福を祈った後、静かに歩き出した。
駅馬開拓団のうしろに、煙筒山開拓団の百人が続く。報馬開拓団の人々とは、磐石で合流するはずである。
この一行を、かげながら見送る三人の日本の女がいた。いずれも満人の妻妾になった、子持ちの女である。
清水団長は吉林へたつ前夜まで、彼女たちに強く帰国をすすめたが、今さら、どの面さげて、と満洲に残る決意を変えなかった。
子供たちに腹いっぱい食べさせたい――と満人の許へ行った彼女たちは、応召した夫の生死を知るすべもない。
翌二十九日朝、汽車は予定通り磐石駅に着いた。
救出列車の通知を受けた後に、気のゆるみからか急に発病した真下幸三郎はこの日、石租子から大車で運ばれてきたが、駅に着く直前に息絶えた。
三開拓団に双河鎮(そうがちん)開拓団が加わり、九百四十人の喜びを乗せて、列車は吉林に向かった。
しかし彼らの受難の日々はまだ終わらなかった。
吉林滞在中、双河鎮開拓団の一人が真性コレラと診断され、強制隔離が行なわれたが、次々と感染者が出た。
八月八日、吉林出発の日には、駅馬開拓団の星野かねも発病し、間もなくこの地で死んだ。
薬もない難民は、発病すれば死を待つばかりである。
一人でも犠牲者を少なくするため、清水団長は強引に吉林を出発した。
車中でもコレラ患者の数は増し、死者を乗せた無蓋車は、洪水のためレールも見えない海のような大平原を走った。
八月十日、錦州に着き、ここで十八日間の俘虜生活を送った。この間にも、コレラで十数人が死んだ。
八月二十八日、乗船を許されない病人に心を残しながら、一同はコロ島から日本へ向かった。
九月五日、博多着。この日、祖国を目の前に見ながら長田時太郎が死んだ。栄養失調であった。
祖国の第一夜、宿舎の食卓に赤飯と日本酒一本がつけられた。生きて帰ってきた――信じられない喜びであり、その底から、満洲で死んだ仲間の顔が浮かび上がった。
食事の終わるころ、清水団長が立って団の解散を宣言した。
「たくさんの人を死なせて、すまなかった」
団長は顔も覆わず泣いた。
6 故郷の土を踏む女たち――ニ十一年九月以降――
top
西尾さと、加藤きよ江のいる方正収容所にも、春以来何度も“帰国”の噂が流れた。
そのたびに痩せ衰えた人々の頬にわずかの生色がよみがえり、その色を消す失望が繰り返された。
二十一年九月、今度こそ間違いのない帰国命令が出た。
もう見ることもないと半ばあきらめていた故郷の山河の姿が、急にはっきりと心に浮かんでくる。
さとときよ江は手をとって、遂に帰国列車に乗る日まで生きぬいたことを喜び合った。
一年間を、人間の耐え得る限度をはるかに越した生活を共にしてきた二人は、喜びも悲しみも二人のものとして分け合う習慣を身につけていた。
帰国命令を聞いて以来、泰阜(やすおか)村開拓団の熊谷さつえは早朝から収容所をぬけ出し、夜になって失望を顔に刻んで帰ってきた。
さつえは十二歳を頭に、六人の子供を連れて方正収容所にはいった。食べ盛りの子供たちばかりである。
三日、四日と絶食同様の日が続き、彼女は子供の衰弱を見るにしのびず、四人をそれぞれ満人にあずけた。
さつえ自身も放心状態であったため、子供をあずけた相手がどこの誰であったか、よくわからない。
また満人の方は“あずかった”のではなく、もらい子をしたつもりであったろう。
帰国と聞いて、さつえは足を棒にして心あたりをたずね歩いたが、四人のうち一人だけしか見つからなかった。
彼女は満洲に残って子供たちを捜そうと、この時の帰国をあきらめた。
方正収容所の人々が乗った船の甲板に、唇を固く結んだ一人の満服の少女が立ち、遠ざかる陸地に強い視線を向けていた。
張家屯信濃村開拓団の十歳の前田文子である。
満洲で死んだ祖母、母、兄、弟二人に、彼女は無言の別れを告げていた。
日本という国がどのような所か、文子は知らない。
応召したままの父の生死もわからず、その故郷で誰が彼女を迎えてくれるかも知らない。
しかし文子は、死のまぎわの祖母との約束を守り、李一家の執拗なひき止めの手を払いのけて、ただ一人引揚船に乗った。
二十一年十月十三日、長野県更埴(こうしょく)市に住む山口道子は、終戦以来その安否を気づかい続けていた姉・塚田浅江の帰国の報に、狂喜して篠ノ井(しののい)駅へ向かった。
昭和十六年に、東安省宝清県尖山の更級(さらしな)開拓団の小学校教師として渡満した姉である。
更級開拓団は二十年八月二十五日、避難行の途中立ち寄った佐渡開拓団跡でソ連軍に襲われ、小学五年生までか決死隊に加わって玉砕した。
塚田浅江は小学生と一緒に突撃したが途中で倒れ、子供たちが走るうしろ姿を見ながら服毒した。
手榴弾の破片を浴び気を失ったが、青酸カリが湿気のためきかず、生きかえった。
篠ノ井駅に着いた道子は、引揚げの一団がすでに駅前旅館にはいったと教えられた。
姉・浅江は歩く力もなく、人々に両側から支えられて、旅館の一室に寝かされたと聞き、その部屋の襖をあけた道子は、声を呑んで立ちすくんだ。
掛ぶとんには、人間の体を覆っているらしい厚みというものがない。
その平らなふとんの衿(えり)からのぞいているのが、姉の顔なのだろうか――。
栄養失調特有のあお黄色い皮膚がブヨブヨとむくみ、その全面にインクを吹きつけたような青い無数の傷あとがある。
しかも片目は無残につぶれ、眼窩(がんか)の形もあらわに落ちくぼんでいた。
枯れ枝のような手がさし伸ばされて、道子は名を呼ばれた。五年ぶりに聞く姉の声であった。
浅江が連れ帰った三人の孤児たちの姿も、道子に改めて開拓民の受難のすさまじさを見せつけた。
痩せさらばえた十歳前後の子供たちは、頬に刻まれた深いしわで老人のような表情を示した。
短く刈りこまれたまばらな髪は、赤茶けてかげろうのように頼りなく、頭皮がすけて見えた。
極度の栄養失調に、髪の毛は生え揃う力を失っていた。
塚田浅江は故郷の小学校で再び教壇に立つまで、半年の入院生活を送った。
顔のはれはひいたが、手榴弾の破片で受けた無数の青い傷あとは、いれずみのようにいつまでも残った。
佐渡開拓団跡でほとんど全員が自決した万金山高社郷(こうしゃごう)開拓団の生き残りの一人――二人の子供が団員の手で射殺され、自分の番と思った刹那にソ連軍の砲撃を受けて逃げ出した高山すみ子は、ハルピン収容所で越冬した。
四千五百人の収容者中、二十一年八月十五日に、帰国命令でここを出発したのは千五百人であった。
十月二十七日、引揚者を満載した船は佐世保に入港した。
すみ子は古い軍服に、十文と十一文のびっこの軍靴という姿だった。
佐世保の街には、アメリカ兵の腕にぶらさがって歩く、ケバケバしい服装の女たちがいた。
こうした女たちの姿を目にして、すみ子は腹の底から湧き上がる怒りに、身をふるわせて泣いた。
自決場でおとなしく死んでいったわが子が、あわれでならなかった。
すみ子自身の記憶によれば、この時が、子供たちのために涙を流した最初である。
佐渡開拓団跡の自決場から夢中で逃げ出して以来、彼女の感情の流れは停止していたのかと想像される。
わが子を射殺してくれと頼み、その死を目前にした母は、あまりに激しい衝撃に悲哀さえ感じ得ない精神状態で、その後の収容所生活を過ごしたのであろう。
top
**************************************** |