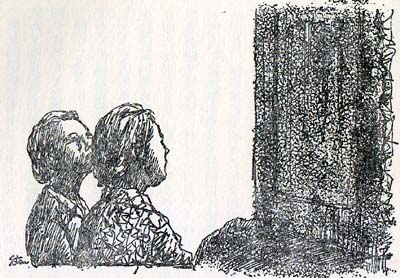|
****************************************
Home 概要 敗戦 帰国 戦後
第三部 戦 後(満蒙開拓団の壊滅3)
1 加藤松三、シベリヤから帰る――二十三年十一月六日―― top
昭和二十三年十一月六日、シベリヤから送還された加藤松三は、痩せさらばえて上陸した舞鶴から、長野へ向かう汽車に乗った。
舞鶴で松三は故郷の兄に帰国を打電した。
松三は妻の清乃あてに電報を打ちたかったが、清乃や子供たちや母が無事に帰国しているという保証はない。
シベリヤの収容所にも敗戦直後の満洲開拓民の受難の噂は伝わっていた。
シベリヤの収容所を転々とした三年間、松三は故郷との文通を断たれていた。
舞鶴から打電した兄も、はたして健在であるかどうかはわからない。
しかし、多少なりとも確実性のある宛名は兄のほかなかった。
松三は兄からの返電を待つ間もなく、汽車に乗せられた。
窓外に流れる十二年ぶりの母国の風景も、まだ懷しさを感じるほどに彼に近づいてはこない。
長野が近づくにつれ、彼は次第に濃くなる不安に胸をしめつけられていた。
清乃が生きて帰っていると期待はできない――と、松三の理性は知っていた。
シベリヤで、帰国できるとわかってからも、松三は改めて家族の死に対する覚悟を確かめて船に乗ったつもりだった。
覚悟はできているはずだったが、長野が近づくにつれ、松三の胸に浮かぶ清乃の顔は次第に鮮明になっていった。
あれから三年、子供たちは見違えるほど大きくなっているのだろうか――。
長野駅のプラットホームに降り立った松三に、兄の竹二が駆けよった。むずと手を握って、兄は声もない。
病身の老人のように変貌した弟を目のあたりにして、竹二は喉をふさがれたのである。
そのうしろに立つ兄嫁は、ハンケチで顔を覆っていた。
松三は落ちくぼんだ目を左右に走らせ、兄の肩越しに一つの顔を捜し求める。
だが視線は受けとめられることなく宙に迷い、次第に不安の色を濃くして兄の顔に止まった。
「松三……」竹二は弟の名を呼んで、絶句した。
清乃や子供たちの死を、何といって伝えたらよいのか――。
竹二はことばを失って、かすかに首を横に振った。彼の目から涙がしたたり落ちた。
松三はどのようにして支線に乗りかえ、兄の家に伴われ、寝かされたのか、のちに何の記憶も残していない。
彼にとって、一切が消えていた。横たえた体が絶えず地底にのめりこんでゆくような絶望感の中で、松三は目を閉じたまま動かなかった。
何日かが過ぎ、何十日かが過ぎ、半年余りを彼は病床で過ごした。
兄嫁のすすめるままにかゆをすすり、薬を飲み、ただ人の意思のままに最小限に体を動かす虚脱の状態が続いた。兄とさえほとんど口をきかず、仰向けに寝たまま、いつまでも乾いた目を天井に向けていた。
兄夫婦はひそかに、松三がこのまま廃人になるのかと語り合って、吐息をもらした。
二十四年の夏が近づくころ、松三はようやく裏の背戸(せと=裏口)に出て、放し飼いの鶏を眺めるまでに回復した。
艶を失った皮膚を内部から突き上げるように見えていた骨も、さほど目立たなくなっていた。だが上背もあり、元来たくましい骨格であるために、かえって、にぶい動作が痛ましかった。
松三はカンナの黄色い花を見つめて、今は遠い昔のように感じられる収容所の日々を思い返した。
寒気と飢餓にさいなまれ、常に死が肌にすりよって来るような生活であったが、しかし当時の松三には生きがいがあった。
彼は灼けつくように故郷を思った。放郷とは、清乃が彼の帰りを待っている場所であった。
家族は満洲で死んだかもしれない――と思いはしても、すぐあとから否定する声があった。
清乃の死に対する覚悟など、実は何もできてはいなかった。
妻が生きているものと決め、それ一つに希望をつないで彼は生きぬいてきた。
松三が快方に向かったころから、彼の枕はしたたかに涙で濡れた。
頬を伝う涙の冷たさに、彼は何度か目をさました。
夢の中で、彼は妻に、母に、子供たちに、手をついて詫びた。
このかけがえのない人たちを殺しだのは、おれなんだ――としか思われなかった。
松三が開拓民として渡満する決意を固め、故郷に深い愛着を持つ妻を無理に伴わなかったら、そして、兄嫁と折合いの悪い母を強引に呼びよせなかったら、今もこの村で静かに暮らしていたはずの人々である。
それに、敗戦直前に応召したとき、牡丹江の将校に、帰れといわれながらノコノコとハルピンの部隊まで兵隊になりに行き、自分からシベリヤ抑留の原因をつくったことも、今は自分の愚かさから犯した罪としか思えなかった。
あのとき牡丹江からひき返していたら、あるいは清乃や家族の命を救えたかもしれない。
松三は目覚めてからも、申しわけなさになおも涙を流した。
どのように詫びても許されることのない罪の前に、彼はわが身を責めに責めた。なぜシベリヤで死ななかったのかと、自分の命までを呪った。
帰国後一年ほどが過ぎ、松三は兄の製材所をひき受けて自立した。
耕地を分け与えようという兄の好意を、彼は辞退した。
親から譲られた狭い土地を、兄弟で分け合っては共倒れだ――と思えばこそ、新妻を連れて渡満した松三である。
今さらその土地をもらうことはできなかった。
また、生まれながらの農夫である松三だが、清乃という伴侶を失った今、再び土を相手にする気持を失ってもいた。
妻の死と共に、土は彼から離れたものになっていた。
しかし、いつまでも兄の好意に甘えて遊んではいられなかった。
彼は兄が放棄していたも同様の製材所を譲りうけて、自立した。
松三の希望通りにさせた竹二は、製材所が利潤の薄い仕事と知りながら、これをきっかけに弟が再起することを願っていた。
松三は製材所のそばに建てた小屋同様の家に、身よりのない遠縁の老婆サキと二人で住んだ。
彼はサキはじめ、製材所で働く男たちとも、必要以外のことばを交すことがない。
無表情のまま、松三は早朝から夕方まで黙々と働いた。
毎日きまった時間に、サキのととのえる粗末な食膳に一人で向かって、一定量を口に運ぶ。
食事にも、衣服にも、住居にも、何の関心も示さなかった。
四季の移り変わりさえ、松三の目には映らない様子だった。
全く感情の動きのない松三の顔が、夜だけは生きた表情をとり戻す。
サキが早々と寝部屋へひきとった後、毎夜、松三は手づくりの仏壇に向かって、長時間念仏をとなえた。
そこには母と妻、二人の子供たちの俗名が「昭和二十年没」の文字と共に並んでいる。
死亡のときは敗戦の二十年というだけで、日付はない。
いつ、どこで、どのように家族が死んだのか、彼は知らない。
松三に読経などできるはずもない。それをおぼえようともしない。
彼は夜ごとに「南無阿弥陀仏」を繰り返し、その中に感情のすべてを注いで、死者に許しを乞う。
信州の冬の夜さえ、彼の額に汗がにじんだ。
だが、位牌から、彼の胸に応える声はない。
死者は松三の苦悩の前に無言である。
許されるはずはない――と決めている松三は、母や妻の沈黙を当然のものと受け、なおひたすらに詫び続ける。
生きている限り、許しを乞い続けることを、いつか松三は当然の報いと思っていた。
そのためにこそ、おれの命は残されているのだろう――。
松三の帰国を聞き伝えて、何人かの満洲引揚者が訪れてきた。
その多くは、満洲時代の松三の知らない人々であったが、彼らは同じ開拓民同士であり、またはシベリヤ抑留組であることで、結束しようという気持を抱いていた。
彼らは在外私有財産補償問題について、松三が帰国した二十三年までの動きを語った。
――GHQの命令による大蔵省令第九五号とやらで、おれたち引揚者は在外財産の申告をさせられた。
むずかしい書式などわからないので、書類をつくるのに費用もかかったが、いったいいつ補償してくれるのか。
二十一年十一月、引揚者団体全国連合会が結成され、十二月、石橋大蔵大臣は各党代議士立会いの前で、引揚者に現金一万五千円を在外私有財産補償の見返りとして交付すると発表した。
だがGHQの強い圧力で実現しなかった――。 |
いっさい外出をしない松三にも、補償問題と共に、次第にそれまでの内地の引揚者受入れ態勢がわかってきた。
昭和十七年に外務省亜細亜局、対満事務局、興亜院、拓務省を統合して発足した大東亜省は、終戦直後の八月下旬、マッカーサー総司令官の着任前に廃止され、事務一切は外務省に設けられた管理局に移管された。
終戦時、大東亜省拓南局長であった森重干夫が管理局長に就任した。
同年九月、最高司令部から軍人軍属を合む在外邦人六百数十万を、内地に引揚げさせよという指令が出た。
管理局の第一の仕事は在外同胞の援護である。
出先機関にそれぞれ緊急指令を出したが、各地の情勢はまちまちで、特に満洲の情況は全く不明であった。
断片的に伝わる情報は、絶望的なものばかりである。
当時の日本政府は何事も司令部の指令を仰がねばならず、管理局がどうあせっても、満洲との連絡の道はふさがれていた。
森重局長は、満洲関係を担当する矢野征記第二部長と計り、密偵による連絡を企図し、また救援物資の輸送も計画した。
引揚者援護に対して、総司令部はきわめて冷厳な態度だった。――
軍人、引揚者、また内地の被戦災者は、特別に援護すべき筋合のものでない。これらの人々が生活に困窮するならば、一般的社会政策としてこれを救援すればよい――という立場で、のちにはかなり緩和したが、当初は政府による援護対策は全く認められなかった。 |
しかし、引揚者援護は緊急の問題である。
民間団体がこれにかわるほかはなく、財団法人在外同胞援護会が発足した。
また二十年十二月には、財団法人開拓民援護会が設立された。
敗戦によって本来の使命を失った満洲移住協会の後身である。
当時はまだ満蒙開拓民が現地にとどまって営農を続けられるか、全員が帰国しなければならないかも不明であった。
しかし土地、財産を処分して渡満した開拓民の多数が帰還するものと予測をたて、その人々の帰国後の生活援護、また満洲に留まる人々への支援を目的に発足したものである。
その事業計画には、上陸地援護施設、地方援護施設、収容保護施設、就農補導施設、婦女子援護施設、開拓民自興会の育成、資料の作成配布、開拓民相談所の設置などがあった。
援護会の最初の仕事は、二十一年二月に朝鮮経由で帰国した和歌山県送出の高野(こうや)開拓団員への、援護物資を持っての見舞であった。
二十一年、満洲からの集団帰国が開始されてからは、引揚上陸地に駐在員を置き、その援護をした。
援護会がその育成に力を入れた開拓民自興会は、引揚開拓民の自力更生を目標に設立した援護組織である。
終戦当時、大東亜省満洲事務局の開拓課長であった和栗博は、引揚開拓民の多くが再び内地で開拓にあたろうとする決意を知り、官庁側としてこれを援護するため農林省に移った。
「我々はヤミ屋になれば食ってゆけるが、それでは敗戦日本の再建に何らの貢献をなし得ない。国内開拓をして食糧増産を計ることこそ、引揚者が国に尽す唯一の道である」
という一引揚者のことばが、和栗の胸に強く響いていた。
そして、二十一年八月帰国した千振(ちぶり)開拓団長・吉崎千秋などと相談した結果、開拓民自興会を結成することになった。
昭和二十一年当時の疲弊しきった状況の中で、引揚開拓者は自ら再起する以外に道なし――という意味で、和栗が選んだ名称である。
引揚開拓民の各県代表は東京に集合し、再起更生対策を協議して、次の決議をおこなった。
① 自興精神を振起し、自力で更生の途を拓く。
② 自力更生の方途を、敗戦祖国再建に通ずる国内開拓に置く。
③ その運動の推進母体として各県にそれぞれ自興会を結成し、東京に全国開拓民自興会を組織する。
こうして東京麹町一番町の旧満洲移住協会焼け跡の開拓民援護会内に、全国開拓民自興会が創立された。 |
その後この二つの組織は提携して引揚者の援護にあたってきたが、二十三年五月、援護会は、自興会の独立自営の能力を認めて、解散した。
その全財産を譲渡された自興会は、新たに社団法人開拓民自興会を設立し、全国開拓民自興会はそのまま残され、両者一体となって運動を続けた。
2 駅馬開拓団の再建――二十二年―― top
昭和二十四年八月三十一日、群馬県長野原町応桑大屋原(北軽井沢)の野面を覆う熊笹は、すさまじい風の襲撃になぎ倒され、幅広のたくましい葉も地上に身もだえて、豪雨にたたかれていた。
三十年立ちの落葉松も、キティ台風(占領時代、台風には英語名がつけられた)の暴威には抗しきれず、すでにほとんどが倒れた。
しかし人々はひるむ色も見せず自然の暴力にたち向かい、闘い続けた。
血のにじむ苦心の末この高原にうち建てた住居を、ムザムザと台風の餌食にはさせられない。
清水圭太郎を中心に、再び未墾地を拓こうと、北軽井沢に入植した駅馬開拓団の引揚者たちである。
キティ台風は、二十六棟の新築家屋のうち半数を倒潰して去った。
昭和二十二年の入植以来、彼らの受けた最初の試練であった。
昭和二十一年九月、駅馬開拓団の人々は、夢にまで見た故国に帰り着いた。博多に上陸した時は、「もうこのまま死んでも本望だ」とまで感激したが、彼らを迎えた相国の現実は、満洲の難民生活の中で想像したものとは、かなりの隔たりがあった。
連合国の占領下であることはもちろん知っていたが、それさえ彼らが実感として掴んだのは帰国後のことである。
内地の人々は長い戦争に疲れ果て、それに終止符を打った敗戦にただ茫然とした表情を向けていた。
戦争遂行のため強化されていた国策は、何によらず“悪”と断定された。
物資の窮乏は激しく、占領下の統制は厳しく、その裏に闇物資が横行していた。
国、村、家など、かって日本人の思考の根底であったものは否定され、それを口にする者は封建的、反動的と嘲笑された。
駅馬開拓団の人々は、劣等感と自己否定に満ちた祖国を、複雑な気持で眺めた。期待を裹切られた気持は強かったが、彼らは現実とかけ離れた想像を抱いていた自分たちに“満洲ぼけ”という自嘲を向けて、新しい覚悟をうながした。
渡満前、彼らが所有していた土地は、GHQ命令による農地解放の当然の措置として政府に買い上げられ、人手に渡ることになった。
おれたちは国策に沿って渡満したのだから――と思ってみても、それを理由に特別な扱いをされる時勢ではなかった。
かっての仲間であった内地農村の人々は、食糧難にあえぐ都会の人々に頭を下げさせて“わが世の春”に酔っていた。
だが一寸の土地も持たない引揚者が、そこに割りこむ余地はない。
政府の援助による開拓援護会と、満洲開拓の指導者たちの良心的責任感から発足した全国引揚開拓民自興会が、引揚者を未墾地に入植させる国内開拓の運動を起こしていた。
おれたちも新しい村づくりに立ち上がろう――駅馬帰りの人々は、旧団長・清水圭太郎を中心に再び団結した。
他県の引揚開拓民も次々に入植地を定めて、再出発していた。
昭和二十一、二年の入植者数は三万五千人に達した。
二十三年度は一万五千八百人余、二十六、七年にはそれぞれ一千戸を増し、昭和四十一年現在の引揚開拓民の入植戸数は三万二千戸、約七万五千人に達している。
この数は、引揚開拓民のほぼ半数にあたる。
群馬県下の引揚開拓民は、昭和二十一年に群馬県開拓民自興会を結成し、県の開拓課内に事務所を置いた。
ここを中心に県内各地に適地を物色して、引揚開拓者を入植させ、満洲での経験を生かして、再度の村づくりに更生の道を見出させるためである。
煙筒山開拓団員を佐波郡東村女堀と勢多郡新里村東板橋に、報馬開拓団員を榛名山麓西榛名に、駅馬開拓団員の一部を木瀬村の各部落有林であった大胡町金丸と新里村西板橋および赤城北麓久呂保村の高原に入植させた。
最後に決定したのは駅馬開拓団の主流と、第六次海倫群馬村、第九次九道溝甘楽郷の人々が入植した吾妻郡長野原町応桑大屋原(北軽井沢)であった。
母村木瀬村の斎藤順衛、田代宗三郎の熱心な協力と指導の下に、赤城山麓、白根山麓、浅間山麓、大峰山麓などの調査が行われ、最後に選び出された入植地である。この地は浅間山の噴煙を西南方に眺める、標高千二百メートルの高原である。
かって明治の中頃、北白川宮の経営した“宮様牧場“の跡で、浅間をはじめ、“鼻まがり”“鷹つなぎ”“浅間かくし”の峰々にかこまれ、熊川、地蔵川に挾まれた平原は、腰に達する熊笹に覆われていた。
生産経済の限界を越えた黒色火山灰土の瘠薄地(せきはくち)であり、営農には不利というほかない。
しかし開拓民は、もとより覚悟の上である。有利な土地が、やすやすと引揚者のものになるはずはない。
彼らが“骨を埋める地”をここと定めた理由の一つは、この高原の風物が、満洲駅馬のそれによく似ていたためであった。 |

駅馬開拓団の入稙地。千二百米の高原で、
満州駅馬(えきば)と似ていた。
|
また、当時なおシベリヤに抑留中の旧団員が復員して来ることを思えば、彼らのために相当の面積を用意しておかなければならない。
この高原は、その条件をも満たすことができた。
大陸寒冷地の農業経営に豊かな経験を持つ彼らは、帰国の翌二十二年、清水圭太郎を先頭に、自信を持って入植した。
駅馬からの引揚者全員が、この計画に参加できたわけではない。
各家庭の事情により、故郷で家業にたずさわる者、親族知己を頼って更生の道を選ぶ者、また養老院にはいる者もあった。
さらに、孤児や未亡人など、働き手のいない家族も、村づくりに参加することはできなかった。
きびしい戦後の国内開拓には、こうした戦争犠牲者までをひき連れてゆく余裕はない。
大屋原開拓地は無霜期間百~百十日、最高気温摂氏三十度、最低零下二十度、大体、北海道札幌地区に等しい気候である。
初めから冷害の危険を考えた彼らは“実”を穫(か)る農業を避けた。
一戸当たり四町歩の耕地と約三町歩の附帯地に“草地農法”を確立し、乳牛、鶏、豚などの畜産を中心に据えた。
入植者の大部分は満洲の零下三十五度の酷寒に耐え、難民生活を共に過してきた駅馬帰りの人々である。
乳牛の管理、搾乳などに経験者が多く、二十三年、北海道と千葉から二十三頭の乳牛を導入して、“乳と蜜の流れる郷”を目指した村づくりが進められた。
キティ台風の試練に、彼らの闘志はますます燃え上がった。毎年、復員者を加えて、村の戸数は増してゆく。
3 河原に住みついた小林吉太郎――二十四年―― top
加藤松三の村には、多数の引揚者がいた。
その誰もが、敗戦直後の開拓民のむごたらしい死を語った。
外務省の調査によれば、終戦時の在満邦人は約百五十五万(関東州在住二十五万を含む)で、開拓民関係はその十四パーセントにあたる二十七万であった。
敗戦に基づく邦人の死亡者は全満で十七万六千人に上るが、このうちの八万人は開拓民である。
在満邦人数の十四パーセントにすぎない開拓民が、死亡者数では全体の半分弱を占めている。
松三と同じ黒台信濃村開拓団から帰った人の話から、この団の遭難の模様も次第に彼に伝わった。
松三が仏壇の前に坐る時間は、ますます長くなった。
兄・竹二の期待に反して、松三はいつまでも製材所の仕事を続けていた。
新たな意欲を持って拡張を計ったり、他の仕事に向かおうとする気配は、さらにない。
製材所には老境に入ろうとする男二人と、おしの少年が働いていた。
何の変化もない仕事の繰り返しではあったが、これら三人に僅かの給料を払い、松三と老婆サキのほとんど金のかからない生活を辛うじて支えることはできた。
かっての意欲に富んだ松三なら、とうてい続けるはずのない仕事だが、彼は黙々と働いていた。
相変わらず、夜ふけてただ一人仏壇に向かい死者に許しを乞う時だけ、彼の顔の筋肉は感情の流れを伝えた。
苦悩にゆがむ表情であった。
松三の製材所も部落からかなり離れた山裾にあったが、そこからさらに一キロほど離れた河原の荒地に、小林吉太郎の一家が住みついた。
吉太郎もシベリヤ帰りであり、妻子は満洲国三江省の開拓村から九死に一生を得て、二十一年に帰国していた。
吉太郎が帰還した昭和二十四年の農村には、職がなかった。
新しい仕事を始めるにも、都会へ出るにも、資金は全くない。
シベリヤの抑留生活で健康を害した彼は、再び開拓の鍬を振う自信もなかった。
しかし、それまで妻子が寄食していた兄夫婦の家に、吉太郎までがいつまでも世話になるわけにはいかなかった。
兄もまた子だくさんの貧農である。
吉太郎は妻と六歳の男の子を連れて、石だらけの河原の小屋に移った。
何に使用されていたものか、長年捨てられていた小屋に申しわけばかりの手入れをしたものが、この一家の住居となった。
その小屋さえ、村の人々の好意でやっと手に入れたものである。
吉太郎はどうにかリンゴ組合に職を見つけ、妻は小作に出て働き、一家三人が細々と食ってゆくだけの生活が始まった。
米一升百五、六十円という値段は、吉太郎が朝七時から夕方七時まで働いて得る賃金と同額である。
セリ、アカザなどの野草を副食にあてても、一束四十円の薪は買えず、夫婦は遠い夜道を歩いて山の雑木の枝を伐った。
文字通り、洗うがごとき赤貧の中で、妻は満ち足りた微笑を吉太郎に向けた。
敗戦後の北満の逃避行で、またそのあとの収容所で、地獄の中に生きていたころの彼女は、再び夫とめぐりあり日があろうとも思わなかった。
内地にたどり着き、子供と共に義兄に養われた三年間もまた、気がねの連続であった。
電灯もないあばら家でも、一家が身をよせ合って暮らせる現在を、彼女は心からありかたく思っていた。
梅雨期になると、河は水かさを増して河原の石をかくし、やがて吉太郎の小屋の床下も次第に水面が上がって、遂に畳がわりのゴザも浮き上がった。
吉太郎と妻が仕事を休み、必死にシャベルを振って防水工事にあたっていることを、松三はおしの少年の手まねで知った。
彼は黙って製材所を出た。
手をかそう――挨拶もぬきの松三のことばが、吉太郎を驚かせた。
人づき合いをしない松三は村人から変人扱いされ、“シベリヤぼけ”とも呼ばれていた。
松三のたくましい腕力は、小屋から河下へ溝を掘り、土手を築く仕事を見る見るうちにはかどらせた。
吉太郎は思いがけない松三の援助に深く感謝すると共に、同じ引揚者の経験を持つ話し相手を得たことに、心をはずませていた。
リンゴ組合で働く彼は――長い間こうした話し相手に恵まれていなかった。
満洲はよかったなあ――吉太郎としては、珍しく明るい声であった。
満洲では、働きさえすれば豊かになった。安い賃金で満人を雇うこともできた。
そして、日本人同士は実に気持よく結束していたものだった。
互いに競争はしたが、みなが成功し、開拓団の成績が上がることを心から喜び合ったものだった。
どの家の生活も平等で、差別待遇などは初めからなかった――。
松三は黙々と聞いていた。
それにひきかえ――と、吉太郎の声が曇った。
――内地は相変わらずだ。おれたち引揚者への好意にさえ、裏がある。うっかりありがたがっていると、いつの間にか相手に利用されている。内地では、何かの得がなければ、好意さえ示さないものなんだ。みんな自分の利益ばかり追っている。。農地解放とかのためだそうだが、雑草を生やして遊ばせている土地も、おれたちには貸してくれない。金持は、貧乏人をよせつけまいとしている――。
吉太郎は反応のない松三の様子にも気づかないように、話し続けた。
――引揚者は信用できない、とぬかしたやつがいる。みんな生活に困っているんだから、中には悪いことをした者もいるかもしれない。だがな、おれたちは、国策だ、勝つためだといわれて、土地や財産を処分して満洲へ渡ったんじゃないか。絶対に負けないといっていた日本軍が負けたから、たくさんの仲間が殺され、おれたちは無一文で帰ってきたんだ。それだのに、国は何もしてくれない。内地で暮らしていたやつらが、どの面下げて、おれたちを信用できないなどといえるか。国はおれたちに“すまなかった”と頭を下げて、補償金を出すべきじゃないか――。
吉太郎は日ごろの不満を一時にはき出す勢いで、しゃべり続けた。
だが、やがて帰り支度を始めた松三に、彼はまた明るい声に戻って、いった。
――不足をいうのは間違いかもしれない。とにかく、生きて帰ってきたんだ。おれが何か不平をいうと、かかあがいつもそれをいうんだ。満洲やシベリヤで死んだ人のことを思えば、一家がまた一緒に暮らせるようになったことだけで、ありかたいと……。本当にそうだ。それだけで満足している女房や子供の顔を見ると、おれはどんな辛抱でもする気になる。どんな――。
急に、吉太郎のことばが切れた。彼はこの時、松三が妻子を失っていることに思いあたった。
――おれももし妻子を満洲で殺されていたら、この男のようになっていたかもしれない――。
吉太郎は黙りこんだ。
4 在外私有財産返還運動―二十六年―― top
講和条約締結の気運が高まるにつれ、引揚者がそのなり行きを見守る在外私有財産の問題が表面化してきた。
二十六年一月、ジョン・フォスター・ダンス国務長官は、トルーマン米大統領の特使として来日し、日本側各界の講和内容についての要望を打診した。領土、安全保障、在外資産に重点がおかれた。
このうち在外資産に関する要望は、政界筋は「在外私有財産の公正処理を期待する」、財界は「日本の在外資産は全部没収になるようだが、政府所有のものは別として、民間人が苦労して築き上げた私有財産まで没収するのは妥当でない」というものであった。
また引揚者団体全国連合会は、私有財産不可侵、基本的人権尊重の立場から、在外私有財産の返還を要望した。
この年六月末、引揚者千二、三百人が東京築地本願寺の広場に集合し、「国家は在外私有財産を補償すべし」という声をあげた。全国各地から集まった人々である。
戦後六年がたち、一般市民の生活はかなり回復していたが、本願寺に集まった人々の姿にはまだ敗戦の打撃がそのまま残っていた。
その中の一人小林吉太郎の服装も、一目で引揚者とわかるものであった。
ヨレヨレの国防色のズボンと、妻が丹念につぎを当てたシャツのほかに、彼は着がえなど持ってはいない。
上京の費用も地元の引揚者が僅かずつ集めて、彼に渡したものであった。
吉太郎は、味噌をつけて焼いた握り飯の包みを下げていた。滞在費を節約するためである。
同二十六年九月、サンフランシスコ条約が締結された。
この平和条約第十四条によって、連合国は邦人在外財産を処分する権利を取得し、第十九条によって、日本は在外資産請求権を放棄した。
イタリア平和条約やドイツのパリ賠償協定には補償条項が規定されているが、このサンフランシスコ平和条約には、補償の義務は明示されていない。
連合国は日本側に補償を期待したが、条約起草にあたり日本側から補償規定の削除を希望して除いた経緯もあって、この問題は日本の裁量にまかされる結果となった。
サンフランシスコ条約調印前後の日本政府の動向には、微妙な含みがある。
二十六年五月、衆議院外務委員会で吉田首相は
「在外資産問題について、原則として連合国は日本から賠償をとらないかわりに、在外資産はその所有国において賠償に当てるということになっている。しかしながらこの原則に対して、いかなる程度までこれを緩和するかということは、その国の気心一つによって違ってくると思う」と述べた。
また同首相は、条約調印後の十一月、参議院平和条約特別委員会で
「私有財産の尊重すべきことは当然であります。しかしながら、この賠償に当てられる私有財産の補償をどうするかというどとは、予算の関係もありまして、希望としては補償はいたしたいと思いますが……」と述べている。
同委員会で外務省西村条約局長は、
「この条約を作るにあたりまして、米国政府は最小限度の条約を平和条約に盛って、それ以外の事項はすべて日本の善処に信頼するという立場を取った次第であります。自然イタリア条約にはいりましたような補償条項も、この平和条約にははいっておりません。この点は日本政府として、それだけ善処する責任を負ったという結果になるわけであります」と述べた。
このほか、池田大蔵大臣は衆参両院条約特別委員会での答弁で、国の補償の義務は認めているが
「日本の財政状態にはその能力がない」と述べている。
このころの政府の意見は、実行するかしないかは別として、補償の義務を認めたと解されるものが多い。 |
同二十六年十一月、小林吉太郎が興奮した顔で加藤松三の家を訪れた。
――政府はおれたちが満洲に残してきた財産を、賠償の引き当てに外国へ渡しておいて、それを補償する義務はない、とぬかしたそうだ。そんな話があるか。賠償なら、日本人全体が払うべきではないか。なぜおれたち引揚者ばかりが、負担しなければならないのだ。それでなくても、多くの死者を出した開拓民の犠牲は大きいのに――。
吉太郎が引揚者仲間から聞かされたのは、十一月の参議院条約特別委員会での政府の答弁である。
「政府が補償を実行しなければ、“私有財産を公共の用に供したとき政府はこれを補償する義務をもつ”と定めた憲法第二十九条第三項に反するのではなしか」という質問に、政府の見解は、
「憲法におきましては明らかに私有財産権というものを尊重すべきことを認め、またそれに対する国家の処分につきましては、必ず補償しなければならないという規定をおいております。しかしながら、ここに問題となりまする財産は、いわゆる在外財産でございまして、これは日本国憲法の適用区域にある財産ではなく、その所有国の外国の法制に服する財産でありまして、またその外国というものは、日本の主権の直接及ぶところではありません。
法律論の立場から申しますると、連合国にある財産に対して、平和条約第十四条の規定によりわが国としては、連合国が直接にこれを処分することを容認する。これに対してわが国が在外資産に対する保護権の行使を見合わせるということになったのでありますが、この損害の起こる直接の原因というものが、あくまで当該連合国の主権によるものでありまして、これは、わが国政府の措置によって処分されるのではなく、所在国の主権によって処分されるのでありますから、この際においてわが国の主権の行使について規律いたしました日本国憲法という問題は、生ずる余地がないのであります」 |
この見解に対し、のちに京都大学教授・大石義雄は次のように述べて、反対している。
「私は、このような政府の見解には賛成できない。私の法理論によれば、このような政府の見解は、国家対国家の国際法論と国家対国民の国内法論とを混同するものである。
なるほど平和条約によれば、わが国としては、わが国民の在外財産を連合国が直接これを処分することを容認し、これに対してわか国が在外資産に対する保護権の行使を見合わせるということになったとしても、それはわが国対連合諸国との法律関係で、わか国対わが国民との法律関係ではない。
たとえわが国は条約で在外資産の連合諸国による接収を承認したとしても、接収された在外資産の所有者たる日本国民と日本国との法律関係はどうなるかの問題は、国際法の問題ではなく、日本国対日本国民の国内法関係の問題である。
いうまでもなく、国内法の最高法は憲法である。だから、日本国民の在外資産が日本国の行為によって接収された場合、日本国対在外資産の所有者たる日本国民の法律関係は、日本国の憲法によって定めたところによって処理されなければならない。
わが国では、旧憲法も現憲法も、共に国民経済の基本原則として私有財産制をとっている。
私有財産制の下では、国民個人個人が財産の所有を認められ、それが国家によって保護される。
だから、旧憲法では“日本臣民はその所有権を侵されることなく、公益のため必要な処分は法律の定むるところによる”と定め、現憲法では、その第一項で“財産権は侵されない”と定め、その第三項では“私有財産は正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる”と定めている。
いうまでもなく、日本国が平和条約で国民の在外資産の連合諸国に接収を承認したのは、日本の国策によるものである。
ということは、日本国民が在外資産を失ったのは、日本国の行為によるものである。
そうだとすれば、憲法上日本国は日本国民に対して補償の義務を負うのは当然である。(以下略)」 |
吉太郎は松三に向かって、いいつのった。
| ――「日本は戦争に負けた。外国に賠償を払わなければならない。だから日本人全部が、その財産や収入に応じて金を出せ」というのなら、おれはこの通り貧乏だが、何としてもその金を出そう。だが、引揚者が外国に残してきた財産を賠償に当てておいて、その補償はしない、というのはどういうことだ。おれが今、食うや食わずで、電灯もない家に住んでいるのも、満洲で築いた財産をなくしたからだ。なぜおれが財産をなくしたか。国が財産を補償するまで、おれはがんばる。―― |
松三は痛ましげに吉太郎の顔を見て、深くうなずいた。
松三もまた吉太郎と同じに、満洲で築いた財産のすべてを失っているのだが、彼はそれとは無関係に、吉太郎に同情していた。
無理もない――と、松三は吉太郎の憤りを聞いていた。
――この男の気持は、敗戦を迎え、シベリヤに抑留された後も、戦前と変わっていないのではないか。妻子と共に、よりよく生きようとあがき続けている。国というものにも、戦前と同じ気持を抱いているのではないか。
心の底で国を信頼していればこそ、こうまで腹が立つのではないか――。 |
松三は他のすべてにそうであるように、国に対しても腹を立てる力を失っていた。
彼の心は、外に向かって動こうとしない。松三の生涯はもう終わった、といえるのかもしれない。
誰に向かっても、何に対しても、もはや期待するものがなかった。
昭和二十六年、北軽井沢の旧駅馬団員は、満洲で非業の死をとげ、再度の村づくりに参加できなかった仲間の霊を慰めるため七回忌を催し、村のほぼ中心にあたる広場に開拓地蔵尊を建立して、その冥福と加護を祈った。
開拓村は牛乳、鶏卵、食肉などのほか、厩肥の投入による地力増進で、馬鈴薯、コーン、高原野菜などを生産した。
裸はだしの引揚者であった彼らは、資金のほとんど全額を借入金でまかなってきた。
その債務の重圧に耐え、前途に希望を描いて働いた。生産は年ごとに上昇してゆく。
昭和二十八年、満蒙開拓民のうち、何かの事情で現地に留まっていた人の多くが帰国した。
三江省樺川県の大八浪泰阜郷(やすおか)開拓団の中島嘉代も、その一人である。
敗戦の年の冬、方正収容所の飢えと寒さと死の中で、嘉代の長女・千世子は母や弟妹の命をつなぐため、満人農家の長男に嫁した。
嘉代と子供たちはその家に温かく迎えられて、思いがけなく無事の日を送ることになった。
千世子が二十二年に生んだ初孫・玉珍を抱いて、嘉代は平和な満人農家の姑になって暮らしていたので、日本人の集団帰国の時期も知らなかった。
二十四年、不幸なことに、千世子は難産のため死亡した。
若い夫の身も世もない嘆きを見て、嘉代は一家の犠牲ともいえる娘の結婚が、決して不幸なものでなかったことを知って、いっそう泣いた。
二十八年、嘉代は「これが最後の帰国」という知らせを受け、祖国へ帰る決心をした。
この時は次女・千鶴も満人の妻となり、二子の母になっていた。
千鶴も帰国に心を動かしたが、夫や子供たちの悲しみを見て、満洲に留まった。
5 清乃は礼をいって死んだ――二十九年目撃者・横山秀子の話―― top
松三は道で何気なく追い越した女に、声をかけられた。
加藤さんではないか。もしや清乃さんの――という女のことばに、松三は耳を疑い、狼狽した。
清乃さんの――と、現在生きている人を呼ぶように、女は妻の名を口にした。
しかし松三は、汚れたもんぺ姿の女の顔に、全く見おぼえがなかった。
横山秀子――松三と同じ黒台信濃村開拓団に入植していた者と女は名のり、去年、二十八年に満洲から帰国したばかりだ、といった。秀子の話によると
――秀子が清乃たち一家に出会い、その自決を見とどけたのは、避難行の三日目の深夜、鶏寧県通道地区の山裾の野原であった。黒台信濃村開拓団はソ連参戦の翌日、八月十日に避難をはじめ、その三日目、満人部落に仮泊していたとき匪賊に襲われた。秀子は三人の子供を連れて近くの草原まで逃げのびたが、行くてを敵にはばまれた。次々に自決してゆく仲間を目撃しながら、青酸カリの包みを落としてしまった秀子は子供を抱いて死ぬこともできずにいた。
このとき秀子のかたわらで自決したのが、清乃とおばあちゃんと二人の子供だった。「おばあちゃん、長い間よくしてもらって、ありがとう」と、清乃はいい、互いに長年の好意に礼を述べ合い、微笑さえ浮かべていたわり合った。そして清乃は首の手拭いを解いて水たまりにひたし、それをしぼった水で服毒した。――それを私は、ぼんやりと見ていました――。
銃声が四方から近づき、逃げ場もなく立ちすくむ秀子は、肩に衝撃を受けて意識を失った。
子供の声に秀子が意識をとり戻したのは、翌早朝であった。二人の子供はすでに息絶えていたが、五歳の男の子だけが無傷で、泣きながら母の体をゆすぶっていた。秀子は肩の激痛によろめきながら、子供の手を引いて、死体の散る草原を歩き出した。
方角もわからず、どこへ行くあてもない。飢えと疲れに、子供の足は進まない。秀子は死を求めて、さまよった。井戸を見つけ、ここに投身しようと近づいてみれば、すでに死体が折り重なっていて、水も見えない。母子はそこに坐ってしまった。
一人の老農夫が通りかかり、わが家へ来いと、声をかけてくれた。しかし、母子とももう歩く力もない。満人農夫は秀子にここで待つようにと告げて、子供を背負って去った。
間もなく、大勢の乱れた足音が近づいたが、秀子は逃げる気力もなく坐ったままであった。殺気だった暴徒の一団が彼女のそばを走りぬけ、中の一人が鈍器で彼女の頭をなぐった。秀子は再び意識を失った。死神にも見放されていたのか――
と、秀子が松三に語ったように、この時も彼女は死ななかった。
――秀子が意識をとり戻したのは、ある農家の納屋の中であった。その家の主婦が倒れていた秀子をかつぎこみ、手当をしてくれていた。回復までに、三ヵ月かかった。頭のきずを見ようと、借りた鏡に秀子が目をこらすと、頭の地肌も見えないほどに虱がうごめいていた。
秀子の夫は昭和十九年に応召し生死不明であったが、秀子は満洲に留まり、生き残った男の子を捜し求めて、農家を転々とした。作女となって働き、仕事の合間に方々をたずね歩いた。が、五年、六年とたっても、子供は見つからなかった。
秀子は子供の年を数えて、小学校をたずね歩いた。七年目、遂に彼女は子供と分れた場所から四十キロも離れた村の小学校で、わが子と思われる少年を見つけた。幼な顔をそのまま残して、十二歳になっていた。その子の両親に会ってみると、彼らも、終戦の年に道ばたで助けた子であることを認めた。しかし、少年は「日本人などではない」と大声で泣いた。日本語も話せない彼は、育て親にすっかりなついていた。
秀子の失望は深かった。何のために帰国もあきらめて、七年間を作女として働き通してきたのか――。昭和二十四年からは、日本と満洲との間の文通が可能になっていた。秀子が日本の兄の家に残してきた長女は、両親のいない生活の不幸を訴え、しきりに母の帰国を求めていた。しかし秀子は、男の子を見つけるまではと、娘の願いをしりぞけてきた。秀子と育て親との相談に村長も意見を述べた結果、少年が成人した後に本人の意志で日本か中国かを選ぶ――と決まった。もうこの子は日本に帰ることはない、と秀子は思ったが、それ以上どうすることもできなかった。それが去年のことでした――。 |
秀子は松三の製材所の前まで来ても話が終わらず、軒下に立ってようやく語り終わった。
そして、現在の住所である隣り村の寺の名を告げて去った。
松三はなおしばらく立つたまま、秀子の淋しい後姿を見送っていた。
長い間、彼女の話を聞いていたのだが、松三の心には、妻・清乃の最期の様子だけが鮮明に焼きっいていた。
彼は静かに家に上がり、仏壇の部屋にはいって、障子をしめた。
正坐した松三は、母、妻、子供たちの名前の並ぶ位牌に目を注いで動かなかった。
これまで、家族の最期の模様は一切わからなかった。暴徒の手で虐殺されたかと、松三は何度かそのむごたらしさを夢に見て、うなされた。
子供の殺される姿を目前にした清乃が、無理に一家を満洲に移住させた夫を恨んだであろうと、想像もした。
勝気な母もまた悲運を呪い、とり乱して、最期の瞬間まで嫁の清乃をののしったのではなかったかと――松三はこれらの想像にさいなまれて暮らしてきた。
もともと渡満に反対であった母や妻を、無理に悲運につながる道へ連れこんだ自分は恨まれるのが当然と、松三は思いこんでいた。
松三は、深く心にうなずいた。
母と清乃の最期の時に居合わせた秀子は、彼女たちが互いに礼を述べていた、と語った。
長い間ありがとう、と清乃はいってくれたか――。
母も清乃も、すべてを許してくれていたのか。運命にも、おれにも、恨みを抱かず、許して、静かに死んでいったのか――。 松三は長年の心のしこりがほぐれてゆく思いで、位牌に向かっていた。
翌日、松三は隣り村の寺へ、秀子をたずねた。彼女は寺の離れに住んで、墓守りをして暮らしていた。
秀子は墓の掃除をしながら、松三に乞われるままに、清乃の最期の場所の風景などを語った。
秀子は帰国までの八年間、毎年八月十三日には見おぼえのある山裾の野原に立って、そこで死んだ二人のわが子と、自決した仲間の冥福を祈った。
終戦の翌年には、草むらに人骨が散らばり、靴や布きれらしいものも残っていた。
二十二年には、ところどころ草がはげたように、小さな骨片が散っていた。
そして二十三年には、もうその辺りは耕されて畑になっていた――と、秀子は語った。
松三の心に浮かぶものはすべて――蒼草の上に伏した清乃の横顔も、草むらに散る白い人骨も、耕された畑に注ぐ日の光も――すべて静かだった。
この夜、松三は位牌の「昭和二十年」という文字の下に「八月十三日没」と書き入れた。
あしかけ十年目に、家族の命日を正確に知った。その後も、松三の生活は少しも変わらなかったが、夜ごとに念仏を唱える彼の顔から苦悩のかげが消えた。
やがて、同じ家に住むサキも、松三の変化に気づいた。
サキはときどき、彼の口許にかすかな微笑を認めた。以前には、たえてないことであった。
妻はおれを許してくれていた――と思えた日から、松三の胸に清乃は住みついていた。
6 過去を持つ少年少女――二十八年・二十九年―― top
昭和二十八年、引揚者の在外私有財産補償の声が高まったころ、政府は「在外財産問題調査会」を設立し、翌二十九年には「在外財産問題審議会」として総理府に置いた。
この問題に対する引揚者の運動が活発になったことを知りながら、松三はそれに加わらなかった。
当然の要求、とは思うのだが、彼は満洲での辛苦に満ちた八年間の開拓生活や、それに続く家族全員の死を、声を大にして人に語る気になれなかった。
すべて過去のこと――と、水に流す気持になっているのではない。
松三は、彼自身にもはかりしれない深さを持つ痛手を、胸にかかえて生きてゆこうとしていた。
それは、何によっても、いかなる方法によっても、いやすことはできないと思われた。
この痛手を人の前にさらして、それを補償金の数字に換算することに、松三は説明のつかない抵抗を感じた。
――そんなことでない。金で済まされることではない――と彼の心は抗議する。では、どうしてくれというのか。他に方法はない。誰にも、どうすることもできないのだ――残るのは、救いのない思いだけであった。
――無一文でシベリヤから引揚げた小林吉太郎のように、生活の土台の全くない内地で妻子を扶養しなければならない者が、少しでも多くの補償金をと望むのは当然である。日本全土には、吉太郎のような引揚者かどれほどいるかわからない。それを思えば、引揚者の一人でありながら、補償金要求運動に加わらない自分は、義務を果たしていない――と松三は思うのだが、しかし、どうしても積極的な動きはとれなかった。
しかし松三が、他の引揚者に対して冷淡だというわけではない。
ことに、清乃が温かく彼の胸に帰ってからは、松三は妻への供養の心をもこめて、人のために尽した。
松三の行為はいつもひそやかで、目立つことがなかった。
引揚者の苦悩は、同じ経験を持つ者でなければわからないと、松三は信じていた。
わが身にひきくらべて、人の痛手に触れることを極度に恐れる彼は、決して他人の生活に踏みこむことをしなかった。
松三が接触を持つ引揚者の中には、自分の手でわが子を殺し、または遺棄した人もいるはずであった。
松三はたびたび隣村の寺に秀子を訪れて、語り合った。秀子の長女は母の帰国を待ちきれず、伯父の許を離れて行方不明になっていた。
秀子は蟇守りをしながら、この娘の行方を捜している。
満洲で苦心のすえ見つけ出した男の子は母の許に帰ろうとせず、その間、母を求め続けていた娘は、待ちぎれずに姿を消した。
秀子はまたも徒労に終わるかもしれない子供捜しに、すべてをかけている。
梅雨や台風の季節には、松三は必ず吉太郎の家を水から守る作業を手伝った。
彼が製材所から商売物の板を運んで修理を繰り返すので、この家は今もなんとか形を保っていた。
電気がひければなあ――と、吉太郎は松三の顔を見るたびにいった。
彼は方々に運動していたが、河原の一軒家に電灯をひくには、かなりの金がかかった。
とうてい吉太郎に負担できる額ではない。
日が暮れれば寝るほかない、まるで明治時代のような生活も大人は我慢するが、これから勉強しなければならない子供のために――と、吉太郎は辛抱強く電気をひく交渉を続けていた。
二十八年の帰国者に連れられて、十二歳の孤独な少年がこの村に引揚げていた。
武夫という名が示す通り、彼は日本人には違いないが、終戦後の混乱期に母や兄弟は死亡し、その後、満人に育てられたため日本語も話せなかった。
しかも、書類上の間違いのためか彼をひきとるはずの“シベリヤ帰りの父”にあたる人物は、この村にはいない。
少年をひきとった農家は、たちまち彼をもて余した。
言葉が通じないだけでなく、彼は人になじまず、日本の農村の生活に全くとけこまなかった。
親捜し運動のかいもなく、父と名乗り出る人はいない。少年は学校から逃げ出し、一日中草原に坐っていた。
松三は、武夫を製材所にひきとった。
おしの少年相手では言葉の差も気にならないためか、武夫は次第にこの単調な生活になじんだ。
強制されることもなく、彼は少しずつ仕事を覚えていった。
いつからともなく、松三の家には引揚者が集まるようになっていた。
松三は相変わらず口数が少なく、人の相談ごとにも積極的な意見を出すことはまれであったが、しかしいい聞き手には違いなかった。
“誰かに話したいこと”を胸に抱えた人々は、松三を相手に心おきなく語ることができた。
松三はいつも温かい心でそれを受けとめた。
年をとったサキの手伝いに、前田文子かときどき立ち寄るようになった。
文子は張家屯信濃村開拓団で終戦を迎え、祖母、母、兄弟などすべての肉親を失って、ただ一人故郷に帰り、そこでシベリヤの父の死亡通知までを受けとった。
祖母の遺言通り「前田の家の血筋を伝える、ただ一人の者」となった文子は、叔父の家に養われ、義務教育を終わった後はその農家の仕事を手伝っていた。
日焼けした頬の線のきびしい、整った顔だちだが、十八歳という年齢にふさわしい華やいたちののない娘である。
中学の成績のよかった文子は、ひそかに進学を望んだが、周囲からその声の出ないままに彼女の希望は消えた。
愛嬌のない娘、何を考えているのか底の知れない性質――などといわれながら、文子は働き手として養家で重宝がられた。
彼女自身も、人に心を開くことのできない自分の性格をよく知っていた。
文子はある日、松三に向かって、私は子供の時に地獄をくぐりぬけたから、もうほかの人と同じには暮らせないのかもしれない――といったことがある。
人間が見てはいけないものを、たくさん見てしまった――ともいった。
文子がこのようなことを話せる相手は、松三一人であった。
7 タケオを捜す母――三十年―― top
昭和三十年の早春の日暮れ時、松三の家の軒先に、旅疲れを顔に現わした中年の女が遠慮がちに立った。
サキに案内されて松三の前に坐った女は、気おくれに身の置き場もない様子で畳に手をついたか、その目にはつきつめた一途な光があった。
タケオという子供をあずかっておいでだろうか――東北地方のなまりで、女はいきなり問いかけてきた。
松三のうなずくのを見るや、女の顔に光が射すよりに喜色が溢れた。
正子と名乗るこの女もまた、引揚者であった。
終戦後の避難行の途中で子供を捨てた――と語る時、正子は自分の犯した罪の恐ろしさに、身をおののかせて泣き崩れた。
彼女は自分の属していた団の名をいわない。みんなが子供や年寄りを捨てた。
ほかの人の迷惑にもなるから――という正子の言葉を聞くまでもなく、松三は決して彼女に質問を浴びせようとはしない。
青森の方にそのような団があった、と思いながら、痛ましさに、彼はただ目をそむけていた。
正子は三人の子供を連れて団を逃れたが、山中をさまよう間に赤ン坊と三歳の子供は死んだ。
最後に残った長男・武男は、山中のある場所に置きざりにして別れたままだが、どうしても死んだとは思えない――。
必ず迎えに行けると思って武男を残したのだが、なぜ私も一緒に残らなかったか――と、正子は松三に罪を詫びるように何度も頭を下げて、苦しげに語った。
鬼のような母と自分を責める正子のことばは、涙にとぎれて聞きとりにくい。
違う、人違いだ――と、話の途中から、松三は何度か胸のうちで繰り返しながら、正子の失望を思って、それを口に出しかねていた。
松三がひきとった武夫は終戦時には四歳であったが、正子の子供はそのとき八歳になっていた。
名前の字も違い、武夫の母が死んだことは確認されている。
もし松三の想像通り、正子が大青森開拓団に属していたのなら、山中に遺棄された百人ほどは、その後全く消息が知れず、全員死亡と推定されている。
その中で、八歳の子供一人が助かるはずはない。まして、あれからすでに十年がたっている。
偶然手にした古い新聞の、引揚者消息欄で、親さがしをしていた武夫の記事を読み、問合せもせず一途にわが子かと長野まで来た正子の行動は、軽率というほかない。
しかし正子の日ごろの生活を聞くと、そうした行動に出た彼女の心情が、松三にはよくわかった。
夫に死なれ、三人の子供も失った正子は、孤独の身を姉の婚家の世話になって暮らしている。
周囲への気がねも多く、何一つ喜びのない彼女が、ただ一つ心の支えとして抱き続けてきたのが、満洲の山中に遺棄した子供の生還――という夢だったのである。
他人からは、全く可能性のない“夢”としか呼びようのないものである。
しかし、それをとりのぞいたら、この孤独な女は何を支えに生きてゆけばよいのか。松三は胸がつまった。
その夜、サキのかたわらに寝た正子は、高熱を発した。馴れない長旅に、かぜをこじらせたらしい。
四日間を、彼女はサキにいたわられて、床についていた。
起き上がってからも、まだ長旅は無理とひき止められるままに、正子は滞在した。
一時はわが子かと思った武夫に親しみを覚えるらしく、彼女は少年の僅かばかりの衣類を全部洗って、つぎを当てた。
サキが珍しく改まった顔で、松三の前に坐った。彼女は、正子を松三の後妻にしてはどうか、といい出したのである。
だめだ――短く答え、松三はにがい微笑を浮かべて首を横に振った。
あの人がいいの、悪いのということではない。おれには、女房を持つ気などない――。
松三は正子に深くあわれを感じ、その静かな人がらを好ましくも思った。
しかし彼には、再び妻を持ち、一人の人間の生涯をあずかる気持など全くなかった。
おれの生涯はもう終わっている――重い木材を運びながら、松三は改めて思った。淋しさはない。
長野駅で、出迎えの兄から、清乃はじめ家族全員の死を告げられた時を境に、松三は自分が全く違う人間になった、と感じていた。
それまでは、シベリヤの俘虜収容所にいた時さえ、体は衰えきっていても、生きて妻の許に帰ろうと、何事にも耐える強籾な意志を持ち続けていた。
だが妻を失ったと知って以来、彼は“意欲”と呼べるものを持ったことがない。
かって生涯をかけようと意気ごんだ一切が、空しかった。
以前には、周囲から積極性のある男といわれ、彼もひそかにそれを誇っていた。
それが一切のわざわいの基となった。何ということか。
国に尽し、一家の繁栄の基礎を築こうとしたばかりに、母を、妻を、子供たちを殺してしまったではないか――。
松三は自分を枯れ木のように感じた。風に倒されるまで立ってはいるが、もう新しい芽をふくことはない。
こんなおれが、どうして再婚などできるか――。
翌日、正子は松三の家を去った。
8 大崎良作と二人の妻――三十一年―― top
昭和三十一年の夏の夜、二十四歳のたくましい青年となった小川健吉が、眉を曇らせて松三と語り合っていた。
何事も明快に割り切る健吉としては、珍しいことである。
終戦の翌年、母・ヨネと共に十四歳で内地に帰った健吉は、伯父の許で成人した。
食糧難時代の農家は、金まわりがよかった。普通より二年遅れて中学を卒業した後、彼は高校へ進んだ。
そのころから健吉は、彼に土地を分け与えて農業につかせようとする伯父の意向に、従う気がなかった。
伯父の好意は、ありがたかった。しかし、たださえ狭い土地を二世帯に分けて、どうするというのか。
健吉の亡父が満洲へ渡ったのも、それを避けるためではなかったか。
うっかり狭い土地に縛りつけられたら、それきり身動きができなくなる――と、十七歳の健吉の若さが自由を求めた。
また「土地を与える」という伯父の決意に、ためらいのあることを健吉は感じていた。
シベリヤで死んだ兄への義理が、その遺児である健吉に土地を分ける義務感となっていた。
これもまた、健吉には重苦しかった。先祖が残したという田畑にも、義理人情にも縛られず、自分の力だけで自由に生きて行きたかった。
高校を卒業した健吉は、長野市の食料品店に勤め始めた。
母が口をさしはさむひまもなく、健吉がさっさと決めた就職であった。
商売のコツを覚え、僅かずつでも将来のため資本を蓄えようという計算である。
満洲時代の松三は、わが子と仲のよい健吉少年をかわいがったものだった。
帰国後の松三にとって、自決の場に居合わせたという秀子をのぞいては、亡妻・清乃について語ってくれるのは健吉母子だけであった。
健吉は、ソ連参戦の翌日、避難命令を受けて集合した黒台信濃村開拓団の二区で、姑と子供を乗せた馬車の手綱を握っていた清乃の姿を、鮮明に記憶に残していた。
気の毒なことになったものだ――力強く発達したあごを上げて、健吉が憮然とした顔でいった。
松三も眉をよせて、うなずく。
健吉母子と同じ引揚船で、当時二十八歳であった大崎鶴代がこの村に帰って来た。
避難行の途中で七歳の一人息子・勇を見失い、ただ一人故郷に帰った彼女は、小作に出て働きながら行方不明の夫を待った。
夫は十九年に応召し、朝鮮の部隊にいたはずだが、帰国後何年たっても連絡はなかった。
「死んでしまったのだろう」と周囲にいわれても、彼女は待った。
やがて人々は、行方不明の鶴代の夫のことなど忘れてしまったが、それでも彼女は待ち続けた。
十年がたった。そして突然、昨日になって、鶴代の夫・良作から帰国したという通知が村に届いた。
良作は新しい妻と子供を連れて帰って来る――と、健吉は松三に告げに来たのである。
この二人妻の難事件の解決をまかされた健吉の伯父が、思い余って、鶴代への報告役を松三に頼みたい、といい出した。
健吉はその使者である。
おれのような口ベたな者が――と、松三は何度かことわった。十年間を待ち続けた鶴代の心情を思えば、あわれがこみ上げてきて、松三はいっそうこの役に自信を失った。何といえば良いのか――。
なぜ良作は、二度目の妻を迎えたのか――松三はその無責任に怒りを感じたか、しかし、本人の話を聞いてみれば、何かわけがあるかもしれない、と思い返した。
松三の知る良作は一本気で、誠実な男であった。良作は鶴代が死亡したと聞かされたのではなかったろうか。
終戦後の混乱期には、ときどきこうした間違いがあった。
松三は、先に良作に会うことを条件に、この難役を引き受けた。
鶴代と二度目の妻と、この二人のどちらをも傷つけない解決策などあるわけもなかったが、松三はよく事情を呑みこんだ上で、三人の複雑な関係から生まれる不幸を、いくらかでも少なく食い止めたいと念じた。
事実だけを鶴代に報告すれば済む、というわけにはいかない。
松三と良作は、十二年ぶりに再会した。昭和十九年、満洲での良作の応召以来である。
二人ともまだ四十代のなかばのはずだが、顔に刻まれたしわに、びんの髪の白さに、それぞれの過去の苦難を読みとって、しばらくは無言だった。
良作はすでに、鶴代が十年間彼を待ち続けた事実を聞かされていた。
良作は首を垂れて語り出した。
朝鮮で終戦を迎えた良作は、満洲の開拓団に残した妻子を思って矢もたてもたまらず、混乱の極にあった部隊から単身逃れ出て、北へ向かった。
何度か死地をくぐり、飢えによろめきながら、彼が団の所在地にたどりついたのは一ヵ月半のもの、十月であった。
開拓団は本部、倉庫をはじめ住宅まで、すさまじい掠奪の跡を見せて、人影もない。
妻子の消息は知れず、周囲の満人部落でも誰も答えてはくれない。
絶望的な気持でさまよううち、良作は隣りの団になお数家族の日本人が留まっていることを知った。
日々、周囲の満人暴徒におびやかされているその団にたどりつくと、良作の子供が満人に連れられて行く姿を確かに見た――という者がいた。
良作は狂喜した。妻も無事でいたか、という彼の問いに、相手は冷笑を浮かべて答えた。
鶴代は子供を捨て、自分だけ避難してしまった――。
良作は逆上した。そんな女だったのか――。
この隣団の男のことばが、満人暴徒の襲撃に日夜生命の危険にさらされて、異常を呈した精神状態から発したものか、または全くの誤解であったのかは、不明である。
しかしこのひとことが、良作夫婦の仲をさく結果となった。
良作もまた人のことばを冷静に聞き分ける状態でなかったことが、不幸を深くした。
人一倍子ぼんのうな彼は、それからの三ヵ月を、狂気のように一人息子・勇を求めてさまよった。
この期間の良作の行動は子供への愛に貫かれていたには違いないが、繰り返される満人の迫害、飢餓の試練は妻への憎悪を燃えたたせもした。
林口の近くの部落で、遂に良作は、満人農家の豚追いをしているわが子を見つけた。
勇を抱きしめた時もまた、良作の心に妻への憎しみが燃えた。
獣医であった彼は、子供と共に現地に住みついた。
日本人の難民収容所は死体の山を築いているという情報が、この辺りにも伝わり、とても子供を連れて行ける場所ではないと判断された。
獣医として、良作は食べてゆけた。
偶然の機会に、良作は子供連れの日本の女を助けた。開拓団から逃れる途中、力尽きて一行からとり残された母子であった。
母のない勇は間もなくこの女になつき、良作もまた、自然に彼女と結ばれた。
翌二十一年から日本人の集団帰国が始まったが、二人はそれも知らずに暮らしていた。やがて子供も生まれた。
十年を過ぎた今、なぜ良作は帰国したのか。
彼は「あの国も変った。我々には住みにくい所になった」とだけいって、話を終わった。 |
松三が重い口を開いて、ソ連参戦後の鶴代の行動を語った。
| 鶴代の一行は、団を離れた日から敵機に襲われ、多くの死者を出した。二日目、山裾を進む一行はまたも敵機の機銃掃射をりけ、人々は馬車を捨て、先を争って山林地帯へ逃げこんだ。この時、鶴代と勇の、つないでいた手が離れた。あわてて子供を捜そうとする鶴代は、山林を目指して必死に走る人の波に呑まれ、突きとばされ、押し返され、爆音と機銃の音に意識も消されたらしく、気がついた時は大木の根元に身を伏せていた。敵機が去るやいなや、鶴代は死体の散乱する山裾へひき返し、声を限りに勇の名を呼んで捜した。答える声はない。負傷者を乗せた最後の馬車にせきたてられ「子供だから、弾の下を駆けぬけて、先へ行ったのだろう」という団員のことばにひかれて、鶴代は歩き出した。足を早めて先発隊に追いついてみたが、そこにも勇はいなかった。鷯代は再びひき返したが、今度はソ連戦車に道を断たれ、逃げるほかなかった。その後に続く連日の逃避行の、疲労と飢餓の中で、鶴代は次第に息子は爆死したものとあきらめていった。自分が生きていることさえ、はっきりとは意識できない状態であった。あの非常の時に、女にこれ以上を求めるのは無理だろう―― |
松三の口調は、無意識に鶴代の弁護になっていた。その現場にいた者も、引揚げている。この話にうそはない――。
良作は深くうなずいて、頭を垂れた。
今、さらに、妻を憎んだ自分が軽率であった――などということばは、口に出ない。
松三の前に坐って、鶴代はただ泣いた。十年の歳月を無に流す涙であった。
鶴代はその十年の間、夫の帰国を確信して待っていたわけではない。
とっくに戦死したかも知れない、と思いながら、それでも待ち続けたのである。
夫についての初めての知らせが死亡通知であれば、鶴代はこれほど混乱することはなかったであろう。
何もかもあまりに思いがけなかった。
一筋に待ち続けた夫が、長年自分を憎んでいた――といり事実に、まず彼女は驚愕した。
そして、いま夫は誤解をとき、鶴代に詫びている――と聞かされて、彼女はそれをどう受けてよいのか、全くわからなかった。
爆死したものとあきらめ、日夜その冥福を祈ってきたわが子は、十八歳の青年になってこの村に帰っている、と松三に告げられた。
胸に描き続けた七歳の勇の姿を、急にその青年に置き変えることさえできない。
だが、あの子が生きていた――という喜びは、混乱する鶴代の胸を灼(や)いてつき上げてくる。
静かな十年の歳月の後に、急に襲いかかった幾筋もの激流が渦を巻いて、激しく鶴代をゆする。
彼女に、それを整理する能力はない。ましてそれを表現することばなど、持ち合わせてはいない。
鶴代はとめどもなく涙を流し、松三は痛ましげに目を伏せて無言である。
長い時間が過ぎた。鶴代は涙を納め、意外なほど静かな声でいった。
わたしが、身を引きます――。
このことばに誘われたよりに、再び鳴咽が起こり、鶴代は畳に顔を伏せて、肩を震わせた。
数百年の昔から、あらゆる階級の日本の女が、自己犠牲によって窮状を打解しようと口にしたことばを、鶴代もまた心の底に探り当てて、口に出した。
このほかに、彼女はどのような生き方も思いつかないのである。
勇を、今日まで育ててくれた第二の母はありがたい――と鶴代はいった。
自分を憎んだ夫の気持も、無理はない。誰が悪いわけでもない。誰を恨むこともできない――。
鶴代が帰った後、松三はなお同じ姿勢で坐り続けていた。鶴代の最後のことばが、彼の胸に残っていた。
十年という月日も、国に捧げたと思えば、あきらめもつく――と鶴代はいったのである。
“国”とは、何だろうか。
良作夫婦が渡満を決意したのも、地主になる夢はあったにせよ、多分に「お国のため」というかけ声に影響されたからであろう。
そして営々築き上げた満洲の生活を、一挙につき崩したのも国ではなかったか。
その上、夫を失い、子供を失い、鶴代が一切の喜びを奪われたのもまた、国のせいではないか。
それでもなお彼女は、応召したままの夫を待ち続けた十年を、国に捧げたものとして、あきらめようとしている。
それほどに“国”とは、絶対至上のものなのか――。
これまでにも松三は何度か「開拓民にとって、国とは何だろうか」と、考えてみた。
それは常に、捉えようもなく巨大な、不可解ななにかであり、遙か高所から人民を見下している冷厳なものと感じられた。
その人民を殺す非情なもの、そんなもののために、微力を尽くそうと渡満の決意をしたおれが間違っていた――としか松三には思われなかった。
“国”とは、決して人間のしあわせをはかり、保護してくれる温かいものではない。
それを、開拓民の一人としてその非情をさんざん味わったはずの鶴代が、今もなお十年の歳月を、国に捧げたものとしてあきらめようというのか――。
9 在外財産補償に触れない給付金――三十一年・三十二年―― top
昭和三十一年、政府は「第二次在外財産問題審議会」を設ける一方、同年六月から、厚生省令第十三号により引揚者在外事実調査を実施した。厚生大臣は調査を全国都道府県知事に委託し、知事はこれを引揚者団体に委託した。その結果、八十一万五千三百三十世帯の調査表が厚生大臣に提出された。
三十一年十二月、第二次在外財産問題審議会は「法律上補償の責任ありとする意見と、法律上補償の責任なしとする意見の両論があり、いずれとも断定はできないが、審議の経緯からみて、主として引揚者がその全生活の基盤を失ったという観点から、引揚者に対して特別の政策的措置を講ずることが適切であるとの結論に達した」と答申した。これに従い、昭和三十二年五月「引揚者給付金等支給法」が成立し、約五百億円が記名国債として支給されることになった。
この法律の趣旨は「引揚者、その遺族及び引揚前に死亡した者の遺族には、この法律の定めるところにより給付金を支給する」と第一条で述べており、在外財産補償には全く触れていない。
神田厚生大臣の衆参両院の社会労働委員会でおこなった提案理由説明にも「在外財産補償のためではない」とある。
この金はなくした財産の補償でなく、我々引揚者の立上り資金だというが、結局、見舞い金、涙金ということか――小林吉太郎が、納得のいかない顔で加藤松三にいった。いくらかでも、もらっただけありがたいという者もあるか、この金額を十年に分けて受けとるのでは、資金として使えないじゃないか――。
引揚者が受けとる金額は、次のように区分されていた。
終戦時に
五十歳以上の者 二万八千円
三十歳以上の者 二万 円
十八歳以上の者 一万五千円
十八歳未満の者 七千円
死者に対しても、終戦時の年齢によって上の通りに給付された。
おれは終戦の時三十二歳だったから、二万円だ。それを十年で割ると、一年に二千円か。一ヵ
月では二百円足らずだ。いくらおれが貧乏でも、これで助かったとはいえない――吉太郎の声は暗かった。
松三には彼自身の分のほかに、母、妻、二人の子供の分か給付されることになった。
家族の死に対する、初めての国の行為であった。
松三はただ無性に悲しかった。何もしてもらいたくなかった。
また、熱心に補償金請求運動を続けてきた吉太郎たちとは違い、彼は何一つしたことかない。
それを思うにつけ、この金を自分のために使うことはできなかった。
松三は初めて兄に、金を貸してくれと頼んだ。
給付金を引当てに、十年先の分までを含む全額を、兄はこころよく貸してくれた。
何か仕事を始めるなら、もっと貸してやろう――という兄の前で、松三は黙って首を横に振った。
そんな気持は、将来とも彼のうちに起こりそうもなかった。
松三は兄に借りた金を、そっくり吉太郎に渡した。これで電気がひけるだろう――といわれて、吉太郎はやっと松三の意図を悟ったが、彼は金の包みを押し戻した。
とんでもない。これは受けとれない。この金は、いわばあんたのおっかさんや奥さんへの、国からの香典じゃないか――。
だからこそ、受けとってくれ。とてもおれに使える金じゃあない。
この家に電灯がついて、夜も子供が勉強できるようになれば、仏への供養になる。清乃も喜ぶだろう――。
やがて、吉太郎の小屋のある河原に、真新しい数本の電柱がたち並んだ。
夏の夜、小屋は四方に明るく電灯の光を放って、遠目にはほたる篭のように見えた。
三十二年の引揚者給付金で電灯を引いたのは、吉太郎の家だけではない。
北軽井沢開拓村の旧駅馬団員たちの家も、この金によって急に明るくなった。
これは、とにかく国家が我々に払ってくれる金だ。有効に使おう。
しかし一人一人がこの金額を握っても、何もできまい。全部をひとまとめにしたら――。
かって敗戦直後の石租子の難民生活で、個人の金を全部供出して集団生活を営んだ彼らである。
この伝統は、戦後の国内開拓の生活にも生かされていた。
いま、一番必要なものは何か――全員が電灯敷設を望んだ。
一人の反対者もなく、記名国債が集められ、それを担保にして国民金融公庫から金を借りた。
牛のやつ、初めて電気見て、たまげてらあ! 子供たちまでか、明るい夜にはしゃいだ。
しかし言論界は「引揚者給付金等支給法」の成立に批判的であった。
各新聞は「今や戦後ではないのに、引揚者だけを特別扱いする必要はない」という主旨の社説をかかげた。
10 読書村の灰色の拓魂碑(たくこんひ)――三十四年―― top
長野県読書村の故郷に帰りついた西尾さと、加藤きよ江は、シベリヤから帰還したそれぞれの夫を迎えて、静かな主婦の座に戻っていた。
かって開拓団の指導員であったさとの夫・西尾春太郎は、読書村自興会の会長として、引揚者の援護に力を尽している。
木曾川沿いの天白台の中腹に立って、さとときよ江は、真新しい灰色の拓魂碑と、そのかたわらの白い殉国慰霊塔を見上げ、いつまでも動かない。
昨日、昭和三十四年九月十五日に除幕式を済ませたばかりだが、二人は今日も連れだって、ここに来た。
二十一年に引揚げて以来、片時も忘れ得ない満洲での犠牲者のために、この村の引揚者二十人が中心となって、長い年月をかけ、やっと建立したものである。村役場をはじめ多くの村民から寄付がよせられ、町長・鈴木常雄が碑文に筆を振った。
さとが声に出して、拓魂碑の文字を読んだ。 |
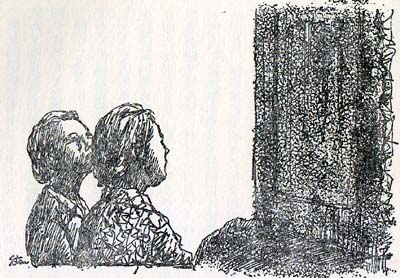
真新しい灰色の拓魂碑を訪れる西尾さと、加藤きよ江
|
「読書村は当時国策に応え、新しい村造りを村是として分村計画を樹て、大陸進出に踏みきった。
是がため先遣隊員二十名は昭和十三年七月、満洲三江省樺川県公心集に開拓の第一歩を印した。
爾来二星霜、受入体制は整い、終戦時には戸数二百戸、人口八百十四名、報国農場隊員四十名に達したが、その間未開地の開拓事業は筆舌につくせぬ苦難を記録にとどめつつも、これを乗り越えた」(原文のまま) |
二人は顔を見合わせた。開拓初期のつらい日々が、そして年ごとに広がった耕地の緑が目に浮かんだ。
さとは、次を読み進んだ。
「しかるに逆転した戦局は昭和二十年八月、終戦を告げ、此の日を境に、営々辛苦、文字通り血と汗によって築き上げた分村読書村は悲運の深淵に落ち、すべてのものを放棄した。ことに方正県に於ける飢餓と病魔は悲惨をきわめ、生地獄と化し……」
その生地獄を、手をとり、助け合ってくぐりぬけてきた二人である。
紙と鉛筆がほしかった――と、さとがいった。収容所の思い出である。
人々がうそのように多数死んでゆく中で、彼女も生きて故郷に帰りつく自信はなかった。
いつ死ぬかわからないが、せめて敗戦後に目撃した事実を書き残したい、と彼女は望んだ。
“国士(こくし)”とまで呼ばれ、軍人なみの壮行会を開いて送り出された開拓民とその家族が、ひとたび敗戦となるや、どのような扱いを受けたか。せめてそれを記録に残し、内地の人々に知らせたい――と願ったのである。
しかし命をつなぐ物資さえ入手困難な収容所で、紙や鉛筆が得られるわけはなかった。
帰国後、何年たっても、二人は会うたびに「よく生きて帰ったもの」と語り合った。
命のせとぎわに立った人間が、人間でない生きものに化すさまを、いやというほど見てきた二人である。
その中で結ばれた友情は、帰国後もなお二人を固く結んでいた。
軍人には叙勲があり、新聞には遺骨収集や現地墓参の記事があるが――と、さとはきよ江に語りかけた。
関東軍に置きざりにされ、無惨に殺されていった開拓の仲間を思って、さとの声に怒りがこもっていた。
軍人の遺家族には田畑がそのまま残されているが、故郷の生活の根をたち切って渡満した開拓民の遺家族には、それもない――と、きよ江がいった。
満洲に残った娘さんたちは、どうしているか――二人がいた方正の収容所から、姿を消した娘たちである。
その多くが満人の妻となり、中には祖国に帰りついた親と文通している者もあった。
里帰りを希望する者もあるが、日本の親元から送金しなければ帰国できないなど、実現には多くの困難がある。
むごいこと――と、きよ江がいった。だが内地の人には、敗戦のみじめさも、むごさも、本当にはわかっていないのではないかしら――
長野県下の木島平村に住む高山すみ子も、シベリヤから帰った夫と共に再び平和な家庭を築いていた。
帰国後に、子供二人も生まれた。
すみ子は、佐渡開拓団跡で射殺された子供たちの生れかわりとも思って、その弟たちを大切に育てている。
彼女にとって、何もかもが尊かった。満洲の収容所で夜ごと夢に見た故郷の山河に囲まれ、再び会う日があろうとも思わなかった夫と語り合う生活は、一度海中に落とした真珠を再びとり戻したほどの、まれな幸運と思われた。
しかし、時には「えらいもんだ。わが子を撃ち殺して、自分だけ無事に帰ってきた」などという村人のことばも耳にはいる。
すみ子は唇をかんで、耐えた。
経験のない人には、わからないのだ。何といわれようと、私には支えてくれる夫がいる。
子供たちもいる。佐渡開拓団跡で死んだ仲間のことを思えば、もったいないほどしあわせだ――。
11 地獄を見てしまった女――三十六年・三十七年―― top
「もう帰らなければ……」前田文子はすでに何度か口にしたことばを、また低くつぶやいた。
だが立ち上がる気配はない。彼女の前に坐った松三も、無言のまま動かない。
文子は二十五歳になっていた。これまでに、いくつかの縁談をことわってきたが、今度は、帰国以来世話になっている叔父からの話で、その息子――文子とは同年のいとこの嫁にと望まれた。
今までのように、気が進まないとことわれる相手ではない。
だが、どうしてもいやだ――と、文子は松三の前で泣いた。松三はなお、無言を続けている。
文子か叔父の家を出て、松三の家に住まわせてもらいたいと望んでいることは察しられたが、彼はそれを承諾することをためらっていた。
文子の叔父と気まずくなることなど、松三は少しも構わない。
だが、たださえ周囲となじまず、二十五歳の今日まで結婚する気持も持たなかった文子を自分の手許にひきとっては、ますます彼女の将来を閉ざすことになりはしないか。
文子の“かわり者”といわれる性格は、敗戦直後の満洲で少女の心に焼きつけられた不信感が基調になっている――と松三には思われた。
文子自身、何度もそれを彼に語っている。
敗戦国民として地獄を見てしまった自分と、それを経験したことのない内地の人とは違うのだと、彼女は常に周囲と自分とを隔てているが、その気持を捨てなければ、しあわせは得られないのではないか――。
文子は叔父の家を出て働きたいというが、村の農家は叔父への気がねから雇ってはくれず、世間のせまい彼女は都会へ出る手がかりも持たない。
戸口をたたく音に、文子は身を固くしたが、夜ふけの訪問者は健吉であった。
健吉は泣きはらした文子のまぶたの赤さにも気づかず、松三を相手に明るく新しい仕事を語り出した。
彼は食料品店を円満に退職し、その店の援助を得て、工員相手の食堂を開こうとしていた。
やがて、文子を家まで送ることを頼まれた健吉は、彼女と連れだって帰っていった。その後姿を見送る松三はふと、文子が 健吉の店で働いたら――と思った。健吉はかねがね食堂経営にあたって、信用できる助手を欲しがっていた。
息子の食堂を手伝う気になっている母親を彼はもてあまし「満洲の難民生活以来、おふくろはすっかりボケた」といっていた。
母親のヨネは、当時十三歳であった健吉を頼りに、とにかく生きぬいて祖国に帰りついたが、その間の心身の消耗はほとんどとり戻されることなく、彼女に定着してしまった。
同じように満洲で敗戦国民になった者も、その影響の受け方はさまざまだな――仏壇の前に坐った松三は、改めて思った。
松三のように、満洲で妻子に死なれた者も、大部分は再婚して新しい生活を築いている。
それを心から祝福して眺めながら、松三自身にはそれができない。
同じ十歳前後の年齢で敗戦を味わった健吉と文子も、受けた影響は全く違っている。
肉親のすべてが斃死した中でただ一人生き残り、満人のひき止め策に抗し続けて遂に帰国の目的を達した文子は、他人を受け入れられないかたくなな心を残して、孤独に生きている。
だが健吉は、生来の明るさを少しも失っていない。
彼もまた「引揚者の気持は、他国で敗戦を経験した者でなければわからない」といいはするが、それがかえって彼の自信の基盤にさえなっている。
十三歳で、地獄の中を生きぬいてきたおれだ。
あの当時を思えば、どんな難関も乗り越えられる――という自負が、常に健吉の行動に積極性を与えている。
この二人が一緒になったら――と松三は思いついた。
単に仕事の助手ではなく、文子は健吉の妻としてふさわしいのではないだろうか。
文子は常に、内地だけで暮らしてきた人々と自分とを異人種のように区別して親しまないが、健吉なら開拓民の子供として、彼女と同じ経験を持っている。
彼ならば文子を理解し、その心を固く覆っている殼を突き破ることかできるのではないか――。
だが松三は、この考えを口に出すことなく、健吉に助手として文子をすすめるにとどめた。
よかれと思ってしたことも、どんな結果を生むかわかるものではない――松三は何によらず、運命を左右することに本能的な恐れを感じた。
数ヵ月後に健吉は、文子の仕事ぶりに満足していると松三に報告した。
文子は責任感が強く、さすがの健吉か“しぶとい”と嘆声をあげるほどの根性を示した。
翌三十七年春、健吉と文子は結婚した。健吉は三十歳、文子は二十六歳になっていた。
松三の喜びは深かったが、相変わらず彼はそれをおもてに現わさず、仏壇に向かって二人のしあわせを祈った。
文子はやっぱり変わり者だ――ときどき健吉は微苦笑と共に松三にもらした。
結婚後も文子は、周囲の人の好意を素直には受けられず、冷遇されることにむしろ安らぎをおぼえるらしかった。
「好意を示さない人は、嘘をついていないからいい」と文子はいうのだが、ただ一人の例外として扱われる健吉は満足していた。
翌年、文子は男の子を生んだ。満洲で死んだ彼女の祖母の遺言通り、文子によって前田の家の血筋は伝えられた。
12 仏門に帰依した引揚者、山本慈昭――三十八年―― top
昭和三十七年一月、引揚者団体全国連合会(全連)は、在外私有財産補償請求登録運動を開始した。
この年四月二十七日が、平和条約発効時から十年目にあたり、請求権がもし民法上の権利であるとすれば時効になるからである。
この登録運動の開始により、在外私有財産補償獲得運動は一段と活発になった。
この前年、三十六年四月に、全連は一兆二千億円という最初の要求額を打ち出していた。
その根拠は、終戦直後の二十一年、大蔵省がおこなった引揚者の在外財産調査によると、総額約三十億ドル、これを現在の為替レートで換算すると約一兆八百億円になり、それに未届け分を推定して加算した数字である。
これに対して大蔵省は、三十億ドルは終戦当時の為替レートで約三百五十億円となり、これ以上は出せないという態度をとった。
両者の間には、埋めようもない大きな差があった。
政府は三十二年に“立上り資金”を給付して以来「この給付金によって、引揚者の在外財産問題は処理済みとする」という統一見解をとり、三十六年二月の衆院予算委での水田蔵相答弁、三十八年三月の黒金官房長官の記者会見、四十年五月の参院大蔵委での田中蔵相答弁で、これを繰り返し言明してきた。
新聞を熱心に読みあさる小林吉太郎は、政府がこういうハラでは我々の運動はだめか――と失望し、またこれらの発言を問題にせず、全連が示す膨大な要求額に、目を見張った。
吉太郎には、政府がいったんこうと態度をきめたからには、その面目にかけても変更はできないだろう、と思われた。
彼の素朴な推察をよそに、在外財産補償問題は二転、三転しながら大詰へ進んでゆく。
昭和三十八年秋、長野県下伊那郡天竜村の平岡ダムを見下ろす高台に、中国人殉難者慰霊碑が建立され、その除幕式に中国紅十字会常任理事会の倪斐君(げい・ひくん)女史が出席した。
下伊那郡阿智村駒場、長岳寺住職・山本慈昭が、戦時中この地で死亡した外国人捕虜の遺骨収集に努めた結果である。
この中には六十二人の中国人捕虜がいた。
山本は満洲国東安省宝清県北哈嗎(きたこうま)阿智郷(あちごう)開拓団の小学校の教員であった。
ソ連参戦によってひきおこされた混乱の中を、五十人余りの生徒を守って逃げる途中、彼の妻と二人の子供は死んだ。
彼自身はソ連に抑留された後、待つ人もない故郷に生還した。
満洲の山野に、虫ケラのように果てた肉親、同胞を思い、山本はひたすら彼らの冥福を祈った。
せめて遺骨だけでも――という願いも叶えられる望みはない。
こうしたある日、山本は故郷・下伊那にも、祖国を恋いながら無残に死んでいった外国人多数のあることを知った。
電力増産の国策で天竜川下流の平岡ダム工事に、多数の連合国軍捕虜が投入された。
過労と栄養失調、工事場の事故などで、その多くが死亡した。
戦争が終わっても、犠牲者の名簿は焼きすてられ、遺骨は四散したまま、葬う人もない。
満洲で死んだ開拓団員やその家族と、全く同じではないか――山本はこの日から困難な遺骨収集を始めた。
それを肉親のいる祖国へ送り届けるのが、彼の念願であった。
昭和三十九年秋、山本は仏教界の代表として中国へ渡った。
六十二柱の中国人捕虜の遺骨は、山本の手で祖国に帰った。
山本は阿智郷はじめ旧満洲で死んだ開拓団員の慰霊のため、その最後の地を訪れたかったが、中国東北部への旅行は許されなかった。
万里の長城で、彼は心をこめて国策の犠牲となった同胞へ読経を捧げた。
13 満人の妻となった娘と再会――四十一年十一月―― top
全国の開拓民送り出し数三十二万のうち、約三万八千を出して一位を占める長野県は、戦後二十年をすぎても、中国との間に開拓民と関連した種々な運動が続けられている。
満人と結婚した日本女性の里帰り希望者には、県が旅費の半額を負担しようというもの、戦時中に長野県で死亡した中国人捕虜の遺骨と、旧満洲で死亡した日本人の遺骨を交換しようというものなどが、それである。
昭和四十一年十一月には、信濃毎日新聞社が推進体となり、日中友好協会の計らいで、引揚者の代表十六人が犠牲者慰霊のため中国に渡った。
この中に、もと更級郷(さらしなごう)開拓団の小学校教員・塚田浅江もいた。
常に浅江の念頭を離れないのは、佐渡開拓団跡で木槍を手に、ソ連兵に向かって躍りこんでいった教え子たちの姿である。
子供たちは食糧も尽きた逃避行に「先生、おなかすいたァ」と訴えながら、よろめき歩いた。
畑に残されたとうもろこしを見れば、むしゃぶりついて生のままかじり、泥水を飲み、下痢を続けながら必死で大人の歩行に遅れまいと努めた。
おなかすいたァ――という声は、二十年を経た今も、浅江の耳に生々しくよみがえる。
浅江は旅の荷物の中に、子供たちの霊に供えようと、故郷の菓子落雁(らくがん)を入れた。
一行はハルピン、長春(もと新京)、瀋陽(もと奉天)とまわった。
彼らは同胞の慰霊祭を行うつもりで中国に来たのだが、もとの満洲国にあたる中国東北部に足を踏み入れることはできず、他の土地での慰霊祭もなかなか許可されなかった。
「日本との戦争で中国側はどれほどの犠牲者を出したと思いますか」という案内者のことばに、浅江は改めて戦禍の深さを思い知らされた。
ハルピンを去る時期も迫ったころ、ようやく慰霊祭が許可された。
ハルピン郊外の、人影もない松花江の河畔が選ばれた。
日本人一行は、花束を河に流し、それぞれ合掌して敗戦による犠牲者の冥福を祈った。
河畔に立って、浅江は改めて人の命のふしぎを思った。
敗戦から二十一年たった今、自分は日本で平和な生活を送り、犠牲となった人々の慰霊のため、ここに来ているが、彼女自身が冥福を祈られる立場にあっても、何のふしぎもなかった。
むしろその方が自然であった――と、浅江は一冬を過ごした勃利(ぼつり)の収容所を思い浮かべた。
幼い教え子の生き残りを連れて収容所にたどり着いた浅江は、手榴弾の破片で右の目を失っていた。
与えられる食糧は、朝と晩に小さなコーリャンのお握り一個ずつである。
子供たちの命をつなぐため、浅江は片目で靴下を編み、仕事を求めて満人の家から家へさまよった。
にれの葉をむしって食べ、道ばたに捨てられた卵の殼までを口に入れる子供たちを見て、浅江は何としても守りぬこうと心に誓った。
みな親を失った教え子たちである。
浅江がついていなければ、朝晩の小さなお握りさえ、子供たちの手には渡されないことがあった。
大人たちも、飢餓(きが)に“人の心”を失っていたときである。
子供たちは一人また一人と幼い命の火を消し、内地まで連れ帰ったのはそのうちの三人に過ぎなかった。
――子供たちを生かすために、私も死んではならない、という気持に支えられて、自分は祖国に帰り着いたのだ――。
飛行機が長春につくころから、一行の中の加藤ふみは興奮していた。
ふみは終戦の年ここに残した八歳の女の子との再会を期待しているのだが、彼女はその娘について、住所をはじめ何一つ知らない。
別れた時の年齢と日本名前だけが頼りの、雲を掴むような話である。
しかし中国側の好意で、それらしい女性が見つかった――という知らせが来た。
やがて慰霊団の宿舎に、子供を抱いた二十七、八歳の女が現われた。
ふみは彼女の方へ駆けよったが、その顔には次第に困惑の色が現われた。
二十年会わなかったとはいえ、これがわが子の成人した姿とは思えないが――。
通訳が伝えるその女のことばで、ふみの疑いの正しいことがわかった。
女は――自分は日本人の子で、八歳で満人にもらわれたが、母は収容所で死んだ。ふみの娘でないことは明白だが、日本人に会いたかったので、ここに来た――と語った。
女はふみの失望に同情したらしく「日本人をたくさん知っているから、ふみの娘を捜せるかもしれない」とつけ加えて、くわしく説明させた。
やがて彼女は心当たりがあるといって帰った。
長春の滞在時間が間もなく終わろうとする時、また二十七、八歳の女が日本人宿舎に現われた。
その顔を一目見て、ふみはいきなり抱きついた。
満服をつけたその農婦の顔が、八歳の童女の顔とぴったり重なったのである。
二人は固く抱き合って、ただ泣いた。
何を話そうにも、通訳を頼まなければ、ひとこともことばの通じない親子であった。
三十分たらずで、出発の時間になった。
二十年ぶりで娘と再会したふみだが、一人だけこの地に留まる自由は許されない。
聞きたいこと、話したいことは山ほどあるが、二人には何をする時間もない。
手を振りながら顔も覆わず泣くふみを乗せて、自動車は飛行場に向かった。
塚田浅江は各地で、この国に残った日本女性と語り合った。
その多くが娘盛りに敗戦を迎え、満人の妻となった女たちである。
今は中年の主婦となり、その子供たちは母の祖国も知らず、紅衛兵旋風の吹きすさむ中国の若者として育っている。
日本の女性たちはみな祖国を懐しみ、それぞれの故郷の様子をたずねたが、彼女たちの望むものが単に里帰りではないことを、浅江は知った。
――私たちも故郷は恋しい。一度は帰りたいと思う。しかし中国と日本が今のままの関係では、姑息な手段でほんの一時帰国するに過ぎない。私たちの子供は中国人であり、中国の次代を担う者たちである。母の祖国である日本と中国とか、国交を回復することこそ、私たちが最も希望するところである。この二国の人民が手をつなぐために、できるだけの努力をしたい――と、彼女たちの多くが語った。
かつて幼い日に親に連れられて満洲に渡り、敗戦後、身を捨てる気持で満人の妻となった彼女たちは、その後の二十年間で、新しい中国女性に生まれ変わっていた。
14 旧駅馬開拓団の新しい夢――四十一年十二月―― top
昭和四十一年十二月、完成したばかりの北軽井沢開拓農業協同組合の事務所は、薄くかぶった雪に朝日を受けて輝いていた。
組合の専務理事・永井鎌二は、正面のガラス扉に金文字で書かれた組合名にしばらく目を止めた後、ひと気もない内部にはいった。明日は開拓二十周年記念祭と併せて、この事務所の落成式が行われる。
二十年か――。
組合長・清水圭太郎の名で印刷された「挨拶状」を前にして、永井は過去をふり返る顔になっていた。
帰国後、永井と改姓した彼は、満洲の駅馬(えきま)開拓団時代の星野経理指導員である。
終戦の時、彼は応召中であった。母・星野かねが石砠子(せきそし)での難民生活に耐えぬき、いよいよ帰国となって吉林までたどりつきながら、コレラで死亡したことを、永井は復員後に知った。
満洲時代の仲間が再度の村づくりに邁進しているという北軽井沢に駆けつけ、駅馬時代そのままに清水圭太郎の片腕となって、この困難な仕事を推進してきた。開拓二十周年記念祭の挨拶状の一字一句が彼の胸に響く。
| 「……顧りみますのに、昭和二十年八月十五日、祖国日本の敗戦以来きびしい占領下の環境の裡にあって、引揚者、戦災者、復員軍人など、いわゆる戦争犠牲者たちか国策の示す処にしたがい、この浅間山麓の不毛の火山灰地に入植して、祖国の再建と自己運命の開拓のために、不退転の開拓魂の下に闘ってきました。言語に絶する苦難の道を切り開いて営々苦節ここに二十年、この間、同志のうちには不幸にして病に斃れたるもの数十名、酷薄不遇の難路に志を中道に捨てて離農した者若千名を出しましたが、その遺志をたくましく継いで、現在戸数百六十八戸、約六百ヘクタールの耕地を拓き、約六百ヘクタールの附帯地を管理し、酪農と高原野菜の栽培を主体として……」(原文のまま) |
農産粗収入は年額二億数千万円、乳牛は七百五十頭に達した――と、永井は改めて現在の成績を眺めた。
四十二年度の粗収入は優に三億に達し、乳牛の数も九百頭を越すはずである。
今日までの借入金の負担は決して軽いものではなかったが、しかし二十周年を迎えた現在のこの成績は、一応満足すべきものといえよう――永井は明るい表情で、村の見まわりに出かけた。
開拓地蔵尊のある広場に雪かきの人々の姿を認めて、永井は車を止めた。
地蔵尊を安置した昭和二十六年にはまだ小さかったかたわらの松が、今は根元から分れた三本の幹を遙かな空に伸ばして、傘のように枝を開いている。
青年の一人が、地蔵尊の左にたつ物故者名碑の雪を払った。
四段に分けて書かれた満洲での犠牲者名の中には、永井の母・星野かねをはじめ、酒づくりの名人であった福田団次、逃避行の第一日目に伝令となって敵弾に倒れた筑井梅乃の名前もある。
昭和三十六年、第十七回忌法要記念に建立された碑である。
永井はまた見まわりの車に乗った。
この村には旧駅馬団員のほかに、満洲の北安省海倫(ハイロン)県の海倫駅馬村開拓団の引揚者、東京の戦災者、地元農家の二、三男などがいる。
ほぼ同じ条件で入植しても、発足から二十年たった今、各戸の成績にはかなりの差があった。
成功者は一戸で二十頭からの乳牛を飼っている。
今も海倫集落と呼ばれる地域に、協同で建てられたルーズバレ畜舎が見えてきた。飼料を積んだトラックが止まり、青年たちが雪の中で敏捷な動きを見せている。
永井の車はその横を通りぬけ、個人所有の牛舎の並ぶ地区へ進む。
凍りついた冬のさ中にも、永井には二十年の蓄積の厚みが感じられた。
おれたちの村も、ここまでになったか――明日の記念祭を前にして、彼の思いは深かった。
海倫の人たちは、満洲で文字通り未開墾地を拓いたのだが、おれたち駅馬帰りの者は、この浅間山麓で初めて真の開拓をした、といえるのではないか。
我々が村づくりを始めるまで、ここは不毛の地として人々にかえり見られない場所だった。
開拓とは未墾の地を切り拓くことであるとすれば、駅馬で我々がやったことは“国策“の名で奪った満人の土地への入植に過ぎなかったのではないか――。
満洲の駅馬開拓団の建設時代はすでに二十五、六年の昔になったが、古い思い出の中の一つの顔を、永井は今も忘れることができない。
満人農家で出会った老婆の、白髪の乱れかかるしわの深い顔である。
昭和十五年に入植した吉林省磐石県駅馬村は、駅馬五山に囲まれた高原の盆地で、面積二万三千町歩、人口は満鮮人合わせて約七千であった。
日本人の開拓団用地と指定された地域の一部はすでに満人の手で拓かれ、彼らが住みついていた。
しかし関東軍を後だてとする満洲拓殖株式会社がここを選定した以上、満人はいや応なく立ちのかなければならない。
“買上げ”ではあるが、日限つきの立退き強制であり、買上げ値段も二束三文であった。
当時、経理指導員であった永井は、これら満人農家をまわった。
“買上げ”るためである。
そのうちの一軒から老婆が走り出てきて、地面に坐り、両手を合わせて永井を拝みながら何事かを懇願した。
満語はまだおぼつかなかったが、永井には老婆の願いがよくわかった。
涙を浮かべてかきくどく老婆は、追いたてないでくれ、と家庭の事情を述べている。
しかし、永井の一存ではどうすることもできなかった。
彼は、当時まだ内地に残していた母の姿を思い浮かべて、ことばもなく立っていた。
その無言を拒否ととった老婆は、いきなり額を地にうちつけた。
二度、三度と鈍い音が続き、老婆の泥まみれの額はたちまち血の色に染まっていった。
永井の止めるのも聞かず、彼女はその動作を繰り返し、そして彼に向かって手を合わせた。
いつか老婆は、声をあげて泣いていた。
五族協和を目標に渡満した我々だが、これでは関東軍の侵略の手先ではないか――若い永井の心は暗かった。
満洲での日本人開拓史の第一ページにこのような汚点を残して、果たして我々の子孫は末長くこの国で繁栄してゆけるだろうか――。
祖国に帰還して知った敗戦直後の開拓民のむごたらしい受難は、永井の心を凍らせた。
肉親や仲間を殺されたことに、当然強い憤りが湧いた。
しかし心のどこかに――受けるべくして受けた不幸な報いではなかったか――という声があって、彼の気持はいっそう救いがたいものになった。
北軽井沢の開拓村に加わった時、この土地の持つ不利な条件は少しも永井をたじろがせなかった。
開拓が荊(いばら)の道であることを、彼はよく知っていた。
利用されずに捨ててある土地を拓くのは、生やさしい仕事であるはずはない。
当然、苦難を伴うが、しかしそれだけの価値のある仕事、と彼は信じていた。他の人々も同じである。
かって満蒙開拓民であった一世が基礎を築いたこの農産協同組合は、やがて二世、三世にひき継がれて発展し続けなければならない。七十歳を過ぎてなお衰えを見せないかっての駅馬団長・清水圭太郎をはじめ、初代の人々が最も力を注いでいることの一つに、開拓後継者の育成がある。
その中には幼い日に満洲の収容所の苛酷な生活を味わい、母に伴われて祖国に帰った者もある。
また内地で生まれた子供たちも、上は二十歳に達した。
いずれにせよ、若い世代は満蒙開拓の経験を持ってはいないか、しかし彼らの血に両親の奮闘の歴史は伝わっているはずである。
また不利な条件を持つ北軽井沢での開墾が、彼らの心身を鍛えたはずである。
ここの子供たちは、開拓士として筋金入りだぞ――と、大人たちは期待の目を注ぐ。
やがて人数がふえてくれば、ここに固まってはいられない時代が来る。親の血をひいて、勇敢に新しい土地を拓いてくれ。
戦前すでに親たちは、鍬をかついで海外へ出たものだ。
どうか二代目、三代目も、広く世界を見まわして、まだ人間に利用されていない土地を、人間に幸をもたらす土地につくり変えてくれ。
これは最も男らしい、意義ある仕事ではないか。
そして、他国で開拓にあたるには、その国の民族との真の融和が繁栄の基礎だということを、肝に銘じて忘れないでくれ――。
この村から、すでに一人の青年がアメリカに渡った。組合の指導者たちが南米諸国の移住事情を熱心に研究しているのも、二世、三世の将来と結びつけてのことである。
満蒙開拓の夢は、多くの犠牲者を出して無残に消えたが、彼らはあの時代につちかわれた開拓魂を二世、三世に伝えて花咲かせようと、新しい夢を抱いている。
15
「これで戦後処理にケリをつける」(佐藤首相)――四十二年―― top
昭和四十一年十一月、第三次在外財産問題審議会(会長・山田義見)はその答申の中で、引揚者が外地で失った財産を国が補償する義務は“法的にはない”と述べた。
しかし引揚者が生活の基盤を根こそぎ奪われたことなどを考慮して「特別交付金を出すべきだ」と、政府に政治的配慮を要望する内容であった。以後の補償問題の動きは、この答申に基づいている。
その翌月、十二月二十三日に、引揚者団体全国連合会はその主催する大会で、六千億円という要求額を決めた。
三十六年に打ち出した要求額一兆二千億円の半分である。
その根拠は、農地報償の総額が国の田畑買上げの約十三倍に決定しているので、それと同じ計算方法をとったものである。
これに対し大蔵省は、引揚者一世帯あたり十万円、総額九百五十億円か限度だと応じた。
これは三十六年に大蔵省が示した三百五十億円の二・七倍強にあたる大幅の譲歩である。
昭和四十二年四月十八日、塚原総理府総務長官、西村自民党政調会長、植木在外資産問題議員懇談会長の三者会談で、支給の範囲を――終戦当時十八歳以上の者に限り、年齢別に四つの段階を設けて、高齢者ほど厚くする――という原則で一致した。
「六千億円補償ならびに全連法案要求貫徹引揚者全国大会」を前にして、この運動に参加している全国の引揚者たちは本格的な動きを見せ始めた。
動員を予定された二万人のうち、半数の一万人は特別行動隊である。
小林吉太郎は、長野県の特別行動隊の一人として上京した。
戦後二十年がたっても、彼はまだ極貧からぬけ出せずにいた。
シベリヤ抑留で痛めつけられた肉体は、二度と完全な健康体には戻らなかった。
親子がやっと食べてゆく生活の連続である。
その中で彼は、これ一つが生きがいであるかのように、補償金獲得運動に努力を注いできた。
彼のこの態度は、周囲から決して温かい目では眺められなかった。
――いつまで戦後だと思っているのか。戦争の被害を受けたのは、満蒙開拓民だけではないぞ――こうしたことばを吉太郎は何度か浴びせられた。
――引揚者はすでに立上り資金をもらっているではないか。原爆被災者の援護、空襲で死んだり家を焼かれた人々への救済、強制疎開で家を壊された人々への対策などが、まだ残っているのだ。引揚者ばかり勝手なことをいうな――。
違うのだ。全く立場が違うのだ――と、吉太郎はいいたい。
おれたちは国策だといわれて満洲へ渡り、敗戦直後には肉親や多くの仲間を無残に殺され、その上、やっと築いた財産は国が賠償に当てて他国へひき渡してしまったのだ。
内地で戦災にあった人たちも気の毒だ。だがおれたちの立場は、それとは全く違うのだ。
“国”が済まなかったと頭を下げて、在外財産を補償するのが当然ではないか――。
政府は、引揚者の在外私有財産を賠償の引当てにしたとはいっていないぞ。
サンフランシスコ条約の中にも、そんな文句はないそうだ
――という声に対しては、吉太郎は返すことばもない。条約、法律などというものは、そんなに冷たい、身勝手なものなのか――。
「サンフランシスコ条約第十四条(a)2の規定するところは、連合国が日本関係の一定の財産を処分する権利を有するというだけのことであって、日本国の支払うべき一定の損害賠償債務額が客観的に存在し、その一部として在外日本財産の処分額を見込むことにより、国がそれだけの債務を免れたということではない」
などと読み聞かされても、吉太郎にはわけがわからない。
敗戦と同時に所有者であった自分の手を離れ、外国に処分されてしまった財産は、賠償として取られたのだ――としか彼には思いようがなかった。
それに、おれなどにはその理由はわからないが、京大名誉教授・大石義雄や一橋大学教授・大平善梧など、たくさんの学者も、賠償の引当てだと認めているではないか――吉太郎は、どうしても補償という名目で“国”の金をもらうべきだ、と心を高ぶらせながら、東京に向かう汽車に揺られていた。
五月九日、自民党本部前の集会から、十一日、日比谷音楽堂での集会まで、吉太郎は人波にもまれながら、あまりに大がかりな運動に気を呑まれていた。読み上げられる宣言文も、きれぎれにしか彼の耳にとどかない。
「在外財産問題審議会は、在外資産という“物”と、引揚者という“人”との特別の意味と価値を強調し、これらの財産とその喪失者に対し、国の責任で特別措置をもって最終解決するようにと答申している。
すなわち、これらの財産とその所有者の負担によって、わが国は賠償支払いを免れ、これが起因となってわが国の平和回復、再建に貢献したことを、答申は裏付けしている。この審議会の精神に則り、議員連盟はさきに在外財産補償総額を六千億円に決定し、これを公表した。また総選挙で自民党公認候補者は六千億円を公約した。党員の公約は党の責任で……」 |
当然の要求なのに、こうまで運動しなければ“国”は承諾してくれないものか――という疑問が、ときどき吉太郎の頭をかすめた。
この運動の第一日にあたる九日、自民党の有志議員で結成されている在外財産問題議員連盟(代表幹事・永山忠則)は、総額三千百四十二億円の要求を決めた。対象は引揚者全員で、年齢別四段階である。
五月十七日、自民党の正式機関である在外資産問題議員懇談会は、総額二千五百七十九億円という案を決めた。
対象は引揚者全員で、年齢別五段階である。
六月七日、水田蔵相と塚原総理府総務長官が会合して、それぞれの案を出した。
大蔵省案は千百二十六億円で、終戦当時二十歳以上、四段階。総理府案は千六百五十九億円で、終戦当時十八歳以上、五段階である。この会合の後、大蔵省はさらに妥協案として総額千三百一億円、千四百八十八億円、千五百七十三億円の三つの案を出した。
六月二十六日から二十七日早朝にかけて、引揚者代表たちが自民党本部で徹夜のねばりを見せる間に、政府と自民党は折衝を重ね、遂に総額千九百二十五億円、引揚者ほぼ全員に支給と決めた。
「引揚者等特別交付金支給法案」の国会通過を待って、十ヵ年均等償還の国債で支給される。
今度もまた“補償金”ではなかった――と、小林吉太郎は加藤松三に向かって、重い口調でいった。
――おれは貧乏だから、金はほしい。当然のことだし……だが金だけの問題じゃない。なぜ国は補償金として、おれたちにくれなかったんだろう。そのわけは「補償と名づければ、私有財産だけでなく、法人関係の補償も問題になってくるからだ」と聞かされたが、おれにはわけがわからない。補償すべきものはすっぱりと補償し、出来ないものは出来ないと、なぜいえないのか。これでは、金額こそ多いが、三十二年度の“立上り資金”の上積みじゃないか。これでは、おれの気持は治まらない――。
松三は、いつもの通り無言で聞いていた。補償問題に関して彼は一度も積極性を示したことがなく、意見さえ口にしない。その態度をあき足りなく思いながらも、吉太郎が胸を開いて語れる相手はやはり松三であった。
世間はおれたち引揚者の組織を圧力団体だという――吉太郎は憮然とした顔で、ことばを続けた。
――中には、そういわれても仕方のない者もいるかもしれん。引揚者といっても全部が開拓民ではなし、中には満洲の“一旗組”もいるだろう。だがな、圧力をかけたり、ごてたりしなければ、当然なすべきこともほっかぶりするのと、どっちがいやしいだろうか。国とは、そんなものであるはずはないのだが――。
松三の沈黙の前で、吉太郎のことばはなお続く。
――農地補償が呼び水になって、引揚者も補償などといい出したと悪口をいうが、そうだとしても、どこが悪い? あたり前じゃないか。この二つをくらべてみろ……。大票田にものをいわせると、にがにがしい顔をするやつもいる。だがこれは、それほどたくさんの人間が、ひどいめにあっているという証拠じゃないか。相手は“国”なんだ。どれほど多くの票を持った人間の集団だろうと、その要求が筋違いのものなら、つっぱねればいいんだ。そうできないというのは、おれたちのいい分が正しい証拠だろう――。
痩せたあごをつき上げていいつのる吉太郎に、松三は悲しい目を注いでいた。
――こんなことをいって歩く吉太郎は、バカにされ、きらわれるだけではないか。それにも気づかず、気負いたっている彼が、あわれでならない。国とは、そんなものではない、と松三はいってやりたい。しかし、それではどんなものかと問われれば、彼には説明のことばがない。決して吉太郎が考えているようなものではない、といい切る自信だけはあるのだが――。
三十二年度の第一回給付金で「この問題は処理済み」という見解をとり続けてきた政府が、審議会答申を表面に出して、一挙に態度を変えたことが、今も吉太郎はふしぎでならなかった。
彼は引揚者の一人として、目的を達したと素直には喜べなかった。
内地の者は、敗戦の時の開拓民がどんな目にあったか、いっこうに知らんなァ――と、吉太郎がまた重い声でいった。
戦後二十年余りが過ぎた今も、彼は“内地の者”ということばで、自分と周囲とを区別している。
満洲からの引揚者であることが、彼の生活に常に影響を与えてきた結果である。
補償問題について引揚者を批判する人々の多くが、敗戦直後の開拓民の惨状を知らないことに、吉太郎は不満だった。
同じ日本人同士なのに、なぜたくさんの開拓民が虐殺されたことが、日本には知られていないのだろうか――吉太郎はたびたび、疑問を抱いた。
――そのくせ、ナチス・ドイツがユダヤ人を虐殺したなどという話になると、内地の者はいやに関心を示して、くわしく知っているのだが――。
新聞には「これで戦後処理にケリをつける」という佐藤首相のことばが出ていたが、おれは“補償”という名で金をもらうまでは、済んだとは思えない。
今度のは補償金ではないそうだ。おれはこれからも運動を続けるつもりだ――という吉太郎を、松三は暗い目で眺めた。
その行為が、いっそう吉太郎を不幸にするとしか思えなかった。しかし「やめておけ」ということばは出なかった。
松三もまた佐藤首相のことばを新聞で読んで以来、これを胸に置いていた。
首相のことばは、「在外財産補償を他の戦後処理要求の導火線とすることなく、これをもって戦後処理の最後とする」という意味であろうと松三も一応はわかるのだが、しかし彼には「この給付金支給で引揚者問題にケリをつける」と響いた。
ケリなどのつけられる問題か ――と、松三は胸の内で、首相のことばに答えていた。
給付金にしろ補償金にしろ、彼にとっては同じである。どれほどの額であろうと、金で始末がつくことか――。
それでは、どうすればいいのか。どうしてくれというのか。それは松三にもわからない。
ただ、決してケリのつく問題でないことだけが、彼にははっきりわかる。
引揚者の中には、ケリなどつける必要のない人もいる。自力でケリをつけた人もいる。
だが、どうにもケリのつけようのない人もいるのだ。努力が足りない、などとはいわせない。
今さら、努力などではどうしようもない傷を受けた者のいることを、忘れないでくれ。
国が犯した大きなあやまちによって破滅した人間が、どうやってケリをつけるのだ。
おれの周囲だけでも見まわすがいい――。
目の前にいる吉太郎は、補償金と名のつく金を国からとれば、それで納得がいく、という。
政府はもう引揚者に金を出すはずはない。
救われない執念に落ちこんだ吉太郎は、ありもしない目的にいらだちながら、一生、周囲となじまずに暮らしてゆくだろう――。
隣り村の寺で墓守りをしている秀子はどうだ。まだ娘は見つからない。
敗戦直後に二人の子供を殺され、その後の八年間は満洲で男の子を捜し、帰国後は娘を捜し続けている。
何という生き方だろう――。
十年、夫を待ち続けた鶴代はどうなったか。夫は二度目の妻と子供を連れて、帰ってきた。
身を引いた鶴代は、その翌年、健吉の伯父のすすめるままに、遠くの村へ嫁いでいった。
前夫やその家族と顔を合わせる辛さから逃れるために、この村から出ていった――。
生きているはずもないわが子を求めて、はるばる長野まで来た青森の女は、その後どうしていることか――。
松三は、自分自身を数えなかった。彼が自分について考えることをやめてから、久しい。
引揚者に支給される特別交付金は、終戦日の年齢別に五段階に分れていた。
当時、
五十歳以上 十六万円
三十五歳以上五十歳未満 十万円
二十五歳以上三十五歳未満 五万円
二十歳以上二十五歳未満 三万円
二十歳未満 二万円
死亡者に対しては、それぞれの年齢に応じて、この七割が支給されるはずである。
松三はやがて受けとるであろう交付金を、彼の手許で成人した武夫に与えようと心を決めた。
すでに二十六歳になった武夫は、松三の養子として彼の籍にはいっている。
だが松三には彼に譲る財産など、あるはずもない。
彼の製材所は時代の波にとり残され、ますます細々とした存在になっていた。
松三はかえってそれを自分にふさわしいと思っていたが、若い武夫にひきつがせるべき仕事ではない。
松三はこれまでに何度か武夫を手離して、戦後の社会に若者らしく巣立たせようとこころみた。
しかしそのたびに、武夫は強くそれを拒んだ。
無理に町工場に住みこませてもみたが、数日後に彼は黙って松三の軒先に立っていた。
彼は自分の殼にとじこもって、決してそこから出ようとしない。
十二歳で満洲から連れ帰られた時のまま、周囲を白い目でにらんでいた。
武夫が、今どきあるはずもない文盲であることも、彼を社会に溶けこませない理由の一つであった。
十二歳で帰国した時、彼は学校に通う義務を持っていたのだが、日本語を全く解さなかったため義務教育の期間をうやむやに過ごしてしまった。
松三の製材所に引きとられた武夫は、たちまち満語を忘れたが、松三が彼に読み書きを教えようと気づいた時は、もう手遅れであった。
決して愚鈍な少年ではなかったが、彼には机に向かう習慣が全くなかった。
製材所の仕事にまぎれ、いつか二人とも勉強をおこたってしまった。
すまないことをした――と、松三は二十六歳になった武夫に、心でわびた。
武夫がこんな半端な人間に育ってしまった責任の一端は、自分にある。
だがこれもまた、国のあやまちが生み出した結果といえないだろうか。
武夫は敗戦直後の避難行で母を失い、その後の八年間を満人の家を転々として育った。
少年期に当然与えられるはずの大人の配慮も愛情もなく、農家の雑役にこき使われていたらしい。
もの心ついたばかりで無残に傷つけられ、いためられた武夫の性格が、成人した今、社会に溶けこめないのはむしろ当然ではないか――。
松三は自分の死後、武夫は一人になって、どうやって生きてゆくだろうか――と思う。
この細々とした製材所さえ、武夫が独力で支えてゆけるとは思われない。
しかし松三には、武夫の将来を安全に固めてやる力はない。ただ暗然とするばかりである。ここにも、ケリをつけることのできない人間がいる――。
松三が、死んだ家族の分も合わせて受けとる給付金の総額は、二十二万五千円である。これを全部武夫に渡しても、大した額ではない。
しかし、せめてそれだけでも武夫のものにしておいてやろうと思いついたことで、松三の心はいくらか慰められた。他に、彼がしてやれることは何もない。
吉太郎が例によって長ばなしをして帰った夜ふけ、松三は仏壇の前に正座してローソクに火をともした。
低く念仏を唱える声が起こる。シベリヤから帰って以来、一日も欠かしたことのない彼の習慣である。 |

戦後のケリをつけられない吉太郎が帰ったあと、
一人で仏壇の前に座り念仏を唱える松三。
|
top
**************************************** |