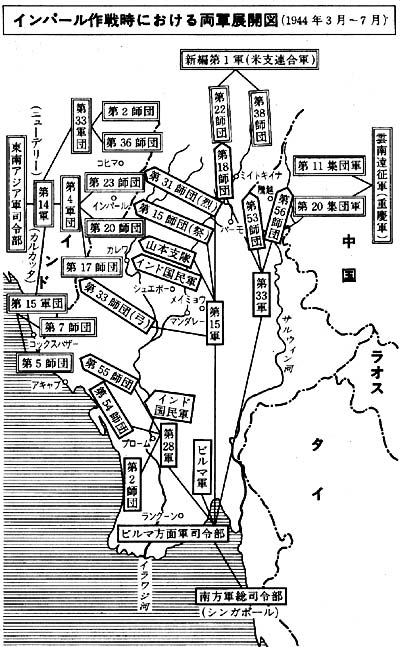|
��������������������������������������������������������������������������������
�T�v�@�@�����@�@���́@�@��O��
���́@���{�R�̃r���}�ł̐푈
��A�r���}���̌ܒi�K top
�@�O�̍��
�@�����m�푈�̓A�W�A�E�����m�ɂ�����A�����J�A�C�M���X�A�I�����_�̊������_��ׂ��A�A�W�A�ɔ��I�ȐV���������i�哌�����h���j������A����ɂ���ē��{�̎������q���ς��낤�Ƃ������̂Ă������B
�@�]���ĎO�̍�킪�s��ꂽ�B�n���C����i�^��p��P�j�A�t�B���s�����A�}���[���ł���B
�@�������q�̂��߂ɂ͐Ζ������̊m�ۂ��挈�����ƂȂ�B
�@���{�̎�̓͂��Ƃ���ɂ���ő�̐Ζ������̓X�}�g���̖��c�n�тł���B
�@�����ւ̒ʘH�Ƃ��ē��{�R�̓t�B���s������{���l�I�A�W�����o�R�ŃX�}�g���ɂ�������̂ƁA�}���[����X�}�g���Ɍ��������̂Ƃ̓��I�B
�@���ꂪ�t�B���s�����ƃ}���[���ł���B
�@�����������{�R�̍s���̓A�����J�̋��͂ȑ����m�͑������S�ł������s�\�ŁA��������n���C��킪�\�z���ꂽ�B
�@�������V���K�|�[������n�Ƃ���p���̓��m�͑��̑��݂͑傫�ȋ��ЂŁA�}���[���ɂ̓X�}�g�����c�n�тւ̒ʘH�[�J�ƂƂ��ɃV���K�|�[���U���Ƃ����傫�Ȗ������^����ꂽ�B
�@�}���[�����x�����邽�߂Ɍv�悳�ꂽ�̂��^�C�i�����ƃr���}���ł���B
�@�}���[�����s���ɂ͕����̒ʉߒn�A�⋋��n�Ƃ��ă^�C���d�v�Ȑ헪�I�ʒu���߂�B
�@�����œ��{�̉e�����ɂ��̈�����m�ۂ��邱�Ƃ��������Ȃ������ƍl������B
�@�r���}�ɂ��Ă������ŁA�����ɋ��͂ȉp��R������A�q���n�����݂��Ă��Ă̓}���[���͑傫�Ȋ댯�ɂ��炳���B
�@�^�C�A�r���}�Ƃ��}���[�����̑��w�ɂ���Ƃ����헪�I�ʒu���l�����ꂽ�̂ł���B
�@�������^�C�ɑ�����͏����́u�i�����v�����ŁA����ȍ~�̍��͂��ׂăr���}�ɂ����čs���邱�ƂɂȂ�B
�@����ɂ̓r���}�R�ƃC���h�����R�����͂����B�r���}���͎��X�Ɋg�傳��A�̂��ɂ͌R���ړI�A�����ړI������ݍ����āA�ɂ߂Đ����I�ȍ�킪�W�J�����B
�@���̒��_���C���p�[�����ł������B
�@���i�K
�@�r���}���͌ܒi�K�ɕ������B
�@���i�K�i���l��N�\�`�l��N�O���j�́A�^�C�i���A�암�r���}�i�e�i�Z���N�n��j�U���A�����O�[���U���̎O��킪�s���鎞���ł���B
�@��핔���͑�\�܌R�i�R�i�ߊ��ѓc�˓�Y�����B�ʏ̗яW�c�j�̓�t�c�i��\�t�c���t�c���|���������A�ʏ̏|���c�Ƒ�O�\�O�t�c���t�c������ȎO�����A�ʏ̋|���c�j�A���̑��ŁA�����͎͂O���������B
�i����R���i�ߊ��͎�������叫�B���l��N�\�ꌎ�Z���C���j�B
�@���̂Ƃ��r���}�ɂ���p��R�̓n�b�g���������R�i�ߊ��Ƃ��A�����͎l���Ɛ��肳�ꂽ�B
�@�암�r���}�ɒ�������̂͑�\���t�c�i�t�c���X�~�X�����j�ŁA�����O�[�����ӂɋ�Z�Z�Z�i��s��O�j�A�e�i�Z�����n��Ɏ��Z�Z�Z�i��s�ꎵ�j�̕��͂�z�u���Ă����B
�@���̂ق��k�r���}�ɏd�c�R�i��܌R�A��Z�R�j���i�o���Ă���A�d�c�R�A�p��R�̑��h��������ɓ`����ꂽ�B
�@�u�암�r���}�̗v��v�ɉp��R���������A�}���[���͐₦�����w���狺�������킯�ŁA���v����m�ۂ��邱�Ƃɂ���Ă����������Ђ��������Ƃ����̂��������ł���B
�@���i�K
�@���i�K�i���l��N�O���`�܌��j�́u�k�����v�i������j�̍s���鎞���ł���B
�@�����O�[�����U��������\�܌R���s������p��R�A�d�c�R��ǂ��Ėk�サ�A�قڃr���}�S�y���̂���܂ł̊��Ԃɂ�����B
�@��핔���͑�\�܌R�̑O�L��t�c�̂ق��ɐV���ɉ�����ꂽ��t�c�i��\�Z�t�c���t�c���n�Ӑ��v�����B��\���t�c�\�t�c�����c�����璆���j�ł���B
�@���̎����ɂ͍��ړI���R���I�A�����I�Ɋg�傳��A�d�c�R�A�p��R�̌��ŁA���Ӄ��[�g�i�r���}�E���[�g�j�̎Ւf�A�����A�C���h�ɑ��鈳�͂̋�������������B
�@����̓}���[��킪�\�z�ȏ�ɏ����ɐi�W���������i���l��N�\�ܓ��A�V���K�|�[���ח��j�A�p��R�A�d�c�R�̒�R���ӊO�ɂ��낭�A���̋@�ɏ悶�A�����̕��͂��ꋓ�Ƀr���}�S�y�����|���ׂ����Ƃ���咣�����܂��Ă������ƁA���Ӄ��[�g�̎Ւf����������ɂ͉��ӕ����̗g���`�ł��郉���O�[����}���邾���ł͕s�\���ŁA�k�r���}�A�_��ɕ�������K�v������ƍl����ꂽ���ƂȂǂɂ��B
�@��������{�c�͂��Ƃ��ƃr���}�����v��𐋍s���邤���ł̓���v��́u�k�����_�v�Ƃ��Ē��ڂ��Ă����B
�@�k�����_�Ƃ͉��Ӄ��[�g��ؒf���A�p�E��ԂɃN�T�r��ł�����ŗ��҂̗��Ԃ��͂��肤��헪�I�v�@�����Ȃ��Ă���n�_�Ƃ����Ӗ��ł������B
�@��{�c�͊J�퓖������r���}�S��ł̍������{���邱�Ƃ��l���Ă����Ƃ����B
�@�i������l�Y���u�哌���푈�S�j�v��j
�@�]���ăr���}�i�U�ɂ������ẮA�U���͈̔͂́u�r���}�̈ꕔ�v�u�암�r���}�̍q���n�v�Ƃ��ꂽ�����ŁA���v��A�U�����߂ɂ́u�������������r���}�����̂��߂̍����s���v�u�r���}�ɑ��鎢��̍����������ׂ��v�ƁA������\������߂��Ă����B
�@�����ɂ�������ړI�̊g��͗\��̋؏��������Ƃ�������B
�@�u�r���}�����̂��߂̍��v�͉��Ӄ��[�g�̎Ւf�i�����푈�̉����j����ړI�Ƃ����B
�@�d�c�Ɍ�ނ����������{�͓����A�l�̕⋋���[�g�ɂ���ĘA��������̐헪���������ē��{�R�ɒ�R���Ă����B |
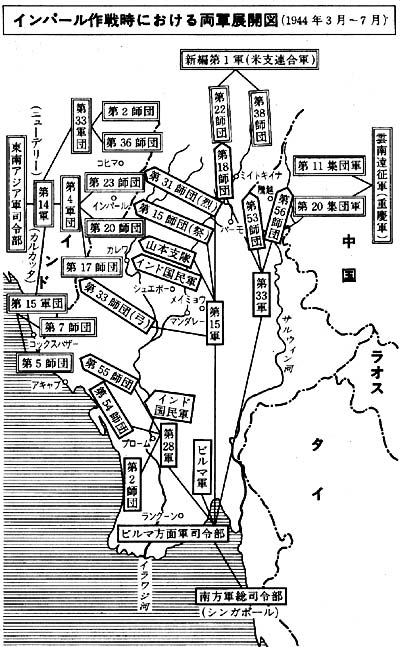 |
�@���͐��k���[�g�ŁA�\�A����V�d�ȁA�Ïl�Ȃ��ւ���́A���͉��݃��[�g�ŁA�ؒ��A�ؓ�̉��݂�L�B�p�A���`���ւ���́A��O�͕��[�g�ŁA�n�C�t�H������^�z�����ւč����ɏo�邩�A�n�C�t�H�����烉���\�����o�ē�J�A�S�F�ɏo����́A��l�̓r���}�E���[�g�ŁA�����O�[������}���_���[�A���V�I���o�č����ɏo����̂ł���B
�@���̂������[�g�ɂ���đ�����R�������̗ʂ������Ƃ������A�����r���}�E���[�g�ł������B
�@�����푈�̐i�W�ɂƂ��Ȃ��Đ��k���[�g�A���݃��[�g�̕⋋�\�͂͑啝�ɒቺ���A���[�g���܂����{�R�̐i���i�k���i���͈��l�Z�N�㌎�A�암�i���͈��l��N�����j�ɂ���ĂقƂ�Ǖ⋋�@�\�������Ă����B
�@���ꂾ���Ƀr���}�E���[�g�̖������傫�������̂ł���B
�@��O�i�K
�@��O�i�K�i���l��N�Z���`�l�O�N�����j�͓��{�R���r���}�̍������ɐi�o�A�S�r���}���قڎx�z���ɂ����Ėh�q�Ԑ��ɂ͂��鎞���ł���B
�@���Ȃ킿�����̏����̌��ʁA�d�c�R�̂�����͂̓r���}�E���[�g�����n�悩��ێR���ʂɁA���̈ꕔ�̓t�[�R���k�J���ւē����A�b�T���̃��h���ʂɁA�p��R��͖͂k�r���}����}�j�v�[�����ʂɁA���̈ꕔ�̓A�L���u���ʂ���`�b�^�S�����ʂɂ��ꂼ��ދp���A�����ē��{�R�͏d�c�R�A�p��R���r���}�̓�����قڈ�|���A�r���}�E���[�g�̎Ւf�A�C���h�ɂ���p���ւ̈��͋����Ƃ������ړI�͈ꉞ�B����ꂽ���Ɍ������B
�@�����ŘA���R�̔������ăr���}�S�y�̈�����m�ۂ��邱�ƂɎ�C�����ڂ�B
�@���ꂪ��O���ł���B
�@�ϋɘ_�Ə��ɘ_
�@�r���}�̖h�q�A�܂�r���}�̈���������ɂ��Ċm�ۂ��邩�ɂ��ẮA���܂��܂̈ӌ��������āA�������c�_���������킳�ꂽ�B
�@��\�I�Ȍ����͓�������B�ϋɘ_�Ə��ɘ_�ł���B
�@�ϋɘ_���\����̂���\�ꍆ���v��ł��낤�B
�@����͓���R���i�ߕ����ŏ��ɂ܂Ƃ߂��������̂ŁA�q���������ăJ���J�b�^���ʂɂ�����A���R�̍q���n���������A���̊Ԃɒn�㕔���������ē����A�b�T���ƃ`�b�^�S������P�U�����A���Ӎq��H���Ւf����Ƃ������̂ł������B
�@���ɘ_�͍��R�i��\�܌R�j�̓^�C�E�r���}������˔j���ăr���}�ɐi�U���Ĉȍ~�A�s�R�A�퓬�̘A���ŁA�����̔�J���͂Ȃ͂��������ƁA����ɓ����C���h�w�̐i�U���ƂȂ�ƁA�⋋���ɂ߂č���Ƃ�����̗��R����A�قڍ��������m�ۂ��ăr���}�̖h�q���͂��낤�Ƃ�����̂ł������B
�@���ǁA�ϋɘ_�͑ނ����A��\�܌R�͉_����ʂɑ�\�Z�t�c�i�t�c�����R�S�O�����j�A�t�[�R�����ʂɑ�\���t�c�i�t�c�����c�����璆���j�A�A���J�����ʂɑ�O�\�O�t�c�i�t�c�����c���O�����j�A�쐼���ݕ��ʂɑ�\�t�c�i�t�c���ÊՌ������j��z���A�V���Ȗh�q�Ԑ����Ƃ����B
�@���l��N�\����̂��Ƃł���B
�@�A���R�̔���
�@�Ƃ��낪�V�����h�q�Ԑ��������Ԃ��Ȃ��A���R�͎O���ʂ��甽�����J�n�����B
�@���Ȃ킿�_����ʂł͏d�c�R�����X�Ɣz�����������čU���ɓ]���A�A�L���u���ʂł��p��R�����͂����čU���������Ă����B
�@���l�O�N�ɂȂ�ƁA���k�r���}���ʂł̓E�B���Q�[�g�y���̎w���������c�̒�g����������A�N�����Ă����B
�@���̂��������A�b�T���ł͂����V�I�`���ˁ`�����Ƃ����]���̃r���}�E���[�g�ɑ����āA���h�`���K�E���`�~�C�g�L�C�i�`�o�[���`���ˁ`�ێR�`�����Ƃ����V�����r���}�E���[�g�i���h���H�j�̊J�݂��}�s�b�`�ōs���A��ɃA�b�T���ɓ������d�c�R��Ď������̐V�t�c�ɉ��҂����Ƃ��i�݂������B
�@������A�̍s���͘A���R���e����Ƃ����ĉ����Ĕ������ɓ]���钛��ƍl����ꂽ�B
�@�����A�A���R�̓J�T�u�����J��k�i���l�O�N�ꌎ��\�ܓ��A���[�Y�x���g�A�`���[�`������]��k�j�Ńr���}�D������s�����Ƃ����肵�A����Ɋ�ĕĉp���W��]�ҊԂŎl�O�N�\�ꌎ�������A�_��A���h���ʂ���d�c�R���A�J��������p��R�����ꂼ��i�����A�r���}�쐼���ݕ��ɉp��R���㗤���ă����O�[�������Ԃ��Ƃ��������U�\�z����������A���̎�͂��߂ɓ{�]�i�T���E�B���́j�A���h�A�C���p�[���e���ʂ������U���ɏo�邱�Ƃ����ӂ���Ă����̂ł���B
�@�r���}���ʌR
�@�����ŁA����ɑΉ����邽�߂Ɉ��l�O�N�O���A�r���}���ʌR���ݒu���ꂽ�B
�@�i�ߊ��ɂ͉͕Ӑ��O�������V�C����A�i�ߕ��̓����O�[���ɂ����ꂽ�i�l���O���A�Ґ������j�B
�@��\�܌R�i�ߊ��ɂ͖��c���������C������A�i�ߕ��̓��C�~���E�ɂ����ꂽ�B���ʌR�͑�\���t�c�i�c���V�ꒆ���j�A��O�\�O�t�c�i���c���O�����j�A��\�Z�t�c�i���R�S�O�����j�A��O�\��t�c�i�V�݁B�����K�������j�A��\�t�c�i�V�݁B�R�����������j�A��\�t�c�i���ʌR�����B�ÊՌ������j�̘Z�t�c��i���A���̔C���̓r���}�̈�����m�ۂ��邱�Ƃɂ���Ƃ���A���̂��߂̖h�q�k�͉_���i�T���E�B���́j�A�t�[�R���~�n�A�W���s�[�R�n�A�A���J���R�n��A�˂�v���Ƃ��ꂽ�B
�@�������A�h�q���͈��l��N������̘A���R�̔��U���Ŏ��X�ɓ˔j����Ă������A�Ȃ����l�O�N��������̒�g���c�̗V�����͍����h�q���ɂ��r���}�h�q�̎v�z�����ꂩ��h���Ԃ����B
�@���k�r���}���ʂł́A�ǂ̗v���ɂ���ăr���}�̖h�q���͂��邩�A�ꉞ�A�h�q���͍������A�`���h�E�B���́A�W���s�[�R�n�̎O���l����ꂽ���A�E�B���Q�[�g��g���c�́A���̎O�����Ƃ��Ƃ����͉������B
�@��\�܌R�͍��������z���Ă̐i�U�����ւ����Ă����B
�@�����Ȃ�ƁA����ނ����ƂɂȂ낤���A�ނ��āA�͂����āA�ǂ̐��Ŗh�q�Ԑ���g�ݗ��Ă��邩�B
�@�_����ʂ��T���E�B���͂ɂ��h�q���͕���A�A�L���u���ʂ��A���J���R�n�ɂ��h�q�͂قƂ�Ǖs�\�ɂȂ��Ă���B
�@��\�܌R�A���ʌR�̋�Y�͐[���ŁA����������Y�̒�����Ăѓ����������Ă����̂��C���p�[���i�U���ł���B
�@��l�i�K
�@�r���}���̑�l�i�K�i���l�O�N�㌎�`�l�l�N�����j�̓C���p�[�����̍s���鎞���ł���B
�@���̂Ƃ��A���R��
�@�@�@�j���[�f���[�ɓ���A�W�A�R�i�ߕ��i���l�O�N������\�ܓ��n�݁B�ō��i�ߊ��̓��C�X�E�}�E���g�o�b�e���C�R�叫�j�@�J���J�b�^�ɑ�\�l�R�i�i�ߊ��X���������j�A
�@�A�@�C���p�[���ɑ�l�R�c�i�R�c���̓X�N�[���Y�����B���͂͑�\���t�c���g���U���A���\�t�c���^���A�����[�A���\�O�t�c���C���p�[���k�����j
�@�B�@�R�b�N�X�o�U�[�i�A�L���u���ʁj�t�߂ɑ�\�܌R�c�i�R�c���̓N���X�`�\�������B���͂͑�t�c�A�掵�t�c�A�攪�\��A���j
�@�C�@�k������i���h�A�t�[�R���J�n�A�~�C�g�L�C�i���ʁj�ɐV�ґ��R�i�w���̓X�`���E�F���������Ƃ�B���͂͑��\��t�c�A��O�\���t�c�A��ԑ��A�J�`���������A�ČR�A���j
�@�D�@�_����ʂɏd�c�R�i�_�쉓���R�B���͂͑�\��W�c�R�A���\�W�c�R�j
�Ƃ����z�u�������B
�@����ɂ������ē��{�R��
�@�@�@�����O�[���Ƀr���}���ʌR�i�ߕ��i���l�O�N�O����\�����n�݁B�ʏ̐X�B�i�ߊ��͉͕Ӑ��O�����j
�@�A�@���C�~���E�ɑ�\�܌R�i�ʏ̗сB�i�ߊ��͖��c�����璆���B���l�O�N�ꌎ�O�\���t�C���j
�@�B�@�u���[���ɑ��\���R�i���l�l�N�ꌎ�O�\���Ґ��B�ʏ̍�B�i�ߊ��͍���ȎO�����B���͂͑��A��\�l�A��\�܂̎O�t�c�j
�@�C�@���C�~���E�ɑ�O�\��R�i���l�l�N�l����\����Ґ��B�ʏ̍��B�i�ߊ��͖{�����ޒ����B���͂͑�\���A��\�Z�̓�t�c�A�̂���\�O�t�c���j
�Ƃ����z�u�������B
�@��\�܌R�̍\���́A
�@��O�\�O�t�c�i�ʏ̋|�B�t�c���͖��c���O�����B�̂��c���M�j�����j
�@��\�t�c�i�ʏ̍ՁB�t�c���͎R�����������B�̂��ēc�K�ꒆ���j
�@��O�\��t�c�i�ʏ̗�B�t�c���͍����K�������B�̂��͓c�Ƒ��Y�����j
�̎O�t�c�ł������B
�@��\�܌R�̎Q�ے��͏����M�Ǐ����i�̂��v�쑺���㏭���j�ł������B
�@�����͂́A�A���R�����p��R���Z���A�A�����J�R�ƕĎx�A���R��Z���A�d�c�R�O�Z���A�v��Z�Z���A
����ɂ������r���}���ʌR�̑����͓͂��{�R��A�C���h�����R�ꖜ�]�A�r���}���R�ꖜ�]�A�v��ܖ��ł������B
�@���v��
�@�C���p�[���i�U���̌v��͑�̂ɂ����Ė��c���i�ߊ��̕��Ăɂ����A�����O�[���ɂ����镺�����K�i���l�O�N�Z����\�l���`�Z����\�����j�ł̌������ւĂ܂Ƃ߂��A�����͂��ߑ�{�c�������R�ɂ�������폀�����{�̎w�����o���ꂽ�B
�@����R�͎w���Ɋ�Ĕ��������A���ʌR�ɂ��������̏����𖽂��A���ʌR�͔����\�����A��\�܌R�ɂ������č�폀���v�j�����B�����B
�@��\�܌R�͍��\�z�����肵�A������\�ܓ��A���C�~���E�ɗꉺ���c���Ɩ������W�߂ĕ������K���s�Ȃ��A�C���p�[�����Ɋւ���ӎv�̓�����͂���A����ɏ\��\��������\�Z���܂Ń��C�~���E�ŕ����������s�Ȃ��Čv����ɂ߂��B
�@����܂łɂ��C���p�[�����̉ۂɂ��Ă͋�̓I�ȍ��v����܂߂Ď^�ۗ��_�����������A���ǁA���F�̕��j�����܂�A�Q�d�����͈��l�l�N�ꌎ�����A�F����|�̎w�������R�ɏo���A����R�A���ʌR���ւđ�\�܌R�͈ꌎ�\����A�����{�̖��߂���̂����B
�@�C���p�[������
�@�@ �|���c����͂ƌ����Ă��������s�����������A�������C���p�[�������߂����Ėk�コ����A
�@�A �|���c���ʂɉp��R�̒��ӂ��������Ă����āA�Օ��c�𓌕�����C���p�[�������Ɍ������Đ��i������A
�@�B ���̊Ԃɗc�͊�}��铽���čŖk�[�̃E�N�����R�n�ɂ͂���A������˔j���Ē���R�q�}�ɏo��A
�@�C ����ɂ���ĉp��R�̑ޘH��f���A�p��R���C���p�[�������ɕ�́A���ł���A
�@�Ƃ����\�z�ł������B
�@��Z
�@�Ƃ��낪��\�܌R���C���p�[�������J�n���悤�Ƃ��钼�O�i���l�l�N�O���ܓ��j�ɂȂ��āA�A���R�͍ĂуE�B���Q�[�g�y���̎w������������\�܌R�̌���n��ɓ��������B
�@����ɂ���Ďw���n���A�⋋���͐��f����A��\�܌R�͐i�U����W�J������Ԑ��ɂȂ������B
�@�Q�d�̂Ȃ��ɂ��ϋɓI�Ɏx��������̂͂Ȃ��A���c���ƂȂ�ƁA�S�����������B
�@���������c���i�ߊ��͂��̂܂ܐi�R�𖽂����B
�@�r���}�̉J�G�͂��������ɂ����Č܌�����\���܂łł����i���G�͏\�ꌎ���痂�N�l���܂Łj�B
�@�����ʼnJ�G�ɂ͂���O�̖�ꂩ���ō����I��낤�Ƃ����̂ł���B
�@���͂قڌv��ʂ�ɐi�݁A�e���c�Ƃ��C���p�[�������̊O�f���ɂ͂��ǂ�������A�����ɉp��R�̏W���C�����тė����������Ă��܂����B
�@�e���c���͍��̐��s�ɋ^�`���������B
�@�Ƃ��낪���c���i�ߊ��͕��c�������X�ɉ�C���A�����܂ł��������s���悤�Ƃ����B
�@�i��O�\�O�t�c�����c���O���������l�l�N�܌��\����C�A
�@�@��\�t�c���R�������������Z���\����C�A
�@�@��O�\��t�c�������K�������������ܓ���C�A
�@�Ȃ���\�܌R�Q�d�������M�Ǐ��������c���i�ߊ��ƈӌ������킸�A���l�O�N�܌���\�Z����C����Ă���j�B
�@���ɑ�{�c�͎����O���i���l�l�N�j�A�C���p�[�����̒��~�����肵���B
�@�i���������A�T�C�p���ח��A�����\�����A������t�����E�j�B
�@��풆�~���߂͑�{�c�������R�ɁA����R������ʌR�ɁA���ʌR�����\�܌R�ɓ`�B���ꂽ�B
�@���̓d�����ʌR�͎����O���A��\�܌R�͎����ܓ���́A��\�܌R�͎����\���A�ꉺ�t�c�ɂ������A�U���C���������A��������𖽂����B
�@�`���h�E�B���n�͂���l�����ɂ��āA�����̈�̂��J�Ɩ��т̂Ȃ��ɂ��炵���܂܁A�C���p�[�����ɂ͏I�~�����ł��ꂽ�̂ł���B
�@��ܒi�K
�@�r���}���̑�ܒi�K�i���l�l�N�㌎�`�l�ܔN�����j�͔s�����ɂ�����B
�@��������i���l��N�O���`�܌��j�̗��Ԃ��ł���B
�@�C���p�[�����͎��s���A��\�܌R�͈��l�l�N�����\���A��������ɂ͂���A�����P�ނ��J�n�����B
�@�A���R�͑S����Ŋ��C�Â��A���������ɐi�o���Ă����B
�@���͂�k�r���}�̖h�q�͍���ƂȂ�A�r���}���ʌR�́u��r���}�̗v�_�v���m�ۂ��邱�Ƃɍ���傫����ނ������B
�@�����ŕ��ʌR�͘A���R�̐i�o���\�Ȍ���x�点�A���̊Ԃɕ��������e���A���Ē������ƁA�e�n�ɂ��܂��܂̍���W�J�����B
�@���킭
�@�@ �f����i��x�n��A���Ւf���j�A
�@�A ������i�C���h�m���ݐ��ʂɗ��U����A���R�ɑ�����j�A
�@�B �Ս���i�}���O���[�ƃC�����W�͔Ȃɗ��U����A���R��͂ɑ�����B�C�����W���j�A
�@�C �g���O�[���A
�@�D �V�b�^�����ł���B
�@�f���͉_�쉓���R�i�d�c�R�j�A�Ďx�A���R�i�V�ґ��R�j�̑����U���͂˕Ԃ��A�k�r���}���Ȃ��m�ۂ��ĉ��Ӄ��[�g�̍ĊJ��j�~���悤�Ƃ�����̂ŁA��O�\�O�R��������A���l�l�N�㌎�\����ɊJ�n���ꂽ�B
�@�������d�c�R�A�Ďx�A���R�̈��͂ɑς����˂āA��ꎟ�f���͎��s�����B
�@��O�\�O�R�͏\�������A��O���A��l���f�������Ŏ��{�������A����������������A���肶��ƌ�ނ�����ꂽ�B
�@�����͓쐼���ݐ��ʂɑ���p��R��\�܌R�c�̍U����j�~���A�����ʂ�h�q���悤�Ƃ�����̂ŁA���\���R��������A���l�l�N�\���J�n���ꂽ�B |

�A���R�̔����́A�����_��Ȃ���Ē��R���A�C���h�A�b�T������p��R���A
�x���K���p�̃A�L���u����p��R���{���̂悤�ɐN�����A�h����͎��X�Ɠ˔j����A
�זɁi�����߂�j�S���Ń^�C�ɒE�o�ł����҂͑����͂Ȃ������B
|
�@�Ս���i�C�����W���j�͑�\�܌R��ǂ��ă}���_���[���ʂɔ���p��R�̍U���������Ƃ߁A�}���_���[�ȓ�̒����r���}���Ȃ��m�ۂ��悤�Ƃ�����̂ŁA��\�܌R��������A���l�ܔN�ꌎ�\�Z���ɊJ�n���ꂽ�B
�@�C���p�[����킩��h�����ė��E������\�܌R�͎l�l�N�\���܂łɃ`���h�E�B���͂�n��A���͂̓��ݒn��ɏW���A�����̍ĕ҂��s�Ȃ����̂��A�Ăэ���ȐV���̂��߂̐헪�W�J�Ɉڂ����B
�@�W�J�����͑�\�܌R�̎O�t�c�Ƒ�\�O�t�c�A���t�c�i�ꕔ�j�A��\���t�c�i�ꕔ�j�ł������B
�@���̍��͒f���̎��s�̂��ƁA�f���Q�������̈ꕔ�������A����Ɋ���퐳�ʂ�����ꕔ�����𒊏o���đ����A�r���}���ʌR�̉^���������������̍\�z�ł������B�Ƃ��낪�A�Ԑ��̐���Ȃ������Ɏl�Z�Z�p�̋@�b�������V���G�{�[�O�ʂɗ��P�A�܂��s�ӂ��Ղ��Ďl���c�̉p��R�����ʂ���}�P�A����ɋ��͂ȋ@�b���������C�N�e�[���{�w�̒�������˔j�A��\�܌R�A��O�\�O�R�͒ח���ԂɊׂ�A�����܂��}���_���[��D�悳��āA���̍������s�����B
�@��ނȂ����ʌR�̓g���O�[�������������B
�@�Ս�킩���ނ�����\�܌R�A��O�\�O�R�A����킩���ނ������\���R�����Ē����āA�}���_���[���ʂ���E������A���R���s���}�i�A�g���O�[�t�߂ł����Ƃ߂悤�Ƃ����̂ł���B
�@�Ƃ��낪�O�R�̕z�w������Ȃ������ɁA�܂�����A���R�̋@�b�����ɓ˓�����āA�g���O�[���̍\�z�͈�u�ɂ��ĕ����B
�@��ނȂ����ʌR�͎l����\�O���A�i�ߕ������[�������Ɉڂ��A�V�b�^���͂̐��ɍŌ�̖h�q����~�����B
�@���ꂪ�V�b�^�����ŁA����ɂ���ăe�i�Z�����n���h�q���悤�Ƃ����B
�@�������܌�����ɂ͎�s�����O�[����D�ꂽ�B
�@�Ԃ��Ȃ������ƂȂ�A�������~���̓��������B
�@�e�i�Z�����h�q�Ɏn�܂����r���}���̓e�i�Z�����h�q�̐U�o���ɂ��ǂ��ďI����}�����B
�@���̎����ʌR�̑����͈͂�O���Ɍ����Ă����B
�@���Ӄ��[�g��f����A�d�c���������������ē����푈���I�����A�C���h�ɐi�U���Ďl���̖����u����v���A�p�Ďx�A������f���đ����m�푈����������Ƃ������͂Ȃ₩�Ȗ�����͂��܂������B
�@�����͈�O���Ƃ����Ă��A�e�i�Z�����n��ɂ��ǂ�������͕̂a�݁A�����A��ꂫ���Đ����Ȃ������B
��A �r���}�R�ƃC���h�����R top
�@�r���}�Ɨ��`�E�R
�@�r���}���ɂ̓r���}�Ɨ��`�E�R(�a�h�`��Burma
Independence Army�j�ƁA�C���h�����R(�h�m�`��Indian
National Army)����������B
�@�r���}�Ɨ��`�E�R�͑����m�푈�̊J�풼��A�r���}����E�o���Ă����^�L���}���i���p�Ɨ��^���𐄐i����r���}�l�̐������Ёj�A�^�C�ݏZ�̃r���}�l�ȂǓ�����������ăo���R�N�Ō������ꂽ�B
�@�w��Ŏw���ɂ��������̂͑�{�c�����̃r���}�H��@�ւƂ��ĂЂ����Ɍ������ꂽ��@���i�@�֒���،h�i�卲�j�ł������B�c���r���}�̓Ɨ����߂����r���}�N�����̊�]�ƁA���ւ̋��͂����߂���{�R�̗v���Ƃ����т��Đ��܂ꂽ�Ɨ��`�E�R�ł���B�@�`�E�R�̓r���}���̑����i���l��N�\�`�l��N�O���j�A�E���̖͗l�̂����r�͂����r�ɂ܂��A�u�h�[�o�}�v�i���j��A�Ă����{�R�ƂƂ��Ƀ^�C�E�r���}������˔j���ăr���}�̂ɂ͂������B |

���[���������s�i����r���}�Ɨ��`�E�R�i1942�N1���j
|
�i���j�FDaw Burma�̓^�L���}�̓}�́A�u����̃r���}�v�Ƃ����Ӗ��A�r���}������
�@�`�E�R�͉p��R�̓��Â�T��A���邢�͉p��R�̑��w�ɍs�����ē��{�R�̍U������傫���������B
�@�Ɨ��`�E�R�Ƃ����Ă������W�[�E�X�^�C���i�r���}�l�̓`���I�����ŁA���ɒ����z�������t���������̎p�j�̎҂�A�V���[�g�E�p���c�ɃV���c�[���Ƃ����������������A����Ƃ����Γ��A���_�A�|���A�ÓS�C�ɂ����Ȃ��������A�ӋC�͍��������B
�@�ǂ��ł��劽�}�ŁA��҂��������X�ɎQ�����A�����O�[���ɂ͂������Ƃ��ɂ͌܁Z�Z�Z���߂��ɂӂ��ꂠ�������B
�@���ꂾ���Ɨ��ւ̃r���}�l�̊��҂������A�`�E�R�͊��V�̎��J�̂悤�Ƀr���}�l�Ɍ}�������ꂽ�̂ł���B
�@��������i���l��N�O���`�܌��j�ɂ͂���ƁA�`�E�R�͓�t�c�A��A���A��Ɨ�������ɉ��҂��ꂽ�B
�@�I���T�����R�i�ߊ��Ƃ��A���t�c�i�O�A���B�t�c���̓{�[�E�l�E�B���卲�j�A���t�c�i�O�A���B�t�c���̓{�[�E�[���卲�j�A�Ɨ��A���A�����O�[��������ł���B�����͖͂���Z�Z�Z���������B
�@�`�E�R�̓C�����W�͂̐��ݒn���k�サ�A���{�R�̎�̋y�Ȃ��n����J�o�[�����B�����͈����A�⋋���v���ɂ܂����Ȃ��������A�`�E�R�͉����o�[���A�^�}���e�B�A�A�L���u�ɂ܂Ői�o�����B
�@�����Ɉꕔ�������Ď�s�����O�[���̖h�q�ɔC���A����ɓ��{�R���ʉ߂������Ƃ̎����ێ��ɂ��������B
�@�r���}���R�̔���
�@��O������i���l��N�Z���`�l�O�N�����j�Ɉڂ�ƁA�`�E�R�͍ēx���҂���A�O����i�O�Z�Z�Z���j�Ґ��ɏk�����ꂽ�B
�@�R�i�ߊ��̓I���T�����R�ł��邪�A�R�̖��̂̓r���}�h�q�R�Ɖ��߂�ꂽ�B
�@�`�E�R�͍����x�����h�q�ɂ��������B
�@���l�O�N��������A�r���}�͓Ɨ����A����ƂƂ��ɖh�q�R�̓r���}���R�Ɖ��̂��ꂽ�B
�@���͈͂ꖜ�܁Z�Z�Z���������B
�@�������A���̎�C���͂����ς���{�R�̌���x���ł������B
�@����͑�l������i���l�O�N�㌎�`�l�l�N�����B�C���p�[�������j�A��܊�����i���l�l�N�㌎�`�l�ܔN�����j�ł��p������A�r���}�R�͖����Ƃ��ɓ��{�R�̕⏕�����Ƃ��ꂽ�B
�@����̓r���}�R�ɑ傫�ȕs�������������B
�@�r���}�R�͑n�݈ȗ��A�r���}�̓Ɨ��������������ɏI���̂ł͂Ȃ����Ƌ���Ă������A����������������āA���{�R�̉��ł̓r���}�̐^�̓Ɨ��͂��肦�Ȃ����Ƃ�m�����B
�@�܂����\�܌R�ɂ��C���p�[�����͎��s���A�A���R�̓`���h�E�B���́A�_��A�A�L���u�e���ʂ��炢�������ɔ���������B
�@���炩�ɐ�ǂ͓��{�R�ɕs���ŁA�A���R�̕��A��������₪�Ă���ł��낤���Ƃ͖ڂɌ�����悤�������B
�@�I���T���͂Ђ����ɘA���R�ƘA�����Ƃ�A���{�R�̔s�ތ�A�����ɂ��ăr���}�̓Ɨ��������Ƃ邩�ɐS���ӂ����B |

�I���T�����R
|
�@�I���T���̓������_�́A�r���}�Ɨ��́u�������v�𗧂Ă邱�Ƃɂ���ăr���}�̓Ɨ���A���R�ɔF�߂����邱�Ƃł������悤�ŁA�����ăI���T���͈��l�ܔN�O����\�����A���{�R�̎w���n���𗣂�A�S�������g���ē��{�R�Ɍ������čU�����J�n�����B
�@�r���}�h�q�̓V���R�Ƃ�����ꂽ�u�Ս��v�i�C�����W���j�ɂ����{�R�͔s��A�����r���}�̗v�Ճ��C�N�e�[������A���R�ɒD�ꂽ�Ƃ��ł���B
�@�r���}���R�̔����\�\���{�R�̘��S�łȂ����Ƃ������u�������v�͂���ȊO�ɂȂ��ƁA�I���T���͍l�����̂ł��낤�B
�@�������s���̓��{�R�ɂƂ��Ă���͂����������B
�@�C���h�����R
�@�C���h�����R�̓}���[���̃C���h���ߗ��𒆐S�Ɉ��l��N�㌎����A�V���K�|�[���ŕҐ����ꂽ���̂ŁA�����̕��͈͂ꖜ�܁Z�Z�Z���A����ɊԂ��Ȃ�����A�W�A�e�n�ɍݏZ����C���h�l�N�܁Z�Z�Z�����������đ������̑啔���ƂȂ����B
�@�����R�̓C���h�̓Ɨ��^�����h�����A�C���h����p����߂����A����ɂ���đ����m�푈�������������Ƃ��閲�̂悤�Ȑ����\�z�̂Ȃ��ň�܂ꂽ�����ł���B
�@���̓_�A���̓���A�W�A�e�n�őg�D���ꂽ�`�E�R�Ƃ͐��i�I�ɈقȂ���̂���������Ă����B
�@�����R�͈��l�O�N�\����\����A�V���K�|�[���Ɏ��R�C���h�����{����������A�X�o�X�E�`�����h���E�{�[�X�����{��ȁA�C���h�����R�i�ߊ��ɏA�C����ɂ����ŌR���Ƃ��Ă̌`�𐮂��A�܂��C���h����̈ӎ����������悤�ɂȂ����B
�@�₪�ē�̗V���t�c���Ґ�����A����ɑ�O�V���t�c�̕Ґ����i�݂������B |

�C���h�����R�̌R��
|
�@�C���h����̂��߂ɂ͉����{�������R���C���h�ɐڋ߂����n��ɐi�o���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�����ăr���}���{�̍��ӂĈ��l�l�N�ꌎ�����i�r���}���̑�l���j�A�����{�͋�H�����O�[���ɂ͂������B
�@�����������R�̈ڒ��͓��{�R���g���A���@�ւ��\���ɂ����Ă��Ȃ������W�������ė\��ʂ�ɐi�܂��A���V���t�c�͗��H�^�C�E�r���}�������������B
�@���p�s���ɂȂꂽ�C���h�l�����ɂƂ��ēk���ɂ�鍑���˔j�͑z�����������s�R���������A�c���C���h���߂��ƁA�����͓�H�������A����Ƀ����O�[���ɐi�݁A�x�ފԂ��Ȃ��������őO���Ɍ��������B
�@���{�R�Ƃ̍�틦�͂ɂ��ẮA���ʌR�ƃ{�[�X��ȂƂ̊Ԃňӌ������킸�A���Ȃ蕴���������A���ǁA���V���t�c�i�t�c���L���j�[�����j�̑��A���̓A���J���n��ɁA���A��O�A���͎R�{�x�����ʂɁA��l�A���͗c���ʂɂ��ꂼ��o�����ăC���p�[�����ɑS�ʓI�ɋ��͂��邱�ƂɂȂ����B
�@�����R�͗V���A�����A���A��[�̎l���Ґ����Ƃ�ꂽ�C�B
�@�����R�̈琬�A�����A�����R�Ɠ��{�R�Ƃ̘A���ɂ͓����@���i�@�֒�������s�����j�A��ȋ@���i�@�֒���ȍ��Y�卲�j�A���@���i�@�֒���c�O�Y�����j�Ȃǂ��������őg�D����āA����ɂ��������B
�@�����]�R���Ă���R�{�x�����ʂɂ͑��A���i�A�����L���j�[�卲�j���W�J���A�����ς�o�����ɂ���p��R���\�t�c�̑��w��ɂ��������B
�@�A���͐ϋɓI�ɍs�����A�E���ɐ�����B
�@�������C���p�[�����̎��s�ɂ���ē��{�̐����͕��A�C���h�Ɨ��ւ̃{�[�X��Ȃ�̊��҂͋��e�����B
�@�����R�̓A�b�T���̉J�ɑł���A�Q��Ǝ��a�ɔY�܂���O�����牺�����B
�@���͑��A���ƂƂ��ɑO���ɐi�݁A�܂����A���ƑO�サ�ăJ�{�E�J�n���������B
�@�ЂƎR�����Αc���C���h���Ƃ����̂ɁA�����R�̂Ȃ��ɂ̓C���h�̑��Ɍ��������̂͂Ȃ��A��������J�X����J�̂Ȃ����r���}���Ɍ������ĖفX�ƕ������B
�@�@�@�O�A �l�l�̃T�����C ��op
1�@�C���p�[���̎l�l
�@�C���p�[�����̈�̎R����Ȃ��R�q�}�̐퓬�ɎQ�������p���̃A�[�T�[�E�X�E�B���\����т͐��A�u�l�l�̃T�����C�\�\�����m�푈�������ߌ��̏��R�����v�i�|���r��j�Ƃ����{���������B
�@�l�l�̃T�����C�Ƃ�
�@�@�@�{�ԉ됰�i�����A�t�B���s���̑�\�l�R�i�ߊ��j�A
�@�A�@�R�����i�����A�}���[�̑��\�܌R�i�ߊ��A�̂��t�B���s���̑�\�l�R�i�ߊ��j�A
�@�B�@���c�������i�����A�r���}�̑�\�܌R�i�ߊ��j�A
�@�C�@�{�������i�����A�r���}�̑�O�\�O�R�i�ߊ��j���������B
�@�����ł̓C���p�[�����̎l�l�̃T�����C�Ƃ���
�@�@�@���c�����璆���i��\�܌R�i�ߊ��j�A
�@�A�@�͕Ӑ��O�����i�r���}���ʌR�i�ߊ��j�A
�@�B�@�X�o�X�E�`�����h���E�{�[�X�i�C���h�����R�i�ߊ��E���R�C���h�����{��ȁj�A
�@�C�@�I�[�h�E�`���[���Y�E�E�B���Q�[�g�y���i�k�r���}��𗷒c�i�ߊ��j�������Ă݂����B
�@�C���p�[�����ɂ͎��ɂ��܂��܂̐l�����o�ꂵ�A�ԗ��Ȑl�ԊW�̃h���}��`�������Ă��邪�A���𐋍s���A���邢�͍�팈��ɑ傫�ȉe�����y�ڂ����l���ƂȂ�ƁA���̎l�l�ɂ��ڂ���ł��낤�B
�@�s�R�̏�
�@���v�悪�j�]���A�S�R�̑ދp���n�܂������A���̓N���^���̑�\�܌R�i�ߕ��Ŗ��c�����R�ɉ�������Ƃ�����B
�@�R�i�ߕ��Ƃ����Ă��A�X�̂Ȃ��Ɍ��Ă�ꂽ�����̘m�����ɂł���B
�@�J���J�X�ƍ~��A�ǂ̏��ɂ���������������Ă����B���ނ��Ă����ł���B
�@�e�t�c�̐퓬�����͂����͂₭�ދp���A�i�ߕ��̗v�������łɂقƂ�ǂ�����ɉ���킸�������̉��m���A�����c�邾���������B
�@���̏��ɂ̈���ɏ��R�͍������Ă����B
�@�ǂ̂悤�Șb�������̂��v���o���Ȃ����A��������������Ԃ͂��Ȃ蒷�������Ǝv���B���̍��A���͑����ׂ�A���͂̂сA�قƂ�Ǒ̑S�̂�畆�a�ɂ�������A���䂭�āA�����ڂ�ڂ�̂������Ă����B
�@���R�Ƙb���Ă���Ԃ��A���͂��������r���������B
�@���R�͈���łȂ�Ȃ��Ƃ������\��ŁA�����W�b�ƌ����B
�@�����Ƃ��킳����A���l�̋C���Ɏv�����������悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A���������Ɏ����������ʂ��Ƃ���ꂽ���R�̖ʉe�͂ǂ��ɂ��Ȃ������B
�@�����̂��炷�Ƃ���ɂ��ƁA���R����������̂ł͂Ȃ����ƁA�������C�������Ă���Ƃ������Ƃ������B�lje���R�A�܂��ɔs�R�̏��������B |

���c���N�璆��
|
�@�������悤�Ƃ���ƁA���R�͈�ӂ�̓�����肾���āA���̑O�ɂ������B
�@��\���t�c�̎t�c���Ƃ��ăV�����B�ɒ������Ă������A�y�瑡��ꂽ�u�v���Ƃ����B
�@��͋�ŁA���g���܁A�Z�\�Z���`�قǂ������B�V�����̖����Ȃ̂ł��낤�B
�@���R�́u�L�O�ɂ��������܂��傤�v�Ƃ������B���͖ق��ē��������A�������������ĕʂ���������B
�@���̓��̗[���A���R�͕����ɂ������A�J�̂Ȃ����Ђ�����Ɖ����Ă������B
�@���͓���厖�Ɉ����A�J�{�E�J�n������Ƃ����A�����g�ӂ��痣�����A���ɃT�C�S���܂Ŏ����Ă����B
�@�������A�₪�ē��{�͖������~�����A���ǂ�����l�ɗ}�����ɓ�����邱�ƂɂȂ����B
�@�A���R�����̃C���h�V�i�ɐi�����Ă����B
�@�T�C�S���ɏ㗤���Ă����̂͊�����`���E�q���ŎR�{�x���ƌ�����������p��R�̑��\�t�c�������B
�@�A�b�T���̃W�����O���ŁA�����J���Ă����̂ŁA���x�͋C�y�ȓs�s�����ɂ܂킳�ꂽ�Ƃ������Ƃ��������A�R�{�x���ƍs�����Ƃ��ɂ��Ă������Ƃ��Ă͋C���C�łȂ������B
�@���A�ǂ��������R�Ŏ�蒲�ׂ��邩�킩��Ȃ��Ǝv�����B
�@���܂ł͑z�����ł��Ȃ����Ƃ����A�s�풼��A���ǂ��͂�����������Ă����B
�@���́A�����ƒ����V���x�ǂ̃x�g�i���l�������ɓ����������B
�@���̌�A���̓��ƃx�g�i���N�͂ǂ��Ȃ����ł��낤���B
�@���c���̎g����
�@�C���p�[�����̐ӔC�́A���̔�������I���܂ŁA���܂��܂̐l�ɋA������ł��낤���A���R�i�ߊ��Ƃ��Ă̖��c�����R���͂����������͌���I�ɑ傫�������Ǝv���B
�@���c�������́u��\�ꍆ���v��v�i�ŏ��̃C���h�i�U���v��j�����Ă��ꂽ�����͑�\���t�c�̎t�c���ŁA��\�܌R�i�ߊ��ѓc�˓�Y�����Ƃ̉�k�ŁA�C���h�i�U�́u���s����v���Ɠ����Ă����i�h�q���h�q���C����j�����u�C���p�[�����v�j�B
�@�Ƃ��낪���l�O�N�O���A�r���}���ʌR���V�݂���A����ƂƂ��ɔѓc�����ɑ����đ�\�܌R�i�ߊ��ɔC�����ꂽ���Ƃł͐ϋɓI�Ȗh�q�헪���咣����B
�@�������A����͖h�q�̑������W���s�[�R�n����`���h�E�B���͂̐��ɐ��i����Ƃ��������\�z����A�A���R�̔��U�̍n�ł���C���p�[���ł��A�����C���h��}����Ƃ�����\�z�ɂ܂Ŕ��B
�@���̗��R�Ƃ��Ă͎O�̂��Ƃ��l������B
�@��͌R���v�z�̖��ŁA�u�ŗǂ̖h���͍U���ɂ���v�Ƃ���l�����ł���B
�@����͓��{�̌R�l�����������Ă���M�O�̂悤�Ȃ��̂ł��������A�Ƃ��ɖ��c�����R�ɂ͋��������悤�ł���B
�@���ۖ��Ƃ��Ă��A���R�̔��U���ɉ����A���̂ǖh�q����V�݂�����A���邢�͑O�ɐi�߂�Ƃ����̂ł́A�h�q���ʂ��g�債�A��葽���̕��͂�h�q���ɒ�����邱�ƂɂȂ�A�Ƃ��Ă��A���R�̔�����j�~�����Ȃ����낤����ł���B
�@������͌R�l�Ƃ��Ắu�g�����v�ł��낤�B
�@���c�������́A���̎�L�u�r���}���Ɋւ����z�^�v�̂Ȃ��ŁA
�@�u�����b�a�������̂������������������A�����͂���Ɋg�債�Ďx�ߎ��ςƂȂ�A���ɂ͍����哌���푈�ɂ܂Ŕ��W���Ă��܂����B��������A�����̗͂ɂ���ăC���h�ɐi�U���A�哌���푈�Ɍ���I�ȉe����^���邱�Ƃ��ł���A�������u���̉��������������Ƃ��Ă͍��Ƃɑ��Đ\���킯�����B�j�q�̖{���Ƃ��Ă��܂��ɂ��̂����Ȃ����Ƃł���v
�Ə����Ă���B
�@�b�a�������̂����́u�x�ߒ��ԌR�v�i�i�ߕ��͓V�ÁB���͎͂l�Z�Z�Z�j�̗��c�����͕Ӑ��O�����A�A���������c���卲�������B
�@����͕ӂ͒����ƂȂ��ăr���}���ʌR�i�ߊ��ɁA���c���͒����ƂȂ��đ�\�܌R�i�ߊ��ɂƁA�b�a���̃R���r���r���}�ōČ������B
�@���̂��Ƃ����c�����R�̎g�������������Ă��悤�ł���B
�@��O�͌R���v�z��g�����̔w��ɂ��閴�c�����R�̐l�ԓI���i�ł������낤�B
�@���c�������́u�^��ƖҋC�v�������A�u�܂�������ɐi�ސ킢�v���D�݁A�u��������A�����Ǝv�����߂A���̎v�����݂��v���l�߂ɁA�m�M��M�O�ɁA����ɐM�ɂ܂ō��߂Ă��܂��v�l���������Ƃ���Ă����i���������u�p��̒J�v�j�B
�@�E�C���Q�[�g
�@�C���p�[�����̌��肪�O�I�����ɂ���ĉe�����ꂽ���Ƃ͎����ł��낤�B
�@���������e���������^�������̂̈�͈��l�O�N�t�A�k�r���}�ɐi�������E�B���Q�[�g��g�����ł������B
�@�I�[�h�E�E�B���Q�[�g�͉p���̗��R�m���w�Z�𑲋ƁA�����̍����n�тŃA���u�l���A�G�`�I�s�A�̍��n�тŃC�^���A�l��ɂ��ꂼ��Q�������킢�A���M�����Ă��B
�@�����m�푈���͂��܂�A���{�R���r���}�ɐi�����A�����O�[�����ח������A�C���h���݂̉p�R���i�ߊ��E�F�C���F�����R�ɌĂ�A���{�R�̐i����j�~���邽�߃Q���������������悤������ꂽ�B
�@���l��N�O���\����ł���B
�@�����O�[���ח���\����ځA���{�R���폟�C���ɐ����Ă���Ƃ��������B
�@���ꂩ��E�B���Q�[�g�y���͖k�r���}�e�n�ɂ����ނ��Ēn�`�ׁA�J�������A�J�`���������ɃA�v���[�`�����B
�@�J�������A�J�`�����͉p���̐A���n���ォ��p���̓��ʂ̕ی���A�e�p�I�Ȏ푰�������B
�@�E�B���Q�[�g�́A�����̕������Q������̋��_�ɂ��悤�ƍl�����B |

�͕Ӑ��O����

�E�B���Q�[�g�y��
|
�@��������g�s��
�@�܂��A���{�R�̐퓬�������������u��������g�s���v�i�����O�E���C���W�E�y�j�g���[�V�����j�Ǝ��炪�Ăԕs���K���𗧈Ă����B�����
�@�@�@����̕⋋�ɂ���ĕ����̐�͂��ێ�����A
�@�A�@�����̍s���͖����ɂ���Ďw������A
�@�B�@�����͓G�ɑ��K�v�ȑŌ���^��������x�̕��͂ŁA�G�̊Ď��Ԃ������蔲������K�͂̂��̂Ƃ���A
�@�C�@�G�̔w��n�ɐi�����A���̎w���̌n�A�⋋�̌n��j��A
�@�D�@����ɂ���đS�ʂ̐�ǂ������ɓ����A
�Ƃ������̂������B
�@���l��N�Z���A�v��̓E�F�C���F�����R�ɂ���ď��F����A�E�B���Q�[�g�͒�g�s���ɂ��������c�i�掵�\���������c�j��Ґ������B
�@���c�̓C���h�����ŌP�����s�Ȃ��A�l�O�N�ꌎ�A�f�B�}�v�[���Ɉړ����A�����ŃC���p�[���ɂ͂������B
�@�����ŏ����𐮂��A��g���͓����A�C���p�[�����o���A�`���h�E�B���͂�n�������ƁA�����A���ɂ���čq��@����̕⋋�����̋������A�������Ԃ̑��ݘA�����Ƃ���ɂ킽���đ�\���t�c�̖h�q�S���n����ɐ[���N�����A���̎w���E�ʐM�n���A��������f���荬�����������ƁA�Z�����{�܂łɈꕔ�͒����̓��ɁA��͂̓C���h�̓��Ɉ����g�����B
�@�E�B�[���Q�[�g���c�̗V�����͑�\�܌R�̎w���������R�Ƃ������B
�@�啔���̍��͍���ƍl���Ă����C���h�E�r���}�����n��ƃW���s�[�R�n��˔j���Ĉ���c�̕��͂���\�܌R�̉��[�������Ă�������ł���B
�@�������A���ꂾ���̑啺�͂��⋋�����œ��Ԃ���\�܌R�̂��G���ő�_�ȗV��������W�J�����̂ł��邩��A��\�܌R�̎��Ռ��͑傫�������B
�@�E�B���Q�[�g���c�͂����ɐe�p�I�ȃJ�������A�J�`�����̕�����`����čs�������B
�@���u�n�ɂ�����Ɨ������V�������͒n��Z���̋��͂Ȃ��ɂ͍���ŁA�E�B���Q�[�g���c�̐�����킪���������w��ɂ͖k�r���}�Z���̋��͂����������Ƃ��l�����A�������\�܌R�̐S�_�������炵�߂�ɏ\���������B
�@�E�B���Q�[�g���c�̍s�������đ�\�܌R�̎w���������́A�r���}�E�C���h�����n�тɑ���n�`�F����ς����B
�@�����̖��ђn�т��啺�͂̒ʉ߂������A��K�͍����\�ɂ���ƂȂ�ƁA�r���}�̖h�q���r���}�̍��������ɂ����čl����R���v�z�͔j�]����B
�@�������獑���O�̗v�����m�ۂ��邱�Ƃɂ���ăr���}�h�q���͂��낤�Ƃ���R���v�z���o�ꂵ�A�C���h�i�U���̍\�z�����悢������ɏ���Ă���B
�@�v�_�w�n
�@���ڂ̋�����́A���ꂩ���N��̈��l�l�N�O���ܓ��Ɍ��s���ꂽ�B
�@�C���p�[�����͈��l�l�N�O�������A�|���c�i��O�\�O�t�c�j�̃`���h�E�B���n�́A�`�����n�i�o�ʼnԂ����ꂽ���A���̎O���O�ł���B
�@���������ڂ͈���c��O�Z�Z�Z�����������A���ڂ͖�Z���c�i������t�c�����̑啺�́j�������B
�@����͍q��@����⋋�����̋������čs���������A����͕������O���C�_�[�ɏ悹�A������q��@���g�s���Ė��ѓ��ɂ��炩���ߊJ�݂���������ɂ��낵���B
�@�O���C�_�[�͎g���̂āA���X�ɐV�����O���C�_�[�ŕ������^��ł���B
�@�~���n�_�̓J�[�T�A�C���h�E�A���[���A���K�E���A�~�C�g�L�C�i�ȂǃC�����W�͂̐��ݒn��A�܂��\���t�c�̔w��n�ł���B
�@�������āA��Z�Z�@�̃O���C�_�[�Ɖ��טZ�Z�Z��̃_�R�^�@�ɂ���āA��Z�Z�Z���̕����ƈ��Z�Z���̓�������T�ԑ��炸�ʼn^��A�܂�����A�e��A�H�ƂƂƂ��ɒz��ޗ�����ʂɋ�A���ꂽ�B
�@����ŋ���͗v�_�ɐw�n���\�z�����B
�@���S�����[���̍��n�Ɍ��݂��ꂽ�~�^�w�n�ŁA���͂ɂ̓x�g���i�R���N���[�g�j���Γ_�����肠���A�d�����C�A�����C�A�d�@�֏e�A�y�@�֏e��z�����A���̊O����S��Ԃň͂ނƂ������͂ȁu�T�̍b�w�n�v�u�I�̑��w�n�v�������B
�@�������猩��ƁA���n�̐w�n�͏e��ł������Ă���悤�������B
�@�w�n�͍q���̎x�����A���{�R���ڋ߂���ƁA�w�n���̉ΖC���W���𗁂т��A�q�����}�~��������������Ƃ����A�q�v���[���p�ӂ���Ă����B
�@����́A���̐w�n�����_�Ƃ��ċ@�����ďo���A��\�܌R�̕⋋�ԁA�w���n�����e�n�ŎՒf�����B
�@���c���i�ߊ�������̍~����m�����̂̓C���p�[�����̊J�n���ꂽ�O�������������Ƃ����B
�@�i�ߊ��͍�푱�s�𖽂���ƂƂ��Ɍ���ɂ���ꕔ�̕����������ċ�����U�������A���ʌR���ꕔ���͂������čU���ɎQ���������B
�@�������v�_�w�n�ɂ͎��������Ȃ������B
�@������̂��Ӗ�
�@�E�B���Q�[�g����̍��͒��ړI�ɂ͐V�ґ��R�̓쉺�����X�ɑj�ޑ�\���t�c�i�t�c���c���V�ꒆ���j�w����h���Ԃ낤�Ƃ������̂ł��낤���A�傫���͘A���R�̃r���}�����U���̈���Ȃ����̂ł������B
�@����̕��͋K�͂��\�z�O�ɑ傫���A�A���R�̔��U�v�悪�e�ՂȂ炴�錈�ӂ��߂����̂ł��邱�Ƃ���������ɂ�A���ʌR�i�����O�[���j�����ɂ͋���ɂ��������\�܌R�̊S������Ȃ��Ƃ��đ�\�܌R��ᔻ����c�_���o�����A�C���p�[�����𒆎~���ċ���̔r���ɑS�͂������ׂ����Ǝ咣������̂��������B
�@�����A��\�܌R�͑�i�U����W�J������Ԑ��ɂȂ������B
�@���������c���i�ߊ��́u����~���͓G�̔��U���ߔ����Ă���؍��ł��邩�瑬�₩�ɃC���p�[������f�s�����v���v�ƍl�����B
�@�u�G�͋�����ɒ��ӂ��D���Ă���ł��낤����A���̋��ɏ悶�čU����f�s����A�킪��}�̐��s�c�c�͋p���ėe�ՂɂȂ�ł��낤�v�Ǝ咣���i���c�������L�u�r���}���Ɋւ����z�^�v�j�A�i�ߊ��̋��s�_�ɉ�����č��͑��s���ꂽ�B
�@�����Ƃ����ʌR�����ɂ��C���p�[����킳����������A����͎��R�ɃC���h�̓��ɑދ�����ł��낤�Ƃ��������ՁA���ӔC�Ȋy�Ϙ_���������悤�ł���B
�@�C���p�[�����͋��s���ꂽ���A����͑�\�܌R�̖h�q���̂܂��������ɒ������݂Ƃǂ܂��āA�����łȂ��Ƃ��s�\����������\�܌R�̕⋋�@�\������ɒቺ�����A�w���n�������悢�捬���������B
�@�C���p�[�������l���邤���ŃE�B���Q�[�g����̎��Ӗ��͋ɂ߂đ傫�������B
�@�ŏ��̋�����͑�\�܌R���C���p�[���i�U�������ӂ���ɂ������̌_�@�ƂȂ������A����̋�����͑�\�܌R�̔s�ނ�����Â���_�@������o��������ł���B
�@�{�[�Y�̑s�r
�@�C���h�����R�̎Q��ƁA�����R�i�ߊ��E���R�C���h�����{��ȃX�o�X�E�`�����h���E�{�[�X�̉e���͂��������Ȃ������B
�@�C���p�[�����ɂ̓C���h�����R�͑��V���t�c�������ċ��͂����B
�@�{�[�X��Ȃ͋@��邲�Ƃɓ��{�R�̃C���h�i�U��v�������B
�@�����A���{���͑�\�܌R�̍�킪�S������邱�Ƃ�����A�����R�Ƃ̋������ɂ͏��ɓI���������A�̂������R�Q��̂������I�Ӌ`�Ɉ�����ċ������ɓ��݂������B
�@��x�A������킪�͂��܂��A�{�[�X��Ȃ̎��s�͂�C���h����̔M�ӂɂ�����A�܂��p���i�肩��j�Ƃ������x�̐����ڕW�ɑ�����č�킪���s���ꂽ�Ƃ�����B�@�i�������C���h���ɂ́A�����R�͓��{�R�ɂ���ăC���p�[�����Ɉ������܂ꂽ�Ƃ���ӌ�������j�B |

�|�[�Y���
|
�@�C���p�[�����̓C���h�i�U�v�z�̋�ł������낤�B
�@�i�U�̎v�z�����萶���A�ǂ̂悤�ɂ��Č`���A���W����Ă��������́A�푈���x�Ƃ���Ԃ��Ȃ����߂ɓO��I�ɐȂ����Ă݂Ȃ���Ȃ�Ȃ��d��Ȗ�肾�Ǝv���B
�@�C���h�i�U�̔��z�͉p�Ԃ��͂���A����ɂ���ĕĉp�̕����\�A��������̐ؒf�|�����m�푈�̉����Ɏ����Ă䂱���Ƃ����{�c�̐����i�Έ�{��j����o���Ƃ���Ă���B
�@���v��Ƃ��Ă͓�\�ꍆ���v�悪�o���_�ƂȂ�B
�@�������v�z�Ƃ��Ắu�哌�����h���v�̍\�z�Ɠ����悤�ɖ������̃A�W�A��`�A��i�_�������Ƃ��A�x����������̉�������Ɉʒu�Â�������̂ƍl������B
�@����A���̏I���ɂ��ẮA���n���R�������D�������A�ꋫ�Ɋׂ��Ă���̂�m��A���I�������߂�܂łɂ��Ȃ�̓����̂������Ă��邱�Ƃ����Ƃ����B
�@�����Ɂ@�u�`�����h���E�{�[�X�̑s�}�����E���ɂł��ʋꋫ�������Ȑ헪�I���f�������������v�i�r���}���ʌR�i�ߊ��͕Ӑ��O�����̏q���A�h�q���h�q���C����j�����u�C���p�[�����v�j�Ƃ��鎖������������������Ȃ����A���ǁA�C���p�[�����̔ߎS�ȏI���͑�\�܌R�i�ߊ����c�������́u�ߏ�ȍ��w���v�ƁA�����}�����Ȃ������A���邢�͗}���悤�Ƃ��Ȃ��������ʌR�i�ߊ��͕Ӓ����́u�ߏ��ȍ��w���v�ɑ傫�ȐӔC���������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B
�@�T�����C�����̂��̌�
�@���I����A�͕Ӓ����A���c�������͂Ƃ��ɎQ�d�{���t�ƂȂ�A�̂��͕Ӓ����͑叫�ɏ��i���čq�R�i�ߊ��ɁA���c�������͗\���m���w�Z���ɔC����ꂽ�B
�@�͕Ӓ����ɑ����Ĉ��l�l�N�����A�r���}���ʌR�i�ߊ��ɂȂ����ؑ������Y�����͏I�풼�O�A���[�������ɂ��ǂ�����Ƃ��A�叫���i�̓d����Ƃ����B
�@�܂��ɖ����͂�Ĉꏫ���Ȃ����̂ł���B
�@�Ƃ��낪�A�u�����ɂ�����푈�Ƒ����m�푈�̐��s�ɖڂ����������v���͂����A�u�זɓS���̌��݂ɂ�����ߗ��̎g�p�Ƌs�ҁv�u�r���}�e�n�ɂ�����ߗ��̋s�҂��ʼn߂��A�푈�@�K�����{���ׂ��`����ӂ����Ƃ��ċɓ����یR���ٔ����ɂ���Ă`����ƂɎw������A���l���N�\��\�O���A�i��Y�����s���ꂽ�B
�@���c���i�ߊ��̕⋋�y���̍��w���ɂ͏]���Ȃ��Ƃ��č�풆�A�ƒf�ň�t�c�𗦂��đO���𗣒E���������K�M�����͌�ނ̓r�Ɏt�c�����Ƃ���A�̂��\�����ɕғ����ꂽ�B
�@��x�ɂ킽���_�ȋ�����ő�\�܌R��O��I�ɖ|�M�����E�B���Q�[�g�y���͍�풆�̈��l�l�N�O����\�l���A����Ă��������@���C���p�[�������̍��n�тŒė����A�s���̎����Ƃ����B
�@�E�B���X�g���E�`���[�`���p�̓E�B���Q�[�g�y�����u�V�˓I�Ȏw�����v�Ƃ��������B
�@�u�A�W�A�̃��[�����X�v�Ƃ������̂��������B
�@�X�o�X�E�`�����h���E�{�[�X��Ȃ̓����O�[���ɖ߂�A�T�C�S���A��k�o�R�œ����Ɍ����������A���l�ܔN�����\�����A����@����k��s��𗣗���������A�ė����A�s�A�̋q�ƂȂ����B�l�\���������B
�@�@�@�@�l�A�d�|����ꂽ� top
�@����ƌ�Z
�@�E�B���X�g���E�`���[�`���́A���̒��u�����ژ^�v�̂Ȃ��ŁA�u�푈�͊T���Ď���̖ژ^�ł���v�Əq�����Ă��邪�i�����V���|��ψ����A���Z���j�A�����m�푈�ƁA���̂Ȃ��̃C���p�[����������ƁA�u����v�̗]��ɑ����̂ɋ����B
�@���Ƀ��p�[�����͌���ƌ�Z�̘A���������Ǝv���B
�@����Ƃ͉p���̐푈���s�ӎv�������Ɍ��łł���A�r���}�A�C���h��ێ����悤�Ƃ��錈�ӂ��ǂ�قNj��łł��������A�r���}�E���[�g�i���Ӄ��[�g�j���ێ��A�g�債�悤�Ƃ���d�c�����Ɖp�ė������{�̕��j�������ɕs���̂��̂ł��������𗝉������Ȃ��������Ƃ������B
�@������t�́A���Ƃ��ȒP�Ɂu�C���h���O�̌��N�v������A�p�����C���h����ǂ������A�A���R�������p����E�������邱�Ƃ���Ɍ��ɂ��Ă������A�����A�p�����̐����A�R���ɂ������킽�l�����̃������[��������ƁA���{���ӔC�҂̌����������ɍ����̂Ȃ��A�v�������͂Ȃ͂��������̂ł����������킩��B
�@��Z�Ƃ͐헪�E��p�̃~�X�������B
�@���̍ł�����͉̂p��\�l�R����\�܌R�̃C���p�[���i�U���v���m���A����܂ł̍��v���ύX���A��\�܌R���C���p�[���ɗU������Œ@���Ƃ����������ɐ肩���Ă����̂ɁA���̂��Ƃ��\�܌R�͑S���m�炸�A�݂��݂����˖Ӑi���āA���̏p���ɗ��������Ƃł��낤�B
�@����O�������c�A��t�c�𗦂��ăC���p�[����������W�F�I�t���C�E�G�o���X�����iGeoffrey Evans�j�ƁA���������c�ʐM���𗦂��ē����悤�ɃC���p�[����������A���g�j�C�E�u���b�g�E�W�F�[���X(Antony Brett-James�j�͐��A�����̌`�Ŋ��s�����u�C���p�[���v�i���Z��N�A�}�N�~�����Ёj�̂Ȃ��ŁA�C���p�[����͓��{�����̗��j��A�����������ɂ�����ő�̔s�k�ł������Ǝw�E���Ă���B
�@���������s�k�������炵���v���̌���I�Ȃ��̂́A�����炭��픻�f�̌��ł������낤���A���̈Ӗ��ő�\�l�R�̍��]���ɋC�Â��Ȃ��������Ƃ̐ӔC�͂܂��Ƃɑ傫�������Ǝv���B
�@����U��
�@���{�R�́u�A���i����Ă��j���v�Ƀr���}��ǂ�ꂽ�p��R�͈��l��N�܌��A�h�����ă}�j�v�[���ƃ`�b�^�S���ɓ����̂т��B
�@���̌�A�p��R�͐ϋɓI�ȍU�����s�����ƂȂ��A�����ς�h�q�p���ɓO���Ă����B
�@�������s��̏����悤�₭��������\�l�R�͈��l�O�N�\�A�V�������v��𗧂āA���̏������l�R�c�ɖ������B�@�V���v��̓`���h�E�B���͐��ʂ̓��{�R�ɑ���u����U���v�ł������B
�@����͓��{�R���`���h�E�B���͐��ʂɈ������Ă����A���̊ԂɃt�[�R�����ʂ���V�ґ��R��O�i�����A�����ɃE�B���Q�[�g���c�������ē��{�R�̑��w�n����h��������Ƃ����\�z�ł������B
�@�p�R�̓��h����t�[�R���J�n���ւă~�C�g�L�C�i�Ɏ���r���}���k�����ɂ߂ďd�����Ă����B
�@�����́u���Ӄ��[�g�v���ʂ��A�ĉp�����ƏӉ�ΐ����́u�����v���\�ɂ���헪�I�v�悾��������ł��낤�B
�@�u����U���v�́A���̗v����m�ۂ��邽�߂Ƀ`���h�E�B���͐��ʂŗz�������s�Ȃ����Ƃ������̂̂悤�ł���B
�u����U���v�̍��q��
�@�@�J���~���E�̓��{�R�O�i�w�n���U�����邩�̂悤�Ɍ����āA��l�R�c�͍D�@������ő��\�t�c�����i�^���A�V�b�^���j�Ń`���h�E�B����n�͂���A
�@�A���̂��߈��l�l�N�l���܂łɃo��������^���ɂ������Ԑ��̑S�V�H�����݂���A
�@�B�����[�ɓ�t�c���̒e��A�R���A�Ɩ����W�ς���A
�Ƃ������̂ł������B
�@���̌v��Ɋ�đ�\���t�c�i�t�c���c�E�s�E�R�[���������j�͂����͂₭�e�B�f�B������t�H�[�g�E�z���C�g���ւăJ���~���E�ɒʂ��铹�H�����Ɋ����ȍs�����J�n�����B
�@�����ɂ͑�O�\�O�t�c�i�|���c�j���i�o���Ă����̂ŁA��\���t�c�͐��ʂ����O�\�O�t�c���U������`�ɂȂ����B
�@����A���\�t�c�͂������������`���h�E�B���͂̐��ɐi�o���悤�Ƃ����B
�@�e��A�R���A�Ɩ���ςg���b�N�Q�͘A���A�C���p�[�����烂���[�ɓ����A�����̃C���h�l�Z�t�A�u���h�[�U�[�A�J���҂���������A�o�������烂���[�A�^�����ւăJ�{�E�J�n�ւƁA�җ�Ȑ����ŐV���H���݂��i�߂�ꂽ�B
�@���T�m
�@�Ƃ��낪�Ԃ��Ȃ����{�R�̐V�����U����}���T�m����A��l�R�c�̃X�N�[���Y�����͑�\�܌R�̃C���p�[���i�U���ؔ����Ă��邱�ƂɋC�Â����B���l�l�N�ꌎ���ł���B
�@�펀�������{�R�����̈�̂���N�W�������ށA���L�i���{���͍����ɓ��L����������厖�ɕۑ�����B���L�ɂ͎��Ȃ̏����A�����̍s���A�v�悪���ƍׂ��ɋL������A�����ɂ͍�햽�߂܂Ŋ܂܂�Ă����j�A����@�ւ̊����A��@�Ȃǂɂ�鑍�����f�ł���B
�@���Ƃ��Έ꒳���̓`���h�E�B���͂�n��A�W���s�[�R�n�̃W�����O����˔j���ĉ����C���h�E�̔�s��߂��ɂ܂Ő������đ�\�܌R�̓��H�Ԃ̌��ݏA��s��̎g�p�������ɒ��ׂ������B
�@��l�R�c�̒�@�@�̓`���h�E�B���͗��悩��k���r���}�[�тɂ����Ĕ�сA���H�A�{�݂̍\�z�A���ޏW�ς̏������ɎB�e�����B
�@���̌��ʁA�k�r���}����`���h�E�B���͂Ɍ������ċ}�s�b�`�Ō��݂���Ă����퓹�H�⓯�͂̓��݂ɏW�߂�ꂽ�����̊ۑ��A�U�����������̔����m�F���ꂽ�B
�@��O�\�O�t�c�i�|���c�j�͂����͂₭�`���h�E�B���͂�n���ă`���E�q���ɐi�o���Ă����̂ŁA���̑��݂͊m�F����Ă������A���̌�̒n���@�����ŐV���������̏o�����킩��A�₪�āA����͑�\�t�c�A��O�\��t�c�ł��邱�Ƃ����{���̈�̂���m�F���ꂽ�B
�@���͂�C���p�[���i�U�ɂ͋^���������]�n���Ȃ������B
�@�C���p�[������
�@��l�R�c�͏d��Ȋ�H�ɗ������ꂽ�B�X�N�[���Y�����͑�l�R�c�Ƃ��āA����ɂǂ��Ώ����ׂ����ɂ��ċꗶ�����B
�@�G�o���X�A�u���b�g�E�W�F�[���X�����́u�C���p�[���v�ɂ��ƁA�X�N�[���Y�������^��ɍl�����̂̓C���p�[���������ɂ��Ď��炷�邩��
�������Ƃ������B
�@�C���p�[���h�q�͑�l�R�c�ɂƂ��Ď���̉ۑ肾�Ƃ����̂��A�X�N�[���Y�����̐M�O�������Ƃ�����B
�@�Ȃ��Ȃ�C���p�[���̓}�j�v�[���B�̏B�s�ł���A�C���h�w�̓��̌����ɂ��������B
�@�����͉p�A�āA�d�c���{�����Ԑ헪�I�v��ł������B
�@�C���p�[���ɂ͔�s��A�⋋��n�A�e��A�R���A�Ɩ��̏W�ώ{�݁A�a�@�A�H�ꂪ�������B
�@�����C���p�[����������Ȃ�A�}�j�v�[���B���ł̑g�D�I��R�͍���ƂȂ����łȂ��A����A�W�A�ɂ�����p�R�̎m�C�͋ɓx�ɒቺ���A�C���h�̈��S�ۏ����@�ɂ�������B
�@�������{�R���⋋�����Đ��i����A�����}���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤���A�r���}������{�R���쒀����v��̓��[���b�p����ł̏�����������܂ň����������ł��낤�B
�@�C���p�[���̎��ׂ͉p�R�ɂƂ��Ēv���I�ȑ����ł���A�A���R�ɂ������Ă��͂���m��Ȃ��Ō�����������ł��낤�B
�@���̎��i���l�l�N�O���`�����j�A�p�����̊S�̓h�C�c�Ƃ̐킢�ɏW�����A�h�C�c�R�̉p�{�y�����A�A���R�̃m���}���f�B�㗤����i�Z���Z���j�ɐS��D���A�����A�W�A�ł̐킢�͗]����ɂ���Ȃ��������A�X�N�[���Y�����͓��ʂ̐ӔC�҂Ƃ��ăC���p�[���̎�������A�헪��̏d�v���͂ǂ�قǏd�����Ă��d���������邱�Ƃ͂Ȃ��ƍl���Ă����Ƃ����B
�@�X�N�[���Y�����ɂƂ��ĖړI�͖����������B
�@�C���p�[����ێ����邱�ƁA���̂��߃C���p�[�����U�����悤�Ƃ��邢���Ȃ�G���A��������ł��邱�Ƃł������B
�@���]��
�@�������A����͗e�ՂȂ��ƂłȂ������B
�@�n���̂����A�X�N�[���Y�����́u����U���v��@�ɑ����ăC���p�[�������ɂ����������̗p���ׂ��ł͂Ȃ����ƍl���A���̎|���������ɑ�\�l�R�i�ߊ��X���������ɐi�������B
�@���l�l�N�ꌎ������͂��߂ɂ����Ăł���B
�@�������Ƃ̓`���h�E�B���͐��ʂɒ�����Ă���O���������C���p�[�������Ɍ�ނ����A�������œ��{�R���}�����Ƃ�����@�ł���B
�@���]���̗��R�͎O�������Ƃ����B
�@��͒n�㕺�͂Ɋւ���l���ł���B
�@�C���p�[���U���Ɍ��������{���̑�\�܌R�ƁA���ꂪ�h�q�ɂ�����p�����̑�l�R�c�Ƃł͕�����͂��قڋj�R���Ă�����̂ƌ���ꂽ�B
�@�i��\�܌R�͑�O�\�O�A�\�܁A�O�\��t�c�̎O�t�c�Ґ��A��l�R�c�͑�\���A��\�A��\�O�t�c�̎O�t�c�Ґ��A�̂���t�c���j�B
�@���͑�l�R�c����\���t�c���e�B�f�B���n��A���\�t�c���J�{�E�J�n�ƍL��Ȓn��ɕ��U�����Ă������Ƃł���B
�@��\���t�c�Ƒ��\�t�c�Ƃ̊Ԃɂ͓�Z�Z�}�C���ɂ킽��W�����O���ƎR�n����������Ă���A����̎t�c���������x������ɂ́A������̏ꍇ����x�C���p�[���ɖ߂�A�������瑼�t�c�́D���ݒn�܂ʼn��߂ċ}�i���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
�@����ȒʐM�������{�R�ɂ���Đؒf�����댯���������B
�@����ł͓��{�R���S�ʍU���ɏo���ꍇ�A�e���j����邨���ꂪ�������B
�@���̗��R�͋@���́A�Η͂Ɋւ���l���ł���B��R�͂ł͉p�R�����͂邩�ɗL���ȑԐ��ɂ������B
�@��l�R�c�͂���ɋ��͂��鎵��s������i���Ă���̂ɂ������A��\�܌R�ɂ͏펞���͂����s�����Ȃ������B
�@��ԁA�ΖC���p�R�����D���������B���������݂̕��U�z�w�ł́A�����������͂ȋ@���͂��\�����������Ȃ����낤�B
�@��O�̗��R�͕⋋��̍l���ł���B���{�R�͌��n���ق��|�Ƃ��A�]���đO���ւ̗A���ʂ͉p�R�ɔ䂵�ď��Ȃ����̂ƍl����ꂽ�B
�@����ɓ��{���ɂ̓}���_���[���~�C�g�L�C�i�S��������A���S������`���h�E�B���͂Ɍ������Ă��Ȃ�ǍD�ȓ��H�����{���̂тĂ����B
�@�f�B�}�v�[������C���p�[���o�R�A�e�B�f�B���ɂ�����p�R�̕⋋���ƁA�}���_���[���~�C�g�L�C�i�S���ƁA���S������`���h�E�B���͂ɂ̂т铹�H�𗘗p������{�R�̕⋋���Ƃ��r���Ă݂�ƁA���{���̕⋋�����Z���A��l�R�c�ɔ䂵��\�܌R�͂��Ȃ�s���̎��R�������̂Ɣ��f���ꂽ�B
�@�������
�@�L��Ȓn��ɕ��U�������͓W�J�͑�\�l�R����ɍ\�z�����u����U���v���ɂ͓K���Ă����ł��낤���A���{�R���V���ȃC���p�[���i�U�����ӂ��Ă����Ƃ���A���̑S�ʍU���ɑΉ�����ɂ͕s�K���ł������낤�B
�@���{�R�̃C���p�[���i�U�v��ɑ���͕��͂̏W���A�@���͂̔����A�⋋���̒Z�k�ȊO�ɂ���܂��B
�@��l�R�c�̕s���Ƃ���Ƃ�������āA���̗L���Ƃ���Ƃ���������Ď��Ȃ̓y�U�Ő키���Ƃł��낤�B
�@���ꂪ�C���p�[���������ł������B
�@�������̗v�͎̂��̂悤�Ȃ��̂ł������B
�@�@ �@���{�R�̍U�����������Ȃ�Α�\���t�c�͉\�Ȍ��葬�₩�ɓ��{�R�̑O���������痣�E���ăC���p�[���ɓP������B
�@�A�@���̂����C���p�[�����e�B�f�B�����̎l�Z�}�C���n�_�Ȃ����܁Z�}�C���n�_�܂ł͈ꋓ�Ɍ�ނ��A���Ԗh�q�w�n��݂��Ȃ��B���n�_�Ɉ���c��z�u���Ďt�c��͂̃C���p�[����ނ����삷��B�t�c��͂̓C���p�[���ɓ����������ƌR�c�̗\�����ƂȂ�B
�@�B �@�r�V�F���v�[���t�߂ɖh�q�w�n���\�z���A��q���c�̌�ނ����삷��B�C���p�[�����e�B�f�B������j��B
�@�C �@���\�t�c�̓J�{�E�J�n�ɂ�������{�R�̍s����@�s����B���������ݐ����z���ĒJ�n��쉺���Ȃ��B
�@�D �@�����Ŗ��߂�҂��ă����[�t�߂Ɏt�c���W������B
�@�^�����o�������̌��݂ɂ������Ă���J���҂ƌ��ݎ��ށA�@�B�������g����B
�@���ꂪ�I��������ƁA�t�c�̓^�����o���������V�F�i���Ɍ������ď��X�ɓP�ނ���B
�@�����[�̏W�ώ��ނ̓C���p�[���Ɉڑ�����B�ڑ�����Ȃ��͎̂t�c�̓P�ނɐ悾���Ĕj��B
�@�E �@�V�F�i���̓C���p�[���̏d�v�Ȍ����ł���B���\�t�c�͂����ɂƂǂ܂��Ėh�q����B
�@�F �@���\�O�t�c�̎�͂̓R�q�}���C���p�[������h�q���A�C���p�[�������ɓ����Ă�����{�R�̌��łɂ�����B���t�c�ɂ̓C���h����߂���\�����V���[�g���c�Ƒ��l��ԗ��c�����������B
�@�G �@�E�N�����ɔz�u����Ă��铯�t�c�̈���c�͖k������_���Ɍ��������{�R�̍U���ɂ�����B
�@�H �@�C���p�[�������̔�s��A�����W�Ϗ��A�a�@�̖h�q�ɂ͏��݂̊e�핺�͂������Ėh�q����g�D���A����ɂ��Ă�B
�@�L���Ȑ�@
�@���̑�Ăɂ��čl���Ă݂悤�B
�@���Ƃ��`���h�E�B���͂̐��ݒn��A�܂�`���E�q���œ��{�R���}�����Ƃ����v��͂ǂ����낤���B
�@����́A���łɎ������݂������B
�@��������i���l�O�N�\�ꌎ�j�`���E�q���ɐi�o������O�\�O�t�c�͂����܂��t�H�[�g�E�z���C�g�A�t�@�����A�n�J�̗v�n�����Ő�̂��Ă�������ł���B
�@�`���E�q���ł̖h�q�͍���ł������B
�@�`���h�E�B����n�͂��A�k���r���}�ɐi�o���đ�����s���Ƃ����v��͂ǂ��ł��낤���B
�@���̏ꍇ�͑�K�͂ȓn�͍������{���Ȃ���Ȃ炸�A�n�͒���ɗD���ȓ��{�R�ɐ^���ʂ����������B
�@����ɕ⋋�������сA���̈ێ����ނ��������B
�@����ɔ����������́A�������ɗL���Ȑ�@�ƌ������B
�@�C���p�[�������̊O�f�ɖh�q���������A�����ɓ��{�R����������B
�@�����ł͓��H�Ԃ����A��Ԃ���p���ڂ̉ΖC���爽�鋭�͂ȋ@��������Ґ����Ă����B
�@�q������ɂ�����x������B
�@���{�R���O�f�h�q���̈�Ɍ���ꂽ��A�Ԕ�����ꂸ�S�@�������𓊓����A�W���Η͂𗁂т��Ēׂ��B
�@���̐w�n�ɗ�����A�@�������͔��]���Ă����@���B
�@�C���p�[�������ɂ̓r���}�E�C���h�����n�т��������W�����O�����d��R�n���Ȃ��B
�@�n�������J������Đ�ԁA�q��@�̊������S��������̂͂Ȃ��B
�@�]���Ď��Ă�͂���Z�Ƃ���A��l�R�c�͂�����Z�̗͂������đ�\�܌R�ɑΉ��ł���B
�@�Ƃ��낪��\�܌R�͕��U���ĊO�f�w�n�ɐڋ߂��ł���B
�@��w�n�Ɏw��������͂��O�Ƃ���A���r�̉����ɂ��敾�ƁA�⋋��Ŕ����ł����͈͂���x�ɗ�����������Ȃ��B
�@�����Đ퓬�͏�Ɉ�Z�Έ�̊����Ő����B
�@��������ĘJ��҂Ƃ��Ƃ����̂ł���B
�@�����X�[���̓�������܌��܂ŊO�f�̖h�q�����ێ�����悢�B
�@���ꂩ��́u�厩�R�v���킢�����߂Ă����B
�@�����X�[���̂Ȃ��ɑ�\�܌R�͎��ł��邾�낤����ł���B
�@�X�N�[���Y�����̓������v��͑�\�l�R�i�ߊ��X���������̂��Ƃɒ�o����A�₪�ď��F���ꂽ�B
�@���͓��{�R�̑S�ʍU���J�n��T�m�������ƁA���A�����ɂ��đO��������P�ނ����邩�A�܂��o�����ƃ����[�ԁA����Ƀ����[�ȓ�̃J�{�E�J�n�œ��H�H���ɓ����Ă��鑽���̘J���ҌQ���ǂ̂悤�ɂ��ăC���p�[���Ɉ����g�������邩�ł��������A���̓_�͌��n�R�i�ߊ��Ƃ��ẴX�N�[���Y�����̔��f�Ɉς���ꂽ�B
�@㩂ɂ͂܂�
�@�������ēW�J���ꂽ�������݂͂��ƂɁu�����v���A�u�L�j�ȗ��̍ő�̔s�k�v����{�R�ɂ������邱�ƂɂȂ邪�A��\�l�R���̍��ɂ����s�����i�����j�͂������B
�@�R�q�}���ʂɐi�o�����c�̕��͂�����������Ƃł���B
�@�p�R�͏������̐i�o�͑z�肵�Ă������A���͂ȁA��t�c�ȏ�̑啺�͂��E�N�����R����˔j���ăC���p�[���k���n��ɏo�Ă���Ƃ͗\�z�����A�]���ėc�̏o���ɋC�Â��Ă���̕��͑��h�ɂ͑傢�ɂ���Ă��B
�@�܂��������̌v��ɏ]���đ�\���t�c�͑f�����|���c�̍U����U�肫���ēP�ނ��ׂ��ł������̂ɁA���̋@�������ăg���U���A�V���O���Ԃ̋��A�Ȓn��ɕ�͂���ċ��Ɋׂ������Ƃ�����B
�@�������A����ȊO�ł́A�قڊ��S�ɑ�\�܌R�̗����������B
�@�����̃r���}���ʎԂ̍��Q�d�������s�j�������́u�C���p�[�����v�i�h�q���h�q���C����j�����j�̂Ȃ��ŁA���̂悤�ɏq�����Ă���B
�@�u���͏I���A�X���������̉�ژ^�w�s�k��菟���ցx��ǂ�Ŝ��R�Ƃ����B
�@�S�����z���ɂ��Ȃ��������Ƃ�������Ă�������ł���B
�@��l�R�c�̓C���p�[�����n�֎���I�Ɍ�ނ���͂��W�����ē��{�R�̐i�o��҂��\���Ă����Ƃ����̂ł���B�c�c
�@���߂ēG�̌�ލ���m�����Ƃ��A�d�������ŃA���J���̌��s��ːi���Ă����������̏����̎p�����̋����ɂ�݂�����A�Μ��i���j�̎v���ɑł��ꂽ�B�c�c
�@���́A�����ɉ͕ӑ叫��K�˂Ĉȏ�̂��Ƃ�����B
�@�͕ӏ��R�����߂Ă��̂��Ƃ�m��A���R����v�������ꂽ�v
�܁A ����ƌ�Z�̐푈 top
1�@��\�ꍆ���
�@�C���p�[�����ɂ������Z�̂͂��܂�͓�\�ꍆ���v�悾�����Ǝv���B
�@����̓C���h�i�U�̌v�悪��������̓I�ȍ��v��̌`�ōŏ��ɓo�ꂵ�����̂ŁA���l���i���a�\���j�N�����A����R�i���R�j�̍���C�Q�d���������ɂ���Ĕ��āA�N�����ꂽ�B
�@�ђ����̓r���}���̑����i�k�������j�A��\�܌R�̎Q�d���Ƃ߂����Ɠ���R�ɓ]�����B
�@�юQ�d�͑��R�̂Ȃ��Łu���C���h�͋���ۂ��B�G�̕s���ɏ悶�A���܍s���ăC���p�[����A���i����Ă��j���ׂ����v�Ǝ咣���A�C���p�[�����z���āA�����S���K�b�g�܂Ői�U�������ȕ@���������B
�@�������юQ�d�͔�s�@�Ń`���h�E�B���͂̐��܂ŏo�����Ƃ����邾���ŁA�n��̏͂قƂ�ǒm�炸�A������A���J���R���ɂ��Ă͉��̗\���m���������Ă��Ȃ������Ƃ����B
�@�����A��{�c�̍��ۂɂ������Ґ��M�Q�d�͒e��A�Ɩ��̕⋋�ʂɂ��Ė₢�߁A�u���z�͂悢���A���s�͍���v�Ƃ������B
�@�������юQ�d�̔M�ӂɂ�����A�ҎQ�d�͍��v��̍쐬�ɓ��ӂ����Ƃ����B
�@���v��̍\�z�͎��̂悤�Ȃ��̂ł������B��\���t�c�������ăC���p�[�����ʂɐi�U���A���݂̓G�����ł����̂��V���O�n�b�g�A�`���p�����N�A�o�_���v�[���A�V���W���i�[���̐��ȓ��̒n����m�ۂ���B
�@��O�\�O�t�c�̈ꕔ�������ăA�L���u����`�b�^�S�����ʂ̓G�����ł��A�]�������K���W�[�ȓ�̒n����m�ۂ���B
�@��O�\�O�t�c�̎�͂͏̕ω��ɑ���������悤�ɃJ�����t�߂ɏW���ҋ@�����i�헪�\���j�B
�@��O�q��R�͎�͂������ăJ���J�b�^���ʂ̓G�q���n����P���A���̂��ƃ`�b�^�S���t�߂ɍq���n�𐄐i���A�C���h���k���ɂ�����G�q�͂̑|�ł��͂���B
�@���J�n�͈��l��N�\����A���{�A���I���͏\�ꌎ��{�Ƃ���B
�@�C���h�i�U�̎v�z
�@���̌v��͈��l��N�����ܓ��A����R���i�ߕ�����u�C���h���k���ɑ���h�q�n��g���Ɋւ���ӌ��v�Ƃ��đ�{�c�ɒ�o���ꂽ�B
�@��{�c�͌v��ɋ^�`�����������A������̊ϓ_����A�Ƃ�����������\����A��폀���̖��߂����R�ɉ����A����R�����\�܌R�ɓ`�B���ꂽ�B
�@��������\�܌R�͓�F���������B
�@���̌��ʁA�v��͂��肼�����A���������z���Ă̐V���Ȑi�U���͓���R�̋���K�v�Ƃ��邱�ƂƂ���A������A��\�ꍆ���v��͒I�グ���ꂽ�B
�@��{�c���l��N�\�ꌎ��\�O���A�����ɍ��̎��{���u�ۗ��v����Ƃ̖��߂��o�����B
�@��������{�c�̖��߂́u�����{�̌�����ۗ��v����Ƃ������ƂŁA���̒��~���߂ł͂Ȃ������B
�@���߂�
�@�@�@�u�{�������{�����߂���ꍇ�A���̊J�n�����͓��i���l�O�N�j����K���Ƃ��ׂ��A�ꉞ��폀���͂��̎�����ړr�Ƃ��Đi�߂�ꂽ���v
�@�A�@�u����Ɏ��{���̍�폀���͐i�߂�ꂽ�������c�̈ړ��A��픭�N���t�߂ɂ�������R���i�̏W�ςȂǂ͕ʂɎw��������܂ŕۗ�����ꂽ���v
�Ƃ������̂ŁA�͂������폀���̌p�����w�����Ă���B
�i�h�q���h�q���C����j�����u�C���p�[�����v�j
�@�]���ē���R���玦�B���ꂽ��폀�����߂Ɋ�č��v��̌����A��퓹�H�̍\�z�ɂƂ肩�����Ă�����\�܌R�͏�����Ƃ����̂܂܌p�������B
�@����͍��R�Ƃ��ē��R�̂��Ƃł������낤���A����������폀�����ςݏd�˂��Ă䂭�����ɒm�炸�m�炸�̊ԂɃC���h�i�U�̎v�z����������A���ꂪ��̐����ƂȂ�A�}���������Ȃ��Ȃ�A�₪�č����{�̎��ԂɗU�����܂�Ă䂭���ƂɂȂ�B
�@��\�ꍆ���v��͌��ǁA�C���p�[�����ƂȂ��Č����������A���{���푈�ɓ����Ă䂭�v���Z�X�͂��������ɂ����āA���������ł���B
�@�Ύx�헪����Έ���
�@�C�ɂȂ�̂́u�Ύx�헪�v����u�Έ��v�ւ̂��킽�������]���ł���B
�@�r���}���̓r���}�E���[�g�i���ӕ⋋�H�j���Ւf���A�d�c�������Ǘ��������邱�Ƃɂ���ē����푈���I���ɓ������Ƃ������̂ŁA����͍��J�n������C���p�[�����O�܂ň�т��Ď��ꂽ���ړI�ł������B
�@�C���p�[�����ł������̍\�z�ɂ͓����A�b�T���̃��h�t�߂ɐi�o���āA���Ӄ��[�g��ؒf���悤�Ƃ���v�悪�������B
�@��U�����ʂ̓C���p�[���ł��������A�Ȃ������푈�����ւ̓����̍��v�z�͐����Ă����B
�@�Ƃ��낪�Q���A�Έ����D�悵�A�C���h�̔��p�Ɨ��^�����h�����ĉp�����C���h����ǂ������A�A���R�������p����E�������A����ɂ���đ����m�푈�������������Ƃ���ӌ������������Ă���B
�@�₪�ďd�c�����ւ̗A���H��f���낤�Ƃ���l���͎����A�S�͂����ς�C���h�Ɉڂ�B
�@�C���p�[����킪�r���}�E���[�g�̎Ւf�����Ƃ�����̂ł������Ȃ�A�r���}���Ƃ��Ă̈�ѐ��͎���A��`�����������A�]���ď����̃R���Z���T�X�邱�Ƃ͂ł����ł��낤�B
�@�⋋�y��
�@��Z�̓T�^�͎��R�i�A�b�T���̉J�j�̖����A�⋋�̌y���������Ƃ�����B
�@�C���p�[�����́u�Ɩ��͓G�n�ɂ��v�Ƃ����Ă킸����Z�����̗��a�������g�s���čs�������������B
�@�������i�H�͌��n���J�̎R�x�E���ђn�тŁA���B��������a�͂Ȃ��A�g�s�Ɩ����������J���͂��������Ă����B
�@�q��@�̎x�������҂ł��Ȃ������B
�@���������헪�̋]���������ꂽ�̂��Ŗk�[�́u�̐��v�[���������ꂽ�c�ł������B
�@�c�̍������������ɋ^�`�������A����ɒ�R���A�Ō�ɔ�������͕̂⋋�����閴�c���i�ߊ��̍��w���ɑ��Ăł������B
�@���������́A����ȏ�A�R�̖��߂ɂ����������Ƃ͕��c���u�k���v��������̂��Ƃ��ē{��A���ɓƒf�A�S���c�𗦂��Đw�n���̂Ă��B�⋋������n�_�ɂ܂ʼn���Ƃ����̂ł���B
�@�l�Ő���𗣒E������͂��������A��������������������܂��ĔC�n�𗣂ꂽ���Ƃ�����B
�@�������헪�P�ʂł�����t�c����̂ƂȂ��Đ���𗣒E�����Ƃ����O��͂Ȃ��B
�@���������͕⋋������ӂ߂�Ƃ������̂��ƂɈ�t�c��ČR�̓����ɒ��킵�����ƂɂȂ�B
�@�������A���̎������͎�����A���Ă����B
�@�������c�̐�����E�͍Օ��c�̑��w���p��R�̑O�ɂ��炯�������ƂɂȂ�A�Օ��c�͂���ɋꋫ�ɒǂ����܂ꂽ�B
�@���R�����邱�Ƃƕ⋋���y�����邱�Ƃ́A���Lj�̂��Ƃ��Ӗ�����B
�@�l�Ԃ̂����肪���R�ɔs�ꂽ�Ƃ������Ƃł��낤�B
�@�W�����O���E�E�H�[
�@������A��Z�̑傫�ȗ�Ƃ��āA�����C���h�����R�̗V������K�˂��Ƃ��E���������q�������Ă݂����B
�@�����q�͏T�����قǂ̑傫���A�����͓�Z�y�[�W�قǁA�\���͊D�F�ŁA�����Ɂu�W�����O���E�E�H�[�v�iJungle War�j�Ə�����Ă������B
�@�y�[�W�������Ă݂�ƁA�}���[���ɂ�������{�R�̐�@��}����ŁA���ƍׂ��ɋL�q���Ă������B
�@�����R���i�o����O�A���̂�����ɂ͉p��R���o�v���Ă����B
�@���̐܁A�����q�͒u���Y�ꂽ���̂̂悤�ł������B
�@���Ƃ��Γ��{�R�͉p�R�h���w�n�ɂ������A�����ɐ�ԁA�C���A���������̂����݂ȘA�q�v���[�������đ��w����U�߂āA������ח����������A���{�R�̓��ӂƂ��鑤�w�U�������̐������ł������B
�@���{�R�͂������Đ��ʂ���U�����Ă��Ȃ��A���ʂɂ͈ꕔ�����āA��͂͊�}��铽���đ��w�ɂ܂��A�ӕ\�����čU�����Ă���Ƌ������Ă������B
�@�����q�ɂ́A���̎������}���[���̍��Q�d�Ґ��M�卲�̒k�b����Ƃ������̂ł���ƋL����Ă������B
�@�ҎQ�d�̓V���K�|�[���U����A�}���[���������ɐ�������X�Ƃ��Č��A���̒k�b�������̐V���̑��ʂɑS�ʂԂ��đ�X�I�Ɍf�ڂ��ꂽ���Ƃ�����B
�@�p�R�͂�����������Ȃ������B
�@�����ɗ���ɂ�������{�R�̓`���I��@�����ĂƂ�A�����������ĕ����ɔz�z���A���̑Γ��틳�͂Ƃ��ČP�����d�˂Ă����悤�ł���B
�@���́A���̏����q��厖�Ɏ����Ă������A�̂��A�����T�C�S���Ɉڂ�ƁA�J�{�E�J�n�Ő���Ă����p��R���\�t�c��������암�C���h�V�i�̂��߃T�C�S���ɏ㗤���Ă����B
�@�����q��������ꂽ��낢�Ǝv���āA���͋}���ŏċp�����B
�@�����̃r���}����ł͓��{�R�̑��w�U���͐����������A�̂��A���R�͓��{�R�̊�P��@�ɑ���V��@��҂ݏo���A����������Ē��킵�Ă������ߓ��{�R�̍U���͂ǂ��ł��ڍ�����悤�ɂȂ����B
�@���{�R�̎�̓��͂��炯������Ă����B�Ƃ��낪�A���̂��Ƃɓ��{�R�͋C�Â��Ȃ������B
�@�E�B���Q�[�g���
�@�����������{�R�̓`���I���w�U����@�ɐ^���ʂ��璧�킵���̂̓E�B���Q�[�g�y���̎w������ēx�ɂ킽�������ł������B
�@����̋�����ł̓E�B���O�[�g�y���͉q�\���t�c�̔w��n�̂悤�ɑ���ʂ��Ă��������A����̋�����ł͑啺�͂������đ�\�܌R�̔w��n���h�����v�_�Ɍ��łȗ��̐w�n���\�z���A��������Q�������W�J�����B
�@��\�܌R�̌���h�q�Ԑ��͍������A�������v�_�w�n�̑��݂ɂ���č����͒����ɂ킽���đ������B
�@����ɂ́A�ǂ̂悤�Ȑ�@�����ʂȂ��A���{�R���ӂ̑��w�U����@�A��P�A��͐�p�͂قڊ��S�ɕ������߂�ꂽ�`�������B
�@�p��R�̐V��@�́u�������v�i��A�L���u���B���l�l�N�l���J�n�j�ɂ�����V���[�C���~�n�̐퓬�ł��łɎ�����Ă����B
�@���̖~�n�͓�����܁Z�Z���[�g���A��k�O�Z�Z�Z���[�g���قǂ̋����n�悾�������A�p��R�掵�t�c�̎�͌܁Z�Z�Z���͐�Ԉ�Z�Z�p�A�����ݎԌ܁Z�Z�p�������Ă����ɂ��A���Ԃ͂����݂ɒn��i�����イ�j�⎀�p�𗘗p���ĕ����U�����A��ɂȂ�Ɛ�Ԃ��O���ɔz�u���A�����ɉΖC�𐘂��A�S��ԂŊԌ����ӂ����œ��{�R�̖�P��j�~�����B
�@�������ē��{�R�̕�͉��ɓ�T�ԁA�⋋������ċ����Ȃ������B
�@���w�U���̐�@�͂��͂�ʗp���Ȃ��Ȃ��Ă����B
�@���w�U���͕��́A�e��A�����A���ށA�Ɩ����\���łȂ��A���͕����i�q��@�A��ԁA�C�������j�̎x����]����҂ł��Ȃ������ȗ͂������āA���傫�ȗ͂ɑR����B��̐�@�ł������B
�@�܂����w�U���͐��ʂ���̍U��������ȏꍇ�A���ʂł̑Ό�������A�G�̕⋋�H�����������Ƃɂ���ēG�ɐw�n����̗��E�������悤�Ƃ����@�ł������B
�@���ꂪ�ʗp���Ȃ��Ƃ����Ă͓��{�R�Ƃ��Ă����肠���Ă���B
�@�W���M�X�J���̖�
�@�W���M�X�J���͉����̌R���������ɂ������āA��ɑ����̉ƒ{��A��Ă��������A���̌̒q�ɂȂ���Ė��c�����R����ʂ̋��A�n�A�ۂ���핔���ɓ��s�������B
�@�r���}���ʌR�̑q���Q�d�i�����C�j�ɂ��ƁA�ŏ��̌v��ł́u�ʋ��v��O�����A�u���n�n�v���Z�Z�Z�����W�߂���肾�����B
�@����́u����v��v�̂Ȃ��́u�A���́E��Ɨ͂̒��B�����v��v�̈ꕔ���Ȃ����̂ŁA�]���Ĉ��l�l�N�O�����݂ŋ����i�m���Ƃ��j��l���p�A�u��Ɨp�l�v�v�l�㖜�l�B����v�悾�����Ƃ����B
�@����ɂ���čq��@�̉����������̕⋋�ɗ]��ˑ����邱�ƂȂ��A�r���}�E�C���h�����̖��l�E���ђn�т�Ɨ͂Ői�ނ��Ƃ��ł���Ƃ����̂ł���B
�@�����͕���A�e��A���ނ̉^���Ɏg���A�Ɩ����s������ΎE���ĐH�ׂ�B
�@������H�ׂ�Ζ���Ƃ�Ȃ��Ă��ށB
�@�����S���l�͖���قƂ�ǐH�ׂȂ����A����͐�������H�Ƃ��Ă��邩�炾�Ƃ����B
�@�]���āu�Ɖ҂�G�n�ɂ��v�Ƃ������{�R�̓`���I��@�͂����ɂ͂��߂Đ�������Ƃ����B
�@�����S���R�ȗ��A�͂��߂Ă̐l�ԂƓ����̑����͂ɂ����ł���ƁA��Q�d�͌������B
�@�c�̋{��x���i���ːi���B�x�����͋{��ɎO�Y�����j�͍��O�A���Z�Z���̋����W�߁A�����A��Ă䂭���ߓ�܁Z���̕����������ē��ʂ̕⋋������Ґ������B
�@�������A�قƂ�ǂ̕����͋��ɂ���������Ƃ����Ȃ������B
�@�P���͂܂����������ɓ��邱�Ƃ���͂��߁A���Ƀr���}�̋��͈Ƃ��������Ƃ��Ȃ��̂ňƂ����邱�Ƃɋ����炵�A����ɈƂɉו���ς�ŕ������Ƃ������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
�@���ꂪ�ł��Ă��A���ꂾ���̋��������ɂ��ă`���h�E�B���̑�͂�n�点�邩�ł���B
�@���̓n��
�@�⋋�����́A���炩���ߓ�Z������O�Z���́u�w�����v��I�B
�@�����͓n���D�ɏ��A�M�ׂ�Ŏw�����̌D�i����j���Ƃ��ėU�����A���̂��Ƃő����̋����͂̂Ȃ��ɒǂ����݁A�w�����̂��Ƃɂ��ĉj���œn�͂����邱�Ƃɂ��āA�����ȉ͂ŗ��K�����B
�@���K�͐����������B
�@�������`���h�E�B���̖{���͑傫���A����������B
�@����̓n���i���l�l�N�O���\�ܓ���j�ł͎O�Z�Z���̋����͂ɒǂ������A�͂����ċ��ꂨ�̂̂����́A�����f�����́A�͂ɓ����ĉj���͂��߂����̂́A�r���Ŋ݂Ɉ����Ԃ����̂����o�����B
�@�E���ɉj���Â������̂����������A�r���ŗ͂��A�����ɖv������́A�����A���݂�����Ă䂭���̂��������B
�@���������n��I���݂ɔ������������r�[�A�������ē|�����̂��������B
�@�Â��đ���̓n�͂Ɉڂ�A�c��̋����͂̒��ɒǂ����B
�@�悤�₭�锼�̎O������A�n�͂��I�������A��Z�Z���قǂ͔�ꂫ���ē������A���ǁA��r�I���C�ŁA�ו����ڂ��ăE�N�����R���ɐi�͓̂�Z�Z���O�ゾ�����Ƃ����B
�@���̎��̂��Ƃ������\���A���̊��S�]�P�Y���т́u���A���Ƃ��Ɏ��͂������Ă̕����ɂ͋����������v���ł����v�Ɖ�z���Ă���B
�@�i���c���ҁA�ܔ���s�u�r���}����v���h�q���h�q���C����j�����u�C���p�[�����v�j�B
�@���͏s�ӂȖ��ѓ��̒ʉ߂ɂ͓��Ă��Ȃ������B
�@���тɂ͖q���n���Ȃ��A���͂����܂������ׂ����B���m�ɂ͋������̌o�����Ȃ��A�e������������疧�т̂Ȃ��ɋ���ǂ��Ƃ����ĉ����a�C�����o�����B
�@�Q���̗]�蕺�m�͋����E���Ď���̐H�ƂƂ����B�����Đ����čĂу`���h�E�B���͂�n�鋍�͂Ȃ��A�n�C�͔��Ɍ����A�ۂ̓W�����O���ɂ͂���O�ɑS�������Ԃ����B
�@�W���M�X�J���̖��͈꒩�ɂ��Ēׂ����B
�@���p�̐킢
�@�C���p�[����킪���̂悤�Ȍ���ƌ�Z�̏W�ς������Ƃ���ƁA�ǂ����Ă�������u���p�̐킢�v�Ƃ���������Ȃ��B
�@�܂��S�ʓI�Ȑ�ǂ��l���Ă݂����B
�@�C���p�[����킪�J�n����鎞�@�i���l�l�N�O���j�ɂ́A���łɑ���|�����m�푈�̋A���͂قڌ��܂��Ă����Ǝv���B
�@���[���b�p����ł͈��l�O�N�Ă̔��ɐ�ǂ͕�������������B
�@�p���͊C���ʂ̎��R���قډ��A�\�A�̓��j���O���[�h�A���X�g�t��������A�암�E�N���C�i�ɑO�i�A�p�ČR�̓V�V���[���ɏ㗤�A�C�^���A�̃��b�\���[�j�����͕����B
�@���l�l�N�t�ɂ͕ČR�̃x���������Ԕ������͂��܂�B
�@�₪�ă��[�}���������A�A���R�̓m���}���f�B�ɏ㗤�A�\�A�R�̓h�C�c����̒������ɐ[������ł����B
�@�����ĉ����Ă̑Γƍ�킪���悢��J�n���ꂽ�̂ł���B
�@�����ւ̖��炩�ȓW�]�ɗ����ă`���[�`���ƃ��[�Y�x���g�́A�������A�푈�I���̕����Ƃ��Đ��������̖������~���������ł������Ă���B
�@����A�����m����̃��}��̓��[���b�p�������N�����A���l��N�Z���ɖK�ꂽ�B
�@�~�b�h�E�F�C�C��ɂ�������{�C�R�̌���I�s�k�ł���B
�@����ɂ���ĘA���͑��́u�C��哱���v�͎����A��ǂ͍U������琨�ւƑ傫�ȓ]����������ꂽ�B
�@���l�O�N�ɂ̓K�_���J�i������D���A�������N�_�Ƃ���A�����J�R�́u���`�����v���͂��܂�A���l�l�N�ɂ͂���ƁA�A�����J�R�͒��������m�����ɐ��͂�L���A���{�{�y�U���ւ̑�����ł߂Ă䂭�B
�@�p�ė����̐����Ƃ͑�������u�h�C�c�͓��{���s��Ă��푈�ɏ���������Ȃ����A���{�̓h�C�c���s���ΐ푈�ɂ͏������Ȃ��v�Ƃ݂Ă����B
�@�i�q�E�b�E�j�E�G���\�[���A���R���F��E�u����E���j�v�j�B
�@���̃h�C�c�͈��l�l�N�t�ɂ͔s�F�Z���A�܂����{���g�����葫���������悤�ɊO�f�w�n��D���������B
�@���łɑ吨�͌����Ă����B�V����K�v�Ƃ���ł͂Ȃ��������A�C���p�[�����ɂ���Đ�ǂ����E�����鎞�@�ł��Ȃ������B
�@����p�̐킢�Ƃ��鏊�Ȃł���B
�@�������A�����ɐ�ǂ���ł��낤�Ƃ��A������ŏI�i�K�ɂ����ċt�]���邱�Ƃ͉\�ł��낤���A������������͐�j�ɂ��L�^����Ă���B
�@�������A����͐헪�A��p���܂����Ă���ꍇ�Ɍ�����B
�@�C���p�[�����ɂ́A���ꂪ�Ȃ������B
�@���낢�h�q��
�@�r���}���ł́A���܂��܂̖h�q�����ݒ肳�ꂽ�B
�@���Ƃ��Γ����A�}���[���̑��w����̂��߂ɍl����ꂽ�h�q���͓암�r���}�̃e�i�Z�����n��̐��̋��E���i�T���E�B���͂̐����A�V�b�^���͂̐����͖��炩�łȂ��j�ł������B
�@�����ō��ړI���r���}�ɂ���A���R�����ł��A���Ӄ��[�g���Ւf���邱�ƂɂȂ�ƁA�S�r���}�̊m�ۂ��K�v�Ƃ���A���{�R�͂��̂܂ܑS�r���}���̂����B
�@�����őS�r���}�̈�����m�ۂ��邽�߂ɂ͖h�q�����ǂ��ɐݒ肷�邩�����ɂȂ�A���܂��܂̗v�����l����ꂽ�B
�@���̂��������A�k���ɂ��Ă͕��@�A�f�ЁA���z�A�~�C�g�L�C�i�A�J�}�C�������Ԑ���h�q���Ƃ��邱�Ƃő���̈ӌ��͈�v�������A�����ɂ��ẮA
�@�@�@�W���s�[�R�n�i�C�����W���ƃ`���h�E�B�����̒��Ԃ𓌖k���琼��ɐL�т�R�n�j�̗v���A
�@�A�@�`���h�E�B���͂̐��A
�@�B�@�A���J���R�n�i���������j�A
�ȂNJe��̍l�������������B
�@�r���}�͓������^�C�E�r���}�R�n�A�V���������A���t�v�R�n�A�T���E�B�����i�{�]�j�A�k�����p�g�J�C�R�n�A�t�[�R���J�n�A�������A���J���R�n�ɂ���Ĉ͂܂�A��Ɠ���A�쐼�͊C�ɖʂ��A���R�̗v�Q�����̂܂܍��������`�����A�����قǖh�q��A�b�܂ꂽ���y�͑��ɂȂ����Ƃ��l����ꂽ�B
�@���������k���ɏd�c�R�A�k���ɕĎx�A���R�A�����Ɛ��암�ɉp��R�̑�R�������āA���ꂼ�ꑊ�ĉ����ė��U����Ƃ����ٔ��������ɂ����ẮA�����ɂ���ăr���}�̈�����ɂ킽���Ċm�ۂ�����悤�ȓK�Ȗh�q���͗e�Ղɐݒ肵���Ȃ������B
�@�����Ŗh�q�n����C���h���k���Ɋg�����悤�Ƃ���c�_���o�Ă���B
�@���ꂪ����R�Q�d���������̍쐬�����u��\�ꍆ���v��v�ŁA����͈ꎞ�A�I�グ���ꂽ���A���ǁA�C���p�[�����ƂȂ��Ď��������B
�@�����Ȃ�ƁA���x�́A�C���p�[������邽�߂ɂ́A�ǂ��ɖh�q������������悢�������ɂȂ�A
�@�@�@�C���p�[�������̋u�ˁA
�@�A�@�S���K�b�g�A�f�B�}�v�[���A�V���`�A�[����A�˂�A���J���R�n���[�̗v���A
�@�B�@�V���O�n�b�g�A�`���p�����N�A�o�_���v�[���A�V���W���i�[���A�]�������K���W�[��A�˂�v���A
�@�C�@�V������n�A
�@�D�@�u���}�v�g���͂̐��A
�Ƃ������\�z�����X�ɒ�N���ꂽ�B
�@�C���p�[������A���{�R�͔s���̉ߒ��Ŗh�q����ݒ肵�A����𒀎���ނ����Ă䂭���A���������h�q���͍ŏ������V�I�A�}���_���[�A�G�i���W�����A�A�L���u��A�˂�v���A�����g���O�[����y�O�[�R�n���ւă����O�[���t�߂ɂ�����v���A�Ōオ�V�b�^���̗͂v���ł������B
�@�������A������������Ƃ����ԂɘA���R�̋@�B�������ɓ˔j���ꂽ�B
�@����A�p�R�����{�R�̃r���}�i�U��펞�ɂ͖h�q�����A
�@�@�@�p�v���A���[�������A�����O�C��A�˂���i���l��N�ꌎ�B���{�R�̃r���}�i�����O�j�A
�@�A�@�T���E�B���͐��݂̐��A
�@�B�@�V�b�^���͂̐��A
�@�C�@�y�O�[�R�n�̐��A
�@�D�@�v���[���A�g���O�[�̐��A
�@�E�@�}���_���[�A�G�i���W���������Ԑ�
�@�ƁA���X�ɐݒ肵�A��ނ��Ă���B
�@�O���̉����R�ɂƂ��ăr���}�̈�����m�ۂ�����h�q���͌����A�r���}�����ɂ͑��݂��Ȃ������B
�@�r���}�h�q��
�@����Ȃ�r���}���g�ɂƂ��ăr���}�h�q�̐헪�v���Ƃ�����悤�Ȃ��̂͂��������낤���B
�@�r���}�̗��j������ƁA������������A�ɉh���A�Ő}���g�傳��Ă���ƁA�Ō�ɂ́A�_��A�A�b�T���̍U���Ɏ肪�����Ă���B
�@�r���}�ł́u�̑�ȉ��v�Ƃ���鉤�l���O�l���݂���B
�@�@�@�p�K�������i��|�\�O���I�j�̃A�m�[���^�[���i��Z�l�l�`��Z�����N�݈ʁj�A
�@�A�@�g���O�[�����i�\�Z�`�\�����I�j�̃^�r���V���G�e�B���i��O��`��܌܁Z�N�݈ʁj�A
�@�B�@�V���G�{�[�����i�\���`�\�㐢�I�j�̃A���E���p�����i�ꎵ�ܓ�`�ꎵ�Z�Z�N�݈ʁj�ł���B
�@�A�m�[���^�[���̓p�K�������̒����̑c�A�^�r���V���G�e�B���̓g���O�[�����̑n�ݎҁA�A���E���p�����̓V���G�{�[�����̑n�ݎ҂ŁA������������̕���ɏI�~����ł��A�r���}�ꂵ�����Ƃɂ���āu�̑�ȉ��v�Ƃ��ꂽ�B
�@�A�m�[���^�[���͉�������i�_��Ȃ̑�_�𒆐S�ɋN���������j�ɕ������A�^�r���V���G�e�B���̓}�j�v�[�����Ƃ��A�A���E���p�����̓}�j�v�[���ɐN�����Ď�s�C���p�[���ɓ����i�ꎵ�ܔ��`�ꎵ�܋�N�j�A����ɃA���E���p�����̎�����V���G�{�[�����͂����A�b�T���ɐN���A�A�b�T�����r���}�̊��S�x�z���ɓ��ꂽ�i�ꔪ�ꎵ�`�ꔪ���N�j�B
�@����A�^�r���V���G�e�B���̎���̃g���O�[�����̓}�j�v�[�������̍U�������i�ꎵ��l�`�ꎵ�l��N�j�łт��B
�@�g���O�[�����̖ŖS�ɂ̓A���^�������i�\�l�`�\�����I�j�Ƃ̒����킢�ɂ��敾�A�����R�i���̈�b�̌R���j�̐N���A�����A�����ȂǑ����̗v�������������A���̈�̓}�j�v�[�������R�̐N���ł������B
�@�r���}�̍��y�͉_����ʂɂ������Ă͔�r�I�悭�J���A�A�b�T�����ʂ͐[���W�����O���ƍ��s�ȎR�x���A�Ȃ��Ă������A���̊Ԃɓ��͒ʂ��A�×��A�k�r���}�͉_��A�A�b�T���ɒʂ����ʂ̗v�ՂƂ���Ă����B
�@�̑�ȉ��l�����͖L���Ȍo�ώs���J�����i�ߗ��j����ɓ���A�������̈АM���֎����悤�Ƃ��ĉ_��A�A�b�T���ɉ��������̂ł��낤���A�����Ƀr���}�̓���ƈ���ɂ̓A�b�T���A�_��Ƀr���}���̉e���������y�Ԃ��Ƃ��K�v�ƍl����ꂽ�̂ł��낤�B
�@�r���}�͂܂��^�C�Ƃ̍������ʂɎ����̈��S�ۏ�������A�^�C�̃A���^�������Ƃ̊Ԃɂ����Ό������U�h������肩�������B
�@�����ɂ����Ă��A����قǃr���}�̖h�q�͂ނ��������ƍl����ꂽ�̂ł��낤�B
�@�p���Ƃ̎O���ɂ킽��푈�i��ꎟ�͈ꔪ��l�`�ꔪ��Z�N�A��͈ꔪ�ܓ�N�A��O���͈ꔪ���ܔN�j�ł����ǁA���ʓI�Ȗh�q���͂��肦�Ȃ������B
�@�i�p�R���O���̐N���R�ł���Ȃ��珟���������߂��͈̂��|�I�ɋ���ȌR���͂̂��߂ł������j�B
�@�s���̖h�q��
�@�h�q���͏ɉ����ĕς����̂ł��낤���A�h�q�����ݒ肳��A�ύX����Ă䂭�ߒ�������ƁA�����ɂ킽��A�m�������s���̖h�q���Ƃ������͖̂{���A���肦�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@��������{�R�͌��Ƀr���}�̈���m�ۂ��������A�r���}�l�̃r���}��h�q����̂łȂ��A�r���}�ɂ�����{�R�̈��S�������l���Ă����B
�@�C���p�[����킪�s���悤�ƁA�s���Ȃ��낤�ƁA�r���}�ɂ�����{�R���r���}���瑁�Ӕr�����ꂽ�ł��낤���Ƃ͋^��������Ȃ��B
�@���łɃC���p�[����킪�J�n���ꂽ���_�ŁA�����m�푈�̔s�k�͂قڌ���I����������ł���B
�@�������C���p�[����킪�s���Ȃ������Ȃ�A��\�܌R�̓E�B���Q�[�g����̍U���ɑS�͂������A�����r�����ē��ʁA�k�r���}���m�ۂ��邱�Ƃ��ł����ł��낤���A���̌�ɗ\�z�����_��A�t�[�R���J�n�A�`���h�E�B���͕��ʁA�A�L���u���ʂ̘A���R�U���ɂ������Ă��A�ꎞ���A�����}���A�}������Ȃ��܂ł����R�Ɛ������ނ����邱�Ƃɂ���Ď��Ԃ��҂��A�������̑��Q���ŏ����ɗ}���邱�Ƃ��ł����ł��낤�B
�@�Ƃ������C���p�[�����ɂ�鑽��̋]�������͖h�������͂��ł���B
�@�R�q�}�̋u
�@�C���p�[����킪���p�̐킢�������Ƃ���A�����Ő킢�A�h�����Đ��҂��������̂�펀�ҁE�폝�a���҂̈⑰�ɁA���̂��Ƃ��ǂ�����������悢�̂��B
�@���߂ɒ����ɂ����������l�����́A�ǂ��l������悢�̂��B
�@���p�̐킢�ł���A�펀�͖��Ӗ����������ƂɂȂ�̂��B
�@�����̖₢�����ɓ����邱�Ƃ͂ނ��������B
�@���A�͂��߂ăC���p�[���A�R�q�}�A�E�N�����n���K�ꂽ������}����̒����u���J�̊�E�����̊�v���Ƃ����āA���̂��Ƃ��l���Ă݂����B
�@�������₽���J�̉����Ȃ��~��Â��R�q�}�̋u�ɗ����Ă݂�ƁA������������̏����̖S�삪���܂悢�łāA�킢�����Ĉ�Z�N�A�����̍�����͂��߂ĖK�ꂽ���E�Ɂu�߂�������v��b�������A�u�R�q�}�̎R�͂͜ԚL�i�ǂ������j�v���Ă���悤�������Ƃ����B
�@�����̐l�����͂�������
�@�u���{�R�̓r���}���瓞�������Ƃ��͖{���ɗ��h�ŗE���ł������A�A��Ƃ��͌��������ȏ�Ԃł����v
�@�u����ł����{�̕����́A���ɗE���ł����B�p��R�ɂ͗��h�ȕ��킪����܂����B
�@�����Ĕ�s�@���B���{�̕����͏e����ŗ��������Ă����܂����B���ʂ��Ƃ����������킪���Ă��Ȃ��悤�ł����B
�@����ɂƂĂ��R�������т��������v
�@�u���{�̕����͎������̕w���q�Ɍ����Ĉ������Ƃ����܂���ł����B
�@�H����D���Ƃ�ꂽ���Ƃ͂���܂������A�������ɕ�����̂́A����͎d�����Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�p��R�̂Ȃ��ɂ͎������̕w���q�ɂ����Ԃ�Ђǂ����Ƃ������̂���������܂���ł����B
�@�������́A�������Ƃ͂����A���{�R�̂��̗E�����ƌR���̂��т������A���ł����h���Ă��܂��v
�ƌ�����B
�@������Ē�������̓z�b�Ƃ����Ƃ����B
�@��������́A���̊�����
�@�u�i�R�q�}�̐l�����́j���{�R�ɓ��E�𑽂��E����Ȃ�����A�����݂������āA���Ȃ����̗E�������������Ă���B
�@���̎ƂȂ������̂��A�Ō�܂Ő킢�ʂ������{�̕����̗E�����̎����̂����������m��Ȃ��B
�@���͖��d�ȍ��Ɍ���������������Ȃ�����A���̒n�̐l�X�̋��[���ɓ��{�̏����̍Ŋ����P�����������Ă��邱�Ƃ�m��A�������ȈԂ߂����o�����悤�ȋC������̂������v
�Ǝ������Ă���B
�@��������ɂ��ƁA�R�q�}�̃C���p�[���X���ɖʂ����Ƃ���Ɍ��Ă�ꂽ�p�R�펀�҂̋L�O���ɂ�
�@�When you go home�C tell them we died for their tomorrow�v
�@�i���Ȃ����̍��ɋA�����Ȃ�A�������͌̍��̐l�X�̖����̂��߂ɐ���Ď��Ƃ������Ƃ�`���Ă��������j
�ƍ��܂�Ă������B
�@�l�Ԃ͐₦�������������A�����������ď��߂čĂь���Ƃ��܂��ƌ��ӂ���B
�@�C���p�[������킢�A����Ɏ��s���āA�悤�₭�푈�̌���g�������Ēm��A����̌��ӂ��s���̂��̂ƂȂ�B
�@���ꂪ�R�q�}�L�O���Ɏ����ꂽ�u�����̂��߂ɐ���āc�c�v�Ƃ������Ƃł��낤���B
�@���͂��̂悤�ɍl�����B
top
��������������������������������������������������������������������������������
|