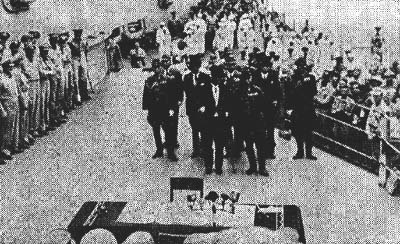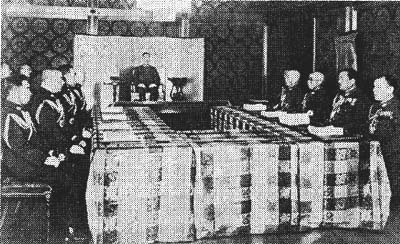|
****************************************
HOME
記者の見た昭和史 敗戦の歴史 記録写真 太平洋戦争講座
太平洋戦争講座――誰が悪かったのか
(『君は第二次大戦をしっているか』中野五郎著、第一部太平洋戦争講座、光人社1982年刊 遺稿
なお、第二部 第二次大戦50大事件、第三部 第二次大戦ミステリーは省略)
Ⅰ 太平洋戦争の評価と反省 top
1 国民は一体なにを学んだか
我々日本人同胞三百二十万人の尊い生命を奪い、さらに数千万の老若男女大衆に、耐えがたいような犠牲と、苦痛と破壊をあたえた太平洋戦争が終ってから、多くの歳月が流れた。
そして、敗戦のいまわしい洗礼をうけて、廃墟と混乱のドン底から、ようやく再生した民主日本と、危うくも生き残った国民大衆は、あらゆる困難と辛苦をたくましく突破して、めざましい復興と繁栄を取戻して、今日を迎えたのであった。
(注、この戦没者三百十万という数字は、昭和四十年八万十五日の終戦記念日の追悼式に政府が発表した数字であり、その内訳は昭和十二年七月七日の盧溝橋事件〈日中戦争〉から太平洋戦争の敗戦まで、八年余にわたる大戦災による戦死、戦病死した軍人、軍属、準軍属二百三十万人と、外地で死亡した民間人三十万人と、内地の戦災死亡者五十万人を合計したものである。
しかし、軍人、軍属の戦没者にたいして、恩給や叙勲の特典が復活実施されているのに反して、民間人の犠牲者と遺族が無視されている現状は、平和日本の建前から不合理ではないだろうか?)
これはまことに、現代総力戦時代の敗戦国としては、じつに、まれにみる幸運な国家再建であり、確かに欧米のマスコミが賞めてくれたように『奇蹟の復興』である。
そのかわり現在、我々一億の日本人の大半は、おそらく太平洋戦争の血みどろな悲痛も、おそろしい悪夢も、すでに忘れてしまって、ただ目前の商売繁盛と、身辺の幸福を願いもとめているだけではなかろうか?
とくに、戦後に生まれ育ったような若い世代の人々は、太平洋戦争の敗戦のおかげで、『進駐軍』という名の外国占領軍隊の下であたえられた『平和』と『自由』を、腹いっぱいにむさぼり食って、ぬくぬくと気楽に成長したので、まったく戦争の教訓も、敗戦の実感も学ばない、享楽的なレジャー族と化したのではなかろうか?
それはムリもない。
彼らは、日本国民の義務教育とされている小学校でも、中学校でも、けっして、太平洋戦争について、正確な知識も、公正な理解もあたえられていなかったからだ。
そして、今日でさえも、日本の大新聞は、文部省の反動的な教科書検定方針をめぐり、太平洋戦争の史実と認識についての激しい論争を報道しつづけているのである。
これは、奇怪千万なことではないか!
なるほど、我々日本人にとって太平洋戦争は、途方もない無謀な『負け戦さ』であり、それは国家としても、国民としても、また、天皇一家としても、けっして内外に向けて自慢になることではない。
しかし、絶対天皇制の下で軍国日本が、まるで『清水の舞台より飛び降りる』(東条大将の有名な言葉)ような大決断で、大戦争へ突入した事実は、すでに現代世界史上に、永久に刻みこまれているので、たとえ、戦後日本の文部省がいくら国家的体面上、体裁が悪いからといって、『真珠湾攻撃から東京湾頭の降伏調印まで』の、厳然たる三年八ヵ月間の史実を勝手に歪(ゆが)めたり、都合よくゴマ化したりすることは許されない。
太平洋戦争の真相を知らないのは日本人ばかりなり――ということであってはならないのだ。
なぜ、文部省は、いわゆる官製、検定の現在の小、中学校用歴史教科書に、太平洋戦争の開戦から敗戦までの、正しい史実と意義を、正々堂々と記述させて、戦争をまったく知らない若い世代に、この貴重な『民族の遺産』を、素直に理解させることをおそれたり、妨げたりしているのであろうか?
おそらく、これらの文部官僚と、一部の、いわゆる御用歴史学者の胆(はら)の中では、戦前、戦中と相通ずる、『絶対天皇制護持』の封建的な偏見と、独善的な超国家主義(ウルトラ・ナショナリズム)にもとづく『皇国史観』を、いまだ強く温存して、日教組を中心にした左翼的、革新的勢力に、あくまで対抗しようと努力しているのであろう。
私は、自由、公正な戦史家として、太平洋戦争を第二次世界大戦の視野から調査、研究しているが.このような文部官僚と日教組の対立、抗争のために、太平洋戦争の真実を、それぞれの政治的立場を守るために、勝手に歪曲したり、変造したりして、日本の次代をになうべき若い青少年大衆にたいし、誤った戦争認識をあたえたり、あるいは敗戦無視を教えたりすることには大いに反対する。
なぜなら、そのような姑息(こそく)な、近視眼的な太平洋戦争観こそ、かえってこの戦争の貴重な教訓を忘れて、平和な民主日本を、再びつぎの戦争へ、知らず知らずのうちに巻きこみ、引きずりこむ危険がきわめて大きいからである。
英国の世界的軍事評論家リデル・パートがつねに強調しているように、『平和を欲するならば、戦争を理解することである』という警句は、けっして欧米諸国にかぎらず、日本の場合にも、ピタリと当てはまるだろう。
すなわち、私たち日本人が、我々の子孫代々のために、あらゆる努力を惜しまず、平和を守りぬく覚悟であるならば、まず、なによりも、太平洋戦争の、もろもろの苦い教訓を正確に知り、戦争の起因と責任までも、厳正に理解することが必要である。
では一体、太平洋戦争の貴重な教訓とはなんであろうか?
それはまず第一に、太平洋戦争の起因を、正しく突きとめて反省することである。
もちろん、その起因は、直接の近因から間接の遠因まで、複雑な要因をふくんでいるのは、当然である。
しかも太平洋戦争のような、世界的規模の現代総力戦では、日本の立場が、敵国の米国、英国、オランダと真っ向から対立し、たがいに敵視し、憎悪しあったことは当然である。
だからといって、日本の開戦理由がすべて正当であるという独善的な考え方は、結果論として、戦勝国なる連合国側の『大義名分』が百パーセント正しかった、と現在もなお認めるのと同様に、反省不足であり、時代錯誤であろう。 |
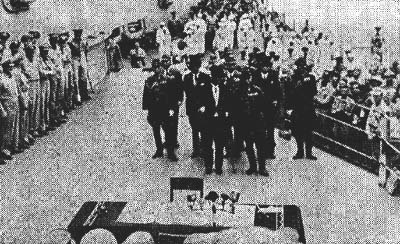
昭和16年12月8日、真珠湾攻撃によってはじまった
太平洋戦争は、昭和20年9月2日、東京湾頭、「ミズーリ」艦上の
降伏調印(写真)で幕をおろした。
|
すなわち、太平洋戦争は、軍国日本の超国家主義者一派が主張したような、神がかりの『八紘一宇のための聖戦』(皇道日本を全世界に宣布するための正義破邪の戦い)ではなかった代わりに、また米英側で声明したような『世界を征服しようと努めている、野蛮で野獣(やじゅう)的な軍隊に対する共同闘争』(一九四二年一月一日、連合国共同宣言)でもなかった。
これを言いかえると、古今東西を通じて、戦争は人間の狂気がもたらす、国家間の大量殺戮である点には変わりがないが、たがいに敵国の侵略性と残酷性を憎みながら、みずから『侵略』と『残酷』を犯して平然たるのが通例である。
もちろん、勝者は有利であり、敗者は不利ではあるが、後世の史家の判断は、正しく評価するものだ。
結局、公正に史実を検討して、太平洋戦争は、中国にたいしては、確かに『侵略戦争』であったが、いわゆる、米英蘭三国にたいしては、『自存自衛のための先制攻撃による予防戦争(大本営発表)』であったと、強調できないこともないだろう。
だが、いずれにせよ、日本は真珠湾奇襲による開戦の責任を負うことは明白である――というのが私の見解である。
戦争の起因、目的と、戦争の決断および遂行とを混同してはならない。
2 太平洋戦争への大きな疑問 top
戦後、わが国で発表、または刊行された太平洋戦争にかんする戦史、戦記、評論、読物類は、新聞、雑誌、単行本を通じて、じっに数万点以上にたっしていると思われるが、それを大別すると、つぎの三つにわけられる。
(一) 軍国日本の『侵略戦争』と、はっきり認めるもの。
(これは、米英ソ、中国はじめ連合国側の第二次大戦史観にもとづいたものであり、したがって、敗戦後の連合軍占頷下に、日本で発表された、太平洋戦争の記事、刊行物の主流をなすものである。 しかし、日本の独立後から今日まで、軍国日本の破滅と、絶対天皇制の終止を歓迎する革新的、民主主義的立場から、太平洋戦争の侵略性を認めて反省する向きが多い)
(二) 国際情勢の変転と日米関係の変化(軍事、政治、経済上の緊密な協力関係)によって、近年は太平洋戦争の解釈もおのずから一変し、戦前、戦中と同じような『皇国史観』を復活して、程度の差こそあれ、日本の正当性と戦没勇士の栄光化を認めるもの。
(これは、日米安保体制の維持、強化を熱望する日本の保守政治勢力と、米国政府筋の見えない圧力から、この数年来、とくに太平洋戦争の正邪を、真剣に論議することを避けて、たがいに、『日米双方の誤解にもとづく不幸な過去の出来ごとであった』というふうに軽く受けながし、公正な戦史の調査、究明を黙殺する傾向が目立つようだ)
(三) 戦争の起因、目的、責任などはすべて関知せず、ただ他人事(ひとごと)のように、太平洋戦争のすさまじい戦闘経過のみを、小説や、ニュース映画や劇映画、テレビドラマで面白く再現して、数千万の若い世代のために、いわゆる戦争物の通俗的な『スリル』と『ヒロイズム』を提供するもの。 |
このような、三者三様のカテゴリーのちがった日本人の戦争観の中に、いまや太平洋戦争の偉大な教訓はひそかに葬られ、忘れられようとしているのである。
これまで、わが国の旧軍人の手で、またジャーナリストの手で、あるいは大学の歴史学者の手で、太平洋戦争の開戦から敗戦までの戦闘経過と戦争指導については、十分に書きつくされてきた。
したがって、真珠湾奇襲も、シンガポール攻略、ミッドウェー海戦も、またガダルカナル島争奪戦も、アッツ島、タラワ島、サイパン島、硫黄島の死闘も、マリアナ沖とレイテ両大海戦も、最後の沖縄大決戦も、すべて、その流血と玉砕の詳細は広く知れわたっている。
かくて人類最初の米軍機による、原子爆弾の広島、長崎への投下と、ソ連軍の対日参戦、満州進撃によって、日本帝国は、あえなくも崩潰して、太平洋戦争は悲壮な敗戦の幕を下ろした。
太平洋戦争の作戦経過の史実は、戦前、戦中、戦後の三世代に、よく知れわたっているように思われるが、意外にも、長年にわたり故意に、あるいは軽率にも頬被(ほおかぶ)りして忘れかけていた、幾多の重大な事実が残っている。
しかもそれは、いずれも太平洋戦争史のいわば首尾一貫した背骨をなすものであり、米英流の表現を借りれば、日本の『世界的戦略』(グローバル・ストラテジー)の正体とゆくえである。
まず、米英の戦史家たちは、
『日本の軍部も政府も、ただ戦争を開始する準備、決断と、シンガポール、フィリピン、蘭印諸島(現在のインドネシア)の南方地域を攻略する作戦計画を立ててはいたが、それから以降は一体どうするのか、明確で合理的な、世界戦略方針を持ち合わせていなかった』
と、いかにも日本流の、大マカな腹芸的な考え方で、現代総力戦に挑んだ無謀な点を、痛烈に指摘している。
これに対して、旧日本陸、海軍の最高責任者たち(すでにその大半は亡くなってしまった)は、ほとんど良心的に反論したものはなく、また戦後の日本政府も国民大衆も、『太平洋戦争の真相調査』については、ほとんど無関心であったようだ。
すなわち、太平洋戦争の悪夢のような約四年間を通じて、最大の疑問の一つは、『はたして日本はいかなる勝算があって、開戦に踏み切ったのか?』という点であったが、これは当時の戦争指導者のだれからも、明確な回答を得ないままである。
そして、戦後の歴代の日本政府は、太平洋戦争をめぐるこれらの重要な根本問題を、いかにも厄介物あつかいにして、とくに天皇の道義的責任問題のむしかえしを恐れ、醜い古傷の跡を、強いてかくすように努めてきたように思われる。
それだから、憲法調査会には、多くの歳月と数億円の費用(これも、国民の負担した税金だ)を喜んで浪費しながら、官民協力の権威ある太平洋戦争調査会の方は、いくらたっても、けっして実現しないし、また、今後も日米協力、親善関係に悪い影響をあたえないようにという、よけいな政治的配慮から、到底実現しそうもない。
それは、日本国民へ戦争危機感を吹きこんで、日米軍事協力を強化するためには、太平洋戦争の冷静な研究調査は、かえって日本国民の反戦、平和感情を高めて、有害無益であるからだろう。
3 神がかり『皇国史観』の正体 top
さて本書では、これまでの戦史の形式をやぶり、まず、これらの重要問題――とくにいまだに解明されない、軍国日本の開戦当時の立場と、その戦争観=聖戦イデオロギーについて、分析、検討したい。
そして、日本軍部には、チャーチルやルーズベルト、スターリン、ドゴールが、つねに討議し、論争し、協調してきたような、米英流の合理的な『世界的戦略』というものは欠けていた代わりに。まったく対外的(ヒトラーにもムッソリーニにもわからぬ)にも、対内的(日本国民大衆に実際には全然、共鳴されず、理解もされず)にも、けっして通用しないような独善的な『皇国的戦争観』によって、いわゆる、大東亜戦争政策なる大綱をつくり上げて、『皇道日本』による、八紘一宇(はちこういちう)的な世界制覇を夢想していたわけを知りたいのである。
では、いったい、軍国日本の『大戦略』(グランド・ストラテジー)であった『皇国的戦争観』とは、どんなものであろうか?
それは皮肉にも、文部省の歴史教科書検定問題で、非難のマトになっている、戦前、戦中の反動的な御用学者による、『皇国史観』から生まれた聖戦イデオロギーなのだ。
したがって、この神がかりの、『皇国史観』の正体を知れば、それにもとづく軍国日本の狂信的な戦争理念の根源と影響力も明らかにされるわけだ。
この軍国日本の神がかりの理想像(ビジョン)であった、『皇国史観』について、自由民主化の、今日の若い世代の人々に説明、納得させることは、きわめてむずかしい。
それは太平洋戦争敗戦前まで、天皇が『現御神』(あきつみかみ=この世に姿を現わしている神の意味)と呼ばれて、いわゆる紫雲につつまれて神格化され、我々国民大衆は、天皇のいる宮城前を通るたびに、電車の中でさえ、脱帽、敬礼を要求された、狂信的時代の日本史観であるからだ。
戦時中、文部省は軍部と呼応して日本国民に対し、この極端に超国家的な皇国精神を鼓吹(こすい)するために、いわゆる国民教育の根本指針として、天皇のために徹底的な『滅私奉公』と『七生報国』を強要した『国史概説』(菊判、上下二巻、各四百八十頁、昭和十八年八月、内閣印刷局発行)という大冊の本を数十万部も編集、刊行して、全国の小、中学校、高校、大学教育者へ広く配布した。 |

昭和20年8月15日、「現御神(あきつみかみ)」と呼ばれて
神格化されていた天皇の終戦を告げる“玉音放送”に耳を傾ける人々。
翌年には「人間宣言」が行なわれた。
|
これがいわゆる『皇国史観』の決定版であり、軍国精神総動員の教典であったと同時に、また、学徒総動員や、神風特攻隊のための推進力となったものである。
つぎに掲げるのは、『国史概説』(結論――わが国体)の内容である。(以下、原文のまま)
『大日本帝国は万世一系の天皇が皇祖天照大神の神勅のまにまに、永遠にこれを統治あらせられる。
これ我が万古不易の国体である。
しかしてこの大義に基づき、一大家族国家として億兆一心、聖旨を奉体して、克く忠孝の美徳を発揮する。
これすなわち我が国体の精華である。
国史は各時代に於いて、常に推移変遷の諸相を呈するにも拘らず、それらを一貫して肇国の精神を顕現している。
国史の神髄はこの精神によって貫ぬかれたる大なる生命であり、国史の成跡は、国体を核心とする国家発展の姿である。
かくの如くして、宏遠なる太古に肇まり、不易の国体を中心として、撓(たわ)むことなき生命を創造発展せしめつつある国家は、世界広しと雖(いえど)も独り我が国あるのみである。
他の国にあっては、建国の精神は必しも明確ならず、しかもそれは革命や衰亡によってしばしば中断消滅し、国家の生命は終焉して新たに異なる歴史が発生する。
したがって建国の精神が、古今を通じて不変に継続するが如きことはない。
すなわち、外国は個人の集団を以て国を形成し、君主は智・徳・武等を標準として、それらの力の優れたるものが位につき、これを失へば位を追われることがあり、或は民衆が主権者となり、多数の力によって政治が行われる。(中略)
我が国家はこれと異なる。天皇は皇祖皇宗を祭らせられ、これと御一体にあらせられて神ながらに御代治しめし、宏大無辺なる聖徳を具へさせられ、国土国民の生成発展の本源にまします。
国民は天皇の聖徳を仰ぎ、淳美なる良俗に啓培せられ、神皇一体、君民一致の国家を形成している。
不動の国体を基幹として日に新たなる創造が展開されるのであって革命はあり得ない。国家の進展が特に顕著なるときには、いわゆる維新の鴻業が行はれるが、それは同時に復古であり、したがって復古的維新ともいうべきものであって、国体を特に著しく発揚せしめる政治改革である』 |
そのつぎに『国民性』と題して、生きた神である天皇の命令}下、日本国民が生命をいさぎよく捧げて、戦場へ赴くことを大いに称揚している。
『すでに述べた如く、天皇は御親ら皇祖皇宗の神霊及び諸神を祭らせられ、神を祭り給う大御心を以て民を治しめし、国民もまた神々を崇め祭り皇室を宗家と仰ぎ、祖孫一体となって、現御神にまします天皇に帰一し奉る。
これすなわち古今を通じてかわらざる我が国家生活であると共に、更に郷土の生活には必ず氏神があって国民は聚落の融合一体を実現する。
これらに見られる国民の敬神の念は、実に国民性の基礎をなすものである。
かかる敬神の念は、我が国にあっては特に報本反始の誠を致す国民精神として顕現する。
この精神がすなわち忠孝の徳の根源となり、また天地万物に対する敬虔感謝や愛護の心ともなるのである。
神に仕へる心は、また身心一切の穢(けがれ)を去り、純一無雑の心意に帰する清明心であって、これは古来まことの精神として特に尚(とうと)ばれている』 |
それは今日の時点より考えると、まことに難解、複雑な、神がかりの独善、尊大な、『万邦に冠たる天孫民族の国民思想』とみなすほかはないが、しかし、このような文部省制定の『皇国史観』から、いわゆる『神兵の聖戦』というような『皇国的戦争観』が生まれたのは当然であった。
それは、ヒトラーの狂信したナチズムを光栄化した哲学者のアレフレッド・ローゼンバーグ(悪名乱い『二十世紀の神話』の著者、戦後の一九四六年十月、ニュールンベルクの戦犯裁判で絞首刑を宣告、執行された)の場合とはちがうが、しかし、『支那事変』以来の日本の侵略戦争を正当化し、さらに光栄化するために、この『皇国的戦争観』が、いかに忠勇な日本軍将兵を激励し、奮起させるのに役立つたか、はかり知れないであろう。
私は日本の戦史家として、太平洋戦争中の決戦下で、このような日本独特の天皇制国家における、忠君愛国の国民精神と、一死報国の軍隊精神の長所、美点をよく理解するものである。
が、しかし、その短所と欠点も明らかに認めざるを得ない。
それについては、太平洋戦争の各作戦段階にしたがって、十分に究明するつもりでいるが、ただ一つここにはっきりと指摘しておきたいことは、天皇自身が終戦直後に、みずから建国以来、二千六百年にわたる神秘的な神格を公然と否定して、いわゆる『人間宣言』をした事実である。
したがって、戦後だいぶたった今日、文部省の一部に、もし、まだ独善的な、非民主的な『皇国史観』を、ひそかに信奉する絶対天皇主義者がいて、小、中学校用歴史教科書の中の、太平洋戦争の記述について、公正な史実をことさらに歪め、開戦の原因や敗戦の理由をゴマ化すような干渉、検定をこころみるようなことがあったら、かえって彼らの口ぐせにする『承詔必謹』の鉄則に反して、それこそ天皇の大御心に背く、不忠の臣となるわけだ。
この天皇の『人間宣言』は、いわば『平和憲法』と抱き合わせの形で、戦後の民主日本の再建に、二大支柱とされたものであるが、近年どういうわけか、一般の戦争記録書などにもまったく再録されず、意外なくらい、その原文に接したものが少ないようである。
とくに、読者諸君の中でも若い世代は、それを知らないのではなかろうかと思って、つぎに、その勅語(ちょくご=天皇のお言葉)の一節(昭和二十一年一月一日の勅語)を紹介しておく。
『――惟(おも)フニ、長キニ亘レル戦争ノ敗北ニ終リタル結果、我国民ハ動(やや)モスレバ焦燥ニ流レ、失意ノ渕ニ沈淪(ちんろん)セントスルノ傾キアリ。詭激ノ風激ク長ジテ道義ノ念頗(すこぶ)ル衰へ、為ニ思想混乱ノ兆アルハ洵(まこと)ニ深憂ニ堪ヘズ。
然レドモ朕(ちん)ハ爾等(なんじ)国民卜共ニ在リ。
常ニ利害ヲ同ジウシ休戚ヲ分タント欲ス。
朕卜爾等国民トノ間ノ紐帯(じゅうたい)ハ、終始相互ノ信頼卜敬愛ニ依リテ結バレ、単ナル神話卜伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。
天皇ヲ以テ現御神トシ、且ツ日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基(もとず)クモノニ非ズ』 (以下略) |
Ⅱ 太平洋戦争の神話と迷信 top
1 公正な評価と責任のゆくえ
『歴史は自分の国においてのみ、立派に書くができる』
とは、十八世紀のフランスの大思想家ボルテールの言葉である。
確かに古今東西を通じて、『言論と思想の自由』がみとめられていない国では、真実の歴史を書くことは許されなかった。
したがって、国王または皇帝のような、絶対権力者に対する民衆の反抗や、闘争の歴史が、当時、つねに抹殺されたり、歪曲されたりして、正しく伝えられないのは当然であった。
それはなにも、中世の欧州の絶対君主国家だけにかぎらず現代でも、ヒトラー、ムッソリーニ、スターリンたちの全体主義独裁国における、いわゆる『一党専制政治』と『言論抑圧』と『思想統制』の、暗い思い出がまだ生なましい。
わが軍国日本でも、満州事変――日中戦争(支那事変)――太平洋戦争の暗雲の十五年間に、歴史の真相がいかに国民大衆の眼から掩い隠され、真実がつつまれていたかは(早耳の新聞記者たちにたいしても)、――敗戦後はじめて『言論と思想の自由』を獲得(じつは戦勝の連合軍からあたえられ、助長されたのだ!)した我々日本人の、身にしみて痛感したところである。
戦争の歴史もまた同様である。とくに独裁、専制国では、戦争中、国家の緊急非常時という美名のもとに、国民の戦意昂揚と、決戦体制を最大限に強化するため、『言論』も『思想』も、すべて国家へ奉仕して戦力化されるもの以外は、すべて弾圧され抹殺された。
我々日本人もまた戦時中は、いわゆる『依(よ)らしむべし、知らしむべからず』の政府、軍部の強硬方針の下に、『言論の自由』どころか、国民大衆の心の糧ともいうべき『報道の自由』まで抑圧されたまま、ついに痛ましい敗戦の日を迎えたのである。
たとえば、太平洋戦争の開戦後わずか六ヵ月で日本軍が主導権をうしない、敗勢の重大転機をむかえた昭和十七年六月五日と六日の、ミッドウェー決戦の致命的な大敗北についても、大本営は、日本艦隊の大勝利と発表、報道して、国民大衆をだまし、大いに喜ばせたものである。それは、ただ軍部の威信を保つために。
なるほど、軍国日本は、開戦前から独、伊の枢軸国と盟邦関係を結んではいたが、その国柄と独裁政権の成り立ちもちがうので、ヒトラー独裁のナチス・ドイツや、ムッソリーニ独裁のファシスト・イタリアと、軍国日本を、同列に論ずることは日本人の立場から、不穏当でムリな点がある。
ここに、満州事変――日中戦争――太平洋戦争という十五年間の、いわゆる『昭和戦乱』の責任問題をめぐり、天皇、政府、軍部の三者三様のデリケートな論争点があるが、公正に、かつ良心的に触れてゆくつもりである。
たとえば、第二次大戦の起因について、米、英、仏、ソ各国の戦史では、ヒトラーとムッソリーニという、野蛮な独裁者兄弟こそ、『最大、最悪の戦争犯罪者』と断定している。 |

東京裁判でキーナン検事(右手前)の訊問、追求に抗弁する
“太平洋戦争の憎むべき張本人”とされた
開戦時の首相・東條英機(左)は戦犯一号となった。
|
また、敗戦国側でも、戦後にドイツ共和国(東西両ドイツとともに)とイタリア共和国では、
『戦争は狂信的な独裁者が善良な国民大衆をだましたり、暴力でおどかしたりして、計画し放火したものである』
と、すべての戦争責任(開戦責任も敗戦責任も)を、ヒトラーとムッソリーニ両人に、それぞれ押しつけることによって、きわめて明確に割り切っていた。
要するに、戦後の独、伊の国民大衆は、ただ、ヒトラーと彼のナチ党を、またムッソリーニと彼のファシスト党を、それぞれ極悪非道の悪玉あつかいにして、あらゆる怒りと憎悪を、この独裁者の上に吐きかけることによって、万事、重苦しい胸のなかを晴らしたものだ。
したがって、戦後に、独、伊両国では、その建国の歴史を別に書き変える必要などは毛頭なく、ただ現代史のごく一部分、すなわちヒトラー独裁政権時代の、わずかに歪められた史実を訂正して、その誤った解釈を変更するだけで、すべてこと足りたわけだ。
ところが幸か不幸か、敗戦の結果、軍国日本の場合には、そう簡単に都合よく、昭和史の一部だけを是正して、日本とつなぎ合わせることはできなかった。
すなわち、軍国日本の精神的中核をなした、ふるめかしい『絶対天皇制』や、厳(いか)めしい神がかりの『皇国史観』を、ただ敗戦の結果によって、また、戦後の米英流の民主日本に、うまく適合するように、自由自在に改廃するわけにはゆかなかった。
すなわち、危険な日本の神国思想を打破し、日本の歴史を根本的に書きなおすような、空前の民主化作業を必要としたのだ。
だから、ヒトラーやムッソリーニのような野心的独裁者を排除するように、軍国日本の戦争責任者としての、東条首相(陸軍大将)以下、いわゆるA級戦犯の政府、軍部の要人だけを、いくら悪者あつかいにして憎み、恨んでも、太平洋戦争の起因はけっして究明されず、また公正に評価されないのは当然である。
そこに太平洋戦争の特異な本質と、評価のむずかしさがあるのだ。
独、伊両国の場合は、いったい、だれが悪かったのか、その解答も解釈も、すこぶる簡単明瞭である。
しかし、軍国日本の場合には、いったい、だれが悪かったのか?
その真相は、きわめて複雑怪奇であり、またその実情は、アイマイにはぐらかされて、今日、かえって、ますます黒い霧におおわれたまま、現在の教科書論争の深刻な原因をつくったのである。
2 東条首相は“大悪人”か! top
確かに、敗戦直後の日本では`東条英機大将が最大の悪者あつかいにされた。
しかし、彼が、東京裁判でA級戦犯第一号として絞首刑を宣告、執行された後味は、我々日本人にとって晴れぱれとした、さわやかなものではなかったようだ。
なぜなら、『東条は、六百万のユダヤ人を虐殺したヒトラーほど、悪いやつではなかった』と、一般に思われたからだ。
また、ナチス・ドイツでは、だれでも、『ハイル・ヒトラー!』(ヒトラー万歳)という挨拶が強制されて、戦場でも銃後でも、厳重に励行されたが、軍国日本では、だれひとり、『東条大将万歳!』と叫んで、死んだ兵士はいなかったからだ。
軍国日本では、日本国民は、すべて天皇の命令で戦場へ駆り立てられて、『天皇陛下万歳!』と叫んで玉砕していった、冷厳な事実を忘れてはならぬ。
とくに、『勝者の裁判』とよばれた東京裁判の市ヶ谷法廷で、見るからにやつれ果てて、みすぼらしい東条被告(当時六十四歳)が、直立不動の姿勢で、米国の検事のするどい訊問、追及にたいして、
『私の経験した間には、天皇は、御前会議でも、ほとんどご発言なさったことはありません。
日本国民として、私は陛下が裁判にかけられるのを見るにしのびません。
一九四一年十二月の開戦と、真珠湾攻撃に関して、私が起訴され、裁判にかけられる責任を持つものである点は妥当なことです。
しかし、私は、陛下が裁判されるということは、考えるにしのびません。
私自身ばかりでなく、日本国民すべて、天皇陛下が裁判にかけられるとしたら悲しむでしょう。
私は主として、国務大臣の観点から責任を負うべきものであります。
――統帥の観点からなら、参謀総長および軍令部総長に責任があります。
他の閣僚も責任がありますが、私よりも責任の程度は少ないと思います。(中略)
戦争の避けられなかった原因は、統帥権の独立、その他いろいろありますが、いま自分が弁明しようとすることは、臣下として、自分と陸、海軍統帥部長が、陛下に対する輔弼(ほひつ)の責任を果たさなかったという点であります。
天皇陛下には、絶対に責任がありません』 |
と、大ミエを切ったとき、彼の失墜した人気は、右翼、保守主義者たちの間でにわかに盛りかえした。
確かに、太平洋戦争の憎むべき張本人と、米英ではみなされた東条大将も、私が戦時中に交換船で帰国後、朝日新聞記者(前ニューヨーク特派員)として、再三、親しく面接したが、けっして狂気の大悪人というような印象を受けなかったくらいである。
太平洋戦争では、軍国日本にはヒトラーもムッソリーニもいなかった、という平凡な結論に達する。
『あの顔の青白い神経質な、軍人としては、むしろ小心な律義者のようにみえた人物が、なぜ軍国日本の興亡と、一億玉砕の暴挙を賭した大戦争にあたり、平和念願の天皇の切々たる「大御心」(神格化された天皇の心境)に添わない、無謀な開戦の決断に踏み切ったのであろうか?
しかも彼は、戦後の東京裁判法廷で、「独裁者東条大将」として被告席にならんで、旧敵国の代表と、日本国民大衆の面前で生き恥をさらしながら、その内心では、東条は国民にたいしては、逆賊といわれるかも知れないが、陛下をお守りすることだけは、命がけでやり通す覚悟である。
自分が自殺し損ねてこうして生きているのも、ただ一点そのことのためだ』
(東条被告弁護人、元逓信院総裁塩原時三郎氏の手記による) |
と、ひそかに誓っていた。
こうなると、軍国日本の戦犯追及問題はきわめて困難で、いわゆる戦争責任が行方不明になりやすい。
戦後の東西ドイツでは、いずれも連合国の手による、ニュールンベルク裁判とはまったく別個に、両ドイツ政府が、戦時中のナチス犯罪に対する厳正な摘発、裁判を、長年にわたり根気よく続行し、さすがは権利と責任と法律観念の強い、ドイツの国民性の合理主義を発揮したものだと、私は戦史家として大いに感嘆させられたものだ。
これにたいして戦後の民主日本では、めざましい経済的復興と物質的繁栄のかげに、太平洋戦争の起因究明も、責任追及もすでに忘れられてしまって、むしろ戦争の過去の古傷や悪夢を、戦後派の有力な政治家や財界人までもが最近、ウヤムヤに葬り去ろうとする傾向が目立ってきた。
また、日本人の国民性の一つといわれる健忘症のせいか、戦犯として刑死した東条大将の、戦争内閣の有力メンバーだった、岸信介(当時、商工大臣=現安倍首相の祖父)と賀屋興宣(かやおきのり=当時、大蔵大臣)両氏が、戦後もわが政界で依然として健在で、保守勢力(自民党中心)の長老として、権勢をふるっていたのは、まことに戦後の独、伊両国には見られない現象である。
それを、別に怪しまない日本人独特の政治的センスは、けっして健忘症のせいばかりではあるまい。
私のように、太平洋戦争をあくまで第二次世界大戦の一部であるとみなして、ヒトラーとムッソリーニ両独裁政権下の独、伊両国が戦った、欧州戦争と同時に並行、関連させて、パノラマ的に総合、比較、検討する立場からみると、たとえてみれば、ヒトラー内閣の商工相や、ムッソリーニ内閣の蔵相が、戦後まで元気よく生き残って、しかも、新しい民主政権の首相や閣僚に返り咲いたり、再び時めくようなことは、到底信じられないことである。
ここにも太平洋戦争を、欧州戦争と同一の普遍的な戦史的レベルから、公正に評価することの特殊な障害と困難があると思う。
もっとも、日本人の淡白な国民性から、日本人同士が戦後に、たがいに戦争責任をなすりつけ合ったり、あばき立てて争うことは、あまり好ましくないようであった。
しかも太平洋戦争には、いかに軍部独裁とはいえ、ヒトラーのような狂信的な残虐行為――たとえば六百万のユダヤ人大虐殺や、占領地域における敵性市民男女にたいする、大規模な集団的テロ行為などは、さすがに日本軍の性質には合わなかったとみえて、幸いにも模倣されなかった。
それだけに、我々日本人は一般に、識者も、大衆も、戦争にたいする罪悪感が少なく、したがって、連合軍総司令部(GHQ)から、とくに命令されたり、要求されないかぎりは、戦後の国民的反省も、自己批判もたりないで終ってしまったのではなかろうか?
たとえば、終戦直後から東京裁判の判決(昭和二十三年十一月)の下るまでの約三年間、天皇の戦争責任問題は、当時の幣原(しではら)内閣にとっては、国民大衆の食糧不足や、戦災復興の緊急問題よりも重大視され、天皇制の廃止はないとしても、天皇の退位は、相当にその可能性があるものとして心配された。
しかし、その当時でさえ、いわゆる民主化されたはずの戦後の日本の各新聞は、やはり天皇制を論評することを、戦前同様に『畏(おそ)れ多い』ものとして極力、これを敬遠したため、かえってGHQから、
『天皇制についてもっと自由に論議、報道して世論を起こすべし』と、新しい戦後の『主権在民』のあり方について、指示と指導を受けたものであった。
このような点にも、太平洋戦争の公正な責任論争が、早くから日本では不評判に終わり、時の流れによって、いつのまにか、戦争責任が行方不明になっても、国民大衆がほとんど怪しまない理由があるのではなかろうか?
しかし、私がかっての日、歴史的な日米開戦を新聞特派員として、敵国(当時)の首都ワシントンで迎えてから戦後の今日まで、じつに長い間、太平洋戦争をふくむ第二次大戦の真相と経過と結末を、日本の自由、公正な戦史家として丹念に調査、検討してきた結論は、まさにつぎの通りである。 |

戦火の爪跡が残るがれきの間から見る国会議事堂。
終戦後の幣原(しではら)内閣の緊急問題は、
天皇の戦争責任問題であった。
|
『軍国日本は、武力戦で敗れて無条件降伏をした。のみならず、思想戦でも徹底的に敗れ去った。
したがって、軍国主義を打破された日本は、戦後に急速に政治、経済制度の民主化には成功した。
だが、いわゆる「国体の精華」である、八紘一宇の皇国史観と、皇尊絶対の民族精神をひとたび粉砕されたら、その思想的空白状態を、新しい民主主義の精神でみたすには、数十年の長い歳月と、忍耐づよい国民的努力を要するであろう。
なぜなら、制度の改革はやさしいが、国民精神の改変はきわめてむずかしいからである。
しかも、軍国日本の象徴であった天皇が敗戦の結果、みずから民主日本の象徴(シンボル)に変身したことを認めて、これまでの神話と、伝説にもとづいたところの神格を否定し、「人間宣言」の歴史的な詔勅を発した(昭和二十一年一月一日)からには、天皇はもはや、再び、もとの神性にもどることはできない。
――これは将来の天室制のあり方について、大きな希望と深い矛盾をもたらすであろう』 |
3 開戦の決断をめぐる天皇の立場
top
むかしから戦争の勝敗は、いわば『時の運』であるから、軍国日本が、たとえ米英相手の大戦争で武運つたなく敗北したとて、けっして卑下したり、卑屈になるにはおよばない。
ドイツ民族は、二十世紀の前半に、二回も世界大戦をみずから起こして、無残にも敗北しながら、またもや戦前にまさるすばらしい復興ぶりをみせて、そのたくましい民族的エネルギーを発揮しているではないか。
日本も太平洋戦争で敗れたりとはいえ、米、英、蘭、中国、(終戦直前にソ連)を相手に、三年半以上もよくぞ堂々と戦い抜いたではないか。
しかも、インド、ビルマ、マレー、インドネシアなど東亜の白人植民地は、すべて日本軍の手で解放し、独立させたではないか――と、太平洋戦争を日本に有利に過大評価する旧軍人も少なくない。
確かに、このような戦争観にも一理はあり、とくに東京裁判で、
『満州事変以来、過去十五年にわたる日本の行動は侵略戦争なり』
と、日本が一方的に烙印(らくいん)をおされたことには強い不満と異議をとなえる人々も多いであろう。
しかし、このような戦争観の致命的な欠点は、太平洋戦争をただ武力戦として解釈して、その戦争の結果である勝敗だけにこだわっていることである。なぜなら、現代総力戦の究極的な目的は、けっして単なる武力的勝利ではなくて、じつは百七十年前に、プロシアの偉大な戦争哲学者カール・フォン・クラウゼビッツ将軍が、
『戦争は他の手段による政治の延長である』
と、いみじくも喝破(かっぱ)したように、政治的目的を達成することであるからだ。
だから軍国日本は、たとえ武力戦では不運にも敗れても、もし、思想戦にはあくまで屈服せずに、その政治的主体性を確保していたならば、我々日本人は、いわば『負けるが勝ち』と称しても、かならずしも単なる負け惜しみではなかったであろう。
その代わり、敗戦後、日本はけっして戦勝国たる米国の安易な援助、救済を受けず、天皇以下、政府も全国民もすべて『臥薪嘗胆(がしんしょうたん)』の苦労を重ねて、戦後の祖国復興はもっとおくれたであろうが、かえって、物心両面のバランスのとれた堅実な再建が実現したことであろう。
そして、今日のような、日本のはなばなしい経済復興のカゲに、日本人の精神的空白と思想的迷いが生ずるような、国民的不幸をもたらすことはけっしてなかったであろう。
私は日本人である以上は、長い長い民族の歴史が生みはぐくんできた、いわゆる神話と伝説にもとづいた『皇国史観』を、けっして、バカらしいものだとは思わない。
しかし、戦前、戦中の軍国時代を通じてあまりに誇張され、あまりに独善的に国民大衆に押しつけられた、行きすぎた思想統制が、皮肉にも、かえって敗戦後の日本人の思想的混乱と、国民精神の喪失をまねいた重大な原因になったと信ずる。
それはまさしく、『過ぎたるは及ばざるにしかず』という感がふかい。
たとえば、米英的民主主義(デモクラシー)を全面的に否定した文部省制定の『皇国史観』を、敗戦後、日本政府みずから、たちまちホゴ紙のごとく放棄して、占領軍の命令のままに、国民教育制度を根本的に改変し、さらに民主主義を鼓吹、普及するために、日本の歴史の書き変え作業まで、意のままに追従してきた文部省官僚が、いまや、再び保守反動の逆コースにのり、歴史教科書の検定騒動を起こしつつあることは、なんとしても醜悪な不手ぎわではないか?
くどいようであるが、私は戦史家として、太平洋戦争における軍国日本の敗北、降伏は、その武力戦の敗北による物的損失よりも、その思想戦の敗北による精神的損失の方がはるかに重大であり、しかも現在から遠い将来にわたり、我々の子孫代々にまで深甚な影響をおよぼすであろう、と心配している。
なぜなら、国家の物的損害は、早急に経済力によって回復されるが、国民のうしなわれた民族精神は、けっして容易に取りもどすことができないからだ。
我々日本人は、一般に、つごうの悪いことは忘れやすく、また、にがい教訓を学び、きびしい忠言に耳をかすことを好まないようだ。
しかし、太平洋戦争の開戦から敗戦までの暗い真相を、できるだけ率直に、なるべく相異する見解も公正に取り上げて、国民教育のため、歴史教科書に収載することは民主主義の教育上、もっとも望ましいことである。
たとえば、昭和四十一年度用の中学、高校歴史教科書にたいする文部省検定では、満州事変――日中戦争(支那事変)――太平洋戦争の記述、説明について、つぎのような逆コース的方針が、明白に実施されたと新聞報道されて反響をよんだことがある。
(一)『皇国史観』(絶対天皇制と一君万民を国体の精華とみなす)の復活と、十五年戦争の正当化と光栄化。
(二)太平洋戦争の肯定と米、英、蘭、中国(ABCD)の、対日包囲陣の日本圧迫を戦争原因とみなす。
(三)天皇神話の重視。
(四)戦後の新憲法の平和尊重と戦争放棄の精神、規定に対する逆行。
(五)戦争観の国家統制の危険。
(六)日本人の立場で愛国的に書くことの強調。
(七)検定から検閲へ。 |
この新検定歴史教科書の実例をみると、『戦争の暗い面を強調しすぎるからいもっと明るい面を出すように』とにいう文部省側の指示によって、これまで、長らく使用された広島の原爆キノコ雲の歴史的写真や、広島のいたましい廃墟の実況写真が、多くの教科書から自発的(?)に削除され、その代わりに、『遺児をはげます東条首相』の写真が新しく登場した。
また、旧版で使われた『勤労動員の女学生の群れ』とか、『配給を受けるモンペ姿の家庭の主婦たち』とか、『強制疎開で、家財を運び出す住民たち』といったような、決戦下の国民生活の光景写真まで、遠慮して、いっせいに姿を消したといわれる。
これでは、いわゆる反戦的な左翼学者たらずとも、中正穏健な歴史学者たちが、みんな怒るのもムリはないだろう。
なぜなら、戦争というものは、古今東西を通じて、つねに残酷であり、きわめて非人道的な暗いものであるからだ。
とくに世界史上、人類最初の原爆被災国民として、日本人の平和護持の悲願を、次代の国民へ強くアピールするために、各教科書は、太平洋戦争をもっと大きく真剣に取り上げて、戦争の暗い場面と、残酷な正体を十分に知らせ、しかも平易に説明、反省すべきであると思う。
そして、軍国日本が敗戦によってはじめて巨大な軍備を放棄して丸腰になり、これまで『菊のカーテン』の奥にかくれて、『現御神』とおがみ奉られていた天皇か、みずからその非近代的な神格を否定して『人間宣言』を行ない、主権者たる国民大衆のまえに、おごそかに、日本の民主化と、平和保持の決意を誓ったことも、ぜひ教科書にのせて、後世のために明記せねばならない、と私は信ずる。
またもう一つ重大な点は、戦後はじめて東京裁判、その他で公表された、極秘の記録や貴重な手記(元内大臣木戸幸一供述書および『木戸日記』、元首相近衛文麿著『平和への努力』、元侍従武官長本庄繁陸軍大将の覚書、元国務相、情報局総裁下村海南博士著『終戦秘史』その他)によって、開戦前に天皇は平和を求めて大いに気をもんでいたが、その大元帥たる統帥大権を発動して、断固として太平洋戦争を押しとどめることができなかった真相を、はっきりと教科書に記入すべきである。
それは軍国日本にとって、けっして都合の悪いことではなくて、むしろ天皇自身にとって、名誉ある平和への切望と、戦争回避の努力を、日本の現代史上に永く銘記するものだ、と私は思う。
太平洋戦争の開戦決断をめぐり、天皇の立場はきわめて微妙であり、またその責任は重大であった。
前記の信頼すべき記録・資料によると、天皇は二・二六事件と支那事変以来、これまで、言行不一致とウソの多い軍部(陸軍をさす)にも統帥部にも、再三、不信の念を表明し、いつも戦争反対と、対米英協調と、平和愛好の態度をとってはいたが、ただひとり、皇居の奥深く苦慮するばかりで、はなはだ遠慮がちであったようだ。
結局、神格化された絶対天皇の大権はかえって形式化し制約されて、消極的なものになり、国家百年の大計のために、戦争を主張する強大な軍部と右翼、国家主義勢力の前には、天皇個人は意外にもきわめて孤独で微力な、気の毒なロボット的存在になっていた――というのが、内外の歴史家の定説である。
せめて天皇が開戦直前、昭和十六年九月六日の御前会議の席上で、戦争決意の重大決定が行なわれたとき、列席した政府、統帥部の最高責任者たちのまえで、
『四方(よも)の海みな同胞(はらから)と思う世に、などあだ波の立ちさわぐらん』
という明治天皇の御製を朗読して、平和愛好の意思表示をしたのが、悲しい最後の抵抗であった――ともいわれている。
要するに、天皇自身の善意と、性格の弱さ(東京裁判のキーナン首席検事の言葉)と、軍部と側近が手をむすんだ主戦論の重圧が、ついに、孤独な天皇の、平和への悲願を裏切って、はじめから勝算のすくない戦争へ、軍国日本の突入を勅許したというわけである。
それにつけても、太平洋戦争の実体を正しく直視するために、すでに我々日本国民が、忘れかけようとしている、『悪夢のような古証文』のごとき宣戦の詔書(Ⅵ-5)を、あらためて読みなおしてみよう。
それは前述の『皇国史観』の、神がかりの発想と、むずかしい美辞麗句の羅列で、今日の若い世代には到底理解できそうもないが、軍国日本の対米英蘭開戦の理由と、目的とを明らかにしている点では、やはり太平洋戦争にかんする日本側の、もっとも重要な歴史的ドキュメントの一つである。
4 勝算なき戦いへの契機 top
今日の時点から太平洋戦争の起因、経過、敗因をきびしく検討することは、当時の政府・軍部の主要な戦争指導者にたいして、彼らの人知れぬ心痛を無視した、いわゆる、「後(あと)ヂエ」の結果論議におちいり、日本人として不公平である、という意見を旧軍人から聞くが、私は一日本の戦史家として、けっしてこのような意見を無視するものではない。
開戦直前の和戦の決定する御前会議にせよ、政府と軍内部の深刻なジレンマについては、戦後はじめて発表された、大本営と陸軍統帥部の極秘記録によって、いまでは日本人の間に、よく理解されており、私もその運命的な開戦の決断が、決してなまやさしいものではなかったと認識している。
だが、いかに祖国日本のためによかれかし、と確信して、太平洋戦争の重大決断と戦争準備に精根をつくしたにせよ、敗戦の結果がもたらした、果てしなき犠牲と、物心両面の重大な損失については、責任を負わねばならぬと思う。
戦時中に、その要職にあった旧軍人たちは、天皇に対してもまた、国民に対しても、戦争の指導、判断の重大な錯誤について、『われ誤てり』と、いさぎよくカブトを脱いで、沈黙を守ることこそ、『さすがは日本武士道の典型』と、戦後も国民のひそかな敬仰と同情を集めたことであろう。
私は日本人として、終戦直後に重大責任を感じて自決した阿南陸相、大西中将、本庄大将、田中静壱(しずいち)大将、杉山元帥、吉本貞一中将その他の軍人にたいして、今日なお深い哀悼(あいとう)と共感を禁じえない。
そういう意味から、太平洋戦争の神話や伝統を打破して、その歴史的意義と、日本人の子孫代々に伝える偉大な遺産として、公正に評価するためには、今日こそまさに、内外のあらゆる権威ある、貴重なドキュメント資料が出そろった絶好の機会であるといえよう。
太平洋戦争の開戦に先立ち、はたして軍国日本の指導者たちは、『日本はかならず勝つ』と天皇のまえで、また神に誓って、はっきりと明言することができたであろうか?
また、もし天皇自身が戦後に、しきりに伝えられた(とくに東京裁判で、東条首相が“天皇に責任なし”と熱弁をふるったように)ごとく、戦争反対と平和愛好の熱意があったならば、なぜ、神格化された天皇の、無限大の絶対大権を発動(終戦の聖断のように)して、軍内部の強硬主戦派を断固として押さえつけ、あくまで開戦を回避することができなかったか。
このような重大な疑問は、今日のいわゆる、「後ヂエ」から発せられたものである。
したがって、開戦直前の緊迫した国内の雰囲気を正しく理解しなければ、我々が、軽率に天皇の優柔不断を怪しむことは失礼である。
だが一方、当時の陸海軍最高首脳部が和戦の決断にたいする自己責任を恐れて、陸軍側では、『これは海軍の決意ひとつである』といえば、海軍側は、『それは海軍が独自に決定すべきことでなく、すべて総理(近衛公)に一任したし』と応じて深刻に対立するしまつだった。これは、当時の統帥部が、米英を相手に、けっして即戦即決の勝算がなかったことを物語っているものである。
とくに山本五十六元帥は、陸軍の独走による日独伊軍事同盟に強く反対して、日米開戦を極力、回避しようと努力した人であった。
しかし、陸軍側より、『海軍の決意いかん』と、ふくみのある申入れを受けた以上は、もはや国家の運命を、戦争によって打開するよりほかに、海軍軍人としては、まったく策なし、と覚悟したのであろう。
『それは、是非やれといわれれば、はじめの半年か、一年間は、大いにあばれてご覧に入れる。
しかし、二年、三年となれば、まったく確信がもてない。
三国条約が成立したのは致しかたないが、かくなりし上は、日米戦争を回避するよう極力、ご努力を願いたい』 |
と、山本元帥は、奇しくも開戦一年三ヵ月前の、日独伊三国同盟調印直後に、当時の近衛首相に申入れていた。
また、開戦直前の、十一月一日の大本営政府連絡会議の席上で、当時の海軍軍令部総長・永野修身大将は、
『いま戦争をやらずに、三年後にやるよりも、いまやって三年後の状態を考えると、いまやる方が戦争はやりやすいといえる。 それは、必要な地盤が取ってあるからだ。
(いつ戦争をしたら勝てるか――という質問にたいして)、それはいまだ! 戦機は後には来ない!』 |
と、語気も強く発言している。
また、同席した陸軍参謀総長・杉山大将も、
| 『戦機はいまなり。陸軍作戦は、海軍の海上交通確保とともに、占領地確保に自信あり』 |
と、開戦必至を主張した。だが、東郷茂徳(しげのり)外相は、ただひとり、
| 『数年もさきの戦争のことは不明なるにつき、決心しかねるが、このさい、あくまで自重して戦争を回避し、臥薪嘗胆(がしんしょうたん)すべきである』 |
と、堂々と反対した。
要するに軍国日本は、『長期戦になることは、止むをえないが、しかし、持久不敗の態勢を確立して勝機をつかむ』という、いわば『神国不敗』の迷信を信じて、昭和十六年十二月八日、パールハーバー奇襲による、対米、英、蘭開戦に踏み切ったわけである。
それは、アメリカの著名な戦史家サミュエル・モリソン博士の言葉によれば、『日本は敗戦の第一歩を踏み出した』のであったといえよう。
Ⅲ 太平洋戦争の前夜 top
1 昭和十六年の国内情勢
昭和十六年(一九四一年)は日米開戦の年だ。それは、すでに半世紀近くもむかしのことであるから、戦後に育った若い世代の人々が、いくら当時の日本の大新聞の古い切り抜き記事や、縮刷版を手がかりにして、この開戦の年の実相と、ムードを知ろうとこころみても、おそらく、無益な骨折りに終わるであろう。
なぜなら、その当時の軍国日本は、すでに戦時体制をますます強化して、国民精神総動員が政治、経済、社会の各方面から、市町村の各家庭にまで徹底的に実施されていたから、もはや対米英戦争はいつ起こるかも予測できないほど、政府と軍部は緊迫感にみなぎっていたからだ。
いやしくも、反戦的な言動や平和愛好の気分は、五年越しの『支那事変』(日中戦争)の完全遂行のために危険、有害であるとみなされて、今日では到底想像もできないような、厳重な『思想、言論統制』と『新聞検閲』が励行されていたから、まさに日本国民たるものは、すべて絶対的神聖な天皇の有難い『御稜威(みいつ)』(天皇の威光と仁徳)の下に、欣然と『一億総決起』の大覚悟と勇猛心が要請されていた。
それで毎日の新聞は、中央紙も、地方紙も、いっせい、一律に軍部の主戦論と、国粋右翼の好戦主義を強く反映し、内閣情報局の監督と指導による、反米英調の強烈な軍国的色彩がおどろくほど目立ってきた。
いわゆる、皇国史観にもとづいた米英撃滅の思想的攻勢か、全国の新聞論説にも、雑誌記事にも、恐ろしい威力をふるっていたものであり、いかにも国民大衆が熱狂し、軍部を支持していたような錯覚をあたえやすい。
しかし、これは、あくまで新聞論調や記事面の表面に現われた強がり現象であって、一般大衆のまったく知らない日本政府の奥座敷では、軍部(とくに海軍側)の自重派をまじえて、天皇自身の穏健な希望(日本の皇室が明治、大正、昭和三代を通じて親米英的な伝統が強かったことは、昭和軍部強硬派の反米英主義と皮肉な対照を示していた)にそって、ひそかに戦争回避と危機打開のため、最後の努力が、大いに行なわれたものであった。
その一つの努力が、野村吉三郎海軍大将の駐米大使任命であった。
それは、いかに軍部の強硬派といえども、世界一の富強を誇る米、英両国を相手にして、日本が独力で戦争を起こしてかならず勝つという自信と成算を持つものは、だれもいなかったからであろう。
軍部も内閣情報局長も、口先では、国民大衆の前で、いかに『米英撃滅』の大言壮語を勇ましくブッてみても、五年越しの『支那事変』さえ、軍部の思う通りには到底片づかず、ますますドロ沼化して、長期消耗戦の悪あがきを露呈しつつあった当時だけに、軍首脳部の本音はむしろ、第二次大戦初期の、独伊両軍の圧倒的勝利の余勢に便乗して、米英のいわゆるアングロ・アメリカン世界支配体勢の打破をめざした和戦両様のかまえで、『支那事変』の収拾について、重慶政権(蒋介石主席)支持、援助から、手を引かせるように、米英ブラッフ(強がりを誇示しておどかす)をこころみたのだろう。
軍部とは、かならずしも折り合いのよくなかった枢軸派の松岡洋右(ようすけ)外相のねらいも、またそのあたりにあったようだ。
その意味から、昭和十六年一月二十三日、横浜出帆の鎌倉丸で、野村新駐米大使が波高き太平洋を渡り、はるばる赴任の途についたとき、軍部のひそかな期待は、複雑で切実なものがあった。
とくに海軍側では、かがやかしい経歴を持つ海軍の長老が、素人外交に利用されたあげく、最悪の事態に、万一おちいった場合は、全責任を負わされるおそれがあるため、野村大将個人に傷がつかないように心配する向きが多かったようだ。
それだけに全海軍の希望をこめて、戦争回避のため、ぜひとも野村大使の使命達成を願望する空気が部内に高まっていたようである。
しかし、陸軍側の少壮幕僚のなかには、
『いまさら、親米派の海軍大将を駐米大使に任命して、ワシントン政府と外交交渉をしてみたところで、日本の弱腰をただ見すかされるだけで、かえって、支那事変の完遂に有害な影響をあたえ、また国民士気にも反戦、和平の悪影響をおよぼす。
もはや、日米交渉はけっして期待されず、ただ開戦準備の時をかせぐのみ……』 |
と、豪語する連中も少なくなかった。
要するに、日、独、伊三国軍事同盟にもとづいて、日本はおそかれ早かれ、第二次大戦に突入して、米英と対決して東亜百年の禍根を断ち、聖戦の大使命を実現すべきである――
というのが、彼らの革新的主張であった。平和外交を職分とする外務省の若手外交官のなかにさえ、当時このような革新派、あるいは枢軸派と呼ばれた強硬分子がいたことを忘れてはなるまい。
彼らは軍部の主張に同調して、従来の米英追従政策の打破を要望していた。
このような陸、海軍間の矛盾した対米交渉の根本的認識について、当時の第二次近衛内閣は、いわば捨て身の決断力に欠けていたので、つねに優柔不断で軍部の独走を押さえ切れず、また閣内でも、近衛首相と松岡外相の反目、対立など日にあまるものがあった。
そのせいか、野村大使がワシントンへ赴任する直前に、同じ海軍出身で、海軍兵学校で三期後輩に当たる前首相・米内光政(よないみつまさ)大将を訪ねたとき、米内大将は、
『あなたが、この大任を受諾されたことは、感謝にたえません。
ただし、現下の国内情勢は憂慮すべきものがあり、自分としては、あなたが渡米中に、二階に上がって梯子を取り上げられるような事態に立ちいたることを心配しています』 |
と、野村大使の手を固く握って語ったといわれる。
確かに野村大使が、戦争回避の重大使命をおびて赴任したとき、日本国内は政情が険悪で、波はすでに高く、風雲は急を告げて、その前途は、けっして明るいものではなかった。
陸軍の横車を身にしみて痛感していた米内前首相の忠言は、結局、その後の日米会談の進行につれて、果然、的中することになり、野村大使の努力にまず、日本国内から水をさされるような憂き目を見たのだ。
(注、米内光政海軍大将は明治十三年、岩手県生まれ。明治三十四年、海兵卒。
佐世保鎮守府長官、連合艦隊司令長官、海相、軍事参議官を歴任した。
海軍部内の清廉硬骨な反枢軸派の重鎮で戦争反対、回避の主張を堅持し、宮中方面の信望も厚かった。
昭和十五年一月に米内内閣の首班となったが、汪精衛政権成立をめぐり、支那事変の処理について陸軍側と折り合い悪く、そのために彼のめざした親米英外交は行き詰まり、内外の難局に直面したまま政治力不足により、同年七月、あえなく総辞職した。
その直後に、いわゆる軍部の総意に便乗した第二次近衛内閣が出現した)
2 野村大使の米国上陸第一歩 top
この当時、私は朝日新聞ニューヨーク特派員として、野村大使よりも数ヵ月早く太平洋を渡り、その途中で平和的な美しいハワイの真珠湾軍港を視察し、またハワイ地方と米本土西岸のサンフランシスコ、ロサンジェルス両市方面の在米邦人一世、二世の状況を現地調査して、いわゆる、日米危機の実態を、太平洋の向こう側から熱心に観察していた。
そして、野村大使の横浜出発が、予定よりもだいぶおくれて手間どっていた間に、私は隣邦のメキシコへ足をのばして、首都メキシコ・シチーで、カマチョ新大統領の右腕として知られたパディーヤ外相と特別会見して、その記事を本社へ打電していた。
歌と踊りの、メキシコの異国情緒を、たっぷり楽しみながら、私が数日間を仕事と闘牛見物などでいそがしくすごしていたとき、本社から『野村大使、本日出発した』という電報をホテルで受け取って、にわかに緊張したし、また大いに元気づいた。
それは、『もしも野村大使が出発を取り止めたら、日米関係は、戦争の心配があるが、もし出発したら、日米会談は有望で戦争の危機は避けられる』というのが、その当時の十数万の、在米邦人の一致した希望的観測であったからだ。
私は、数日後にメキシコに別れを惜しんで、飛行機でメキシコ・シチーよりロサンジェルス経由で、サンフランシスコに舞いもどり、野村大使を迎える仕度をととのえた。
それは野村大使一行に、ただ一人の日本人記者として特別参加し、同じ特別急行列車でシカゴ経由、ワシントンまで同行するためであった。それは、日米開戦の年のはじめの、私にとっては、永久に忘れられない思い出のひとつとなった。
(当時、サンフランシスコには、日本の大新聞社も特派員を常駐させず、地元の邦字紙の記者を通信員として特約し、何かあるたびに臨時ニュースを打電させた)
それで、東京の本社から派遣された正式の新聞特派員として、はるばる米国に赴任した野村大使を、サンフランシスコ港に出迎えて、長文の会見記事を綴って、打電、報道したのは、私だけであった。
それは、太平洋戦争の前夜に関する、貴重な歴史的記録の一つとして、たいへん興味ぶかいものであるから、つぎにその一部分を私の手許のメモと、当時の東京朝日新聞の紙面より転載して紹介しよう。
私が戦後の今日でもまだ生々しく記憶している点は、その当時には日米戦争の恐怖と懸念は、米国では現実的なものではなくて、『いくら日米関係が悪化してもまさか戦争にはなるまい』と米国人は、誰でも常識的に楽観していたようだ。
すなわち、昭和十六年初頭の時点では、物資の不足した日本国内では、きびしい戦時体制下に、物情が騒然としていたが、さすがは世界一の富強をほこる米国では万事、ゆったりとしてコセコセせず、とくに米国の西岸最大の港都として、長年、日米貿易の繁栄に依存していたサンフランシスコ市の各界有力者と市民大衆は、衷心より『太平洋の平和』を願望して、野村大使の着任を明るい表情で歓迎したものだった。
また米海軍も、この遠来の提督大使を親しい儀礼をもって迎えた。
*
昭和十六年二月六日、サンフランシスコにて――
太平洋の危機に重き使命を帯びて赴任する新駐米大使野村吉三郎大将は、二月六日午前九時入港の鎌倉丸で、多数の在留邦人の感激的出迎えを受けながら、元気よくサンフランシスコに上陸第一歩を印した。
この朝、未明に、アメリカ駆逐艦『キング』『ローレンス』二隻が港外三十五マイルの沖合いに野村大使を迎えて敬意を表し、やがて金門湾(ゴールデン・ゲート)の入口に近づくとプレディシオの要塞から、殷々(いんいん)たる十九発の礼砲が発射され、劇的光景を呈した。
前夜来の濃霧は名残りなく晴れて、サンサンたる陽光が青き空と海に輝き、いかにも新大使を歓迎するようだ。
私も薄暗いうちから、日本郵船会社の埠頭に出掛けてみると、各新聞社の米人記者とカメラマン、それにニュース映画の連中がじつに六、七十人もすでに詰めかけてたいへんな騒ぎだ。
そこへ河崎総領事代理をはじめ、百名以上の在留邦人官民代表が集まったので、大きな二隻のランチも、超満員だ。
『過去五十年、日本から多くの大使が来たが、こんな盛大な出迎えを受げたものはない』とは、在留同胞の古老の感激した話である。
午前八時に検疫が終わると、米人記者団を先頭に、一同は鎌倉丸になだれのように乗り込んだが、巨体の野村大使はグレーの背広服にくっろいだようすで、二コニコ笑いながら、みんなと愛想よく握手を交わし、少しも長い船旅の疲れを見せない。
この数日来の冬の荒天で、海はだいぶ荒れて、顧問役の司行り若杉公使など、すっかり弱っていたが、野村大使は、さすが海軍で鍛えた提督大使らしく元気よく、ただちに記者団の包囲の中で、悠然と煙草をくゆらせながら、まず別項の声明書を発表した後、自由質問にうつった。
米人記者のヤンキー流の不遠慮な質問は、
『アドミラル、日米関係は絶望だと思うがどうか?』
と詰め寄れば、野村大使は相変わらず童顔をほころばせて、通訳もぬきにして、少しなまりの強い流暢な英語で、
『私は日米関係の前途に大きな希望を持っている。
その希望を抱いて、これからワシントンに赴くのだ』
と、なかなか素人放れのした名大使ぶりだ。 |

真珠湾奇襲の直前まで、戦争回避の重大使命を
おびて日米和平公渉をつづけた
野村吉三郎大使とハル米国国務長官。
|
問『提督は、ルーズベルト大統領を知っておられるか?』
答『私が、一九一五年(大正四年)のはじめより一九一八年(大正七年)の秋まで、ワシントンで海軍武官をしていたとき、ルーズベルト氏は海軍次官であったから、よく知っている。
このサンフランシスコには、一九二九年(昭和四年)に、練習艦隊司令官として来たので懐かしい』
問『日米戦争について意見は?』
答『私は日米間の戦争など、いまだかって考えたこともない。
いま私の考えていることは、ワシントンに赴いて日米関係を改善することだ。戦争など、到底考えられないことだよ』
問『では、日米関係の改善は可能なりや? それならば、その理由は?』
答『日米関係を改善することは、私の信念である。
それは理由などを超越した断固たる信念である。
私はこの信念を持って太平洋を越え、いまからワシントンへ向かうのだ』
問『日本国民の対米感情は?』
答『わが国民は全体からみて、日米両国の友好親善を望んでいるよ』
問『シンガポールは、東亜新秩序の中に含まれるや?』
答『そんなバカなことはあるまい。
現に、シンガポールは英国の海軍根拠地ではないか!
蘭印(オランダ領インド諸島)についても、いまわが国は堂々と、通商使節を派遣して交渉している。
目的は、ただ貿易の増進にほかならぬ』 |
かくて、米人記者団の包囲線を、みごとに突破した野村大使は、今度は新聞カメラ班と、ニュース映画陣の二重包囲を受けたが、悠々たる態度で、たくさんのマイクの前で英語のスピーチを二分間ばかりやってのけて人気を博した。
さすが人なつっこいヤンキー連は、だれも野村さんを『大使(アムバセダー)』とか『閣下(エクセレンシー)』とは呼ばず、きわめて親しそうに『提督』と敬称ぬきで呼んでいたのは面白い。
(中略)
上陸後、午後から野村大使は答礼の意味で、陸軍司令官デ・ウイット中将、海軍管区司令官ヘップバーン少将、サンフランシスコ市長ロッシー氏らを訪問して歓談した。
また同夜、市内の日本人倶楽部で在留邦人団体合同主催の大歓迎会が開かれる。
(後略)
3 評判がよかった提督大使 top
さすがに米国は、『新聞と言論の自由』を、なによりも尊重する民主主義の国だけあって、たとえワシントン政府が、いかに刻々悪化する欧州戦局と国際情勢について、反日独伊枢軸の政策を強調しても、『太平洋の平和』を熱望する米国西岸地方、とくにサンフランシスコ、ロサンジェルス方面の新聞論調と世論は、意外なくらい日本にたいして友好的であり、とくに野村大使の赴任を、『平和の使節来たる』と呼んで大いに歓迎した事実を、私は日本人記者として、現地で目のあたりにして忘れることかできない。
それで当時の私の打電した記事を、もう少しつぎに引用して読者諸君の参考に供したい。
それは後述するように、ヒトラー憎悪とナチス打倒と、反枢軸熱に燃え立つ戦時的色彩の強烈な、首都ワシントンの雰囲気と新聞論調とは、まったく『これでも同じ米国の新聞であろうか?』とおどろくほど、相反して不思議な対照を示していたからだ。
しかし、よく考えてみると、当時の軍国日本のような厳重な新聞、言論統制と暗い検閲で規正された新聞界とはちがって、ルーズベルト大統領の対英ソ軍事援助反対、参戦反対、徴兵反対と、なんでも自由に堂々と政府を非難、攻撃できたアメリカ新聞界なればこそ、広い国内で東部と西部で、米国民の対日観がいろいろ異なっていたのは当然であったろう。
野村大使、大いに笑う――米紙鳴物入りの歓迎振り
(当時の東京朝日新聞の見出しによる)
昭和十六年二月七日、サンフランシスコにて――二月六日、米国に上陸第一歩を印した新駐米大使野村吉三郎大将は、その堂々たる米人にひけを取らぬ体格と、人なつこい鷹揚な態度が非常に好感をあたえたとみえて、サンフランシスコの各新聞は、いっせいに大使の写真を、驚くほど大きく第一面に掲げ、いずれも二百行ないし三百行の長文の会見記事を、記者の署名入りで派手に掲載している。
まず、六日付夕刊では、『コール・ブレティン』紙が、第一面の三分の一ほどのズバ抜けて大きな写真をのせて、その大見出しは、
「新しき日本の使節、サンフランシスコで歓迎さる。
彼は平和を予見す、日米関係は決して望みなきにあらず、いな有望なり」とあった。
また、有力なスクリップス・ハワード系(全米チェーン)の『サンフランシスコ・ニュース』紙は、野村大使の大クローズ・アップ写真の見出しに、『私は偉大なる希望を抱く』と記して、大使の人物と経歴を詳細に紹介している。
つぎに七日付の朝刊では、『サンフランシスコ・クロニクル』紙が、非常に友好的な筆致で、『日本の使節野村提督、平和の希望を抱いて着任す』と大見出しの下に、つぎのように論じている。
『野村提督は偉大なるアメリカの友である。そのすばらしい体格は六フィート豊かで、体重は百九十ポンドである。
六日午後、第四軍司令官ジョン・デ・ウィッ卜中将の案内で、野村大使はプレシディオ兵営を視察し、歩兵第三十連隊を閲兵せり』
また、『サンフランシスコ・エキザミナー』紙は、野村大使がキワドイ質問をたくみにそらしてゆくのを、皮肉まじりで、『野村提督は、みずから外交の素人と称しているが、なかなかどうして立派な外交官ぶりである。
なにを訊ねても、肝心なところは豪快にハッハッハッと哄笑してゴマ化してしまう』と、大々的に書き立てている。 |
サンフランシスコの新聞界では、日本人でこんなに大きく書き立てられたのは、じつに一九二一年(大正十年)のワシントンの軍縮会議に出席するため渡米した日本代表(日本全権徳川家達公、加藤友三郎海軍大将)一行以来はじめてのことである、といっている。
また、七日午後には、サンフランシスコ第一の社交クラブであるボヘミアン・クラブで、米国西岸一流の有力者と名士を網羅した、商工会議所と、外国貿易協会共同主催の野村大使歓迎午餐会が盛大に開かれた。
出席者は商工会議所会頭パース氏。市長ロッシー氏、陸軍司令官デ・ウィッ卜中将、海軍司令官へップバーン少将以下百数十名で、いずれも野村大使の平和使命達成を祈って乾杯した。とくに、パース氏は一同を代表して、
| 『サンフランシスコの繁栄は太平洋の平和にあり、我々は評論家連中のいわゆる、「すでに手遅れだ」という言葉を信じない。なぜならば我々は今ここに、閣下のごとき日米親善に努力する偉大な、理解のある友を見出すからである』 |
と歓迎の辞を述べた。これに応えて大使は力強い口調で、
『いま貴下は、サンフランシスコの繁栄は太平洋の平和にありと述べられたが、太平洋の平和は、ただサンフランシスコの繁栄の重要な要素であるのみならず、日米両国の繁栄の重要な要素である。
さらに我々は実際に、全人類の平和を守護する義務がある。この狂瀾怒濤時代において、平和達成は日米両国民の非常な努力に待つのみであるが、我々はここに、微力を尽くして努力する覚悟である』 |
と述べて、満場の喝采を博した。
このように野村大使は、米国上陸第一歩のサンフランシスコ市では、予想外に日米関係者多数から熱烈な歓迎をうけて大いに感動したようすであり、それらの歓迎会に同席した私もまったく肩身の広い思いがして、『日米関係はまだまだ大丈夫である』という楽観的気分がわき上がった。
ところが、太平洋岸のサンフランシスコから、はるか数千マイルもはなれた東部地方、とくに首都ワシントンの空気はガラリと一変していた。
私は野村大使一行とともに、最新式流線型特急に同車してシカゴ経由、ワシントン入りをして冷厳な現実に驚いた。
それはサンフランシスコの熱烈な歓迎が、シカゴ(列車乗り換えのため途中下車して、ホテルでしばらく休憩したが、インタビューにやって来た米人記者はわずか数名だった)では無関心に変わり、さらにワシントンでは、冷やかな敵意に変ったのだ!
この太平洋戦争直前の歴史的な一年間の、米国の政治的気候と社会的雰囲気については、これまで日本側の戦史、戦記類には一切、取り上げられていないようであるから、その当時の私の古い手記から、つぎの一節を引用、紹介しておきたい。
これは日米戦争への道の、ささやかな歴史の指標となるものだ。
『蒼茫たる太平洋を一望に眺める港都サンフランシスコ市のノップ・ヒルの丘の上に聳える古めかしいフェアモント・ホテルの同じ五階に、私は野村大使一行と部屋をわかち、またモダン高層建築のマータ・ホプキンス・ホテルの夜会に、あるいは古風なボヘミアン・クラブの歓迎宴に、私もまた招かれて出席して、いかにも力強く頼もしい六十三歳の老提督大使の巨姿と人気に深く印象づけられた。
二月八日夕、サンフランシスコ対岸のオークランド発の流線型特急「サンフランシスコ市」号は、太平洋の平和の希望をのせて東へ発進したが、町深きロッキー山麓のオグデン(ユタ州)でもシャイアン(ワイオミング州)でも、途中の停車駅には、かならず多数の在留邦人代表が家族を連れて、遠方よりはるばる駆けつけて出迎え、早暁や深夜にもかかわらず、野村大使に心尽くしの花束や握りずしや、果物を贈って、同胞の涙ぐましい熱誠を捧げたのであった。
老大使もまた、寝る間を惜しむように、特急列車の停まるごとに服装を正して駅頭に降り立って、わずか数分間の停車の合間に、在米同胞の意気と覚悟を励まして、
「日米関係はかならず好転するように全力を尽くしますから、みなさんは心配せずに、生業に精励してください」と感激をこめて応えたのであった。
二月十一日、紀元節の朝、野村大使一行と共に私はワシントンに到着したが、さすがにヒトラー打倒のため、対英ソ軍事援助に懸命な米国の首都には、独伊枢軸国と結んだ軍国日本に対する冷やかな敵意が満ちていた。
早朝の駅頭に出迎えたのは日本大使館幹部と、在留邦人商社代表たちとワシントン駐在の独、伊両国大使のみで、米国務省から儀典課の役人一名が姿を見せたが、新聞記者はまったく野村大使の着任を黙殺したように来なかった。
太平洋沿岸地方の日米間の平和を願望する雰囲気は、ここには少しも感じられなかった。
それは東亜の新秩序をめざす日本の生死を賭した闘争に対し、米国全権帝国主義の露骨な挑戦の相貌であった』 |
はたせるかな、野村大使のかがやかしい使命は、じつは暗い険悪な道であり、日米交渉は予想以上に当初から難航を覚悟せねばならなかった。
その理由は、いろいろ複雑多様ではあったが、最大の難関は、すでに深刻なドロ沼化した『支那事変』(日中戦争)の処理に関する、日米両国の立場の根本的対立と、日本の政府対軍部の不統一(とくに近衛首相、松岡外相、東条陸相の三者三様の思惑と権力争いと責任回避)であった。
かくてワシントン着任以来、野村大使の個人的信用と、努力と善意が、いかに涙ぐましいものであっても、米国側ではまったく強硬で譲歩する気配がなく、しかも交渉方針をめぐり、松岡外相と野村大使の間には、しだいに感情的なミゾが深まり、日米交渉の前途には、時日がたつにつれて、暗い影がただよってきたのだ。
それは、いかに旧友のルーズベルト大統領の信用が厚くとも、野村個人の力では到底破れない厚い、非情な壁であった。
では、野村大使は、はたして日米交渉について、本当に成算があったのであろうか?
また、日米関係が刻々と悪化していた昭和十六年(一九四一年)はじめに、彼はなぜ軍人大使として、この至難な大任を引受けて渡米したのであろうか? |

松岡洋右外相。交渉方針をめぐり
野村大使との間にミゾを生じた。
|
かって野村大使が、大正四年(一九一五年)一月、在米日本大使館付海軍武官(海軍大佐)としてワシントンに着任した当時、ルーズベルト大統領は、少壮の海軍次官であったので親しく交際していたが、それ以来この両人は一体、どのような友情を持続していたのであろうか?
歴史的な日米交渉において、ルーズベルト大統領は、野村大使をいかに評価して扱っていたか?
これらの日米交渉をめぐる幾多のナゾと、奇怪な軍事、外交の内幕こそ、まさに日米開戦前夜の軍国日本の秘めた矛盾と、苦悶を深刻に象徴するものであった。
なお、日米開戦の年――昭和十六年の重大な歴史的意義については、つぎに掲げる一覧表を、ぜひ精読していただきたい。
昭和十六年の主なできごと――
|
1月8日
1月11日
1月16日
1月28日
3月1日
3月8日
3月11日
3月12日
4月1日
4月6日
4月13日
4月16日
4月20日
4月22日
4月23日
5月6日
5月10日
5月10日
5月12日
5月27日
6月6日
6月12日
6月20日
6月22日
6月23日
7月2日
7月7日
7月16日
7月21日
7月25日
8月1日
8月14日
8月28日 |
陸軍が『戦陣訓』を示達す
新聞紙等掲載制限令を公布実施す。
全国の青少年団体を統合して、大日本青少年団結成式を挙行す。
支那事変臨時軍事費累計百七十四億五千万円と議会で発表す。
教育の戦時体制化をめざして国民学校令公布。(従来の尋常小学校を、国民学校へ切り換えた)
野村吉三郎駐米大使がワシントンで、ハル米国務長官と日米交渉を開始す。
米国政府は、画期的な武器貸与法を成立実施す。
松岡洋右外相は、ソ連、独、伊三国訪問のため出発、スターリン、ヒトラー、ムッソリーニと重要会談を行なう。
東京、大阪で米の通帳配給制実施、また生活必需物資統制令公布。
欧州戦線でドイツ軍がギリシア、ユーゴスラビア両国へ侵入す。
日ソ中立条約成立。満州国と外蒙の領土保全と不可侵を日ソ両国が声明。
野村大使とハル米国務長官の間で日米了解案が成立す。
米国、カナダ協定成立す。
松岡外相が欧州より帰国し、日米交渉の了解案に反対す。
ギリシア、対独降伏。(ユーゴスラビアは四月十七日に対独降伏)
スターリンがソ連首相(人民委員会議長)に就任す。(それまではソ連共産党中央委員書記長)
独副総統ルドルフ・ヘスが和平交渉のためひそかに英国へ単独飛行して、英官憲に逮捕さる。チャーチル英首相は彼を相手にせず、ヒトラーは面目を失して激怒し、ヘスを狂人とみなす。
国防保安法施行。
松岡外相は日米了解案の日本側修正案にもとづく交渉開始を野村大使に訓令す。
ルーズベルト米大統領は、無制限国家非常事態を宣言す。
日蘭会談決裂す。(十八日に打切り声明)
日ソ通商協定、貿易協定成立す。
ハル米国務長官が野村大使へ覚書(日本修正案に対する米国対案)を手交す。
独ソ開戦(独軍が対ソ総攻撃、侵入)、英国はソ連支持を声明す。米国も二十四日にソ連支持を声明。
南京政権主席汪精衛が来日、近衛首相と会見す。支那事変解決につき討議の上、共同声明を発表す。
ソ連政府は対日政策が松岡外相の訪ソ当時と変わらずと声明す。しかし、同日御前会議で、『情勢の推移に伴う帝国国策要綱』をひそかに決定す。(松岡外相は対ソ開戦を主張す)
『関特演』(対ソ戦を想定した関東軍特別大演習)の動員令下る。これにより関東軍の総兵力は倍加して約七十万、馬匹約十四万、飛行機約六百機と記録されている。
閣内不統一を理由に、第二次近衛内閣総辞職す。ただし近衛は、対ソ開戦と、独伊枢軸外交強化を主張する松岡外相を追放した上、七月十八日に大命再降下を受けて第三次近衛内閣成立す。
日・仏印共同防衛協定成立し、二十八日、日本軍は南部仏印(サイゴン地区)に進駐す。
米、英両国は日本軍の南部仏印進駐に対する報復措置として、日本の在外資産の凍結令を発布、対日経済断交す。
米国は対日石油輸出を完全停止す。
ルーズベルト米大統領とチャーチル英首相の洋上会談により、『大西洋憲章』を発表、対独伊戦争目的、ナチス打倒、戦後の平和世界建設など八項目の米英共同宣言を行なう。(米国の対独参戦は、もはや時間の問題とみなされた)
野村大使はルーズベルト米大統領に会見して、日米首脳会談を提唱した近衛メッセージを手交す。 |
|
9月2日
9月6日
9月15日 |
政界の戦時体制化に即応して、翼賛議員同盟結成、三百二十六議員が参加す。
御前会議で対米英蘭戦争を辞せずとする『第一次帝国国策遂行要領』を決定す。
米穀(べいこく=穀物)国家管理実施要綱を発表。 |
10月15日
10月16日
10月18日 |
赤色スパイ団首領ドイツ新聞記者リヒアルト・ソルゲ、元朝日新聞記者、近衛首相側近の尾崎秀実ら一味が一斉検挙さる。同日、ソ連政府はモスクワよりクイビシェフヘ移転す。
第三次近衛内閣辞職。
東条英機内閣成立、現役軍人が首相と陸相を兼任した軍部独裁体制が出現す。 |
|
11月5日
11月6日
11月10日
11月16日
11月17日
11月20日
11月22日
11月26日
11月26日 |
御前会議で対米英蘭戦争を決意した『第二次帝国国策遂行要領』を決定す。(ただし、日米交渉が十二月一日零時までに成功すれば、武力発動を中止す)
野村大使と協力して最後の日米交渉に当たるため、来栖(くるす)三郎大使が東京発、香港よりパンアメリカン旅客機で渡米す。
チャーチル英首相は日米が開戦すれば、英国も即時参戦すると演説す。
第七十七回臨時帝国議会召集。
ワシントンで米、英、蘭、中国四ヵ国会議開催。
日米公式会談開始、野村、来栖両大使出席す。
国民勤労報国協力令が公布施行さる。
ハル米国務長官は野村、来栖両大使へ米国政府の対日回答――いわゆるハル・ノートを手交す(日本側提案の甲、乙両案とも拒否さる)。同日、米軍部はハワイ現地の陸海軍司令官に戦争警告を発す。
南千島列島エトロフ島ヒトカップ湾に集結中のハワイ攻撃機動部隊(正規空母六隻基幹、指揮官南雲(なぐも)忠一中将=第一航空艦隊司令長官)は出港、オアフ島めざして進航す。 |
12月1日
12月8日
|
日米会談はついに最終段階に到達し、御前会議でついに対米英開戦を決定す。
(米国時間では十二月七日、日曜日)日本軍はハワイ真珠湾軍港を奇襲攻撃、またマレー半島に上陸、米英両国に対して宣戦布告の詔勅下る。かくて太平洋戦争の火蓋が切られた。 |
Ⅳ 日米会談かくて決裂す
top
1 野村吉三郎大将未公開手記
いま私の手元には、泥史的な日米会談に関する、当時の駐米大使野村吉三郎大将の貴重な手記がある。
これは、昭和三十五年十一月に、私が監修者として関係していた、日本テレビの連続ドキュメンタリー番組「日本の年輪――風雪二十年」(全百十一回)の一篇として、「日米会談」取材のために、テレビ・カメラ班数名を同行して、東京・日本橋にあるビクター本社の社長室で、野村老(当時八十三歳)と会談、録音したとき、几帳面な野村老(当時ビクター社長)が、みずから便箋数枚にメモ的に手記して、私に手渡してくれたものである。
野村大将は、終戦直後に、『米国に使して――日米交渉の回顧』(昭和二十一年七月、岩波書店刊)と題する大冊の記録を刊行して、その当時のいきさつを、くわしく述べているが、しかし、戦後十五年もたっているので、その考え方も、回想の内容も、変わってきたことは当然であろう。
その意味から、この私の手元に残された手記こそ、いまは亡き野村大将の、おそらく絶筆として、きわめて貴重な価値があり、興味ぶかいものであると信ずるので、ここにはじめて紹介、発表するしだいである。
*
(1)米国赴任当時(昭和十六年二月)
『私は、駐米大使の就任を一応、辞退しましたが、それは、日本が新たに日独軍事同盟を結ばんとしており、いわゆるイタリアを加えての三国同盟は、それ以前の平沼内閣で論議された防共協定を強化した三国同盟とは性質を異にし、米国の英国等援助のための参戦を阻止せんとする、すなわち戦争を制限せんとするものである。
これは対米、対英関係を極端に悪化するは必至と考え、かかる国際情況をつくり上げては、自分は日米間の妥協を遂行する十分の自信なしと認めたからである。
海軍の当局者は。日米戦争は避けねばならぬ、と考えていて、私がルーズベルトと個人的親善関係にあるのを好材料として、出馬をうながし、松岡外相もまた、熱心に私を推すので、とうとう就任いたしました。
松岡氏との話の間では、あるいは日米戦争はアーマゲドン(世界最終の決戦場)であるとか申し、また、「君も、もはや湊川に行って然るべき時ではないか」とも言い、さらに日米戦争を避けたいが、あるいは避け得ず、私に楠木正成の役割を演ぜよとも言ったわけである。
私は、けっして楽観はしていなかったが、米国の軍備情況より見て、米国も二正面戦争を避けるよう努力するであろうから、ここに活路を見出せるかも知れないと思っていた』
(2)日米交渉有望(昭和十六年三月-五月)
『ピショッブ・ウォルシュと神父ドラウト(昭和十五年十二月にひそかに来日して、近衛首相、松岡外相とも会見し、日米妥協工作に努力す)は、日米戦争は愚だと考えていた。
私も同じ考えで、ギブ・アンド・テイクの常道をもって、平和の方へ方針を確定すべしだと考え、これはわが国の国利民福の上からも当然の途だと確信していた。
私は、第一次大戦の間、約四年間、海軍武官として米国の国力を熟知し、また米国の歴史と、その国民性とを熟知している。
私としては当然のことであり、開戦のまぎわまで、いかなる協定も戦争よりましだ、戦争は、両国間の問題を解決し得ないと、両人も申していた。
私と通じる米人は、よくこれを承知しており、国務長官ハル氏の著書にも、私が平和を維持するため終始一貫、誠実をもって努力したことで「クレジッ卜」をあたえると書いている。
また、評論家のデヴィッド・ローレンスなども、同様の批評を、しばしば、くりかえしている。
そこでこのメリノール教派(米国のカトリック教の有力な教派)の二人の宗教家と、日本から出張した井川忠雄(元大蔵省官吏)、岩畔豪雄(当時、陸軍省軍事課長、陸軍大佐で野村大使を補佐するため特派された)の両人とが作成した平和の案を見て、大使館の公使、参事官、陸海軍の武官を加えて慎重に審議した上にて、一日、ハル長官と会見し、東京へ回訓を求めた次第である』
(3)日米交渉難航(昭和十六年六月~十月)
『瀬踏(せぶみ)的の話は太平洋の平和を維持するための話であり、それには支那問題はつきものである。支那問題となると、撤兵問題が大問題となってくる。
はじめは、防共(共産の文字は、米側にはばかって地下工作とす)、駐兵は認めねばならぬぐらいの気分であったか、先方は、だんだんと硬化してきた。
そこで日本は、仏印のサイゴンまで進出したとき、経済断交となった。油が来なくなるとなれば、日本としては大問題である。
このころ、近衛首相は大決心をもってルーズベルト大統領との会見を申し込んだ。
当時、チャーチルと大西洋で艦上会談をやり、大酉洋憲章を作成して帰ってきたばかりのルーズベルトは、即刻八月十七日(月)に私を呼んで警告をなし、近衛との会見には、大なる色気を示した。
しかし、予備会議で成案を得てから、両者会見では批准をすることを申し出て、交渉は頓挫(とんざ)をきたした』 |

近衛文麿首相。ルーズペルトとの
会見を望んだが果たせなかった。
|
(4)日米交渉決裂(昭和十六年十一月~十二月)
『そのころ、私も会談が行きづまれば、しばらく中止し、私は帰朝を命ぜられてよかろうと、いちじは考えた。
私は、元駐日米国大使だった米人の友人を訪問して(この人は日米戦うべからずとの信者であったが)、私は、いちじ話を中止して、世界の形勢をも見つつ、若干のときをへてから、話を再開するのも、一方法であろう。
米国は民主国であるから、突然日本にたいしては戦争はしない。
日本もまた、米国にたいし戦争をはじめないと思う、と私はかたった。
戦後に、同氏より、「あの君の言葉は忘れない」と申して来た手紙があります。
しかし、十二月七日(米国時間)に、ついに戦争がはじまった。
当日、私は、午後一時に国務長官に、最後的公文を交付すべく命ぜられた。
電文の翻訳、タイプ清書がおくれ、国務省に到着したのが、午後一時四十分であり、ハル長官に会ったのは、午後二時二十分であった。
ハル氏は当時、すでに真珠湾攻撃の実情を知っていて、また私の持参した公文をすでに傍受、暗号解読していたらしい。
私は、その公文をよく読むひまもなく持参したくらいで、真珠湾攻撃はまだ知らなかった。
ハルの著者には、「野村は泰然自若としていた」と書いてあり、その後に、当時の心境を、私に問い合わせにきた新聞記者もあった。
いま私は、日米親善が、太平洋の平和を保ち、日本の経済発展に、もっとも重要な基盤であると確信している。
中立政策などは、過去の経験に学んでも、絶対にとり得ざるものと信ずる』 |
また、日米交渉の当時、野村大使の下で一等書記官として勤めていた私の旧友の奥村勝蔵君(戦後に外務次官、スイス大使を歴任す)は、昭和三十九年五月八日に、八十七歳で死去した野村老の追悼文の一節で、つぎのように述べていた。
これもかくれた史実の断片だ。
『野村さんが、近衛内閣から、駐米大使の話をはじめて持ちかけられたのは昭和十五年の夏である。
松岡外相は、文字どおり三顧の礼をつくしたが、野村さんは、頑強に断わりつづけた。
当時の政府の方針の下では、日米交渉はできない、とみていたからだ。
ところがある日、まったく突然、これを引受けてしまった。
「陛下に御心配をおかけするようなことになっては……」
という声が耳にはいったからである。日本海海戦に初陣を飾った海軍大将である。
まさかの時には、勝敗にかまわず、戦(いくさ)に出ねばならなかったのだ』
2 米英討つべしの徳富蘇峰(とくとみそほう)
top
戦前と戦時をつうじて、軍国日本の国家主義的な言論の大指導者として、きわめて大きな勢力を張り、また多数の論策で国民大衆をあおりたてて、いわゆる、『米英撃滅』とか、『一億総決起』へ拍車をかけていたのは、言論報国会会長徳富蘇峰翁であった。
彼は、明治、大正、昭和の三代にわたる言論人の最長老であり、その烈々たる皇室中心主義と大東亜政策は、まことに軍国調の強烈なものだった。
そして、国家主義陣営の大御所として名声を高めていた。
近衛内閣が、昭和十六年一月、海軍部内の米国通として知られる野村吉三郎大将を駐米大使に起用して特派したころには、すでに徳富翁の『米英討つべし』という熱弁が、日本全国にこだまするようにひびきわたっていて、もはや、時期おくれの感じさえある日米交渉の前途には、その第一歩から、すでに暗い影がただよっていた。
では、米英排撃をめざした、当時の国家主義思想と論策とは、いったいどのようなものであったか?
その見本として蘇峰翁の、いわゆる、『憂国の大文字』を、つぎに紹介しよう。
これは、今日の若い世代の人々には、まったく理解しがたい奇怪千万な印象をあたえることだろう。
*
敗北思想――
『およそ、必勝にもっとも大切なるは、戦闘意志の熾烈(しれつ)なることである。
戦争においては、いかなる場合においても、もっとも避くべきことは生(なま)ぬるいことである。
ことに戦闘に対する生ぬるい根性は、一膜を隔てたる敗北思想にほかならない。
世の中には、いずれ遠からず講和の時節も来るであろう。
その場合には米英とも握手せねばならぬ。
その時節到来をいまから準備して、必要もなきに彼らの感情を刺激するやら、彼らをして、わが国に対して怨恨を抱かしむることは、なるべく控え目にするがよしという者があるが、語を換えて言えば、どうせ喧嘩の仲直りをするから、叩くにもなるべく怪我をさせぬごとく叩けという話であって、すなわち、これは品を変えたる立派な敗北思想と言わねばならぬ。
元来、米英のわれに対する敵意は、我らが想像するほどなまやさしきものではない。
彼らは、病院船と知りつつ、ことさらこれに向かって魚雷を発し、爆弾を落としたではないか。
彼らはなんら戦争にゆかりのなき、わが在留国民をあたかも敵国の捕虜同様、いな、それ以上に残酷に取り扱い、ほとんどわが同胞をして死に至らしめんとし、しかも死する以上の苦痛を舐(な)めしめたではないか。
現に米日親善使節と標榜して、わが国に在留したるクルー(開戦前まで日本に十年間駐在していたジョセフ・Cクルー米国大使)のごときも、いまは抗敵思想、抗日思想の宣揚を御用第一として、全国を行脚しつつ宣伝して回っているではないか。 クルー曰(いわ)く、
「強大なる敵日本を打倒するには、ただ日本の軍事力のみでなく、歴史的なる日本人の民族的精神と伝統を抹殺するところまで行かねばならぬ」と。
また曰く、
「我らは日本の軍隊さえ殲滅すれば、日本の脅威を除去し得るがごとく速断すべきものではない。
日本の脅威の抜本的除去は、日本の軍隊を絶滅したる上、歴史的なる日本の精神、伝統まで抉(えぐ)り出してしまわぬうちは、日本に勝つたということはできない」と。
これは、クルー一人の意見ではない。ルーズベルトが日本人を世界より葬り去れと言ったことは、かならずしも、単に大言壮語とのみみなすべきではない。
彼らはまさしくあくまで日本を憎んでいる。また恐れている。
かかる場合において、我らが彼らにたいして、何を酬ゆべきかということは多言を要しない。
我らは我らの生存を擁護するために、我らを滅絶せんとする敵に向かって、一大打撃を加うるは、これは我らの祖国と祖先とに対する一大任務である』 (以下省略) |
自由主義の一掃――
『わが国においては、共産主義か猛獣毒蛇よりも憎むべきことをみな知っている。
しかし、自由主義がさらに恐るべきものであることには、ほとんど注意する者は少ない。
されど自由主義はお玉杓子(たまじゃくし)のごとく、共産主義は蛙のごときものである。
自由主義は毛虫のごとく、共産主義は蝶のごときものである。
おおむね共産主義は自由主義が行き詰まったところに出できたるものであって、自由主義を歩行する者が、その関門に行き当たり、その一関を排しきたるところに、共産主義は出できたるものである。
されば共産主義を杜絶せんとせば、まず自由主義に警戒を加えねばならぬ。
わが国が共産主義のもっとも流行したるときは、他方において自由主義のもっとも流行したるときであった。
明治末期より大正の上期を回想すれば、我らはじつに、今日でも戦慄を禁ずるあたわざるものがある。
我らは単に東亜よりアングロ・サクソン人を退却せしむるばかりでなく、アングロ・サクソン人が植えつけたる自由主義を一掃せねばならぬ。
自由主義、すなわち、アングロ・サクソン思想である。この思想が存在する間は久しからずして、再びアングロ・サクソン人が頭首をもたげきたることは疑いを容れない。
王陽明(一四七二年~一五二八年、支那の明代の有名な儒者、役の知行合一の説は陽明学としてわが国にも栄え、中江藤樹、熊沢蕃山などを出した)は、
「山中の賊を破るは易く、心中の賊を破るは難し」
と言うたが、敵の軍隊や飛行機や、戦車や魚雷やは、みなこれ山中の賊である。
しかも自由主義は、すなわち心中の賊である。
この賊を退治せざる以上は、東亜は決して新秩序を樹立することは出来ない』(徳富蘇峰著『必勝国民読本』、昭和十九年二月、毎日新聞社刊より引用) |
3 日本人とドイツ人 top
これが、いわゆる決戦下の、軍国日本の国民思想の中核をなす考え方であったが、このような偏狭、独善、狂気のような皇国イデオロギーは、すでに、満州事変から日中戦争(支那事変)にかけて、軍国日本の新聞、言論界を、強大な軍部の圧力を利用して、しめつけるように、刻々と圧倒しつつあったのだ。
戦後の自由、民主主義の今日から回想すると、これは、まことに奇怪な、軍国主義的な思想の悪夢というほかない。
だが、戦時中は、日本中の新聞も、雑誌も、すべてこのような決戦思想と、聖戦史観で埋めつくされて、『一死報国』とか、『一億玉砕』とかいった、人間性をまったく無視した、神がかりの超国家主義が、日本国民大衆を、まるでガンジガラメに重苦しく押さえつけていたのである。
結局、軍国日本は、武力戦にも完全に敗れたが、思想戦にもまた見苦しく敗れ去り、いわば百八十度の思想転換と、完全な西欧デモクラシーによる洗脳を行なったわけだ。
このような敗戦の重大な結果を、いったい開戦前に、日本政府と軍首脳部の中で、だれが、はたして予想したであろうか?
ここに、結果論ではあるが、太平洋戦争の奇妙な誤算と、大義名分上の深刻な矛盾があることを忘れてはならない。
我々日本人にとっては、忌まわしい敗戦の結果をもたらした太平洋戦争の正体と真相を、このような武力戦と並行した思想戦の観点から再検討することは(これまであまりに黙殺されてきただけに)、大いに意義があると信ずる。
`西ドイツでは、老練なジャーナリストのヘルマン・アイヒの著書『気味の悪いドイツ人』が大評判になったが、これは『愛されないドイツ人』と題した英語版まで出て、欧米で大論争をまぎ起こした。
それは、二回の敗戦をなめたドイツ人がいっこうに、精神も根性も考え方も変わっていない点を強調した、自己反省と弁解の本であり、
『我々ドイツ人は神を恐れるが、それ以外は世界中でなにも恐れるものなし』
と、国会で豪語したプロシアの鉄血宰相ビスマルクの言葉が、つねにドイツ民族の精神の中に生きていて、それが世界中からドイツ人が嫌われ、憎まれ、孤立している理由である――と説いている。
これに反して、我々日本人の場合は、ただ一回の敗戦の結果、しかも同一の天皇制が、形式を変えて残ったのに、幸か不幸か、日本精神も、国粋主義も、考え方も、あまりに一変し、急変してしまったのは、いったい、どういうわけなのであろうか?
皮肉にも、そのせいか、戦前にあれほど好戦国民として憎まれた日本人が、いまや世界中から『愛される日本人』として、大歓迎をうけている。
そして、米英の代表的新聞は、こぞって今日の民主日本における平和愛好と、反戦感情の強さに驚いているようだ。
敗戦によって、魂から思想まで、すっかり一変したらしい日本人と、敗戦によって精神も根性もいっこうに変わらないドイツ人と、はたしてどちらが幸福なのであろうか?
4 天皇制は衣がえして残った top
世界の注目を集めた東京裁判の判決が終った昭和二十三年十一月、大任を果たした裁判長ウイリアム・ウェップ卿(オーストラリア代表判事)は、つぎのような感想を、内外の新聞記者団にもらした。
それは、彼が豪州人であるという立場から、米、英、ソ三大国の圧力に、かならずしも左右されないで、独自の厳正公平な発言をすることができたからである。
日本占領行政の政策的目的から、天皇擁護を強調した米国側と対立した彼の、いわゆる少数意見は、終戦直後の天皇制存廃にかんする、内外の悪夢のような世論を反映するものとして、忘れてはなるまい。
『天皇の権威は、天皇が戦争を終結したとき、疑問の余地のないまでに立証された。
それと同じように開戦にあたって天皇の演じた顕著な役割が、検察側から指摘されたが、それと同時に検察側は、天皇を起訴しないことを明らかにしたのである。
私は天皇が開戦にさいして果たした役割にもかかわらず、その裁判を免除されたという事実は、本裁判の被告らの刑を決するにあたって、当然に考慮されなければならないと思う。
天皇が平和を望んだという証拠はあるが、立憲君主制下の日本の元首として、天皇は、政府、その他からの好戦的勧告を、自己の意思に反してかも知れないが、とにかく受入れたのである。
戦争開始には、天皇の権威が必要であり、もし天皇が、戦争を欲しなかったのであるならば、天皇は当然、その権威を保留すべきであった。
天皇がつねに、周囲の進言にもとづいて行動しなければならなかった、という意見は証拠に反するが、またかりにそうだとしても、天皇の責任を軽減するものではない。
私は、天皇が処刑されるべきであったというのではない。これは私の管轄外である。
天皇が裁判を免除されたことは、疑いもなく、すべての連合国の最善の利益にもとづいて決定されたものである』 |
|

東京裁判の裁判長として大任を
果たしたウィリアム・ウェッブ卿。
|
いっぽう、マッカーサー元帥の極秘の命令により、天皇の戦争免責、無罪論について、東京裁判の法廷で最大の努力をつづけて成功した米国側主席検察官マ元帥の最高法律顧問キーナン検事は、この判決をめぐるウェップ裁判長の談話にたいして、
『ウェップ裁判長は、天皇が、かならず補佐者の意見を受入れなければならなかった、ということについては証拠不十分だと思っているが、天皇が平和論者であったことは、証拠によって証明されている。
その事実に、ウェップ裁判長は触れていない。
もし検察側が責任ありと考えたならば、天皇は被告席に座っていたであろう』 |
と、ただちに強い語調で反駁したものだ。
また、キーナン検事は、その歴史的な任務を首尾よく遂行して帰米する直前に、東京裁判の最大のヤマであり、世界注目の最大焦点であった天皇問題について重要談話を発表したが、それによると、つぎのような新しい事実が確認されて、その当時、大きな反響をまきおこした。
(一) 天皇制廃止を主張したソ連のスターリン首相も、結局、天皇不起訴に同意した。
(二) 最初、キーナン検事は、天皇を証人として、東京裁判法廷に召喚するつもりであった。
(三) もし天皇自身が法廷に召喚されれば、天皇にとって有利な証拠をまったく無視して、自分一人で全責任を負う決心である、とマッカーサー元帥に天皇が告げていた。
(マ元帥は、この天皇の言葉を重視して、天皇の不起訴はもちろん、不召喚をもひそかに指示したらしい) |
この赤ら顔のデップリ肥ったキーナン検事は、日本占領中の米軍の威光をカサにきた首席検察官として時めいて、傲慢な態度を示していたので、一般に日本では、あまり評判がよくなかったようであるが、ただ天皇制支持の一点だけは、日米両国のために彼の大手柄であったようだ。
彼は帰米直前に、宮中方面といわゆる生残りの重臣たちから、ひそかに深甚な感謝の意を示達されたそうであるが、彼の発表した談話の要旨は、つぎの通りであった。
それは、『かくて天皇は退位もせずに居残った』という感慨が深いものだった。
『――天皇は、東条英機とともに戦犯容疑者として裁かれなかった。
これは、戦勝諸国が政治的理由から、天皇に免罪の特典をあたえることに意見の一致をみたからである。
証拠の点からみても、天皇を起訴する理由はなかった。
しかし、天皇を裁判から除外したのは、連合国の政治的決定であって、この点については、ソ連のスターリン首相も、しぶしぶながら同意をあたえた。
この決定は、政治的であり、検察当局のあずかり知るところではなかったが、いずれにせよ、私は首席検察官として、天皇を戦犯として起訴するだけの証拠はないと考えた。
証拠の示すところによれば、天皇は、我々西欧的な考え方からすれば意志の弱い人物であった。
しかし、天皇が終始、平和を望んでいたということは、はっきり証明されている。
私個人としては、天皇自身の立場を説明するだけでもよいから、証人として出廷させたい、と思っていた。
しかし、日本と同じように国王を戴く英国側から、そういうことは忍び難いとの反対があった。
マ元帥の考えも、どちらかといえば、この英国の見解に近いものであったが、おそらくこれには、占領行政上の考慮があったものと思う。
マ元帥が、私に語ったところによれば、もし天皇が証人として出廷させられたならば、天皇自身は、我々が証拠によって見出した、彼にとって有利な事実をすべて無視し、日本政府のとった行動について、みずから全責任を引受ける決心があったという。
すなわち、証拠によって天皇は立憲国の元首であり、法律上また職責上、かならず側近者の補佐にもとづいて行動しなければならなかったことが証明されているが、それにもかかわらず天皇は、もし出廷させられたとしたら、このようなことを自己の弁解に用いるようなことは一切しなかったであろう』 |
5 無条件降伏方式の大失敗
top
結局、軍国日本は太平洋戦争に敗北して、米英はじめ連合国側に無条件降伏をしたが、幸運にも連合国の主勢力たる米国側の政治的理由――とくに天皇の日本国民にたいする権威を、巧みに利用する占領行政の便宜上から、絶対天皇制は、いわゆる『位(くらい)すれども治(おさ)めず』とする民主的な象徴天皇制と衣がえをして戦後に残ったわけである。
もしも米英側で、天皇制(いかなる形式にせよ)の存続を暗黙に認めて日本軍の降伏を要求していたならば、おそらく太平洋戦争は、広島、長崎両市への非人道的な原爆攻撃の大惨害をもたらす一年前(昭和十九年七月十八日、サイパン島失陥の責任を負い東条内閣が総辞職した時間をさす)か、おそくもレイテ大海戦(昭和十九年十月二十三日~二十六日)で、わが連合艦隊が壮烈に全滅した直後か、あるいは沖繩大決戦(昭和二十年四月一日~六月二十一日)の終了までに、降伏交渉は成立したことであろう。
そうすれば、人命をあまりに軽視した特攻隊の悲劇も、B29による日本本土の残酷な焦土化もみないで、和平が実現したであろう。
現在、米英の歴史家の間でも、ルーズベルトが、まず提唱して、チャーチルがこれに同調した、いわゆる『無条件降伏方式』の大戦略が、いかにドイツ国内の大規模な反ナチス抵抗運動(とくに一九四四年七月二十日の軍・民協力のヒトラー暗殺陰謀事件以後)を失望させて、無用の流血、抗戦をさらに、一年間も続行させたかについて反省、再検討を余儀なくされている。
軍国日本の無用の抗戦も、やはり天皇制日本の打倒をめざした『カイロ宣言』(一九四三年十一月二十七日、カイロでルーズベルト、チャーチル、蒋介石が署名、声明す)がわざわいして、天皇制護持のみを、絶対の悲願として叫んだ狂信的な日本軍を徹底抗戦へと、ムリに追いつめて、日本軍にも日本国民にも、連合軍と同じように、莫大な犠牲者を続出させたわけだ。
要するに、太平洋戦争にかぎらず、すべて戦争というものは、昔も今も、つねに開戦から終戦まで、敵味方ともに、誤算と矛盾の連続というべきであろう。
いま、日米開戦の真相を追い、その内幕をさぐりながら、私は、公正で自由な戦史家として、やはり、この平凡な戦争の教訓をみとめないわけにはいかないのだ。
確かに、軍国日本には、軍部の独善、独走をたしなめたり、抑制する勇気と実力と遠大な見識を備えた大政治家が、まったく欠けていたけれども、米、英、ソ三大国の三巨頭――ルーズベルトも、チャーチルもスターリンも、太平洋戦争をふくめた第二次大戦の遂行と処理については、やはり、後世の史家に、その真価を問われるような誤算とヘマをおかしていた。
すなわち記録によれば、ルーズベルト大統領は、悪名高いヤルタ会談より帰米後まもなく、一九四五年(昭和二十年)四月十二日に急逝(当時六十三歳)する直前に、すでにソ連の独走によるヤルタ協定無視と冷戦の兆(きざし)を認めて心痛し、スターリンの不信を責める覚悟を、ひそかにかためていた模様である。
また、第二次大戦の前半期に、孤軍奮闘中の英国の重大危機を奇蹟的に救った英雄的政治家チャーチルでさえも、この大戦こそ『不必要な戦争である』といみじくも喝破したのみならず、戦後の冷戦をむかえていち早く、『我々は戦争には勝ったが、平和に破れた』と長嘆息したものだ。
またソ連では、『大祖国戦争の勝利の大指導者』として崇拝された独裁者スターリンも、その死後には、忠実な弟子のようなフルシチョフの手で、無残にも偶像の地位から引きずり下ろされて、ソ連大衆の前に、その狂乱した晩年の正体をばくろされる始末――。
まことに、第二次大戦は、太平洋戦争をふくめて、敗戦国の指導者にとっても、勝利国の指導者にとっても、誤算と矛盾にみちた悔い多き戦争であった!
Ⅴ 真珠湾奇襲をめぐる黒い霧 top
1 真珠湾奇襲の意義と再評価
太平洋戦争は真珠湾で始り、東京湾で終ったといわれている。
それは一九四一年(昭和十六年)十二月七日、日曜日(ハワイ時間)の朝七時五十五分、日本海軍の強力な空母機動部隊(指揮官南雲忠一中将、大型空母六隻基幹)が、ハワイの主島であるオアフ島の米太平洋艦隊基地、真珠湾軍港を、突然、大奇襲攻撃して太平洋戦争の火ぶたをきり、それから血戦死闘をかさねること三年八ヵ月後の一九四五年(昭和二十年)九月二日、日曜日(日本時間)の午前九時、東京湾内外に集結した米大艦隊の旗艦『ミズーリ』の甲板上で、日本政府および大本営各代表(重光葵外相と参謀総長梅津美治郎大将)が、連合国軍最高司令官マッカーサー元帥の前で『天皇および政府の命により、かつ天皇および政府の名において』降伏文書に署名して、血みどろな太平洋戦争の幕を閉じたことを意味しているのだ。
おもえば開戦前から、軍国日本が世界一の富強を誇る米英両国を相手に戦っても、勝ち目は、ぜんぜんなかった。
ただ日本の軍部は当時、まったくドロ沼化してぬきさしならぬ最悪状態に陥っていた支那事変(日中戦争)を、武力で打開するただ一つの、死にものぐるいの最後の方策として、いわゆる『米英撃滅』の聖戦へ、天佑神助を念じて突入したわけである。
したがって、それは戦後の結果論から合理的にいえば、まことに無謀きわまる開戦決断ではあった。 |

昭和16年12月8日、日米の和平交渉もむなしく
戦乱の火蓋が切って落とされた。
フォード島から見た燃える真珠湾。
|
しかし、再三にわたる御前会議で、平和念願の天皇自身さえズルズルと戦争への道へ引きずられていったのであるから、軍国日本の悲壮な宿命として、我々国民大衆は、あきらめなければなるまい。
だが、大本営が計画を立て、天皇が正式に裁可した対米、英、蘭戦争の開戦理由が、昭和十六年十二月八日付の詔書の中にいみじくも明示されたとおり、
『東亜安定ニ関スル帝国積年ノ努カハ悉ク水泡ニ帰シ、帝国ノ存立モマタ危殆ニ瀕セリ、
事スデニ此ニ至ル、帝国ハ今ヤ自存自衛ノタメ決然起ッテ一切ノ障害ヲ破砕スルノ外ナキナリ』 |
ということを、一応認めるとしても、はたして戦端を開く手段として、真珠湾奇襲が最善の策であったかどうかについては、当時、大本営の内部にさえ強い異論があったくらいであるから、戦後に米英戦史家の間で、論争の的になったのは当然である。
そして、日本人にとっては、まったく耳の痛い批判だが、有力な歴史家の見解はすべて、真珠湾奇襲が戦術上では、一時的の成功をおさめたとはいえ、戦略上からも、政略上からも、バカげた大失敗であったと、痛烈にコキ下ろしている事実は、けっして負けおしみの結果論として、黙殺することはできないだろう。
もちろん、開戦劈頭の真珠湾奇襲をふくめて太平洋戦争の全貌と、真相の正しい評価ということは、旧交戦各国の異なる国民感情や、国際情勢のめまぐるしい複雑怪奇な変転によって、ますます困難になっているか、さりとて日本人にとっては、『忌わしい負け戦さ』であった太平洋戦争の実相を、もはや忘れたり、あるいは知らないままですましてしまうことは、二百六十万分同胞犠牲者に対しても、申し訳ないことではないか!
その意味から、私は真珠湾奇襲の諸問題を、権威ある内外の最新資料にもとづいて、徹底的に究明して、いまだに世界的論争の的になっている、いわゆる、『真珠湾の黒い霧』の正体をできるだけ明らかにしてみたいと思う。
要するに、実際、太平洋戦争の発端となった真珠湾奇襲こそ、軍国目本の敗北の第一歩であり、また、『ミズーリ号への道』の起点になることを公正に認識するならば、真珠湾奇襲の歴史的意義と功罪と、再評価は太平洋戦史上で、いちばん重大な問題であると信ずる。
私の長年の親友で、太平洋戦争中に米国著名の軍事記者であったロバート・シャーロッド君(太平洋戦記三部作『タラワ』『サイパン』『硫黄島』の著者、米国の雑誌王カーチス出版社副社長)は、真珠湾奇襲の歴史的意義を、米国側の観点から、つぎのように論断しているが、それは、多数の米英歴史家の共通した評価を要約したものとして、注目すべきであろう。
『日本軍の真珠湾攻撃は、歴史上で一国が他国にくわえた、もっとも効果的な痛撃の一つであった。
軍事上から見ると、それは、じつに完全な奇襲であり、まったく赫々(かくかく)たる大成功であった。
しかし、全般的な戦略としては、それは正気のさたではなかった。
すなわち、わずか二時間のうちに、山本五十六元帥(当時、海軍大将)麾下の日本海軍機の数波の編隊は、それまで和戦両論が争い、世論が分裂していたアメリカ合衆国を首尾よく一致団結させてしまった。
そして、全世界の鉄鋼生産の半分を独占する人口一億四千万(当時)の、アメリカ全国民の強烈な戦意と怒りを、日本に対して圧倒的に投げつけさせるにいたった。
かくて軍国日本にとって、太平洋戦争の最悪の錯誤は、じつにこの開戦のときにあったのだ』 |
もちろん、日本人の立場から、このようなドライな真珠湾奇襲論にたいしては、いろいろ異議もあるであろうが、それは、後でゆっくり取り上げて検討することにして、まずつぎに、いわゆる『真珠湾の黒い霧』のナソについて、その主要なものを列挙して、読者のみなさんの研究討議の課題として提供しよう。
どうか、よく考えてみていただきたい。
それについては、これから、じゅんじゅんに追及、検討するつもりである。
(1)戦前からすでに、日本側の暗号電報を自由に傍受、解読して、日本軍の軍事行動を明らかに察知していた米国政府および軍部首脳が、なぜ十二月七日(米国時間、日本では十二月八日に当たる)に、あのように油断して、大惨害をこうむったのであろうか?
(これが米国内の反ルーズベルト派の政治家や軍人や、歴史学者や言論人たちが、戦後にとなえた、“ルーズベルト陰謀説”の論点である)
(2)開戦の前夜――すなわち、米国時間で十二月六日――(土曜日)の夜から翌七日の朝にかけて、米軍首脳のマーシャル陸軍参謀総長と、スターク海軍作戦部長の行動には、わざと日本側の開戦行動にかんする緊急な重要情報を見ないふり、知らぬフリをする不審な点が多かった。それはなぜか?
(それはルーズベルト大統領から、なにか極秘に重大な指示があったような疑惑を起こさせるに足るものだった)
(3)日本政府から、ワシントン駐在の野村吉三郎大使を通じて、開戦直前――正確には真珠湾攻撃実施の三十分前――の十二月七日午後一時に米国政府へ手交すべき『日米交渉打ち切り通告』(事実上の最後通牒)は、なぜ別表の示すように一時間二十分ちおくれて、日本が『だまし討ち』とか『犯罪的攻撃』とか『裏切り奇襲』という屈辱的な汚名を着せられたのであろうか?
(真珠湾奇襲を論ずる場合、日米間の時差と日付変更の点がよく混同され、誤解されやすいので、私は興味ぶかい開戦の歴史的事実にかんする一覧表を作成したから、よく御覧をねがいたい)
|
日本機動部隊のハワイ真珠湾攻撃時刻と日米交渉打ち切り通告提出時刻(予定と実際)比較表 |
|
場所 |
通告予定時 |
攻撃予定時 |
実際の通告時 |
実際の攻撃時 |
| ワシントン |
1941年〔昭和16年〕
12月7日、日曜日午後1時(米国東部標準時) |
12月7日午後1時30分
(同 左) |
12月7日午後2時20分
(同 左) |
12月7日1時25分
(同 左) |
| ホノルル(ハワイ) |
12月7日午前7時30分
(ハワイ時間) |
12月7日午前8時
(同 左) |
12月7日午前8時50分
(同 左) |
12月7日午前7時55分
(同 左) |
| 東 京 |
12月8日月曜日午前3時 (日本時間) |
12月8日午前3時30分
(同 左) |
12月8日午前4時20分
(同 左) |
12月8日午前3時25分
(同 左) |
2 戦史家モリソン博士の正論
top
|
真珠湾攻撃でのアメリカの人的損失 |
〈備考〉この真珠湾攻撃による米軍死傷者の内訳、数字は戦後の一九四七年に米海軍省医務局が補正発表したも
のであり、また、同年に米陸軍参謀本部次長事務局報告によるものであるが、戦時中の発表数字よりだいぶ減少している。その後、一九五五年に刊行された米海軍省戦史部編『第二次大戦アメリカ海軍年表』によると、戦死=(海軍)二、〇〇四名(海兵隊) 一〇八名(陸軍)二二二名、戦傷=(海軍)九二一名(海兵隊)七五名(陸軍)三六〇名と多少の増減を記録している。 |
| |
戦死、行方不明、
戦傷死 |
戦 傷 |
|
海 軍
海兵隊
陸 軍
一般市民 |
2,008
109
218
68 |
710
69
364
35 |
|
合 計 |
2,403 |
1,178 |
米国の歴史学者で、ベストセラーの名著『オックスフォード版アメリカ国民史』その他、数十冊の一般歴史書と、米海軍省の準公刊戦史とみなされる『第二次大戦におけるアメリカ海軍作戦史』(全十五巻)の編著者として、世界的名声の高い戦史家サミュエル・E・モリソン博士(退役米海軍少将、ハーバード大学名誉教授)は、開戦直後にハーバード大学時代より親交のあった故ルーズベルト大統領へ進言して、厖大な『海軍作戦史』の編修計画を立てて、その全責任を引受けただけに、ルーズベルト支持派であることは当然である。
モリソン博士はさすがに、古今東西の歴史に精通した大歴史家にふさもしく、太平洋戦争の背景と原因を精密に調査、検討した結果、米国側にいくつも誤算と油断があった事実をみとめながらも、真珠湾奇襲はあくまで、日本側の一方的な『だまし討ち』であったと、つぎのような結論を下した。
『――朝の十時には、戦い(真珠湾攻撃をさす)はすでに終っていた。
いちばんしんがりの敵機群は、オアフ島(ハワイ群島の主島、首府ホノルルと真珠湾軍港がある)北部の上空で集合してその母艦ヘそれぞれ帰航した。近代史上で、戦争が一方の側による、かくも殲滅的な勝利によって開始されたことは、いまだかってなかった。
そしてまた人類史上で、緒戦の勝利者が、その計画しただまし討ち払たいして、最終局に、かくも高価な代償(日本の惨敗、本土荒廃、海外の全領土喪失、無条件降伏をさす)を支払ったことも決してなかった。
しかし、日本軍の飛行機パイロットたちが、はたして、正しい攻撃目標にたいしてむけられたかどうかは、日本側の観点より見てさえも、相当に議論の余地がある。
すなわち、彼らは、米艦隊の戦艦部隊を撃滅し、所在の機動航空兵力を抹殺したが、真珠湾軍港の恒久的な諸施設(海軍工廠、大ドック、燃料貯蔵地区をさす)を無視した。
そのなかには、あまり甚大な損害をこうむらなかった諸艦艇の修理のために、おどろくほど迅速な作業をすることができる修理工場もふくまれていた。
さらに彼らは、動力施設や容量一杯に充満していた、莫大な液体燃料用の「油槽地帯」を、攻撃することさえしなかった。
これは、当時の米アジア艦隊司令長官トーマス・H・パート海軍大将の意見にもあるように、もしそれを損失したならば、米太平洋艦隊のこうむった損害より以上に、米軍の太平洋反攻を遅延させたであろう。
かくてアメリカ合衆国海軍は、このただ一回のだまし討ちで、それ以前の二つの戦争、すなわち米西戦争と第一次世界大戦において、対敵戦闘のために失った兵員の約三倍を、わずか二時間でいっきょに喪失したのである。
真珠湾攻撃による米軍、および一般市民の死傷者は、右表の通りであった』 |
また、モリソン博士は、『アメリカ陸、海、空軍が真珠湾で不意打ちをくわされたのは一体、だれの責任であるか?』
という重大な問題について、一九四八年に、すでに戦史家の厳正な立場から、つぎのように述べている点は注目されるだろう。
『真珠湾問題を考究するものは、だれでも一定の基本的要因に留意せねばならない。
まず第一に、航空母艦による航空攻撃は、あらゆる形式の攻撃中で、もっとも予知するのが困難なものである。
なぜなら、たとえ大艦隊といえども、広大な大洋上では、はなはだ小さい一つの点にすぎないものであるからだ。
米海軍の空母部隊は、第二次大戦中に、しばしば奇襲の成功をみることができた。
たとえば、ハルゼー=ド・リットル東京空襲(昭和十七年四月十八日)は、その空母部隊が日本本土に近い洋上で日本海軍の監視艇に発見、通報されていながら、日本軍当局にとってはまったく奇襲であった。
また、ハルゼー、ブラウン、シャーマン、ポウノール諸提督は、開戦後の二年間に、日本軍占領下の島々にたいして、相ついで奇襲を敢行した。
さらに大戦後半の一九四四年(昭和十九年)から一九四五年にわたる間、ハルゼー提督(当時、米第三艦隊司令官)の沖縄、フィリピン、仏領インドシナ各地にたいするめざましい大空襲は、だんぜん、その不意打ちに成功した。
また、一九四四年十月、ルソン島沖でミッチャー提督の指揮する米空母機動部隊と、小沢治三郎中将の指揮した日本空母機動部隊より、それぞれ発進した偵察機群は、朝から晩まで互いに必死で索敵飛行を続行しながら、ついに何物も発見することができなかった。
したがって、アメリカ太平洋艦隊か、宣戦布告もなければ、また、外交関係の断絶さえもなくて、まったく対敵状態にはなかった時点にあって、日本軍のハワイ攻撃機動部隊の接近を探知しなかったことは、別に驚くには当たらないのである。
しかしながら、アメリカ太平洋艦隊は、その可能性にたいしては、準備をすべきであったろう。
この準備を怠ったことこそ、責任を査問する要点である』 |
要するに、モリソン博士の論点は、戦時中でも、航空母艦(複数)を基幹とした、高速機動部隊による神出鬼没のような、洋上からの航空攻撃は、一般的に予知、警戒が困難であり、いわゆる敵の奇襲を防ぐことが容易ではない。
いわんや、ワシントンで、日米会談がまだ続行している時点では、真珠湾奇襲のような、『だまし討ち』を、到底予想することは、至難である。ただ万一の可能性に対処することは当然であったから、米軍側に誤算と油断の責任はあるが、しかし、ルーズベルト大統領が、日本軍の奇襲を挑発、予知していたという陰謀説はナンセンスである――というわけである。
3 事実は小説よりも奇なり top
戦史家モリソン博士は、真珠湾奇襲をめぐる米国政府と軍部の、意外な誤算と、油断の諸事実をつぎのように、いろいろ指摘しているが、それは、まったく古い表現ではあるが、『事実は小説よりも奇なり』と、いうほかはない。
それは、まことにウソのような話ではあるが、開戦直前までルーズベルト大統領以下、政府と軍部首脳は、もちろん、ハワイ現地の陸海軍責任者までか、日本の戦力を過小評価して、南方侵略をめざす日本軍にはハワイ攻撃の余力は到底ない、と独善的に判断していたのだ。
しかも半年前には、ハワイ奇襲の恐怖感が一部にはまだ残っていたが、ワシントンの日米交渉がいよいよ行きづまって、日米対決の危機がついに深刻化した秋ごろには、かえってハワイの安全感が高まり、
『日本軍はタイ国、マレー、シンガポール、フィリピン、蘭領東インド方面へ進攻する恐れがあるから、とてもハワイへ攻めてくることはできない』
という考え方が、支配的になったのは、じつに不思議な心理作用であった。
(1)開戦の年、すなわち一九四一年(昭和十六年)の前半の八ヵ月間には、ワシントンとハワイの米陸、海軍統帥部は真珠湾にたいする、敵の航空攻撃の危険について、多大の関心をはらっていたが、その年の八月以後は、この可能性が、最高責任の地位にあったすべての軍人、または文官の頭の中から、うすらいでしまったようにみえた。
このことは、米陸、海軍を通じて最優秀の知謀者の一人であった、海軍諜報部長ウィルキンソン少将さえも、それに同調していたことを自認していた。
すなわち、日米対決の危機が増大するにつれて、意外にもハワイの危機はうすらぎ、忘れられていったのだ。
(2)米海軍作戦部長ハロルド・スターク大将は、同年四月一日付で、全海軍管区司令官にたいして、とくに各週末(土曜日、日曜日)の時期には、敵襲にたいする警戒を厳重にすべきことを警告した。
また、ノックス海軍長官とスチムソン陸軍長官も、ワシントンにいるマーシャル陸軍参謀総長とスターク海軍作戦部長も、ハワイにいるショート陸軍中将とキンメル海軍大将にたいして、それぞれ、たびたび通信連絡が交わされて、
『真珠湾をめぐる敵の航空攻撃の危険にかんして起こる可能性』のある、すべての様相を詳細に検討していた。
(3)ハワイ駐屯の米陸軍航空部隊司令官マーチン准将と、米海軍航空部隊司令官ベリンジャー少将の両人は、同年三月三十一日付で、陸海軍合同機密報告をして、そのなかで、
『オアフ島にたいするもっとも起こりそうな、そして、もっとも危険な攻撃形式は、航空母艦より発進した航空攻撃であろう』
と述べたうえ、さらに、
『もしそこで、夜明け時に発進したならば、完全な奇襲をこうむる公算が多い』と指摘した。
かくて、八月二十日には、マーチン准将は、ショート陸軍司令官にたいして、
『日本軍の航空母艦部隊が、もっともオアフ島に接近してくる公算の多いのは北西方からであろう』と進言した。
(4)同年の五月二十六日に発令された米海軍基本戦争計画(戦争計画第四十六号、または「レインボー」第五号と呼ばれた)は、真珠湾軍港内の米艦隊にたいする奇襲攻撃の公算を、明白に予見していた。
また、キンメル大将が七月二十一日付で布告した、太平洋艦隊自身の作戦計画では、敵の開戦劈頭の行動は、
『おそらく、ウェーク島、ミッドウェー島、またはその他の米国外辺の領土にたいする空襲あるいは直接攻撃』となるだろうと述べていた。
(5)だが、これらのあらゆる適切な判断と、決心と警告にもかかわらず、危機感は同年八月以降には、責任の地位にある陸、海軍軍人の胸中から消え去ったように思われた。
『私個人としては、まさか、日本軍が思い切ってわが方に攻撃をくわえてこようとは信じられない』と、スターク海軍作戦部長みずからが、十月十七日付で、ハワイの太平洋艦隊司令長官キンメル大将あてに、手紙を書き送っていた。
(6)また、キンメル司令長官の幕僚の戦争計画主務参謀マックモリス大佐は、十二月最初の三日間に開かれた作戦会議の席上で、
『真珠湾に対する空中からの攻撃は決してないであろう』とキンメル海軍大将とショート陸軍中将に告げた。
(7)要するに、『根本的な災厄は、日本軍がいったい、なにをなすことができるか、また、なにをなそうとしていたかについて、わが海軍が正しく評価することに失敗したことであった』と、戦後に米海軍作戦部長アーネスト・キング元帥が語ったのが、真珠湾奇襲の一面の真相であろう。
また開戦前に、日本軍が同時に二つ以上の大海軍作戦、もしくは水陸両用作戦を敢行することができると信じた米海軍士官は、ほとんどいなかった。
また、同年四月の米、英、蘭三ヵ国軍事会議で米海軍のパーネル大佐とともに、その公算を検討した英国と、オランダの両海軍士官たちも同じように、日本海軍の多正面作戦の能力を信じたものはいなかった。
(8)キンメル司令長官の幕僚の戦争計画次席参謀マーフィー大佐は、戦時中の一九四四年(昭和十九年)に非公開でひそかに開かれたパート査問委員会(開戦当時の米アジア艦隊司令長官パート大将を委員長とした真珠湾攻撃に関する海軍軍法会議に相当するもの)で、『不意打ちの航空攻撃』にかんして、つぎのように供述したが、それは真珠湾奇襲にたいするハワイ現地の米海軍幕僚の真実の声であったろう。
『私は、かくのごとき攻撃が行なわれようとは、夢にも思いませんでした。
私は日本軍にとって、真珠湾において米軍を攻撃するのはぜんぜん、バカげたことであろうと、考えていました。
私は日本軍が、おそらくタイ国とマレー半島へ、さらに、ことによったら蘭領東インド(蘭印=現在のインドネシア)の進攻は可能であると考えていました。
しかし、日本軍が、真珠湾を攻撃しようとは思いませんでした。
なぜなら私は、自分の見解にもとづいて、日本軍がそうすることの必要があるとは考えなかったからです……。
我々は、補助艦艇の増強、各艦船の施設、とくに高射砲の改善など、米太平洋艦隊が具体的に強化される時期までは、日本艦隊と対決するために西太平洋に出動することができるとは信じていませんでした。
私は、我々が劣勢な艦隊をもって西太平洋に出動せんと企てることは、自殺行為であろうと考えていました』
(9)一方、アメリカ国務省では、日本政府の部内には米国を怒らせて米国民を団結させ、日米戦争に導くような、無制限の侵略行為を回避するのに十分な、政治的才覚があるものと想像していた。 |
4 ハルゼー元帥の真珠湾批判 top
太平洋戦争を通じて、米海軍で『猛牛』の勇名をとどろかせたウィリアム・F・ハルゼー海軍元帥は、開戦当時は米太平洋艦隊司令官キンメル大将の部下で、空母機動部隊の指揮官(第三艦隊司令官)として海軍中将の地位にあった。
したがって、開戦直前の太平洋艦隊の動向と、ハワイ方面の配備、警戒状況については有力な現地の証言者である。
その彼は、真珠湾奇襲の全責任をハワイ方面の米海、陸軍両最高司令官、すなわちキンメル元海軍大将とショート元陸軍中将のみに負わせることは不当であるとして、つぎのように正々堂々と主張していることは注目される。
ただし、彼のこの発言は、戦後の一九五三年九月に、キンメル元太平洋艦隊司令長官を弁護して、故ルーズベルト大統領の戦争挑発政策をはげしく非難攻撃した、ロバート・シオボールド海軍少将の論争の書『真珠湾の審判』(中野五郎訳、昭和二十九年、講談社刊)の序文として寄せられたものであって、やはり戦時中は、硬骨漢の彼も、米国の世論統一と国家安全保障のために、沈黙をよぎなくされていたのだ。
したがって、言論の自由の米国でも戦時中には、いわゆる『国賊』とか『卑怯者』の汚名をきせられて、まったく発言の自由を抑圧され、黙々とくらしていた当時の旧上官キンメル元大将のために、彼が職を賭して正論を吐いたわけではない。 |

開戦前の米太平洋艦隊の配備、
警戒状況の証言者・ハルゼー元帥
|
結局、程度の大差こそあれ、『自由の国』を誇る米国でさえも、戦時中は、軍国日本と同様に政府の戦争政策や、真珠湾惨敗の責任を批判することは禁止されていたわけだ。
『あの当時、私はアメリカ太平洋艦隊の三人の上級司令官の中の一人として、キンメル司令長官の麾下にぞくしていた。
私は、彼が入手したあらゆる情報をつねに欠かさず、私に知らせていてくれたものと、今日でも信じている。
それにもかかわらず、あの適切な「魔法(マジック)情報」(ワシントンの米軍首脳部が傍受解読していた日本の外交暗号電報の隠語呼称)は一通たりとも、確かに私は、読んだおぼえがないのだ。
我々が入手していた軍事諜報はすべて、日本軍び攻撃がフィリピンか、マレーまたは蘭印など、南方地域へ指向されることを、明示したものばかりであった。
なるほど真珠湾が日本軍の攻撃目標になるかも知れないということは一応、考慮されていて、けっして度外視されたわけではなかったけれども、我々の入手できた、たくさんの証拠はみんな、真珠湾以外の方向に攻撃の公算が多いことを指摘していたのである。
もし我々が、「魔法情報」の中ではっきりと示されていた通り、日本が真珠湾内の米国艦隊の正確な位置と行動をつかむために、いかにたんねんな調査をつづけていたかを知っていたならば、真珠湾攻撃の現実的な確実性にそなえて、我々の全神経をこれに集中して対処していただろう、ということは火を見るよりも明らかである。
そうすれば、私の指揮下の機動部隊を開戦直前の十一月下旬から十二月初旬にかけて、ウェーク島へ軍用機輸送のために出動させることには、私は極力、反対したことであろう。
いやむしろ私は、そんな反対こそ、まったく不必要だったろうと確信している。
なぜなら、もしもキンメル元大将が、当時、この情報を入手していたならば、あのような艦隊行動を命ずるはずがなかったからだ。
当時、私の艦隊は航空母艦「エンタープライズ」を旗艦としていた。
これは、その当時に太平洋方面に就役中の、米空母二隻中の一隻であった。
他の一隻は、「レキシントン」で、ニュートン海軍少将の指揮下の別の檐動部隊にぞくしていた。
また別にもう一隻の空母「サラトガ」が、太平洋艦隊に所属してはいたが、あいにく、その当時には米本国西岸のドックに入り、定期の点検修理中であった。
我々は、長距離偵察機がみじめなほど不足していた。
当時、ハワイ方面に配置されていた米陸軍機で利用できたものは、ただ、B18双発中型爆撃機だけであった。
しかし、この機種は速力がのろくて、航続距離もみじかく、到底洋上偵察飛行には適さなかった。
また、米海軍のPBY飛行艇(通称「カタリーナ号」)も、機数が不足していた。
この図体のバカでかい偵察機は、いわば海の駄馬で、ガッシリしてはいるが、旧式で速力ものろく、もし広い洋上を三百六十度の全方向にわたり、連続的に索的飛行を実施させるならば、ただ不足した機材と、乗員をクタクタに疲れきらすばかりであったろう。
そのうえ、我々をさらに苦しめた困難は、このPBY飛行艇の乗員の大多数を、大西洋方面の戦線へ出動させるために訓練せよ、という本省からの命令であった。
このような事情と、空母「ヨークタウン」が米本土東海岸へ移動、配置についたためとによって、我々のすでに手薄な人的、物的戦力は、いっそうはなはだしく、弱体化していたわけだ。
しかしながら、もしも我々が、重大な「魔法情報」を以前から知らされていたならば、当然、三百六十度の全方向にわたる洋上索敵飛行の実施を命令していたであろうし、また、そのためにはどんな無理をしても、機材と乗員がその損耗と疲労の極点に達するまで、この洋上索敵飛行をつづけて強行していたことだろう。
私はつねにキンメル元海軍大将とショート元陸軍中将について、つぎのように考えてきたものである。
――この優秀な二人の軍人は、自分の力では絶対に自由にならぬ、ある目的のために犠牲の山羊として、狼群の前に放り出されたようなものである。
この両軍人は戦備の点でも、情報の点でも、ただ、あたえられただけのものによって、行動せねばならなかったのだ。
この二人こそ、わがアメリカの、偉大な軍人の殉教者である』 |
Ⅵ 真珠湾論争への審判
top
1 奇襲とだまし討ちの相違
『兵は詭道なり』とは、二千五百年前の有名な孫子の兵法のなかの名句である。
それは、戦争の本質が、相手のウラをかいてだますことを、いみじくも喝破したものであり、また、現代の戦術として、奇襲(サプライズ・アタック)の重要性が古今東西に相通じることを教えている。
『攻撃戦争の最強の武器の一つは、奇襲攻撃である』とは、十九世紀はじめ(約百七十年前)のプロシアの偉大な戦争理論家カール・フォン・クラウゼビッツ将軍の『戦争学』の中の警句である。
したがって、奇襲は、相手の油断を衝いた戦争の正攻法の一つであって、けっしで卑怯な『犯罪的攻撃』(クリミナル・アタック)と呼ぶことはできないはずである。
それは、むしろ戦備を怠って奇襲をこうむり、大損害をうけた国の負け惜しみといわれても仕方がないであろう。
ところが、世界戦史上に、すでに堂々と明記されているように、太平洋戦争の火蓋をきった日本軍の真珠湾奇襲は、日本軍独特の卑劣な『だまし討ち』(トレチャラス・アタックまたは、スニーク・アタック)であるという忌(いま)わしい烙印が押されてしまった。
しかも、ルーズベルト大統領自身が、十二月八日(米国時間、日本では十二月九日に当たる)の米国議会にたいする有名な対日開戦教書で、つぎのように日本の奇襲を『だまし討ち』であると強調して、挙国一致の米国民の総決起をうながしたのだ。
それは、ハワイの現地の米陸海軍当局の油断と怠慢の責任を、いちおうタナ上げして、もっぱら奇襲の重大責任を日本側の軍事的犯罪に押しつけ、たくみに、全米国民大衆の対日敵愾心(てきがいしん)と、復讐心を煽動する宣伝効果を発揮したものだった。
『昨日、一九四一年十二月七日(米国時間)――それは、国辱(汚名)の日として永く残るであろう――アメリカ合衆国は、日本帝国の海軍および空軍のために、突如、しかも用意周到に攻撃された。
しかるに合衆国は、日本と平和関係にあり、しかもまた、日本の懇請によって太平洋の平和維持のために、その政府ならびに元首と会談をまだ続行中であった。
実際に、日本航空部隊が、オアフ島(ハワイ群島の主島でホノルル市と真珠湾軍港がある)の爆撃を開始してから一時間後に、駐米大使(野村吉三郎大使をさす)は、その同僚 (来栖三郎大使をさす)とつれ立って、国務長官にたいし、最近のアメリカの通牒への公式回答を手交したのであった。、
この回答には、現在の外交交渉の継続の無益なることを述べていながら、少しも、戦争あるいは武力攻撃の威嚇、または示唆をふくんでいなかった。
日本・ハワイ間の距離は、この攻撃が数日前はおろか数週間以前に用意周到に計画されたことが明瞭であることを記録するものであろう。
この引きのばし期間中に、日本政府は虚偽の声明と、平和継続の希望表現によって、アメリカ合衆国を、用意周到に欺(あざむ)かんと努めたのであった。
昨日、ハワイの攻撃は、アメリカ陸、海軍に甚大な損害をあたえた。はなはだ多数のアメリカ人の生命が失われた。
さらに、サンフランシスコとホノルル間の大洋上で、アメリカ船舶が、魚雷攻撃されたと報じられている。
昨日、日本政府は、またマレー半島を攻撃した。昨夜、日本軍は香港を攻撃した。
昨夜、日本軍はグアム島を攻撃した。昨夜、日本軍はフィリピンを攻撃した。
今朝、日本軍はミッドウェー島を攻撃した。
日本はかくのごとく太平洋全域にわたり奇襲攻撃を敢行したのである。
この昨日の諸事実こそ、みずから事態をもっとも雄弁に物語るものだ。
それは、アメリカ国民が、すでに国論を一致させて、国家の存立と安全が、危殆に瀕していることを十分に了解するところである。
この計画的侵略を克服するのに、いかに長い年月を要するとも、アメリカ国民は、その正しい力をふるって絶対的な勝利を、勝ちとるであろう。
我々が全力をつくして、我々を防衛するのみならず、この種のだまし討ちが、けっして我々を、再び危険ならしめないために戦うということは、私の主張であるばかりではなくて、じつにアメリカ国民および議会の総意であると信ずる。
戦闘は開始された。
わが国民、わが国土、わが権益が重大脅威にさらされている事実に目をおおうことはできない』(中野五郎訳、ルーズペルト大統領の米国議会にいたする開戦教書より) |
確かに、大衆政治家として老練なルーズベルト大統領は日本側のいちばん痛いところを衝いて、真珠湾奇襲はワシントンで、まだ日米外交交渉(野村・ハル会談)が継続中に、卑劣にも抜き討ちに行なわれた『だまし討ち』であると、米国内はからは、全世界へ向けて吹聴した。
それは、日本側の外交交渉打切りの対米通告が、ハワイ攻撃の、開始時刻の三十分前(ワシントン時間十二月七日の日曜日午後一時に当たる)に、ハル国務長官へ野村大使から手交される予定のところ、意外にもワシントンの日本大使館の首席書記官と、電信官の油断とミスから、長文の暗号電文の翻訳とタイプ清書がたいへんに手間どり、とうとう提出時間を一時間二十分もおくれてしまったからだ。
それは、日本にとって、まったく歴史的開戦の日を汚した取返しのつかない最大のミスであり、正々堂々たる奇襲作戦の成功に、おしくも『だまし討ち』とか『犯罪的攻撃』という不名誉な烙印を押されてしまった。
すなわち、日本は、武力戦の奇襲には大勝利をおさめながら、宣伝戦には開戦早々から重大な失敗をしたわけだ。
2 作戦の成否は国際法に優先 top
この日米開戦の前夜、日本側では天皇も、開戦の事前通告の点について、重大な関心をしめし、陸海軍統帥部へ注意されていたし、とくに対米外交の全責任をになっていた東郷茂徳外相(当時五十九歳)は、十二月一日の御前会議で、
『対米交渉ついに成立するにいたらず。帝国は、英米蘭にたいし開戦す』という重大議題が、べつに異議もなく、『挙国一致』とか『一死奉公』とか『国難突破』という出席者全員(全閣僚、陸海軍両統帥部総長、両次長、内閣書記官長、陸海軍両軍務局長、枢密院議長)の悲壮な決意の下に決定した以上、国際法にもとづいて、正々堂々たる開戦(または宣戦)通告を、米国政府へ伝達すべきであると確信していた。
そして、それが当然、天皇の公明な意向でもあり、また自存自衛のために決起せんとする皇軍の聖戦のあり方であると、彼は外務大臣の重責をひとしおに痛感していたようだ。 |
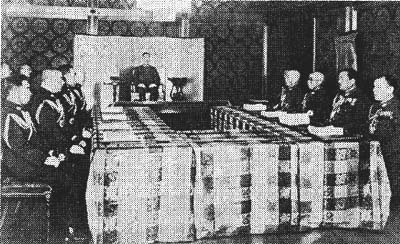
御前会議。旧憲法下では、国家にとって重要かつ
重大なる案件は、天皇出席の下に決定された。
太平洋戦争の開戦、終戦の最終決定もここでなされた。
|
ところが、東郷外相は、当時、大本営政府連絡会議の主要メンバーでありながら、ハワイ攻撃の作戦計画に関しては、まったくツンボ桟敷におかれており、ただ、『奇襲による開戦』ということだけを漠然と示唆されたのみであった。
要するに、陸海軍統帥部は、真珠湾奇襲を成功させるために、『敵を欺くには、味方を欺くにしかず』という古い格言を実行した。
つまり、米国側を、日米交渉継続の形でだまして油断させるために、まず、東郷外相と、ワシントン駐在の野村大使まで、天皇の『宣戦の詔勅』の公明正大な趣旨にも矛盾した戦争の奇怪な本質――『目的のためには手段をえらばず』という『勝利の戦略』の正体を暴露(ばくろ)したものであった。
戦後はじめて、東京裁判で明らかにされた証言記録によると、その当時に東郷外相は、開戦の手続きについて海軍統帥部と大いに論争し、
『正式の宣戦の通告か、少なくとも交渉打切りの通告は、国際信義上、ぜったいに必要である。
その通告時刻は、攻撃開始前に充分の時間の余裕があることを要する』 |
と、ヘーグ戦争条約の開戦規定をかたく守るように主張した。
このヘーグ戦争条約は、一九〇七年(明治四十年)十月にヘーグ(オランダの行政上の首都)で日本も参加して、調印され、翌年に批准公布されたもので、その第一条は、つぎのとおり宣戦布告について規定し、第一次大戦では、交戦国の双方ともが忠実にこれを守った。
ところが、第二次大戦では、皮肉にもナチス・ドイツと軍国日本が、これを破って奇襲によって開戦をしたわけだ。
日本の場合、ハワイ攻撃が決行されたのが、現地時間で十二月七日午前七時五十五分であり、それは、日本内地時間では、十二月八日午前三時二十五分にあたった。
しかし、大本営が、『帝国陸海軍は本八日未明、西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れり』と、開戦を正式発表したのが十二月八日午前六時であり、しかも、天皇の歴史的な『宣戦の詔書』が発布されたのは、さらにおくれて、同日の午前十一時四十分であったから、ワシントンの日本大使館の日米交渉打切り通告の提出時刻の遅延問題とはかかわりなく、国際法上から、由緒ある古いヘーグ条約に、二重にも三重にも違反していたわけだ。ヘーグ条約には。
『締約国は、理由を付したる開戦宣言の形式、または条件つきの開戦宣言をふくむ最後通牒の形式をもつ明瞭、かつ事前の通告なくして、その相互間に、戦争を開始すべからざることを承認す』とある。
ところが、ハワイの真珠湾軍港に大奇襲をかけて、米国太平洋艦隊をいっきょに撃滅せんと決起した海軍統帥部では、あらゆる警戒手段をとって、この空前の作戦計画の発動についての機密保持に努力していた。
それは、孫子の兵法の『兵は詭道なり』という極意を徹底的に実行したかわりに、国際法上の義務であるヘーグ条約の宣戦規定を平然と破ることとなった。
ただ東郷外相の強硬な直言には多少おれて、正式の宣戦通告のかわりに、対米外交交渉の打切り通告を提出する時刻を、ワシントン時間で、十二月七日午後一時に指定するよう手続きを求めた。
しかし、東郷外相には、それからはたして何時間後に攻撃が決行されるかを、全く知らせなかった。
このために、東京の外務省とワシントンの日本大使館の間の外交暗号電報の連絡が、緊密に、しかも計画どおりにうまく行なわれなかったのは不運でもあるが、また海軍統帥部が、あまりに秘密主義にこだわりすぎたせいでもあった。
実際に、外交交渉打切りの対米通告時刻は、最初、伊藤軍令部次長から、東郷外相にたいして、極秘に、ワシントンで十二月七日午後零時半と指定してきたが、その後さらに三十分くり下げて、午後一時に変更してきた。
それは、ハワイ攻撃直前のギリギリでわずか三十分前の猶予しかないものであったから、たとえ通告提出が、本省の指示どおりにおくれないで行なわれたとしても、その通告文の内容は、やはり厳正なヘーグ条約の宣戦規定を破った。
しかも相手をだまして油断させる目的の、インチキな公文書であった――という非難が、米国では、とうぜん起こったことであろう。
なぜならば、単に日米交渉の打切りは、けっして、日米両国の外交断絶、大使の引揚げを意味せず、いわんや日米開戦へ、ただちに発展するものとは、国際慣例の常識では、到底考えられなかったからだ。
3 東郷外相の遺書 top
これについて、すでに病死した東郷外相の遺書となった大戦外交手記『時代の一面』(昭和二十七年刊、絶版)の中のつぎの一節は、まことにミステリー的な興味の深い日本側の真珠湾奇襲の秘密の正体を明らかにしたものである。
その要旨を引用して、読者の参考に供する。
『十二月一日の御前会議の直後の会議で、自分は宣戦通告の問題もあるからと思って、いつから戦闘を開始するつもりかと聞いた。
これにたいして杉山参謀総長は、つぎの日曜日ごろだと、あいまいなことを言うので、その態度にますます疑念を抱き、戦闘開始の通告は、通常の手続きによることが適当だと述べた。しかるに永野軍令部総長は、奇襲でやるのだと言った。
これに引きつづいて、伊藤軍令部次長から、開戦の効果を大ならしめるため、外交交渉は、戦闘開始まで打ち切らないでおいて欲しい、との申入れがあった。
これで統帥部が、さきに急速開戦を主張していたにもかかわらず、御前会議の当日は、はなはだのんきな態度をしめしていた意味がわかった。
しかし、自分はいままで海軍が邀撃作戦にて勝つ自信ありと言っていたのに、突然、奇襲をやるのだと言い出したのには、驚くとともに、奇襲をやらなければ、緒戦においても十分な見込みがないことにも解せられて、戦争の前途を心細く感じた。
しかし自分は、このやり方は、通常の手続きに反して、はなはだ不当であること、開戦の際に無責任なことをしておくと、わが国の名誉と威信とに関して、はなはだ不得策であること、また、野村大使よりも自由行動に出る前に、交渉を打切りおくことが必要であり、その通告は、ワシントンにおいても行なうことが必要である、との意見上申をも引用して、事前の通告は、国際信義上から絶対に必要であると主張した。
自分は、統帥部が開戦決定の後になって奇襲の必要をとなえ、あたかも、これを強要せんとするがごとき態度を示したのに、はなはだしき不満を感じ、他に先約があったから、これを理由として退席せんとした。
すると伊藤軍令部次長は、私の席に来て、海軍の苦衷を訴え、もし交渉打切りの通告が、どうしても必要ならば、ワシントンではなく東京において米国大使になすようにしたい、と申出た。
自分は、この方法については、ある種の不安を感じたので、その申出を拒絶して、そのまま別れた。
しかるに、そのつぎの連絡会議のはじめに、伊藤次長は、ワシントンで交渉打切りの通告をなすことに、海軍軍令部は異存ないと述べ、その通告が、ワシントン時間で十二月七日午後零時半になされるべきことを申出た。
自分は、この論争によって海軍側の要求を、国際法の要求する究極的限界にくいとめることに成功したと思った』 |
だが、東郷外相の期待は、すっかり裏切られた。
なぜなら彼は、十二月五日に外務省に来訪した伊藤軍令部次長に向かって、
『事前通告と攻撃の間隔は、どのくらいの時間が必要か?』
と、念のためにたずねたところ、伊藤次長は。
『それは作戦の機密であるから申し上げられない』
と明答を断わられたからであった。それで東郷外相は内心で、
『まさかと思うが、通告と同時に攻撃するのではなかろうか?』
という不安と疑念がわいたらしい。 しかも、伊藤次長は、
『わが方の通告が在米大使館へあまり早く発信されないように願います』
と意味深長な言葉を帰りぎわに残したので、東郷外相は、
『私は、指定時間(午後一時に変更)に間違いなく届けられるように発信しなくてはならぬ』
とはっきり答えた。
責任感の強い東郷外相は、長文の『対米覚書』を十四部に分けて、最高機密度の暗号電報に組んで、最終のわずか四、五行の第十四部をのぞく全文を、十二月六日(ワシントン時間)の午前六時三十分から十時二十分の間に、逐次、発信させた。 |

伊藤整一軍令部次長。事前通告の問題で東郷外相に苦衷を訴えた。
|
そして重大な最終部を、七日(ワシントン時間)午前三時と四時に二つの路線で、正確と迅速を期して発信させた。
しかし、ワシントンの日本大使館は、東郷外相の緊急訓電を守らず、開戦前日の夕方に着信した十三部までの暗号電報の翻訳とタイプ清書をすませていなかったため、運命の七日午後一時の提出時刻に間に合わなかったのだ。
(注、東条内閣の外相として、開戦の重大責任をになった東郷茂徳(しげのり)は、開戦二年目の昭和十七年九月、米英軍捕虜の取り扱い問題その他について、東条首相と意見が対立したため辞職引退したが、奇しくも敗戦直前の昭和二十年四月に鈴木貫太郎内閣の外相に返り咲いて、終戦促進に大いに尽力した功績は高く評価されている。
すなわち彼は、戦争末期に、天皇の和平念願を達成するために、必死の献身的な努力をつづけ、陸海軍統帥部と一部の極右閣僚の『徹底的抗戦』と『本土決戦』と『一億玉砕』を呼号した狂信的な態度にあくまで屈せず対抗し、ポッダム宣言を受諾して一刻も早く終戦を決断、実現すべしと熱烈に主張した。
彼は、明治十五年、鹿児島県に生まれ、同四十一年、東京帝大文科卒業、大正元年、外交官試験に合格、その後ドイツ大使館参事官、本省欧米局長、欧亜局長、駐独大使、駐ソ連大使などを歴任した。
気骨ある外交官として知られ、開戦の責任を終戦の功績によって大いにつぐなったものとみられたが、昭和二十一年四月に、極東国際軍事裁判所でA級戦犯に指定、起訴された。
そして昭和二十三年十一月、禁錮二十年の判決をうけ巣鴨刑務所に拘禁、服役中に胸部疾患が悪化して昭和二十五年七月さびしく死去した。
享年六十八歳であった。 彼こそ太平洋戦争史上で開戦=終戦の二つの重大時点に外相としての大きな役割をはたしながら、現在では、一般に忘れられた悲劇的な人物である)
4 戦争の教訓から top
昭和四十一年十二月は、太平洋戦争の開戦二十五周年にあたった。
まことに歳月のたつのは、水の流れのごとく、早くてはかない。
我々日本人にとっては、それはまことに忌わしい悪夢のような思い出ではあるが、すでに戦後の若い世代の数千万の人々にとっては、日米開戦の記念日も、まったく遠いむかしの神話か、伝説のようにしか思われないであろう。
それほど今日の日米には、太平洋戦争をすでに忘れた世代と、開戦――敗戦の実感を、全く知らない世代が多くなっている。
しかし、『現在は過去の後始末である』という警句は、太平洋戦争の場合にもピタリと当てはまるのだ。
すなわち、軍国日本の敗北降伏も、『大日本帝国の崩潰』も、神がかりの絶対天皇制から主権在民の民主日本へ更生したのも、さらに現在の奇蹟的な復興と、経済的繁栄と、愛国心の喪失も、また物質万能主義と、自由享楽と、犯罪激増も、すべて春秋の筆法をかりるならば、十二月八日のもたらしたものであり、したがって太平洋戦争が、今日の一億国民に残した明暗両様の『偉大な遺産』であると言えるだろう。
それは、恥ずべきものではなくて、学ぶべきものである。
そういう歴史的な意義を、公正に真剣に考えて、じっくりと再検討してみると、十二月八日を、我々日本人は、永久に忘れてはならないことが明らかになってくる。
民主日本は、幸か不幸か、日米安保条約の改廃をめぐり、政界も言論界も荒れ模様の警戒信号を示した。
しかし、つねに先物買いの日本の政治家連中が、保守、革新の両陣営をとわず、安保問題と自衛隊の増強と国防計画をめぐる大論争に張り切っているとき、まず銘記してもらいたいのは、十二月八日の教訓である。
もはや日本人は、ベトナム戦争を対岸の火災のごとく安閑(あんかん)とながめていたようなことが、今後は許されないのと同じように、平和日本の足許に火のついたような切実な国防問題と 軍事計画について、政治家まかせも、制服軍人まかせも許してはならないときが到来した。
すなわち国民全体で、めいめい自由で冷静な立場から、民主日本の現在の姿をあらためて直視して、あの悪夢のような十二月八日の教訓を、十分に学びとり、しっかり自分の身につけて、戦争への安易な妥協にも、また俗悪な英雄主義(ヒロイズム)にも、感傷的な新軍国主義(ネオミリタリズム)にも、押しながされないように努力し、自戒しなければならない。
第一次世界大戦で、フランス共和国の老宰相クレマンソーは、『戦争は将軍連中にまかせておくには、あまりに重大な仕事である!』と喝破して、みずから戦争最高指導にあたって勝利への道を確保した。
しかし彼は、やはり古い観念の戦勝国の絶対権利のみを主張して、敗戦ドイツの永久屈服をめざした不合理、非道なベルサイユ条約体制を、あくまで強要したため、かえって、欧州の混乱情勢と、独裁者ヒトラーの出現をもたらしたのであった。
そして、第二次大戦の起因のタネを、不見識にもまいたわけだ。
また第一次大戦で、『新しい自由』(ニュー・フリーダム)を提唱して、全世界の共鳴をかちえて、
『米国は戦争を終わらせるために参戦する!』
と大見栄を切った米国のウィルソン大統領も、やはり、国際連盟の彼の夢を実現するためには、ベルサイユ条約で敗戦ドイツをギセイにして恬然(てんぜん=平気)と恥ずるところがなかった。
彼もまた、人道主義の持論をみずからすてて、クレマンソーの報復、懲罰主義に同調し、第二次大戦の起因の責任者に加わった。
それゆえ英国の修正主義派の歴史学者として有名なA・J・P・テイラー博士(英国オックスフォード大学教授、BBC放送外交評論家)は、第一次大戦五十周年記念に刊行した最新の『第一次世界大戦史』の結論で、クレマンソーの警句を皮肉って、つぎのように反論をくだしたものだ。
『戦争は、将軍連中にまかせておくには、あまりにも重大な仕事ではあるが、さりとて、政治家連中にまかせきりにしておくにも、やはりあまりに重大すぎる仕事であった!』
このテイラー教授の警句は、そのままそっくり第二次大戦にもあてはまるものである。
すなわち、ルーズベルト、チャーチル、スターリンの三巨頭は、第一次大戦の教訓をまったく学ばないで、いわゆる『無条件降伏』の世界戦略を固守したため、大戦後半期にナチス・ドイツも軍国日本も、和平交渉のチャンスを絶対に拒否されて、数百万の人命をムダにギセイにして、流血非惨な地獄的死闘に追い込まれたのであった。
しかも、戦勝国の勝利の分け前を、ひそかにヤミ取引したといわれる悪名高いヤルタ会談(昭和二十年二月)で、チャーチル英首相は、
『これこそ米英ソ三大国の団結、協力の最高潮である!』
と、上機嫌でウォッカ酒の乾杯を重ねながら、それからわずか半年後、原爆投下とソ連参戦による軍国日本の徹底的な敗北と無条件降伏後まもなく、米英対ソ連の『冷戦』(コールド・ウォア)の幕が上がるや、いちはやく、
『我々は戦争には勝ったが、戦後の平和には敗れた!』といみじくも嘆息したのである。
戦争は終わったが、人類待望の恒久平和は幻滅と化して、また新しい戦争のタネがまかれたわけだ!
5 十二月八日の歴史的詔勅 top
では一体、何のための七年間にわたる血みどろな第二次大戦であったのか?
また、太平洋戦争の大義名分とは?
要するに戦争というものの正体は、たとえ『平和を守る』とか、『自存自衛』とか、『侵略を排除する』とか、『国家の独立』とか、『民族の解放』とか、『集団安全保障』等、いろんな、もっともらしい大義名分のレッテルを貼付ても、実際には、誤算と矛盾と憎悪の生み出した非人道的な、恐るべき無制限の殺し合いの人間残酷ドラマにほかならないのである。
それは、戦争専門技術者である制服の将軍連中にも、また『文官支配』(シビリアン・コントロール)を自慢した政治家連中にも、到底理性的に、合理的にコントロールすることができないものである。
結局、我々日本人としては、太平洋戦争の真相をできるだけよく知り、深く考えて、十二月八日の教訓をけっして忘れず、いつも左右両派の政治家や新旧の軍人たちが、『国防』という美名の下に、再び戦争の正当化と光栄化を提唱しないように、厳重に監視する必要がある。
そこで私は、戦史家の立場より、いわゆる十二月八日の深刻な教訓の実例として、つぎの印象的な歴史的言葉を引用して、国民大衆のための永久不変の座右(ざう=身辺)銘に呈したいと思う。
これを忘れたら、日本はかならず近い将来に、つぎの戦争に巻き込まれるだろう、と私は戦史家として予言したい。
『天佑ヲ保有シ万世一系ノ皇祚(こうそ)ヲ践(ふ)メル大日本帝国天皇ハ昭(あきらか)ニ忠誠勇武ナル汝(なんじ)有衆ニ示ス、朕(ちん)茲(ここ)ニ米国及ビ英国ニ対シテ戦ヲ宣ス、朕(ちん)ガ陸海将兵ハ全カヲ奮テ交戦ニ従事シ、朕ガ百瞭有司ハ励精職務ヲ奉行シ、朕ガ衆庶ハ各々其ノ本分ヲ尽シ億兆一心国家ノ総カヲ挙ケテ征戦ノ目的ヲ達成スルニ違算ナカラムコトヲ期セヨ
(中略)
皇祖皇宗ノ神霊上ニ在リ、朕ハ汝(なんじ)有衆ノ忠誠勇武ニ信倚シ、祖宗ノ遺業ヲ恢弘シ速ニ禍根ヲ芟除(せんじょ)シテ東亜永遠ノ平和ヲ確立シ、以テ帝国ノ光栄ヲ保全セムコトヲ期ス』(昭和十六年十二月八日の天皇の宣戦詔書より) |
『いま、宣戦の大詔を拝しまして、恐懼(きょうく)感激にたえず、私不肖なりと雖(いえど)も一身を捧げて決死報国、ただただ宸襟(しんきん)を安んじ奉らんとの念願のみであります。
国民諸君もまた、己が身をかえりみず、醜(しこ)の御楯(みたて)たるの光栄を同じくせらるるものと信ずるものであります。
凡(およ)そ勝利の要訣は「必勝の信念」を堅持することであります。
建国二千六百年、我等(われら)は未だかって戦いに敗れたるを知りません。
この史績の回顧こそ、如何なる強敵をも破砕するの確信を生ずるものであります。
我等は光輝ある祖国の歴史を、断じて汚さざると共に、栄ある帝国の明日を建設せむことを固く誓うものであります。
かえりみれば我等は、今日まで隠忍と自重との最大限を重ねたのでありますが、断じて、安きを惧(おそ)れたものでもありません。
ひたすら世界平和の維持と、人類の惨禍の防止とを顧念(こねん)したるに外なりません。
しかも敵の挑戦を受け、祖国の生存と権威とが危うきに及びましては、起たざるを得ないのであります。
帝国の隆替(りゅうたい)、東亜の興廃、正に此の一戦に在り。一億国民が一切を挙げて、国に報い国に殉(じゅん)ずるの時は今であります。
八紘(はつこう)を宇(う)と為す皇謨の下に、私は、ここに謹んで微衷(びちゅう)を披瀝し、国民とともに、大業翼賛の丹心を誓う次第であります』
(昭和十六年十二月八日、内閣総理大臣東条英機大将のラジオ全国放送『大詔を拝し奉りて』より) |
(注=絶対天皇制下の軍国日本では、戦後の若い世代には、とても難解な用語が有難そうに広く使用されていた点も忘れてはなるまい。
御稜威(みつい)とは、天皇の威光の意味、皇謨(こうぼ)とは、天皇の国家絖治のはかりごとをさし、大業とは帝王の事業、翼賛(よくさん)とは、力を添えて天子を助けることを意味する。
また、有名な八紘一宇(はちこういちう)は古代中国の学者、淮南子(えなんし)の地形訓による四方と四隅を意味し、天下=全世界を一つの屋根の下におくという皇道の世界宣布の理想を表現したため、欧米では、軍国日本の世界征服の野望のシンボルとみなされていた。
だが、それが悲しい誤解であっだことは敗戦によって証明された)
私は、あらためて読者のみなさんに訴えたい。
『敗戦の教訓は、だれにでも、理屈ぬきで黙っていてもよくわかる。
しかし、開戦の教訓こそ、じつは本当の戦争の教訓なのだ』と。
Ⅶ 真珠湾奇襲の功罪と遺産 top
1 なぜ太平洋戦争というのか
ここで、太平洋戦争の戦端をひらいた世界戦史上、空前の真珠湾(パールハーバー)奇襲の是非と功罪について、自由公正な々場からその真相と、争点を明らかにするとともに、いわゆる歴史的な真珠湾の大秘密をおおった黒い霧を追いちらせて、いくつもの根本的疑点を迫及し、最新の権威ある調査記録資料にもとづいて、再検討してみたいと思う。
それにさきだち、私はこれまでいちおう、解説するつもりでいながら、まだ機会をえなかった太平洋戦争の呼称について、読者のみなさんのために明確に説明しておきたい。
昭和十六年十二月八日未明三時半ごろ、(ハワイ現地時間では一九四一年十二月七日、日曜日、午前八時ごろ、ワシントン時間では同日午後一時半ごろ)日本海軍の大空母機動部隊のハワイ真珠湾軍港(米国太平洋艦隊根拠地)にたいする奇襲攻撃で戦端をひらいた日米戦争は、正式には、日本の対米英蘭開戦と呼ぶべきであるが、日本側では、この戦争をとくに『大東亜戦争』と名づけ、連合国側ではこれを一般的に『太平洋戦争』とよんだ。
日本側が名づけた『大東亜戦争』(The Greater
Asia War)という呼称は、いわゆる皇国日本を中心とした大東亜共栄圈の建設(東亜の新秩序をさす)という、戦争目的を明らかにしたものであるが、それはけっして、戦時下の日本の新聞、雑誌、ラジオなどマスコミが勝手につけた名称ではなくて、じつに東条首相のお声がかりで、昭和十六年十二月十二日付で内閣情報局より発表された、つぎのような公式声明にもとづくものであった。
したがって戦時中は、すべて『大東亜戦争』という公式呼称で統一され、もっと一般的で、子供にもわかりやすい『太平洋戦争』という名称は、敵性表現として禁止されたも同じであった。
『今次の対米英戦は、支那事変をも含む大東亜戦と呼称す。
大東亜戦争と称するは大東亜新秩序建設を目的とする戦争なることを意味するものにして、戦争地域の大東亜のみに限定する意味に非ず』(原文のまま)
しかし、敗戦後、このいかめしい『大東亜戦争』という呼称は、その誇大な戦争目的を喪失した理由からも、きわめて不適当であるため、日本政府も新聞ジャーナリズムも、いっせいに連合国側で正式に採用し、しかも現代史上で世界共通に広く使用されている『太平洋戦争』という名称を、公然ともちいるようになった。
ところが、この数年らい、政界や言論界の一部では、いわゆる逆コース的風潮に便乗して、戦後に生長した全国の小、中学、高校生たちに自然になじまれた『太平洋戦争』という国際的名称を排して、ことさら、戦時中の『大東亜戦争』という呼称を使用するむきがある。
これは前にのべた内閣情報局発表の趣旨を知らないための誤用であり、それが戦争の地域ではなくて、目的をしめす呼称である以上、敗戦国たる日本ただひとりが使用する、愚劣な、戦前派のノスタルジアといいうべきであろう。
一方、連合国側でも、戦時中(とくに開戦後、まもなく)、『この大戦争をなんと呼ぶべきか?』ということが、さかんにジャーナリズムで論議された。
いちばん自然で、すなおな名称は、『第二次世界大戦』(The Second World War, The World War Ⅱ)という総称のもとに、『太平洋戦争』(The Pacific War)と『欧州戦争』(The European War)の二大正面をふくませるものであった。
そしてそれが戦時中も戦後も一般化して、今日までは世界戦史上でも国際政治上でも、広く普遍的に使用されている。
ただ、ソ連だけが国内むけに、とくに『大祖国戦争』という呼称を長らく使用しているのが例外とみられている。
私は日本でも、けっして戦争に敗けたからという卑屈な理由からではなくて、いちばん自然的な、わかりやすい呼称として、『第二次世界大戦』『太平洋戦争』という、広、狭ふたつの名称を自由に並用するのが、もっとも適当であると思う。
現在はもちろん、将来にも、全世界共通の大戦争の呼称が、時代のうつり変わりや、各国の国内事情によって、あれこれと特別の意味や、解釈をつけて変更されることは好ましいことではないだろう。
ことに今日の日本国民にとっては、ラテン語の『パシフィカス』(平和づくりの意味)から由来した、『平和な大洋』を意味する『パシフィック・オーシャン』(太平洋)という言葉にちなんだ『太平洋戦争』の呼称こそ、じつに『けっして再び戦争をせず』と誓い合い、恒久平和をねがうわが民族の熱望をこめた絶好の、印象的な名称であると信じている。
ところで、自由な世論とマスコミ宣伝のさかんな米国では、開戦そうそうから国民士気の昂揚のために、あれこれと戦争呼称の選定が行なわれ、ルーズベルト大統領までが、新聞記者団との会見で、『なにかうまい名称はないかね?』と名案をもとめたものだった。
当時、私は朝日新聞ニューヨーク特派員としてすでに抑留されていたが、新聞やラジオで、自由に戦時下の『敵国アメリカ』の社会的な呼吸と、脈搏を記録することができた。
その当時の貴重なメモによると、つぎのような名称が、いろいろ提案されて、米国名物のギャラップ世論調査の対象にまでなって、各新聞紙上をにぎわせていた。
『生存の戦争』(生き残り、勝ち残るための戦争、という意味、大統領提案)
『人民の戦争』(カーチン・オーストラリア首相提案)
『世界自由のための戦争』(二十六パーセント)
『自由のための戦争』(十四パーセント)
『自由権の戦争』(十三パーセント)
『反独裁者戦争』(十一パーセント)
『人道のための戦争』(九パーセント)
『デモクラシーの戦争』(八パーセント)
『ルーズベルトの戦争』(皮肉な反ルーズベルト分子の投票)
結局、このようなヤンキーごのみの戦争呼称の名案は、いずれも戦争の進展と激化にともなって影をひそめて、米国でも英国でも、いつのまにか、対日戦争はすべて、『太平洋戦争』という、自然で平凡な呼称に統一されてしまった。我々日本人も、この国際的な呼称をすなおに使用した方がよい、と私は思っている。
2 奇襲をめぐる感激と悲哀 top
日本海軍随一の米国通であり、しかも日独伊軍事同盟にあくまで反対して、日米開戦を回避するために、海軍次官当時より苦心、努力しつづけてきた山本五十六海軍大将(開戦当時の階級、昭和十八年四月十八日、ソロモン群島のブーゲンビル島南端上空で機上戦死後、元帥に昇進す)が、みずから真珠湾奇襲攻撃計画を提案し、連合艦隊司令長官として軍国日本の興亡を賭(と)して、日米開戦の壮烈な火ぶたを切っておとした歴史的事実は、まことに世界戦史上に永久に記録されるべき、人間悲劇であろう。
日本でも米英でも、『山本五十六伝が刊行されて注目されているので、戦後の日本国民にとっては、あまり寝覚めのよくない、真珠湾奇襲大勝の思い出(それはじつに軍国日本の敗北、降伏の第一歩でもあった)が、再びよみがえってきたようだ。
それに十二月は、日米開戦を呼びさまされるので、我々日本人は、好むと好まざるとにかかわらず、真珠湾奇襲の『悪夢のような勝利感』を、皮肉にも、まるで砂をかむような索漠たる気持で味わわせられるにちがいない。
なぜなら、我々日本人の国民的感情と、幻滅的悲哀をまったく無視して、米国はじめ往年の主要連合国では、あの『真珠湾を忘れるな!』(リメンバー・パールハーバー)の歴史的合言葉を、なまなましくマスコミがよみがえらせて、いろんな戦争記念行事か盛大に行なわれるだろう、と私は戦史家として予想しているからである。
幸か不幸か、あの歴史的な十二月八日(日本時間)に、私に、ジャーナリストとして米国に駐在し、内地にはいなかったので、真珠湾奇襲大勝の奇蹟的な吉報に、大元帥たる天皇も機嫌うるわしく、日本中の軍、官、民大衆がいかに狂喜、乱舞して絶大な勝利の感激にひたったか、そのなまなましい姿や、歓声を、自分で見聞して、たしかめることはできなかった。
しかし、後で紹介する有名な米英追放、大東亜主義の巨頭であった大川周明博士(戦時中は、満鉄東亜経済調査局最高顧問、法政大学大陸部長、主著『日本二千六百年史』『日本精神研究』『大東亜秩序建設』など)の真珠湾奇襲大勝にちなんだ感動の言葉と、当時の連続ラジオ放送のテキスト記録を読んでみると、確かに日本全国民の『世紀の勝利感』といったものを、いまさらのように切実に痛感させられたものだ。
あの純情な芸術家気質で知られた詩人、彫刻家の高村光太郎でさえ、
| 『必死にあり、その時、人きよくして強く、その時、こころ洋々としてゆたかなのは、我ら民族の習(なら)いである』 |
と、米英撃滅の無限の感動をこめた戦争詩をいくつも発表した。
戦前、戦後を通じて民衆詩人として愛好された三好達治さえも、『アメリカ太平洋艦隊は全滅せり』と題する、つぎの
ような長詩を堂々とつくって、勝利の祝杯に酔った。
今日から回想すると、まことにハダ寒い悲哀感を覚えるばかりである。
それがいわゆる『戦争のむなしさ』といってもよかろう。
『ああその恫喝(どうかつ)、ああその示威、ああその経済封鎖、ああそのABCD線、笑うべし、脂肪過多のデモクラシー大統領が、飴よりもなお甘かりけん。
昨夜の魂胆のことごとくは、アメリカ太平洋艦隊は全滅せり!
荒天万里の外、激浪天を拍(う)つの間に馳駆(ちく)すべかりし、ああその凡庸提督キンメル麾下の艨艟(もうどう=軍艦)は、一夜熟睡の後、かしこ波しずかな真珠湾内ふかく、舳艫(じくろ)相含みて沈没せり、げにや一朝有事の日、彼らの光栄のさなかにあって、ああその百の巨砲は、ついに彼らの黄金の沈黙をまもりつつ海底に沈み横たわるなり』 |
おそらく私自身も、十二月八日に日本内地にいたら、このような国民的感激を爆発させた戦争詩を、さかんに愛誦していたかも知れない。
だが、真珠湾奇襲大勝について、いちばんムッツリして浮かぬ表情のかげに、『ああ日米ついに戦えり、もはや後にはもどれないが、その前途は?』と矛盾した気持で、国民大衆のカラ騒ぎをひそかに注視していたのは、米国のおどろくべき強大な工業生産力をよく承知していた、山本司令長官ではなかったろうか?
それはそれとして、今日の時点で我々日本人は、たいていが真珠湾奇襲大勝のむなしい思い出を、いまではむしろ忘れたいくらいであろうと思われる。
それに反して、米、英諸国では現在でも、相変わらず『真珠湾を忘れるな!』の警句が生きていて、一般的な多数の第二次大戦史や、太平洋戦史、戦記本の一部分になっているものをのぞいて、真珠湾奇襲だけを主題にしたノンフィクションの単行本が多く刊行され、いずれも好評を博している。
その中には、私が訳述して、日本にはじめてルーズベルト謀略説を、くわしく紹介したロバート・A・シオボールド海軍少将の論争の書『真珠湾の審判』(原題は『真珠湾の最後の秘密』)もあれば、また新しく学問的な立場より、奇襲についての専門研究をまとめた社会科学者ロバータ・ウォールステッター女史の大著『真珠湾その警告と決断』(米国スタンフォード大学出版局、一九六二年刊)のような、良心的な専門書もふくまれている。(しかし、その大半は、興味本位のノンフィクション読物書が占めている)
ではいったい、なぜ、米、英国民は真珠湾奇襲に、いまでも、それほど重大な関心なもっているのでふろうか?
それは、現在の核ミサイル時代で、いちばん恐ろしい『核奇襲』のあり方と、その予知、抑止、防止のあらゆる対策、方法にかんして、真珠湾奇襲の貴重な教訓から、がめつく学びとるためだ!
我々日本人は、いまさら真珠湾奇襲について、かれこれ論じてもはじまらない、といったわびしい気持が一般に強いが、彼らにとっては、真珠湾奇襲こそ、将来の『核奇襲』の原型(プロトタイプ)として、この両者が、不可分なくらい、かたく結びついているのだ!
実際に、戦略上からも、戦術上からも、通常爆弾によった過去の真珠湾奇襲と、メガトン級の原、水爆弾による将来の『核奇襲』との間に、死傷者数と破壊力のものすごいケタちがいをのぞいては、べつに変わりはないわけである。
3 奇襲は予知されていたか? top
終戦後はじめて、米国の新聞、通信の報道によって、日米開戦の前夜ともいうべき重大な日米交渉(野村・ハル会談とも呼ばれた)をめぐり、日本側の最高機密度の外交暗号電報が、すべて米国側に自由に傍受解読されて、日本政府と軍部の手のうちがすっかり見すかされ、また日本の対米英蘭戦争の準備行動までもつつ技けになってした、おどろくべき事実がばくろされて、我々日本人はまさに唖然(あぜん)とし、かつ呆然(ぼうぜん)としたものであった。
要するに軍国日本は、武力戦に敗けたのみならず、開戦前の諜報戦にもすでに敗けていたのだ!。
それから戦後、米国政府がけっして正式に発表したわけではないが、しかし、米国側の熱心な大勢のジャーナリストや軍事専門家の努力により、この奇怪な暗号諜報戦の真相が、しだいに明るみに出てきた。
いまその主要な点をつぎに列挙して、これまで日本では断片的にしか報道、紹介されなかった、いわゆる『マジック』情報の、極秘の正体を総合的に検討してみよう。
(1)最新の権威ある記録資料によると、米陸軍通信隊(シグナル・コアズ)諜報部の暗号班主任(文官)ウィリアム・F・フリードマン(戦後の一九五六年に陸軍大佐の階級で退職す)の苦心努力によって、米国側では、開戦の約一年半も以前の一九四〇年八月に、東京(外務省)とワシントン電報を、はじめて完全に解読することに成功した。
それまでにも一部分の暗号解読は行なっていたが、暗号電報全文の解読成功は、このときが最初であった。
(2)フリードマンは、この機密度の高い暗号解読の技術と研究にかんしては、世界一の専門家とみとめられていたが、開戦の年(一九四一年)の二月、野村吉三郎大使のワシントン着任いらい、ひんぱんに東京の外務省との間に発、受信された数百通にのぼる極秘の、重大な外交暗号電報の傍受解読のために昼夜、やすみなく没頭した結果、精神過労と、心臓病のために開戦直後に倒れて、戦時中は長らく入院療養していた。
しかし、彼のかくれた努力と功績によって、米国側では日米交渉をめぐる日本側の機密暗号電報の内容を自由に知り、きわめて有利な立場にあった。
(3)この偉大な功績によって、フリードマンは、一九五六年に退職したとき、米国議会の承認をへて十万ドル(三千六百万円)の功労金を贈られ、また新制定の『国家安全保障勲章』(NSM)を授与された。
(4)その当時、日本側の、あらゆる種類の外交暗号電報の傍受解読されたものに、米軍諜報部では『マジック』(魔法)という隠語名をつけて、それを極秘の『マジック』情報と呼んでいた。
この隠語名の発案者は、当時の海軍諜報部長アンダーソン大佐であった。
(5)陸軍通信隊諜報部(SIS)の主任暗号官フリードマンの最大の功績は、日本側の各種の外交暗号電報のなかで、もっとも機密度の高い『パープル』(紫色)暗号用の精巧な 暗号機械(日本海軍技術研究所が苦心作製した電気モーター式の『九七式欧文印字機』で外務省へ十数台提供していた)を、手製で開戦時までに四台を完成していた事実である。
この複雑で精巧な暗号機械にかけて、タイプライター式のキーを打たないかぎり、ぜったいに暗号解読は不可能と、日本側で自信を持っていたのに、彼は、十八ヵ月もかかって、その模造製作に成功した。
その四台のなかで、ワシントンに一台、英国ロンドンに一台、フィリピンのキャピテ軍港に一台がそれぞれ配置されたが、かんじんの真珠湾軍港には配置されていなかった。(しかし、記録によると、その五台目は製作中であった)
(6)開戦の年の後半には、この模造された『パープル』暗号機械が大いに活動し、米陸海軍諜報部が、二十四時間交代制(奇数日は海軍担当、偶数日は陸軍担当)で、全米十数ヵ所の電波受信所で特別に傍受した日本外交暗号電報を、片っはしから解読にあたった。
(7)このように米国側では、『マジック』情報をたくさん入手して、日本側の動向と意図を十分に察知しながら、なぜ 十二月七日、日曜日(米国時間)の真珠湾奇襲にあのような 未曾有の油断と、大惨害をさらけ出したのであろうか?
(これがルーズベルト謀略説の出所であるが、しかし、これは、反ルーズベルト派の絶好の攻撃材料にはなるが、厳正な太平洋戦史の調査研究によって否認されている)
(8)要するに米軍は、日本側の外交暗号電報を自由に傍受解読していながら、不覚にも、その『マジック』情報の内容を軍首脳部が迅速に、正確に評価、判断することに失敗したのだ。
その主原因は、陸海軍諜報部とも、暗号解読作業の要員不足と、その作業プロセスにたいへん手間どり、せっかく重大な、緊急の暗号電報を傍受しながら、その暗号解読と英文翻訳に、じつに一ヵ月以上も要したからであった。 |
まさに、事実は小説よりも奇なり、である。
4 大川周明(しゅうめい)の感激と大気炎
top
戦後に育った若い世代の人々は、大川周明博士といってもほとんど知らないであろうが、戦後の東京裁判(昭和二十一年五月~二十三年十一月)の公判中に、おなじ被告席に着席していた、やつれ果てた東条元首相のハゲ頭を、突然、後方から強くたたいた長身の豪傑風の、A級戦犯の右翼論客といえば、あるいは記憶のある人々もあるだろう。
大川博士は、ナチズム(国家社会主義)の理論指導者として、ナチス政治で重きをなしたドイツ哲学者アルフレッド・ローゼンバーグ博士(有名な『二十世紀の神話』の著者、戦後の一九四六年十月、ニュールンベルグ戦犯裁判で絞首刑を宣告、執行された)とならんで、軍国日本の代表的な超国家主義理論家と呼ばれ、A級戦犯に指定されて、スガモ・プリズン入りをしたが、公判中に精神異常をきたして、医師の診断の結果、ついに『発狂』とみとめられて、審理中止をいいわたされた。
かくて彼は、あやうく絞首刑をまぬがれて数年間、精神病院に強制収容されていたが、退院後に、じつはみずから『仮病』を使って裁判をまぬがれたと、堂々と声明して、世間をあっとおどろかせた奇怪な人物である。(彼は結局A級戦犯の裁判を逃れて郷里に帰り昭和32年まで生きた。71歳で没)
この大川周明博士は、明治四十四年、東京帝国大学文学部卒、法学博士の肩書を持った、大正・昭和時代の国家革新運動の大立者であり、昭和七年五月十五日に首相官邸で、当時の犬養毅首相(政友会総裁、七十七歳)を暗殺した、急進的な海軍青年将校一派(陸軍士官学校生徒、民間行動隊多数をふくむ)の有名な五・一五事件の黒幕的人物として、懲役十五年の判決をうけた、熱血の理論家兼闘士であった。 |

国家革新運動の大立者、大東亜主義の巨頭であった大川周明博士。
A級戦犯として捕えられたが、東条の頭を叩くとか異常な言動があって精神病者として釈放された。
|
彼は、はやくから日本主義、大東亜主義、反民主主義を強く提唱して、米英勢力の排撃を大いに主張し、大正八年には極右、国家主義結社『猶存社(ゆうぞんしゃ)』を結成して、狂信的な機関紙『雄叫(おたけび)』を発行、つぎのような目的宣言を発表して、活発な理論、実践の両方面にわたる運動を展開していた。
彼の親しい仲間には後年、皇軍反乱の二・二六事件の黒幕的首謀者として、銃殺刑を宣告、執行された有名な右翼革命家・北一輝(きたいつき)もふくまれていた。
『日本の現状を打破し、日本民族の真精神を発揮し、もって君民同治の革命的大帝国を東亜の天地に建設せん!』
このような思想的立場と、行動的背景を持った大川博士が、日米開戦と真珠湾奇襲大勝の歴史的吉報を聞いて、いかに欣喜(きんき)感激したか、想像にかたくないであろう。
(したがって、戦後に、彼が東京裁判でA級戦犯に指定されたのもムリはないだろう)
彼はその感激を得意の壮重、雄大な健筆にたくして、当時、つぎのように述べている。
『昭和十六年十二月八日は世界史において永遠に記憶せらるべき吉日である。
米英両国に対する宣戦の詔勅は、この日をもって渙発(かんぱつ=公布)せられ、日本は勇躍してアングロ・サクソン世界幕府打倒のために起った。
しかして最初の一日において、すでに、ほとんどアメリカ太平洋艦隊を撃滅し、同時にフィリピンを襲い、香港を攻め、マレー半島を討ち、雄渾(ゆうこん)無限の規模において皇軍の威武を発揚した。
東亜新秩序の破壊を前提とする。東亜旧秩序の破壊とは、東亜における米英勢力の駆逐であり、亜細亜におけるアングロ・サクソン世界幕府支配の打倒である。
かくして事物必然の論理として、日本は米英に対して宣戦するに至った。
世界史は東西の対立・抗争・統一の歴史である。それゆえに世界の戦争史には、不思議なる秩序と統一がある。
人類の歴史的記憶のうち、半ば想像的ではあるが、最初に明確に想起せられたるものは、恐らくトロイ戦争である。
しかしてこの戦争は、実に亜細亜(アジア)と欧羅巴(ヨーロッパ)、東洋と西洋との最初の戦争であった。
ヘロドトス(歴史学の父と呼ばれた古代ギリシアの史家)は、トロイ戦争をかくの如きものと考えたるがゆえに、その大著「歴史」をこの戦争から書き始めた。
そは東洋と西洋との宿命的なる戦争を中心として展開せらるる世界史の序幕であり、爾来(じらい)、戦争の舞台は歴史の進行と共に広大となり、ついに全地球をその舞台とするに至った。
いまやスカマンデル荒野の代りに渺茫(びょうぼう)たる太平洋が、またトロイの代りに尨大なる東亜の天地が、大東亜戦争の壮烈なる戦場となっている。
しかも大東亜戦争は、依然として相対抗する東西両洋の戦いなることにおいて、トロイ戦争(古代ギリシアの有名な伝説的戦争で、スパルタの大軍十万が十年間にわたりトロイの城を攻囲、ついに占領した)と、その世界史的意義を一にする。
あれらは、いま、全身全霊を挙げて、この雄渾なる戦いを戦いつつある。
この戦争の勝敗は、まさに世界史の動向と人類の運命とを決着するものである。
米英亜細亜(アジア)侵略の跡をたどる者は、彼らの支配がいかなる悲惨を世界にもたらすかを明白に認めるであろう』(原文のまま)
|
かくて長年の苦節、苦闘にきたえ上げられた国家革新運動の大立者大川博士は、西欧文明とアングロ・サクソンの金権資本主義を打倒する『聖戦』の世界史的意義を、全日本国民へ強く訴えるために、真珠湾奇襲大勝の直後の、昭和十六年十二月十四日より二十五日まで、十二回にわたりJOAK(当時の日本放送協会の唯一の全国中継ラジオ放送局)から、『米英東亜侵略史』と題する連続講演ラジオ放送で、得意の熱弁をふるった。
いま私の手元にある、当時の大川博士のラジオ放送速記録によると、この注目すべき連続講演放送は、第一日から第六日を『米国東亜侵略史』と題して、
『日米戦争こそ、東洋と西洋との対立、抗争の歴史的帰結であり、この日米戦争における日本の勝利によって、暗黒の夜は去り、天(あま)つ日かがやく世界が明けそめねばならぬ。支那事変の完遂は東亜新秩序実現のため、すなわちアジア復興のためである。アジア復興は世界新秩序実現のため、すなわち人類の一層高き生活の実現のためである。
世界史はこの日米戦争なくしては、しかして日米戦争における日本の勝利なくしては、けっして新しき段階を上りえないのである。
日本とアメリカ合衆国とは、いかにして相戦うにいたったか。
太陽(日本)と星(米国)とは、同時にかがやくことはできません!
いかにして星は沈み、太陽はのぼる運命になってきたか、その経緯をさぐることが、とりもなおさず、私の講演放送の目的である』 |
と、全国民へむけ大見栄を切った。
さすがに彼は、日本有数のアジア通の実践的学者だけに、東条首相以下、政府と軍部要人の紋切り型の、かたくるしい国民への士気激励演説よりも、それははるかに煽動的効果が強烈だったようだ。
さらに第七日から第十二日までを『英国東亜侵略史』と題して、いわゆる英国の三百年にわたる東亜侵略、支配の罪業をあばき立てて、米英撃滅のために、ついに日本が決起した世界史的意義を大いに強調した。
そして彼は、
『大東亜とは日本・シナ・インドの三大国であり、我々日本人の魂こそ三国魂である。
すなわち日本精神とは、大和心(やまとごころ)によってシナ精神とインド精神とを総合せる東洋魂である。
我らの心のなかにひそむこの三国を具体化し、客観化して、一コの秩序たらしめるための戦いが、大東亜戦である。
正しきシナと、よみがえれるインドとが、日本と相むすんで東洋の新秩序を実現するまで、いかに大なる困難があろうとも、我らは戦いぬかねばならない。
いと貴きものは、いと高き価をはらわずば、けっしてえられない。
おもえば、一九四一という数は、日本にとって因縁不可思議の数である。
元寇(げんこう)の難は皇紀一九四一年であり、米英の挑戦は西紀一九四一年である。
私は日本の覚悟と努力とによって、米英の運命また蒙古のそれのごとくなるべきことを信じて、この不束(ふつつか)なる講演を終わることにします』 |
と、全十二日間にわたる大講演ラジオ放送を終わった。
私はこの当時、米国首都ワシントンですでに、連邦検察局(FBI)の手に逮捕、抑留されていたので、この大川周明博士の歴史的な大熱弁を、内地のラジオ放送で聞くチャンスをいっした。
今日、いまは亡き大川博士の名前は、すっかり忘れられ、あるいは、まったく知られずに過去の悪夢のなかへ葬り去られてしまった。
しかし、私は、日本の戦史家の立場より、やはり彼こそ、軍国日本を代表した大東亜理念のたくましき提唱者であり、無定見な東条政府や、大本営のいかなる戦争指導者連中よりも、世界史的な戦争観のめずらしい持ち主であったと思っている。
戦後、わが国では、すでに長年の間、太平洋戦争をただ軍事、政治、外交の面からのみ論議して、思想戦の点をまったく除外、無視していることは、今日の民主主義日本の国民感情としては、もっともに思われるが、しかし、戦時中の狂信的愛国心の正体と、発想を正しく理解するために、最右翼言論人の長老徳富蘇峰翁と大川周明博士の多数の戦前、戦中の発言、著述記録は、十分に再検討されねばならない、と私は信じている。
top
**************************************** |