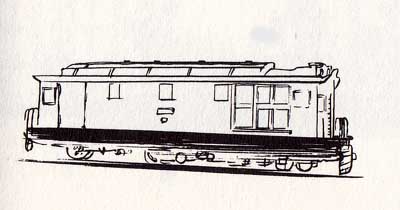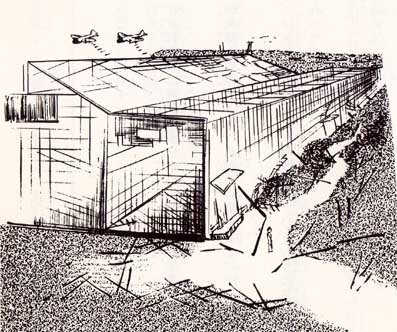|
****************************************
Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ 年譜など
Ⅲ 時代と共に歩む日立
7 時代とともに――大正 top
大正時代は、明治の三分の一、昭和(六十一年現在)の四分の一と短い期間であった。
世界でも日本でも、大きな出来事が相次いでおこっている。
大正三年(一九一四年)の第一次世界大戦、大正九年(一九二〇年)の金融恐慌、大正十年(一九二一年)の東海道線電化計画、大正十二年(一九二三年)の関東大震災などである。
これらの時代の流れの中で、日立製作所は失敗、事故を繰返しながらも、大正の終わり頃には、一流会社としての信用を得るようになったのであった。
浪平自身の職名も変わっていった。
大正の始めのころは、日立製作所主事、四月からは日立製作所所長、そして久原鉱業から完全に独立した九年からは、日立製作所専務取締役となった。
明治四十三年(一九一〇年)日立製作所創業の頃は、働く人の数は四百人足らずであったが、大正末期の頃の人数は、約五千人であるから、十二、三倍の増加ということになる。
しかし故障や事故は、大正時代になっても次々と起きてしまった。
大正四年(一九一五年)の油入遮断機の大爆発事故、大正五年(一九一六年)の二、二〇〇キロボルトアンペア発電機事故、続いて六年(一九一七年)には高速電動機破裂事故が起きた。
この事故では、試験を担当していた従業員が、右足切断という人身事故まで起こしてしまった。
特に五年の二、二〇〇キロボルトアンペア発電機は、日立鉱山に納めるものだっただけに、浪平は、「進退伺 小平浪平」と書いた紙を自分の机におき、いつでも製作所をやめられるように、心の準備をしていた。
高尾も馬場もこの発電機製作の中心だっただけに、浪平の心の中を思い、浪平が製作所を去る時には、自分たちもやめようと決心した。
しかし、二人をよんだ浪平はこういった。
「日立製作所創業以来、発電機や電車のモーターなど大分迷惑をかけてきたし、今回もまた事故を起こしてしまった。
しかし、高尾君、馬場君、責任をとってやめるのは誰にでもできることだよ。ここの所をよく考えて、早く修理にとりかかることが、今一番大切なことだと思う。どうだろう、やってくれまいか。」
二人は早速発電機の修理にとりかかり、完全な形にして鉱山に納めた。
しかし、事故は休みなく起きた。
今度は工場火災である。
大正八年(一九一九年)十一月十四日午前一時、晩秋の寒い夜であった。
日立工場大物工場内の変圧試験場で試験工が二人、徹夜で仕事をしていたが、あまりに寒いのでバケツを火鉢がわりに使っていた。
二人がぬくもりと疲れのため、すこしの間トロトロしていた時、近くの缶の油に火が飛んで、大きな火災となってしまった。
火元の大物工場を始めとして、撚線工場、事務所、倉庫が焼け、その上貨車に積んであった製品も焼失した。
浪平は前の年、大雄院の社宅をひきはらって、東京市本郷区東片町に移っていたが、高尾から工場火災の電報をうけ、五時間汽車にゆられて工場に到着した。
さすがの浪平も、焼けこげた工場を見てぼう然自失し、一言もいわなかった。
しかし、工場の被害状況を聞いた後、高尾や馬場だちと、これからのことについて話し合った。
規模を小さくしてはどうかという意見も出たが、浪平はそばにいた高尾に、
「高尾君、今まで通りやるか。」といった。
高尾は浪平の顔をジッと見てから、「やります。」と力強い声でいった。
再建が決まったのである。
損害百万円といわれたこの大火災も、浪平の激しい意欲をくじくことはできなかった。
浪平はこの火災を「天が与えたお灸」として受止め、仕事の情熱を高めていった。
次の年大正九年(一九二〇年)の三月三日には、日立製作所所属の亀戸工場が火災で焼失し、小型モーター百台が焼けてしまった。
しかし浪平は、電気係長兼消防長の北湯口が謝(あやま)ったのに対して、
「木造だから焼けたのだ。今度は鉄筋コンクリート造りにしよう。」といって、責任も問わなかった。
ここに浪平の、合理主義者としての一面がよく出ている。
事故、火災と大正時代の日立製作所は、数多くの災害に遭いながらも、一歩一歩いい仕事を続けていった。
大正の初め、群馬県の利根川発電は、一万馬力の水車をドイツフォイト社に注文した。
しかし、同五年七月、第一次世界大戦が始ったため、水車を積んだ船が港は出たが行方がわからない。
利根川発電はすっかり困ってしまった。
それを聞いた日立製作所は、天才的な営業マンの大谷が利根川発電に働きかけ注文を取った。
設計は秋田と福元が受持ち、大正五年(一九一六年)見事につくり上げた。
当時の電気機械の業界では、日立製作所の信用はほとんどなかった。
「できるのかね、日立さんに、一万馬力の水車が。」
「頼む方も頼む方だが、請負う方も請負う方だよ。」
「失敗ばかりしている日立さんが、こんな大仕事を引き受けるなんて。」
「失敗することは、初めからわかっているよ。」
「小平さんは気が強いからなあ。」
こんなうわさがとびかったが、それは成功によってピタッととまった。
明治四十五年(一九一二年)入社した倉田は、勝気で積極的な男だけあって、自分の仕事に不満を持っていた。
製作所の首脳は、ほとんどが大学卒業なのに対して、倉田は高等工業学校卒だった。
大正六年(一九一七年)倉田は藤田と相談し、電線製造計画書を小平に提出した。
間もなく倉田は浪平によばれた。
「倉田君、君が提案した電線製造の計画、じっくり読ませてもらった。やり給え。」
「私にできましようか。」
気の強い倉田も、そういわれて一瞬たじろいた。
「お前ならできる。まかせる。」
倉田はうれしくなり、目がポォーとかすんできた。
今までの不満が、霧が晴れるように消えた。
浪平はすべてのものを自分たちでつくる主義だから、外へ注文することもできない。
銅線をつくる機械は、本を見たり大学の先生の指導をうけたりして、まがりなりにもつくったが、故障・修理、故障・修理、の連続だった。
電線を買っていた古河電工から「電線製造を中止するなら、これから十年間の電線による利益をわが社は保証しよう。」
という手紙が届いたが、浪平は、電線製造をやめなかった。
大正七年(一九一八年)の九月には、平角銅線の製作に成功したのである。
大正十二年(一九二三年)九月一日、関東大震災が起きた。
死者二十万、焼失家屋四十万戸という大災害である。
工場長の高尾は、副工場長の柏村以下十四名の東京派遣を決めた。
食料、薬品、マッチ、ろうそく等を持った十四名は、三日の朝、助川駅をたち東京へ向かった。
船による救護班も、会瀬の浜から海路東京をめざした。
本社、亀戸工場、久原鉱業などの被害は少なかったが、東京電灯は、変電所、電線、電柱などが、半分近くやられてしまった。
東京電灯、東京市電、鉄道省などから、復旧のための注文が次から次へと殺到した。
日立製作所が茨城県の田舎にあったということが、幸いしたといっていいだろう。
大震災以来、日立製作所を見る世の中の目が、ガラリと変わった。
「日立さん、なかなかやるわい。」他の電気機械の業者も、一目おくようになったのである。
鉄道省が東海道線電化計画を発表したのは、大正十年(一九二一年)のことである。
その計画にしたがって主なものを、国内の電気機械製作の会社に発注しようとしたが、大型電気機関車は無理なことがわかり、外国製とすることに決めた。
浪平はこの事を知り、心の中に電気機関車製造の夢がふくらみ始めた。
一度決心したことは、必ずやりとげるという、浪平のねばり強さは、ここでも十分発揮された。
大正十二年(一九二三年)二月日立製作所は、電気機関車の試作を決定し、翌十三年(一九二四年)暮もおしつまった十二月十六日、鉄道省大宮工場において、大型電気機関車の公開試運転を行い、大成功したのである。
翌十四年十月十一日、貨車けん引用五十九トン電気機関車三台(一台十六万円)が、鉄道省に買い上げられた。 |

関東大震災で東京、横浜は大被害を受けたが、
茨城県の工場は被害をうけなかった。
そして東京電灯、東京市電、鉄道省などから復旧の注文が相次いだ。
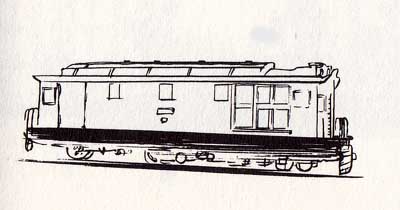
試作した電気機関車を鉄道省大宮工場で公式試運転を行い成功、
この頃はすべて輸入機関車だったが、それから国産化が始まった。
|
8 時代とともに――昭和 top
大正十五年(一九二六年)十二月二十五日、大正天皇がお亡くなり昭和時代となったが、元年は七日間しかなかったので、アッという間に昭和二年(一九二七年)がやってきた。
小平家では昭和にはいるとすぐ、喜びと悲しみが続いた。
昭和二年(一九二七年)の十一月六日、菊の花が秋晴れの下で咲いていた日、二十二歳になった長女の百合子が、茨城県庁の農林課長岡田包と結婚した。
岡田は後日、北海道庁長官にまでなった優秀な役人であったが、浪平は岡田がすっかり気に入ったらしく、
「包(かね)さん、今日からお前は息子になったのだ。」
といって、冷酒をぶどう酒のコップに注ぎながら、水力電気調査のため山々を歩いたこと、鉱山の修理工場から大日立になるまでの苦心、日立市と水戸市の間に工場をつくる計画などを、よく岡田に聞かせた。
岡田と百合子の間には、四人の子供もでき、浪平と也笑はどこにでもいる、よい爺さん、お婆さんになった。
しかし次の年昭和三年(一九二八年)長男の儀平と一緒に栃木に住んでいた母親チヨが、七十五歳でなくなった。
浪平は父惣八から、失敗にめげず仕事をやってゆくひたむきな精神を、母チヨから正直とねばり強さに加えて、弱い者に対するいたわりの気持ちをさずかったのである。
次の年次男の俊平が、兄良平の後を追って、北海道大学予科に入学するため、父母の許をはなれて札幌へ向かった。
小平家にも、巣離れの時がやってきたのである。
関東大震災後日立製作所は、鉄道省、東京電灯、東京市電、大阪市電、京都市電、大同電力、日本電力などからの注文が相次ぎ、断わるのに苦労したほどだった。
しかし昭和二年(一九二七年)の恐慌を境に、注文はバタッととまってしまった。
とくに昭和四年あたりはひどく、十月三十一万円、十一月三十四万円という、どうにもならない状態に追い込まれていた。
そのあおりを受けて電力が余り、水力発電所では水をただ流すという有様であった。
この余った電力を使って、それまで輸入していた窒素肥料を作る会社がつくられることになった。昭和肥料である。
注文がすっかりとだえ、工場では紙の裏まで使い、お客には白湯をだすほどだった日立製作所にとっては炎天の雨とでもいうか、救いの神の昭和肥料であった。
早速営業部が中心となって昭和肥料と交渉し、電解槽二、二五〇槽(後に追加して二、五〇〇槽)の注文に加えて、日立製作所の得意ともいうべき、日本最大の六、〇〇〇キロワット回転変流機十台の注文もとったのである。
電解槽というのは、水を分解してつくった水素と、空気を液化してつくった窒素とを化合してアンモニアをつくり、これに硫酸を加えて硫酸アンモニアをつくる化学装置である。
日立製作所が電解槽をつくるという話は、またたく間に硫酸アンモニアの業界に伝わった。
「アンモニアは、外国の技術、機械がなければ絶対にできっこないよ。」
「それもよりによって、化学装置などつくったことがない日立さんに頼むなんて。」
「昭和肥料の社長も専務もとうとう血迷ったか。」
「川崎(昭和肥料のあった所)でアンモニアの匂いがしたら、首をやってもいい。」
など、昭和肥料、日立製作所をあざ笑う言葉が各地で聞かれた。
昭和四年(一九二九年)浪平は日立製作所の社長に就任したが、昭和肥料の電解槽については、迷いの日が続いた。水素に他の気体がまじって爆発でもすれば、昭和肥料だけでなく、注文を受けてつくった日立製作所の信用も、吹き飛んでしまうことは目に見えている。
しかし浪平は、責任者の馬場にすべてをまかせた。神にも仏にも祈りたい気持ちで、浪平は電解槽の完成を待った。 |

窒素肥料を作る化学工場の電解槽も手掛けることになった
|
責任者の馬場は設計も担当し、昭和肥料から示された図面をもとに研究したが、その図面通りではできないことがわかり、日立製作所独自の設計図面をつくった。
これによって試作品をつくり始めたが、アスベスト(石綿)の貼付や電気溶接など、次から次へとむずかしい問題が出てきて、さすがの馬場もすっかり疲れ、
「わしはやめる。」とまでいったが、高尾になだめられ思い直し、製作を続けていった。
昭和五年(一九三〇年)十月二十七日、言葉ではいいつくせないほどの苦心、工夫の末、四槽ができあがった。
試験してみると、水素九九・八パーセント、酸素九九・六パーセントという、高純度のガスが発生したのである。
馬場を初めとして、電解槽の仕事をした大勢の人々は、手をとり合って喜び、完成祝の酒を飲みほした。
翌昭和六年(一九三一年)六月、電解槽二、五〇〇槽は、日立製作所から昭和肥料に納められた。
前々月の四月、六、〇〇〇キロワットの回転変流機十台も完成し、日立製作所の名前は、日本中に知れわたるようになったのである。
電解槽を完成した次の年、昭和七年(一九三二年)日立製作所はまたまた大きな仕事にとりかかった。
八幡製作所から注文された、圧延用ミルモーターの製作である。
七年の八月から作り始め、翌八年二月に完成、三月納入という、超スピードの仕事であった。
さてできあがったものの、芝内の工場から助川駅に鉱山電車で運び、ここから貨車で九州福岡の八幡まで輪送するのであるから、大変なことである。
当時鉄道の輪送は五十トンまでだったので、これを超すと運んでもらえない。
途中の隅田川駅で測ったら四九・七トンだったので、輪送責任者の社員二人は、ホッと胸をなでおろした。
昭和三年の秋頃から、高尾は浪平の命を受けて、助川駅近くを何回となく歩き、工場建設の土地を探していた。
浪平は高尾にいった。
「工場は現在芝内の山手にある。鉱山電車で製品を駅へ運び出すのも大変だから、助川駅近くに土地が欲しい。」
高尾は驚いた。不景気で仕事もないのに、工場を建てる土地を探すのは、無謀だと思ったからである。
「不景気で、どうにもならないのが現状です。」
そう高尾がいうと浪平は、
「土地というものは、不景気の時買うのが一番いいんだ。」といって、自説を頑として曲げなかった。
会社には金がなかったので、浪平は第一銀行、日本興業銀行に土地を買う資金の借用を申しこんだが、断られてしまった。
困った浪平は日本勧業銀行に申しこみ、三百万円を借りることができた。
この金で浪平は、助川駅近くの海沿いの土地十万坪(約〇・三平方キロメートル)を、五十万円足らずで手に入れ、昭和四年(一九二九年)十一月四日日立海岸工場の地鎮祭を行った。
昭和十五年(一九四〇年)山手工場に近い熊野神社のかたわらに、日立製作所創業三十年を記念して、創業石がつくられた。
長さ三メートル、高さと幅一・二メートルの甲州産御影石に、高尾が書いた「小平浪平氏明治四十三年の秋、茨城県日立村の此地に日立製作所を創業す」、という銅板がはめこまれている。
この石のことを、高尾はできあがるまで浪平には話さなかった。
創業の頃の金看板のように、話を聞けば浪平はきっと、「やるな、俺は嫌いだ。」というにちがいないと思ったからである。
除幕式当日の二月十一日、浪平は招待されて東京から参加し、孫たちによる除幕も見たが、機嫌を悪くしたのか余り口も聞かなかった。
派手な事や目立つ事が大嫌いな浪平の気持ちを、よく知っている高尾や馬場らは、ハラハラしながら式が終わるのを待った。
昭和六年に満州事変、十二年に日中戦争、十四年に第二次世界大戦、十六年に太平洋戦争(真珠湾攻撃)と日本は戦争への道を、加速度的に進んでいった。
日立製作所も軍需工場となり、兵器を生産することになった。
社長の専用車は、パッカード、クライスラーなどの高級車だったが、浪平はベビイフォードやダットサンを愛用し、高級車はほとんど乗らなかった。
軍需工場代表の会議が、東条首相の招きで首相官邸で開かれた時も、浪平は小型車でいったが、帰ってくると秘書の森田に、
「今日はさすがに、今を時めく軍需会社社長の集まりだけに、みんな高級車だった。小型車は僕一人なので、いささか気が引けたよ。」といって苦笑いした。
しかし戦争が激しくなると、浪平は小型車も会社のガソリンを使うからと乗らなくなり、満員電車にゆられてお茶の水駅から通勤した。
昭和十九年(一九四四年) 一月、兄儀平が亡くなった。
浪平よりすぐれた才能をもちながら、家計や浪平の学費のため、医学への道を断念し、片田舎の一銀行員として生涯を終わった兄であった。浪平はこの兄に、一生負い目を感じていた。
昭和二十年(一九四五年)にはいると、アメリカの日本本土に対する空襲は熾烈をきわめた。
三月十日の空襲で、本郷湯島三組町にあった浪平の自宅が、焼夷弾により焼失した。
そして六月十日、日立製作所の日立海岸工場が、B29の爆撃によって何から何までたたきのめされたのであった。
死者六六九名、負傷者一〇三名、日立製作所は人も物も、大きな痛手をこうむったのである。
七月にはいると十八日、水戸、多賀、日立の各工場は、海からによる艦砲射撃を受け、二十日には、日立が焼夷弾攻撃により焼失した。
爆弾、艦砲、焼夷弾を浴びながらも、浪平は焼け野原に立っても事業をやめようとは思わなかった。
そして八月十五日、戦争は終わった。 |
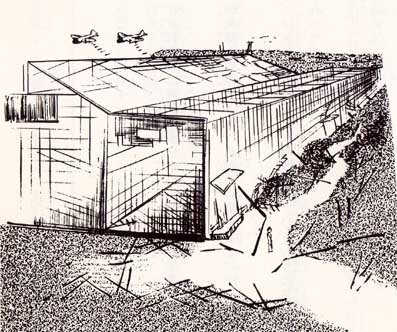
戦争の空襲で日立の工場は多大の被害を受けた。
B29から爆弾が投下される日立工場。
|
9 時代とともに――戦後 top
昭和二十年(一九四五年)十月、日立製作所は軍需生産をやめ、民需品の生産に切りかえた。
しかし六月の爆弾、七月の艦砲、焼夷弾の攻撃により、再起不可能なまでにやられたのである。
クニャクニャにやひん曲がった鉄骨や、ひきちぎられたような機械が、ひまわりの花の向こうに、無残な姿をさらしていたのであった。
「日立もこれで終わりか。」
「こんなにひどくやられては、小平さんもどうにもならないだろう。」
車中の人々は、そんなことをいいながら、爆撃のすさまじい傷跡をながめた。
しかし機械の中には土にうずもれたものもあって、使えるものもけっこうあった。
鍋、釜、パン焼器などが間もなく作られ始め、塩までつくった。
昭和二十二年(一九四七年)三月、浪平は社長をやめ、笠戸工場長をしていた倉田が社長に就任した。
前の月、東京丸の内にあった本社が、GHQに接収されたので、浪平は日立製作所幹部の公職追放を覚悟しての処置だった。
四月二十四日、日立製作所は浪平を始めとして、副社長高尾、専務馬場以下十五名が公職追放に指定された。
浪平は会長だったがそれもやめ、社長の倉田が会長を兼ねることになった。
日立製作所の首脳陣は、根こそぎ追放されたのである。
明治四十三年(一九一〇年)日立の芝内に工場をつくってから三十七年、思ってもみなかったような晩年がやってきた。
浪平は、その年七十三歳であった。
その間、主事、所長、社長として失敗を繰返しながらもここまできた浪平にとって、それは自分が手塩にかけたかわいい子供を、むりやり奪いとられたような、どうにもならない寂しい気持ちであった。
「過去四十年間を回顧すれば欣快(きんかい)の情に耐えざるものあり。」と浪平は日記に記している。
しかしこれは建前であって、本音ではなかろう。
明治の剛直な精神をもっている浪平にとっては、日立製作所から離れることは、正に断腸の思いであったろう。
他の人々には、
「日曜が続いて楽しいよ。」
といっていたが、四十五年近くつれそった妻の也笑には、
「敗けた者はみじめなものだ。四十年間辛苦した会社にも出入りできぬとは。」ともらしている。
これが浪平の心底の声、本音ではなかろうか。
追放中のことであるが、東京常磐橋にあった日立製作所の前を、秘書の森田と車で通ったことがあった。森田が、
「ちょっとお寄りになられてはいかがですか。」というと浪平は、
「僕は事務所へは入れないよ。」といって寄らなかった。
追放中、浪平は東京の小石川に住んでいたが、日課は薪割りと庭の草むしりであった。
平塚の別荘の庭からはこんできた松の木をながめながら、
「これだけあれば、一生薪割りの材料には困らんよ。」といって、「パリッ、パリッ」と小気味よく割った。
薪割りをしていた時、浪平の顔を知らない会社の人がきて、
「爺さん、小平様はいらっしゃいますか。」
とたずねられたことを、やってきた孫たちにおもしろそうに話した。
也笑が、
「あまり精を出すと、体にさわりますよ。」といっても、
「なに、ゴルフのコツと同じだから一向につかれぬ。」といってやめなかった。
長女百合子の末娘真理子がやってくると、浪平は也笑と一緒に、小箱に千代紙をよく貼った。
そのような細工をする時も、几帳面な浪平は、一ミリの狂いもなく精密に貼った。
薪割りをやらない時は、よく上野の博物館に歩いてゆき、ゆっくりと絵を見た。
「金のない我々は、絵を自分の物としないで、ああいう所で見るのが一番いい。」
浪平はそういって、チョイチョイ絵を見にいった。
雨の日は薪割りもできないので、也笑がいれた薄茶を飲みながら、万葉ガナで書かれた「和本太閤記」を読んだ。「わからない字もあるな。」といいながらも、三十何冊を読みつくした。
昭和二十六年(一九五一年)六月二十日、浪平の追放は解除された。
「やっと身が軽くなったよ。」と浪平は喜び、七月から八月にかけて、思い出の土地日立、多賀、水戸の工場を視察した。 |

薪割りをする浪平
|
工場も昭和二十三年(一九四八年)の暮には復興し、前にもましてすばらしい工場になっていた。
続いて八月末浪平は、妻也笑、孫二人をつれて、新潟妙高山の麓にある池の平日立ハウスに旅行をした。
「これからは温泉や芝居見物もできる。長生きしようや。」
旅先で、浪平は也笑にしみじみとそんなことをいった。
池の平から帰って間もない九月の下旬、浪平の右の手首に、梅干し大の腫物ができた。
日課の薪割りも、量をへらしてやっていた。
也笑が病院行きをすすめても、頑として聞きいれない。
しかし二十八日、娘や森田のすすめもあって、病院にいき診察してもらったら「リュウマチ」との事だった。
十月になっても手首のはれはひかず、指の方まではれてきた。
十月四日、病院で診察をしたら、初めて心臓が悪いことがわかったが、大したことはないといわれた。
その夜、夕食をとってから入浴し、也笑と二人で長唄、「ニュース解説」をラジオで聞いた。
午後九時四十分、浪平が也笑に、
「少し変だよ。」
というので、也笑が脈をみると、音がほんのかすかしか聞こえない。
あわてた也笑は、近所の医師やかかりつけの森田院長、娘や息子にも電話した。
しかし浪平は、次の日十月五日午前一時十五分、七十七歳の生涯を閉じた。
いかにも浪平らしい、見事な最期であった。
top
****************************************
|