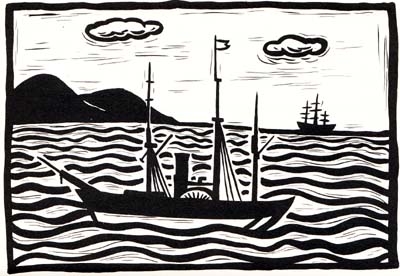|
****************************************
Index その一 その二 その三
真心の人・渋沢栄一(その一)
1 子供は風っ子じゃー top
ぴゅう ぴゅーん
ぴゅーん ぴゅう
体を針でさすような冷たい風が吹いてきます。
ぴゅーん ぴゅーん
冬になると群馬県赤城山(標高一八二八メートル)から、吹きおろしてくる風が、利根川を渡って埼玉県の北部に吹きつけてくるのです。
大人は思わず身震いするというのに、子供たちは冷たい風の吹くなかで、元気よく遊びまわっていました。
どの子も、鼻水をすすっています。
「栄一、風邪をひきますよ。」
と、渋沢栄一のお母さんは、羽織をもって栄一を追いかけています。
栄一は捕まると大変だ、と一所懸命に、逃げるのでした。
栄一が逃げるのは、羽織を着ると体が自由にならないからです。
とうとう鎮守の森の中で、つかまってしまいました。
汗をかいた栄一の頭からは、ポカポカ白い湯気がたっています。ほっぺたは、真っ赤です。
「栄一、風邪をひきますよ。」
お母さんは栄一の顔を、手拭いで力いっぱいふくのでした。そして、羽織を着せました。
また、栄一は友達と遊び回わりました。どうしても羽織が邪魔です。
「子供は風っ子じゃ!」
と、いって栄一は、羽織をポイと脱ぎ捨ててしまいました。
森の中から子供たちの元気な声が、日が暮れるまで、わきたっていました。
子供たちが遊びまわっている土地は、埼玉県深谷市血洗島(ちあらいじま)です。
この土地の名前は現在の地名ですが、栄一の子供の頃は江戸時代で、武蔵国榛沢(はんさわ)郡安部領血洗島村といいました。
栄一はこの村に天保十一年(一八四〇年)二月十三日に生まれました。
村には五、六十戸の家がありました。そのうち十七戸がみな渋沢という姓でした。
同じ姓の家ばかりだから、「中の家(なかんち)」「東の家(ひがしんち)」「西の家(にしんち)」「前の家(まえんち)」などと間違えないように呼んでいたのです。
栄一の家は「中の家」でした。
お父さんの名は市郎右衛門(うえもん)で「東の家」から「中の家」の一人娘、えいと結婚したお婿さんでした。
えいは栄一のお母さんです。
栄一の家は農業と養蚕(ようさん)、それに布地を染める原料の藍玉(あいだま)の製造もしていました。
村人に、お金も貸していました。
お父さんは農民でしたが、学問や剣術を身につけ、俳句もたしなむ風流な人で、村人から尊敬されていたのです。
領主は、市郎右衛門を農民に許されていなかった名前をあたえ、武士のように刀を腰にさす事を許していました。
お母さんのえいは、おとなしく、思いやりの深い人で、人の困っているのを見ると、じっとしていられない人でした。
栄一が五つになったある日の事です。
お父さんは、栄一を部屋に呼びました。お父さんはキチンと座っています。栄一も、キチンと座りました。
お父さんの前に、本立てがあります。栄一の前にも本立てがあります。
お父さんの本立てにも、栄一の本立てにも同じ絵のついた本がたてかけられてあります。
「栄一、偉い人になるには、学問がなければいけません。人の上に立つには、いろいろな知識をもっていなければなりません。いまから、本が読める子になるのです。」
お父さんは、まじめにいいました。
栄一はじっとお父さんのいう事を聞いていました。
「この本は中国の『三字経(さんじきょう)』という本です。この本で、文字を覚えるのです。」
お父さんは、本立ての本をめくりました。お父さんが読むと、そのあとから栄一は、口を大きくあけて、読みました。
この「三字経」は、中国で子供が字を覚えるために使ったテキストです。
人の道や歴史、学問などを、わかりやすく書いた本でした。
お父さんの、手ほどきが始りました。栄一は、友達と一日中遊んでいたいのです。
お父さんの手ほどきは、少し退屈でした。
が、だんだんと文字が読めるようになると、本を読むのがおもしろくなってきました。
教わる本は、だんだんむずかしくなってきました。やがて「論語(ろんご)」を教わるようになったのです。
栄一が七歳になると、お父さんはいとこの漢学者に頼んで、栄一に学問を教えてもらう事になりました。
この学者は尾高新五郎といいます。栄一より十歳年うえでした。
新五郎は学問が好きで、書道と詩も上手でした。
その上剣の心得もあったのです。
江戸時代には学問と文学、それに武道を身につけた人が理想の人物だったので、ちようどその理想の人物が新五郎だったのです。
まだ年の若い青年新五郎は、村人から尊敬されていました。
栄一は今まで、新五郎を親類の「お兄ちゃん」と思っていましたが、今度は栄一の「先生」になったのです。
新五郎の家に通いはじめた頃、栄一はカチカチに緊張していました。
「栄一君、本は寝転んでいても歩きながらでも読めるのだよ。何もかしこまって読むだけではないのだよ。」
といった新五郎は、栄一にやさしい、おもしろい本を読ませました。
いつのまにか栄一は書物が好きになっていました。
栄一を夢中にさせた書物は、江戸時代の小説家、滝沢馬琴(たきざわばきん)の書いた「里見八犬伝(さとみはっけんでん)」や中国の歴史をおもしろい物語にした「通俗三国志(つうぞくさんごくし)」がありました。
栄一が十二歳になった正月の事です。
親類の家に、挨拶まわりをしている時でした。
栄一の家の裏に「清水川」という小さな小川が流れていました。 |

本を夢中で読んでいて、川に落ちた七歳の栄一
|
その川にかけた狭い橋を、栄一は本を読みながら渡っていました。
「あっ!」と栄一が思ったときには、足をはずして、ストンと川に落ちていました。
正月の晴れ着はずぶぬれです。
「おお寒む。」栄一は、身ぶるいしました。
家にいそいで帰ると、家族の人たちは大笑いしました。
「いや、ぬれネズミだ。正月にネズミをお迎えするとは、縁起のよいこと。」
また、お父さんもお母さんも、笑いころげました。栄一はずぶぬれの着物をきたまま、チョコンとしていました。
栄一が十四歳になった時の事です。
栄一のお父さんは、藍玉をつくっていました。地方から藍(あい)の葉を買ってきて、藍玉をつくっていたのです。
お父さんは藍の葉が、良いか悪いかをみわける名人でした。
お父さんは栄一をつれて、藍の葉を買いに地方へ出張しました。
栄一はお父さんが藍の葉を買うのをじっと見ていたのです。
そして、売る人とお父さんが言葉を交ししているのを、ちゃんと覚えてしまったのでした。
ある日の事です。
お父さんは、ほかの用事ができて、藍の葉を買いにいけなくなりました。栄一は、おじいさんとゆく事になったのです。
おじいさんだと、藍の葉を売る人に誤魔化されるのではないかと栄一は思ったのです。
おじいさんを、うまくいいくるめて、その朝は一人で、栄一は買い出しにでかけました。
売る人たちは少年の栄一をみて、
「この子が、このむずかしい藍の葉を見分けられるのかね。」と、からかい半分でした。
ところが栄一少年は、「おじさん、この葉は駄目だよ。肥料がたりなかったね。」
と、からかい半分に出された葉を、栄一は、ビシッと決め付けるのです。
おじさんたちは、ビクッとしました。
それでは、これはどうだ、と次の葉を出しました。
「こいつは乾燥が不十分じゃないか。」と、栄一はいいました。
おじさんたちは、またビクッとしました。
「この子の目を、誤魔化す事はできない。」と、おじさんたちは思いました。
「いや、市郎右衛門さんの跡取だ。さすが目ききの子供だけある。かしこい子だ。将来、大物になるぞ。」
と、おじさんたちは、お互いに話しあっていました。
その日、栄一は上質の葉を安く買ってきたのでした。
栄一が十六歳のときでした。
お姉さんが、長いこと病気にかかっていました。
お父さんは、病気の保養のために、群馬県の温泉宿に、お姉さんを連れてゆきました。
お父さんが、留守しているのをよい事に、親類のおばさんが、栄一のお母さんにいいました。
「娘の病気は、何かタタリがあるにちがいないよ。行者に占なってもらいなさいよ。」
と、いっておばさんは、一人の女の行者(ぎょうじゃ)を連れてきました。
行者は棒についた紙をふりまわして、さかんに指を組んだり、薄気味の悪い呪文(じゅもん)を唱(とな)えるのでした。
栄一たちの家族のひとたちは、かしこまって頭をさげていました。
「無縁(むえん)ぼとけのタタリじゃ。早く祭らなければ娘の病気はなおらぬ。」
すると栄一は、いきなり、
「無縁ぼとけの出たのは、何年前の事ですか。」
「それぱ、五、六十年前のこと。」と、行者はこたえました。
「年号は何といいますか。」と、また栄一はききました。
「うん、それはじゃな。天保三年ごろ。」
栄一は、小首をかしげました。
栄一が生まれたのぱ天保十一年だったから、天保三年は栄一の生まれる八年前の事になります。
栄一は十六歳です。十六に八をたすと、二十四になります。
暗算は、お父さんと藍の葉を買う時、値段をきめるのにすばやく暗算ができなければなりません。
栄一はお父さんについて、暗算の勉強をしていたのです。
「天保三年は今から二十四年前です。無縁ぼとけのことまでわかる人が、こんな簡単な年号を間違えるとは、おかしい。そんなオツゲは信じられません。」
と、栄一はいいました。
家の者は、どうなることかとハラハラしていました。
「うーん、おかしいことよ。キツネが乗りうつったのかな。」
といって行者は、コソコソ帰っていきました。
お母さんは「人の困る事は、いうものではありません。自分だけで思っていればよいのです」と栄一をいましめました。
栄一が十七歳のときでした。
風邪で寝ている栄一のお父さんのところに、陣屋から呼び出し状がきました。陣屋というのは、役所の事です。
栄一の住んでいる血洗島村は安倍(あべ)摂津守(せっつのかみ)という小さな大名が支配していました。
その陣屋が、隣村の岡部村にあったのです。
「栄一、もうおまえは武士であれば、元服(げんぷく)をとうに過ぎた立派な大人だ。私のかわりに出頭しておくれ。」
と、お父さんは栄一に名代(みょうだい)を頼みました。
「お父さん、心配しないでください。陣屋にいってまいります。」
といって、栄一は、元気よくでかけました。
親類の名主の渋沢宗助も呼び出されていました。
役人は一段高いところから、偉そうな顔をして、すわっている栄一と宗助を見おろしています。
「エヘン、ごくろうである。
実はこのたび、殿さまのお姫さまがおこし入れ(お嫁にゆくこと)あそばされる事にあいなった。
ついては、なにかと費用がかかる。その方どもに御用金を申しつける。
渋沢宗助は千両、渋沢市郎右衛門(栄一のお父さんのこと)は五百両。
おめでたい御用金、名誉この上ないこと。ありがたくお受けするように。しかと申しつかわすぞ。」
「へっへっー。」
宗助は地べたに額をすりつけるように、頭を下げました。
栄一は、「父のかわりにきましたから帰って父に申し伝えたうえ、ご返事をします。」と答えました。
「なにを、たわけた事を申すな。その方いったいお上の御用を何と心得ているのか。
十七にもなれば、いっぱしの大人。もっと分別を出せ。すぐさまお受けいたせ。」
役人は真っ赤になって怒りだしました。
「父に申し伝えましたうえで……。」
栄一は、同じ言葉を繰返しました。
「なにお、百姓の身分で、ここをどこだと心得ておるのか。」
役人は、ますます、声をあらだてるのです。それでも栄一は、一歩も引きません。
とうとう役人は、根まけしてしまいました。もし断わられると、その役人は上役に叱りとばされてしまうのです。
「そうか、そうか、帰って、父上に伝えるがよい。」
と今度は、手のひらを返したように、いいました。
栄一は陣屋の帰り道、役人の態度に腹がたってきました。
えらそうに怒鳴りちらす人間、農民からお金をもらうのがあたりまえという役人、「お姫さまの嫁入りのお金を出すのをおりがたく思え」といった役人の考え方、栄一は思いつめているうちに、
「このばかやろう!」
と、怒鳴りたくなりました。
家に帰った栄一はさっそくお父さんに陣屋の事を話しました。
「腹のたつ事はよくわかる。お上と百姓の関係は今すぐ、どうにもなる事ではない。
やたらに反抗しても、あとで意地わるされては損だ。このたびはまあ、お引き受けするよりしかたあるまい。」
といってお父さんは、栄一をなぐさめました。
一本ぎな栄一は、お父さんに役人の事をいわれましたが、どうしても納得しません。
自分の考えを本当にわかってもらえる人は、新五郎先生だと思いました。
翌日、栄一は新五郎をたずねました。
新五郎は栄一をみると、ニコッとしました。
「栄一君、君は立派だ、感心したよ。」と新五郎はいいました。
陣屋の話はもう、村中にひろまって、新五郎の耳にも入っていたのです。
「結局、政治が悪いのだね。役人も人間、お殿さまも人間、農民も人間、同じ人間だから、お互いにいたわりあわないといけないな。いばりくさっている人間をたくさんつくった幕府がいちばん悪い。」
新五郎は、かみしめるように、栄一にいいました。
栄一は胸がすうっとしました。さすが天下の事をしっている先生だと思いました。
新五郎の家から外にでた栄一は、そのまま家の裏の崖の上に、一人ポツンと座っているのでした。
栄一は少年時代、悲しい事があると、この崖の上にきて、心をなぐさめるのでした。
崖の上にいると、はたおりの音がきこえてきます。そして糸がまの煙がスーとたってきます。
辺り一面は桑の葉の緑の海原、その上に高くそびえる赤城、榛名(はるな)、妙義(みょうぎ)の山々、遠くに浅間、黒髪の山が連なっています。 足の下をのぞくと、深くすんだ淵の水があります。
山と緑の海原と淵の水の雄大な風景をみつめていると、栄一少年の心は大きくふくれあがるのでした。
栄一の心を救ってくれた淵の水にちなんで、栄一は十六歳の時、「青淵(あおぶち)」という号を自分につけたのです。
新五郎に元気をつけてもらった栄一は崖の上で「政治が悪い、幕府が悪い、農民をいじめる幕府を倒すのだ!」と、大声で、叫びました。 |

崖の上に座って、世の中のことを
考える17歳の栄一
|
2 江戸は黒船で大騒ぎ top
栄一の家から北へ二キロのところに利根川が流れています。
その川にかけた上武大橋の東側一帯は、江戸時代に、中瀬(なかせ)という河岸(かし)がありました。
河岸は船つき場で、船から人や荷物をあげたり、おろしたりするところです。
利根川は江戸時代には船の交通機関に利用され、江戸から荷物をつんだ船が江戸川を上り、利根川に入ってこの河岸に船をつけたのです。
ちょうど、中瀬河岸は利根川の上流と中流を結ぶ大きな基地の役目をしていました。
江戸から来るときには船は帆をいっぱい張って上り、下るときには、帆をたたみ埼玉県や近県から集めた野菜や穀物、生糸などをたくさん積んで、江戸に運びました。
江戸末期頃には一日に五十隻から百隻の船がつきました。
回船問屋や船頭宿もできて、旅館が十五軒もでき、船にのってきた人や旅人でにぎわったところです。
江戸からきた旅人や商人は、江戸の町でおきたいろいろな事件や噂やニュースをいち早くとどけてくれるのでした。
人から人へと新しいニュースは、すぐ、栄一の村にも伝わってきたのです。
栄一が十三歳のときの嘉永六年(一八五三年)、アメリカのペリー提督(ていとく)が艦隊をひきいて、神奈川県の浦賀(うらが)港に現れました。
「黒船が来た、黒船だ。」
今まで、みた事もない軍艦に、日本人はどぎもをぬかれて、江戸がひっくりかえるようなさわぎになりました。
この大ニュースが中瀬河岸についた人達から伝えられて、栄一の村にも拡がりました。
翌年の安政元年に、またペリーは東京湾に現れて、下田、函館を開港する日米和親条約をきめました。
この条約によって、外国とつきあわない政治をしていた徳川幕府が、初めて外国とつきあう事になったのです。
「夷狄(いてき)、紅毛(こうもう)人とつきあう幕府は、けしからん。」という人。
「外国とはつきあっていかねばならない。」と、いう人。
日本国中で、この二つの意見がするどく対立しました。
そして四年すぎた安政五年(一八五八年)幕府は、アメリカの外交官ハリスと日米修好通商条約を結び、貿易の自由をみとめました。 |
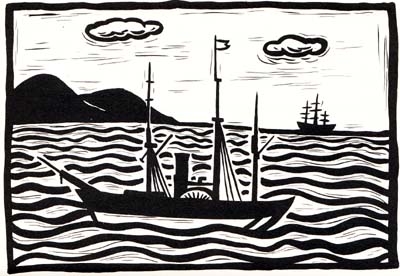
栄一が13歳の時、アメリカの黒船が浦賀にやっていきて、
それ以来日本は、尊王攘夷派が騒ぎ始めた。
|
また、オランダ、ロシア、イギリス、フランスとも、通商条約を結びました。
この条約は、朝廷の許しを受けないうちに、幕府が勝手に結んだと、尊王攘夷(朝廷を中心に政治をする事、そして外国とつきあわない事)の人たちを、カンカンに怒らせてしまいました。
「幕府を倒すのだ!」
日本の尊王攘夷の指導者たちが、密かに連絡をとっていました。
この動きに気づいて驚いた幕府は、アメリカなど五ヵ国と条約を結んだその年に公卿(くげ)、大名、志士(しし)の百余人を捕まえ牢屋にいれました。
つかまった吉田松陰(しょういん=山口県出身、尊王論者)、橋本左内(さない=福井県出身)、頼(らい)三樹三郎(みきさぶろう=広島県出身、儒者、頼山陽の子)たち八人は死刑になりました。
この事件を「安政の大獄」といいます。
江戸の大事件のニュースは、すぐ栄一の耳に入り、栄一はすばやく新五郎の家に飛び込みました。
「先生、タッタッ大変です。幕府が、勤王の志士たちを、捕まえました。」
栄一は胸をはずませていいました。
新五郎は、口をかたく結んでいます。新五郎も大事件をしっていました。
「いよいよ、幕府を倒す時がきたね。」新五郎は、低い声で栄一にいいました。
儒者の新五郎は、水戸の朱子学(しゅしがく)を学んだ人で幕府をたおす勤王の志士だったのです。
栄一は新五郎から学問を学んでいるうちに、新五郎と同じ考えの勤王の志士になろうとしていたのです。
陣屋で栄一が役人に馬鹿にされた時、幕府の政治が悪い、幕府を倒してやろうと強く思っていたところに、またその翌年、ペリーが来て条約分結び、栄一は「外国人を追っぱらえ」とさらに感情をたかぶらせていました。
「先生、いよいよ、やりますか。」
栄一は、まわりをうかがうように目をするどくして、新五郎の耳元でいいました。
「もうすこし、幕府の動きをみていよう。栄一君、この事は秘密ですよ。」
「はい。」
栄一は、うなずきました。
新五郎と彼の弟、長七郎と栄一の三人はよく藍玉(あいだま)を売りに、上州(じょうしゅう=群馬県)信州(しんしゅう=長野県)秩父(ちちぶ)地方へ旅にでかけていました。
商売といっても、三人は旅をしながら漢詩をつくったり、天下国家を論じたり、青年らしい旅を楽しんでいたのです。
旅をしながら新五郎は、幕府をたおす同志を集めていたのでした。
長七郎は江戸で、海保(かいぼ)という人の塾に入って勉強をしました。
そして天下の志士たちと話しあっていました。
長七郎はずば抜けて、剣術が強い人だったのです。幕府を倒す運動にも参加していました。
栄一も家業が暇になった時、お父さんの許可をもらって、二度も江戸へ出かけ、海保塾で勉強しながら、志士たちとお友達になりました。
栄一の様子がどうもおかしいと思ったお父さんは、家業をまじめにしてもらいと思って、栄一が十八歳の時、新五郎の妹、十七歳のちよを嫁にしました。
しかし栄一は妻をむかえても、家業より天下国家の事に熱中しているのでした。
また江戸で大事件がおきました。
栄一が二十歳のときの万延元年(一八六〇年)三月三日、開国をすすめる幕府の大老、井伊直弼(いいなおすけ)が、江戸城の桜田門(さくらだもん)の外で、水戸藩と薩摩藩の浪士十八人に殺されたのです。
この事件を、「桜田門外の変」といいます。
この暗殺事件で、幕府は天下を治める力が弱くなったと地方の藩主たちに思われては大変な事だと、天皇家と徳川将軍家が親類になる事を考えるようになりました。
この考えを「公武合体論(こうぶがったいろん)」といいます。
そこで幕府の努力で、文久二年(一八六二年)仁孝(にんこう)天皇の皇女、和宮(かずのみや)さまが十四代将軍徳川家茂(いえもち)のお妃(夫人)になられました。
ところが尊王派の志士は、「幕府は思い上っている」と、猛烈に反対しました。
とうとう、文久二年一月十五日、水戸浪士や武士をまじえた七人が、江戸城の坂下門外で、老中の安藤信正(あんどうまさのぶ)を襲いましたが、暗殺は未遂におわりました。 この事件を 「坂下門外の変」といいます。 |

栄一が20歳の時、井伊大老の暗殺事件でひっそりと
してしまった江戸の町。その後、幕府をめぐる事件から、
23歳になって倒幕の志士として、江戸に旅立つ。
|
江戸市中は、大さわぎです。号外のかわら版が飛ぶように売れます。
かわら版は栄一の村にも持ちこまれてきました。
新五郎の家の二階には栄一、長七郎それにいとこの渋沢喜作が新五郎をかこんで、四人はかわら版をみつめていました。
栄一は二十三歳、立派な青年になっていました。 「いよいよ、僕たちの出ばんだ。」新五郎がいいました。
四人の目が、一段と輝きました。
「いつ、決行するのですか。」栄一は、新五郎にききました。
「十一月二十三日、冬至の日に、兵をあげよう。」
三人の目を、かわるがわる押えて、新五郎がいいました。
コト、コトと下からかすかな音がしました。
「しっ」
新五郎は腰をおって、ジッと耳をそばたてました。手は刀の柄(つか)を握っています。長七郎も刀の柄を握っています。
「ネズミのようだ。」
新五郎がいうと、三人はほっとしました。
この討幕の計画は、新五郎が総大将、栄一、長七郎、喜作は参謀格。
総勢六十九人で高崎城をのっとり、その勢いで一番手薄な鎌倉街道をつっぱしって横浜へ、横浜の町を焼き払って、異国人を斬り殺し、それから徳川幕府をやっつける、というものでした。
江戸から槍や刀、着込みなどを取りよせて、新五郎と栄一の家の倉に隠していました。
長七郎は、京都の様子を偵察にでかけました。
九月十三日、栄一はさりげなく、月見をしながら詩をつくろうと、新五郎と喜作を家に呼びました。
実は討幕を決意したからには、たとえ命があっても家にいられないから、お父さんに家を継ぐ人をきめておきたいと栄一は思ったのです。
「家を出て、政治運動に加わりたいと思っています。」
栄一は、お父さんに、うちあけました。
「国をおもう心は立派だが、まだ、その時期でない。」
お父さんは、栄一たちにいいました。
お父さんは勤王の漢学を勉強した人だから、栄一たちのいう事は、よくわかっていました。
「ぜひ、させてください。」
新五郎と喜作が、栄一にかわっていいました。
お父さんは、いいました。
「駄目だ、栄一は、私の家の跡取です。」
「お父さん、私を勘当してください。」
「それは、ならぬ。」
と、お父さんはいいました。
十三夜の月は、深くすんでいます。そして四人の顔を青白く照らしていました。
お父さんは考えこんでしまいました。
東の空が、しらじらと明るくなってきました。
「お前は、お前の道をゆくがよい。家の事は心配するな。」
うなだれていたお父さんは、さっと顔をあげて、栄一にほほえみかけていいました。
「お父さん、ありがとうございます。」
栄一はすわり直して畳に両手をつき、ふかぶかと頭をさげました。
お父さんに討幕の心を理解してもらった栄一は、新五郎たちと京都にいる長七郎の帰りを、今日か明日かと待っていました。
長七郎は二人の志士をつれて役人たちの目をごまかし、やっとの思いで帰ってきました。
その年の十月二十九日の夜、新五郎の家の二階に、栄一たち六人が集まって、秘密の会議を開きました。
長七郎は討幕の情勢がかわったから、高崎城を乗っ取る計画は止めたほうがよい、といいました。
喜作と栄一は、あれほど討幕に情熱をかけていた長七郎のかわりぶりに、怒りがこみあげ、はげしい議論がつづきました。
「無念であるが、しばらく天下の形勢を見る事にしよう。」
と、新五郎が、最後の判断をして、高崎城乗っ取り計画は中止する事になったのです。
栄一たちの動きに、役人たちが疑いをもっている様子で、栄一と喜作はお伊勢まいり(三重県)をするからといって、雲がくれする事になりました。
栄一は妻の千代に「お伊勢まいりに行ってきます。」といっただけで、文久三年十一月十八日、住みなれた村を離れる事になりました。
3 敵につく、何故か? top
栄一と喜作はお伊勢まいりの途中、京都によって、一橋慶喜(ひとつばしよしのぶ)の用人、平岡円四郎をたずねました。
平岡とは、二人が江戸で勉強をしている時、何度も会っている人でした。
慶喜は皇居(京都御所)を守る一番偉い人でした。
京都には勤王の志士たちが集まっています。
栄一は同志たちと討幕の事で、心のゆくまで話しあっていました。
長七郎のいったとおり、徳川幕府は一時より安定している事をしったのです。
希望に胸をふくらませて京都にきたものの、討幕の目標をうしなって、二人はがっかりしていた。
ある日、勤王の志士から「外交の事で近いうち、幕府は倒れるに違いない」と情報をもらいました。
栄一はこおどりして、郷里の長七郎にこの情報を手紙に書き、至急、京都にきていろいろと幕府を倒す作戦をねろう、と書き込み、長七郎におくりました。
長七郎は栄一の手紙を受けとると、ニコッとしました。
「さあ、時機到来だ、京都へゆくぞ。」
長七郎は飛びあがりました。
長七郎は栄一の手紙を胴巻に入れ、二人の志士をつれだって、三人は京都に急ぎました。
ところが途中で飛脚(ひきゃく)風の男がすれちがった瞬間、どうしたことか長七郎は、一刀のもとに、その男を切り倒してしまいました。
あまりにも見事な早業に、二人の志士はあっけにとられました。
三人が道中を京都へいそいでいるところ、役人につかまってしまいました。
三人は、江戸の伝馬町の牢屋に入れられてしまいました。
そして栄一の手紙は、役人に取上げられてしまったのです。 |

倒幕の動きに苦慮している一橋慶喜。
その用心の平岡円四郎の縁で、
栄一は一橋家に仕えることになる。
|
長七郎は牢屋の役人をだまして、栄一と喜作に栄一の手紙が取上げられたいきさつを書いた、手紙を出す事ができました。
長七郎の手紙を手にした栄一と喜作は
「じきに白分たちを捕えに役人がくる。このまま京都にいられない」と思いました。
どこに逃げたらよいか困りはてている二人のところに、平岡円四郎から呼び出し状がきました。
平岡は、手紙の一件を二人から聞きました。
「ここに一つ助かる道がある。本当に一橋家の家来になる事だ。どうだ、慶喜公に仕える気はないか。」
平岡は、二人にいいました。
二人は悩みました。
しかし、一橋家は水戸家につながる尊王の家柄、そこに仕えれば、徳川の内部から討幕の気運を高める事もできる、と栄一は思い、喜作をなだめて二人は、元治元年(一八六四年)二月、慶喜の家来になったのです。
そこで牢屋に入れられることから、逃れる事ができました。栄一は二十四歳でした。農民から武士になったのです。
仕事は奥口番(おくくちばん)、用談所の下働きです。
慶喜が政局の中心になって活躍しているので、用談所の仕事は、やる気があれば、次から次へと仕事があります。
栄一は、一所懸命に仕事をしました。
栄一の仕事ぶりをみていた平岡は「やっぱりわしの見込んだ青年だけある。よく仕事をするわい」と喜んでいました。
ある日、栄一は平岡の極秘の仕事をする事になりました。
それは薩摩藩の動きと、その藩で築城法にたけている折田(おりた)という武士を調査する事でした。
一ヵ月ばかりで、栄一の調査は終わりました。
折田は弁舌の巧みなわりに築城法の専門知識を持っていないこと、西郷隆盛と文通している事を鼻にかけているがさほど薩摩藩に重じられていないこと、などから一橋家で抱えるほどの人材でない事を栄一は報告しました。
平岡は、栄一の報告に感心したのです。
「すばらしい。この青年は、大物になる。」
平岡は思いました。
そこでまた大切な使いを栄一に頼みました。
京都の相国寺にいる西郷隆盛に書面を渡す役です。ただ会うだけでなく話しもしてこいというのです。
西郷は三十七歳、身分は軍事の司令官、薩摩藩の京都代表でした。
西郷は時勢の動きを注意深くみつめているときでした。
西郷は、栄一をみると、
「いや、ご苦労さんです。サアサア、こちらへどうぞ。」
人なつこく、栄一を招くのでした。
二人は、話しがはずんで、お昼になりました。
西郷は好物の豚鍋を出しました。
(牛や豚は外国人の食べるもの、日本人が食べるものでない、とその頃の日本人は思っていたのです。)
それなのに西郷さんが豚を食べるなんて、とても攘夷の人とは思えない、と、栄一は思い、不思議でなりませんでした。
「同じものば食わんと、外人と戦しても勝目はごわさん。」
西郷は栄一の顔を見ながら大声で、笑うのでした。
栄一は、正直にものをいう。西郷も正直にものをいう。二人は、話に夢中になりました。
「この青年は、観察が鋭い。そして器が大きい人じゃ。」
西郷は栄一の人柄に、ほれてしまいました。
「また、会いましょう。おはん、おまえさんが、好きになりもうした。」
「また、私をご指導ください。」
と、栄一は西郷にいって別れました。 |

倒幕派のリーダー西郷隆盛。
栄一は平岡から、西郷に手紙を渡し、
直接話もしてくることを命じられる。
|
その後、栄一は平岡の使いで、諸藩や公家の屋敷に出され、相手の動きもさぐらされました。
今度は、栄一が計画をたてて「関東人選御用」という仕事で人材を集める事になりました。
京都から江戸に出て、それからお父さんや妻子のいる血洗島村に立ち寄ろうと思い、密かに一人の使いを出しました。
使いが戻ってくると、栄一たちを岡部藩が捕えようとしている事がわかりました。
密かに家族の人たちとは、宿根(しゅくね=深谷市)で、お父さん、妻の千代、娘の歌子に会いました。
栄一が立派な武士になっているのに、お父さんはうれしく思いました。
初めて、栄一の武士の姿をみた妻の千代は、びっくりしました。
武士はいつ主君のために、死ぬかしれません。妻の千代は、その覚悟ができました。
「時局が混乱している。いつどうなるかわからない。慶喜(よしのぶ)公のために働きなさい。もう、会えぬかもしれない。」
お父さんは、涙をおさえて栄一にいいました。
妻の千代と娘の歌子は、栄一との別れがつらくてつらくて、栄一にいつまでもすがっているのでした。
栄一が京都に戻ってみると、平岡円四郎は暗殺されていました。
そして黒川嘉兵衛(かひょうえ)が一橋の用人筆頭になっていました。
黒川も栄一と喜作の二人を、大切にしてくれました。
慶応元年(一八六五年)三月、二十五歳の栄一は、農兵を集める仕事にでかけました。
栄一の知恵で、予定の約五百人が集まりました。
栄一は慶喜の前に直接呼び出されて、
「篤太夫(とくだゆう=栄一の武士の名)ご苦労であった。褒美(ほうび)をとらせるぞ。」
と栄一の苦労を慶喜はねぎらい、ほめたたえました。
幕末の政治の動きはめまぐるしく、徳川幕府も二度ほど、長州征伐をしました。
二度めのときには、「勘定組頭(かんじょうくみがしら)」の栄一は「御出陣中、御使番(おつかいばん)兼帯(けんたい)」を申し渡され、慶喜にしたがって慶応元年(一八六五年)五月、出征しました。
このとき栄一は、妻の千代に手紙と懐剣を送ったのです。
出陣するからには戦死しないともかぎりませんので、その遺品だったのです。
ところが翌慶応二年、大阪城で将軍家茂が急に亡くなり戦争は中止になりました。
そして、十五代将軍に慶喜がなったのです。
討幕の一念で、今まで辛抱してきた栄一と喜作は、大変びっくりしました。
このままだと敵方の幕臣(ばくしん)になってしまうのです。
その政変のまっ最中に、大沢源次郎という幕臣が、薩摩藩の武士と通じあって、陰謀をたくらんでいるという噂がたち、陸軍奉行は、栄一に大沢を捕えて、訊問するように命令を出しました。
大沢は剣術にたけ、共謀者も武器をもっているといわれましたので、栄一に、新撰組をつける事にしました。
栄一は隊長の近藤勇に会いました。近藤は副隊長の土方(ひじかた)歳三と五人の隊士を栄一につけました。
大沢のいるのは寺です。
寺の門まできました。栄一たちは、ピタリと足音をとめました。
「まず拙者らが踏込み、大沢をとらえる。そのあと、貴公が奉行の申し渡しを伝えよ。」
土方歳三が栄一にいいました。
「それはよくない。まず拙者が踏込み、申し渡しを伝える。」
「いや、大沢は死にものぐるいで、抵抗してくる。貴公ではあぶない。ここは我々新撰組におまかせを。」
「今日の役は拙者が正使、貴公らは副使、正使が奉行の命令を伝達しないうちに、副使が先に踏込んでは、役目の筋道が立ちませぬ。」といって、栄一は一人で大沢のいるところに乗込みました。
「陸軍奉行の名代で参った。」
栄一は目を鋭くして大沢に伝えた。
すると大沢は覚悟していたようで、すぐ栄一の申し渡しに従いました。
「渋沢さんの勇気に感心しました。」土方は栄一にいいました。
近藤勇もこの話をきいて、
「渋沢さんの勇気は、役目の筋を通した捨身の姿ですぞ」と近藤勇隊長は隊士たちに語ったそうです。
本当ならば栄一は、新撰組に斬られていたかもしれません。
たまたま、慶喜が徳川将軍になったため、幕臣にされていたから助かったのです。
栄一は幕府の役人を辞めようと考えていました。
ところが、その年の十一月、慶喜の弟昭武(あきたけ)がフランスのパリで開かれる万国博覧会に出席する事になり、そのお供をするようにと、慶喜は栄一に命じました。
栄一にとっては、全く考えてもいなかった事です。よく考えてみました。
日本は今、変りつつあると栄一は、肌で感じていました。
外国をよくみてこないで、ただ外国人を嫌うのは、間違いだと考えました。
栄一はいつまでも、同じ考えをしている人ではありません。
自分の考えが狭いと思ったら、すぐ直してゆく人です。
「パリ?」
今まで見た事もない外国の町を見られると思うと、栄一の胸は大きくふくらむのでした。
4 花の都パリヘいく top
慶応三年(一八六七年)二月十五日、栄一は一行にまじって、横浜港からフランス船「アルヘー号」に乗って、一路パリヘむかいました。
栄一は二十七歳でした。船の中は快適です。
初めてコーヒーを飲みました。パンを食べました。バターがでました。西洋料理もでました。
出されるものは、どれも初めて口にするものばかりでしたが、おいしく食べました。
「国が変れば、食べものも変るわい。」
栄一は出されるものがすべてめずらしくて、目をキョロキョロさせました。
「相手をよくしらないで、軽蔑する事はよくない事だ。」
栄一は、教えられるような気がしました。
気の早い栄一は香港についた時には、「郷に入れば郷にしたがえ」ということわざのように、栄一は出発するときもらった燕尾(えんび)服と縞のズボン、それに、あわてて買った古い革靴をはいて、デッキに現れました。
頭は丁髷(ちょんまげ)です。 |

羽織はかま、チョンマゲ姿で出発した栄一
|

モーニング姿で山高帽、
ステッキを持って帰ってきた栄一
|
この姿で栄一は得意になって町を歩くつもりでした。
栄一のおかしな姿をみていた外国人が、ソッと栄一を船室に戻しました。
「渋沢さん。その服は儀式のとき着るものです。お取換えなさい。」
外国人は親切に教えてくれました。
「なるほど、洋服にもふだん着と礼装用とがあるのですか、ありがとう。」
栄一は、外国人にお礼をいいました。
香港(ほんこん)に上陸して町を見物した栄一の一行は学校、病院、造幣局(ぞうへいきょく)などをみました。どの建物も、立派でした。
「外国はすばらしい。学ぶ事がたくさんある。パリにいったら、さぞ文明の香りを、たくさん嗅ぐ事ができるだろう。」
と、栄一は、感心するばかりです。
一行はサイゴン、シンガポール、セイロン、アデン、スエズ、マルセイユ、リヨンを経て、パリヘ四月十一日に着きました。 横浜を出てから五十六日めです。
パリで万国博覧会の式典に参列しました。
参列者は各国を代表するえらい人ばかりです。
ナポレオン三世とも会見しました。
オペラを見物しました。
栄一は只々、珍しいものばかりで、ビックリ仰天しました。ただ、ビックリしているだけではありません。
栄一は、郷里の新五郎に手紙を書きました。
「西洋の開化文明は、聞いていたより数倍も上で、驚き入るばかりです。
日本にいては、とても想像もつかないくらいです。
私は外国に深く接して、よいところを学びとり、わが国のために役立てるよりほかありません。
このままでは、日本は孤立する事になるのではないかという思いを深くしています。」
と、栄一は書きだして、パリの街で見たガスと水道と下水道のすばらしい事にふれていました。 |

パリの万国博会場
多くの外国の知識を得て帰国した日本は、
幕府が敗れ恩人の慶喜がお寺に一人、籠っているのを知る。
|
栄一たちはパリからスイス、オランダ、ベルギー、イタリア、イギリスを訪問しました。
栄一は、なんでも見てやろうと、元気いっぱいでした。
この旅行で、いちばん強く栄一の心をとらえたのは、つぎの三つの事でした。
一つは、パリの銀行家に、肌で株式会社の仕組みを教わった事です。
銀行や会社が、多くの人からお金を集めて、大きな仕事ができる事です。
会社が利益をあげると銀行や会社に預けたお金は、預けていた時より増えて預けた人に返ってきます。
これは、国を豊かにする事になるのです。
庶務会計係の栄一は、昭武一行のお金をフランスの公債と鉄道会社の公債にかえていました。
日本に帰る時、公債をお金にかえると、お金はふえていたのです。これには、栄一もびっくりしました。
栄一は日本に帰ったら、この仕組みをさっそく使ってみようと、心を強くしたのです。
二つめは、フランスには日本のように武士や役人を大事にして、庶民をいやしく思う官尊民卑がない事でした。
三つめは、ベルギー国王レオポルド一世の言葉でした。
「日本は、これから強くなるためには、たくさんの鉄を使わなければなりません。
私の国は良質の鉄を多くつくっています。だから、あなたの国で鉄を使うときは、ベルギーの鉄を、使ってください。」
国王が、昭武(あきたけ)に熱心に話していました。
当時の日本では身分の高い人は、お金のことや商売の事を口にだすと、品位がさがるといわれていたのです。
ベルギーの国王が、セールスをしているのですから、栄一は考えこんでしまいました。
しかし、よく考えてみると、国王はその国民を代表しているのだから、国の利益を守り、国が栄えるために力をつくすのが、当然の事でした。
「ベルギーの国王はえらい。」
栄一は一人で感心しました。
栄一がパリにいる時、ついに二六六年続いた徳川幕府が倒れました。
天皇を中心にする新しい政府が生まれたのです。
栄一たちは、急いで日本に帰りました。
明治元年十一月三日に横浜港に着くと、港を支配しているのは、明治政府の役人や兵士なのです。
一年の間に、ガラッと世の中が変ってしまいました。
出発した時はたくさんの人が見送ってくれましたが、帰ってくると栄一たちは元幕臣で「朝敵」になっているのです。
迎えにきた人はほんのわずかでした。
栄一は人目をさけて、そっと、東京(江戸は東京に地名がかわった)の友達の家で、お父さんと会いました。
新五郎は牢屋から出て、元気にしていましたが長七郎は病死していました。
喜作は彰義隊(しょうぎたい)にはいり、今は北海道の函館にいるらしく、消息不明でした。
彰義隊や振武軍(しんぷぐん)に入っていた長七郎の弟、平九郎は、官軍に追われて切腹していました。
栄一のおさななじみの友達が病死したり、消息不明になって、栄一は寂しく思い、思わず泣いてしまいました。
お父さんと別れた栄一は、急いで慶喜(よしのぶ)公のいる静岡へゆきました。
慶喜は宝台院という寺にとじこもっていました。栄一が寺に入ると、境内には秋の虫がと寂しく鳴いています。
月が青白く冴(さ)え、寒さが肌にしみてきました。
栄一は粗末な狭い部屋にとおされました。灯(ほ)の暗い行燈(あんどん)の灯影(ほかげ)が、ユラユラゆれているのです。
お化け屋敷のようです。
ここに、天下の将軍だった人が住んでいるのかと栄一は思うと、人間の運命はわかるものでないと、つくづく思いました。
慶喜公は、栄一の恩人です。
いまは朝敵になっていますが、栄一はどうしても慶喜公をもう一度、世の中の明るいところに出したいと決心しました。 慶喜と悲しい対面をして栄一は、別れました。
top
****************************************
|