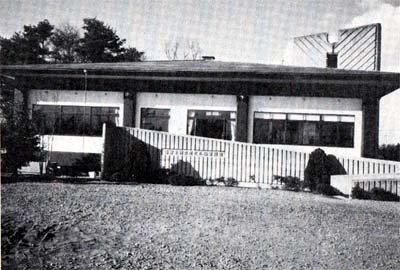|
****************************************
Index 一章(その一 その二) 二章(その三 その四)
第一章 上流の風土(その二)
15 高岩に佇(たたづ)んで
top
黒羽城址公園の対岸に、一見百坪三階建ビルぐらいの大きさの天然の奇岩が、那珂川に重箱を浮かべたようにデンとそびえている。
高岩神社と波切不動尊のある高岩園で、明治の初期ごろまでは帆かけ船や筏で舟運が盛んだった時代に、近郊農民が五轂豊じょうを、船頭さんが舟運の無事息災を祈願したところである。
話がズレるが、五穀とは米、麦、粟(あわ)、きび、豆の五種類かとばかり思っていたが、念のために広辞苑で確かめてみたら、稗(ひえ)、麻を入れている説もあるそうで恥ずかしかった。
この高岩に、土地の人の話では昭和二、三十年ごろまでは川の流れが激突して飛沫が見事な景観だったという。 |

高岩神社側の那珂川の奇岸
|

高岩神社の境内 |

波切不動尊 |
今は川の水量が減って激突という凄味はないが、流れに終日洗われている奇岩の素晴らしさはそのままの姿で残っている。
高岩神社の杉の枯葉が、ペルシャじゅうたんのように厚く敷かれた境内の小径を、ほんの少し歩いただけで高い岩の頂上にでる。
目の下は那珂川で、流れが激突していたころは、水しぶきがこの高岩の上まで跳ねあがり、着物の裾を濡らしたことであろうと容易に想像できるほどの川の中に突きでている。
この周辺は鮎釣りの名所として知られているが、たまたま七、八メートル下の岩場で釣りをしていた六十年配の男性がいたので、今頃はなにが釣れるのか声をかけてみた。
釣り人は空を仰いでなにか言ったが、波の音て声が消されて聴こえない。
それで改めてわかったのだが、静かに洗われているような高岩も、真近ではかなり激しい渦を巻いて流れているのである。
何回目かにやっと「ザコッ」という声が聴こえた。雑魚(ざこ)だという。
何というザコが釣れるのかと聞きたかったが、声が波と風の音にさえぎられることを憚(はばか)って、ただじっと見ているだけにした。
見ているあいだ中、竿を何回も上げ下げしたが、ついに一匹も釣れなかったようである。
高岩に立って右岸沿いが淀みになっている。
その淀みにジュースの空き缶やビニール製の袋や紙くずなどのゴミが溜まって、川を汚しているのに気がついた。
清流那珂川にふさわしくない光景である。
心ない人たちが空き缶やゴミを川に捨てたものか、こういう状態は残念なことだが上流でも見られたし、私の住んでいる下流でもしばしば見られる。
川は美しさを失ってはならない。美しさとは川の場合は涼やかで清澄でなければならないし、愁いとか哀れとか愛する心であり、川は愛する以外に川を美しくすることはできない。
いまの那珂川は、“すこぶる美人”とは言いがたい。
しかしそれは川の罪ではなく人間の責任である。
昔から川は多くの恩恵を人間に与えてきた。
そしていまも与えつづけているが、川に空き缶やゴミを投げすてるなど、それは憐れみを知っている人の行為ではない。
話がそれてしまったが、何といっても「水の黒羽」とさえいわれている所である。川は大事にしていきたい。
この高岩にある波切不動尊というのは、農民が無事息災を祈願したというだけでなく、その昔、那須与一が源平屋島の合戦に扇の的を射ようとした時、波が荒くてねらいが定まらなかったので、波切不動尊に祈ったところ、ご霊験があってか、みるみる波が鎮まり見事に的を射落すことができたと伝えられている有名なところである。
ちなみにこの周辺は中世の一時期、那須氏支配の地であり、与一出生の地であるとも伝えられているのである。
16 彼岸 top
黒羽町から国道二九四号線を七キロほど南下すると湯津上村へでる。
さらに十二、三キロ小川町を経て下ると馬頭町にいたる。
このあたり一帯は那須国の中心地だったところである。
そしていまでも当時の歴史がそっくりそのまま残されている伝統のある町村である。
那珂川はその湯津上村の東を、そして馬頭町の西を流れているが、川面からあがる大量な水蒸気のせいか、他所から来てこの町村にはいると、空気が水色に染まっているような気になってしまう。
那珂川の岸にたたずんで、何ということもなく川の流れを追っていると、柄にもなく感傷的な気分になっているのがわかる。
ぼんやりと向こう岸を眺めていたら“彼岸”(ひがん)という言葉が脳裏の奥で絵になって瞼に焼きついた。
お彼岸というのは仏教用語で、一年に春と秋の二回ある。
現在は春分の日、秋分の日がお彼岸のお中日にあたっている。
現世との反対側、つまり此岸(しがん)ではないあの世を指すものだが、別に今がお彼岸の季節でもないのに、ああ、あちら側は彼岸なんだな、とこの言葉が妙に懐かしさをもって私の心にまつわりついた。
向こう側の田園風景が、地球の回転を一時停止させたように動じなくって、何ひとつ動くものがない。
鳥影さえ視野にはいらない沈黙の景色が、そのあたり見渡すかぎり展開していたせいかもしれない。
多分、昔はこの川ひと筋があるために、向こう側とこちら側では付き合いの度合が限られていたのではないかと思ったりした。
小川ならば下駄を濡らすていどで渡れるがこのあたりの町村を流れる那珂川は多くの細流を合流しながら成長してきた川である。
水の色は青く、川底の石も青く見える。この青い石が光に反射して、水もまた青く見えるのかとおもったりした。
もちろん深いところの石は見えない。深みはとこまでも蒼くて、見詰めていると吸いこまれそうな錯覚さえ感じる。
なにかの拍子で深みに落ちこんだら「不思議の国のアリス」のウサギの穴ならぬ那珂川の水底の、異次元の世界に迷いこむような気がして、神秘な想いにかられると同時にたじろいだ。
湯津上村から馬頭町にかけては、古墳の町といわれているだけに、その道の愛好家にとっては次々と興味が尽きないところであろう。
私のように不粋なものでさえ古墳群が非常に良い状態で保存されているのを見ると、改めてその時代の人々の生活の一端を垣問見たような想いをもってしまう。 |

神秘をさそう那珂川の水底
|

美しい河畔の田園風景 |

山の中腹にある唐の御所 |
この土地を拓いて農耕し、あるいは養蚕し、そして機織りして暮らしてきた人たち、または川で漁猟し山で狩猟してきた住民たちの風俗に、じかにふれるような親しみと尊厳さを同じ意識のなかで感じてしまう。
そのころから今日まで、ありがたいことにはこの那珂川の生態系はあまり変っていないのではないかと思ったりする。
近代工業は日本の風俗文化を根底からくつがえしてしまったと言っていいほど、急速な進み方をした。
その功罪は問うところではないが、世俗的でない魅力を濃厚に含有しているこの村は、私のように水戸市街に住んでいる人間からみると、村そのものが、きらきらと澄んでいるのがよくわかる。
17 古代からの文化の地 top
栃木県の歴史(山川出版社、大町雅美他著)の中で、「那須国の中心は小川町から湯津上村にかけた那珂川流域であった。
このあたりが国造統治の地域であることは、小川町吉田の那須八幡古墳、湯津上村の上侍(かみさむらい)塚、下侍塚古墳をはじめとする前方後方墳が多く分布し、那須国造碑などがあることによって明らかである。」――と簡明な説明がなされている。
そのなかの一つ、那須国造(なすのくにのみやっこ)直韋提(あたいいで)が祀られている笠石神社は、国道二九四号線沿いにあり、黒羽方面から向かうと湯津上小学校から約一キロほどのところである。
笠石神社の境内は旧水戸藩の飛び領地で、ご神体は笠形の石をかぶった古碑である。碑の高さは笠石を含めて約一四八センチ、幅四十五センチ、石は花崗岩である。
碑文は八行十九字詰で一五二字からなっている。国造は現在の知事のような官職にあたり、草提は名前である。
直は姓で国造に賜った家柄の尊称である。碑文の冒頭に「永昌元年」とあるが、この年号は唐の則天武后の時代で、わが国では持統天皇の三年に当たっている。 |

笠石神社の那須国造の古碑
|
西暦でいえば六八九年で、聖徳太子が没したのが六二二年だから以後六七年ということになり、知名人では柿本人麻呂の時代である。
当時、韓(韓国)三国(高句麗=こうくり、百済=くだら、新羅=しらぎ)がたがいに覇を競い、攻防を繰返していた。
六六三年に百済が滅び、六六八年には高句麗が滅んだ。日本は百済や高句麗からの難民や渡来人を受入れていたが、統一新羅からも政治亡命者を多数受入れた。
このように韓からの渡来人は頻繁で、日本書紀によれば、那須国には新羅人が入植して高い文化を伝えたとある。
その新羅人のなかでも教養のある人が韋提の死後、韋提の子弟に依頼されてこの碑文を刻んだものと想定されている。
碑文の解読については諸説があるが、いずれにしても韋提の遺徳を偲んで建碑したものであることは間違いない。
碑の内容は、韋提に恩顧を蒙った新羅からの帰化人が、故人の徳を石に刻みつけ不朽に伝えるというものである。
韓からの渡来人が入植したということについて、創元社発行の段煕麟(たんひりん)著の「日本に残る古代朝鮮(関東編)の中に興味をひく部分があるので紹介してみたい。
それによると韓人の来往したところを地名によって列挙しているが、たとえば芭蕉の句にでてくる「落ちくるや高久の宿のほととぎす」の高久は「高麗人が来往しかところ」として高来(たかく)の借音仮字であるうと思われるとしている。
また駒木根という地名は高麗来根(こまきね)の通音仮字と思われるとしている。
さらに唐木田は唐来(からき)で、韓来(からき)の借音仮字であるとして、新羅人がきて田地を開拓したところであるとし、大日本地名辞書でも、古へは唐来と唱えしとぞとあると述べている。
段煕麟氏は著作の経歴紹介によると、韓国ソウル大学校法科大学中退後、一九四七年に渡日、関西大学法学部卒業、同大学院文字研究室で橿原(かしはら)考古学研究所にて研修、高校、大学の講師を勤め「韓来文化」の著作が多いと記されている。
18 笠石の尊厳 top
那珂川沿いにに走る国道二九四号線は、湯津上村を縦断している。その湯津上村にある笠石神社のご神体が那須国造の古碑である。
この古碑は江戸時代初期のころまでは、草むらの中で苔むしていた。
湯津上村教育委員会がまとめた「那須国造碑」の小冊子から孫引して要約すると、「那須拾遺(しゅうい)記」に次のように記している。
石の笠をかぶった石碑があるが、その謂(いわ)れは里人たちは知らなかった。
昔は笠の石をはずして下に置いておき、長いこと雨が降らないときには笠石をかぶせて雨乞いすると、かならず雨が降ったという。また、この碑を里人が誤ってけがすとたたりがあったとも記している。
この話を聞いた馬頭の庄屋犬金重貞が、石に刻まれた碑文を写して徳川光圀に報告し、光圀は家来の儒者の佐々宗淳に命じて調べさせたところ、那須国造碑であることがわかったという。
光圀は碑を安置するために、この地は水戸領ではなかったが、領地替えして水戸藩の飛び地として現在地にお堂を建て碑を祀ったものである。
碑は笠をかぶっているところから笠石神社と称されている。
笠石神社縁起によると、古くから子供の虫切には神徳はなはだあらたかなので、遠方から参詣祈願するものが多いという。
子供の肌身につける衣類を神前にささげ、祈祷したあと子供の肌につければ、いかなる強い虫でも立ちどころに全治するという神徳である。
雨乞いの行事といい、虫切といい、まぎれもなく民俗的な土の匂いである。そして水の匂いでもある。
話が少し脇道になるかもしれないが、古来から日本は「豊葦原(とよあしはらの)瑞穂国(みずほのくに)」と称したほどに瑞穂(水稲)の盛んな農耕民族の国であり、稲を大切に扱ってきた。 |

笠石神社
|
「お米は百姓が八十八回も丹精して作ったもの」米という字はそれを表していると老人などに教えられてきた。
だから昔のひとは一粒の米も粗末にしなかったものだ。
ところがここ十年来、日本は経済成長の伸展に伴って物資があり余るようになってくると、米だけにかぎらず、ものを大切に扱う心をどこかに置き忘れてしまった。
それでもまだお年寄りは物の貴さを知っていた時代を生きてきたから、昔ながらの崇める心構えを失っていないが、一部ぜいたくに馴れきった人たちは実に粗末に物を扱うようになってしまった。
またまた話がズレて恐縮なのだが、私は児童相談所の仕事を二年間ほどしていたときに、非行少年問題を扱ったことがある。
そのとき実感として体験したことは、すべての非行問題に欠如していることは「思いやりのある愛情」であることを知った。
極論かもしれないが、どのようなケースでも「思いやりのある愛情」が子供たちの周囲にあったなら、子供は非行に走らなかった――と確信するほどになった。
物を崇める、大切にするというのも根本は「思いやり」である。
作った人への感謝、思いやりの念が生ずれば、物は粗末にできないけずである。
笠石神社のご神体も、里人たちはその碑文の謂われは知らなかったけれども、誰とはなしに雨乞いの“神”として祀った心底には、やさしい心根とともに古碑にたいしての尊厳を感じていたのであろう。
この碑文を作った新羅人は、かなり文化の面においても深い素養があったことが考えられるのである。
人植者は単に農地の開拓という生産経済面だけでなく、地域の文化の向上に大きく寄与するところがあったのだろう。
19 侍塚(さむらいづか)
top
笠石神社の近くに、前方後方墳が二基、約七〇〇メートルの間隔である。
いずれも那珂川に沿っていて、北方にあるのを下(しも)侍塚、南にあるのを上(かみ)侍塚と呼んでいる。
上の方がひと回りほど大きく、全長一一四メートル、後方の広い方の幅が六十メートル、高さは十二メートルある。
下の方は長さ八四メートル、幅四ハメートル、高さ九メートル余りだが、両侍塚ともこじんまりと盛りあがった姿はいかにも古墳の標本といったような美しい態をしている。
那須国造韋提の碑文を確認した徳川光圀は、この古墳は韋提の墓ではないかと考えて発掘させたと記録にある。
発掘の目的はこの古墳は韋提の墓であるという傍証資料を求めるためであったが、期待していた誌石もなく、従って墓の主もわからなかった。 |

那珂川段丘上にある待塚古墳
|
湯津上村教育委員会の編した「侍塚古墳」の記載文によると、両塚から出土した遺物は、鏡、管玉、鉄斧、高杯、鉄製刀身残欠、須恵器などで、光圀はそれらの出土品を記録させたのち、丈夫な松材の箱に納め、腐敗防止のための松やにをかけて元に埋め戻している。
古墳はもと通りに修復し松を栽えて崩壊を防ぐ手当てもしている。
この時の発掘調査を「日本の考古学史上に残る古墳発掘の先駆である」として「墳丘を修理し保護の策を講じたことは文化財保護の最たるもので、現在ですら、これに優る策はない」と激賞している。
両古墳が光圀の命によって発掘されたのが元禄五年(一六九二)だから、ほぼ三百年を経た現在も完全なる原型を残しているということは光圀の功績である。
大体徳川光圀という殿さまは、小説やテレビで「水戸黄門」として家来の助さん、格さんを伴って大活躍――という風に大衆化して馴じんでしまったが、大日本史の編纂のため史局を設けて着手したり、笠石神社の古碑の祭祀、両侍塚の調査など学術的なことに関心の高かったかたである。
現代で言えば歴史学者で、幕末に尊王攘夷論が沸騰して倒幕に至るわけだが、この「尊皇攘夷論」の思想は犬日本史に影響されているのである。
もっともこの場合の「夷」というのは中国北方の蒙古人の意で「皇」は宋朝を指している。
蒙古人によって宋朝は滅亡するわけだが、この時に祖国復興の思想として宋人がうち出したのが「尊皇攘夷論」である。
横道にそれるが、日本にも関係があるのでついでに触れると、この宋朝をほろぼした蒙古軍がわが国に来襲するのである。
文永の役(一二七四)、弘安の役(一二八一)と呼ばれているのがそれで、わが国はそのとき、有名な“神風”によって救われたのである。
このように徳川光圀が力をそそいだ大日本史の影響をうけて、尊王思想が幕末に昂まり、ひいては徳川幕府崩壊へと時代は移行することになるが、これは、皮肉な観察かもしれない。
それはともかくとして、湯津上村にある侍塚古墳が、現存のように美しい姿で拝見できるというのも、光圀の学究的姿勢の反映であり遺徳のあらわれであろう。
20 古墳に想う top
古碑の顕彰文に見られるように、那須国とあるからには独立した先進文化圏が、古代からこの那珂川流域に存在したということを示している。
これに関係した調査や研究の記録は多くの学者たちが、それぞれの立場から述べられているが、それらを総合すると四世紀から七世紀頃という古いものである。

湯津上村から出土された古墳群 |
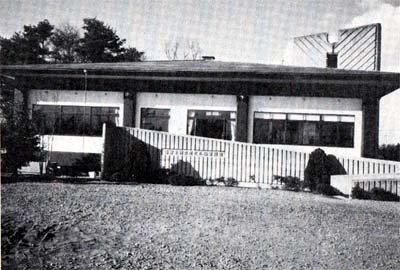
湯津上村歴史民俗資料館 |
日本書紀には七世紀に多数の新羅人が那須国に入植して高い文化を伝えたとある。
いずれにしても黒羽町、湯津上村、小川町、馬頭町、烏山町一帯は那珂川をはさんで那須国の中心であり、この地域に古墳が群在しているのがその証拠であろう。
主な古墳を北から列挙してみると、
●銭(ぜに)室古墳(黒羽町)
●小舟渡古墳群、上下侍塚古墳、富士山古墳群(湯津上村)
●梅曽(うめぞ)大塚古墳、駒形大塚古墳、那頂八幡塚古墳、吉田富士山古墳(小川町)
●川崎古墳、北向田古墳群、唐御所(からごしょ)横穴群(馬頭町)
●大桶古墳群(烏山町)、など見事な古墳文化を展開している。
これだけから推察しても、那須国の歴史の重みが偲ばれ、私などの門外漢が勝手に想像すれば、ひところ世間で話題になっていた邪馬台国の女王卑弥呼とも、何らかのつながりがあったのではないかと思うほどの古さである。
そのような想像をしても、おかしくないほど年代的には似通っているし、さらに無責任に想像を逞しくすると、隣りの中国では三国時代であり、魏(ぎ)、蜀(しょく)、呉(ご)が鼎立(ていりつ)していた。
劉備(りょうび)玄徳や関羽(かんう)などは死んでいたであろうが、軍師の諸葛孔明(しょかつこうめい)は、まだ活躍していたむろうなどと夢想していると、那珂川のほとりを歩いていても、つい昨日まで那須国がそこにあったような親近感が湧いてくる。
邪馬台国の女王卑弥呼(ひみこ)が魏に使いを送り、魏の明帝は詔書宣tして卑弥呼を倭(わ)王とした。
そのころ那須国の王はどうしていかのだろうか。
そのあと、わが国では大和朝廷が成立し、国内の統一がはがられたわけだが、このように、たわいがない飛躍した想像をしていると、案外、歴史というものは学問として敬遠するほど冷たくなく、先祖さまていどに身近に迫ってくるものである。
下侍塚古墳の前、国道二九四号線をはさんで湯津上村の歴史民俗資料館がある。
また小川町には中央公民館があって、それぞれ文化財の展示をしているが、たとえば旧石器時代、縄文時代、古墳時代の土器、石斧、勾玉、鉄剣、賺など古墳から出土したものが展示されて、考古学の貴重な資料となっている。
散在している古墳群はもちろんのことだが、この古墳から出土した各種の生活用具などを眺めていると、つくづくと那珂川流域のこの土地は、人間が褄みついてから実に古いと溜め息が出てしまう。
21 煙草余聞 top
侍塚古墳から那珂川右岸を国道二九四号線に沿って、約十二キロほど小川町を経て南下すると、那珂川左岸に馬頭町がある。
戦国時代に常陸太田の佐竹氏が侵攻して佐竹領となっていたが、徳川家康が実権をにぎるようになって佐竹氏は秋田に転封となり、徳川頼房が水戸(当時は水府)に入封して馬頭は水戸藩となった。
この地に武茂(むも)山馬頭院という寺があるが、徳川光圀の時代になって光圀が再建し保護したところから町名の由来となったとされている。
馬頭といえば、昔ながらの愛煙家は「馬頭煙草」を想いおこすかたもあろう。
那珂川流域の芳賀、那須あたりは、戦前までは煙草の特産地として全国的に知られていたもので、大正ロマンと称された紳士たちが好んで喫った口付き紙巻きの「朝日」はこの地の、葉煙草が原料だった。
煙草小史などを見ると、徳川家康の墓が静岡から日光東照宮に移された元和三年(一六一七)に、馬頭の香林寺の住職が、上州の光台寺から「館林煙草」の種子をもち帰って栽培したことに始まるとある。
この館林煙草を原種とした馬頭煙草は、その後、水戸藩の奨励によって、年ごとに作付面積が増え、水戸藩の特産品として那珂川の水運によって江戸へ回送された。
馬頭煙草の中でも、那珂川上流の東岸で栽培されたものは特に「寺内煙草」「御前煙草」とよばれ珍重されたという。
有名な刻み煙草水戸の「水府」の原料はこの那珂川上流東岸で栽培された葉が使われていて、その芳香は五丁(約五五〇メートル)も先から薫るというので「五丁煙草」ともいわれたという。
一時期には、米作の二倍もの収益があげられるということもあって、煙草耕作は盛んとなり、元禄十五年(一七〇二)の記録によると七万三千斤が収穫され、正徳年間(一七一一〜一五)には二百十六万斤の収穫があったという。
水戸藩の葉煙草の盛業に刺激されて、幕末には黒羽、真岡、茂木なども葉煙草耕作が盛んになり、明治維新後に専売制になると専売局が積極的に品質改良を行っている。 |

馬頭町にある煙草神社
|
しかし、その後は外国種のマイルドな原料に押されて、勢いは急速に失われてしまった。
江戸時代から明治、大正にかけて、庶民たちから愛用されていた煙管につめて吸う刻み煙草も、今ではすっかりと衰退してしまった。
特有の辛みがあって、煙草飲みは目を細めて吸っていたものだが、肺ガンになるとかニコチンが多いとかの理由からか、大衆の嗜好は軽い煙草に変ってしまった。
大体、煙草が旨いというのはニコチンが強いから煙草飲みにはうまいのであって、軽い煙草などはアルコールの少ない酒と同じようなもので、それならいっそう、禁煙した方がましではないか、と思ったりする。
今は喫煙していないが、私は数年前までは一日八十本ぐらい煙草を吸っていた。
やめた当時は胃がかきむしられるようになって、ずいぶん苦しんだものだが、梅仁丹やアメなどをなめて結局はごまかしてきた。
それほどやめにくいのが煙草で、煙草の味の真価も、そこにあるのではないかと思ったりしている。
22 古社 top
馬頭院の東に乾徳寺(けんとくじ)がある。
明応八年(一四九九)建立というから、コロンブスが新大陸を発見して数年後のことで、かなりの歴史がある。
山門は千鳥破風の四足門で「室町建築の様式をよく伝えているから、ぜひ見ておけ」と知人にいわれて久しいが、残念ながら私は未だに見ていない。
機会をみて見に行きたいと思っている。
このあたりには古代の横穴古墳が多く、その一つに唐御所横穴古墳がある。
里伝では「都山」とも呼んでいて、伝説が多い。
平将門の女(むすめ)が助命されて、のがれてきて、この地で男子を出産したが、世を憚(はばか)って、唐土の后妃が遠流したものだと言触したので「唐(から)の御所」と言うとも。
また一説では僧・道鏡*(どうきょう)が岩室を築いて住み祈祷した甲斐があって、孝謙天皇(奈良時代の女帝)がこの地を訪れ、崩御されたので御廟を造ったとされ「唐御所」の伝承となっているとか、話題は豊富である。
* 孝謙天皇は道鏡がお気に入りで政治をとらせていたが、九州の宇佐八幡のお告げがあるということで、和気清麻呂を使いにだしたが、道教を跡継ぎにすることを否定され、さらに道教はこの地に流された事件。しかし孝謙天皇がこの地を訪れたというのは伝説にすぎない。
この伝説は茨城県のあちらこちらでもきかれる。
さきに紹介した段煕麟著「日本に残る古代朝鮮」のなかで、段氏は次のような推測をしている。
唐御所の「唐(から)」は「韓(から)」の借用仮字で、ここに入植した韓人が穴居生活をした遺跡ではないか、と吟味している。
この古墳は七世紀頃のものといわれているだけに、年代的には符合している。
いずれにしても那珂川と沿道は、古代における奥州街道としての幹道であり、那須国と関連して当時における先進地域であったろうことは間違いないのではあるまいか。
やはり、私は行ったことがないのだが、馬頭の東南の栃木県と茨城県との県境に鷲子(とりのこ)山があり、その山頂に鷲子山神社がある。 |

馬頭院
|
社伝によれば宝珠上人が大同二年(八〇七)に阿波国の天日鷲命(あめのひわしのみこと)を勧請した古社とある。
この山深いところに昔から神社が建てられているということは、馬頭の文化の古さを顕している。
この古社は、製紙と殖産の神だという。
馬頭町の隣りは烏山町で、烏山(からすやま)和紙は特産品としていまでも生産されている。
古社と烏山までの距離は直線わずか七キロである。
烏山町観光協会のパンフレットに、和紙の手すきをしている写真が載っているが、説明によると、七百年ほど前に越前から手すきの職人が招かれて、楮(こうぞ)を原料として那須奉書をすいたのがはじまりと伝えられている。
以後、農家の副業として発達し、障子紙、からかさ紙など厚めのものを作っていたが、今日では、押し絵、名刺入れ、札入れなどの民芸品を作っている。
淡黄色の艶(つや)があって、なめらかな和紙を鳥の子(とりのこ)紙という。
この名の起こりは鷲子山神社からといわれているが、真偽のほどは定かでない。
それにしても、紙の神さまなんてユニークで実にいい。 |

烏山(からすやま)町にある和紙製造工場
|
23 小砂焼の祖 top
馬頭町は旧水戸領である。
町の北方に小砂(こいさご)という地があって、ここの土が陶土に適していることを発見して殖産に手を染めたのは、水戸第九代藩主徳川斉昭(なりあき=烈公)である。
烈公さんは自領の経済力をつけるために、他領から陶器の買い入札をしないで、水戸藩の自家製でまかなおうと考えたらしい。
当初は小砂の陶土を那珂川から舟に積んで水戸へ運搬した。
ところが、安政元年(一八五四)に幕府の幕制参与となり、大砲の鋳造をすることになって、小砂の陶土で耐火レンガを作り、那珂湊に反射炉を築造した。
これについては那珂川下流でまた触れることもあろう。
ともかく、この前年にはペリーが浦賀に来航し、この年、日米和親条約を締結しているのである。
いわゆる幕末で徳川幕府有史上もっとも困難な時期にあたる。
同じころ小砂の名家藤田半三郎は越中の陶工斉藤栄三郎を招いて陶窯を築き、楽焼の製造をはじめた。
この陶器が「小砂焼」(こいさごやき)と称して今日にいたっている。
小砂焼の陶土は、花崗岩が風化したような土で火に強い。
これを二九○○度の高熱で焼く過程で赤金色の光沢が出てくる。製品は硬く重量感がある。
以後、伝統を守って百三十年余も続いているが、この時の窯が作業所の裏にあるので一見する価値がある。
表は製品の展示、即売所になっており、花瓶、茶器、灰皿、酒器など手作りの民芸品がおかれている。
益子焼は有名だが、小砂焼は宣伝不足のせいか、あまり知られていない。 |

むかしの小砂(こいさご)焼の陶窯跡
|
趣味の問題になるが、焼きあがった製品を真近に見ていると、舞楽に合わせてしずしずと登場する能舞台の媼(おうな)のような品格を覚える。
盛業だったころには窯元も七軒あったが、いまは藤田製陶所一軒になってしまったのは、さびしい限りだが、烈公さんお声がかりのこの窯の火は消したくないものである。
陶工の斉藤栄三郎は藤田半三郎と後に父子契約を結び、栄三郎は藤田半平と改名する。
この藤田半平のことを伝える碑文が「小砂焼」陶業年表に読み下しとして掲載されており、当時の苦労を偲ぶよすがにもなるので、平明にして紹介すると、
翁(藤田半平)は越中国井波町の町年寄斉藤佐兵衛の五男で、幼にして埏殖(えんしょく=陶器をつくるため土をこねて、のびやすくした土)で土器を造るを喜ぶ。
天保十一年三月常州茨城郡宍戸町の山口勘兵衛翁に従いて陶器の製法を受ける。
留学はおよそ七年、しかして郷に帰る。(中略)
さきに水戸烈公は小砂の地は山高く水清くその土質陶土に適するを発見せられ、新たに陶業建設の計画あらせるといえども、内外多事にして年を経るに至る。
小砂の名家藤田半三郎、大金彦三郎の二人は公命を服して安政元年九月栄三郎氏を呼ぶ。
同氏は窯を造る。ところが安政三年八月の暴風で、陶窯および製造所は一瞬にして全壊した。
再び窯を築いたが、この時に終身誓って他に従わないとして藤田半平と改称する。
明治二年水戸昭武公の御巡覧を得て製造所の諸器を賜る。(後略) |
この碑は翁の弟子たちによって明治三十二年三月に建てられた。
翁はこの前年まで、「七十の高齢におよぶも壮者の如し」であったという。
24 烏山(からすやま)周辺
top
馬頭(ばとう)町から国道二九四号線に出て、七キロほど南下すると烏山城がある。
烏山町の中心部より北西の方向で、別名を臥牛(がぎゅう)城というが、どうして臥牛というのが理由は知らない。
ただ、この城山を遠くから見ると、牛が横たわっているような姿にみえるから、そのような名前がついたものかと勝手に想像して納得することにした。
那須与一の子孫の那須資重(すけしげ)が室町時代の応永二十五年(一四一八)に築城したものと伝えられている。
その後、江戸時代には城主がたびたび交替して、明治維新のときは大久保氏になっている。
この城山の下に寿亀山(じゃきさん)神社がある。
このあたりは城の三の丸跡で、私が訪ねた七月の初旬には芝生と雑草がところ狭しと茂っていた。
鳥居をくぐって四十段ぐらいの石段をのぼると、二間四方の小さな社がある。
両側には直経十センチはどの太い孟宗竹が周囲の空気を藍色に染めていて、裏山は杉林である。
境内は梅林で梅の咲くころは見応えがあるだろうと思った。
ここには映画にもなった蛇姫様の作者川口松太郎氏の句碑が記念として建っている。
「梅雨くらく蛇姫様の来る夜かな」と石に刻まれているが、私が行ったのが入梅どきで、雨はあがっていたが、季節は符合していて、それなりの趣があった。
烏山城から六、七キロで町の中心部に入るが、烏山駅の南西に那須家歴代の菩提寺である南台山天性寺がある。
墓は、こじんまりとした六基の五輪塔で、肩を寄せあうようにして立っている。
帰り径に下を向いて階段を降りていたら、黄色味を帯びた梅の実が一個ころがっていた。
今更のようにあたりを見まわすと、梅と桜の樹が入りまじった小さな林で境内は囲まれていた。
境内にはお救い小屋の跡がある。
伝えられるところでは、天保年間に大飢饉があったとき、城代家老と天性寺住職が力をあわせ、境内に小屋を建て、困った人たちに食物を与えたという。 |

那須家の菩提寺南山台天性寺
|
天性寺まで来たのだから、那珂川とちょっと離れるが、烏山線(宇都宮−宝積寺−烏山)滝駅に近い太平寺と龍門の滝を見物してみたいと思い足を伸ばすことにした。
太平寺は延暦二十二年(八〇三)征夷大将軍坂上田村麻呂が東夷のおり大願成就のために千手観音菩薩を勧請創立し、嘉祥元年(八四八)に慈覚大師が堂宇を再建したと伝えられているから、それだけでこの地の古さを物語っている。
太平寺の山門は赤塗りの仁王門で当時は草屋根だったが、今は亜鉛ぶきで補強してある。柱を支えている礎石は五、六十センチ大の自然石で、ふぞろいながらもガッチリと坐っていて、仁王門と調和がとれていた。
太平寺の近くに龍門の滝がある。那珂川の支流、江川にかかっている滝だが、高さ二十メートル、幅六十五メートルの見事な滝である。
四、五日前に雨台風があった影響からか、私が見たときにはすごい水量で、毎秒何十トンとも知れない水が、すさまじい音とともに落下していた。
滝の中段に女釜、男釜という縦穴があり、伝説によると、その昔、男釜から大蛇があらわれ太平寺の仁王門を七巻半しても尾は男釡に残っていたという。
龍門の滝という名は、それにちなんでつけられたといわれている。
25 与一さんのかついだ不動明王 top

断崖絶壁にある木戸不動尊 |

木戸不動尊から見下ろす那珂川 |
烏山町と茂木(もてぎ)町の境の那珂川は、絶壁を仰ぐようにして流れている。
その断崖絶壁に木戸不動尊の堂宇があると聞いて、ぜひ拝見したいと勇みたつ思いで出掛けて行った。
那珂川の左岸に渡り、舟戸観光やなを右手にみながら、下境を過ぎて小原沢を少し行くと間もなく茂木町に入る。
そのあたりまでは見当をつけて行ったのだが、周囲は畑ばかりで、そこから先がわからなくなった。
畑のわきに立っていた農家のおばあさんに尋ねると「そこの右の道をカギの手に曲がったところだよ」と指さして「しかし、那須の与一さんが不動明王さまかついできて、ここがよかろうとお堂を建てたんだよ」と、まるで与一さんの身内のように親しみをこめて教えてくれた。
教えられたとおりに、畑と畑の間の畦道のように狭い径をたどると奥にお堂がみえた。
烏山町観光協会が発行しているパンフレットによると、大同元年(八〇六)貴顕上人の開山と伝えられているとあるから、那須与一とは三百七十年はどのひらきがあり、与一さんでなくて残念だったが、私の心の中では、それを訂正する気が起こらずに、与一さんが不動明王をかついでいる姿がいつまでも残っていた。
堂宇は半高床のめずらしい宮で、往古は確かにこの堂宇から真下の那珂川を見下ろせたにちがいないが、今は杉の密林におおわれて、ひと筋の川もみえない。
パンフレットに那珂川の絶壁上に鎮座する不動明王とあったので、早合点し、そこから見渡す川の眺めを楽しみに想像していただけに、ちょっとガッカリした思いである。
遠くでウグイスの鳴き声が聴こえたので、耳を澄ませていたら、かすかに川のせせらぐ音が聴こえてきた。
杉の幹の太さから推察して、往古とはいわず、百年ぐらい前には那珂川は見えたのではないかと思う。
カギの手の径をもどって、表通りに出るとさきほどのおばあさんが、竹寵に掘りたてのじゃが芋を入れて立っていた。
おいしそうなじゃが芋だね、と挨拶がわりに声をかけると、にっこりとして、「入れものがあれば、あげっぺ」といった。
そして二、三キロのじゃが芋をビニール袋に入れてくれた。
お金を払うというと、いいって、ときかなかったが、なにがしの小銭をムリにエプロンのポケットにつっこんで別れた。
あとで、与一さんの堂宇を見舞ったのが、おばあさんには嬉しかったのかもしれないと、ふと考えて、走る車から振りかえったら、おばあさんは、まだこちらを見詰めていた。
私がそのあたりをウロウロしていたのは、十五分か二十分ぐらいだったが、その間、おばあさんのほかは人も車も見かけなかったから、余程に人里はなれているのかと地図で確かめてみたが、それほどではない。
あの堂宇の場所が、もし眺望絶景で小公園にでもなっていたら、これはまた別の味合いで那珂川を楽しむことができるかも知れない、などと想像をふくらませながら、車を走らせていた。
26 もてぎ焼をたずねて top
茂木(もてぎ)とは、何ともいえない風韻の籠った町の名前だろう。
物の本によると、源義朝の庶子八田知家(ともいえ)の子知基(とももと)が、築城にあたり城の東南にケヤキを植えたところ、この木が繁茂したことを吉兆として、茂る木にちなんで茂木氏と称するようになったと伝えられている。
徳川江戸時代には、細川藩一万六平石の城下町であった。
茂木町には、もう数えきれないほど来ているが、と言うより、通過しているといった方が適わしいのだが、今度ばかりは那珂川のことを書くにあたって、意識して、観てみたいと思い、茂木町の隣り町で、茨城県になるのだが、国民宿舎御前山荘に一泊し、二日間にわたって町を歩きまわった。
茂木町の観光協会で発行しているパンフレットに、大々的に宣伝している“もてぎ焼”について、不覚にも私は知らなかったから、この機会にぜひ見たいと思い立ち、町に二十数軒のもてぎ焼窯元があるというので出かけたわけである。 |

細川家の菩提寺能持院山門

町観光物産会館内展示の茂木焼
|
ところが、私の探しかたがわるいためか、いくら探しても見つからない。
もちろん、町の人に訊きながら歩いたのだが、ついにわからず仕舞いであった。
もてぎ焼の窯元? 益子焼きじゃないの……。
窯元? さあ……地元のものは案外知らないんだよ。
二、三の人、それも商店主とか主婦とか、老人などに聞いて廻ったが、反応はサッパリである。
何回めかに、そう言えば、あすこに窯元があるよ、といって教えられた道を行くと、確かに窯元があって、三十代の男性が蓋付きの壺を制作している最中であった。
こういうわけでお邪魔しましたと、突然に訪ねた失礼を詑びながら作品を拝見させてもらったが、彼は不思議そうに、
「ここに住んでいるけど、私のは益子焼ですよ。ただ、茂木の作品展には出品していますけど……」
帰り途、茂木駅前の観光物産会館に寄ると「もてぎ焼」の作品が展示してあった。
その説明にもあったように、茂木焼の作家の多くは笠間焼や益子焼を学んだ人たちだそうで、茂木焼の誕生が昭和五十年というから、陶芸としての歴史も浅く、独特の作風が固定するのは、もう少し先のように思えた。
しかし、それはいい。
それはいいが、パンフレットに大きく宣伝するのなら、せめて茂木焼窯元の一つ二つは、わかりやすい道順を示してもらいたいものである。
もっとも、私の探し方が悪いと言われれば、それはまあ、そうかもしれないが、と思うだけである。
茂木という、いまにも翠(みどり)したたり落ちるような風流な名のついたこの町の、多分、草木の香りが染みついた陶土を焼きあげた、もてぎ焼は、茂る木のような吉兆をやがてもたらすことだろう。
現在は、観光物産会館で見た「もてぎ焼」しか経験がないから、何とも言えないが、益子焼から出発して試行錯誤している段階のようにおもえた。
27 細川家の杉 top
茂木町の北東、那珂川の左岸を山側にのぼったところに、元禄時代(一六八八〜一七〇三)に建築された古い家が保存されていると聞いて、早速行ってみた。
羽石家住宅というのだが、元の持主が羽石さんという方で、別にそれ以外の理由はないようである。
由緒も明らかではないが、藁(わら)屋根の葺替(ふきかえ)のときに梁(はり)から棟札(むなふだ)が発見されて時代が判明したという。
昭和四十三年に重要文化財に指定されている。
棟札というのは、家の棟上げのときに建主や大工が、工事の由緒、建築年月日、建築者の氏名などを記して棟木に打ちつける木札のことで、寺院や神社などの立派な建物にはたいてい打ちつけられている。 |

国指定重要文化財の羽石家
|
頭部が山形をしているのが普通で、羽石家の棟札も山形になっている。
羽石家住宅の場合は農家風の民家で、一般民家から棟札が発見されたということは大変めずらしいケ−スとされている。
藁屋根が三層になっている重厚な構えで、私が行ったときは厳重に戸締りがしてあって内部の様子がうかがえなかったが、一見、五、六十坪ほどの広さがあるようだった。
敷地内にはなんの説明書きもなく、仕方なく裏手の「やまなみ荘」でたずねたら、住宅のしおりをいただけた。
それには数葉の写真が載っていて、土間、ひろま、屋根裏の棟木など当時の民家を知る貴重な資料になっている。
羽石家を出て那珂川沿いにの道を少し行き、大藤橋を渡って、再び町の方角に進むと能持院がある。
このお寺の総門は四脚門で、切妻造り茅葺になっている。
もちろん国指定の建造物で重要文化財となっている。
見るからに風格のある山門で、文明年間(一四六九〜一四八六)に茂木知持(とももち)が再建したと伝えられている。
関ヶ原の合戦後に主筋にあたる佐竹氏が秋田に転封となったとき、茂木氏も秋田に移り、その後は細川氏が入封して茂木藩を興した。
能持院は歴代の茂木城主の菩提寺である。境内には杉の木が多く、午(ひる)をちょっとすぎたばかりだというのに、薄暗い空気が境内の隅々まで支配している。
それがこの寺を一層厳粛にしているようで、足音にも気を遣わないと申しわけないような気分になってくる。
山門をくぐって左側に細川家の墓所がある。墓所といっても墓石はない。
一霊ごとに杉一本を植えてあって、そのわきの石灯籠に没年月日を刻してあるだけの、大名としては質素な墓地だが、三百七十年を経た今日になってみると、杉の木が生きているだけに畏敬の念さえ覚えるのである。
その杉が六本、亭々と聳え、幹はふたかかえもある。
しかも、六本のうちの三本は、地上十メートルの高さでも幹の太さは変わらないほど堂々と天に達している。
もちろん、杉にはいのちがあって、人間界では初代と六代目は当然のことながら面識はなかったが、杉同士となった今は、毎日のように会話をかわしているのである。
それが、細川家の思い出話なのか、将来のことについてであるかは、私にはわからないが、樹々の間をそよいでいった風は、確かに会話の“かけら”であったことは間違いなかった。
top
****************************************
|