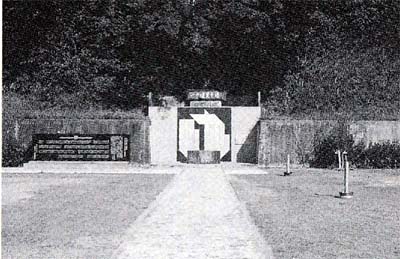|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 付録
三章 沖縄の近現代
一 琉球処分 琉球王国から沖縄県へ
top
1 東アジア国際関係のなかの「琉球処分」
英仏艦船の琉球来航
清国を中心とする東アジアの国際秩序=冊封進貢(さくほうしんこう)体制は、十九世紀に入ると、密貿易の増大、海賊集団の横行、進貢貿易をめぐる宗主(そうしゅ)国と属国の利害対立などに加えて、東アジアを世界市場に組み込もうとする欧米列強の圧力にも直面し、内外から揺さぶられはじめる。
イギリス東印度会社所属のアマースト号が貿易拡大の可能性を探るため、非合法的に中国沿岸各地から朝鮮半島を回って那覇港へ寄港し、琉球当局に貿易を要求したのは一八三二年のことであった。
アヘン戦争の最中には、イギリス遠征艦隊所属の輸送艦一隻が沖縄島の北谷沖で遭難して救助・送還されたのを契機に、琉球諸島の戦略的位置が注目されるに至る。
戦争の最終局面では、イギリス遠征軍所属の戦艦と思われる異国船が琉球諸島へ接近し、無断上陸した異国人が牛・鶏・野菜などの生鮮食料品を強奪する事件も頻発した。
アヘン戦争を契機に、東アジアの国際秩序は再編成の過程に入る。琉球と福州の進貢貿易ルートが欧米諸国へも注目され、南京(ナンキン)条約による福州「開港」の前後、イギリスの戦艦サマラン号が琉球諸島の海陸を長期にわたって測量調査し、琉球当局を狼狽(ろうばい)させた。
同時期に、フランスもまた艦船一隻を派遣して修好・貿易を要求しただけでなく、宣教師のフォルカードらを琉球に留めて引返した。
その二年後の四六年、セシーユ提督に率いられたフランス東洋艦隊の戦艦三隻が運天(うんてん)港に集結し、条約締結を要求して琉球当局と交渉した。
その最中に、イギリス艦船一隻が那覇に入港し、宣教師ベッテルハイム一家を留めて引上げた(『大日本維新史料』第一編ノ一、『琉球王国評定所文書』第一巻等)。
英仏艦船の琉球来航と修好・貿易・布教の要求は琉球当局を狼狽させただけでなく、琉球の内政・外交に関与してきた薩摩藩や江戸幕府、琉球の宗主国を自認する清国にとっても、前代未聞の事態として受け止められた。
薩摩藩や幕府は当面の間、欧米列強の日本開国要求を回避するために、琉球を幕藩制(鎖国制)から切離し、欧米列強との貿易を黙認して琉球の「開国」を既成事実化する方針を決定した。
もっとも、薩摩藩はこの機会を利用して逼迫(ひっぱく)した藩財政を立て直すために、秘かに琉球における大規模な外国貿易を推進する方針を策定し、琉球にその受入れを迫った。
そのプロセスにおいて、薩摩藩にとっての最善策は何かという視点から、「所属」問題をも視野に入れた琉球問題の論議が開始され(五代秀堯『琉球秘策』)、広義の琉球処分が始まったのである。
欧米列強と琉球
欧米列強もまた琉球王国の日清両属的位置に注目し、将来保護国あるいは植民地として獲得する企図を秘めつつも、当面は琉球王国を日本開国のための足場として位置づけた。
四六年の条約締結交渉で、セシーユ提督は琉球が「日本の支配」を脱してフランスの保護国となるよう勧告している。
また琉球に居座る英仏宣教師の退去問題をめぐっで、清国当局との交渉に応じた広州駐在のイギリス公使は、琉球を清国の版図とは認めないと言明して、清国当局の宣教師退去要請を拒絶している(『籌辮夷務(ちゅうべんいむ)始末』道光朝二、巻七七)。
126-64()
一八五〇年代に入ると、既存の国際秩序を無視しようとする欧米列強の意図と行動はますます明白となった。
五二年四月、米国船籍ロバート・バウン号上での虐待に耐えかねて反乱を起こし、石垣島へ逃れた中国人苦力(クーリー=労働者)を、米英側は海賊とみなして武装兵を石垣島へ上陸させ、苦力の射殺・捕縛作戦を展開したことから、琉球当局は一年半もの間、苦力の保護・送還問題に翻弄された(西里喜行『バウン号の苦力反乱と琉球王国』)。
その最中に、アメリカ艦隊のペリー提督は繰返し琉球へ寄港し、日本開国の前線拠点として利用しただけでなく、本国政府へ琉球占領の必要性を進言した。
アメリカ政府内部の事情で琉球占領は当面回避されたものの、日米和親条約を締結したペリー提督は、五四年七月、琉球王国との間でも琉米修好条約を締結した。
次いでフランスやオランダも琉球当局を威嚇して条約を締結させた。琉球王国は欧米列強の強いる新たな国際秩序へ組込まれたのである。 |

図67 ベリーの沖縄訪問(「沖縄訪問記」)
|
琉球王国の財政破綻
他方で、東アジアの伝統的な国際秩序も琉球王国の内政・外交を規制しつづけた。
薩摩藩の干渉・介入は島津斉彬(なりあきら)の貿易推進政策の展開にともなって強まり、斉彬急死後の五九年以降、琉球内部の斉彬協力派と非協力派の凄惨な派閥闘争が展開され、政治的混乱が引き起こされた(牧志(まきし)・恩河(おんが)事件)。
この間に、薩摩藩が強制した貢糖制(貢租の砂糖代納制)の復活・拡大措置も王国財政に大打撃を与え、その埋め合わせとして薩摩藩と琉球当局の暗黙の了解のもとに実施された文替り(鉄銭と銅銭のレート変動)が琉球農民の窮乏を加速し、六〇年代の琉球経済を大混乱に陥れた。
加えてまた、宗主国の清国から冊封使を迎えるために巨額の費用を必要とした琉球当局は、増税あるいは民間からの借金や献金に頼るだけでなく、薩摩藩からも巨額の借金を余儀なくされた。
六六年、尚泰は冊封使の趙新を迎えて清国皇帝から正式に国王に認知されたものの、文替りによる経済混乱の中で、その後もなお冊封の儀式に要した巨額の借金に苦しめられることになる。
この間、薩摩藩が主導した日本国内の政治闘争は、江戸幕府の倒壊、明治政府の樹立へと帰結した。
清国でも外に英仏との第二次アヘン戦争、内に太平軍との内戦が展開され、清国政府は満身創痍の状態であった。
日清両国内部の政治的激変は、経済・財政破綻へ向かいつつあった琉球王国の危機をも増幅させた。
七〇年代初頭、財政破綻に直面していた琉球王国は、明治政府を保証人に立てて東京国立銀行から二〇万円の融資を受け、当面の財政破綻を免れる外はなかったのである。 |

図68 尚泰
|
琉球藩設置と台湾出兵
一八七〇年代の初頭、明治政府の内部では、琉球王国の位置づけをめぐって日本専属論や日清両属論など、様々の論議が提起されたものの、明治政府は副島種臣(そえじまたねおみ、外務卿)の提案を採用し、七二(明治五)年九月、琉球王国を琉球藩とし、国王尚泰を改めて藩王に冊封することにした。
この尚泰冊封の措置が琉球併合へ向けて用意周到に案出された第一の布石であることを、琉球当局は事前に察知して当惑したものの、明治政府の「保証」で財政破綻を回避した矢先のこ
とで、冊封回避の有効な対応策を講ずる余地はなかった。
国王尚泰の代理として冊封詔書を受取った摂政の伊江(いえ)王子らは、ついでに薩摩藩の賦課した重税の軽減と道の島(奄美大島など)の返還を要請し、副島外務卿から善処する旨の回答を得て帰任した。
七三年八月、副島と会見した与那原(よはなばる)良傑(馬兼才)も、琉球の「国体政体永久に替わらず」との言質を得て帰任し、琉球の人心を安堵させた。
しかし、明治政府は空約束を重ねて琉球当局をコントロールしながら、琉球併合のための第二の布石を打つ準備を進めていた。
七一年末琉球人が台湾に漂着して現地住民に殺害された事件を契機に、台湾出兵計画が浮上しのである。
琉球当局は台湾出兵計画に再三反対の意思を表明し、欧米各国も非協力的な態度を明示したにもかかわらず、七四年五月、西郷従道(つぐみち)に率いられた日本軍は清国へ通報することなく独断で出兵し、六月上旬には台湾東南部を占領、台湾上陸の日本兵は三六〇〇余名に達した。
前年に日清修好条規を批准して友好・同盟関係を樹立したばかりの日本と清国は、日本軍の台湾出兵を契機に、開戦の危機に直面した。
北京における日清談判は決裂寸前に至ったものの、駐清イギリス公使の調停によって北京議定書(日清互換条款)が締結され、開戦の危機は回避された。
議定書に遭難琉球人を「日本国属民」と明記させ、間接的に「琉球=日本専属」論の論拠を獲得した明治政府は、琉球併合の準備を加速させるに至る。
琉球救国運動
一八七五(明治八)年七月、琉球へ派遣された松田道之(内務大丞)は、琉球を日本専属と言明し、琉球当局に対して清国との通交関係(冊封・進貢)の停止を要求した。
琉球当局は日本と清国を「父母の国」と称して日清両属の現状を維持することに固執し、二ヵ月にわたって松田と論争を繰り返した。
この開、琉球社会の内部では、明治政府の命令を遵奉(じゅんぽう)して清国との通交を断ち日本の専属国となるか、従来通り日清両属の国是を死守するか、二つの選択肢をめぐって論議が沸騰したが、いずれの選択肢も琉球国の存続を前提として提起されていた。
日本専属論を受入れて生き残ろうとする少数派の主張は、日清両属論に固執する主流派の大義名分論に圧倒された。 |

図69 松田道之(前列中央)
|
世論の動向を背景に、琉球当局は明治政府へ直接請願したいと松田に要望、松田もひとまず受入れて同年九月帰任した。
松田に同行し七三祠官の池城(いけぐすく)親方(うえーかた、唐名は毛有斐=もうゆうひ)らは、東京に到着すると琉球藩邸に身を寄せ、以後三年間東京を舞台に琉球救国運動を展開、明治政府当局へ中琉通交関係断絶命令の撤回を要請する請願書を提出しつづけたが、そのつど拒否された。
その間に、池城は使命を果たせず悶死(もんし)した。
池城の命を受けて帰国した幸地朝常(こうちちょうじょう、唐名は向徳宏=しょうとくこう)は、七六年十二月、蔡大鼎(さいだいてい)・林世功(りんせいこう)らを同伴して清国へ密航し、福建当局へ琉球国王尚泰名の密書を提出、進貢使迎接のための接貢船派遣が日本側の干渉によって不可能となった事情を陳述して救援を要請した。
廃琉置県処分
清国側も事態を重視しはじめ、七七年十一月、初代駐日公使の何如璋(かじょうしょう)を日本へ派遣して対日外交交渉に当たらせた。
何如璋は救国請願運動を継続しつつあった在京の琉球人とも接触して対応策を検討し、琉球王国の対外関係(清国との冊封・進貢、欧米列強との条約締結など)を論拠として明治政府の進貢停止命令に強く抗議すると共に、清国政府に対しては、外交と軍事を併用した対日強硬策を最善の策として進言した。
日清提携・日清友好を対日外交の基調に据えていた清国政府は、琉球問題をも外交交渉の枠内で平和的に解決する方針を堅持し、引続き対日交渉に当たるよう何如璋に指示した(『何少倉文鈔』など)。
しかし、日清間の交渉は進展せず、明治政府は琉球当局の懸命の請願と清国側の抗議を一切無視して、琉球王国が締結した対外条約の継承、司法権の接収、熊本鎮台兵の琉球進駐など、琉球併合のための既成事実を着々と積み重ねた。
この間、在京の琉球人は清国公使だけでなくアメリカ、フランス、オランダなどの駐日公使へも請願書を提出し、国際世論に訴えた(『琉球救国請願書集成』)。
琉球問題の国際化を恐れる明治政府は、在京の琉球人に退去を命ずると共に、琉球併合過程を加速させる措置を講じた。
一八七九年三月、琉球処分官の松田道之は一〇〇名余の警察官や内務官僚と数百名の熊本鎮台分遣隊を率いて那覇港に到着、四月四日琉球藩を廃止し沖縄県を置くことが内外に布告され、最後の国王尚泰とその一族郎党はまもなく東京へ連行された。五〇〇年続いた琉球王国の歴史は名実ともに断絶されたのである(琉球王国から琉球藩をへて沖縄県設置に至る一連の措置を廃琉置県処分と称することにする)。
琉球社会の内部には、廃琉置県を圧制からの解放のチャンスとして歓迎し世替わりを期待する人々もいたが、大多数の農民層の間では、清国の救援を期待しながらも、待ちくたびれて「日本命令の通り従順するより外にしかたなし」(『琉球処分』)と諦める雰囲気が支配した。
士族層や地方役入層の中には廃琉置県を受け容れず、血判誓約書に署名して隠然・公然の抵抗をつづけ、清国へ亡命して救国運動に奔走するものも少なくなかった。
琉球分割交渉
廃琉置県すなわち琉球国の消滅によって体面を傷つけられた清国当局は、明治政府へ抗議すると共に、外交的解決の方針を堅持したが、琉球問題をめぐる論争は平行線をたどり、日清関係は緊張した。
日清両国の内部には琉球の独立を容認する議論も存在したものの、圧倒的な主戦論の論調にかき消された。
折しもアメリカの前大統領グラントが日清両国を訪問する時期に当たり、両国の政府当局はグラントの仲介を期待した。
グラントは両国当局との会談で琉球諸島の分割による解決を示唆した(『日本外交文書』一二巻)。
これを契機に、日清両国は直接交渉に踏み出し、七九年十二月から翌年三月にかけて、明治政府の意向をうけた竹添進一郎と北洋大臣の李鴻章(りこうしょう)が、天津(テンシン)において水面下の予備交渉を繰返し、日清提携の立場から妥協を模索した。
この間、天津滞在の琉球人向徳宏も李鴻章に琉球救国への援助を要請しつづけている。
予備交渉は不調に終ったが、日清両国とも内外情勢に迫られて正式交渉の可能性を模索しつづけた。
正式交渉は八〇年八月十八日にはじまり、二ヵ月にわたって八回もの会談が繰返されたが、日清両国の代表団はもはや琉球の所属論には固執せず、もっぱら自国の体面を保つことに腐心した。 |

図70 李鴻章
|

図71 向徳宏
|
同年十月二十一日の最終会談で、両国代表団は琉球分割条約ともいうべき「琉球処分条約」を妥結した。
その主内容は沖縄島以北を日本領、先島(さきしま、宮古・八重山)を清国領とし、同時に日清修好条規を改訂して日本に清国内地通商権と最恵国待遇を認めるというもので、日本側にとっては琉球分割は国益(経済利権)獲得の代償にほかならなかったが、清国側にとっては先島に琉球国を存続させるための止むを得ない譲歩のつもりであった
(『台湾琉球始末』等)。
交渉妥結に漕ぎ着けた両国代表団は、一〇日後の調印、三ヵ月以内の批准をも約束して、祝杯をあげるに至ったのである。
琉球分割阻止運動
琉球分割の危機に直面した清国内の琉球人たちは条約調印阻止に立上がった。
天津滞在中の向徳宏は李鴻章に対して、琉球二分割を前提とした琉球縮小復国案に断固反対する決意を表明し、北京滞在中の林世功(りんせいこう)は総理倚門(がもん、外務省に相当)あてに決死の請願書を認め、八〇年十一月二十日辰の刻(午前八時)、琉球分割に抗議して自決した。
向徳宏や林世功らの激しい意思表示は、琉球分割条約を容認してきた李鴻章らの清国当局に衝撃を与えた。
李鴻章はついに条約調印延期・反対論者へ転身した。
これを契機に、清国政界では条約調印可否論争が展開され、八一年三月に至って、調印延期と再交渉を命ずる清国皇帝の上諭が下された。
琉球分割はひとまず阻止されたのである。
しかし、八一年三月以降も明治政府は内外情勢に迫られて主導的に再交渉の機会を探り、分割条約復活の可能性を追求した。
八一年後半から八二年前半にかけて、天津領事の竹添は李鴻章と水面下の再交渉を繰返し、条約復活に全力を傾注、外務卿の井上薫(かおる)も尚泰引渡しの譲歩案まで用意して、竹添に再交渉の妥結を促した。
この時期、清国側でも新任の駐日公使黎庶昌(れいしょしょう)や李鴻章らも分割条約の手直し復活の方向へ傾きつつあった。
再度、分割の危機に直面した琉球人指導層は急遽旧三司官の富川盛奎(せいけい、唐名は毛鳳来=もうほうらい)を清国へ派遣し、総理倚門や礼部(れいぶ)へ琉球全面返還の請願書を提出させた、琉球側の請願趣旨を考慮した総理衙門は対日強硬論を堅持し、李鴻章と竹添の再交渉の妥結を牽制した。
その結果、再度の琉球分割の試みは挫折したものの、その後も日清両国は朝鮮問題や越南問題と連動させながら、琉球問題の外交的解決を模索しつづけた。
八〇年代の後半から九〇年代前半に至っても、琉球問題は日清外交の懸案として位置づけられ、日清戦争への導火線として伏流しつづけたのである。
2 近代化の矛盾と迎合同化政策と近代化
top
沖縄と日清戦争
七〇年代の廃琉置県処分から八〇年代の琉球分割交渉をへて日清戦争に至る狭義の琉球処分の時期、内外で琉球=沖縄の選択肢をめぐる論争と対立がつづいた。
廃琉置県以前の日清両属派と日本専属派の論争は、置県後には独立派と自治派の対立・論争へと引継がれたほか、日本本土の他府県から入り込んできた寄留商人や官吏・警察官・教員などの内地人(ヤマトウンチュ)が近代化の推進役となり、日本への併合派を形成した。
三派の潜在的対立は日清戦争がはじまると顕在化した。
沖縄島の中城(なかぐすく)湾に日本海軍が集結し、清国艦隊も琉球へ向かったとのニュースが東京の諸新聞を経由して伝わると、沖縄は異常な緊張に包まれた。
寄留商人などの内地人(併合派)は同盟義会を組織し、清国艦隊来襲の際には琉球独立派の拠点(久米村)を焼き払う計画を立て、刀剣銃で武装して軍事訓練に励み、県当局も秘かに刀剣類を県官吏に配布して不測の事態に備えた。
置県後の新教育の拠点となった師範学校や中学校でも義勇隊が組織され、生徒たちは軍事訓練に動員された。
沖縄人(ウチナーンチュ)の中でも、日清戦争を琉球独立のチャンスとして期待していた独立派は、清国の勝利を祈願するために各寺社へ集団参詣して気勢を上げた。
日清開戦の前年に『琉球新報』を創刊して文明化・近代化のためのヤマト化を模索しつつあった太田朝敷(ちょうふ)らの自治派は、日本軍の連勝ニュースを報じて独立派の動きを牽制すると共に、併合派の久米村襲撃計画をも「軽佻者」(けいちょうしゃ)の軽挙妄動として非難せざるを得なかった。
沖縄社会を引き裂いた日清戦争は、九五年前半には日本側の勝利に終った。
県当局や寄留商人などの併合派は戦勝祝賀会を開催して気勢を上げ、戦勝に乗じて沖縄的風俗や習慣を徹底的に排除しつつ、自らのイニシアティブを振りかぎして戦後改革に踏み出した。
尚順(しょうじゅん)・太田らの自治派も戦後の新たな情勢を沖縄の主体性回復のチャンスとみなし、終戦直後に士族層を結集して愛国協会、ついで公同会を組織して特別自治制要求運動を開始した。
清国の敗北によって琉球独立派の権威と影響力は著しく失墜したが、その一部はなお救国=独立の選択肢に固執した。
諸勢力の対抗
沖縄人内部の党派対立を克服して自治派だけでなく独立派の大部分をも再結集した公同衾は、戦後の九六年から九七年にかけて、松方正義(総理大臣)あての「請願書」と「趣意書」を作成し、県知事を尚家に委任すること、「議会を置き各地方より議員を選挙」することなどの要求項目を掲げ(「公同衾関係資料」『那覇市史』)、組織的な署名運動を沖縄全域で展開、短期間に七万三三〇〇人の署名を得た。
公同衾の請願運動は一定の大衆的基盤の上で、主体性回復を目指した自治運動へ発展する展望を示していたのである。
請願代表団は九七年秋に上京して請願書などを提出したが、戦勝によってもはや沖縄人の要求を顧朧する必要はなくなったと判断しか政府当局は、請願代表団の要請を一蹴した。
公同会=自治派は、戦後の県政改革のイニシャティブを握る県当局の寄留商人などの併合派へ合流する以外に、もはや別の選択肢を提起する意思も能力も持ち合わせてはいなかった。
特別自治制要求運動と前後して、新たな選択肢を提起したのは、置県後に新教育を受けて成長した地方農村出身の青壮年層であった。
東風平(くちんだ)村の謝花昇(じゃはなのぼる)や金武(きん)村の当山久三らは九九年一月、「自治の制度」や「地租の改正」に対応するため沖縄倶楽部を設立し、機関誌『沖縄時論』を発刊、「衆民の為めに奸邪(かんじゃ)を排し、平民的進歩主義の先鋒」となることを宣言した(『琉球新報』広告)。
謝花らの提起した選択肢は、政府=県当局の差別的統治策と対抗する手段として、近代日本の諸制度を主体的に導入し、それに依拠して沖縄の主体性を回復することであった。
主体的統二派を形成した謝花らは日清戦争後の県政改革の主導権をめぐって、併合派や併合派に合流した自治派とも対決せざるを得なかったのである。
沖縄県の地租改正すなわち土地整理と参政権問題が当面の主戦場であった。
九九年二月から三月にかけて、謝花らは衆議院の土地整理法審査委員会に「陳述書」を提出、杣山(そまやま、共有林)の民有を要求したが却下され、杣山は官有と規定された。同時期に、衆議院特別委員会では、謝花らの要請を受け容れた高木正年議員によって沖縄県への選挙法施行の議案が提出され審議に付されたが、貴族院で審議末了となり、事実上先送りされた。 |

図72 謝花昇
|
この間、奈良原繁(ならはらしげる、県知事)らの併合派や太田朝敷らの琉球新報は、謝花らの参政権要求運動などを激しく批判し、主体的統一派への弾圧を強めた。
一九〇〇年一月、農工銀行株主総会の役員選挙で敗北した謝花は最後の活動拠点を失い、同志たちも次々に離脱したため、「平民的進歩主義」を掲げた沖縄倶楽部の主体性回復運動もまた挫折を余儀なくされたのである。
旧慣制度の改革
沖縄社会の内発的な主体性回復の試みを押し潰しながら、政府=県当局は置県から日清戦争前後まで温存されてきた旧慣諸制度の改革に主導的に着手した。
旧慣温存を必要とした歴史的諸条件(琉球「所属」問題をめぐる日清間の外交交渉、独立派の琉球救国運動、松方財政に主導された明治政府の増税至上策)がひとまず歴史的役割を終えたからである。
地方制度の改革は日清戦争の直後から漸進(ぜんしん)的に積重ねられ、他府県とは区別された特別区制、特別町村制、特別県制などの時期をへて、一九二〇年前後に全国並みの地方制度へ移行した。旧慣の根幹であった土地・租税制度の改革(地租改正)は日清戦争後の県政の最重要課題であった。
政府=県当局は戦争終結時点で秘かに地租改正法案を策定したものの施行せず、四年後の九九年に土地整理法を制定して抜本的改革に着手した。
同時期に、新植民地の台湾でも土地調査事業が実施されている。
沖縄の土地整理事業は諸政治勢力の利害対立を引き起こしながらも、終始政府=県当局の主導の下に推進され、五年の歳月をかけて土地所有権などを確定し、一九〇三年に終了した。
その結果、民有地は一一万二九二一町歩、新地租額は二一万円余と算定され、旧貢租額四六万円の半額以下となったものの、新たに賦課される地方税を加算すれば、実質負担額にほとんど変化はなかった。
しかし、土地整理によって沖縄の社会・経済は一定の影響と変化を蒙った。
第一に近代的所有権の確立にともなって土地売買が自由となり、緩慢ながらも社会の階層分化を促進したこと、
第二に納税主体となった個々の家族と経営が、地租の金納化と商品=貨幣経済の拡大に対応して換金作物の栽培へ傾斜したこと、
第三に諸制度を全国並みの帝国体制へ統合するための諸条件が形成されたこと、等々である。
もっとも、土地整理の後も「芋(いも)を作って食べ更に砂糖を売って米その他を買う」経済構造は、依然として維持された(『仲原善忠選集』上巻)。
甘蔗作(かんしょづくり)・製糖業を中心とする糖業モノカルチャー的構造を維持しながら、近代化の荒波へ漕ぎ出した
県経済は、きびしく不安定な環境に取り巻かれていた。
第一に諸産業の生産力は著しく低く、他府県との市場競争に耐えうる水準には達していなかった。
第二に貧弱な県財政の中で貧弱な勧業費予算だけでは諸産業の政策的保護は期待できなかった。
第三に日清戦争後の日本資本主義の糖業政策は台湾糖業を重視して沖縄糖業を見捨てる方向へ傾斜したこと、等々である。
経済の近代化
このような厳しい環境の下で、二〇世紀初頭の十数年間、県経済の近代化が試行された。
糖業の面では、政府=県当局は一九〇六年臨時糖業改良事務局を設置、近代的な製糖工場を建設して分蜜糖(ぶんみつとう)の製造を開始したものの、数年後には財政整理のため事務局は廃止され、製糖工場も県外資本の沖台製糖会社へ払い下げられた。
しかも、数年後の一九一七年には、沖台会社も台湾糖業との競争に押され、台湾の台南製糖会社の傘下に入った。
近代化の牽引役としての分蜜糖業は政府の政策的保護を得られず、県内全産糖量の三割を超えることはできなかった。
沖縄糖業の七割は農民的経営の可能な含蜜糖(がんみつとう、黒糖)で占められ、従来通り零細農民グループの共同作業で手工業的に生産された。
黒糖生産農民は砂糖商人に従属して収奪されただけでなく、砂糖消費税によって国家的収奪の対象ともなった。
にもかかわらず、二十世紀初頭の十数年間黒糖生産が好調であったのは、第一次世界大戦などで世界の砂糖需給バランスが崩れ、糖価が上昇しつづけたためであった。
一九〇〇年代まで一〇〇斤当たり五~六円の水準で推移した黒糖価格は、一〇年代前半には七円を超え、一九年・二〇年に至って二〇円を上まわり、糖業者の間からあだ花のような「にわか成金」を輩出した(太田朝敷『沖縄県政五十年』)。
糖業黄金時代に対応して、二十世紀の一〇年代以降、陸上・海上の交通網も漸次整備された。
一四年に県営鉄道(那覇~与那原)、電車(首里~那覇)、馬車軌道(与那原~泡瀬)、一七年に乗合いバスが登場し、県営鉄道は二〇年代に嘉手納(かでな)線、糸満(いとまん)線が開通して近代的輸送機関の役割を担ったものの、国有鉄道はついに導入されることはなかった。
海上輸送の面では、沖縄航路をめぐる寄留商人の大阪商船・鹿児島郵船と尚家の広運会社の過当競争が激化し、一六年には広運会社は大阪商船に身売りするに至った。
同化政策と教育
近代化の担い手を養成するための教育は置県以来、「言語風俗ヲシテ本州卜同一ナラシムル」こと(『沖縄県史』一二巻)、すなわち日本への同化=ヤマト化を目標として展開されたものの下層社会には浸透せず、日清戦争をへて九〇年代後半になると、学齢期児童の就学率はようやく三〇%台に上昇し、地方役人層の子弟はほぼ全員就学するに至る。
十九世紀末から二十世紀初頭にかけて、一般民衆の子弟の就学問題を重視し始めた県当局は、階層上昇志向をあおる功利的就学奨励策を推進すると共に、様々の理由で就学に拒否反応を示す階層に対しては、「尊皇愛国(そんのうあいこく)の道」を知るための国民の義務として就学を督促(とくそく)した。
一九〇一年、四年制義務教育制度を発足させたのも、一般民衆の子弟全員を就学させ、同化教育を徹底させるためであった。
就学させない保護者に対しては、罰金を科するなどの強制的方法がとられた。
県当局の強力な就学奨励督促に加えて、日露戦争前後には民衆の内部からも就学要求が芽生え始め、一九〇六年には就学率は九〇%を超えた。
もっとも、政府=県当局は財政難を理由に、中等教育の拡大・普及には消極的に対出し、唯一の県立中学校の入学定員枠を若干拡大しただけであった。
増大する進学希望者の要望に対応するため、民間の有志家が七〇〇〇円の寄付を集めて私立の養秀中学校を建設、一九〇八年に開校した。
師範学校については、九六年に校舎新築、定員増をはかると共に、順次女子講習科、男子講習科、簡易科を設置し、教員急増の需要に対応した。
二十世紀初頭には、県内の小学校校長・教員は師範学校出身者によって占められるに至る。
しかし、教育界の実権は依然として他府県出身者(ヤマトウンチュ)ににぎられ、「滋賀県出身者でかためた中頭(なかがみ)、国頭(くにがみ)郡と九州出身者でかためた島尻(しまじり)郡とが相拮抗しているかの観があった。
沖縄出身者はよそもの扱い」であった(比嘉(ひが)春潮『沖縄の歳月』)。
教育界の差別的状況に不満を抱く沖縄出身の教員たちも、差別的状況を克服するためには沖縄人の社会的地位の向上を図らなければならないとの立場から、同化教育・皇民化教育の推進に積極的に呼応した。
政府=県当局も「教育家と云ふものは実に非常の大責任を負ひ、善良なる第二の国民を造出す人々である」と位置づけ、教員たちに地方住民の模範となることを要求した(『琉球教育』九五号)。
沖縄差別とヤマト化
太田朝敷らの『琉球新報』も他府県人の沖縄に対する差別的言動を激しく批判しながら、沖縄の文明化すなわち国民的同化の達成こそ差別克服の道であるとの立場から、同化教育の推進を積極的に支援した。
しかし、差別的状況は改善されるどころかますます深刻化した。
一九〇三年、大阪の博覧会会場周辺に設置された「人類館」に、中国人・韓国人・琉球人・アイヌ・「生蕃」などが見せ物として収容されていることを知った中国人留学生が抗議行動を展開すると、沖縄でも『琉球新報』が一方で自らアイヌや「生蕃」への差別意識を露呈しながら、他方では沖縄差別の鼓吹(こすい)者として「人類館」の設置者を激しく論難した。
大阪の人類館事件は日本社会における人種差別・民族差別の根強さを示すと共に、沖縄社会の内部でも沖縄独自の文化(言語・風俗・習慣など)を排除して国民的統合すなわちヤマト化を推進しようとする風潮を一層促進する梃子(てこ)の役割を果たした。
ヤマト化の中心的推進役は官製教員組織としての沖縄教育会が担った。
沖縄教育会は学校教員だけでなく官吏・軍人・警察官などの有志家も参加した半官半民の組織であり、機関誌として『琉球教育』(一九〇六年『沖縄教育』と改称)を発行したほか、夏期講習会・名士講演会・県下大運動会などを開催して、教育・文化のヤマト化に拍車をかけた。
名士講演会には志賀重昂(しげたか)らの著名人が招かれた。
一九一一年四月、旧慣土地制度(地割制度)の調査のために来県した河上肇(京都帝国大学助教授)も教育会に招かれ、「新時代来る」の演題で国家主義・帝国主義に心酔しない沖縄人に「大いに意を強くする」旨の講演を行った。
河上の講演は同化教育に水を差すものとして沖縄社会の有識者から猛反発を受け、『琉球新報』も連日激越な批判の論陣を張った(河上肇舌禍(ぜっか)事件)。
他方で、伊波普猷(いはふゆう)・普成(月城=げつじょう)兄弟をはじめ沖縄の主体性を模索しつつあった知識人たちの中には、河上の講演に共鳴する者も少なくなかった。
二十世紀の初頭、沖縄の歴史と文化の研究を開始した伊波普猷らは、日琉同祖論の視点から国民的統合(ヤマト化)を受け容れながらも、個性的な沖縄文化の価値を強調し、公然と沖縄民族の「復活」を主張した。
しかし、沖縄社会において国民的統合と沖縄の主体性回復を同時に推進することは不可能となりつつあった。
政府=県当局は両者を二律背反と受け止め、同化=皇民化の徹底のために一切の沖縄的なものを排除し、歴史隠滅政策を推進する方向へ傾斜したからである。
3 沖縄を越える人々 海外移民
top
ソテツ地獄
土地整理と特別制度の撤廃によって沖縄県が近代日本の帝国体制へ完全に併合されたのは一九二〇年前後のことで、日本経済が第一次世界大戦期間の好景気のピークを過ぎ、大戦終結と共に一転して戦後恐慌へ向かう時期と重なっていた。
主要輸移出品の黒糖の相場は二〇年一月平均の一〇○斤当た旦二五円から急落し、年平均にして二四円、翌年には一二円となり、二六年以後は一〇円以下へと下落しつづけた。
分蜜糖や他の農工産品の価格も同様に崩落した。
甘蔗作モノカルチャー的構造を特徴とする県経済は、砂糖価格の大聚落によって深刻な影響を受けざるを得なかった。
銀行や企業の倒産が相次ぎ、県や市町村の財政難は深刻化した。
全県下のいたるところで、主食の米や雑穀はおろか芋さえも手に入れることができない飢民が溢れ、食糧不足に陥った人々は野生のソテツの実や幹の澱粉(でんぷん)を調理して食べ、飢えをしのぐ状態であった。
ソテツの幹の調理方法を誤って一家全員が中毒死する事件も相次いだ。その悲惨な状況を、新聞などのメディアは「ソテツ地獄」と報道した。 |

図73 ソテツの群落
|
二〇年代から三〇年代前半までつづいた経済不況=ソテツ地獄は、第一次世界大戦後の日本資本主義を襲った世界恐慌の沖縄的発現形態であったが、世界経済の変動に起因する不況圧力が沖縄で増幅された背景には、前近代的な零細農民の含蜜糖(黒糖)生産、糖業以外の県内諸産業における生産力の極度の低さ、黒糖需要度の高い全国農村の不況にともなう需要量の減少等々、様々の要因が存在した。
沖縄社会を覆い尽くしたソテツ地獄の状況が全国的に注目されるようになると、その原因や対策をめぐって、県内外で多くの論議が展開され、銀行の放漫乱脈経営、モノカルチャー的経済構造、輸移出入の不均衡なども原因の一つに挙げられたものの、最大の原因が県民の国税負担(国庫収入)と政府の国庫支出のアンバランス、すなわち国税収奪にあることを、多くの論者は一致して指摘している。
併合策の帰結
国庫収支の不均衡(国税収奪)がソテツ地獄状況の最大原因であることを二四年の時点で指摘したのは、『琉球新報』の太田朝敷であった。
その翌年、新城朝功は「結局多年に亘(わた)る国税の苛斂誅求(かれんちゅうきゅう)に加うるに、国家事業の不備を以てした為め、遂に民力の疲幣、産業貿易の不振、資金の枯渇となって現れ、結局今日の惨状を呈するに至った」と結論し、置県以来の「やらずぶったくり」の沖縄政策こそソテツ地獄状況の根本原因であることを強調した(『瀕死の琉球』)。
伊波普猷も「要するに、沖縄県窮乏の原因は、遠くは中央政府の搾取とその政策の責であり、近くは、沖縄それ自体の支配階級の消費過多によるものである」と指摘し、沖縄救済のためには「島民の負担をうんと軽くして貰わなければ駄目だ」と強調した(『孤島苦の琉球史』)。
県民負担の軽減と共に、緊急に実施すべきプロジェクトとして、県営鉄道の国営移管、国立の水産試験場・農事試験場・高等工業学校の創設などが提案された。
置県以半五〇年間の併合策によって、沖縄は制度的には近代日本の帝国体制に完全に組込まれたものの、その間「経済的、物質的内容方面ニハ、何等(なんら)ノ進歩発展ヲ見ズシテ、四百年前卜少シモ変リナイヤウノ状態」に放置されてきたことを、県当局も認めざるを得なかったものの(『沖縄県史』一五巻)、国有鉄道や国立大学はおろか国立高等工業学校さえも沖縄近代化のプロセスに登場することはなかったのである。
「やらずぶったくり」の沖縄併合策の帰結と世界経済の変動に起因する糖価暴落の相乗作用によって、ソテツ地獄に突き落とされた沖縄社会には、半世紀前の廃琉置県処分前後のような混乱と動揺が再現された。
失業状態のまま路頭に放り出され、生きるための新たな活路を求めて、県外や海外へ流出する人々が急増したのである。
ハワイ移民
土地整理が開始された一八九九年には、すでに当山久三らの尽力によって最初の海外移民二七人がハワイへ送り出されていたものの、一九〇〇年代には年平均二一〇〇人、一〇年代には一七五〇人に過ぎず、移民先もほとんどハワイに限られていた。
海外移民が急増しだのはソテツ地獄の時期以降で、農業経営の破綻などで働く場所もなく失業状態にあった沖縄の人々は、一攫千金の夢を懐(いだ)いて陸続(りくぞく)として海外へ移民した。
移民先はハワイだけでなく、中南米と南洋地域が主となった。
二〇年代後半の五ヵ年間で、沖縄人移民は一万五六八七人(年平均三一三七人)に達し、日本全国の移民の二〇%前後を占めた(石川友紀『日本移民の地理学的研究』)。 |

図74 沖縄県出身移民の分布
(石川友紀『日本移民の地理学的研究』裕樹書林1997年所収図を一部改変)
|
ハワイや中南米の沖縄人移民は、当初は甘蔗・コーヒーなどのプランテーション農場で働いたが、しだいに都市へ集中して雑貨店や軽工業などを経営するようになった。
各地に定住した沖縄人移民は言語・風俗・習慣などの相違から、日系移民社会の中でも沖縄差別に苦しみ、相互扶助・親睦団体として沖縄県人会を組織して独自のコミュニティを形成した。
他方では、海外における出稼労働で溜財し、数年後に帰郷して豪邸を建てた成功者の事例が注目され、一攫千金を夢見る移民熱に拍車をかけた。
出稼
海外出稼の対象地は日清戦争後に併合された台湾、第一次世界大戦後に日本の信託統治領となった南洋諸島へも拡大された。
台湾へ渡った沖縄人は、巡査・官吏・教員・弁護士から工員・土木人夫・行商・家政婦に至るまで、あらゆる職種に進出した。
沖縄師範学校卒業後教員免許状を持ちながら県内で就職できない沖縄人の多くは台湾へ渡り、台湾人子弟の同化教育・皇民化教育にあたった。
台湾在住の沖縄人の多くは日本人社会の中で差別をうけながらも、社会的地位の上昇を図るために、台湾の植民地統治に協力した。
南洋諸島への出稼・移民は二〇年代後半から三〇年代を通じて増加しつづけ、全国比五〇%以上を維持した。
三九年時点で、南洋諸島の日本人七万七〇〇〇人余の内、沖縄人は四万五七〇一人に達した(『沖縄県史』七巻)。
当初出稼で甘蔗栽培や漁業などに従事した沖縄入は、しだいに定住して各種の職域に進出し、あるいは家族呼び寄せて沖縄人コミュニティを形成するに至り、相互扶助のための沖縄県人会を各入植地に設立した。
沖縄人コミュニティ
海外へ流出した移民や出稼と共に、仕事を求めて全国の他府県へ向かう出稼労働者もソテツ地獄の時期に急増した。
二〇年代以降、沖縄入出稼労働者は毎年一万人を超え、二五年八月の統計ではほとんど二万人に達した。
その大半は阪神地区や京浜地区、とりわけ大阪(四二%)、神奈川(一四%)に吸収され、経済不況で苦しんでいた全国の農村地帯からの出稼労働者と共に、日本資本主義の労働市場に組込まれた。
沖縄人出稼労働者の場合、紡績資本などの低賃金維持政策によって集中的に雇用され、経営難による人員整理の際には真っ先に解雇の対象とされる短期出稼型の労働者として位置づけられた。
低賃金労働力として集中的に導入された沖縄人労働者を取巻く労働環境は劣悪で、肺結核などを患い廃人同様の姿で放り出される者や日本社会のなかの沖縄差別に苦しめられる者も少なくなかった。
在日沖縄人労働者の多くは、劣悪な条件の中で生き拔くために、各地に相互扶助・親睦団体としての沖縄県人会を結成し、工場側に待遇改善の要求を提出したり、他府県出身の労働者との交流を重ねて、全国的な労働運動への関心をも高めた。
いつの日か成功者として帰郷する夢を懐いて海外や全国の他府県へ渡った沖縄人労働者の多くは、きびしい環境の中で風土病や文化摩擦に苦しみ、貧苦の生活に耐えながら営々と働きつづけ、世界各地や日本全国の各地に定住して沖縄人コミュニティを形成・拡大すると共に、ソテツ地獄の沖縄に残された家族や親戚へも送金しつづけた。
二六年の県外出稼入のうち、送金人員は二万五五二人、送金額は七九万余円であった。
海外移民からの送金額は二六年から三七年までの一二年間、毎年平均二〇五万円に達した。
海外移民・県外出稼労働者からの送金によって、ソテツ地獄に苦しむ沖縄県の輸移出入バランスは辛うじて破綻を免れることができたのである。
二 近代の帰結・沖縄戦 top
1 太平洋戦争と沖縄の位置
南進国策と「南の生命線」
太平洋戦争の直前まで、沖縄県は軍隊とも軍事施設とも無縁の唯一の県であった。
歴史的な特殊事情から徴兵令も他府県からはるかに遅れて一八九八(明治三十一)年一月から施行されたが、郷土部隊をもたない沖縄の現役兵は遠く海を渡って九州各県の連隊に入営しなければならなかった。
ただ、徴兵事務をとりあつかう沖縄連隊区司令部が那覇市に置かれていたので、「連隊区司令官の乗馬一頭が唯一の軍備」と揶揄されていた。
沖縄にはじめて軍事施設が建設されたのは一九四一(昭和十六)年夏のことであった。
同年七月から十月にかけて中城(なかぐすく)湾(沖縄本島)と船浮(ふなうき)湾(西表島)に陸軍要塞が建設され、それぞれ重砲兵連隊が駐屯した。
奄美大島をよくか南西諸島の要塞は、南方から石油やゴムなどの軍需物資を運んでくる輸送船団を援護する中継基地であった。
一九四〇(昭和十五)年七月、第二次近衛(このえ)内閣は「大東亜(だいとうわ)共栄圈」構想を国策の基本としてかかげ、「南進国策」にふみきった。
同年九月にはドイツ・イタリアと三国同盟をむすび、英米との武力衝突をも辞さない武力南進への姿勢をみせ、同年九月にはフランス領の北部インドシナに進駐し、戦線は泥沼化した中国大陸からさらに南方へ拡大していった。
南進国策は、これまで軍事とは縁のなかった沖縄を「南方の生命線」に浮上させた。
県内でも以前から「朝鮮が満州にたいする咽喉であると同様沖縄は南進日本の咽喉であり国防上其他からしても将来頗(すこぶる)る重要な地点である」(昭和十四年十月『琉球新報』)などと南進論がとなえられ、第一次大戦後委任統治頷となった内南洋諸島へ多数の県民が農業・漁業移民として進出していた。
四一年一月、「翼賛(よくさん)知事」の異名をもつ第二五代県知事早川元(はやかわはじめ)が国民服姿で赴任したが、新任知事は、「南方発展の第一線に立つ沖縄県人の使命は愈々(いよいよ)重大さを加えてきたのであるから県民は豪宕(ごうとう)雄大なる祖先の民族精神を益々高揚し、以て国策に寄与すべきである」妥里延『沖縄海洋発展史』序文)と南進ブームをあおった。
四一年十二月八日、落成したばかりの沖縄放送局から突如として太平洋戦争(大東亜戦争)開戦の臨時ニュースが流れてきた。
「帝国陸海軍は本八日未明西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れり」と繰返し流される大本営発表は、時局認識にとぼしいと嘆かれていた県民にも異様な興奮と緊張の波紋をもたらした。
全島要塞化と県民総動員
太平洋戦争の緒戦で破竹の進撃をみせた日本軍も四二年六月のミッドウェー海戦の大敗を転換点として米軍を主力とする連合軍の反撃の前に連敗をつづけて後退しつつあった。
主力空母群と多数の航空機と搭乗員を失った日本は中部太平洋において制空権と制海権を失い、四三年二月のガダルカナル島の悲劇的な撤退へとつながっていく。
一九四三(昭和十八)年九月、日本の戦争指導部は、戦局の劣勢を挽回すべく、千島から内南洋、ビルマにいたる圏内に戦線を縮小し、これを「絶対国防圏」として死守する戦略を立てた。
しかし、戦局は予想よりも早く悪化の一途をたどった。
一九四四年二月、米機動部隊は日本海軍の中枢基地であるトラック島に奇襲攻撃をかけ艦船と航空機に壊滅的な損害をあたえた。
絶対国防圏の最前線に位置するマリアナ諸島(サイパン、テニアン、グァム)も風前の灯(ともしび)となった。
これを支えるために台湾から南西諸島にいたる位置に強力な航空基地を建設する計画が浮上してきた。
四四年三月、大本営は戦局の窮迫に対応して新たな作戦方針「十号作戦準備要綱」を策定した。
新作戦は、「日本本土と南方圏を結ぶ交通線を確保するために南西諸島に十数個の航空基地を建設し、これを防備するために第三二軍を新設し配備する」というものであった。作戦準備は航空戦力が主で、地上戦力は従という位置づけであった。
沖縄は航空基地として戦略的に重要な位置にあることが認識されたのである。
新作戦方針にもとづいて沖縄守備軍・第三二軍(初代軍司令官・渡辺正夫中将)が新設され、四四年四月一日をもって活動を開始した。
守備軍の任務は航空基地の整備・補給・警備であるが、四月現在、警備すべき飛行場は一個も完成していなかった。
軍中央の航空作戦計画では、南西諸島と台湾に各一個師団の航空部隊を配備することになっていた。
これだけの大部隊を収容するために、伊江(いえ)島、沖縄本島、宮古島、石垣島、南大東(みなみだいとう)島に一五個(奄美(あまみ)を除く)の飛行場を建設しなければならなかった。
四月から五月にかけて、飛行場大隊や要塞建設部隊が続々と移駐してきて、学校や公民館や民家に分宿した。
全島で飛行場建設と陣地構築の突貫工事が一斉に開始された。
各飛行場で連日、三〇〇〇~五〇〇〇人の防衛隊・義勇隊・徴用工・勤労奉仕隊などが動員され、軍民一体となって緊急建設作業に汗をながした。
沖縄県は戦時行政の重点施策として、
①前線の軍隊に兵士を送ること、
②軍需工場に労務者を送ること、
③食糧を増産し供給すること、の三大目標をかかげて本土の軍需工場へ数万人の徴用工を送り出していた。
そのうえに飛行場建設へ徴用や勤労奉仕で根こそぎ動員されたので労働力が払底し、食糧増産に支障をきたし、沖縄戦中の栄養失調やマラリア死の遠因になった。
サイパン玉砕と県外疎開
一九四四(昭和十九)年七月、全島要塞化の突貫工事に忙殺されている沖縄にサイパン玉砕の噂が伝わってきた。
サイパンなどのマリアナ諸島には沖縄から多数の農業開拓移民が入植していた在留邦人約三万人のうち県出身者が六割をしめていた。
そのサイパン移民の沖縄出身者が義勇隊を編成して戦闘に参加したうえ、孤島にのこされた婦女子までも激しい地上戦闘にまきこまれて集団自決においこまれたという。
親戚縁者の悲惨な最期を知った県民の衝撃は大きかった。サイパンの悲劇は沖縄の未来図のようにおもわれ、「次は沖縄だ」という噂がささやかれた。
七月七日、政府はサイパン玉砕の反省から、南西諸島の老幼婦女子の疎開(引揚げ)を決定した。
計画では、沖縄本島から九州へ八万人、宮古・八重山から台湾へ二万人を七月中に疎開させるという緊急措置だった。
政府の通達をうけた沖縄県では特別援護室をもうけて疎開事務を開始した。
市町村、町内会・部落会、学校などを通じて疎開督励を行ったが順調には進まなかった。
この時期、沖縄近海はすでに“閉ざされた海”になっていた。
米軍の潜水艦部隊は“群狼作戦”と称して南方と本土を結ぶ輸送船団をねらって無差別攻撃を展開し、沖縄守備隊の戦闘部隊や徴用労務者などをのせた輸送船が雷撃で沈められる被害が相次いでいた。
危険な海路を、老人と子供と母親だけで疎開することに多くの人々が尻込みした。
疎開業務が難渋しているとき、同年十月十日の大空襲(十・十空襲)がはからずも追い風になった。
十・十空襲は、レイテ作戦の前哨戦として米機動艦隊が南西諸島の軍事施設を破壊すべく決行した奇襲攻撃であった。
終日五波におよぶ空襲で、完成まぢかな飛行場や港湾施設が大きな損害をこうむったほか、県都那覇は焼夷弾(しょういだん)で市街地の九割を焼き払われてしまった。
初めて経験する近代戦の破壊力のすさまじさと、沖縄戦は必至という実感が追い風になって、疎開に踏切る人々が急増した。
焼け野原となった那覇から疎開者をのせた軍用輸送船が続々出ていった。
七月中旬から翌年三月までに一八七隻、約六万人が沖縄本島から九州方面へ渡っていった。
しかし翌年三月二十三日に出発する予定の疎開船は、米軍上陸部隊の空襲をうけて那覇港で炎上し、これをもって沖縄本島からの本土疎開に終止符が打たれた。
結局、県外疎開者は、九州方面へ約八万人、台湾へ約二万人にとどまり、約五〇万人の県民が約一〇万人の軍隊と共に戦場の島に閉じこめられることになった。
防衛隊・義勇隊
沖縄戦け総動員体制の極限だといわれている。
正規の軍人とはべつに防衛隊・学徒隊・青年義勇隊・女子救護班などに根こそぎ動員された。
はじめ防衛隊は、飛行場建設の労務部隊として「陸軍防衛召集規則」にもとづいて編成されたものであった。
「防衛召集規則」は四四年十月に改正され、満一七歳から四五歳までの男子に拡大して適用されるようになった。
たまたま同年十一月から第三二軍の最精鋭部隊であった第九師団(武部隊)がにわかに台湾に引抜かれることになった。
レイテ決戦に関連して台湾の防備を強化するための緊急措置だった。
軍中央(大本営)は後詰めの部隊を送らなかったので、穴埋めは現地自給で間に合わせるしかなくなった。
年末から翌年三月にかけて二次にわたる大規模な防衛召集が行われ、約二万五〇〇〇名が戦闘部隊の指揮下に入って地上戦闘の第一線に立たされることになった。
だがそれでも兵力不足は埋められなかった。
「一木一草をも戦力化せよ」という軍の方針のもとに中等学校や青年学校(青年団)の男女が学徒隊や義勇隊に編成された。
一般には「鉄血勤皇隊」や「ひめゆり学徒隊」などの学徒隊が知られているが、地域の男女青年団から役場を通じて部隊に徴集された義勇隊や救護班のほうが多数をしめている。
学徒隊だけで二〇〇〇名以上になるが青年団の義勇隊の実数はまだ不明である。
防衛隊や学徒隊、義勇隊は装備や訓練の状態からみても戦闘要員とはいえない後方勤務の補助部隊にすぎなかったのだが、敵上陸後はこれらの“にわか兵隊”までも最前線に動員されて、弾薬運搬、通信隊、伝令、救護班などに従事させられたあげく、最後は正規兵と共に爆雷や手榴弾をもって斬り込みに参加する者もあった。
こうして防衛隊の約六割、学徒隊の約五割が戦死した。 |
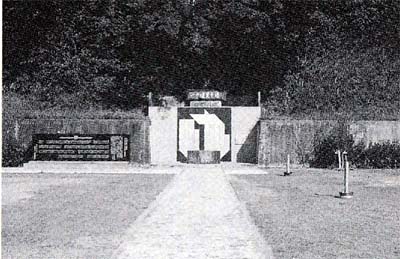
図75 鉄血勤皇隊一中健児の塔
|
沖縄住民の戦闘参加はこれにとどまらなかった。
米軍総数約五四万八〇〇〇人にたいして沖縄諸島の守備軍十一万人という劣勢で長期持久戦をつづけるために各部隊は避難民にたいしても手当たりしだいに戦闘協力を強要した。
弾薬運搬、炊事班、救護班、道案内、避難壕の提供、食糧の提供などで、多くの一般住民が戦闘に協力させられた。
2 沖縄戦の経過 top
アイスパーク作戦
一九四三(昭和十八)年から翌年にかけて米軍は中部太平洋を二つのコースで北進していた。
一つはニューギニアからフィリピン方面に向かうマッカーサー陸軍最高司令官のコース、今一つは中部太平洋の島づたいに台湾、沖縄方面にむかうニミッツ海軍最高司令官のコースである。
ニミッツは当初台湾攻略作戦の計画を検討していたが、マッカーサーが予想より早くレイテ島とルソン島に進撃したので、日本軍が南西諸島に建設しつつある巨大な航空基地に関心をひかれた。
目的が本土進攻のための航空基地の確保である以上、より少ない兵力で沖縄の航空基地を攻略した方が有利であるという構想が浮上した。
四四年十月、米統合参謀本部は当初の台湾攻略作戦を変更して小笠原(硫黄島=いおうじま)――沖縄の攻略作戦に変更し、「アイスパーク(氷山)作戦計画」(沖縄攻略作戦計画)を策定した。
四五年三月十七日、硫黄島では一ヵ月におよぶ地上戦闘のすえ日本軍守備隊は全滅、米軍の攻略の矢は次の沖縄本島に向けられた。
一九四五年三月二十三日、米機動部隊が沖縄本島へ空襲を開始、翌日から南部・島尻地区へ艦砲射撃を開始した。
沖縄戦が始まったのである。
米軍の最初の目標は沖縄本島の西方に浮かぶ慶良間(けらま)諸島であった。
沖縄本島上陸作戦に備えて、慶良間諸島に艦隊の停泊地と補給基地を確保し、長距離砲をすえて日本軍の軍司令部がある首里方面を砲撃する作戦であった。
三月二十六日早朝、米歩兵一個師団が三〇〇隻の舟艇をならべて慶良間に上陸を開始した。
諸島には敵上陸部隊を背後から奇襲攻撃する海上特攻隊(海上挺進隊)がひそかに配置されているだけであったが、約三〇〇隻の特攻艇は米軍の砲爆撃でほとんど破壊され、少数の特攻部隊は山中に退避して小型銃器をもってゲリラ戦に移行した。
守備隊から置き去りにされ雲霞(うんか)のような上陸部隊を目のあたりにした島民は保護を求めて友軍(日本軍)陣地に殺到したが、作戦の足手まといになるという理由で追い返された。
逃げ場を失いパニックにおちいった人々は凄惨(せいさん)な「集団自決」に追い込まれた。
その犠牲者は約五〇〇人におよんだ。
沖縄本島上陸作戦
慶良間諸島に足場を固めた米軍上陸部隊(第十軍)は、四月一日、沖縄本島の中部西海岸に上陸作戦を開始した。
艦船約一五〇〇隻、陸軍・海兵隊七個師団、一八万三〇〇〇人、さらに後方にひかえる後続部隊や補給部隊、海軍部隊などをあわせると総勢五四万八〇〇〇人にのぼり、中部太平洋のどの激戦地にくらべても数倍する大規模な兵力だった。 |

図76 米軍の沖縄本島上陸
|
猛烈な艦砲射撃と爆撃で海岸線をたたいた後、上陸部隊が上陸用舟艇と水陸両用戦車をならべて幅一三キロの密集隊形で読谷山村(よみたにざんそん)と北谷村(ちゃたんそん)の海岸に殺到してきた。
これを迎え撃つ沖縄守備軍(第三二軍)は、沖縄本島に第二四師団〈山部隊〉、第六二師団〈石部隊〉、独立混成第四四旅団〈球部隊〉の二個師団半、防衛隊や義勇隊などの補助兵力をあわせても十一万人に満たず、敵上陸部隊に水際で正面から反撃すれば一週間ともたない劣勢であった。
第九師団を台湾に引き抜かれて弱体化した沖縄守備隊は、飛行場の守備を第一任務とする従来の作戦方針を変更して、本土決戦の時間をかせぐための持久戦をつづけるために、自ら飛行場を破壊して、首里北方の中部丘陵地帯の地下陣地に主力部隊を集結させた。
上陸部隊の第一の目標は飛行場を奪取することであったが、読谷(よみたん)山村の読谷飛行場(陸軍北飛行場)も北谷村の嘉手納(かでな)飛行場(陸軍中飛行場)もすでに放棄されて守備部隊は撤退していた。
米軍は陸からも空からもほとんど抵抗を受けることなく無血上陸をはたし、午前中には第一の目標である読谷、嘉手納の両飛行場を占領した。
さらに無抵抗の進撃をつづけて翌二日には東海岸に到達し、沖縄本島を南北に分断することに成功した。
上陸地点の読谷山村や北谷村には飛行場建設や陣地構築に協力してきた数千人の村民が敵前に放置されていた。
米軍の急進撃で逃げ場を失った住民は集落周辺のガマ(洞窟)や墓の中に避難したが、避難所はただちに上陸部隊に包囲され、絶望的になった避難民の中には自ら命を断つ者が続出した。
読谷山村チビチリガマでは地元住民が集団で自害し、北谷村嘉手納でも女子義勇隊が「集団自決」に追い込まれた。
四月五日までに中頭(なかがみ)郡の大部分を制圧した米軍は、上陸地点の渡具知(とぐち)に海軍軍政府を開設し、避難民対策の軍政を開始した。
米軍の“捕虜”になった数千人の避難民は金網の中に隔離され、はやくも戦後の“アメリカ世”の生活が始まった。
北部・離島の戦況
沖縄本島を南北に分断した上陸部隊の一部は北部国頭地方(国頭郡)の制圧に向った。
海岸線を北進した米第六師団は一〇日間に本部(もとぶ)半島の突端に達し、さらに北上した海兵連隊は十三日に本島北端の辺戸(へど)岬に到達した。
本部半島の山岳地帯には、国頭支隊(宇土部隊)約三〇〇〇人が配置されていた。
支隊の本拠地である八重岳では十四日から山岳戦が始まった。
日本軍は、防衛隊や学徒隊もくわえて起伏のはげしい地形に拠って小型兵器で応戦したが、米海兵隊は突撃を繰返したすえに、十六日早朝、頂上を奪取した。
宇土隊長以下の残存兵は包囲網を突破して国頭方面に移動し、十月初めまでゲリラ戦をつづけた。
国頭の山林には中・南部から疎開してきた約一五万人の避難民が食糧難とマラリア病に苦しんでいたが、そこへ敗残兵が割り込んできたので食糧強奪やスパイ嫌疑の住民虐殺など、いまわしい軍民摩擦が多発することになった。
伊江島には東洋一を誇る飛行場が建設され、国頭支隊から派遣された守備隊が布陣していた。
守備隊約二七〇〇人のうち約二一〇〇人は現地徴集の防衛隊、青年義勇隊、女子救護班、婦人協力隊であった。
四月十六日、米第七七歩兵師団が軍艦三六隻による艦砲射撃の後に南岸から上陸してきた。守備隊はガマ(洞窟)や亀甲墓(かめこうばか)や塹壕(ざんごう)にたてこもって、速射砲や機関銃で応戦したが、陣地は次々破壊され、死傷者が続出した。
守備隊の指揮下におかれた島民も急造爆雷、手榴弾、竹槍などをもって斬り込みに参加した。
なかには髪を切って男装した女子義勇隊員や乳児をおぶった婦人協力隊員の姿もあった。
一週間の激闘の後、守備隊はほぽ全滅、戦死者約四五○〇名のうち約一五〇〇名は伊江島の村民だった。
伊江島の攻防戦では米軍も一七二名の戦死者をだしたが、この中には著名な従軍記者アニー・バイルも含まれていた。
久米島には小規模の電波探信隊(鹿山隊)が配置されているにすぎなかったが、米軍は六月下旬、飛行場を建設する目的で上陸してきた。
山中にたてこもった鹿山隊員は「下山する者は米軍に通ずる者として銃殺する」と警告し、違反者とみなされた島民はスパイ容疑で次々に“処刑”された。
鹿山隊の住民虐殺の犠牲者は七家族二〇人におよんだ。
宮古島には第二八師団(豊部隊)の将兵・朝鮮人軍夫・防衛隊などの約三万人の部隊が駐屯し、陸海軍あわせて三個の飛行場が建設されていた。
石垣島にも独混第四五旅団(宮崎部隊)約一万人が駐屯し三個の飛行場が建設されていた。
沖縄戦の初期、英国東洋艦隊が両諸島に砲爆撃を行って市街地に損害をあたえたが、米軍の上陸はまぬがれた。
距離的に遠いため本土進攻の航空基地としては不適と判断されたためだった。
海上交通が途絶した宮古・八重山では、長期の軍民雑居の状態で極度の食糧不足におちいり、おまけに戦争マラリアがまん延したために軍民に多数の犠牲者がでた。
とくに八重山郡では軍命によってマラリア有病地へ強制移動させられたために郡民の五四%が罹患(りかん)、死亡率二二%に相当する三六四七人が犠牲になった。
中部戦線の激闘
首里城の軍司令部壕に戦闘指揮所をおく守備軍は、首里北方の嘉数(かかず)高地(宜野湾(ぎのわん)村)、前出高地(浦添(うらぞえ)村)に地下陣地をきづいて第六二師団(石部隊)を中核とする精鋭部隊を配置していた。
米軍が進発地点とする宜野湾村普天間(ふてんま)から首里までは約二〇キロの一本の県道で結ばれているが、沿道の丘陵地帯につらなる二重三重の地下陣地線が両軍の主力攻防戦の舞台となった。
米第二四軍団は、四月五日から戦車隊を陣頭にたてて大謝名(おおじゃな)-我如古(がねこ)-和宇慶(わうけ)の陣地線に一斉攻撃をかけてきた。
米軍は上陸直後からただちに飛行場と砲兵陣地を整備して、空・海・陸からの砲爆撃の援護のもとに歩兵部隊を突撃させてきた。
守備部隊は、地下の陣地壕で猛烈な砲爆撃にたえながら至近距離からの砲撃で敵戦車に多大な損害をあたえると共に、日没をまって地下陣地からはいだして敵陣地に夜襲をかけて撃退した。
四月六日、日本軍は「菊水第一号作戦」を発動、九州や台湾から航空機を発進させて沖縄本島を包囲している米艦隊に攻撃を開始した。
特攻機の体当たり攻撃は米艦船に少ながらぬ損害をあたえ、米軍に衝撃をあたえたが、航空作戦と地上作戦の連携がかみ合わず、戦況を好転させるほどの効果は発揮できなかった。
中部戦線の一進一退の攻防戦は南北わずか二〇キロの区間で五〇日余もつづき、守備軍が意図する持久戦になった。
最新兵器と最大規模の物量を投入した米軍も、日本軍の頑強な抵抗にあって予想以上に大きな損害をだし、二ヵ月間の戦死傷者は約二万六〇〇〇人にのぽった。
戦闘の熾烈さは米兵の中に戦争神経症が多数でたことでも想像できる。米軍戦史で「戦史上もっとも熾烈な血みどろの戦闘」と表現される激戦がつづいた。
第一線の激戦場にも現地住民が多数まきこまれていた。
青壮年の男性はほとんど防衛隊に召集され、残る婦人や少年たちまで弾薬運搬、水くみ、炊事班、道案内、野戦包帯所の救護班などに動員された。
疎開もできずに村内にとどまっていた老人、幼児、母親たちは数百人単位で集落周辺の洞窟壕に避難していたが、激戦にまきこまれて多くの一般住民が犠牲になった。
たとえば激戦地の前田高地に隣接する前田集落では、総人口の五九%が戦没している。
五月中旬までに守備軍は主力部隊の約八五%にあたる約六万四〇〇〇人が戦死し、「軍の戦力は消耗しつくした」と軍司令部も判断し、だれもが残存部隊の総突撃をもって沖縄戦は終るものと信じていた。
しかし五月二十二日の作戦会議で軍司令部は急きよ作戦方針を変更して島尻への撤退をきめた。
「軍は残存兵力をもって玻名城(はなしろ)-八重瀬岳(やえざだけ)-与座岳(よぎだけ)-国吉-真栄里(まえざと)の線以南喜屋武(きやん)半島地区を占領し、努めて多くの敵兵力を牽制抑留すると共に、出血を強要し、もって国軍全般作戦に最後の寄与をする」(防衛庁戦史室『沖縄方面陸軍作戦』)というものだった。
沖縄戦はまさに「時間かせぎの捨て石作戦」になったのである。
地獄の南部戦線
沖縄守備軍の残存部隊は五月二十五日頃から南部(島尻郡)の喜屋武半島に移動を開始した。
梅雨の泥道に足をとられながらの撤退作戦は難渋した。
約一万人と見積もられる負傷兵を輸送する車両はなく、全軍の備蓄食糧が一ヵ月分しか残ってない状況では戦闘能力のない重傷患者の面倒をみる余裕はなく、風原(はえばる)陸軍病院をはじめ各地の野戦病院では歩行不能の重傷患者には自決用の毒薬や手榴弾をあたえて放置するはかなかった。
軍司令部も二十七日から津嘉山壕(つかざんごう)を中継して摩文仁(まぶに)の洞窟壕に移動した。
牛島軍司令官は小禄(おろく)地区の海軍部隊にも喜屋武半島へ合流するように命令したが、大田実海軍司令官は、喜屋武半島に海軍部隊約一万人を収容できる空間がないことを理由に小禄海軍飛行場の地下陣地から動かなかった。
海軍部隊は六月六日から米軍海兵隊の攻撃をうけ、約一週間の戦闘で壊滅、十三日、大田司令官は有名な
「沖縄県民カク戦ヘリ。県民ニ対シ後世特別ノ御高配ヲ賜ランコトヲ」の電文を打ったあと、豊見城(とみぐすく)の司令部壕で自決した。
島尻地方のサンゴ石灰岩の台地には無数の地下洞窟(ガマ)が点在し、地元住民や首里・那覇方面から移動してきた避難民が避難生活をおくっていた。
そこへ突如として戦闘部隊が移動してきたので、南北七キロ足らずの喜屋武半島には約三万人の軍隊と十数万人の避難民が雑居して袋のネズミになった。
六月上旬、米軍は喜屋武に総攻撃をかけてきた。
守備軍は八重瀬岳~与座岳の断崖線で頑強に抵抗したが、十七日、戦車部隊が断崖線を突破して岬の台地に侵入し、地下に潜った日本軍に爆雷や火炎放射器やガス弾で“馬乗り攻撃”をくわえてきた。
断末魔の戦場では、日本兵に壕を追い出されて弾雨のなかをさまよったり、食糧を徴発されて餓死したり、敵の投降呼びかけに応じて壕を出て行こうとするとスパイ嫌疑で“処刑”されたり、幼児が泣くと敵に探知されるといって“始末”されるなど、いまわしい事件が多発した。
長期間にわたる極限状況下の避難行動で、軍人も避難民も最後に行きつくところは、「人間が人間でなくなる」状態だった。
米軍は摩文仁の牛島軍司令官にたいして再三降伏を勧告したが軍司令官はこれを拒否して抵抗を続行した。
六月十八日、第一〇軍司令官バックナー中将は、真栄里付近で戦闘状況を視察中、日本軍の攻撃をうけて戦死、最高司令官の死にパニック状態となった米軍は付近の避難民や負傷兵に至近距離から無差別に掃討をくわえて多くの犠牲者をだした。
翌十九日、牛島軍司令官は残存部隊に最後の軍命令を打電して指揮をうちきった。
これをもって沖縄守備軍(第三二軍)の組織的抵抗はおわっだが、軍命令は戦闘の終結ではなく、「最後迄敢闘シ悠久ノ大義ニ生クペシ」という遊撃戦(ゲリラ戦)への移行を命じたものであった。
牛島軍司令官と長参謀長は六月二十三日未明(二十二日の説もある)、摩文仁の軍司令部壕で自決したが、残存兵は南部戦線の地下や北部戦線の山林の中でなおゲリラ戦を続行した。
喜屋武半島の掃討を終えた米軍は、七月二日、沖縄作戦の終了を宣言した。
しかし、守備軍の最高司令官と参謀長が自決したために終戦交渉の責任者が不在となり、ゲリラ戦はなお長くつづいた。 |

図77 米軍による洞窟壕攻撃
|
ようやく変則的な形で、嘉手納基地の米第一〇軍司令部で両軍代表による日米降伏調印式が行われたのは、ミズーリ号上の降伏調印式から五日も遅れて九月七日のことだった。

図78 平和祈念公園(摩文仁岬) |

図79 「平和の礎」と平和祈念資料館 |
近代沖縄の総決算
沖縄戦は沖縄近代の総決算といわれている。
琉球処分以来沖縄県民が歩んできた「ヤマトヘの一体化」路線は国家総動員体制の中でさらに徹底され、沖縄守備軍の配備と全島要塞化の軍民一体行動の中で高揚し、ついには学徒隊や青年義勇隊の戦闘協力と犠牲という悲劇的な形で最高潮に達した。
若人たちは、自分たちが皇国と友軍(日本軍)のために命をささげることが沖縄人が一人前の日本人になるための試練であると教えられて戦場に赴いた。
しかし、日本国民がはじめて体験した戦場の現実は若人たちの甘い幻想をうらぎるものだった。
日本軍にとって沖縄作戦は、国土や国民を守るためでなく、本土決戦を有利にするための時間かせぎの捨て石作戦にしかすぎなかったのだ。
しかも、あれだけ献身的に協力してきた皇軍将兵は、沖縄人を心底から信頼することなく、「沖縄人はみんなスパイだ」と放言してはばからなかった。
これらの戦場体験から受けたトラウマ(心的傷害)は戦後の本土からの分離と異民族支配の“アメリカ世”にもちこされて複雑に屈折していくことになる。
沖縄戦の一つの特徴は、米軍の軍事占領が長期におよんだことである。
米軍は上陸と同時にニミッツ布告を公布して沖縄を日本政府の施政権から切離し、戦時刑法を基本法とした軍政を開始した。
住民を収容地区に囲い込み、その間に各地に軍用キャンプを建設し、米軍が排他的に自由に使用できる「基地の島」につくりかえたのである。
沖縄の分離統治の方針は五一年九月の対日講和条約第三条で国際的に認知され、七二年五月の施政権返還まで「太平洋の孤児」といわれる状態がつづいた。
日本軍が「不沈空母」として利用したこの列島を、米軍は「太平洋の要石」とよんで極東戦略の前線基地として利用されつづけたのである。
沖縄県民が沖縄戦の体験と戦後の米軍統治の体験から学んだことは、この世に戦争ほど残忍で非人間的なものはないという事実と、「命どぅ宝」という沖縄の古い言葉にこめられた生命尊重の思想であった。
この血のにじんだ教訓を後世の人々に伝えるために、沖縄県は摩文仁岬の平和祈念公園に「平和の礎」を築き、沖縄戦のすべての戦没者の名前を刻んだ。
約二四万人の戦争犠牲者の名前が、軍人と民間人の区別なく、男女の別なく、米軍将兵や植民地出身者も含めて国籍のへだてなく並んでいる。
「平和の礎」を“沖縄の心”のシンボルとして沖縄県は世界に向かって平和のメッセージを発信しつづける平和の島として生きることを宣言している。
三 米軍統治から日本復帰言 top
1 収容所からの出発
引き裂かれた列島
一九四五(昭和二十)年四月一日、沖縄本島に上陸した米軍は、ニミッツ布告(米国海軍軍政府布告)を公布して占領地区住民の保護と統治にあたった。
ニミッツ布告第一号は「日本帝国政府の総ての行政権の行使を停止す」と宣言しており、事実上、沖縄・奄美(あまみ)の南西諸島は日本本土から切離された。
九月七日、嘉手納(かでな)基地で日米両軍代表の間で降伏条約調印式が行われて沖縄戦は正式に終結した。
降伏文書では、米軍の占領にゆだねた琉球列島の区域は、北は北緯三〇度線、南は北緯二四度線となっている。
北緯三〇度線は、もともと沖縄守備軍(第三二軍)の守備範囲をさだめた作戦上の区分線だったのだが、四六年一月、GHQ(連合国軍総司令部)は「若干の外郭地域を政治上日本から分離することに関する覚書」をだして、この区域の日本からの分離を追認した。
マッカーサー最高司令官は「沖縄人は日本人でなく、本土において日本人と同化したことはなかった。
日本人は彼らを蔑視している」という談話を発表して沖縄分離を正当化した。
沖縄は、北は北緯三〇度線、南は北緯二四線内に閉じこめられ、「祖国なき沖縄」「太平洋の孤児」と呼ばれることになった。 |

図80 嘉手納基地
|
軍政下におかれた南西諸島は、さらに奄美・沖縄・宮古・八重山の群島に分割され、四群島それぞれに軍政府と民政府が設置された。
分割統治のもとで互いの往来は制限され、南海の「海上の道」は寸断され閉ざされた。
ゼロからの出発
米軍上陸直後の四月上旬から沖縄本島の占領地区に避難民収容所がもうけられ、はやくも戦後の「アメリカ世」が始まった。
全島一四ヵ所の収容地区に約三六万人の避難民が収容され、それ以外の占領地区には米軍のキャンプが建設された。
戦後の沖縄は「はじめに基地ありき」から出発したのである。
軍政府は徹底的に破壊された沖縄本島の行政機関の空白を埋めるべく、八月に沖縄諮詢(しじゅん)会を発足させ、翌年四六年四月に沖縄民政府を設立した。
しかし、沖縄住民の強い要望にもかかわらず、民政府知事は軍政府が任命し、民政府といっても自治権をもたない下請け機関にすぎなかった。
以後、二十数年にわたって自治権獲得は沖縄住民の最大の政治課題となる。
軍政下での食糧不足と米兵犯罪の頻発、そして任命知事制は、しだいに軍政への不満をうっ積させ、各地で軍民のトラブルが発生した。
やがて人々は政党を結成し、生活保障と住民自治を要求して政治活動に立上がった。
しかし、軍政府幹部の回答はこうだった。
「軍政府はネコで沖縄はネズミである。ネコの許す範囲しかネズミは遊べない」。
テント村にひしめく人々は、無一物の中から生活用品を生み出す技術を身につけた。
戦場跡から拾ってきた砲弾殼や飛行機の残骸などが、鍋・椀・フライパン・洗面器・鍬などに生まれ変った。
石川収容所で戦後最初の学校が開校されたのは、まだ中部戦線で一進一退の死闘が繰広げられている五月上旬のことだった。
青空教室で砂文字をかいて授業が始まった。
軍政府は英語中心の教育を期待していたが、教師たちは「日本語による教育」をゆずらなかった。
“戦果”と密貿易ブーム
連合国軍の日本占領が一段落した四五年十月頃から、沖縄本島では不要となった軍用地がじょじょに開放されて、住民の旧村への復帰が許可された。
廃墟となった故郷に帰ってきた人々はまず散乱した遺骨と不発弾や兵器の残骸を片づける共同作業から始めた。
つぎに掘っ建て小屋を建て、田畑を耕して生活の再建に取り組んだ。
四六年四月に第一次通貨切り替えでB円軍票が法定通貨になり、六月からは軍物資の無償配給が打切られて賃金制になったために、多くの人々は現金収入を得るために軍作業(基地業務)に通った。
しかし正規の給料だけでは衣食住の必要経費をまかなえない。
軍作業からの帰りに軍用物資をかすめてくる“戦果”が副業になった。
戦果ブームは戦後復興の必要悪だと黙認される風潮もあったが、「窃盗行為で米兵に撃たれた死傷者、年間五五〇人」(『うるま新報』紙)といういたましい記事も散見された。
四七年度からガリオア資金(占領地域救済基金)の援助が開始されたが、県外からの引揚者で人口は五六万人(四八年度)に膨張し、食糧と医薬品などの欠乏は栄養失調者やマラリア病死者を続出させた。
物資不足をおぎなうために、台湾~香港~沖縄~本土のあいだを密航船が活躍するようになった。 |

図81 B円軍票
|
香港ルートでは沖縄から砲弾殼や屑鉄を積んで行き日用品とバーター貿易を行った。
日本ルートではアメリカ製の医薬品と日本製の木材・鍋・瀬戸物などと交換した。
密貿易船は日本の教科書や参考書、日本国憲法や教育基本法などの解説書なども運んできて沖縄の行政再建にも貢献した。
民衆の旺盛な復元力が人為的な国境線を乗り越えて「海上の道」を復活させたのだった。
伝統文化への回帰
衣食住についで人々が渇望したものは、戦場でずたずたにされた心の傷をいやしてくれる沖縄の伝統芸能であった。
空缶と落下傘糸でカンカラ三線(さんしん)がつくられ、ドラム缶を改造した蒸留装置で島酒(泡盛)が密造され、空缶ランプをともして「命のお祝い」が催された。
テント長屋の中から戦場体験をうたった島唄が生まれてきた。
琉球処分後の近代沖縄では、帝国政府による同化政策と皇民化教育によって琉球王朝文化を源流とする沖縄の伝統文化は蔑視され、抑圧されてきた。
沖縄県は「標準語励行」を県治の熏要施策にかかげて方言撲滅につとめ、風俗改良運動を展開して沖縄風の生活文化を追放してきた。
日本の敗戦は一種の解放感をもたらしたのである。
沖縄民政府は四六年四月の発足早々から、生残った沖縄芝居の経験者を集めて公営の劇団を編成し、収容地区を巡回させて慰問公演を行わせた。
松(団長・島袋光裕)、竹(団長・平良良松)、梅(団長・伊良波尹吉)の三劇団員は沖縄民政府の公務員の待遇をうけた。
沖縄芝居や琉球舞踊や三線音楽のプログラムは各地の収容所で人気を博し、時には数千人にのぼる観客がおしかけて、古き良き時代の郷土の姿をおもいだして涙と笑いのひとときをすごした。
収容所時代から始まった沖縄文化の復興は、県民に自己のアイデンティティを自覚させ、異民族支配下での「沖縄ルネッサンス」をもたらし、ひいては復帰後の沖縄芸能ブームにまでつながっていく。
2 「太平洋の要石」
基地の中のオキナワ
ー九四八(昭和二十三)年秋頃、極東における冷戦がきびしさを増すなかでアメリカの沖縄政策が固まってきた。
沖縄の施政権はアメリカが保有し、自由に使用できる恒久基地を建設する、という内容だった。五〇年初頭から恒久基地の軍工事ブームが始まった。
五〇年六月、朝鮮戦争が勃発した。アメリカは対日講和を急いだ。
同年十一月、対日講和七原則が発表された。沖縄、小笠原をアメリカの信託統治領とする方針が明らかになると、沖縄現地は騒然となった。
軍政下では日本復帰を唱えることはタブーになっていたが、超党派で復帰促進期成会を結成し、集会や署名運動を展開した。
復帰署名は全有権者の七二・一%にのぼった。しかし復帰すべき祖国の政府はこの要請を黙殺した。
五一年九月、サンフランシスコ講和会議で対日平和条約が調印された。
条約第三条で、北緯二九度以南の南西諸島と小笠原は無期限にアメリカが保有することになった。
アメリカの極東戦略は、アリューシャンからグアムに至るまでの軍事的な反共包囲網を構築し、その要石(キーストーン)の位置に沖縄を置いた。
在沖米軍は沖縄基地の重要性を誇示するかのように軍用車両のナンバー・プレートに(keystone of the Pacific=天平洋の要石)」というニックネームを標示した。
平和条約第三条によって無期限の支配権を得たアメリカは、恒久的な統治機関として、一九五二年四月一日、琉球政府を創設した。
琉球政府はアメリカ式の三権分立の形態をとって、行政主席・立法院・民裁判所で構成されているが、最終的な権限は琉球列島米国民政府(USCAR・ユース力ー)に握られている。
しかも、行政主席と民裁判所主席判事は任命制とし、唯一公選制を認められた立法院議員の選挙も任命主席の与党に有利なように極端な小選挙区制がもうけられた。
恒久的な沖縄統治のレールがしかれた直後から、米軍は軍事優先政策を露骨におしすすめた。
五三年四月、米国民政府は布令第一〇九号「土地収用令」を公布して軍用地の強制接収に乗出してきた。
すでに基地の面積は全土の一二・七%を占めていたが、冷戦に対応する核基地の拡張・整備のために、さきに開放された集落や田地を再収用することになったのである。
土地取上げに反対する住民をカービン銃とブルドーザーで追い払いながら集落をまるごと鉄条網で囲いこんでいった。
五三年四月から五五年七月までに軍用地は全土の一四%、耕地面積の四二%に拡大され、「基地の中の沖縄」という状況となった。
父祖伝来の土地を銃剣とブルドーザーに奪われた銘苅(めかる)、具志(ぐし)、伊江島(いえじま)、伊佐浜(いさはま)などの農民は行政主席や立法院に請願デモを繰返した。
軍事的植民地化の状況に民族的な危機感をおぼえた一般住民も「祖国の土地を守れ」を合い言葉に、土地取上げ反対に立上った。
大衆運動の高まりの中から、これまでタブーとされてきた「祖国復帰」が公然と叫ばれるようになった。
沖縄住民の抵抗運動に、米軍は「日本復帰運動は共産主義者の扇動である」という理由をつけて露骨な攻撃をくわえてきた。
人民党弾圧事件、琉球大学学生退学処分事件、沖縄教職員会弾圧事件など、言論・集会・出版にたいするきびしい監視と処分、本土渡航の制限、軍雇用員の思想調査と解雇、日の丸掲揚の禁止等々の思想統制が日常化した。
島ぐるみ土地闘争
琉球政府立法院は、五二年十一月以来、一一回におよぶ軍用地強制接収にたいする中止要望決議を繰返してきたが、五四年四月の請願決議では、「土地を守る四原則」を宣言して運動の目標を明確にした。
①軍用地の買上げ、永久使用、使用料の一括払いに反対(一括払い反対)、
②軍用地の適正完全補償(適正補償)、
③損害にたいする適正賠償の実施(適正賠償)、
④不要土地の即時返還・新規接収絶対反対(新規接収反対)の四原則が以後数年にわたる土地闘争の統一要求になった。
しかし、四原則要求にたいしてアメリカ政府は一括払いと新規接収を柱とする「プライス勧告」をもって答えてきた。
五六年夏、民衆の怒りはついに爆発した。全琉五六市町村に「土地を守る会」が結成され住民大会が開かれた。
全人口の半数におよぶ約四〇万人が各地の大会に参加した。
土地を守る総決起大会は琉球大学をはじめ各地の高校にまでひろがっていった。
七月の「四原則貫徹県民大会」には全島から約一五万人の住民が詰めかけ、まさに島ぐるみの闘争へと発展した。
米国民政府は、琉球大学のデモ隊が「ヤンキー・ゴー・ホームー」と叫んだ行動を「共産主義に同調した反米活動」とみめつけ、大学当局に圧力をかけて学生会のリーダー七名を退学・謹慎処分においこんだ。
このことが逆に民衆の反米感情に油をそそぐ結果となった。
「忍従の民」といわれてきた沖縄の民衆が、島ぐるみの大衆行動に立上って自己主張したのは歴史上初めてのことだった。
四年余にわたって全島をゆるがした土地問題は、やがて代表団をワシントンへ派遣して琉米折衝の場に舞台を移したが、アメリカ政府の懐柔策などで、一括払いこそ回避できたものの、新規接収などは容認するという譲歩案で妥結した。
しかし、島ぐるみ闘争で高まった沖縄民衆の政治意識は来るべき復帰運動の大きな力になった。
土地闘争で政治意識を高めた那覇市民は、五六年一二月の那覇市長選挙で“抵抗のシンボル”となった瀬長亀次郎(せながかめじろう)沖縄人民党書記長を当選させ、瀬長市長が米国民政府の新布令で追放されると、瀬長支持派の後継市長と市会議員を送り出すなど、市民自身が米軍統治への抵抗を行動で示した。
五七年六月、沖縄民衆の抵抗に危機感を抱き始めたアメリカ政府は大統領行政命令をだして基本的自由の保障や高等弁務官制などの新政策を発表、翌五八年九月にはB円軍票の米ドルヘの通貨交換、住宅資金や産業資金の融資などの経済向上政策をうちだして宥和政策へと転換した。
3 日本復帰運動 top
復帰協の結成
一九六〇(昭和三十五)年四月二十八日、沖縄県祖国復帰協議会(復帰協)が結成された。
172-87
四月二十八日は平和条約第三条が発効して沖縄が日本から分離された「屈辱の日」である。
政党、労働組合、教職員会、青年団協議会、婦人連合会、学生自治会など二〇余団体がこの屈辱の日に決起して復帰要求県民大会を開催し、復帰協の結成を宣言した。
参加者は日の丸の小旗と提灯をうち振って市内をデモ行進した。
日の丸は、祖国復帰要求のシンボルでもあり、米軍統治への抵抗をも意味した。
この日行われたデモ行進が、以後十数年にわたって毎年繰広げられる「四・二八復帰行進」や北緯二七度線上の「返還要求海上大会」の第一歩となったのである。
誕生まもない復帰協が統一運動組織の真価を発揮したのが「アイク・デモ」だった。
一九六〇年六月、アイクの愛称をもつアイゼンハワー大統領は日本訪問の旅に出発したが、安保改定反対運動の高まりに日本訪問を断念、予定を変更して沖縄に立ち寄ることになった。
復帰協はただちに「復帰請願デモ」を計画して県民へ参加を呼びかけた。
要請の内容は、①沖縄の祖国への返還、②日の丸掲揚の自由、③渡航制限の撤廃、④主席公選、⑤国家的経費の負担、などであった。
六月十九日、嘉手納基地に降り立って那覇市内の琉球政府に向った大統領一行が市街にはいると歓迎の星条旗よりも日の丸と赤旗がふえ、沿道では一万五〇〇〇人の武装兵と請願デモの隊列が対峙してものものしい空気につつまれていた。
危険をかんじた大統領一行は琉球政府・米国民政府の合同庁舎から予定コースを変更して裏道を通って那覇空港へと急行した。
復帰協は勝利宣言を発して自信を深めた。
二・一決議と佐藤首相訪沖
一九六二(昭和三十七)年二月一日、立法院は「施政権にかんする要請決議」を全会一致で採択した。
立法院の復帰要請決議は恒例になっていたが、今回の決議は国運の「植民地解放宣言」を引用して、
「沖縄を日本から分離することは、正義と平和の精神にもとり、将来に禍根を残し、日本の独立を侵し、国連憲章の規定に反する不当なものである」ときびしく批判していた。
決議文は日米両政府はじめ国連加盟国一〇四ヵ国に発送され、国際的な反響をよんだ。
六三年二月にコナクリで開かれたA・A連帯会議は、アメリカの沖縄撤退と沖縄の日本復帰を要求する決議を採択し、四月二十八日を「沖縄デー」として国際共同行動の日と決めた。
日米政府は協調して沖縄問題の解決に取組まねばならない立場に立たされた。 |

図82 1969年4月28日沖縄デーの統一集会
(那覇市与儀公園)
|
六二年三月、ケネディ大統領は「沖縄新政策」を発表した。
ケネディ新政策は、
「沖縄の核基地は極東の平和の維持に重要であるので引続き維持する」と従来の沖縄統治政策をふまえながら、
「琉球住民の安寧(あんねい)・福祉・経済開発の増進のために日米協力体制で経済援助を行う」などと、日米共同で沖縄の基地を維持・管理していくという「日米琉新時代」構想をうちだした。
ところが、六一年二月に就任したキャラウェー高等弁務官は県民への宥和政策どころか、「沖縄において自治は神話である」と公言し、弁務官の絶大なる権力を発動して、立法院決議の法案にたいする拒否権行使、金融界の汚職・不正・背任行為の摘発、経営者の粛清、軍雇用員の思想調査と追放、本土渡航パスポートの拒否など、強硬政治を断行した。
“キャラウェー旋風”はさらに、政財界人をふるえあがらせ、親米与党の自民党を分裂させ、ついには大田任命知事が高等弁務官へ辞表を提出するという異常事態をまねいた。
一九六四年十月、後任主席を指名するための臨時議会が招集された。
主席指名阻止をめざして立法院を包囲した五〇〇〇人規模の阻止団と機動隊五〇〇人が三日間にわたって衝突を繰返し、数十人の負傷者と逮捕者をだすという惨事になった。
大混乱の中で、結局松岡政保(まつおかせいほ)が第四代行政主席に任命されたが、新主席は就任式で、「私は最後の任命主席でありたい」と宣言した。
一九六五年八月、佐藤栄作(さとうえいさく)首相が戦後はじめて総理大臣として沖縄を訪問することになった。沖縄返還運動とベトナム反戦運動の高まりを背景にした緊張した空気の中で、総理大臣としては戦後はじめての沖縄訪問であった。
八月十九日、那覇空港におりたった佐藤首相は、「私は沖縄の祖国復帰が実現しないかぎり、わが国にとって戦後は終ってないことを承知しております」と述べた。
迎える沖縄側は、歓迎派と抗議派にわかれた。
佐藤首相は行政主席、与党、財界などが主催する歓迎式典で、経済援助の拡大と本土並一体化論の演説を行って「復帰近し」のムードづくりにつとめた。
同日、復帰協は「佐藤総理に対する祖国復帰要求県民大会」をひらいて抗議決議を行い大規模なデモ行進を行って宿舎のホテル前の軍用道跡一号線に座り込んだ。
ベトナム軍需輸送でフル回転していた幹線道路は五万人のデモ隊に占拠されて遮断され、首相一行は米軍基地内で一夜を明かすはめになった。 |

図83 佐藤栄作
|
教公二法闘争と主席公選
一九六六(昭和四十一)年五月、中央教育委員会から立法院へ「教公二法」の議案が送付された。
教公二法(地方教育区公務員法と教育公務員特例法)は、教職員の身分を本土なみに保障する一方、政治活動の制限や争議行為の禁止、勤務評定など、教職員の権利を制限する条項が含まれている。
戦後一貫して復帰運動や土地闘争、自治権闘争などの大衆運動をリードし、復帰協や革新共闘会議などの中核部隊をなしてきた教職員会が政治活動の制限をうけて弱体化することは革新勢力にとって死活問題であった。
六六年から翌六七年にかけて、教職員会と復帰協傘下の団体は「教公二法阻止県民共闘会議」を結成して阻止行動を展開した。
地域オルグ、ハンスト、十割年休闘争を進めると共に、立法推進派を阻止するために立法院を包囲する実力行動に踏み切った。
デモ隊と警官隊の激突がくりかえされ、流血の惨事になりかねない事態に長嶺議長はついに本会議の中止を決断した。
結局、法案はしばらく棚上げになり、まもなく廃案になった。
この激烈な政治決戦の背景には、主席公選は遠くないという保革両陣営の政治判断があった。
教公二法闘争は来るべき主席公選の前哨戦でもあったのだ。
六八年二月一日、アンガー高等弁務官は立法院で、「大統領行政命令を改正して、来る十一月の第八回立法院議員選挙と同時に主席公選を実施する」と発表した。
同年十一月、行政主席、立法院議員、那覇市長の三つの大きな選挙が実施されることになった。
選挙戦は復帰問題の選択をめぐる保革両陣営の総力戦になった。
革新陣営は革新共闘会議を結成し、主席候補に、教職員会会長、復帰協会長を歴任し、一貫して復帰運動を指導してきた屋良朝苗(やらちょうびょう)を擁立した。
保守陣営は本土自由民主党の支援をうけた沖縄自民党が中心になって保守陣営のエースといわれる那覇市長の西銘順治(にしめじゅんじ)を立てた。
三大選挙の争点は復帰問題と基地問題にしぼられた。
革新共闘会議は「平和条約第三条撤廃、核基地の撤去、安保条約反対、即時・無条件・全面返還」を統一綱領にかかげた。
対する保守陣営は、日本政府に歩調をあわせて「本土一体化」をかかげ、復帰時期尚早論で論戦をかまえた。
「本土一体化」政策は前年十一月の第二次佐藤・ジョンソン会談で合意されたもので、沖縄返還問題を継続討議とし、その間に経済援助の拡大と本土一体化をはかるという政策だった。 |

図84 屋良朝苗
|
本土一体化のための日米琉諮問委員会も設置されていた。
内外から注目された選挙戦の結果は三選挙とも革新共闘会議が勝利した。
「即時・無条件・全面返還」の潮流はもはや阻むことのできない勢いになった。
沖縄返還協定
七〇年安保改定を目前にひかえて、沖縄返還問題はもはや猶予ができなかった。
一九六七(昭和四十二)年十一月の第二次佐藤・ジョンソン会談では、小笠原諸島の返還だけをさきに決めて、沖縄返還問題は「両三年以内に返還の時期について合意する」というあいまいな表現で継続討議に付された。
その後、政府レベルで返還交渉が進められた結果、「沖縄問題の核心である核基地問題については、基地の態様と自由使用権は現状維持として施政権の返還時期を早める」ことで合意に至った。
六九年十一月、佐藤・ニクソン会談がワシントンで開かれる運びになった。
沖縄現地では「即時・無条件・全面返還」を要求する統一行動が波状的に一週間も続けられた。 |

図85 1972年沖縄返還協定調印抗議集会
|
一方、全国統一行動は主要都市二一○ヵ所で取組まれ、ストと集会に参加した人数は本土三七〇万人、沖縄で六万五〇〇〇人と発表された。
全国的なはげしい抗議行動のなかをワシントンに向かった佐藤首相はニクソン大統領と首脳会談を行い、十一月二十二日、日米共同声明を発表した。
声明は「一九七二年施政権返還」を約束するものであったが、肝心の基地の態様については「核ぬき、本土並み返還」と説明されながら声明文への明記はなく、実質的には核疑惑をのこしたまま米軍基地の機能維持と自由使用をみとめる内容であった。
これ以後、一九七二年五月の復帰の日まで、沖縄は息つくまもなく激しい政治の嵐に揺れ動いた。
七〇年一月、全軍労は軍雇要員の大量解雇に反対して四八時間ストを決行した。佐藤・ニクソン共同声明をふまえて米軍は基地雇用員二千数百人の大量解雇を発表、基地の再編合理化策にストライキを繰返して抵抗する全軍労の闘争は全国から注目された。
七〇年十二月の深夜、基地の街・コザ市で大規模な反米騒動が突発した。些細な交通事故がきっかけで日頃の米軍の人権軽視への不満が爆発、数千人の一般市民が八十数台の車を焼き払った。沖縄の反米感情を象徴する事件として内外に大きな反響をよんだ。
七一年五月十九日、返還協定に抗議して復帰協傘下の労組、団体がゼネストを決行、県民総決起大会には全島から約一〇万人が参加した。
七一年六月十七日、この日、沖縄返還協定は東京とワシントンでテレビで相互に中継しながら同時に調印された。協定は本文七ヵ条からなり、施政権の返還(一条)、安保条約の適用(二条)、米軍基地の維持(三条)、対米請求権の放棄(四条)、米統治下の裁判の効力の承認(五条)などが盛り込まれている。
七一年十月、返還協定を批准するための「沖縄国会(第六七回臨時国会)」が始まった。
屋良主席は沖縄国会に向けて琉球政府が自主的にまとめた「復帰措置に関する建議書」を携えて上京したが、十一月七日、沖縄返還協定特別委員会では突如として関連法案が強行採決され、建議書は宙に浮いてしまった。
数次のゼネストなどの抗議行動にもかかわらず、結局、返還協定の内容を変更さぜることなく、県民は不安と不満をいだきながら復帰の日を迎えることになった。
4 末来へのびる海上の道 top
復帰後の沖縄社会
一九七二(昭和四十七)年五月十五目の日本復帰によって沖縄社会は“世替り”の激動を迎えた。
日本国憲法をはじめとする諸法令や諸制度が本土並みに適用され、通貨が米ドルから日本円に切替えられ、本土渡航の制限が撤廃され、交通方法が左右変更され、行政機関や組織や団体が本土中心に系列化され、本土資本がドッと押しよせてきて土地と市場をおさえた。
政治・経済・教育・福祉、あらゆる分野で急激な「ヤマト化」が進んだ。
しかし、復帰によって沖縄問題が一挙に解決したわけではない。
本土との格差、米軍基地の存続、自衛隊の配備、為替差損(かわせさそん)と物価高騰、軍雇用員の大量解雇、軍用地の再契約問題、不発弾・遺骨・旧軍用地などの戦後処理など、問題は山積していた。
日本政府にとって沖縄政策の重点は、
①沖縄の本土との一体化、
②沖縄経済の本土との格差是正、
③日米安保条約に基づく米軍基地の維持・管理、の三本柱であった。
長期的な振興策として沖縄開発三法(沖縄振興開発特別措置法〈沖振法〉・沖縄振興開発金融公庫法〈沖縄公庫〉・沖縄開発庁設置法)が制定され、沖縄振興開発計画(一〇年計画・三次継続)が実施された。
全国平均の五八%という低い県民所得を八〇%の水準まで高めることが当面の目標とされた。
沖縄公庫の投融資と高率補助によって、道路・空港・港湾・農業基盤・学校施設などのインフラが整備され、生活環境は飛躍的に向上した。
しかし、三次におよぶ振興計画事業で六兆数千億円の国費が投入されたにもかかわらず、県民所得は全国平均の七十数%に低迷し、自立的経済の確立という目標にはほど遠い。
基地問題はあいかわらず沖縄がかかえる最大のアキレス腱になっている。
復帰後も、全国の米軍専用基地の七五%をしめる沖縄基地はそのまま残され、基地の機能もほとんど変らず、沖縄の海も空も事実上の自由使用の状態が続いている。
「米軍基地の整理・縮小」は日本政府の公約であったが、約束された施設の返還は遅々として進まず、核にまつわる疑惑も払拭されないままである。
基地から派生する爆音や公害、事故・犯罪も深刻である。
九五(平成七)年九月に起きた米兵による少女暴行事件は県民の怒りを爆発させ、八万五〇〇〇人の抗議集会が開かれるなど、基地の整理縮小と地位協定の見直しを要求する島ぐるみ運動へと発展した。
未来へのびる海上の道
沖縄の日本復帰と共に日本の国境線は南端は北緯二四度線、西端は東経一二二度線へと拡大した。
戦後二七年間に、北緯三〇度(降伏文書)、北緯二九度・平和条約)、北緯二八度(奄美復帰)、北緯二四度(沖縄の施政権返還)と国境線はたえず変動してきた。
沖縄県民は一六〇九年の薩摩侵入以来の歴史をふりかえって、国境というものはたえず変動するもの、という無常観をもっている。
むしろ、変転きわまりない国境線にとらわれることなく、東アジアの海上の十字路として栄えた「万国津梁」(ばんこくしんしょう)の時代を想起して、アジアの経済・文化交流の拠点となる道を模索するようになってきた。
日本に復帰して、軍用道路一号線が国道五八号線に変り、那覇の明治橋から西海岸をとおって国頭村奥集落まで延びていた幹線道路は、さらに海上を通って奄美大島、薩南諸島を通って㈲児島に連結された。本土一体化を象徴する「海上の道」が現出したのである。
しかし本土への一体化がすすむなかでも、県民意識の基層において本土とは異質な文化意識が根強く存在するのも事実である。
①強烈な郷土意識、
②独自の伝統文化にたいする愛着と矜持(きょうじ=誇り)、
③伝統的な横型社会の人間関係、
④異文化に寛容な開放性、
⑤根強い平和意識、等々。
これらの特徴的な県民性は次のような沖縄独特の風土や歴史に裏打ちされたものである。
①亜熱帯の温暖な気候、
②本土とは異なる歴史過程、
③琉球王朝文化の伝統、
④沖縄戦の体験、
⑤戦後の異民族支配と異文化体験。
これらの視点から、あらためて沖縄の地政学的位置をながめてみると、朝鮮半島も中国も台湾もフィリピンも東京と等距離にあることが実感される。
本土一体化という中央志向へのこだわりを棄てて、「アジアの中の沖縄」という自覚をもって東アジアの地図の上の新たな「海上の道」を描いていけば、平和と文化の発信地としての沖縄の可能性が開けてくるのではなかろうか。
top
****************************************
|