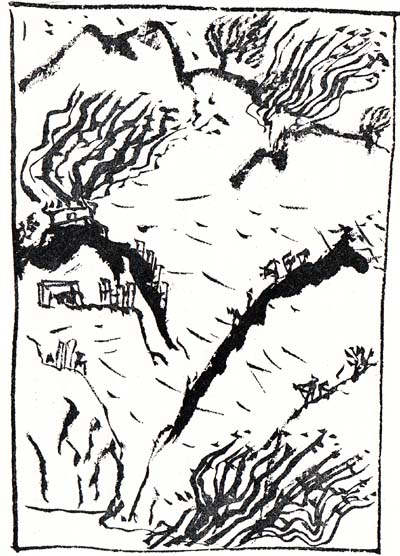|
****************************************
Index その一 その二 その三 その四
秀衡と牛若丸4
13 義経を送りだす
① 出陣
② 宇治川の戦い
③ 吉次ばなし
14 夢やぶれて
① 落人あわれ
② あい会わぬ人 |
15 秀衡の死
① 親の心
② なぞとしてのこるもの
③ 暗雲うずまく平泉
16 四代め、わなにおちる
① 義経の最期
② せめよせる鎌倉勢
③ むすび |
13 義経を送りだす top
① 出陣
世は動くと義経にいった吉次のことが、いつか秀衡の耳にもはいりました。それをきくと、
「吉次、けしかけるな、いらぬ知恵をおん曹司につけて、そなた、困ったやつじゃ。」
と、しかりうけました。
せっかくこの地に迎えて、しずかな日々をすごしまいらせているのに、その静心に火をつけるようなことは、してもらいたくないのです。
秀衡は義経をわが子のように、いとしく思っていました。
できることなら、恩誼(おんぎ)ある源氏直系のおん曹司を、この地の主に迎えて、泰衡(やすひら)、忠衡(ただひら)とともに三人力をあわせ、出羽陸奥(でわむつ)を、平和に治めたい考えをもっていました。
それには奥州(おうしゅう)を三分してもいいとまで、思っていたのです。
けれど、秀衡の恩は恩と感じても、義経の心はそこにありませんでした。
なんとしても、平家を討ちほろぼしたいという、雄々しい心にかられています。
だが、吉次の予言した天下が動く、というあらわれが、治承三年(一一七九)になって起こりました。
いままで平清盛のイノシシぶりの歯止めとなっていた嫡男(ちゃくなん=後継)の重盛(しげもり)が若くして亡くなると、清盛のわがままぶりが、ますますひどくなったのです。
清盛は突然、後白河法皇を、鳥羽殿(とばでん)におしこめました。
たしかに法皇は煮ても焼いてもくえないような、計略の多いお方でしたが、臣下が法皇をとじこめるとは、おだやかでありません。
いままで源家にそむいてまで、清盛の味方をしてきた源三位(げんさんみ)頼政(よりまさ)が、七十七歳の老いの身をひっ
さげて、まず、以仁王(もちひとおう)をもりたてて、平家追討の旗じるしをかかげました。
頼政がたつというのはよくよくいきどおりを感じたからでしょう。
旗あげは治承四年(一一八〇)四月九日のことです。
ただちに追討の命令は諸国にひそむ源氏にむかって発せられました。
このとき、頼朝は三十四歳、義仲二十七歳、平泉にある義経は二十二歳の若さでした。
頼政のこの旗あげは二十万の兵をただちに動員できるという清盛を相手では所詮、斧に立ちむかうトウロウ(かまきり)でしがありません。
早くも五月二十六日の宇治川の合戦で、もろくもやぶれ去り、平等院で頼政は自刃しはてております。
けれど、頼政の投じた一石はけっしてむだではありませんでした。
以仁王の命令が、地にひそむ源氏を、ゆり動かしたのです。
六月、まず、伊豆の頼朝がたち上がりました。
それから三月おくれて九月四日、義仲が信濃(長野県)に兵をあげました。
「たちましたろうが、源氏の公達(きんだち)が………。
したが、吉次の才覚、源三位(げんさんみ)どのの旗あげだけは、見おとしておりましたな。
ほい、こんなことをいうたらまた、お館さまに、きついお目玉ちょうだいじゃ。」
吉次は、こういって、にやにやしました。
義経はもう、居てもたってもいられない心地です。
伽羅(きゃら)の御所に、秀衡をたずねました。
「兄も木曽どの(義仲)もおたちになりました。
お館どの、義経もおくれをとらぬよう兄上のもとにゆかせてください。」
秀衡はそれをきいて、もうおとめもうすことはできないと、さとりました。こころよく、
「ゆかれませ、おん曹司、五千がほどの手勢を、お付け申しましょうほどに、ご武運のほど祈ります。」
と、晴れの出陣をいわってくれ、「青海波(せいがいは)」という、足の走いことで知られた名馬を贈りました。
五千の手兵というのに義経は
「いそぎますゆえ………。」と、三百騎だけをもらいうけて、さっそく平泉館をうちたちました。
関東に入って、平塚、足柄、三島と、頼朝の軍のあとを追い、ようやく駿河(静岡県)の浮島が原で、追いつきました。
「お兄上が末の弟、九郎義経にございます。奥州より参上つかまつりました。
なにとぞ旗あげのすえにお加えくださいますよう。」とねがいでました。
「おお、奥州にあった牛若か。そなたがことは鞍馬から脱出して平泉にいったとか、風のうわさにききおよんでいたぞ。
よくきてくれた。頼むぞ。九郎義経!」
生まれてはじめての対面でしたが、そこは腹ちがいとはいえ、血のつながる兄弟、喜びの涙にかきくれました。
その頃、平維盛(これもり)が五万の兵をひきいて富士川の岸に出陣していましたが、源氏の勢二十余万、浮島が原にありときき、うき足だっていたところに加えて、ある夜、水鳥がなににおどろいたか、いっせいに飛び立った羽音に、さては源氏の夜襲とあわてふためき、一矢も射ず、ほうほうのていで京に逃げ帰ったという話はあまりにも有名です。 |

義経は浮島が原で頼朝の軍に追い付き、初めての兄弟の対面をおこなった。しかし、平維盛軍が水鳥の音で逃げ帰ったので、頼朝は後は義経と梶原景時にまかせ、自分は鎌倉に帰った。義経、頼朝の対面はこれ一度きりとなった。 |
② 宇治川の戦い top
義仲は木曽殿とよばれました。
このような句がありますが、これは義仲の悲運をうたったものでしょう。
義仲も義経と同じように、源氏正統の一人です。
祖父に為義(ためよし)をもち、義朝(よしとも)の弟義賢(よしかた)を父として生まれた第二子。
義経とは従兄(いとこ)どうしにあたります。
おさないときの名は駒王丸(こまおうまる)。十三歳で元服して、木曽次郎義仲を名のりました。
以仁王(もちひとおう)の令旨(れいし=天皇の命令)をうけてたったときは義仲、二十七歳でした。
頼朝よりも三か月遅れてだったのですが、都にはいったのは頼朝よりも、ぐんと先でした。
もっとも頼朝は弟の義経たちに軍勢をあずけて、都入りの準備をさせますが、自分は鎌倉にとって返して、関東から動きませんでした。
これにはわけがあったのです。
頼朝が京にのぼったあと、鎌倉のねじろを、陸奥の鎮守府将軍、藤原秀衡に疲れることを、恐れたからです。
それほどに当時の秀衡の勢力は重みのあるものでした。
さて、木曽義仲ですが、頼朝におくれてたちあがりましたたが、その行動はまことにすばらしく、まず越中(えっちゅう=富山県)と加賀(かが=石川県)の国ざかいで、平家の十万の大軍をむかえ討って、その半分の兵でさんざんに討ちやぶり、にげる敵を追って京に都入りをし、平家を西国へ追いおとしました。
いままで都をまもっていた平家にとってかわって、義仲がまもることになったのです。
その勢いのさかんなこと、朝日ののぼるようだったので、「旭将軍」の名でよばれるようになりました。
だが義仲はなにしろ木曽谷にそだった野生の子です。
野生のままおとなになったのですから、いかにも気性があらく、やることなすこと、出すぎた行いが多かったので、後白河法皇ばかりか、都の庶民たちにまで、嫌われるようになりました。
法皇はついに、義仲の追討を源頼朝に命じました。
頼朝はその命をうけると自分から動くことなく、弟の範頼(のりよし)と義経に兵をさずけて京にむけて進発させました。
従兄どうしを敵味方にして戦わせる――後白河法皇とは、こんなことを平気でお命じになるお方でした。
そういう立ち場におかれた義経も義仲も、ともに悲しい運命にあやつられるあやつり人形のようなものでした。
つまり法皇は人形使い、二人は人形ということになります。
平家を都からけ落としたのは義仲です。
そのいさおのある人を、範頼と義経の追討の軍に立ちむかう立ち場におかれました。
朝敵ということになります。
義経と義仲の軍が宇治川をはさんで向かいあいました。
ここは以仁王(もちひとおう)をいただいてたった源三位(げんざんみ)頼政が、平家との戦いにやぶれて自刃しはてた、悲しい土地です。
義経も義仲も、ともに平等院を見ながら、さぞ同じ思いにがられたことでしょう。
でも、いまは戦わねばなりません。くしくもこの戦いは義経にとって、弓矢をまじえる初陣となりました。
「木曽どのとは、ほこをそろえて源氏のためにともに戦うべきお人だったのに、なんというめぐりあわせ。
ほこをあわせるはめになるとは――。」
悲しいというよりも、腹だたしくさえなりました。でも法皇の命では戦わねばなりません。
寿永三年(一一八四)一月二十日のことです。
|

宇治川の先陣あらそい。これには義経配下の川底の杭と網の撤去があった。
|
この合戦には義経のやぐらかけひきと、宇治川先陣争いの話が伝えられております。
まず義経は宇治川の平等院がわに陣をしくと、川岸に高いやぐらを組ませました。
その上に、平等院からかりてきた大太鼓をすえました。
この太鼓で、いくさのかけ引きをしらせようというのです。
あわせて書き役をのぼらせ、味方の手柄の数々を書きしるさせました。
この川には橋がかかっていましたが、義仲は義経勢が川を渡れないように、まえもって橋をこわし、川底に杭を無数に打ちこんで網をはってしまいました。
この障害物をとりのぞかなければ、むこう岸へ渡れないのです。
第一番に、鹿島与一というものが、はだかになって寒中の川にとびこみ、熊手でもって網をからめとり、杭をひきぬきはじめました。
それにならって皆もまた川にとびこみ、杭のぞきにかかりました。
こうして川を渡れるすきまができますと、梶原景季という若武者がまず馬を乗り入れ、つづいて佐々木高綱が間をおかず乗り入れました。
敵の矢のふりしきるなか、この二人の先陣争いは見事なものでした。
二騎とも、先になったり後になったり、並んだりしながらきそいあいましたが、対岸についた時は佐々木、梶原の順になっていました。
「宇治川の一番乗り、佐々木高綱!」
つづいて、
「梶原景季、二番乗りをつとめそうろう!」と、声をあげました。
その見事さに、味方も敵も、やんやとほめそやしました。
「それっ、佐々木、梶原を討たすなっ、ものどもつづけっ!」
畠山次郎重忠の一隊が、これまたどっと乗り入れます。
こうして、初陣の義経は、宇治川の合戦に戦い勝ち、敵のにげるを追って、なだれのように、都に入りました。
やぶれた義仲はとうとう琵琶湖のほとりの粟津(あわづ)で、戦死をとげてしまいました。
③ 吉次ばなし top
「やりおりましたぞ、やりおりました。おん曽司が!」
伽羅の御所にきょうは常になく明るい、そうそうしい声が、はねかえっております。
例の吉次の声でした。
ひさかたぶりに京から戻ってきて、首をふりふり、見聞きしたさまを秀衡のおん前で、のべたてているのでした。
九郎義経のいくさぶりを、まるで自分の手柄のように、数々ならべております。
きく秀衡のほうも、
「ほうほう。」
と、これまた、たあいもないほど、うれしそうです。
この人、すでに養和の年(一一八一)に、陸奥守(むつのかみ)に任じられ、一段と王者の風格も見事になっているはずですが、吉次にかかっては、いつもその大ぶろしきに巻込まれがちです。
吉次という男はそんな余徳のある人物でした。
「木曽どのを宇治川にやぶってからのおん曹司の働きは、めざましというはおろか、まるで鬼神のようなものでござりました。
京にお入りになったおん曹司の喜びようといったら、ありませなんだ。
まるで牛若か遮那王の昔にかえられたよう………。
私めも、とるものもとりあえず陣中におうかがいつかまつりましたが、しばらく見ぬまに、見違えるほどの、あっぱれな若大将ぶりになってございました。」
「さむらい大将の子はさむらい大将になるのだと、常日頃おおせたったが………。
そうか、お会いできたか。若ももう、おん年二十六におわすはず。
思えばわれらが年とるのも、ぜひないのう。なにかことづてなどなくてか。」
「かならず出陣の地、平泉に、錦をかざって凱旋(がいせん)のつもり。
お館さまのご長命をお祈りもうすとのことでござりました。」
「そういってくだされたか。そなたまた会う日があったなら、お待ち申上げておると伝えてくりゃれ。
で、吉次よ、おん曹司の手柄話をつづげてくれぬか。」
「はい。宇治川決戦のあった翌二月には早くも平家追討の軍を西にすすめて、平家と一の谷にむかいあいました。
このときは平家の裏をかき、ひよどりごえの難所からさかおとしをかけ、ひとたまりもなく敵を追い落としましたげな。
もちろん、お館のお贈りくだされた『青海波(せいがいは=名馬)』にうち乗ってでございます。
この手柄で、おん曹司は法皇さまから判官(はんかん)の位をさずかり、いまは九郎判官義経さまとよばれるようになり申した。」
「吉次、そなた見てきたような話ぶりをしよるが、どこまでがまことよ。」
秀衡は、こうまぜかえしました。
「へっへっへ、はて、それはお館さまのお心まかせということにいたしましょう。」
吉次は、げろりとしたものです。
|

ひよどりごえの難所からさかおとし
|
「さて、次の年、寿永四年(一二八五)の一月には四国の讃岐にわたり、八島(香川川県屋島)ぜめをとりおこなうはずでございました。
おりもおり、頼朝からつかねされた梶原景時(かげとき)という、いじわる軍監(軍のお目つけ役)がやってまいりましてな。
“さかろ”問答というおかしげな横車をおしましたげな。」
「ふむ、景時なら悪名をきいておるぞ。梶原タヌキという嫌われ者はのう、頼朝どののふところ刀であろうが。」
「はい、そのお子の景季(かげすえ)は例の宇治川で、佐々木高綱と先陣争いをいたしましたほどのさわやかな若武者ですのに、その親父さまは人からの嫌われ者。
このタヌキ軍監、義経さまのおん前で、さかろを船にとりつけるようにと横車をおしました。」
「さかろとは、いざというときの逃げじたくをしておけというのか。」
秀衡は、にやにやしました。
「さよう、船の前後に櫓(ろ)をつけておいて、進むもひくも自由というのでしょう。
が、おん曹司はそれをおとりあげなさらぬ。
そればかりかおん曹司は北風の強い日をえらんで船をこぎ出させ、風に乗せて矢のように軍船を走らせて、半日がほどで、阿波の国(徳島県)へ上陸、わずか百五十人の手勢で、八島ぜめにとりかかりました。
「ふむふむ。」
「ここでも小勢で平家を海に追い落としましたが、ごぞんじのとおり、平家は水軍が強く、源氏は
陸戦をとくいといたしおります。海ににげられてはさすがの義経さまも、困りはてられましたげた。」
「さもあろう。」
秀衡もあいづちを打ちました。
「ところで、こんな激しさいいくさの間にも、風流があるもの。
沖の平家の軍船のなかから、小舟が一艘、こぎもどしてきて、玉虫の前という女官一人乗りこみ、長い竹ざおの上に扇をかかげ、これを射よ、というかのようにございましたそうな。
これをながめた源氏の勢はどよめきました。
源氏には、この扇を射とめるほどの、弓の名手はおらぬであろう。
さあどうだと、いどみかかってきたのでござります。
この挑戦をうけてたったのは、畠山重忠の家来、弓の名手としてはまれ高い、那須与一(なすのよいち)というもの、馬を海に乗り入れて、ただ一矢にて扇のかなめを 射ぬき海におとしました。
おりからの夕日をうけて、扇がさんらんと散っていくのを見た敵味方、いずれもやんややんやのほめ言葉で、しばしやまなかったとございます。」
「吉次、そなたの話は嘘と真が、どのくらいずつまじりおる。」
秀衡は笑いだしました。
「さあな、うそと思えば嘘、真と思えば、みな真でございましょう。
でもお館さま、吉次の話、けっこうおもしろうございましたろうが。」
またまたけろりとしたものです。
「そうな、そういわれれば、吉次話はおもしろい。またまた仕入れてきて、このわれをたんのうさせてくれ。」
こんな主従もないものです。
そういえば、どちらも主とも思わず、家来とも思わぬ、といって、仲間でもないのです。
とにかく二人の仲は、こんなへだたりのない、世にもふしぎな間柄でした。
14 夢やぶれて top
① 落人あわれ
吉次がこのようなおん曹司義経の手柄話を、おもしろおかしく秀衡にきかせている間にも、時の流れは大きく動いていました。
八島(屋島)に平家をやぶり、このたびは水軍を加えてにげる平家を長門(ながと=山口県)の壇の浦に追いつめて、ここでいどんだ決戦で義経は、平家を西海のもくずと消し去ってしまいました。
このときが義経生涯の、もっとも輝かしい盛りだったといえましょう。
いくさの“いさおし”をかざって都へもどり、法皇のおほめの言葉をいただいたあと、兄頼朝にもこの喜びを分けあってもらいたく、報告のため鎌倉さしてはせ下りました。
ところが鎌倉ちかくの腰越まできたときです。頼朝から使者がたって、ここより足をふみ入れてはならぬ――という、厳しい命令です。
兄上にお会いできる喜びをもって、はるばるここまできたのに、このお言葉、義経には何が何やら、さっぱりわけがわからなくなり、途方にくれました。
本当の頼朝の腹は、たとえ義経にどんな手柄があろうと、それは自分の手のものとして弟があげた手柄、大将をさしおいて、かってに法皇から判官の位をいただくなどもってのほかと、その筋違いを怒っているのでした。
「身がってな。わがままにもほどかおる。この兄をさしおいて、みだりに位をうけ、九郎判官義経を名のるとは!」
どうやら後三年の役の原因とたった清原真衡の考えかたににているところがあるようです。
頼朝には、そんなほがらかでない一面がありました。
それに加えて、例の悪軍監、梶原景時の、あることないことの告げ口が、頼朝に義経不信の暗いかげを植えつけていたのです。
「判官の位をうかつにうけましたは身のあやまりでした。
義経に二心あるはずもなく、兄上にしたがうもの、そむく心などみじんもございませぬ。」
と、理をつくして長い手紙をかき、許しをこいましたが、どうしても鎌倉へ入れてくれませんでした。
これが世にいう「腰越状(こしごえじょう)」なのです。
「兄上のお怒りがこんなに強いとは、つゆ思わなかった。
いまになって、ほめていただこうなどというあまい考えはすてるが、せめて、よく来たと迎えてほしかった………。」
むなしい心をいだいて、義経は、再び京へとってかえしました。
それを追いかけるように頼朝は、土佐坊昌俊(しょうしゅん)なるものに手勢をさずけ、義経を討ちとりにさしむけました。
土佐坊は熊野まいりの法師のいでたちで、一行九十三人で京都にもぐりこみ、義経の館、堀河屋敷に夜襲をかけました。
この夜襲は土佐坊がわの失敗に終わり、さんざんにやぶれて鞍馬にかくれひそみましたが、山の法師たちに見やぶられてつかまり、義経君を討つとはとんでもないやつと縄かけて、堀河へ引渡されました。
義経は六条河原にこれをひき出して斬ってしまいました。
これで兄頼朝に、はっきりと、はむかったことになります。
そのうちに頼朝が、舅(しゅうと)の北条時政に兵をさずけて、義経を討つ準備をしているという、うわさが立ちました。
「このままでは殿のお命かあぶない。
九州なら遠い土地、頼朝どののお手も届きかねましょうほどに、九州に安住の地をみつけられては、いかがでござりましょう。」
弁慶はじめ家来の皆々がこのようにいってくれるので、義経もついその気になりました。
いそいでしたくをととのえると、摂津(せっつ=大阪府)の浜から、船出をしました。
ところが悲運が、ここにも待ちうけていたのです。
海上はるかに出たと思ったら、きゅうに逆風がふきだして、櫓(ろ)も櫂(かい)もまにあわず、もとの浜辺にひきもどされ、そこに待ちうけていた鎌倉勢と、会ってしまいました。
この戦いで、船も味方も残りすくなくなり、九州ゆきも思いとどまらねばならなくなりました。
「皆のものはそれぞれの里にかえり、時節を待つように。」
そういいきかせ、わずかな腹心の家来を供に、大和(奈良県)の吉野へ、落ちのびました。
もういまは風の音にも追っ手加と、心さわがせられる落人の身です。
この吉野での静御前(しずかごぜん)との別れ、身がわりになった佐藤忠信の忠節――と、悲しいことのみがつづきます。 |

兄頼朝と戦う破目になった義経は、船で九州に
渡ろうとしたが、嵐に押し戻されて、失敗した。
そして吉野、越前、さらに平泉の秀衡の元へ戻る。
|
はては近江から越前(福井県)へとぬけ、そのさかいの安宅の関で、弁慶がここで見やぶられてはと、必死の思いで忠節をつくす、有名な「勧進帳(かんじんちょう)」の話が残されるなど、さまざまな苦しみをなめながら、道を北海道にとるうち、義経の心はしだいと、いつくしみぶかい父のような平泉の秀衡の暖かい胸に、とびこみたくなってくるのでした。
② あい会わぬ人 top
義経のこの悲運のうわさは、いつか秀衡のもとにも届きました。
「今頃はどこをさすらっておいでなのか………。」
一刻もはやくおさがし申して、おつれいたさればと、秀衡の心はいたみます。
さて、月見坂の大スギの上では大天狗の声が風にまじって一段と高くなりました。
二十一夜の月はしたいと中天にのぼりかけています。
『おん曹司九郎判官義経さまに、悲運な旅がおつづき申しておじゃるとき、ここ平泉には、旅の法師の西行さまがまたまた、ひょっこりとおいでなされた。』
『なににおいでなされた。』
木の葉天狗の一人が、茶々を入れました。
『なにって、東大寺修復にいりような黄金を、寄進しておもらいになるためにじゃ。
西行さまはもう七十にとどくお齢での、枯れた雲水のお姿じゃったが、それがよくにあう。
おいでになったはたしか、文治二年(一一八六)、秋もすえのころのことであったげな。』
『ああ。そのことなら、おらだも知っている。で、お館さまはなんぽご寄進につかわれました。』
『これ、えげつない。』
と、大天狗はしかっておいて、それでも鼻高々といいました。
『さあ、五千金とも、その上とも………。この東大寺寄進では頼朝さまでさえ、千金だったとか。』
『へっへっへ、だから、うちのお館さまは、えろうござったげな。』
木の葉どもまでが鼻をぴょこつかせます。
『ああよ、お館さまもえらかったが、西行さまもえらかった。
西行さまが京から奥州へのとおりすがりに、鎌倉の鶴が岡八幡宮にまいられたところ、ここで思いがけなくも頼朝公に、ばったり出会うた。
頼朝公のおさそいで一夜、歌の道、武の話などいろいろきかれたが、あまりうれしげではなかったげな。
別れしなに頼朝公からしろがねづくりのネコの置き物をもらったが、おしげもなく門前のわらべにくれて、ひょうひょうとたち去られたとか………。』
『へえな、なら、西行さまは、頼朝ぎらいであったげな。』
『そうさ、頼朝ぎらいの判官ずき。どうやら西行さま、うちのお館さまと同じじゃったということになる。』
大天狗は胸をはりました。 |

鎌倉に立ち寄った西行。
しかし彼は頼朝嫌いであった。
|
|
たしかに秀衡のえらさは、だれのさそいにものらないことにありました。けっして動かないのです。
木曽義仲が旗あげしたとき、まっさきに東西あいこたえるようにさそいをかけられましたが、動きませんでした。
この動かぬ秀衡を一番恐れたのは、鎌倉の頼朝でした。
みちのくに秀衡あるために、これまた鎌倉から動けないのです。
だからこそ頼朝は京へも弟の義経や北条氏を上らせ、自分から都入りをなかなかしませんでした。
頼朝が全国の総追捕使(そうついぶし)という役目になったのは、文治二年(一一八六)ですが、奥州の秀衡には手をつげかねておりました。
そこで、その年の五月に、秀衡に一書を送りました。
「お館(秀衡の意)は奥六郡の司(つかさ)、私は東海道の惣官(そうかん)である。
もっと仲良くしなければならないのに、遠い土地ゆえ、なかなか自分の心をお伝えできないでいる――。」といった意味のものでした。
つまりこの手紙で頼朝は、自分のほうが高い位にいるのだぞと、はっきりいい切っております。
頼朝の手紙には秀衡のことを奥六郡の司としかいっていませんが、秀衡はれっきとした陸奥守鎮守府将軍なのです。
でも秀衡は、いっこう気にもとめませんでした。どっしりとかまえているだけです。
なおのこと、頼朝は手も足も出せないのです。
西行が、平泉をはなれてまもない文治三年(一一八七)の三月、かねて気にかけていたおん曹司の義経が、すっかり悲しみに打ちひしがれた身を秀衡のもとによせてきました。
「おいたわしや………。」と思いましたが、秀衡は言葉にしませんでした。
ただ、「よくぞ、よくぞ………。」といっただけ。
二人はひしとだきあって、再会を喜びあいました。
「錦を着て凱旋をねがい、ここから出陣させていただきましたのに、その夢もやぶれ、このありさまで、ようように………。」
義経は、涙を見せまいと、必死に歯をくいしばりました。
「おん曹司のおもどりこそ、なににもまさる喜びでござります。」
と、秀衡は、大きな胸に義経のくやし涙をつつむのでした。
この義経と西行は、二度ともゆきちがいになって、ついに生涯あい会う日がありませんでした。
もしこのたび、二人が会っていたなら、西行はなんとこのおん曹司に言葉をかけたことでしょう。
なにかなし、心に残る思いがします。
『まあな。こんなよけいなおもわくは、やめようて………。』
大天狗は、ここまでかたって、空をあおぎました。
いつか月は中天をすぎていますが、東の空にはしきりと、星が流れます。それはおびただしい流星の群れでした。
里にときをつくるのは、一番どりか二番どりか、あかつきが近くなったようです。 |
15 秀衡の死 top
① 親の心
昔から、窮鳥(きゅうちょう)ふところに入れば、これを撃たず、という言葉があります。
義経という追いつめられた鳥が、秀衡のふところにとびこんできたのです。
それに秀衡は猟師ではなくて、慈父のようなかたであり、義経の偉大なうしろだてでもありました。
羽根のおれた義経を、なんで撃ちましょう。
それどころか。心からふかい愛情で義経をつつみこんでくれたお人です。
しかし、頼朝にいわせると、義経は反逆者なのです。
なにひとつ兄に対して悪いことをしていないのに頼朝はその大きな功労のあった血のつながる弟を、反逆者ときめつけてしまいました。
反逆者をかばうからには秀衡も当然、同じあなのムジナということになります。
追討の口実は、こんなふうにしてつくりあげられていきました。
秀衡はそうなることを、再びおん曹司をむかえたときから、すでに覚悟しておりました。
それにもう今年は、六十六歳の齢をかぞえるようになりました。
なんとはなく、心身ともに疲れがでてきていました。
死期が近い――と、感じはじめていたのです。
となれば、これからが厳しい世の中になるのに、わが子らがそれに耐えていけるかどうかが、もっとも気になることでした。
秀衡は義経が平泉にきてから、自分が死んでからのちの奥羽の治め方について、一つの策を心に描くようになりました。
秀衡にはさきの奥方との間にできた子国衡(くにひら)に加えて、藤原基成の姫との間にできた泰衡(やすひら)、忠衡(ただひら)、高衡(たかひら)、通衡(みちひら)、頼衡(よりひら)の、六人の子がありました。
一日、この兄弟を手もとにまねき、六人に遺言をいいわたしました。
「この頃、わが身も心も、いたく疲れを覚えるようになった。すでに天命も短いと知った。
そこで遺言を申しのこすのだが、私が死んだときけば、鎌倉の頼朝はその機をのがさず奥羽にほこをむけるであろう。
これを防ぐには、おん曹司、源九郎判官義経の君を、そなたらの頭(かしら)にいただき、兄弟ひとしく力をあわせて、まもるしかない。
おん曹司は音にきこえたいくさじょうずの大将、このお方を上にいただけば、鎌倉勢など、恐れるにたらぬ。
また頼朝はずるがしこいお方ゆえ、おん曹司をわたせば、さらに国をふやしあたえるなどと、おまえたちの喜びそうなえさをもってさそうであろう。 |

死期を悟った秀衡は六人の子供に、義経を頭として
みちのくをまもることを、遺言として伝える。
|
そなたら、けっして、奥羽以外の領地をほしいなどとは思うな。
ゆめゆめ、鎌倉のたくらみにつられて、兄弟どうし争ったりしてはならぬ。」
そして、兄弟の不和は国をほろぼすもとになることを、古今の話や、後三年の役などを例にとって、順々とさとしました。
そのうえ、それぞれに起請(誓いの言葉)二枚を書かせて、一枚は秀衡の手もとに、他の一枚は、飲みくださせて、かたくまもることを誓わせました。
これだけが奥羽をやすらかにしておく、ただひとつの道と、秀衡は固く心にきめていたのです。
「義経の君、さだめしご迷惑でもありましょうが、わが老いの心をおくみとりくださって、ぜひお引受けねがいたてまつる。」と、義経に、子らのゆくすえ、奥羽のまもりを、頼むのでした。
「お館、それをいわれると、われの心がいたみます。
義経、この地にまいらねば、お子らの心をさわがすことも、この地の安泰をみだすこともなかったと思われるに、かえって身にあまるお心使い、恐れいる。
いっそわれが、平泉をたち去れば、この地の安泰もたもたれましょうに………。」
と義経は、くるしげに頭を下げるのでした。
「もったいない。わが子ら、判官どのがおられてこその安泰を念じるばかり。
いまもごらんのとおり、けっして、お心にそむいたりは、いたしませぬ。」
そして、義経が秀衡のねがいを聞きとどけるという答えをうけると、鎌倉からのせめに対するふせぎも、着々とととのえにかかりました。
こうして、義経を頭とする奥羽のまもりが、かためられていきました。 |

秀衡の頼みを受け、義経もその準備を始めた。
|
この間にも頼朝、秀衡、双方のの間偵察、つまりスパイ戦が、火花を散らしました。
「秀衡、義経を救け、反逆のようすがじゅうぶんにあります。」
頼朝はこう、朝廷にうったえました。
義経も秀衡も共に、天朝に対して反逆を起こす心づもりなど、つゆほどもあるはずがありません。
それをこうきめっけるのです。
ただ、花園をあらしにくる鎌倉の花ぬすびとを入れさせぬための、まもりにとどめたのです。
こじつけと、無法――。頼朝とは、こんな人でした。
このようなせっぱつまったまっただなかに、藤原三代、北方の王者といわわれた巨大な星、秀衡は、ついに地に落ちて、長い眠りにつきました。
文治三年(一一八七)十月二十九日のことです。
つめたい秋雨にぬれて、音もなく落ち葉が散りしきる中でした。
② なぞとして残るもの top
『三代さまがお亡くなりになられたのじゃもの、平泉のおん館のまわりは、悲しみの雲におおわれ、その嘆きの声は奥六郡の隅々にまで満ちみちた。』
大天狗はしんみりとした声を出しました。
『あんときは、おらだみんなも、わんわん泣いたっけ。お師匠さんなど、大声立てて泣かれたげな。』
『これ、また茶々を入れよる。でい六木っ葉の悪たれが!』
大天狗はぎょろんとにらんだものの、当時を思い出したのか、その目をすぼませると、しばしばさせました。
それを見て、でい六天狗は小さく縮こまり、首をすくめました。
なにしろご他界は、いまから三年ほどまえのことなのです。
つい昨日のことのように思えて、涙になるのも、むりがありません。
義経はこのとき、秀衡の遺骸をかきいだき、
「いかかる親の嘆き、子の別れも、これに過ぐるものはなかろうに………。
お館よ。われらを残してゆかれるとは無情な。」
と、男泣きに、涙もとどまらなかったといいます。
『いやあ、のう、そのご葬儀の、おごそかさ、うるわしさといったら、言葉にもつくせぬものだった。
わしは初代さま中尊寺一山の、落慶供養をこの目で見てきているが、それにまさるともおとらぬご盛儀じゃった。』
と、大天狗は思い出にふけるのでした。
なきがらは初代、二代にならって、そのまま生けるがごとく永世に残る処理がほどこされ、ウルシぬりの金棺におさめられて、藤原氏の葬堂である金色堂の左壇に安置されました。
初代清衡の壇をまんなかに、右の壇は二代基衡、左の壇は三代秀衡と、その遺体はいまもミイラのまま、眠りつづけているのです。
この遺体については昭和二十五年に、「中尊寺学術調査団」の手によって、三つのひつぎがひらかれ、くわしく調査研究が行われました。
そのときのようすは調査報告にくわしいのですが、あらましをのべますと、初代清衡は両脚をおりまげた姿の半屈葬という形、二代基衡、三代秀衡はともに、両脚をのばした伸展葬の形だったと、いわれています。
三体とも元の形にちかい姿で、それぞれがミイラになっていましたが、清衡だけは頭部と胸からひざまでがミイラで、あとは白骨になっていたとあります。
これに立ち会った作家の大仏(おさらぎ)次郎氏はとくに秀衡の遺体についての印象を、次のような言葉で語っておられます。
「………まぶたの肉は失われていて、目が深く窪み落ちていましたが、くちびると鼻の頭に、いたましい損傷があったのは、印象的でした。
それにしても、このマスクは人の顔のりんかくを彫刻的に残していました。
彫刻が未完成のままながら、すでに仕上ったときの、全体の美と力とをしめしはじめている段階を、見るような心地でした。
白骨ではむろんありません。肉の厚味も残り、皮膚も部分的にとどまっています。
石綿がふくむ湿気の害をうけなかった昭和のはじめ、いや、それよりもさらに古く、元禄年間の記録が、尊容(おごそかな姿)生けるがごとしと伝えたのは誇張ではなかったと信じられます。
総体の色の印象も暗いものではなく、明るみを残していました。」
とのべられ、
「胸部はいっそう見事に、武人の胸にふさわしく、強いはりをしめして、たくましくもり上っていました。
木彫りの仁王像の胸が感じられます。肩もしっかりしていて、円味をおびていました。
………高いい鼻すじはさいわいに残っていました。
ひたいも広くひいでていて、秀衡法師と頼朝が書状にしるした入道頭を、はっきりと見せています。
下(しも)ぶくれのした大きなマスク、北方の王者にふさわしい威厳のある顔立ちといって、はばからないでしょう……。」
とも、のべておられます。
三体のどれにも、脳髄や内臓はなく、ともに同じようなミイラになっているのです。
それが人工的になされたものか、人工と自然がまじりあってそうなったものか、結論がでなかったようです。
そればかりではありません。
どうしてこの藤原三代にかぎって、永世に残るミイラとして埋葬されたものか、その意図も方法とともに学術調査の結果でも、なぞとして残されました。
③ 暗雲うずまく平泉 top
『それにしても………。』
と、月見坂の大天狗は、ふかいためいきを、ほうともらしました。
『先代のお館さま(秀衡)がお亡くなりなってからは、この王城楽土に黒雲がわき起こって、ものの“あやめ”もわからぬ土地となりはてたげな。』
『げに、まこと、』
『げに、まこと、』
と、木っ葉たちはいっせいに、声をそろえました。
秀衡を失ってのちの、義経の嘆きも大きなものでしたが、三条吉次の気落ちのしようといったら、ふためと見られないものでした。
「へえな、この世に神も仏もないものか。」
こんな、おかしな言葉をはくようでは、いつもの吉次らしくあ力ません。
「ようし、神も仏もないならば、こっちが鬼にも蛇にもなってやる。」
吉次は泰衡兄弟たちの動きに、目をひからせるようになりました。
「忠衡さま、頼衡さまは若の大の仲良し、判官さまのお味方に間違いないが、はて、泰衡さまはどうもあぶない。」
その泰衡は、父亡きあとの藤原氏四代めをついだのですが、その頃からしだいに、鎌倉の頼朝の、いやがらせ作戦が、激しさくなってきていました。
まず、二つの罪問(つみと)いをしています。
その一つは、義経をかくまって、平泉にとどめおくことの罪、その二つは秀衡法師が死んだからには奥羽の地を、都にかえすべきなのに、みだりにかすめとっている罪。
ただし、義経の身がらを鎌倉に引渡すときはその功に免じて、あとの罪は許してやるかもしれない――といった意味のものでした。
やるかもしれない――ここに頼朝の落し穴があるのです。
泰衡は、家をついだはじめはとにもかくにも父の遺言をまもって、義経を中心に心をあわせて、奥羽をまもってきていました。
白河に砦をもうけ、異母兄の国衡に、みちのくの入口をかためさせました。
それが文治四年(一一八八)以来、頼朝からどうだどうだと、せめたてられるにつれて、心に迷いがでてくるようになりました。
迷いにはまた、迷いがかさなります。
「判官どのさえ、ここにいてくれなかったなら、このようないざこざも起こるまいに………。」
と、考えるようになりました。
そんなやさきでした。
だれが放ったのか、たぶん鎌倉方のスパイが流したのでしょうが、弟の忠衡が、判官としめしあわせて、奥羽の地を、泰衡からうばおうとしているという、けしからぬうわさが、どこからともなく泰衡の耳に入ってきました。
なるほど、そういわれてみると、忠衡と頼衡が、義経と大変なかがよく、この兄弟、家来のように判官につかえています。 あやしい――と思いました。
「しやっ、足元に火がつく!」
もう、前後の見さかいもなくなってきた泰衡は文治四年十二月、夜襲をかけて、弟忠衡を討ちとってしまいました。
こうなると、時の勢い、うたがいの心は、さらにひろがります。
翌五年(一一八九)の二月には、末の弟の頼衡をも、突然おそって殺してしまいました。
手とも足ともなるべき血肉をわけだ兄弟たち二人までも、みずからの手で失ってしまったことになります。
これは藤原氏にとって、大きな戦力の損失でした。
泰衡が、こんな迷いのうずまきのなかで、自分を失いかけているとき、とうの頼朝は泰衡を討つ決心を、はっきりとかためていました。
義経を引渡せというのは、ほんの名目で、それに名をかりて、奥羽藤原氏をほろぼそうというのが、本当のねらいだったのです。
泰衡はうかつにも、それを見やぶる目がありませんでした。
義経になかのよいものをしりぞけ、義経を討ちとりさえすれば、奥羽をわがものとして、安泰におくことができると、あまく考えていたのです。
「あぶない。あぶない。あぶないですよ、若! つぎは泰衡め、若をねらうにきまってます。
いまやこの平泉は、若の身のおくところでは、なくなり申した。
吉次、どこへでもお供つかまつりますゆえ、心をおきめくだされ、越後には吉次の恩人、菊方の舎人どのがおわすことが、最近わかりました。
このお人、舎人などという位の低い役目の人でしたが、きもはぐんと太い。
二代め基衡さまと、円隆寺の額で一歩もひかぬ問答をなされ、のちには秀衡さまにそれがしめをお引き合せくださったお方。
お齢は召していますが、えらくたよりになるお人です。
そこに一時おひそみをいただき、おりをみて京にもぐりこみ、延暦寺の山門入りをなさるのです。
山門には来光房(らいこうぼう)、千光房(せんこうぼう)など、いつでも若のおいでをお待ちしている寺衆がいますし、法皇さまのご側近にだって、刑部卿(ぎょうぶきょう)頼経さまや、按察(あぜち)大納言頼方さまらもおられましょうに………。」
吉次はしきりとこう、すすめます。
「吉次、そなたにともなわれてきたのも平泉、いままたそなたが案内に立つという。
だが、義経はもうどこにも動かぬ、動かぬときめた。
どうでも命ないものなら、秀衡どののたましいのしずまるこの平泉を義経は死に場所にしたく思う。
それにつげても、心の友、忠衡、頼衡二兄弟の災難に、義経はなんの救けもできなかったことをくやむ。
さぞ無念であったろうに、義経生涯の不覚であった。」
吉次の好意は好意としてうけながら、義経はついに動きませんでした。
16 四代め、わなにおちる top
① 義経の最期
『判官さまの館、高館めがけてのあかつきの襲撃は、いま思い出しても、身がすくむ思いだったぞい。』
大天狗はここで一息、肩で息をし、
『あれはことしもことし、つい先の日の閏四月三十日の朝あけじゃった。』
と話をつづけました。 |
義経が柳の御所から、この高館にうつり住んだのはまだ秀衡の亡くなるまえのことです。
もとここは秀衡の肩御藤原基成の住まいでしたが、せめにくい要害の地だったので、基成に柳の御所に入ってもらい、ここにひきうつったのです。
館のまわりは弁慶の屋敷や従臣たちの住まいでかためました。
いつでも頼朝の鎌倉勢をむかえ討てる用心をしたのです。判官館とも、衣川館ともよばれました。
鎌倉勢に対しての要害だったはずのこの高館が、こともあろうに、自分の味方のはずの泰衡の手勢、長崎太郎の勢におそわれたのですから、義経はよくよく悲運の将と、いわねばなりません。
泰衡の手勢五百に対しこちらは従臣武蔵坊弁慶をはじめとして、増尾十郎兼房、鈴木三郎重家、
亀井六郎重清、片岡八郎弘経、鷲尾三郎経春、備前平四郎成実ら三十余人。不意討ちに加えて、多勢に無勢です。
義経は泰衡がおそってきたと聞いたとき、はっきりと覚悟をきめました。吉次のいった言葉に間違いはなかったのです。
「動かぬといったら吉次め、涙をぼろぼろこぼしまった。この日のあることを、われも知り、かれも知っていたのだが。」
くいはありませんでした。
「どうやら、われらに死に花さかすときがきたようだな、兼房。」
義経はかたからの兼房をかえりみて、にっこりしました。
「御意、兼房、重清とかに、われら兄弟、老い花散らしに、まにあったようです。」
この兼房は、山科権守ともいい、義経にしたがって、平氏追討に数々のてからをたてた武将でした。
兼房兄弟が平泉にかけつけたのは、この不意討ちのちょうど二日まえ。
ですから――死に花散らしにまにあった――の言葉にもなったのです。
このとき増尾十郎兼房(かねふさ)は六十余歳。
その老いの背に、ウノハナの白い花むらが、もりあがるように朝日をうけてかがやいていました。
だからこそ、のちの世に芭蕉とともにこの地をおとずれた弟子の曽良(そら)が、
| 卯(う)の花に兼房(かねふさ)見ゆる白毛(しらが)かな |
と、しのんでおります。 |

忠臣の家来兼房に言葉をかける義経
|
多勢に無勢ながら、おいおいかけつけてきた家の子たちを加えて、激しさい戦いとなりました。
義経は先頭に立って敵をけちらしましたが、次々と味方が討たれていくのを見ると、もはやこれまでと、皆にあとを頼み、
「わが最期の時とみた、しずかに死なせてくれ。」
と、妻と子をともなって、持仏堂(仏をまつってあるへや)に入り、香をたきました。
「やっと平安にめぐりあえたと思ったのに、なにもかも夢の夢でしかなかった。
そなたら、父を、夫をうらんでくれるな。」
美しい二十二歳の妻と、おさない姫にいいきかせ、まず奥方を刺し、返す刀で姫の息の根をとめて、みずからは自害しはてました。
このとき源九郎判官義経は、齡三十一歳。この人ほど、不運な星のもとに生まれた人はないでしょう。
「はや、君は、ご最期にそうろうぞ。」
その声とともに、館からは浄めの火が、えんえんと燃え上りました。
皆のもの尽力のつづくかぎり戦い終わって、ついに全員百二十余人、一人のこらず討ち死にしはてました。
最後にたった一人残ったのは、武蔵坊弁慶でした。
「わが君が、心やすらかにご自害なされますように。」
と、敵を衣川の中の瀬にひきつけて、一歩もひきませんでしたが、高館に火の手のあがるを見ると、
「ワッハ、衣川とはよき死に場所よ。」と、高々と笑いました。
そのうち遠矢(とおや)近矢(ちかや)に射すくめられ、川洲(かわす)に立ったまま、立ち往生をしてしまいました。 |

火の手のあがる高館
|
『その戦いの激しささ、むごさ。われら、胆太ければ、お味方もしたろうに、ふがいなや、腰ぬかして、がたがたぶるぶるであったげな。』
『さよう、お師匠さまでさえ、それじゃけ、われらなんぞ、歯の根もあわぬ。』
『とんだ腰ぬけ天狗の、弱虫天狗になりおった。』
みんな顔を赤くし、鼻も一段と低くなったように見えます。
この天狗たち、どうやらお手のものの神通力も忘れはてたわけでした。 |
② せめよせる鎌倉勢 top
義経の首は、黒いうるしぬりの櫃(ひつ)におさめられ、香りの高い美酒にひたされて、泰衡の弟の一人、高衡がひきいる二十余騎にまもられて、鎌倉にむかいました。
鎌倉に近い腰越に着いたのが、六月十三日、義経が高館で自害しはててから、四十三日めにあたります。
このとき高衡はみずから首を持たず、家来にさし出させましたので、頼朝は腰越から先に入れないばかりか、その非礼を怒って、首持参の使いの者を斬り殺してしまいました。
腰越は義経にとって、うらみふかい土地でした。
いちどは兄頼朝の怒りにふれて鎌倉に入れてもらえず、死んでのちのいままた、腰越での首実検とは、心あらばさぞかしつらい思いがしたことでしょう。
実検は梶原景時と和田義盛が、頼朝の代理で行いました。
その首が義経に間違いないとわかると頼朝は、いかにもふしぎな言葉を高衡に、あびせかけました。
「さてもおかしなこともあるものよ。
義経を鎌倉に送れとは申しつけたが、討ちとれといった覚えはさらさらにない。
この兄頼朝のもとに、弟と知りながら、われに首さし出すことこそ奇怪至極。」 |
手柄顔にとくとくと、実検にそなえた泰衡こそ、いい面の皮だったといえましょう。
これで頼朝は泰衡を討つ立派な口実ができたことになります。
この年の七月十九日、頼朝は泰衡討伐の軍を起こしました。
まず、軍を三陣にわけ、千葉介常胤(つねたね)、八田知家(はったともいえ)を主将として、東海道筋をいまの茨城をまわって阿武隈(あぶくま)に出るよう、兵三千をあたえて進発させました。
また北陸道には比企(ひき)藤四郎能貞(よしさだ)、宇佐美平次実政(さねまさ)を将に越後路から出羽に出るよう命じ、頼朝みずからは畠山重忠を先陣に、中道をとおって奥羽にむかいました。
泰衡はおどろきあわてて、「これはぺてんじゃ、二枚舌じゃ。」と、地団太ふんでくやしがっても、あとの祭り。
大体、頼朝とはそういう策略の強い大将だったのです。
それを見ぬけない泰衡は、やはり大天狗のいうとおり、どあほうか、大たわけだったにちがいありません。
泰衡はあわてふためいて、防ぎ戦うそなえをいそぎました。
まず、兄の西木戸太郎国衡に、阿武隈河畔から、阿津賀志山一帯にかけて要塞をきずかせ、二万の兵をあたえて、鎌倉勢にそなえました。
つぎに、苅田に砦をきずき、名取、広瀬の二つの川の川岸に柵をめぐらして、第二陣としました。
泰衡は、多賀国府の南、国分原鞭楯(こくぶんがはらむちだて)に陣をしき、栗原、三迫、黒岩口、一野辺と、若九郎太夫や、余平六(あまみへいろく)らを将としてまもらせ、出羽口には、田河太郎行文(ゆきぶみ)、秋田三郎致文(おきふみ)をつかわして、陣をしかせました。 |
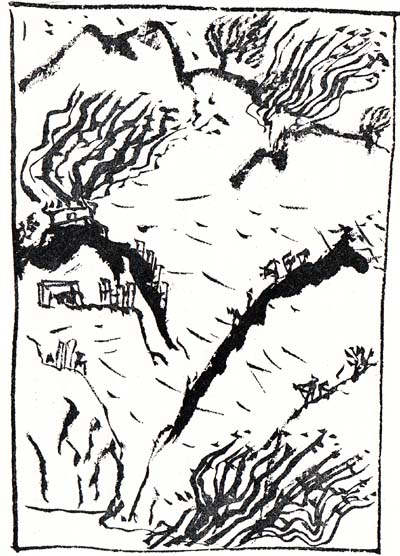
義経の首を差し出したために、鎌倉ぜいの総攻撃が始まった。
頼朝は義経を捕えて差出せと命じただけであるというのです。
|
泰衡がなぜこんなふうに、兵を分散したのかわかりませんが、あわてたあまりに、ただもう、恐くて恐くてたまらず、四方八方を守ろうとしたものと思われます。
義経がもし、この世にあったなら、そのおろかさを、なんといったでしょうか。
これに対する鎌倉勢の進撃は、いかにも急でした。鎌倉をたってから十日で、白河の関をこえています。
もっともここは国衡(くにひら)の守り口でしたが、阿武隈河畔に陣をひいていましたので、鎌倉勢はやすやすと進むことができました。
両軍最初のぶつかりあいは八月七日。阿津賀志山のまわりで起こりました。それからの四日間。
おしつおされつの激しさい戦いがくりかえされましたが、国衡勢はついに総くずれとなり、逃げはじめました。
秀衡があるあいだは、一歩もふみこめなかったみちのくも、頼朝はいま、みずからの足でふむことができたのです。
「よきかな。ものども、おせや、おせ!」
月の二十日には本陣を玉造まですすめました。いよいよつぎは平泉の総攻撃です。
ついに号令が下され、勝ちにのった鎌倉勢は潮のように、北上します。
そのあまりのはやさに、あわてふためいた泰衡は、平泉の館、伽羅(きゃら)の御所にとどまることもできず、北方はるかににげうせました。 |

泰衡は平泉からも逃げ出し、無人の平泉は鎌倉勢に焼き払われた。
|
③ むすび top
『このときじゃげな。四代の“こけ”さまが、その“こけ”ぶりを一気にさらしなされたのは――
見てみいや。平泉一山の堂塔伽藍はいうにおよばず、柳の御所、伽羅の御所をはじめとして、大路小路の武家屋敷まで、鎌倉勢ならまだしも、なんと自分から火をつけて、焼きはろうてしまわれた。
なむあみだぶつ。それはつい、昨日のことよ。思うても涙が出てくるわい。………
ああ、あれっ、あれ見ろや。煙のくすぶるなかに、残っておったぞ。残っておった。なんというしあわせ。
中尊寺、経蔵、それに金色堂もぶじぞ。ほう、毛越寺も残りおる。こりゃ、ありがたや………。』
『ほんによ。残りおる。残りおる。』
『というてるま呪もはや夜明けじゃ。』
大天狗、木の葉天狗のわめき声に、月見坂のスギのてっぺんはわやわやがやがや、きゅうににぎやかになりました。
二十一夜の月が、まだ名残おしげに、西にかかっております。
そして八月二十二日の朝べ廃虚の中に明げました。
長い長い大天狗の、安倍、清原、藤原の三族にまたがる、王者話もこれで終わりをつげました。
さて、大天狗のいい残したその後の話をすこしばかり、つけたしましょう。
やぶれた泰衡はひたすらにげつづけて、秋田鹿角(かずめ)のにえの柵に、河田次郎をたよって身をよせましたが、かえって心変わりした次郎のために、首を斬られました。
このとき泰衡三十五歳、せっかく二十万の兵をもちながら、こんなみじめな終わりをつげるとは、“こけ”殿にしても気のどくのいたりです。
次郎はその首をもって、頼朝の本陣、陣が岡にかけつけました。
おこがましくも恩賞にあずかろうというのです。
頼朝はにがりきって、
「家来が主を殺すとはその罪、はかり知れず。」と、その場で斬り殺してしまいました。
こうして、泰衡の夢、まどかだった北方の王城の地は、むなしくついえ去り、のちの世に芭蕉をして、
となげかせたのです。
top
**************************************** |