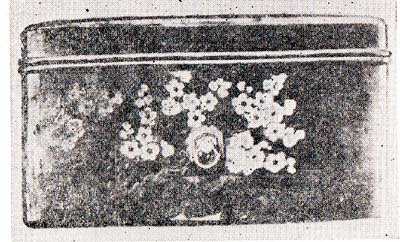|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章
|
二 東国をにぎれ
|

義経夫人静(しず)の舞い
|
1 鎌倉へ top
みどりの田んぼをとりまくあしの原野が、夕日をあびて、金色にかがやいています。
「主人さまがかわったっていうことだが、わしらは一体どうなるのかのう。」
「田んぼはちゃんとまもってくれるんだそうじゃ。年貢をさげてくれたらいいんじゃが。」
「でもな、ご主人さまがだれになろうと、わしら百姓には、同じことじゃないかのう。
朝から晩まではたらいても、あらいざらい年貢にとられてしまうんじゃ。」
村の一本橋のたもとにたてられた、真新しい木の立札のまえで、そまつな身なりをした数人の百姓たちが、かまやくわを大切そうにかかえながらしゃべっていました。
ここは、蒲屋御厨(かばやのみくりや)といって、山木兼隆(やまぎかねたか)の一族が支配していた荘園です。
「もう一度読んでみてくだせえ。」
百姓の一人がそばでじっと立っている背の高い、たくましい僧を見あげていいました。
百姓たちへ
以仁王(もちひとおう)から、東国の支配権をあたえられた。
きょうかぎりで、山木の悪政をやめさせる。百姓らは心配しないように。
治承四年八月十九日 |
声たからかに読みあげた僧は、荒法師として名を知られた文覚(もんがく)です。
「もう、山木一族は、おまえたち百姓には、かってなまねはできん。
この札は、山木を討ちとった源朝朝どのが立てられたのじゃ。」
「へえ………。」
百姓たちは、いっせいに顔を見あわせました。
「じゃが、頼朝さまは石橋山で負けて、ゆくえしれずということじゃ。この立札は、どうなるんだろうか。」
髪をボサボサにした若い百姓は腰にまいたなわに、かまをはさみながらつぶやきました。
「この荘園はどうなってしまうんじゃろうか。
ご主人さまがいなくなってしまったら、とても俺たちの力では、土地をまもれないぞ。
ぼやぼやしていると、新しい目代に取上げられてしまう。」
年をとった百姓が、しわだらけの顔をゆがめました。
「そうじゃ。役人からわしらをまもってくれるつよいご主人さまが必要だっていうのに………。」
「肝心の頼朝さまは、どこへいっちまったんだろう。」
「舟で、海へにげなさったと、もっぱらのうわさじゃがな。」
「ほお、きっと安房へいかれたにちがいねえ、安房には、昔頼朝さまの家来だった武将がいっぱいおるからな。」
百姓たちの声は、だんだん熱をおびてきました。
「安房か………。」
ひとしきり百姓たちの言葉に耳を傾けていた文覚は、ポツリとつぶやくと、川にそった上手道を歩きはじめました。
――殿はきっと再起される。――このわしの目に狂いはないわい。
墨染のころもにつつんだぶあつい胸をそらせると、文覚は、はるか東の空をあおぎ、大きく息をすいこみました。
その安房の国では………。
文覚のにらんだとおり、そこでは奇跡がおころうとしていました。
命からがら落ちのびた頼朝のもとへ、東国武土たちが続々とばせ参じてきたのです。
「長年、権力をかさにきて、すきかってなことをしてきた目代どもめ、いたいめにあわせてやる。」
「大将があらわれるのを待っておったのじゃ。
将門のように、東国に新しい政府をつくって、わしらの土地をまもってもらおう。」
日ごろの不満を爆発させるかのように、武土たちは気勢をあげました。
「わしは父君義朝どののもとで、保元のいくさをたたかったものじゃ。なつかしいこと………もう一度、源氏の大将のもとで合戦ができるとは、このうえもないしあわせでござる。」
目代を血まつりにあげてかけつけてきた下総(千葉県)の豪族、千葉介常胤(ちばのすけつねだね)は、大声で笑いました。
つづいて、上総(干葉、茨城県)の豪族、上総介広常は(かずさのすけひろつね)、二万騎の部下を引連れてやってきました。
木の葉のような小舟で安房にのがれた頼朝は、あっというまに二万七千騎もの大軍をしたがえたのです。
房総半島の安房、下総、上総の三国は、完全に頼朝の支配下にはいりました。
「相模の国、鎌倉へすすもう。鎌倉は、八幡太郎義家どのが居をかまえたところ。
お父上、義朝どののやかたあともまだ残っているはず。
なによりも三方を山でかこまれて、守りにはもってこいの場所でござる。」
常胤にすすめられて、頼朝は、鎌倉めざして出発することになりました。
江戸川をわたって武蔵の国(東京都)にはいると、石橋山の合戦では平家がたについた畠山重忠、河越重頼らの武士たちが、つぎつぎにやってきて、頼朝軍にくわわりました。
石橋山で負けてからたったの四十日。
房総三国、武蔵の国の武士の大軍をひきつれた頼朝は、源氏の白旗を空高くなびかせながら、相模の国(神奈川県)の鎌倉めざしてすすみました。
「まるで、夢をみているみたい。でも、私は信じていました。
頼朝どのは、どんなにつらいめにあっても、きっとそれをのりこえてゆく勇気のあるお方だと。
それに、東国武士は、いつまでも貴族のいいなりになって、いまの境遇に満足しているようないくじなしてはありませんもの。」
伊豆山のかくれがで、不安な日をおくっていた政子のところへ、安房でのすばらしいニュースが伝わってきます。
うれしくて、うれしくて、とびあがりたいほどの気持ちでした。
とうとう、待ちこがれだ頼朝からの使いがやってきました。鎌倉に本拠をおくことになったという知らせです。
――ああ。はれて殿とお会いできるのだ………。
政子の心は、もう鎌倉にとんでいます。
「今日は日が悪うございます。出発はもうしぱらくしてからになされ。」
「私は、もう一目も待ってはいられません。」
法音尼の言葉は、いまの政子にはくりかえされる波の音と同じです。
「気のつよいお方じゃのう。せめて、鎌倉ちかくまでいって、吉日をお待ちなされ、」
何からなにまで神や仏の力に支配されていると考えられていた時代です。
法音尼(ほういんに)は、いいだしたらあとへひかない政子の強情さに、苦笑いしながら、大姫をだいて山をおりる政子を見送りました。
――とにかく、第一の関門を通過したんだわ。
生きるか死ぬか、本当にそのギリギリのところでの、いちかばちかのかけだった。
もう駄目かと思ったときもあったけれど、とにかく、最初の勝負には勝つたんだわ。
政子は、この二か月半の苦しい日々を思いかえしました。宗時が澄んだひとみで笑いかけて
いるような気がしました。
鎌倉で、頼朝と感激の再会をしたのは、十月十一日のことでした。
三方をかこむ低い山々の木は、色づいた葉をすっかり落とし、朝夕は冬の気配がこくなっています。
「かならず、生きてお会いできると思っていました。――でも、ほんとはとっても心配でしたの。」
頼朝の顔を見ると、山木ぜめのときと同じことばが、口をついててます。
幀朝のおちついた顔を見ると、政子はだかいあいだはりつめていた力が、体からいっぺんにぬけるのを感じました。
「宗時は、かわいそうなことをした。この鎌倉へつれてきてやりたかったのだが。」
頼朝は、いたわるように政子を見ました。
ほんの二か月の間に、二人の運命はなんと大きく変ったことでしょう。
――これから、私は鎌倉で生きていくん百石。殿とご一緒に、
政子の目のまえに、わずかな田んぼがわりこんだ黄色いあれ地がひろがっていました。
海のあかるさをうつした空には、海鳥のかげが飛びかっています。
――わびしい海べの村も、すぐに東国武者たちであふれるようになるわ………。
砂をあらう波の音が、政子の耳をくすぐっていました。
2 武士のみやこ top
「平家の大軍が鎌倉めざしておしよせています。何万もの大軍勢でございます。」
いつまでも再会の喜びに、ひたっていられません。
頼朝が旗あげしたというニュースは、京にいる平氏や貴族たちをびっくりぎょうてんさせました。
さっそく、平維盛(これもり)を総大将とする平氏軍が京を出発しました。
その軍勢はもう駿河(静岡県)の手越まで、おしよせてきていたのです。
「まべ出陣ですか。」
政子は、大姫をだきながら、心ぼそそうにいいました。
鎌倉へきてまだ十日、ようやく新しい屋敷ができたばかりです。
「本当の戦いは、いまはじまったばかりだ。心配そうな顔をするなんて、おまえらしくもないぞ。」
頼朝は、からかうようにわらいました。
鎌倉がたは東海道を西へすすんで、平氏軍をむかえうつことになりました。
「あとはしっかりたのんだぞ。」
頼朝は、言葉すくなにいうと、よろいかぶとに身をかため、馬上の人となりました。
顔には、自信がみちあふれています。
もう。旗あげのときのように、くどくどと別れをおしんでいることはゆるされませんでした。
――殿は、見ちがえるほど、立派になってしまわれた。
私だって、もしものことがあっても、けっして取乱したり、見ぐるしい振舞いをしないようにしなければ………、武将の妻なんだから。
政子は、心の中で、なんども自分にいいきかせながら、ながい隊列を見送りました。
鎌倉を出て三日め、頼朝の軍勢は西から押し寄せてきた平氏軍と、富士川をはさんでにらみあいになりました。
頼朝を先頭に、東国武士の軍勢は意気にもえています。 |
 |
「わしらは、長年、いばりちらしてきた目代の首をとってまいったぞ。」
「もう二度と、おもい年貢をとられるのはいやしゃわい。」
各地の武士たちが、続々集ってきます。
これにひきかえ平氏軍は、数万の軍勢で出発したものの、いく先々で地方の武士の反抗にあい、逃げ出すものもでて、さっぱり気勢があがりません。
むこう岸の頼朝軍の数が多いのにどぎもをぬかれ、寝返りをうつ者も出るありさまでした。
この夜、なににおどろいたのか、富士川にいた数万ばの水鳥が、いっせいに飛び立ったからたまりません。
「敵がおそってきたぞ!」
水鳥の羽音にかんちがいした平氏軍は、あわてふためき、いちもくさんに逃げだしてしまいました。
「わっはっは、平家のこしぬけめが、」
「全くじゃ、ひょうしぬけしてしもうたわ。」
東国の武士たち晩あさぐろい顔を見島わせて、大声で笑いました。
「このまま、いっきにみやこへせめのぼる。清盛の首をうちとって、父上や兄上のかたきをうつのだ。」
頼朝は平氏軍を追いかけようとしました。いっときもはやく、平氏をほろぼしたい気持ちでいっぱいです。
それに、なんといっても東国の武士たちとはちがって、源氏という由緒ある家柄、みやこへいって、高い位にのぼりたいという気持ちもあったのです。
「殿。お、お待ちください。」
千葉介(ちばのすけ)常胤(つねたね)は、真赤な顔をして頼朝に食い下がりました。
「なによりもまず、東国の基礎がためをやることです。
平氏をたおすのは、それからじゃ。
それに、いま京へせめのぼることは危険ですぞ。
みやこは飢饉で苦しんでいるという。
僧兵どもも、暴れまわっておるといううわさじゃ。」
上総介(かずさのすけ)広常(ひろつね)、三浦義澄(みうらよしずみ)たちが口をそろえて頼朝の考えに反対しました。
「武士たちのねがっているのは、なによりも自分の土地をまもってもらうことでござる。土地争いなど、いっときもはやく殿に解決してもらいたい問題が、山ほどもあるのです。まずそれをやってからじゃ。」 |

源 頼朝
|
自分たちの棟梁が、みやこへいって公家になってしまったのでは、何にもなりません。
「ひとまず鎌倉へもどり、作戦をねりなおすべきじゃ。」
頼朝は、武士たちの願いで、鎌倉へ引返しました。はなばなしい、凱旋でした。
この知らせを聞いて、一番よろこんだのは政子です。
「わたし、京へいって、貴族のような生活をするなんて、本当に嫌ですよ。
それよりも、この鎌倉を立派な武士のみやこにしなくては………。」
政子の言葉に、頼朝はだまってうなずくと、大姫をだきあげました。
「政子どののいわれるとおりじゃ。鎌倉が、武士のみやこじゃ。」
千葉介常胤がもじゃもじゃのもみあげをなでながら、愉快そうにいいました。
「由比が浜を海の玄関にして、そこからまっすぐに道をつくる。
そのつきあたりに、源氏の守り神、八幡宮をおまつりしよう。」
「その東どなりの大倉は、総大将の屋敷じゃ」
「武士のみやこはなんといっても守りが第一。
鎌倉の大手口、稲村が崎の要所には、安達盛長どののやかた、亀が谷には武田どののやかた………。」
たくましい武士たちはカラカラ声をはりあげて、新しい町づくりに懸命です。
由比が浜には、毎日のように、太い丸太が、舟から荷あげされます。
ついこの間までは、昼間でもタヌキがでてきそうなわびしい村だった鎌倉が、すっかり生まれ変ろうとしているのです。
十二月十二日。鎌倉の空は雲ひとつなく晴れあがり、相模湾の海もまっさおな空をうつして、明るく輝いていました。
 |
狩衣に烏帽子(えぼし)、太刀(たち)を身につけた武士たちが、神妙な顔をして、木の香のがある頼朝のやかたに続々と集ってきます。これから、盛大なひきうつりの儀式がはじまるのです。
武士たちをとりしまったり、世話をやいたりする侍所(さむらいどころ)の別当(べっとう=長官)には、和田義盛が任命されていました。
「千葉介常胤ども北条時政どの、上総介広常どもそれから梶原景時どの………。」
義盛は、ぶきような手つきで、あつまった武士一人一人の名前を、帳簿につけています。
――義盛どのったら、今日はばかによそゆきの言葉づかい。
まあ、常胤とのも、白髪をあんなに丁寧にゆいあげて、かしこまっている。
頼朝のうしろにひかえた政子は、いならぶ東国武士たちの顔を一人ずつ見まわしました。
――武士たちは、なれない儀式なものだから、みんな緊張している。
これで本当の武士の政府ができるんだから、当り前なんだわ。
とうとう。東国武士が、自分たちの政府をつくったんだから。
京の政府にくらべれば、まだまだ小さな力しかないけれど、――宗時が生きていたら………。
政子は、父時政の左どなりにならんでいる弟の義時を見ました。
宗時が死んだいまは、この義時(よしとき)が、北条家のあととりです。
十八歳とは思えない、おちついた風格をもった青年になっていました。
式がはじまります。
武上たちは一人ずつ頼朝のまえへすすみ出て、大きな声で自分の名前を名のり、誓いの言葉をのべました。
頼朝と東国武上たちは、こうして正式な主人と家来の関係になったのです。
主人の頼朝は、「本領安堵(ほんりょうあんど)」といって、武士たちの土地をまもってやることを約束し、そのかわりに、家来の武士たちは、いざというときには、命をなげだすことを誓いました。
「いやいや、めでたい、めでたい。」
「鎌倉殿がおられるかぎり、わしらの所領は安心というものじゃ。」
頼朝は、鎌倉のあるじ「鎌倉殿」とよばれました。
その夫人の政子は「御台所(みだいどころ)」、家来の武士たちは「御家人(ごけにん)」です。
「さあさあ、御台所も、いっぱいやってくだされ。」
酒もりがはじまると、よそゆきの顔はとこかにふきとんでしまいます。
――よかった。みんなのこのそこぬけに明るい顔。大きな声。これこそ、東国武土の本当の顔なんだわ。
政子は、御家人たちがついでくれたお酒を、生まれてはじめてのみました。
ほろにがい味に顔をしかめると、それを見て頼朝も目じりをゆるめました。
鎌倉で、武士たちが意気ようようと新しい政府の基礎がためをはじめたその同じころ、京では、飢饉のなやみがますますひどくなってきていました。
道ばたには、飢え死にした人の死体が町じゅうにころがっています。
においをかぎつけたガラスが京の町をわがもの顔で、のさばっています。
「東国では、あずまえびすどもが義朝の子、頼朝をかしらにして、乱暴のかぎりをつくしているそうだ。
鎌倉とかいう田舎の村を、新しいみやこにするなどと、なまいきな口をきいているという。」
「全く、そらおそろしいこと、二百年も昔の平将門と同じですな。」
「いやいや、今度はずっと手強いようですぞ。平氏の軍勢があっさりかぶとをぬいで逃げ帰ったきたのですからな。」
直垂を着た男がふたり、六条の河原をはなしながら歩いています。
あまり身分の高くない貴族です。
「おかげで、東国の荘園からは、米ひとつぶも送ってこなくなってしまった。
頼朝がたについた武士どもが、年貢をみな自分のものにしてしまっているのだ。いまいましい。」
橋のたもとにさしかかると、やせこけた浮浪者たちがはいだしてきて、男たちの裾にしがみつきました。
「これ、あっちへいけ、けがらわしい乞食め。」
二人は、うるさそうに浮浪者たちをはらいのけると、足をはやめました。
「そもそも、清盛どのが、みやこを福原へうつしたりしたからいけないのだ。
たった五か月で、また、もとどおり京へもどったものの、すっかり運がかたむいてしまった。」
「もう、平氏の天下も先がみえておりますぞ。平氏の力じゃあ、鎌倉の頼朝の軍勢にはかないますまい。」
「そう思いますな。頼朝ばかりじゃない、みやこの中でも、みやこの外でも、平氏に反対して、清盛を追いおとそうというものが、手ぐすねひいている。」
四国でも中国、九州地方でも、あちこちで武士たちが反乱をおこして、京都へ運ぶ途中の年貢を奪いとっていました。
北陸方面では、頼朝とほとんど同じころ、木曽で旗あげした木曽義仲の軍勢が、みるみるうちに大きな力にふくれあがって、この地方を支配していました。
義仲は、源義朝の弟、義賢の子で、頼朝のいとこにあたります。
地方の武士ばかりではありません。京都や奈良の僧兵たちも、清盛に反抗していました。
たまりかねた清盛は、大軍をさしかけて、僧兵のいる興福寺や東大寺などを焼きはらってしまいましたが、そのために平氏への反感は、ますます強まりました。
「私は、いまに大戦争がおこって、この京のみやこがめちゃめちゃになってしまうのではないかと、悪い予感がしてならないのです。」
「そうでなくたって、武士どもの力がこれ以上のびたら、私たち公家の地位はあぶなくなってしまう。
おそろしいことです。」
二人の貴族は、まゆの間にしわをよせて、お互いに顔を見あわせると、気ぜわしそうに立ち去っていきました。
男たちがはなしていたように、京のみやこは、日に日におもくるしい空気におおわれていきました。
そして、平氏にとっては悪いことがかさなるもので、養和元年(一一八一)の年がかわると、肝心の清盛が、おもい熱病にかかってしまったのです。
一族をあげて、つきっきりで看病したが、さっぱりよくなりません。
「わしが死んでも供養はいらぬ。
それよりもなによりも、あのにくい頼朝をほろぼし、その首を、わしの墓にそなえてくれ。」
清盛は、そう言い残して死んでしまいました。東の鎌倉のほうを、いまいましそうににらみながら………。
3 大姫の涙 top
「おめでとうございます。立派なお世つぎができましたな。」
御家人たちの言葉に、いつもは無口な頼朝も、ほおがゆるみっぱなしです。
やかたの庭は、贈物の馬でひしめいていました。
どの馬も、射るような陽ざしのなかで、つややかな毛なみがてり輝やいています。
旗あげしてからちょうど二年めになる寿永元年(一八八二)の夏、政子は男の赤ちゃんを生みました。
お祝いの一行事で、鎌倉じゅうがお祭りのようににぎやかです。
丈夫な後継が生まれるようにという祈りをこめて、海から八幡宮のまえまでの道は、まっすぐな広い道路に改修されていました。
この道をとおって、御家人たちが、とっておきの坂東馬や刀をもって、かけつけます。 赤ちゃんは「万寿」と名づけられました。のちの頼家です。 |

鶴岡八幡宮
|
「大姫が生まれたときは、殿はまだ流人の身で、とてもこんな華やかなものではありませんでしたげれど、」
政子は、すやすやねむっている万寿をみながら、苦しかった昔のことを思いやりました。
頼朝の喜びようは、それは大変なもので、ひまさえあると、万寿がねているへやへやってきます。
「はっはっは、この子は力のつよそうな体をしている。源氏の、立派な後継になるぞ。」
すもものような万寿のほおをつついて、頼朝は目をほそめます。
鎌倉の町は、しだいに人の数がふえてきました。
武士ばかりでなく、商人たちも移り住むようになって、浜辺ちかくでは、市がたちはじめました。
たびかさなる飢饉や、僧兵のさわぎのためにすっかりあれはてた京のみやことは反対に、鎌倉は東国武士の都会として、活気があふれています。
頼朝を中心に、政治の仕組も、少しずつ形をととのえてきました。
「御台所、わが一族の先祖のまつりをしたいのですが、お手をかしていただけませんか。」
「御台所、万寿どのは、幼いうちから先生をつけて、武芸のうでをみがいたほうがよいと思われますぞ。」
御家人たちは、なにかあると政子のところへやってきました。
頼朝は元々口数の少ないほうですし、東国政権のぬしとして御家人たちのうえに立たなければならないのですから、だんだん近よりがたいものになりがちです。
そのてん、根っからの東国武土の娘である政子は、気さくで何でも相談できるのでしょう。
御家人たちは、自分の所領に帰れば、その地方では一番力のある領土ばかりでしたから、自尊心がつよく、個性的なつわものばかりです。
ある日のこと、舟からあがる頼朝を、御家人一同が砂浜に勢ぞろいして迎えました。
みんな馬からおりて、頭をさげているのに、上総介(かずさのすけ)広常(ひろつね)だけは、馬にのったままです。
「殿にたいして、ぶれいだぞ。」
千葉介(ちばのすけ)常胤(つねたね)が注意しました。
「わが一族は、父の代も祖父の代も、馬からおりて挨拶するなどということはしたためしがない。」
広常はそう言いはって、おりようともしません。
こんな豪傑たちをまとめるのですから大変です。
頼朝と御家人たちの間が気まずくならないように、また御家人たちが喧嘩をしないように気をつかうのは、みんな政子の役目でした。
――武土のみやこで、私も少しずつかわっていく、もう伊豆の田舎娘ではないのだ。
頼朝に会いにやってくる御家人たちの相手をする政子の横顔には、二人の子供の母。
鎌倉のあるじの妻としての重味がそなわっていました。
「木曽義仲の息子、義高(よしたか)を鎌倉へよびよせることになった。子供たちと一緒に面倒をみてくれ。」
頼朝が、ことさらさりげない口調で、政子にいいました。
「まあ、義高どのが、たしか、十一歳になられたと聞いておりますけれど、どうしてまた鎌倉へ。」
政子は、おどろいて、たずねました。
「いや、その、人質としてだ。」
いいにくそうに、頼朝がこたえます。
「人質ですって? 義仲どのは同じ源氏の一族、殿のいとこにあたられるかたではありませんか。」
政子は胸のなかに、黒い雲がむくむくとわきおこってくるのを感じました。
「同じ源氏ではあるが、義仲の父は、私の兄の義平どのに殺された。
だから義仲は、私に怨みをもっているかもしれないのだ。」
頼朝は、しかめっつらをしています。
「でも………。」
「いや、政子も知っているように、京都の平氏、北陸の義仲、それに東国の私と、いまの天下はこの三つに色わけされている。
そのなかでも義仲の勢いは目をみはるばかり、京へのぼって、平氏を追いおとそうとねらっている。
この私を、せめてくるかもしれぬ。油断はならぬ。」
頼朝は、いつのまにか真剣な目つきになっていました。
政子は、嫌な気持ちでした。子供を人質にとるなんて、母親として考えただけでもゾッとすることです。
でも、ほかの御家人たちの意見もあっての頼朝の言葉です。政子一人ではどうすることもできません。
「それでは義高どのを、大姫のいいなずけということにしてください。私が義高どのの母親がわりになりましょう。」
こうして、寿永二年(一一八三)の春、義高は鎌倉にやってきました。
大姫はもう七つ。生まれたばかりの万寿は元気のいい赤ちゃん。
こんななかに、新しい少年がはいったのですから、大倉の屋敷は、だいそうにぎやかになりました。
とくに大姫は大喜びです。
「ねえ、母上。義高は弓がとてもじょうずなのよ。きょう裏で、こんな大きな山鳥をつかまえてしまったのよ。」
大姫は目をまるくして、両手をひろげました。
「ねえ、母上。義高は、馬に乗るのがとてもうまいのよ。“わしは木曽の山ざるじゃから、”ですって!」
大姫は、義高がすっかり気にいって、一日じゅう、義高のはなしばかりしています。
「母上。私は義高のお嫁さんになるの?」
大姫は、きゅうにむずかしそうな顔をしました。
「そうですよ。もっと姫が大きくなったら。」
政子は、笑いながら、娘のくろかみをなでました。
「でも義高は、鎌倉が気にいっているのかしら、ときどきさみしそうな顔をするの。」
政子は、人質としてここにきている義高のおだやかな。すずしい目を思いうかべました。
「一人だから、さみしくなるのかもしれないわ。姫かなぐさめてあげなければ………。」
「ええ、だから、お願いがあるの。いつか、みんなで義高を海につれていってあげたいの。三崎の海に。」
大姫は、黒いひとみをかがやかせながら、母を見あげました。
「いいですよ。約束しましょう。」
しかし、このとき、天下の形勢は、大きく、ぱげしく動きはじめていました。
雪がとけると、北殃に陣どる義仲と、京の平氏との間に、戦いの火ぶたがきっておとされたのです。
木曽の谷に育ち、山や野原を庭のようにかけめぐっていた義仲の軍勢は、平氏の軍隊をさんざんいためつけ、勢いにのってみやこめざしてつきすすみました。
「ウォー。」
ときの声をあげて、木曽の田舎武土たちが京のみやこへなだれこみました。
平氏は大あわてで、六波羅の屋敷に自分から火をつけ、六歳の安徳天皇をつれて西国へと逃げ出しました。
平治の乱いらい、二十八年もの間、みやこで勢力をほしいままにしてきた平氏が、ついに京を追い出されたのです。
天下のうごきは、いよいよはげしくなってきました。
朝廷では、後白河法皇がひそかに陰謀をたくらみはじめました。
「義仲の軍勢をけしかけて、平家をけろぼさせよう。
それと同時に、義仲と頼朝を仲違いさせて、源氏の力を弱めれば、一石二鳥。
そうなれば、朝廷の勢力をもりかえすことができる。」
一方、鎌倉にいる頼朝は、義仲がひと足さきに京のみやこへはいってしまったので、うかうかしていられません。
そのうちに、京へはいった義仲の軍勢は、貴族たちの間で大変評判が悪くなってきました。
飢饉で食料が不足していたため、兵士たちが略奪をはじめたからです。
「頼朝にたのんで、義仲を追いだしてもらおう。」
いまがチャンスとみた頼朝は、後白河法皇のたのみをうけて、弟の範頼、義経を大将とする軍勢を京へとさしむけました。
鎌倉の軍勢は、あくる年の一月にみやこにはいり、義仲の軍をさんざんにうちやぶりました。
義仲は、力つきて戦死してしまいました。
京から鎌倉へ、はや馬が矢のように飛びました。
人質になったままの義高は、父が殺されてしまってから、まえよりももっと、さびしそうな顔をすることが多くなりました。
義高の身のまわりが、きゅうにあわただしくなりました。
「義高さま、すぐにおにげください。」
大姫のせわをする侍女が、かけつけてきて、あえぎながらいいます。
「やっぱりそうでしたか。」
義高は、もっていたさいころをほうりなげると、いそいで立ちあがりました。
大姫は、あっけにとられています。
それでもまわりの人が、馬の用意をととのえたりするので、一緒に義高の旅だちのしたくを手伝います。
「私のきものを着て! 義高さま、くらには布をまいて!」
大姫は義高のあわただしいようすに、夢中でさけびました。
義高は、だまっても、姫にほほえみかけると、馬にのって屋敷を出ていきました。
「一体、どうしたわけなの?」
大姫は、口ごもる侍女にしつこくたずねました。
「義高さまの父上、義仲どのが、姫の父君に討たれたのです。それで、義高さまの命もあぶないのです。」
「ほっほっほ、父上はそんなことをするはずないわ、義高もすぐ帰ってくればいいのに、」
しかし、一日、二日とたつのに義高は戻ってきません。
義高がいなくなってから五日ののち、大姫は、義高が殺されたことを聞きました。
その瞬間、大姫は大きな目をみひらいたまま、口もきけませんでした。
まっさおになり、くちびるがふるえています。
つぎの日からは、一日じゅう涙を流していて、はなしかけても返事もしなくなってしまいました。 |
 |
「なんとかしなければ、このままでは、あの子は死んでしまう………。いくら何でも、殿のやりかたはひどい。」
政子は頼朝のところへいきました。
「どうして、義高を殺したのです。どうしてそのまえに、私にひとこと、いってくださらなかったのですか。」
「しかしな、政子。これが政治というものじゃ。
いまは、新しい時代をつくるために、命がけの戦いがつづいているときなのだ。
生きるか、死ぬかの時代なのだ。
父を殺された義高が、私に復讐心をもったとなれば、あとあとまでくいをのこすことになる。
清盛は、私を殺さなかったばかりに、くやみながら死んだではないか。」
しずかにいうと、頼朝はじっと政子の目を見すえました。
「でも、かわいい娘を、あんなに苦しめて、殿。私には………。」
口をうごかしながら、政子は自分の心が、二つにわれていくのを感じました。
「それはたしかに、この鎌倉が、武士の政権がつよくなっていくのはいいことだわ。
これこそ、私たちの夢だもの。けれど、大姫は、私の娘はどうなるんですか!」
頼朝は体をこわばらせています。二人の目の中に、パチパチと火花が散りました。
かすかな波の音にまじってぶきみなしずけさが、たちこめています。
『ねえ、母上。三崎へつれてって、』
政子の耳の底に、まりのようにはずんだ大姫の声が残っています。
そのとき、政子は頼朝が石のように動かないのに気がつきました。
――この武士のみやこに、もっともっと苦しいことが待ちかまえているのだろうか。
政子は、なんともやりきれない気持ちでした。
4 太陽はひとつ top
鎌倉へは、三日とあげず、西国からの早馬がやってきます。
平氏との、天下わけめの決戦がはじまっているのです。
義仲に京から追いだされた平氏は、いったん九州へのがれたあと、再び勢いをもりかえし、京めざしてせめのぼってきました。
すぐに義仲を討ったばかりの義経の軍勢がつかわされ、一ノ谷でおそいかかって、平氏軍を屋島へ追いやってしまいました。
その平氏軍を討つために、頼朝は、範頼を総大将に命じて、大軍勢を西国にさしむけていたのです。
西国は元々平氏の地盤なので、わが源氏軍は、兵士への食料も思うように手にはいりません。
海のいくさにかけては、平氏軍はなかなか手強いのです。 |
範頼(のりより)からの手紙は苦戦をつたえていました。
源氏軍は、屋島にたてこもる平氏軍を、瀬戸内海のまわりから、じわじわとりかこんでいこうという作戦です。
しかし、海戦がとくいな平氏軍は、たくさんの船をもっていたので、源氏軍はなかなか手を出せません。
宿敵、平氏との戦いが思うようにすすまないので、頼朝はイライラしていました。
「どうぞ、源氏の白旗をおまもりください。」
政子は、毎日のようにも幡宮へお詣りします。
文治元年(一一八五)の年があけました。
しびれをきらした頼朝は、京都にとどまっていた義経を総大将に任命して、平氏を討たせることにきめました。
「義経どのなら大丈夫。きっと、平氏をほろぼしてくれます。」
「うむ。」
頼朝は、政子の言葉が聞こえたのか、聞こえないのか、なま返事をしたきりでした。
この兄弟の仲が、あまりうまくいってないことを、政子は感づいていたので、それ以上は口をつぐみました。
喜びいさんで出陣した義経は、あっというまに、たちまち平氏軍を壇ノ浦へと追いつめます。
源平最後の一戦は、三月二十四日のことでした。
西の海に夕日が落ち石ころ、南の流れにのった源氏軍は、平氏の軍勢を追いつめ、全滅させたのです。
勝利をしらせる使いが、鎌倉へかけこみました。
「敵の総大将、平知盛(とっもり)は自害。安徳(あんとく)天皇は、三位尼(さんみのあま)にだかれて壇ノ浦の海中にしずみました。大勝利にございます。」
御家人たちの喜びの声のなかで、一人正座した頼朝は、目をつむって使いの報告を聞いています。
とうとう、平氏をうちまかしたのです。
――ああこのお姿だ。北条のやかにいて、いつも経をよんでいた時と同じ。
殿はいま、長年の夢がようやくかなったのだわ。 |

源 義経
|
十三歳で伊豆に流されてから、二十五年もの間、一日として忘れられなかった夢が………。
政子には、頼朝の感激が、いたいほどつたわってきました。
平氏軍をほろぼした義経の名声は、大変たかまりました。
「義経どのは、天下一のいくさじょうずじゃ。」
「義経どのにかなうものは、世の中にはおらぬ。」
頼朝と義経は、どちらも義朝の子ですが、母親はちがっていました。
父が平氏に殺されてから、頼朝は伊豆へ流され、義経は鞍馬山へ修業にやらされ、二人とも、つらくさみしい思いをしてきました。
だから、旗あげのことを知ると、義経は、大いそぎで兄頼朝のもとへかけつけてきたのです。
兄弟なのに、二人の性格はまるでちがっていました。
心の底からあけっぴろげな義経は、「俺たちは兄弟なんだから」と、頼朝にたいしても気さくな態度を取り続けていました。
けれども、頼朝には、鎌倉殿としての立場があります。
御家人たちの上に立つ者として、たとえ兄弟でもえこひいきするわけにはいかないのです。
そこにつけこんだのが、後白河法皇です。
法皇は、頼朝と義経を仲違いさせて、源氏の力を弱めようと、策略をめぐらしました。
そしてまず手はじめとして、佐衛門少尉(さえもんのしょうじょう)検非違使(けびいし)という高い位を義経にあたえました。
「鎌倉殿は、御家人たちがかってに朝廷から官位をもらってはならないという命令を出されたはずじゃ」
「いくさのほうびは、すべて鎌倉殿から出されるはず。
義経どのは平氏をやぶったのは、みんな自分の手柄だと思いあがっておられるのではあるまいか。」
鎌倉では、御家人たちが、義経のかげ口をきくようになりました。
頼朝も、自分の命令がないがしろにされたとあっては、だまっていられません。
――義経どのも、もう少し自分の立場を考えて、慎重に行動してくれたらいいのだけれど、
――兄と弟、力をあわせれば、この世の中でおそれるものはないのに………。
政子の心配をよそに、頼朝と義経のなかは、日がたつにつれて悪くなっていきました。
五月になって、義経は、平氏の捕虜をつれて鎌倉へむかいました。
「兄上も、はなせばわかってくださるだろう。」
ところが、義経一行が鎌倉を目のまえにした腰越まできたとき、頼朝の使者がきて、鎌倉へはいってはならないとつげたのです。
兄弟の仲は、もう取返しのつかないほど悪くなっていました。
「兄上がそういうのなら、こっちにも考えがある。鎌倉殿に不満のあるものは、ついてこい。」
かんにんぶくろの緒をきらした義経は京へ引返してしまったのです。
後白河法皇はこうなるのを待っていました。
とうとうこの年の十月、義経に頼朝を討つよう命令をくだしたのです。
これに対して頼朝は、義経追討の軍勢を京へさしむけました。
義経は、西国へおちのびて軍勢をととのえようとしましたが、その途中、嵐のために船が難破して、ゆくえ不明になってしまいました。
あっさりみやこを逃げ出してしまった義経のあとを追うように、東国の軍勢は京にはいりました。
あわてた後白河法皇は、今度はてのひらをかえすように、義経を討てという命令をだしました。
頼朝は、かんかんにおこりました。
――わしを討てと義経に院宣(いんぜん)をくだしたその舌の根もかわかぬうちに、こうもあっさり寝返りをうつとは?
さっそく大江広元や、三善康信もまじえて、これからの対策の打合せをはじめました。
大江も三善も、みやこでは低い身分の公家でしたが、
――このままみやこでぐずぐずしていたら、一生低い身分のままで終わってしまう。
どうやらこれからの天下は、東国の武士たちのもののようだ。
かれのところへいって、はたらき場所をかちとったほうが、ずっとおもしろいぞ。
そう思って、三善は頼朝の流人時代から、大江は一の谷の合戦ののちから、頼朝に協力していたのです。
みやこの事情にはあかるいし、政治的なことにもくわしいので、とかく荒武者ぞろいの東国にとっては、とても大切な人間となりました。
頼朝は、ことあるごとに、大江や三善に相談して、政策をたてたり、文書をこしらえたりしています。
「法皇のなされかたは、我慢がならぬ。わしもみやこへ出陣しよう。」
わきあがる怒りをおさえるように、頼朝はかたくこぶしをにぎって、心なしかふるえる声でいいました。
「お待ちください。」
おしとどめたのは大江です。
「殿のお気持ちはわかります。しかし、まだ殿がこの鎌倉を留守になさるのは、危ないと思います。」
「あぶない?………奥州の藤原か。」
「さよう。平泉を中心に勢力をはっている藤原秀衡(ひでひら)。
彼がまだ殿のもとにひざまづいていないいま、殿が鎌倉を留守になさるのは、オオカミにえさを残していくようなものと思われます。」
大江のいうとおりです。頼朝もかえす言葉がありません。
「では、どうしろというのだ。」
「そこです、殿。二年まえのことを思いだしてください。
法皇が、義仲を京から追い出そうとして、殿にさそいをかけてきたときのことです。
我々のいう治承七年(一一八三)の十月。殿は、法皇の要求をさか手にとって、正式に流人の身分をとかせ、みやこで使っている寿永の年号を東国でも使うようになりました。
そのとき、殿が朝廷からかちとられたものは、何でしたか?
殿が東国の荘園の年貢をとどこおりなく京へ送らせると、後白河法皇に約束しました。
そのかわりに、東国を支配する権利を法皇に認めさせたではありませんか。
また、そのてをつかうのです。ただし、今度は法皇領もふくめて、西の国ぐに一帯にひろげる。
そして、荘園を監督するために、地頭という役職をつくって、御家人をさしむけるのです。」
「奥州は、どうする?」
「それは時を待ちましょう。たしかに秀衡は、ひとすじなわではいかない武将です。
でも、いつかは、熟しきった果実のように、落ちるときがくるはずです。
それよりも、もうひとつ、大切なことがあります。
東国、西国の年貢運上の監督と同時に、とが人をかくまう不心得ものがいないかどうか、それを厳しくただすための追捕使をおかせてもらいましょう。」
「とが人をかくまう? なんのことじゃ。」
「それは。」おそれながら、義経どの………。」
大江の言葉に、さすが頼朝も、うーんとうなってしまいました。
でも、たしかに大江のいうとおりです。武士の政権を確立するためには、鎌倉殿にたてつくものが、一人もいてはならないのです。
しかも、平氏をたおしたとはいえ、本当の敵、貴族の政権との戦いはこれからというときたのですから、
「鎌倉の力を全国にひろげる、またとない機会です。
義経どのをさがしだすという口実で、国ごとに守護をおいて、武士の取り締りにあたらせるのです。」
大江広元の案が認められて、京にむかっている時政に、さっそく使いが送られました。
頼朝の代理として、後白河法皇に東国の要求をつきつけて、ぜひともうんといわせるようにと、その夜、頼朝からことのしだいを聞いた政子は、義経追捕の言葉に、さっと顔から血の気のひくのが、自分でもわかるほどでした。
「あまりといえば、むごいことを………。」
「大江の言葉を聞きながら、わしも、このことをそなかが聞いたら、そういうであろうと思った。」
「なぜ、おとめにならなかったのです。」
「それは、できぬ。天にふたつの太陽があるわけにはいかないのだ。
そのためには、乱の芽は、早くにつみとらねばならぬ。たとえ血をわけだ兄弟であっても………。」
政子にはもう、なにもいえません。
――武士の棟梁に立つとは、こんなにもつらいものなのか。
殿は口ではああいっておいでだけれど、心の中ではきっと、苦しんでおられることだらうに。
それにしても、いま三歳の万寿は、かわいいさかり。
あの子が大人になったら、こんな苦しみを味あわせたくないものだけれど………。
政子はくちびるをかみしめて、じっともの思いにふけるのでした。
5 天下のはじまり top
去年の暮れ、朝廷にさしだした要求は、後白河法皇が、しぶしぶこれを認めました。
これで、頼朝の任命する守護や地頭が、国ぐにの荘園にのりこむようになったのです。
「朝廷にたいする父上のはたらきかげは、お見事でした。
今度ばかりは、朝廷がたも、手も足も出ないといったかっこうですね。」
弟の義時は、もう二十三歳。
平氏との戦いでは手柄をたてて、頼朝じきじきにおほめの言葉をもらい、一人前の御家人になっていました。
冷静で、口数は少ないけれど、知性的なするどい目が、いつも輝いています。
「これで武士の力は、いままでとはくらべものにならないほど強くなります。いよいよ、武士の天下のはじまりです。」
若い義時は、喜びに目をかがやかせています。
政子は、十年ほどまえ、父の時政が、貴族の警備にあたるため、いやいや京へのぼったときのことを思い出しなから、満足そうにうなずきました。
でも、そのとき。政子の心をいためるできごとがおこっていました。
頼朝は、諸国の武士に命じて、義経のゆくえをさがさせました。
しばらくして、義経夫人、静御前(しずかごぜん)が、大和の国(奈良県)の吉野山でつかまりました。
鐵倉へつれてこられた静には、頼朝じきじきの厳しい取り調べが待っていました。
「義経のゆくえを申せ。」
「どんな姿をしてにげておるのじゃ。」
静は、ひとことも口をきかずに、ただうつむいているばかりでした。義経をかばっているのです。
「舟がてんぷくしてから、吉野の山の中へ逃れました。
そこのお堂に身をかくしておりましたが、義経どのは山伏の姿に身をかえて、山おく深くにげていかれました。
あとのことはわかりません。」
うちつづく取り調べにたえられなくなって、とうとう口をひらいた静は、それだけいうとどっと泣きくずれました。
――静(しず)は、本当に心のそこから、義経どのをしたっている………。
政子は、静が気のどくでなりません。
「そなたには、なんの罪もありません。もう心配しなくてよいのですよ。」
政子のはからいで静は、安達新三郎という御家人の屋敷にあずけられました。
このとき、静のおなかの中には、義経の子供ができていました。
――静は義経どのの赤ちゃんを生んだら、殿はきっと、義高を殺したように、その子も殺してしまうだろう。
大姫は、いまだに泣いてばかりいるというのに。
政子は、いてもたってもいられない思いです。
その大姫が政子のそばへきました。
「母上。安達のところにいる静どのは、京の舞いの名手だと聞きますが、私も一度でいいから舞いを見たいわ。」
大姫は、目をかがやかせていいます。義高が殺されてから、はじめてみせる、目のかがやきです。
「たのんでみましょう。」
政子のたっての願いで、四月八日、鶴岡八幡宮につくられた舞台で静の舞いがまわれました。
この日、浜辺のまちは、朝はやくから静のうわさでもちきりです。
京の名高い白拍子の舞いが見られることなど、東国の住人たちは考えてもみないことだったのです。
鼓(つづみ)は工藤祐経(すけつね)、拍子(ひょうし)は畠山重忠(しげたた)がつとめることになっています。
「畠山どの、今日はとくと、そなたの拍子の腕前をみせていただきますぞ。」
ほかの御家人にひやかされても、重忠は自信満々。
幼いとき、京で暮らしたことがある重忠は、拍子もなかなかの腕前で、日ごろから自慢していたのです。
「わしは、とにかく、運を天にまかせてやってみるわい。殿の命令とあっては、あとへはひけぬ。」
祐経(すけつね)のほうは心配そうな顔つきです。
「なーに、静どのは、京でも一番といわれる名人。そちの鼓(つづみ)が、多少まずくても、うまくおどられるわ。」
やがて、頼朝がはいってきて、上座にすわりました。いよいよ舞いのはじまりです。
御家人からは、緊張したおももちですおりなおしました。
静がしずしずと舞台にあらわれました。
白い小袖、白い袴、唐綾(からあや)を上に重ね、わり菱の紋をぬいつけた水干(すいかん)といういでたちです。
瀬名かでたばねた黒髪が、こい緑色に輝いています。
春の陽が静をてらしました。ほんのり赤味をさした静の頬が、ぴりっとひきしまります。
「ほう!」
天女のような静の立ち姿に、だれからともなく、溜息がもれました。
ドン、シャン、ドン、シャン。
鼓も拍子も、なかなかの腕前です。
静(しず)は、舞いはじめました。 |
 |
大きなおうぎをひらくと、静は、すずをふるようなすきとおった声で、うたいはじめました。
吉野山 みねのしら雪ふみかけて いりにし人のあとぞ恋しき
しずやしず しずのおだまぎくり返し 昔をいまになすよしもがな |
義経のことをしたう歌でした。
吉野山の山奥ふかくはいっていってしまった義経どのが恋しい、昔のことが夢のようだ、というのです。
遠くをみつめる静のひとみに、涙がキラリとひかりました。おうぎをもつ手が、かすかにふるえています。
あたりは、水をうったようにしずまりかえりました。
頼朝の頬がピクピクひきつっています。
「も、もう、やめい。八幡宮に奉納するというのに、義経をしたう歌をうたうとは何事じゃ!」
頼朝のいかりにふるえた言葉で、御家人たちはみなうつむいてしまいました。
「殿、なにをおっしゃるのですか。静の気持ちもさっしてあげてください。」
政子の声がひくく、しずかに、流れるようにあたりにひびきました。それでいて、力強く、暖かみがこもっています。
「私には、いちずに愛する人のことを思う、静の気持ちは、貴いものだと思われるのです。
私にもおぼえがあります。
殿がまだ伊豆にいらっしやるころ、父上の反対をおしきって、あらしのなかを、あなたのもとにはしりました。
また石橋山のいくさのときは、どんなに心ぼそい思いで、殿のぶじを祈ったことでしょう。
その頃の私の気持ちと、いまの静の気持ちは、同じようなもの。私には、静の胸のうちがよくわかります。」
政子の意見に、頼朝もかえす言葉がありません。気をとりなおして、静にほうびをあたえました。
やがて静は、義経の子供を生みました。男の子でした。
政子は、赤ちゃんの命を助けてやるようにたのみましが、頼朝はやはり義高のときと同じように、義経の子供を殺してしまいました。
政子には、ただ、静をなぐさめてやることしかできません。
秋風がたちこめるころ、静はさみしく京のみやこへ帰っていきました。
政子は大姫と二人で、いつまでも静のうしろ姿を見送りました。
――大姫と静、二人ともなんて悲しい運命をせおっているのでしょう。
政子は、松林をふきぬける冷たい風の中にたたずんだまだ溜息をつきました。
全国の武士で、頼朝の命令に従わないのはもう、奥州の藤原氏だけでした。
この藤原氏のもとに、ゆくえ不明だった義経がかくまわれていることが、やがてわかりました。
義経をつかまえてひきわたすよう、頼朝が何度いっても、藤原秀衡(ひでひら)はききいれません。
「このチャンスに、藤原氏をほろぼそう。」
鎌倉幕府は、いくさの準備をはじめました。
秀衡(ひでひら)が死んであとをついだ泰衡(やすひら)は、幕府と戦争するのをおそれ、衣川(ころもがわ)の館にいる義経をおそって殺してしまいました。
けれども頼朝は藤原氏を討つ計画はやめません。
文治五年(一一八九)の夏、頼朝は、二十八万という大軍をひきいて、奥州へと出発しました。
九年ぶりの出陣です。
政子は、八幡宮へ出かけ、勝利のお祈りにはげみました。
鎌倉の山々がまっかにそまろころ、頼朝の軍勢は、奥州をたいらげて鎌倉へ戻ってきました。
日本じゅう、武力で頼朝にたちむかうものは、もういなくなりました。幕府の権力は全国にひろがったのです。
さむらいたちを取り締り、いくさのことをとりしきる侍所のほかに、政治一般のことを扱う公文所(くもんじょ=のちの政所)、裁判を行う問注所(もんちゆうじょ)なども整って、鎌倉は、立派に政府としての形も整いました。
旗あげ以来の、いくさの時代は、ようやく幕をとじました。
しかし、戦いがおわったわけではありません。
東の鎌倉幕府と西の朝廷、武士の政府と貴族の政府、この二つの間の本当の戦いは、実はまだ、はじまったばかりなのです。
6 母の願い top
「との! との!」
かやぶきの大きな門のまえで馬をすてると、和田義盛が、がらがらの大声をあげて、かけこんできました。
「生まれたのか!」
「はっ。元気な男のお子でございます。」
頼朝の顔が、とたんにほころびました。
建久三年(一一九二)の夏、政子は、千男の千幡(せんまん)を生みました。のちの実朝(さねとも)です。
政子のところへ戻ってきた義盛は息をはずませていいました。
「たびかさなるおめでたで、殿は、ことのほかお喜びですぞ。
殿のあんなにうれしそうな顔は、これまで見たことがありません。」
ひと月ほどまえに頼朝は、朝廷から征夷大将軍の位をうけ、ついさきごろ八幡宮で盛大なお祝いの儀式があったばかりだったのです。
征夷大将軍は、武士としては最高の位でした。
ほかのだれよりも鎌倉幕府をにくみ、なんとかして朝廷の力をとりもどそうとしていた後白河法皇は、この世を去っていました。
鎌倉幕府のまえには、こわいものはなくなったように思えました。
――苦しいことの連続だったけれど、ようやく私も、ひといきつけそうだ。
殿も念願の大将軍になったし、あとは、御家人たちが力をあわせて、幕府をもりたててゆくばかり。
私は母として、子供たちを立派なあととりに育てるよう、努力しましょう。
政子はもう、三十六歳でした。
長女の大姫(おおひめ)は十五歳、万寿(まんじゅ)は十一歳、そのあとに生まれていた次女の三幡(さんまん)は八歳になっていました。
政子の願いどおり、長男の万寿は、なかなかたくましい少年にそだっていました。
「おーい、そんなやりかたじゃ、鹿はにげてしまうぞ。」
「若殿の見事なたずなさばきには、とてもかないません。」
万寿は、おつきの少年たちをひきつれて、馬の稽古に余念がありません。
建久四年(一一九四)の夏のこと、富土のすそ野で大がかりな巻き狩りがあるので、その練習をしているのです。
「さすが鎌倉殿のあととりです。
殿も伊豆に流されておいでのころから、弓と馬にかけては右にでるものがありませんでした。」
安達盛長が万寿の姿に目をほそめながら、政子にはなしかけました。
「ええ、なにしろあの子は、東国一の弓の名人といわれる下河辺行平(しもかわべゆきひら)を先生にしていますから………。
でも、あの子のまえでは、けっしてほめないでくださいよ。
まわりのものがちやほやするものだから、この頃あの子は、少しばかり天狗になってします。
わがままな子になってしまうとこまりますから………。」
「そこまで、ご心配なさらなくても、御台所はなかなか厳しい母親でござりますな。ハッハッハ。」
盛長は、白くなったあごひげをなでながら笑いました。
巻き狩りといってもけっして遊びではありません。
全国から何千人もの御家人たちがあつまって、頼朝のまえで腕をきそいあう、いくさの演習のようなものです。
はじめてつれていってもらうので、万寿ははしゃぎながら、鎌倉を出発していきました。
いく日かした夕方のこと、留守番の政子のところへ、頼朝からいそぎの使いがきました。
「なんてすか。なにか、悪いことでもあったのですか。」
政子は、びっくりしてききました。
「いやいや、めでたい知らせでございます。」
使いは息をととのえると、話しはじめました。
「若殿が、馬ほども大きな鹿を射とめられたのです。
つのをふるってむかってくる鹿を、たった一本の矢で、ドゥとばかりに射たおしたのです。
殿は大喜びで、祝いの酒もりをひらかれました。
御台所にいっときもはやく伝えようと、この私を使いに………。」
さすがは万寿、政子には、頼朝の満足そうな顔が見えるようです。
しかし、政子は、しずかな口調でいいました。
「武士のあととりが、弓を射るのは当り前のこと。鹿を倒したくらい、さわぐほどのことではありません。
殿に、そう伝えてください。」 |
 |
使いのものは、拍子ぬけしたような顔をして、引返していきました。
――殿も本当に困った方だ。貴族の子供じゃないんだから、厳しく育てなくてはいけないのに。
政子は、心のなかで、にが笑いしました。
このところ、幕府の政治はなかなかうまくいっていました。
けれども政子にも頼朝にも頭のいたいことが一つだけありました。大姫の健康がよくないことです。
もう十年にもなるというのに、大姫は、殺された義高を思いだしては、一人で涙ぐんでばかりいました。
体の具合も、だんだん悪くなってきます。
政子は、大姫の健康をお祈りするために、冬のある寒い日に、伊豆山神社へ出かけました。
二十年近くもまえの、あの嵐の夜と同じように、肌をつきさすような冷たい風がふきあれていました。
万年杉の木立が、ヒューヒューとうなりをあげています。
神社につくと、昔のままに社殿の脇に、なぎの木があって、強い風にあおられていました。
今度ござれば もてきてたもれ
伊豆のお山の なぎの葉を |
この地方には、なぎの木の葉をひそかにたもとにしのばせておくと、愛する人と結ばれるという言い伝えがあるのです。
――私は父上の反対までおしきって愛する頼朝どののところへ走り、自分の生きる道を見つけることができた。
それにひきかえ、心をよせる人とむりやりにひきさかれてしまった大姫………。
かわいそうな大姫に、なんとかして心のやすらぎをあたえてやりたい。
政子は、いつまでも、祈りつづけました。
けれども、大姫の病気は、悪くなるばかりでした。
「どうしてもお嫁にいけというなら、私は海か川にとびこんで、死んでしまいます。」
気分をかえさせようと、結婚をすすめても大姫は首をふるばかりです。義高のことが忘れられないのです。
「それでは大姫どのを、後鳥羽天皇の妃になさってはどうでしょう。」
だれからともかく、こんな話がもちあがりました。
「天皇は十六歳。大姫どのは十七歳。年はちょうどいい。
それに、天皇の妃とあっては、姫もそう簡単にはお断わりできますまい。
姫の心のやまいをなおすには、少々むりにでも、結婚させたほうがいいですぞ。」
「うーむ。」
頼朝は考えこんでしまいました。 |
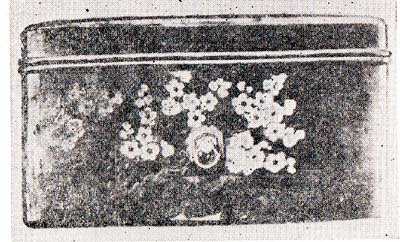
政子が愛用した手箱
|
富士川で平氏軍をやぶったときに京へいかず、鎌倉へ戻って武士のみやこづくりをはじめたときから、朝廷との関係は慎重にやってきた頼朝です。
「私はあまり気がすすみません。大姫を朝廷に嫁がせるなんて、それに第二の清盛になってしまう心配があります。」
政子は、この話には反対でした。
「だがな、政子。後白河法皇は亡くなられたし、幕府の政治も基礎がかたまってきている。
そう神経質になることもないかもしれぬぞ。それに、なんといっても大姫のためだ。」
頼朝の頭のなかでは、天皇の親戚になるのも悪くない、という考えが、ちらつきはじめたのです。
もとはといえば京の由緒ある家柄に生まれた頼朝です。
一度思いつくと、やもたてもたまらなくなってしまいました。――やれやれ、また殿の貴族ごのみがはじまった。
殿の心の底には、みやこのきらびやかな生活をあこがれる気持ちがいつもかくれているのだから。
政子は顔をしかめました。しかし、大姫のためといわれれば、反対もできません。
――ひょっとしたら、大姫も、具合がよくなるかもしれない。
そう思って、結局政子も賛成しました。
「そうときまったら、一度京へのぼってみょう。ちょうど、来年の三月に、東大寺再建のお祝いがある。
まえから、おまえや子供たちに、京のみやこを見せてやりたいと思っていたのだ。」
政子にとって、はじめての大旅行です。子供のころから、話に聞く、はなやかな京………。
みんながあこがれたみやこですが、政子はこれまで、一度もたずねてみたいと思ったことがありませんでした。
でも、今度は、大姫のためです。
――あの手をつれて、京のお寺や神社をお詣りしましょう。
あくる年の二月十四日、一行は、鎌倉を出発しました。
比企能員(ひきよしかず)と千葉常秀が先発隊、頼朝や政子、万寿(まんじゅ)、大姫(おおひめ)、三幡(さんまん)、それにまだ赤ちゃんの千幡(せんまん)たちの一行は、和田義盛や梶原景時らがまもるという長い行列でした。
二十日間の大旅行のすえ、三月四日の夕方、政子たちは京につきました。
「まあ、なんてたくさんの家があるんだろう。」
子供たちは、目をまるくしました。うわさに聞いていたとおり、京のまちは、色とりどりできらびやかでした。
宿舎はもと平氏の屋敷がたちならんでいた六波羅にありました。
つぎの日から、頼朝は東大寺の式に出たり、朝廷への挨拶まわりに大いそがしです。
政子は、大姫をつれて、清水寺や石清水(いわしみず)八幡などへお詣りにいきました。
「大姫を天皇の妃にするには、権(ごん)大納言土御門(つちみかど)通親(みちちか)と丹後局(たんごのつぼね)に頼まなければいけないらしい。
なにしろ、あの二人が、後鳥羽天皇に一番気にいられているという。」
ある晩、知りあいの公家を訪ねて帰ってきた頼朝が、いいました。
その頃朝廷では、鎌倉幕府と仲のよい九条兼実(かねざね)が一番高い位についていました。
この兼実に反対して、手をむすんでいたのが通親(みちちか)と丹後局(たんごのつぼね)でした。
通親は、後白河法皇の近臣だった男です。
丹後局もまた、後白河法皇にかわいがられていた女性で、もう四十をすぎていましたが、頭がよく、大変な美人でした。
「でも、丹後局や通親どのは、元々幕府を悪く思っておられるそうです。
殿がこの二人と仲良くなったら、兼実どのが困るのでは………。」
政子が不安そうにいいました。しかし、大姫を天皇の妃にしたい下心の頼朝です。
「とにかく丹後局(たんごのつぼね)を、この屋敷へまねくことにした。局の気にいるように、絶対してくれ、」
うわさのとおり丹後局は、天輪の花のようにあでやかでした。
「田舎者でございますが、なにぶん娘のことをよろしくお願いします。」
政子は頭をさげました。もちろん、貴族の女を尊敬しているわけではありません。
――きれいなきものを着て、おしろいをぬりたくっていても、それはうわべだけのこと。
私には、鎌倉幕府がある。本当の力をもつ武士の政府がある。
いまはただ、大姫のために、頭をさげておくのだ。
政子は、心の底ではそう思っていましたが、局のいうことにおとなしく従いました。
頼朝は、銀の蒔絵(まきえ)のはこに砂金をいれてプレゼントしました。丹後局はすっかり気をよくしました。
四か月近くもの間京にいて、政子たちは、六月末に帰りの旅にたちました。
「どうやら大姫を天皇の妃にする話は、うまくいきそうだ。」
頼朝は、満足そうでした。
「私もホッとしました。肩がこってしまいましたよ。」
政子は笑いました。 |
 |
――はやく鎌倉へ帰りたい。でも、あんなに丹後局と仲良くしてよかったんだろうか。
局と通親どのは、幕府の力が大きくなるのを嫌っている人なのに………。
ちょっぴり、あとあじの悪いものが残りました。
一行が美濃の国(岐阜県)まできたとき、鎌倉からはや馬がきました。
稲毛重成の妻となっていた政子の妹の一人が、危篤(きとく)だというのです。
重成は、ひとあしさきに帰りました。
政子たちが鎌倉についたときには、妹はもう死んだあとでした。
7 暗くながい冬 top
あけはなされた板戸の外では、ぎんねずみ色の雨がしとしとふっていました。
――六月も雨だった。そして、七月も………。
政子は、かたい板じきのえん先で、ぼんやりすわっていました。
手のなかの古びたさいころを、思いだしたようににぎっては、力なく溜息をついています。
あんなにいろいろ手をつくしたのに、大姫は京から帰ってきた年の冬のはじめ、とうとう動けなくなってしまいました。
食事ものどを通らなくなって、たましいがぬけたようになってしまったのです。
政子は、一生懸命に看病しました。
けれどもそのかいなく、建久八年(一一九七)の夏、大姫は、とうとう息をひきとってしまったのです。
父に反対されながら流人の頼朝のもとへはしり、苦労していたころに生まれた長女だけに、とりわけいとおしい娘でした。
そのうえ、いいなづけの義高を殺されて気がへんになってしまったのですから、かわいそうでなりません。
――大姫のあとをおって、私も死んでしまいたい。
あんなに苦しいめにあわせて、私は母親なのに、何もしてやれなかった………。
政子は、すっかり気をおとしてしまい、ふりつづける雨を、いつまでもながめていました。
でも、そういつまでも悲しんでばかりはいられませんでした。
大姫を天皇の妃にしようとした計画は、大変な結果をまねいてしまっていたのです。
まえの年の十一月、朝廷のなかでも幕府の味方として活躍していた九条兼実(かねざね)が、突然関白という一番高い地位からはずされてしまったのです。
そのあと、実際の政治の権力をにぎったのは、通親(みちちか)と丹後局(たんごのつぼね)でした。
大姫を朝廷に送りこみたいばかりに、頼朝は通親や局(つぼね)と手をむすんだのでしたが、そのために、元々味方だった兼実の力がおとろえてしまったのです。
そのうえ、建久九年(一一九八)になると、通親は自分の養女が生んだ四歳になったばかりの土御門(つちみかど)天皇を位につけました。
「通親は、自分が中心になって反対する者をしめだし、幕府に反撃しようとたくらんでいるのです。
朝廷への幕府の発言力は全くなくなってしまいました。」
頼朝はこのところ、いつになくいらいらしながら、京のことにくわしい大江広元などと、これからのことについて相談をくりかえしています。
――いつまでも、娘を失った悲しみにひたっているわけにはいかない………。
鎌倉幕府が生きのびるためには、まだまだ朝廷との厳しい戦いが必要なのだ。
黒い雲をはらいのけるように、政子は自分で自分をはげましながら立ち上がりました。
しかし悪いことは、まだまだつづきました。
しかも政子にとっても、鎌倉幕府にとっても、そしてたくさんの武士たちにとっても、一番不幸なできごとが………。
「と、とのが大けがをなさいましたっ!」
使いのものが大あわてでかけこんできたのは、その年の暮れの二十七日の夕方でした。
御家人の稲毛重成が、死んだ妻の供養をするために、相模川に橋をかけました。
その完成式の帰りみち、こともあらうに頼朝は馬からからおちてしまったのです。
打ちどころが悪く、頼朝はそのまま寝こんでしまいました。
大黒柱の頼朝が重体だとあって、武士たちは大さわぎです。
「たたりじゃろうか。弟の義経どの、範頼どのを殺されたたたりじゃろうか。」
頼朝は義経につづいて、範頼をも「むほんをたくらんでいる」といって、殺してしまっていました。
「いや、あんなにかわいがっておられた大姫さまが亡くなられて、気落ちしておられたのが原因じゃ。」
「京でも、いろいろむずかしい問題がおきておられるから、気苦労がかさなかったのじゃろう。」
御家人たちの間でも、浜辺の市でも、うわさはうわさをよびます。
「八幡宮のそばのやかたの火事は、つけ火だそうじゃ。」
「本当かい。ほれ、朝比奈の切り通しの火事さわぎ、あれもあやしいといううわさだぞ。」
鎌倉じゅうがうきあしだって、おだやかでない空気にとりまかれています。
政子は、夜もねないで、必死の看病をしました。
――いま殿が亡くなったら、せっかくできた鎌倉幕府があやうくなる。
子供たらはまだ一人まえじやない。何が何でも、殿に元気になってもらわなければ………。
しかし頼朝は、とうとう起きあがれませんでした。
あくる正治元年(一一九九)の正月、五十三歳でこの世を去ったのです。
あまりに突然のできごとでした。
――殿が死んでしまうなんて、考えたこともなかった。
苦しいことの連続だったけれど、殿のそばにいたからこそ、私はここまでやってこれた。
その殿が、さきに死んでしまうなんて………。
政子の胸は、はりさけそうでした。
――小さな子供たち、主人を失った幕府の政治、一体何から手をつけたらいいのだろう………。
頼朝が先頭になっておしすすめた幕府づくりにあわせて、ただひたすら前へ前へと歩みつづけてきた政子です。
厳しい試練にぶつかったいま、鎌倉じゅうが音をたててぐるぐるまわっているように思えました。
長く寒い冬でした。
波の音で目をさましては、暗闇のなかで、政子は言いようのない不安におそわれるのでした。
top
**************************************** |