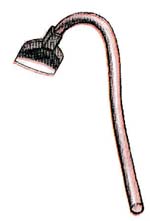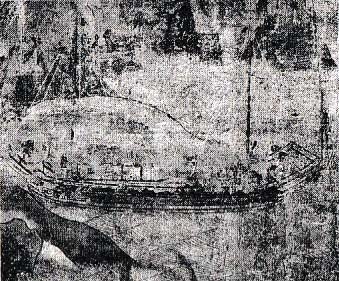|
****************************************
Index 一章 二章 三章 付録
二章 政治の舞台へ
1 蘇我・物部の戦い
top
真夏の太陽が、ジリジリ照りつけている。
いまはなき用明天皇二年(五八七年)七月はじめ、大和の各地から軍勢がぞくぞくと池辺双槻宮の北の広場に集まり、つぎには、物部守屋が軍勢をととのえてそなえる河内の国渋川(くにしぶかわ)に立っていた。
長い軍列のなかに、聖徳太子の姿もあった。
太子は、白い馬にのっていた。
蘇芳色(すおういろ)の衣と褌(はかま)のうえに短甲(たんこう)をつけ、腰には征箭(そや)をいれた革箙(かわえびら)をつっている。
左腰におびた太刀の金具が、日の光をうけてきらめいた。
「上宮皇子さま、この暑さ、短甲は重く、さぞかし暑苦しゅうございましょう。」
白馬によりそって進んでいる膳臣河鴈(かしわでのおみかわなり)が、太子に声をかけてきた。
河鴈も、同じように軍装をととのえ、鉄の小札(おざね)を二枚重ねにした衝角(しょうかく)つき胄(かぶと)をかぶっている。
太子のものは、金銅の目びさしつき冑、二人のうしろにやはり馬で従う舎人の調子麻呂(ちょうしまろ)が、左手にあずかっていた。
彼は昨年、十八歳のとき太子の舎人になった。
「いや、たいして重くはない。それにもともと、私は夏の暑さには強いほうだ。」 |

短甲(たんこう)
古代のよろいの一つ。
鉄の板で胴のまわりをつつむ。
古墳からたくさん出土する。
|

小札(こざね)
札(さね)は甲胄(かっちゅう)を
かたちづくる、細長い板のことで、
鉄または革でできている。
小札は、札の小さいもの。
|
「そうでございましたな。このたびの戦いは、皇子さまにははじめてのもの。
この河鴈(かわかり)が日ごろからお教え申し上げてきましたわざを、充分に発揮してくださいまし。」
「わざとか、腕前とかいっても、いくさは、鹿や猪を射るのとはわけがちがう。
どれだけの働きができるか、おぼつかなく思っている。」
「なにを申されますやら。日ごろから弓矢や剣、また乗馬の訓練にはげんでまいられた皇子さまの腕前をもってすれば、守屋の軍勢など、わけなくたおせます。
上宮皇子さまは、ほかの皇子さまがたとはちがいますぞ。」
河鴈は太子にいい、うしろをよりかえった。
一万数千の軍兵が、河内にむかって進んでいる。
かわきあがった夏の道に土ぼこりがまい、前後がはっきり見えないほどだった。
その土ぼこりのなかに、竹田・泊瀬部(はつせべ)・難波・春日ら四人の皇子たちの短甲姿がながめられた。
彼らは、ともに皇位につく資格をもつ皇子たちで、聖徳太子もその一人だった。
そのなかに、大王の位に一番ちかいはずの押坂彦人大兄皇子
* の姿がない。
* 大兄(おおえ)皇子 皇后がうんだ長男のことで、皇位をつぐ、もつとも有力な皇子をさした。
後の安閑天皇を勾大兄(まがりのおおえ)皇子とよんだのに始まり、中大兄(なかのおおえ)皇子(天智天皇)で終った。
この皇子は病床についていたか、それともすでに死んでいたという説もある。
用明天皇二年(五八七年)四月の条を最後にして、この皇子の名前が歴史からきえていることから、蘇我系の皇子を天皇につけるため、馬子が物部守屋との合戦のまえに、殺したのではないかとも見られている。
穴穂部皇子をうたれた守屋が、かれのかわりに、もっとも皇位に近い大兄皇子を味方にしようとしたとすれば、ありそうなことだった。
「河鴈、おまえはそういうが、ほかの皇子たちにくらべ、私はまだ十四歳、たいした働きはできないかもしれない。」
「いいえ、皇子さまはもう立派な大人でございます。
おからだのご成長も、ほかの皇子さまにひけをとりません。
来年ぐらいには、お妃さまをおむかえしなければなりませんな。」
彼は、歯のない口を見せ、からからとわらった。
その頃結婚が許される年齢は、男が十五、女が十三歳だった。
それからすれば、太子の結婚はもう目のまえにせまっていた。
蘇我家の手勢にかためられ、すぐまえを進む馬子の子の蝦夷(えみし)は、太子より三つ年上だった。
彼は十五歳で妻をめとった。
「そなたは昔から、なんでも簡単に申してきた。今度のいくさも、私はなにか、ためされているように思えてならない。」
太子は、いくぶんくらい表情でつぶやいた。
蘇我馬子が、父用明天皇の殯をつづけている池辺双槻宮(なみつきみや)をおとずれ、母の穴穂部間人(あなほべのあしひと)皇后と、長い時間なにか相談したあと、太子をよんだのは、昨日の朝だった。
「何事でございます。」
太子は、母の弟たちをうった蘇我馬子に、いくらかこだわりをもったままたずねた。
母間人皇后の顔はなぜかなごんでいる。
穴穂部・宅部(やかべ)の二人の弟を殺したはずの馬子を、さして憎んでいるようには見えないのであった。
馬子からは、すでに父の死後、殯宮(いがみのみや)でおくやみをうけていた。
「上宮皇子さま、母妃さまにいまお話し申し上げたところでございますが、このたび、河内の国阿都にひきこもった大連物部守屋と、ついに決着をつけることになりました。
そこでご相談でございますが、皇子さまにもご出陣していただきたいと、こうしてお願いにあがっだのでございます。」
馬子は平伏したうえ、ていねいにのべた。
「蘇我と物部の両家がなにやらさわがしい、いくさの気配がするとは、舎人たちからきいていました。
しかし、いまは父用明天皇が亡くなられてまもない。
御魂(みたま)にやすんじていただくためにも、そのいくさはさけられませんか。
蘇我は大臣、物部は大連、どちらも天皇家には大事な重臣です。」
太子は姿勢をただして注文をつけた。
父用明天皇の薫陶(くんとう)をうけ、七、八歳のころから経典にしたしんできた。
そのなかには、争いの心をおさえ、慈悲をもてと書かれている。
蘇我氏はそうした教えをとく仏教をすすめてきたのではなかったか。
争う心をおさえれば、血をながしての解決はさけられるはずであった。
「皇子さまが申されることは、この馬子にもよくわかります。
しかし、私がそのように考えましても、相手の物部守屋は同じように考えてくれません。
皇子さまはまだおわかく、純真でいらっしゃいますが、国の政治はなかなか一筋なわではいきません。
ましてや天皇がお亡くなりになり、つぎの天皇がまだきまっていないこのとき、国をみだそうとするやからは、どうしてもうたなければなりません。
くわしいことは、おいおいおきかせいたしますが、守屋討伐にご出陣のこと、なにとぞご承知くださいませ。」
馬子は、太子の意見を充分にきこうともしないで、あわただしく殯宮からさがっていった。
「大臣馬子どのは、天皇家の力を大きくし、諸国をまとめて政治をすすめるために、やむをえないいくさだと申されていました。
そなたさまのほか、竹田・泊瀬部・難波・春日の皇子さまたちが、ご出陣なざるそうですが、皇子さまがたのご出陣が、馬子どのに大義名分をあたえ、いくさを有利にするぐらい、この私にもわかっております。
でも、それはそれでいいではありませんか。真心をもった下心、蘇我家は天皇家には血のこい同胞、何事にもわるくはいたしません。」
母穴穂部間人皇后は、弟たちをうしなった悲しみをどう克服したのか、蘇我馬子を支持した。
「母上さまが守屋討伐にいきなさいと申されるなら、上宮はおおせに従います。」 太子は、母妃のすすめにうなずいた。
けさ、上宮にやってきた膳臣河鴈にてつだわせ、軍装をととのえた。
かれの手で短甲をさせられ、ちょうつがいをがちゃがちゃとしめられたとき、国をまとめるためならいくさもしかたがないと、仏の心にそむく自分のうしろめたさを納得させた。
太子がつけた短甲は、五世紀の古墳からよく出土している。
胴がわきなどでひらくかたちのもので、黒うるしがぬられていた。
「りりしいお姿でございます。」
河鴈にほめられ、上宮の宮門から外にでると、蘇我馬子の命令で、膳臣傾子が自分につけてくれた屈強の手勢五十人ほどが、馬にのったり徒歩でひかえていた。それに上宮の舎人十数人がくわわる。
集合の場所には、おびただしい軍勢があつまっていた。整然とした兵列のまえに、父用明天皇の病室で見た群臣の姿があった。
「記紀」のなかで群臣(まえつきみたち)と書かれる良家のものたちで、紀臣男麻呂(きのおみおまろ)・巨勢臣比良夫(こせのおみひらふ)・膳臣傾子(かしわでのおみかたぶこ)・葛城臣鳥那羅(かつらぎのおみおなら)・大伴連噛(おおとものむらじくい)・阿倍臣人(あべのおみひと)・平群臣神手(へぐりのおみかむて)・坂本臣糠手(さかもとのおみあらて)――などである。
彼らは大臣(おおおみ)・大連(おおむらじ)の下で、重臣として国政にくわわっていた。 蘇我馬子は、長い年月をかけ、自分の味方をつくりあげてきた。 |

うるし
古代に、中国をへて渡来し、ひろく各地で栽培
された。高さ七〜十メートル。秋口紅葉する。
樹皮から、汁がとれ塗料となる。
ふれると、皮膚がかぶれる。
|
その時期は、敏達天皇の末期から用明天皇の時代にかけてだと考えられ、かつて蘇我氏の上にたっていた物部氏は、馬子のすぐれた手腕にまけ、政治的地位を逆転されていた。
有力豪族といわれる彼らの顔ぶれを見れば、その優位性がなによりもよくわかる。
一方の物部守屋軍は、『日本書紀』に、大連、みずから子弟(やから)と奴軍(やつこいくさ)とをひきいて――と、書かれている。
この場合、子弟とは一族をいい、奴軍とは守屋の奴隷たちにすぎない。
大王家の軍事・警察権をにぎっていたはずの大連守屋が、この程度の軍勢しかもっていない。
彼は馬子と一戦をまじえるにいたり、重臣たちから見すてられ、人気をうしなっていたのだ。
もちろん、勢いのあるほうについた人々もいただろうが、はっきりいえることは、多くの豪族たちが、馬子の考えている政治のありかたや指導力に、信頼をよせていたのである。
守屋や穴穂部皇子の行動は、大王家をたてて日本の中央集権化をはかる馬子にとっては、王権を分裂させる悪い行いだった。
とても許すわけにはいかなかった。
磐余をたってきた蘇我軍は、耳成山をすぎたころ、二つにわかれた。
馬子にひきいられた主力軍は、二上山の北の逢坂峠をこえて、守屋の本拠地渋川をめざした。
第二軍は逢坂峠を左に見て北上し、大和川にそい、竜田道をこえて進んだ。聖徳太子は、この第二軍にくわわっていた。
三輪山のふもとから国中平野をえんえんとながれてきた大和川が、川幅を大きくひろげて斑鳩(いかるが)の地をうるおし、大和と河内を急流によってむすんでいる。
斑鳩からは難波もちかく、交通のかなめであることが一目でわかった。
「上宮皇子さま、ここが私の本貫の地でございます。よいところでございましょう。」
傾子と仲のいい平群臣神手が、馬をちかづけ、太子と河鴈に話しかけてきた。
「本当に美しい土地だ。大和が一望できる。ここから船で、三輪山のふもとまでどれくらいでいけよう。」
「水量にもよりますが、ゆっくり一日。難波には半日もかかりません。」
神手は、ほこらしげにいった。
大和川は葛城山地と信貴山地をぬけたところで、南からながれくだってくる石川と合流する。この北西に、物部守屋の本拠地渋川があった。 |
 |
その夜、第二軍は太和川の右岸で夜営した。
一帯は蘇我氏発祥の地でもあり、蘇我の門流たちがはせさんじてきた。
夏の日がすっかりくれ、夜になった。ひろい川原とそれにつづく草原に、さかんに夜営の火がたかれた。
大槍をかかえた宿直(とのい=夜警)が、とおくに見える守屋の陣をにらんでいる。
「ねむれませんか。」
熊の皮をしいてよこたわる太子に、河鴈が声をかけてきた。
太子がいくども寝がえりをうつのを見て、彼は気づかったのである。
「胸がたかぶり、なかなかねわりにつけん。」
「さようでございましょう。しかし、充分にねむっておかなければ、明日のいくさにさしつかえます。」
河鴈にいわれ、太子はうなずいた。
夜空の星が美しかった。ながれ星が、すっと尾をひいてきえていった。
――あの星がちらばっている天空は、どうなっているのだろう。仏の国はあのむこうにあるのだろうか。
太子はやみの底にいる自分か、とても小さく思われてきた。
天地はかぎりなくひろい。
そのなかで人間は、愛しあい、憎しみあい、様々な悩みをかかえ、それでいて死や目に見えない神や仏といった存在をおそれて生きている。
明日のいくさもちっぽけなものに思えてならなかった。
にの小さな生きものの私は、これからどう生きていけばいいのだろう。
そんなことを考えているうちに、太子はふかいねむりにおちていった。
「皇子さま、おめざめください。」
河鴈におこされ、まわりを見ると、夜はまだ明けていなかった。
あわただしくむし飯をたべ、鳥の肉をほおばる。水でそれをのどにながしこんだ。
「いそいでください。夜明けとともに、守屋の陣に攻めかかるのです。」
立ったまま口をうごかしている太子に、河鴈が短甲をつけさせ、ちょうつがいをかけた。
守屋軍との合戦は、東の空がしらんできた頃、主力軍と合流して始まった。
物音をひそめ、渋川まで進んだ全軍は、いなたばでまわりをかこった守屋軍の「稲城」に、いっせいにおそいかかったのである。
「火矢を放て、稲城をやいてしまえ。」
膳臣傾子の命令で、稲城にはげしく火矢が射こまれたが、どうしたことか稲城はもえあがらなかった。
火矢の攻撃を予想し、守屋軍は稲束を水でぬらしていたのだ。
寄せ手がとまどっているところへ、守屋軍から矢が、雨あられととんできた。ばたばたと兵士たちがたおれる。
そこをねらい、守屋軍から屈強の兵士がうってでる。はげしく槍や剣をふるい、形勢が不利になると、さっと稲束でかためた砦の中ににげこんだ。
朝はやくから昼すぎまで、そんないくさが何度もくりかえされ、たくみな守屋軍の反撃にあい、蘇我軍は大軍で攻めながら、三度もしりぞいた。
|

四天王寺
大阪市天王寺区にある。いわゆる四天王寺式の伽藍配置で有名である。
たびかさなる災害のため創建当初の建物は、ほとんど残っていない。
|

白膠木(ぬりで)
高さ五メートルぐらい。夏から秋にかけて
黄白色の花をつけ、紅葉する。
当時、神の霊がやどる木と考えられた。
「ぬるで」ともいう。
|
太子もそんななかで、革箙(かわえびら)から矢をぬきとり、守屋の兵をめがけて弓をひいた。
ねらいが的中し、胸に矢をうけた敵兵がどっとたおれていく。
あの敵兵にも親や妻子があるだろうにと思うと、太子の胸がいたんだ。
いくさは昼からもはげしくつついた。
だがそのうち、戦況は蘇我軍に有利になってきた。
『日本書紀』によれば、太子が白膠木(ぬりで)を切りとり、仏をまもる四天王像をいそいで彫り、頭にくくりつけ、
「もし私を勝たせてくださるなら、かならず四天王のためにお寺をたてます。」と誓い、全軍の出気をふるいださせたからである。
蘇我馬子も、自分に味方してくだされば、寺をたて、三宝をつたえますとちかった。
太子のたてた四天王寺、馬子の法興寺が、この誓いにもとづいたものだという。全軍は勇気づけられ、敵をにらんだ。
このとき、馬子がくりだした別働隊が、守屋軍をうしろからおそった。
守屋軍はきゅうにおじけづき、いっせいに退却し始めた。
それにしても、『日本書紀』をまとめた人々は、このエピソードをどこからえたのだろう。
それは、四天王寺は聖徳太子によってたてられたと伝える四天王寺系(してんのうじけい)古縁起(こえんぎ)を参考にしたのである。
四天王寺の『古縁起』をつくった寺側の人々は、創建の歴史的意義を、はなばなしく説こうとした。
蘇我氏と物部氏が仏教をめぐって争い、そこに太子の戦勝祈願がくわわり、それで四天王寺が太子の誓いどおりにたてられたとすれば、四天王寺のありがたさがいっそうひきたってくる。
そのため、物部氏は徹底して排仏をとなえてきたと、『古縁起』に書かれたのだ。
蘇我氏と物部氏の権力争いは、仏教をめぐってのあらそいにすりかえられた。
物部氏の本拠地の渋川廃寺から、飛鳥時代初期の軒丸瓦が出土していることを思い出せば、歴史のつくった嘘がよくわかる。二氏の崇仏か排仏かの争いは、歴史的にはなかったというべきであろう。
四天王寺の創建は、太子の時代よりずっと後ではないかとも、今いわれている。
ともあれ、勢いをとりもどした蘇我軍に追われ、物部軍は本拠をすて、衣摺(きぬずり、東大阪市)までしりぞいた。
「ものども、にげるな。ここにふみとどまって、敵をはねかえすのだ。」
物部守屋は全軍に指図し、自分も大木の枝にのぼり、ひたひたと攻めてくる蘇我軍に手ばやく矢を射かけた。つきすすんでくる蘇我軍の兵士たちが、矢をあび、次々と血にそまる。
その時、ものかげに身をかくし、一人の男が大木にちかづいた。男は守屋のゆだんをたしかめ、弓に矢をつがえた。男は物部守屋にそむいた中臣連勝海(かつみ)を、以前、守屋の命令で殺した迹見首赤檮(とみのおびといちい)であった。
守屋が不利だと見て、かれもまた蘇我馬子にねがえったのである。
満月のようにひきしぼられた赤檮(いちい)の弓から、矢がひょうと放たれた。
直線をえがいてとんでいった矢は、物部守屋ののど首に、まっすぐつきささった。
「ぐわおっ――。」
守屋は大きな声をあげ、枝から地面にころげおちた。
大将を射殺され、物部軍はあわてふためき敗走した。
この合戦のとき、守屋の部下、捕鳥部萬(ととりべのよろず)が、難波にあった守屋の屋敷をまもっていた。
萬(よろず)は、いったん山に逃げたが、数百人の兵士にかこまれると、姿を現し、弓矢で十数人を射殺した。
そして再び山ににげようとしたところを、ひざに矢をうけて転倒した。
彼は矢をひきぬき、草のなかにふした。
「この萬は、つねづねから天皇の盾としてその勇をあらわそうとこころがけてきたのだが。
わしを殺す気か、とらえるつもりか、しかるべき者にたずねたい。」
萬は、悲痛な声でよびかけた。
それでも討つ手たちは、萬の勢いにおそれ、やみくもに矢を射かける。
すさまじい形相で草のなかからとびだしてきた萬は、またたくまに三十人ほどをうちたおすと、かたくにぎりしめていた剣をおしまげ、川になげすてた。
そして腰から小刀をひきぬき、首をさして自害した。
『万葉集』のなかに、萬(よろず)の思いと同じ歌がある。
今日よりは顧(かえり)みなくて大君の醜(しこ)の御盾(みたて)と出で立つわれは
(今日からはあとを顧みることもなく、大君の強い御盾になって、私は出発するのだ。)である。 |
萬のさけびには、猛将のさいごの言葉として、胸にひびくものが感じられる。
守屋軍を破った蘇我軍は、戦場をかたづけ、数日後、磐余に凱旋してきた。
だが、太子の顔色はなぜかさえなかった。自分が手にかけた人々の顔が、心からはなれないのだ。草を血でそめ、ごろごろと横たわっていた戦死者たちの姿が、夢にまであらわれて太子を苦しめた。
八月二日、泊瀬部皇子(はつせべのみこ)が即位し、名を崇峻(すしゅん)天皇とあらため、磬余の倉梯(くらはし、奈良県桜井市倉橋)に宮をもうけた。
十月中旬、まだ苦しんでいる太子を、もっと悲しませることがあった。
母妃が蘇我馬子にすすめられ、太子の異母兄田目皇子(ためみこ=多米王)と結婚したのである。
「人とはいかなるものだ。私には自分をふくめ、人というものがわからなくなった。」
わかい太子に、母の再婚はゆるせなかった。
「それでもあのおかたさまは、上宮皇子さまの母上でございます。」
膳臣河鴈が、太子をなぐさめた。
2 崇峻暗殺 top
山の雪がさえ、季節が春めいてきた。
上宮のまわりでは、梅の花の匂いがただよい、すぐ桃の花があたりをいろどった。
季節は、めまぐるしくかわっていく。さくらのあと、山々はまもなく新緑におおわれ、つぎ
には夏の暑さがきた。
「宮におこもりのままでは、お体に毒でございます。すこしは外に出かけられませ。」
膳臣傾子が上宮をおとずれ、すすめたのは、弟の河鴈から太子の毎日をきいたからだろう。
聖徳太子は昨年の末から、ほとんど部屋にとじこもったままであった。
窓のそばに丹塗りの机をすえ、百済からもたらされたいろいろな経典や、それを注釈した経論(きょうろん)、また道教の教理をまとめた『雲笈七籤』(うんきゅうしちせん)などを読んでいた。
幼い頃から学問にはげんできただけに、大体は意味がわかり、仏の教えもつかめた。
もっとも、むつかしいところには、印をはさんでおき、父用明天皇の死に立ちあった豊国法師(とよくにのほうし)や河鴈にたずねた。
豊国法師は、河鴈と年かっこうが似ていた。どんな経歴をもつのかだれも知らなかったが、とにかく仏典にくわしく、豊富な知識をたくわえていた。
大臣蘇我馬子ともしたしく、河鴈によれば、豊国法師が上宮にとどまっているのは、馬子の指図らしかった。
そのせいか、百済から献上された経典を必要とすれば、わけもなくもってきてくれる。
また彼は、百済や中国の言葉も話せるらしく、いつか檜隈(ひのくま)からきた渡来人の造寺工と、訳語もまじえずに言葉をかわしていた。
「皇子さまの学問の師のおつもりで、馬子さまが上宮にすめとお命じなされたのでしょう。」
河鴈は太子が豊国法師についてたずねたとき、さらっといった。
仏教の教典を読んだり、そこに書かれた意味を考えたりして時をすごすのはすきだった。
興味がわくと、太子は夜ふけまで机にむかう。
外を出歩かないことも苦にならなかった。
「河鴈もここに顔をみせるたび、同じ言葉ですすめてくれる。そなたたち兄弟の気づかいはうれしいが、もう私はもとどおり元気になった。仏の教えを学ぶことがすきだから、こうして毎日をすごしているだけです。」
太子は傾子に、やわらかな笑みをうかべていった。
みんながふさぎこんでいる自分のために、炊屋姫のむすめ菟道貝鮹(うじのかいだこ)皇女を妃にすすめ、気持をまぎらわしていただいてはどうかと、相談していることも知っていた。
田目皇子と再婚した母妃は、しあわせそうだという。
この春三月、崇峻天皇が、大伴連糠手(あらて)のむすめ小手子(こてこ)を妃としたこともきいていた。
「この結婚は、蘇我馬子さまや炊屋姫さまに、ひとことの相談もなかったそうで、馬子さまはひどくおはらだちとうけたまわりました。」
上宮にこもっていても、いま朝廷でおこっていることは、そのつど河鴈や豊国法師がきかせてくれる。
「崇峻天皇さまは、蘇我家の血をうけているため、いくぶんお人柄にくせがあっても、大臣や炊屋姫さまがたが目をつむり、天皇にいたされた。それなのに、大伴連のむすめを妃にされれば、天皇家の外戚として、国の繁栄につくしてきた馬子の面目はたたないだろう。
腹立ちももっともだ。
崇峻天皇さまは、馬子からあれこれ指図されるのを、うるさく思われているのだ。
何事も自分のおもいどおりにされたいのだろうが、そんなわけにもいかぬわなあ。」
男として一人前の十五歳になっただけあり、その時太子は、母妃の弟になる天皇の行動を批判した。
崇峻天皇にすれば、馬子のおかけで天皇になれたとはいっても、兄穴穂部皇子を殺されたうらみを、馬子にまだいだいているだろう。
そのうえ、いつも馬子に監視されているようにおもえば、考えがあさく気ままな性格だけに、反発したくもなってくる。
一方、蘇我馬子にすれば、天皇家の権威をもっとたかめ、中央集権化をすすめたいと一生懸命、努力している自分の考えを、どうして理解してくれないのかと、腹がたってくるのだ。
――わしの同胞とはいえ、姉の小姉君の息子たちは、どうもできがわるい。
堅塩媛のむすこ豊日皇子や、その子の上宮皇子とくらべればひどくおとる。まるで駄馬、悪霊としかおもえぬ。
この頃馬子は、こう頭をいためていた。
かれに殺された穴穂部(あなほべ)皇子の上には、茨城(いばらき)皇子と葛城(かつらぎ)皇子がいた。
しかし茨城皇子はおろかで、斎宮(いつきのみや)として天照大神(あまてらすおおみかみ)につかえていた磐隈(いわくま)皇女に乱暴し、一線からしりぞいた。
葛城皇子は早死にしていた。
太子は、こうした外のできごとをきくたび、馬子や叔母の炊屋姫が、なにを思っているのか考えた。
自分と叔母の長男竹田皇子は、まだ年がわかい。
馬子は自分や竹田皇子に、学問にはげんではやくそだてと期待している。
太子はそんなとき、竹田皇子があまり健康にすぐれないのが気がかりだった。
豊国法師や膳臣河鴈も馬子と同じことをいう。
「いまこの大和に、馬子さまほどのお人が何人おいでになりましょう。
皇子さまが馬子さまと心をあわせ、朝政や外交にあたれば、国はもっと立派になりますのになあ。」 |

斎宮(いつきのみや)
斎皇女(いつきのみこ)ともいう。天皇の即位のとき、
伊勢神宮などに天皇の名代として奉仕する未婚の皇女。
|
二人のささやきが、太子には聞こえるように思われた。
この年のはじめ、百済から使者がきた。そして僧恵聡(そうえそう)・令斤(りょうこん)・恵寔(えしょく)らが仏舎利を献上した。
つづいて首信(すしん)たちが飛鳥や磐余の地を踏んだ。
「馬子さまが善信尼さまたちを首信どのにおあずけになるそうでございます。」
このとき豊国法師が太子にもらした。
海石榴市(つばいち)ではずかしめをうけた善信尼(ぜんしんに)たちは、釈放されたあとも、馬子の槻曲(つきくま=明日香村)の屋敷にいた。
彼女たちはまえから馬子に、百済留学を願っていたのであった。
そこで馬子は、百済の使者首信(すしん)に彼女たちを托し、百済にわたらせた。
半月ほどあと、善信尼たちが多くの人々に見送られ、たっていってから、飛鳥の真神原(まかみのはら)で、法興寺の建立がはしまった。
造寺工も瓦博士も百済からやってきている。
坂田原にすむ鞍作鳥(くらつくりのとり)たちは、おおっぴらに大きな仏像を刻みだした。
法興寺の建立は、一部の人たちだけに信じられていた仏教が、いわば国家仏教として高らかにうぶ声をあげたことを意味していた。
いままで蘇我氏の私邸にもうけられた仏堂は、寺といえる規模のものではない。法興寺が、日本最初の本格的寺院になる。
当初は蘇我氏の氏寺として工事がはじまったが、やがて崇峻天皇のあと即位した推古天皇によって、国家の権力がくわわり、三宝興隆の詔(みことのり)へと発展していくのだ。
|

地鎮祭(ちしんさい)
土木建築工事をはじめるまえに、工事の安全を祈り、
その土地の神がおこらないように、神の心をしずめる祭り。
|
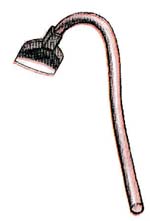
ちような
大工道具。あらけずりの材木をなめらかにするためにもちいる。
|
聖徳太子は地鎮祭が行われたとき、馬子にさそわれ、真神原にいったきりであった。
「法興寺では柱もたち、木づちやちょうなの音がこきみよくひびいております。気ばらしに、見物にいかれませんか。」
自分はこうしているのがすきだという太子に向かい、傾子は、でもございましょうかと前置きして、また外出をすすめた。
「傾子、すまぬが、私をかってにさせておいてくれ。書物を読んで気持があきたら、この窓から野山をながめる。
世の中のできごとは、そちたちみんなが聞かせてくれるではないか。
私はいま、生活を単純にして、精神を複雑にしている。そうしなければ、仏典は理解できないからだ。」
太子の言葉をきき、膳臣傾子は、すなおに一礼してさがっていった。
かれの足音が上宮の主殿からとおざかる。
窓から見ると、高床式の楼のそばをぬけ、宮門のほうにきえていった。
太子は、またものおもいにふけりはしめた。
人とは、どうして多くのものに執着するのだろう。権力・財物・色欲など、かぞえあげたらきりがない。
釈迦は心身をなやますいっさいの欲望を、煩悩と名づけている。
自分が母妃の再婚を不快に思ったのも、煩悩の一つであった。
だがそれも、いまは大きな気持でゆるせる。人間はこの煩悩をもつために、たがいにはてもなく争うのだ。
太子は、さきほどまで、『法華経』の譬喩品(ひゆほん)第三を読んでいた。
諸苦所因(もろもろのくのいんとするところは) 貪欲為本(どんよくをもととなす) 若滅貪欲(もしどんよくをめつすれば)
無所依止(えしするところなからん) 滅尽諸苦(もろもろのくをめっじんせるを) 名第三諦(だいさんのたいとなづく)
為滅諦故(めつたいのためのゆえに) 修行於道(みちをしゅぎょうするなり) 離諸苦縛(もろもろのくのばくをはなるるを)
名得解脱(げだつをえたりとなづく) |
――この解脱(げだつ)にいたれば、人は間違いなく解放され、やすらかにくらせるのだ。
太子の心で、なにかがふと光ってみえた。
『日本書紀』は、推古天皇三年(五九五年)に来朝した高句麗僧恵慈(えじ)と百済僧恵聡(えそう)の二人が、太子の先生になったと書いている。
だが太子はこの時すでに二十二歳。二人を先生にしたが、それまでも太子に仏典やいろいろな学問を教えた人がいたにちがいない。
その人が豊国法師であった。
翌推古天皇四年(五九六年)、太子は恵慈たちと伊予(いよ、愛媛県)の道後温泉にいき、碑文を書いているが、その文章は立派で、一年や二年の勉強ではできないものだった。
崇峻天皇一年(五八八年)から三年(五九〇年)にかけ、太子はほとんど仏典にしたしんですごした。
上宮の外では、新しい天皇をいただき、様々な政策が実行されていた。
二年(五八九年)七月には、東山道に近江臣満(おおみのおみみつ)、東海道に宍人臣鴈(ししひとのおみかり)、北陸道には阿倍臣(あべのおみ)を見まわりに派遣した。
欽明天皇のときからつづけられてきた屯倉(みやけ)の経営はうまくいっているか、朝廷の権威がそこなわれていないかなどを、確かめるためだった。
翌年の春三月、百済に留学した善信尼たちが帰国し、桜井寺におちついた。
わかい女性の留学は大変だった。彼女たちをむかえた人々は、苦労をたたえ、その手引きで出家するものが何十人もでた。
冬になり、飛鳥の東や南の山々から、法興寺建立のため、さかんに犬木がきりだされた。
年がかわっだ崇峻天皇四年(五九一年)の四月、それまで広瀬の殯宮(もがりのみや)におかれていた敏達天皇のご遺体が、河内の国石川郡にもうけられた磯長陵(しながりょう)にあらためてほうむられた。
六年間も正式にほうむられなかったのは、朝廷ではなにかといそがしかったからだ。
太子はこのとき、数年ぶりに公式の場に姿を現した。
すでに太子も十八歳、品位と知性をそなえた姿が、人々の目をみはらせた。
「おやさしいお顔だちは、母妃さまそっくりだ。
皇子さまが菟道貝鮹(うじのかいだこ)皇女さまを妃にされたというのは、きっと本当だな。」
貝鮹皇女は敏達天皇と欸屋姫のむすめ。竹田皇子の姉だけに、聖徳太子より年上だった。
妃の父を陵に送るために、太子は公式の場にでられたのだと、物知り顔でいうものもいた。
夏がすぎ秋になる。まもなく寒い冬がきた。
十一月、紀臣男麻呂こ曷城臣鳥那羅・巨勢臣猿・大伴連噛の四人を大将軍として、二万あまりの軍勢が二上山の北をまわり、とおい筑紫にむかった。
新羅に支配されてしまった任那を回復するためで、それは欽明天皇以来の悲願だった。
遠征の軍列が、半日がかりで西にきえていったあと、大和はきびしい寒波におそわれ、ふかい雪にすっぱりとおおわれた。
役人の諸国派遣や、任那遠征は、崇峻天皇が即位したあとも、馬子がさいはいをふる諸政策が、着々と進んでいることをしめしている。
大任をおびて出発した大将軍たちは、物部守屋との合戦で、馬子に味方したものばかりだ。
『日本書紀』には、任那回復は崇峻天皇の発議と書かれているが、本当は馬子がいいたしたにきまっている
。内政をととのえた自信が、馬子に任那遠征を決意させたのだろう。
もっともこの遠征は、海をわたり新羅までいくつもりは最初からない。
二万あまりの軍勢が、海をわたってたたかうには、たくさんの船や食料がいる。
馬子を中心にした大和朝廷は、筑紫に兵を集めることで、新羅に圧力をかけ、以前のようにみつぎものを出させようどしたのだ。
北九州と朝鮮半島の間には、その頃ひんぱんに人や船が行き来していた。
二万あまりの数が正しいかどうかわからないが、それほどの大軍が筑紫に集まれば、すぐ新羅の政府にもきこえる。
圧力にはなった。
それにもう一つ、大和朝廷の大軍が西国を通れば、各国に権威が見せつけられ、中央集権化に役だつはずであった。
馬子は、そんな計算もしていた。
だが崇峻天皇は、自分にたいして相談もせずに、馬子がどんどん政治を進めていくのが気にくわない。
「わしは、ただのかざりものか。」
したしい人々に、いつも不満をもらしていた。
馬子は崇峻天皇のまえの結婚が、天皇家と蘇我家の関係をよわめると考え、むすめの河上娘(かわかみのいらっこ)を妃に入れていた。
天皇には、馬子の政権を安定させようとしている気持がわからない。新羅遠征軍を見おくり、一年たってもそうだった。
ただおもうままに政治をとりたいと考え、馬子をころして主導権をにぎろうとした。
『日本書紀』には、天皇が献上された大猪を見て、いつかこの猪の首をきるように、わしが嫌だと思っているやつをきってやりたい――といわれたと書かれている。
そのためか、天皇は自分につかえる兵士をすこしずつふやしていた。
『日本書紀』は本文のなかに、「ある本」という言い方で、時々世間の噂や言い伝えをのせている。
それによれば、馬子にむけた天皇の怒りの言葉を、馬子に告げ口したのは、天皇から愛されなかった大伴小手子(こてこ)だという。
「天皇がわしを殺すおつもりなら、先手をうたなければならん。」
馬子は、一族をいそいで集め、相談した。
人柄を心配しながら、崇峻天皇を即位させたのは、ほかでもない馬子と炊屋姫だった。
相談に炊屋姫も、しかたがないとうなずいたことだろう。
蘇我馬子は王権を確立させるためにはたらき、いますべてはうまく運んでいる。
馬子が殺されれば、世の中が混乱する。
十一月三日、馬子は高官たちに、きょう、東国からみつぎものがとどく。
倉梯宮(くらはしのみや)で儀式を行うから集まれと、使いをやった。
使いをうけた高官たちが、衣服をただして参上してきた。
「上宮皇子さまも列席しなさい。」
炊屋姫から太子にも使いがきた。
太子も新しい袍(ほう)をつけ、圭冠(はしはこうぶり)をかぶり、笏(しゃく)をもって、倉梯宮正殿の階段のそばにならんだ。高官たちが、次々に目礼する。
同母弟の来目皇子や殖栗皇子たちも、ならんでいた。異母弟当麻皇子の姿もあった。
日ぐれがちかく、宮の庭ではかがり火がたかれていた。それが北風にあおられ、火の粉がとぶ。
その時先駆けが息をきらし、宮門をくぐってきた。
ほどなく正殿に崇峻天皇が姿を現し、うしろに側近や女官たちがしたがっていた。
すこしずつくらくなっていく空から、雪がふりはじめ、それとともに、儀式の鼓吹(こすい、太鼓と笛)が宮門の外からひびいてきた。
すんだ鈴の音もいくつかなっている。
白装束の舎人たちが、足にひもでむすんだ鈴をふりならし、宮門をくぐってきたのだ。鈴の音が悪霊をはらう。音楽は国の権威をあらわす一つであった。
彼らと鼓吹の楽人たちのうしろに、みつぎものをかついだ人々がつづき、短甲に身をかためた兵士たちも、宮の庭にあらわれた。
正殿の中央に立った崇峻天皇は、満足そうにみんなを見おろした。
兵士たちを指揮するのは東漢(やまとのあやの)直駒(あたいこま)。
彼は蘇我馬子から、崇峻天皇をころせと命じられていたのだ。
だが、その馬子の姿は庭になかった。
――大臣が見えないが、どうされたのだろう。
東国からの使いと一緒に、宮門をくぐってくるものと思っていた太子や高官たちは、顔にいぶかしい色をうかべたが、使いが階段のまえにうずくまり、天皇に奏上をはじめたのを見て、笏をもつ姿をただした。
|

かがり火
鉄製のかごのなかに、脂の多い松材をもつてもやす火。
夜間の照明、警備にもちいた。
崇峻天皇が大きくうなずき、階段から庭におりる。
その時、身をひくくした兵士の先頭にいた東漢直駒が、すっくと立ちあがった。
「ものども、かかるのだ。」
かれの大声とともに、短甲のむれが腰から剣をひきぬき、天皇めがけて殺到した。
かがり火に、剣がきらっときらめいた。雪をまじえた風が、火の粉をとばし、闇につつまれたまわりの木々をゆする。
怒号(どごう)が、みんなをすくませた。
「兄上さま――。」
そばにいた殖栗(えくり)皇子が、太子に声をはしらせたが、太子だけでなくその場にならんだ高官たちにも、いま目の前で行われている騒ぎが、まるで信じられなかった。 |
 |
崇峻天皇におそいかかった兵士たちは、かついできた台からみつぎものをなけだし、その上に血まみれになった天皇を、ひきずりあげた。
みつぎものは、わらたばを白布でおおったものにすぎなかった。
その白布で天皇の姿をかくした。
「上宮皇子さま、おやめなさいませ。」
笏をなげすて、太刀のつかをつかんだ太子をとめたのは、膳臣傾子だった。
まわりは、騒然としている。
突然のできごとに、立ちすくんだまま、ガタガタふるえている者もいた。
「傾子(かたぶこ)、なぜだ。」
太子は、するとい声で傾子にたずねた。
「なりません。これは大臣(おおおみ)さまがお命じになったことでございます。」
「なにっ、大臣の命令だと。」
太子は、一瞬にすべてを理解した。
崇峻天皇をのせた台が、兵士たちによって、さっと宮門の外へ運ばれていく。
悪夢をみるおもいで、天皇にくわえられた惨劇を見つめていた人々も、すぐにすべてを察したようだった。
「天皇の資格のない人のなれのはてだ。」
だれも殺戮(さんりく)者のあとを追わなかった。
――私は、しずかに仏典を読み、学問にはげんでいていいのか。
天皇家の人々が、馬子によって次々に殺されていく。
この世で私にできることはないのか。こんなみにくい世の中をあらためるためには、どうすればいいのだ。
太子は馬子の人柄や考えがわかりながら、かれの人間性にあるおそろしさを感じた。
この頃、天皇を殺すという行為は、それほど重大な罪とは考えられていなかった。
『日本書紀』も、馬子を非難していない。
馬子は、天皇も蘇我家の一人と見ており、一族の代表者として罰したのである。
そうしなければ、天皇家や蘇我家が理想としてきた中央集権国家がつくれない。
蘇我家の優位をはかることは、そのまま天皇家の権威をたかめることでもあった。
東漢(やまとのあや)直駒(あたいこま)によって倉梯宮(くらはしにみや)から運び出された崇峻天皇の遺体は、殯の儀式も行われず、すぐ倉梯岡にほうむられた。
直駒はほどなく、蘇我馬子に殺されている。
馬子は世間の目を、表面だけでもつくろうため、直駒を自分の命令といつわり天皇を殺したのはゆるせないと、罰したのである。
「わしは大臣さまだけがおえらいとおもい、天皇の尊さを知りませんでした。」
車漢直駒は、全身に矢をあびながらいった。
ここで思い出してもらいたいのは、物部守屋の猛将捕鳥部萬(ととりべのよろず)が、自分は天皇の盾として、その勇を現したかったといった言葉だ。
直駒(あたいこま)と萬(よろず)の二人が天皇にいだいた考えには、これほどのひらきがあった。
二つの言葉から、天皇の権威がまだかたよっていなかったことや、政治の仕組みが、一般にそれほど理解されていなかったことなどがわかるだろう。
太子は、上宮の一室にすわっている。
天皇の急死が、世上に不安をもたらせているのが、しずかな上宮にいても感じられた。
――私はどうすればいいのだろう。平和な世の中をつくりあげたい。
仏は私にそれをしなさいと命しているのかもしれない。
太子の胸に、『法華経』の文字が、はっきりうかびあがってきた。
3 女帝と摂政 top
山から、二人の男がおりてくる。
肩にかついた棒に、鹿がぶらさかっていた。彼らは、人でにぎわう海石榴市(つばいち)にくると、みんなのまえで鹿の皮をはぎ、肉にして売りはしめた。
とおくに炊屋姫のすむ海石榴市宮が見える。
「だれが天皇になるのだろうなあ。」
客がとだえたとき、一人の男が手をよきながら、仲間にたずねかけた。
「そうよな、だれがなるのだろう。
順序としては押坂彦人皇子、上宮皇子、竹田皇子の三人だが、彦人皇子は死んだか、病気でねているとの噂だ。
さっぱり見かけない。だからあとの二人というわけだが、これがまたちょっとやそっとではきまらない。
大臣馬子は、だれを天皇にするかで、頭をかかえていると、飛鳥の槻曲(つきくま)の屋敷につかえているわしのいとこがいっておった。」
二人の男が話すとおり、蘇我馬子はだれを天皇に即位させるかで悩んでいた。
皇位につく資格のある皇子たちの顔をおもいうかべると、それぞれに一長 一短があった。
やがて最後には、上宮皇子と竹田皇子の二人が、候補者としてのこされた。
「わしは子供のころから聡明で、仏教、儒教、道教となんでも学んでいる上宮皇子を、推薦したいのだがなあ。
あの皇子なら、人にも信頼されている。わしも皇子の成長をたのしみにし、そのつもりで手助けもしてきた。」
馬子は、息子の蝦夷につぶやいた。
「それなら、そうきめればいいじやないですか。」
蝦夷は、たいした考えもなくいった。
「ばかをいうな。いくら上宮皇子さまが適任でも、わしからそれをすすめられるか。炊屋姫さまは、竹田皇子さまの母上だぞ。」
自分の子供に皇位をつがせたいのは、母親として当然だろう。
それを無視して上宮皇子をすすめれば、上宮皇子が聡明でみんなから特別な目で見られているとわかっていても、炊屋姫が機嫌をわるくするにきまっている。
結果、天皇家と蘇我氏との仲がわるくなる。竹田皇子が病弱のうえ平凡であっても、母親というものは、そうしたものだ。
いま馬子は、炊屋姫の同意がなければ、大きな問題はきめられなくなっていた。
炊屋姫は敏達天皇の大后として、長い間に朝廷のなかで力をたくわえてきた。
天皇が死んだあと、政界のみだれと皇位をめぐる争いのなかで、炊屋姫の地位と発言力は、しだいに大きくなり、彼女の発言が天皇家の考えにまでなっている。
群臣もそれにしたがった。
自分は炊屋姫の立場をたかめるため、用明天皇の妃穴穂部間人(あなほべのはしひと)皇女を、多米王と再婚させた。
その間人皇女は、多米王とのあいだに佐富女王をもうけ、天皇家の争いの外で、幸せにくらしている。馬子は、自分の手でやりにくくしたのだ。
「では、つぎの天皇は竹田皇子ですな。」
蝦夷は、父馬子に念をおした。
「そうも考えるが、竹田皇子は十八歳、どうかと、また迷う。」
その夜、馬子は一晩じゅう、考えつづけた。
翌日、決心がついたのか、炊屋姫のもとにうかがった。
「だれを皇位につけるか、妙案がうかびましたか。」
炊屋(かしきや)姫は三十七歳、ゆうぜんと馬子にたずねた。彼女もよくよく考えたが、結論はだしていなかった。
母妃として、わが子を皇位につけたい。だが竹田皇子は、上宮皇子にくらべればやはりおとる。
病弱でもあり、皇位についた心労から、命をちぢめるおそれもある。
第一、朝廷の高官にも評判のいい上宮皇子をさしおいて、わが子を天皇にできるものではない。
それにもう一つ、竹田皇子を天皇にすれば、天皇家はすべて馬子のおもうままになる。
また皇位をめぐって異母兄弟たちが、ころしたり殺されたりするのを見てきただけに、炊屋姫はわが子をそんな危険にさらしたくない気持もいだいていた。
とにかく自分は天 皇家の代表として、すべてをうまくやっていくように考えなければならない。
――上宮皇子にとついだむすめの貝鮹皇女(かいだこのひめみこ)が生きていたら、私はためらいなく上宮皇子を天皇にするのだが。
聖徳太子の正妃、菟道(うじ)貝鮹皇女は、結婚してほどなく亡くなったのである。
炊屋姫は上宮皇子の聡明をおもいながら、なぜかすぐ返事をしない馬子の顔をながめた。
「どうしました。なぜこたえないのです。」
「はい、では申し上げます。私は炊屋姫さまに皇位についていただくほかないと思案いたしました。」
馬子は炊屋姫の顔を、じっと見つめていった。
自分かどうしてこう考えたか、炊屋姫はいわないでもわかるだろう。
『日本書紀』は、群臣が即位をもとめたと伝えている。
「そなたは、私に天皇になれともうすのか。」
炊屋姫は意外なことをきき、馬子の言葉を確かめた。
いわれれば、なるほどそれが一番の妙案だ。
「はい、そうしていただけば、すべてがうまくまいります。」
「しかし、天皇家で女子が皇位についた先例はありません。」
胸のよろこびをかくし、炊屋姫はいった。
「炊屋姫さま、さようなことはどうでもいいではございませんか。
天皇家に先例がなければ、炊屋姫さまがその例をおつくりになればいいのでございます。
そんな迷いより、いまはこの日本の国を、一日もはやく平和におさめることが、大切でございましょう。」
馬子は、真剣にすすめた。
いま世間は息をひそめ、朝廷の動きを見まもっている。
自分に悪意をもつ人々は、崇峻天皇を殺すチャンスをつくるために、自分か朝廷の大軍を筑紫にいかせたのだとまでいっている。
どう考えればそうなるのだろう。
筑紫にくだった大将軍たちは、いずれもこの馬子に忠誠をつくす高官たちばかりだ。
世間の悪口をきいたそのときの馬子の気持は、燕雀(えんじゃく)いずくんぞ鴻鵠(こうこく)のこころざしを知らんや――だっただろう。
燕雀(えんじゃく)は小さな鳥で小人物、鴻鵠(こうこく)は大きな鳥で、大人物や英雄をさしている。 |
 |
小人物には大人物の心がわからないたとえである。
「大臣(おおおみ)、そなたがいうとおりかもしれません。それでは私は、大臣の言葉に従いましょう。」
炊屋姫は、わざと不機嫌な顔でこたえた。
「これでみんなうまくいきます。ところで、もう一つお願いがございます。」
「なんですか。」
「実は炊屋姫さまのご即位を、飛鳥でおこなっていただきたいのでございます。
飛鳥の豊浦(とよら)に宮をつくりたいとぞんじますが、いかがでございましょう。」
「即位も宮も飛鳥がよいのですか。それはまたどうしてです。」
炊屋姫は、ふしぎそうにたずねた。
「はい、この海石榴市宮がある三輪山のかたわらや、多武峰、また磐余の土地は、古くから歴代の天皇が、宮をもうけてまいりました。
しかしいま、仏教をうけいれて新しい政治を行うには、古い神の土地からはなれるのが一番いいと考えるからです。
いや、宮を飛鳥にうつして、国神をおろそかにするわけではございません。
それはそれとしてまつり、人心を一新して政治にあたらなければならないと申しているのでございます。」
馬子は言葉をえらび、自分の前にゆったりすわっている炊屋姫に、三輪山の文化圏からはなれるべきだと説明した。
炊屋姫が日本最初の女帝として、古い習慣のあるこの磐余で即位し、宮をいとなめば何かと面倒がおこるだろう。
仏教をうけいれて、新しい土地で新しい政治を行う。
うなずいてきく炊屋姫に反対はなかった。
数日あと、飛鳥の豊浦で、宮殿がたてられはじめた。
豊浦から甘橿丘ひとつをへだてた真神原(まかみのはら)の一画では、法興寺の建立がつづけられている。
百済の首信(すしん)につれられてきた寺工(てらだくみ)の太良末太(だらみだ)、文賈古子(もんこし)たちが、工事の中心になって働いていた。
先月、金堂(こんどう)と歩廊(ほろう)ができあがったところだった。
豊浦宮(とゆらのみや)の工事は、文賈古子が大勢を指図してあたった。
『日本書紀』は、冬十二月の壬申(みずえさる)の朔己卯(ついたちつちのとのう)の日に、皇后、豊浦宮に即天皇位す――と書いている。
推古女帝の誕生であった。
即位の式には、聖徳太子も列席した。そうごんに儀式がすすみ、推古天皇は太子を別室にまねいた。太子は天皇になった叔母のまえに手をついた。
「上宮皇子、かたくるしいあいさつはやめにしましょう。それより私のそばにきて、きいてもらいたいことがあります。」
天皇のまねきに従い、太千はひざをまえにすすめた。
「そなたも知ってのとおり、飛鳥、とくにこの豊浦のあたりは、蘇我家の一族たちがたくさんすみ、いってみればここは蘇我家の中心地です。
私もそなたも蘇我氏の血をうけていますが、蘇我氏の人であって、蘇我氏の人ではありません。
なにより多くの民の上に立つ天皇家の一人であると、強くいいたいのです。
大臣馬子が、日本や天皇家のために悪くはからうはずがないと考えていますが、そうかといって、政治のすべてをまかせるわけにはいきません。
政治にかたよりがあってはいけないからです。
しかし、即位したとはいえ、この叔母は悲しいことに女子、政治を行うには知恵がたりません。
そこでそのうち、そなたの聡明さや、これまではげんでおいでの学問に助けてもらいたいのです。
だれもまじえずに、それを頼んでおきたかったのです。」
物部氏がたおれたいま、このままでは大臣・大連の合議制がくずれ、大臣の独裁で政治が行われるおそれもありますと、天皇はつけくわえた。
本当のところ天皇は、自分の即位は、わが子竹田皇子と太子の即位の問題を、一時たなあげにした結果だと白状したかったが、それはぐっとこらえた。
「かしこまりました。天皇さまのお気持は、自分なりに考えてみます。」
太子はきらびやかに着かざった天皇にこたえ、宮門の外にでてきた。
即位の式に出席した高官たちがさがっていく。だれもが太子にうやうやしく頭を下げた。
近年、豊浦宮跡だろうといわれている豊浦の広厳寺境内が発掘され、東西百メートル、南北三百メートルの遺構が確かめられた。
豊浦宮の大きさは、これくらいだったと見られている。
宮門をでた太子は、舎人の調子麻呂がくつわをとる馬にのった。甘橿丘の北をまわり、飛鳥川をわたる。すぐ東に法興寺の金堂がそびえていた。
きょうは天皇の即位を祝い、工事の物音はきこえなかった。
道を東に進むにつれ、飛鳥の地が大きくひらけてきた。
宮が豊浦にもうけられ、これからこの地に宮殿や寺院がどんどんたつにちがいない。
太子は胸に大きな熱い希望がふくらんでくるのを感じた。
うしろにつづく調子麻呂や家人たちをうながし、上宮にむかい、馬をいそがせた。
年がかわり、推古天皇一年(五九三年)、聖徳太子は二十歳の春をむかえた。
世の中は、新しい天皇をいただき、どこか落着きをみせていた。
すぐ花の季節がきて、四月になった。
聖徳太子が、推古天皇と大臣蘇我馬子からの使いをうけ、飛鳥の豊浦宮に参上したのは十日であった。
「私に、なにかご用でございましょうか。」
太子は正面の天皇にふかく頭を下げたあと、そばにひかえる馬子にも目礼してたずねた。
左右に高官たちがずらっとならび、太子を見まもっていた。
「上宮(かみつみや)皇子さま、さっそくよくおいでくださいました。」
馬子が、まず口をきった。
「蘇我の大臣、皇子へはこの私がもうしつけます。」
推古(すいこ)天皇は姿勢を正し、太子に目をすえた。
馬子とすでになにかをきめ、それを太子に言い渡すようすだった。
――きっと即位のとき、もうされたことだ。
太子はしだいに緊張してきた。
「大臣には先ほどいいましたが、本日から上宮皇子に、私の下で国の政務にあたるように命じます。
大臣と手をたずさえ、何事も相談してきめ、行うのです。皇子は仏典や学問をきわめました。
大臣とともに、それをこれからの政治にいかしてほしいのです。わかりましたね。」
推古天皇は太予にいうというより、自分が太子に命じた立場を、左右にひかえる高官たちに、強く認めさせる口ぶりであった。
『日本書紀』は、廐戸豊聡耳(うまやとのとととみみ)皇子をたてて、皇太子とす。
よりて録(まつりごと)摂(ふさね)政(つかさど)らしむ。萬機(よろずのまつりごと)をもってことごとくに委(ゆだ)ぬ――と書きあらわしている。
だが、『日本書紀』の表現は、本当のところ正確でない。上宮皇子が皇太子になるのは、これより数年あとだといわれ、はっきりした年は伝わっていない。
『日本書紀』をまとめた百年後の人々は、偉大な天皇といわれているのちの天智・天武両天皇の立太子が、大化一年、天智一年であることから、両天皇におとらない聖徳太子の立太子を、推古一年とかってにきめたのだ。
太子が推古天皇から、録摂政(まつりごとをとりまとめる)、萬機(すべてのまつりごと)をまかせるといわれたころ、日本には一人の皇族を皇太子として、つぎの天皇に予定しておく制度や習慣はなかった。
皇太子をさして「皇嗣」(こうし)、「ひつぎのみこ」という。
ところが当時、「ひつぎのみこ」とは、大勢の皇族につけられるよび名にすぎなかった。
また『日本書紀』に「摂政」とありながら、『上宮聖徳法王帝説』には摂政(せっしょう)でなく「輔政」(ほせい)と書かれている。
このことから、聖徳太子の摂政の地位は、のもの摂政の考え方とはちがい、法律的な根拠のない、大臣との共同執政者にすぎなかったという研究者もいる。
こうしたこまかい意見の違いは、「皇太子制」がいつできたかを、はっきりさせるためのものだが、聖徳太子がやはり日本ではじめての皇太子であると考えて、大きなあやまりはない。
推古天皇の時代は、皇太子制が制度として考えられだした時代だった。
ではどうして、聖徳太子がかつてない皇太子という地位につけられたのだろう。
実は天皇家をとりまく時代の状況が、皇太子という存在を大きく必要としていたのである。
推古天皇の時代は、天皇の中央集権化がはっきりしてきた最初の時代だという。
それまで国の政治は、氏族の代表者にまかされてきた。
それを天皇が完全ににぎり、政治的地位と力を大きくたかめていく。
そして天皇を神聖でおかすことのできないものに位置づける。そうしながら国の政治をやっていく。
聖徳太子が政治の表舞台にあらわれた意義は、このような状況をつくりあげることにあったといえよう。
これがうまくはこべば、大きな権力をもってきた蘇我氏の力もうすれ、ただの貴族・高官になり下がる。
こんなすばらしい天皇家と政治のしくみを、いったいだれが考えだしたのか。
推古天皇が、蘇我馬子と相談して考えたのだろうか。
あるいは推古天皇が、こっそり聖徳太子と話し合ったのだろうか。
三人は、仏教やそれがもたらすいろいろな技術・文化をもちい、国をまとめ日本をゆたかにしたいと考えた点では、意見が一致していた。
蘇我氏の仏のあがめかたが、この世の利益を願うものだとしても、非難することはないだろう。
太子は、叔母の天皇から、政治への参加を命じられるまえに、ひそかに相談をうけていた。
そして自分の考えをのべていたと思われる。
しかし、だれがこれを考えたにしても、すぐれた才能をもつ人物、聖徳太子がいなければ、実現できなかった。
またそれに妥協した蘇我馬子も、立派な人物であった。
「皇子には、私の命令がわかりましたか。」
だまって平伏している太子に、推古天皇は威厳をもって訊ねかけた。
「はい、うけたまわりました。大臣には、未然な私をおみちびきください。」
太子のあいさつに、蘇我馬子は満足そうにうなずき、高官たちを見まわした。
彼は、むすめ刀自古(とじこ)郎女(いらつめ)を、そのうち太子の妃とすることを推古天皇に願い、すでに許されていたのであった。
緊張がゆるんだ宮殿のなかに、すずしい風がふきこんできた。
4 三宝(さんぽう)興隆(こうりゅう)すべし
top
みんなの声が明るかった。
上宮が、はなやいだ雰囲気につつまれていた。
それは、妃(ひめ)菟道貝鮹(みめうじのかいだこ)皇女が亡くなってから時々さみしそうにしていた太子が、蘇我馬子のむすめ刀自古(とじこ)郎女(いらつめ)を妃にしたからであった。
「摂政太子さまも、これで蘇我氏という、強いうしろだてをえられたわけだ。
太子さまが政治をいたされるうえで大きな力になる。
すこしぐらい不満があっても、だれも文句をいわないだろう。」
人々は太子の立場と権威が強まったといっているのだ。
太子は馬にのって、上宮(かみつみや)と豊浦宮(とゆらのみや)を行き来した。
豊浦宮では高官たちが集まり、政治について相談する。
だがいまとはちがい、「政府」の規模は小さく、太子が毎日姿を見せる必要はなかった。
最初は政治のようすなどを、だまってうかがっている。そのあと、摂政としての意見をすこしずつだしていく。
これが摂政を命じられた太子の方針だった。
「まず、まわりをよくごらんになることです。いきなり新しいお考えを発表されてはなりません。
いくら太子さまでも、出る杭はかならずうたれます。」
うしろにかくれ、太子をそだててきた豊国法師や膳臣傾子、河鴈たちはこう忠告していた。
「よくわかっています。私は何事もいそぎません。
人の心をかえ、天皇家の権威をたかめ、この国を一つにまとめていくのは大変なことです。
ゆっくり、いそがずにやっていきます。」
太子は三人にだけでなく、妃の刀自古(とじこ)郎女にも推古天皇にもいっていた。
「それには意見はありません。それより上宮から飛鳥の豊浦宮までくるのは、近いとはいっても大変でしょう。
いっそこの飛鳥の地に、仮宮でももうけてはどうですか。」
推古天皇は叔母として心をつかい、めぼしい土地を胸にうかべた。
あそこはどうかと思った場所は、太子の父用明天皇が仮宮としていた飛鳥川のほとりの高台にある土地だった。
そこなら、豊浦宮まですぐの距離である。
聖徳太子誕生の地で、用明天皇即位以前の橘宮(たちばなのみや)があったといわれている飛鳥の橘寺の地がこれであった。
もっとも近年の発掘では、これらのいい伝えはあるが、それらしい遺構は認められなかったといっている。
この付近のどこかに、当時の遺構がまだねむっているのだろうか。
「かしこまりました。よく考えてみます。」
太子は推古天皇にうやうやしく頭を下げた。
二人だけの場合と、朝廷の高官たちがいるときでは、太子の天皇に対する態度が全くちがっていた。
みんながいるときには、おおげさに天皇をうやまう。
自分が天皇にうやうやしく接すれば、人々に天皇は神聖だという気持や、おかしてはならないとの考えが生まれてくると思ったからであった。
推古天皇が即位して、足かけ三年めになった。
『日本書紀』などでは、前年、難波(なにわ)の荒陵(あらはか)に四天王寺が建立(こんりゅう)されたと伝えている。
難波は、朝鮮や中国への海の玄関口だった。
海を西にのぞむ高台に、広さは三町四方で、高い五重の塔をもつ大きな寺をたてることは、海外に国の力を見せようとする人々の気持がよく表われている。
この四天王寺が建立された時期についての疑問は、すでに「蘇我・物部の戦い」のところでふれた。
過去の事実を遺物ではっきり証明する発掘調査によれば、大阪の四天王寺と、聖徳太子が父用明天皇の遺言をまもってつくった法隆寺のたてられた時期は、それほどちがわないという。
なぜそうしたことがわかるかといえば、二つの軒丸瓦(のきまるがわら、素弁八葉蓮花文)が、同じ範型でつくられたものであり、そのうえ範型に型くずれがなかったからである。
なお法隆寺の創建は、推古朝中期と、聖徳太子死後の推古朝末期の二つの説がある。
だが、これら二寺のことはともかく、飛鳥では法興寺の工事が、いよいよ進んでいた。
推古天皇が飛鳥の豊浦宮にすんでいるため、せまい飛鳥の地は、活気にあふれていた。
春二月一日、朝服をきた高官たちが、朝、豊浦宮にぞくぞくとあつまってきた。
「なにごとだろう。」
彼らを見送る人々が口々にいった。
この日、朝堂で「三宝を興し隆(さか)えさせる」という詔(みことのり)が出されたのである。
三宝(さんぽう)は諸法のなかで一番すぐれた法で、天竺(てんじく、インド)より三韓(さんかん、朝鮮)にいたるまで、どの国々でも敬い、信じないものはいない。
天皇があつく敬いなさいといわれておられます。」
詔(みことのり)をみんなに伝えたのは、太子だった。
詔の文は全部、太子がつくった。つまり太子が天皇や馬子にすすめ、仏法興隆の命令をださせたのである。
仏教とはどういうものか、公伝(こうでん、西暦五三八年)からもう六十年ちかくたっているだけに、人々はこの世の利益を願うという敬いかたや、ついでに異国から伝えられるものの便利さなどを充分に知っていた。
仏教は造寺・起塔・造仏といった中心になるもののほか、医事・医薬・学問・芸術など、生活文化にかかわる様々なものをもたらしてきた。
簡単にいえば、それらはこれまでつづいてきた日本人の古い生活を、一度に変えてしまうほどのものであった。
「かしこまりました。詔に従い、国民のすべてにこれを伝えます。」
馬子がみんなを代表していい、上座の推古天皇と太子にひれふした。みんなも馬子につづき頭を下げた。
――これでいいのだ。こうして回を重ねれば、天皇は神聖で尊厳なものだと考えられていく。
太子だけではなく、推古天皇も馬子も、胸のなかで成功だとよろこんでいた。
雄略(ゆうりゃく)天皇のころなら、武力と勇気をもった人物が、相手をほろぼして王となり、犬王になっただろう。
だがいまはそんな時代ではなく、天皇はおかしてはならない存在だと、みんなに徹底しなければならないのだ。
天皇がすべての権威をにぎり(中央集権的統一国家の長として)、その下に群臣(まえつきみたち)や国民がいる状能がのぞましかった。
三宝は仏教徒が敬まわなくてはならない仏宝(ぶつぼう)・法宝(ほうぼう)・僧宝(そうぼう)の三つをさし、仏の異称でもある。
仏宝は、さとったものを意味する仏をいう。法宝は、その仏が説く教えを意味する法をいう。
僧宝はその教えに従い、自分もさとりをひらこうと努力する人たちを意味する僧のことだ。
聖徳太子は二十一歳になるまで、一族や肉親が血で血をあらう争いを見つづけてきた。皇位をめぐって争いがおこれば、人は敵味方にわかれて憎しみあう。
それにつれて、社会不安もまし、天皇家も国も、たえず薄氷をふむあぶない状能におかれる。
しかし、いまはそんなときではない。絶対の価値をつくりだすべき時代だった。
三宝のうち、仏宝は日本をおさめる天皇であり、法宝は国をうまく運営していくための憲法。僧宝は群臣や国民であり、国はこの「三宝」がうまく調和してはじめて存在すると、聖徳太子は考えた。
「三宝興隆の詔」には、こんな三宝の見かたがこめられていたのであった。
上にたつものが仏教を信じあがめて、こうした三宝の見かたを、たくさんの人々に理解させる。
仏教の実践者として聖徳太子は、釈迦がたどりついた真如(しんにょ、絶対的な真理)をうまく活用したことで、蘇我馬子にもおとらない大政治家であった。
ただし、この大政治家は、推古天皇や馬子たちにくらべ、やはり釈迦の真如に価値のすべてをおいていた。
神や仏は、絵や彫刻といったもので見ることができるが、それは神や仏の本当の姿ではない。
その精神は、澄んだ心で真如をふかく見つめなければ、わからないものだ。
聖徳太子は、生まれながらやさしい性格のうえ、仏典をきわめ、学問にはばかことで、いよいよ澄んだ心をみがき、目に見えないはずの仏を、見ることのできる人であった。
日本の歴史がはじまってから、一番はじめに学問によって「知性」をそなえた人であり、そのうえその知性は、人間の本質をふかく見つめたものであった。
――人間がこしらえたもののなかで、神仏はやはり最高のものである。
と聖徳太子は考えたにちがいない。
仏は真如(しんにょ)であり、真如は人間の汚れた心を美しく清めてくれ、いかに生きるべきかを考えさせてくれる。
聖徳太子は、「三宝興隆の詔」から十年あとの推古天皇十二年(六○四年)に、有名な「憲法十七条」をつくって発布したが、十年の月日をへだてながら、この二つは実は密接な関係をもっている。
憲法十七条の二で、太子はこう説いている。
「いずれの世、いずれの人か、是の法(のり、仏法)を貴ばざらん。人はなはだ悪しき者少なし。
能く教うれば従う。それ三宝に帰せざれば、なにを以ってかまがれるを直くせん。」
(いつの世のどんな人も、この法を尊ぶだろう。非常にわるい人間はすくなく、うまく教えれば従うものだ。
三宝こそまがった心を正しくすることができる。) |
ほかによりどころはないとまで、太子はいいきっている。
まがった心とは、太子にとってやはり人と人が争う心だろう。
それを「解脱」(げだつ)してなくすれば、平和な社会になり、統一された国家ができる。
太子が「三宝興隆の詔」をだしたうしろには、「法華経」の譬喩品(ひゆほん)にもとづくこうした願いがあったのである。
「なんだかこの飛鳥も、さわがしくなったなあ。あちこちで寺がたてられている。」
「三宝興隆の詔」のあと、人々があきれた顔でささやきあうほど、氏寺(うじでら)の建立がつづいた。
翌推古天皇三年(五九五年)の四月、淡路島の海岸に、長さが八尺ほど、まわりが一かかえもある大木が流れついた。
香木(こうぼく)の一種の沈香(じんこう)だったが、島人たちは知らずに木のはしを切り、たきぎと一緒にかまどで炊いた。
するといい匂いがひろがり、その匂いは、遠くまでただよった。
「みょうな木だ。わしは仏というものがあらわれるとき、妙香がただようと飛鳥の京人(みやこびと)から聞いたが、この木はそれとかかわりがあるかもしれんぞ。」
村長がききつけ、大木は天皇に献上された。
太子は、推古天皇からこの名木をもらいうけ、仏師に観音像をきざませた。
五月、聖徳太子の内教(ほとけのみのり)の師といわれ高麗僧の恵慈(えじ)、百済僧の恵聡(えそう)の二人がやってきた。
二人は、わかい太子の人間形成に大きな役割をはたした。
恵慈は在日二十年、推古天皇二十三年(六一五年)十一月、帰国している。
恵慈はそれから十年後、故郷で太子の死の知らせをうけたとき、太子がこの世におられないなら、一人生きていてもしかたがない。
来年の太子の命日にわたしもあとを追う――といい、そのとおり、太子の一周忌に死んだという。
恵慈と恵聡の二人の僧は、それまであらけずりだった太子の仏教の理解に、論理性をあたえたが、彼らは一をきいて十を知る、太子の聡明さと理解のふかさにおどろいた。 |

沈香(じんこう)
インドから東南アジアに分布。
高さ二十メートルにもなる。花は白、
果実は楕円形。材は香木として貴重。
|
太子は朝鮮の言葉を自由につかうばかりか、中国の言葉まで理解する。
二人は、しだいに太子を尊敬するようになっていった。
――この太子はただ人ではないわい。
これが二人の率直な気持だった。
二僧は翌推古天皇四年(五九六年)十一月、八年にわたって工事がつづいた法興寺が完成すると、ここにすんだ。
前年の七月、崇峻天皇が暗殺される直前に、筑紫に派遣された紀臣男麻呂(きのおみおまろ)や大伴連噛(おおとものむらじくい)たち大将軍が、飛鳥にもどりついていた。
大将軍たちの出兵は、任那(みまな、加羅(から)諸国)を征服した新羅に、みつぎものを要求するためだったが、新羅は言葉を左右にして、すぐにはみつぎものをださなかった。
話は先にとぶが、推古天皇十八年(六一〇年)の十月、新羅は日本のたびたびの要求に、やっと任那の調を認めて、みつぎものをもってきた。
だがこれは、要求にこたえたのではなく、新羅のずるい計算からだった。高句麗と百済のあらそいで、新羅の立場がわるくなったのだという。
高句麗が南に力をのばすため、新羅を攻めていた。高句麗の南進は、新羅と百済に危険を感じさせた。
二国は崇峻天皇二年(五八九年)、陳(ちん)をほろぼして中国を統一した隋(ずい)に、軍事的な助けをもとめてもいた。
こんな事情のある新羅は、海の東の日本と友好をむすんでおいたほうがいいと考え、その年、ようやく任那のみつぎものをとどけてきたのだった。
話はもとにもどり、推古天皇五年(五九七年)の四月、大きな使命感をもち日本に仏教を伝えてきた百済から、その頃の威徳(いとく)王が、王子阿佐(あさ)を使者としてつかわしてきた。
聖徳太子は二十四歳、摂政についてから四年たっていた。
「百済の王子が遠いところから、はるばるとおいでくだされた。おでむかえしましょう。」
太子は長男の山背大兄(やましろのおおえ)王と、弟の殖栗(えくり)皇子をしたがえ、阿佐王子のまえに姿を現した。
「聖徳太子二王子画像」は、このとき阿佐王子がえがいたと伝えられているが、実は七世紀後半以降のものだという。
十一月、吉士磐金 * (きしいわかね)が、任那の調(ちょう)を請求するため新羅へたち、翌推古天皇六年(五九八年)の四月、新羅からかささぎ二羽、八月には孔雀一羽がとどけられた。
* 吉士(きし) 朝鮮からの渡来氏族で、『日本書紀』に、しばしば登場する。いまの大阪に居住し、海外との交渉に活躍した。
推古天皇七年(五九九年)四月二十七日、大きな地震があった。
秋九月、百済からラクダ一頭、ロバ一頭、羊二頭、白雉一羽が献上された。
「それにしても新羅はけちだ。いっそ新羅に遠征軍をやるか。」
推古天皇八年(六〇〇年)一月の遠征は、蘇我馬子が発案したという。
『日本書紀』は、大将軍境部臣(さかいべのおみ)と、副将軍穂積臣(ほずみのおみ)の大軍が、五つの城をおとし、六つの城を日本にかえすと新羅に約束させ、みつぎものの献上もとりつけて、日本に凱旋してきたと伝えているが、ふしぎなことに、こんな事実はどこにもない。
『日本書紀』をまとめた人々は、百年ほどまえ、任那がどうなっていたか知らなかった。
「わしはさっぱりわがらんが、ええい、こう書いてしまえ。」
筆一本で日本の国威をつくりだしたのだろう。
推古天皇九年(六〇一年)二月、聖徳太子は飛鳥の地からはなれた斑鳩(いかるが)に宮をつくりはじめている。
この宮は四年あとの推古天皇十三年(六〇五年)の十月に完成し、太子は斑鳩にうつるのである。
聖徳太子と推古朝政治との関係は、大きく時代を三つにかけて考えられる。
はじめは摂政になった推古天皇一年(五九三年)から推古天皇十年(六〇二年)まで、つぎは推古天皇十一年(六○三年)から推古天皇十九年(六一一年)まで、最後が推古天皇二十年(六一二年)から太子が死ぬ推古天皇三十年(六二二年)までの三期間である。
一期めは、「三宝興隆の詔」のほかは、めだった動きはせず、太子は馬子のかげにかくれて政治と学問をおさめ、精神をふかめていた。
二期めは政治の表にでて、馬子と共同して、革新的な手腕をみせる。
三期めは政治の第一線からしりぞき、しだいに精神世界にとじこもっていくのである。
斑鳩をつくりはじめる前年、太子は中国に第一次遣隋使をおくり、国交をもとめた。
ひろい中国を統一した隋とまじわりをもち、日本の国際的な地位をたかめるのが目的で、また仏教や、そのほか進んだ文化や情報をとりいれるためだった。
太子の目は朝鮮の三国よりも中国にむけられ、積極的な姿がよくうかがわれる。
太子のよび名の一つ“八耳(やつみみ)皇子”の名は、太子が考えた推古朝の政治機構が、うまくうごいていたことを、私たちに教えてくれるのではないだろうか。
八省八官の八省は、のちの大宝令の制で、太政官におかれた八つの中央官庁のことである。
その原形になる組織を、太子が推古朝につくり、問題がスムースに処理されていくおどろきの気持が、太子に八耳の異名をあたえたのではないかと考える。
蘇我馬子にとっても、太子が共同執政者として評判になるのは、よろこばしかった。
自分一人で政治をおこなっていれば、どうしても独裁者と悪口をいわれる。 馬子のたくみな処世ともいえるが、そこまでゆがんで馬子を見る必要もないだろう。
|
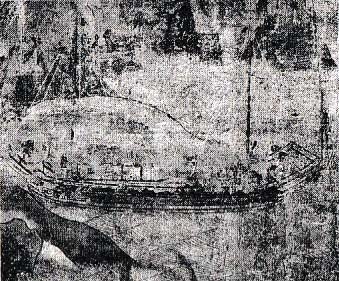
遣隋使(けんずいし) 五回派遣されたらしい。
中国の制度・文物をまなび、わが国の文化の発達や、
のちの大化の改新に役だった。
この役は、遣唐使にひきつがれていく。
|
|

|
遣隋使の派遣につき、太子が推古朝政治へ大きくかかわったのは、推古天皇十年(六〇二年)一月、弟の来目皇子を征新羅将軍に任命して筑紫に向かわせたことだ。
外征(がいせい)将軍にはじめて皇子が命じられた。
「天皇家を安泰にするためです。苦労だろうが、いってもらいたい。」
太子はあまりじょうぶでない来目皇子にいった。
やさしいことにかけてなら、皇子は太子をうわまわっていた。
四月、来目皇子は二万五千の軍勢とともに出発する。だが翌年(六〇三年)二月、皇子は筑紫で病死する。
『聖徳太子伝暦』には、新羅の奴たちが将軍をのろいころしたiとの記事があり、皇子は新羅のスパイに殺されたという説もあるが、これはつくり話だろう。
悲報が筑紫から飛鳥の豊浦宮にとどいてまもない四月、太子は弟当麻皇子をつぎの征新羅将軍に任命した。
将軍をうしない、遠征軍はむなしく筑紫の島郡(しまのこおり、福岡県糸島郡)にとどまっている。
兵士たちの心細さがおもいやられた。
筑紫の島郡は、百済や新羅への玄関口だ。
前年(六〇二年)の十月、ここをへて、百済僧の観勒(かんろく)が来朝し、暦本・天文地理書・遁甲(とんこう)方術書(星占いなどの本)を献上した。
観勒について、陽胡史(やこのふひと)の祖玉陳(たまふる)が、暦法を学んでいた。
「兄上さまの命に従い、筑紫にまいります。」
当麻(たぎま)皇子は、太子や馬子、正面にすわる推古天皇に手をついた。
七月、当麻皇子は妃の舎人姫王をつれ、難波から船出した。
ところが、船が播磨の港についたとき、舎人姫王が病死する。当麻皇子は、彼女の遺体を赤石(あかし、明石市)の槍笠岡(ひがさのおか)にほうむり、飛鳥に戻ってきた。
当麻皇子の態度でもかかるように、新羅遠征の本当の姿は、この程度のものだった。
軍勢二万五千も、事実は二千人か三千人ぐらいだろうと考えられる。
十月、推古天皇は、かねてから工事をすすめていた飛鳥小墾田(おはりだ)に宮をうつした。
小墾田宮は、豊浦宮の北へ数町ほどになり、古い宮が手ぜまになったからだった。
ここには南に「南門」がかまえられている。
ふつう「宮門」とよばれるここをくぐると、ひろい「朝庭」がひらけている。
左右対称に朝堂がならび、外国使節の接見や儀式はここで行う。
大臣の蘇我馬子や高官たちは、この朝堂で政務にあたった。
その北にまた門がたっていた。そのおくに推古天皇のすむ大殿があった。
「上宮皇子、斑鳩宮の工事はふつごうなく進んでいますか。」
推古天皇は、とおくに見える耳成山(みみなしやま)に目をやりながら、そばにひかえる太子にたずねた。
どこにいくのか、つるが東にとんでいく。
太子と蘇我馬子の共同執政がうまくはこび、世の中はなんとなくおちついている。
天皇は満足そうだった。
「はい、無事に進んでおります。」
太子は鼻の下にたくわえたひげを、左の人指指でしずかになぞってこたえた。
気品と荘重な雰囲気が、三十歳になった太子の全身を柔らかくつつんでいた。
top
**************************************** |