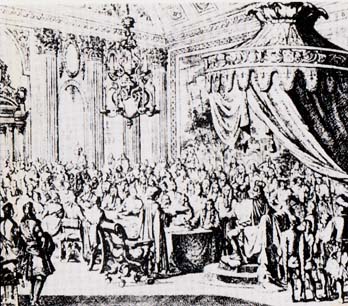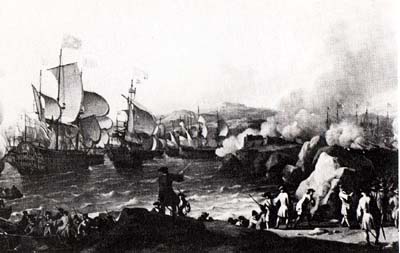|
****************************************
Index エリザベス女王 ルイ十四世 ピーター大帝 ニュートン 図解コーナー
|
ルイ十四世の写真集 |
|

ルイ14世 「太陽王」とよばれ、ヨーロッパ第一の
君主としてフランスの栄光をおいつづけた。
|

ルイ14世とマリア・テレサの結婚式
ルイ14世は、スペイン王女マリア・テレサと結婚した。

フランドル戦争 リール包囲戦におけるルイ14世
フランス軍はこの戦争で、スペイン領だった
フランドル地方の都市リールをうばった。
|
|

右上=ベルサイユ宮殿ルイ十四世の部屋 豪華な部屋がたくさんつくられた。
左上=ベルサイユ宮殿ルイ十四世騎馬像 馬にのってフランス軍を指揮するルイ十四世の雄姿。
左下=ベルサイユ宮酘「鏡の間」 庭園に面した豪華な回廊である。
中央下=ベルサイユ宮殿の庭園 水利のわるい土地だったので、水をひくために巨費がつかわれた。
右下=ベルサイユ宮殿 1661年から本格的に工事が進められ、1682年にルイ14世がうつり住んだ。
|
1 王子の誕生
top
「王子がうまれた」
という知らせに、パリ郊外の王宮の人々は、わきかえった。
「本当か。奇跡、ではないか」
と、いぶかしげに首をふる貴族もいた。
フランス国王ルイ十三世(在位一六一〇〜一六四三年)と、その王妃アンヌ・ドートリッシュとの間には、結婚後ずっと子供がうまれなかった。
「――それが、何と二十三年もたって子宝にめぐまれるとは……」
と、父親になった国王も、おどろいていった。
「まさに、神さまのおさずけものだ」
一六三八年九月五日のことである。
赤ん坊は、のちに「太陽王」とよばれ、フランスの王政時代に、もっとも勢いさかんな時代をつくった。
すなわち、ルイ十四世である。
「大変な赤ん坊だ」
という噂が、やがて宮廷じゅうに流れはじめた。
「王子つきの乳母が、何人もいるんだが、その乳母だものおっぱいを全部のみほし、それでもまだたりなくて怒り出し、出ない乳房にかみついたそうだよ」 |

ルイ十三世 ルイ十四世の父。
勝利の女神に祝福されている。
|
それだけ、たくましい生命力をもってうまれた、ということだ。おとなになってからも、 「王さまには、胃が二つある」といわれるほど、ルイ十四世は大食家だった。
ところで、王子ルイがうまれたころのフランスの政治は、どんな状態になっていたか。
まず、フランスはスペインとの間で「三十年戦争」(一六一八〜一六四八年)をつづけていた。
三十年戦争は、ヨーロッパのカトリックとプロテスタントが争ったことにはじまったが、この時期には、同じカトリック教国であるフランスの「ブルボン王家」
*
と、スペインの「ハプスブルク王家」との勢力争いとなっていた。
* ブルボン王家 1589年、ヘンリ4世が王位についてからフランス王家となり、ルイ16世までつづいた。フランス革命で一時とだえたが、ふたたびかえりざき、スペイン王家にもなった。
すでに宗教戦争ではなくなっていたのである。
じつは、王子ルイの母アンヌ・ドートリッシュは、スペインのハプスブルク王家からとついできている。
そこに厄介な問題があった。
また、フランスを代表する枢機卿(すうききょう=ローマ教皇につぐ高い位の聖職者)リシュリューは、王国を強大にするため、中々戦争をやめようとはしなかった。 |

30年戦争のときの兵士 槍や弓矢にかわって鉄砲がつかわれた。
|
一方、国のなかではしだいに戦争につかれて商工業がふるわなくなり、税金に苦しむ貧しい人々がふえてきていた。
王子ルイのうまれた翌年には、「はだしのシャン」とよばれた謎の人物が、労働者たちをひきいて反乱をおこしている。
そのような、いかにも前途多難の時代に、赤ん坊のルイは、王への道を歩みはじめた。
2 王母アンヌと宰相マザラン
top
「よろこべ、リシュリュー * が死んだぞ―― 『私に対抗できる者は、国王と国家だけ』とうそぶいた、あのごうまんな枢機卿(すうききょう)が……」
* リシュリュー ルイ13世の時代にブルボン王家の権力を強め、絶対王政の基礎をきずいた政治家。プロテスタントを弾圧し貴族勢力をおさえつけて外国勢力とも戦った。
「潰蕩(かいよう)におかされ、担架にのせられて、遠征から帰ってきたのが、つい数日前たったそうじゃないか」
と、パリの民衆たちが噂するのは、一六四二年十二月四日のことである。 |

リシュリュー ルイ十三世の
信頼があつく、政治こ力をふるった。
|
「これで、わしらもすこしは息がつけるぜ。なにしろあの男は、スペインのハプスブルク王家と、きりもなく戦争をするばかりか、国内では各地にアッタンダン(監察官=かんさつかん)をおいて、わしらをギュウギュウおさえつけていた」
「反抗しようものなら、すぐつかまって、死刑だったんだから――」
ある町では表通りで、反乱の指導者が、生きながら手足を切断されたりした。
そんなことをアッタンダンにさせた「鉄の爪」をもつ男、リシュリューが死んで、半年とたたないうち、ルイ十三世も病気で亡くなった。
一六四三年五月十四日である。
王子ルイはまだ五才だったが、ただちに王母アンヌ・ドートリッシュにつきそわれて、パリの宮殿に入り王位をついだ。 すなわち、いよいよルイ十四世(在位一六四三〜一七一五年)の時代の開幕である。
その数日後、高等法院の天井に幼いルイ十四世の声がひびいた。
「私の意志は、大法官によって伝えられるだろう……」
大法官はこれをうけて、
「国王が未成年の間は、絶対的な支配権を王母(おうぼ)にまかせることを、認める」とつげた。
この頃、高等法院(最高裁判所のようなところ)というのは、国王の力を左右するほどの、国の最高の裁定機関だった。
こうして王母アンヌ *
は、幼いルイ十四世のうしろだてとなり、権力をにぎることになった。
* 王母アンヌ アンヌ・ドートリッシュ。ルイ13世の妃となり、王の死後、おさないわが子が国王ルイ14世になると、その政治をたすけた。マザランを登用してブルボン王家を繁栄させた。
「宰相(さいそう=総理大臣)は、マザランにやってもらいます。
イタリア人だけど、知識は広いし、冷静で辛抱強いし、するどい判断力と用心深さをそなえているし、……」 |

ルイ14世の会議 右から3人目がルイ14世、
その左が王母アンヌ、ひとりおいてマザラン。
|
と、王母は、ある日、人々の集る席でいう。側近の女官がすぐ、
「社交にもたくみで、それは魅力的な方ですものね」と、つけくわえた。
要するに、数ある家来のなかで、マザランこそ、王母アンヌの最高のお気にいりだった。
「鉄のつめ」の男といわれたリシュリューにくらべて、マザランは、顔つきも人あたりもやさしかった。
ここから、王母アンヌと宰相マザランによる政治がはじまった。
3 少年王ルイ十四世の教育
top
幼い時から、ルイ十四世は、体格がよく、ものおじしない性格をしめしていた。
行儀作法などを、王母が非常にきびしくしつけてから、はやくも自信にみちた王者の貫禄を、そなえるようになっていた。
マザランが宰相になってからは王母は、ルイの教育をも彼にゆだねた。
「……いずれ政治は、ひとまかせにせず、ご自分でなさることです。それに……」
とマザラン * は、少年ルイに教えた。
* マザラン イタリアにうまれ、フランスの国籍をとっだ。リシュリューやアンヌ・ドートリツシュにひきたてられ、ブルボン王家の力を強化するのに功績があった。
「支配力のある大貴族たちを、簡単に信用してはなりませんぞ。
いつ裏切られるか、わかったものではありませんからな。
むずかしいのは、なにより国の財政をしっかりさせること。
本心を、けっして外にあらわさないこと……」
さらに、ある司教もルイの教育にあたり、こう教えた。
「王の座は、人の座ではなく、神みずからの座です。
王とは、神にかわってこの世を治める者のことです……」
こうして、少年ルイのなかで、権力への自信と政治への野心とが、ますます大きくふくれあかっていった。 |

少年ルイ14世 10才のルイ王。
ルイ王はマザランの教育をうけて成長した。
|
4 フロンドの乱
top
「つい先日、民衆がパリ市にはいるための関税(通過税)をつくったかと思ったら、今度はパリの城外区で住むばあいの、家屋税(家の税)か」
「でたらめな課税だよ。マザランは、民衆から税金をしぼりとることしか、考えていないようだな」
「自分たちのおさめる税金が、そのままそっくり国の収入になるのなら、まだゆるせるさ。
半分以上は、政府との間に立つ徴税請負人(ちょうぜいうけおいにん=税金を集めることをまかされた人)が、かってにふところにいれてしまうのだから!」
こういったパリ市民たちの不満の声がしだいに高まったのは、ルイ十四世がようやく十才になった年、一六四八年八月なかばのことだ。
一方、高等法院の人々も、自分たちを無視したマザランと王母アンヌとの政治に、おおいに不満を感じていた。
ことに高等法院の反マザラン派の一人は、
「国王のアッタンダン(監察官)が、徴税請負人の家来のようになっているとは、なさけない話だ。
徹底的に調べて、悪い請負人(うけおいにん)たちをクビにしろ」と強く主張した。
八月二十六日朝、ルイ十四世は王母やマザランとともに、ノートルダム寺院のミサ(教会の儀式)にくわわっていた。 一方そのころ、王母アンヌの指令をうけた親衛隊の兵士たちは、ひそかに反マザラン派の高等法院の評定官たちをおそった。しかし、
「――なんだって。評定官が、逮捕された? 郊外の森につれ去られたって?」
事件を知った民衆は、おとなしくしてはいなかった。
「武器をもって、あつまれ。親衛隊がなんだ! 評定官をとりもどせ! 釈放させろ!」
民衆は、パリの町のいたるところから集り、団結して、王宮の前にすわりこみ、政府と交渉した。
このとき、民衆はフロンド(石投げ機)をつかい、王宮の衛兵たちに石を投げつけたので、この騒乱はフロンドの乱
* とよばれている。
* フロンドの乱 ブルボン王家がしだいに権力を強めていくのに、不満をいだいた貴族勢力がおこした反乱。この反乱は王家の軍隊に鎮圧され、以後ブルボン家の絶対王政が確立した。 |

フロンドの乱
民衆が立ちあがっで反抗し、これに貴族たちもくわわった。
|
「危険だ! サン・ジェルマンヘにげてください!」
と、マザランにすすめられ、ルイ十四世は王母や弟のオルレアン公とともに、夜、ひそかにパリ郊外へ脱出した。
国王とその一族でありながら、大事な宝石もすべて金貸しの手にわたり、夜はみんなでわらの上に寝る――
この当時は、そんなひどい生活状態だったという。
「ルイ十四世は、あらっぽい『人生学校』で育てられた。
彼は市街戦や、屈辱や、うらぎりや、野営(やえい=野宿)生活などを体験しだのだから」
と、のちにある作家はかいている。
ちょうどそのころ、幸いにも貴族の名門コンデ公
*
は、ドイツ方面での三十年戦争に勝利をおさめて帰ってきた。
王とマザランの政府を救ったのだった。
* コンデ公 コンデ家はブルボン家とおなじ家系から出た一族で19世紀までつづいた。フロンドの乱で活躍したコンデ公は大コンデともよばれ、17世紀のすぐれた軍人の一人。
5 貴族たちの反乱
top
ところが、
「……コンデ公は、自分の弟や義理の兄と手をむすんで、ひそかに政権をねらっていますぞ」
という報告が、マザランの耳にはいった。
「けしがらん。先手をうってやれ!」と、マザランは側近の者に命じた。
一六五〇年一月のある日、コンデ公とその一門は突然逮捕され、監獄にぶちこまれた。
これが、かえってマザランにたいする貴族たちの反感をあおり、またも騒ぎをひきおこした。
「王さま。しばらくのご辛抱を……」
ふたたび、マザランは当時十二才のルイをつれて首都を脱出し、東へ南へと逃げ歩いた。
一時は、ドイツに亡命 * (ぼうめい)したこともあった。
* 亡命 政治的な理由で、じぶんの国から脱出して、よその国にのがれること。命とは戸籍の名前ということで、戸籍をぬけだしていなくなる、というのがもとの意味である。
マザランの首には、一五万リーブル(リーブルはお金の単位)の「賞金」がかけられていたのである。
コンデ公の軍と、都を奪い返そうとする王党派(マザラン派)の軍とが、パリの城外サン・タントワーヌで激突するのは、一六五二年七月のことである。
このとき、ルイ十四世のいとこにあたるグランド・マドモアゼル(大令嬢)は、女ながら武具に身をかためて、苦戦するコンデ公の応援にかけつけだ。しかし、
「私はいま、絶望のはてにある」
と、鎧(よろい)をズタズタにさかれたコンデ公は、嘆いた。
戦いには勝っていたとしても、パリの民衆の気持ちはすでに、コンデ公からはなれていた。
「コンデ公は、ルイ十三世の弟を国王代理にしたてたりして――
自分たちの出世と利益のことしか考えていないではないか」
と、民衆は思った。
三か月後、コンデ公はさびしく北フランスへおちのびていく
* 。
* おちのびるコンデ公 コンデ公は、一時パリの王としてじぶんの夢を実現するところであったが、乱暴にふるまったうえに、スペイン兵をつれていたので、市民の反感が高まった。
それにかわって、
「――王さまだ。ルイ十四世の入城だ!」
十月、黄金色のマロニエの落ち葉がまうパリに、なつかしげな人々の声がわいた。
最初の乱は高等法院のフロンドとよばれたのにたいして、このときの乱は貴族のフロンドとよばれている。
ひと足おくれてパリにもどったマザラン――苦労したひげ面のマザランを、十四才の王は出迎えて抱きしめた。
「フロンドの乱が、やっとおわりましたな、王さま」
「うん。今夜は大きな祝い火をたこう、爆竹をならそう、マザラン!」 |

グランド・マドモアゼルの活躍 コンテ公の応援にかけつけ、
マザランとその一派を、一時国外に追放した。

反乱貴族たちの降伏 少年のルイ14世に、反乱を指導して
いた貴族たちがあやまっている。長い内乱がまくをとじた。
|
6 マリア・テレサとの結婚
top
一六五四年六月七日、ルイ十四世の戴冠式が、ランスの大聖堂で行われた。
王が神の授け物であることをしめす、ページェント(劇的なもよおし)である。
その六年後、パリの民衆はまた大さわぎをすることになる。といっても、これは、おめでたい大さわぎで、
「王妃の馬車がくるぞ! 新発明のすばらしい馬車だそうだ、見にいこう」
「新婚ホヤホヤの王妃は、スペインの王女で大変な美人ですってね。ひと目みたいものだわ」
フランスとスペインとの戦争 *
は、前年の一六五九年に、フランスの優位のうちにおわっていた。
* フランスとスペインの戦争 三十年戦争のさなかにはじまったが、1659年にピレネー条約がむすばれて終結した。このなかでマリア・テレサとルイ14世の結婚がきめられた。
今度の結婚も、両国の仲なおりの意味がこめられていたのである。
「ホラ、きたぞ! 何と王さまが馬にのり、王妃の馬車につきそっているではないか」
などとさけびながら、人々は表通りを走っていった。
一六六〇年六月九日、ルイ十四世とマリア・テレサの結婚式は、スペイン国境の近くで行われた。
二人とも、二十二才である。
王妃マリアはふっくらした可愛いい素直な娘だった。
ルイ十四世よりさきに、スペイン王家からきていた王母アンヌのほうが、この結婚を気にいった。
なぜなら、
「マリアはいい子よ。何といっても、スペイン王フィリップ(フェリペ)四世の娘――ということは、マリアは私の姪ですもの。 あなたたちが一緒になってくれれば、私はいつでも姪とおしゃべりが楽しめますものね」
と、いうわけだ。
王母は祝いの品として、ダイヤをちりばめた置時計を、弟のスペイン王に贈った。
この結婚をすすめたのは、マザランである。
「スペイン王女との結婚は、かならず両国の間に平和をもたらしてくれましょう」 |

ルイ14世の戴冠式 14才のルイ14世は、
これから2000万人のフランス国民を支配していく。

ルイ14世とマリア・テレサの結婚
スペイン王(中央右側)にあいさつするルイ14世。
|
と、マザランは、ルイ十四世にいった。
「それに王女には、巨額の持参金(結婚するときにもってくるお金)か、でなければそれにかわるスペイン王位の継承権がつきます……」
政治的、外交的なかけひきである。
しかし、そんなことはおかまいなしに、結婚後、二人は仲むつまじくくらした。
7 太陽王の時代はじまる
top
|

馬上のルイ14世 マザランの死を機会に、ルイ14世は
みずから統治すること宣言した。22才の若い「太陽王」が誕生した。
|

|
一六六一年三月はじめ、宰相(総理大臣)マザランは病の床についた。
ある日、ルイ十四世が見舞いにいくと、弱々しい声でだが、マザランは別れをおしむように長話をした。
「三十年もつづいたヨーロッパの戦争も、一六四八年のウェストファリア条約でほぼおさまりました。
また、一六五九年のピレネー条約で、フランスのブルボン家は、スペインのハプスブルク家
* を、充分におさえております。 王さま、もう、おおかたの地ならしはおわりました」
* ハプスブルク家 オーストリアの王家。代々神聖ローマ帝国の帝王となった。1556年にスペインとオーストリアの2派に分れ、やがてスペインの方は衰えた。
「長い間、ご苦労だった」
手をとって礼をいうルイ十四世に、マザランは涙ぐみながら、
「最後に、ぜひ申しあげておかなければならないのは……」
「最後などと……」
ルイ十四世もなみだぐみ、首を横にふった。
「いいえ、王さま。―みずから政治をおこない、宰相をおかないこと。ぜひ、そのようになさってください」
それからまもなく、五十九才のマザランは死んだ。
マザランの死の翌日(三月十日)、ルイ十四世は、会議室に重臣(おもい役めの家来)たちを集めて、宣言した。
「これからは、フランスは私がみずから統治する!」
やがて、彼は「太陽王」とよばれるようになる。
祭りのバレーのためにつくらせた衣装に、きらめく黄金の太陽がデザインされていたのがきっかけだが、もちろん、若いさっそうとした王の姿かたちと能力に、人々は「太陽」を見たのだった。
この「太陽王」というよび名とともに、よく知られているのが、
「朕(ちん)は国家なり(国王の私の意志が、そのまま国家の意志である)」という言葉である。
8 実力者コルベール
top
「本当に政治能力のある、数人の国務大臣が参加するだけでよい」
親政(王みずからか政治をとること)をはじめたルイ十四世はそう考え、最高国務会議のメンバーを、少数のすぐれた政治家だけに絞った。
そのなかでも特にすぐれた人物が、財務長官のフーケと、のちに財務総監となるコルベールである。
この二人は互いに対立する運命にうまれついていた。
フーケの家の紋章 * は、「リス」。
* 家の紋章 ヨーロッパでは、家の紋章は王家や貴族しかもっていない。日本では家紋といい、天皇家から一般の庶民までもっている。日本では家紋の種類は一万もある。
「のぼれないところがあろうか」という銘がきざまれた図案の、木のいただきには王冠がえがかれていた。
それにたいして、コルベールの家の紋章は「ヘビ」。
性格もフーケは陽気で派手好み、コルベールは、冷たく暗い印象だった。 |

フーケ 巨額の富を得たため、
ルイ14世の怒りを買ったが、
弁護する人も多かった。
|

コルベール ライバルである
フーケの罪を調べあげ、ついに
とらえて失脚させてしまった。
|
「御用商人(政府とつながりのある商人)や徴税請負人とつながりがあって、フーケは多額の公金(政府のお金)をへいきで自分のものにしている。
彼は、私にとって邪魔なだけではない。王のために、たおさねばならない」
と、コルベールはおもい、ひそかにフーケの罪を調べあげた。
そうとは知らないフーケは、八月のある夜、宮殿のような自分の大邸宅に、ルイ十四世を招待し、「夢の国のような宴会」をひらいた。
その贅沢きわまるもよおしは、かえって王に反感をいだかせた。
数日後、コルベールの報告をうけた王は、フーケをよびつけ、財政の不明なところを追及した。
「政治には、かなりの機密費(ひそかな目的におうじて自由につかうお金)というものが必要です」
と、フーケはおうじた。しかし、コルペールは別のわるい情報をつかんで、王にさしだした。
「ブルターニュ半島の沖にある島を、フーケが買いとっています。
彼はここに砦をきずき、反乱をおこして、王位をうばおうと計画しているのです」
フーケはとらえられ、監獄(かんごく=牢屋)にいれられた。
かわってコルベールが財務総監となり、「重商主義」といわれる政策によって、国の経済力を大きく育てていく。
重商主義というのは、国内の産業や貿易に国家が保護を加え、有利な貿易を行って利益を得て、国家を豊かにしていこうというもので、十七世紀にもっとも栄えた考え方である。
「国家の強さは、銀の豊かさによる。だから、貿易をして(輸出をふやし)銀をよそから奪い取るのだ」
というのが、コルベール * の考え方だった。
* コルベール ルイ14世の政治を財政面から支えるため、産業の保護や貿易の発展に力をそそいだ政治家。リシュリューやマザランとともに、フランス絶対王政の最高実力者であった。
9 王さまのひとにらみ!
top
「統治を他人にまかせてはいけない。自分が支配者になり、政治についての決定は、自分でしなさい」
とは、のちにスペイン王となった孫(フィリップ五世)におくった、ルイ十四世の言葉である。
ルイ十四世は、みずからその言葉どおりに、重要な政治の会議は、自分が中心になってすすめ、決定をくだした。
宮廷の貴族や国務長官たちを、思い通りにあやつり、気にいった家来には、そのしるしに、金銀の刺繍(ししゅう)をほどこした水色のコートをあたえた。
そして、司法(しほう=裁判)、治安(ちあん=警察)、財政そのほかそれぞれの分野に、
「王の目、王の耳、王の腕」
といわれた地方監察官をおいて、いわゆる「中央集権化(中央にすべての権限を集中させる)」をすすめていった。 |

ルイ14世の行進 衛兵たちにまもられて、
ルイ14世ののる馬車が高等法院にむかうところ。
|
ルイ十四世の威光をしめず例として、つぎのような話が残っている。
「あの森の木々は、実に目ざわりだ」
と、あるとき、散歩のおり、ルイ十四世はつぶやいた。何日かして、同じ場所をルイが通りかかると、突然、木々はいっせいに倒れた。
「ある取巻きの貴族が木こりに命じ、それらの木々を根元できり、王が通りがかるまで倒れないように細工してあったのだ」
「王さまのひとにらみで倒れました」と取巻きがいうと、ルイは満足げにこういった。
「はじめてゆかいな光景に接したぞ」
10 エネルギッシュな生活
top
赤ん坊のころ、何人もの乳母のおっぱいをのみほし、まだものたりず、出ない乳房にかみついたほどのルイ十四世は、なみはずれた健康とエネルギーにめぐまれていた。
「王さま、八時でございます」
と係の者がおこすと、ルイ十四世はアルコールで手を洗い、えらんだかつら
* をかぶる。
* かつら バッハやモーツァルトをえがいた絵でもわかるように、ヨーロッパでは社交の場にきかざって出るときには、男でも毛の長いかつらをかぶるのがきまりになっていた。
――それから夜遅く床につくまで、
「暦と時計があれば、遠くはなれていても、王のしていることはわかる」
といわれるくらい、規則正しく、いそがしいスケジュールをこなしていった。
もうすこし、くわしく王の生活を紹介すると、――
○ きがえのあと、朝食。これは、白パンと水などの、ごく軽い物。
○ 剣、装身具、帽子などを身につけると、「政務の間」にはいり、さまざまの命令を出す。
○ ミサ * (教会の儀式)に出席する。
* ミサ キリストのからだを意味するパンと、血を意味するプドウ酒を神にささげ、神父をとおしてそれをいただくための儀式。聖歌隊がミサ曲をうたい、神父が神の教えを説いたりする。
○ ふたたび「政務の間」で、国務会議。
○ 一時、昼食。
○ 食後は、散歩、あるいは短時間の狩り。
○ その後またしばらく「政務の間」ですごす。
(ルイは、一日合計六時間も政治についての仕事をした、と伝えられている)。
○ 一族の者や親しい貴族たちも同席する、おそい晩餐(ばんさん)。もりだくさんな料理。
○ 食後は、舞踏会、音楽会、トランプ遊び、王つき、庭園でのつどいなど。
(ルイは踊りの名手だったし、クラブサン〈ハープシコード。ピアノの前身〉とギターをたくみに演奏した)。
○ 入浴。就寝。 |
|

人々の請顧をきくルイ14世
体力にめぐまれたルイ14世は、いそがしい仕事も、
テキパキとこなしていった。
|

17世紀フランスの舞踏会
貴族たちのはなやかな生活ぶりが、うかがわれる。
|
ついでにいえば、
ルイ十四世は、女性たちにも大変人気があった。当時のある貴族の夫人がかいているように、
「上背があり、均整のとれた見事な体格、威厳と気品のそなわった顔かたち……
それに、婦人にたいしては特に礼儀正しくて、宮廷づきの洗濯女にでも、王がみずから帽子に手をふれて礼をした」
というのだから、人気の出ないわけがない。
11 ベルサイユ宮殿の大工事
top
さて、「すべてをおこなった」といわれるほど、ルイ十四世は精力的に仕事をし、史上まれな「繁栄の時代」をきずいたのだが、とりわけルイ十四世の名を華やかにのこす記念碑は、「ベルサイユ宮殿」
* である。
「プロットの乱のいまわしい思い出が、いまだによみがえるので、パリはよくない。
ルーブル宮殿 ** は古ぼけて、悪い臭いをはなっているし、サン・ジェルマン宮殿は狭すぎる」
と、いつ頃からか王は不満をもらしはじめた。
* ベルサイユ宮殿 パリの西南にあるベルサイユにつくられた大宮殿。広大な庭園と劇場や教会をふくむ城館からなり、とくに「鏡の間」は有名。ルイ14世の富と権力の大きさを忍ばせる。
** ルーブル宮殿 パリのセーヌ川右岸にあるフランスの古い王宮。1791年から国立美術館としてつかわれている。「モナ・リザ」や「ミロのビーナス」など世界的に有名な美術品が数多くある。
「あらたに宮殿をおつくりになるとすれば、どこがよろしいでしょうか?」
インドにもうけた商社の貿易活動や、北アメリカの植民地を広げることに熱心なコルベールは、大きな費用の支出をおそれながら、王にきいた。
「――うん。子供のころ、父と一緒によく、ベルサイユへ狩りにいった。
パリ西南の村だが、快適ないこいの地だ。そこにしよう」
と、ルイ十四世はこたえた。
王妃マリア・テレサが最初の王子をうんだ一六六一年―ある皮肉屋の批評家にいわせれば、
「自然をむりやりつくりかえることを、このうえない楽しみとした工事」つまり、ベルサイユ宮殿の建設工事ははじまった。
その後、四十年間もつづくこの工事の間に、事故や伝染病で倒れた労働者たちの死体が、荷車に山とつまれてはこびさられ、その回数はかぞえきれない。
どんなに規模の大きな宮殿だったかは、関係者の一人の、つぎのような回想からも、うかがえるだろう。
「王がもっとも熱中したのは、庭園づくりの工事でした。――
大運河を庭園にとおすために、一つの丘がきりくずされ、迷路や洞窟がつくられ、方形(ほうけい=四角形)や円形の池もほられました。
もとのフーケの城から、手数百本のオレンジの木がうつされ、さらに一五万本におよぶ花樹が次々と植えこまれたのです。――
そして、直線と曲線の組合わせによる幾何学的な大庭園が、できあがりました」
しかし、ベルサイユは水に不便な土地だが、大運河の水や池の噴水は、どうしたのか。
「――それは、セーヌ川に直径一二メートルもある大水車を、一四台すえつけ、たくさんのポンプを使って、マルリの丘(高さ一五四メートル)まではこびあげ、そこから八キロメートルの距離を水道でおくったのです。
揚水機は『マルリの機械』とよばれ、当時はめずらしがられました」
このベルサイユ宮殿にルイ十四世が移住するのは、一六八二年だが、それまでにもたびたび、彼は工事中におとずれ、「魔法の島の楽しみ」などと称する大宴会を、何日もつづけて催している。
12 貴族と貧しい人々
top
王は、美にたいする理解も深く、へたな写実的な絵をみせられると、
「サルどもの絵なんか、みせるな!」 と、どなった。
彼はまた、学問や芸術を保護し、「アカデミー・フラッセーズ(文芸を学ぶ学校)」を官営にきりかえ援助した。
こういう学問や芸術に理解ある「太陽王」のもとで、文化がかってなく華やかに栄えたのも、当然だろう。
デカルト、パスカルなどのすぐれた思想家、――
ラ・ロシュフコーそのほかのモラリスト(人間観察家)がいる。――
詩人はラ・フォンテーヌ、ボアロー、――
作家としては、セビニェ夫人、ラファイェッ卜夫人。――
そして演劇の方では悲劇のコルネイユ、ラシーヌ、喜劇のモリエール等々、実にたくさんの天才が活躍した時代である。
音楽界ではリュリが、美術界ではル・ブランが、「古典主義」
* の時代をつくった。
* 古典主義 古代のすぐれた作品をみならって、かたちのととのった芸術をうみだそうとする考え方。文学ではゲーテやシラー、音楽ではハイドンやモーツアルトたちが代表的。
いまでもベルサイユ宮殿に残っている、金ピカの立派な装飾をほどこした家具や美術品から、王や宮廷貴族の贅沢な生活は、たやすく想像でできる。
だが同じその時代、一方には貧乏にあえぎ苦しむ労働者や農民の、暗いわびしい世界があった。
当時のルイ・ルーナンという画家の作品をみれば、そのみじめな現実がうかがえるだろう。
しかし、ルイ十四七は、彼ら貧しい人々のことを、忘れていたわけではない。
「一六六二年の飢饉(ききん)のおり、王は、庶民にパンをあたえた」
と、記録に残っている。
「金持ちがやすく買った穀物をとりよせ、貧しい人の家にくばらせた。困っている者には、税金を免除してやった。……」
ルイ十四世の人気は、そういうところからもうまれた。 |

貧しい人々 ルイ・ルーナン画。生活苦にあえぐ貧民も多い。
|
13 フランドル戦争
top
「……西インド諸島 * (中央アメリカにある島々)や新大陸(アメリカ大陸)に次々と植民地をつくって、いまやイギリスの勢いは、あなどれませんな」
* 西インド諸島 キューバ、ハイチ、ジャマイカなどの島々。コロンブスが最初に発見して、ここをインドと間違えたことから、西にあるインドという意味でこの名がついた。
ある日の国務会議である国務卿(国務大臣)が、ルイ十四世にむかって溜息まじりに述べた。
「サトウキビの栽培や砂糖の生産が、豊かな経済力をつちかっているようで……」
「歴史の重心は、フランスからイギリスヘうつりつつある、などという学者もいるようで……」
と、別の国務卿が口ごもる。
「なにをいうか!」 ルイ十四世の顔が、怒りに赤くそまった。
「歴史はつねに、私を中心にまわっている。そして、領土を広げることこそ、君主にふさわしい仕事なのだ」
と、ルイ十四世は考えている(ある軍人にあてた手紙に、そうかいていた)。
「軍隊の力を強くしろ!」 とルイ十四世は命じた。
陸軍は、ルーボアという将軍が全力をあげて兵力をふやす。
一六六七年ごろの報告では、七万二〇〇〇にすぎなかった兵力は、一七〇三年には、実に四〇万に近づいている。
「ヨーロッパ第二といわれる陸軍が実現したのである。
「クルミがらの船隊」とからかわれていた海軍のほうもまた、コルベールの指導によって、大きくなり、一六八三年ごろにはすでに、二七六隻の軍艦をかかえていた。
「わが妃マリア・テレサが相続すべき遺産を、わがものとするため――」
という侵入の口実をもうけ、
「攻めこめ、スペイン領フランドル(ベルギーを中心とする地域)へ!」
と、ルイ十四世が命令をくだすのは、一六六七年五月のことだ。
スペイン王フィリップ四世が亡くなったのは、その二年前で、ルイ十四世の母アンヌも、一年前に亡くなっていた。 もう、スペインと戦争するについて、だれにも気がねはいらなかったのである。
フランス軍三万五〇〇〇にたいし、スペイン軍は、八〇〇〇――「フランドル戦争」
*
とよばれるこの戦争の、勝負ははじめからきまっていた。
「スペインがたちまち悲鳴をあげたぞ。これは、気をつけねば……」
と、オランダ、イギリス、スウェーデンの三国は、同盟をむすんで、休戦をよびかけた。
* フランドル戦争 ルイ14世がスペイン領フランドルをうばおうとしておこした戦争。オランダ、イギリス、スウェーデンが同盟をむすんで対抗したので、ルイ14世はこれを恨んだ。 |

王妃マリア・テレサ ルイ十四世を
一生愛しつづけたという。
|
14 オランダとの戦争
top
ところが今度は、その三国のひとつオランダ *
にむかって、ルイ十四世は戦いをいどんでいった。
* オランダとの戦争 フランドル戦争を第一次ネーデルラント戦争といい、オランダ戦争を第二次ネーデルラント戦争ともいう。ルイ14世が復讐のために、オランダに攻めこんだ戦争。
「盟友(めいゆう)フランスにそむき、スペインに味方するとは、けしからん!」
というのだが、じつは海上貿易によって繁栄をきわめたオランダこそ、フランスの最大の敵であった。
ライン方面に進出するとき、ルイ十四世は、みずから陣頭に立って兵をすすめた。しかも、
「軍隊の移動のため、人々に迷惑がかかってはいけない。村々へは、もれなくお金を配っておくように」
と、こまかい気づかいぶりをしめした。
それでむしろフランス軍は、人々に歓迎され、同時に、
「ルイ王は、敵にまわせばおそろしいお人」という噂が広まっていった。
「ライン川を渡るとき、その作戦は王みずからがとり、大胆にも歩兵と一緒に船をならべた橋を渡っていったそうだ」 |

オランダへの遠征 1672年にルイ14世は、スペインに味方したオランダを討つため、その南部に軍を進めた。
|
「――後々までの語りぐさ」として、その噂も王の人気をあおった。
ルイ十四世の人がらを、つぎの話から感じとることもたやすいことだろう。
強敵オランダ海軍 * の名提督(艦隊の司令官)といわれた人物が、戦いのさなかに倒れ世を去った。
* 強敵オランダ海軍 オランダはイギリスと共にアジア、アフリカへの進出の主役となった国だけに、すぐれた造船技術と強い艦隊をもっていた。名提督の名はデ・ロイテルという。日本の長崎の出島も、オランダが植民地ジャワを中継地として日本の鎖国時代のヨーロッパへの窓口となった。
取巻きの一人が、ルイ十四世に、
「厄介な人間が一人へって、よかったではありませんか」というと、王は怒りをかくさず、
「英雄の死は、悲しむのが当然だ」とこたえたそうだ。
15 コルベールの死
top
一六八三年は、ルイ十四ガにとって、つらい年だった。まず七月、王妃マリアが死んだ。
「――それは、王妃がはじめて私にあたえた悲しみだ」 と、王は語った。
王妃との間には、王太子をはじめ六人の子供があった。しかし、最初の王太子のほかはみな、次々に早死にしている。
ルイ十四世が「太陽」なら、マリアは「月」のようなさびしい雰囲気のつきまとう運命だった。
さらに、同じ年の九月、コルベールも死んだ。
そのしばらく前、――
建築中のベルサイユ宮殿の天井がおちてくる、という事故があった。
「それは、コルベールが建築技師たちと組んで公金(政府のお金)をわがものにし、手ぬき工事をしたからおきたのです」
と、ルイ十四世にうったえて出だのは、陸軍卿(陸軍大臣)のルーボアだった。
王は笑ってとりあわなかったが、コルベールは、うったえられたショックで寝付いてしまった。
もっとも、関節などに炎症をおこす痛風(つうふう)の持病があったうえに、ガンをわずらってもいた。
そしてまもなく、コルベールは六十四才で亡くなった。
「太陽王」の栄華の時代を、裏でささえる財政・経済・貿易などの国務の担当者――コルベールという片腕の死は、ルイ十四世にとって中々つらい現実だった。 |

上=ルイ14世時代のひじかけ椅子
フランス・バロック建築を代表する
豪華な宮殿には、それにふさわしい
立派な調度品や家具類がつくられた。
下=ルイ14世時代のテーブル
かざりたてが多い。
|
16 オランダとの和平
top
オランダとの戦争では、ルイ十四世の弟オルレアン公
* も、かなり活躍していた。
* オルレアン公 好きかってなことをするので、ルイ14世には嫌われていた。ルイ14世が亡くなると、ルイ15世の摂政(王にかわって政治をとる人)となり、政治の流れをかえようとした。
「――意外ですな」 と、ルイがこの弟にあまり好意をもっていないと承知している側近の一人は、いった。
「あのデップリ太って、女性的で、紅おしろいなどつけた、高慢な弟君が、戦争でわが軍を勝利にみちびこうとは――」
「なに、戦いのだくみな騎士たちに、たすけられてのことだ」 と、ルイ十四世はまゆをよせてこたえた。
「けっして弟に軍隊の全権をゆだねてはならない」
あくまでも、栄光を独り占めにするのが、「太陽王」とよばれるゆえんなのだ。
一六七八年には、オランダとの和平交渉におうじ、ナイメーヘン条約
* をむすんだ。
* ナイメーヘン条約 ルイ14世がおこしたオランダ戦争のあと、フランス、オランダ、ドイツ、スウェーデン、デンマークの国々のあいだで、領土をはっきりさせるためにむすばれた。
それによって、フランスは領土を広げたが、もちろんオランダ人たちは、はげしくルイ十四世を憎むことになった。
いずれが勝ちいずれが負けても、戦争は常に人間を獣(けもの)のようなあさましい姿にかえ、憎しみや怒りを、いつまでも残すものだ。 ルイ十四世の数々のすぐれた政治の仕事のそのかたわらには、戦争のみじめさや軍人たちのむごたらしい行為が、残された。
17 新教徒の弾圧
top
「――竜騎兵(りゅうきへい)がきたぞ!」
のさけび声で、だれもがまっ青になった時期がある。一六八一年のころだ。
| 「新教徒(プロテスタント)の家におしかけた竜騎兵は、家の主人をののしりなぐりたおし、女たちを馬にのせてつれだし、暴行するというようなひどいことを平気でやった。――それほどまでにしてカトリックヘ変ることをせまり新教徒を弾圧した」 |
と、そのころの記録文書にしるされている。
その弾圧のみなもとはやはり、新教徒嫌いのルイ十四世にある。 「ただ一つの王、ただ一つの法、ただ一つの宗教」を、ルイ十四世はめざした。 「最大のカトリック信徒の王」としてルイ十四世は、一六八五年にナントの勅令を廃止した。
ナントの勅令とは、一五九八年に、ヘンリ(アンリ)四世(在位一五八九〜一六一〇年)がだしたプロテスタントを認める命令である。 当時フランスでは、カトリック教徒が大多数であったが、プロテスタントとの対立がはげしかったので、国内をまとめるため、ヘンリ四世は
*
、プロテスタントの信仰の自由をも認めたのであった。
* ヘンリ4世 フランスのブルボン王朝の最初の王。ナントの勅令をだして、プロテスタントの信仰の自由をみとめた。しかし、これをおこったカトリック教徒によって暗殺された。
それを、
「ヘンリ四世が新教徒を保護するためにつくったテントの勅令なんて、無用ですぞ」 と、ルイ十四世にけしかける者もいて、廃止してしまったのである。 その結果、何十万、いや何百万という新教徒が、国外へ亡命(ぼうめい=のがれること)していった。
なかには、すぐれた技術者や熟練工や研究者たちもふくまれていたので、フランスの損失は大変大きかった。 |
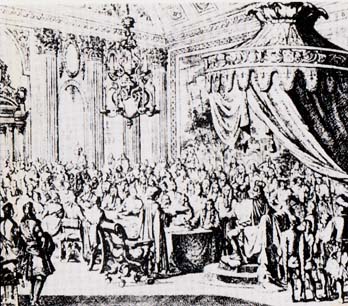
ナントの勅令の廃止 ルイ14世は宗教を統制しようとし、
プロテスタントをみとめたナントの勅令を廃止した。
|
18 ファルツヘの侵入
top
ヨーロッパの盟主(めいしゅ=代表者)をめざすルイ十四世の動きは、ほかの国々に強い反発をよびおこした。
そして一六八九年には、フランスに対抗するためのアウクスブルク同盟が結ばれる。
この同盟は、スペイン、ドイツ、スウェーデン、オランダなどの国々が手をつないで、フランスをのけものにしようという狙いをもつものである。
「けしからん! 先制攻撃(先に相手をふうじこめること)をしかけて、ファルツ(ドイツ西部の領地)を占領してしまえ」
と、ルイ十四世は命じた。
たちまち、首都ハイデルベルクをはじめ、多くの美しい村が焼け野原となった。
「……住居のない者たちは、荒れ果てたあとに穴をほって、原始人のようにくらしている」
と、そこを通ったある旅行者は、手帳にしるした。
「ルイ十四世は、神をもおそれない残忍な怪物だ!」 そういう恨みの声が、ドイツ全体にわいた。
この戦争は、九年つづく。 |

ルイ14世時代のフランス軍 戦争はたえまなくつづいていった。
|
全ヨーロッパがルイ十四世に反対して立ちあがったので、戦争は長びき、国々は共に疲れはてるばかりであった。
そのあげく一六九七年にライスワイク条約 *
を結び、ルイ十四世は征服したいっさいの領土を敵国に返した。
* ライスワイク条約 アウクスブルク同盟戦争が終ったあと、フランス、イギリス、オランダの間で、領土や国王の承認問題などを取決めたもの。
19 スペインヘの野心
top
「スペイン王チャールズ(カルロス)二世が病気で、もうだめだろうという話です」
ある寒い朝、ルイ十四世の耳もとで、スパイ役の家来の一人が、あたためられたガウンを着せかけながらささやいた。
「三十代で、もう老人のようなふけこみようだったからな……」
と、ルイ十四世はおうじながら、そのねむたげな目の奥は、するどく光った。
「チャールズ二世は、病弱で、子供がいない。――ということは、スペインの王位を誰が継ぐかだ!」
と、ルイは考えていた。
一六九八年一月のこと。
「アメリカ大陸、フィリピン、ネーデルラント(オランダ、ベルギーなど)、イタリア……それらの大きな領土という“遺産”は、どうなりますか」
と家来は、薄いくちびるをひきつらせ、剣を手渡しながら聞く。
「フン……」ルイは、鼻先で笑った。
「私のものだ! チャールズ二世の叔母にあたるアンヌが、私の母だった。
それに、チャールズ二世の姉にあたるマリアは、私の妻だった。――私にも当然、継承権がある。
しかし……競争相手がいる。ドイツ皇帝レオポルド
* だ。
彼もまた、マリア・テレサの腹ちがいの妹と結婚している。
そうだ、先手をうってやれ……」
* レオポルド 神聖ローマ(いまのドイツ)の皇帝。レオポルド一世という。スペイン継承戦争では、ほかの国々と同盟をむすんでルイ14世のフランスを相手に戦ったが、途中で死んだ。 |
ルイ十四世は、レオポルドに会った。
そして、「チャールズ二世が死んだら、二人でスペインを分割しよう」と相談した。秘密協定である。
ところが、イギリス王(ウィリアム三世)がそれをかぎつけ、彼らの間に割込んできて、別の協定を結ばせたりした。
そして、事はいつかチャールズ二世に知れてしまった。
「――嫌だ。彼らのおもいどおりにされてたまるものか」
死の床でスペイン王は怒り、最後の抵抗をしめした。
「領土は分割しない。王位は、アンジュー公にゆずる」と遺言したのである。
アンジュー公というのは、ルイ十四世の孫のことである。
「スペイン王となるかわりに、フランスの王位への権利をいっさい、放棄すること」がその条件となっていた。 |

フィリップ五世
ルイ十四世の孫で、スペイン王となった。
|
こうしてフランスのブルボン家から、スペイン王フィリップ五世(在位一七〇〇〜一七四六年)がうまれた。
20 スペイン継承戦争
top
ところが――
「イギリス王、ドイツ皇帝、オランダ諸領との間に、フランスと対抗するためのパーク同盟がむすばれました。
これによりますと、スペイン王位はドイツ皇帝がつぎ、スペインの海外植民地は、イギリスとオランダで分割することになっております。 これは、わがフランスの強大化をおそれるイギリスのしわざです。
イギリスは、世界帝国をめざしていますからな……」 |
こういう問題が、最高国務会議にもちだされたのは、一七〇一年のことである。
「イギリスおよびドイツ帝国を敵にまわし、いずれ一戦をやらねばならない。それが、私たちの運命なのだ」
と、ルイ十四世は決心していた。
翌一七〇二年、こうしてスペイン継承戦争 *
がはじまる。
* スペイン継承戦争 ルイ14世がおこなった最後の侵略戦争。ルイ14世が孫のアンジュー公をフィリップ5世としてスペインの王位につけたため、イギリスやオランダなどが反発したもの。
今度の戦争は、苦しかった。
一七〇四年、ドナウ川のほとり、プリントハイムで行われた大会戦では、フランス軍は五万のうち三万を失うほどの大敗北をきっした。
一七〇六年になると、ドイツ皇帝の軍がスペインに攻めいり、マドリードが陥落する。 |
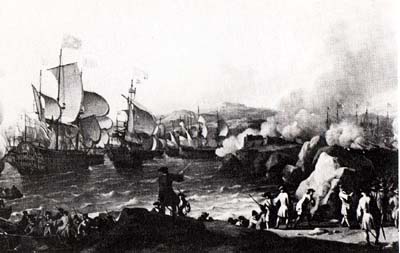
スペインのビゴ湾における海戦
フランス艦隊は、イギリス・オランダ連合艦隊に破れた。
|
逃げのびる孫のスペイン王フィリップ五世のことが心配で、ルイ十四世は夜もロクロクねむれず、しきりに苦しげにうなっていた。
一方、フランス国内では、新教徒(プロテスタント)たちの内乱があったり、農民たちの反乱があった。
また飢饉(ききん)のため乞食がふえ、子供たちも病気で死ぬ者がふえた。
「――休戦すべきではないか?」 すでに七十才をむかえたルイ十四世は、ときおり気弱く考えこんだ。
「いや、いかん。弱気をだしてはいかん。この世で戦いが行われねばならない以上、私は子孫と戦うより敵と戦うことをえらぶ」
ルイはそう自分につげ、絶望的な泥沼の戦争 *
をつづけた。
* 泥沼の戦争 どちらが勝つかみきわめがつかず、いつおわるとも判断がつかず、敵も味方も死者やけが人ばかり多く出て、勝っても負けても両方に大きな被害が出るような戦争。日中戦争も最初は小競り合いだったのが、泥沼の戦争となってさらに大きな太平洋戦争になり、原爆を落されてやっと決着した。
21 太陽王の死
top
「人民を愛せよ。戦争を好むな」
ルイ十四世の孫の教育をうけもっていたフェヌロンは、教材の中でしきりにこう説いていた。
一七一一年に王太子のルイが死去してしまったので、ルイ十四世の後継は孫のブルゴーニュ公となっていた。
しかしこの孫も、翌年に麻疹(はしか)のため、ルイ十四世よりも先に死んでしまった。
一七一三年四月十一日――やっと講和条約が結ばれ、十一年もつづいた戦争はおわっだ。
その二年後、一七一五年九月一日、ルイ十四世はこの世を去った。七十七才の高齢であった。
“えそ”という病気が、命とりになった。
「家来たちよ。私がこのような悪いお手本をしめしたことを、許してくれたまえ」
という、しおらしい最後の言葉を、ルイ十四世はのこした。
偉大な「太陽王」ルイ十四世も病気と死には勝てなかった。
しかし、泣く家来たちをみて、死ぬ直前のルイ十四世が、
「なぜ泣く。私を不滅(ふめつ=死なない)とでも思ったか」
と叱りつけたのは、さすがだった。
「太陽」は沈んだ。時代はまた変る。 |

宮廷のルイ14世 偉大な「太陽王」として、
栄光の生涯をおくった。
|
top
****************************************
|