|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章
四 永遠にのこる人間像
|

有名な「鉄のカーテン」の言葉を演説したときのチャーチル(1946年アメリカ・ミズーリ州フルトン市
|
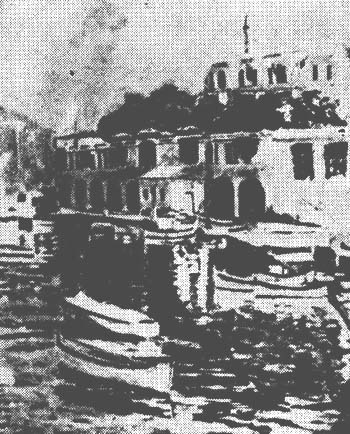
チャーチルの絵
|
チャーチルは第二次世界大戦がおわる約一ヵ月前の七月、首相を辞任(総選挙で自由党に敗けた)して時間的にかなり余裕ができた。
彼は旅行や好きな絵筆にしたしむことができた。
翌年の一九四六年三月、アメリカのミズーリ州フルトンで演説したが、このとき彼はソ連を警戒すべき演説のなかで、「鉄のカーテン」という言葉を使った。
この言葉は「冷たい戦争」という言葉とともに、さっそく世界中の言葉となった。
一九四七年には、王立美術院に得意の油絵を出品した。
チャーチルは暇があればレンガづみや絵筆に親しんだが、この悠々たる人柄がますます人々に親しみをあたえた。
チャーチルはこのころから、第二次世界大戦の記録をのこす仕事にとりかかった。
これが全六巻におよぶ約五千ページの偉大な著作となり、一九五三年、七十九歳の誕生日の一ヵ月前にノーベル文学賞を授与され、ペンの人としても最高の名誉を得た。
これよりさき一九五一年十月二十五日、自由党政府が総選挙でやぶれて再び保守党が政府を組織すると、いまは七十七歳のチャーチルであったが、またも首相となった。
そして一九五四年十一月三十日、八十歳の誕生日のお祝いに、イギリスの上下両院から肖像画を贈られ、歴史にのこる政治家として最高の栄誉ある人物にされた。
しだいに老齢をかさねるチャーチルは、余生をしずかにおくるため、一九五五年四月、首相と保守党首の両方を辞退し、後任にイーデン首相を推薦し、長い政治生活にわかれをつげた。
まさに功成り名をとげた人物の、悠々たる引退ぶりというべきである。
軍人として、政治家として、または著述家、画家として、偉大な才能をみせたチャーチルは、いまは、イギリスの歴史ばかりでなく、世界の歴史に永遠にのこる偉人となったが、チャーチルが老境にはいってからの私生活は、どうであったろう。
チャーチルは人一倍情に厚い、そして人一倍、茶目っ気(ちゃめっけ)のある人物であった。
第二次大戦がおわった翌年の一九四六年夏から、チャーチルの身のまわりの世話をみるようになった従者の話はおもしろい。
この従者はまえから、チャーチルが非常にえらい人であることを知っていた。
海軍兵あがりのこの従者はまだ二十一歳の青年だったので、総理大臣をやったような人のところへ奉公するのは大変なことだろうと考えた。
しかしチャートウェルのチャーチル邸に奉公することになると、チャーチル家の人々は、みんな暖かくむかえてくれた。
一家の空気はすべて暖かかった。
彼の仕事は主人の衣類の世話と、絵の具の用意やあとしまつなどで、俸給は週給五ポンド(約五千円)である。
もちろん部屋と食事と雑費はあたえられる。
従者は気持のよい部屋をあたえられ、そこに荷物をほどいた。
すぐにチャーチルのところへ挨拶にいかなければならないのを考えると、気持は落着かなかった。
チャーチル邸に今まで奉公した人たちは、みんな立派な人たちである。
自分にそのように立派につとめることができるだろうか。まだ年が若いので経験もすくない。
チャーチルのようなえらい人が、はたして自分のようなものに満足してくれるだろうか。
彼は本がぎっしりつまってがる書斎に案内された。
書類をテーブルの上にいっぱいちらかして、どっしりとすわっている老紳士がいた。
彼はてっきり、秘書の一人だなと思った。
彼がしばらく立ってまっていると、その老紳士は書類から顔をあげた。それはチャーチルだった。
チャーチルは立ちあがると、この若い従者のそばによってきて握手した。
それからおだやかな声でいった。
「ノーマンだね――私の世話をみてくれる――」
「はい、そうです。」
チャーチルは、しばらく従者の顔を見ていたが、
「しっかりやろうよ」といった。最初の挨拶はただそれだけだった。
従者はオドオドしながら、どんなふうに働けばよいかとたずねた。
するとチャーチルは、葉巻に火をつけていった。
「まあ、じょじょにやっていこう。それより、まずミセス・チャーチルに会ってくれ。そして指図をうけようよ。」
ノーマンはチャーチルのあとについて、長い廊下を応接室のほうへ歩いた。
ここにチャーチル夫人がいた。
「これがノーマンくんだ。私の世話をみてくれる。」
一方チャーチル夫人は、ただ二つのことだけ、指図した。
「主人が食事と約束の時間におくれないように、気をつけてくださいね。寒いときはオーバーコートを着せるようにね。」
このような簡単な命令だったが、これがなかなか大変なことだった。
翌朝チャーチルは、ベルを押して従者をよんだ。
「朝刊はどこにある?」
従者はさっそく、おおいそぎで新聞をとりに階段をおりだが、すでにメイドにしてやられていた。
ノーマンが新聞をほしいというと、彼女は声をたてて笑いとばしながら、新聞を持ってチャーチル夫人の部屋へ走っていった。
ノーマンはしかたなく、チャーチルのところへ戻って説明した。
すると、チャーチルはいった。
「私はベッドのなかで新聞を読むんだ。すぐに持ってきなさい。」
ノーマンは何度も夫人の部屋とのあいだを往復して、やっと夫人が読みおわった部分のページだけを受取ることができた。
これではどうもぐあいが悪い。なんとかしなければならないと、ノーマンは思った。
その翌朝からノーマンは、新聞配達の少年のペルに耳をすまし、ペルが鳴るとすぐメイドのマーシャと競走で玄関へ走った。
こういうことになればノーマンは、男である。男の足のほうが勝った。
しかしときには、メイドに負けることもあった。
そんなときは前のように、チャーチル夫人から数ページずつわけてもらって、自分のご主人にとどけなければならなかった。
こんなときには長官閣下(彼はチャーチルをこうよんでいた)は、ひどくご機嫌が悪かった。
そこでノーマンは、なんとか考えなければならなかった。
数週間、毎朝、先陣あらそいをつづけたすえ、ノーマンは一つの解決案を見つけた。
つまり新聞を二部ずつとれぱよいのだ。これで長官閣下のご機嫌もよくなった。
新聞問題はこれで解決したが、長官閣下が外にでかけるとき、オーバーコー卜を着せることと、食事と約束の時間に遅れさせないようにすることは、これまたひと苦労だった。
いくら夫人がいってもご主人のチャーチルは、寒い晩、秋のころでも、オーバーコートなしで屋敷をぬけだす癖があった。
そこでノーマンは、まえもって玄関にはりこんでいて、むりやりにオーバーコートを着せなければならなかった。
夫人から命令されている時間をまもることも、ホトホトこまらされた。
なにしろ長官閣下が食事時間に遅れるのはいつものことで、夫人もこれには手をやいていた。
夫人はノーマンに、なんとかきまった時間にきちんと食卓につかせる方法がないか、と相談をかけた。
そこでノーマンは、あれこれと考えた。
「昼食は午後一時四十五分ですが、主人には一時だといっておいてください。」
夫人はノーマンにこういった。
そこでノーマンはこのことを長官閣下にもうしあげると、長官閣下はわかっているよというようにニヤニヤしていたが、食堂にあらわれるのは、午後二時だった。
夫人が考えついたもう一つの作戦は、チャーチルが不在中にベッドルームにはいって、時計の針を三十分すすめておくことだといった。
ところがこの作戦も、さっぱりききめがなかった。
というのはチャーチルはいつも、時計を二つ持っていたのだ。
長官閣下はなんでも積極的な人間がすきだった。
ノーマンのやったことは、ちいさいことだったが、新聞のことでいろいろ考えて努力したことや、むりやりにオーバーコートを着せたり、みえすいた嘘をいって昼食時間に遅れないようにしたことなどが、かえってチャーチルをうれしい気持にさせたようだった。
一ヵ月間のノーマンの試用期間がおわると、ノーマンは妻と赤ちゃんといっしょに、邸内の小さな住宅に住んでもよい、といわれた。
チャーチル夫妻はまえからノーマン一家のことをいろいろ考えていたのだが、今はそうしてやってもよいと思ったのだ。
当時イギリス人は住宅難に苦労していたので、自分たちだけの住み心地のよい住宅を持てたのは、ノーマンには夢のようにうれしかった。
チャーチル家の日常生活は、すべて主人を中心に回転した。
大政治家の家庭はたくさんの仕事に追われると同時に、親しい友人や親類のためにも時間をさかなければならない。
それだけ使用人の日課も、いろいろと忙しい。
チャートウェルの私邸は、ハイド・パーク・ゲートや、ダウニング・ストリート一〇番地の官邸より、おおぜいの使用人が必要である。
私邸には料理人、夫人係のメイド、二人のハウスメイド、キッチン・メイド一人、それに主人専属のノーマンがいた。
使用人たちの用事はそのほかにもある。
秘書たちや私服刑事たちの声に応じて、その用事も引受けなければならない。
六人の秘書は当番制である。秘書たちのまえには、山ほどの仕事がある。
ノーマンの日課は長官閣下しだいである。
午前八時を時計がうてば、ノーマンは長官閣下の部屋にはいって、カーテンをひく。
チャーチルはいつもの習慣で、チョッキを着てベッドのなかにいるか、すでに部屋着に着かえてすわっている。
しかしノーマンがベッドルームにはいっていっても、まだチャーチルは眠っているときがある。
しかしノーマンは時間を八時半以上にはのばさなかった。
ノーマンはいつも静かにゆりうごかし、そして一歩さがってまつ。
ノーマンはこの瞬間のご機嫌で、その日のことを察(さつ)した。
もしチャーチルがブツブツいうときは、その日一日は悪い日である。
もし「おはよう、ノーマン」といえば、その日一日は良いのだった。
ノーマンはすぐにオレンジ・ジュースをさしあげるわけだが、チャーチルはいつも、それをすすりながら窓の外を見た。
ノーマンはいつも、なんとかよい天気であるよう、祈った。
しばらくするとチャーチルは、部屋着のままで窓のところへいくが、雨がふっていたり、くもっていたりすると、ノーマンがベッドをなおしているあいだ、しばらく天気のことをブツブツいった。
|

書斎におけるチャーチル
|

書斎でしらべ物をするチャーチル
|
しかし九時すぎまでに、ベッドで朝食をすませると、その日の仕事がはじまる。
チャーチルは昼食までベッドのなかにいるが、この間(あいだ)のんびり頭をやすめているわけではない。
まずロンドン・タイムスと、デーリー・テレグラフの大きなニュースに目をとおす。
それからほかの新聞にも目をとおすが、このとき共産党のデーリー・ワーカーも、ちょっとのぞく。
それから著作のゲラに目をとおす。そして、文章の言葉づかいひとつにも苦心する。
正午がすぎるとノーマンは、なんとかチャーチルを、ベッドから昼食時間に間に合わせるよう、作戦をたてる。
一番よい方法は玄関にいって、ベルをはげしく鳴らすことだった。
ノーマンは、おおいそぎで戻っていう。
「お客さまが、おみえになりました。」
するとチャーチルは、そばにいる秘書たちへの口述の仕事を、しぶしぶやめていう。
「ノーマン、風呂だ。」
ところがこれがまた、簡単なことではない。
チャーチルはベッドのまくらに背をもたせて、またゲラ校正をはじめる。
一時間だってもまだベッドのなかにいる。ノーマンは何度も湯かげんをみては、温度を調節する。
あるとき、どうせチャーチルは、すぐには風呂にはいらないだろうと思って、一時間くらいすれば、ちょうどいいかげんになるように、かなり温度を高くしておいた。
ところが、このときにかぎって、はやくはいったのだ。
ひと足いれたとたんに、「なんだ、これは!」と、どなられてしまった。
ノーマンはおそろしくて、しばらくかくれていた。
またこんなこともあった。風呂湯のなかでチャーチルの声がするので、ノーマンは「何か御用でございますか?」といった。
「私はおまえをよんだんじゃない。下院の演説をやってるんだ。」
そこでノーマンは、風呂場は重要な演説を考える場所なのだと思った。
午後一時、長官閣下を風呂場からだすのが、ベッドからでてもらうくらいむずかしい。
夫人はいつもバスルームのドアをたたいて「ノーマン、なんとかしてくださいよ。お客さまたちがお待ちですよ」といった。
長官閣下に着かえさせるのも、ひと苦労だった。
絹のチョッキとアンダーパンツを身につけ、さて次はズボンというときになるときまって秘書をよんで、また口述をはじめる。
ノーマンは口述がおわるまで、ズボンを持つたままである。
チャーチルが食堂にあらわれるころには、訪問客はたいてい一時間以上まっている。
長官閣下はさかんにいいわけをしてから、いつもノーマンをよんで、いった。
「ノーマン、どうして、お客さまがおまちになっているのを、知らせなかったんだね?」
ノーマンはこれには、ひとことの返事もせずに、このあまいおしかりをうけながら、いつもニヤニヤと笑っていた。
昼食後のチャーチルは客がいないときは、よく庭園を散歩し、池の魚にえさをやったり、愛犬のループスに、ボールをなげてやったり、借地人と話したりした。
それからベッドルームヘもどると衣類をぬいで二時間ほど、子供のように眠る。
議会開会中でもチャーチルは、院内にベッドルームをつくって午後の眠りをとった。
また選挙で遊説中も、汽車のなかにベッドをつくって眠った。
この午後の眠りで、こんな出来事があった。
あるときチャーチルは、ウィンザーにでかけた。
ある日、突然チャールズ殿下がチャーチルに会いたいとたずねてこられたので、チャーチルの部屋に案内した。
突然の訪問客ににチャーチルはうやうやしく握手をかわして若い殿下と数分間話したが、ハッと気がつくと、シャツとアンダーパンツ姿で立っていた。
顔をあかくしたおつきの役人たちは、チャールズ殿下を案内して部屋をでた。
チャーチルの葉巻きと昼寝は有名だが、これはすべて若いときキューバ革命に参加したときの習慣である。
チャーチルの夕食もおもしろい。メイドが食べ物をいれた小さなボウルをはこんでくる。
それを受取ると、チャーチルは愛犬をまずよびいれて、食べ物をあたえる。
犬が食べおわるまでは、人間の食べ物はでない。
チャーチルは真夜中ごろ二階の書斎にはいるが、隣室のベッドにははいらない。
秘書をよんで、二時間以上の口述をはじめる。
最後にいつもやるのは、頭髪にブラシをかけることである。
「頭髪をたもつ方法はこれだよ、ノーマン」と彼はいつもいった。
いよいよベッドにはいるときするのは、「目かくし」である。
これは朝の光線をさけるためである。こうして十八時間か二十時間の一日がおわる。
|

愛犬をつれて自動車に乗るチャーチル
チャーチルの動物好きは有名である。
馬、犬、ネコ、ブタ、牛、ブラック・スワン、魚、それに一ぴきの黒ヤギ、みんなこれを飼っていた。
黒ヤギについてはこんな話がある。
チャーチルはモロッコの保養地として有名なサルタン領土のマラケーシというところへ、休みを利用して絵を描きにでかけたことがある。
ノーマンも、もちろんお供した。
アトラス山脈の中だが六つの食卓を持っていき、近くの渓流で飲み物のびんをひやして暮らすという、ぜいたくな旅だった。
チャーチルは絵筆をとって、画架のまえにすわったが、「どうもうまくない」といいながらキャンバスをやぶって、新しいのをはりなおした。
もちろんだれも、うしろからのぞくことはゆるされない。
ところがある日、ひと群れの黒ヤギを追うアラブの少年が、つかつかとそばにやってきた。
チャーチルはたちまち、黒ヤギの群れにかこまれた。
アラブの少年は、めずらしそうにチャーチルのうしろから絵をのぞいていた。
遠くからこれを見ていたノーマンたちは、いまにもチャーチルがおこって、少年はどなられるだろうと思ってハラハラしていたが、それどころかチャーチルは黒ヤギたちとふざけはじめた。
群れのなかに一ぴきのやせた弱々しい小さな黒ヤギがいた。
チャーチルはこれに卓上の食べ物をあたえた。
これがきっかけになってそれから毎日、アラブの牧童が黒ヤギの群れを追ってくると、チャーチルはいつもこの一番弱い小ヤギに食べ物をあたえた。 |
|

モロッコの保養地でのチャーチル

74歳の誕生日、自宅近くを馬で散歩するチャーチル
|
そして「はやく元気になるんだよ」と頭をなでていった。
ところがある日、フランス人の運転する自動車がヤギの群れにつっこみ、チャーチルが一番かわいがっていた小ヤギをひきころしてしまった。
このことがわかれば、チャーチルはどんなに悲しむだろう。
そこでノーマンは護衛の一人とでかけて、もう一ぴきのやせた黒ヤギになわをかけてつれてきて、岩かげにかくしておいた。
そしてアラブの牧童が、また黒ヤギの群れをつれてやってきたとき、チャーチルが「小さいヤギは、どこにいる? 食事の時間だよ」というのをまった。
さてかくしておいた場所からひきだすと、このやせた小ヤギはメーメーと鳴きながら、角を立ててあばれまわった。
これにはさすがのチャーチルも、よわった。おまけに、チャーチルの手にかみつくありさま。
「これは一体、どうしたのだ?」と、チャーチルはたずねたが、本当のことは話せなかった。
もしいつもの小さいヤギが死んだことがわかれば、長官閣下はどんなに悲しむだろう。
またノーマンの犬がドアに足をはさまれて、包帯をまいているのを見るとチャーチルは、「二週間ばかり犬の病院にいれなさい。びっこをひいて歩くのを、かわいそうで見ていられないから」といって、二週間分の入院費をはらってくれた。
一九五一年、チャーチルはアメリカとカナダへ旅行に出発した。
多数の随行者をつれて豪華船クィーン・メリー号ででかけたが、大西洋上で新年をむかえるため、チャーチルは随員一同とパーティーをひらいた。
このときノーマンは船員と戦争中の話をして、すっかり時間を忘れていた。すると船内のラウドスピーカーが「ノーマン・マックゴーワンさま、すぐチャーチル氏のお部屋においでください」と放送した。
ノーマンは青くなってとんでいくと、長官閣下の部屋の入り口にえらい人たちが夫人たちとともに正装で、ノーマンをまっていた。
秘書のひとりがノーマンの腕をとらえると
「ああ、よかった。閣下は君がくるまでパーティーを開くのをまとう、とおっしゃるんだ。」
ノーマンはすっかりおそれいったが、ひかえの間に一人立っていたチャーチルは、ノーマンの手をにぎると、
「新年おめでとう、ノーマン」といい、やがて洋上のパーティーが始った。
チャーチルは戦う男だったが、敵ながらも立派な男には非常な尊敬をはらった。
ボーア戦争で敵の指導者だった南アフリカの首相スマッツ元帥が死んだとき、チャーチルは議会でその死を惜しむ演説をして人々を感激させた。
二人は五十年の親友で、チャーチルはスマッツ将軍の忠告には、耳をかたむけてきいた。
チャーチルは社会主義者を攻撃したが、しかし国家の将来を思うあまり、自分の信念をいつわらずに公表する社会主義者は、ふかく尊敬した。
反対党の人でも立派な人は立派なのだ。
一九五一年、労働党をひきいていたアーネスト・ベバンが死んだときラジオで彼の死を惜しみ、イギリスは偉大な政治家を失ったといった。
自分の良心に恥じない堂々と戦う信念の人物に、チャーチルは敵味方の区別なく尊敬をはらった。
一九六五年一月二十四日、二十世紀の偉人チャーチルは全世界の人々の見まもるうちに、その波乱に富んだ九十年の大生涯を、静かにおえた。
イギリス国民は国葬の礼をもって彼の死をおくり、偉大な功績を永遠に歴史のなかにとどめた。
チャーチルが死ぬまぎわに最後に口にした言葉は「私も疲れた」ということであった。
top
**************************************** |