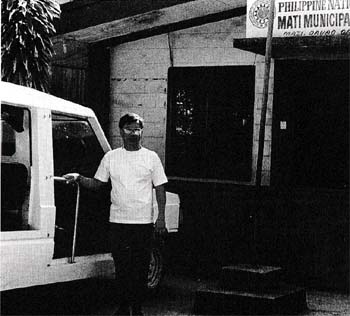|
****************************************
Index 一章 二章 三章 写真集
三章 悲惨な過去を乗越えて
1 戦争に翻弄(ほんろう)された人間のドラマ――クワエ・ヨシトモ65歳 top
|

山の中の一軒家、クワエ一家
国と国とが争いをおこす時、いついかなる場合でも犠牲が出るのは、一般市民である。
第二次世界大戦で、正確には数えきれないほど、多くの尊い人命が失われたが、それはけっして実際に戦争に参加した戦闘員だけではない。 |

山刀を手にするクワエ・ヨシトモ
|
ただ逃げまわるしか方法がなかった、非戦闘員も数多く戦争で血を流している。
親や子や、愛する夫を失って残された人々の苦労は、言葉では言い表わせない。
それにまさるとも劣らないのが、戦争による肉親の生き別れである。
クワエ・ヨシトモをかしらに六人の子供たちが、母親とともにダバオの地に残されて、父親と生き別れになったのは、敗戦翌年の一九四六年八月のことだった。
日本に送還された父に、残留せざるをえなかった母と子が再び生きて父と顔を合わせる機会は、ついに訪れなかった。
父の名は桑江良志(くわえりょうし)といい、一九二六年に数百人の日本人と一緒に、ダバオに入植した。
彼らは商業と農業に従事するのが目的で、マニラ麻畑の労働が主だ。
桑江は沖縄県出身で、一行の中には沖縄や九州から渡った人たちが多かった。
桑江が移住したのは、ダバオの町の西側に位置するトリルからまだ奥に入ったバヤバスというところで、大きなマニラ麻畑の一角だった。
フィリピンに出稼ぎに行った日本人の多くは独身だったが、中にはすでに日本で結婚し、妻子を日本に置いて働きに出た者もめすらしくなかった。
現在、アジアから日本に出稼ぎにきている外国人労働者を思い浮かべてみれば、一九二〇年代後半(昭和初期)の日本の事情が想像できよう。
つまり、それだけ当時の日本、とりわけ農村地帯が貧しかったということである。
桑江良志の場合も沖縄に、妻と子三人を置いてきた。
昔よくいわれたことはだか、良志もおそらくフィリピンで“一旗あげ”(財産をつくって)、“故郷に錦を飾る”つもりだったに違いない。
その頃は、ダバオへ行けば大いにかせげるといううわさが、日本で広がっていたようである。
ともあれ桑江も、ダバオで成功した一人だった。
マニラ麻で金を貯めた桑江は、その後トリルの町へ出て、馬車引きを始めた。
人や物をはこぶ馬車引きでかせいだ金て、トリルの中心街に一軒の家(ビル)を買い、それを改造して「沖縄イン」という名の宿屋を経営した。
それだけ商才があったということだ。
日本に妻や子を置きながら、良志は現地でバゴボ族出身の娘アキータ・オキと知り合い、一緒になった。二重結婚である。
一九三二年に、二人の間に生まれた長男がヨシトモで、後に一男・四女が続いた。
良志がトリルの町で馬車引きをやっていた頃は、毎週日曜日になると、そこから二五キロもあるバヤバスの家に帰ってきたという。
子供たちにとっては、よきパパだったわけだ。
「父は体格がよくて健康でした。
日本人の子として、私たち子供のしつけはきびしかったが、それも今考えると大変ありかたいと思っています」
――ヨシトモの思い出の中の父親像は、しつけこそきびしいが、ふだんはやさしくて、親切だった。
近くに同郷の沖縄出身者がいて、休みの日にはみんなが集まって、三味線や三線(蛇皮線)を鳴らし、琴やオルガンを弾き、にぎやかに歌ったり踊ったりしたという。
マニラ麻の栽培を中心に、桑江良志のように事業でそれなりに成功したダバオの邦人社会の繁栄は、そうながくは続かなかった。
第二次大戦が始まり、日本とアメリカとの戦争がフィリピン全土を戦場と化したことによって、豊かだった日本人入植者たちの生活は、根こそぎ破壊されていく。
“故郷に錦を飾る”という夢は、無残にもまぼろしとなり、消えてしまった。トリルにあった良志の宿屋「沖縄イン」も廃業し、バヤバスの家族のもとに引っ込んだ。
その後良志は日本軍に徴用され、トリルのバゴに駐屯していた陸軍部隊の炊事係をやらされた。
しかし、米軍の進攻にともない、部隊はもっと奥のタムガンに移動することになり、部隊を離れた。
それから敗戦を迎えるまでの苦労は、かろうじて生きのびることができた他の日本人、日系人と同じことだった。
ヨシトモがその時のことを記憶に焼きついているのは、食べる物が何もない日が何日も続いて、ひもじい思いをしたことだ。
敗戦により、アメリカ軍の命令でヨシトモの父良志はダリアオンの収容所に入れられることになった。
その前夜、バヤバスの家で家族そろって食事をした。
ヨシトモはその夜、父が子供たちを次々に抱きあげては頬にキスをし、母は涙をためてやさしい言葉で「さようなら」といったことを、今でも覚えている。
しかしそれがこの世での、父親との最後の別れになろうとは、考えも及ばなかったようである。
ダリアオンの収方所から、四六年、父良志は日本に送還され、着のみ着のまま沖縄へ戻った。
その後は、日本・フィリピン両国とも戦後の混乱のため、音信不通となる。
戦後フィリピンでは、戦争中日本軍が行なったありとあらゆる不法行為のしっぺ返しで、日本人と見ると敵視され、迫害された。
父親が日本に還されて、母親と一緒に残された六人の子供たちは、それまでの日本名も日本語も、一切使うことが許されないことになる。
長男クワエ・ヨシトモは、EUSTOMOOD KUAYという名にかえ、誰が聞いてもフィリピン人と思えるようにした。
カズコはELINAに、ヨレノリはRAFAELというように、五人の弟妹もみなフィリピン名を名乗ることになる。
それだけでなく、日本人の子だと思われるすべての証拠書類は焼き捨てた。
父親の貯金通帳やパスポートはむろんのこと、家族の写真も破り棄てた。
そうしなければ、日本に恨みを持つフィリピンのゲリラから、「敵(日本人)の子」としていじめられ、狙われるからである。
フィリピン残留日系人の多くが、父親は日本人であると証明するものを持ち合わせていないのは、こうした事情が大きく響いている。
フィリピン人になりすませたことで、ヨシトモの弟妹たちの中には小学校を無事卒業できた子もいる。
しかし、十分な教育を受けるに至らなかっだのは、戦争によって財産を奪われ、貧乏に追い込まれたからである。
|

裏側から見た家、かなり痛んでいたが、その後修理した
五九年の夏、クワエ一家のもとに一通の手紙が届いた。
それは沖縄から出たもので、そこには日本に送還された父、桑江良志(りょうし)が、病気で亡くなったとあった。
敗戦後の大変な時代に生き別れた父が、もう還らぬ人となったという悲しい知らせだ。
母も子供たちも、父が死んだからといって、まだ見たこともない日本の沖縄へなど、とうてい訪ねていくことはできない。
戦争の傷跡は、後々まで人の心を苦しめつづけるものである。
七一年になって、思いがけない人物がヨシトモを訪ねダバオにやってきた。
戦前、バヤバスで桑江一家の近くに住んでいた大城(おおしろ)ユウイチだ。 |

バナナの木の手入れをする
|
大城は父良志と同じく、戦前沖縄からダバオに入植し、敗戦後日本に送還された一人だった。
二人は抱きあって、二五年ぶりの再会をよろこんだ。
ヨシトモは大城から、初めて父親に関するすべての話を聞くことができた。
沖縄へ帰ってからも、桑江と大城は深いつき合いがあったからである。
五九年に良志が亡くなる前、大城を枕元に呼んでこう言った。
「私はもう長いことはないだろう。そこであなたに頼みがある。
どうかフィリピンへ行って、残してきた子供たちに会ってはくれまいか」
――その約束を果たすために、大城はわざわざダバオにやってきてくれたわけだ。
その時初めて、父良志がフィリピンへ来る前に結婚していて、二人の子供がいたことも聞かされた。
それからは、大城は何回となくフィリピンを訪問し、そのたびに桑江一家を訪ねた。
大城の招きで、ヨシトモが初めて父の祖国の地に降り立ったのは、九四年のことである。
「父が住んでいたところに案内されて、感無量でした。
行くまでの重い気持ちが、軽くなったような気がしましたよ。
腹違いの兄が三人いると聞いていたが、一人しか会えなかった。
もう八五歳になるという兄に会った時、涙を流してよろこんでくれました」
大城が持っていた昔の写真を見て、「うんこれだ、間違いない」と、たがいに確認しあったという。
ヨシトモは一九日間沖縄に滞在し、父の親類にも会い、あちこち名所・旧跡を見せてもらった。
滞在中、大城はヨシトモに、「日本に住まないか」といって一軒の家を指さした。
大城の店(そば屋)の後ろに家が建っていて、そこには今だれも住んでいないという話だった。
「たしかに日本は、フィリピンとは大違いだ。
道は舗装されているし、みんな乗用車を持っていて、生活水準は高い。
でも私はこっちで生まれてフィリピンでいろいろ責任があります。
いいなあとは思っても、それはできない」――それがヨシトモの答えだ。
今、クワエ・ヨシトモが住んでいるのは、トリルから三〇キロも奥に入った、バラカタンの山の中の一軒家である。
むろん、電気もガスもない。
九六年の八月、初めてここへきたときは、家がかなり傾いていたが、年が明けて再度行ってみると、新しい材木などが立てかけてあり、目下補修中。
それも人だのみでなくて、全部自前でやる仕事だ。
みんな町にあこがれて山を出ていくのに、どうしてここに住むのか、理由を聞いてみた。
「みんな都会の生活にあこがれる。
テレビや電気洗濯機など、そういうものをぜんぜんいらないとは主わない。
でも都会では、電気から水から、野菜や果物でも、すべてのものがお金がなくては手に入らない。
こっちにいれば、なんでも自分でつくって食べられる。
だから、電気やテレビなどなくても、こっちの方がいい。
第一、空気がきれいだし、健康的ですよ」
たしかに、フィリピンでも大都会の町中は車があふれ、道を歩いているだけでノドがせきこむ思いをすることがしばしばだ。
ヨシトモの孫がとってきてくれたヤシの実のジュースをのみ、樹で熟したマンゴやバナナを口にすると、本当においしい。
日本で食べるものとは大違いで、しあわせな気分になれるから不思議だ。
人間は文明の利器で生活が近代化し、それをだれもが世の中の進歩だと思っているが、ひょっとしたら、どこかが狂っているのかもしれない。
クワエの暮らしぶりをつぶさに見て、都市化や近代化によって人間は失うものも大きい、という思いを深くした。
日本人との関係で、クワエ夫妻にとってはもう一つ、忘れられないことがある。
しばらく前のこと、ヨシトモは日本兵がフィリピンのゲリラに殺される夢を見た。
それも二度、三度と続くので、妻のアナに話すと、実はといって、アナが古い話をもちだした。
それはこういうことだった。
まだ二人が結婚する前のこと、ちょうど日本が戦争に敗けた頃である。
クワエ夫妻が住む家から五〇〇メートルほど行った、今では一家の畑になっているところに家があり、そこにアナたちが住んでいた。
ある日、病気だった母が死んだ。そのとむらいの日に、二人の日本兵がやってきて、何か食べ物をくれという。
怖かったが、おとなしそうな兵隊で、そう危険も感じなかったので食べさせた。
死んだ母を埋めるとき、男手がいないのを見て、日本兵が母をかかえ手伝ってくれたりした。
今はもうないがその家は二階家で、アナたちは二階に住んでいた。
一晩だけ泊めてくれといわれ、アナたちは二階に上がり、日本兵は下にいた。
うす暗くなった頃、フィリピンのゲリラが大勢きて、外で銃声が聞こえ、日本兵がつかまえられたようだ。
ややしばらくして、大きな声で「助けて」という叫び声が聞こえ、あたりは静かになった。
翌朝行ってみると、マンゴの木の下に、二人の日本兵の胴体だけがあり、首はなかったという話である。
それを聞いたヨシトモは、自分が見た夢とあまりにも似ているのにおどろいた。
そこで日本のお盆の日に当たる七月一五日に、その場所へ行き、線香はないからローソクを立てて二人で手を合わせた。
不思議なことにそれからは、二度と日本兵が殺される夢は見なくなったそうである。 |

このマンゴの木の下で、日本兵二人が殺された
|
ヨシトモ自身は日本に往むことは考えていないが、クワエ一家と日本との関係は深まっていく。
沖縄の大城や父の親類はひんぱんにダバオを訪れ、数年前には娘のクワエ・テルマが日本に一年以上留学した。
テルマは四人の子持ちでありながら、日本で日本語を学び、助産婦の資格をとった。
今はトリルにある「医療センター」(日本・フィリピンボランティア協会の支援で日系人会が運営)で仕事をしている毎日だ。
しかし、二重結婚という複雑な事情もあって、フィリピンで生まれたヨシトモ兄妹の名は、日本人桑江良志の戸籍には入っていない。
ヨシトモが求めているのは、子供たちが将来、日本に自由に出入りできるように、自分が日系人であるというなんらかの証明である。
2 土間に埋めた自爆死の父の骨――カトウ・タツ68歳 top
工事はマニラとバギオを結ぶ難所「ベンゲット」の道路建設で、フィリピンを支配したアメリカの植民者が、猛暑の首都マニラの避暑地として、高地で涼しいバギオに目をつけたということである。(16ページ参照)
一九〇五年に道路が完成した後も、加藤関造はバギオに残り、ゴボウを栽培し、農業を営んだ。
現地人の女性との間に、タツほか八人の子が生まれた。
第二次大戦前のバギオには、父が日本人、母がフィリピン人という家が三〇〇軒以上もあったという。
戦火の中で、二人の男の兄弟が死に、べつの兄はフィリピン人の抗日ゲリラに殺された。
タツにとってもっともつらい思い出は、近くの防空壕で、父と叔父の二人が自爆し、自ら命を絶ったことだ。
進攻してきたアメリカ軍やゲリラにつかまるのを恐れてのことだった。
それを目の前で見ていた女たちは、二人の骨を拾い、箱にいれて大事にしまって、家を建て直した後も、この土間のたたきの下に埋めてあると話す。
父たちを失って、家族はみんな山へ逃げた。
その後で、今よりも大きかった昔の家は、焼かれてしまった。
今の家は、かなりの年月を経た後、同じ場所に建て直したものである。
生残ったタツや姉のキクたちは、父の名を捨て、母の姓を使い、日本語も一切口にしなかった。
「バギオの日本人学校を出たんだけど、日本語は使わないから忘れた」というタツ。
さいわいにしてタツの名は父の戸籍に入っていたが、通称オタチとなったのは、そうした経過からきているようである。
なぜか姉キクの名は、戸籍にはない。
タツはフィリピン人と結婚し、八人の子を生んだ。
三男は弁護士になってバギオで活躍し次女はアメリカで看護婦、畑仕事は末の男の子が手伝う。
日本人の父、関造の思い出につながるのは、地下に埋葬した骨と一枚の写真と、父親のあとを継いだゴボウづくりだ。
3 日本・フィリピンのかけ橋に――カルロス・テラオカ66歳/マリエ・テラオカ63歳 top
|

バギオの日本国名誉総領事カルロス・テラオカ(兄)
二千人を超すフィリピン残留日系孤児の中で、最も成功し、社会的にも高い地位を占めている人といえば、日系人ならだれでもその名をあげるのがカルロス・テラオカだ。
長年にわたって、千人を超す林業会社グループの代表をつとめ、それを退いたあとは広大な農場の一角に個人滑走路をつくり、小型機やヘリコプターの操縦かんをにぎって、自宅と往復したりする。
アジアでは初の、バギオにおける日本国名誉総領事にも任命された人物だ。 |

母と兄弟の墓の前に立つマリエ・テラオカ(妹)
|
カルロスの父、寺岡宗雄は山口県大島郡大島町の農家の長男で、一九一〇年代にマニラに渡った。
年は一六歳、大工の弟子としてマニラ近郊で働いていた。
そのうち肺炎にかかり、空気のよいバギオに移る。
一人前の大工になった宗雄は、建築請負業を初めて成功し、日本から大勢の大工を呼ぶほどになった。
フィリピン女性アントユーナ・バウテスクと結婚して、六人の子が生まれた。
カルロスは一九三〇年生まれで、三男だ。
後には名だたる成功者となるカルロス・テラオカだが、その半生は、個人の力では抗しきれない、戦争という名の壮大な暴力行為の渦にまきこまれて、辛酸をきわめたものであった。
悲劇の象徴がテラオカ家の墓碑銘である。
右上の写真をよく見ていただきたい。
一番上は母で「ANTONINA・B・TERAOKA=一八九八−一九四五」とある。
続いて長男「VICTOR=一九二五−一九四五」 次男「SIXTO=一九二七−一九四五」 次女「CATALINA=一九三六−一九四五」 四男「EDWARD=一九三七−一九四五」
――母と兄妹四人の名が刻まれている。
しかも没した年がいずれも「一九四五」とあり、これは日本が太平洋戦争に敗れた、その年をさしている。
父、宗雄はすでに戦前に病死していたから、寺岡家の母と子六人のうち五人までが、この年一年で世を去ったということである。
しかも、その死に方がすさまじい。
長男は日本の憲兵隊にスパイの容疑をかけられて射殺され、次男は逆にフィリピンの抗日ゲリラに、殺された。
あとの三人は、避難した山中で米軍機の爆撃にあい、母は即死、次女と四男は重傷を負って満足な手当ても受けられず、その後亡くなった。
七人家族であとに残されたのは、三男カルロスと、その妹で長女マリエのたった二人だけだ。
墓のうしろに立っているのがマリエ、その人である。
戦争というものの非情さ、残酷さが、寺岡一家を集中的におそったということだ。
あらためていうまでもなく、戦争の被害は当時フィリピンに在住していたすべての日本人、日系人におよんだが、これほど不運で悲惨なケースはありえないようだ。
それは単に、亡くなった人数の問題ではない。
人数だけでいえば直撃弾を受けて一家全滅という事例も少なくないからだ。
テラオカの場合は、敵・味方にわかれた日本軍とアメリカ・フィリピン軍のはざまで、こともあろうに二人の兄が双方の手にかかって殺されたということである。
母と弟・妹も爆撃が原因で死亡した。ひとたび戦争となれば、民衆におよぼす被害に敵も味方もない。
軍人や政治家がしばしば口にする「正義」も何もあったものではない。
あるのは非情な大量殺りく行為のみである。
日本が戦争に敗れたあと、生残った兄と妹は九歳になる従兄弟と三人で山をさまよい、放浪しているところを米兵に保護されトラックに乗せられた。
捕虜収容所へ連れていかれる道々の途中で、フィリピン人から罵声をあびせられ、石を投げられたことを、マリエは今でも覚えている。
兄カルロス一四歳、妹マリエは一一歳だった。
戦争で大黒柱だった母や兄たちを失い、すべての財産を奪われた二人の幼い兄妹はフィリピンから日本へ送還された。
二人にとって日本は、父が生まれ育った国といっても、まだ見たこともない遠い国である。
ただ祖父がいるということだけを頼りに、戦後一番最初の引揚船に乗り、一路山口県大島町に着いた。
祖父とは全くの初対面だったが、カルロスとマリエの来訪を、あたかも息子の宗雄が生きて還ったかのように思い、よろこんだという。
二人は地元の小学校と中学に再入学したが、フィリピン女性との混血二世のため日本人より色が黒いのを理由に、「黒んぼ」とはやし立てられたのがつらかった。
カルロスは高校卒業後、国家試験に合格して無線の免許をとり、無線機を売ったり、ラジオの修理などをして、早くから経済的に自立していた。
しかし二人が日本で暮らして行くうえで、大きな問題となったのが国籍である。
二人とも、父の戸籍にその名がいれてなかった。
当時はしばしばあったようだが、父、宗雄はフィリピンで生まれた子供たちの出生届けを出していなかったからである。
裸同然で日本に来た男妹は、父や祖父との関係を証明するものは、何一つ持っていなかった。
結局「無国籍」という扱いだ。
はるばる海を渡り、祖父にめぐり会えだのはよかったが、無国籍で日本人として扱ってくれない。
その仕打ちにうちのめされたような気分になるのは当然だろう。
この問題について、日本政府は「二一歳の誕生日を迎えた時点で、自分の判断で国籍を選べ」という態度だ。
まずカルロスが、その選択を迫られる年齢になった。
この辺の事情は大野悛著『ハポン』(第三書館)に詳しく述べられており、ここではそれを引用することにする。
「そんな折、国際赤十字社を通じ、亡き母アントニナの従兄弟からカルロスのもとに『バギオに帰ってこい』という手紙が屈いた。
従兄弟の手紙によると、寺岡一家が住んでいた土地も家も戦後、フィリピン政府に没収され、アカの他人に貸与されているという。
カルロスには、父の建てた家がいつのまにか他人のものになっていることが耐え難かった。
そのため、二一歳を迎えた一九五二年、躊躇(ちゅうちょ)なくフィリピン国籍を選び(中略) カルロスは、七年開暮らした日本をあとにした。
結局カルロスは裁判に持ち込み、最高裁まで控訴して争った末、自分の土地と家を奪還することができた。」
(同書73ページ) |
父が建てた家や土地を、何としても取返したいというカルロスの願いが、フィリピン国籍の選択につながったということは、これでよく事情がのみこめる。
しかし、それ以前に日本政府が、いたずらに「無国籍」という冷たい扱いをすることなく、敗戦時の特殊な事情をくんでもっと温かくカルロスに接していたとしたら、果たして、「躊躇なく」日本国籍を袖にしたがどうかわからない。
いずれにせよ、そうした日本での経験がカルロスにとって、「フィリピン人になることを決意してバギオに戻ったあと、強くたくましく生き抜くバネになったことは事実のようである。
バギオに帰ってから、カルロスは保険屋をやり、トラックの修理をやったりもした。
そのうちに材木会社に勤めるようになり、カルロスが生まれ育ったバギオの地で、成功をおさめることになる。
手がけた仕事は山から木材を伐採し、それを製材する林業である。
その昔、日本からバギオに来た父、寺岡宗雄が、犬工と建築請負業で成功したのと、どこかで相通じるものがあるようだ。
三五年間手にかけた林業を退いてからは、パンガシナン州の農場経営に余念がない。
一〇〇ヘクタールを超える農場にはマンゴ、山地にはマホガニーの苗木が育つ。養鶏・養魚も事業化した。
およそ日本では考えられないのは、農場の一角にミニ飛行揚があることだ。
小型航空機のセスナ二機と、ヘリコプター一機を所有し、週末にはみずからそれを操縦する。
戦争中、予科練にあこがれていたというカルロスの空への夢が、半世紀後に平和な世界で実現したということだ。
一方、無国籍のまま日本に残っていたマリエも、二二歳になるのを待ってフィリピン国籍を取得し、たった一人になった兄のもとに戻ることにした。
しかし、戦後一〇年経つたといっても、戦時中の日本軍の蛮行はフィリピン人の記憶に焼きついており、対日感情は悪かった。
それまで日本にいて、日本語しか話せなかったマリエがもっともつらかったのは、
「兄に日本語で話しかけても、一切、口をきいてくれなかった」ことだ。
日本では国籍を与えられず無国籍だったが、日本人の血が流れているというだけで、フィリピンでは迫害されたからだ。
カルロスにしてみれば、フィリピン人として生きることを決意した以上、妹にもそれを求めて、けっして甘やかすことはしなかった。
マリエはバギオに着いてから一ヵ月間、ほとんど泣き通したという。
事業のかたわら、カルロス・テラオカはバギオ日系人会の会長をつとめ、日系人の地位向上や、国籍回復の運動にも力を入れている。
|

バギオ日系人会があるアボン。この中に総領事室もある
まだ多くの日本人たちが、日本名を隠して“ねずみのような暮らし”を余儀なくされていた七〇年代の初頭に、バギオの地で初めて日系人を一人ひとり訪ねて、「もう心配しなくていいわよ」と手を指しのべたのは、聖フランシスコ修道会のシスター・海野だった。
その仕事を引きついだのが、テラオカ兄妹だ。
シスター・海野がはじめた「バギオ教育基金」の仕事も、カルロスが受けついでいる。
日本からボランティアを募って、子供たちの教育のための「里親制度」をひろげ、四人の小学生からスタートした教育基金の受給者が、すでに千人を超えている。
この対象は日系人だけでなく、一般のフィリピン人の子供にも広げているのが特徴である。 |

アボンの前に集まった日系二世

カルロス・テラオカ夫妻
|
九五年四月二七日、バギオでは「解放五〇周平記念」のパレードが行なわれた。
三〇〇人以上の日系人のほか、フィリピン人、アメリカ人も参加しての大慰霊祭となった。
その席上、日本の松田慶文大使(当時)から、カルロス・テラオカを、バギオの「日本国名誉総領事に任命する」といわれ、臨席していたラモス・フィリピン大統領からも「おめでとう」といわれる場面があった。
四〇〜五〇年前、戦後直後の日本で、無国籍という冷たいあしらいを受けたテラオカが、当の日本政府から世界で六人目という「名誉総領事」に任命されるとは、一体、誰が想豫できたろう。
歴史の皮肉としかいいようがない。
カルロス・テラオカが、名誉総領事として心掛けているのは、フィリピンと日本との「懸け橋」になることだ。
「バギオ日系人会」の会長としては、日系人の国籍回復に力を入れている。
ただし、本人はきわめて冷静だ。
それは日系人が日本の国籍を取得した場合、フィリピンでは外国人の扱いになるからだ。
「外国人では土地を持つことができなくなり、すでに土地を持っている人はどうなるのか」
――そうした解決を求められる問題があるからである。
カルロス自身も、日本人の子であるということの証明は申請しているが「日本国籍を取得したいとは思わない」という立場だ。
それが、カルロス自身の苦い体験を通しての結論であるだけに、重いものが感じられる。
4 祖父の「ルーツ」を探したい――ニシグチ・マウリロ51歳 top
|
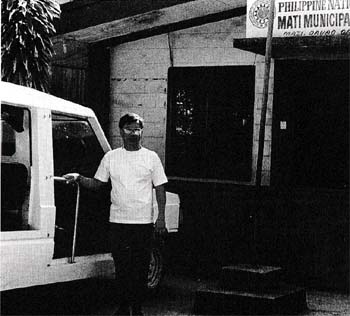
マテイ警察署前のマウリロ
|

日系二世と三世のニシグチ親子
|
ダバオ市内から東ヘ一七八キロ、ダバオ・オリエンタルの町マティヘ行く。
朝の七時半に出発して、途中何ヵ所か立ち寄り、夕方近くにマティの町中に入った。
目指すのはこの町の警察署だが、警察に人を探してもらおうというわけではない。
そこに勤務するニシグチが、目当ての日系三世だ。もう仕事を終えて帰ったというので、自宅を訪ねた。
バラック建てが密集している細い露地を抜けて、探しあてた家は二階家だ。
案内役のハギオ・ユキトシが声をかけると、恰幅のいい五十年輩の男が顔を出した。
ニシダチ・マウリロという日系三世だ。
ダバオの日系人会のメンバーだから、ハギずとはすでに顔見知りの仲で、さっそく二世の父親を呼んでもらう。
父は隣の家に住んでいる。
二人を待っている間に、この国の警察官の社会的地位がどんなものか、ハギオに聞いてみた。
ハギオによると、国や地方都市の公務員の中でもっとも給料が高いのが教師で、逆にもっとも低いのが警察官だそうだ。
ポリスマンの月給は四千ペソ(円にして一万六千円=九五年当時)くらい。
きびしい仕事のわりに給料が安いから、悪事に走る警察官が少なくないという話である。
二人でそんなやりとりをしているうちに写真を撮るといったからマウリロは制服に着替えて父と一緒に部屋に入ってきた。
日本語の会話は通じないとわかっていても、あんな話をしていたから、ドキッとしたことを覚えている。
ニシダチ・シゲオは一九二三年、この地で生まれた。
シゲオの父は西口シゲジローといい、和歌山県の出身。
母はこの土地の出のバレリアーナ・レイズ。シゲオは両親の結婚証明書を大事に持っている。
話がそこまで進んだところで、今夜、泊まるところをまだ決めていないことに、ハギオが気がついた。
悪いけれども、ニシグチの家には、私たちが寝られるスペースはなさそうだ。
警察官のマウリロがいうには、マティは地方の町で、ダバオ市内にあるようなホテルなどない。
あるのは商用や働きにきた人たちが泊まる、簡易宿舎のようなものだそうだ。
そういうことになるとマウリロはお手のもので、さっそく私たちを案内してくれた。
あいにくこの日は満杯が多く、三ヵ所目でようやく泊まれるところがみつかった。
ただし、部屋は六畳間ほどあるが、真ん中に大きなダブルベッドが一つあるだけの殺風景なもの。
ここに男ども三人が寝るのかと、ためらいもあったが背に腹はかえられない。
結局、ダブルベッドにハギオと運転手、私はコンクリートの床に補助ベッドで我慢することにする。
宿舎が決まると、マウリロが食事に行こうと言いだした。
表で長い串に肉をさした、焼き鳥ならぬ豚を焼いている店で、フィリピンでもっとも多く飲まれているビール「サンミゲル」で乾杯。アルコールも手伝ってか、マウリロの口の滑りがよくなった。
「五十年ぶりに日本人に会えてうれしい。
オレはフィリピン国籍を持ち、フィリピン国家警察の一員として公務を遂行している。
しかし、本当のところは、フィリピン人より日本人に親しみを感じる。
というのは、オレの体に流れている血は、祖父シゲジローから引きついだ、日本人の血が入っているからだ」 |
|

マウリロの住むマテイの町中。ここは台風も地震もないので、つぎたしの家でも大丈夫
|
大変なごきげんで、今夜の食事は「オレがおごる」と言いたした。
先刻、ハギオから聞いた警察官の安月給がチラッと頭をよぎったが、せっかくの好意だから甘えることにする。
ランタナの自宅での話と、ビールを飲みながらの会話をまとめると、次のようなことになる。
祖父シゲジローは農業を経営し、かなり広い土地を祖母の名でもっていた。
シゲジローは戦前、三六年に病死し、父シゲオは日本軍の軍属となった。
戦争で家屋敷はすべて焼かれてしまったが、土地だけが残っていた。
日系人の土地所有ということで、いろいろあったが、裁判官に助けられ、一千アールほどの土地がニシグチの所有になっている。
その土地の半分を市に寄付して、そこにメモリアルホールを作る計画だ、と。
日系三世のマウリロの話は、アルコールの勢いもあるから、多少割り引きする必要があるかもしれない。
ただ、ニシグチのことで気がついたのは、同じ日系人といっても、フィリピンの地域社会でフィリピン人として、それなりに地位や財産を保有し、堂々と生きている人もいるということだ。
日系人イコールかわいそうという発想では、あまりにも単純すぎるようである。
マウリロは、その後私あてに手紙をよこし、祖父の親類さがしを依頼してきた。
和歌山県出身の祖父は西口シゲジロー。シゲジローの父も出生地は和歌山県で、西口オトマツとあった。
関西にいる友人に、何か手がかりでもつかめるかと思って依頼したが、今までのところ、何もわからない。
要するに、ニシダチ・マウリロが求めているのは、自分のルーツ(先祖、源)をさぐりたいということである。
「母をたずねて三千里」ではないが、だれでも自分の祖先がだれで、どこで生まれ、何をしていたか、ということを知りたいと思う。
ルーツをさぐることによって、初めて自分のアイデンティティ(存在証明)が確立することになるからだ。 |
5 日本人として生まれてよかった――タナカ・アイコ66歳 top
|

日本青年館であいさつするタナカ・アイコ
「日本人の子として生まれ、日本人として育てられてきました。 一九四一年に戦争が始まり、それまでの豊かな生活がメチャメチャになりました。
戦争で父は亡くなり、家族は散りぢりに、豊かな生活からとたんに貧乏な生活にかわりました。
日本名をフィリピン名に変え、愛もなしに結婚して、みんなのために犠牲になりました。
あの戦争さえなければ、こんなことにはならなかった」 |
――澄んだ女性の声が、日本青年館の大ホールにひびき渡った。
一九九五年六月、戦後五〇年目に実現した、フィリピン残留日系二世三二人の集団帰国時の訴えだ。
正確な日杢語で話すその人、タナカ・アイコは、からだ格好といい、顔の表情にしても、どこからみても日本人だ。
住む土地や気候風土がちがい、食物がちがうところに長年いると、その土地の人にどこか似てくるものだが、アイコの揚合はそんな感じがしない。
父は熊本県出身の田中吉郎、母はアリガン・オヨ・バゴバで、ダバオのバゴボ族出身だ。間違いなく日系二世である。
田中家では母が父の意をうけて、子供たちを日本式にきびしくしつけ、家の中では日本語しか話させなかった。
それが六〇歳を超えた今日のクナカ・アイコにつながっている、と本人は思っている。
|

参議院会館で報告を聞く。中央がタナカ・アイコ

入植当時のダバオ風景(ダバオ会提供)
|
父、吉郎がフィリビンに移住した最初の目的地は、ルソン東北部のベンダット州である。
首都マニラから、避暑地としてアメリカ植民者が開発しようとしたバギオに通じる、ベンゲット道路工事に出稼ぎに行く。
今世紀の初め、明治の中頃のことである。
ベンゲット道路が完成したあと、ミンダナオ島ダバオ州のカタルナルに転住。
後にダバオがマニラ麻の栽培で繁栄するようになる、開拓初期の草分け的存在の一人となった。
ダバオ・パラカタンに麻山一四町歩(約二四ヘクタール)を獲得し、そこに永住の決意をして、現地の娘と結婚した。
暮らしは豊かだったようだ。
五人の男と四人の女が生まれ、アイコは四番目の子で三女。一九三一年の誕生だ。トリルの日本人小学校を卒業した。
「母は日本語を歌から覚えたようでした。
咲いた 咲いた チューリップの花が とか、白地に赤く 日の丸染めて とか、よく歌っていましたよ。
日本の字も書けました。
子供たちが家で日本語を習っている時は、横に座って、一緒に勉強していました。
父は兄に向かって『しっかり勉強しろ』とよく言いましたが、きっと兄には日本へ行かせて、日本の教育を受けさせるつもりだったようですね」
父、吉郎はアイコには言わなかったが、兄吉次には「白いいい服を着て日本で生活するんだよ」と話していたのを、今でも覚えている。
当時の日本人の家庭では、男の子には教育を仕込んで立身出世を期待するが、女の子は嫁に出すだけだから教育はいらないというのが普通だった。
田中吉郎もその考えに近かったようである。
しかし、家の中では、現地のチャバカノ語もバゴボ語も使わせない。
父も母も必ず日本語で話し、子供たちには日本式の行儀やあいさつを教え、整理整頓にもやかましかった。
戦争を境に大変な紆余曲折(うよきょくせつ)はあったにしても、そうした育て方をされたことがアイコにとっては、後になって大いに役立ったことは事実である。
二四ヘクタールもの土地にマニラ麻を栽培していたから、大勢の労働者を使っていた。
多い時には三五〜四五人のフィリピン人がそこで働いていた。
アイコの記憶では父はあまり働かなかったが、母は毎日農場へ出て監督したり、労働者と一緒になって働く働き者だった
豊かな暮らしが一変したのは、四一年一二月に戦争がはじまってからだ。
はじめ父は、日本軍の飛行場設営に勤労奉仕、後に海軍の軍属として徴用された。
長男の吉次は現地で召集され、入隊した。
アイコも飛行場の滑走路をづくるため、基礎の石並べにかり出された。
フィリピンで生活していた、一般人の日本人とその子たちが、老若男女を問わず日本の戦争政策に組み込まれ、フィリピンにおける軍事行動に直接協力させられたということである。
営々として築きあげた家や財産も、日本軍の敗退、敗戦と同時に、すべてを失うことになる。
この戦争で、アイコの父は病死し、末の弟は砲弾で幼い命を奪われた。
戦争に負けて山へ逃げ込んだ時、父吉郎もアイコたちと一緒だった。
しばらく谷底に隠れていたが、食物もなく、みんな栄養失調になった。
すでに大勢の兵士や民間人がアメリカ軍につかまり、収容所へ送られている頃だ。
もう逃げ切れないと思った父は、母に「みんなで出ていきなさい」と投降をすすめ、自分一人だけ手榴弾を持ってその場を立ち去ったという。
母とアイコたちが白旗をもって行く途中、日本軍の小さな部隊と出会い、「どこへ行くのか」ととがめられた。
「谷底にいたけど、もう食べる物が何もなくて、子供たちの具合が悪くなるばかりです。
バゴボ族のところへ食物をもらいにいく」と母が言いのがれようとした。
すると、母が持っていた白旗を指して「その旗を捨てろ」とどなり、「中尉殿どうしますか」と上官に聞く。
今思い出しても「生きた心地がしなかった」
というアイコ。話しているうちに、その兵士たちと兄吉次が同じ部隊に所属していたことがわかり、九死に一生を得た。
「ここに日本兵がいることを絶対に言うな」と口止めされただけで、無事その場を立ち去った。
父吉郎の死を知ったのは、しばらくしてからのことだ。
家族と別れ、手榴弾をもって山に入ったものの、手榴弾が濡れていたため自爆はできなかったようである。
しかし、何日も食べないでいて栄養失調が悪化し、それと病で、木の蔭にくずれるようにして死んでいたのが見つかったということだ。
敵の捕虜になるのをいさぎよしとせず、自らの命を絶つ自爆や集団自決は、敗戦後フィリピン各地でみられたことである。
日本軍の『戦陣訓』にうたった「生きて虜囚(りょうしゅう)の辱(はずか)めを受けず」の教えが、軍人に限らず民間人の間にも浸透していたわけだ。
田中吉郎は軍人ではなく、たんに徴用されただけの軍属であったが、それだけ戦前・戦中の軍国主義教育が、一般市民の間にも徹底していたということになろう。
生きてさえいれば、日本に帰れたはずである。
父と弟を戦火で失ったタナカ・アイコの一家には、さらにつらい別れが待っていた。
アメリカ軍の収容所に入れられていた兄、吉次が日本に送還されたからだ。
すでに結婚していた二人の姉のうち、長女も日本に還ることになった。
一五歳になっていたアイコは、父がいなくても自分の判断で日本へ行くか、フィリピンに残るかを決めることができたが、さんざん迷ったあげく残ることにした。
それは母親が泣いて引き止めたからである。兄や姉たちがいなくなったので、アイコが残された幼いきょうだいたちの最年長だったからだ。
戦争が終わった後、ダバオの奥、バラカタンでの生活は、恐怖につつまれた日々だった。
日本人の子とわかると「人殺し」とどなられ、さまざまか嫌がらせを受けた。学校へ行こうとすると、途中で男の子が待ちぶせしていて、怖くて行けなかった。
そんなことがたびたびあったため、六ヵ月ほどで学校を退め、以後まともな学校教育を受けられなかったことを、アイコはとても残念に思っている。
そうこうするうちに、結婚話が持ちあがった。相手は中バラカタンの村長の息子である。
まわりでは日本人の子だからといじめられる、まだ幼い弟や妹たちのことを思うと、断ることができなかった。
「母親も病気がちで、妹たちは小さい。みんなを助けるには、結婚するよりしかたがない。
それが親孝行だと思って、愛もないまま結婚したんです。
私の人生にとって、一番つらかった」と語る、タナカ・アイコ。
時は敗戦二年後の一九四七年、アイコは一七歳だった。
「愛のない結婚」でも、二人の間には男三人、女六人、合計九人の子が生まれた。
しかし、子供たちが大きくなるにしたがって、子供の教育をめぐり、夫婦の考え方のちがいがしだいに大きなミゾとなっていく。
夫は、男の子は教育を受けさせて、行きたいなら大学までいかせてもいい。
しかし女の子は読み書きさえできれば、それで十分という考えだ。
直接ケンカになることはなかったが、アイコの頭の中には、自分が学校へ行きたくても行けなかった、その思いが強く残っていた。
「女の子でも、教育を受けたいと思うのなら行かせたい」
――自分と同じ思いだけはさせたくない、そういう気持ちが強くはたらいたようである。
バラカタンの山の中にも学校はあるが、歩いて五キロも七キロもあるという。
子供を学校へやるには都会へ出なければということで、ついに夫と別居するごとになった。
子供の教育のためには、バラカタンを出て、町に住む必要がある。
しかし、アイコの夫は都会に住かのを嫌がり、「どうしても行きたければ、好きにしなさい」といい出す始末。
やむをえず、夫の家を出て町に住むことにした。九人の子供は、いずれもアイコについてきた。
「子供を教育するうえで、私は日本人の子として生まれて、本当にしあわせだった。
誰にでも言うことですが、何の学問もない四〇を過ぎた女を、会社が雇ってくれたのはただひとつ、日本の言葉ができたという理由からです」
最初に就職が決まったのは、日本人が経営する、うなぎ養殖の会社だった。
アイコが幼少の頃、父母が日本人としての教育に力を入れ、日本語を学んでいたことが、ここにきて思いもかけないところで役立った、ということである。
「戦後の二〇年間は、日本人であることを隠すために、日本語は全く使えませんでした。
でも、七〇年代の初め頃、日本から墓参団が来るようになり、その前後から独学で日本語を習っていたんです」
――フィリピン名の「ビニータ・マトゥテ」で通してきたアイコが、堂々と「タナカ・アイコ」を名乗るようになったのも、この頃からのことである。
うなぎ養殖の会社がゆきづまったあとは、同じく日本人の維営するキュウリを大量に栽培する会社に就職。
そこでは通訳と監督が仕事だった。子供たちもだんだん育っていって、大きい子は昼間はアルバイ卜をやり、夜は夜学に通って勉強するようになる。
小さい子は、実家にアイコの母親が健在だったから安心して預けることができた。
上の子三人が大学を終えると、よくしたものでその子たちが、下の妹や弟の面倒をみてくれるようになった。
その頃になると、毎年のように日本人がダバオに来るようになり、通訳をたのまれてその報酬が入るようになった。
みやげにもらう衣類や洋服も、大変役立った。
「日本人に応援されて、ここまでくることができた」というのが、アイコの口ぐせだ。
それもこれも、日本語ができたからである。
八六〜八七年頃から、自分がおぼえた日本語をだれかに残したいと思い、日系人会で日本語を教えることにした。
まだキュウリの会社に勤めていたから、毎週土曜日に仕事から帰って、日曜日に教えたあと、その足で会社に戻る、忙しい生活だった。
|

父親の写真を指差す
そうしたアイコの活動に手を差しのべたのが、「日本・フィリピンボランティア協会」だ。 |

トリルの日系人会館前で息子と

会館内で戦中、戦後の苦労を話すアイコ
|
九〇年にはその網代正孝(あじろまさたか)会長がトリルに土地を買い、そこに会館を寄贈する話が持ちあがった。
それを機にアイコは勤めていた会社をやめ、日系人会の仕事に専念することになる。
九四年に会館はオープンし、地域における日系人会の活動の拠点となった。
むろん、日本語教育も、後継者たちによってずっと続いている。
タナカ・アイコが、戦争によって遠く引き離された日本にいる兄、田中吉次と感激の対面が実現したのは、戦後四三年も経った後のことである。
さらに九一年以降は、父か母が日系二世であることを証明する書類があれば、その子、つまり三世は、日本に就労できることになり、アイコの子供たちもあいついで日本に働きに来るようになった。
九五年六月のフィリピン残留日系人三二人の「集団帰国」の際に、戸籍にはっきりとその名が書かれていたタナカ・アイコは、九人の仲間と一緒に、日本国籍を取得した。
名実ともに、はれて日本人として認められたわけだ。
現在、アイコの子九人は、すべて日本に職を得て、日本で暮らしている。
孫五人のうち、フィリピンにいるのは初孫だけで、あとは日本にいる。
アイコ自身は、トリルの日系人会館に寝泊まりして、「日本・フィリピンボランティア協会」の支援のもとで、日本語学校と日系人会の活動のほかに、地域の医療活動にも精を出す毎日だ。
6 あわてない海の日系人――ヨシミネ・タケモト62歳 top
|

漁師小屋の前に立つヨシミネ・タケモト
|

モスクで礼拝する
|
ダバオ市から北へ七二キロ、北ダバオ州マビニに住むヨシミネ・タケモトの家に向かう。
二度目の訪問だ。
前回撮影に行った時、漁師をやっていると聞き、あらためてじっくりと漁や生活を撮らせてもらおうと思ったからだ。
船にも乗りたいし、それには泊めてもらわなければなるまい。
電話が通じるところではないから、直接行ってたのむほかはない。
通訳兼案内をたのんだハギオ・ユキトシのすすめで、マーケットに立ち寄り、米を買うことにした。
フィリピンでは、まだ何よりも米をよろこぶという話だ。
普通米は一キロ一四ペソ(九六年当時一ペソは約四円)だが、奮発して最高のキロ一八・五ペソの米を一〇キロ買込んだ。
日本円にして七四〇円。
日本よりかなり安いが、物価水準のちがいを考えれば、当地では結構高価なプレゼントになるようだ。
そういえば、日本でも戦後の一時期まで米は“貴重品”の部類で、田舎からのみやげに父母がおおよろこびしていたことを思い出した。
タケモトは沖縄出身の吉峯ミネモリを父に持つ日系二世で、父はマニラ麻畑で働くために日本から移住してきた一人だ。
母はモスレムと呼ばれるイスラム教徒で、モスレムはミンダナオ島に比較的多い。
男二人、女二人の四人兄妹で、うち一人の姉は早く亡くなった。
タケモトは一九三五年生まれで六二歳。
父ミネモリは三八年、つまり第二次世界大戦の開始以前に病死した。
四一年に戦争が始まり、後に米軍が再上陸してからは、母や兄たちと山へ逃げた。
タケモトの思い出の中で、もっともつらかったのは、逃亡生活でろくに食物がなかったことだ。
敗戦時に一〇歳の育ち盛りだから、無理もない。ヤシの実を落として、その芯を食べた。
昼間は米軍の爆撃や機銃掃射から逃れるため、山中に隠れているだけだ。
煮炊きなどもできない。火の煙を敵に見つけられるからだ。
夜になると移動し、食料をさがし歩く。他人の畑と承知の上で、イモや野菜があれば取って食べた。
山中では何もなくなったという。
ヨシミネは日系二世でも、日本語は全く話せない。
戦争中に日本人学校で日本語を習ったが、わずか二週間ばかりで米軍の爆撃が始まり、すぐに中止になったからだ。
戦後は日本語どころか、日本人とも全く無縁の生活が先頃まで続いていた。
浜に出て、海の潮の動きを見ていたヨシミネが立ち上がった。
日本より一時間遅れの、現地の時間で午後三時半を回った頃だ。
井戸端で水を汲み、手足をすすぎ、これから礼拝に行くという。
宗教がちがうといって、ハギオはタケモトと一緒に行くのを引き止めたが、本人がノーと言わないのでついていく。
浜と家との中間にある、コンクリートの建物の中ヘヨシミネに続いて入ると、それがイスラム教のモスク(寺院)だった。
真正面に時計、その両側に窓が開いていて、コンクリートの荒壁にアラビア語だろうか、文字が書かれている。
それに向かって、ヨシミネは立ったり座ったりしながら何回も頭を下げ、ついにはひざまずいて敬虔な祈りをささげていた。
日本でも、海の男たちが漁に出る時は、水神に海の安全を祈ると聞くが、ここでもモスレム流の安全祈願が行なわれているところだ。
広々としたモスクの中には、昼間はほかにだれの姿も見られなかった。
モスクを出て、再び浜へ向かって歩いていく。
今日の漁に、いわしが目的だ。幅の狭い、小さな四人乗りのボートにエンジンがついている。
フィリピンの漁船は、船首から中央にかけて両側に三本の犬い竹を渡し、その両端に竹をくくりつけているのが特徴だ。
船体は細くても、その竹が水面でつっかい棒の役を果たして、横転しないようになっている。
かつお漁には、もっと大きなモーターボートを使うが、今日はいわし漁だから、この小さな船でいく。
日が沈みかける頃、船は猛スピードで沖合いへ進んでいく。
潮風が心地よい。船首に陣取っているのは、ヨシミネ本人だ。
その昔、海のいくさで敵に立ち向かうときの、指揮官の姿が連想されてくる。
その後ろ姿は、まさに真剣勝負そのものだ。岸辺を離れて三〇分も経った頃、船はエンジンを止めた。
音もなくするすると、真っ白い網が海に落ちていく。
幅が一六メートル、長さが三六〇メートルもある網だ。
あたりはもう真っ暗で、遠くに一つ、二つ、明りが海に浮かんでいる。
この船と同じようないわし漁の船のランプだ。
静かに待つこと約一時間、ヨシミネの合図で若い二人が船べりを櫓でたたき出した。
パンパンパンパン――魚を音でおどろかせて、網に入れるのだ。
いよいよ網を引き上げる。銀色のウロコが、石油ランプの光にキラッと光る。いわしだ。
日本の近海でとれるものに比べると、形は小ぶりだが、身がしまっている感じがする。
次々と網にかかったいわしをばけつに入れる。三キロくらいのものだ。
初めて見るフィリピンのいわし漁は、原始的でかなりの重労働といっていい。
ヨシミネの家では、日系二世の親方は指示・監督するだけで、実際に仕事をするのはその息子たちの三世である。
若者でなければ勤まらない仕事だろう。
長い網を海におろし、一〜二時間待って引き揚げるという作業を、一回海に出れば一晩中続けるという。
「昨夜は一四キロしかとれなかった」というから、この時期は大漁とはいえないようである。
網を引き揚げた後、船はエンジンの音を立てて、浜辺へ引き返す。
「え? もう帰るの」と聞くと、「写真が撮れただろうから、今日は帰る」という返事。
ガソリン代も出ないのに、悪いことをしたなァと申しわけない気持ちになった。
真っ暗な海を灯台もないところで、よくも海路を間違えずに帰れるものだ。
刺身というよりはいわしのたたき状のものから、丸ごと煮たり焼いたりしたいわし、スープもいわしのスープだ。
これだけで大変なごちそうだからだろうか、ご飯といわしのほかには何も出なかったのが少し気になった。
コカコーラの大きなペットボトルが三本、でーんと出された。
フィリピンで最大のシェアを持つ「サン・ミゲル」のビールが欲しいと思ったが、“招かれざる客”でそんなぜいたくを言えるはずがない。
夕食には、うわさを聞いて訪ねてきた、近くに住む実兄のヨシミネ・スワコが加わった。
兄は三三年生まれで六四歳、タケモトとは二歳ちがいだ。
ハギオをまじえて、食卓は現地の言葉がとびかい、大いににぎわった。
食事は五本の指を上手に使って、俗にいう手づかみだ。
郷に入っては郷に従えというから見よう見まねでやってはみたものの、指の間からご飯粒や魚の実をこぼしてしまい、なかなかうまくいかない。
ハギオがいうには、モスレムの世界では、普通、他人を家に泊めたりすることはしないようだ。
私が日本人だということで、ヨシミネの特別のはからいで無理を聞いてくれたようである。
モスレムの部落で何か事があれば、部落の全員が集まってくるそうだ。
案内してくれた部屋は、コンクリートの床の上に板を敷き、その上にゴザが一枚敷いてある。
からだを横たえると、腰骨のところが痛む。
これは下が固いというだけでなく、いわしの漁に同行したときに、狭い船内で写真を撮るのにからだの支えにした、横木が何かで腰をすりむいたからだ。
それでもいつの間にか、深い眠りに落ちた。
突然「コケコッコー」という声に目が覚める。
鶏の鳴き声も、国によって表現がちがい、英語では「コッカドゥドルドウ」というようだか、フィリピンの鶏の声をタガログ語でどう表現するのかはわからない。
自分の耳に聞こえるのは、やはり「コケコッコー」だ。
そんなことをうすぼんやりとした寝不足の頭で考えながら時計に目をやると、三時半を過ぎたところ。
虫の声や鳥のさえずりにうとうとしていると、高らかに響くテノールの声。
昼間見たモスクの方から聞こえてくる、コーランの祈りだ。
それから一時間くらいだったろうか。再び鷄の鳴き声とコーランの祈りに目を覚まし、土間に降りてみた。
五時前だが、娘が土間を掃いている。日本時間は朝の四時。
フィリピンでは朝が早いと聞いていたが、まさしくその通りだ。空はすっかり明るくなっている。
浜に出て若者に聞くと、今朝は七時に「フィッシング」―― 再びいわし漁に出るという。
昨夜一回の漁だけで早く帰ってきた、その分を取り返すためかもしれない。
朝早く、食事を終えた子供たちが、学校へ出かけて行く。
一般にフィリピンでは子供の教育に熱心なようである。
日系二世に限らず、家が貧しくても学校へ通う子供はみなこざっぱりした格好をさせている。
失業率が五〇パーセントを越すといわれ、定職につけないでいる若者が多いこの国では、学校を出なければますます就職がむずかしいからだ。
それにしても、二回目の訪問でしかも泊めてもらったというのに、この家では他の日系人ほどさし迫った、日本国籍への執着があまり感じられなかった。
聞けば両親の結婚証明があるというが、まだダバオ日系人会にも加入していない。
男五人、女九人のヨシミネの子供たちが、将来日本で就職したいという希望はあるようだ。
しかし、ヨシミネがあわてて日本国籍の回復を求めていないのは、これまでこの地でフィリピン人として育てられ、立派に漁師として生計を立てているからではないか、ということに気がついた。
同じ日系人でも、置かれた状況がちがえば、日本への思いや対応も違うということだ。
top
**************************************** |