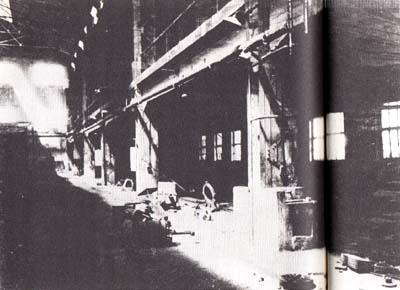|
****************************************
Index 第二章 第三章 第四章 第五章
第二章 悪化する国際環境
1 香港に居座る英国 top
英中間の懸案、香港帰属問題
第二次世界大戦終了後のアジアにたいして、米国は、共産党の宣伝にまどわされながらも、門戸開放主義を実現し、アジア平和を確立させようと努力を続けた。 しかし、他の二強、すなわち英国とソ連は、それぞれの思惑にとらわれていた。
つまり英国はかっての植民地主義の夢を捨てず、ソ連はまた赤色帝国主義をほしいままにして、中国の領土侵略を企んだのである。
まず、英国と香港の問題から触れよう。
香港は一八四二年、清廷時代の“屈辱外交”によって英国に割譲された。
隣接の九竜(英国の租借地)とともに、その取り扱いは、長い間、英中間の懸案となっていたものである。
真珠湾直後、英中間で行われた不平等条約撤廃交渉のさいも、その帰属をめぐって論議が行われたが、英国のかたくなな態度によって、新たに結んだ条約ではタナ上げのままになっていた。
しかし中国はそのさい、英国に「照会」を送り、香港・九竜の帰属を将来同時に解決するため、回収の権利を留保することを通告していた。
そのような香港で、日本軍の投降受入れをめぐって、トラブルが起きた。
連合軍の当初の規定では、香港の日本軍の投降は、中国戦区の統帥部が接受することになっていた。
ところが英国は、香港が「割譲地」である以上、主権は英国にあると主張、英海軍を独自に派遣して、英国の手で日本の投降を受入れようと策したのである。 |

大陸と地続きの九竜は、現在も英国の
租借地だが、双十節にはなお
「青天白日満地紅」をかかげる中国人住民
が多い。1976年10月、新界大窩口
|
トルーマンの肩入れ
『英軍艦がすでに香港付近の海上にかけつけている。英国は再度香港を占領しよう』(一九四五年八月十七日の日記)
しかし、香港を英国の「領土」とは認めていない中国としては、英国が中国戦区内で勝手に日本軍の投降を受入れることを承認することができなかった。
この間題についてはトルーマンも英国に肩入れし、
「英国の香港における主権に疑問はない。投降の儀式をめぐってトラブルが起れば、取返しのつかない悪い影響があろう」と電報を打ってきた。
やむを得ず、香港の主権を持つ中国の立場をくずさない範囲で最大限の譲歩をし、八月二十二日、マッカーサーに電報を打ち「中国戦区最高統帥(蒋介石)の名で英軍司令官にたいし、香港の日本軍の投降を受ける権限を与える」と伝えた。
同時に香港、九竜方面の政府軍を後退させる措置をとった。
しかし英国は、香港にたいする英国の主権は、第二次大戦今中英新条約の締結に影響されないとあくまでも主張、受降の権限は、元来、英国にあるもので、中国戦区最高統帥から与えられたものではないと、これを拒否してきた。
強権的行為に抵抗
『わが国が英軍にたいし香港の日本軍の投降接受を委託する、との我々の提議を英国が拒否した問題を、ハーレイ、ウェデマイヤーとともに協議した結果、「委託」という原則を堅持することを決定した。
英国の拒絶は、法にそむき、紀律をぶちこわすもので責任は英国にある。
私(蒋介石)は、中国戦区統帥の権威と責任を守らなければならない』(八月二十六日の日記)
『英国大使セイマーにははっきり次のように告げた。
英国将校に香港接収を委託するとの主張を、私(蒋介石)は必ず貫徹する。
私は英国が香港に派遣したハーコート少将にたいし、中国戦区統帥の代理として、香港の日本軍の投降を接受する権限を委託する。
このことを英国に通知してほしい。
もし、英国がこの委託を受けつけず、勝手に受降するならば、連合国の協定を破壊した責任は英国にある。
私は自分がもつべき職権は放棄できないし、強権的な行為には必ず抵抗する』(八月二十七日の日記)
『英国は強引にも香港の再占領を欲し、我々の接収を許さず、我々が英軍将校に香港接収を委託する指令も拒絶した。 痛憤やるかたない』(八月三十一日、本月反省録) |

毛筆で降伏文書にサインする第二遣支艦隊司令長官・藤田類太郎。
左に立っているのは陸軍司政官・牧村慶治=1945年9月16日香港政庁で
|
この間に、ミズーリ号における日本の正式な降伏調印(九月二日)が迫ってきた。
さすがに英国も、それ以上の横車は押せず、投降接受の委託を受ける形をとることをようやく承認した。
『英国は、私(蒋介石)が英軍に香港の敵軍投降を接受することを委託した指令を、最後になってようやく承認、受入れた。これは公義が必ず勝利をうることの明らかな証明である。
ただ、英国の中国侮蔑の思想は、いまなお伝統の政策となっている。
もし、わが国が自強できなければ、今後、ますます侮辱をこうむろう』(九月一日の日記)
九月十六日、香港における受降式が行われ、中国戦区最高統帥の代表としてハーコートが日本軍の投降を接受した。
英国の中国蔑視
中国は羅卓英(らたくえい)を参加させたが、英国は受降式において自国を優先し、中国代表をことさらに冷遇した。
この種の「中国蔑視」「香港切り離し」の策動は、枚挙にいとまがない。
九月一日、中国は車両の右側通行を全国いっせいに実施、香港もそれに当然含まれたが、英国は商業的利益を損なうとの理由をあげて、香港での実施を拒否した。
このようにして香港に居座った英国は、一九五〇年一月六日、西側諸国のトップを切って北平の共産党政権(中華人民共和国)を承認するという背信行為に出た。
当時大陸では、数多くの政府軍が、共産党の反乱軍と戦っていた。
香港の既得権益欲しさから、英国はいち早く、共産政権に媚びを売ったのである。
この行為は、自由諸国の結束にヒビを入れ、その後の世界情勢に新しい緊張をもたらすものであった。
その三日後の一月九日、ニューヨークにいた宋美齢は、全米に向けた放送で、自己の利益のみに強欲な英国を厳しく批判、自由と民主主義のとりでである米国の理解と支持を求めた。
「英国はわずかばかりの銀塊(香港)を得る代価として、民族の精神を売り渡したのです。
“英国はあまりに恥知らずである”と私(宋美齢)は言います。
この銀塊が生む利息は、他日、自由の戦場において流される血と汗、そして涙によってあがなわれなければなりません。
道義のうえからみて邪悪な所業は、政府のうえからみても、永遠に道理あるものとはならないのです」
中華民国はこれをもって英国とは国交を断絶、現在、文化、経済上の交流は続いているが、正式な外交関係はない。
2 東西緊張の出発点 top
約束を反古にしたソ連
日本敗戦直前に対日宣戦したソ連は、またたく問に東北全域を制圧した。
ソ連の東北占領には、さきの中ソ友好同盟条約により、「三週間以内に撤退完了」というスターリンの約束があった。
しかし、ソ連は当然のことのように約束を反占にし、あくまでも居座りを続けた。
このソ連の背信行為は、戦後の東西緊張の出発点となるのである。
国民政府は、日本の敗戦後、間もなく、軍事委員会東北行営の主任に熊式琿(ゆうしきき)、外交特派員に蒋経国(しょうけいこく=蒋介石の長男)を任命、一九四五年十月には長春に赴任させて、ソ連との現地交渉にあたらせた。
しかし、ソ連側には交渉に応じる誠意が全くなく、交渉が進展しないまま、政府軍が共産軍の抵抗を排して錦州に到着したのは、十一月二大在日であった。
スターリンの約束しか撤兵期限三ヵ月はとうに過ぎていたわけである。
その間、ソ連は共産軍を東北に招き入れ、十一月十一日には、長春に共産軍がはいっていた。
十二月五日、蒋経国と東北行営経済委員会主任委員・張嘉 (ちょうかごう)は、長春で駐東北赤軍(ソ連軍)司令官マリノフスキーと会談、 (ちょうかごう)は、長春で駐東北赤軍(ソ連軍)司令官マリノフスキーと会談、
①中国は長春に一師を空輸、瀋陽に二師を陸路で進駐させる
②ソ連は同地区内の非合法部隊の武装を解除し、中央政府に協力する――などの要求を提出した。
マリノフスキーは異議をはさまなかったものの、なお撤退期限はボカし続けた。
しかし、交渉の結果、ソ連軍の撤退期限を「一九四六年二月一日」とすることが、改めて決定された。
蒋経国、ソ連を訪問
このころ、スターリンから、蒋経国をモスクワによこしてほしいという話が伝えられた。
スターリンは当時、難局に直面している東北問題に、米国が介入してくることを極度に恐れていた。
蒋経国の来訪を求めたのも米中間の離間をはかる謀略と考えられた。
しかし、ソ連との交渉をスムーズにさせるため、十二月二十五日、蒋経国を主席私人代表としてモスクワに派遣、スターリンと直接話させた。
このときの模様は蒋経国が次のように書き残している。
「そのときスターリンは私にこう言った。
“君たち中国人は次のことをはっきり知る必要がある。
米国人は、自分たちの利益を満足させる道具として、中国を利用しようと考えているのであって、必要なときにはいつでも君たちを犠牲にする。
しかしソ連は自国の生産機械、自動車および中国にはないものを、中国に供給しよう。
と同時に、中国は中国で生産される鉱産品や農産品をソ連に供給するよう希望したい。
ソ連はまた、中国が東北で重工業を建設し、新疆で経済発展をはかることに協力することができる。
ただし、私の最大の要求は、君たちは決して米軍の一兵たりとも中国にこさせてはならない、ということだ。
米兵が一人でも中国に来れば、東北問題はきわめて解決が困難となる”」
蒋経国の報告は、日に日に先鋭化する米ソ間の対立が、東北にも色濃く影を落としてきたことを示すものでもあった。
撤退を引き延ばすソ連
『経国がソ連訪問から帰り、スターリンの意見と態度を詳しく報告した。 スターリンは私(蒋介石)が提出した東北の門戸開放と中米ソ三国合作問題について、口では拒絶できず、しぶしぶこれに応じたものの、内心それを願っていないことは問違いない。
今週は憂いの心にとざされた。
すでに政治協商会議で共産党とその取りまきの圧迫を受けているうえ、ソ連軍の脅威を受けている。
ソ連が東北でズルズルと撤兵を引き延ばしていることが私にはいちばん心配である』(一月十九日、本週の反省)
国民政府は、ソ連が約束した「二月一日撤退」に合わせて、東北の完全接収の準備を進めた。
一月二十二日には、東北の民衆と政府軍をはげますため、宋美齢を主席代理として長春に派遣した。
しかし、瀋陽、長春、ハルビンの三大都市をはじめ、各地を占拠したソ連軍は、車両や燃料の欠乏を理由に撤退の気配すらみせなかった。 |

長春を訪問、ソ連軍の出迎えを受ける宋美齡(左端)。中央は蒋経国
|
それどころか、瀋陽にはいった政府軍はソ連軍に駐屯地域を制限され、また長春では、国民政府が編制した保安団隊がソ連に武装解除されるという事態まで起こった。
二月一日の撤退期限はまたもや無視された。
ソ連は「中ソ経済合作が未完成である」「米国が中国から撤退すれば、ソ連も撤退する」など、いろいろな理由をかかげた。
『東北のソ連軍は期限を過ぎても撤退せず、口実を設けて駐華米軍と同時に撤退するとの声明を出した。
米国を公然と敵とすることをはばからなくなったのだ』(二月二十八日、本月の反省)
ソ連軍のあくなき略奪
この間、二月十一日にはヤルタ密約が米国国務省からはじめて発表された。
中国を売り渡すような内容に怒った中国の民衆は、ヤルタ密約に抗議し、ソ連軍の東北からの撤兵を求める大衆運動をおこし、情勢はますます緊張した。
ソ連軍が様々な言辞を弄して東北に居すわった目的は、二つあった。
一つは、東北での略奪をほしいままにするためであり、もう一つは、中国の共産軍に東北をゆずり渡すためである。
まず、東北でソ連軍が行ったあくなき略奪ぶりを明らかにしたい。
最初の略奪は、一般兵士によるものであった。
彼らは中国人家庭や商店、工場に乱入し、片っぱしから金目のものを奪い去った。
瀋陽、長春、ハルビンでは、列車に乗るうとする中国人に金や銀の装飾品の供出を強要し、拒否すると射殺した。 ソ連軍の規律は乱れに乱れ、彼らの進駐するところは、たちまち無法地帯と化した。
そのあとにきたものは、さらに大規模な、そして組織的な略奪であった。
「九・一八事変」以来十四年間、日本は百億ドルを超える資金を東北に投下、膨大な発電設備をはじめ、銅、鉄、石炭の採掘、セメント、紡績、石油、化学工業など最新設備の工場を建設し、三千五百万人の東北同胞の血と汗のうえに、一大軍事工業システムをつくりあげていた。 国民政府は、これら東北にある日本の鉱工業資産は、すべて中国にたいする現物賠償に当てることをソ連に通知していた。
しかしソ連側は、これに一切耳をかさず、東北の鉱工業はソ連の“戦利品”だと言い張り、そっくり取りはずして盗み去ったのである。 |
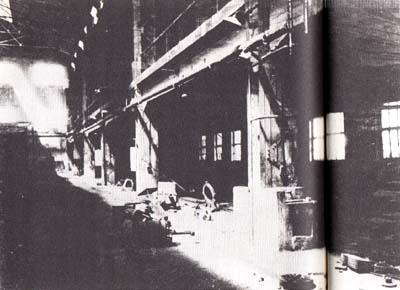
ソ連軍が設備を持ち去ったため、空っぽになった日本の工場=瀋陽で
|
3 共産軍、東北に進駐 top
民衆を憤激させた惨殺事件
十月十七日(一九四五年)ソ連は、
①日本が東北で経営していた企業はソ連の戦利品とみなす。
②「満州国」および中国人が経営していた企業は中国政府に手渡す。
③日本と「満州国」の合弁企業は、中ソ両国の正式会談で解決する。
などの要求を中国側に提起した。
さらにソ連軍全権代表マリノフスキーは十一月二十四日、東北行営経済委員会主任・張嘉 (ちょうかごう)にたいし、その“戦利品”は百億ドル以上にのぼることを明らかにし、また、百五十四におよぶ接収企業リストを出して、これを中ソ共同管理とするよう建議した。 (ちょうかごう)にたいし、その“戦利品”は百億ドル以上にのぼることを明らかにし、また、百五十四におよぶ接収企業リストを出して、これを中ソ共同管理とするよう建議した。
十二月七日、マリノフスキーは再度同じ要求をくり返し「この“経済合作問題”が片付かないかぎり、ソ連がいつ東北から撤退するかは予測できない」と開き直った。
“合作”の名でソ連の略奪の承認をせまってきたのである。
年が明けて一月十七日、撫順炭鉱の接収に行った経済部接収委員・張萃夫(ちょうしんぷ)の一行八人が、同炭鉱をすでに占拠中の共産軍に追い返され、帰り道で全員が惨殺されるという事件がおき、中国の民衆を憤激させた。
一行の安全保障についてはソ連側に責任があり、ソ連と共産軍が結託している事実を示す事件であった。
二月一日、マリノフスキーは再度“中ソ経済協力”に関する声明を発表し、中ソ共同経営を要求して、「第三者」の参加を希望しない、と表示した。
東北における独占的文配をねらう態度を露骨にしたのである。
米英、ソ連をけん制
この声明には、米国も敏感に反応、国務長官バーンズは「ソ連が東北の企業を戦利品とするのは、国際公法の範囲を逸脱している」として、二月九日、
①東北の工業を中ソ共同管理とすることは門戸開放の原則に反する。
②日本の国外資産は連合国が組織する日本賠償委員会で最終的分配を決定すべきである。
との「照会」を中ソ両国政府に提出、ソ連をけん制した。英国も米国に同調した。
バーンズは二月二十六日にも「ソ連が東北の工業設備を運び去ることを認めた協定はない」と声明している。
ソ連は、これにもかまわず三月二十七日「中ソ経済合作建議草案」を中国に提出、東北の工業の共同経営を要求したが、外交部長・王世杰(おうせいけつ)はこれを拒否した。
『ソ連軍の東北における行動は、演習に名を借りて、脅迫、威圧のかぎりを尽くしている。
なかでも、すでにわが国に交付した長春電気総公司を奪取し、錦州付近の各鉱山工場への電力供給を止め、我々に経済上莫大な損失を与えた』(三月九日、本週の反省)
ちょうどこの時期、瀋陽、長春一帯で取材活動を行っていた米国人記者が、ソ連軍から追放されるという事件がおきた。
『追放された米国人記者が帰ったあと、ソ連軍の東北における陰謀と暴行は完全に暴露された。
米国のソ連を譴責(けんせき)する世論は日増しに積極化している。
加えて、チャーチルが米国での演説で、米英の同盟を主張し、英語民族が力を合わせて対ソ作戦を準備することを強調した。
ことによると第三次大戦がやってくるのではないかとの感をいだかせる』(同前)
日本軍の武器を共産軍に引渡す
電力関係では東北の総発電量の六五パーセントに相当する電力供給設備が持ち去られた。 鞍山、宮原、本渓などの製鉄工場は、設備の八〇八-セントが盗み去られた。
撫順、本渓、阜新、北票などの炭鉱も、略奪の被害は甚大であった。
米国国務省が現地調査の結果として、一九四六年十二月に発表した数字によれば、ソ連軍の占領中、東北の工場がこうむった被害は二十億ドルに達した。 ソ連の略奪は、生産設備にとどまらなかった。日本の関東軍の武器、装備も大量にのぼる。
その量は、関東軍がかつて「十年間の戦争を維持できる」と豪語したものであった。これらの武器を、ソ連は共産軍にそっくりそのまま引渡した。
日本の軍閥が中国の民衆を殺すために用意した弾丸は、引き金を引く人こそ違え、戦後も同じ目的のために使用されたのである。
二月十三日、延安の新華社はおよそ次のような事実を伝えた。
「共産党は東北に三十万近い“東北民主連軍”を組織し、各県に“民主政権”を成立させ、さらに党中央の彭真、陳雲、林彪の到着とともに、東北における党の最高指導機関を樹立した。 この民主連軍には張学詩(張学良の弟、のち学思と改名)、呂正操の部隊をはじめ、八路軍、新四軍、およびチャハル、熱河、遼寧にいた李運昌らの部隊が含まれる。
東北の治安はこれらの部隊が維持し、国民政府が東北に進駐する兵力には制限を設ける」 |

日本軍の武器を接収するソ連軍
|
ソ連の手引きで共産軍進駐
すでにマーシャル三人委員会の停戦、軍隊の移動禁止命令が出てから、一ヵ月を経過していた。
共産党は、自らの約束を平気で破り、東北へ兵を集中させていたのである。
軍隊の移動禁止令では、政府軍の東北進駐だけは例外とされていた。
しかし、ソ連は、政府軍の進駐に妨害のかぎりをつくした。
その間に、共産軍がやすやすと進駐したのは、ソ連の“手引き”があったからである。
はたして、共産軍が配置についたのを見すましたように、ソ連軍が一斉に動きはじめた。
『この週末、ソ連軍はしきりに東北内を移動し、北方への撤退が目立っている。
それがどのような意味をもつか、まだわからない』(同前)
そのわけは、すぐに明らかになった。ソ連軍はこっそり共産軍にあとを引き継いで撤退していたのである。
ソ連から“事後通告”を受けた政府軍が接収に向かうところを、待ち伏せていた共産軍が攻撃するという筋書きである。
最初の事件は瀋陽でおきた。
『先週、ソ連軍は東北での移動を活発化させながら、その理由を明らかにせず、かつわが国の長春駐在の連絡人員と会うのを避け、防衛引き継ぎの協議をすることができないようにした。
今日になって、ソ連は瀋陽駐屯のソ連軍をすべて撤退させると宣布した。
わが軍が進駐すると、瀋陽付近には共産軍がいて四方から襲いかかり、わが軍の防衛引き継ぎのすきに乗じて、侵入、占拠を企図した。
しかし、わが軍が十分準備をしていたため、すべて撃退し、ようやく瀋陽は完全に収復することができた。
いま、東北接収の目標の第一歩を達成したが、今後の困難はさらに大きくなろう』(三月十三日の日記)
4 “容共”迫る米国 top
ソ連、公然と共産軍を援助
瀋陽に続いて、四平街でも回しような混乱がおこった。
三月十三日夜(一九四六年)、ソ連軍は突然四平街を撤退した。
政府軍はただちに少数の行政人員を先行させたが、共産軍はすでに市街を包囲しており、いっせいに攻撃をかけてきた。
その結果、四平街は三月十六日、共産軍に占領されるところとなり、政府軍が収復するのは二ヵ月先の五月二十日に延ばされた。
さらにその北方、東北の心臓部である長春(新京)の接収は、さらに困難をきわめた。
国民政府は、さきに一個師団を長春に先駐させていたが、ソ連軍は瀋陽以北の旧満州鉄道のレールをとりはらったうえ、ペストが流行しているという理由をもうけて、政府軍増援部隊の長春への移動を拒んだ。
その一方で共産軍をつぎつぎに招きいれ、増強をはかっていた。
共産軍の用意がととのったところで、ソ連軍は四月十四日、長春からにわかに撤兵した。
その三十分後、共産軍三万がソ連製の戦車、重砲を用いて進攻を開始、政府軍は撤退のやむなきにいたった。
『共産軍は長春を攻略し、政府軍が東北の主権を接収するのを妨害し、停戦協定を破壊した。
彼らは恐れることなく反乱を発動したのだ。
またソ連は公然と飛行機をくり出して共産軍の補給に当たり、ハルビンから長春にいたる鉄道を共産軍の南下輸送のために提供している。
ソ連は北満に共産党のニセ政権をつくり出し、東北をひきさくことを決心したのだ』(四月二十日、本週の反省)
生まれかわる共産軍
ハルビンにもソ連軍は四月二十六日、政府軍に先がけて共産軍を入城させた。
チチハルもソ連軍の撤退と同時に共産軍がはいった。その結果、東北の中部、北部の主要都市はほとんど共産軍の占拠するところとなった。
ソ連軍は、日本の関東軍から押収した武器を共産軍に与えた。
近代兵器にうとい共産軍の兵士たちは、はじめ、それらの武器の扱い方を知らなかったが、ソ連軍は軍事教官を派遣し、使用法を訓練した。
この結果、一九四六年の暮れには、共産軍は“精鋭部隊”に生まれかわるのである。
国民政府は、中ソ間の条約にもとづき、ソ連側に再三、武器の引渡しを交渉した。
しかしソ連は回答をさんざん引き延ばしたうえ、最後にこう答えたものである。 |

接収のための政府軍や必要物資の輸送は、ほとんど米軍の空輸に
よって行われた=上海・江湾飛行場で。米国国防総省所蔵
|
「申しわけない。関東軍の武器は鉄道の駅に置いていたのであるが、積み間違えてモスクワへ運んでしまった」
我々は改めて公文で質問した。
「このような大量な物資をどうして積み間違えることがあるのか」
これにたいし、ソ連側も正式な回答をよこした。
「あなたからの書簡は受取りました。現在、同盟友好関係にもとづき、我々は関東軍の武器をあなた方に引渡します。
総計歩兵銃三千丁、乗馬刀百四十八振り。現物はハルピンにありますから、あなた方自身で取りに行ってください」
しかし、そのハルビンには共産軍が居座っているというわけであった。
米国の苛酷な条件
こうした東北情勢の変化から一時帰国していた米国大統領特使マーシャルは、四月十七日、急ぎ帰任した。
マーシャルは、北平に直行して軍事調処執行部の報告を受けたあと、十八日重慶に戻った。
翌十九日、面会を求めてきたので会談した。
席上、マーシャルは「共産軍と妥協すべきだ」と主張した。
そこで、彼に向かって率直にこういった。
『マーシャル自身の共産党にたいする態度と方針を改めない限り、決して調停の目的を達成することはできない。
このさい、米国側が政府にたいし積極的に協力するという政策を堅持することによってのみ、はじめて消極的ながら“容共”の目的を達成できるのだ。
もし、依然として、これまでと同し共産党にたいする懐柔、妥協の方策をとり続けるならば、最後には大計を誤り、根本的な失敗を招かずにはおかないであろう』(四月十九日の日記)
四月二十一日、米国の対共産党政策を分析した。
『米国は、ソ連が東北を一人占めすること、および共産党がカイライ政崕を組織することに必ず反対し、わが政府による東北の主権収復に協力することを願うだろう。
もしマーシャルに卓見があるならば、客観的な態度で、ソ連共産党には誠意が全くないことを認識すべきである。
しかし、マーシャルは絶境にたちいたらないかぎり、その妥協慰撫政策を放棄しそうにない』(四月二十一日の日記)
翌四月二十二日に、マーシャルと話し合った。
ところがマーシャルは共産軍と妥協しなければ、米国は政府軍の東北移送の支援を中止すると切り出してきた。
ソ連が全力をあげて共産軍を支援しているこの場におよんで、米国は政府軍支援を打ち切るというのである。
マーシャル、政府側の一方的譲歩を要求
『政府軍の輸送は米国に頼らなければならず、一切の計画は米国の牽制を受けている。
ところが米国は、その海軍の出動を見合わせ、輸送を中止すると脅迫し、共産党に妥協せよという米国の建議を、我々がのまざるをえないようにしている。
いま共産党と妥協することは、ソ連に屈服することにほかならないということが、全くわかっていないのである。
共産党の意気が高揚しているいま、米国の苛酷な条件を甘んじて受けることは断じてできない。
このことをマーシャルにはっきり述べて、彼の覚醒をうながすべきであろう』 (四月二十二日の日記)
四月二十四日、マーシャルと会談したさいには、東北における停戦条件を次のように提案した。
『一、本年一月十日の第一次停戦協定およびその付属文件で決められた約束を、東北において、完全に実行する。
二、東北におけるすべての軍および各軍付属単位の移動は、本年二月二十五日の整軍協定の規定にもとづいて行う。
三、東北境内の長春鉄路全線およびその両側三〇キロ以内の地区は、すべて政府軍が接収し、共産軍は政府軍の接収を妨害しない。
四、第三項以外の共産軍駐留地区の政治問題については、政府および共産党双方の代表が協議して解決する』
この提案は、ことさら新しいものではなく、すでに合意に達している“原点”を再確認するものにすぎなかった。
しかし、マーシャルは、声を荒らげてこの提案をはねつけ、政府側の一方的譲歩を要求した。
5 東北失陥の遠因 top
共産党を恐れるマーシャル
国共の調停にあたる米国大統領特使マーシャルは、公平な調停者たるべき義務を忘れ、明らかに共産党の“なだめ役”にまわっていた。
『最近のマーシャルの心理と態度を察すると、共産党との交渉が決裂したり、停頓したりすることばかりを心配している。
恐懼のあまり、対応のすべがなくなる状態も時々みられるほどで、彼の精神はほとんど完全に共産党にコントロールされている。
ただひたすら共産党の要求に従い、あえて異を唱えようとしない。およそ共産党の心理に抵触するような条件は、いっさい共産党側に打診しようともしない。
彼の共産党を恐れる心理はここまできてしまった。
私(蒋介石)はていねいに教えてやらなければなるまい。
米国は従来の消極政策を改め、実力によってわが政府を積極的に援助しなければ、米国の政策は貫徹できない。
また米国の東亜における声望も完全に失われ、挽回のしようがなくなるであろう。
マーシャルがもし政治を見る眼と国際正義を備え、米国自身の利害を弁別することができれば、私の言うことが誤謬でないことを悟るはずである』(一九四六年四月二十八日の日記)
四月二十九日、マーシャルから、共産党代表・周恩来との交渉経過の報告を受けた。
それによると、マーシャルは周恩来にたいし、東北停戦の“絶対条件”として、共産軍が長春を退出し、中央軍の接収を受けること、およびマーシャル三人委員会の派遣する小委員会が現地で監視にあたることを示し「そうしないならば、私(マーシャル)は、もはや、調停から手をひく」と伝えた。周恩来は、具体的な意見を表示せず、延安に電報で必ず伝えると、述べたという。
八年半ぶりに南京に還都
報告を聞いたあと、マーシャルにたいして次のように告げ、米国が東北において影響力を発揮するようすすめた。
『米国は東北にたいする政策と、ソ連、共産党にたいする態度を改めて検討し、すみやかに決定しなければならない。 これはじつに米国のアジア全局の問題への対応のキーポイントとなるもので、消極的に出てアジアを退出するか、あるいは積極的に出てアジアに参加、指導するかを選択すべきである。
かつて「九・一八」(満州事変=第9巻参照)のとき、消極的であったがために第二次世界大戦という禍患を醸成した。
あの轍を二度と踏むことがあってはならない。
あのとき、米英がかりにわずかでも日本に圧力をかけ、積極的な行動を示せば、日本はああまで猖獗をきわめず、戦禍もおのずから取り除くことがでかたのである。
今日、ソ連、共産党の東北における形勢も同様である。
いま共産党はすでに言葉によって制止できるものではなくなっている。
ただ実力を背景に、積極的行動によってわが政府を助け、米国の決心を明示すれば、ソ連、共産党はいずれも屈服しよう。
さもなければ米国のアジアにおける指導力は声望を保つことができず、第二次世界大戦もまたこれを起因とするに違いない』(四月二十九日の日記)
五月五日、国民政府は、八年半ぶりに南京に還都した。
それに先立ち、五月三日、漢口から宋美齢とともに空路南京入りした。
空港から市内にかけて、沿道はすべて歓喜する市民で理まり、万歳の声が嵐のようにわきおこった。
スターリンからの訪ソ要請を拒絶
翌五月六日、スターリンから駐華ソ連武官ロージン、蒋経国を通じて、訪ソの要請があった。
『スターリンが私(蒋介石)に訪ソを要請してきたが、これは中米関係を離間させる最大の陰謀である。
スターリンは他人をもてあそぶのに慣れているが、私はだまされない。
こちらはえん曲に拒否したが、このあとスターリンは陰謀が成功しなかったことで、恥ずかしさを怒りにかえてくるであろうことは断言できる』(五月十一日、本週の反省)
『このたびスターリンからの訪ソ要請をえん曲に拒否したことは、わが外交の成敗に重大な関係がある。
マーシャルの私(蒋介石)にたいする最近の態度には、失望するばかりだが、かといって中共を助け中国を赤化するというソ連の一貫した政策は、私がソ連にいったからといって決して変わるものでない。
逆にマーシャルの疑惑をいたずらに増し、スターリンの中米離間の陰謀にはまるだけでしがないことは、私にはよくわかっている。
今後とも、対米、対ソ外交の基本的国策をマーシャル個人にたいする一時的な好悪によって変えてはならない』(五月三十一日、本月の反省)
この間、政府軍は五月十九日、四平街を接収し、さらに長春をめざした。
『わが軍が四平街をとり戻したことにより、共産軍主力は壊滅し、その態度も一変した。
また、私(蒋介石)がスターリンからの訪ソ要請を拒絶したため、共産党はなお米国のマーシャルの調停継続に頼らざるをえなくなっている』(五月二十一日の日記)
焦点の地・東北(瀋陽)へ宋美齢とともに赴いたのは五月二十三日である。 一九一四年、孫文の命を受けて革命情勢の調査にきて以来、じつに三十二年ぶりの東北入りであった。 |

瀋陽を巡視する蒋介石夫妻。後方は北陵隆恩門=一九四六年五月
|
第二次停戦命令
これに合わせるように、この日、長春を完全に接収、またソ連からは「五月三日にソ連軍の満州からの撤退は終了した」との通告を受けた。
前線からの報告では、共産軍はすでに徹底的な打撃を蒙り、再起不能の状態になっていた。
東北問題も、ようやく順調に解決の見通しとなった。
六月六日、マーシャルの再三の要請をいれ、七日正午から十五日間の停戦命令(第二次)を発布した。
『停戦は、共産党に彼らのあやまちを改めさせ、国家に忠をつくす機会を与えようとしたものであった。
しかし、じつはこの第二次停戦命令こそ、国民政府が東北において失敗を演ずる最後のキーポイントとなったものであった。
そのとき政府軍は、ハルビンに迫ること一〇〇キロ以内の双城付近にいた。
その追撃部隊が、かりに追撃を停止しなかったならば、中東鉄路の戦略的中心であるハルビンを占領することができた。
そうすれば東北北部に散らばった共匪はしだいに粛清され、東北全土は容易に平定できた。
さらに共匪が東北北部に足がかりを失えば、ソ連もまた共匪を助けることができず、東北問題はおのずから解決し、共匪が東北によみがえることもなかったのである。
のちに一九四八年初冬、政府軍が東北で最後に失敗する原因は、このときの第二次停戦命令が招いた結果であった』
6 ソ連の介入を恐れる米国 top
“戦わず和平もせず”で引きのばし
第二次東北停戦命令の期限は、六月二十二日(一九四六年)までの十五日間だったが、マーシャルの強い要望もあり、さらに三十日正午まで延長された。
この間、共産党は停戦命令を無視して、東北の松花江(スンガリー)方面で政府軍を攻撃、山東、熱河、チャハル、山西、綏遠の各省でも兵を集結、政府軍の手うすな地域を狙って侵入を続けた。
一方、三人委員会の共産党代表・周恩来は、東北への共産軍増駐、“解放区”への立ち入り拒否など、これまでの協定や約束をくつがえすような難題を持ち出し、調停が成立するのを妨げた。
その“かけひき”の手口は次のように分析できる。
『共産党の陰謀を分析すれば、
①まず、全面的かつ長期にわたる停戦を主張する
②各種協定は別個に解決していく
③政治と軍事はからみ合わせて解決にもちこむ
④調停にソ連をひきいれて参加させる
⑤米国代表の仲裁插は、局部的事件または、特定の事件だけに限定し、全体的事件にたいしては、三人委員会の中で米国代表が最終的決定権を持てないようにする
――といったことがあげられる。
これらはすべて各問題の解決ができないうちに、自らの発展をとげようとするための時間かせぎである』(六月二十二日の日記) |

張家口に入城した共産軍
|
『共産党の策略は不戦不和(戦わず和平もせず)、似戦似和(戦うようであり、和を求めるようでもある)の局面のもとで、とりきめを引きのばし、国家を混乱状態におちいらせ、政治を動揺させ、経済を破産させ、もって政治を転覆し、中国を赤化することをもくろむものである』(六月二十四日の日記)
共産党、米国を「内政干渉」と非難
六月三十日、停戦命令はついに時間切れを迎えた。
この日、政府は「共産党問題ではなお平和的統一の方針を捨てておらず、今後は政治的解決をめざす」との声明を発表した。
『共産党との交渉の結果がどうなろうと、現在の段階では、軍事行動は正式の討伐方法をとってはならない』(六月二十七日の日記)
これにたいして共産党は、七月七日、抗日九周年「七・七宣言」を発表し「反動派があえて挑戦するならば、我々は、いっさいの準備をして彼らをたたきのめすであろう」と、宣戦布告にもひとしい声明を出すとともに、「マーシャルとウェデマイヤーは、集団的武装干渉政策をとっている」と、米国の調停を「内政干渉」だとしてはげしく非難し、米軍の中国からの撤退を要求した。
『マーシャルは共産党が発表した「七・七宣言」に強く刺激され、共産党に調停を受入れさせようとしてもその希望はすでにないことを知った。
にもかかわらず、なお、共産党に妥協し、絶えず我々にたいして圧力をかけ、終始武力無用の主張を堅持し、わが国の存亡を顧みようとしないのは残念である』(七月十三日、本週の反省)
マーシャル、ソ連の介入を警戒
マーシャルが警戒したのは、共産党を締めつけることによって、ソ連を刺激し、ソ連の介入を招くという点であった。
『マーシャルの最大の気がかりは、局部衝突が全面内戦を引き起こすのではないかということである。
同時に短期に解決できずに、ソ連の干渉をまねき、第三次世界大戦が発生することを恐れているのである』(七月十四日の日記)
はたしてモスクワ放送は二十二日、「ソ連は米国の対華政策を座視するわけにはいかない」と、米国を攻撃、共産党もまた、マーシャルらにたいし、「中国共産党はモスクワの指導に従う」と言明、国共調停を米ソ共同で行うことを要求してきた。
『米ソ関係は日ましに悪化している。ソ連の世界赤化の野心もまた、ついに世人の認識するところとなった』(七月三十一日の本月反省録)
こうした事態を迎えてマーシャルは、中国在住が長い北京・燕京大学校長スチュワートを、空白だった駐華米国大使に推薦、調停の行き詰りを打開しようと試みた。
当初、新任大使に内定していたのは、我々国民政府の信頼の厚いウェデマイヤーであった。
ところが発令直前にそのことが共産党側に漏れ、周恩来がマーシャルに強く反対したため内定は取消され、スチュワートにきまったといういきさつがある。
スチュワートは、良心的な教育者ではあったが、武力で政権を奪取しようとする共産党の強権政治の実態は理解していなかった。
しかも、彼の秘書こ傅淫波(ふけいは)は共産党から送り込まれたスパイで、米国側の情報は、共産党につつぬけの有様であった。 |

蒋介石夫妻とウェデマイヤー(左 から2人目)スチュワート(右端)
|
毛沢東の「ハリコのトラ発言」
米国が共産党をいかにぼやかしていたかは、七月二十九日、北平郊外の安平鎮でおきた米海兵隊豌唯事件の処理をみてもわかる。
この事件は「米国の中国内政干渉反対」を叫び、米軍の中国からの撤退を要求する共産軍が、天津から北平へ移動中の米海兵隊を攻撃、三人を殺害、十二人を負傷させた事件だが、マーシャルたちは共産党にたいして強く出ず、むしろとり入るような態度に出た。
『米国の民族性の天真らんまんさは、理解に苦しむ。
マーシャルのような要人でさえ、共産党に侮辱されながらまだそれを悟っていない。
はなはだしきは、米軍が平津公路上で共産軍の襲撃を受け、その国誉と軍威を大きく損ねながら、なおもそれをかえりみなかった。
かえってわが政府にたいし直接間接、有形無形の圧力をかけてきた。
彼はこうすることによってのみ、その調停を達することができると考えていたが、共産党とソ連が彼の調停の成功を決して許しはしないことを知らない』(八月三日、本週の反省)
| ▼毛沢東が、米国の女性ジャーナリスト、アンナ・ルイズ・ストロングのインタビューで「原子爆弾は、米国の反動派が人をおどすために使っているハリコのトラで、見かけはおそろしそうでも、実際には、なにもおそろしいものではない)と、いわゆる「ハリコのトラ発言」をしたのも、ちょうどこの時期であった▲ |
共産党はこのように、一面では協定によって政府軍を金しばりにし、一面ではソ連の力をかりて米国を萎縮させ、その間に全面反乱の準備を着々と重ねた。
共産軍は、太原攻略総司令に聶栄臻、平漢鉄路戦線総司令に劉伯承、津浦鉄路戦線総司令に陳毅、北平包囲総司令に楊成武、天津包囲総司令に陳濟らを、それぞれ任命して態勢を固めにかかった。
7 米国、対華政策を誤る top
共産、“総動員令”を発令
八月十四日(一九四六年)抗戦勝利一四年にあたって、「全国同胞に告げる書」を発表、憲政の推進、政治協商会議の尊重などを確認するとともに、共産党問題について、次のような方針を明らかにした。
『我々は停戦の原協定を必ず順守し、履行する。我々は、共産軍が停戦発令後に占領した地区からの全面的撤退を要求するものではなく、和平の障害となっていたり、交通阻害の危険がある若干地区からの撤退を求めているのである。
政治紛争については、なお、政治的解決の方法をとる。ただ、これには、共産軍が停戦を実行し、軍事調処執行部の整編実施を尊重し、軍隊の国家化をはかるなど、協定を空文にしないことを保障しなくてはならない』
これにたいして、共産党の延安放送は、八月十六日、「全解放区軍民総動員」の呼びかけをもって答えた。
この“総動員令”は、国民政府にたいする全面的反乱の宣言であり、調停の幕切れを一方的に宣告するものであった。
この時期にいたっても、米国はなおも中国政策を誤り続けた。
トルーマンは八月十日、駐米中国大使・顧維鈎に書簡を渡し、「もし中国の国内問題の平和的解決の話し合いが、短期間に進展を見ない場合は、私(トルーマン)としては、米国の立場を再検討しなければならなくなる」と告げた。
一段と強くなった米国の圧力
続いて十八日、トルーマンは国民政府にたいする余剰武器輸出禁止の行政命令を出した。
政府軍の装備、武器はほとんど米国製であり、この禁輸によって、補給の道を閉ざされた政府軍の戦力は、大きく低下せざるをえなかった。
政府軍から武器をとりあげて共産軍の反乱を鎮圧できないようにし、国民政府に妥協を迫るというこの措置は、このあとの戦況に、決定的な影響力を持つものであった。
『米国務省は我々が現金で買った武器にたいし、輸出許可証を出すことを拒絶した。
これによってマーシャルが我々にたいして加える圧力は、さらに一段と強くなった。 |

トルーマン米大統領
|
米国の対華政策がマーシャルの調停の不調によって、さらに悪化したと知るべきである。
マーシャルが共産党に寛容なことは、わが国を害するばかりでなく、米国自身を害するものである』(八月三十日の日記)
宋美齡と台湾を視察
このころ共産軍は、山西省北部の要衝、大同に大規模な攻撃を加えつつあった。
このため、現地で調停に当たっていた軍事調処執行部の小委員会は、八月十六日、北平に撤収せざるをえなかった。
政府は、再三にわたって、共産軍の進攻停止を求め、「もし、共産軍が大同への進攻を停正しないなら、政府軍は、共産党の拠点である承徳(熱河省)、張家口(ハイラル省)および延安を攻撃する」と警告した。
しかし、共産党は、これに全く耳を傾けようとしなかった。
やむを得ず政府軍は八月二十九日、承徳に進攻、九月十四日には、大同を包囲していた共産軍を追い払い、十月十一日には張家口を回復した。
これとともに、東北、山東などでも掃討戦を実施、十月末までに通化、安東などを収復した。
宋美齢とともに台湾をはじめて視察したのは、ちょうどこのころ(十月二十一日~二十八日)である。
『台湾はまだ共産分子の浸透を受けておらず、清潔な土地ということができる。
今後、積極的に建設を行い、模範省の一つとしたい。
ソ連と中共はあらゆる詐計をめぐらしているが、どうということもない。
今回の台湾巡視は、政治L、台湾の人心に与えた影響がきわめて大きい』(十月二十六日、本週の反省)
『台湾巡視の収穫は、東北巡視の収穫よりも、いちだんと大きかった。全国民の心の向くところを知ることができた』(十月三十一日、本月の反省)
十一月八日、国民政府は共産党が態度を変えるよう最後の願いをこめて、十一日正午から全軍一律に停戦(第三次)を実施するよう命令した。
しかし、共産党の強硬な態度は、軟化することがなかった。
十一月十一日から開かれる予定だった国民大会に、共産党は出席を拒否、民主同盟もそれに同調した。
国民政府は彼らの参加を待って、三日間、開会を延期したが、同十三日、周恩来はマーシャルに会い、大会ボイコットを宣告した。 |

台湾を訪れ、群衆の歓呼に応える蒋介石夫妻
台北市中山堂で
|
対華政策の誤りを指摘したケネディ top
マーシャルもついに調停打ち切りを決意した。
十二月十八日、米国大統領トルーマンは、中国の内政不干渉を声明、マーシャルもまた、一九四七年一月八日、「和平の障害は国共両党にある」との声明を残して帰国、間もなく国務長官に就任した。
武器輸出禁止、調停打ち切りという米国の“中国離れ”は、中国大陸の情勢悪化に拍車をかける大きな節目であった。
このあと、マーシャルは、米国議会から非難を受け、一九四七年七月、米国は再度、ウェデマイヤーをトルーマンの特使として中国に派遣した。
ウェデマイヤーはトルーマンに「東北の国際管理、中国への軍事、経済援助の復活、軍事顧問の派遣」を要請する報告書を提出したが、トルーマンはソ連への気がねから、これを受入れなかった。
米国議会も、対華援助の再開を、しばしば取上げたが、マーシャルをはじめ、駐華大使スチュワートらは最後まで反対、ようやく再開がきまったのは、一九四八年四月であった。
この間に東北は共産軍に奪われ、大陸の戦況は抜きさしならない状況に落ち込んでいたのである。
一九四九年一月、米国のジョン・F・ケネディ(当時下院議員、のち三十五代大統領)は、その演説の中で、米国の対華政策のあやまりを、次のように評した。
「一九四一年十一月、米国は極東政策の目標が中国の統一を実現し、国民政府と強固な関係を維持することにあることを、明確に宣示していた。
ところが、戦後、国民政府を支持すべきか、それとも対華援助を代償に国民政府に中共を受入れさせるかで、国論は二つにわかれた。
その結果、米国の対華政策は自ら悪い報いを招いた。
もし米国が連合政府に固執しなかったならば、国民政府がこのような悲惨な打撃を受けることはなかったであろう。
中国の赤化を防げなかったのは、米国の利害に重大な影響を与えた。
我々は自由中国を維持するために一戦を惜しんではいけない。
米国の外交家と大統領が、すべてを“無”にしたのである」
top
**************************************** |