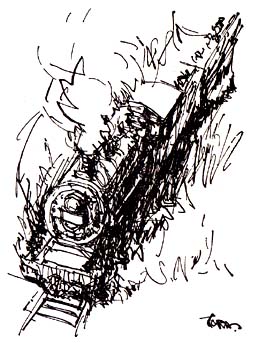|
****************************************
Home 概要 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Ⅰ 涙の丘
|
1 駅までの四キロ top
昭和二十年八月九日の夜十時半ごろ、はげしく私の官舎の入口をたたく音がきこえた。
(注=8/8:ソ連の日本への宣戦布告、8/15:終戦日)
子供たらは寝ていた。私たちは、ゆうべおそかったから、今夜は早く寝ようかといっているところであった。
「藤原さん、藤原さん、観象台(日本の気象庁)の者です。」 わかい人の声であった。夫と二人でドアーをあげると、木銃をもった二人の男が立っていた。
「あ、藤原さんですか。すぐ役所へきてください。」
「一体なんですか。」夫が問いかえした。
「なんだかわかりませんが、全員を非常召集しているのです。ではおねがいします。」
二人の青年は、非常にいそがしそうに、つぎの住宅をめざして出かけていった。
ドアーをしめると同時に、私はかるいめまいがした。
私は夫を一人でこの夜の闇の中に、だしてやれないような気がした。
「あなた一人で大丈夫ですか?」私は夫にいってから、夫の目の中に、何か重要なものを読みとろうとした。
夫には何か私にいわないで、隠しているものがあるように思われた。この二、三日、夫の目の中には、何か不安の色があった。
「大丈夫だよ、心配しないで、まっていなさい。
くるときが、とうとうきたようだ。
そら、外の物音をききなさい。
確かに今までの新京ではない。」 |

著者のたどった道――新京から釜山まで、
右上が夫が収容されていた延吉
|
私は耳をすませて外の物音をきくと、遠く自動車のはしる音、人の声、いろいろの物音が、何か大きな変動のおこる前兆のように、月のない夜の空気をふるわせていた。
「やっぱり、来るときがきたのね。」
私はせまい廊下にすわると、急に力がぬけたように、夫の丹前のすそをもったままふるえていた。
「ばか、なにをいっている、早く用意をするのだ。すぐにでもここを出られるような用意を。」
「ここを出るって、この家から出てどこへいくんですか?」
「それは僕にもわからない。出るか出ないかもまだわかってはいない。ただ、その心がまえが必要なんだ。」
夫はゲートルをまくといそいで出かけていった。
夫の勤務している観象台は新京(いまの長春)の南端、南嶺(なんれい)という郊外にあった。
ここから歩いてすくなくとも三十分はかかる。そこへいって、すぐ帰ってくるとしても、およそ一時間はかかる。
私はどうしようかと二階にあがった。
二階の窓から見ると、官舎街の電灯は灯火管制下であるにもかかわらず赤々と光をもらしていた。
今夜は私の家だけでなく、どこの家でも大変なことがおこっているにちがいない。
この窓にうつる影は、なぜか非常にあわただしくうごいていた。
私はこうしてはいられないとせかれる思いで、非常持ち出しのトランクをあけた。
冬じたくを主とした子供のもの、大人のものがきちんと整理してあった。
非常食糧について私は考えた。若干の砂糖、乾パン、缶詰、それらのものはすでにトランクにはいっていた。
もしこれから新京をはなれて遠く出るようになったならば、一体、このほかになにを持ち出したらよいであろうか。
そう思うとむやみに心がせくだけで、私は何をとりそろえてよいのか、わからなくなってしまった。
八畳の部屋につったかやの中に、いっぱいになって寝ている子供たちの顔を見ると、とてもこの家をはなれて遠くにはいけそうに思えなかった。
正広が六歳、正彦が三歳、そして咲子は生まれてまだやっと一ヵ月になったばかりであった。
リュックサックやトランクの中に、品物を出したり入れたりしているうちに、私はきゅうにさびしくなって涙ぐんできた。
私の力ではどうにもならないと思うと、私は夫の帰りをひたすら待つばかりであった。
じっとして座っていると遠くのほうから、自分の家をおしゆすぶるようにいろいろの物音が伝わってきた。
窓から見ると大同大街をつぎからつぎと走るトラックのヘッドライトが、いままで見たこともない光のたばを官舎街の白壁に投げかけていった。
夫が帰ってきた。蒼白な顔を極度に緊張させて、私の前に立った夫は別人のようにいった。
「一時半までに新京駅へ集合するのだ。」
「えっ、新京駅ですって!」
「新京から逃げるのだ。」
「どうして?」
夫はそれにたいして、言葉みじかに説明した。
関東軍の家族がすでに移動をはじめている。
政府の家族も、これについで同じ行動をとるように上部からの命令である。
新京が戦禍の巷になったばあいを考慮して、いそいで立ちのくのだとのことだった。
観象台の他の家族たちも、それぞれ準備をしている。いますぐに出発しなければならない。
「汽車の割り当てがきまっている、あと三十分で出発しなければならない、いそぐんだ。」
夫は命令するようにいった。
「もちろん、あんたも一緒でしょう。」
私は、これ以上夫といいあらそえなかった。
しかし、夫としっしょなら、なんとかできるだろうと夫の顔を見た。
「駅まで送ってぼくは引きかえす。」夫の言葉に私はぎくりとした。
そしてこみあげてくる悲しさと怒りで、私は常識を失った女のように激しいことばを夫になげつけた。
夫は、仕事、がまだ残っている。自分の立場として、もうすこし後始末をつけてからでないと動けないというふうなことを、私にいっているようだったが、私の言葉に圧倒されて、やがて黙って私の目を見つめていた。
私はしずかな夫の目が私にそそがれているのを見ていると、とてもこれ以上いってもだめだと思った。
泣きくずれた私の肩に夫の手がかかって、
「さあ早く、子供たちを。」といった言葉に私ははっきり母としての責任を意識した。
私は、子供をまもるために逃げるのだと、はっきり決心がつくと、もう泣いてはいられなかった。
もう一回、はじめから荷物の整理をした。
しかし、子供三人のほかに、どれだけの荷物がもてようか、ほんの身のまわりの物、子供たちの冬着だけでいっぱいになってしまった。
三歳の正彦を私がせおって、夫はリュツクサックの上に咲子を乗せて、両方にトランクをさげ、正広は澎るかせて新京の駅までいくことにした。
ドアをおけると、さっと冷たい大気がほおにあたった。
子供たちには、きられるだけきせ、私も冬のしたくであったから、大陸の夜のつめたさにはちょうどよかった。
庭いっぱいに植えたトマトの実を二つ三つとって手さげに入れた。
夫が早く早くとせきたてるので、私は隣組の人たちに別れの挨拶もしなかった。
せめて仲良くしてくださった前田さんと佐藤さんのお宅だけはお別れの挨拶がしたいと思ったが、今夜にかぎって他の官舎は灯がともっているのに、私たちの並び六軒の官舎は、どの家もくらかった。
私は心で“さよなら”をいって大同大街へでた。
大同大街にでて、もう一度私たちの二年間住んだ家をふりかえって見ると、ただ黒く四角な土のかたまりのように見えるだけであった。
新京(しんきょう)駅は、大同大街(だいどうだいがい)を一直線にここからはるか四キロはあるだろう。
一キロも歩かないうちに私はへたばってしまった。
咲子を生んで一月たつかたたない私には、重い正彦はむりであった。
大同公園のほとりに一息ついて、私は、生まれていままで感じたことのない悲しみにおそわれた。
目の前をひっきりなしに通るトラックの上に、軍の家族と荷物が満載されている。
私たちのように、子供の手を引いていく人もいる。
ほんの二時間もまえは、あんなに平和に暮らしていた私たちが、どうして急にこんな姿で星空を見なければならないのだろう。
公園のしげみをこしてほとんど水平に近く、大きな流れ星が尾を引いて飛んだ。
私はぞっとするようなさびしさにおそわれると、
「ねえ、帰りましょう、どうせ死ぬなら家で死にたいわ。」
夫はなにもいわない。懐中時計をだしては、星明りにすかして見ている。私に歩けといっているのだ。
あと三キロもこのまま歩いたら、私は貪血でたおれてしまうだろう。
「ねえ、帰りましょう。」
私はどうにもならないことを、もう一度いってみた。
2 別れ top
|

満州国の首都、新京の市街(昭和16年)
|
新京駅の前はごったがえしていた。私たちの団体が、五十名ばかり交通公社の前にかたまっているのを見つけて、
「ああ、間に合った。」と、夫はいった。
知っていない人たちばかりであった。
土の上にぐったりとくずれると、もう自分ではどうにもならないほど、私の体は疲れきっていた。
軍の家族がぞくぞくと列をなして、駅の中へすいこまれていく。
私たちの出発は翌朝七時ときめられた。一枚の毛布を土の上にしいて、子供たちとともにまるくなってねた。
夫が出発までそばにいてくれるのが、せめてものなぐさめであった。
なにか、大勢の人にかこまれているような不安な気持ちが、私の頭の中に強くうかびあがってきた。
妙にほこりっぽい空気をすっているようで、私は咳(せ)きをして目をさました。
夜はあけていた。私は人の群れの中にぎっしりかこまれて、ふみつけられそうになって眠っていたのであった。
夫はいなかった。あたりを見まわすと、目のまえに顔見知りの大地さんの一族が、元気な顔をならべていた。
夫は、役所へ連絡にいったとのことだった。総務課長の柴田さんが、いろいろの世話をやいていた。
「藤原さんはまだこないかなあ。」
柴田さんが私の夫をよっているらしい。夫がきたころはすでに七時はすぎていた。
乗車は九時だそうだ。
「台長はなんといいましたか?」
まちかねたように柴田さんが話しかけた。
「人選はてきとうに私たちできめるようにとのことでした。」
二人はちょっとはなれたところで、こそこそ話をはじめた。
人選とは私たち女、子供の保護のためについていく男たちのことであった。
四名の男がえらばれた。その家族たちはうれしそうに自分の夫や、自分の父のそばにあつまった。
「団長はだれにする?」
柴田さんが夫の目を見ていう。
「戸野さんがいいだろ。」
夫はそういっているらしい。
「ねえ藤原さん、あんたいかないかね。あんたの家族が一番小さい子供さんが多い、台長にはぼくからあとで話すから。どうせあと、い残ったって二、三日の問題ですよ。」
夫は返事をしない。私はよろよろ立ちあがって夫に近よって、いった。
「ねえ、あなたいってよ。」夫はとがめるような目で私を見ると、
「ぼくはいきません。」と、柴田さんにいって、
「戸野さん、戸野さん、あなたがこの疎開団の団長ときまりましたよ!」とみなに聞こえるようにどなった。
最後まで見栄と体裁のために、私たちを犠牲にしようとする夫にむかって、私は、ただひとなみの妻としての涙を流すよりしかたがなかった。
夜は全くあけた。そのなかに昨夜よりもまして混雑をきわめている新京駅があった。幾列も幾列も列がつづいた。
その大部分は女と子供、それを軍人がしわがれた声で整理していた。
夫は大きなふろしき包みをもってかえってきた。役所へいった途中にもってきたらしい。
「どうせすてるようになるかもしれない。しかし家においても同じことだ。」
主に衣類であった。夫は片手にもぎたてのトマトをいっぱい入れたかごをさげていた。私にはこのほうがうれしかった。
子供たちと食べながら、一睡もしない夫の充血している目を見ていると、汽車の出るまでのもうあと一時間がおそろしかった。
団長の戸野さんの奥さんをむかえにいったはずのサイドカーは、だれの荷物か知らないがいっぱい荷物をもってかえってきた。
しかし戸野さんの奥さんはのっていなかった。柴田さんが大地さんと大声でいいあらそっていた。
私は人ごとのようにきいていた。八時にホームにいれられた。
そして三十五番と白墨(はくぼく)で書いた無蓋貨車に乗せられた。
夫にたすけられて貨車に引きずりあげられると、貨車の特等席は、すでに身軽の人たちで占領されていた。
私たちは汽車の進行方向にたいして、一番わりがわるい位置、ちょうど石炭がらをまともにかぶるような位置に座をしめた。 |

日本人の引揚者でごったがえす新京駅
|
「おおい、みんな役所へかえるぞ。」
柴田さんが男たちによびかけた。
夫は、次男の正彦を一番かわいがっていた。
夫は正彦をだきあげると、
「正彦ちゃん、お父さんの顔を、よくおぼえているんだよ。ね、お母さんのいうことを、よくきくんだよ。」
それから、ぼんやり座っている正広にむかっていった。
「正広ちゃんはいくつ?」
正広は六つと小さな声で答えた。
「そう六つだったね。では、お父さんの言うことよくわかるだろう。
これからこの汽車で、お母さんと正彦ちゃんと赤ちゃんと、ずっと遠いところへいくんだよ。
お父さんはまだ新京にのこっているんだよ。
お父さんがいないから、お母さんのいうことをよくきいて、いい子でいるんだよ。」
正広はうんといってうなずいた。
夫は私にむかって、
「では頼むよ。」と簡単にいって立ちあがった。
私はもうこれが夫を見る最後かと思うと、とてもこのままさよならがいえなかった。
立ちあがって、夫の耳にささやくようにいった。
「ね、生きていてね。どんなことをしても生きていてね。」
私はくりかえしくりかえしいった。
夫は、体にぴったりあった協和服のポケットから、懐中時計をとりだして、黙って私に手わたした。
夫の愛用しているロンジンであった。
「子供たちを頼むよ。」
そういって、くるりと背をかけて貨車から飛びおりようと身をかがめた。
このとき夫の腰につるしていたタオルが手にふれた。
夫はおりかけたのをやめてもどってきて、腰のタオルを引きぬくと、正彦の顔をほおかむりしてやった。
「日に焼けると暑いからな。」
夫はまじめな顔でそういうと、あとをも見ずにひらりと貨車から飛びおりて、プラットホームを大幅な足どりで、いってしまった。
私は夫の姿が人波の中に見えなくなっても、また夫が引きかえしてきはしないかと、いつまでもいつまでも、見ていた。
3 無蓋(むがい=屋根のない)貨車 top
私は貨車の外枠に体をもたせかけて、じっとしていると、一人になったさびしさが大波のようにおしよせてきた。
全くたよるものをなくしてしまった私が、どうして生きていけようかと思うと、ただ、じっとしていられない気持ちであたりを見まわした。
戸野さんは、それでも奥さんが間に合うかと心まちにまっているのだろう、しきりに駅のほうを気にして立っていた。
十時になって汽車は発車した。私はほっとした。
私はこの汽車が、このまま私たちを故郷へつれていってくれればよいというような、たわいないことを考えた。
汽車がうごきだすと、みな駅のほうへむかって手をふった。
私は夫がそこにいるはずがないとわかっているけれども、やはりみなのあいだからハンカチをふりながら駅を見た。
人の波の雑踏しているだけで、知っている顔はひとつもなかった。
「新京よ、さようなら。」
だれかそんなことをいった。どんな気持ちでそんなことをいっているのだろう。
私は発車と同時にふりそそいでくる石炭がらを、どうして防ごうかと考えた。
正広も正彦もさすがにつかれたのか黙って座っていた。
ねんねこの中でねむっている咲子の顔に、石炭がらがかからないように、私は正彦のほおかぶりの手拭いをとろうとした。
「いやあん。」案外つよい拒絶をしたので手をひいた。
正彦は夫のしてくれたタオルのほおかむりをして、そのまんまるい目をぱちぱちさせていた。
私は夫の残していった、正彦への愛情をもうすこしこのままでおいてやりたいと思った。
リュックサックの口をあけると、かわいたおむつがあったから、それを石炭がらよけに咲子の顔にかけてやった。
きゅうに私は泣けてきた。私は貨車の木わくにむかっていつまでも泣いていた。
泣いているのは私だけではなかった。幾人かの奥さんが泣いていた。
目をとじるとゆうべまでのありさまが頭にうかんできた。
昨日までたのしく暮らしてきたあの煉瓦だての官舎の二階から、庭の野菜畑を見おろしていたおちついた気持ちから、きゅうにこの貨車の上で、ごとごとゆられているのが、とても現実ではないと思われた。
夢なら早くさめてもらいたい。
私は、咲子のために作った赤い着物を、押入の一番上においてきたことを思い出した。
あの着物を一度着せてやりたかった。
咲子が、二階の南側の窓の下でねむっている姿を思いうかべて、そう思った。
何か咲子はまだ二階の部屋にねむっているような気がしてしかたがなかった。
私ははっとしてそばにいる咲子を見た。
私の乳はゆうべからちっともはってこない、乳が出なかったらこの子は死ぬにきまっている。
私はまた涙ぐんでしまった。
「みなさんにちょっと申しあげます。」
そういって戸野さんが立ちあがった。
「この団体は観象台疎開団といいましょう。私が団長として、みなさんと一緒にまいります。」
戸野さんの声は風にふきちぎられて、時々ききとりにくかったが、団体として行動すること、子供の多い人は優先的に保護してやらなければならない、各自のかっての行動はしてはいけない、いちおう団長にことわってからしてもらいたい。
戸野さんは、ふとい眉をぴくりぴくり動かしながら、全員に注意をあたえた。
日が高くなるとさすがに八月だ。
やきつけるような日ざしの下で、人間はひからびてゆく植物のように影をもとめ、水をもとめた。
子供たちはひっきりなしに水を私に要求する。
ときおりとまる小駅で、もっている水筒に水をくもうとするが、いつも力の強い男たちに先をこされて、むなしく貨車にもどらねばならなかった。
それよりもこまったことは、おむつの洗濯である。
停車が長そうに見えたとき、駅にある井戸端で洗おうとすると、列をなしてバケツに水をくんでいる男たちに、
「きたないことをするな。」としかられる。
やむなく駅のそばに臭気をあげて、青黒くよどんでいるどぶ溝で、おむつを洗わねばならない。
「お母ちゃん、水がくめた?」
そういってまっている二人の子供に、私はなんといっていいかわからない。
「くめなかったの、ごめんなさい。」
そういって席に座って、うらめしく熱い空を見あげてふかい息をついた。
ふと前を見ると特等席にいる若夫婦は、一升びんの水をなべにあけている。
ざっというこころよい音が、水ののめない人たちの耳をそばだたせている。
若い男はどっこいしょとなべをもちあげる。
たぶん私たちにわけてくれるんだなと思っていると、そのなべは、となりに座っているまる顔の奥さんの前におかれた。
「おなべで顔を洗うなんて、はじめてね。」
まる顔の奥さんは、たのもしい若い夫の顔を見ながらむぞうさに両手をつっこんで、ざぶざぶと顔を洗う。
そしてその水は、おしげもなく汽車のそとにすてられてしまった。
大きな駅につくと、日本人の婦人会の人たちがおにぎりをもちこんでくれた。
おかずのかぼちゃの煮つけなどもくばられた。子供たらがよろこんで食べている。
私はあとで水を要求されるのがおそろしい。この私の食欲がぜんぜんでてこない。
この女の人たちは、くる汽車、くる汽車にこうしてサービスしているのだろうが、なぜ自分の逃げる用意をしないのだろう。 もうすぐ日本がどうなるか知らないのであろうか。
奉天(ほうてん)を出ると日は西に傾き、貨車の片側にはじめて見るような日かげができた。昭和十八年の四月、日本からはるばる転任してきたときにとおった駅は、もっとしずかな、美しい駅だとおぼえている。
あのときは、正広一人だけであった。今は三人の母として、貨車の上につかれきっている自分は一体どこへいくのだろう。
通化(つうか)へいくとうわさがしきりにとんでいたが、そうではなかった。
蘇家屯(そかとん)からまっすぐ南へくだるか、おりかえして南下するか、大連(だいれん)か朝鮮方面か、いま汽車はその分岐点へきたのである。
どっちでもよい私は、貨車のわく板に背中をもたせて目をつかっていた。
いく先は安東(あんとん)か、朝鮮方面とはっきりわかった。
「ああきれいな夕日だこと。」
立ちあがって地平線を見ている人がいた。私は重たい頭をもちあげた。
空は一面に赤い夕焼けであった。第一夜がおとずれた。
子供たちをなるべく近くひきよせて、さて自分がねむろうとすると、いままでにない孤独がひしひしと身にせまって、見あげる夜空の無数の星が、うごかないで、じっとしているのがさびしく感じられるのであった。
目をあけると汽車はとまっていた。連山関(れんざんかん)であった。遠くどこまでもつづく緑の高黍(こうりゃん)畑の上をわたのような雲がしきりにとんでいた。
汽車が走り出して日が高くあがると、昨日のような暑い一日が、またくりかえしてやってきた。私は昨日よりすこし元気を回復していた。そしていくらかずうずうしくなっていた。まくわ瓜を買ったり、トマトを買ったりする要領がいくぶんじょうずになったらしい。 |
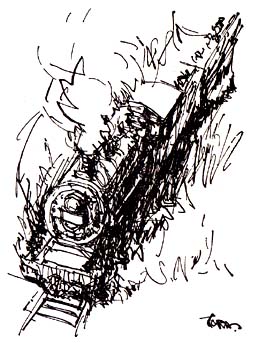
貨車に引揚者を乗せた汽車は、
朝鮮方面へと走って行く。
|
劉家河(りゅうかがわ)で雨にあい、ずぶぬれになったものをいそがしくかわかしながら、今日一日もどうやら無事にくれていくらしい。
地平線に黒くかたまった雲が紫色にそまるころ、私たちの汽車は国境にむかってはしっていた。
男たちが貨車の中央にあつまって、何か相談をはじめた。衆議は一決したようだ。
戸野さんは私たちにいった。
「まもなく汽車は鳳凰城(ほうおうじょう)を通過する、鳳凰城観象所は線路のすぐそばにあるから、みんなで大声で、私たちがこの汽車で南下したことを知らせましよう。鳳凰城観象所から新京の中央観象台へ、電報を打ってもらうんです。」
私はきゅうに救われたように立ちあがった。
夫が新京にいて私たちのことを心配しているに相違ない。その夫につながる一つの連絡線が、まだのこっていると思ったのだ。
私はそこにかわかしてあるおむつの白い一枚をとると、貨車の木わくの人がきの中にわりこんだ。
赤い観象所の建物はすぐ見えた。特徴のある塔とその上に回転する、風速計に風信器(ふうしんき)、私はなつかしいものを見るように見つめた。
汽車はそうとうな速度ではしっている。
どうやらこの小駅は通過するらしい。風力計の風椀(ふうわん)が、きらりきらりと西日に光って美しかった。
「おうい観象所、おうい観象所。」 |

汽車は宣川(せんせん)までで、ここで全員下車した。
ここに一年近く、生活することになる。
|
汽車からの最短距離五十メートルもはなれていないところにある観象所にむかって、みなで声をかぎりに叫んだが、そこには人がいるのかいないのか、だれも出てこなかった。
いよいよだめだとあきらめても、独りくるくる回転をつづけるロビンソン風速計がとてもにくらしかった。
がっかりしてすわりこんで、まもなく第二夜がおとずれた。どこまでいくか、私たちにはわからない。
不安な状態のまま、汽車はごうごうと音をたて、あの長い鴨緑江(おうりょくこう)の鉄橋をわたり、私たちは北朝鮮にはいった。
そのうち、最終地点につくかもしれないという話が、あちこちでいいかわされていた。
しかしなかなか汽車はとまるようすはなかった。
ゆうべのように座ったまま、ねむったような、ねむらないような時間をすごしているうち、すこし大きな駅へ停車した。
南市(なんし)と書いてあった。
ここで停車しているあいだに、各車両の責任者がよび集められ、この列車の最終点は宣川(せんせん)であるとはじめて知らされた。
せんせん、せんせん、私たちを迎えてくれる、せんせんとはどんな町だろう。
私たちは下車の用意をはじめた。ゆっくり眠りたいとそればかり考えていた。
4 終戦の日 top
町はずれの校舎の冷たい板の上に一夜をあかして、さて私はどうしてよいのかと周囲を見まあした。
みな昨夜のままねむっている。ほこりにうすぎたなくよごれた子供たちの顔が、朝の光に白々しく疲れて見える。
宣川(せんせん)農学校、私たちの収容されたこの校舎には、三百名ばかりの女子供が避難してきていた。
私が目をさましてすぐ考えることは、おむつの洗濯である。
一枚の毛布にだきあっている三人の子供をそっとしたまま、私はそとに出た。
朝つゆにぬれている野道をすこしのぼると、きれいな小川がながれていた。
川の岸にそって森の中にはいると、立派なれんがづくりの洋館があった。
その前をとおりぬけると、ぱっと目の前がひらけた。
美しい町であった。
教会の塔らしい洋館、学校の図書館のようにがっちりした建物、その下にきっちりならんだ人家は、うすい朝霧の中にねむっている。
四方山にかこまれた盆地の中に、四角におかれたようなこの町の中央をつらぬく一筋の川と、川をよこぎって山のあいだにきえている鉄道線路がみょうにさびしい。
学校のうらでは男たちが炊事場をつくっていた。
きゅうごしらえのかまどをきずき、釜をおき、共同炊事がはじめられた。
大豆と白米半々ぐらいにたいた握り飯が、一日二回配給された。
大豆がわるかったらしい。子供はほとんど全部、おなかをこわし、大人でも大部分の人がいやな下痢にみまわれた。
だるい体にむち打ちながら、何回も川へ洗濯にいった。
ときおり、飛行機が上空をとぶたびに、一体私たちは、どうなることかと考えながら、そのゆくえを見つめていた。
八月十四日のひるごろ、一台の飛行機が上空を旋回しはじめた。
何かよい知らせにちがいないと、日本人たちは外へとびだしてきれをふった。
飛行機はそれに答えるように、ビラをまいてとびさった。
そのビラは、関東軍の一高級将校が、その家族のゆくえをたずねるためのものであった。
八月十五日は、よく晴れあがっていた。私は正彦をせおって、校庭のポプラの木の下にいた。
そのとき、きゅうにベルが鳴りひびいて、農学校の生徒がどやどやと校庭へ集合をはじめた。
およそ四、五百名いただろうか。体操台の上へ、頭のはげた一見して校長先生とわかる人がのぼった。
私は、これからはじめられる何かをまって、その光景をながめていた。
すると、校長先生は、右手を大きくふって、校舎へはいるようにと合図をした。
どうもその視線が私のほうへむいている。
私はふりかえった。うしろにだれもいない。また大きく手をふっている。
私は、けんぶつをあきらめて、ぎらぎらとてりかえる石段を、ゆっくりゆっくり、のぼっていった。
そのとき、とつぜん背後の生徒の群れの中から、波のような騷音がきこえた。
私はふりかえって見た。その音は、すぐ泣き声にかわった。
白い開衿シャツのイガ栗頭の群れの中からおこるその声は、みょうに私の神経を刺激した。
思わず立ちすくむような気持ちを引き立てて、私は、まっくらな下駄箱のよこを通りすぎて、自分の部屋へいそいだ。
何かおこったにちがいない。
青い顔をした戸野さんの口から、戦争がおわったのだと知らされたのは、その直後であった。
戸野さんの目から涙がぽつりぽつりおちるのを見ていると、突然病的な声で泣きだした女があった。
神経がほそくほそくとがっていて、ちょっとした刺激でも、すぐ感じるようになっていた私たちは、一人の女の泣きだしたのに同調して泣きだした。
私は新京出発以来、何度となく泣いた。
そしてこのニュースを、夫がどこできいてるかと思うと、また泣けてくるのだった。
べつの不安が、私たちのあいだに、すぐわきあがった。
それは、直接死に直面しているような恐怖感からくるものであった。
日本は負けた、すぐそのあとに何かおこるにちがいない。
そのおこるものを極度に誇張して考えた私たちは、いつでも逃げられるように用意をして、十五日の夜をむかえた。
私は咲子をせおったまま座っていた。逃げるとすればこのわずかなリュックサックの全財産をすてねばならなかった。
夫のロンジンをだして星明りにすかしてみると、十二時をすぎていた。
闇の中に白い運動靴をはいたまま、眠らせた正広と正彦の足がからまったり、はなれたりしていた。
朝がまちどおしかった。座ったまま明け方になってすこしうとうとしたと思うと、もうすっかり朝がきていた。
私たちは自分のかげにおびえていたのだ。しずかな朝だった。
子供のねむっているまにおきると、下痢がひどくなって、衰弱してきた体に心のむちをあてながら、乳のような霧の中を歩いて、おむつの洗濯に川へとのぼっていった。
この農学校には乳牛が一ぴきいて、私たちは乳児のために牛乳をすこしずつわけてもらった。
乳児をもつ母親たちは、ずいぶんこれで助かったが、何しろ多数の人たちだったから、とても充分の牛乳は、もらえなかった。
乳の出ない人の乳児はますます衰弱してゆくようだった。
旗の行列が学校のそとをとおり町中にぎやかになった。
私たちは外出を禁止されたまま、不安な日をすごしていった。
5 夫との再会 top
八月十八日の夜おそくなってからである。校舎の中央玄関のあたりがきゅうににぎやかになった。
私は正彦と咲子を寝かせて、子供たちのほころびをぬっていた。
なんだかむなさわぎがするので、手をとめて玄関のほうに気をつけていた。
「観象台の人ですって。」
廊下で、どこかの奥さんの立ち話がきこえた。私は、はっとなって廊下にとびだした。
くらい電灯の下に、十名ばかりの男たちが立っていた。
その人たちの中から、まず、私の知っている新田さんを発見した。
私の夫はどこにいるかとはしりながらさがしたが、その中には見えなかった。
私は絶望のあまり、そこにすわりこんでしまった。
生きる希望を失ったように、ぼんやりとリュックサックをおろして、荷物の検査をしてもらっている男たちの顔を見ていた。 |

観象台の人間が八名、戻ってきた
|
と突然正広が、「お父ちゃんがいるよ。」と、とんでもない声をあげた。
私ははっとなって正広のゆびさすほうを見ると、夫はみなとはなれた前のテーブルにしゃがみこんで、大勢の人にかこまれて何か書いていた。
夫は書きおわると学校関係の人や、送ってきてくれた保安隊の人たちに挨拶した。
私は正広をだいたまま、そこへ泣きくずれてしまった。
男は八名であった。八名の男が合流して完全な家族は十一家族となり、六家族が主人のいない家族として残された。
私は他の人がするようにもちましょうかと、夫のリュックサックに手をかけたが、夫はいいよと、まるで無関心のような顔を私にむけた。
私は夫にいいたいことが山ほどあった。
しかし、夫は私の“おうち”に荷物をおろすとねている正彦と咲子をちょっと動かしてみて、正広に笑いながらおみやげの包みを渡し、戸野さんの庭へいこうとした。
私はいそいでよびとめて、「戸野さんによくお礼をいってね、とても親切な方だったわ。」
夫はうなずいて、するどい視線を私の“おうち”の板の上になげ、それからぐるっとひとわたり室内を見まわすと、大股で戸野さんのほうへ歩いていった。
戸野さんとひそひそと、しばらく話がつかないようであった。
夫の荷物を整理して私はよろこんだ。
毛布一枚を新しくもってきてくれたことと、夫の冬の下着類がそうとう用意してあったからである。
私は今夜から毛布をしいてねむれると思うとうれしかった。
あちらでもこちらでも新しく合流した家族たちは、話がつきないようであった。
あとに取残された六宗族はさびしそうにじっとしていた。
私は夫がそばに座るのをまって、早口で言いたいことだけ言ってしまうとほっとした。
つまらない女のように不平だけならべている自分であったが、言ってしまうと、もうこれまでのことは、どうでもよいというような気がした。
私はモンペの下にもっていたロンジンを引きだして夫に見せた。
「ほら。」
ロンジンは黒いふとい絹紐にぶらぶらしていた。
夫はそれを耳元にもっていって、なつかしそうにその音をきいていた。
時計をはずして夫に渡そうとすると、夫は手でそれをおしとどめた。
私にはロンジンの音のかわりに夫の寝息がそばにあると思うと、もう用のない一個の時計でしかなかった。
ロンジンの針は午前二時をさしていた。
夫は、私たちに会えるとは思っていなかったらしい。
夫の荷物の中には、一つとして私や子供に必要なものはなかった。
いくえにも布でつつんだ四角いものが、底のほうから出てきたので中身を確かめると、それはアルバムからはぎとってきた写真であった。
結婚した当時のものや、子供たちと写したおもな写真だけ、十枚ばかり大事につつんであった。
夫は子供たちのそばに横になると、すぐ寝ついてしまった。
私は夫のもってきてくれた毛布の暖かみがありがたく、ならんで寝ている夫の日に焼けた顔を窓の月あかりでしみじみと見ながら、幾日かぶりの安眠にはいった。
6 新しい不安 top
「藤原さん、だめです。今日から、汽車は平壌以南へはいきません。」
運命の日八月某日(たしかではないが二十四日だと思う)、かくて三十八度線を境として交通は遮断された。
私たちは、ぼうぜんと旅じたくのまま立ちすくんでしまった。
夫はくちびるをかみしめたまま、東の空をにらめつけて長いあいだ動かなかった。
南下がだめだときまると北上をするものがでてきた。
満州は治安が回復しているから、いままで生活基盤をもっていた土地のほうが、ここよりもいいだろうという意見をもった団体(主として満鉄関係)はぞくぞく北上し、また一方、三十八度線が閉鎖されても、なんとかして、とおってかえろうとする少数の人たちもいた。
私はきゅうに移動するときの準備のために、一枚の毛布をきって、正広と正彦のオーバーを作った。
そして不安な日を幾日もおくっていくうちに、九月になった。
私たちは農学校をでて、宣川の町はずれの丘の上の一軒家に、移動することを命ぜられた。
残暑の日ざしが、かんかん照りつける中を、農学校からかりた二台の牛車に四十九人の荷物をかるがるとのせて、町の中心をとおるのをさけて、大きく遠まわりし、昼すぎに丘の下へたどりついた。
見あげると、とても牛車がのぼれそうもない坂である。私たちは手に荷物を持った。
丘の上の一軒家は、宣川神社社務所と書いた小さい木札がさげてあった。
終戦の日に、やけてしまった神社の残骸ととなりあわして、偶然にもやけ残ったこの一軒家は、畳がきちんとしいてあり、何一つ破壊されたものはなかった。
今夜から畳の上でねむれると思うと、私たちは、なんだかここへきたことが、救われたことになるような気がした。
社務所は、町のはずれの丘の上にあって、背後が山つづきとなっていた。
八畳間、六畳間二間、四畳半が二間、つごう五つの部屋にわかれていて、勝手もあり便所が二つあった。
丘の上だから水道の水の出がわるいけれども、夜中におけの中にたくわえておくと、ひるの使用にはどうやら事かかなかった。
夜になると、木かげをとおして町の灯が目の下に見え、町中の騒音が手にとるようにきこえるときもあった。
それよりも私たちにとって関心をもったのは、毎日毎日、目の下の鉄路をとおるおびただしい貨車や、こぼれおちそうに汽車にのって南下していく朝鮮の人たちの群れであった。
いつかえれるかと、なんでもかんでも帰国にむすびつけて考えたがる私たちは、その汽車に日本人らしい姿でも見えると、もしや帰国がはじまったのではないかといいあった。
日本人らしい一群れが乗車していたぐらいの話が二、三日するとデマとなって、疎開団本部にどこかの団体からもちこまれて、夫が会合にいって日本人の一団が確実に南下している、などときいてくることがあった。
私たち四十九人の団体は、畳の上に寝るようになったことと独立して炊事ができるようになったため、にわかに病人が減じ、ときにはたのしい笑いがきこえることもあった。
さらに幸福だったことは、駅の貨車の中に新京からもってきた所属不明の布団が山ほどあったことだ。
雨にぬれて半分くさりかけたようなものだったが、これをかわかしていくらか補修すると、立派に寝られる寝具ができた。私たちは、二枚のかけぶとんをもらってしいて寝た。 、
私たちの家の周囲には、白い野菊が一面に咲いていた。そのなかにときおり黄色い野菊も咲いていた。
私の子供たちは元気を回復してきた。
この丘からは、いろいろのところへつうずる間道があった。
町の中心をさけて、マーケットにいく通路を発見して、男たちは毎日買い物にいった。
そしてすこしばかりのほし魚のようなものを買ってきては、各自が自分の飯ごうで副食物を作って食べた。
サツマ芋を買ってきてにたり、とうもろこしをやいて食べたりして、私の胸はいくらかはりを見せだし、乳もやっと咲子に充分なだけ出るようになった。
一円に三本のとうもろこしを安いとか高いとかといいながら買ってきては、山からひろってきた薪でやいて食べて、満足していた。
五つの部屋に十七家族、四十九人が適当に座をしめて、ほっとしたのもつかのま、この丘の上の一軒家の地理的な条件による新しい恐怖が、私たちをおそってきた。
私たちは、もち金をそとにかくすことを考えねばならなかった。
木の根や石の下、縁の下などに缶詰のあきかんの中に金を入れてかくすのであった。
まず自分たちの団体のだれにもわからないようにかくさねばならなかった。
外部からのおそろしさより、団体のあいだでの盗難は、すでに何回もあった。
私と夫は相談して、金を三つにわけて家の外と家の中にかくした。
私たちは自分たちのもってきた金をだしあって協同生活をしている。
そのうちだれかが、まず金が全部なくなる、そうなったときに、その人をみんなで見てやるかどうかが今から考えられたが、おそらくそれはむずかしいことであった。
最後に協同生活は完全にできないで、自活の道をえらぶだろうが、最後のだんかいにたちいたるまでの命の綱は、満州からもってきた紙幣であった。
十日に一度ぐらい、みなで出しあった満州紙幣をまとめて、朝鮮銀行券と交換した。
百円が五十円になるのであった。日本紙幣は完全に通用しなくなっていた。
男たちは、毎日労働(使役)に出なければならなくなった。朝早くおきて、夜おそくかえってくる夫のつかれきった姿にむくいるものは、一本のとうもろこしか、一個のリンゴぐらいであった。
7 とうもろこしの皮 top
その日、夫は町から三里もはなれた山へ、使役に出かけて留守であった。
私が丘の下の川で、洗濯をしてあがってくると、手にくわやかまをもった一団の朝鮮人が、私たちの家の周囲の木の根や石の周囲を、端から掘りかえしているところであった。
その辺には、私たちの私製金庫がかくしてあるはずだ。
私の部屋の窓のはしから遠くの岩を見とおして、三本目の落葉樹の根毛とに、私の金がうずめてあった。
ところが、いま一人のハンチングをかぶった男が、その落葉樹のとなりを掘っているのである。
その男は念入りに、その付近の木の株を、一つ一つ掘ってはその傾斜面をのぼってきたのであった。
「奥さん、ほら、あなたのところを掘られそうよ。」
すぐそばに、立っていた、大地さんの奥さんがいった。
私は、しいっと口で制して息をのみこんだ。
その男は念入りに、その落葉樹の根を、ほじくりかえすと、今度は、すぐ横の私の場所へやってきた。
私は思わずおっと小さい声をあげた。
その男は手をとめて、下から私たちの顔を見あげた。
とどうじに、その男から一間ばかりはなれた岩のところで、大きな音をたて、石が下へころがり落ちたその石の下から、小さい缶詰の缶が現れた。
誰かのがついに掘り出されたのであった。
私の金庫の前に立った男はきゅうに気をかえた。
くわをもちかえると、いま発掘されたところのほうが確率がよいと見たのか、いそいでそちらに位置を加えた。 |

埋めて隠してある引揚者のお金を探して、
方々を掘りまくる朝鮮人
|
そして数人の男が岩を中心として発掘をはじめた。
保安隊の人が、馬にのって口笛をふきながら坂をのぼってきた。
男たちは、あわてて姿をけしてしまった。
被害者は崎山さん一人であった。
二人の幼児をつれて八か月の身重で、しかも主人がいない崎山さんは、条件の悪いほうでは、この団で一か二であったろうが、その人のお金がなくなってしまったのである。
もちろん全部ではないはずである。すくなくとも、三か所以上に分散しておくというような規則を守っていたなら……。
奥さんは涙をためていた。だれにもなぐさめられたくない、というような、恐ろしい顔をして立っていた。
私は、はっとしてあたりを見交わして、大地さんの奥さんと顔が合ってはっとした。
私のかくし場所を大地さんの奥さんが、どうして知っていたのだろう。
「奥さん、どうして、私のかくし場所を知ってたの?」
「あら、私だけではないわよ。みんな知っていたようよ。」
あの金をかくした朝は霧にふかい朝、みなの食事中を利用して私が部屋で監視している間に夫がうめにいったはずで、だれもこの家から出たものがないのに、どうしてみなが知っていたのか、私は自分たちの周囲がおそろしくなった。
私はやぶの中をかけおりていって、いそいで掘り出してきて金庫の中をしらべた。
紙幣は土くさかったが金額には異状がなかった。
紙につつんでそれを飯ごうの下に入れ、主人の夕食のぶんとして配給されたすこしばかりの芋ごはんを、その上にもって安心した。
私の主人の帰るまで、飯ごうとにらめっこをしていればよい。
身のまわりに金をおくと、あぶない。そとにおいてもあぶない。
一体どうしたらよいか。
着物のえりや、帯のあいだや、糸巻のしんに、百円札を入れておくといったことは、だれでも知りすぎていることであった。
私と夫は毎日このことを考えていた。
夫は時々考えこんで、ものをいわないことがある。
ある朝夫は朝食の途中で、箸をうごかすのをやめた。夫は窓のそとの何かに、するどい視線をおくっていた。
「何を見ているの。」
そこにはとうもろこしの皮が、捨てられてあるだけだった。夫は労働に出かけるときに、私の耳もとでいった。
「よい方法が見つかった。とうもろこしの皮をできるだけ集めて、かわかしておいてくれ。」
「どうするの?」
「ぞうりを作るんだ、今夜から。」
夫には、何か深いたくらみがあるにちがいない。
私は夫にいわれるままに、とうもろこしの皮を集めておいた。夫はその晩から、ぞうりを作りはじめた。
農家の出である長須さんから、ぞうりの作り方を教わっていた。
「藤原さん、なんだって、とうもろこしの皮なんかでぞうりを作るんですか。」
長須さんは、けげんそうな顔できいている。
「ぼくは大発見をしたんですよ。とうもろこしの皮には脂肪分が若干はいっていて、それに、非常に強い繊維でできているから、わらぞうりより強いし、第一ぬれても、びしょびしょにならないからね。」
夫はかってなりくつで、長須さんを煙にまいてから、ぶかっこうなぞうりを二足ばかり作った。
あまりおかしいのでみなが笑ったが、本人はへいきであった。
三足目を夜おそくなってから靴ぬぎのところで一人ではじめた。
とうじは不寝番が、一人ずついることになっていた。
夫は自分で、前半、夜の不寝番を引受けてぞうり作りをした。
夫はぶさいくなとうもろこしの皮ぞうりを、二足作った。
その皮の中には、小さくたたみこんだ百円紙幣、十円紙幣が千円ばかり、非常用としてあみこまれた。
私は夫の思いつきに、なるほどと感心した。
そして夫にいわれるままに、二、三度はいて歩いて底に泥をつけて、子供の靴と一緒にリュックサックのかたわらにおいた。
つぎに夫のロンジンは大きな洗濯石鹸をくりぬいてあなをあけ、パラフィン紙につつんで中に入れ、べつの石鹸から、あなにあうように一片を切りとって間隙をうすめ、注意ぶかくすきまに石鹸の粉をすりこんでから暖めてやった。
だれも知らない間に、時計のはいった石鹸ができあがった。
何度も何度も火にあぶって、完全に一つの固体に見えるようになってから、その石鹸を水で使用した。
角がしぜんにまるくなった。私はそれを、あきかんの中へほうりこんでおいた。
こうして私の大きな財産は、充分に隠匿(いんとく)できた。
幾日もかかって、この二つの大仕事をなしとげてほっとした。
だれも気がつかないらしい。
8 夫よどこへ top
庭に一本のもみじの木がある。みきがくの字になっていて、その頂点から、三本の枝が同時にはりだしている。
もみじが全部おちると、すでに十月、靴下をはいて寝ないと冷えて、夜中に目をさます。
でも日中はまだ暖かい。木のみきからみきにひっぱった綱におむつをとおしていると、爆音がきこえる。
見あげると、見たことのない標識をつけた飛行機が、北のほうへとんでいく。
「大地さんいませんか。」
ふりかえると、駅の人が、にやにやしながら立っている。
私たちはニュースにうえていた。
大地さんが運動してこの駅の人と仲良くなり、夜になるとこっそり丘をくだって駅の人のラジオを聞きにいく。
そしていろいろのニュースをきいてくる。
十一月に南下するという情報もここらあたりからでたちのらしい。
大地さんとつれだって森のほうへのぼっていく駅の人のうしろ姿を、私はなにか新しいニュースでもあるかもしれないと、期待をかけて見おくっていた。
私はぐうぜんの機会で、夫の遠縁にあたる五味老人を知った。北鮮で小学校の先生をしていた人であった。
老夫婦二人で小さい部屋にとじこもっていた。
ときおりこっそり、衣類や古雑誌(紙は貴重品であった)をもってきてくれた。
十月二十日、ひょっこり五味老人がやってきた。
疎開してきた団体からさきに、十一月早々内地へ引き揚げるそうだが、もしできたらあなたの家族の一員として一緒に帰れないものかと相談にきた。
夫はそのうわさの根拠をつきとめようとしたが、かいもくわからなかった。
もとをただせば「駅の人の情報」から出たのかもしれない。
五味老人は、人のよさそうな顔をして笑ってかえっていった。
十月二十五日ごろ、駅のほうの人の動きがなんとなく活発となり、貨車の入換えがさかんに行われていた。
私たちは、もしかすると帰国できるのではないかと胸をときめかしていた。
夕方、男たちがかえってくると、まえよりまして、希望にみちた笑い声がどの部屋にもおこった。
翌日は旅行用として、飴や携帯食糧が用意されはじめた。
しかし駅のほうは、その後一日に三回か四回とおる汽車以外に、べつにかわったことはなかった。
十月二十八日、まだ、ふかぶかとねむっている私たちの家の門を、しずかにノックする音がきこえた。
不寝番がすぐ応対した。れいの駅の人であった。
駅の人は大地さん、大江さん、私の夫の三人に外へ出てもらいたいといった。
私は何か胸がさわがしかった。不吉の予感が私の胸をはしった。
どの部屋でもみな目をさましたらしい。しずかに三人のかえりをまっていた。
三人は死人のように青い顔をしてかえってきた。
いそいで食事の用意をするように、炊事の当番にいってから、三人はふたたび四畳半にひっこんで何か重大な打ち合せをしているらしい。
夫が紙をとりに帰ってきたとき、私は小声で、
「何かおこるの? いって。」
しかし、夫は周囲の人に気がねしたのか、
「いますぐ発表する、とにかく用意しておいて。」
「なんの用意?」
それには夫はこたえなかった。
外へでてみると、町は完全に霧に中にしずんでいた。
その底のほうから、まだ薄暗いころだというのに、いろいろのひびきが伝わってきた。
何か容易ならぬできごとの前兆のように、子供の泣き声や、ものをうごかす音などが不規則にきこえてきた。
そして、すぐこの丘の下の小学校の校庭では、時々するどい号令のような男の声がきこえてきた。
女たちは、ただうろうろするばかりであった。
でも用意しろといった夫の言葉どおり、いちおう私の全部の持ち物をそろえてみた。なんにもありはしない。
馬のかけあがってくる音がきこえると、保安隊の人がきて、団長に、すぐくるようにいった。
夫はどこへいったか見えなかった。不安になって外へでると、霧にふかい山の中から缶詰の金庫をもってきた。
夫はいそいで中身をぬきとっていった。
「十八歳以上四十歳までの日本人男子全部が、汽車で平壌へいくのだ。さあこれが全財産だ、あとはおまえにまかせる。」
「平壌にいって何をするの。」
「それはわからない、シベリヤへ、いくのかもしれない。」
「シベリヤへ?」
私はもう何をいってよいやらわからない。
すべてがおわりになったように、その紙につつんだいくばくかの紙幣をにぎりしめたまま、立ちすくんだ。
「すぐ用意してくれ、金はいらない。必要品だけそろえてくれ。」
夫は、私にそういっているまも、気がせくようにしていた。
夫は共同で隠匿(いんとく)した金のしまつや、いままでの団のひきつぎやらを、しなければならなかった。
団長がかえってきた。
「三十分以内に、下の学校の校庭へ、十八歳以上四十歳までの男子は集合せよとのことです、すぐ用意してください。」
大きな動揺がおこった。私はすぐまえにいた長須さんの顔を見た。四十歳までといったとき長須さんはにやりとした。
長須さんは四十三歳であった。すべての用事をすませると、夫は私たちのそばへかえってきた。
これで、永久の別れになるかもしれない。
夫は黒い背広を詰えりになおした服をきていた。
朝食はのどにとおらなかった。夫の弁当箱へ残りのめしをつめた。
夫はリュックサックの中に、さ着替えのシャツやズボンをいれたのを、もう一度検査してから、
「それはいらない、これもいらない。」といって冬物をはねだした。
夫は、あとの私たち母子のことを、考えているにちがいない。
保安隊の人がむかえにきた。
「早くしてください。」
そういいながらも、気のどくそうに私たちから目をはなしていた。
毛布をもっていくように、私がいうと、夫はつよく反対した。
なんとかなるからと私は泣いて頼んだ。夫はふしょうぶしょう承知した。
金も五百円やっともたせた。いよいよ最後がくると、夫は咲子の寝顔を見ていった。
「よく寝ているなあ、正広の小さいときとそっくりだよ。」そして片ひざを立てて、正広の肩をゆすぶりながらいった。
「今度はお父さんは、かえれないかもしれない。お母さんのいうことを、よくきくんだよ、ね、ね。」
正彦は、私がひざにだきかかえていた。三歳でまだあまえたりない正彦は、私のお産と終戦とがどうじにきたので、いきなり激しい嵐の中におしだされて、やせて目ばかりが大きかった。
正彦のめんどうは夫が見ていてくれた。毎夜二度おしっこにおこすのも、夫の仕事であった。
「正彦ちゃん、お母さんのいうことをよくきくんだよ、ね。」
正彦はおそろしく大きな目で夫をにらみつけるように見つめたまま、なんともいわなかった。
私には、簡単に一言いった。
「直接、故郷へかえるように。子供たちのことを頼んだよ。」私はなんにもいえなかった。
ただ、ほろほろとおちる涙の中で、
「元気でね、きっとかえってきてね。」というようなことをくりかえしていた。
十一名の男のうち、四十歳以上の大江さん、新田さん、大地さん、長須さんの四名を残して、七名の男は門前に整列した。
夫は、残ったみなにむかっていった。
「みんな協力して、仲良くやってください。」
みんなに挨拶がおわると、夫はもう一度私のそばにきて、抱いていた正彦のほおを指でちょっとつっついて、
「正彦ちゃん、さようなら。」といった。
と、いままでおびえたように黙っていた正彦がきゅうにはげしく泣きだした。
正彦よりもっと大きな声で、私は泣きたかった。
霧はしだいに晴れていった。
|

収容されていく男たちを丘の上から見送る日本人家族たち
|
内地引き揚げ列車だといわれた貨車は、この町の男たちほとんど全部をどこかへもってゆくためのものであった。
私たちは、全員丘の上に立って、真下をとおる男たちの乗っている汽車を見送った。
その無蓋貨車は、ゆっくりゆっくり発車した。夫の黒い服はすぐ見つかった。
ハンケチをふっている夫に私も手ぬぐいをしきりにふった。
夫はハンケチをまるくふった。私も手ぬぐいをまるくふって最後のさよならをした。
一瞬、汽車は速度をだし、眼下をとおりすぎていった。
十月二十八日、それは忘れられない悲しい日の一つであった。
9 涙の丘の上 top
秋の日は高くなっていった。
私たちは汽車ののこした煙が見えなくなり、駅の人波がちって町全体がしずかになっていっても、まだ丘の上に座ったまま黙っていた。
汽車が見えなくなっていった遠い山のほうをむいて涙ぐんでいた。
夫とわかれた奥さんは、一人ずつはなればなれに、草の上の石の上に座って泣いていた。
「藤原さん。」
うしろをふりむくと、大江さんが立っていた。
「藤原さんから、これを奥さんにかえしてくれとたのまれました。」
大江さんは、手に毛布と毛糸のズボン下をもっていた。
「これをどうして。」
「こまるだろうって心配していましたよ。そして、このお金も渡してくれるようにだのまれました。」
金は三百円あった。
「ばか、ばか。」
私は心の中で、はげしく夫をせめた。
一体シペリヤヘいくというのに、どうして一番大切なものを返してよこしたんだろう。
まるで自殺行為のようなものだ。夫は私や子供たちのために、これを残しておいて、気持ちの上で満足するかもしれない。
しかし私はこの毛布を見るたびに、毎日毎晩、夫の身の上を案じなければならない。
そんな、精神的重荷を残していった夫をうらんだ。私は大江さんに、ありがとうをいうのを忘れて立っていた。
「奥さん、それからあなたは知らないかもしれませんが、藤原さんにずっとまえ、市場で四十円貸してあったんですが……」
「ええ、何か四十円ですか?」
「四十円、私が立てかえておいたんです。」
四十円なんてどうでもよい。しかもいま私がこんなに心をいためているときに、貸し金を忘れずに取っておこうとする大江さんの顔は、まともに見るのがいやだった。
私は四十円を大江さんにかえした。そして、「今日からしっかりしなければ。」と強く感じた。
社務所の炊事場のふきんに輪になって、私のほうを見て、ささやきあっている人たちがいる。
はじめから、夫と別れてきた人たちであった。
この人たちは、いまや自分たちと同じような境遇におかれた七人の女たちが、あちこちでべそをかいているのを、すこし高いところからながめおろして、何かひそひそ話をしていた。
私の視線が、その人たちの目とぶつかると、何か悪いことをいいあっていたあとのように目を平らして、グループの輪をといた。
「奥さん、これから大変ですね。」
名越さんがいった。一人の乳飲み子をもっていて、私たちの団のうちでは、一番若い奥さんであった。
名越さんは私に、お世辞だか、なぐさめだか、からかいだか、わからないことをいうと、ぷんとすまして背を向けた。
今日からしっかりしなければと、私は胸のそこに強く思った。
ぼうぜんと立っている私のかたわらによりそって、時々私を見あげる正広の顔や、あいかわらず、おこった顔をしている正彦の顔を見ると、夫と別れた悲しさが、はげしくこみあげてきた。
私は咲子のことが心配になって、部屋に帰った。部屋にはめすらしくだれもいなかった。
咲子はねむっていた。
「咲子、お父ちゃまは行ったんだよ。ね、咲子、行ったんだよ。」
私は咲子のねむっている顔にほおずりして泣きふした。
声をたてて泣く自分の姿がどんなみじめなものか、三人の子供が、一番よくわかっているのであろう。
正広はいっぱい涙のたまった目を見ひらいていた。
私は、それから三日間はただぼんやりしていた。しっかりしなければと私のどこかでだれかがささやく。
でも私は何もすることがない。一人になると涙ぐみ、夫のゆく先のみ案じているのだった。
残った四人の男は、日本人会の本部に、かわるがわるいってきては、額(ひたい)を集めてしきりに話をしていた。
いままでのけ者にされていた新田さんも、その一員にくわわっていた。
四十歳までと年齢を制限されたとき、長須さんはにやりとした。そして二、三日、おおいに張切って働いた。
「奥さん、泣いてばかりいたって、しょうがありません。さあ、働いてください。」
と、人ごとのようにいいながら、血色のよい顔でおかゆの釜をのぞきこんでは、女たちに世話をやいていた。
その長須さんが、三日目の夜になると、がくりと首をさげて考えこんでしまった。
私は、病気にでもなったかと思って、大地さんの奥さんにきくと、
「男は全部だめだって、四十五歳までは病人でないかぎり、つれてゆかれるんですって。」
大地さんの奥さんは、心配そうにいった。
「それほんと?」
「ほんとらしいんたって、私はどうしたらよいか、わからないわ。」
そのデマがどこから出たのかわからないが、残った四人の男たちはきゅうに元気がなくなって、身のまわりの整理をはじめた。
夫とわかれて四日目に、私はやっと自分をとりもどした。泣くより、今後の方針を立てねばならなかった。
七名の男たちがいってから、ちょうど五日目の朝、くらいうちに、まえと同じように悪い運命を知らせる人、あの駅の人が戸をたたいて、残りの四名の出発を予告した。
朝八時までに小学校の校庭へ、このまえいかなかった男と、四十五歳までの男全部が集められた。
新田さんは熱をだす弱い体で、とてもみなと一緒に行動はできないと思われた。
さいわいに新田さんは、病気の理由でゆるされた。五日前に見たと同じ悲劇を、今度は私が観察する立場となった。
大江さんは団長としての責任を新田さんに引きついでから、姉さんとしみじみ話していた。
団長として三ヵ月間よく働いて、団の人から尊敬よりもおそれられていた大江さんは、ところどころに白髪が見える頭をみなの前にさげていった。
「長いあいだ、ありがとうございました。姉をおねがいします。」
私はいつかの晩、私の夫をささいのことで畳の上に手をついてあやまらせたこの団長に、敵意を感じていたが、いまさびしく丘をくだっていくその姿には、なんのうらみも感じなかった。
大地さんの一番上のせい子ちゃんは、「お父さん、お父さん。」とさけぶように泣いていた。
十四歳の美しい少女は、奥さんのとめるのもきかずに、父の手にすがりながら丘をくだっていった。
その姿に私たちは泣かされた。
「―― 体を丈夫にしてな、むりをするでないぞ。」
長須さんは、奥さんと五歳のひさ子さんにそういって、男泣きにぽろりぽろりと涙をおとしながら、その大きい体を何度もねじ向けては、こちらを見ながらおりていった。
新田さんは今日も熱があるのか、赤くほてった顔をななめに苦しそうにかしげて、無表情に立っていた。
汽車は丘の下をすぎていった。貨車に乗せられた男たちは、まえよりもずっとすくなかった。
「ひさ子、おお、ひさ子、おお。」
と風にちぎれて切れるような長須さんの声が、貨車の上からきこえてきた。
一人娘の身の上に、最後まで執着している長須さんのまっ黒い顔とその声は、丘の下を横にながれる汽車の煙でむなしくへだてられ、やがて煙のきえるころ、もう汽車の姿は山のむこうにさって、音もなかった。
私は、ここで、人員点呼をしなければならない。私の団は、
男子(大人)
人妻
娘(倉重さんの妹)
未婚老婦人(大江さんの姉)
子供 |
新田さん一人
十六名
一名
一名
二十名 |
|
計 |
三十九名 |
病人の団長の下に、骨抜きにされた三十九名の小団体は、今夜から新しい涙とともに、粥(かゆ)をすすらねばならなかった。
10 無抵抗主義 top
私たちは日本人とよばれた。あたりまえのことであるからだれも腹をたてるものはいなかった。
それなのに、私たちが、朝鮮人というと、彼らは非常に腹をたてた。
それで、彼らの感情を刺激しないためにも、私たちはこちらの人とよぶことにきめていた。
でもうっかりすると、すぐ朝鮮人と口からでてしまう。
ゆうべからふきつづけている北風が、今朝になってもまだやまなかった。
私たちは背をまるめて、部屋のすみへかたまっていた。
そのとき、西側の窓がものすごい音でやぶれた。一同顔を見合わせた。つづけてまたわれた。
ワァーッと子供の声がしたので、そっとのぞくと、十四、五歳の子供が五、六人、両手に石をにぎって、窓をめがけて投げている。
私はあわてて咲子をせおった。やがて、どの窓も、あのようにされるかもしれないからである。
新田さんが立ちあがって、北側の雨戸を音のしないようにしめた。
そして私たちは、そのまっくらな部屋へのがれるようにかくれた。
子供たちは一声もあげはしない。私に手をにぎられたままじっと鼻水をすすっていた。
保安隊へ連絡すれば、どうにかとりしまってくれるかもしれない。
しかしこの丘の一軒家から、だれが坂をおりて知らせにいくのか。だれにもその勇気はなかった。
うかうか外へでれば、ふくろたたきにされるか、間違えば殺されるかもしれない。
ガラスのくだける音が足元に炸裂する弾のような恐怖をさそう。
新田さんの一人ごとは怒りにふるえていた。
白い首の包帯が、雨戸の隙間からくる光にぼんやりうつっていたいたしかった。
「新田さん、あとで紙をはれば何とかなりますわ。」
私は、それでもいくぶんなぐさめるつもりでいった。
新田さんは、「たかが子供に。」といっただけで、黙ってしまった。
まもなく子供の足音が、炊事場のほうへまわったらしかった。
ガタン、カシャン、と金属性の音がした。
「あ、飯ごうが。」とだれかがいった。そしてまもなく音はしなくたった。
私たちはあわてて炊事昜へとびこんでみた。そこへおいてあったはずの飯ごうが、五つとられていた。
「あれ一つきりないのよ、あれがなければ、これからなんで煮炊きすればいいの……」
大地さんは、げっそりやせたほおへ、いく筋も涙をおとした。
「それにあれは、おいもをいっぱいつめておいたのよ、お夕飯にするつもりでねえ。」
「泣いたって、しかたないじゃないの。」
せい子ちゃんが横から大地さんの袖をひっぱって、部屋の中へはいっていった。
目つきのよくない男が、家のまわりをうろうろする日があったり、つまらない、いいがかりをつけてくる男があったり、平壌にいる夫たちから依頼されたなどといって、じょうずに近寄ってくる男などがいた。
近くに寄ってくる朝鮮人すべてにたいして、私たちは警戒の目でながめていた。
本当に私たちに好意をしめしてくれる朝鮮人は、けっして私たちに近寄ろうとはせず、道ですれちがったときに、そっと子供たちにリンゴをにぎらせたり、飴をくれたりした。多くは老人であった。
若い人は、私たちを見ないようにして通るほうが多かった。
私たちはすべてに対して、無抵抗主義にならされていった。
そうしないと、一部の日本人ぎらいの朝鮮人に、どんな目にあわされないともかぎらないからであった。
子供たちもそれを知って、土地の人に会うと明らかに恐怖の色を顔にうかべて、母親のそばにすりよるのであった。
11 流れる星は生きている top
雪はやんでいた。風がふきだすのに、しばらくのまがある。私は正広の手をひいて外へでた。
くずれかけた石段のわきに一本の松の木があった。
私はいつもするように、その松の葉のひとつかみをとった。松の葉はひやりと手につめたかった。
松の葉は根元で二本がかたく結ばれている。
私はしっかり結ばれて離れない松の葉の一対を一個にかぞえた。口でかぞえながら一つずつすてていった。
そしてその全部の数が偶数であったならば、夫はまだ丈夫で生きているということに、心できめていた。
もしその数が奇数であったならば、夫とはもう二度とあえないものとした。この松葉の占いはだれにもないしょで、ずっとやっていた。最近二、三日つづけて、占いは凶に出ていた。正広には私のやっていることがわからないけれども、私の占いが吉にでて私がうれしそうな顔をすると、正広も笑ってくれた。
占いのおわるまで正広はしんぼう強くまっていた。
今夜はとくに心に夫の身のぶじを念じながら、雪の上に針のようにこおった松の葉をおとしていった私は、最後の数が二十六であった。夫はまだ生きている、私は最後の松葉を大事そうにとりあげて、
「正広ちゃん、ほら。」
正広にその葉を渡してほっとした。 |

いつものように松葉の占いをやって、久しぶりに“吉”と出たので、
正弘に最後の松葉を渡してほっとする筆者
|
「奥さん、何をしているんですか?」
突然、背後で若い男の声がした。私のすることを黙って見ていたにちがいない。
その男は保安隊の腕章をしていた。私は悪いことでも見つかったように小さくなった。
「観象台の疎開団は何名でしたか。」
この人はべつに私のしていることを、気にとめてはいないらしかった。
あがりこんできたこの人はいちおう人員、性別、年齢、生活状態などをしらべてから雑談にはいった。
この人は、日本の航空隊にいたとのことであった。
日本の終戦当時の混乱のようすを、そうとうくわしく話してくれた。
私たちの帰国に関してきいてみても、夫たちのゆくえについても、全くわからないと、正直に話してくれた。
金さんというこの人は、毎晩のように雪の道を私たちの団へ遊びにきた。
子供たちは金さんのくるのをまっていた。かならずポケットに飴をしのぼせていたからである。
金さんはとても美しい声の持ち主たった。
流行歌をうたってくれた。さびしい流行歌を、なんべんもうたってもらった。
「だれも知らない歌を、ご紹介しましょうか。」
といって金さんはある晩、ほんとにだれも知らない歌を紹介してくれた。
「南方にいたとき、私の部隊の兵隊が作詞して、べつの兵隊が作曲したんですがね。
二人とも終戦まぎわに死んでしまいました。」
金さんは当時を思い出すのか、ことさら悲しい声でうたってくれた。
そして私たちはいつかこれをおぼえ、口ずさむようになった。
流れるように悲しいメロディーは、沈みきっている私たちの心の中で、やっとこらえている涙を、いつのまにかさそいだしていた。
歌は三小節から成っている簡単なものであったが、何か私たちをひきつけてはなさない魅力を持っていた。
私の胸に咲いている
あなたのうえたバラの花
ごらんなさいね 今晩も
一人でまってるこの窓の
星にうつって咲いている
私の胸に泣いている
あなたの呼んだあのお声
ごらんなさいぬ 今晩も
二人でちかったあの丘に
星はやさしくうたってる
私の胸に生きている
あなたのいった北の空
ごらんなさいね 今晩も
泣いて送ったあの空に
流れる星は生きている
私はこの歌をおぼえてから、ぶじに国へ帰りつくまで、心の中でうたいつづけていた。
ちょっとした空虚ができると、口をついて出てくるものはこの悲しい歌であった。私だけではなかった。
私たちの団体が最後までうたいつづけた歌が、またこれであった。
木本さんはとくに美しい声でよく歌っていた。
私は働く手をやめて、木本さんの声にききほれていることが何度もあった。
金さんは十二月末になると、ぷっつりこなくなった。一体金さんは、なんのために私たちのこの団に遊びにきたのか、わからなかった。
最後まで金さんは、私たちの団のよい友だちとしてきてくれた。
あまり日本人と仲良くするから、保安隊をやめさせられたというような風評がたった。
金さんにはずっとあとになって市場で一度出あった。
その姿がずいぶん変っていたので声をかけるのをさしひかえているとむこうから話しかけてきた。
「やあしばらく。みな元気ですか、あなたの子供さんも元気ですか。」
そういう金さんは、まえからみるとずっとやせほそっていた。金さんは二言三言、話してからいった。
「一体、どうしてあなた方は、生きているんですか。私たちでさえ、生きるのに苦しんでいるのに。」
金さんとこんな会話をしたのは、ずっとあとになってからであった。金さんはなつかしい思い出の人であった。
12 今ぞ恋しき top
雪がふりやむと風がふく。風がすきまから雪をふきこんで、部屋の温度をさげる。
風がやむと骨のいたかような寒さが襲来してくる。
山の上の一軒家は寒さの中に取残されて、ぴしりぴしり音をたてている。
私は、もっているすべての衣類を子供にきせて、一枚のふとんの上に三人ならべて寝かせ、その上に一枚の毛布をかけた。
それでも子供たちは、足がひえるので寝られないらしく、咲子と正彦は、がわるがわる泣くのであった。
私は六本の足を全身で暖めてやった。
足を私の胸やおなかにだいて、じっと体をまるくしていると、すこしずつ子供の足が暖まってくる。
子供たらがやがて静かな寝息をたてる。しかし私の背中は氷のようにひえきって、背骨が寒さにいたい。
子供がか眠ると私は寝られない。暖まった足を、そのまま動かさないように、じっとして朝のくるのをまっていた。
こんな夜がつづいた。
私は昼間ガラス戸をとおして、太陽が暖かくさしこむころをみはからって、一時間か二時間縁側に出て仮睡した。
十二月の中ごろの、このきびしい寒さにたえられていく自分が、ふしぎに思われた。
十二月がおわりに近づくと、副団長の倉重さんは、団長の新田さんと性格があわないという理由で、副団長をやめた。
そして選挙が行われて、私にそのお鉢がまわってきた。
なんという残酷なことをする団体だろう。私はいままでになくとりみだして抗議した。
倉重さんは六歳の子供が一人、しかも妹さんがいてなんでもしてくれる、恵まれた条件であった。
ほかに子供のない身がるの女たちが五人、子供一人の女が二人もいるのに、この団でもっとも子供の多い私にその役をさせるとは。
新田さんはほとんど半病人である。
いろいろ外部との折衝は、私が咲子をせおって、雪の道をあるかねばならない。
でも選挙すると私に全部が投票した。
私が八方美人的に、だれとも喧嘩しないので人気があるのかもしれない。
私はけっしてけっして、八方美人的の女ではない。
私の夫がよくいっていたように、私は冷たい激しい性格の女であると自分でも思っている。
ただ私のいない留守に子供がいじめられてはと思って、猫をかぶっているのである。
国へかえるまで、だれとも喧嘩をしないことにしているのである。
私がもし一人だったら、とっくに敵をつくっていたと思う。
おそらく団体全部をむこうにまわして、私は喧嘩をしていたにちがいない。
副団長はやはり私にもってこられた。
日本人会本部との交渉、保安隊との折衝、配給、予算、私は新田さんと、これをやらなければならない。
「それなら、当然もらう権利のある私の家族の配給分の米二合をかえせ。」
私は何度も胸の中でいってみた。しかし、これもついに歯をくいしばって、我慢した。
十二月三十一日の晩、忘年会をしようということになった。
一人あたり二円ずつ出しあった。私は十円のおさつ一枚を出すのがとてもつらかった。
でも協同してお正月の用意をするのは楽しかった。かたどおりのゴマメ、こぶ巻き、煮つけなどができあがった。
それに、ほんのすこしばかりの餅をついたのである。杵(きね)も臼(うす)もいらない、簡単な餅つきであった。
十二月三十一日の晩、全員一人一本ずつの飴がくばられて忘年会がはじまった。
一人ずつかくし芸をすることになった。男がいないとなると、女はこんなに心臓がつよくなるものかと思った。
大人も子供もみんな歌をうたった。
五十二歳の大江さんまで「黒い瞳よ今いずこ」と古い歌をうたい、笑顔をけっして見せたことのない崎山さんまでが、佐渡おけさをじょうずにうたったのである。
新田さんの奥さんは「コロラドの月」を英語でうたい、私は「小諸なる古城のほとり、雲白く遊子かなしむ」をうたった。
たった一人うたわない人がいた、新田さんであった。
新田さんは部屋のすみに小さく横になって毛布を頭からすっぽりかぶっていた。
一通りうたいおわると、今度は声に自慢の人が、何度も何度も立ってうたい、また座ってうたった。
歌はしぜんと悲しい歌にかわっていき、その歌声にききほれては涙ぐんできいていた。
倉重さんの妹のくに子さんが立ちあがった。二十歳の胸はまるく、目は大きくうるんで、美しい娘さんであった。
「私の自作の短歌を朗詠いたします。みなさん笑わないでくださいね。」
くに子さんは一瞬しずかになった部屋の中央に立って目をつむっだ。
そして流れるようになめらかに高くあるいは低く、悲しい悲しい短歌をひといきにうたいきった。
くちびるをわが手に当てて 泣きいたりし
かの人恋し いまぞ恋しき
くに子さんは、結婚直前にわかれた愛人のことをうたっているにちがいない。
かの人こいし、いまぞこいしき、その言葉は全員に共通した合言葉であった。
「もう一度、うたって。」
金屋さんが感激していった。朗詠は二度、三度とくりかえされた。
そして、その悲しい歌を、みな涙を流してきいていた。それでもまだやめさせようとしないで、
「もう一度、ね、もう一度。」と、くに子さんに泣き声で頼むのであった。
くに子さんはあふれる涙をふきもしないで、何度も何度も歌っているのである。
ついに泣き声で声がつぶれてしまうと、くずれるようにたおれてしまった。だれもだれも泣いていた。
何も知らない子供たちまでが、母にとりすがって泣いていた。
13 氷の日時計 top
一月になってから、日本人の小学校の開校がゆるされた。紙も鉛筆も教科書もない子供たちだったけれども、よろこび勇んで坂をくだっていった。
私たちの団からは三名がかようことになった。
私たちの団体(他の団体もそうであったと思う)には時計がなかった。
あってもいろいろの方法でかくしていた。
学校へいくようになると、時間が問題になった。
新田さんは日時計を作ってくれた。家の前の日あたりのよいところに、縄を半径として円を書いて、その円周上に方位のしるしに棒をうちこんだ。
新田さんは星の夜、北極星を観測して方位をきめた。そして枝切れで作った三角じょうぎと縄のコンパスでみごとに日時計を作りあげた。
バケツに水をくんできて棒にかけると、こちこちにこおった。
氷の日時計ができあがった。
最後に、中心に立てた棒がすこしまがっていたので、新田さんはしぶい顔をして、
「だれか、まっすぐの棒をさがしてきてくれないかな。」といった。
「あれだけまがっていると、ずいぶん時間がちがうんですか?」私がきくと、
「そうですね、十分ぐらい誤差が出るでしょう。」
「十分なら、けっこうじゃないの、ねえ。」
私はそばに立っている倉重さんを見あげていった。
「ほんとに、そんなによくわかるものかしら。」
倉重さんも感心していた。しかし新田さんは、あくまで中心の棒のまっすぐなものを、ほしがった。
棒一本もなかなか見つからなかった。
十分誤差のあるという日時計は、その効力を発揮しだした。
新田さんは私たちにその見方を教えた。みんなよろこんで日時計を利用した。
保安隊の人が私たちの団体に用事があってきたとき、その人の時計と比較してみた。日時計との差が十五分あった。
「十五分もちがうのはおかしい、あの人の時計のほうが狂っているにちがいない。」
新田さんは、あとでそういっていた。
14 氷を割る音 top
私は夜がくるのがおそろしい。私は夜中におきて氷を割らねばならない。
みな寝しずまってしずかになり、子供たちの足を体温で暖めてやって、やっと安心した寝息がきこえてくると、私は耳をすませて、そとの音をきいていた。
やがて、ぴちりぴちりという音が、戸口のほうできこえると、そっと寝床をぬけたして、左手にバケツをもち右手に重いつるはしをもって、そとに出た。
星の光が、ぞっとするほど、冷たくまたたいている。
玄関のわきに、コンクリートで作った防火用水のタンクが二つならんでいる。
タンクの中には夏のころ雨水がたまって、そのまま厚い氷になっていた。
その氷のなるべく中央をめがけて、つるはしをぶちこむと、手にいたくカーンと強い反響がくる。
同じところに、何度も何度もつるはしの先を打ちこんでいると、やがてころっと氷の一かたまりがとれる。
それをバケツにいれては、また、こつんこつんと氷を発掘する。
しずかな山の中から、山彦となってくるこの音が、私はこわくてたまらない。
バケツに半分ほども、氷のかたまりを掘りとると、ほっとして腰をのばす。
東の空に、高くオリオン星座の三つ星がかがやいて、天頂から長く流れ星が、今夜も尾をひいてきえていった。
私が結婚したころは利根川のちかくの出張所の官舎にくらしていた。
夏の夜、利根川にうつる星を美しいといいながら、よく散歩した。流れ星が、遠くにきえてゆくのを見たことがあった。
「ね、流星は、燃えてなくなるんでしょうね。」
「そうだよ。」
「宇宙の星がみな流星になったら?」
「あなたは何か、哲学的なことを考えているんだね。
流星は空気との摩擦で、いちおう、姿はなくなるけれども、流星のもっていたエネルギーは、なにかに変換されて生きている、そうでしょう。」
夫はそのころはやさしかった。私もあまえていた。
私はこのときから、流星とエネルギー不滅の法則とを観念づけていかにちがいない。
いま目で見てきえていく流星が、どこかでちがった形で生きていると信じ、それを夫の生存とむすびつけて考えていた。
気休めであった。ほんとに、泡のようにはかないものにとりすがって、生きている自分であった。
私はバケツの氷を部屋のすみにそっとおいて、こごえきった体で、子供たちの眠りをさまさないように、しばらくじっと座っていた。
朝になると、この氷の半分ぐらいがとけていた。
お湯の残りがすこしでもあると、それを入れてとかしておむつの洗濯をした。
倉重さんが炊事当番のときは、きっと私にお湯をよけいにくれた。
独身の女の人のうちで佐藤さんだけが、自分のお湯の分けまえを、このバケツに入れてくれるときがあった。
私は夜中に氷を掘ることによって、昼間谷川までいくことの体力の消耗をたすけた。
私がもし病気にでもなったら、そのときを考えると、すぐ目の前に三人の子供がやせほそって、私の寝ているまえに、じっとして座っている姿が思いうかばれて、ぞっとした。
私の病気は、子供三人の死を意味するものであった。
ふぶきの晩は、ふきこむ雪を集めてバケツにいれた。
しかし、それをとかした水は黒くにごって使用できなかった。
新雪があると私はよろこんだ。
バケツにいれておくと、朝までにきれいな水ができていた。
「藤原さん、なぜ昼間、氷を割らないの?」
とはじめのころ、みなからよく質問をうけた。
私は一日じゅう何回もこころみていたのであった。
この丘の上に日がかがやくと、にわかに気温が上昇して、水槽の表面の氷は柔らかになるのであった。
つるはしを打ちこんでも、大きなかたまりが割れてこないのである。
ざくざくした少しばかりの氷は、とかしてもいくらの水もとれない。
それに、氷をとかすバケツがおいているのは、夜間だけであった。
夕方やってみたが、やはりだめだった。早朝はよく割れた。しかし二人の奥さんから抗議が出た。
「ね、藤原さん、人の安眠を妨害しないでよ。」
この二人に文句をいわせた陰の人は、何もすることがないので、日本人会から借りてきた小説本を、一日じゅう読みふけっている独身奥さんのグループであった。
一週間に一回か二回労働に出るのを鼻にかけて、
「私たちが、勤労にいくから、あなたがたはお米の配給をもらえるのだ。」
ということをいっている人たちであった。
top
**************************************** |