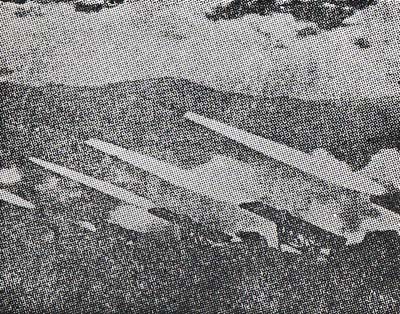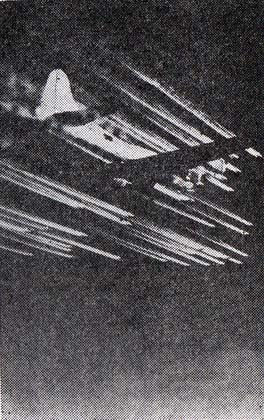|
****************************************
HOME サイパン島全滅 対馬丸 ひめゆり 満州からの引揚げ 満蒙開拓団の壊滅 ビルマ脱出記 シベリア抑留
流れる星は生きている――満州からの引揚げ
(藤原てい著 少年少女世界ノンフィクション 偕成社 1965年刊)
皆さんは戦争というものを、どう考えていますか。
テレビや映画でよく見る光景、……たとえば、飛行機がとび、戦車が野をこえ、地雷が破裂し、そのなかを鉄かぶとの兵隊が走りまわる。……
あれが戦争というものだと、思っているのではないでしょうか。
とんでもありません。あれは戦争ではなくて、戦争ごっこなのです。本当の戦争というものはお互いに、人間が人間を殺しあう、もっとも野蛮で残酷でみじめなものなのです。
私は女ですから直接、戦争には行きませんでしたが、戦争によって引き起こされたいろいろな苦しみを、三人の小さな子供と一緒に、身にしみてあじわいました。
あるときは、赤土の泥の中をもがきました。また橋のない大きな川を、首までつかりながら渡りました。雨にうたれて、ふるえて夜を過ごしたこともありました。食物はほとんどありませんでした。それでもついに頑張りとおして、生きてきました。
この本は、そうした私の体験をもとに書いたものです。ぜひ、若い皆さんに読んでいただきたいと思います。そしてどうか皆さんは、私たちのような苦しみを、なさらないでください。
そのためには決して決して、戦争など引き起こさないでください。 (筆者) |
 |
解説――田中澄江
Ⅰ 涙の丘
Ⅱ 教会のある町
Ⅲ 三十八度線をめざして
Ⅳ 魔王の声 |
著者“藤原てい”の略歴 一九一八年、長野県に生まれ、県立諏訪高等女学校卒業。
一九三九年、気象庁勤務の藤原寛人(ひろひと=後の作家:新田次郎)氏と結婚。一九四三年、新京観象台に赴任の夫君と渡満し一九四六年帰国。のち病床でこの書を執筆。「灰色の丘」「三つの国境線」他の著書がある。 |
「流れる星は生きている」を読むまえに
著者の藤原さんは、戦争中、満州の新京(今の中国の東北・長春)で、観象台(かんしょうだい=日本の気象庁)に勤めるご主人と、三人の幼い子供たちと平和に暮らしていました。
ところが、昭和二十年八月九日の晩、突然、新京はソ連軍の空襲をうけました。
そして、その夜のうちに新京を脱出しなければならなくなりました。
ご主人は仕事の関係で残り、藤原さんは、三人の子供と貨車にのって北朝鮮へ逃げ込みました。
それから丸一年間、日本へ生きて帰るために、ある時は雨に打たれて野宿をし、食べ物もなく、赤土の泥の中をもがき、かれ枝にさされて足から血を流しながら、三十八度線を突破しました。
そこからアメリカ軍に救われて、釜山に送られ、やっと日本にたどりつきました。
戦争というものが、直接、戦争に参加しない女・子供にまで、どんなに苦しみをあたえるものか。
この本は、それを体験した藤原さんの、血のにじむ記録です。
解説――「流れる星は生きている」について 田中澄江(劇作家 1965/3記) top
来たるべきもの
|

日本海軍の奇襲をうけたハワイの真珠湾
|

日中戦争で中国の奥地を進軍する日本軍
|
戦争は、なぜ起こるのだろうか。人間の心の中に、悪魔がすむということであろうか。
同じ人間同士が殺しあい、うばいあいして、この大地に血を流す。
私が物心ついたときから、この日本に戦争のない日はなかった。
そしてまた、日本の戦争は終わっても、地上に戦争のない日はなかった。
戦争。――この人間生活のおそろしい破壊者が、地上から姿を消すのは、いつの日のことであろうか。
一九四一年(昭和十六年)十二月八日、私たちは、勇ましい軍艦マーチとともに、いきおいよいアナウンサーの声で、米・英を敵として、わが陸海軍は、交戦状態にはいったという臨時ニュースにおどろかされた。
ハワイの真珠湾に奇襲攻撃をおこない、多数の米艦を撃沈させたという知らせがとどいた。
西南太平洋におけるアメリカやイギリスの軍事基地にも攻撃がかけられ、わが国は、自衛のためという名のもとに、宣戦布告を内外に発表したのだった。その日は一日じゅう、町でも家の中でも、いよいよきたるべきものがきたという興奮と緊張が、はげしい渦をまきおこしていた。
きたるべきもの。――それは一九三一年(昭和六年)の九月十八日に、満州事変がはじまったときから、私たちの胸に、ひそやかに育っていた恐れの実現することでもあったのだ。
太平洋戦争が始まるまで top
明治以後、日清・日露という二つの大きな戦争を経て、急速に国力の発展をとげた日本は、満州を舞台として、着々、資本主義国家としての内容を充実させていった。
ヨーロッパが、第一次世界大戦にまきこまれたころは、アメリカとともに、戦争のすきに乗じて漁夫の利をしめ、中国に市場をひろげることができたが、戦争が終わるとひどい不景気にみまわれ、国民生活の不満のはけ口を、大陸政策の遂行に求めた。
すなわち満州事変を起こして、一挙にここを軍事占領し、一九三二年、ついに満州国をつくってしまったのである。
そのころ、さかんに日本の生命線という言葉が流行して、満州を手中におさめることが、日本を発展させることだと信じられた。
これはもともと、よその国の中にかってになわ張りして、ここが自分の領土だと宣言したようなもので、中国の南京国民党政府は、国際連盟(第一次世界大戦後成立した、世界平和を目的とした諸国家の団体)に日本の不当な侵略を訴え、日本は、連盟から脱退した。
ついでドイツもイタリアも脱退した。
この二国もまた、日本と同じように国民生活の繁栄のために、軍備をさかんにして、他国への示威に明け暮れていた。
日本はやがて、ドイツやイタリアとのあいだに防共協定をつくり、一九三七年には盧溝橋(ろこうきょう)事件から日中戦争を引き起こし、南京を占領した。
ヨーロッパにおいても、ドイツがオーストリアに進出し、チェコスロバキアを占領した。
イタリアもまたアルバニアを攻め、ドイツがポーランドになだれこんだのをきっかけに、第二次世界大戦となったのである。
このころ、日本の政治家や軍人の間には、アメリカやイギリスや中国、オランダなどの国々が日本を包囲して、日本の自滅を待っているという意見が行なわれた。
そして、日本は逆にこれと戦って、これらの国々の圧力を打破する以外の道はないという信念が強固につくりあげられ、ついに十二月八日を迎えたのであった。
満州の悲劇 top
|

満州国の首都・新京の国務院(1941年当時)
|
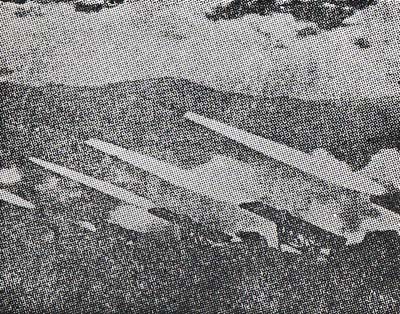
第二次世界大戦におけるソ連軍のロケット砲によるドイツ攻撃。
ソ連が日本に宣戦布告したとき、満州の日本軍は硫黄島や沖縄等に移動してしまっており、満州国は有名無実となってしまっていた。 |
「流れる星は生きている」の著者、藤原ていさんとその家族が、一九四三年に気象庁勤務の夫君の赴任にともなって行った先は、日本の植民地、満州国の首都新京であった。
太平洋戦争の戦況は、はじめのうちこそ、アメリカ・イギリスのすきをついて、成功をおさめたようであったけれど、一年たたぬ間に、あまりにも遠くまで、その手をのばしすぎて補給がつづかず、連合軍の反攻がはげしくなった。
一方二年めには、ヨーロッパ戦線で、イタリアが連合軍のまえに屈伏、三年めには南方の島々がアメリカ軍に占領され、四年めには、ドイツがついに降伏して、日本だけとなった。
しかし、これも本土への空襲がたびかさなり、ついに広島、長崎の原爆降下によって、最後のとどめをさされることとなった。
この戦争で、日本では百五十万の軍人が戦死し、銃後の国民は、七十万ちかくが空襲で殺された。
悲惨とも、なんともいいようがないが、戦禍をもっとも無残な形で身に浴びたのは、非戦闘員でありながら、日本以外の領土にいて、敗戦の悲劇をむかえた人たちであろう。
南のサイパン島では、敵兵上陸に際して、逃げ場を失った数百の日本人婦女子が、海岸の断崖から身を投げて命を断ったと聞いている。
満州では、農村の二、三男が、新天地の開拓をすすめられ、義勇隊として荒れ地を開墾していたが、その多くはソ連兵の侵略のまえに自決し、あるいは殺されたとも聞いている。
藤原さんのご主人は、日本が、満州という国の実質上の経営者であったために、国家から派遣されていた役人であったが、ほかにも満州国を日本の延長として、そこで生活していた日本人がたくさんいた。
敗戦とともにそれらの人々が、日本にむかってなだれのような引き揚げ作戦をとったのである。
どんなに大きな不安と絶望が、その心身を噛んだか、想像するさえ胸がいたくなる。
住みなれた生活の場が、一夜明けるあいだに、周囲はすべてこれ敵ということになってしまったのだ。
営々として築いてきた財産も捨てて、立ち去らなければならないのだ。
しかも、か弱い子供たちを何人かひきっれて。
母は強し top
|

満州の開拓村で働く日本人家族
|

外地から敗戦によって博多に帰ってきた引揚者たち
|
「流れる星は生きている」を拝見して、私は外地からの引き揚げの悲惨さ、生と死に直面しての苦悩の深さに、ほとんど胸がつまって、いくたびかページをおおって、先へ進むことが容易でなかった。
藤原さんたちは、内地の私たちが、とにかく自分の国の領土という安心感にひたされて、その中で戦後生活の困難さと戦っていたとき、そして昭和二十一年といえば、町に占領軍があふれて、その手にぶらさがった娘たちも、たくさん巷を流れ歩いていたころ、かつては権威をもってのぞんだ人たちから逆な立場に追いこまれ、悲惨と恥辱の長い耐乏生活に耐えなければならなかったのである。
子供たちを飢えから守るために、子供たちのいのちの灯を燃やしつづけるために、乳飲み子をせおって、春風に髪をふりみだし、必死な瞳に石けんを売り、煙草を売りあるいたお母さん。寒夜に氷をわって、おむつの洗たくをするお母さん。
引き揚げの旅のなかでは、血のにじむ足に石ころ道の山坂をあえぎあえぎ、列から一番おくれてついてゆくお母さん。
いくつもの川を、はげしい流れに足をとられまいとしながら、一人ずつ子供を抱いて、渡らなければならなかったお母さん。
夫は遠くシベリアにつれてゆかれ、この母は、自分の手に残された三人の子供を、一歩でも日本に近づいた土地までっれてゆこうと、目を血走らせ下くちびるをかみしめる。
「前には私はよく泣いた。しかし今は泣かない。戦争だ戦争だ、生きるための戦争だ。」
全編にこのすさまじいまでの気迫が満ちあふれて、母とはこんなにも強いものか、母とはこんなにありかたいものかと、読行者の目に熱い涙をしたたらせる。
ことに悲惨なのは、長旅にあえぎ疲れて、母も子も死の寸前までに追いこまれた後半の記述である。母の乳房は涸れ、子はひもじさに一歩も足の進まぬ雨の夜の徒歩後に、
「私は最後の時がきたら、この紐でこの子供たちを殺し、自分も死のうと考えていた。」
と結んだ文字は、母という女がしるすもっとも残酷な言葉でありながら、それがもっとも深い愛情に満ちたものを思わせる。
それほど状況の悲惨さが切迫していたのだが、このとき、その死へのすごい一瞬を鋭く生に転換させたのも、母という女に与えられた、なみなみならぬ生命力のゆたかさであったろう。
母子心中などの悲劇のたえない日本の現実には、あまりにも死を軽くあっかう国民感情が、深い病根となって巣くっているのだと思う。
藤原さんのこの記録のすべての文字が、安易な自殺者への強い拒否姿勢を打ち出しているのは、その底に、あくまでも強い生命へ、ゆるぎない信念が、ほとんど本能そのものの強さで、しっかりと根をおろしているからだと思う。
戦争、この恐ろしくむごいもの top
|
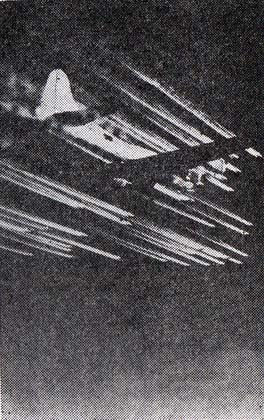
日本本土の空襲にむかうアメリカ軍B29の編隊
|

1945年8月、広島に落とされた原子爆弾
|

藤原ていさん(右より二人め)のご一家
|
私はこの本をまず、戦争を知らない、若い年ごろの少年少女に読んでほしいと思う。
戦争。――それは、あるいは、平行にやまれぬ事情を導火線として、国と国とが、その全能力をあげて、ぶつかりあうものかもしれないが、結局は、人間の殺しあいなのだ。平和な生活の、乱入者なのだ。
戦うのは軍人ばかりでなく、その国の国民の末々にいたるまで、非常な苦しみのなかに投げこむことを、本編ほど読者の臓腑(ぞうふ)にしみて、痛切のひびきとともに語りかけてくれるものは少ないと思う。
それが伸びゆく幼い生命の芽の子供と、わが身にかけても、子供を死守したいという、母のせつな願いをおびやかすだけに、その残酷さもひとしお深く読者の胸をつらぬく。
いくたびかの危機を脱してこの母と子が、ふるさとの山河にいだかれるくだりは、鬼神をも泣かしめる感動の場面となっているのだが、そのことはまた、戦争がいかに無残に真実の人間性を破壊するかを語っていよう。
私はまたこの本を、若い娘さんや、青年たちに読んでもらいたい。
あの戦争のさなかに、子供を育てることの痛苦は、当時の日本の母のだれしもが経験したのだが、その個々の痛苦を、さながらにもっとも深く、もっとも強く、集大成してくれたかのような形で、ここに書き出してくれたのが、引き揚げ者としての藤原さんのこの記録である。
母と子の上にふりかかる戦争の悲惨さは、読後感の最大なものとなるのであろうが、私が願うのはこれらの悲惨さを二度とくりかえさぬものとして、若い皆さんこそ、鋭く見まもってほしいのだ。
あわせて新しい家庭をつくり若い両親となる皆さんが、この本を読んで、いまさらに母と子のきずなの深さを知ってほしいと思う。
母は、その胎内に子供を宿した日から、自分の肉体の一部として子供を育てる。
子供にとって、その日々の記憶はまったくないが、母には激痛をもってその子供が生まれ出るまえから、すでに自分の子供としての意識をもっているのだ。
その子供を守るためには、甘んじてわが身が失われることをも辞さないのが、母というもののありがたさである。
ここでは、異常なまでに、非情な世界の中で発揮された母性愛がうつし出されているが、私たちの日々の周囲にも、いかに多くの母たちが、子供のためにわが骨をけずり、身をきざんでいることか。
若い読者の皆さんのなかには、その母の受の深さが、やりきれない人もあるかもしれないが、そのやりきれなさと、母の愛を失った時のむなしさをくらべてみてほしい。
そのとき、そのやりきれなさなどということが、どんなにぜいたくな感情であるか、思い知ることができよう。
ともあれ、子供がどんなにそむこうと、うるさがろうと、子供のことを思わずにはいられない母というもの。
その狂暴に近いまでの愛情あればこそ、世の多くの母たちは、極みない困難な状況の中でも、子供を捨てずに生きぬくことができるのである。
だいぶ前のことになるが、私は何かの婦人雑誌で、藤原さんがお子さんの東大入学をよろこんでおられる記事を拝見した。
この辛酸の果てに成長されたお子さんである。どんなにか、うれしかったことであろう。
お目にかかったことは一度もないが、子供一筋に思いつめた瞳のいろが目にうかぶようだ。
激しさや潔癖を、愛情のあたたかさにつつんで、つつましく微笑しているような、そんなおかたと想像している。
この本はあのはげしい歴史の一時期に、藤原さんにはおよばないまでも、自分もまた三人の子供を抱きかかえて必死だったことを思い出させた。
この本はそうしたお母さん方にとっても、自分の過去をよびもどす貴い機会になるのであろう。
top
**************************************** |