|
****************************************
HOME サイパン島全滅 対馬丸 ひめゆり 満州からの引揚げ 満蒙開拓団の壊滅 ビルマ脱出記 シベリア抑留
絵入シベリア収容所
(竹内錦司著 シベリア抑留叢書 国書刊行会 昭和57(1982)年刊)
|
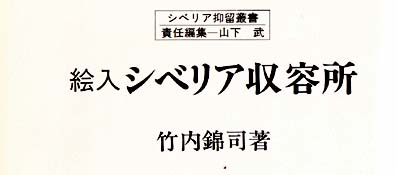
本書は昭和二十五年に刊行された
『画信日本の捕虜はソ連でどんな生活をしていたか』(光文社)
を再刊したものである。
|
1 あいさつ 元兵長、ソ連俘虜 竹内錦司 一九五〇(昭和25)年 春たけなわの時
top
私は専門の漫画家でもなければ文章家でもありませんが、ソ連に抑留された人々は、一体どんな仕事をどのようにして来たのでしょうか。
帰られた方々からいろいろと話を聞いたり、その方々の体験をつづった本も出てはおりますが、読んだり聞いたりしたのでは百聞は一見にしかずの百聞であって、一見を望みだいところであります。
そうした意味から筆をとったのが、つたないとの一冊なのです。
が、私とて、抑留中に、「日本へ帰ったら、一つソ連の様子を絵に描いて、みんなに知らせてやろう」なぞという気持があったわけではありません。
ただ多少なりとも国民の皆様に、特にいまだ帰らざる留守家族の方々にお知らせしてあげたいとの一念から、急にこんなことを思いついたのです。
何しろ参考品一つあるわけでなく、まったく凡知な一個人の記憶にのみよって描いたのですから、すでに帰られた方達から見れば、ずいぷんと間違いもあるかも知れません。
風景や建物は、特に記憶が悪く、どうして描いたらいいかと苦労しました。
そのためずいぷんと見にくい点もあろうかと思われますが、素人のことゆえカンペンしてください。
なお、私のこの虜行(りょこう=旅行)記は、シベリアの奥地で苦労された人達とくらべれば非常にめぐまれたものだったので、この点もあわせてよろしくお察し願いたいと存じます。
2 あとがき 竹内錦司
昭和五十七(1982)年一月 top
昭和二十二年末、ツ連抑留から帰って以来、逢う人によく捕虜生活を問われ、話しました。
そんなある時、フッと、ただ話すだけよりは画があった方が、よりよくわかってもらえるのではなかろうかと思い、まだ生々しかった思い出をつづったのでした。
私の著書、シベリア捕虜体験記『日本の俘虜はソ連でどんな生活をしたか』が発行されてから、はや三十余年……。
今の現在の私の人生には、その記憶も体験も、何となく前世の出来事だったかのような錯覚にさえおちいりそうなこの頃でした。
それではいけない。あの体験は、決して忘れてはいけないのだ。
語り継がねばならぬのだ。日本国民が二度とあのような目に合わぬためにも……。
しかし、いくら私か子供達に語ったとしても、実感としてとらえることはできないことでしょう。
ましてや他人に語ったとてなおさらでしょう。
やがて、その私の悪夢は、日本の過去の悪夢として、消えさってしまうことでしょう。
でも私は、せめて、私個人の一体験記ではあっても、今日の大平の世(あえていわせてもらいます)に、形として、活字として、残っていればなあと思っていました。
そんなある日、国書刊行会の佐藤さんから、お電話をいただき、「シベリア抑留叢書」シリーズの一巻として、私の体験記を加えていただくこととなりました。
すでに私の手元からも散逸してしまった、私の幻の本が、違う形で残ることになり、失われかけたシベリア捕虜の日々の記憶が、次々と頭の中をかけめぐっています。
つたない画文ですが、一片のうそも、誇張もありません。
悲惨な体験の多いシベリア抑留記の中で、めぐまれた体験だったのでしょうが、これも真実です。
3 刊行にあたって 国書刊行会・佐藤今朝夫 昭和五十七(1982)年 早春
top
《戦争と平和》を語る啓蒙の書や論文は多い。
しかし、この問題は限りない広がりを持っていて、論議はとどまるところを知らない。
永遠に結論の出ないテーマであり、時と状況に応じて新しき説がくり返されている。
この種の哲学は民族はもとより、各国家、そして人類にとって最も必要なもののはずだが、論旨があまりに遠大なためか、内容が多岐にわたるばかりで、民族的発想の原点となるような具体的視点をもった書は極めて少ない。
私はここに思いをいたし《要は事実を識ることである》の論理を久しく展開してきた。
この論を具現すべく編んだのが本シリーズである。時間の経過のなかで忘却され、歪曲され、誤って伝えられやすい極限状況下の《さまざまな事実》を、正しく伝え、“戦争と平和”を考える礎となることを求めたのが本叢書刊行の第一の目的である。
*
明治以降の歴史をよりかえってみると、陸海軍誕生(慶応三年)から三十八年目にして、満州を戦場としてロシアと戦い、満州事変・支那事変(日中戦争)を経て再び三十八年目に、アメリカを主軸とする連合軍との戦いがはじまった。
そして昭和二〇年八月、国は破れ、軍国日本は音をたてて瓦解した。
その未曽有の困難の中で、同胞日本人は如何に生き、如何に死地に赴いていったか――
……極寒のシベリアにくりひろげられた地獄の諸相を綴り、絶望に耐えた人間の不屈な精神のドラマを伝える《シベリア抑留叢書》
……南方諸島で死闘の末、奇跡的に生き残った将兵を待っていた苛酷な虜囚の運命、収容所の実態を綴る魂の告白《南方捕虜叢書)
……正義と人道の名のもとに戦争裁判という復讐劇が始まり、悲運に苦悩する人々、死刑囚独房で呻吟する者、刑場の露と消えた人間の心の叫び《戦犯叢書》
本シリーズは各地で展開された生と死のぎりぎりの事実を伝える珠玉の記録集である。
収録の諸篇はいずれも、一個人の絶叫を示すにとどまるものではなく、民族の興亡の淵にあって赫々と燃え照らすごとき生命からの証言である。
今日の読者にその証言を伝え、安逸に流れる時流に棹さし、正しい国益と平和を求める指針たらしめること、このことこそ本シリーズ発刊の第二の目的である。
*
今、あの悲嘆の日から三十七年が過ぎた。かくも長きにわたって泰平が続いたのは何を意味しようか。
神の恵みか、好運か。われわれは現在、不自由なき繁栄の中に生きている。
しかし好運がいつまで続くか保障の限りではない。
歴史は平和のあとの《忘れた頃の戦争》の悲劇を教えている。
だからこそ、今、平和への道を誤ってはならない。
なんとしても、戦争をくりかえしてはならないのである。
ここに私は、一過性の平和であってはならないと思うが故に、そして民族の滅亡につながるような敗北があってはならぬと思うが故に、他民族の大地を土足で踏みにじるような言動を、《紛れなく否定する歴史的教訓の書群》として本シリーズを刊行するものである。
真実を語る一冊一冊は読者に拒否し難い重みをもって迫ることだろう。
この歴史的教訓の書としての役割と期待こそ、本シリーズ発刊の第三の目的である。
*
かつての日本の拡張主義については、世上に多くの反省と批判がある。
しかしその矢面にたたされる日本陸海軍は、われわれ日本民族の外部に存在していたものではなく、疑いもなく民族の内に生成していたものであり、他人事のような批判は許されないと言えるのではないだろうか。
今こそ国民の一人一人が果しなき道程である《戦争と平和》について、自らのこととして考えを深めてゆく必要がある。
――読者とともに、真剣なテーマとして深めてゆこうとしたのが本叢書の第四の目的である。
*
歳月は忘却の良薬であり、どのような苦しみも、悲しみも、嘆きも、歳月の経過とともに、自然に風化してしまうものである。
しかし、風化させてはならぬこともある。
日本民族の盛衰に関わる最大のテーマ《戦争と平和》こそ、国民の心の中で進行するなしくずしの風化を阻まねばならない第一のものである。
昭和二〇年のあの廃墟から、今まさに三十七年目を迎えた早春、出版人として、先人の誤りし轍を再び踏むことなく、後世の人々へ戦争の無意味さと、熱い血潮のかよう平和の尊さを伝えることができればと心から願ってやまない。
*
本書は、昭和二十五年に光文社より刊行された『画信日本の俘虜はソ連でどんな生活をしたか』を再刊したものである。
本叢書の刊行にあたり、収録をご快諾いただいた各著者及びご遺族の方々、初版発行所等の関係者各位に、心から感謝申し上げるものである。
またシリーズの責任編集の労をとられた山下武氏に深甚の謝意を表する。作家・評論活動のかたわら、書誌学的に多方面に活躍されている山下氏の、特に、戦争・捕虜に関する蔵書の中から本叢書の大部分は厳選されたものである。
なお、本叢書への収録に際し、それぞれご諒解を得て、初版当時のタイトルを改題したものや、ペンネームであった著者名を本名に改めたものもある。また、著者による加筆・訂正もいただいた。
更に編集部の責任において、各巻とも常用漢字と現代仮名づかい等に改めた。 編集部
top
****************************************
|