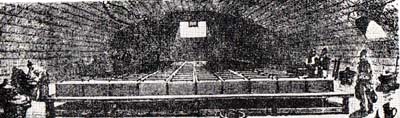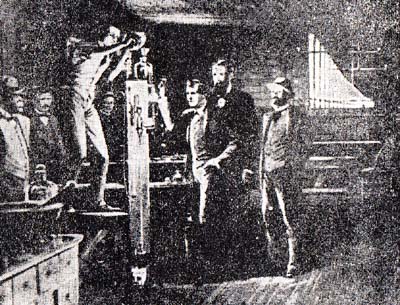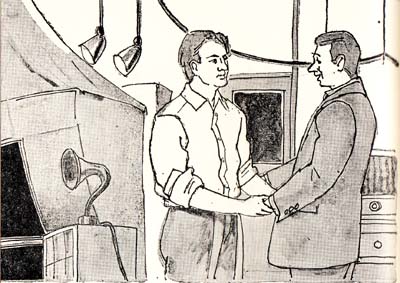|
****************************************
Index 磁石 電気実験 電気の利用 電化生活 付録
Ⅳ 電化生活の始り
第十三章 電灯――
すべての家庭に電気を送れ top
エジソンは、蓄音機の発明をすませると、一時休息をとってから、またまた大発明に取組んだ。
(エジソンの前半の仕事は11章“蓄音機”のところを見てください)
いままではたくさんの発明を一緒にやっていたが、今度はほかの仕事は全部やめて、ただ一つ、電灯の発明に全力をあげたのである。
その頃、一般の家で使われていた「明り」はガス灯だった。 ガス灯はその頃から五十年ほどまえに発明されたばかりだったが、それまでの石油ランプやローソクよりズッと便利なので、すばらしい発達をとげていたのだ。
しかしガス灯をつけるには、ガスを一軒一軒にガス管でくばらなければならない。 そこで、これが使われるのは都会だけで、アメリカでも九割以上の人は、便利なガス灯の恩恵をうけられないでいた。 |

電灯と電話の普及で、街に電柱が張り巡らされた
|
1 アーク灯ではなく
一方、電気を利用して「明り」をとる考えも、七十年も前から考えられていた。
それは、一八〇八年にイギリスのデービーが二千個もの電池をつないで、炭素ぼうの間に火花をとばしつづけて見せたのが始りだった。
このアーク灯の実験は、そののちたくさんの人たちによって研究され、この頃にはかなり実用化した。 |
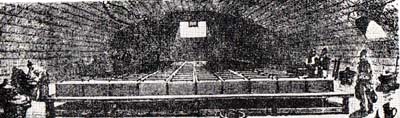
デービーがアーク灯の実験に使ったたくさんの電池
|
一八七八年九月八日、エジソンもこの話をきいて、ウオレスという人の発明したアーク灯を見学にでかけた。
この人はアメリカ人で初めて発電機を作り出した人で、これで電気をおこし、五〇〇燭光もあるアーク灯八個をつけて見せてくれた。
エジソンは感激した。彼もまえに、電気から明りをとる実験をしたことがあった。
けれども彼は、この時初めてほかの仕事をほっぽりなげても電気から明りをとる研究だけにうちこむ決心をしたのだ。
しかし、エジソンが発明しようとしたのは、アーク灯ではなかった。
「アーク灯は目のつぶれるほど明るくてすばらしい。
しかし、これでは一軒一軒の家でつけるには明るすぎるし、費用もかかり嫌な匂いもだすし取扱いも不便だ。
これではだめだ。
やはりガス灯と同じくらいの明るさにして、電気もガスと同じように一軒一軒のうちに配給して使うようにしなくてはだめなのだ。 その発明はこのエジソンがやるんだ。」 |
エジソンはそう考えると、さっそくこれまでいろんな人がやった実験をくわしく調べてみた。
金属線に強い電流を流すと明るい光を出す。
このことはわかっていたが、金属線はすぐ焼き切れてしまい、なかなか実用にはならない。
そこで、フランスのド・ラ・リトフという化学者は、すでに一八二〇年にガラス球を真空にして、その中の金属球に電気を流して電灯をつくろうとしていた。
またイギリスの化学者スワンは、長い間、白金線や炭素線を使って、電灯にする研究を着々とすすめていた。
そのほか同じような発明をしようとして実験していた人はたくさんいた。
しかし、エジソンのしるかぎりでは、まだ白熱電灯を数秒間以上の間つけるのに成功した人は、誰もいなかった。
2 スイッチひとつで電気を! top
しかも、エジソンは、明るくて長もちする電灯をつくろうと考えていただけではなかった。
彼は最初から、どんな家へも簡単に電気が送れて、スイッチ一つで電灯をつけることができるようにしようと考えていたのだ。
計算したり実験した結果、電灯はできるだけ電気抵抗が大きくなくてはいけないことかわかった。
つまり彼の計画している電灯をつくるには、うんと細い金属線を使わなければならないのである。
ところが、その細い線が燃え切れないようにしなければならないとなると、これは大変なことだった。
しかし、エジソンは、まもなく八分間のあいだ電灯をつけるのに成功した。
そこで、彼は、もうすごい自信をもつようになった。
「もう電灯は発明されたにもひとしい。」
彼がこういうと、資本家たちはすぐにエジソンにとびついてきた。
そしてまだ発明ができていないうちに、もう資本家が集って「エジソン電灯会社」が生まれることになった。
「エジソンのことだから、きっとうまくやるにちがいない」と資本家たちも考えたのである。
しかし、実験は思ったよりはるかに困難だった。
はじめ、エジソンは「この発明は六週間でやって見せる。」と宣言していたが、一年たち、二年たっても、まだ実験が成功にこぎつけるところまでゆかなかった。
資本家たちも心配になってきた。
科学者たちまで、エジソンの計画は間違っているから成功しっこないといいだすありさまだった。
しかし、エジソンは自分の研究所の設備のすぐれていることと、たくさんの助手たちが優秀であることに自信をもっていた。
四十人以上もいる助手たちは、エジソンを尊敬していて、実験にあぶらがのりだすと、エジソンと一緒に、ほとんど夜もねむらないで実験をつづけた。
彼らは溶けにくいものなら、あらゆるものを細くして、空気をぬいたガラス管の中にいれてためしていった。
炭素、白金、イリジウム、硼素、クローム、モリブデン、オスミウム、ニッケル、そのほかさまざまな合金、実験は数百回、数子回とつづけられ、その記録をとる実験ノートは、またたくまに部厚くなっていった。
一方ではまた、ほかの助手たちが、ガラス管の中をよりよい真空にするための研究や、発電機を改良する実験もすすめていた。
エジソンは、それらの助手の先頭に立って、研究をつづけていった。
「天才は一パーセントの霊感(インスピレーション)と九九パーセントの汗(努力)とから生まれる。」 |
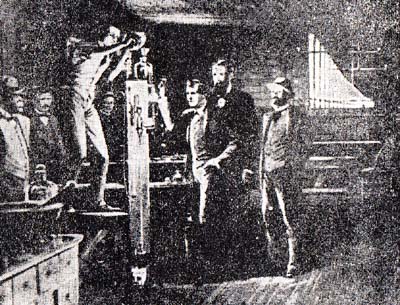
電灯の実験にうちこむエジソンと助手たち
|
エジソンは、ある時こんなことをいったが、これこそ天才エジソンの姿であった。
「ほかの発明家たちの弱点は、ほんの二、三のことをやってみただけでやめてしまうことだ。
しかし、私は、自分のもとめているものを手にいれるまでは、絶対にやめはしない!」
エジソンはこんなこともいっている。
3 電灯とにらめっこの十時間 top
長い長い間の努力がついにむくいられる日がやってきた。
そにれは一八七九年の十月二十二日のことであった。
細い木綿糸をうまくそのまま炭にすることにやっと成功したので、さっそくこれをガラス管の中に封じこんで実験をすることになった。
第九号電灯をつける試験は二十一日から二十二日にかけての夜中に始った。
「この電灯もすぐにもえつきてしまうだろう。」
おそらくこんな考えもあって夜中の一時半に電球に電流をとおしたのだが、うれしいことに、この考えは間違っていた。
一時間、二時間…………。
いつも電灯が、線香花火のように消えてしまうのになれっこになっていた人たちも、だんだんに興奮してきた。
そしてその夜、明るくともる電灯がいま消えるか、いま消えるかとにらめっこしたままついに朝をむかえてしまった。
いや、このフィラメントは昼になってもきえなかった。
研究員たちはもうクタクタだった。しかし見張りはつづいた。
そしてその日の午後三時になって、ついにこのフィラメントも切れた。
「成功だ! これならうまくいくぞ。」
それからまた実験がすごい勢いで始った。つぎの電灯は四十時間もつづいた。
興奮した人々は、まるで眠るときがなかった。
いつ消えるか、いつ消えるかと、四十時間もぶっとうして見張りをつづけたのである。
何日も、何ヵ月も 何年もかかった研究も、こうして突然にむくいられる日がきたのだ。
電灯の絹い発熱体――フィラメントにするには、ねばり強い繊維状がものを炭にしたほうがよいということがわかったので、今度は強い繊維質の植物をかたっぱしから試すことになった。
麻ぶくろの布、メキシコ産のマホガユー、ツゲ、西洋杉のけずりくず、 セルロイド、釣糸、アマ、ヤシの実の殼(から)、より糸…………。
はてしない実験がまた始った。
エジソンはじめ研究所の人たちは、思い出せるものぱなんでも実験した。
その結果、まずかたい上質の紙をやいて、毛のような細いフィラメントにしたものが一番よいことがわかった。
このフィラメントは百七十時間光りつづけた。
つぎには、竹の繊維がよいということがわかった。
そこで今度は、世界中からいろいろの種類の竹がかき集められた。
その結果、日本から送られてきた京都の竹が一番よいことがわかった。
エジソンは、これで電灯の大量生産にふみきった。
電灯が完成すると、エジソンは中央発電所をつくる仕事にとりかかった。
「電灯だけでなく、力と熱と光の必要なところには、どこへでも電気を送ろう。
食べ物を料理するにも、エレベーターやミシンを動かすにも、モーターのいるところには、どこへでも送電しよう。」
これが前々からのエジソンの夢だったのだ。
一八八〇年、ニューヨークに世界最初の中央発電所がつくられてエジソンの夢は実現した。
そこには、エジソンの改良した発電機がすえつげられたが、この発電機でおこされた電気は、周りの家々に電灯線をつうじて配電され、八百個の電灯をともすことになった。
そして、一年あまりのあいだに、その数は一万二千七百個にもたっした。
世界に電灯の時代、いや電気の時代がおとずれたのである。
どこの家でもコンセントやスイッチ一つで電灯やラジオ、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などに、電気を送りこむことができる時代が始ったのだ。
4 最後の発明をかざった日本人 top
エジソンの電灯は、その後さらに改良がつづけられた。
イギリスのスワンは、フィラメントの研究では、エジソンに一歩さきんじていた。
スワンは、竹の繊維よりも木綿の繊維をドロドロにとかして、細い糸をつくったほうが、よいフィラメントをつくることができることをみつけたのである。
しかし、やがて炭素線の電球にかわるものが現れた。
二十世紀のはじめ、アメリカのジェネラル・エレクトリック会社が大きな研究所をたてて、電灯の研究を始めたが、この研究所のクーリッジがタングステンを細い糸にひきのばすことに成功した。
そして、これをフィラメントにすれば、炭素電球のわずか三分の一の電力でたりることが明らかになった。
昔の電球は、しぱらくするとガラスの内面が黒ずんできたが、これをとりのぞく研究もすすめられた。
クーリッジと同じ研究所のラングミュアは、電球の中に特殊なガスをいれておくとすすがつかないことを発見した。
また細いフィラメントをラセン状にまけば、これまでよりもずっとよい電球になることも明らかにされた。
また、昔の電球はガラス球のさきから空気をぬいていたので、球のさきが出っぱっていて、こわれやすかったが、一九一九年からは、口金のほうから空気をぬきとるようになり、電球の形も、今のような形の良い物になった。
ここまでくると、もう今の電球とほとんど同じものになっている。
これに最後のみがきをかげて、今の電球を作り出した大事な発明――それは日本人がやったものである。
そのひとつは、電球がまぶしすぎないように、電球の内側を磨(すり)ガラスにしたことである。
これは、一九二五年(大正十四年)に、日本の不破橘三(ふわきつぞう)とアメリカのピプキンがほとんど同時に発明した。
第二の発明はフィラメントのコイルを二重まきにすることで、これでフィラメソトは丈夫になり、そのうえさらに明るさも二〇ハーセントもふえた。
この方法は日本の三浦順一が一九二七年(昭和二年)に、発明したものである。
もっとも、これは作り方がむずかしくて、なかなか実用にならなかったが、オランダのフィリップスという会社が、このフィラメントをつくる機械を発明して、初めて今のような電球が生まれたのである。
5 その後のエジソン top
電灯の発明に成功したのち、エジソンはさらに新しい発明をもとめて、次々と研究をつづけた。電車、磁力選鉱法、映画、蓄電池、ゴムなど、エジソンの発明は数かぎりない。彼がとっだ特許の数は、于三百種以上もあるといわれている。
一九二九年五月三十日、アメリカでは大統領の音頭とりで、エジソンの電灯発明五十年記念祝賀会がひらかれた。
八十二才のエジソンは、元気に式典に出席した。
「私は、本当にうれしいのです。」
彼はポツリというと、あまりの感激につ彼が出たのか、きゅうに体の力がぬけてそのままぐったりとくずれるように腰をおろしてしまった。
それからエジソンは病気になり、二年後にこの世を去った。
葬式の日、アメリカの人々は、いっせいに一分間、電灯を消して、彼の功績に感謝した。
第十四章 電波――
予感・理論・実験・発明の先駆者 top
1 ファラディの予感
「マイケル・ファラディはきっと真理をかぎつけることのできる、すばらしい鼻をもっているにちがいない。」
ドイツのコールラウシという有名な実験物理学者は、ある時、こんなことをいったが、実際ファラディは、一人ですばらしくたくさんの大発見をやってのけた。
その頃からノーベル賞があったら、そのノーベル賞をもらえそうな大発見だけ取上げても、つぎのようにたくさんある。 一八二一年にやったモーターの発明につづいて、一八二三年には、塩素ガスを液体にすることに成功し、一八二五年には、ベンゼンを発見した。
そして、一八三一年には、電磁誘導の現象を発見して発電機を発明し、一八三三年には、電気分解の法則を発見した。 |

海上の汽船と無線の実験をするマルコニー
|
また、一八三八年には、真空放電を研究して、ファラディ暗部というのを発見し、一八四五年、光が磁石の影響をうけるということを発見するとともに、普通の磁石とは、正反対の性質をもったか反磁性という物質があるのを発見した。
これまでの長い科学の歴史のなかでも、これほどたくさんの大発見をした人はいないといってもよいほど、ファラディはたくさんの大発見をしたのである。
鍛冶屋の息子で学校もろくに出ていない装本屋あがりの科学者(ファラディについては12章、“モーターと発電機”をも見てください)そのファラディが、一人でこんな大発見を次々とやってのけたのだから、ほかの科学者が感心するのをとおりこしてあきれてしまったのもむりぱない。
ところが、そのファラディがある日、つぎのような話をした。
それは、一八四六年の四月のことである。
その頃ロンドンの王立研究所では、金曜日の夕方ごとに集りをひらいて科学者たちの話をきくことになっていたが、この日は予定されていた講師が急にこられなくなったので、司会者のファラディがかわりにしゃべることになったのである。
「これは、全くばくぜんとした予想にすぎないことたんですけれど……」と弁解しながら、彼はこんな話をした。
「みなさんは、光が波だということをごぞんじでしょうか。
科学者たちは、エーテルというものがこの空間をみたしていて、それが光の波を伝えるのだ、といっています。
しかし、私は、そんな特別なものを考えなくたっていいと思うのです。」
会場はシーンとなった。ファラディは元々実験学者であった。
だからいつもの彼は、実験上の発見の話しかしないのだったが、今日はめずらしく実験以外の想像上の話を始めたのだ。
「みなさんは、私がこれまで、電気や磁気の力の伝わりかたについて実験してきたことをごぞんじでしょう。
私の考えでは、電気や磁気の力は空間をゴムのような力の線となって伝わっていくことは確かだと思うのですが、私にはどうもこの電気や磁気の力を伝える力の線が横に振動した波が光なのだ、と思われるのです。
私は、光と磁気との関係をさがそうとして、去年とうとう光が磁石の力をうけて回転することを実験で確かめることかできました。
おそらくこれも一つの証拠になるでしょう。
また、最近ドイツのコールラウシは、電気の伝わる早さと光の早さとはほとんど同じだ、ということを確かめました。
これもその一つの証拠ではないでしょうか。」
彼はこのほか、電気や磁気の力を伝える力の線が、本当にゴムひものような性質をもっているということなどいろいろと話した。
「何という大胆な考えだろう。」ファラディの話をきいた人々は、みんなそう思ったが、さてくわしいことになると、専門の科学者にも全くわからない。
「全く雲をつかむような話だなあ。」
「なにしろ、ファラディ先生の話には数学が出てこないから、全くとらえどころがないよ。」
科学者たちは、煙にまかれたように当惑するのだった。
それもそのはず、何でも数学の式を使わないと、ものを考えることのできない大学の科学者たちは、ファラディの話は全く苦手だった。
小学校もろくにでていなかったファラディは、いつも「力の線はゴムひものようだ。」とか何とか、まるで自然の姿を絵のようにえがいて説明していて、たくさんの論文にもただの一つの数式も書いたことがなかったのである。
「ファラディはすばらしい実験家だ。しかし、理論家としては、全く、落第だな。」
科学者たちはそう考えたのだった。
そこで、ファラディの考えは、だれにも理解されず、忘れられてしまった。
2 マックスウエルの理論 top
それから八年たった一八五四年のことである。
この年、イギリスの名門ケンブリッジ大学を卒業したばかりの一人の科学者が、とうとうファラディの理論に目をつけた。
彼はクラーク・マックスウェルで、ファラディと違ってズッとめぐまれた環境にそだった秀才青年だった。
マックスウェルが生まれたのは、ちょうどフフフデーが発電機の原理を発見した一八三一年のことであった。
彼の父は弁護士で、財産家であった。そのうえ、学問もあり、教育熱心だった。
マックスウェルは、小さい頃からよく父につれられて、エジンバラの王立学会の会合に出席したが、ある時、そこで「完全なタマゴ形はどうして書くか」という問題が議論されているのをきいた。
これは大変むずかしい問題で、大学の先生にもよくわかがらなかった。
ところが、当時十六才のマックスウェルは、この問題をきくと、さっそく家で研究しはじめ、まもなく見事な数学の論文を書きあげた。 |

マックスウェル(1831~1879)はファラデーの実験的研究をもとにして、
整然とした数学的理論にまとめた。
|
これをしったエジンバラ大学のフォーブス教授はびっくりした。
この論文はすぐに学会で報告され、学会の雑誌にも発表されるようになった。
マックスウェルは、このように小さい時から人並みはずれた才能を示していたのである。
マックスウェルは大学を卒業すると電気の理論の研究を始めることになり、たくさんの論文や本を読みあさっていった。
その頃、電気の理論といえば、ファラディの考えとは全く正反対のほうへすすんでいた。
ファラディは電気や磁気の力は、ゴムひものような力の線を伝わって空間を順々に伝わっていくものと考えていた。
ところが、その頃の科学者たちの大部分は、これらの力は空間をいっぺんに飛越して伝わるものと考えていたのだ。
しかし、マックスウェルは、当時評判のよかった電気の理論があまり気にいらなかった。
数学的な理論は見事だが、どうもその土台となっている考えに作り事のような不自然さがあると思ったのだ。
そこで、彼は、ファラディの理論をもう一度見かえしてみようと考えるようになったのである。
しかし、ファラディの理論は大変わかりづらい。
それは、この理論が、元々、これまであったような数学の式で書き表わせないようなことを、問題にしているからである。
これまでも何人かの科学者が、ファラディの理論を取上げようとしてあきらめたのもそのためだった。
しかし、マックスウェルは強引にすすんでいった。
「これまでに数学の法則がなければ、自分で数学の法則を発見して、それを使って理論を書き表わせばいいじゃないか。」
これが彼のやりかただった。
そして、とうとうその翌年には、「ファラディの力の線について」という数学的な論文ができあがった。
しかし、これはファラディの考えの一部を数学の式で表わしただけで、充分なものではなかった。
そこで、マックスウェルは、ファラディの力の線の考えをさらに忠実に数学の法則に書き表わす努力をつづけた。
するとどうだろう。彼の書きあげた数式から電気の波を表わす式がでてきたのだ。
しかもその理論によると、この波は光と同し早さで伝わる性質をもったものであるはずだ。
マックスウェルは驚いてしまった。
実は彼も「光は電気や磁気の力線の波と同じものだ。」というファラディの考えは、これまであまり本気にしていなかったのだ。
ところが、それと同じことが、マックスウェルの理論から予言されることになってしまったからである。
「やっぱりファラディ先生は実験だけでなくて、理論家としてもすばらしい人だったんだなあ。」
マックスウェルはそんなことを考えながら、一八六二年に発表した論文「物理的な力線について」の中にこう書きつけた。――「上の理論からすると、光は電気や磁気の現象をおこすのと同じものの横波だと考えないわけにはゆかなくなる。」
3 ヘルツの実験 top
しかし、そんな電磁気の波などというものが本当にあるのだろうか。
――まだそんな波を見つけた人はいないのだから、これはむしろファラディやマックスウェルの理論が根本的に間違っている証拠じゃないだろうか。
――ファラディの考えをうたがった人々は、マックスウェルの理論も信用できないといいたした。
そして、世界の電磁気学の理論は、ファラディやマックスウェルのと、それ以前のと、二つに大きくわかれてしまった。
二つの理論の対立はなかなかおわらなかった。
どちらも相手を間違っているとはっきりいえるだげの確かな証拠をもっていないし、普通のことなら、どちらも同じように説明できたからである。
そこで、マックスウェルの理論を支持する何人かの若い物理学者たちは、何とかして電磁気の波を作り出してみせようと努力した。
しかしこれは、大変むずかしいことだった。
たとえ電磁気の波を作り出すことができたとしても、どうやったら、確かにその波ができたと証明することができるだろうか。 科学者たちは困ってしまった。 |

ハインリッヒ・ヘルツ(1857~1891)
電磁気の波をつくり、それを
とらえるのに成功した。
周波数のヘルツは彼の名前。
|
ところが一八八八年、ついに電磁気の波を作り出し、それをとらえるのに成功した、という発表が現れた。
発見者は、ドイツの三十一才の物理学者ヘルツで、彼の実験は全く簡単なものだった。
彼は、ライデン瓶につめた電気を放電して、金属棒の間にはげしい電気火花をおこさせた。
そしてそこから、十数メートルも離れたところにおいた大きな針金の輪のすきまに、火花が飛ぶことを確かめたのである。
つまり、ライデン瓶を放電させると、勢いよく流れだした電気は、ちょうど振子のおもりのように、流れすぎては戻ったり、また戻りすぎては返ったりして火花を出すので、この電気の振動か波となって空間に伝わる。
そしてこれが、遠くの針金の輪のすきまに火花をちらしたというわけである。
ヘルツはこの波が、光線と同し性質をもっていることも確かめることができた。
光と同じように空問をとんでくる電気の波を金鎖の板にあてて反射させることもできる。
彼はこの目に見えない電波の波を、自由に取り扱うことができることを示したのだ。
自分の実験に使った波の一つの波長は九・六メートルであることを確かめることもできた。
ヘルツの実験によって、ファラディの考えと、マックスウェルの理論の正しいことが明らかにだった。
しかしおしいことに、この時にはもうとっくにファラディ(一八六七年)もマックスウェル(一八七九年)も亡くなっていたのだった。
ヘルツの実験は、ただマックスウェルの理論の正しさを証明しただげではなかった。
この実験は、新しく電波の時代を切り開いたたのである。
しかし、ヘルツ自身は、そんなことはまるで考えなかった。
「あなたの発見を使って、電信を伝えることができるようになるのではありませんか。」
ある時こうきかれた彼は、
「いや、おそらく何の役にもたたないと思います。」と答えている。
それにヘルツは、一八九四年の元日、わずか三十七才という若さで、亡くなってしまった。
そのため彼は、実際に電波が無線電信に使われるのを見ることはできなかったのである。
4 発明事業家のマルコーニ top
しかし、この時代の人々がみんなヘルツと同じように考えたわけではない。
いつの時代だって、新しい発見があれば、それを使って何かうまい発明かできるのではないかと考える人がいっぱいいるものだ。
「電気の波が空間を伝わっていくのなら、電線なしで電信を伝えることもできるはずだ。」
こんなことを考えて、研究をはじめた人がたくさん現れたのも当然のことである。
しかし、そのなかで、電波の時代を実用的な発明で切り開くことに成功した人、それはグリエルモ・マルコーニであった。
マルコーニは、イタリアのボローニャに生まれた。
父は大地主で実業家であった。
母はアイルランド生まれのイギリス人で、音楽の国イタリアに留学している間に、彼の父と結婚したのだった。
マルコーニが電波の研究を思いだったのは、一八九四年の夏で、彼が二十才のときのことだった。
避暑地にいた彼は、好きな電気の雑誌で、この年亡くなったばかりのヘルツにかんする記事を読んだのである。
「この電波を使えば、電線なしで信号を送ることができるかもしれないぞ。」
彼はこんなことを考えると、さっそく実験を始めたのである。
彼は幸福な発明家だった。
父の別荘には立派な科学の図書室があったし、大学教授にたのんで個人教授までうけることができた。
父の知人でボローニャ大学の教授だったリーギは、イタリア一の電波の研究者だった。
マルコーニは大学にゆかなかったが、このリーギ教授からいろいろな指導をうけることもできたのである。
三階の仕事部屋にとじこもって研究を始めたマルコーニは、数ヵ月ののちにはもう父母をたちあわせて、電線を使わずに三附の研究室でボタンをおせば、地下室のベルがなる実験にまでこぎつげた。
そして彼の研究は、母に暖かく支えられて、父からは必要なだけの研究費をうることができて、本格的な研究へとすすんでいった。
このようにして、野外にまで出てするようになった彼の研究は、さらに急速に進展していった。
一八九五年十二月には、平地で一・七キロメートルの通信にこぎつけ、さらに丘を越えて一・二キロメートルの通信にも成功した。
これはすばらしいことだった。
これまでも電波で通信をすることを考え九人はいくらもいたが、電波をこんなに遠くまで、障害物をこえて送ることのできた人はいなかったからである。
それでは、マルコーニはなにを発明したのかというと、彼の無線電信装置の一つ一つの部品は、どれ一つとして彼の独創になるものはなかった。
それらはみな、これまでの研究者たちによって発明されていたものだった。
彼は、それまでのほかの人の発明したものを実にたくみにむすびつけて、遠くまで電波を送ることに成功したのである。
長距離の無線電信の実験に成功すると、彼はさっそく特許を申しこみ、郵政省にこの発明を取上げてくれるように申しこんだ。
しかし、イタリアの郵政省は実験をやってみてくれなかった。
5 アメリカ大陸とヨーロッパを結ぶ top
失望したマルコーニは、イタリアを去ることにした。
「そうだ、もっとズッと商業のさかんな国へいこう。」
こう考えた彼は、母の祖国イギリスへ向けて旅だった。
この遠征は彼に幸運をもたらした。
イギリス郵政省の技師長のプリースは、自分でも無線電信の発明に取組んでいたが、自分より三十七才も年下のマルコーニの実験のほうがすぐれているのをしると、自分をすてて応援してくれた。
そして一八九七年の七月、いち早く無線電信会社を設立して、事業を始めることができた。
その後も、彼の無線電信装置は、改良に改良が重ねられた。
彼の目標は海をこえて電信を送ることだった。
この頃、海底に電線をしいて大陸間に電信を通すことがさかんだったが、無線電信でまにあえば、長い長い電線もいらなくなるわげだ。
彼の無線電信は、だんだんと通信距離をのばしていった。
一九〇一年十二月十四日には、彼の無線電信は、ついにアメリカ大陸とヨーロッパとを結ぶことに成功した。
マルコーニの無線電信は、全世界をおおうことができるようになったのだ。
第十五章 テレビジョン――
ペアード、五十年間の夢を実現
top
1 なーんだ、犯人は日光か
一八六六年、大西洋を横断する海底電線がしかれて、初めてアメリカ大陸とヨーロッパとが電信で結ばれるようになった。
この話はそれから七年後の一八七三年のことである。
海底電信会社のヨーロッパ側の電信局に勤めていた電信手のメイは奇妙なことを見つけた。
「どうも、へんだなあ、今度の部品はまるででたらめだぞ。 電流が急に強くなったり、弱くなったり、全くめちゃくちゃだ。」
こういってメイが取り出したのは、この頃、電気抵抗を大きくするためというので新しく使われるようになった、一つの部品だった。 |
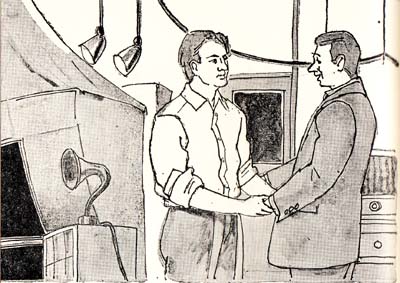
機械式のテレビジョンを初めて作った発明好きのベアード
|
この部品は、セレンという、その頃めずらしい金属でつくられたものだが、その抵抗が時々変るらしいのだ。
「同じ金属の抵抗が、ときによって大きくだったり、小さくだったりするなんていうことがあるもんか。」
そう思ってよく注意して見ても、確かにこの抵抗は時々変るのだ。
そこで、メイはどういうときに抵抗が大きくだったり、小さくだったりするのか、見張ってやろうと考えた。
そしてしばらくこの部品の抵抗を調べているうちに、彼はやっとその正体をつきとめた。
「なーんだ、犯人は太陽なのか。」
彼はあきれてしまった。
日光がセレンによくあたると、電流がたくさん流れるようになることがわかったのだ。
つまり、セレンは光を敏感に感じとって、電気をたくさん流す性質をもっていたのである。
だから、低抗を大きくするためにセレンを使うときは、本当は、この部品をいつも日光のあたらないところにしまっておかなければならなかったわけだ。
2 最初の着想 top
通信子のメイは「奇妙なことを見つけた」と思ったので、そのことをみんなにしらせただけだったが、このニュースが科学者や発明家にしれるようになると、空想ずきな人々は、すぐにこれと新しい大発明を打すびつげて考えるようになった。
「セレンに光があたると、その光の量によって流れる電気量もかわる……
とすると、もしかすると、これを使うと絵や景色を電気で送ることができるようになるかもしれないぞ。」
その頃は、ちょうど、音を電気にかえて遠くへ送る電話が研究され始めていた頃だったから、光を電気にかえて遠くへ送る機械のことを考える人が現れるようになったとしても、ふしぎではない。
実際、光を電気にかえるセレン光電池というのがさっそく発明されて、テレビジョンの研究が始ったのである。
では、一体どうやったら、絵や景色を電気にかえて送ることができるだろうか。
――これにたいする答えは簡単だった。
メイの発見から二年後の一八七五年には、早くもアメリカのケアリーがこんな答えを出している。
「絵をモザイクのようにばらばらにして、一つずつ電気にかえて送ればいいのさ。
電気を受取ったほうで、それをもとどおりに組み立てればもとの絵ができるわけさ。」
ケアリーはこう考えて、たくさんのセレニウム光電池を集めて、絵を電線で送る装置をつくりあげた。
これは、まだ実用になるものではなかったが、写真電送の始りといえるようなものだった。
テレビジョンと違って、まだ絵が動くところまではいっていなかったわけだ。
絵を電気で送ろうとした発明家はケアリー一人ではなかった。
一八八〇年には、もうグラハム・ベル(電話の実用化に成功した人。10章参照)はじめ数人の人たちが、この発明で特許をとっているほどだ。
しかし、それからしばらくすると、テレビジョンの研究は全くゆきづまってしまった。
セレン光電池では、テレビはできそうもないことがわかったからだ。
セレンは光によく感ずるけれども、感じ方がノロノロしていて、次々とうつりかわる光景を電流にかえるには適していないのである。
そこで、テレビジョンの発明家もだんだんと少なくなっていった。
3 電気の正体――電子 top
けれども、科学者たちは、その間にも、テレビジョンとはおかまいなしに、電気の正体をおってどんどん研究をおしすすめていった。
「どうしてセレンは光をうけると電気をよく通すようになるのか。」ということもまだわかっていなかったし、
「電気は粒のようなものなのか、それとも電波のように波のようなものなのか」ということだって、まだわかっていなかった。
だから、科学者たちは、何としても電気の正体をつきとめてやるのだと勢いこんでいたのだ。
「そんなことを研究して、一体何の役にたつんだ」――せっかちな人たちのなかには、科学者たちに向かってこんなことをいう人もあったが、科学者たちは、そんな悪口にかまっているひまもなく、熱心に実験や議論をつづけていった。
そして二十世紀の初めにもなると、その研究によってたくさんのことがわかった。
まず、もっとも大事なのは、電子が発見されたことだ。
電気のもとになっているのは、電子という粒であることが確かめられたのだ。
これはイギリスの科学者、J・J・タムスンが一八八七年につきとめた結論である。
また、金属のなかには、自由に動きまわることができる電子がたくさんあることもわかった。
そしてその金属に光をあてたり、熱したりすると、この電子が飛び出してくることもわかった。
(これはエジソンが発見したことだ)
また、真空にしたガラス管のなかに電子を飛び出させて、それを自由に操縦する方法も研究された。
このような研究は、元々科学者たちが何も特別な発明をめざしてやった研究ではなかった。
しかし、これらの研究は、真空管を生みだしてラジオを実現させ、さらに新しい電気の時代
――つまり電子の利用の時代を切り開くもとになった。
テレビジョンの発明も、このような地道な科学者の研究があって初めて実を結ぶことができたのである。
4 ベアードの登場 top
実用的なテレビを、世界で初めて発明したのは、イギリスのベアードである。
ベアードは、グラスゴー大学の学生だった頃から、自分の家の台所でセレン光電池などを使って、いろいろな実験をやっていた発明ずきの学生だった。
しかし卒業まであとすこしというところで、第一次大戦がおこり、彼のうちの生活が苦しくかったので、とうとう大学をやめて、働かなければならなくなってしまった。
それから、ベアードはいろいろな仕事をやった。
はじめは電力会社の技師として働いたが、元々体の弱かった彼は勤めがむりだとわかると、会社をやめて自分の発明した「ベアード式靴の下敷」や「靴クリーム」をつくって売り出した。
この商売は成功だったけれども、商売に熱中しているうちに、体が悪くなってしまったので、体のことを考えて西インド諸島へ渡った。
そこで、今度はジャム製造業を始めたが、一年ほどするとこんどはジフリヤ熱にかかり、イギリスにもどって蜂蜜屋をやったり、石鹸屋をやったりした。
これらの商売もみなうまくいったが、彼はそのたびにすぐ体をこわしてしまって、静養しなければならなくなった。
そして、とうとう強い神経衰弱になって、医者から仕事を全部やめて静養するように、きびしくいいわたされてしまった。
イギリスの有名な温泉地ヘイスチングで、数ヵ月何もしないで静養している間に、ベアードは学生時代にやったテレビジョンのことを思い出した。
ちょうどその頃、ラジオ放送が始ったばかりなので、「これからはテレビジョン放送の時代がくるにちがいない」と本気で考えるようになったのである。
体がいくらかよくなると、ベアードは、さっそく研究材料を集めだした。
捨てるばかりになったモーターをゆずりうけてきたり、自転車のランプに使うレンズを安く買ってきたり、古道具屋で、中古の無線通信機械や、茶テーブルを買ってきたり……どの材料もみなガラクタばかりだった。
病気で収入のなかった彼は、できるだけ費用をきりつめなげればならなかったのだ。
おかげで、彼の部屋は、まるで古道具屋みたいになった。
しかし、材料がひととおりそろうと、彼は自信まんまんだった。
「テレビの原理は簡単なものさ。」彼はそう考えて装置を組み立ててみた。
が、どうしてもうまくいかない。
その原因は、ズッとまえからわかっていたように、セレンの光電池がよくないためだった。
ベアードもこのことに気がつくと、今度は、全力をあげて光電池の改良に取組んだ。
5 ベアードの前宣伝 top
テレビの発明なら、これまで、ずいぶんたくさんの人が取組んでいた。
初めてテレビのことが考えられるようになってからもう五十年近くにもなる。
それなのに誰もその発明を完成することができなかったのだから、ベアードのような病人あがりの貧乏人が、その発明をやりとげようというようなことは、むりなことのようだった。
しかし、ベアードにも有利なことがあった。
テレビジョンの発明はいつまでたってもできそうもないというので、大きな電気会社などでは、ほとんどテレビの研究をやらせてくれなかったから、この頃、朝から晩まで、テレビジョンのことを考えていられたのは、べつに職業をもたないベアードぐらいのものだっただろう。
貧乏で、体の弱い彼は、そのかわりに研究の時間にはめぐまれていたわけだ。
それに、彼は、初めの頃のテレビジョン発明家たちと違って、それよりズッと進んだ科学の知識を利用することができた。
光電管だってかなり良い物ができるようになっていたのである。
新しい科学の知識、それとめぐまれた研究時間に、もちまえの忍耐力と発明の力、これがあわさって、ベアードはとうとう一九二四年の初めに、人形の形をうすぼんやりと電気で送ることにまで、こぎつけることができるようになった。
ところが、この頃には、ベアードは、ほとんど貯金も使いはたしてしまっていたので、誰か彼の研究を助けてくれる人をさがさなければならなくなった。
しかし、そこはこれまでいろいろの商売で苦労してきたベアードのことだ。
彼はうまいことを考えだした。
新聞社の人たちをよんで、まだできあかっていないテレビジョンの装置を実験してみせたのである。
これは成功だった。ベアードの研究室をおとずれた新聞記者たちは、いくら不鮮明でも初めて見るテレビの装置に感心して、おかけさな記事を新聞にのせてくれた。
やがて、その記事を読んだかね右ちの中から、分明の桓利とひきかえに資金をだしてやろうという人が現れてきた。
ベアードが、この資金か使いつくしてしまうと、今度ぱ、ロンドンでも一流のデパートから、
「宣伝にもなるから、あなたのテレビジョンを三週間公開してくれまぜんか。」といってきた。
一九二五年四月、セルフリッジ百貨店でのテレビの公開実験は、すばらしい前評判をよんだ。
そして、毎日、たくさんの人々がこのデパートにつめかけてきたが、ベアードのテレビジョンを見た多くの人々は、 「なーんだ、こんなものか。」とがっかりしてしまった。
テレビの装置は、石鹸箱に小さな穴のあいた円板を取付けて、それをモーターで回すだけのもので、全く貧弱に見えたし、このテレビでは、まだ人間の顔の区別もつかなかったからだ。
6 感激の日 top
こうしてついに感激の日がやってきた。
一九二五年十月二日、彼はいつものようにいろいろな方法でテレビを映す実験をしていたが、この日の午後、ふとテレビののぞき窓を見て、ハッとした。
そこには、はっきりと人形の顔が映っているではないか。
テレビジョン撮影機の前においてある人形の顔まではっきり見えるのだ。
ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン……
ころげるようにして三階をかけおりたベアードは、すぐ下のクロス商会の事務所にとびこんで、そこにいた給仕さんの腕をものもいわずにつかむと、しゃにむに三階にひっぱりあげてきた。
給仕のティントンさんが、「どうしたんです、ベアードさん」といっても、
「なんでもいいんだ、とにかくきてみてくれ。」というだけだ。
ベアードは、さっそくティントンさんを隣の部屋のテレビジョン撮影機の前にすわらせると大きな声で怒鳴った。
「口をひらいて! ティントンさん!」
「よーし、今度は首をまげて!」
迷惑なのはティントンさんのほうである。
彼は強い雷球にまともにてらされて、まぶしいやら熱いやら、いまにも頭がへんになりそうになったからである。
「ごめん、ごめん、交替しよう。今度はきみがここで見ていてごらん。」
ティントンさんはベアードにかわって、おそるおそるのぞきまどをのでいたところびっくりしてしまった。
すこしボーッとしているが、そこにはベアードが口をあけたり、首をまげたりするのが見えたからである。
「これこそ、世界最初のテレビジョンだ。」
ベアード・テレビは一九二八年には、大西洋をこえて、ロンドンからニューヨークまで、電波でテレビを送るのに成功し、さらにその翌年には、イギリス放送局がベアードの発明を使って、世界最初のテレビジョン放送を開始したのだった。
第十六章 電子式テレピジョン――
テレビジョンの父ズボリキン
top
1 機械式と電子式
ベアードのテレビジョンは、世界最初の実用的テレビジョンであったが、これは今のテレビジョンと全く原理が違っている。
今のテレビジョンはブラウン管が大切な役目をしているが、ベアードのテレビジョンには、ブラウン管などつかわれていない。
彼のテレビジョンにはモーターがついていて、穴のあいた円板をグルグル回すようになっている。
つまりベアードのテレビジョンは機械式テレビジョンで、いまのテレビジョンは電子式であって、その原理は全くちがっている。 |

ズボリキンの電子式のテレビの発明で、テレビ放送が普及した。
|
電子式テレビジョンを初めて完成させたのはロシアに生まれて、のちにアメリカにわたったウラジミル・コズマ・ズボリキンである。アメリカ読みでいうと、ツオリキンということになる。
ズボリキンは、ロシアのセント・ペテルスブルク大学の学生であった頃から、テレビジョンの研究を初めていた。
それは彼の先生のロジング教授の影響があったからである。
ロジング教授は一九〇九年に、モーターを使って円板を動かすよりも、真空管の中で電子を自由にあやつったほうがよいといいたした人で、電子式テレビの第一人者だった。
ロジング教授は、早くからブラウン管に目をつけていた。
ブラウン管というのは、ドイツのストラスブルク大学の教授だったフェルディナンド・ブラウンが一八九七年に発明していた一種の真空管で、これは科学者たちの電子の研究の副産物だった。
その頃、電子の流れに電磁石の力を加えると、その運動の方向を自由にかえることができることがわかっていたが、ブラウン教授は電子がどこにぶつかったかを目に見えるようにするために、真空管の端に螢光板をおくことにしたのである。 |

ウラジミル・ズボリギン(1889~ )は、テレビジョン撮影用の
アイコノスコープを発明した。
|
これはべつに、テレビジョンのために発明されたのではなかったが、ロジング教授は、これはテレビジョンを映すのにもってこいだと考えた。
2 ズボリキン、アメリカヘわたる top
ズボリキンは、大学を卒業すると、ロシア無線電信電話会社に勤めたが、ここで、一九一七年に、テレビの本格的な研究を始めた。ベアードよりズボリキンのほうが研究のうえで先輩だったわけである。
しかし、ロシアはこの頃、戦争や、革命の大騒動の中にあり、おちついて研究することもできなかった。
革命がおわって、ロシアがソビエト連邦共和国(ソ連)に生まれかわると、ズボリキンはアメリカへわたり、自分のテレビジョンの研究を事業化しようとした。
しかし、資金がなくて失敗し、一九二〇年にウェスティング・ハウス会社の技師になった。
この会社は、モールスの電信会社のあとを継ぐ会社だったが、その頃はラジオ放送の研究にかかりっきりで、ツオリキンつまり、ズボリキンがテレビジョンの研究をしたいと申し出ても、全く聞き入れてくれなかった。
しかたなく、彼はほかの会社にうつったが、それからまた一九二三年の二月、ウェスティング・ハウス会社にもどって、やっとテレビジョンの研究を始めることが許されるようになった。
幸い、会社の研究部長が、ズボリキンのそれまでの発明をみとめてくれたのである。
そこで、ズボリキンはさっそくテレビ実験の準備をし始めたが、この実験は失敗だった。
そこであらためて光電池の研究を深くやりなおすことになった。
ところが、その間に、ベアードの実験成功の報告がもたらされ、彼はさきをこされることになった。
また一九二七年には、日本でも浜松高等工業専門学校の若い教授だった高柳健次郎が、受像管にブラウン管を使ったテレビをつくることに成功して、十一月二十八日、東京の電機学校で、初めての公開実験を行った。
このテレビの撮影機のほうは、機械式だったので、純電子式テレビジョンではなかったが、受像機にブラウン管を使った最初のテレビジョンであった。
電子式テレビジョンができれば、機械式のテレビジョンよりもズッと小さくて雑音がなく、しかもズッと鮮明な像ができることは確かだったから、この頃の発明家たちは電子式のテレビジョンの発明に全力をあげていたのである。
ズボリキンも負けてはいなかった。
純電子式テレビジョンの発明に向かった彼は、ついに一九二八年に電子式テレビジョンの撮影用の真空管を発明し、特許の申込みをするまでにこぎつけた。
この撮影用の装置は、一九三三年にアイコノスコープと名づけられて、初めて発表され、野外テレビジョンの試験が行われたが、これによって、純電子式のテレビジョンが初めて実用化されるようになったのである。
アイコノスコープの発明は、すぐに会社の人たちにみとめられて、それから大々的な研究が始った。
その頃はもう、イギリスやドイツでは、機械式テレビジョンによるテレビジョン放送が始っていたから、アメリカものんきにかまえてはいられなかった。
一九二九年になって、アメリカでたくさんの会社が合同して、アメリカ・ラジオ会社(RCA)がつくられたが、ズボリギン博士もこの新会社にうつると、六十人もの研究者を指導して研究をすすめることができるようになった。
しかし電子式テレビを広くゆきわたらせるには、まだまだたくさんの問題が残っていた。
たとえば、アイコノスコープではまだまだ感度が悪くて、撮影するへやを特別明るくする必要があり、映される人は汗だくにならなければならなかった。
だから、自然のままの野外のありさまを映すことなど、とてもできることではなかった。
そこで、ズボリキンは一九四一一年頃、さらにイメージ・オルシコンという新しい機械を発明して、この困難をのりこえることに成功した。
この機械は、アイコノスコープより数百倍も感度がよいので、どんなものでも自由にテレビジョンに映すことができるようになったのである。
3 アンテナは八木・アンテナ top
ところが、その頃不幸なことに第二次世界大戦が始ってしまった。
そしてもうテレビジョンの研究どころではない、ということになってしまった。
日本でもその頃までテレビジョンの研究はさかんだったのだが、日本でもどこの国でも、テレビジョンを研究していた科学者や技術者たちぱ、電信やレーダーなど、そのまま戦争に役だつ研究に使われてしまった。
テレビジョンの研究はあとまわしになってしまったのである。
第二次大戦が終ると、世界中でふたたびテレビジョン研究がさかんになった。
テレビジョンを本当に実用的なものにするためには、解決しなければならない問題が山ほどあった。
たとえば、アンテナをどうしたらよいかとか、テレビジョンの中継局をどうするかというような問題があった。
テレビ用のアンテナとしては、戦争中、レーダーに使われていたアンテナが使われるようになった。
これは、もとをただせば、一九二五年に、日本の八木秀次が東北大学の教授のときに発明したものだった。
日本でははじめこのアンテナはあまり重要なものと思われていなかったが、戦争中にアメリカ軍が、これをヤギ・アンテナとよんで、広く使うようになってから、このアンテナが有名になってきたのである。
電子式テレビジョンは、第二次大戦前にも一時放送されたことがあったが、大戦後になって初めて、急速な勢いで広く使われるようになったのである。
top
**************************************** |