|
****************************************
Ⅰグラビア写真 Ⅱ青木槐三(鉄道作家) Ⅲ堀内敬三(音楽評論家) HOME
東海道本線だった時代の御殿場線
(苦しい鉄路――御殿場線 青木槐三鉄道ピクトリアル No60 1956/7
|
明治期の東海道線の建設は驚くべきスピードだった。M19/11/10横浜-名古屋間の工事を横浜、名古屋両側から開始し、9ヶ月でM20/7/1に国府津まで、2年余のM22/2/1に静岡まで、そして西からの工事の静岡-浜松間がM22/4/10に繋がり完成している。
しかし国府津-御殿場-沼津は25‰の勾配の山線だったので、後藤新平鉄道院総裁の指示で、M42に新線の調査を開始し、T7に丹那トンネルの掘削を始めた。しかし地質が悪く工事が難航し、多くの犠牲と多額の費用をつぎ込んで、S8にやっと貫通させた。トンネルだけで16年、調査開始以来4半世紀に及ぶ大工事となった。
M40年にすでに日本電気鉄道会社から、電気鉄道で急勾配を克服する第2東海道線の申請が出されていたにもかかわらず、それを何度も却下し、丹那トンネル掘削にこだわり続けたのである。東海道線の全線電化は戦後のS28のことである。御殿場線はもっと早く電化すれば十分活用できる線路であった。
1 苦しい鉄路
2 昼夜突貫工事の建設
3 開通後の運転、保線の苦労
4 御殿場線の電化案と日本人機関士第一号
5 御殿場線を走った特急列車つばめ
|
 T T |
1 苦しい鉄路 top
御殿場線のことでも書いてくれと鉄道ピクトリアル社長の田中隆三さんから話があった。
「ああ、御殿場線のことなら何んかあったような気がしますね」
と答えたのは、あの線がゾッとする苦しい線であったからだ。
新聞記者だった私がゾッとしたのは油断をしていると、その度不通事故が毎々あったからなんだが、古い鉄道人にとっても、この線路はさらにゾッとする線であったろうと思う。
もちろん御殿場あたりの富士山に近い風景は懐かしい限りで、山中湖などで鉄道主催キャンプを毎夏やった思出は忘れることのできないものである。
でも、これを最初に建設した鉄道技師も、その後この線の上を走った運転従事員も、又この線を持っていた鉄道現場などの人々にとっても、まことに厄介なゾッとする線であったと思う。
だからこそ、25年もかかって熱海線を建設し、2,600万円もかけて延長7,804mの丹那トンネルを掘ったのだ。
熱海線を考えたのが後藤新平で明治42年(1909)のことである。
東海道線ができた明治22年7月1日から御殿場線の苦労は始ったわけだ。
いや、この区間が汽車が走ったのは厳密に言うとそれより5ヶ月前の明治22年2月1日と言う話だから、定期列車の動いた国府津-静岡間の開業の日から苦しんだのだろう。
ゾッとし続けた結果、この七つものトンネルがあって、しかも1/40の勾配の山線、橋梁が10ケ所、見上げるような切通しの山裾を走る線を、何んとかして逃れたいと言うのがオール鉄道人の願望だった。
それを解決したのが時の鉄道院総裁をしていた後藤新平なんだが、熱海線が開通してしまうとこの線はすっかり鉄道の旅客に忘れさられてしまった。
松田・山北・足柄・御殿場・裾野などの駅名すら不思議な感で受取られる。
それが又この頃、電化と電車の乗入れや熱海線の行詰りなどからフットライトを浴びて来つつあるのは興味がある。
2 昼夜突貫工事の建設 top
さて、この御殿場線の工事は言うまでもなく、東海道線の主要工事の一部だった。
それは横浜から沼津までを受持った原口要技師が主任で指揮をやったが、実際の仕事は当時一等技手だった元満鉄総裁野村竜太郎氏が担当した。
原口要と言う人は肥前の人で、1844年に生れて1927年に歿し、日本の鉄道のそもそもの創業期の功労者で高崎-名古屋間、上野-青森間、東海道線、山手線、中央線の測量やら工事をやったと言う人物だ。
とても厳しい雷親爺だったから部下に恐がられた。
突然製図室などにこの人がはいって来ると、小役人は思わず机の下にもぐりこんでしまったことがあったと言う伝説があるほどだった。
従って、工事も猪突主義であった。
この線を造る時は鉄道頭の井上勝が
「是が非でも第一回国会の開会に間に合わせる。
いつ清国(いまの中国)と開戦があってもそれに間に合わせるように建設する」
と堅く政府要人と約束していたから、原口技師に
「君の受持箇所のうち横浜-国府津間は何日位かかるか」
と訊ねた。原口は大体6ヶ月位でしょうと笞えると、
「その期間にできなかったら君はどうするか」
と井上勝がたたみかけて聞いた。随分酷いことを言ったものだ。すると原口技師は
「できなかったら切腹します」
言った。こんな曰くつきの線であったから原口は生命がけであった。
6ヶ月で横浜-国府津間が、1886年と言う鉄道建設技術も進歩していなかった時代に、どうしてできたんだろうと思っていたが、いま手元の控を見ても、東海道線の工事にかかったのが、明治19年の11月10日東海道幹線横浜-熱田間工事を起すとあり、明治20年7月1日東海道線横浜-国府津間は開通しているから、これは切腹しないで済んだ次第である。
さて、この御殿場線と野村竜太郎氏の担当した国府津から先、沼津まではと言うと明治19年の11月に工事を開始して、明治22年の2月1日に国府津-静岡間が開通しているから、2年余で出来た事になる。
この速さではいかに工事に苦労したかが判る。
当時の請負の記録によると、この工事の請負は鳶出身の松井組が引受け、箱根のトンネルは現業社が請負った。
7ケ所のトンネルは合計の延長が2,000m余で、峻嶮に架した橋梁は10ヶ所であった。
トンネルの中で最も長いのは312mの第2号、次が284mの第1号で、一番短いのは第6号の86m、いずれも当時穴掘の名人と言われ小川徳平、如来儀兵衛の両人がこれを堀った。
今は全くその名を知る人もないが、その時代にはそうそうたるトンネル技術家であった。
この2人は現業社南一郎平の輩下で、南と言う請負人は「トンネル南」と呼ばれ、その頃橋の技術家で「鉄橋小川」と呼ばれた小川勝五郎と並称された。
当時天下無双の穴掘の達人であったのだ。こんな名人が掘ったトンネルであることが興味がある。
でも、この七つのトンネルはすべて手掘で、鉱山用の火薬を用いた位の工事方法であった。
ところが一番長い第2号トンネルの坑内から水が噴き出してとまらず、このトンネルを掘るために非常な失費が入り、借金が増えて遂にこのために、さしもの南一郎平の主催する現業社と言う請負業も潰れると言う悲運に際会した。
この線路は橋梁とトンネルがほぼ出来上った頃に、大暴風雨が襲来して方々の築堤が崩れた。
鉄道頭の井上勝は期日までに工事の完成が覚束ないのを心配して、工事総指揮官の原口要技師を激励して
「この復旧工事の良い方策がないとならば天に祈って雨を降らせないようにするがよい。
そいつを考えてくれよ」
と言ったと言う話が請負の歴史にある。皮肉だ。
御殿場線の雨禍はすでに工事中から初っていたのである。
この工事は請負人が潰れるほどの難工事であったが、それよりも短時日に竣工すると言う制約があって、井上鉄道頭の激しい要請は原口技師に雷をしばしば落すこととなり、原口技師はそれに輪をかけた雷を、野村竜太郎技手や同じく木村懋(つとむ)技手の頭上に落した。
野村技手は温厚玉のごとき人柄だったからこれをいつも軽く受けとめ、豪雨中には工事を休止して時々工夫を休憩させたりしていると、蓑笠姿の原口技師が豪雨の中を突然巡視に来て、
「雨が降った位で仕事を休む奴があるか、馬鹿!」
と、どなりあげる有様で、主任の野村竜太郎は寝る閑もなく、昼間眠りながら監督して歩いたので、沼津-御殿場間の築提から下に屡々転がり落ちたと伝記に書いてある。
とにかく御殿場線は激しい突貫工事であったのである。
いや東道線全線工事がそうであったが、天下の険を貫くだけに苦労した。
――岩きり通し山を抜き 行くや千里の鉄の道――
の苦労であったのである。
3 開通後の運転、保線の苦労
top
こうした艱難辛苦の末でき上ったこの御殿場線は東海道線の癌になった。
一寸雨が降ると土砂崩壊で不通となる。
不通となると国府津と沼津には貨物列車も旅客列車も立往生となる。
まことに東海道には矢張箱根の関所があるわけで、この貨客の滞留の苦しみは大井川の川留と同様で、西から東京にはいって来る物資はここて喰いとめられ、東西両京の交通は遮断されてしまうのであった。
当時の鉄道人の苦しみは現在の人には想像もできないことであった。
筆者が新聞記者になった許りの1920年前後でも箱根の崖くずれ、列車不通は台風期に2・3日箱根に雨が降り続けば当然のことで、不通の予想記事を書いて置いても間違いがなかったほどである。
明治43年(1990)の8月8日から13日まで山北-御殿場間が水害不通で、横浜から熱田港まで汽船を運航して旅客を運んだことがあった。
大正2年に新橋の運輸事務所長をしていた元日本交通公社総裁の大蔵公望さんは、わが鉄道生涯中の3度の生命拾いの2つだと、この御殿場線の水害実地踏査を語って居られる。
暴風雨のため箱根線は線路は寸断され、橋梁は流失してしまい、33ヶ所も寸断になった。
山北-小山間が一番ひどかった。
現場に1週間以上も泊りこんでいたが、その雨の降るある夜、洗われた枕木の上を歩いて同僚の2人と並んで行くと、アット言う間にその人の影がない。6m余の泥中に落ちてしまったのだ。 |
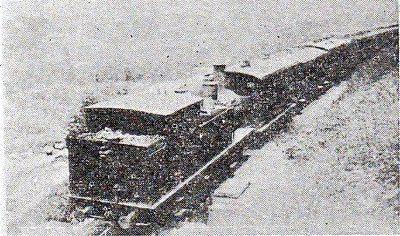
谷峨-駿河間を後向きで牽引するB6機関車列車
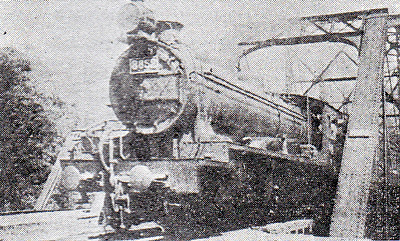
谷峨-駿河間第3相沢川橋梁進行中の8850
|
持参のカンテラで足下を見ると自分も板も土もない洗い流された枕木の上に偶然立っているのでゾッとした。 全くの生命拾いであったと語っている。
それから45日ほどたって、やはり、水害の復旧工事で線路視察にトロで出かけることになったが、用事があったので次のトロで行くことにしたら、その乗るはずであったトロは上りのトロと衝突して20名が全滅してしまって、大蔵さんは不思議に生命拾いした。
しかし、こうした経験は大蔵さんだけではなく御殿場線を東海道線が通っていた頃は鉄道人の誰もが、毎年雨期には苦い経験する鉄路であった。
機関手ばかりではない、旅客列車の車掌でも大苦労であった。
明治23年に東海道線列車の車掌だった長唄界の長老松永和風さんの話をきいたときも、この箱根を列車で越えるときの苦労が一番つらかったと言う話だった。
何しろマッチ箱のような外びらきの客車で、車掌は車長と言って名前こそよかった板敷の狭い室の中に居たのだから、たまったものではなかったろうと思う。
そのとき松永さんが紫檀の机を小さく叩いて鉄道節を唄ってくれたが、その中の文句にも
――ハア七つの穴で苦労する――
との箱根のトンネル通過の感想が唄われていたほどであった。
乗客が1/40の勾配を上るシュシュと言う響とのろい速度、その上に窓からはいる黒い煤煙で、白いワイシャツも見る見るまっくろ気になり、国府津か沼津で洗面してやっと生き返ったのは当り前のことだが、機関手となると全くこのトンネルをくぐるのは生命がけであった。
トンネルの中では車輪が空転して、湯のごとき蒸気が顔にかかって窒息しそうになる。
新鮮な空気を求めて機関車の床より下に這って息をして、濡れた手拭で口を蔽って息もたえだえに煙に巻かれるのを免れたことは、老機関手の一様に語るところであった。
鉄道運転界でもっとも古い技師の一人に工富准さんが居る。
工富さんはこの御殿場線て苦労をした技師で初任級45円で箱根越えの罐たきに年期を入れた。
でも工学土工富のくべる石炭がよく燃えたそうだ。
この罐たきの苦しさは、いま考え出してもおぞ毛が振うと言う。50年たった今日の話である。
その後工富が運転の主任になった明治40年代機関車はB6と言った奴で、この勾配を換算28両をつけると、機関車2台でも上り切れない。
そこで工富は機関車3両をつけて運転した。前に1台、真中に1台、後部に1台で運転した。
列車のまん中に機関車を挟んだのは連結が切れるのを恐れたからだそうだったが、操車がやりにくくて仕方がないので後部に2両つけることにした。
それでも7トンの貨車が20数両やっと勾配を上る位で、下り勾配では時にプレーキが利かず、分離した列車がえらいスピードで突走ってしまって、途中の駅ではすさまじいブンと言う音だけ聞いて、今のは列車だったのかと戸迷うこともさいさいてあった。
こんな輸送力だったので箱根を越える貨物は、明治40年代には1日880両を越したことがなかったと言うのである。機関車が小さかったからだったが、何んと云ってもトンネルの多い勾配線と言うのが本質的な欠陥であったろう。だからこの線の列車運転は技術が入用であった。
4 御殿場線の電化案と日本人機関士第一号 top
丹那トンネルは前後16年もかけて堀ったが、このトンネルが建設中に幾度も事故を起した頃は
「御殿場線を電化して複線にすれば立派な線になる。
電気機関車の強力なものが出現している今日、トンネルや勾配は少しも恐れるところではない。
地質の判っているところにもう1本トンネルを掘るなどは訳のないことだ」
と、大分御殿場線が息を吹き返すような話題も囁かれたのであった。
この大戦中に
「石炭は悪質になって泥が半分だ。石炭のよいのを鉄道に廻わして貰わなくては」
と、いま国鉄副総裁をしている小倉俊夫氏が商工省の難波燃料局長に機関車に乗って貰ったのも、この御殿場線でカロリーが5,000を下回ると倍の石炭がいるし、6,000カロリー以上だとそれが半分ですむと言う体験をして貰う為だった。
勾配線と言うのでは御殿場線は標準タイプだから、今までも試験には度々使用されているが、国鉄がアメリカから大量に機関車を購入していた昔の話だが、初めてアメリカの会社が大形機関車を売り込みに来た時、やはりこの御殿場線で試験運転をやった。
この勾配区間に来るとどうも蒸気が上らないで成績がよくなかった。
そこで当時もっとも機関手界で腕ききと立てられて居た平野平左衛門が、この難物機関車をこの勾配線でうまく運転したところ、立合ったアメリカ人技師が大枚200円を手に握らしたと言う。
金を出された天才機関手も驚いたが、これを上司に訊ねると貰って良いことになったそうである。
平野平左衛門氏は日本人で初めて機関士になった人物である。すなわち
「明治12年4月14日、建築師長ホルサムの上申により機関手乗組火夫業務習熟者を試験の上、落合丑松・平野平左衛門・山下熊吉に旅客列車機関方を命じ、新橋-横浜間を乗務せしむ」
と記録のあるのはこの人であった。
5 御殿場線を走った特急列車つばめ top
さて、この御殿場線を通る度にいつも苦労した私も胸のつかえが一度におりた経験があった。
それは昭和になってからで、超特急つばめの練習運転の時であった。
この間故人になられた鉄道運転界の鬼才結城弘毅さんが、補機を運転中に付けて、運転中に放してこの勾配線を征服すべく研究し、随分練習もさせた上、それは実行可能な域に達していた。
進行中の列車を後から追いかけた機関車が実にうまく連結するのであった。
これを見物に行った私は実に運転の妙技を見る心持がして愉快でたまらなかった。
だがこの妙技は実施されなかったから、見た人達はごく少ないであろうと思う。
今から思うと懐かしいこの線の思い出である。
超特急の試運転は昭和4年12月4日だったが、国府津から補機を付けた世紀の列車は、山北-御殿場間1/40上り勾配を平均50キロで走った。
このとき私は手帳にこう書いている。
「国府津を出発したのが9時27分強、いよいよ箱根ごえの難所、山北-御殿場間の1/40勾配に差掛かった。
特筆すべきはこの急勾配区間で平均50キロの進度でぶっ通して走破したことだ。
われ等の超特急は1/40の勾配を平地を走るように登って行くではないか。
特急でもこの箱根山では従来32キロの速度を出していない。
歩行すれば五歩に一休み、十歩に一休みの区間を50キロの速度を一度も落さず走って行く。
このときほど快哉を叫びたくなったことはなかった。
難なく補機、を進行中に切り離して沼津に到着したのが10時32分、最高速度松田付近56キロ、東京-沼津間2時間8分1秒だった。」
数々の懐かしい苦しい鉄路の思出である。
top
**************************************** |