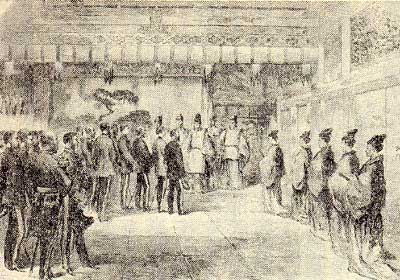|
****************************************
Index 岩瀬忠震 孝明天皇 徳川慶喜 小栗忠順
幕末悲運の人びと 3
「大君制」創設に敗れた徳川慶喜(とくがわ・よしのぶ)
|

日本式の盛装の徳川慶喜
|

洋服姿の徳川慶喜
|
はじめに
イギリス公使パータスの懐刀であったサトウは、慶喜を「私がこれまで見た日本人のなかで最も貴族的な容貌をそなえた一人で、色が白く、前額が秀で、くっきりした鼻つきの立派な紳士であった」と評している。
これは、慶応三年(1867)三月、パークスに随行して大坂で慶喜と会見したときの印象である。
慶喜の写真からすると、サトウがたたえた彼の容貌はけっして偽りでないことがわかる。
のちに述べるように、このときの慶喜の態度はすっかりパークスを魅了してしまった。
それは、慶喜の気品ある貴族的な容貌のみによるものではなく、彼が情勢の変化に対応できる能力をもっていたからである。
すでに慶応元年(1865)ごろから慶喜は洋服を着用していたらしい。
西洋嫌いの朝廷側では、彼の洋装が気になって仕方がなかった。
この年八月二十七日の賀陽宮の日記には、洋服をやめるようにという朝旨を守らないのは「不忠」であり、亡父斉昭(なりあき)の遺志を守らないのは「不孝」で、「実に天下の大罪人」として申入れる、としるしている。
このような朝廷側からの申入れにもかかわらず、慶喜の西洋ずきはこの後、いよいよつのった。
翌慶応二年(1866)九月二十七日の中山忠能の日記には、慶喜が洋服を着用するにとどまらず、諸道具・食物、ことごとく洋風を用いているとの説を伝えている。
さらにその後十一月十六日付の西周助(のちの西周=にし・あまね)らの書簡は、慶喜が側室三名を写真で選んだ、と報じた。
こうしたことからみると、慶喜はまさに明治期における文明開化の先駆者なのである。
慶喜の西洋ずきは、彼が情勢の変化に対応できる人物であることを示す。
この意味で、彼は激変する時期の政治的指導者として、まことに適格であった。
徳川政権の安定期ならば、そのすぐれた資質からいって、慶喜は吉宗と並ぶ「英主」と仰がれたにちがいない。
いや彼は、十四代将軍との血縁の遠さから、徳川の安定期なら、とうてい将軍の座には就けなかったであろう。
1 権力欲の燃焼 top
「ネジアゲの酒飲み」
慶応二年七月二十日、十四代将軍家茂(いえもち)が第二次征長出陣中に大坂城で二十一歳の短い生涯を終ったとき、徳川幕府は、いまだかつてない重大な危機に直面していた。
二度目の対長州戦は、はじまってから一ヵ月あまりで、敗北はすでに決定的であった。
そればかりではない。
第二次長州戦がはじまる前後から、米価をはじめもろもろの物価が天井しらずの値上がりをみせ、江戸・大坂およびその周辺には、激しい世直し一揆がまきおこり、それが、幕府はじまっていらいの規模で全国に拡大する傾向を示してきた。
このままでは、幕府といわず、諸藩といわず、すべての封建支配者の土台を根こそぎ押し流してしまいかねない。
この情勢をおそれて、長州戦停止論は高まりつつあった。
一方長州藩と同盟関係にある薩摩藩は、島津久光・茂久父子の名で朝廷に建白書を提出し、この大きな危機に対応するため、長州に対して寛大の詔を下して戦争をやめるように主張した。
そして、朝廷内の反幕的勢力と結んで、家茂の死を機会に幕府を廃して、王政復古を実現しようとしていたのである。徳川一門のうち、この難局をせおって立てるものが慶喜以外にないことは、衆目の一致するところであった。
慶喜はそのとき三十歳。
松平慶永(よしなが=春嶽)が、御三家・御三卿の将軍候補者を一人ずつあげ、その六人までを不適格として打ち消したのち、やおら七本目の指を慶喜の顔前に突き出すと、慶喜は大笑いしてしばしなにもいわず、一時は承諾しそうな顔色であったが、どうしても将軍就任を引受けようとしなかった。
だが慶永は、慶喜の態度を「ことわざにいうネジアゲの酒飲みで、じゅうぶんネジアゲられたうえでお受けになるのだ」と評したという。
その後も、京都守護職松平容保(かたもり)・京都所司代松平定敬や老中板倉勝静(かつきよ)が京都にある慶喜の宿舎に日夜詰めきってくどき落とそうとしたが、彼は巌(がん)として応じない。
ところがさらに慶喜の近臣、一橋家用人の原市之進らの勧告が彼の意を動かしたもののごとく、容保・定敬および板倉の重ねての懇請にあって、慶喜は、将軍になることはいちおう別にして、徳川宗家(将軍家)の相続のみを承諾する意向を表明した。
それも年来の主張である「弊政改革」を条件としたのであった。
こうして慶喜の相続が確定したのは、七月二十七日のことである。 |

越前福井藩主・松平慶永(よしなが)
徳川家の後始末をした
勝海舟、大久保一翁に近いハト派
|
慶永の「ネジアゲの酒飲み」という予言はみごとに的中した。
そうすると、慶喜はなぜあれほど頑固に拒んだのであろうか。
ここで慶喜がたどってきた道をふりかえってみよう。
タカ派姿勢の展開
慶喜は水戸藩主徳川斉昭(烈公)の第七子として、天保八年(1837)九月、江戸小石川の藩邸で生れた。
幼時より健康に恵まれ、武術を好んだが、読書は嫌いで、近侍の諌めをきかなかった。
それでしばしば灸をすえられることもあったが、平然としていたとのことである。
とにかく相当のきかん坊で、後に「強情」のニックネームをつけられる素質はすでに幼年時代にきざしていたといえよう。
父斉昭は慶喜を「天晴(あっぱれ)、名将ともなろうが、よくしないと手に余るだろう」と評し、暗にその将来に期待をかけたという。
弘化四年(1847)、十一歳で御三卿の一つ一橋家を継いだ。
やがて黒船渡来後の重大な時局となり、病弱無能な将軍家定(いえさだ)ではまことに心もとないというので、将軍継嗣問題が起った。
そのとき慶喜は、幕府・諸藩を通じる改革派によって「年長・賢明・人望」のスローガンのもとに継嗣の候補におされ、「血縁の近さ」を一枚看板とする紀州藩主の慶福(よしふく=のちの十四代将軍家茂=いえもち)と対立した。
慶喜を支持するものを一橋派といい、慶福を推すものを南紀派という。
しかし南紀派の首領井伊直弼(いい・なおすけ)の登場によって一橋派は政界から一掃され、安政六年(1859)八月、慶喜も隠居・慎みを命じられた。
文久二年(1862)になると、政局は大きく転換した。
この年四月、島津久光は、兵をひきいて入京し、勅使大原重徳(しげとみ)を擁して江戸におもむき、暴府の改造を企てた。
大原は登城し、勅旨をもって、慶喜を後見職とし、慶永を政事総裁職とするよう、将軍に伝えた。
その結果、七月六日、慶喜は一橋家再相続の上、後見職を命ぜられ、つづいて慶永は政事総裁職を命ぜられた。
慶喜・慶永の復活は、安政期における一橋派の再登揚を思わせたが、いまやかっての一橋派は、タカ派の慶喜とハト派の慶永とに分裂していた。
慶永は、将軍継嗣問題以来の持論に従って、幕府の私政を去り、天下の公論に従うべきことを説いた。
この原則から、慶永は安政大獄関係国事犯人の赦免を主張したのに対して、慶喜はこれに反対し、意見が対立したが、結局、慶永の説に従わざるをえなかった。
また対外問題についても、慶永は、幕府が専断で結んだ条約をいったん破棄し、改めて全国の諸大名を集めて、将来の対外方針を決定すべきことを主張した。
しかし、慶喜はこれに反対して、開国の趣意を朝廷に奏上すべきことを力説し、大名を集合させても、時勢に適応しない愚論を吐けば、いかに処置するか、と反論した。
将軍上洛の期を明春にひかえた文久二年の末、慶喜と慶永は全く違った政治構想をもっていた。
慶喜は、大兵をひきいて上洛し、京都を威圧しようと企てた。
このころ、外国奉行らは英・仏・米三国公使を歴訪して、幕府が攘夷派の諸大名を抑えようとするとき、外国側に幕府を援助する意向があるかどうかを打診しているから、慶喜の企図はこれと関係があるのであろう。
慶喜はこの計画を慶永にはかったところ、慶永は同意を表明しなかった。
慶永は島津久光と結んで、幕薩連合を策していたのである。
文久三年(1863)三月将軍家茂が上洛すると、たちまち京都を支配する尊攘派のスケジュールに振りまわされた。
四月十一日攘夷祈願の石清水(いわしみず)行幸にさいして、将軍は慶喜の勧告により、病気を名目に随行を辞退した。
そして石清水社頭で、天皇から将軍の代りに慶喜へ攘夷の節刀を授けようとする計画があったが、慶喜は急病ということで出席しなかった。
慶喜が極力、尊攘派の圧力を払いのけようとしたにもかかわらず、四月二十日、将軍は五月十日を攘夷期日として布告するのやむなきにいたった。
しかも将軍の東帰は容易に勅許がない。いまや将軍は、尊攘勢力の重囲におちいった。
このとき、将軍留守中の江戸では、新しい情勢が生じた。幕府が容易に生麦事件の償金を支払いえないのは、京都における攘夷派勢力の圧力によるとみたイギリス代理公使ニールとフランス公使ドゥ・ベルクールは、文久三年三月、攘夷派を鎮圧するため幕府に軍事的援助を提供しようとしていることを、外国奉行に提案した。
外国奉行は、京都における幕府首脳に連絡した上で、かの提案の受入れを謝絶したが、一群の幕臣が、提案受入れを幕府に建議していたことに注目する必要がある。
このような幕臣の動きを背景に、五月九日老中格小笠原長行(ながみち)は、個人的行為として生麦償金を支払い、その後、兵をひきいて上京し、攘夷派を一掃しようと企てた。
生麦償金支払の前日、慶喜は、攘夷の勅旨を伝達するため江戸に帰り、翌日登城して、攘夷の勅旨を老中以下の要職に伝えたが、これには一同強く反発した。
しかし慶喜はそのまま引下がり、やがて小笠原と行動を共にすることになった。
予定の計画であったのかもしれない。
ところが予定された五月二十四日になると、彼はまた急病と称して出発を延期した。
おそらく小笠原のクーデタが必ずしも成功しないであろうことを予想して、逃げを打つたのであろう。
この間の慶喜の行動は謎に包まれているが、同じくタカ派として、小笠原との関係がこれからも続くことに注目しておこう。
一方小笠原は、幕府の船にイギリスからチャーターした二隻の汽船を加えた合計五隻の汽船に、新装備の軍隊千四、五百人を乗せて大坂に向った。
六月のはじめ小笠原は、軍隊をひきいて京都に向う途中、将軍の命令で阻止され、攘夷派一掃のクーデタは未発に終った。
小笠原はその職を罷免されたが、形式的な尋問だけで江戸へ帰された。 |

老中格小笠原長行(ながみち)
『大日本名家肖像集』/
国立国会図書館蔵
|
あまり深く追及すると「諸親藩満城の輩まで」も累が及ぶのを恐れてであるという。
そして「諸親藩」のなかには、まず慶喜が入るであろう。
雄藩勢力との対立
小笠原クーデタが失敗してから二ヵ月余、薩摩藩兵を主力とする八月十八日政変で、尊攘派は京都から追放された。
政変後は、公武合体派が政局の収拾に当り、十二月三十日、慶喜および松平容保・松平慶永・山内豊信(とよのぶ=容堂)・伊達宗城(むねなり)が参与を命ぜられ、翌元治元年(1864)一月十三日には、島津久光も参与に加えられて、ここに参与会議が成立した。
これは久光の主唱によるもので、雄藩連合政権をめざしている。
参与会議が開催されると、幕府内のタカ派を代表する慶喜と島津久光ら雄藩勢力とのするどい対立が展開された。
対立の主題は横浜鎖港問題である。
二月十五日の朝議で、慶喜が横浜鎖港を主張したのに対し、久光・慶永・宗城の三人は、そんな無謀をするのではとても協力できないから、長州藩主父子を召致し、攘夷を委任したほうがよい、と言い放ち、慶喜と激論をかわした。
つづいて翌十六日中川宮邸の会議で、慶喜は酒気を帯びて、中川宮が薩摩藩を信用するのをなじり、ご一命を頂戴し自分も切腹する決心である、などと暴言を吐いた。
さらに彼は、暴言のついでだとして、久光ら三人を「天下の大愚物、天下の大奸物」とののしった。
このような慶喜の激しい挑発行動で、やがて参与会議も解体してしまう。
この会議を短命ならしめたのは、政局の主導権をめぐる幕府と雄藩との対立である。
横浜鎖港をめぐる論争にしても、その底には「薩州の開港説」には乗れないという幕府側の決意があった。
当時薩摩藩では、幕府の貿易独占を排除しようと意図していたのである。
三月九日、慶喜がまず参与を辞任し、ついで他の諸参与もこれにならった。
豊信は、アルコール中毒がこうじたせいか、会議にもほとんど出席しなかったが、藩内における勤王党の動きが気になって、まっさきに帰藩した。
とにかくこのようにして、慶喜の高姿勢が雄藩連合政権成立の可能性をつぶしてしまった。
そののち三月二十五日、慶喜は後見職を辞し、代って禁裏御守衛総督・摂海(せっかい=大阪湾)防禦指揮の任に就いた。
島津久光がかねて摂海防禦の任に当ろうとしているとの風説があったので、先手を打ったのである。
はたして久光・慶永・宗城らは、慶喜の就任を不快に思い、天皇を擁して将軍の権を奪い、天下に号令しようとする野望がある、と非難した。
禁裏御守衛総督等の就任で、慶喜は京坂地方における実権を掌握することになったが、雄藩との間はいよいよ疎隔した。
そして慶喜の両翼をなしたのが、京都守護職松平容保(会津藩主)と京都所司代松平定敬(桑名藩主)である。
慶喜のタカ派的姿勢を示すものに、水戸藩天狗党に対する処置がある。
元治元年十一月の末、天狗党の一隊が京都に入ろうとするとの風説が届くと、慶喜はみずから朝廷に出陣を請うて許可され、十二月三日、京都を出発した。
やがて天狗党は加賀藩の陣営に投降したが、慶喜は池田慶徳(よしのり)らの諸兄弟や加賀藩から、寛大な処分を嘆願したにもかかわらず、翌慶応元年(1865)一月、武田耕雲斎以下八百余人を若年寄田沼意尊(おきたか)に引渡した。
寛大な処分を期待していた一橋家や加賀藩の諸士はみな失望し、口々に慶喜の行動が冷酷なのを非難したという。
はたして田沼は、武田以下三百五十余人を斬罪に処するなど、過酷な処分をした。
慶喜は天狗党の処分について、幕府の嫌疑をはばかったのだと弁解しているが、天狗党の慶喜によせる期待をよそに、はじめから討伐の強硬方針を持していたのである。
将軍側近との暗闘
慶喜が京都で勢力を拡大しつつあるのに対抗して、江戸の幕閣では、大兵を京都に派遣し、慶喜を帰府させ、直接、幕兵をもって京都を守衛しようと企てた。
こうして慶応元年二月のはじめ、本庄宗秀・阿部正外の両老中は、大兵をひきいて入京した。
宗秀は慶喜に会見し、慶喜および容保・定敬を帰府させるという将軍の命を伝えた。
しかし、慶喜はこれを拒否し、関白二条斉敬も、強く慶喜の帰府に反対する朝旨を伝えたので、江戸幕閣の企図は失敗に帰した。
このような空気のなかで五月、将軍が長州征伐を指揮するため大坂におもむく途中で、将軍暗殺の計画があり、その黒幕に慶喜がいるとうわさされた。
このことは、慶喜と将軍側近との暗闘がいかに深刻であったかを物語っている。
それが表面化したのが、将軍側近の老中阿部正外・松前崇広の追放である。
慶応元年九月、イギリス公使パークスをはじめ四国代表は、条約勅許、兵庫の早期開港および輸入税率軽減を要求し、軍艦で兵庫沖に渡来した。
阿部・松前の両老中は、兵庫開港を主張し、幕議はいったん、これに決定した。
ところが慶喜は、阿部・松前が勅許を得ないで兵庫開港を認めようとした責任を追及し、公家たちを扇動しておいて、朝旨をもって両老中を罷免するという離れわざをやってのけた。
朝旨で幕吏が罷免されるのは前例のないことだから、大坂城中は興奮にわきたち、将軍家茂は、抗議の意を表するため、将軍職を辞し慶喜を後任に推す上表を朝廷に提出させたまま、十月三日、東帰の途についた。
このとき、譜代大名・旗本らは慶喜の陰謀を憤激し、慶喜を襲撃する計画さえあったという。
慶喜は、両老中の追放という所期の目的を達したものの、それによってかもし出された事態があまりにも重大なのに驚いた。
彼は松平容保・同定敬らとともに将軍を伏見に待ちうけ、辞職・東帰を思いとどまるよう説得した結果、将軍もこれをいれて、四日京都に入った。
それからすぐに慶喜は参内して、朝議の開催を要請した。
四日夕刻から開かれた朝議に、慶喜は容保・定敬および老中小笠原長行を従えて出席した。
彼は、条約勅許を拒否して戦端が開かれる場合、わが国の敗北は必至で、全国は焦土と化し、皇位の安泰も保証できない、と脅迫的言辞を弄して、速やかに条約を勅許するよう要請した。
その間、有名の諸侯を召集の上、その意見によって、兵庫開港・条約勅許を決定すべきであるという、薩摩藩の策謀もあって、議事は難航した。
しかし結局、慶喜は賀陽宮の支持を得て天皇を威嚇し、一昼夜余に及ぶ朝議ののち、五日夜になって、条約勅許の獲得に成功したが、兵庫開港の勅許はついに得られなかった。
慶喜が将軍に代って、朝廷と交渉し条約勅許を獲得したことは、その名声を一段と高めた。
十月十日、将軍は慶喜に政務輔翼を命じた。
なおこのころ、朝廷では慶喜の官位を従二位大納言に進め、摂海防禦のため摂・河・泉三州を領せしめるよう幕府に命ずるとの内議があったが、彼はこれを辞退した。
幕府の役人たちは、このような賞典が慶喜の意向から出たものと疑惑していたので、もし賞典を受ければ、幕府の内紛が生じるのを恐れて辞退したもののようである。
長州藩処分方針についても、慶喜と大坂の幕閣との間には対立があった。
すでに慶応元年九月、将軍は長州再征の勅許を得ていたが、開戦には必ずしも自信がなかったので、在坂の幕閣は、長州藩三十六万九千石のうち十万石を削り、藩主毛利敬親を隠居させ、世子広封に相続させるという、比較的寛大な処分案を決定した。
ところが慶喜は「病根を断ち切る」ことが必要であるとの見地から、強硬論を展開した。
慶応二年(1866)一月、老中らがかの処分案を慶喜にはかると、慶喜はこれに対し、長州藩の全領地を没収するのが至当であるが、もし恩恵をほどこすとすれば、十五万石のみを与え、その余は削るべきである、と主張した。
結局、協議のすえ、削封は老中の意見に従って十万石とし、敬親父子を蟄居処分に付することは慶喜の意見をいれて、長州処分の方針がきまった。
慶喜の長州処分方針にも、彼の極度にタカ派的な姿勢がみられる。
しかし、非は幕府側にあるとしていた長州藩が、このような処分方針をのむはずはなく、ついに慶応二年六月、戦端が開かれた。
このとき、慶喜はみずから長州問題の衝に当るのを好まぬようにみえたから、はじめは強硬論を主張しながら、いま戦局の困難にさいして、冷淡な態度をとるのを非難するものが多かったという。
これがいままで慶喜のたどってきた道である。
これをみても、彼がけっしてお人よしの貴公子ではなく、むしろ権力慾にもえる陰謀家であり、また最も強硬な幕府権力の擁護者であることがわかるであろう。
このように彼が有能な人物であるだけに、彼に対する敵も多かった。
まず、前将軍の近臣のあいだには、当時もなお反慶喜の空気が濃厚であった。
ことに大奥では、わずか四歳の田安亀之助(のちの家達)を擁立しようとする意向が強かった。
慶喜は、このような空気を十分に察知していたから、京坂地方における幕府関係者の再三の懇請にもかかわらず、容易に権力の座にはつこうとしないジェスチュアを示したのである。
2 将軍の座へ top
強情と変り身の早さ
慶喜は、ひとたび徳川宗家相続を承諾すると、はやくもその翌日の七月二十八日には、すでに死去した将軍家茂の名で、病気危篤にいたれば慶喜に徳川家を相続させ、名代として長州に出陣させるむね、朝廷に申し出て、二十九日勅許を得ている。
停戦論には耳をかさず、あくまで長州藩を実力で屈伏させる意気ごみで、これを「大討込(おおうちこみ)」と称した。
そして慶喜みずから、その陣頭に立つ決意を示したのである。
その後ただちに軍政改革に手をつけた。
彼は、長州戦で敗北したのは幕府の軍制改革の立ちおくれにあることをよく知っていた。
そこでまず幕府直属の軍隊をすべて銃隊に編成しなおそうとした。これが長州攻撃軍の中核となり、諸藩の兵はただこれを応援するにとどめる計画だった。
諸藩の兵の頼むにたりないことが、さきの戦争でよくわかったからである。
彼は、幕府の諸役人のごときも、無用の人員を縮減し、お茶坊主まで銃隊に編成し、衣服飲食もいままで一橋家でやっているように倹約をすべきである、としていた。
そして慶喜自身、戦地へ持っていく荷物はわずかランドセル三個のみ、兵糧も士卒と同様にする覚悟であったという。
このように、なみなみならぬ決意をみせた「大討込」にさいしては、外国の軍艦まで買いあげ、幕府手持ちの艦船とあわせて海陸より併進し、かならず山口まで突入するつもりだ、と豪語していた。
みずからの出陣を前にして慶喜は、旗本一同を集めて
| 「毛利大膳父子は君父の仇である。このたび自分自身出馬する以上は、千騎が一騎になっても、山口城まで攻め入って勝敗を決する覚悟である。そのほうどももこの自分と同じ決心ならばついてこい。しかしその覚悟がないものはついてくるにはおよばぬ」 |
と激励演説をしたという。
彼の弁舌は定評のあるところである。
しかし実際のところは、せめて長州軍の攻撃で失った土地だけでも回復し、相続のはじめにあたって、徳川の威力を示そうとしていたもののようである。
この「大討込」政策は、長州に対する最も強硬な路線を推進しようとするものだから、必然的に薩摩藩とのするどい対立となる。
薩摩藩はさきの久光・茂久父子意見書の線にそい、反幕派の公家正親町三条実愛を動かし、朝議で長州との停戦を主張させたが、徹底した幕府の支持者、孝明天皇の強硬な反対にあって成功しない。
この間にあって松平慶永は、まず長州との停戦を主張し、将軍就任や長州の処分方策その他の重要政務は、すべて諸大名の会議によって決定すべきである、と説いた。
薩摩藩との対立をゆるめようとする主張である。
そのため勝海舟の登用を老中板倉にすすめたが、板倉は、「慶喜公には、勝海舟をことのほかおきらいである」と答えている。
慶永は、慶喜の宗家相続を熱心に勧告したが、その政治上の意見は全くちがっていたのである。
慶永はさきに述べたような見解から、慶喜の出陣に強く反対したが、慶喜に反省の色がないのをみて、八月初旬には国もとの福井に引きあげようとしていた。
一方慶喜はいよいよ「大討込」の方針を推進し、八月十二日が出発の日と定められた。
ところがその前日の十一日、九州方面の幕府軍根拠地小倉城が落ち、指揮官の老中小笠原長行も逃走したという、悪報がもたらされた。 |

軍服に身を固めた徳川慶喜
|
さすがの慶喜も、この絶望的な戦況に接しては、出陣中止を決意せざるをえなかったのである。
松平慶永は、これを「橋公(一橋公、慶喜のこと)の強情の大角(おおづめ)がたちまち折れた」と冷評している。
慶喜は、いったん主張したことは容易に曲げなかったことから、「強情」のニックネームをつけられていた。
しかし情勢の変化に対応しては、変わり身も早い。これなども、その一例である。
このようにして慶喜の要請で、将軍家茂の死から一ヵ月後の八月二十一日、その死を口実に、長州との戦争をしばらく見合わせるという朝廷の命令がくだったのである。
軍制の改革
慶喜は、長州藩との休戦を決定しても、それはたんに戦術上の一時的後退であった。
彼は、休戦の間に幕府の軍事力をととのえ、やがては雄藩を実力で圧倒できる態勢を確立しようとしたのである。
長州との休戦が正式にきまった八月の下旬、イギリス公使パークスは、幕府の軍制改革の進行をつぎのように報じている。
「幕府が長州との戦争で惨敗したのは、長州軍の大部分がライフル銃で装備され、その使用に熟練しているのに、幕府軍の大部分は、刀・槍・弓で装備されているにすぎなかったからである。
この敗北の教訓をいかして、幕府は、軍制の大改革に着手し、昔ながらの武器を火器にかえようと努力している。
新兵は、武士階級以外の下層身分のあいだで徴集されつつある。
常備軍の芽ばえは、直接幕府から給与を受ける少数の、よく訓練されている部隊においてのみでなく、旗本が幕府から提出を命じられた徴募兵の組織にもみられる。
この新たに組織された軍隊は、二十人ないし三十人の小隊単位でめいめいの旗本から差し出され、八十人の中隊、四百人の大隊、二大隊からなる一連隊に編成される。
そしてその大部分が、ライフル銃またはマスケット銃で武装されている。」 |
そしてこの新しい陸軍組織の熱心な提唱者は慶喜自身である、という。
ここに述べられている軍制改革は、慶喜の徳川宗家相続直後のもので、二百年前の慶安二年(1649)にきめられた軍役人数割りを廃止し、新たに一定の石高につき一定人数の兵卒を差し出させることに改めたことをさしている。
この軍制改革こそ、幕藩体制に見合う軍制を廃止し、これにかわって雇い兵よりなる常備軍で絶対主義的軍制を創設するという大きな意味をもつものである。
しかしこの軍制改革でも、まだ統一を欠いていたので、これらの新たに徴集される兵卒を一つの組織に統一する必要が痛感された。
そこで慶応二年九月、幕府の軍制改革にあたる当局は、統一的な常備軍を編成するため、旗本が個別的に軍役をつとめる制度をやめて、その軍役をすべて金納とし、兵卒は直接幕府から雇い入れることとし、当分、三千石以下の旗本の分だけを金納としたい、と幕閣に上申した。
そして翌慶応三年(1867)二月から兵卒を直接幕府でかかえることにした。
親仏政策の強化
さきの軍制改革と関連して、慶応二年八月二十七日、慶喜はフランス公使ロッシュに親書をよせ、幕府の基礎を強化するため、みずから率先して軍制を改革するに決定したことを告げ、歩・騎・砲三兵の訓練はもとより、軍艦その他海軍用の器材および大小砲の購入について、周旋を要請した。
このように慶喜にとって権力を確立する前提になるのは、親仏政策の強化である。
それは、財政経済上の問題から始まった。
これよりさき長州戦争開始の直前、フランスの経済使節クウレが渡来した。
クウレは渡来このかた、事実上の蔵相ともいうべき勘定奉行小栗忠順との間に交渉をつづけてきたが、長州との休戦の勅命が出る前日の八月二十日、六百万ドルの借款契約が成立した。
そしてこの借款の大部分は、兵器・軍需品・軍艦の購入費および横須賀製鉄所の建設費という軍事的用途にあてられるはずであった。
そうすると、慶喜が企図しつつある軍事上の改革は、きわめて大きくこの借款に依存するということができよう。
借款契約の成立から一ヵ月をへて、「フランスの会社と下請け関係になる日本の商業・航海大会社」の組織についても、小栗とクウレとの間に契約が成立した。
「フランスの会社」というのは、ソシエテトジェネラールの子会社として創立を企図される「フランス輸出入会社」のことである。
そうすると「日本の通商・航海大会社」は事実上、ソシエテトジェネラールの支配のもとにおかれることになるわけである。
借款が成立して、その資金のプールから兵器・軍需品が供与されることになると、代償としてフランスが日本に求めるのは、とくに生糸貿易の独占である。そうした対日貿易独占のための機構が「商業・航海大会社」であるといえよう。
「商業・航海大会社」の組織契約が成立すると、小栗は慶喜白身の要求により、その契約を説明するため、ただちに大坂に向ったという。
慶喜がいかにフランスとの経済関係の強化に大きな関心をもっていたかをうかがうことができる。
大名会議召集の形式
慶喜は、いちおう将軍就任とは切り離して、徳川宗家の相続を受諾したものの、たちまち権勢欲に飢える人物の正体を暴露し、早くも八月中旬には将軍になろうとする意向をもらしていた。
しかし当面の問題は、時局収拾のための大名会議をどういう形式で召集するかということであった。
慶喜は朝命を奉じながら、あくまで自分が召集にあたるという形式をとろうとした。
これに対して薩摩藩などの倒幕派は、直接大名に朝命を発して召集すべきだとして、慶喜と対立したのである。
しかし朝廷内では「政治には不慣れだから、大名会議が開催されても、衆議の判定はできない」という自信のなさが正直なところであった。
だから直接朝命で召集されれば、会議の主導権は倒幕派に渡ってしまうことになるわけである。
結局、この対立は、朝命による召集でなければ、諸大名は上京しないであるうとの顧慮から、さすがの慶喜も、初志を曲げ、朝命による召集という形式をとらなければならなくなった。
こうして九月七日、二十四藩への召集は、直接朝命で伝達する形式がとられた。
しかし、そのなかに「決議の趣は中納言(慶喜−著者)をもって奏聞あるべし」という一句がそえられたのは、最も注目されるところである。
これは、原市之進が「この文句を入れなければ、幕威はいよいよ地におちるであろう」と、関白二条斉敬にせまった結果、入れられることになったのだという。
原は、もと水戸藩士であったが、慶喜の宗家相続後、一橋付用人雇から目付に昇進し、慶喜の近臣としてさかんに活動していた。
とにかく原の努力によって加えられたこの文句によって、慶喜は会議を主宰できることになるわけである。
それとともに召集されるべき二十四人の大名の人選も、慶喜によってきめられた。
このように大名会議の召集にさいして、朝命によって召集するという形式の面では譲歩しながら、その運営の主導権を確保しようとしている。
しかも慶喜は、会議指導の能力と弁舌の才においては定評があったので、会議の主宰がひとたび自己の手にゆだねられれば、これをみずからの欲する方向にひきずっていく満々たる自信をもっていたのであろう。
召集の朝命が諸藩にくだった翌日の九月八日、早くも薩摩藩士大久保一蔵(利通)は、慶喜の心底をみぬき、
| 「慶喜はいろいろといつわりの術策をめぐらし、ほんとうに朝命で諸藩を召集することはなんとか拒もうとしているようなしだいである。そこで諸藩の参会までは慶喜の将軍就任を食いとめておき、この絶好の機会を利用して、諸藩の合議政治へもっていき、幕府の権力を破壊すべきである」 |
と西郷吉之助(隆盛)にあてて書いた。
当時、京都における倒幕派の中心人物として活動していたのは、じつに大久保一蔵である。
彼は、薩摩藩がきたるべき諸藩会議の主導権をにぎることによって、倒幕を企てようとしていたのである。
このように当面の問題は同じく諸藩会議であっても、それによせる期待は、慶喜と大久保とでは正反対であった。
将軍宣下
慶喜は、諸大名召集の手続きをとると同時に、九月になると、除服参内を企てつつあった。
その目的は、一つには、八月三十日の「列参」事件に関係した反幕派の公家を処分して、朝廷内の反幕勢力を除き去ること、もう一つは、参内のさい、将軍同様の待遇を受けることにより、早急に将軍就任の道を切り開くことである。
慶喜のこの意向を受けて運動したのは、かの原市之進である。
これに対抗した大久保一蔵らもまた、倒幕派に理解のある山階宮や島津家と関係の深い近衛忠房らに働きかけて、慶喜の除服参内をはばもうと必死の運動を展開した。
原と大久保との対決である。原は
「長州は薩摩のように陰険ではない。
薩摩は、かつては会津と結んで長州を退けたが、のち長州征伐のころから長州を援助するという変わりかたである。
そのほか密貿易をやるなど、その陰険さはとてもいちいちあげることができないほどである」
と語ったという。
慶喜を将軍の座につかせるため、まず排除しなければならないのは薩摩藩の策動である。
結局、原の運動が勝利をおさめて、九月二十六日、慶喜に除服出仕の宣旨がくだった。
この間、松平慶永は、なおも幕府と薩摩藩のあいだを融和させようとする努力をつづけ、慶喜に勝海舟や大久保忠寛(一翁=いちおう)の登用を説くが、慶喜はいっこう耳を傾けない。
慶永は業をにやして、十月一日ついに帰藩の途についてしまい、翌年四月、四藩会議に列席するまで、国もとに引っこんでいた。
一方召集を受けた諸大名も慶喜の真意と情勢の不安とに二の足をふみ、慶応二年十月はじめまでに上京した大名は、わずかに五人で、大名会議はついに流れてしまった。
十月十五日、慶喜に対して参内の朝命があり、翌十六日慶喜は、京都守護職・所司代・老中をはじめ数百人の兵をひきつれて堂々と参内した。宮中で受けた待遇は将軍と同じであった。
慶喜に参内の朝命があった日、とくに朝廷から「何れより彼是申し立て候とも、断然と仰出され候間、採用すべからず」との沙汰があった。
「彼是(かれこれ)申し立て」というのは、いうまでもなく薩摩藩の策動をさしている。
慶喜の参内は、薩摩藩の激しい反対運動と対決する姿勢で強行されたのである。
ついで十月二十七日には、中御門経之・大原重徳ら「列参」事件に関係した公家が処罰され、その同調者と目された山階宮および正親町三条も処分された。
これも、原市之進が慶喜の意向をもって朝廷を動かした結果であると想像される。
八月の「列参」公家の行動に対して孝明天皇が激怨したにもかかわらず、いままでなんの沙汰もなかったのに、ここにいたって処分が断行されたのは、参内以来、慶喜の勢力が朝廷に進出してきたことの現れにほかならない。
こうして朝廷は、孝明天皇を中心とする佐幕勢力で固められ、慶喜の将軍就任をはばむものは、もはや何もなくなった。
そして天皇みずから議奏・伝奏両役を召して将軍宣下の意向を伝え、十二月五日にいたって、ついに将軍宣下が行われたのである。
3 内政の改革 top
ロッシュへの諮問
親仏政策を強めた慶喜は、政策についてしばしばロッシュの意見を聞いた。
まず将軍に就任する直前の慶応二年十一月、二人の外国奉行をロッシュのもとにつかわし、政策全般について諮問した。
そのさいロッシュは、国政改革の参考に供するため、欧州の制度の大略をしたためて提出したというが、その内容はわからない。
外国奉行との会見後、ロッシュは慶喜について、「精力的かつ有能で、契約を尊重し、日本国民を進歩の途へ進ませようとする決意をもち、自尊心や狂信が少しもない」と、べたぼめをしている。
それから将軍に就任すると、慶応三年(1867)一月下旬、慶喜は一人の外国奉行をロッシュのもとに派遣し、国家を改造しようとする目的で、前回よりも広く行政・軍事・財政・経済の諸問題について諮問した。
とくにそのなかに、政治改革の核心として「各国封建の旧制を革(あらため)し仕法」があるのは注目される。
これに対してロッシュはまず、
(一)職務に応ずる恒久的官僚機構の確立、
(二)陸海常備軍の編成、
(三)借款を資金とする幣制改革および資源の開発、
(四)フランス輸出入会社と日本における商人組合との協力、
について意見を述べた。
当時ロッシュは、日本の政治体制を十三世紀のフランスにおける封建制度に比し、将軍の臣下たる大領主は、フランス国王のそれのように、君主の強さに応じ、領主の操縦がむずかしくなったりたやすくなったりする、としている。 |

フランス公使ロッシュ
|
このような状態のもとで、身体・精神ともに弱々しい若年の前将軍家茂のもとでは、大名の離反を生じたのにひきかえ、新将軍慶喜は「有能かつ精力的な人物、外国人の友」であるとして、その君臨による日本の安定に大きな期待をかけた。
そしてロッシュは、日本が対外関係発生以来、変革かまたは衰亡かの岐路に立っているとみなした。
いま日本が急速な変革を必要とするとき、日本人を開化させる最善の手段は、古い封建制の名残や諸大名の怨恨を強めることではなく、日本に適応する改革を吹きこみ、それを支持すること、およびヨーロッパ人が所有する文明の利器を日本人にもたせることである、と彼はいう。
ロッシュの改革意見
この見地に立って、ロッシュは、理想的君主と評価する慶喜に全面的改革の構想をぶちまけようとするのである。
こうして彼は、したしく将軍の諮問に答えるため大坂におもむいた。
そして二月六・七両日に将軍と会見、意見を開陳している。
それは、十三世紀のフランスに比すべき封建制度のもとにある日本を、絶対主義に転換させる方法であった。
まずロッシュは、外様大藩の勢力をけずることの必要性を強調し、政府が強大な軍備をもって、兵権を中央政府に集中すべきことを力説した。
そして長州藩のごときは、軍備の充実を待って、一挙に討ち滅ぼすべきである、とした。
これに対し譜代大名は、旗本にならって軍役を金納させ、譜代大名の家臣および幕臣のうち、有能なものは政府の兵に差出させ、無能なものは農商に帰させるべきである、と述べている。
それは、幕府による廃藩のコースである。また朝廷については、天皇および公家が完全に現実の政治からたちきられ、隠謀家との接近を阻止するよう、監視のもとにおかれることを勧告した。
つぎにロッシュは、官僚機構の近代化について「日本では役職が家格と個人の功績に応して与えられ、仕事の専門に応じて一定の事務を割りあてられる、恒久的な職員の階層をもたない」ことを指摘し、「行政事務をたくみに処理・執行するためには、固定的な職掌とともにその職掌に応ずる責任をもつ専門家を必要とする」と説いた。
それにはまずいままで老中が固定した職務を分担することがなかったことの代りに、「大君の代理者である大老を首班とする六人の老中から構成され、おのおの個別の省(内務・外務・陸軍・海軍・財政農商土木・司法教育宗教)を担当する」内閣制度の設立を提案している。
また彼は、各省には一人の老中のもとに、若年寄二人をおき、若年寄は大名に限らず、旗本の人材をも登用するよう助言した。
さらに財政についてロッシュは、陸海軍建設のための経費の不足は、さきに成立した借款に依存すべきことを説いた。
そして幕府が年貢として収める米はすべて売払い、家来への俸禄は貨幣で渡すことにし、俸禄を差引いた残りの収入を貨幣で貯えて諸経費にあてるべきである、とした。
このように彼は、蔵相が中心になり、将軍の承認を得て各省へ割当てるべき経費をきめる近代的予算編成の方法を説いている。
このほかロッシュは、歳入を増加させるため、商税を中心とする新税の創設を勧め、外国の機械や技術を採用して産業を開発することや、馬車・鉄道の敷設で全国運輸の便を開くことをも教示した。
改革の実施
以上のロッシュの意見は「徳川絶対主義」の建設案で、慶喜の内政改革もおおむね、ロッシュの進言にそって行われた。
まず老中の職務分担については、すでに慶応二年十二月末に、老中格稲葉正巳(まさみ)が海軍総裁に、老中格松平(大給)乗謨(のりたか)が陸軍総裁に、それぞれ任命されていたが、慶応三年五月にいたり、老中稲葉正邦が国内事務総裁に、松平(松井)康英が会計総裁に、ついで六月、小笠原長行が外国事務総裁に、それぞれ任命された。
このほか、首席老中板倉勝静が無任所で首相格であった。
以上のような老中の各総裁兼務によって、御用部屋はようやく内閣のような体裁を備えてきた。
このほか注目されるのは、陸軍奉行・海軍奉行・外国総奉行・会計奉行を若年寄または若年寄並(なみ)が兼務していることである。
これは、総裁たる老中のもとで次官としての役割を勤めさせようとしたものであろう。
従来、若年寄はもっぱら大名から任用されたが、慶応三年になると、旗本出身の人材がぞくぞく、若年寄格または若年寄並に登用された。これも、ロッシュの助言をいれたもののようである。
老中は、慶喜の支配のもとでは、奉行級の人材にくらべて、かならずしも華々しい存在ではなかった。
老中のうち、首相の板倉と外相の小笠原は、すでに家茂の治世に慶喜の推薦によって老中となった人物でもあり、最も有力な存在であった。
板倉がむしろ温厚の人物であったらしいのに、小笠原はするどい才気があり、老中のうち第一の人物であったとみられる。
海相の稲葉正巳と陸相の松平乗謨は、ともに一万石級の小大名で、老中になれる家柄ではなかったが、その能力を買われて老中格に登用されたのである。
老中にくらべて注目されるのは、旗本出身の人材で、若年寄格または若年寄並に登用された人々である。
若年寄格になったものには、大目付兼外国奉行永井尚志・外国奉行向山一履、若年寄並になったものには、陸軍奉行並浅野氏祐・外国奉行平山敬忠・大目付川勝広運・陸軍奉行並竹中重固・外国総奉行塚原昌義がある。
これらの人々は、大名出身の老中にもまして、慶喜の側近にあって、内政・外交の各部面にわたり献策の任にあたった実力者である。
このほか、事実上の蔵相としての勘定奉行小栗忠順がある。
このように旗本出身の奉行クラス人材と直結していたところに、慶喜の政治の特質があるといえよう。
さらに当時幕府では、総裁たる老中のもとに、次官として一人もしくは二人の若年寄をおき、関係諸奉行をこれに配属させる行政部門(局)の編成を計画していた。
もしこれが実現すれば、絶対主義的官僚機構の成立をみることになったであろう。
こうなると、さきに計画された常備軍の編成とあいまって、絶対主義権力の特徴が具備されることになるわけである。
慶喜のもとで、経済上の改革を指導したのは、指定奉行の小栗忠順(おぐり・ただまさ)である。
まず慶応二年十二月、江戸市中融通貸付金が実施された。
これは、幕府の勘定所が関税収入の一部を幕府の為替御用をつとめる三井に貸下げ、これを基金として、さらに三井が一般から集めた預金をも加え、それを江戸の問屋商人に貸しつけるというものである。
これは、明治初期の為替会社の先駆をなす金融機関として注目される。
つぎに兵庫開港を前にして、慶応三年四月、小栗をはじめとする勘定奉行は、兵庫に商社を設立することを建議した。
兵庫開港場の経営には莫大な経費を要するので、大坂の大きな商人に商社を結ばせて、貿易をやらせ、それとともに関税の保管に当らせ、それを基金に紙幣の発行権を与え、その代りに開港場の経営費を出させようとするものである。
それは、商社であることのほかに、発券銀行の機能をもっものであり、明治初期の通商会社と為替会社の機能を兼ね備えたものであるといえよう。
この意見に従って、この年六月、幕府は鴻池(こうのいけ)善右衛門らに商社を結成させた。
また同じころ、横浜では三井を通じて横浜の有力な商人に荷物為替組合を結ばせ、三井に貸下げた資金を融通しようとした。
このように小栗は、貿易からあがる関税収入に目をつけ、その融通を通じて商人の組織化をはかった。
こうした商人の組織が「日本の商業・航海大会社」を形成するものと思う。
小栗に指導される幕府最末期の経済政策は、フランスへの依存という点を除けば、初期明治政府の経済政策のモデルをなしている。
以上のような慶喜の改革は、明らかに幕府権力の絶対主義化をめざす。
さきに幕府は「徳川絶対主義」の路線を推進しようとして、フランスの援助をたよりに、あまりにも早く長州再征を強行し、大失敗を演じた。
慶喜はこの大失敗にかんがみ、薩長と軍事的に対決するまえに、まず内政の改革を企てたのである。
4 外交の攻勢 top
各国公使謁見の政治的意図
次々に幕府強化策を進める慶喜は、将軍の座につこうとしていたころ、その一方で外国公使の招請を意図していた。
全国統治の権力を掌握しているのは徳川政権であることを外国に示すためである。
慶応二年十一月、外国奉行は、サトウが『英国策論』で、日本を進歩させるには、諸藩の連合政府をつくり、従来の幕府にかわるべきである、と述べているのをとりあげる。
そしてそんな方向で諸藩が自立化する傾向をくいとめ、幕府が全国統一の権力をにぎり、「中興維新」の構想を示すため、各国公使を引見すべきである、と幕閣に上申した。
あたかもこれと同じ時点に、福沢諭吉は「大名同盟の説」を退け、「大君のモナルキ」でなくては、日本の「文明開化は進」まない、と書いている。
「中興維新」というのは、福沢のいう「大君のモナルキ」、すなわち、徳川政権を絶対主義化しようとする政治路線である。
そうすると各国公使謁見の企図は、薩摩藩などの動きと対決しようとする慶喜の政治的路線のなかで打ち出されたことがわかる。
この方針に従って、慶喜がまだ正式に将軍に任命されていない十二月二日、早くも幕府は、謁見の式を挙行するので大坂に来るよう、イギリス・フランス・アメリカ・オランダ四国代表に招待状を発した。
幕府側としては、年末もしくは年始に謁見を挙行する意向だったらしい。
ところが、イギリス公使パークスは、たんに幕府側の招請に応じては、一方的に新将軍の権力の増大を助けるだけになるので、この機会に、兵庫などを条約の規定どおりの期日(慶応三年十二月七日)に開くという保証を取りつけるべきである、と考えた。
これが、幕府側の弱点をついた形となった。幕府はまだ兵庫開港の勅許を得ていなかったからだ。
そこで幕府は急に方針を変えて、慶応三年一月十日、孝明天皇の死去を理由に、しばらく謁見の期日を延期するむね、四国代表に通告した。
その後パークスは、大坂におもむいて、兵庫などの開港について協議したい、と申し入れてきた。
幕府側としては、四国代表との謁見以前に兵庫開港の勅許を得ておく必要にせまられた。
しかし、朝廷では元来京都に近い兵庫の開港を好まなかった。
そのうえ幕府は、薩摩藩の策動にはばまれて、なかなか勅許を得ることができなかった。 |
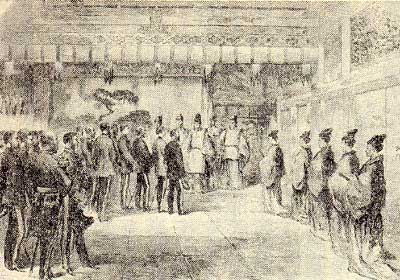
パークスを謁見する徳川慶喜
絵入りロンドンニュース(神奈川県立博物館蔵)
|
当時薩摩藩は、幕府が勅許のない兵庫開港をパークスからせきたてられ窮境におちいるのにつけこんで、あわよくば幕府を倒そうとたくらんでいたので、幕府側としては、どうしても兵庫開港の決意を表明しなければならなかったのである。
ついに幕府は、勅許がないにもかかわらず、兵庫をはじめ両港(兵庫・新潟)・両都(江戸・大坂)を規定の期日に開く、とパークスに回答した。
そして慶喜は、四国代表と謁見のため京都から大坂に向った。
四国代表を謁見
謁見は、慶応三年三月二十八日(イギリス公使・フランス公使・オランダ総領事)および四月一日(アメリカ公使)の二日に分けて大坂城中で行われた。
この謁見は、完全にヨーロッパの宮廷の儀式にならったものである。
すなわち、各国公使があいさつを述べたとき、将軍は直立してこれを受け、かつ答辞を述べたのであった。
謁見にさきだって、各国代表とのあいだには「内謁見」(半公式会見)が行われた。
いま各国公使との謁見のうち最も注目に値するパークスとのそれについて述べよう。
まず内謁見にさいして慶喜は、条約を厳守し外国との友好関係を増進する決意を述べ、遣英留学生の受入れや海軍伝習教官の派遣についてイギリスの示した好意に感謝し、さらに西洋の知識の吸収や近代的企業の振興に大きな熱意を示した。
会談を終わって晩餐会に移ったが、これも完全な洋式で、フランス人が調理にあたったという。
席上、慶喜とパークスとのあいだで乾杯の交換があり、晩餐後は別室でコーヒーが出された。
ハイカラ将軍の面目躍如たるものがある。
このようにして「内謁見」は、きわめてなごやかな空気のうちに終わり、パークスに大きな好印象を与えたのである。
さらに謁見の式では、ほかの公使がみな将軍に対していままでのとおリマジェスティー(陛下)の敬称をよせたにもかかわらず、パークスだけはひとり、ハイネス(殿下)とよんだ。
また彼はほかの公使とちがって将軍に信任状を提出しなかった。
これは、将軍は他国の帝王に比すべき日本の君主ではないという、彼の理論をはじめて公式に実行に移したものとして注目される。
将軍の敬称の格下げに対して、幕府側はその席上では公然と異議をとなえなかったとはいえ、内心は、はなはだ不満であった。
この年十一月、駐英公使格の外国奉行向山一履は、イギリス外相スタンリーと会見し、条約面にマジェスティーとあるのをさして、この敬称の格下げに抗議している。
対英関係の好転
しかしこの敬称問題を除けば、今度の内謁見および謁見により、全体として対英関係をいちじるしく改善したことは、おおうべくもない事実である。
内謁見ののち、パークスはロッシュにあてだ私信で、「あの大坂城のすばらしさも、慶喜の個人的素質が私の心のなかにひきおこしたすばらしさにおよびはしなかった」と、慶喜に最上級の賛辞をささげている。
ついで彼は、外相スタンリーにあてた報告でも「大君(慶喜-著者)の対外友好関係を増進しようとする意向ばかりでなく、すぐれた能力と人を引きっけるような行動や風貌についても、すてきな印象を得た」と語っている。
またパークスは、慶喜の若さと能力を高く評価した。
古い偏見や伝統にとらわれることなく、環境の変化に適応できる人物であり、対外関係の改善はもとより、国内問題の処理も、慶喜によっていちだんと好転されるだろう、と期待している。
パークスは慶喜の徳川宗家相続当時、国内の対立関係を調整する担い手として期待していたのに、彼の強引な将軍就任が国内対立を深めるのをみて、一時、失望していたかっての期待が、いまやこの会見の好印象によって、ふたたびよみがえってきたのである。
謁見外交の成功は、その陰の演出者ともいうべきロッシュを得意がらせた。
慶喜との会見の好印象を伝えたパークスの私信に接したとき、ロッシュの得意はまさに絶頂に達した。
彼は、いまやパークスの心中に引き起した変化が完全であることを認め、「何という驚くべき変化を私は認めなければならないことか。何という有難い影響をフランスは及ぼしていることか」と、全く有頂天になっている。
パークスは、慶喜が日本の君まであることを公然と否認したが、それは、慶喜の日本政界における重要な地位を否認したことを意味しない。
かえって彼は、慶喜が日本国内関係の調整に大きな役割を演じるであろうことを期待したのである。
各国代表の謁見をめぐる外交で、慶喜は大きな成功をおさめたということができる。
まず幕閣は勅許問題をあとまわしにしながら、兵庫などを規定の期日に開くことを外国に言明した。
この言明の率直さと慶喜自身のあいそのよい応対は、パークスにきわめてよい印象を与え、対英関係をいちじるしく好転させた。
これは薩摩藩のもくろみに肩すかしをくわせることになった。
薩摩藩は、幕府が兵庫開港の言明を外国に与えることはできまい、そのときこそ、パークスが直接朝廷に対して条約の締結を提議するであろう、とみていた。
この機会を利用して薩摩藩は、内外あい呼応して、幕府を絶体絶命の窮地に追いつめようともくろんでいたのである。
兵庫開港の言明と対英関係の改善は、薩摩藩の以上の期待を水の泡としてしまった。
四藩会議
慶応三年のはじめから、小松帯刀・西郷吉之助・大久保一蔵ら在京の薩摩藩士は、パークスが天皇との条約締結を提議するのを期待し、これに応じて政権を幕府から雄藩連合に移そうと企てた。
そのため彼らは薩摩・越前・土佐・宇和島四藩の実権者(島津久光・松平慶永・山内豊信・伊達宗城)の上京を勧誘した。
その結果、四藩実権者がみな京都に集まったのは五月になってからであった。
このとき幕府側はとっくに、兵庫開港を外国側に言明していたので、薩摩藩士たちが企図していた四藩会議のタイミングは、ひどくずれてしまった。
薩摩藩士が四藩会議で企図していたのは、
(一)兵庫開港を朝廷と外国との条約できめること、
(二)長州藩の罪を取消すこと、
(三)将軍が勅許を得ずに、兵庫開港を外国に言明した責任を追及して、将軍職を奪うこと、
で、そのうち(三)が最も重要な点であった。
このような戦術を実行するため、いわゆる四藩会議が開かれる。
五月中旬から四藩実権者は二条城で慶喜と会見した。この会見における重要議題は、兵庫開港と長州処分である。
四藩側、とくに久光が長州処分の先決を主張したのに対し、慶喜は兵庫開港の先決を主張し、意見が対立した。
兵庫開港問題で幕府を追いつめようとする術策をとっている薩摩藩としては、兵庫開港の決定を保留しておきながら、長州藩の罪を取消し、場合によっては同藩をもひきこんで、内政の変革へもっていこうと企てた。
そこで幕府としてはどうしても、兵庫開港を先決して、薩摩藩の術策を封じこめる必要があったのである。
四藩会議で、薩摩藩士たちの強硬な意見を慶喜にたたきつける任務を負わされているのは久光である。
しかし彼は慶喜の面前に出ると、とても薩摩藩士の強硬な意見など主張できない。
「弁論の立つ人でもなく、じつはお人よしなのだが、野心家の家来にそそのかされているのだ」と幕府側に見くびられる始末であった。
これに対して幕府側では、慶喜みずから応対の矢面に立ち、兵庫開港問題の先決を主張した。
しかも四藩側では、山内豊信が最も薩摩藩の動きに反発し、慶永もこれに傾き、久光およびこれに同調する宗城との開に、とかく姿勢の一致を欠いた。
結局五月二十一日、久光・慶永・宗城と板倉勝静・稲葉正邦両老中とが協議した結果、
(一)まず長州を寛大な処分に付し、のち兵庫開港に及ぶこと、
(二)兵庫開港は朝命で認めること、を確認して決着がついた。
これで長州処分を先決するという四藩側の主張は貫徹されたかのようにみえるが、それは原則的だけそうなので、これをどう実行するかは幕府側にゆだねられた。
幕府は、ただ形式的に長州処分を先決し、実質的には両問題の同時解決の線を守るうとしていた。
このようにして、はじめ西郷・大久保ら薩摩藩士が四藩会議によせていた期待もむなしく、この会議は終末を告げた。
このことは、薩摩藩の倒幕派が藩主級の人物を通して、非武力的手段で幕府を倒そうとする場合、それがつき当る限界を示している。
兵庫開港勅許獲得
慶喜は、四藩会議解体の好機をつかんで、すばやく兵庫問港勅許を獲得するための行動を開始した。
五月二十三日、慶喜は、板倉・稲葉両老中および所司代松平定敬を従えて宮中に乗りこみ、朝議は午後八時からはじまった。
彼は、いく晩徹夜しても勅許を得るまでは退出しない、と強硬な決意を表明し、流れるような能弁で演説し、それが終ると書見するという、大胆不敵さであったという。
中御門経之・大原重徳らの公家が、強い兵庫開港反対論を吐くと、慶喜は、「そんな『日本書紀』や『古事記』から抜け出したような意見では、すこしもいまの時勢にあわない」と軽くあしらい、一人でよく八方にあたるという奮闘ぶりであった。
このようにして議論に時を移すうちに一昼夜を経過し、二十四日の夕刻を迎えた。
一同が徹夜の会議で「精神恍惚」の状態となったとき、慶喜は、賀陽宮その他佐幕派の公家と結び、長州を寛大な処分に付すること、および兵庫の開港を勅許すること、の二つの御沙汰書を強引に獲得したのであった。
ときに午後八時、朝議が開始されてからまさに一昼夜である。
こうして有志の公家たちが悲憤慨嘆するなかを、慶喜は意気揚々と二条城へ帰ったという。
この一昼夜の朝議は、全く慶喜の独壇場であった。
彼は、「天下の政権御委任の将軍」として思う存分に朝議をひきずっていった。
しかもここで勝ち得られた勝利は、彼のいままでに得たいかなる勝利よりも大きかった。
兵庫開港問題は、一昨年九月このかた薩摩藩が幕府打倒につかおうとしていたきめ手だったからである。
慶喜の成功を聞いたとき、ロッシュは「上様(慶喜)の果断は凡慮の及ぶところではない」と手を打って感嘆したという。
この年二月大坂城で慶喜と会見のさい、ロッシュは、長州をしばらく手なづけておき、軍備の充実を待って討ち亡ぼす策を説き、また諸侯の隠謀に対抗して、兵庫を期限どおりに開港するよう勧告していた。
ロッシュの教えをそのまま、いま慶喜が実行したからである。
ロッシュは、この慶喜の行動によって、政局がいよいよ安定することを期待していたのであった。
国際情勢に暗雲
しかし、兵庫開港の勅許という大きな成功にもかかわらず、国際情勢は幕府側に悪くなってきた。
ロッシュの支持者であった外相ドルーアン・ドゥ・リュイスは、家茂死去のころ辞職し、ドゥ・ムスティエがこれに代った。
慶喜が四国代表を謁見した直後、新外相はロッシュに詰問的訓令を発し、露骨な幕府支持を戒めるとともに、幕府との関係を保ちつつ、諸大名にも接近するパークスの政策の賢明なことを推奨した。
この訓令に接すると、ロッシュは、外相の見解に対して、きわめて激しい口調で反論を加え、自己の行動の正しさを弁明した。
それは六月中旬のことである。
慶喜の頼りとするロッシュが新外相によって解任されることは、いまや必至となった。
もう一つ困ったことは、いったん契約が成立した借款の行き悩みである。この状態を打開する使命をおびて、慶応三年六月、外国奉行栗本鯤(安芸守=明治期はジャーナリスト)がフランスに派遣された。
彼は、蝦夷産物の開発権を借款の担保に提供して、いろいろ運動を試みたが、ついに成功をみるにいたらなかった。 |

外国奉行栗本鯤
『大日本名家肖像集』/
国立国会図書館蔵
|
ただ慶応三年十月ごろになって、約三十万ドルの武器・軍需品が幕府の手に入っただけである。
5 大政奉還 top
慶喜の真意
慶喜が兵庫開港の勅許を闘いとったことは、薩摩藩の武力によらない倒幕戦術を破産させた。
そこでこれから薩摩藩は長州藩との軍事的提携を強めつつ、「挙兵討幕」へと向かうことになる。
こうして幕府と薩長との軍事的激突が必至となるかにみえたとき、土佐藩が調停を買って出た。
これが前土佐藩主山内豊信による大政奉還の建白である。
しかし大政奉還の建白は、幕府にとって寝耳に水だったのではない。
すでに慶応三年七月三日帰藩の途につくまえから、後藤象二郎は大政奉還を慶喜の側近永井尚志に入説しており、九月四日ふたたび入京してのちも大政奉還の必要を永井に力説したのである。
永井はこれに同意し、九月二十日、すみやかに建白書を出すよう、後藤にすすめたという。
こういうわけで、土佐藩からの建白提出以前に、幕府内では、慶喜を中心にして、板倉・永井らのあたりで、大政奉還にいかに対処するかはしゅうぶん考慮されていたはずである。
だから土佐藩の建白が出ると、慶喜はこれを受けとめて、慶応三年十月十四日、朝廷に大政奉還の上表を提出したのである。
上表文は永井の起草するところであった。
永井がよほど大政奉還と深い関係のあったことは、これでも推測できるであろう。
永井にくらべると、板倉はまだ古い幕政に未練があったといわれる。
一般に慶喜の大政奉還は、土佐藩の公議政体論を受入れたものとされているが、はたしてそうであろうか。
大政奉還の翌十五日、慶喜参加のもとに開かれた朝議で、すぐ大政奉還を朝廷に承認させようとする薩摩・土佐の策謀に対し、幕府側は武力行使を進言し、佐幕派の公家にてこ入れをしようとはかった。
しかし都下に動乱の起こるのを恐れて、公家たちが反対したので、結局、朝議は大政奉還をただちに承認することとなった。
この日の慶喜の参内が正午で、その退出が翌日午前二時であることからみても、朝議が大きな波乱を含んでいたことを想像させる。
慶喜が期待しているのは大政奉還の即時承認ではなく、大政の委任であったろう。
大政の委任により、彼自身のイニシアティヴのもとに、諸侯会議を招集し、新しい政治形態の合法化を企図したものと思う。
ここで慶喜が大政奉還によせる政治的意図を知る手掛りとなるものに、かの上表のなかにある「朝権を一途に出で」させるため大政奉還をするという文句がある。
徳川宗家相続以来慶喜の念じていたことは、たんなる将軍の空名よりも実権を一身に掌握することであった。
彼は将軍就任直前、「日本は分裂するには、あまりにも小さすぎる。一つの政府のもとで統一されるときにのみ、日本は栄えることができる。このような政府を引き受けることを欲する」との意向をもらしていたという。
しかし、諸藩士が公家と結びつくことによって、朝権が一途に出ず、朝廷の命令がひんぱんに変動するので、彼のこの念願を妨げていた。
大政奉還から四ヵ月近く前の六月二十一日、板倉は、政令が「朝廷・幕府の二途より出」るのを防止するため、将軍が摂政を兼ねるという「妙案」をもって、松平慶永に周旋を依頼したことがある。
そのとき板倉は、これは将軍の意向ではなく、私と永井と二人で相談した案である、といっているが、こんな重大なことを板倉が勝手にやるはずはないから、慶喜の内意を受けての行動とみてよいであろう。
この日には後藤も京都にいたはずだから、後藤の大政奉還論はすでに永井に知られていたとみてもよい。
そうすると板倉・永井の案は、土佐藩の大政奉還論に対する幕府側の対案とも考えられよう。
こんなところからすると、大政奉還の上表に「朝権を一途に出で」させることの必要を強調しているのは、この構想の連続とみられるであろう。
かの板倉が大政奉還を「土佐藩に迫られてよんどころなくやったのではなく、かねて政権が一途に出ないでは国内が治まらないと考えていたところ、たまたま土佐藩の建白があったのを好機にして、平生、十分に引きしぼっていた強弓を放ったのである」と評しているのは、その証拠である。
西周助の憲法案
大政奉還後における慶喜の政治構想としては、この年十一月下旬、西周助が起草した「制度腹稿」(憲法案)があげられる。
ちなみに西の憲法案は平山敬忠旧蔵の書類のなかから発見されたもので平山の朱筆が加えられている。
こうしたことから平山が慶喜の側近にあって大きな役割を演じていたこともうかがわれる。
西はオランダに留学し、同僚の津田真一郎(真道)とともに法律学・経済学を学んで、慶応元年(1865)十二月帰国、まもなく開成所教授方に昇進した。
慶喜が徳川宗家を相続すると、西・津田の両人を京都に招致している。
津田はまもなく江戸帰還を命じられたが、西は京都に残り、慶応三年三月から慶喜にフランス語を教えた。
これは、洋書を読みたいという慶喜みずからの希望によるもので、内外の政務きわめて多忙のなかにあって、彼の知識欲の盛んであったことがわかるであろう。
このようなわけで西は、慶喜のブレインとして最も信頼されていたようである。
西の憲法案も、慶喜の内意を受けて起草したものとみることができよう。
この憲法案は、大政奉還後、新しい政治体制を決定するため招集される大名会議にかけられるべき、第一の議案とされているのである。
さて西の憲法案では、政府の権、朝廷の権、大名の権を三つの要綱としている。
政府の権とは行政権である。
徳川家の当主は「大君」と称され、行政権の「元首」(首長)として政府を大坂に設け、政府の官僚をおいて全国の政治を行う。
官僚のうち「宰相」だけは、「議政院」の選挙した三人のうちから「大君」が一人を任命し、その他の官僚は、「大君」が自由に任免できる。
各藩領内の政治は、「議政院」で議決する法律に抵触しないかぎり藩主にまかせる。
政府の権が行政権であるのに対して、大名の権は立法権である。
立法機関である「議政院」は上下両院から成立する。
上院は大名から、下院は各藩一人の藩士から構成される。
「議政院」の権限は、法律・予算の議定、外交・和戦など重大事件の協議である。
このように「議政院」の権限は、大名の権として政府の権をじゆうぶん制約するようになっているようであるが、じつはその運営が問題なのである。
「大君」は、上院議長となり、両院会議で議事が決定しないときは裁決権をもち、また下院の解散権をにぎっている。
行政機関の首長である「大君」が、同時に立法機関の首長として議事の統裁にあたることは、たしかに注目に値する。
ここでは行政権(政府の権)と立法権(大名の権)との平衡の重心がいちじるしく行政権に傾いているのである。
一方土佐藩の大政奉還建白書によると、行政機関としての「朝廷」の本体は、「議政所」すなわち立法機関とされている。
西が、「議政院」に立法権のほか行政権をも付与するのは虎に翼である、と暗に土佐藩の議論を批判していることにも注目したい。
大君が政府の首長のほか立法機関の首長をも兼ね、強い権力をもつのにくらべて、朝廷の権はほとんど空名にひとしい。
天皇は、「議政院」で議決された法律に判をおすだけで、拒否権をもたない。
天皇の直臣である公家は、山城国(山城・若狭・丹波・丹後が今の京都府)より外に出るのを禁じられるか、または出た場合にも、庶民と同じ権しかもたない、とされている。
宮廷を警備する軍隊は、幕府直領や大名領から高割りで出し、士官以上は政府から派遣しそのほかすべての武器携帯者が山城国にはいるのを禁じられる。
これは、天皇から政治的権限をなくし、山城一国の領主として封じこめ、「大君」を首長とする政府が軍事的に監視し、諸大名との連絡を断つことである。
大君制創設の野望
ここでまえに、慶喜の大政奉還の目的が将軍と摂関とを統一した政治的地位の獲得にあると想像しておいたことを思い出そう。
西の憲法案は、あまりにもよくこの目的と一致しているではないか。
将軍は、「大君」として政府の首長であるばかりでなく、立法機関の首長をも兼ねる。
これに対して公家は、山城国以外ではなんらの権力をももたない。
公家の首班としての摂政や関白が西の憲法案に出てこないのは当然であろう。
そのほか西の憲法案でひじょうに注目されるのは、軍事権を諸大名に任せておくとしておきながら、これは、しばらくのところ動揺がないよう、これまでのとおりにしておき、数年ののち情勢がおちつくのを待って、政府が統轄する方策をとりたい、としていることである。
おそらく旗本の軍役を金納にした方式を諸大名にもおよぼし、軍隊の統率権を統一しようとしたのであろう。
大名がひとたび軍事権を失ってしまえば、それは宮廷貴族にしかすぎない。
上院議長を兼ねた政府首長の「大君」が、さらに全国統一軍の大元帥ともなれば、彼はたとえ正式に「皇帝」とよばれないでも、ローマの元首制にみられるような「事実上の皇帝」なのである。
私は、この体制を「大君制」とよんでおきたい。
慶喜が大政奉還という非常処置においた最後の目的は、おそらくこの体制の創設にあったのであろう。
昨年八月、長州との休戦にふみきって以来、慶喜は、倒幕派との休戦期間を利用して、まず幕府の軍事力を強めようとした。
そしていまやまた、倒幕派との軍事的衝突が必至となろうとしたとき、大政奉還という新しい手で、たくみに身をかわすことを企てた。
軍事改革がまだこれからといういまの段階では、彼は、どうしても倒幕派との決戦をさきへのばしたかったのである。
大政奉還につぐ大名会議において、慶喜は、その音に聞こえた雄弁と議事指導の巧妙さとによって、会議を自分の欲する方向に引きずっていく自信があったろうし、したがってその会議にまず上程される憲法案が大多数の支持を得る成算もあったであろう。
こうなれば、政府の権力は実質的に強められるとともに、諸大名へは「立法権」の名で大幅に権力を付与したようにみせかけることによって、大多数の大名を手なずけることができよう。
そこから生れる政治的安定期間を利用して、慶喜は軍事改革をはじめ広範な内政の改革を推進する。
これによって政府の実力がじゅうぶんに強められたときを見はからって、軍事権を政府に統一してしまうというのが段取りらしい。
慶喜究極の目的
なお大政奉還によせる慶喜の意図を知る参考となるものに、大政奉還直後の十月十八日、老中格松平乗謨が出した意見書がある。
その中心をなすのは、「全国守護兵」の設置である。すなわち王政施行となれば、諸大名が私兵を貯えることができない制度を定め、全国守護の兵を設け、その経費には、徳川家をはじめ諸大名の石高の三分の二をあてることを提案している。
そして将軍は、新たに設けられる上院の議長となるとともに、「全国守護兵」の総指揮に当る。
これは、さきにあげた西周助の「大君制」と同じような、将軍制に代る政治体制である。
しかも乗謨は、大名で「全国守護兵」の設置に同意しないものがあれば、朝命を奉して討伐すべきである、ともいう。
さらに乗謨によれば、諸大名がその石高の三分の二を軍事費に提供してあり余ったものは、教育費や鉱山開発費、また工場・電信・鉄道等の開設に要する経費にあてる。
そうなると諸藩士で禄を離れるものができるから、それらを全国守護の兵にするよう説いている。
これでは、大政奉還・王政復古が一転してただちに徳川の王政、福沢諭吉の「大君のモナルキ」に転化する。
まるで手品のような話であるが、幕府側が大政奉還によせる期待を最も直截的に語っていると思う。
大政奉還から四十余日をへた十一月二十七日、−西周助の「制度腹稿」起草と同じころ――永井尚志(たかし)は松平慶永の近臣中根雪江に「日本はしまいには郡県制度になるとの意向を、上様(慶喜)はもっておられる」と語った。
慶喜の説は、「英国も昔は封建であったが、公議のうえ郡県でなくては強国になれないということで郡県になった。そこで日本もそうなるだろう」というのである。
永井は当時、慶喜が最も信頼していた腹心である。
したがって彼の談話は、慶喜の真意を伝えたものとみてよかろう。
これで、大政奉還によせる慶喜の究極の目的を推測することができる。
松平乗謨の意見書や西周助の「制度腹稿」における政府による軍隊の統轄は、郡県(廃藩)への途である。
このようにして大政奉還後創設されるべき「大君制」は、徳川絶対主義政権となるのである。
6 開戦と敗北 top
慶喜の憤激
慶喜は、大政奉還にさいして、板倉・永井らきわめて少数の側近にはかったのみだったので、大多数の幕吏は慶喜の真意をつかむことができなかった。
ことに京都から遠く離れている江戸に大政奉還の報が達したとき、激しい動揺でわきたった。
十月十七日、老中以下幕吏は登城して大評定を開いたが、結局、勘定奉行小栗忠順らのとなえる強硬論が大勢を制したという。
それは、第一策としては、ただちに旗本の兵を上京させ、京都から反対派を一掃し、さらに薩・長・土・芸をはじめ将軍の命令に反抗する諸藩の本拠をくつがえすこと、第二策としては、将軍は関東鎮撫の名目で江戸へ引きあげてしまうこと、という強引なものであった。
一直線に徳川幕府の絶対主義化を推し進めようとする小栗たちには、柔軟性に富む慶喜の戦術がわからなかったのである。
しかし慶喜は、大政奉還という路線の正しいことを信じて、すこしも動揺することなく、激動する幕臣の鎮撫につとめた。
十一月十一日、彼は上京した老中格(陸軍総裁)松平乗謨・同(海軍総裁)稲葉正巳両人に、大政奉還の趣旨を説いた親諭書をたずさえて江戸に帰している。
慶喜自身は、大政奉還ののちやがて開かれるべき大名会議に政体改革案(西の憲法案のようなもの)を上程・議決して、いっきょに政局の安定をもたらそうとする予定であった。
しかし討幕派は機先を制して、この予定計画をすべて破算させてしまった。
討幕派は綿密な計画の下に、幕府色を一掃するクーデタを敢行した。
十二月九日、「王政復古の大号令」が発布され、将軍・摂関は一方的に廃止を宣言されたのである。
二条城にあってこのクーデタに接した慶喜は、一時は非常ないきどおり方で、すんでのこと出兵におよぼうとしたが、再三熟慮したすえ、京都にいることの不利を察し、にわかに大坂に下ることに決心したのだ、という。
このようにして慶喜は、十二日夕刻二条城を出て、翌十三日大坂城にはいった。
大坂に着いた翌日の十四日板倉は、徳川家安危のわかれるところとして、ただちに兵隊・軍艦ともありあわせのものはすべて海路で大坂へ送るようにとの「御沙汰」である、と江戸の老中に要求している。
「御沙汰」とは慶喜の命令ということである。
これによると、慶喜は、旧幕府の陸海軍勢力を大坂に集中することによって、決戦態勢の整備を急いだことがうかがわれるであろう。
外交工作の展開
この日、慶喜はパークスおよびロッシュと会見した。
慶喜は、十二月九日の政変が不法であることを強調し、天皇に抗議を提出し、政変の結果成立した政府が正当な政府でないことを天皇に進言しようとする強い決意を述べた。
またロッシュによると、慶喜は「やがて日本は、私のとった行動と反対派のそれとに裁決を下すであろう」と、確信に満ちた調子で語った、という。
ロッシュは慶喜に答えて、日本の内政への介入を避けつつも、フランスは精神的援助を惜しまないことを約束したのであった。
それからロッシュはパークスをも同調させ、外交団会議を開いた結果、六国代表(両人のほかアメリカ・イタリア・オランダ・プロシア各国代表を含む)が慶喜と会見することになった。
十六日に挙行された慶喜と六国代表との会見で、外交団首席のロッシュは一同を代表して、外国代表が日本の内紛に中立を維持するとともに、国際的にみた日本の正当政府を速やかに知りたい、と要望した。
これは、徳川政権がかかる政府に当るものであることを、慶喜から直接聞き出そうとしたのである。
これに対して慶喜は、長文の声明書を読みあげた。それは、締約諸国が日本の内政に介入しないよう求めるとともに、将来の政治形態が大名会議できめられるまで、条約を遵守し対外関係を実施するのが自分の任務である、と述べている。
とくにその最後の部分は、現在の時点では徳川政権こそ、国際的にみた日本の正当政府であることを示そうとしたものである。
この六国代表との会見は、それを演出したロッシュにとっても、また慶喜にとっても、大きな成功といえるであろう。
ことごとに慶喜の行動の弁護につとめている『徳川慶喜公伝』でさえ、王政復古の政変後、「軽々しく公使を引見して王政の復古を非議」したことについて、「其失体は惜しみても尚余りあり」と評している。
しかし慶喜は、あくまでも王政復古の政変を承認しようとはしなかった。彼は、彼が合法的と認めた新政府できるまで、徳川政権が正当政府であることを国際的に認めさせるという実績をかせぎ、京都の政権と対決する姿勢を固持した。
開戦を決意
なおこのころ、慶喜がみずから在坂の役人たちにあてたと思われる文書がある。
それには、朝廷はもっぱら神事を引き受け、政治はすべて武家に一任するしきたりであったのに、いま、大政奉還・王政復古となっては、国家の解体眼前であるから、衆議を尽すべきである、としている。
しかもこの文書には、朝廷に抗議する奏聞書の案が添えられていた。
それには、さきに大政奉還を申し出た事情について、ちかごろ諸大名が「我儘増長」してむりに政権を朝廷に返上するようにというので、やむをえずやったことである。
こうした大名の行動は、徳川家年来の恩義を忘れ、朝廷を口実にして主家を押し倒そうとする「逆心」から出たものだ、と激しい口調で非難する。
そして、いままで申し上げたことは、「全く一時の見込みちがいとおぼしめし、御聞き流しに成し下されたく」、王政復古などとなえるヤカラはみなこのうえもない「悪党」「皇国の大罪人」で、しばらくもさし許しがたいから、かかる「悪党は残すところなく誅伐」する決心である、というものであった。
それは要するに、大政奉還は認識不足でやったことだから、それをキャンセルして「悪党誅伐」に乗り出す、ということである。
その極度に激昂した調子は、十二月九日の政変に接したときの彼の感情をそのままに伝えている。
「挙正退奸の上表」は、「悪党誅伐」の決意の具体化だった。
それは、慶喜にはかることなく王政復古を断行したことに強く抗議し、君側の奸を退けることを求めたものである。
慶喜はさらにこの上表を諸藩に示し、兵をひきいて上坂するよう命令した。
十二月九日の政変の否認は、あの政変にあって以来、慶喜の変わらない主張であった。
当時、彼の最も信頼する側近だったらしい永井尚志も、朝廷で過失を悔い、十二月九日以前にもどさないかぎり、解決の方法はない、と豪語したという。
したがって「挙正退奸の上表」の作成は、強硬派の幕臣や会津・桑名などにつきあげられてやったのではなく、じつに慶喜自身の意思によるものであった。
ただ慶喜は、強硬派が暴発して事をあやまるのを恐れ、兵力を集中したうえで決戦をいどもうとしたのである。
さて「挙正退奸の上表」は、大目付戸川安愛がたずさえて、十二月十八日徹夜で京都におもむき、まさに新政府の総裁有栖川宮(熾仁(たるひと)親王)のもとに提出されようとした。
しかるに事前にこれを知った岩倉具視(ともみ)があやうくとりおさえたので、戦争の危機はまさに間一髪のところで回避された。
ところが、この後十二月二十四日付けで、板倉ら慶喜の側近にいた大坂の老中が江戸の老中にあてて書簡を送り、いよいよ慶喜の開戦決意を伝えた。
すなわち、浪士暴動の本拠が江戸薩摩藩邸にあるとの証拠が明白となった場合には、同藩邸を攻撃することを命じるとともに、当方でも奏聞(「挙正退奸の上表」)の手続きがすみ次第、すみやかに討伐を開始し、東西呼応して「薩賊」をうちひしげば、武力によるまき返しは成功をみるであろう、としている。
当時江戸では、薩摩藩邸攻撃について硬論を吐く小栗や陸海軍士官に対して、一方では相当有力な自重論もあって一致をみるにいたらず、大坂の決裁を仰ぐことになったという。
そうすると、さきの書簡で伝えられた慶喜の決断は、強硬論に軍配をあげたわけである。
しかもその書簡がまだ江戸にとどかないうち、十二月二十五日未明、薩摩藩邸の焼討が決行された。
この間、辞官・納地問題については、新政府内部の討幕派と公議政体派の間で論争がかわされたが、十二月二十四日、辞官については前内大臣と称すること、納地については、徳川家の領地を調査のうえ、天下の公論で政務費を確定すること、にきまった。
この決定は、公議政体派の徳川慶勝・松平慶永を通じて伝えられたが、これに対して二十八日慶喜が提出した請書では、辞官については問題ないとしたが、納地については、政務費を全国から石高割りで出すのでなければ、臣下の鎮撫ができないから、容易におうけしかねる、と事実上、拒否している。
納地問題についての京都・大坂開の交渉は、ここに事実上決裂したのであった。
あたかもこの日、江戸薩摩藩邸焼討の報が大坂にとどき、城中は興奮の坩堝(るつぼ)となった。
この夜慶喜は、老中以下の役人たちを城中に集め、得意の弁舌で薩摩藩の罪悪を糾弾し、ここに京都進撃が決定された。
そして三十日には、軍事上の手配が完了した。
敗れた権力奪回の夢
こうして戦備をすべて整えたうえ、明けて明治元年(1868)元旦、慶喜は「討薩の表」を起草した。
それは、十二月九日政変以来の事態はすべて、薩摩藩「奸臣」の陰謀より出たものであるとして、「奸臣」の引渡しを要求し、もしそれを採用しないならば誅戮を加える、としたのである。
慶喜は、討幕派の陰謀によって建設された京都政権を絶対に否認し、十二月九日以前の状態にもどし、大政奉還で意図したとおりに政局を展開させるため、京都を占拠しようとしたのである。
この日、慶喜の命令一下、一万五千の軍はいっせいに京都に向って進撃を開始した。
すでに去年十二月十三日の大坂入城以来、軍隊を京坂間の要地に配置し、準備万端完了したうえでの軍事行動である。
慶喜は、兵力の圧倒的優勢と京都政権の脆さをたのみ、満々たる自信をもっていたのであろう。
一月三日には京都突入の予定であったという。
ところが『徳川慶喜公伝』には、旗本や会桑二藩の兵が慶喜に挙兵を迫ったので、ついに押えきれず、「空しく手を拱(こまね)きて傍観するの已むを得ざるに至る」と述べられている。
慶喜がそんなに無力な存在だとは、到底信じられない。
大坂入城以来、彼が着々と開戦を準備してきたことは、いままで述べてきたことで明らかである。
『慶喜公伝』の記事は、慶喜の自己弁護的な後日談によるもので、全く信じられない。
しかしこのときになっても、岩倉具視さえ、慶喜が入京参内して辞官・納地の受諾を上奏すれば、議定に任命するという意向をもらしている。
徳川慶勝・松平慶永・山内豊信・伊達宗城ら公議政体派の議定も、最後まで調停の望みを捨てなかった。
ついでにいっておくと、パークスも両者の紛争が調停されるという希望を抱きつづけてきた。
この間にあって討幕派の指導者大久保一蔵は、朝廷に建議書を提出し、徳川氏の処置につき失策を重ねてきたことを説き、こうした失策を取りもどすには、「勤王無二の藩」が決然として戦争を覚悟し、協力して非常の尽力をしなければならない、と強調した。
「勤王無二の藩」とは、いうまでもなく薩長をさしている。はたして三日の夕刻、鳥羽伏見の関門を突破して入京しようとする徳川軍と、この地を守る薩長軍との間に戦端が開かれた。
薩長軍は、数的には徳川軍の三分の一以下であったが、優勢な砲火を狭隘な地域に集中して徳川軍を撃破し、三日間で戦局は決定的となった。
五日まで「千騎が一騎になるまで退くな」と激励していた慶喜は、六日の深夜、あわただしく大坂城を脱出、八日開陽丸で大坂湾を出帆し、途中風波に悩まされつつ、十一日夜、品川沖に到着した。
なぜこんなに慶喜は東帰を急いだのであろうか、それはたしかに一つの大きな疑問である。
これについては、大政奉還直後、フランス公使ロッシュが伝える幕府側の秘密情報が参考になると思う。
それは、反対派の諸侯が大政奉還に耳をかさない場合、慶喜は江戸に退いてそこに政府の中心を再建し、関東の主人たる地位を保持し、譜代大名・旗本および北方の外様大名の支援を獲得する、というのである。
これが幕府側のかねての計画であったとすれば、慶喜の東帰は予定の退却であろう。
予想外の敗北に驚いた慶喜は、少しでも早く退却すればするほど、それだけ江戸を拠点とする徳川政権の再建を有利にすると信じ、例の変り身の早い行動に出だのかもしれない。
7 政治的生涯の終り top
東帰後の動静
慶喜の東帰は、従来一般にいわれるように彼の恭順を意味するものではない。
元に慶喜が江戸城に入った十二日には、今後の模様によっては速やかに上坂するという意向が表明されている。
江戸城中では連日連夜議論がかわされたが、抗戦論が優勢で、わけても勘定奉行兼陸軍奉行並小栗忠順・歩兵奉行大鳥圭介・軍艦頭榎本釜次郎(武揚)のごときは、強硬論を展開した。
そのなかで一月十五日、小栗は突如慶喜によって罷免されている。
彼の激しい性格と非妥協的な抗戦論が、慶喜の感情を害したからであろうが、同時に慶喜の心境の微妙な変化が読みとれるかもしれない。
小栗は、財政改革および軍制改革において、徳川幕府の絶対主義化の推進者として、慶喜から多大の信頼を得ていた。
彼は大政奉還に不満であったが、慶喜の開戦決意によって両者の見解はふたたび一致した。
慶応三年十二月末に、小栗が陸軍奉行並の要職を兼ねるにいたったのは、このことを示すものであろう。
ところがいまこの抗戦論のチャンピオンが罷免されたことは、抗戦論の前途を占なうかのようである。
しかし小栗の罷免は、いまだ慶喜が恭順へふみきったことを意味しない。
一月十七日、彼が慶永へ送った書簡には、鳥羽伏見の戦争を、先駆のものが不意に衝突したまでであるとし、追討令を「甚だ以て心外の至り」と抗議しているるからである。
ロッシュとの会見
その直後、慶喜とロッシュとの後の会見が行われた。
羽伏見戦後もロッシュは、徳川政権を支持する態度を変えなかった。
一月十三日、ロッシュは対日政策についての意見書を各国代表に送った。
そのなかで彼は、成立の事情からみて天皇政府の合法性を否認し、同政府が外国人を保護できる能力に疑惑を表明した。
これに反し、「大君政府」は従来条約の実施に忠実であったのみでなく、将来外国の利益の拡大を企図していると信じられるとして、「大君政府」を支持すべきことが力説されている。
ロッシュは、このような政策から徳川政権の動静をうかがうため、兵庫から海路江戸に向った。
そして十九日・二十六日・二十七日の三回にわたって、江戸城中で慶喜との会見が行われた。
まず十九日の会見で慶喜は、徳川家の主人としてその領地が侵犯されることに反対し、全力を尽してそれを防衛しようとする決意を表明した。
さらに彼は、天皇は目下監禁状態にあり、自由意志で行動していない、といった。
ところが二十六日の会見になると、慶喜は態度を緩和し、自分は隠居して紀州藩主徳川茂承を後継者とするが、その後もみずから新徳川家主の後見に当るであろうこと、天皇に対して戦争をするのは、ただ祖先伝来の領地を防衛するだけを目的とすること、を述べている。
一週間のうちに、朝廷に対する慶喜の態度に変化が起っているのが認められる。
二十一日、慶喜は松平慶永に書簡を送り、朝敵の汚名を受けたことと病気とを理由に隠居の意志を表明し、朝敵の汚名をすすぐよう斡旋を依頼している。
「恭順」へと一歩近づく姿勢であるといえよう。
はたして二十三日、徳川政府の組織が改められ、従来の老中・若年寄が国内御用取扱として背後に退き、旗本出身者を総裁および副総裁に登用した。
これは、全国的政権の職制から地方的政権の職制への切りかえを意味するであろう。
とくにこれにともなう人事で注目されるのは、ハト派の勝海舟・大久保一翁がそれぞれ、陸軍総裁・会計総裁に任命されたことである。
これも、ロッシュとの会見で表明された慶喜の姿勢の変化と関連するものと思う。
慶喜は、名目的隠居を条件にしハト派を手先に、東日本の政権として天皇政府との間で、できるだけ有利な講和を獲得しようとしたのであろう。
そしてこのような態度の変化が、ロッシュとの第二回の会見で表明されたもののようである。
これは、江戸帰還当時、全国的政権であることを主張していたのにくらべると、大きな後退ではあるが、まだけっして「恭順」とはいえない。
慶喜は、東日本の政権たる立揚が侵されれば抗戦する決意を、ロッシュに表明しているからである。
ロッシュの調停策
はたして二十七日の会見のさい、慶喜はロッシュに声明書を渡した。
この声明書では、大政奉還以来の行動が正しいことを弁明し、外国との条約を実行するばかりでなく、進んでそれを改善する意向があることを表明し、内乱を避けるためには犠牲をいとわないが、忍耐には限度があるとして、外国人の同情に訴えている。
忍耐に限度があるというのは、東日本の領地が侵犯される揚合をいうのであろう。
この声明書の原案がロッシュの起草であることに注目しておきたい。
このほかロッシュは、関東を根拠にして西軍に抵抗する方策を慶喜に示した。
軍事面については、陸上では駿河に防備線をしき、海上では江戸湾の入口を大砲・軍艦で固め、外人教官による軍隊の訓練や外人部隊の編成を勧告した。 |

フランス軍事教官団
|
また財政面では、さきに成立した借款契約をあげ、外国の方法にならって会計方法を改革し、むだな費用を省き、それを軍事費に振りむけることを説いている。
それは、東日本(駿河に防備線をしくとあるのによると、駿河以東であろう)を支配する徳川政権の自衛策である。
ロッシュは、天皇政府との妥協が失敗したさいの対策を提示したのである。
慶喜との一連の会見後、ロッシュは慶喜の隠居表明によって、もはや日本には「大君」が存在しなくなり、外国はいまや日本で天皇と向きあっているという冷厳な事実を認めざるをえなかった。
それとともに彼は、慶喜を依然として「日本の強い君主」であると評価し、「その領地において条約を将来完全に実施し、文明化への意志を捨てることなく日本を指導して、その切り開いた道を前進することを決意した」とみている。
さらにロッシュによると、慶喜は天皇政府の破綻を予想し、「他日時機至れば、封建制度の廃止と信教の自由によって、社会改革に着手しようとする意向をみせた」という。
そうすると、慶喜は天皇政府が久しからず破綻するのを予想し、そのとき中央政界への復帰を狙っていたのであろう。
それまでの間、慶喜は天皇政府との問にできるだけ有利な妥協を取りつけ、実力を保存しつつ待機しようとしていたらしい。
従来の説では、ロッシュとの最後の会見で、慶喜はロッシュの援助提案をすべて退け、「恭順」の態度を変えなかったという。
しかし事実によれば、彼は他日政治攻勢を回復できる見通しのもとに、天皇政府との妥協策および妥協が失敗した場合の抗戦策について、ロッシュと協議したのである。
そしてロッシュは、慶喜との間で一致した線にもとづき、各国代表の圧力で天皇政府と徳川政権の紛争を調停しようとして、兵庫におもむいた。
恭順決意
ところがロッシュが江戸に滞在していた一月下旬、パークスは、外国の利益のため「大君政府」支持を説くロッシュの見解を批判し、天皇政府が国民的性格をもつ中央政府たる可能性を内包すると評価しているのに反し、徳川政権を一箇の封建領主としかみなかった。
ついで二月三日、神戸事件の責任者を極刑に処するという通知を受けると、パークスは、天皇政府の統治能力と外国人への善意を確認するとともに、慶喜へよせた期待が誤っていたことをはじめて告白した。
すなわち彼は、慶喜が政局の動きを主導する機会を逸し、かえってその動きの反対者になった、ときめつけ、慶喜は「ひとたび権力の座につくや、なんらの改革をも導入しなかった」と述べている。
さてロッシュは、二月八日兵庫に来て、各国代表との会議に臨んだ。
おそらく席上、ロッシュから慶喜との間で協議された内紛の調停案が出されたであろう。 |

イギリス公使パークス
|
しかしそれは、すでに天皇政府を日本の統一政権として評価していたパークスからは、問題にされなかったと思う。
ロッシュの調停が不調に終ったのとは別に、二月五日、慶喜は慶永に嘆願書を送り、はじめて明白に「恭順」の意向を表明するにいたった。
これは、一月二十八日慶永が慶喜へ送った書簡で、慶喜の反逆の状態が明白であることを列挙し、近く征討の大兵を発せられるという状況を述べて、謝罪を勧告したことに応じたものである。
慶永は、慶喜の謝罪以外に徳川家を保持する途がないと考えたのである。
慶永が、従来幕府内のハト派として、勝海舟・大久保一翁と気息が相通じていたことにも注目しておきたい。
ついに二月十二日、慶喜は江戸城を出て、寛永寺内の大慈院に引きこもることになった。
江戸退去
慶喜の大慈院退居で、徳川政権内部における勝海舟・大久保一翁、とくに前者の地位がいよいよ高まった。
大慈院に退居した二月十二日、慶喜は慶永に書簡を送り、官軍の発向をしばらく猶予するよう懇願した。
この書簡を受取ると、同十九日、慶永は朝廷に上書し、東征軍発向の停止を請うた。
謹慎中の慶喜に征討軍を向けることになっては、徳川家臣の敵意を強めるばかりか、国際的には「公法」に反し、外国側の異議を恐れる、というのである。
ここで慶永が展開する論理は、のちに海舟が西郷隆盛へあてた書簡で述べているそれと一致し、さらにパークスが江戸攻撃に圧力を加えるさいに用いる論理とも一致していることに注目したい。
そこにおける共通の論理は、「恭順」の姿勢を示すことによって、国際的世論の圧力を利用し、政府軍への降伏条件をできるだけ有利にするということである。
さきに慶喜がロッシュと協議した方針は、慶喜の名目的隠居を前提とする徳川政権と天皇政府との講和だったから、慶喜の「恭順」を前提とする以上、それよりも後退した姿勢である。
しかし、徳川の勢力をできるだけ保存しようとする点で、さきの構想は生きている。
二月二十五日、「軍事取扱」として徳川政権の最高の実力者となった勝海舟が政府側に展開したのは、まさにこの「恭順」戦術であった。
当時、政府側の要人からは、慶喜の抹殺さえ辞さないという声も聞かれたが、これはむしろ一種のジェスチュアであった。
政府側の実際の要求は、慶喜の軍門投降、備前(岡山)藩へのお預け、江戸城の明渡し、軍艦・兵器の接収という、いわば無条件降伏の線であった。
これに対して三月十四日、勝が西郷との会見にさいして、徳川有司嘆願書の名で提出した条件はつぎのようなものであった。
すなわち、慶喜が隠居して水戸で謹慎することのほか、江戸城の自主的明渡しと田安家による保管、軍艦・兵器の相当数の徳川氏保留、戦争責任者の寛大な処置などを含むものである。
これによって、慶喜の備前藩お預けという屈辱的処分が避けられるほか、相当の大藩としての「徳川藩」の存在が確保され、場合によっては江戸城居坐りの可能性さえ持てることになる。
勝は、名誉ある降伏の条件を押すために、政府に対し大きな影響力をもつパークスを利用した。
すでに勝・西郷会見の前日、パークスは東海道先鋒総督府参謀木梨精一郎に対し、慶喜の「恭順」を理由に武力行動に反対する意向をほのめかしている。
こうした事情を察知した西郷は、三月十五日と予定された江戸攻撃を中止させ、京都へ急行した。
西郷が着京すると開催された朝議では、勝から提出された嘆願書の条項を大幅に入れた徳川処分策が作成された。
江戸城を田安家の代りに尾張藩に引き渡すとあるのが、嘆願書と違うくらいなものである。
西郷は、徳川処分策をたずさえて江戸におもむく途中、四月一日横浜でパークスと会見し、徳川処分策を示して了解を求めた。
そして同四日、東海道先鋒総督橋本実梁(さねやな)・同副総督柳原前光(さきみつ)が勅使として江戸城に入り、さきに朝議で決定した徳川処分策を朝旨として、江戸城の主宰者、徳川(田安)慶頼に伝えた。
その第一条には、慶喜の恭順謝罪と実父斉昭(なりあき)の勤王を認め、徳川の家名を立て、死罪一等を減じ、「水戸表へ退き、謹慎罷在るべき事」と述べられている。
この朝旨に従って、四月十一日、江戸城の明け渡しが行われた。
この日の未明、慶喜は、ちょうど二ヵ月間引きこもっていた大慈院を出て水戸に向った。
慶喜は、積日の憂愁に面はやつれ、髭がぼうぼうと生えており、黒木綿の羽織に小倉の袴をつけていた。
彼の痛々しい姿を見た者は皆むせび泣き、目を上げる者はなかったという。
こうして慶喜は、「大君制」創設の夢もむなしく、まだ満三十歳を越えたばかりの若さで、政治的生涯を閉じたのである。
参考文献
渋沢栄一『徳川慶喜公伝』(竜門社)
石井孝『増訂明治維新の国際的環境』(吉川弘文館)
同上『維新の内乱』(至誠堂)
同上『勝海舟』(吉川弘文館)
top
****************************************
|