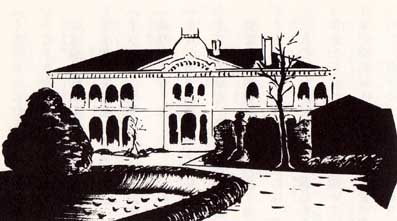|
****************************************
Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ 年譜など
Ⅰ 小平浪平の生い立ち
1 少年時代 top
明治七年(一八七四年)一月十五日、新暦の正月はもう終わったが、田舎で行っている旧暦正月にはまだ日がある、冬の寒い日であった。
小平家では二番目の子供が生まれるというので、家中の者は気もそぞろであった。
母親のチヨは、奥の部屋に敷いた床の中にいた。
「また男の子かな。」
「初めが男の子だから、今度は女の子じやねえか。」
手伝いに来ていた近所のおばさんたちが、台所での手を休め、奥の部屋の方を気にしながら、ヒソヒソ話をしている。
間もなく奥の部屋から、赤ん坊の元気な産声が聞こえてきた。
「男の子ですよ、かわいい丈夫な。」
産婆さんの声である。
父親の惣八が、そっと部屋に入った。
いそがしく立ち働く祖母よしのわきに、三歳の長男儀平がまつわりつきながら、弟の顔を不思議そうにのぞきこんでいる。
惣八の少しくぼんだ目と、チヨのうるんだ目とが、カチッと合った。
と、つかれたようなチヨの顔に、かすかに笑みがうかんだ。
栃木県都賀郡家中村大字合戦場にある、小平家に生まれたこの赤ん坊は、浪平と命名された。
浪は強くそしてやさしいという、二つの意味があるとして、母親のチヨがつけたのである。
長男儀平、次男浪平と、男の子が続いたのであるから、父親惣八の子供たちへの夢は、大きくひろがっていった。
明治十三年(一八八〇年)六歳になった浪平は、合戦場にあった小学校淑慎学舎(しゅうしんがくしゃ)に入学した。
今から百年以上も昔のことだし、田舎の小さな学校だったので子供の数も少なく、勉強らしい勉強もしなかったが、浪平は、先生のいう事をよく聞く、頭のよい少年であった。
父親の惣八は時代を先取りするような人で、これからは学問をしなければ、一人前にはなれないという考えを持っていた。
その惣八にとって合戦場の小学校では、浪平の持っている力を十分出すことができないと思った。
浪平が十一歳になった明治十八年(一八八五年)、父親の惣八は浪平を、合戦場から四キロメートルばかり離れた、栃木小学校に転校させる事にした。
きちんと膝をそろえてすわっている浪平に向かって、父親の惣八はいった。
「浪平、これからは学問をしないと、一人前の人間にはなれない。栃木小学校で勉強してこい。」
父親の鋭い目がチカッと光った。
「栃木町だから、合戦場から通うのは大変だ。栃木町のわしの実家から通うようにしたから。」
父親の命令に逆うことはできない。
浪平は首をたてにふり、「ハイ」といった。
兄の儀平は前の年、東京の親戚にあずけられ、勉強していたので、浪平も学問をしたいという希望は、少しずつ心の中に育っていた。
浪平が栃木小学校に通学した父親惣八の実家は、栃木町の城内にあった。
屋敷の東から南にかけて、流れの速いきれいな小川があり、庭には池もあった。
その池には、赤や白の緋鯉(ひごい)が何十匹も泳いでいた。
浪平が合戦場の小学校にいたころ、父親の惣八は浪平をつれて実家に帰った時など、池のそばによくいったものだった。
「浪平、ほら、右側の石の所にいるでっかい緋鯉、赤と白の。あれはわしが子供のころから、この池にいるんだ。もう四十年も昔からな。」
「四十年も。」
浪平は驚いたような顔をして、ゆうゆうと泳いでいる大きな緋鯉を見つめた。
気が遠くなるような長い年月を、生きてきた鯉のすがたは、王様のように浪平には見えた。
それから四十年たつと、浪平がつくった日立製作所は、電気機関車や回転変流機をつくったりして、一流会社としての信用が高まったのであったが、その時の浪平には、四十年後の自分の予測はできなかったであろう。
浪平が学んだ栃木高等小学校は、その当時栃木県内でも有名な小学校で、浪平が卒業した十一年後に、「路傍の石」「真実一路」などを書いた山本有三が入学している。
栃木町での四年間は、浪平のそれからの生き方に、多くの影響を与えている。
栃木町はその名の示すように、栃木県第一の町であった。
しかし一度は県庁所在地になったのを断ったり、東北本線が通るのを反対したり、現代の人なら考えられないような事をしている。
そのために、古風でしっとりした気風を、長く保ち続けてきたのであろう。
栃木市には今でも、道の端に掘割があり、きれいな流れの中を鯉が泳いでいる。
こういう町は、もう日本の町の中でも数少ないのではないだろうか。
この町のもつかたくなさと、父親惣八から受け継いだ仕事へのひたむきな情熱とがまじり合って、後世の浪平をつくったのである。
浪平は小学校に通学するだけでなく、放課後になると漢学の先生の家に通って、中国の歴史の本である「史記」の勉強も始めた。
この当時の学問好きな少年たちの間では、漢学塾にいくことが流行になっており、小説家山本有三も漢学塾に通い、「日本外史」や「文章軌範」の勉強をしている。
浪平はまた、明治二十年(一八八七年)栃木町に開校された「栃木協立英語学校」にも入学した。
何しろ昼の間は、小学校に通っているのであるから、英語学校へいくわけにはいかない。
幸いな事に朝の授業があるというので、浪平はそれを選んだ。
授業は六時半から始まるので、父親の実家は五時半には出なければならない。
夏の間はそれでもいいが、秋から冬にかけては、まっ暗い中を通学しなければならなかった。
気が強いしっかり者の浪平も、それにはこたえたようである。
通学途中にある江戸時代の首切り場のあたりは、人っ子一人通らず不気味であった。
心と体の中を、スゥーと冷たい風が吹き抜けるような時など、浪平は足が前へ進まないで、立ちすくんでしまうこともあった。
そんな時でも浪平は、英語の教科書だけは両手でしっかりと持っていた。
明治二十年(一八八七年)浪平は十三歳になった。
頭もよく、体もすんなりとした少年に成長していた。
「そろそろ元服の祝をしなくちや。」
浪平を目の中に入れても痛くないほどかわいがっていた祖母のよしは、目を細めてそんな事をいった。
この地方では男の子は十三歳になると、日光の二荒山(ふたらさん)神社に参拝するしきたりがあった。
「わしが二荒山に詣でたのは、たしか嘉永七年(一八五四年)のことじゃった。前の年浦賀の港にペリーが黒船でやってきて、日本中が大さわぎになった。もう三十三年も昔のことだが、今でもはっきりおぼえている。」 |
 |
父親の惣八は旅仕度をしながら、三十三年前の元服祝の事を思い出しているのだろう。
その声は、いつもの父に似あわずしんみりとしていた。
二人は日光東照宮にお参りしてから、中禅寺湖畔に宿った。
合戦場と栃木町しか知らなかった浪平にとって、この旅行は少年時代の最後にふさわしい、楽しい思い出になった。
東照宮の華やかな色彩と雄大さに心をうばわれ、満々と水をたたえてひろがっている中禅寺湖に体が吸いこまれ、少年浪平の心と体は、雲の上を歩いているように幸せであった。
宿について少し休んでから、惣八と浪平は一緒に風呂に入った。
暖かい湯気の中で、父と息子は裸の肩をよせあい、目と目を合わせ満足そうに笑った。
「いい体になったな、浪平、背中を流してやろう。」
いつになくやさしくいうと、惣八ぱ浪平の背中を洗ってくれた。
こんな父を、浪平は一度も体験したことがなかった。
二人が部屋へ戻ると、女中が黒ぬりの膳(ぜん)を二つ運んできた。
一つの膳の上には、料理のほかに徳利(とっくり)が一本、盃が一つ置いてある。
「さあ、始めようか。」
惣八が膳の前にすわった。
「お父さん、お酒。」
浪平は徳利をつかむと、父の前に出した。
「すまんな。」
惣八はそういって盃をもち、酒をついでもらう。
間もなく惣八は、少しばかりの酒によったのか、口数がいつもより多くなった。
鼻の下のひげが酒のしずくでぬれている。
「いよいよ、事業をはじめるんだ。」
惣八は、物につかれたようにしゃべり始めた。
「浪平、私は合戦場に帰ったら、鉛丹(えんたん)の工場をつくるぞ。」
「鉛丹って。」
「鉛を鍋の中でとかし熱を加えると、赤い粉ができる。この粉を船の底にぬると貝がらもつかないし、さび止めにもなるんだ。」
うるしを入れると、お前がさっき見た東照宮で使う赤い塗料にもなる。
きっと成功するぞ。もし失敗しても、最後には必ず成功する。」
「父さん、がんばってください。」
「ああ、お前も、中学になったら、うんと勉強するんだ。」
そんな話をしている間、父の鋭いくぼんだ目が、火花でも出るようにキラッキラッと光った。
その晩惣八と浪平は、一つの部屋でならんでねた。
布団の中に入っても、夕食の時の父の言葉が頭にこびりついていて、なかなか眠れなかった。
2 父の死と出発 top
明治二十一年(一八八八年)四月、浪平は栃木高等小学校を卒業した。
四年前から勉強のため東京へ出ていた兄の儀平は、学校が休みになるとよく合戦場の家に帰ってきた。
儀平は栃木にいたころから、頭のきれるキリッとした少年だったが、しばらく東京にいるせいだろうか、たちいふるまい、言葉づかい、着ているものもあか抜けていて、浪平の目にはまぶしく映った。
「浪平、お前も小学校を卒業したら東京へ出てこい。東京にはいい学校もあるし、いい先生もたくさんいる。」
「東京は栃木の町とくらべて、どんなふうです?」
「くらべものにならない。乗合馬車や人力車がひっきりなしに道を通り、たくさんの人がいったりきたりしている。」
合戦場と栃木の町と、父と一緒にいった日光しか知らない浪平にとって、兄の言葉は聞いても想像できなかった。
「そうそう、鹿鳴館が明治十六年にできた。」
「鹿鳴館(ろくめいかん)?」
「なんだ、浪平は鹿鳴館も知らないのか。
東京の上流家庭の人々や外国人が、舞踏会や仮装会をする建物だ。
最近、白熱電灯がついたので、夜も昼のように明るいということだ。」
派手な事は性に合わない浪平なので、舞踏会や仮装会には興味がなかったが、白熱電灯がともったという兄の一言には、激しいショックを受けた。
二人の話を、父の惣八は満足そうに、その後生まれた妹の満舞(まん)や弟の陣平(じんぺい)はわかったようなわからないような顔で聞いていた。
父の惣八は、浪平が小学校を卒業したら東京へ出して、中学受験の勉強をさせる腹だったので、儀平のすすめにたちまち同意した。
ちょうどその頃、東京浅草に住んでいた祖父の妹平井リツの夫が急死したので、浪平はリツの家に住む事になった。 |
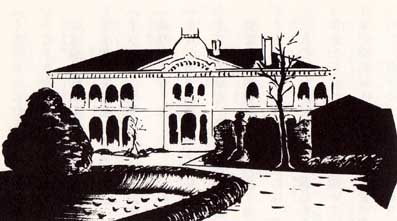
鹿鳴館(ろくめいかん)

エジソンの発明した電灯も日本にすぐ導入された
|
明治十七年(一八八四年)、兄の儀平が東京へ出た頃は鉄道がなかったので、川蒸気船で川を下って東京へいったが、浪平は小山駅から汽車に乗って上京した。
東京での浪平の生活が始まった。
右も左もわからない、田舎者の浪平にとって頼りになるのは、四年前上京した兄の儀平であった。
「お前もおれと同じように、東京第一高等中学校がいい。そのためには、しっかり勉強しないと入れないぞ。
英語は杉浦重剛先生の東京英語学校、数学は下谷の至誠学舎(しせいがくしゃ)、漢学は九段下の蒲生重章先生がいい。」
兄の儀平はなれたふうに、テキパキと学校や先生を決めてくれた。
しかしこれらを決めるのに、兄は父惣八とよく相談した。
惣八は男の子二人を東京へ出し、勉強をさせるだけあって、当時の学校や先生の事について、しっかりした知識を持つていた。
兄の儀平は、医学を一生の道として選んでいたので、ドイツ語をドイツ教会学校で学び、明治二十二年(一八八九年)第一高等中学校の入学試験に合格した。
翌明治二十三年(一八九〇年)兄儀平の勧めもあって、浪平は第一高等中学を受験したが落ちてしまった。
試験の成績がさんざんだったことは、当の浪平が一番よくわかっていたので、別に悲観もしなかった。
浪平にとっては、故郷の合戦場に、しばらくぶりに帰れることの方がうれしかった。
帰る途中、浪平は小山でバッタリ父惣八に出会った。
宇都宮からの帰り道だといったが、頬がこけ頬骨がやけに高く見えた。
「どうした、試験の結果は。」
「落ちました。」
「また来年もある。失敗あっての成功だ。くじけちやいかん。わしだって何回失敗したかわからない。」
「はい。」
「浪平が一人前になるまで、私も頑張るから、お前もしっかりやれよ。」
浪平は父に叱られるかと思ったが、惣八はそういって、浪平を励ました。
しかし顔色が悪く、つかれているようだった。
事業がおもわしくないので、その気苦労で元気がないのだと、その時浪平は思った。
後でわかった事であるが、父惣八の体の中で、病気が相当すすんでいたのである。
それから五か月後の十二月十五日、父惣八は亡くなった、四十八歳の若さであった。
父惣八が亡くなった時、母のチヨは三十八歳であった。
十九歳の長男儀平(ぎへい)を頭に、浪平、満舞(まん)、陳平(ちんぺい)、梅(うめ)、勲(いさお)、八重(やえ)の七人の子供と父惣八のかなりの借金が残された。
それに次の年死んでいった祖母のよしもいた。
葬式、そして初七日が終ると、チヨを中心に親戚の人たちが集まり、これからの小平(おらいだ)家に事について相談が始まった。
いい話でないことは、だれもが始めからわかっていたので、話を切り出すものがいない。
気まずい沈黙の時間が過ぎてゆく。
しびれをきらすように、惣八の兄が口火を切った。
「事業に失敗した惣八の借金も相当あるようだし、このままではどうにもならない。
せっかく東京の中学に入った儀平には悪いが、この際学校をやめる他に方法はあるまい。」
「儀平、どうだ、お前の気持ちは。」
末席にすわっていた儀平が、ムッとした顔をして亡き父の兄の顔をにらんだ。
母親のチヨがおろおろした顔で、息子の儀平を見た。
「学校を退学するなんて、私はいやです。私は医学の道を進んで、小平家を建て直す覚悟です。」
茶と陶器の商いをしている、父惣八の弟が口ばしを入れる。
「儀平の勉強したいという気持ちはよく分ける。しかしなあ、おっかさんの気持ちも考えてみるんだな。
お前を頭に七人の子供を、今から女手一つで世話しなくてはならない。
兄(惣八)の四十九日でも過ぎれば、借金取りがおしかけてくることは、目に見えている。
世間というものは、お前が考えているような、そんな甘いものじゃない。
儀平、おっかさんを助けてやれよ。」
儀平には、もういう言葉がなかった。
座った膝の上に、固くにぎりしめた手をおき、悲しさとくやしさをこらえている。
脇で母のチヨが、たもとに顔をうずめている、きっと泣いているのだろう。
儀平は決心した。キッと顔をあげると、しっかりした囗調でいった。
「わかりました。東京での勉強はやめます。しかしひとつだけお願いがあります。
弟の浪平だけは、東京で勉強させてください。私が働いて、仕送りをします。」
間もなく兄の儀平は、東京第一中学校を退学し、一家を支えるため、栃木町の銀行に勤める事になった。
「兄さん、俺も学校はやめる。兄さんと一緒に働くよ。」
「いかん。なんのために俺が跡をつぐのか、お前にはわからんのか。」
浪平も東京での勉強をやめたいと、母や兄にいったが、儀平は、
「お前は俺の分まで、東京で勉強して、来年は第一高等中学に入ってくれ。」
といって承知しなかった。
浪平は涙ながらに、
「兄さん、ありがとう。……それじゃ、東京で頑張るよ。」
浪平は、東京浅草の平井の家に戻り、二階六畳の間で勉強を始め、翌明治二十四年(一八九一年)七月東京第一高等中学校に合格した。
受験者一、二〇〇名のうち合格者七〇名、浪平は七番の成績であった。
中学合格を故郷の祖母よし、母チヨ、兄儀平たちに知らせようと、帰る支度をしていた浪平の所に、母から手紙が届いた。
「祖母のよしが、七月初めから病気になり危篤なので、大至急帰ってきてもらいたい」という文面であった。
兄弟の中で一番祖母にかわいがられた浪平は、すぐ合戦場にむかった。
しかし、二、三日後、祖母よしは七十八歳でその生涯を閉じた。
浪平は、祖母の仏壇の前で心にちかった。
「おばあちゃんや、お父さんのためにも、そして母さんや兄さんの分まで、勉強をして、役に立つ人になる。」
半年余りの間に、相ついでこの世を去った、父や祖母の志に報いるには、将来自分にしかできないいい仕事をする事しかないと、浪平は思うようになった。 |

兄のおかげで東京で勉強できことになった浪平
|
3 村井弦斎との出会い top
浪平の青春時代を語るには、村井弦斎(げんさい)との出会いをぬかすわけにはいかない。
浪平のそれからの人生を決定した、村井弦斎とはいかなる人物なのか、その略歴をたどってみよう。
村井弦斎(1861〜1927年)は愛知県豊橋の儒家の生まれで本名は清、慶応三年(一八六七年)父に伴われて江戸へ出る。
明治六年(一八七三年)、東京外語学校に入学し、ロシア語をおさめたが病気のため中退する。その後、経済、社会、政治、商法、文学などを学んだ。
明治十五年(一八八二年)、北関東、東北、北海道を、たばこの行商をしながら放浪する。
その時惣八の実家大沢家や、合戦場にあった浪平の家にも立ち寄り、自炊生活をしながらたばこを売り歩いた。
合戦場の浪平の家にいたころの弦斎について、妻の多嘉が次のように書いている。
「主人が合戦場の小平様のお宅で、自炊をしていたころのことだそうですが、夕方煮物をしようとしたら醤油がきれてしまった。 困っていると坊ちゃん(浪平)が、『買ってきてやる』とおっしゃって、小さな瓶を持って醤油を買いにいってくれたそうです。その後ろ姿が今でも目にうかぶと、よく申しておりました。」
弦斎はその後アメリカのサンフランシスコに渡り苦労する。そこで矢野竜渓(りゅうけい)を知る。
そういう縁故で、浪平は東京へ出てからも弦斎の家をよく訪ね、一緒に舟に乗って遊んだりもした。
明治二十七年(一八九四年)四月、浪平二十歳、東京第一高等中学の四年生であった。
十二日は土曜日だったので、授業は午前中で終わった。
校庭の桜は満開を過ぎ、雪のように散っている、暖かい春の午後であった。
浪平は鉄道馬車と汽車を乗りつぎ、品川にあった弦斎の家を訪ねた。
当時弦斎は、都新聞に小説「桜の御所」を連載中で、執筆に追われ多忙であった。
弦斎は小説家だけあってかたくなな所があり、原稿を書いている最中は、どんな人が訪ねてこようとも会わなかったので、妻の多嘉がその断り役になっていた。
しかし浪平だけは特別で、どんな時でも喜んで迎えた。
弦斎と浪平は十一、年が違っていたが、弦斎は実の弟のように浪平をかわいがった。
その日の弦斎は特に機嫌がよかった。
「先生、こんにちは。」
「浪平、よう来たな、今日は夕食に牛肉をごちそうしよう。寄宿舎ではうまいものも食えんだろうから。」
いつものことながら、浪平は弦斎に会うと心の中のしこりがとけて、ニコニコとしていつの間にかゆったりとした気持ちになった。
「儀平さんが結婚したそうじゃあないか。」
「はい、お客さんが百六十人集まり、夜の七時から朝の三時すぎまでかかりました。」
「三時までか、それじやあ花婿花嫁は、寝る暇もないな。」
弦斎はカラカラと笑った。
「先生、今日はこれから進む道について相談に来たのです。」
浪平の思いつめたような様子を見て、弦斎も真顔になった。
「あと二年くらいたつと、私も大学に入らなければならないのですが、いろいろ考えた結果、工学の方に進みたいと思っています。」
「工学にもいろいろあるじやないか、造船、建築、冶金、機械、応用化学、電気など。」
弦斎は小説家であるが、工学の知識もゆたかであった。
「はい。」
弦斎はしばらく考えていたようだったが、きっぱりとした口調でいった。
「浪平、電気はいいぞ。これからは電気の世の中だ。間もなく日本国中電灯がつくだろうし、機械だって電気で動かす時代が必ずくる。これからは電気の世の中だ。」
弦斎の答えは明快でめった。
「京都では近いうちに、町中を電車が走るということだ。」
弦斎はいろいろな事を知っている。その物識りに浪平は舌をまいた。
(よーし、電気をやろう。)
その日、浪平は自分の進む方向を決定した。
夕食に牛肉をごちそうになり、暖かい春の宵の道を歩きながら、浪平は寄宿舎に戻った。 |

浪平は弦斎の勧めで工学の電気の道へ進む決断をした
|
自分の将来がはっきりしたようで、浪平の心は明るく、軽かった。
それから二年後の明治二十九年(一八九六年)九月、浪平は東京帝国大学工科大学電気工学科に入学した。
母チヨ、兄儀平はもちろん、弦斎夫婦も心から喜んでくれた。
日立製作所を創業して三年目の大正元年、(一九一二年)村井弦斎(げんさい)夫婦は、浪平の招待で日立鉱山を見学している。
こうした浪平と弦斎との、兄弟のような師弟のような交わりは、弦斎が死ぬ昭和二年(一九二七年)まで、明治、大正、昭和と三代四十五年間続いた。
弦斎が死んだあとも妻の多嘉(たか)の事には、自分が死ぬ昭和二十六年(一九五一年)まで、なにくれとなく気を使った。
4 大黒屋会談まで top
大学へ入学してからの一年間が、アッという間に過ぎていった。
明治三十年(一八九七年)七月七日は進級試験結果発表の日である。
勉強はそっちのけにして、小説を読み、活動写真を見、写真の撮影や引き伸ばしなどにうつつをぬかしていたので、まん中より上での進級は、初めから思ってもみなかった。
七日は朝からよく晴れた、夏の暑い朝であった。
浪平は学校の道を、ゆっくりと歩いていった。
道のそばの家ののきばには、短ざくや星や輪かざりをつけたささだけが飾ってある。
「今日は七夕だったんだな。」
浪平は故郷合戦場の、青い水のような夏の夜空にちりばめられた、無数の星をふっと思い出した。
と同時に、自分の進級、卒業を待っている母チヨ、兄儀平の顔が、心の中をサッと通り過ぎた。
男の子が二人、小さな笹(ささ)だけを持って、「勇敢なる水兵」を歌いながら、かけてゆく。
煙も見えず 雲もなく 風もおこらず 浪立たず
鏡のごとき 黄海は くもりそめなり 時の間に |
一昨年日本が勝った、日清戦争中の歌である。
浪平は学校の門を入った。
校舎の壁に、学生の名簿がはってある。
浪平は氏名を順々に見ていった。
浪平の顔から血がすっとひいた。
“△ 小平浪平” とある、落第であった。
下宿の丸山館に帰る途中、浪平の頭の中で亡き父惣八と母チヨの顔が、ぐるぐるまわりながら入り交じった。
父がもし生きていたら、
「一回、二回の落第で失望し、あわてふためいてはいけない。わしなどは何回事業に失敗しても、最後の成功を信じて生きたのだ。」というかもしれない。
しかし母はちがう。
合戦場や栃木の町の人に息子の自慢をしてきたのだから、母は面目丸つぶれの苦しい立場に立つであろう。
その晩、浪平はあれこれ思って、朝の一番どりが鳴くまで眠れなかった。
次の日の朝がきても、浪平の心と足は、故郷合戦場の方へは向かなかった。
このささくれたイライタ気持ちのまま、思い悩んで母や兄に会うのは、どうしても嫌であった。
浪平は今までの生活を根こそぎぶっ切ろうと、七月十日千葉の海岸へ思い切って出発した。
サンサンと輝く夏の太陽を体いっぱいにあびながら、浪平はすべてを何もかも忘れて水泳をした。
「今度こそ、進級試験に合格します。お母さん、お兄さん、すみません。」
帰りの汽車の中で浪平はつぶやいた。
千葉から東京へ帰ると、母から一通の手紙が来ていた。
「進級試験の結果はどうでしたか。一日も早く帰る事を、母も儀平も待っております。」
という文面であった。
浪平はやっとの思いで上野発午前五時の列車に乗り、合戦場の家へ帰った。
母や弟の陳平、妹の満舞などが迎えてくれた。兄はまだ銀行から帰ってこない。
「進級試験の結果は……。」
母がそこまでいった時、浪平は母の言葉をひったくるようにしていってしまった。
「駄目でした。ごめんなさい。」
「そう、駄目でしたか。」
母はガクンと肩をおとした。
「私が買うのを許した、写真機のせいではないでしょうね。」
さすがに母親だけあって、浪平の心を見透かすような言葉であった。
浪平はドキンとした。
「九月からはしっかりやりなさい。」
「はい。……一生懸命にやります、必ず。」
浪平は頭をさげた。
夕方遅くなって、兄の儀平が帰ってきた。
三年前結婚した妻との仲がうまくいかないこともあってか、儀平は機嫌が悪かった。
母や浪平のふさぎこんでいる様子を見て、儀平はすべてがわかったらしい。
「浪平、俺が医者の道を断念して、田舎町の下っぱ銀行員になり下がり、他人の札束を数えているのは、誰のためだと思うんだ。そのお前が落第したなんて、はずかしくて誰にもいえないじゃないか。
この間の手紙にもあったが『青木堂で飲んだチョコレートはうまかった』とか『写真撮影旅行に六日もいった』とか、お前、何のために大学へいってるんだ。
大学は学問をする所なんだ。遊びほうけるために、俺は仕送りしてるんじゃない。……」
「兄さん、許してください。これからはきっと……。」
激しい兄儀平の言葉に、浪平はうなだれるだけで一言も弁解をしなかった。
浪平が明治二十六年(一八九三年)から書き始めた日記(晃南(こうなん)日記と浪平は名付けた)は、ちょうど落第して合戦場に帰った明治三十年(一八九七年)七月二十六日で終わっている。その日の日記の後に、浪平は次のような文章を書いている。
「ああ晃南生、(浪平のこと)この晃南日記の筆者は明治三十年七月二十六日をもって死す。
好意をもって彼を待っていた家族も反目するに至った。 彼(浪平のこと)は木石ではない。
一言の弁解があるはずだ。しかしそれをいう気持ちはない。その言が信じられない事を知っているからだ。」
叩きのめされて苦しむ浪平の心情のゆれ動きと、一言の弁解もしない男らしさとが入りまじって、読む者の心に食い入る文である。浪平の一番苦しい時期でもあった。
また同年八月に自分で書いた「雲煙過眼録(うんえんかげんろく)」の中の小論文の中で、進級試験を批判し、模倣で満足する限り、日本の工業は論ずるに足らずと、読む人の心をグサリと刺す強烈な口調で言いきっている。
進級試験批判と落第とは、浪平にとっては避けて通ることができない、二つの関門のような気がしてならない。 |

浪平は日記を書いていた。そこには
遊びほうけて落第した自分の反省が記されている。
|
学問の理想は、発明と創造にあると考えている浪平にとって、大学の進級試験は今まで学習した知識や技術をなぞるようなもので、どうしても不満だったのだろう。
しかし文中で母や兄の事にもふれ、再出発の九月からぱ学科の成績をあげ、母や兄の期待に応える決心をしている。
また自分のこれからやりたい研究として、「電信試験法」「化学上の電気の作用」「機械製造法」をあげ、自分は自分である事を貫きたいといっている。
これらを読んでいると、落第した頃の落ちこんだ気持ちから少しずつ解放されて、やる意欲がふくらみ始めたのがわかるのである。
「落第がなんだ、必ず進級してやるぞ」
次の年明治三十一年(一八九八年)七月、浪平は七番の成績で無事二年に進級した。
そして二年後の明治三十三年(一九〇〇年)七月、浪平は東京帝国大学工科大学電気工学科を、十一人の友だちと一緒に卒業した。心配をかけたチヨ、兄儀平の祝杯をうけて。
浪平の卒業は小平家にとって、ポッと灯りがともった感じであった。
浪平二十六歳の夏である。
大学を卒業した浪平の就職先は、秋田県鹿角郡にある藤田組小坂鉱山に決まった。
なぜ浪平は、東京から遠い秋田県の山の中の鉱山へ、いく気になったのだろうか。
その原因の一つは、その頃鉱山の仕事は上り坂時代にあり、最も進んだ技術が入っていたこと、二つ目は地味で堅実、几帳面な浪平にとって、都会のめまぐるしさや華やかさは、肌に合わなかったのかもしれない。
さて、社会人となるためには、大学時代の詰襟の服ではどうにもならない。
浪平は大学のそばの洋服屋で服をつくった。
服は七十五円だったが、ワイシャツやネクタイなどを入れると、なんだかんだで百円近くの金になる。
浪平はその代金を、月賦にしてもらった。
九月の初め、浪平は東京を出発した。
上野〜青森〜大館まで汽車で行き、大館から九里(約三十五キロメートル)の山道を、人力車にゆられてのぼっていった。
山はもう秋で、赤とんぼがとび、すすきが風にゆれていた。
鉱山の事務所では、所長の久原房之助と東京帝国大学工科大学冶金科を前の年卒業し、小坂鉱山に入った竹内が待っていた。
「よく来てくれた小平君、こんな山の中まで。」
久原はいかにも鉱山の経営者らしい、顔も体も堂々とした、スケールの大きい男だった。
「よろしくお願いいたします。」
浪平は久原に挨拶をしてから、かたわらの竹内にも礼をした。
竹内は浪平と同じ明治七年(一八七四年)生まれであるが、大学を三年で卒業したから、一年早く小坂鉱山に入ったのである。
竹内は大学時代から秀才のはまれ高く、卒業論文の「白溶精錬法」の理論は、小坂鉱山で実地にテストし、成功している。 これが小坂繁栄の元となった。
竹内は久原とは対照的で、いかにも頭のきれそうな男であった。
久原三十一歳、浪平と竹内は共に二十六歳であった。
小坂鉱山は事業の拡張にともない、できるだけ早く発電所を建設する必要があった。
「君には大湯の止滝に発電所をつくってもらいたい。君ならできる。」
久原は向こう見ずな性格なので、いうこともてっ取り早い。
「職名は技士兼工作課電気係長、月給は七十円としよう。」
間もなく浪平は大湯川の上流にある止滝へ向かった。
止滝は小坂よりもっと山の中で、太古の自然がそのまま残っている風景を見て、浪平はここで新しいものを作る喜びに燃えた。
工事は三つあった。
一つは水力工事、二つ目は電気工事、三番目は送電路線工事である。
それに使う水車、調速機、発電機、励滋機、変圧器等は、すべてアメリカ製であった。
当時としては、それが当たり前であった。
止滝発電所は二年後の明治三十五年(一九〇二年)の五月、試運転を始めて成功し、十一月には正式の運転を開始した。
銚子と止滝の二つの発電所を並行運転して、一一、〇〇〇ボルト、六五〇キロワットの電力を一六・五キロメートル送電したのである。
しかし浪平は、成功の喜びにひたりながらも、心の中のどうにもならない不満を、かくすことができなかった。
学生時代からの考えである、外国の真似でなく、どんなに苦しくても、自分たちが使う物は自分たちで作る考えを、捨て去ることはできなかったのである。
明治三十七年(一九〇四年)浪平は久原が小坂鉱山を下山したのを機会に、会社をやめ東京へ戻った。
同年五月浪平は、大学の親友小室文夫の妹也笑(やえ)と結婚した。
也笑との生活は、浪平が死ぬ昭和二十六年(一九五一年)まで四十七年続き、百合子、富美子、良平、俊平の二女二男をもうける。(富美子は六十二日で病死)
浪平は一年間広島水力電気会社にいた後、明治三十八年(一九〇五年)五月十日、東京電灯株式会社に入社するため上京した。
東京の家に戻ると、広島から「女の子が生まれた。」という電報が着いた。
男の子なら浪平の平をとって良平、女なら百合子という名前を考えていた浪平は、早速百合子と命名し、広島の也笑(やえ)に伝えた。
「俺も父親になったのか。」
浪平は仕事とは別の、暖かい心のうねりを感じた。
浪平の東京電灯での仕事は、山梨県桂川の水を利用する、駒橋水力発電所建設の大工事であり、浪平が手がけた小坂の止滝発電所などは、くらべものにならないくらい規模が大きかった。
この年は日露戦争が終った年であり、電灯を始めとして、電力の需要は日増しに上昇していたので、東京電灯としてはそれに応えるため、どうしても大型の水力発電所を建設しなくてはならなかったのである。
明治三十九年(一九〇六年)一月、駒橋水力発電所の工事が始まった。
七月十五日、浪平はこの仕事をするため、東京飯田橋発甲府行の列車に乗った。
発車間際車内にあらわれた青年紳士を見て、浪平は驚いた。大学を一緒に卒業した渋沢元治であった。
「おう、渋沢。」
「小平か、しばらくぶりだな。」
「いつ外国から帰ってきたのだ。」
「今年の一月だ、今は逓信省通信局の電気試験所に勤めている、今から駒橋へいくのだ。君は。」
「東京電灯の駒橋水力発電所の仕事をしている。」
「そいつはすばらしい仕事だ、電気科を卒業した者の夢じやないか。」
激しい雨が、窓ガラスをたたきつけるようにして降っている。
渋沢元治の伯父渋沢栄一は、第一国立銀行の頭取をした後、日本の産業界、財界で活躍している大立て物であった。
元治はこの伯父のお供として、明治三十五年(一九〇二年)アメリカへ渡り、次いでイギリス、ドイツへ行ったが、その後一人でスイス、イタリア、フランス、イギリス、アメリカを回って水力発電の研究などをして、明治三十九年(一九〇六年)一月帰国した。
車内での二人の話は、外国生活のこと、小坂鉱山のことと続いている。……
と浪平が、思いつめたような顔で話をきり出した。
「渋沢、少しばかり話したいことがある。猿橋で下りないか。近くに大黒屋といういい宿屋がある。」
「よかろう、今日はこの雨で仕事もできないから、ゆっくり話を聞こうじやないか。」
渋沢が答えた。
二人はその夜、猿橋の大黒屋に泊った。
夜になって雨もあがった、そのせいかひんやりした涼しい夏の夜であった。
「渋沢、小坂鉱山で世話になった久原さんが、茨城県多賀郡にある赤沢鉱山を買い、今年の一月から日立鉱山と名前を変えて仕事を始めている。ここへ来ないかという誘いを受けたんだ。電気関係の仕事をしてくれとな。」
「じゃあ東京電灯の今の仕事を辞めてか。」
「まあそういう事になるか。」
「それは考えもんだな、水力発電はこれから益々発展する仕事でもあるし、日本の国力もそれによって大きくなるじやないか。」
雨のため水かさを増した桂川の水音が、二人の耳を打つ。
「それはよくわかっている。しかし、水力発電の工事といっても、機械はすべてあちらのものだろう。
発電機と地下ケーブルはシーメンス、変圧器はジェネラル・エレクトリック、水車はエッシヤウイス、それに向こうから技師も来るんだ。
日本人はいわれた通り、据え付けるだけなんだ。」
「それはそうかもしれないが、自分でつくるというのは、そう簡単ではないぞ、小平。
外国を歩いてくるとわかるが、あちらは大分進んでいるからな。」
「僕はこの手で自分で自分の使う機械器具をつくりたいんだ、そのために日立鉱山に行くつもりだ。」
「鉱山だって電気の機械はみんな外国製だろう。せいぜい修理するぐらいが関の山じゃないか。」
「始めは修理でもいいと思う。しかしいつの日か、自分で作りたいんだ。」
二人の話は夜遅くまで続いた。
雨があがり、夜空には星が光っていた。
「いつの日か……。」
浪平は心の中でつぶやいていた。
top
****************************************
|