|
****************************************
Index 1
2 3
4
4 織機王、佐吉
1 六十台の愛機 top
動力織機の試運転は、成功でした。これをどう売りだすか、どう使うかというとき、都合のいい協力者が現れました。
石川東八さんです。
東八さんはふとしたことから、佐吉の動力織機を目にして、すっかり惚れ込んでしまっていました。
「佐吉さん、二人で織物工場をやりましょう。あんたの、その織機を使って。」
藤八さんが工場を建て、佐吉は六十台の織機を製作する。会社の名は『乙川綿布合資会社』にしようというものでした。
藤八さんは、名古屋の南の乙川村のはた屋でした。かせくり機もたくさん買ってくれた人で、佐吉とは顔なじみでした。
「やりましょう。やらせてください。」佐吉にとっては、願ってもない話です。
佐吉は東京で工場をやり、初めはいい評判をとりました。
今度も立派な織物を、ドンドンと作り出せば、動力織朧のすばらしい広告にもなるはずです。
それにしても、またたくさんの借金をしてかからねばなりません。
六十台もの織機を製造し、それが働き始めるまでですから、かなりのものになりそうです。
けれども、今度は見通しの明るい借金です。浅子と相談し、吉津村へ行って、なんとかよせ集めてきました。
佐吉は全力をあげて、織機作りにかかり、できあがるあとから、三台、五台と、乙川村へ送りました。
乙川では弟の平吉が、藤八さんと力をあわせて、工場づくりのさしずをしていました。
一年たった夏、乙川に立派な工場ができあがりました。織機も、六十台がせいぞろいしました。
動力は、蒸気機関です。佐吉が、豊橋で手に入れた中古品でした。新品のほしいところですが、金が不足でした。
古いので我慢するほかなく、据え付けなどにかなり苦心しました。
いよいよ試運転の日がきました。すべての機械には、糸がかけられ、動きだすばかりです。
「さあ、いきましょうか。」佐吉が合図を送りました。
うなりをあげていたボイラーの蒸気が、機関へ送りこまれていきました。
ベルトが周り、織機はいっせいに活動を始めました。
成功です。すべてうまく動いています。
カチャ、カチャ、カチャ、カチャ……。
規則正しい音をたて続げる六十台の愛機。佐吉にとっては、六十人のかわいい子供そのものでした。
これまでの長いあいだの苦しみ。その一つ一つが、いまは記念の思い出となって、佐吉の胸によみがえっていました。
こうして、愛知県の田舎の乙川村で、日本製の動力織機が、初めて布を織り始めました。
一台が、これまでの織機の四倍以上の働きをしました。織りの具合も、申し分のない出来栄えでした。
2 外国機との競争 top
動力織機は、たくましく活動を始めました。しかし、まだ木製です。
なるべく早いうちに、これを鉄製にしたいものです。
しかけにも改良をくわえて、もっと働きのいいものにしたいものです。
そして、外国機との競争です。佐吉の夢は、次から次へと、大きくふくらむばかりです。
乙川工場の織物は、どれもそろっていて立派です。
それに目をつけ、たくさんの注文をよこした会社があります。
三井物産といい、その頃の日本では、指おりの大きな会社でした。
三井物産が認めたというわけで、この織物をつくった佐吉の動力織機は、急に有名になりました。
佐吉は、名古屋の豊田商会をほかへ移して、大きくし、動力織機の製造と研究とに、かかりきる事にしました。
佐吉にすると、織物を作る工場よりも、織機の改良、研究のほうに、やりがいを感じていたからです。
それで乙川の工場は、藤八さんにゆずってしまいました。
佐吉はいくつかの部分を、次々と改良し、使いやすく、能率があがるようにしました。
それに木製では故障が多いので、歯車とか軸など、大切なところから、しだいに鉄におきかえていきました。
それから動力として、石油発動機が使えるようにしました。
蒸気機関を動力にすると、小さな工場などでは、しかけが大きくなりすぎるし、費用も多くかかるからです。
石油発動機だと、小型で場所もいらないし、手軽に据え付けられます。
これで、動力織機を使うところが、グンとふえました。
織機をよりよくした事で、特に大きいのは、縦糸の送り出しについての発明です。
布を織りすすんでいくにつれて、自動的に縦糸が送り出されてくる仕掛です。
また、横糸が切れたり、なくなったりしたとき、人が機械を止めて、つないだり、碑(ひ)を取換えたりしなくとも、ひとりでに新しい碑(ひ)とかわる仕組みも発明しました。
これらは、世界に自慢できるすばらしい発明です。
このほかに、佐吉が改良していった点を数えあげたら、きりがありません。
環状織機という、変わった織機の発明にも取組みました。布が、丸い筒の形に織り出されてくるものです。
横糸をもった碑(ひ)は、右、左といそがしく飛ぶ事はありません。同じ方向に、クルクル回るだけでいいわけです。
だから、動力は小さくてすむし、織るスピードもあがるわけです。
布といえば、平らに織るものと、昔からきまっていたことだし、誰もがそう思いこんでいます。
それを、筒の形に織りあげようというのです。
外国の機械が、ヒントになったものでしたが、発明王の佐吉でなければ、手を出せる事でありません。
ところで、佐吉の長いあいだの念願だった事、外国の織布機械との競争ですが、一九〇五(明治三十八)年に、最初の機会がやってきました。
鐘ヶ淵紡績という会社で、豊田式と、イギリス。製、アメリカ製のものとを、一年間使いくらべる事になったのです。
豊田式五十台に、イギリス、アメリカ製あわせて六十台を、様々な点から、成績くらべをするのです。
佐吉は、最も新しい織機をそろえて、競争に参加しました。
重要なところを、鉄におきかえた「三十八年式」とよばれるものです。佐吉には、おちつけない一年間でした。
結果は駄目でした。イギリスのプラット社のものに、かないませんでした。
佐吉は残念がって、敗れた原因をいろいろと調べました。
急いで作った織機だったために、具合の悪い点があったのは確かでした。
ほかに織工さんが豊田式になれていなかった事、糸の質が悪かった事などもわかりました。
外国機との競争に負けたといっても、豊田式は使いやすく、ほかにもいい点がたくさんあったので、売れゆきはのび続けました。
二度めの競争は、三年あとになりました。今度は事情があって、佐吉は自分の手で行いました。
名古屋の菊井町に、試験工場を建て改良をくわえた新織機百台をそろえました。
競争相手は、もちろんプラット社です。
弟の平吉が、審判長というか、監督にあたりました。
今度は見事に勝ちました。
自分の手でやったからではなく、最初からいい成績で、日がたつにつれて、プラット社を引き離すばかりでした。
だから、完全な勝利といえます。
「外国の機械に負けないものを作る。」
長いあいだの願いが、自分の力で、ようやくはたす事ができました。
これからずっとあとになりますが、プラット社では、外国へ織機を売るのに、豊田式を扱わせてほしいといってきました。
佐吉の機械のすばらしさを、プラット社でも認めたわけでした。
動力織機をつくりあげてからの佐吉は、すべて順調だったかといえば、そうではありません。
一つの発明に、そうとう長いあいだ苦しんだ事もありましたし、腹だたしい出来事も、何度かありました。
研究費を使いすぎるという理由で、会社の重役をやめさせられた出来事も、その一つです。
『豊田式織機株式会社』の名でもわかるように、佐吉の力でできたといっていい会社でした。
佐吉は研究費を、おしまずに使うほうです。
よりよい織機にするためには、そうしなければならないし、その事が会社のためにも、また、大きくいえば、日本のためになるという考えです。
ところが社長たちは、研究に金を使いすぎて、会社のもうけが少なくなっては困るというのです。
数年前にも佐吉は、同じような理由で、『井桁商会』という会社を、自分からしりぞいてしまっています。
会社がもうかればいいのだ。そのためには、会社にとってもっとも大切な人の、首切りまでする。
そのあくどさ、えげつなさに、佐吉はがっかりもし、また、腹をたてて、アメリカへわたりました。
アメリカで発明を続け、せまい考えの人が多い日本には、もどるまいとさえ思いました。
しかし、アメリカへ行き、そこの織物工場などを見学した佐吉は、考えなおしました。
やっぱり日本へ帰って、日本の織機をよくする事に力をつくそうと――。
佐吉はほどなく、名古屋に『豊田自動織布工場』をつくり、工夫を加えた新しい機械をそろえて、再び仕事と研究とにかかりました。
佐吉が、人力織機に成功したのが一八九〇年、動力織機を発明したあと、改良に改良をくわえ、ほぼ完成したのは一九二六年です。三十五年間、これにかかっているわけです。
佐吉はいくつかの会社、工場で、動力織機の製造と販売にあたっただけでなく、それを働かせての織物づくり、あるいは紡績などにも力をそそぎました。
これによって、私たちの衣生活が大変豊かになっただけでなく、輸出の花形ともなって、日本に力をつけることとなりました。
3 佐吉、その人柄 top
佐吉は、織機王とか発明王とかよばれるようになっても、見栄をはるとか、気どるなどという事が、全くありませんでした。
お母さんが病気になったとき、佐吉はすぐに吉津へ行って、看病にあたりました。
毎朝、病院へ薬をもらいに行く役目を、佐吉が引受けました。
ある朝、お母さんにおいしい魚を食べさせようと、病院からの戻りに、魚屋へよりました。
魚屋は寝間着姿の佐吉を見て、金を持たない年寄りとでも思ったらしく、魚がないと断りました。
そこへ人力車ひきが通りかかり、佐吉を見て、ていねいな挨拶をしました。
それで魚屋も、目の前の寝間着姿の年寄りが、有名な豊田佐吉とわかり、あわてて奥から、特別いきのいい魚を持って来ました。
旅行に出ても、自分だけの場合は、貧乏時代のときと同じで、見すぼらしい宿を選んでとまりました。
和服に角帯姿。社長となっても、身なりはごく質素で、下駄が好きでした。
そのかっこうで、機械いじりもするのですぐよごれます。すり切れもできます。
浅子がつぎあてをしてくれたのでも、平気で着ていました。
ついでに浅子の事をいえば、結婚してから、お母さんにかわって、佐吉を支えてきたのは、浅子でした。
佐吉は、発明だと寝る事も忘れて夢中になりますが、ほかの事では全く無頓着でした。
金のやりくり、会社の仕事をテキパキとすすめること。浅子にはそれをうまくこなす力が備わっていました。
だから佐吉には、うってつけの妻だったといえるでしょう。
研究室のストーブに、佐吉が自分で火をつけてやる事もあります。周りの者がすまながると、
「いいんだよ。君たちはわしのために研究をしてくれているんだ。ストーブくらいたかないと、すまないじゃないか。」
と、笑いとばします。
工員なみの作業も、しばしばやりました。あるとき、機械の下へもぐりこんで、油だらけになって、仕事をしていました。 そこへ、一人の工員が来てたずねました。
「おい、そいつの調子はどうなんだ。」
返事がないので、のぞきこんだら佐吉ではありませんか。
工員はてれくさがって、その場から逃げ出してしまいました。
汽車の中で図面描きに夢中になって、降りる駅を忘れてしまい、何度も行ったり来たりしたとか、宿屋に泊っても、夜中に起きだしてゴソゴソするので、あやしまれてしまったとか、佐吉の研究熱心を語る話は、キリがないほどです。
佐吉が何時に寝るのか、浅子もしらないくらいでした。
それでいて、朝はだれよりも早く起きて、研究室へ行きます。
夜通し、図面描きですごしたある朝、明るくなるのをまっていたように、できた図面をもって、工場へ飛びだして行きました。
工場には、人影が全くありません。
「おい、誰もいないのか。」
あとを追ってきた浅子がいいました。
「あなた、きょうは元日なんですよ。」
佐吉の頭には、ぼんも正月も、なんにもなかったわけです。
負けずぎらいのエピソードも、たくさんあります。ある晩、大きな台風におそわれました。
いまほど予報がゆき届いていませんから、いきなり強風がふきはじめたわけです。
二階に寝ていた長男の喜一郎が、用心のために、みんなを起こしました。佐吉がいません。
下へおりたら、佐吉は、ギシギシゆれる柱につかまっています。。
「お父さん、どうしたんですか。」
「いや、なに、風のあたる柱のゆれ具合を、研究してるところなんだ。」
負けおしみもいいところです。
また、アメリカの飛行機が、世界一周の途中、日本の霞が浦へよったときです。
「日本の飛行機で、日本が世界一周をやるのだったらなあ。」と、佐吉はひどく口惜しがったともいいます。
|
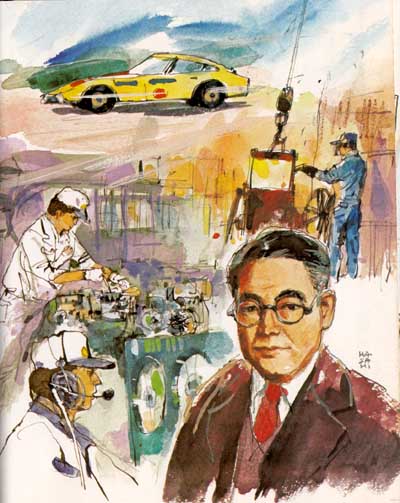
佐吉は、これからは自動車の時代なのに日本の自動車工業が、
ひどく外国より遅れていると、以前から気にしていました。
|

|
4 トヨタ自動車 top
私たちは、トヨタというと、豊田織機のほか、もうひとつの言葉が頭に浮びます。トヨタ自動車です。
この会社を興すきっかけをつくったのも、佐吉でした。
佐吉は、これからは自動車の時代なのに日本の自動車工業が、ひどく外国より遅れていると、以前から気にしていました。 佐吉が取組んだ織機と同じです。
このために、自動車を買う金が、どんどん外国へ流れ出ています。
一九二七(昭和二)年、名古屋で天皇にお目にかかった帰りでした。
自分の乗った自動車の窓から見ていると、外国製の自動車だけが目につきました。
佐吉は家に帰ると、喜一郎をよんで話しました。
「喜一郎は、日本の自動車を作る仕事をやったらどうかね。わしは織機で、日本のために働いてきたつもりだ。
自動車もやりたいのだが、もう年で、手が届かない。かわりに、おまえがやってほしいのだが。」
喜一郎は口数が少なく、おとなしい人でしたが、発明、発見といった点では、父の血を受継いだところがありました。
喜一郎は、父の言葉に従って、会社に自動車部門をくわえ、国産車の製造研究を始めました。
一九三六(昭和十一)年、乗用車とトラックの第一号車が、それぞれ誕生しました。
トヨタ自動車はこれを受継ぎ、大きく育ったものです。
佐吉は残念な事に、この第一号車を見る事はできませんでした。
織機王、佐吉は、それより六年前の一九三〇(昭和五)年に、病気でなくなっていました。六十三才でした。
佐吉の最後の夢は、「自動車をやりなさい」と喜一郎に頼んだ国産車の誕生であったと思われます。
top
****************************************
|