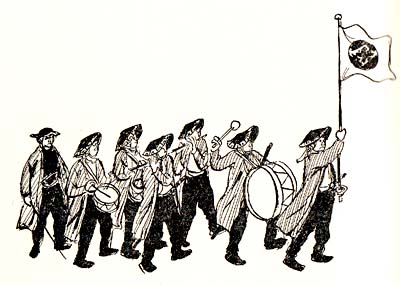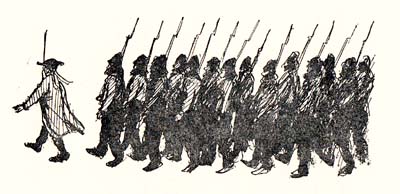|
****************************************
Index 江戸から東京へ(その一 その二 その三 その四 その五)
|
江戸から東京へ(その一)
1 おわれる幕兵
①張本人は、お城のなかに!
②陣羽織とゲーベル銃
③武士の隊と、百姓・町人の隊 |
2 世直しの人々
①たちあがった大工たち
②飯能の川原のあつまり
③世直しだ、思いしれ
④ひきだされた大砲
3 フランス公使ロッシュと将軍慶喜
①新任のフランス公使
②改革の意見
③フランスの軍服 |
1 おわれる幕兵 top
① 張本人は、お城のなかに!
カラカラと、いそがしそうに荷車かとおります。槍や小銃をかついだ兵士の一隊がとおります。
一八六六年(慶応二年)五月初めの大阪の町は、二度めの長州征伐のために動員された諸藩の軍隊で混雑していました。
岡山藩の下級役人、松原弥太郎は、そんな大阪の町を歩いていました。
二十歳になったばかりの弥太郎は、大きく動いている日本の姿を、どうしても自分の目で確かめたかったのです。
弥太郎は、大阪城にちかづきました。
天守閣こそありませんでしたが、大阪城は、弥太郎がいつもみなれている岡山の城とに、くらべものになりません。
高く、美しく、堂々としていました。
――公方さま(くぼう、将軍)が、いま、このお城にきておられるのだ。――
弥太郎は、深いほりと石垣にかこまれた巨大な城をみていると、
「ご公儀(幕府のこと)が倒れるなんてことが、あるのだろうか」という思いがわきあがってきました。
高麗橋(こうらいばし)のたもとまでくると、人だかりがしています。のぞいてみると、貼紙がしてありました。
「おそれながら、今すぐ私たちを殺してくださるか、米の値段を三百文ばかりに下げてくださるか。
二つともできなければ、上町(かみまち)をはじめとして、市中を灰にいたしましょう。
ご返事をうけたまわらせてください。
ご老中さま 難渋者より」 |
「ぶっそうな貼紙をしたものだなあ。」
弥太郎がつぶやくと、そばにいた職人風の男がいいました。
「なにがぶっそうなものか。長州征伐かなにかしらないが、人殺しに血道をあげよって、 大阪で人間のひぼしをつくる公方さんのほうが、よっぽどぶっそうやないか。」
すると、人足風の男が、
「そうとも、去年の暮れには、高い高いといいながらも、米一升が三百五十文で買うことがでけた。
ところかどうや、半年後の今じゃ七百文もするのやで。
ガキは腹をへらして泣くし、かかあはおこるし……。」
「そこで、公方さんが、おまえんとこのかかあと戦争にござったというわけだ。
貼紙をとりまいている人々が、ドッと笑いました。
「あほなこというな。
でもなあ、おてんとさま(太陽)と米の飯はついてまわるというが、公方さんが大阪へいらはってからは、おまんまのほうが姿をけしてしもうた。」 |
 |
「そのうち、おてんとさまのほうも消えるんとちがうか。」
その瞬間、弥太郎の胸に、田のなかで泥まみれになって働いている父母の姿が、うかんできました。
袮大郎も、もともと米をつくっても、米の食べられない、三反百姓の子だったのです。
「米屋じゃお米が売りきれや。公方さんじゃご政道(政治の方針)が売りきれやー。」
うしろのほうにいた飴屋が、とっぴょうしもない声で、うたいだしました。
――ここにも、世直しをねがっているおおぜいの人がいる。――
はなやかな大阪の町に、こうした人たちがいるとしったことは、弥太郎にとっては大きなおどろきでした。
宿屋にかえって、弥太郎が高麗橋でみたことにふれると、宿屋の亭主は、ひざをのりだして話しはじめました。
「ええ、そりゃもう大変でございますよ。あれは去年の暮れからでございますなあ。
長州再征(第二次長州征伐)とやらで、大阪に三万もの軍隊がやってきましたんや。
そうでなくても、近年は不作つづきでお米が高うございまっしゃろ。
そこへ大軍がやってきましたのやから、たまりまへん。
米の値をはじめ、品々の値段がうなぎのぼりにあがる一方ですわ。
それに、いまは麦のとれるまえ。半年で二倍以上になりました。
なにか悪いことがおこらんかったらええのに、とねがっとります。」
「しかし、戦争景気でお店持ちの商人衆は、うんともうけていなさるのだろう。」
「とんでもありまへん。そりゃもうけている人も、すこしはありまっしゃろ。
そやけど、お客さん。今度の長州征伐だって、大阪の町に七百万両もの御用金を、命じなはったのでござりますよ。
町人一戸あたりにして、三百両から二十万両まで、これだけだせばどんな金持ちでもたまりまへん。
それも、この数年のうちに四度め。大阪の町人はみなお上をお怨みもうしておりますよ。」
亭主は小さな声でしたが、きっぱりといいました。
その翌日、ついに兵庫の湊川(みなとがわ、神戸市内)から米の安売りをもとめて、打ち壊しがおこりました。
米の買占めや売りおしみをする米屋におしかけた民衆は、米の安売りが聞き入れられないと、米蔵の戸をたたきこわして、米だわらを運びだしたり、家と道具を打ち壊したのです。
取り締まりにやってきた役人は、こえをからしてさけびました。
「しずまれ! 公方さまも大阪城においでのことだ。長州征伐がいまにもはじまろうとしている、大切なご時勢をわきまえろ。しずまれ!。」
しかし、飢え死に一歩てまえまでおいつめられた民衆が、耳をかすわけはありません。
「わしたちのおまんまは、どないめんどうみてくれるんや。」
このことばに答えるように、「ダン、ダン」というはげしい銃声がおこりました。
役人が飢えた民衆にむけて発砲したのです。数人が死に、数十人かきずをうけました。
湊川にひびいた銃声は、日本の経済の中心であった、大阪湾沿岸一帯に、すさまじい打ち壊しの津波をまきおこす合図となりました。
兵庫の民衆は、いったん追いちらされましたが、その後も数日のあいだ、市内のあちこちに集って騒ぎ、それはたちまち、西宮・伊丹・池田などの町々にひろがっていきました。
将軍が滞在している大阪市中で、打ち壊しがはじまったのは、五月十三日の夜のことです。
市中と郊外の福島・九条・難波などの村々で民衆、かたちあがり、翌十四日には、雨のなかを、群衆が米屋におしかけて、七百文の米を、二百文で安売りするように要求しました。
弥太郎があとできいたところでは、おそった家は八百八十五軒、安売りさせた米は四千石におよんだということです。
打ち壊しの最中、幕府の役人はどうすることもできず、ただ手をこまねいているばかりでしたが、騒ぎが下火になってから、だれかれのべつなく、あやしいとみればひっとらえました。
けれども、とらえられたものは、すこしも役人をおそれずに、うそぶきました。
「こんな世の中じゃ、生きておるかいもないわい。さあ、殺してもらおうやないか。」
「とらえてくれておおきに。牢屋にはいれば、三度のおまんまにありつけまっからな。今晩のめしが楽しみやで。」
奉行所の白州(しらす、罪人の取調べをするところ)で、いかめしい顔で役人が、
「発頭人(張本人)は、いずこのなんというものか、ありのままにもうすのが身のためだぞ。」
ときくと、彼らは口をそろえていいました。
「張本人は、お城のながあるのとちがいまっか。」
お城のなかにいたのは、十四代将軍徳川家茂(いえもち)だったのです。
打ち壊しのおさまった翌日、弥太郎は岡山の同志で、先輩にあたる浅次郎に、つぎのような手紙を書きました。
「ご公儀から人心のはなれていくありさまは、日に日にはっきりしています。
公方さまのおられる大阪城は、ほりはふかく石垣は高く、それを数万の軍勢がまもっていますが、このたびの打ち壊しのまえには、なんの役にもたちませんでした。
このようすでは長州征伐がはじまれば、その最中に百姓・町人が一時にたちあがることになるかもしれません。」
② 陣羽織(じんばおり)とゲーベル銃
弥太郎からの手紙をうけとってまもなく、小原浅次郎は、岡山藩の命令で、広島にむかいました。
長州征伐のようすをさぐるためです。
浅次郎の身分は、台所の下ばたらきというひくいものでしたが、尊王攘夷運動十年の経験があるので、長州藩や広島藩にも知合いがおおく、この役目にはぴったりでした。
広島の城下は、弥太郎からしらされた大阪の町以上に、みだれているようでした。
けれども、町には、大阪のような活気がみられません。
長州征伐のため、町にはいってきた幕兵たちは、ひるまから酒をのんで、わめいたり、けんかをしたりしています。
広島の町人も武士も、そのありさまをにがにかしげにみながら、そしらぬ顔をしてとおりすぎていきます。
征長軍の本営のある国泰寺(こくたいじ)に出入りする、幕府軍の指揮官の顔も、さえません。
それもそのはず。弥太郎の手紙にあったように、民衆の心は幕府からはなれ、大名たちも、財政が苦しいことを理由に戦争に反対しているのに、幕府は長州征伐をむりおしにすすめていたからです。
征長先鋒総督にえらばれた和歌山藩主徳川茂承(もちつぐ)は、
「他藩はしらないが、自分の藩は戦争する気力をもちあわせていません」と幕府に進言しました。
これがすべての大名の、いつわりのない声だったにちがいありません。
幕府は、なかなか腰をあげない有力な大名に、きびしく軍勢をだせと催促しました。
浅次郎の岡山藩も、藩主は将軍補佐役の一橋慶喜の弟で、山陽道きっての有力な藩でしたが、戦争の理由がはっきりしないことをいいたてて協力を断わったほどです。
たびたび催促されると、申しわけのような軍隊を、お城から六キロメートルほどはなれた、備前一宮までだして、出兵したことにしました。そのため、岡山では、
という歌がはやりました。
そのほか、第一次長州征伐では主役をつとめた薩摩藩は、
「今度の戦争は、幕府と長州藩との、私ごとの争いだから参加しない」
といって出兵せず、四国の徳島藩も、御三家のひとつ尾張藩も兵をだしませんでした。
そればかりか、征長軍の本営がおかれ、芸州口先鋒総督を任命されていた広島藩は、
「自分の領内には、幕府の大軍がきて、食糧や物資、人夫を集めるのが大変です。
そのため民衆の怨みがいつ爆発するかわからないありさまです。」と断わりました。
幕府は全く孤立してしまい、直属の軍隊と譜代大名の力だけをたよりに、戦わなければならないはめになったのです。
六月七日、幕府の軍艦は、長州藩の国境にちかい海岸を砲撃し、大島をいちじ占領しました。
これに気をよくした幕府は、いっきに長州藩に進撃しようと、先鋒軍の彦根藩、高田藩(いまの新潟県上越市)の三千の軍勢を、山陽道の長州への入口、「芸州口」にむかわせました。
海上には二艘の軍艦が護衛しています。
広島から幕兵の出発するのをみおくっていた小原浅次郎は、
「こりゃおもしろい。いよいよいくさがはじまるで。
しかし敗けるとわかったほうについていって見物することもないだろう。」
そうつぶやくと、人ごみのなかに姿をけしました。
二日後の六月十二日、浅次郎は、長州藩の支藩の岩国城下に姿をあらわしました。
ここは広島とはちがって、町じゅうに活気があふれ、浅次郎が耳にはさんだ噂話も、自信にみちていました。
「芸州の玖波(くば、広島県大竹市内)のあたりは、敵の軍勢でいっぱいだそうだ。」
「味方の軍勢も多田(ただ、山口県岩国市内)に勢ぞろいじゃ。
遊撃隊・維新団・衝撃隊、それに岩国兵……、幕兵を一歩もご領内にいれぬ意気ごみじゃ。」
「わしも若けりゃ仲間に入れてもらうのだがのう。わしら町人が兵士として働かせてもらえる世になるうとは……。」
浅次郎は、岡山藩士と名のって、遊撃隊の本営をたずね、戦いにつれていってくれるようにたのみました。
さいわい隊長の河瀬四郎とは、京都で尊攘派として活躍していたころの知合いだったので、特別のはからいで、希望をかなえてもらいました。
十三日の真夜なか、長州軍は玖波(くば)の幕府軍に夜うちをかけようと、多田の本営をあとにしました。
河瀬四郎は、みちみち浅次郎にはなしかけました。
「小原さん、我々はぜったいに勝ちますぞ。
よくみて、お国へ報告してください。なぜだがわかりますか。
それは、この戦いは、我々にとっては領土をまもる正義の戦いですが、幕府にとっては、理由のない戦いだからです。
そのうえ、我々長州人は、武士も百姓も町人も、みんなが力をあわせて戦おうと、一所懸命になっています。
ごらんなさい。わが軍の士気を! あなたが見た広島の幕兵に、こんな士気がありましたか。」
河瀬が胸をはって話すのをきいて浅次郎は、その自信がどこからでてくるのか、確かめたいと思いました。
河瀬は浅次郎の疑問をさっしてか、はなしむきをすこしかえました。
「そりゃあ、わが軍にもいろいろなもんだいがあります。
実はさっきも、岩国藩兵にさんざんてこずらされたのですよ。
家柄の正しい武士が、維新団と一緒に戦えるかというのです。
ご承知と思いますが、維新団は、世間の人から差別されいやしめられていた人たちが中心だからです。
しかし、いくさがはじまれば、維新団のほうが、よほど役にたつでしょう。
農工商やそれよりも下の身分のひくいものほど、幕府がたおれて世の中の変ることを強くねがっているのですね。」
物見の兵の報告で、幕府軍が山陽道の九の坂(大竹市内)と、小瀬川(おぜがわ)口の和木村(山口県玖珂郡内)のふた手にあることがわかりました。
長州軍は本営を山陽道の中津原におき、九の坂をせめるとともに、別動隊を小瀬川にそって和木村にすすめました。
浅次郎は河瀬とともに、別動隊にくわわって、和木村にむかいました。
十四日、東の空がようやく白みかけたころ、突然、「ルルル………」という音がしたかと思うと、隊のすぐ後ろで、「ダダーン」と啓発の砲弾が爆発しました。
むこう岸の幕府軍が攻撃をはじめたのです。
砲撃がおわると、ひときわ大きく太鼓の音がひびきわたり、ほら貝が「ブーブー」となりました。
「ワーワー」というかん声とともに幕府軍が小瀬川をわたってせめてくるようです。
河瀬四郎は、禁門の変や下関戦争で実戦の経験をつんだ古つわものです。
兵士たちを村はずれの木かげや海岸にかくれさせ、おちつきはらって、「命令があるまでは、けっしてうつな」と命じました。
朝もやをすかしてみると、川をわたってくる幕兵たちは、よろい・かぶとに身をかためているもの、陣羽織(じんばおり)に立烏帽子(たちえぼし)姿のもの、いずれも槍や刀をふりかざして、太鼓とほら貝の「ドンドン、ブーブー」にあわせてすすんできます。
「こりゃあ、すごい。まるで関ヶ原合戦の絵巻物でもみているようだ。」
河瀬が浅次郎をみてわらいました。
そのとき、和木村の方角がパッとあかるくなりました。
幕府軍の大半が川を渡るのをみはからって、長州の兵が民家に火をつけたのです。
幕兵が火にてらされて、右往左往するのが、手にとるようにみえます。
「うてっ!」
長州軍のゲーベル銃が、いっせいに火をふきました。幕兵がバタバタたおれていきます。
槍や刀しかない幕府軍は、ぜんぜん反撃できません。
生残った者はくもの子をちらすように、逃げていきました。 |
 |
③ 武士の隊と、百姓・町人の隊と
小瀬川のむこう岸の大竹村でも、鍋倉山のふもとで、はげしい戦闘がはじまっていました。
長州兵の一隊が、まわり道をして、鍋倉山から大竹村の幕府軍の背後に、おそいかかったのです。
「それみろ、あの一番いさましく戦っているのが、維新団だ!」
小瀬川をわたって、敵を追撃しながら、河瀬はゆとりをもって、戦況をみていたのです。
「だが、なんだいあれは。山のほうでパラパラ鉄砲をうっているのは岩国藩兵ではないか。
あれでは、たまが敵にとどくわけがないぞ。」
河瀬はいまいましそうにいいました。
突然、大竹村の幕府軍の本営のちかくから、火の手があがりました。
長州兵がちかよって火をつけたのでしょう。
幕府軍は大きくゆれ、幕兵がみぐるしいすがたで、にげまどいました。
馬上の武士は落馬し、川岸へのがれたものは、小舟に、われもわれもとのりこんで、小舟が沈没してしまいます。
にげおくれて木かげにかくれたものは、みつけられて、斬りたおされました。
げれども、長州軍は、避難民には手をださず、安全な場所へにがしてやりました。
それは、日頃から厳しく命令されていたことでした。
岩国藩兵は、どうだったでしょう。
浅次郎らがにげた敵兵ののこした武器をぶんどっているところへ、それまで戦おうとしなかった岩国藩兵がやってきました。
とみるとちらばってぃる武器には目もくれないで、海岸ちかくの焼け残った民家におしいって、略奪をはじめたのです。
遊撃隊や維新団の兵士が、一所懸命にとめましたが、聞き入れません。
浅次郎のいたちかくの家におしいった五、六人の岩国藩兵は、米や着物やそのほか金になりそうなものを、てあたりしだい盗みだしました。
病気らしい老人が、とりすがりましたが、けたおされてしまいました。
十四日の夕方、戦いにやぶれた幕府の先鋒軍は、広島にひきあげてきましたが、彼らは城下をとおりぬけて、九キロも後方にある海田市(かいだいち、広島県安芸郡海田町)まで、しりぞいてしまいました。
ぶざまな姿をみられるのがいやだったのでしょうか。
この戦いにくわわった岡山藩のもう一人、河村又介は、そのときのありさまを、つぎのように岡山藩に報告しました
。
「井伊の兵は六、七割かたも、弾丸にたおれ、榊原の兵も、負傷兵が非常に多い。なかには、肩をうたれて腕のないものもあり、そうでないものも、大部分は杖にすがって歩いている。
顔はみんな土のようだ。
旗や馬印もだらしなくさおにまき、武器らしい武器はみんなすててしまっている。 もっているのは、ほら貝や鐘ぐらいなものだ。もちろん隊伍などととのっていない。 元気なのは、荷物をはこんでいる人夫たちだけで、彼らは敗けいくさをからかった歌をうたって歩いている。」
井伊(いい)・榊原(さかきばら)といえば、徳川氏が天下をとったとき、勇名をはせた最強の軍隊でした。 それがいま、長州の民衆によってつくられた軍隊にさんざんに敗れたのです。 |
 |
「そうだ。岡山にかえったら、このいくさのようすを弥太郎にはなしてやる番だ。
幕府をたおすためには、百姓・町人の力をかりなければだめだということは、弥太郎ならわかってくれるだろう。」
浅次郎には、このことが新しいつぎの時代への道をひらく、ただひとつの正しい道であるように思われるのでした。
2 世直しの人々 top
① たちあがった大工(だいく)たち
一八六六年(慶応二年)六月なかごろ、川越藩(埼玉県川越市)の城中は、はりつめた空気につつまれていました。
夜になると、城内の部屋べやにはあかあかとろうそくの火がともり、いつもならねむそうな目をこすっている宿直の役人も、緊張した顔で、まわりに警戒をおこたりませんでした。
ひときわあかるい奥の間では、藩の重役たちが、ひたいを集めて、こっそりと話合っています。
「さきほどご注進におよびましたとおり、川越の大工どもが、氷川神社の境内に集って相談をはじめてから、すでに三日もたちますが、いっこうに解散する気配もございません。いかがいたしましょう。」
「なに、大工のぶんざいで、徒党を組むとは、お上をおれそぬ不届きなたふるまいじゃ。 主謀者を、ひっとらえて、取調べればよいのじゃ。」
「不届きなことはいうまでもないが、やつらとても、よほどのことがなければ、あのような固い結束がうまれるはずもない。 一刻もはやくご処置をあおぎたいというのが、代官所の願い。せっしゃも同様に思うのじゃが……。」 |
 |
「いや、そのことなら、百文につき白米三合ならば、なんとかいたしてやろうと、先刻申し渡したではないか。」
「それが、やつらのもうすには、昨年にくらべて米の値段が二倍半にもあがったにもかかわらず、手間賃はあがらず、このままではくらしがたたぬとのこと。
ぜひとも、百文で五合にしてほしいといってきかないようなのだ。」
重役たちは、役人からの報告をもとにして、この難題をど片たづけたらよいか、すっかり頭をかかえこんでいました。
強気にでて大工たちをひっとらえ、むりやり解散させるのもひとつの方法です。
しかし、それからあとのしまつが大変です。
米の高値でこまっているのは大工だけではありません。
大工をひっとらえれば、それに同情して、まわりの貧乏人や、近在の百姓が、たちまちぶっそうなふるまいをするのは、めにみえていることです。
結論がでないままに、相談は夜あけ方までつづけられました。
六月十三日、藩はつぎのような、おふれをだしました。
一、貧しいものには、市場より一合安く、銭百文で三合の米の安売りをいたすので、さようこころえよ。
一、町役人、村役人より札をわたされたものにかぎり、分けてつかわす。
一、桝目は充分あるようにとりはからりであろう。 |
米の安売りのききめで、川越城下のおだやかでない空気は、いったんはおさまったようにみえました。
「へえ、なにがありがたく思えだ。ちくしょうめ。
“本当ならば、徒党をくんだおまえたちをとらえるところだが、まだ相談をしただけのことで、打ち壊しなどもしていない。
おまえたちを捕えて、これ以上暮らしがたちゆかぬなるといけないと考えたしだいであるから、ありかたく思え”
とぬかしやがった。」
「六さん、やめな。こえ、か大きいよ。」
茶屋の主人は、さっきからきがきでないようです。
六さんとよばれる男が、酒をのんでいるうちに、大声で本音をはきだしたからです。
さっきから、茶屋のすみの床几(しょうぎ、簡単な腰掛)に腰をおろして、二人のやりとりをきいていた藤五も、役人の耳にでもはいったら、えらいことになるぞと、気になっていました。
でも、六さんのタンカをきいていると、けっこう気分がよくなるのです。
「でもなあ、六さんや。一日に一人三合のわりで、安く売るっていうじゃないか。
それに、なるだけ桝目(ますめ)もたっぷりはかるっていうことだし……。」
主人がなだめるようにいいましたが、六さんはききません。
「なにいってやがんでえ。おてんとさま(太陽)と米のめしは天下りまわりものよ。
それがどうした。この一、二年、おてんとさまのほうはまわってきても、米のほうはさっぱりじゃ。
腕はめっぽうよくても、大工さまの手間賃じゃ食っていけねえ。
いっそのこと、世直し大明神にでもひとあばれしてもらいてえよ、なあ、おやじ。」
「ぶっそうなことをおいいでないよ、六さん。
だがなあ、考えてみると、関八州(かんはっしゅう、関東地方のこと)では、一番おだやかな川越でさえこの騒ぎだ。
米のとれない山よりでは、苦しさもひときわだろうとも。
このあいだの旅まわりの薬売りの話では、十日も米の飯をおがまないところも、ざらだってことだがな。」
大工の六さんのいうことに、主人もとうとうあいづちをうちはじめました。
二人の話に、藤五は、なんど口をだそうとおもったかしれません。
けれども、話のなかにはいりこんでときをすごすより、もっと、大事なことがあるような気がするのです。
――そうだ、いそいで川越でみたことを村にかえってしらせなきや。
いまからいそげば、暮れがたにはまにあうぞ。――
藤五は、勘定をはらうのももどかしく、川越から入間川(いるまがわ)をこえ、飯能(はんのう)の町をすぎて、名栗(なぐり)の家まではしりつづけました。
② 飯能(はんのう)の川原の集り
川越城下に米の安売りのおふれがでた同じ十三日の夕方、川越から四里(約十六キロメートル)ほどはなれた武蔵国飯能(はんのう、埼玉県飯能市)では、百姓たちが、川原に集りはじめていました。
飯能の町はずれをながれる名栗川(なぐりがわ)が大きく右にまわってできた川原は、人々が集るには、かっこうの広場でした。
夕やみにまぎれて、顔を鍋底の墨でよごし、てぬぐいでほっかぶりした百姓たちが、どこからともなく三人、四人と集り、そのまま、夜がふけてもかえろうとはしませんでした。
小さなたき火のまわりに、いくつかの輪をつくって、小声で話合っていました。
顔はわからなくても、おたがいに、声と体つきで、どこのだれとわかる仲です。
年かさの一人が、しわがれごえで、たき火のまわりの人々にはなしかけました。 |
 |
「おらがうまれてから、だいぶの年になるが、いいめをみたことといったら、ただのいっべんもありゃあしねえ。
このあたりじゃ田のあるうちはすくなくて、子供の時分から、あわやひえの飯ばかり。
それじゃ力のいる山仕事はできねえ。米を買って食わなけりゃならねえが……。」
「高くて買えねえ。」
「そうだ、買えねえ。」
「買えねえだ。」
いく人かが声をあわせましたが、それをしわがれ声がおさえました。
「米の値段をあげることは、そういうおらたちに、死ねというのも同じことじゃ。」
たき火をかこむ百姓たちのめは、こえのぬしに集りました。
もう六十八歳になる藤右衛門の顔には、みんなより一足はやくこの世にうまれたために、この世の苦しみを、何倍もせおったように、深いしわが刻みこまれていました。
そのうえ、顔一面に墨をぬっているので、火にてらされると、目玉ばかりが、おそろしくぎょろついています。
「じいさまよ、そんなに生きるのはつらいものかよ。」
「つらいことといったら、死ぬ役より、生きる役が、なんぼかつらいぞ。
こんな世の中ではだめだ、仏さまになったほうがよっぽど楽だろうとおもったこともあったが……。
だがな、権現さまのおつげじゃないが、あの世にいって楽するのもけっこうだが、この世で楽するほうが、なんぼか楽しかろうと思ってな。みなの衆、どうじゃな。」
「そうだ」 「そうだ」とあっち、こっちであいづちをうつものがいました。
くらやみがあたりをすっかりつつんでしまったころ、はりのある大きな声がひびきました。
「やあ、やあ、みなの衆。よう集ってくれた。
今日まわした回状のとおり、これから『世直し』にかかろうと思うのだ。
みなの衆もきいたことと思うが、きょう川越の城下では、お役人衆が大工の願いを聞き入れて、米の安売りをはじめたそうじゃ。
だが、この飯能一帯の米屋も質屋も、地主たちも、わしらがかけあったのでは、うんともすんともいわね。
それどころか、こまった百姓どもに分ける米は、ただの一粒もないとぬかすのじゃ。おだやかなねがいでは、だめだ。」
みんなに話しかけているのは、竜泉寺の住職です。
それまで、だまって住職の話に耳をかたむけていた川原の百姓たちは、あちこちのかたまりごとに、ウォーッと声をあげました。
それは、同感のときのこえでした。
百姓たちは、もってきた斧や、まさかりや、山刀を手に、自分たちのやっつける相手がめのまえにでもいるように、興奮していました。
たき火にちかく腰をおろして、住職の顔をじっとみつめていた藤五も、たかぶる感情をおさえることができませんでした。
だいすきなお盆の祭りの晩に、やぐら太鼓をうつときだって、こんなに胸がはずんだことはなかったのです。
藤五は名栗村の名主のせがれです。
だから、これまできかされてきたことといえば、一揆や徒党のあるときは、それをとりしずめる役だからよくここらえよ、ということばかりでした。
それにしても、ここ数年のあいだ、外国の船がやってきて貿易がはじまってから、米の値段はさがる一方だし、生糸は安く買したたかれるしで、貧しい百姓たちのくらしはたちゆかなくなっていました。
借金のかたに町へ奉公にいかされたまま、山に帰ってこない百姓の子供はいくらでもいました。
おとなしくしていたのでは、もう山の人のくらしはつぶれてしまうのです。
そこで、いくつかの村の名主たちも集って相談しました。
藤五は百姓や木こりのくらしが苦しいことを考えもしないで、たださわぐなとおさえるほうがむりだと考えるようになっていたのです。
この日の昼、川越で米の安売りのおふれをみたり、大工の集りのことをきいたりしたときにも、他人ごととは思えないで、いそいで村にかえって、竜泉寺の住職に相談したのです。
百姓のなかにまじりこんでみて、藤五は自分がずいぶんかわったことに、あらためて気がつきました。
百姓の取り締まりをしなければならないはずの名主のせがれが、貧乏百姓や木こりたちと一緒になって、世直しをおこそうというのですから。
――世の中が新しくかわるというのは、きっとこういうことなのだ。――
藤五は川原をつつむ闇の中に、何かをみつけだそうとするかのように、目をそそいで考えていました。
③ 世直しだ、思いしれ
|

|
「念のために、申合せておくことがある。
よいかな。まず、どんなことがあっても、きめられた家だけをおそうのだ。
大きな家だから打ち壊すのではないぞ。悪いことをして、金をためたやつらをこらすのだ。」
「わかった」とこえがかかりました。
「だまって、注意してきいておれ。いいな。
まじめに商売をやっているものや、相手からすすんで寄進をもうしでるものにたいしては、指一本ふれてはならん。
だれによらず、人を殺してはいかん。
とくに、やみにまぎれて女子供に乱暴をしたり、火つけをするものがあれば……。」
ざわめきがおさまったなかに、きびしい言葉がひびきました。
「そのようなものは、世直しにそむくものだから、きびしく処分する。
村々のかしらや、組頭は、よくこのことをまもらせるようにするのじゃ。」
その夜、名栗(なぐり)や吾野(あがの)あたりから集った五百人あまりの百姓たちは、夜の九時をまわったころから、川原を出発しました。
まだ夏の宵だというのに、どこの家も障子をぴたりとしめきったなかを、世直しの一団がさしかざすたいまつだけが、町なみをてらしました。
世直しの先頭は、やがて、最初の目標のまえでとまりました。金貨しの小山八郎兵衛の家です。
「これより成敗いたす。当家小山家は、貧しいもののなんぎをかえりみず、借金のとりたてばかりをせまり、一粒の米さえめぐもうといたさなかった。
かくなるうえは、世直しの一揆が、天にかわって制裁をくわえる。さようこころえよ。」
いいおわったかと思うと、家の戸はバリバリとこわされ、たいまつのあかりのなかで、たんす、ながもちなどが、次々と道ばたになげだされました。
土蔵の思い戸もこじあけられ、米俵は足がはえたようにはこびだされて、屋敷のまえに山をつくりました。
「わあ、米だっ!」
群衆のあいだから、歓声があがります。
藤五も、夢中で米俵をはこびだすと、
「それ、世直しさまのおかげだぞ。どんどんもっていけ。」
といって俵のなわをほどきました。
「世直し大明神。おかげでやっと助かります。」
貧しい人たちは、拝むようにして、米を思い思いの入物にいれては、持ち帰っていきました。
藤五はいい気持でした。
「これだ、これだ。借金の証文だ。」
「やけ、焼いてしまえ。」
みんなを苦しめていた、借金の証文のたばもみつけだされました。
「火事にならんようにちゅういせい。」
証文のたばをなげこむたびごとに、炎が、一段と高くあがり、人々は「ワアーッ」と歓声をあげました。
こうして、小さな宿場町で六軒が打ち壊され、証文類をやく火が、一瞬夜空をあかるくてらしだしました。
一揆のなかにも、獲物の米や質草(しちぐさ、金をかりるために質屋にあずけた品物)をこわきにかかえて、くらい夜道を家路にいそぐものもいました。
一刻もはやく家にかえって、妻や子に、白い飯をたいて食べさせたいのです。
飯能で一夜をあかした世直しの一揆は、つぎの目標を、一里(約四キロノートル)ほど東へいった牛沢の、増田勘兵衛と勘右衛門兄弟の家にきめて、出発しました。
増田兄弟は、あくどい買占めや売りおしみをしていたので、村人の評判がわるく、怨みのまとになっていたのです。
ところがこの兄弟は、そのまえの日から世直しがおそってくることを予期していたのでしょう。
いつもの兄弟とはうってかわって態度で、こしをひくくして一揆の百姓たちをむかえました。
「みなの衆のおこまりの米を、安く売らせていただきましょう。
なんなら、そのような証拠のものをかいてもよろしゅうございます。
どうか、打ち壊しだけはおゆるしください。」
ぺこぺことあたまをさげて指導者にたのみこむ姿をみて、藤五はふきだしてしまいました。
「なんでえ、ふだんのいばりくさった顔はどこへやった。鬼瓦がつぶれたようなつらで、泣いていやがる。」
藤五のまわりのものがはやしたてました。
一揆の人々は、兄弟が川原に用意した、もてなしの酒や飯で、腹がいっぱいになると、いっそう気勢があがりました。
黒須村の名主、繁田武兵衛も家のまえに酒樽をならべ、食事を用意して、打ち壊しをまぬがれようとしました。
一揆は、繁田家のまえでひといきつくと、ちょうどアリの大軍が反転して、つぎの獲物をもとめるように、扇町屋の町へむかいました。
先頭の一団にはいった藤五は、竹のさきに、白・赤・黄など色とりどりの小ぎれをつけて、ひとめで世直しの一団とわかるようにしました。
のぼりには、竜泉寺の住職の筆で、「日本窮民為救(すくいのため)」(日本の貧しい人々をすくうため)とかいてありました。
世直しは、みんなのためにやるのだと、天下にしめしているのです。
昨日より、今日は新しい人がふえています。
藤五のまわりももう顔見知りの者だけではなくなりました。
世直しときいてかけつけた人や、山からかおれてきた人たちで、二千人にもふくれあかっていました。
扇町屋では、高い米をつぶして酒をつくっている酒屋が、土蔵ごとこわされました。
一粒の米さえ口にはいらない農民にとって、酒つくりは、怨みのまとになったのです。
扇町屋は、先頭が町をぬけでても、うしろはまだ町にもはいっていない小さな町ですが、五軒 打ち壊しました。
つぎの所沢では十五軒を打ち壊し、ますます気勢をあげました。
所沢からさらに北にすすむと、
「さあ、今度は大和田の新井じゃ。」
とさけぶものがでてきました。
「そうだ、そうだ。あいつときたら、貧乏人にほどこしをすると、なまげぐせがついてためにならねえ、というやつだ。」
目標はきまりました。
もう、ゆくさきざきの村の者が、どこを打ち壊したらよいかを、指図するようになりました。
農民ばかりではありません。職人や馬方などもくわわりました。
④ ひきだされた大砲
「ドドドーン」
雷のおちたような音がしたかと思うと、藤五たちのほんの目と鼻のさきの田んぼに、大きな水柱がたちました。
「うわー、大砲だ。」
鉄砲の音はなんどかきいたことはあっても、大砲ははじめてです。
一揆の先頭の一団は、つぎの目標をあれこれ相談しているところでしたから、びっくりして、にげまどいました。
大砲は反撃のはじまりをつげるものです。
飯能で藤五らがあげた世直しのさけびは、武蔵国一帯の村々をよびさましました。
鶴間・大久保・柏原(かしわばら)・笠幡(かさはだ)からは、世直しの一隊が川越城下にせまろうとしていました。
また青梅や五日市をおそい、八王子のちかくまですすんだ一隊もありました。
世直しのあらしが、武蔵国一帯にふきあれたのです。
「世直しのため、打ち壊しをするから、近在の村々の、十五歳から六十歳までの男は、斧、まさかり、のこぎりをもって、すぐに参加せよ。
万一おくれた村々は、役人をはじめ一軒のこらずやきはらうであろう。」
こうしたかきつけが村から村へ、申し送られるようにもなりました。
武蔵国一円の米屋や質屋や大金持ちは、世直し一揆のあらわれるまえから、おびえきっていました。
「金千両、米三十俵をはとこします。今日からは質草をただでお返しいたしますから、ご勘弁ください」と、障子に貼紙をした店もありました。
江戸から十里(約四十キロノートル)あまりしかはなれていない飯能からひろがった世直し一揆は、たちまち幕府や諸藩にしれわたり、大名たちはあわてて一揆にそなえはじめました。
藤五らの行かった大和田は、高崎藩の領地になっていたので、上州(じょうしゅう、群馬県)から、はるばる大砲をはこんで、まもりをかためたのです。
しかし、藩の武士もあわてふためいていたのでしょう。
一揆がせまってくるのをみると、いきなり、大砲をぶっぱなしたのです。 ヽ
藤五らの一揆勢は、大砲の音にきもをつぶしましたが、すぐに気をとりなおしました。
大和田をさけて、入間川へすすみました。入間川の名主綿貫半兵衛も、黒須村の繁田をみならって、一揆に夜食をほどこして、打ち壊しをまぬがれました。
しかし、このころから、一揆のゆくての反撃は強くなってきました。
役人たちは、まだ世直しに参加するものがでない村々に、
「米の値段が高いといって、大勢で人家を打ち壊す不届き者がいたら、代官所までうつたえでよ。』
とさとして、一揆の拡がるのきりくずそうとしました。
地主のなかにも、浪人を雇い入れて、ひっしに防戦する心のもでてきました。
また秩父の大宮(埼玉県大宮市)では、一揆のなかに乱暴をはたらく者がいたことを口実に、一揆とたたかう決死隊がつくられました。
もともと、人を殺すのが目的ではない一揆の人たちのことですから、大砲や鉄砲のまえにはよわかったのです。
そのうえ、大きくふくれあがって、見知らぬもの同志が一緒に行動するようになると、一揆勢のなかの取り締まりもはじめほどうまくいかなくなっていました。
秩父をおそった一団も、藤岡から新町をおそった世直しも、思いがけない武力の反撃にあって、多くの死傷者をだしてしまいました。
ひとたびやぶれた人々は総崩れとなり、一揆のはちまきをとり、たすきをはずし、あたりをはばかりながら、逃げ去りました。
それをみて、役人は、要所要所で、一揆にくわわったものをとらえて、牢屋にほうりこんだのでした。
川越の牢屋へひかれていく藤五は、まわりをみまわしました。
もう八十三歳になる甚右衛門が、腰をおりまげて苦しそうに歩き、肩をいからしてまえを歩いている男は、肥後熊本の浪人と名のっていました。 藤五はみまわしているうちに、はっとして目をこすりました。
顔は泥と墨でよごれ、男のような姿をしていますが、女がいたからです。
きこりの妻のおわしは、病気の夫にかわって一揆にくわわったのでした。
――わしらはつかまった。しかし、いまの世がつづくかぎり、世直しはまたおこるだろう。
いまの世の中が、いつまでもこのままつづいていいものか。――
藤五のつかれきった顔に、赤味がさしました。 |
 |
3 フランス公使ロッシュと将軍慶喜(よしのぶ) top
① 新任のフランス公使
「やあ、しばらくだったね、ロッシュくん。
きみのチュニジアでの活躍ぶりは、こちらでもたいしたうわさだよ。まあ、かけたまえ。」
ドルーアン・ド・ルイ外務大臣は、にこにこしながら、ロッシュをかかえいれました。
ここは、フランス外務省の大臣室です。
レオン・ロッシュは、チュニジアの総領事でしたが、外交にすぐれたうでをふるっていることがみとめられて、新しい任務につくため、ド・ルイ外務大臣から、パリによびもどされたのでした。
「ロッシュくん、きみもよくしっていると思うが、わが国の養蚕業は、いまにもつぶれそうだ。
徴粒子病のもうれつな流行で、かいこが次々と死んでいく。
この方までは、フランスの養蚕業や絹織物業は、全滅ということになりかねない。
これは、わが国の織物業や商業にとっては、一大事だ。
政府もいろいろと手をつくしで、清国(中国)やベンガル(インド東部)産の蚕種(さんしゅ、かいこの卵)を輸入してみたのだが、みんな失敗だった。
ただ、日本から移植した蚕種だけが、予想以上の成功をおさめたのじゃ。
フランスの絹織物業をもりかえして、ふたたびイギリスと対抗できるようにするためには、どうしても、日本の蚕種や生糸を、たくさん手にいれる必要がある。」
ド・ルイ外務大臣は、パイプに火をつけ、ゆったりとけむりをはきだしました。
「ところが、きみもしっているとおり、日本に目をつけているのは、わが国だけではない。イギリスは、もっと熱心だ。
わが国へおくられる中国や日本の生糸のうち、五分の四がロンドンをとおってくる。
この運賃はもちろん、わが国がイギリス政府にはらう関税だってばかにならない。
これがわが国のマルセーユヘ直接におくられてくるようになれば、わが国の絹織物業界は、いつまでも高い原料になやまされなくてもすむようになるだろう。
そこでじゃ、ロッシュくん。
日本の政府がイギリスとはなれて、わが国とふかい友好関係を結ぶようになれば、なにかとうまくいく。
この重要な任務を、ひとつきみの力でやってもらいたい。どうだれ、ロッシュくん。」
ド・ルイ外務大臣は、パイプを手から離して、ロッシュの目をのぞきこむようにしていいました。
「むずかしい仕事だが、きみならきっとやりとげてくれると思うよ。」
そのこえには、ロッシュにたいする信頼感があふれていました。
――イギリスはたくみに日本にくいこんでいるから、相当むずかしいことだ。
だが、これは養蚕業だけではない。わが国が東アジアで力をのばせるかどうかにかかわることなのだ。
よーし、イギリスなどに負けてたまるか。――
闘志をかきたてられたロッシュは、表情をいくらかこわばらせて、こたえました。
「おひきうけしましょう。全力をかたむけて、大臣のご期待にそうようにいたします。」
「そうか、承知してくれるか。ありがとう。私もできるかぎりの援助を約束しよう。」
ド・ルイ外務大臣は、椅子からたちあがると、ロッシュの手をかたくにぎりしめました。
駐日フランス公使、レオン・ロッシュをのせた軍艦が、日本についたのは、一八六四年(元治元年)三月のことでした。
このとき、ロッシュは五十五歳、経験をつんだ外交ばたけのはたらきてでした。
ロッシュは公使にきまったその日から、日本の政治情勢をねっしんに研究しはじめました。
それで、日本に上陸するまでに、ひととおりの知識を身につけていました。
そのころの日本は、三代将軍徳川家光のときから、二百年以上もつづけていた鎖国をやめて、開国したばかりでした。
そして長い鎖国のあいだに、幕府の支配のしくみはゆるぎだしていたのです。
各地におこった新しい産業がさかんになり、幕府や藩がきびしくおさえようとしても、各地でつくりだされる商品は、全国に流通するようになっていました。
オランダ人をつうじて世界の動きを知るようになった人々は、しだいに幕府の政治に批判の目をむけるようになっていました。
こうした動きが、ペリーの来航とその後の開国をきっかけに、幕府をた対して新しい政府をつくろうとする運動にまで、発展していきました。
そのうちでも、討幕の先頭にたつたのが、長州藩や薩摩藩などでした。
江戸幕府はひっしになって、このような反対勢力をおさえようとしていました。
その中心となっていたのが、だれからも、つぎの将軍になるだろうといわれていた一橋慶喜でした。
このようにこんらんした日本を、本当に支配する力があるのはだれなのか。
それをみきわめることが、各国公使のうでのふるいどころだったのです。
イギリス公使パークスは、新しい日本をになう力は、もはや幕府にはないとみて、長州藩や薩摩藩に、大きな期待をよせていました。
彼は長州藩や薩摩藩が要求すれば、武器をどんどん売りこんで、結びつきを強めようとしていました。
ロッシュは、二百六十年あまりも日本の政治をとってきた幕府が、その力をうしなってしまったとは思いませんでした。
日本を代表する政府として、幕府を援助していけば、イギリスにかわって、フランスが日本をおさえることができる。
ロッシュはそう考えて、幕府との結びつきを強めていきました。
幕府にとっても、民衆から諸大名までの、幕府にたいする批判をおさえるためには、武力にたよるほかありません。
フランスの援助にすがりつきたかった幕府と、フランスの利益は、みごとに一致したのです。
「もし、もし、ありゃ一体なんですか。ずいぶんいろいろなしかけがあるようですが……。」 |
 |
江戸湾(東京湾)にのぞむ相州(そうしゅう、神奈川県)横須賀に建設しはじめた巨大な建物をみて、商人ふうの男が村人にたずねました。
「お上のなさることは、わしらにはよくわからん。
なんでも、鉄をとかして大砲や軍艦をつくるとこだそうだ。」
「へえー。それにしても、大きなものだ。
こんなすごいのは、江戸でもめったにみかけませんよ。」
「大きいことは大きいが、わしらにはいっこう役にたたないもんでな。」
「おや、異人さんもたくさんいるようですね。」
「ああ、あの衆か。あれは、フランスとかいうとおい異国からきているのだそうだ。
なんでも、その異国のなんとかいう港と、この横須賀がにているということでな。」
幕府は、フランスのだすげで、製鉄所の建設をはじめていました。
フランスのツーロン軍港の地形に似ているといわれる横須賀が、製鉄所の建設地にえらばれたのです。
製鉄所は、ツーロンの工廠(こうしょう、軍の直営工場)の三分の二の大きさでした。
たくさんの技術者もフランスからよばれ、なにからなにまで、幕府はフランスにたよっていました。
「私は、ちょくちょく横浜の開港場にいくのですが、あそこにもフランス語の学校ができているそうですよ。」
「へえ、そんなものまであるんですかね。」
「二本刀を腰にさしたお武家さまが、鼻のたかいお師匠さんのまえで、なにやら異国の言葉を口をそろえてならっている姿は、ちょっとした見物だそうですよ。」
製鉄所の建設計画がうまくいったロッシュは、フランス商人クーレーを、江戸幕府の勘定奉行小栗忠順(おぐりただまさ)にひきあわせて、幕府に六百万ドルという大金を貸しつける約束を結びました。
これは、フランスから買いいれる武器や軍艦などの費用にあてるためでした。
このころ幕府は、フランスの武力にたよらなければ、自分の力では長州藩ひとつもおさえられなくなっていたのです。
長州藩との戦いで幕府軍が負けたときにも、慶喜はロッシュにたすけをたのみました。
ロッシュは、これにこたえて、フランス兵をのせた軍艦を、すぐおくることにしました。
これは、実際にはおくられませんでしたが、ロッシュは、機会があれば、いつでも日本の内戦に手だしをするつもりでいたのです。
そういえば、幕府の長州征伐の作戦も、ロッシュの意見をいれてきめられたのでした。
ロッシュは実際には、江戸幕府の最高政治顧問のような力をもっていたのです。
② 改革の意見
大阪城に滞在している将軍慶喜の密書をふところにした使者が、ロッシュのところへかけつけました。
一八六七年(慶応三年)の正月もおわろうとするころのことです。
「フランス公使 レネン・ロセスどの。
余は反幕派諸侯をおさえて、東照大権現(徳川家康のこと)いらいの幕府の威光を回復するために、これまでの政治の欠点をあらためたいと思う。
ついては、貴殿のご意見をおきかせ願いたい。」
ロッシュは、さっそく大阪へでむきました。慶喜は二月六日、七日の二日にわたってロッシュとあいました。
慶喜は、前の年の夏、長州征伐のとちゅう大阪で病死した家茂(いえもち)のあとをついで将軍となり、フランスのたすけをたよりに、幕府をたてなおそうとしていたのです。
「遠路はるばるごくろうであった。さっそくながら、貴殿のご意見をおきかせ願いたい。」
「承知しましました。」
いつもは強い意志をあらわすようにギュッとむすばれた慶喜の口元に、力のないのをみながら、ロッシュは自信たっぷりに口をひらきました。
「私のみるところでは、ちかごろの諸大名の動きにはふたつあると思います。
天朝につくものと、幕府につくものです。
また外国人にもふたとおりございます。
ひとつは、幕府にここらからご協力申上げるもの、もうひとつは、日本を分裂させ、諸大名とむすんで、自国の利をはかるものです。
もうすまでもなく、私の国フランスが前者であることはご承知のとおりですが、イギリスは後者でございます。
しかし、イギリスとむすんだからといって、討幕派諸大名などはおそれることはございません。
諸大名ともうすものは、幕府が手をゆるめれば騒ぎ、幕府がシシのごとくなれば、ウサギのようにおとなしくなって、大君(将軍)の命令にしたがうものでございます。」
ここで、ロッシュは慶喜に人ばらいをたのみ、慶喜とさしむかいになって、言葉をつづけました。
「さて、これで大君と私の二人きりになりました。
これからは、ここにいる私は、フランスの公使ではない。
ただ、日本のためを思う一人の外国人、ご家来同様におぼしめして、どのようなことでもおたずねください。
私も遠慮なく申上げることにいたします。」
ロッシュは、おもむろに、ふところから一冊のノー卜を取り出しました。
それには、ロッシュの考える幕府政治の改革案が、こまかくアラビア語で書きこまれていました。
それは人にしられるのをおそれたからでした。
「なかなか用心ぶかいな。かまわぬ、のべてみよ。」
苦笑いをしながら、慶喜はロッシュをうながしました。
「まず強い軍隊をもつこと、とくに陸軍を強くすることがなによりでございます。
イギリスと結ぶ長州藩や薩摩藩より、さらに強い、大きな軍備をもたれぽかりません。 |
 |
いまのしくみでは、諸大名が石高におうじて兵士をさしだすようになっておりますが、服装も武器もばらばらで、このままではなんの役にもたちますまい。
まるで子供だましのようなものでございます。
兵士たちの武器・服装、それに訓練の方法なども、すべてひとつにしなければなりません。
優秀なフランス士官の軍事顧問団を、すでによびよせてありますから、訓練のことは、私どもにおまかせください。」
慶喜は、口をむすんだまま、ききいっています。ロッシュは、さらにつづけました。
「そうなれば、諸大名も武器や兵士をさしだす必要がなくなり、その分の費用を幕府におさめさせて、軍事費にあてることができます。
それでも不足するようならば、フランスは武器でも資金でも、大君のお望みのものを、ご用だていたしましょう。
そのかわりとして、生糸を幕府が買占めて、フランスだけに売ってくださればけっこうでございます。
日本とフランスが資金をだしあってつくった商社に、この仕事をまかせれば、ことは簡単でございます。」
慶喜の表情をじっとみつめるロッシュの目が、キラッとひかりました。
慶喜はしずかにうなずきました。幕府にとっては、軍備のたりないことが、一番大きな悩みだったのです。
ここで、ロッシュは、こえを強めました。
「政府の目的は、なによりも諸大名の力を弱くすることでございます。」
この自信にみちた言葉は、大名をおさえきれないで苦しんでいた慶喜の心を強くとらえました。
「つぎに、政府のしくみについて申上げましょう。
政府に陸軍・海軍・外国事務・会計などの六つの役所をおき、それぞれの役所の責任を、老中に分担してとらせます。
老中の会議をひらいて、老中首席に最高の責任をとらせます。」
つづいて財政のこと、税のこと、……あとからあとからと泉がわくように、ロッシュは改革の意見を語りつづけるのでした。
③ フランスの軍服
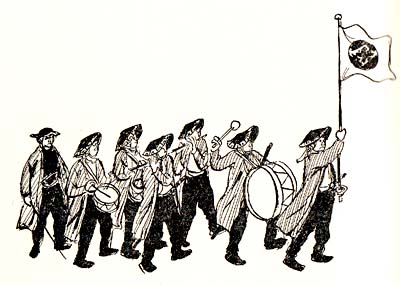 |
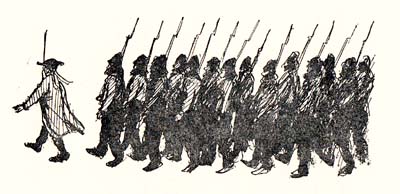 |
「このたびのご公儀のおふれにはこまったものだ。」
「いや、全くだ。我々御家人(ごけにん)は、直参(じきさん、将軍直属の武士)だ。
いざとなれば、命をさしだすために、お扶持米(ふちまい、給与としてもらう米)を頂戴しておるのだ。
それが、もう武器も家来もさしださなくてよろしい、そのかわり金をだせといわれる。なんということだ。」
数人の御家人が集って、酒をくみかわしながら雑談をしています。
酔いがまわるにつれて、ぐちがおおくなっていきました。
「そのうえに俸祿の半分を“軍役金”としておさめろだと……。」
「それでは、お扶持米が半分になったと同じではないか。」
「それどころではない。 わしがきいたところでは、これからは、百姓を雇い入れて、西洋式の訓練をするという話だぞ。」
「茶坊主までが、洋服をきて、鉄砲うちをするという……。」
「うーん、刀にかけては免許皆伝のこの腕も、出るまくがないというのか。くやしくはござらぬか、おのおのがた。」
「ところで、こんなむちゃなことを考えついたのは、なにものだ。」
「それはわかりきったこと、勘定奉行小栗忠順(おぐりただまさ)どのだ。 だが、フランス・ミニストレルの口セスどののさしがねによるらしいと、もっぱらのうわさだ。」 |
 |
「あーら、うらめしや小栗どの。」
「あっはっはっは……。」
だれかが女のこわいろをつかったので、飲み仲間はこえをそろえて笑いました。
しかし、そのあとは、座がしらけきって、みんなは手酌で、ぐいぐいと酒をあおるだけでした。
長い間、特別の身分として、わがもの顔でいばっていた武土たちも、世の中のはげしい動きから、とりのこされようとしていることを、なんとなく感じはじめていたのです。
春になると、横浜にある幕府の陸軍伝習所では、シャノンら、フランス士官十八名の軍事顧問団が、歩兵・騎兵・砲兵の訓練をはじめました。
しかし、通訳をとおさなければ、おたがいに言葉がわからないので、訓練は大変な騒ぎでした。
新しい武器や訓練になれない兵士たちは、とまどって、へまばかりしていました。
そのうえ、兵士たちがきせられた軍服は、からだのおおきいフランス兵の寸法にあわせていたので、小柄な日本人にあうはずがありません。
ながすぎるズボンのすそは、靴の上でだぶついています。
靴も頑丈でしたが、おもくて鉄のぞうりでもはくように、ひきずって歩くしまつでした。
また士官たちは、洋服をきて刀をさしていましたから、上着の裾がもちあがり、ぶかっこうな姿でした。
「まるでサルのようだ、あの、サル芝居のな。」
人々は、こういってわらいました。
このことぼけ、また、ロッシュと慶喜の関係を、ひにくっているようでもありました。
慶喜もまたフランスの軍服を愛用しました。この軍服こそロッシュをつうじて、フランスの皇帝ナポレオン三世から、とくに将軍におくられたものでした。
軍服をかざる金モールは日の光をうけるとキラキラとかがやいて、それまでにない権威をみせるようでした。
一八六七年(慶応三年)も秋にはいると、幕府と討幕軍の対立は、いよいよけけしくなりました。
戦乱を予想して、各藩は軍用米をためこみ、米商人も米を買占めはじめたため、米の値段は、うなぎのぼりにあがっていきました。
くらしにこまった民衆の、世直しをとめる一揆や打ち壊しは、まえの年にひきつづいておこりました。
“米の高いのは公万さまが悪いふらだ”
“天候が不順なのも公方さまのせいだ”
なんでも、公方さま(将軍)のせいにされるようになりました。
こうした民衆のげしい抵抗と、それを利用してたくみに幕府をおいつめた倒幕派によって幕府は廃止され、慶喜(よしのぶ)も政権を追われました。
一八六八年(慶応四年)一月三日、慶喜は最後の運命をかけて、討幕派が中心になってつくった京都の新政府と京都郊外の鳥羽・伏見で戦ってやぶれ、江戸へのがれたときにもまだ、ロッシュの援助にいくらかの望みをかけていたのです。
top
**************************************** |