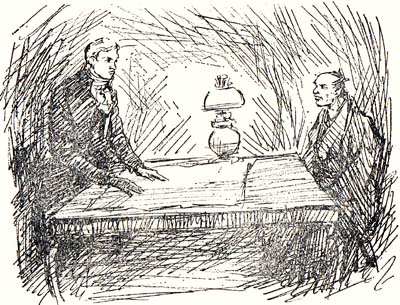|
****************************************
Index 日本の夜明け(その一 その二 その三 その四 その五)
|
日本の夜明け(その一)
1 海をわたった日本地図
① オランダ正月
② うっかりさん
③ 長崎屋の一夜
④ 日本人われを征服せり |
2 新潟のうちこわし
① 諸国のはなし
② 越前屋藤四郎
③ 死刑の日
3 加茂の一揆
① 秋のある夜
② 竹筒のひびき
③ うちこわし
④ 鉄砲と刀 |
1 海を渡った日本地図 top
① オランダ正月
|

|
つめたいこがらしが、くる日も、くる日も、江戸の町々をふきぬけていきます。
そのあとに、まるはだかにされた木々のこずえをみあげると、道ゆく人々にも、寒さがひしひしと身にしみました。
「ああ、もう年のくれもちかくなった。のんびりしていては、年の瀬がこせぬわい。」
そうつぶやいて、おもわずえりをかきあわせ、足をはやめていきます。
ところが、ここ京橋水谷町の蘭学塾、芝蘭堂(しらんどう)の大広間では、そとの寒さもどこふく風と、さきほどから、大勢の笑い声がたえません。
「さあさあ、諸君、今日はおもいきりくつろいで、おおいに飲んでくれたまえ。
これは最近、長崎から、はるばるとりよせたオランダのウェイン、つまり、ぶどうの酒じゃ。
色もよし、香りもよし、味もよし……。」
そういって、三十人ほどの客の中を、ぶどう酒のびんをもって、うれしそうにすすめてまわっているのは、当家の主人大槻玄沢(おおつきげんたく)です。
玄沢は東北に生まれ、江戸にでて杉田玄白(すぎたげんぱく)について蘭学を勉強し、まだ四十歳にもならぬというのに、すでに西洋流の医学の大家として、その名は、彼の号の磐水(ばんすい)、その塾の名の芝蘭堂(しらんどう)とともに、江戸はおろか、全国に、なりひびいていました。
「さきほどから、めずらしいぶどう酒のおもてなし、まことにかたじけない。
オルゴールとやらの美しい音色に耳をかたむけ、異国の酒のさかずきをかされているうちに、まるでこの身がとおい西洋にあそんでいるようなここちになってきましたよ。」
へやの正面には、ギリシアの医学の開祖といわれるヒポクラテスの肖像が、かざられています。
客はみんな、頭のかたちやみなりで、医者とわかりますが、なかにはどこで手にいれたのか、洋服をきこみ、部屋にただひとつの椅子に腰をかけて、得意になっているものもいます。
「米でつくるわが国の酒の黄金いろも美しいが、このぶどう酒の赤と白の二色もきれいですね。
赤と白とは、まことに、西洋ふうの新年をいわおうという今日の宴会にふさわしいではありませんか。」
これをきくと、一同は口々に、「御慶(ぎょせい)、御慶(ぎょせい)」といって手をたたきました。
「御慶」というのは「新年おめでとう」というあいさつのことばなのです。
そのころのわが国のこよみは太陰暦といって、月をもとにして一ヵ月を二十九日か三十日に計算していました。
月が一番まるくみえる日が、ひと月のまんなかの十五日にあたります。
ですから、月のはじめとおわりには、月はでません。
もっとも、太陰暦とはいっても、一年の長さは太陽をもとにしているので、じつは太陽暦の一種なのです。
この太陰暦の計算では、一年が三百六十日ほどにしかなりません。
そこで二、三年にいちどほど、一年を十三ヵ月にします。
この年には、同じ月が二度あるということになります。
ふえたこの月を閏(うるう)月といいました。
寛政六年の閏十一月十一日は、太陽暦では一七九四年の一月一日にあたります。
そこで、大槻玄沢(おおつきげんたく)は、ひごろ蘭学によって西洋のことを勉強している仲間によびかけて、わが国ではじめての、太陽暦の新年の宴会をひらきました。
この宴会はその後、毎年つづけられ新しいこよみでいわう元日の会だというので、新元会(しんげんかい)と名づけました。
また、これはオランダふうの正月だというので、オランダ正月ともよばれました。
「では、そろそろ、諸君にみせたいものがある。さあ、そのへんの皿や盃を、かたづけてくれたまえ。」
そういいながら、玄沢がみんなのまえへひろげたのは、一枚の世界地図でした。
「ほほう、これは、これは、さすがは磐水先生、よいものを手にいれられたものだ。」
「ここはエゲレス(イギリス)、ここは天竺(てんじく、インド)、ここは唐山(とうざん、中国)とみえますな。」
「経度・緯度もきちんと線でしめし、国名や地名もくわしく書きいれてある。これはたいしたものだ。」
そのとき、うしろのほうからのぞきこんでいた一人が、すこし、不服そうにいいました。
「しかし、どうもわが国の部分がたよりないようですな。
この地図でみると、日本はまるでイモムシがころかっているようで、なさけないことだ。
私には、どうも信用できませんね。」
そういわれてみると、だれの目にも、日本の地図が正確でないのが気になります。
「諳君のいわれるとおり、せっかくのこの世界地図も、日本の部分だけは不正確で残念です。
しかし諸君、いま、手にはいる一番新しい世界地図をみても、日本が正確にでていないのはなぜでしょうか。
第一に、わが国は鎖国をして、世界とのつきあいがない。これでは、外国人にわが国のことがわからないのは、あたりまえです。
第二に、幕府は、まだこうしたことを真剣に考えてはいないようです。
第三に、わが国の天文学・暦学・測量学が未熟だから、日本人が、日本の正確な地図を、まだつくっていません。
ですから、世界地図の日本の部分についての責任は、ほかでもない、私たち日本人にあるのです。」
蘭学の第一人者、大槻玄沢先生の真剣なひとこと、ひとことに、オランダ正月に集った学者たちはみんな、身をのりだし、こぶしにちからをいれて、いつまでも耳を傾けていました。
② うっかりさん
はじめてのオランダ正月がいわわれたその翌年、一七九五年(寛政七年)七月のある朝のことです。
こよみをつくっている幕府の役所、暦局(れききょく)へ、一人の老人がたずねてきました。
「お願いでございます。私を先生の門下にくわえて、天文学・暦学・測量学を、教えていただきたいのでございます。」
これをきいた幕府の天文方、高橋至時は、つよくこころをうたれました。
天文方というのは、幕府から、天文学についての最高の地位をあたえられている学者です。
幕府がこよみをつくりなおすについて、大阪の麻田剛立(あさだごうりゅう)という大学者をまねこうとしたところ、剛立は、自分の弟子の高橋至時(よしとき)をかわりに推薦したのです。
至時は、三十二歳でした。
その至時のまえに、五十歳をこえた老人が、ひたいをたたみにすりつけて、入門をぬがいでたのです。
この老人は伊能忠敬(いのうただたか)といい、上総(かずさ、千葉県)で生まれ、少年時代は家庭のつごうで苦労をかさねましたが、ちいさいころから算数のだいすきなはたらきものでした。
十八歳のとき、下総(しもうさ)の香取郡佐原村(千葉県佐原市)の地主で酒造業をいとなむ伊能家にみこまれて、養子となりました。
忠敬は家の仕事にせいをだし、そのうえ、米のとりひきもやり、さらに、薪や炭の売買で江戸に店をだすなど、ますます財産をぶやしました。
しかし忠敬はわかいころから、天文学や暦学の勉強がしたくてたまりませんでした。
そこで、五十歳になったのを機会に家を長男にゆずり、その翌年、暦局に高橋至時をたずねたというわけです。
「伊能さんといいましたね。どうぞ、お手をおあげください。私はまだわかいのです。
弟子になりたいなどといわず、どうか私の手助けをするつもりで、これから暦局(れききょく)へかよってください。」
こうして伊能忠敬は、高橋至時の教えをうける身となりました。
この日から、忠敬は、まい朝、深川黒汪町の家から、浅草の暦局へかようことになりました。
ところが、この忠敬は、まもなく、わすれものをしては、みんなからわらわれるようになりました。
煙草入や手ぬぐい、ときにはわきざしまで置き忘れてしまうのです。
そこで、あの老人はなんというそこつものだろう、とんだうっかりさんだ、とかげでひそひそささやかれることさえありました。
忠敬は、本当にうっかりさんだったのでしょうか。
さすがは先生です。
高橋至時には、なぜ伊能忠敬(いのうただたか)が、そわそわしたり忘れ物をしたりするのか、そのわけがわかっていました。
忠敬がそわそわしだすのは、きまって正午まじかのときでした。
それは、太陽が子午線(しごせん、北極と南極をかすんだ線)のまうえを通過する時刻をはかるときなのです。
また忠敬が夜もおちつかないのは、きまった時刻の天体の観測のため、そのときをのがさないようにと、真剣になっているからでした。
努力家の伊能忠敬は、わずか二、三年ののちには、高橋至時の弟子のなかで、一番の実力をもつようになりました。
さて、ちょうどそのころ、海のかなたのロシアでは、皇帝がさかんに海外へ商人をおくりだしていました。
なかでも毛皮商人などは日本の北のほう、カラフト(サハリン)、千島から北海道あたりまで進出してきました。
そこで幕府もすててはおけず、そのころえぞ地とよんでいた北海道あたりを測量しようと計画をたてました。
「伊能さん。じつはきょう、ご老中からえぞ地測量の命令がありました。
今度の観測と測量は、日本ではじめての大事業です。
これは、私たち天文学や測量学を勉強しているものの、うでだめしでもあります。
第一回は東北地方とえぞ地ですが、ゆくゆくは、日本全国を測量しようというのですから、大事業です。
伊能さん。これに成功すれば、わが国にはじめて正確な地図ができます。
そしたら、すべての学問がこれによって発達します。
そして、日本の民衆の幸せに役立つはずです。
そこでお願いですが、伊能さん。あなたにこの大役を引受けてもらいたいのです。」
これをきいて、伊能忠敬は感激にほおをぬらしました。高橋至時は、伊能忠敬を幕府に推薦しました。
一八〇〇年(寛政十二年)、忠敬は五十六歳の身で、数人の部下と人足、それに二頭の馬に大きな観測器具などをせおわせて、江戸をたちました。
幕府の仕事とはいっても、その費用は、ほとんど自分のもちだしでした。
苦心さんたん、忠敬はえぞ地東南海岸と奥州街道の測量、それに各地での天体観測に成功しました。
彼の観測によってだした子午線一度の数字は、今日のすすんだ科学からみても、感心せずにはいられないほど、正確なものでした。
忠敬は、さらに全国各地に測量の旅をかさねました。
一八〇四年(享和四年)、先生の高橋至時(よしとき)は病死しましたが、忠敬は仕事をつづけました。
彼が、最初のえぞ地測量をはじめてから、一八一六年(文化十三年)、彼が七十二歳になるまで、じつに十七年間の実測によって、そのたびごとに、その地方の正確な地図をつくりあげては、幕府にさしだしました。 |
 |
忠敬はいよいよ最後に、これまでのたくさんの実測図にもとづいて、日本全体の地図をつくる仕事にかかりました。
しかし、残念なことに、それができあがらないうちに、一八一八年(文政元年)、彼は七十四歳でこの世を去りました。
遺言によって、彼のなぎがらは、浅草の源空寺の高橋至時先生のお墓のとなりにほうむられました。
それから三年ごの一八二一年(文政四年)、彼が夢にみていたわが国最初の正確な日本全図は、彼の部下や弟子たちの手によって「大日本沿海輿地全図」として、りっぱに完成されました。
③ 長崎屋の一夜
「コノ日本地図、コレ、タイヘンスバラシイ。コノ地図、イッタイ、ダレガツクリマシタカ?」
ランプの光にうつしだされたわかい一人の西洋人の顔は、興奮に赤みをまし、地図をさすゆびは、ふるえているようです。
「この地図は、私の父、高橋至時の門弟で、伊能忠敬という町人が測量したものでございます。」
江戸の本石町(ほんごくちょう)といえば、日本橋にほどちかく、くすり問屋をはじめ大きな店がたちならび、昼は大変にぎやかですが、夜になると火のきえたようなしずけさです。
その本石町の長崎屋は、長崎からオランダ人が江戸にててきたときの定宿とされていました。
「ワクシガ江戸ニキテカラ一ヵ月タチマシタ。
コノ宿屋へ、薩摩ノトノサマ、中津ノトノサマ、タズネテキマシタ。 学者モ町人モキマシタ。
ケレドモ、イチバンニウレシカッタヒト、ヒトリハ最上徳内老人、ソシテモウヒトリハアナタデス。 |
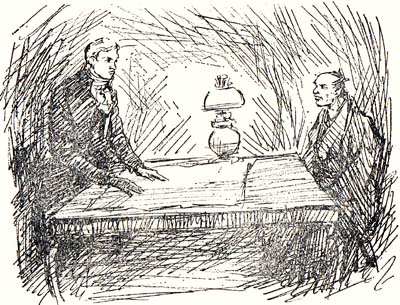 |
最上サンは、ジブンデカラフトヲ探検シタ地図ヲワクシニカシテクレマシタ。
アナタハ、先日、間宮林蔵サンガ探険シタカラフトノ地図ヲミセテクレマシタ。
ソシテキョウハコノ日本地図デス。 アナタガタハ、ワクシノ学問ノ友人デス。」
ランプをはさんでかたりあっているのは、長崎出島のオランダ商館の医者として、わが国にきたシーボルトと、高橋至時(これとき)のむすこで、いま父のあとをついで天文方をつとめている高橋景保(かげやす)です。
シーボルトはドイツ医学の名門の家に生まれ、学生時代から、東洋についての研究をこころざしていました。
とくに日本に興味をもったので、オランダ国王の命をうけて、日本にくるチャンスをつかんだのです。
シーボルトは、歳こそまだ三十まえですが、まれにみる大学者でした。
彼は長崎の郊外の鳴滝に診療所をかねた塾をつくって、病人の治療をし、また、全国各地からかけつけだ学生たちに、医学はもとより西洋のすすんだ学問を教えました。
高野長英(たかのちょうえい)、高良斎(こうりょうさい)、小関三英(おぜきさんえい)、伊東玄朴(いとうげんぼく)など数十名の学生を教育しました。
そしてかれらのなかでりっぱな論文を書いたものには、学位をさずけました。
日本にはじめて、大学ができたといってもいいでしょう。 |
 |
オランダ商館長が将軍にあいさつするため江戸へでたので、シーボルトは、一緒にきたのです。
そこには学問の情熱をもやす学者がたくさんまっていました。一八二六年(文政九年)春のことです。
八つの鐘(午前二時)が、春とはいえ、ひえきった空をふるわせました。
「シーボルト先生、先生に先日みせていただいたご本、クルーゼンシュテルンの『世界周遊記』などは、私たち日本人が、ぜひ勉強したい本です。
どうでしょうか。私にあの三冊の本をゆずってくださいませんか。
そのかわり、私は、この日本の地図のうつしをつくって、あとから長崎にとどけることを、かたく約束いたします。」
それは、命がけの学術の交流でした。
幕府は、せっかくの日本地図を日本国内でもやたらにみせることをゆるしてはいません。
まして、外国人に渡したことがわかれば大変です。しかし、景保は考えました。
この機会をのがしたら、日本の学者のりっぱな仕事を世界にしらせることは、とうぶんできない。
そしてまた、新しい学問の本を手にいれることもできない。やるならいまだ。
高橋景保は、学問の進歩のために、命をかけて決心したのです。
④ 日本人、われを征服せり
一八二八年(文政十一年)の夏、シーボルトは日本での仕事をおえて、いよいよ故郷へかえることになりました。
ところが前もって荷物をつみこんであった船が、暴風のため海岸にうちつげられてしまいました。
幕府の役人が船のなかを調べて、おどろきました。
国外にもちだすことのできない品々が、次々と発見されるではありませんか。
実は幕府は、まえから隠密(おんみつ、スパイ)をつかってシーボルトや高橋景保の行動をひそかに調べていたのでした。
シーボルトの部屋から徳川家の葵の紋服が発見されて、ことはいよいよめんどうになりました。
これは眼科の医師土生玄碩(はぶげんせき)が、将軍からもらったものでした。
玄碩は、シーボルトの目の手術を見学し、目のひとみを開くくすりのききめにおどろいて、これを教えてもらうためにこの紋服をさしだしたのです。
そのとき、玄碩は、息子の玄昌にこういいました。
「紋服を渡したことがわかれば、私は死刑になるにちがいない。
しかし、いま、このくすりをシーボルト先生から教えてもらわねば、日本人の目の病気をなおせないのだ。
いいかい。私はたとえ死刑になっても、おまえがこのくすりを世にひろめてくれ。
国のため、日本の民衆のために、しっかりとたのんだよ。」
幕府の取調べは、厳重をきわめました。
高橋景保(かげやす)は、きびしい取調べのすえ、とうとう獄のなかで死にました。
すると、その死体を大きなかめのなかで塩づけにしておき、一ヵ月もたってから、そのくさった死体にむかって死刑の判決をくだしました。
そればかりか、景保(かげやす)の子供二人も島ながし、そのほか五十余名の弟子たちも、おもく罰せられました。
土生玄碩(はぶげんせき)も家はつぶされ、財産はとりあげられて、牢にいれられました。
一方、長崎のシーボルトも、きびしく取調べられました。
彼は、どんなに取調べをうけても、しらぬ、ぞんぜぬとがんばりとおし、自分に品物をとどけてくれた人たちについて、けっして口をわりませんでした。
ながい取調べのすえ、シーボルトは国外追放となりました。
幕府は、わが国の学問の大恩人であるシーボルトを、まるでのら犬のように、日本から追いだしてしまったのです。
長崎にいたシーボルトの弟子たちの多くも、おもい罰をうけました。
国へかえったシーボルトは、日本についての研究を発表しました。
長崎で役人に取上げられるまぎわに、彼は弟子たちと夜ふかしで、カラフト、えぞ地や日本の地図をうつしとりました。
そして、これらをのちに世界の地理学界に発表しました。
それまで、カラフトは大陸からつきでた半島だと考える人がおおく、ここを探険にきた人も、しっかり確かめることができずにいたのです。
シーボルトは、最上徳内や間宮林蔵という日本の探険家が、カラフトは半島ではなく島であると確かめていることを、世界の人々にしらせたのです。
ロシアの海軍の軍人で、なだかい探険家のクルーゼソシュテルンは、この発表をみて「日本人、われを征服せり」とさけんだということです。
シーボルトはこのとき“MAMIYA NO SETO ”(間宮の瀬戸)と書きいれて、日本の学者・探険家の名を「間宮海峡」として世界の地図のうえにのこしてくれました。
シーボルトは、最上徳内から地図をうつさせてもらうとき、秘密をまもると約束しました。
その誓いをかたくまもって、それから二十五年たった一八五二年になってはじめて発表したのです。
シーボルトは、こう書きそえています。
「私は、これをもっとはやく発表したかった。
しかし、いまもなお日本にいる私の学問の友人に迷惑のかかることを心配して、これよりはやくは世の中に発表することができなかったのです。」
2 新潟のうちこわし top
① 諸国の話
お正月になると真っ白な雪にうずもれた越後(新潟)の人は、子供をつれて、江戸や大阪などの大きな町に、獅子舞(ししまい)をしにいきます。
これを越後獅子(えちごじし)といいますが、その越後獅子の人たちがつたえてくる諸国の話に、雪国の新潟の人たちは、夜のふけるのもわすれてききいるのでした。
話をつたえてくるのは、越後獅子の人たちだけではありません。
ゆたかな越後平野で収穫された米のほか、北国の人たちがつくったゴマ、ベニバナ、タバコ、それに、いわし、さけなどの海産物は、新潟の港で船につまれ、日本海を渡って、大阪などにつみだされます。
それとひきかえに、日本の四十か国から、一年間に三千五百隻もの船が、木綿やこまもの、お茶などの商品をつんで新潟の港にはいってきます。
諸国の商人がはいってくるたびに、新潟の町の人たちは、よりつどってごちそうし、諸国の話に花をさかせるのでした。
ちかごろ伝わってくる話には、新潟の人たちの目をみはらせるものがありました。
「なんでも上野(こうずけ、群馬県)、武蔵(むさし、埼玉県と東京都)あたりの百姓たちが、江戸までおしかけようとしたということだ。二十万人からの百姓衆だったというぞ。」
「なんでまたそんなことに?」
「よくはしらんが、日光の東照宮さまのお祭りのために、お上が助郷(すけごう)をいいつけたためだそうだ。」
「とうちゃん、スケゴウって、なんだ?」
ねているはずの文蔵が、むっくりおきあがってききました。
「なんだこの野郎! 大人の話をぬすみぎきなんかしくさって。
助郷というのはな、お上の荷物をはこぶ仕事だ。とっととねろ!」
文蔵のとっつぁん、権太としゃべっているのは、越前屋のおじさんでした。
「島原の乱いらいの大そうどうというんで、たいした評判だそうだ。」
「俺がきいたのは大阪の話だが、これは、ついこのあいだのことだ。
正月の二十二日だっていう話しだ。
お上が大阪の町人に新しくご用金をかけたのを怒った連中が、金持の家を何十軒とおそってうちこわしたっていうぞ。
その主謀者、七十四人は捕えられて、首をはねられたそうだ。
これは、弥七の話だが、大阪の町人衆は、処刑された人たちに、えらい同情しているということだ。
弥七も、自分でみたというわけでぱないんだが、このうちこわしのことを書いた絵入りの本が売りだされたそうだ。
この本は、みんなすぐにお役人にとりあげられてしまったそうだが、その本をみたという人の話だと、なんでもお寺の門に、悪者たちをこらしめるためにたっている仁王さまが、町人たちの先頭にたって金持をこらしめて、暴れまわるという筋だっていうぞ。」
文蔵は、今度は本当にねたようです。スウスウと寝息をたてていました。
越前屋のおじさんは、夜ふけまで、しゃべりこんでかえっていきました。
三月をすぎてから、船乗りたちがもってきたのは、新潟と海つづきの福井の町で、数万人の農民が、貧しい町人と一緒になって、福井藩の役人とご用商人の家をおそったという話でした。
一揆の指導者は、福井城にせめいるまえに、人々を集めて、
一つ、火の用心をすること。
一つ、人をころしてはならない。
一つ、人の財産をぬすんではならない。
一つ、たいこがしずかに鳴っていたら集り、はやく鳴っていたらはやくすすめ、鐘をうったら、口をむすべ。 |
と申合せ、秩序正しく福井城にうちいったというのです。
一揆の力にまけた藩の役人が交渉しようといいだすと、指導者は全員を小高い台地に集めて力をしめし、全員の食べ物を藩にださせ、とうとう要求した全部のことを藩に認めさせたのです。
藩の役人は、いったん牢にいれた七十人の人たちも、全員釈放しました。
八月になると、今度は、新潟と海をへだてた佐渡の島でおこったさわぎが、すぐ、つたわってきました。
「国中一統」という名まえで、どこからともなくビラ、がくばられたといいます。
それには、「集る場所、用意する武器、おそうところ、要求すること」がかいてありました。
三十ヵ村五百人の農民は、このビラにこたえて、みのかさを着て、竹槍を手に、食糧をもち、同志をさそい、役人のいる相川の町におしだしていったそうです。
しかし、ふしぎなことに、どこまでいっても、指導者は姿をあらわしません。
奉行所におしかけた農民たちは、役人にさとされ、すごすごと村に帰るほかありませんでした。
役人は、ビラを書いたものをさがして捕えました。
ビラを書いたのは、念仏宗の智専(ちせん)という坊さんでした。
智専は、ビラを書いたものの、先頭にたつのがおそろしくなってやめてしまったのでした。 |
 |
新潟の人たちは、こういった話しを、自分たちのことのように、心をおどらせて、きいていました。
この年、新潟の町を治めていた池文右衛門(いけのぶんえもん)という長岡藩の役人が、千五百両というご用金を町人にかけてきていたのです。
町人たちは不景気でくるしんでいました。
しかもこの年は米のみのりがわるく、秋の収穫時をまえに、米の値段はあがるばかりでした。
② 越前屋藤四郎
 |
この一七六八年(明和五年)の九月のこと、新潟のあるお寺に数人の人がひそかに集って、相談をしていました。
越前屋の湧井藤四郎の顔がみえます。
藤四郎は、数代まえから新潟にすみついて、織物のあきない(商売)をしていました。
この町の大商人たちが、藩の役人とむすびついて、もうけを一人じめにしていたので、おりがあれば大商人をおさえ、たくさんの小さな商人たちの苦しみをすくいたいと、ふだんから考えていました。
野右衛門がいいました。
「ちかごろの米の値上がりは、ひどいものだ。
米屋は、値上がりをよいことにして、買いしめるから、米の値はあがる一方。
町の役人は大商人のいうことをきいて、ご用金を不公平にわりあててくる。
町じゅうの不満は、つのるばかりだ。もう我慢ができん。」
須藤佐次兵衛がひきとりました。
「それではきまった。
“八月ちゅうに納めるというご用金九百三十両のうち、十月中うに百八十両だけを納めるから、残りの七百五干両は、景気きがよくなるまでのばしてほしい”
この願書を町じゅうにまわして、町民の署名をとる。よろしいな。」
藤四郎もうなずきました。
この相談を密告したものがありました。
ふみこんできた役人に、藤四郎は捕えられ、牢にいれられてしまいました。
そのほかのおもだったもの三十余人は、謹慎を命じられました。
おもだったものをおさえ、大事にならないうちで、やれやれと役人たちが思っていたときでした。
一七六八年(明和五年)九月十九日、米を買占めていた米屋がおそわれました。
密告者の家が、うちこわされました。
新潟の町の船大工、船頭、荷あげ人夫、猟師、木こり、日雇いなどの人々が、集ったのです。
先頭にたったのは、三四郎、善七、そして文蔵の父の権太がいました。
一揆は、町役人の屋敷など二十軒ばかりをうちこわしたあと、三千人ばかりで、奉行所にむかいました。
役人たちは、一揆のいきおいに手のつけようもなく、右往左往して、ちらばるばかりです。
そのとき、どっと鉄砲の音がとどろきました。
黒煙がうずまいてあがる中から、馬をおどらせて奉行がとびだしてきました。
「ええい、こしゃくな奴らめ、追いのけよ、うちはらえ。」とさけびました。
与力・同心などが、棒や十手をふりかざして、一揆のなかにつきかかります。
さすがに、鉄砲の音にひるんだ一揆ぜいは、わらわらとにげちろうとしたときでした。
どこからでてきたのか、黒装束の男が、
「いかに、みなみな、おそれるな。あれは空砲だ。にげるな、すすめ!」とはげましました。
本当にそうだと一同がきづき、勢いをなおし、どっとわめいて引返しました。
奉行もいまはかなわぬと、馬をかえしてにげだしました。
このようすをみて、うしろにひかえていたもう一人の奉行が、
「空砲ではらちがあかぬ。実弾をこめよ。」
とさしずして、またも鉄砲をうちだします。
百姓・町人あっての武士のことですから、一揆をあいてに鉄砲をうって、百姓・町人をころしては、武士がかえってこまります。
そこで一揆には鉄砲をうってばならぬと、幕府のきびしい達しがあったのに、実弾をこめて鉄砲をうつとは、それまでにないことでした。
楯さえもたぬ一揆ぜいのことです。
先頭かけてすすんでいた権太や善七ら七、八人は、鉄砲のため、ばたばたと将棋だおしにたおされました。
ふたたび一揆がにげだしたとき、黒装束の男が、ふたたび声をかけました。
「屋根にのぼれ。」
屋根にあがったものが、瓦やたきぎをとって、役人になげました。
役人たちは、鉄砲をかまえるひまもなく、にげちりました。
もはや、一揆をさえぎるものはありません。
三千人の町人は、なだれのように奉行所におしかけ、牢にいれられていた越前屋の藤四郎を釈放し、奉行をはじめ、すべての武士を新潟から追放しました。
湧井藤四郎をとりもどし、奉行所を占領した一揆の人たちは、よろこびに涙をながしながら、勝利のかちどきをあげました。
それまで室町時代には、堺の町のようにゆたかな大商人たちが、都市の自治をしたことはいくつも例があります。
しかし、貧しい労働者と商人が町の政治をすることになったのは、新潟のこの事件が、日本で最初のできごとでした。
勝利した一揆の人たちは、つぎりことをきめました。
一、町役人を選挙できめること。
一、税金のおりあてを、町人のなかからえらばれた代表できめること。
一、商品の売りあげ税をこれまで毎年おさめていたが、それを一年おきとし、そのあいだ生活に困っている人のための資金として貸しだすこと。 |
さっそく、新潟の町には、新しい労働者と商人のための政治がはじまりました。
藤四郎は、まず、新潟の全町民から連判状をとって、
「今度の蜂起について、役人からお調べがあっても、一人ずつではけっして出頭せず、町じゅうそろって出かけること。
もしこれに違反したら、どんな処分でもうける。」
と、新潟全町民の団結を約束させました。
米の安売りもはじまりました。
困っている人にたいしては人数を調べて、配給券がくばられました。
配給券のうらには藤四郎の印がおされました。
酒・とうふの値段も、三割から四割、値下げさせました。
米などを買占めていた商人たちはこらしめられ、物価はさがりました。
二分という安い利子(百円かりたら、二円の利子)の質屋も、五ヵ所につくられました。
「俺たちの手で、こんなことをやるなんて、なあ弥七、嘘みたいだな。」
「うん、おさむらいがいなけりや、世の中はなりたっていかないもんだと思ってたのがばかみたいなもんだ。」
二人は、ちょうちんをもって、町内をみまわっていました。
武士を計いだしてから、町の十五ヵ所に自警団の番所がつくられました。
町民二十人ずつが火の用心と、不審なものがたちいらぬように、見回りました。
「それにしても、権太は、気の毒なことをしたなあ。」
「のこされた文蔵が、かわいそうよなあ。」
「藤四郎さまがめんどうをみてくださっているが。……いや、おしゃべりでお役目が留守になってはすまぬぞ。」
「火の用心!」
二人のもつちょうちんには、藤四郎の紋、かついていました。
③ 死刑の日
それから二年たった一七七〇年(明和七年)八月二十五日でした。
人々がおそれといきどおりの目でみつめているなかを、長岡城の処刑場に引きだされてきたのは、あんなにも人々の感謝と尊敬のまとであった湧井藤四郎と、須藤佐次兵衛の二人でした。
新潟の人たちは、二年まえの明和五年九月から、藤四郎たちが捕えられた十一月までの、人々の心をうきうきとわきたたせた二ヵ月間と、そのあとの悲しいおしひしがれた、暗い月日とを、うずくような気持で、はっきりと思い出しました。 |
 |
新潟の奉行所が町人や労働者に占領されたことをしった長岡藩では、九月のすえ、役人に三十五人の足軽をつけて、新潟におくりました。
しかし、新潟港の荷あげ人夫は、藤四郎のさしずをうけ、つみ荷のなかにとび道具があるからといって、誰一人仕事にでませんでした。
また役人たちの宿も、誰一人貸すものがありません。
役人たちは、せっかくつんできた鉄砲、弾薬などを荷あげできず、引返すほかありませんでした。
長岡藩はやりかたをかえました。
十月なかば、長岡藩の代表二人が新潟につきました。
湧井藤四郎らを新潟の町の代表として認め、交渉をするというのです。
長岡藩が藤四郎らを交渉相手として認めたことは、一揆の大きな成功です。
藩の代表は「どんな願いごとがあるのか」ときき、困っているであろうからといって、用意してきた白米一千俵を新潟の町におくりました。
藤四郎は、これにはなにか計略があるにちがいないとうたがい、米を受取ることを断わりましたが、やはり米の不足に困っていたので、受取るほかありませんでした。
米をつくっている越後平野は、長岡藩などの大名が支配していますから、新潟の町ひとつだけではどうすることもできなかったのです。
十一月二十二日になって、長岡藩は、おそわれた奉行所の側と、町人の側と、両方のいい分をきくからといって、まず奉行と町役人をよびだしました。
その翌日には、藤四郎らを長岡によびました。
藤四郎は、奉行がかけたご用金がいかに町人を苦しめてきたかをのべました。
数日の取調べののち、藩の役人は、藤四郎らの返答のしかたに不始末があったといって、藤四郎や佐次兵衛らを投獄してしまいました。
藤四郎と佐次兵術を捕えたのち、役人たちがさがしもとめたのは、あの黒装束の男です。
黒装束の男の水ぎわだった指導ぶりで、さんざん手をやいただけに、役人たちはふかく憎んでいたのです。
ようやくその男が五賀野右衛門だということがわかりました。
野右衛門もついに捕まりました。
数年間、獄にとじこめられたまま、とうとう野右衛門は、牢のなかで最期をとげました。
長岡城の瓲刑場にひきだされた藤四郎と佐次兵衛の二人は、すこしも死をおそれるようすもなく、ゆっくりと、処刑の場にすわりました。
その日、新潟の町の商店は、戸をしめて、藤四郎、佐次兵衛にたいして、悲しみの気持をあらわしていました。
町なかを数百人の武士足軽が、警戒のためにまわっていなければなりませんでした。
役人の刀がきらめき、湧井藤四郎、つづいて、須藤佐次兵衛の首が、はねられました。
文蔵は、父の位牌(いはい)のまえで、ろうそくをあげ、じっと手をあわせておりました。
こののち、新潟の二人の奉行と、その下にいた町役人たちも、職をとりあげられ、責任をとわれ、新潟からおいはらわれました。
ご用金も廃止されました。
これも湧井藤四郎らのおかげだと、新潟の町人たちは、湧井大明神といって、長くあがめたということです。
3 加茂の一揆 top
① 秋のある夜
二束めのわらじができたとき、太平は、腹がグウダウなっていました。
晩めしは、なっ葉いりのおかゆでしたから、もう、おなかがすいてしまったのです。
暗いあんどんの光で、太平とむかいあうようにして、母も、わらじをつくっていました。
ちかごろ、めっきりやせて、ほおがおちくぼんだようです。
二間しかない奥の部屋からは、ねている父のせきが、時々きこえました。
ねどこのなかで、「白いご飯がたべたい」などと、さわいでいた弟と妹も、もうねむったようです。
「ひえてきたな、大平。」と、母が身をふるわせて、いいました。
「うん、火をたこうか、おっかさん。」
「なあに、我慢しよう。もう一束つくったら、寝るとするから。」
母はいうと、わらをしごきました。
コオロギだけが、いせいよく、ないています。また、おなかがブウブウなりました。
ひと月ばかりまえ、はげしい嵐がふいて、すこしばかりの田のイネは、みな、はたきおとされてしまいました。
山国の村ですから、半分百姓、半分きこりで、そうでなくても、米を買わねばならぬ人が多いのですが、この三河国(愛知県)の加茂郡の村々は、どこも嵐にやられました。
川があふれて、水びたしになったところもあります。
焚き木を背負って、とおい山道をおりて売りにいっても、このごろは、酒屋などもやっているどこの問屋も、
「このとおり、焚き木はいっぱいでな。」といって、すぐには、買ってくれません。
しかし、背負ってかえるわけには、いきませんから、むりにたのむと、
「じゃ、おいてくがいい。」といって、まるでただみたいな値で、買いとるのでした。
「ひどい奴らだ。そのうえ、米を買占めて、値段をつりあげ、貧乏人を苦しめているんだ。
血も涙もない奴らだ。それをみのがしている役人も役人だ。」
父は、はぎしりして、おこりました。
そのころから、父は、夜おそくまで、あちこちをとびまわって、なにか相談しているふうでした。
ところが、むりがたたって、持病の神経痛がおこり、五日ばかりまえから、寝込んでしまったのです。
まえの年も、そのまえの年も、天候がわるく、みのりは、よくありませんでした。
それなのに、殿さまは、ごくわずか、まけてくれただけで、年貢は、きびしく、とりたてたのです。
「もう、百姓のくらしは、たたなくなった。このままでは、一家うえ死にだ。」
と、となりのおとうの伝兵衛さんも、話していました。
「なんでも、ここらあたりだけでなく、となりの信濃(長野県)や、ほかの国は、もっとひどいそうじゃ。
北のほうじゃ、うえ死にがなん万とでて、死んだ人の肉まで食っているそうじゃ。」
作物がとれず、みんなこまる年、つまり、ききん年がめぐってきたのです。天保七年(一八三六年)のことです。
有名な天保のききんに太平たちは、ぶつかったのでした。
「はやく大人になりたいなあ。もっと力があったら、牛方(うしかた、牛をつかった運ぱん人)になって、うんとはたらいて、おっかさんに、焚き木をせおわせたりしないんだがなあ。
それに、弟たちにも、たまには白いご飯を食べさせて……。」
太平は、おもいました。数え年で十五ですから、若い衆の仲間にはいっているのですが、背かチビなのです。
しかし、喧嘩だけは父ゆすりで、まだ、泣かされたためしはありません。
そのとき、コトコトと戸をたたくものがいました。
名をきくと、お隣の伝兵衛さんなので、すぐ戸をあけました。
「おとうは、ねむったかな?」
「さあ……。」
すると、ねむっているとおもった父が、おくのくらやみから、きゅうに、母をよびました。
「おかつ、おきるから、ちょっときてくれ。」
「なんのなんの、俺がそっちへいくよ。」
伝兵衛は、すぐ父の枕元のほうへ、歩いていき、母がおいかけるように、あんどんをもっていきました。
松やにをもやしてべつの明かりをつけ、太平と母は、また夜なべをつづけました。
奥に部屋からは、ひそひそと話し声がきこえ、やがて、あらたまった父の声がしました。
「太平、ちょっと、ここへきてくれ。」
「なんだ、おとう。」
太平が、枕元にすわると、父は、声をひくくして、
「太平、いよいよ一揆だ。このままじゃ、百姓はみなうえ死にじゃ。
米をやすく売ってもらうお願いを、いくらやっても、殿さまは、しらぬ顔じゃ。
おまえも、昔の一揆の話は、お爺さんから、なんべんもきいたろ。」
「はい。」
「一揆はわるいことじゃない。百姓が生きるためには、こうするよりほかに手がないのだ。
だが、わしは、このとおりで、足腰がたたぬ。残念だ。みなにすまぬ。
いままでさきだちになって相談してきたのだからな。……そこで、太平、たのみだが
……、おまえに、身がわりにいってもらいたいのだ。」
太平は、胸がドキドキなりました。
「わしと一緒にいこう、こわいことはないぞ。」と、伝兵衛がいいました。
「おとう、おれはいく! いって、悪い奴らやっつけてやる!」
太平の、しっかりした声がひびきました。
② 竹づつのひびき
|

|
山道をふみわけて、たいまつの火をたよりに、まがりくねった道を上ったり、下りたりして、どのくらい歩いたでしょうか。
あちこちに、たいまつの火が見えがくれしていました。
伝兵衛はじめ、大人たちにまじって、太平もあるきっづけました。
月はおちて、星だけがチカチカ輝やいていました。
みんな、黒いももひきにわらじをはき、頭は手ぬぐいでおおい、顔には、かまどのすみをぬっていました。
炭をぬってくれた母は、太平の耳に口をつげて、
「先にたつでねえぞ、みんなのするとおりにやりな。」と、ささやきました。
母がにぎってくれた大きな握り飯を、腰にぶらさげ、そのうえ、とびきり切れる大なたを腰にさしていました。
ふと、ビューヒューという、尺八ともちがう音がひびいてきました。太平がききました。
「伝兵衛のおとう、あれは、なんだ?」
「竹づつの音だ。みんなを集める合図だ。もう石御堂はちかいぞ。」
やみのなかを、あちからも、こちからも、たいまつが、石御堂にむかっています。
道はくだって、またのぼりにさしかかりました。
「伝兵衛のおとう、さむらいがでてきたらどうするだ?」
太平は、やっと聞きました。みちみち、聞こう聞こうとおもいながら、なかなか聞けなかったのです。
「さむらいがでてきたら、ひと合戦やることになるな。
んだが、こっちがたくさんなら、さむらいも、手をだせまい。」
「ビューヒュー、ビューヒュー。」
竹づつの音は、まぢかになり、ざわめきがきこえはじめました。
集合場所の石御堂は、すこし小高いところにある石のほこらで、大木がおいしげり、まえは広場になっていました。
広場には火がたかれ、黒いかげがそのまわりをとりまき、腰のかまや山刀、刀どの武器がぶきみに光りました。
どの百姓も、顔は、炭でまっくろです。
「松平の伝兵衛。」
と、となりのおとうが名のったのをまねて、太平も、力いっぱい、
「同じく太平、太郎兵衛のせがれです。」と、名のりました。
「おっ、ごくろう、おとうは、まだ病気が悪いか。」闇のなかで、声をかけるものがいました。
「はい、代理できました。」
「しっかりやれよ。」
べつの声がしました。いったい、だれだろう、よそ村の人なのに、おとうの病気までしっているとは、
――太平は、うれしくなり、大人にまけずにやろうとおもいました。
五つどき(午後八時ごろ)、たいまつの流れは、ぱったりと、とまりました。
ちょっとたかい石御堂の石だんのうえに、四、五人がたち、そのうちの一人があいさつをしました。
「下河内の辰蔵です。みなさん、ごくろうさんです。
これから、一揆のかしらをえらびますが、どなたがいいでしょう。」
「おまえさんがなってくれ。」
「そうしてくれ。」
という声がおこり、辰蔵がかしらとなりました。人数をかぞえると、六十五人ほどでした。
辰蔵は、もと大工で、あちこちの村に、たくさんの知合いがあったのです。
頭もよくきくし、口もたっしゃでした。辰蔵は、いままでのいきさつを話しました。
「いま、ききんにことよせて、酒屋、問屋などが米を買占めている。
そのため、米を買うものの苦しみは、容易ではない。このままでは、うえ死にしてしまう。
代官さまや殿さまにお願いして、わるい商人をとりしまってもらいたいと、いくら願っても、しらぬ顔である。
このうえは、一揆をおこして、俺たち百姓の力で、こういう奴らをこらしめてやるほかない。
――それで、村々から、有志のものが集って、何回も相談して、とうとう一揆をおこすことにきまった。
十五歳から六十歳までの男は、一揆にくわわることをきめ、ふれを庄屋(いまの村長)にまわしてもらうことにしたわけだ。
あしたになれば、もっとたくさん集ってくるだろう。
今日は、人数は少ないが、これから“うちこわし”をやる。おもうぞんぶん、はたらいてくれ。」
「うわーっ」と、声がわきおこりました。
「だが、“うちこわし”は、ものとり、強盗とはちがう。ものは、けっしてとってはいけない。
とるものがいたら、きびしくしごくぞ。」
「うわーっ」という声に、辰蔵の声は、かきけされてしまいました。
まず、滝脇(たきわき)の庄屋から、うちこわすことになりました。
というのは、滝脇からは、一人も村の人をおくってよこさないからです。
たき火でたいまつをつけてから、たか火を小便でけして、一揆ぜいは石御堂を出発しました。
一揆ぜいはふた組みにわかれ、ひと組みは辰蔵が、もうひと組みは川向の善四郎という百姓が指揮することになり、滝脇村へむかって、山道をすすみました。
夜中でしたが、パチパチとはじけて、明々ともえるたいまつは、帯のようにうねうねと、西へ西へとうごいていきました。
太平や伝兵衛は二組でしたから、一組のほんのすこしあとをついていきました。
いつもなら、ぐっすり寝込んでいる時間なのに、太平は、すこしも眠くなく、カッと目をあけて歩いていきました。
③ うちこわし
 |

|
どのくらい歩いたのか、大きな屋敷の門のまえで、一揆ぜいは、たちどまりました。
門をこじあけ、一組の八、九人が屋敷のなかへかけこみ、ドンドンと戸を叩きました。
滝脇の庄屋の家でした。戸があきました。
「ふれは渡したか。」
問いつめている大きな声が、太平らのいる門のほうまできこえました。
けれども、庄屋の声はききとれません。
そのうちに、
「こら、なぜにげるか。」という高い声して、つづいて、「おうな、おうな」と、おさえる辰蔵の声がしました。
「おうい、庄屋はにげたぞ。それ、うちこわせ!」
「うわーっ」と、門のなかへなだれこみました。
まず、戸、障子、たんす、ながもちなどの家財道具を庭へもちだし、めちゃめちゃに、ぶちこわしました。
柱をのこぎりやなたで切るもの、壁をぶちぬくもの、屋根をはぐもの。
つなをはりにひっかけて、「えっさ、えっさ」とひくと、バリバリ、メリメリという音は、四キロ四方にもきこえます。
「それ、うちこわしがはじまったぞ」と、近くの村々から応援がかけつけてきました。
三、四時間のちには二百人にもなり、村一番の庄屋の家はつぶれて、めちゃめちゃとなり、みるかげもなくなりました。
ちょうど、大地震にあったようでした。
太平も、夢中で、なたをふるいました。あたりがあかるくなってきました。
「さあ、ひとやすみしよう。」
川向の善四郎がいいました。
そのとき、みんなは、きゅうに、はらがすいているのにきづきました。
しばのうえや板きれに腰をおろして、握り飯をほおばっていると、気がきいたのがいて、お茶をくばりました。
かまどと茶がま、茶わんだけはこわさずにおいて、さっそく、お湯をわかしたのです。
朝めしをすませると、太平は、きゅうに眠くなってきました。だが、眠るどころではありません。
「おそくなってすみません。」
「ふれのまわりがおそかったので。」
などといいわけしながら、百姓たちが、十人、二十人とかたまって、次々にやってきました。
「うわっ、みごとに、うちこわしましたなあ、胸がすっとする。」と、いうものもいました。
人数は、ぞくぞくとふえて、四百人にもなりました。
それで百人ずつ、四つの組にわけて、三組の組がしらには川田の千蔵、四組の組がしらには、大津の大吉がなりました。
九月二十二日。かしらたちは、どこへすすむかを、相談しました。南の新居村へむかうことになりました。
ここに、日野屋という酒づくりの問屋があって、米の買占めをやり、焚き木をただみたいに買いとり、百姓を苦しめていました。
新居の人たちだけでなく、このあたりの百姓のうらみのまとでした。
一揆ぜいが、日野屋のまえについたのは、朝の八時ごろでした。
うちこわしにきづいたのか、家のものはにげて、一人もいません。
家の戸、障子、屏風、膳、椀、道具をぶちこわしました。大きな酒蔵が、べつになっていました。
「酒蔵もこわせ。」
「まてい、お茶がわりに、いっぱいのんでからにしようぜ。」
「なるほど、それもそうだ。」
茶わんやひしゃくで酒をあおり、のどをうるおすと、つかれもふっとびました。
太平は、井戸へはしって、水をのみました。
かえってくると、大人たちは、山刀で酒だるのせんをあけているところでした。
酒はどくどくと流れだし、酒蔵は、たちまち川のようになりました。
太平は、酒のにおいで、目がまわりそうでした。
「日野屋、おもいしれ!」
そうさけんで、日野屋をあとにすると、どこからか握り飯がとどきました。
うちこわしを勘弁してもらいたいので、一揆ぜいのご機嫌をとるため、金持が、弁当をとどけてよこしたのです。
腹ごしらえをして、東の折地村へすすみ、助右衛門宅をこわし、岩谷村の米屋もうちこわしました。
このとき、一揆ぜいのなかの一人が、くわをぬすんだのを、太平がみつけてしまいました。
その百姓は、あとでとりにくるつもりか、そのくわをそっと、くさむらのなかへかくしました。
かしらは、「ものをとるな」と、くりかえしいいました。
いままで誰一人、そんなことをしなかったのに、その百姓は、一揆の規律をやぶったのです。
きっとくわもない、貧しい百姓なのでしょう。
だが、――太平は迷いましたが、とうとう、川向の善四郎に、このことを教えました。
「なに、くわをとった? それはゆるせん。」
善四郎の命令で、その百姓はなわで、がんじがらめにしばられて、岩谷の庄屋にあずけられました。
そのころ、一揆の人数は、雪だるまのようにふくれあがり、二千人をこえました。
④ 鉄砲と刀
それから二日のちの九月二十四日の朝、一揆ぜいは川を渡ってひたひたと、挙母(ころも、豊田市)の城下町にせまっていました。
人数は、どれくらいか、けんとうがつきません。一万をこえていたでしょう。
この二日間、太平は、黒石・大津・茅原・下河内・中村・中垣内とすすみ、わるい庄屋・酒屋・米屋・質屋をうちこわしました。
それから二隊にわかれて、ずっと山奥の村へ、うちこわしをしながら、すすみました。
山奥へいけばいくほど、村はこまり、たくさんの百姓が、
「それ、一揆さまがきたぞ」と、くわわってきて、「あそこをこわせ」「ここをこわせ」と、教えてくれるのです。
どのくらいこわしたか、太平には数えきれないくらいでした。
加茂郡のたくさんの村々は、領地がいりくんでいて、殿さま(ここでは旗本のこと)がちがいました。
うちこわしをきいて、役人たちが、さむらいや足軽をつれて、へっぴりごしで警戒していました。
しかし、一揆ぜいが大勢なので、どうすることもできません。
一揆ぜいは途中でひとやすみし、役人たちに、「米は一両に八斗(約百二十キログラム)にしろ」「酒は十一文」「頼母子講(たのもしこう)は二年やすめ」と、要求することにきめました。
倍にあがった米や酒の値段を、もとの値段にひきさげてくれというのです。
頼母子講というのは、みんながすこしずつお金をだしあい、くじびきであたったものから先に、まとまったお金を使うしくみですが、もう、掛金もかけられないほど、みんな困っていたのでした。
役人たちは、いつもの威張りようは、どこへいったやら、頭をひくくして、
「ききとどけたぞ。そのうえは、おだやかに村にかえったら、どうじゃ。」と、いうのでした。
「おまえさんたちのしったことじゃない。」
一揆ぜいは、せせらわらいました。
役人が、かならず約束をまもるなどとは思っていませんでした。
さて、挙母は、内藤山城守という二万石の大名の城下町です。
町へはいるのは、これがはじめてです。
ところが、一揆ぜいのまえには、竹槍などをかまえて、町の人たちが、一歩もいれないとまちかまえていました。
そのうしろには、さむらいたちが、鉄砲、槍をかまえていました。
川向の善四郎がすすみでて、いいました。
「町の衆よ。俺たちは、おまえさんらの敵じゃない。
米がたかくて食べられないから、こうしておしかけたのじゃ。
もとどおりの値段にしてくれというだけじゃ。
おまえさんらも、この苦しみは同じじゃろう。」
善四郎が話していくと、竹槍隊の中にざわめきがおこり、竹槍を杖にしたり、わきへほうりだすものもありました。
そして、そろそろと、道をあけました。
「百姓衆、さあ、とおってくれ。」
だれかがさけびました。
「町の衆、ありがたいぞ。」
一揆ぜいがすすみかけたとき、鉄砲隊の火なわ銃は、いっせいに火をふきました。
「ドドドン……ドドドン、ドドドーン。」
「あっ、伝兵衛さんがやられた。」
だれかの声がしました。太平は、かけよろうとしました。
しかし、そのとき、また、「ドドドン」と、鉄砲がひびき、何人かの胸がいぬかれました。
太平らは、血のにじんだ地面にふせました。
「うぬ、ころしたな!」
いかりにもえた百姓の波は、武士たち目がけて、おしよせました。
このとき、刀をぬいた二百人ほどの武士がきりかかり、ごったがえしの戦いになりました。
太平も夢中で、おおなたで暴れましたが、肩のあたりに、やけどのようないたみを感じたとおもったら、目がかすみ、そのまま、わからなくなりました。
「ビュヒュー、ビュヒュー。」
なにか、竹づつの音をきいたようでした。何時間たったのか、太平は、目をさましました。
「おう、気がついたか。」
伝兵衛さんの声です。伝兵衛さんは鉄砲で殺されたのではなかったのかしら?
それとも幽霊だろうか?
けれどもとなりのおとうの伝兵衛さんは、生きていたのです。
肩の傷は、しっかりときれでまかれて、ずきずきいたみましたが、ふかい傷ではないそうです。
そこは、御船山のふもとで、伝兵衛さんはここまで、背負ってきてくれたのです。
「ビュヒュー、ビュヒュー。」
竹づつの音は、夢ではなく、やはり山のうえからでした。
それは、ちりぢりとなった百姓たちを集めている合図でした。
「伝兵衛さん、山へいこう。」 |
 |
「いや、それはむりだ。おかしらは、おまえを家へおくりとどけるようにいわれて、山へのぼっていったんだよ。」
山へいきたい気持と、家へかえりたい気持が、一緒におこりました。
しかし、伝兵衛に、もう一度いわれて、太平は泣きながら、うなずきました。
二百あまりの村をゆるがした「加茂の一揆」といわれる大うちこわしは、それから、三、四日つづき、とうとう、とりしずめられてしまいました。
そのあと、かしらたちや主だったものが、何十人も召し取られたことを太平はきいて、胸がにえたぎりました。
となりの伝兵衛さんは、信濃のほうへ、しばらく身をかくしました。
米は、いくらか、安くなりました。「うちこわしは、無駄ではなかったのだ」と、太平の父は、話していました。
あくる年三月、太平の傷がすっかりなかったころ、辰蔵、千蔵ら四人のかしらたちが、とうまるかごで、江戸おくりになるとの話がつたわってきました。
それまで、牢屋のなかで、死んだ者も五、六人いるとのことです。
その江戸おくりの日、母は仏だんに、あかりをともしました。
父は縁側にいざりでて、母と太平は庭にでて、とうまるかごのでる赤坂の陣屋のあたりを、おがみました。
もちろん、その陣屋はみえず、みえるのは山々だけでしたが、太平の目には、一揆の先頭にたって、元気なさしずをしてくれた、おかしらたちの姿が、はっきりと、みえるのでした。
top
**************************************** |