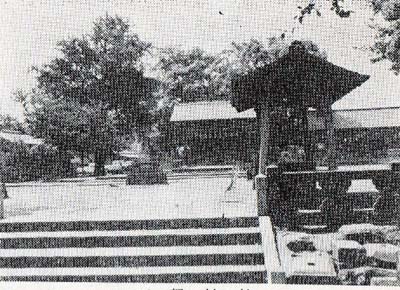|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章
三章 城下町・久留米
1 筑後人気質 top
お国言葉が異なるように、地域によっての気質も多分に相違する。
例えば筑前博多は、横道者(おうどうもん=横着者)である。次のような軽口言葉がある。
――博多ん者(もん)は横道者、青竹割ってヘコ(ふんどし)にかく。
曲がったことの嫌いな一本気のところがあり、そして「おろたえもん」つまり「あわて者」でもある。
佐賀ではがらりと気質が異なり、上野伝七ふうになる。というのは一種のシャレ言葉で「匸」の字を当てる。
七という字になりたいが、同類が足を引っぱるのでなかなか「七」になれない。
なりそこねて「亡」となる。つまり、素直に上に出ない七(ウェノデンンチ)とは「亡」――ほろびることで、古く佐賀人が、佐賀ン者を評して言った言葉である。 |

久留米市の北を流れる筑後川
|
熊本人気質は「モッコス」と呼ばれる。がんこ者である。
わかっているくせにわからないふりをして、右を向いたら死ぬまで左を見ようとはしない。
久留米を中心とした筑後人気質は「じゅうげもん」である。説明しにくい言葉である。
強いて書けば「幽化者」であろうか。
消極的で行動力に乏しく、うらめしそうに他を見るタイプである。
佐賀でいう「いひゅうもんI異風者」つまりヘソ曲がりとも異なる。
九州の各藩が明治維新を迎えた折り、いわゆる「薩・長・土・肥」と袮されたように、薩摩と肥前が時流に乗った。続いて肥後熊本や筑前福岡もそれなりの地歩を築いた。だが筑後久留米で二十一百石の有馬藩は、不運を一手におしつけられた様相であった。
まず十代藩主頼永(よりとお)は文政五年(一八三一)生まれで弘化三年(一八四六)二十五歳で死去。
十一代頼咸(よりしげ)か跡目を相続したけれど、文政十一年(一八二八)生まれで十九歳という年齢であった。
十代頼永が藩主であったのは天保十五年(一八四四)から弘化三年(一八四六)まで、二年二ヵ月の短い期間である。
若い藩主を補佐する重臣たちの意見が食い違い、勤皇・佐幕両派に対する見解が絶えずぐらついた。
有能な人材に時と所が与えられないまま、維新を迎えた。
十一代藩主頼咸は真っ先に藩籍奉還(明治二年二月七日――『久留米小史』)を名乗り出たが 既に時の流れから見ると二歩も三歩も遅れをとっていた。
頼咸は明治十四年(一八八一)五十四歳で死去している。
時流から取残された恨みが一つの性格となって「じゅうげもん」的な言質を残したのであろう。
黒田五十二万石の城下町は福岡で、もともと博多は商人の町であった。
豊臣秀吉に対して神屋宗湛(かみやそうたん)が言明したように、一国一城をもらうよりは気ままな商人として生きたいという、海外を見ている町であった。
豊前小倉で十五万石の小笠原藩も、慶応二年(一八六六)の第二次長州征伐で敗れ、時流から取残されて、小倉商人として立直りを見せた。
久留米の立直りも「久留米商人」というべきであろう。
そして、ゴムと兵隊と苗木がこれを支えたのである。
九州で商人の名のつく城下町は「博多」と「久留米」と「小倉」だけである。
現在ではすっかり忘れられているが、現マーケッ卜風の市場を組織して、実績をあげた点て久留米市は全国から注目された時代がある。
昭和初期の不況の頃であった。その場所は日吉町であったと記憶する。
他地方の人の評言によると「筑後ん者の通った後は草も生えん」と語られている。
同じ評言は「佐賀ん者」にも通用する。
藩の相違はあったにしても、佐賀・久留米・柳川という土地と風土は、共通の面が少なくない。
それは米麦作地帯の貧乏藩というだけでなく、肥後(熊本)や豊後(大分)、そして筑前(福岡)などと比較した場合、一段とはっきりすることがらである。
「じゅうげもん」という気質は言葉で表現し難いものである。
肌で感じるもの、とでも言うべきであろうか。その点ては佐賀の「いひゅうもん」も同様である。
2 青木繁と坂本繁二郎 top
久留米からは画家が輩出している。近代日本の美術史を飾る第一級の人たちである。
青木繁(一八八二〜一九一一)・坂本似二郎(一八八二〜一九六九)・古賀春江(一八九五〜一九三三)などである。
だがこうした大人物が突然生まれたわけではない。それなりの素地があったからである。
青木繁や坂本繁二郎より十年前の明治五年(一八七二)に、この二人に直接絵画の手ほどきをした、森三美が生まれている。
森三美の父は日吉町の醤油屋で番頭をしていた。
尋常中学(いまの明善高校)一年の頃絵の勉強を思い立ち京都府立画学校(後の絵画専門学校)に入学したが、この学校も一年限りで退学した。
学校をやめた後は洋画家・小山三造の門下生となり、四年間洋画の技法を学んだ。
森三美が日吉町に戻ってきたのは明治二十五年(一八九二)彼が二十歳の頃であった。
繁二郎は森三美の画塾に通うことになるが、そのきっかけを作ったのが兄の麟太郎であり、麟太郎の師である日本画家・三谷(みたに)有信であった。
森三美は明治二十七年に久留米尋常高等小学校の図画の教師になった。
繁二郎は画塾だけではなく学校でも森三美の教えを受けるが、青木繁はここで初めて森三美を知った。
森は当時の学校で使っていた臨画の教科書が気に入らず、また教え方も日本画風の方法ではなかった。
教室で教える洋画の手本を作らせられていたのが坂本繁二郎であり、彼は森画塾での俊才であった。
青木繁が画塾に入ったのは学校で森を知った後である。
イギリスから取寄せられた水彩画や油絵の色刷りに、最も血をたぎらせて感動したのは青木繁ではなかったか。
しかし、青本繁の存在は誰からも認められなかった。粗野な少年としか思われていなかった。
ここで三谷有信(一八四二〜一九二八)に触れておかねばならない。
有信が生まれたのは天保十三年で、家は代々藩の御用絵師であった。
当時の風習に従って安政六年、十八歳の折りに江戸に出て狩野勝川院雅信の門下に入った。
同門には狩野芳崖や橋本雅邦、狩野友信などがいた。
有信は画学生の中でも異彩を放ち、師の勝川院から一字をもらって狩野勝沢の名前を許された。
しかし、慶応三年秋徳川慶喜は大政奉還を願い出て、十二月八日に徳川将軍職は廃止された。
江戸幕府の終りと共にお抱え絵師は価値を失い、狩野派は凋落の道をたどった。
当然のこととして有信も久留米へ戻ってきた。
ところで江戸末期からの西洋の学問は、明治を迎えて数倍の価値を生んだ。
美術の世界でも洋画熱が急速に高まった。
有信も新しい画法を学ぶ記めに上京し、洋画の手法を修めたのが明治七年(一八七四)である。
再び藩校の明善校で助教として図画を教えた。教えることは別として、彼自身はあくまで日本画の伝統を守り、狩野派の絵を描き続けた。
有栖川(ありすがわ)宮家の王女が有馬家へ嫁入りする時、江戸の藩邸内に極彩色の絵を描いたことを別にすると、三谷有信が獲得した栄誉は、明治十七年の絵画共進会と十九年の東洋絵画共進会で、狩野派の絵を出品して銅賞をもらっだことぐらいであろうか。
明治九年(一八七六)工部省の工学寮に工部美術学校が開設され、三人のイタリアの美術家が指導に当ったけれど、七年後の明治十六年に廃止になった。
つまり、復古と国粋主義を叫び、東洋の思想を主唱した岡倉天心(一八六一〜一九一三)や、日本古美術の発見者であるアメリカ人のフェノロサ(一八五三〜一九〇八)などの説によってであった。
東京・上野の杜に東京美術学校が開設されたのは明治二十二年(一八八九)のことで、十九年から二十年にかけて天心とフェノロサは美術調査委員として欧米の視察に出かけた。
帰国後の報告書には「西洋ノ事、一トシテ本邦ニ実施スベキモノナシ」と書かれている。
この二人が中心になり東京美術学校が創設されたが、洋画と彫塑は正規の科目に組み入れられなかった。
明治二十三年(一八九〇)岡倉天心は三十歳を迎えないで東京美術学校長に就任した。
東京美術学校に西洋画科が設けられたのは明治二十九年(一八九六)のことで、進歩的な西園寺公望(一八四九〜一九四○)が文部大臣に就任し、美術学校の改革を実施した結果である。
フェノロサは日本の伝統美術に盲目的な愛情を寄せて、狩野芳崖や橋本雅邦を尊敬して、日本におけるミケランジェロに比肩する者として絶賛した。
美校開校の後に橋本雅邦は日本画学科の教授になったが、橋本が再々の誘いをかけたのが、久留米で図画の教師をしている三谷有信である。
だが有信は同門の友からの誘いを断わり、美術学校の教授になろうとはしなかった。
画塾で教えることは洋画でありながら、自らは狩野派の絵を昭和の初年まで守り続けた。
明治四十年(一九〇七)三谷有信は久留米を離れて、三瀦(みずま)郡三叉(みつまた)村(大川市鍾ヶ江)に住居を移した。
六十六歳の時である。
更に晩年(大正十四年)再び上京して、消え失せた日本画・狩野派の復活を図ろうとしたけれど、時代の流れを変えることは、野人の日本画家三谷有信には不可能であった。昭和三年二月東京で死去。八十七歳。
三谷有信の画塾で教えを受けた少年がいた。坂本麟太郎である。
父親は金三郎と言い梅林寺門前の京町に住んでいた。
禄高は百五十石で中級とは言えない久留米藩の武士であったが、家を継いだのは明治十二年(一八七九)である。
妻をめとり長男の麟太郎が生まれていた。
麟太郎というのは勝海舟の幼名である。
勝海舟(一八二三〜九九)は矢部川改修工事の折りに、柳川藩からの招きに応じて訪れ、川幅を広げるだめ「庄の池」を埋め、神亀を祀る祠を建てて「住吉宮」と名づけた。
その書も残っている。佐幕開国論者であった金三郎は、師事した海舟の幼名を長男に継がせたのである。
麟太郎が日本画家のところに絵を習いに通った。
藩からの禄を離れ、細々と暮している坂本という家は自由な家風であり、教養人の家でもあった。
因縁と言おうか、麟太郎に絵の手ほどきをしたのが三谷有信であり、麟太郎の弟が坂本繁二郎である。
兄なくして弟はなく、と言ってもよいであろう。
繁二郎が絵画に心を動かしたのは兄からの影響であり、久留米という土地で森三美を知り(一八九二)、俊才とたたえられながら動ずることもなく、フランス各地を旅行して香取丸で日本に戻ったのは大正十三年(一九二四)であった。
上京を進められても応ずることなく、久留米という地方都市から動こうとはしなかった。
昭和五年(一九三〇)繁二郎四十九歳の頃から、久留米市近郊や阿蘇・雲仙などに馬を探しての取材が始められる。
昭和六年(一九三一)五十歳の七月、繁二郎は故郷の久留米を離れて八女郡福島町(現・八女市)に移住し、自宅から数町離れた畠地の中にアトリエを設立した。
その後、彼か所属する二科展に出品した絵画のほとんどは、馬をモティーフにしたものであった。
昭和十九年(一九四四)に二科会解散。その後は、どの団体にも所属しようとしなかった。
作品は主として清光会や草人社展に発表された。昭和二十一年に芸術院会員として推挙されたが、繁二郎は辞退した。
昭和二十五年(一九五〇)に眼の手術。昭和三十一年(一九五六)文化勲章を受章し、翌三十二年に再び眼疾治療のため入院した。
繁二郎の絵は、次第に幽玄の境を漂わせ始める。
繁二郎の生涯を眺めるとき、ふしぎとそこに先輩である三谷有信が重なり合ってくる。
彼らはつまり、筑後人であった。
坂本繁二郎より四ヵ月遅れて明治十五年(一八八二)七月、青木繁が生まれている。
繁二郎は京町であり、繁が生まれた荘島町とは二キロ足らずの距離である。
青木家は有馬藩の茶道職をつとめていたというが、繁の父の廉吾は硬骨の人であり激しい性格を持っていた。
母方の祖父も昔気質のきびしい人物で、繁は容赦ない鍛えられ方をして幼時を過した。
繁と繁二郎が顔を合わせたのは明治二十四年(一八九一)久留米尋常高等小学校に入学してからである。
しかし、この頃の繁にはまだ絵はなかった。だが繁二郎は既に兄と共に家で絵を描くことに夢中になっていた。
繁が絵に興味を抱き始めたのは森三美を知ってからであり、その出会いは明治二十七年、高等小学校四年生のときである。
繁は高等小学校を卒業すると同時に、明治二十八年(一八九五)旧藩校である中学明善校に進学したが、繁二郎は家庭の事情で中学へは行けなかった。
明治十九年、五歳の折りに父を失っている。
貧しい中で兄の麟太郎が明善校から京都の三高に入学していた。
繁二郎は兄が大学を卒業するまで、待っていなければならなかった。
繁の心には、次第に洋画家としての夢がふくらんでいた。
だが、父の廉吾が簡単に許そうはずはなかった。
中学三年のとき、数学の点が悪くて繁は四年生に進級することができなかった。
このことがきっかけとなり、明善校を退学、上京が実現したのである。
上京した青水繁は不同舎に入門した。明治三十二年(一八九九)七月である。同門には国分浜国太郎(小杉放庵)などがいた。
明治三十三年四月、東京美術学校洋画科選科に入学。繁は目的の第一歩を確実に踏み出していたが、久留米で絵の勉強に励んでいた繁二郎は、同じころ、三高卒業を目前にした兄麟太郎の病死に出会っていた。
繁二郎は久留米から離れることができなかった。兄の大学卒業を辛抱強く待っていた繁二郎の望みは、あっけなく断ち切られた。
森三美の世話で繁二郎は、明冶三十三年から久留米高等小学校で図画の代用教員をすることになった。
明治三十五年(一九〇二)徴兵検査で久留米に帰国した青木繁は、八月の末に坂本繁二郎を連れて東京に戻ってきた。
繁二郎は不同舎に入門したが、翌三十六年から太平洋画会研究所に通い始めた。
当時の洋画界は黒田清輝、和田英作、岡田三郎助、藤島武二などの白馬会が主流であり、太平洋画会は三十五年に中川八郎や満谷国四郎らが創立したものであった。
東京で久留米高等小学校の同級生が二人揃った。いま一人は丸野豊であった。
三十四年九月に丸野豊も東京美衒学校洋画科本科に入学していたからである。
青木繁の傲慢さと傍若無人の態度は変ることがなかった。
いま一つは度のはずれた貧乏ぶりで、借金は返したことがなく、他人の絵具をことわりもしないまま平気で使った。
明治三十六年秋、白馬会は第八回目の展覧会を上野公園で開いたが、この年から白馬会賞が設定された。
そして、第一回白馬会賞を獲得したのが無名の新人・青木繁だったのである。
それは「黄泉比良坂」(よもつひたざか)などの作品で、神話をモティーフに水彩や色鉛筆で描いたものであった。
明治三十七年夏、青木繁は東京美術学校を卒業した。
卒業と同時に房州布良(めら)の写生旅行を計画した。
同行したのは森田恒友、坂本繁二郎、そして運命の女性の福田たね女であった。
福田たねは明治十八年(一八八五)栃木県芳賀郡水橋村(現在の芳賀町)で、呉服商福田豊吉の次女として生まれた。
子供の頃から絵が好きで、単身上京して不同舎に入門したのは明治三十六年であった。その年の秋に、青水繁は第一回白馬会賞を受賞したのである。
白馬会賞をもらったことで、青水繁に対する彼女の目が変った。
一般的に言うなら青木繁の才能には敬服しても、人間的な信頼感情を抱く者はいなかった。
ところが福田たねにとっては分離した感情は全くなく、ひたすら青木繁に傾倒し始めたのである。
傾倒して行っだのは青木繁の方が先だったかも知れない。
干葉県布良海岸(現在の館山市)への写生旅行で、青水繁はまず福田たねを獲得した。
続いて「海の幸」の大作を描き上げた。
明治三十七年は日露戦争の年であり、旅順港が陥落しないまま、日本の国民は異様なまでに緊迫していた年である。
秋九月、上野公園で第九回白馬会展が催された。
そして「海の幸」は画壇だけではなく、一般の人にもすさまじい感動を与えたのである。
だが、このときを境に青木繁は下降線をたどり始めた。
名声とはうらはらに、貧乏の度合いは一段とひどくなっていた。
加えて彼には人間的な信頼を寄せる者がいなかった。
最後まで一緒に暮した坂本繁二郎が、青木繁と別れたのは三十八年四月である。
話はそれるが、久留米の南に隣接して柳川市がある。沖の端の酒造家「油屋」にトンカ・ションが生まれた。
北原白秋(一八八五〜一九四二)である。
酒の銘柄は「潮」と言った。神童と言われていたが、中学伝習館で三年生に進級することができなかった。
成績は学年で三位であったが、数学の点数が不足した。落第に加えて失恋、更に明治三十四年三月に生家は火災に遭い、酒蔵と六千石余の酒が焼失した。
北原白秋の上京は三十七年四月であった。
だが、筑後が生んだ画家と詩人とは奔放な人生を歩きながら、一度も交わることがなかったのである。
繁とたねとの間に子供が生まれていた。
このことは昭和二年(一九二七)の春、朝日新聞社主催で「明治大正名作展」が上野で催された折り明るみに出た。
遺族が名乗り出たからである。
証拠品は「ヘソの緒」で、ヘソの緒を包んだ紙には「明治三十八年八月二十九日誕辰 於茨城県真壁郡伊諾村川島 青木氏第一子幸彦」と書かれていたという。
福田幸彦――つまり福田蘭童である。
明治三十九年の暮れ、青木繁はたねの実家にいて渾身の力作「わだつみのいろこの宮」の制作にすべてを賭けていた。
日露戦争が勝利のうちに終り、明治四十年(一九〇七)東京府勧業博覧会が開催されることになり、画壇ではこの博覧会に賭けて満を持していたのである。
出品審査は三月二十一日からであったが「わだつみのいろこの宮」が完成したのは三月二十日であった。
この作品に青本繁は絶対の自信を持ち、新聞などの評判もよかったが、審査が延びた。審査が延びただけ一般の評価は高まったけれど、七月に行われた結果の発表は意外なものであった。
青木繁の「わだつみのいろこの宮」は三等賞の十席であり、坂本繁二郎の「大島の一部」が三等の一席で入賞した。
このことに関しては坂本繁二郎が「太平洋画会系と白馬会系が勢力争いを行い、審査は必ずしも公平ではなかった。
私自身、自分の作品が青木のものよりよかったとは思わなかった」と語っている程である。
ここから天才画家・青木繁の晩年が始まる。晩年と言っても、まだ数え年では二十六歳であった。
第一回の文部省美術展覧会、つまり「文展」が開催されたのは明治四十年(一九〇七)である絶対の自信を持つ青木繁はここでも敗れた。
最高賞は和田三造の「南風」が獲得した。加えて一通の電報が舞い込んだ。「チチキトク」の知らせであった。
福田たねと、生まれて間もない長男の幸彦に対しても責任がある。
その責任が果せない男の苦しさを、たねの父親の豊吉に手紙で訴えている。
つまり「小生一家を成し候上にて改めて幸彦引取に罷出候在念……」と書き「幸彦儀の事何分御願申上候」と記している。
四十年八月、青水繁は久留米に帰ったが、前夜の二十一日、父親の廉吾は息を引取っていた。
そして、彼を待っていたのは父の負債と、母や姉と弟たち五人を養って行かねばならないことであっだ。
金銭的には無知と言ってもいい青木繁にとって、このような負担は気が狂いそうな思いであったに違いない。
そして、酒におぼれ女におぼれた。結果は破滅でしかない。
わかっていても青木繁という人間は別の道を歩くことができなかった。
青木繁の伝記を読むときに、イタリア人の画家モデリアニ(一八八四〜一九二〇)を思い出すことがある。
明治四十年夏八月、久留米駅に下車した青木繁は、再び東京行きの上り列車に乗ることがなかった。
わがままと自尊心を頼りに迷惑をかけながら、二十八年と八ヵ月、明治四十四年(一九一一)も春浅い三月下旬に、福岡市の病院で悲劇的な生涯を閉じた。
息を引取る寸前まで青水繁は傲岸の人であったという。
青木繁が少年の頃に訪れた山がある。久留米市東方の高良山寄りの兜山である。
いまは耳納(みのう)スカイラインが通じていて通称を「ケシケシ山」という。
思い出の山だったのであろう「当地にて焼き残りたる骨灰は序の節高良山のケシケシ山の奥の松樹の根に埋めて被下度……」という手紙が姉(つるよ)と妹(たよ)あてに書かれている。
青木繁の願いがかなえられたのは、戦後の昭和二十三年(一九四八)坂本繁二郎らの手によってであった。
記念碑が建てられ、望郷の歌が刻み込まれた。
青木繁は多くの短歌を作っており、帰郷前の作品を「うたかた集」、その後のものを「村雨集」と名づけて、彼自身で詠草を整理していた。
父となり三年われからさすらひぬ
家まだ成さぬ秋二十八
今日明日とただかりそめの草枕
旅に三とせを重ねけるかな
わが国は筑紫の国や白日別(しらひべつ)
母います国櫨(はぜ)多き国
転々として無軌道な生活と激しい疲労の日を過していた放浪時代の短歌である。
記念碑には最後の短歌が刻み込まれている。
放浪の旅は久留米から鐘が江、佐賀、小城、唐津、そして博多へと続けられた。
青木繁の祥月命日は三月二十五日である。
前後の頃の日曜日に兜山の記念碑の前で「けしけし祭り」が催され、長男の幸彦こと福田蘭童が毎年のように参加している。
激情の画家・青水繁と理性の画家・坂本繁二郎の二人は、ともに「筑後人」である点に変りはない。
3 井上伝女とからくり儀右衛門 top
久留米藩の財政を潤した木蝋は、中国から伝来して貞享(一六八四〜八八)の頃種子を桜島(鹿児島)に移植したことに始まるとも言われ、九州の各藩ではこれを奨励し、次いで四国・紀州・山陰などの暖地帯で普及した。
福岡県は全国でも最多産で、県内では筑後を主とし八女郡に最も多い。
櫨(はぜ)の全国年産額は明治の中頃までは九千万斤を下らなかったが、昭和十年(一九三五)には三千万斤に減少している。
養蚕業が発達したためであった。
その内訳は福岡県が一千万斤で、佐賀・熊本でそれぞれ四百万斤、長崎の三百、大分の二百など、その他の総計による数字である。(『続久留米市誌・下巻』による)
次に傘の由来は古いけれど「筑後章」の元祖は文政(一八一八〜三○)天保(一八三〇〜四四)のころ佐藤住助が始めたというが、記録や文献は残っていない。
しかし、家業は子孫に伝えられ、同業者がふえた。筑後の山間には良質の竹があり、八女(やめ)地方の和紙が生産されていたからであろう。
その結果、大正・昭和の最盛期には、岐阜県に次いで全国二位の雨傘を作り出している。
前置きが長くなったが、大正年代に百五十万反を生産して一千万円の収益を上げ、今日なお無形文化財として珍重されているのが「久留米がすり」である。
久留米がすりの起源は、寛政(一七八九〜一八〇一)も末期の頃と言われ、十四歳の少女・井上伝(でん)によって発明されたと伝えられている。
同じ年代に北九州の小倉では「小倉織り」が流行し始めていた。
木綿の織物で、紺と白の糸をより合わせた霜降り模様が多かった。
素朴であり丈夫で、明治年代の書生たちは必ず小倉織りの袴を着けたものである。紺色だけのものもあった。
更に「霜降り」という言葉は昭和の初年まで残り、当時の中学生(現在の高校生)は制服として着用させられた。
小倉織りは小倉の城下町や周辺の農村で織られたものである。
井上伝は天明八年(一七八八)十二月に三井(みい)郡久留米通り外町で生まれた。
七、八歳の頃から木綿織りを習っていたが、衣服の洗いざらしに色のあせた部分と白くなった斑点を見つけ、かすり発明の端を開いたと語り継がれている。
これが十四歳の頃だという。
見た目には「かすった」ようなので「加寿利」と銘を打ったけれど、当時の人はアラレのようだ、霜降りのようだと評して「霜降織り」または「霰織り」などと呼んだ。
だが一般的に流行したのは「おでん絣(かすり)」であった。
終戦後の昭和二十年代も終りの頃、赤坂小梅(コロムビア)によって久留米地方の機織(はたお)り娘が、唄で歌われるようになった。 |

井上伝の墓所・徳雲寺
|
当時は「久留米の機織り娘」という題目であったけれど、いまは「久留米のそろばん踊り」とも言われている。
方言と機織り娘の生活を表現した素朴な民謡である。
私しゃ久留米の 機織り娘よ
化粧ほんのり 花なら蕾よ
私しゃサイノ 久留米の日機織(ひばたお)りでございますモンノ 私しがっサイ
日機バ織りよりますとサイノ 村の若い衆(もん)が来て 遊びげ行かんノ 遊びげ行かんノ
と言いますもんノ 遊びに行きとうはありますバッテン 日機がイッチョン 織れまっせんもんノ
惣れちゃおれども まだ気がつかんかね
この唄の伴奏楽器が「そろばん」であったことから「そろばん踊り」とも言われる。もと唄は卑猥であった。
つまり「村の若い者が来て 一ちょサセンノ と言いますもんノ させとうはありますパッテン……」ということになる。
浮気はしたいけれど浮気をしていると、ノルマが果せない。
唄の文句にある「日機」というのは「一日に一反を織る」ことである。
それができない農家の娘は、嫁の貰い手がないと言われた時代であった。
記憶をたどると祖母たちは一本一本糸車にかけて糸を撚っていた。
その糸を束ねた後で藍色に染め、乾かしてから機にかけて、日向に近い場所でトンカラリと老眼鏡をかけながら機を織っていた。
サオが左に走り右に走る。トントンと音がして、かすりの織り目がふえて行った。
井上伝は、二十一歳で原古賀の井上家に嫁ぎ、平山の姓から井上に変った。
平太郎・浅吉・糸の三子を産んだが二十八歳で夫の死に会い、子供を連れて里方に帰った。
自活の道をひらくために織屋三棟を建てて(現在の南薫小学校東側)おでん緋の指導をし、名声を高めたのである。
井上伝女の絣に次いで、明治の初年には小川トク女による久留米鎬などが考案されたけれど、知る人は少ない。
井上伝は明治二年(一八六九)四月、八十二歳で死去した。
井上伝女と同じ土地から田中久重が生まれている。
大発明家として有名になった田中久重は、別の名を「からくり儀右衛門」という。
近所のよしみで十五歳の頃から、機(はた)織りと図案に対し意匠と工夫をこらして、井上伝を助けたと言われている。
久留米市の東に当る石橋文化センター斜め前に五穀神社があり、南側の米屋の平山家が井上伝女の生家であった。
その近くの家で十一年遅れて寛政十一年(一七九九)に生まれたのが、からくり儀右衛門と愛称された田中久重である。
からくりというのは『国語辞典』によると
「糸の仕掛けであやつること。またその仕掛け。からくり人形。また一般にちょっとした自動装置……」
と書かねている。からくりは江戸時代の文化の一つであり、大衆と共に発達し保存された。
現存しているのは岐阜県や愛知県に多い。
春から秋にかけて、山車祭りには伝統のからくり人形が人々の目を奪う。
飛弾高山の春祭りに始まり、犬山市、大垣市、東海市などである。
からくり儀右衛門がその才能を発褌したのは五穀神社の秋祭りの折りであった。
二十五、六歳の頃、境内の池にめぐらされた舞台で、人形たちを活躍させた。
波間からせり上がる鳥居や、次々と矢筒から矢を吹いて的を倒す人形などであったという。
からくり師たちは通常土地にとどまり、名人であったということで生涯を終えているが、儀右衛門の足跡は久留米だけではない。
嘉永三年(一八五〇)に江戸で四百日巻きの万年時計の製作に着手し、翌春に完成。
この万年時計は国立科学博物館に秘蔵されている。
佐賀十代藩主鍋島閑臾(直正)は名藩主として名高いが、嘉永五年十一月、佐賀市多布施(たぶせ)川のほとりに精錬所(藩の理化学研究所)を作らせたが、その中心になったのは田中近江・儀右衛門父子や中村奇輔などであり、他国人であった。 |
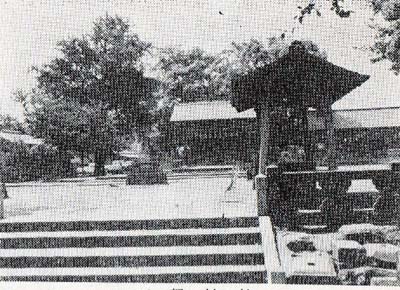
五穀神社
|
推挙したのは精錬方主任の佐野栄寿左衛門(後に日本赤十字社を創設した佐野常民)であった。
日本で初めて陸(おか)蒸気(汽車)が走ったのは、明治五年(一八七二)九月十三日に、新橋と横浜間のことであったが、九州では安政二年(一八五五)八月七日、わが国最初の模型機関車が佐賀藩士たちの期待と好奇の中で動いており、蒸気車の運転は慶応元年(一八六五)七月、長崎の大浦海岸で行われている。
蒸気車はイギリス製であったが、模型機関車は閑臾の命を受けて中村奇輔や田中久重(儀右衛門)などが、三年ぶかりで製作したものであった。
嘉永六年(一八五三)七月、ロシアの艦隊が長崎に寄港したが、パルラダ号の士官室で模型機関車の運転が行われたのが、事の始まりであった。
蒸気車一両と貨車二両、燃料はアルコールを使用する模型であった。
模型機関車が走ってから十年後の慶応元年(一八六五)九月、日本で初めての蒸気船「凌風丸」が三重津の造船場で完成した。
鍋島閑臾が長崎奉行所購入の小型蒸気船を借り受けて、中村奇輔や田中久重らに構造を研究させていた、その結果の製造物であった。
『久留米市誌』付録の年譜によると、
一八六三(文久三年)この年田中久重、久留米藩鑓水(やりみず)製造兼務となる。(毎月上半は佐賀、下半は久留米)
とあり、見に同年十月の項目には「鑓水にて大砲鋳造に着手す。製造所は鑓水古飯田「御并町風流田にあった」と書かれている。
久留米藩が田中久重に目をつけた時は、既に十年以上も手遅れであった。
隣藩の佐賀では嘉嘉永元年(一八四八)に、火縄銃をすべて新式銃に切替えており、嘉永五年の秋には、自分の藩で鋳造した大砲五十余門を長崎港外の島々に備え、警備に当っていたのである。
いわゆる王政復古の劇的舞台で、佐賀は一歩も二歩も遅れを取った。佐賀藩は動かなかった。
その代り勤皇・佐幕の二派に分れでの抗争も起きなかった。
その佐賀藩が、薩・長・土・肥といわれるまでに至ったのは、新兵器による軍備のためであった。
戊辰戦争での活躍は、上野にたて籠った彰義隊を一日で壊滅状態に追い込んでいる。
白虎隊で知られる会津若松での戦いも、佐賀藩自慢のアームストロング砲が大きくものを言ったのである。
その結果として佐賀藩は、やっとのことで「明治丸」に乗込めたのであった。
『久留米市誌』付録年譜には
「一八一三(文化十)年 この年田中久重、絣創業に関与した胼組み方及びその機械を発明す。年十五歳」
とあり、万年時計の製作に着手した嘉永三年(一八五〇)まで、彼の名前は出てこない。
十五歳で市史に残る発明を成し遂げた才能ある少年が、五十二歳になるまで何もしていなかったはずはない。
つまりこの間に田中久重は、ひそかに研究を続けていたのである。研究費は「からくり人形」を持って各地を廻り自分で稼ぎ出した。
例えば大阪の道頓堀では五十日間の興行を打っている。
からくり儀右衛門の名前は、久留米だけのものではなかった。
慶応二年(一八六六)六月には製氷機を発明している。
この年に田中久重は藩の開成方(成産方)の主事・今井栄に従って上海に赴いている。
翌三年七月、久留米藩は今井栄らに命じて水軍取調・軍隊の編成・非常立退場所・四境の警備等についての調査をさせ、同年十一月、開成方主事の今井栄らを長崎へ派遣して、英国製の汽船を購入した。
千歳丸である。備砲六門、六〇〇トンの船で、八万五〇〇〇ドル(六万七千五百両)であったと書き残されている。
この千歳丸は明治元年(一八六八)六月二十八日、海軍軍船として越後の討伐に出発して、十一月十八日若津港に戻ってきた。
ところで納戸役から開成方主事として活躍した今井栄は、明治元年二月に佐幕派であったことから御咎(おとがめ)を受け、次いで四月十八日には揚屋入りを命ぜられている。
運のない人とでもいうべきであろうか。更に彼は明治二年一月二十四日、国是の妨げになるということで切腹を命ぜられ、翌日の夜、徳雲寺で自らの命を絶った。
明治四年、南薫(なんくん)の久留米製進所は閉鎖されて、その後は田中久重の経営となるが、南薫町に久留米製鉄所が開設されたのは、明治二年(一八六九)のことである。
明治六年(一八七三)一月、七十五歳の田中久重は要請があって東京に出た。
電信機や電気機械を製作するためであった。芝の田中工場で十年近く、彼の製作は続けられたが、明治十四年(一八八一)十一月七日、八十三歳で多彩な一生を終えた。
実子がなく二代目の田中久重は養子が継いだ。明治二十年(一八八七)田中工場は従業員の数が六百八十名という大工場に発展した。
その後、田中工場は芝浦製作所へと変身して行く。
4 地下足袋 top
久留米という所は不思議な土地である。
徳川幕府の鎖国によって、海外の事情を知らされないまま二百六十年余の年月を過し、それから後はすべてが西洋の文化への物真似時代が続いた。
ヨーロッパをしのいだものは、柿右衛門を代表とする有田の陶磁器ぐらいなものである。
だが明冶を迎えての日本でも、発明されたものが存在した。
人力車と地下足袋である。
今日的な製品ではないけれど、大正年代末期(一九三二)の頃から約三十年間、日本人にとって地下足袋は、なくてはならない作業用の履物であった。
そして、地下足袋の創始が久留米という土地であった。
この種の産業は、まず「座敷足袋」に始まり「地下足袋」が作られ、更に「ゴム産業」へと発展して今日の久留米市を支えている。
久留米で足袋を作ろうと考えだのは倉田雲平(一八五一〜一九一七)である。米穀や呉服類を扱っていた。
座敷足袋とは縁のない久留米という土地で、十七歳の少年・倉田雲平が足袋に目をつけたのは、どんな理由からであったろうか。
その当時、木綿は埼玉県や大阪方面から移出されていた。
足袋作りの本場は長崎であり、ほとんどが自分で足袋を縫っていた時代である。
明冶三年(一八七〇)二月、二十歳になったばかりの雲平は長崎へ行き小川源助の弟子になった。
足袋作りの修業を終えて久留米に戻ったのは明治五年九月である。
屋号を「つちやたび」と名づけ、独立の旗上げをしこのは明冶六年(一八七三)十月であった。
当時は足袋など庶民には無縁のものであった。
明治三十年(一八九七)七月の定価表によると、十文三分(二四センチ弱)の白足袋が十九銭で、紺足袋は二十五銭と印刷されている。
明治三十八年には同じ文数の白足袋が二十六銭五厘で、紺足袋は三十銭五厘に上昇している。手が出なかった。
それはさて安政五年(一八五八)に、久留米篠山(ささやま)城下の士族の家で男児が出生した。
名前を徳次郎という。龍頭という家の子供であった。
商人である叔父の緒方家に身を寄せて、長女のまつと結婚した後、同家の親族・石橋家を継ぐことになった。
石橋徳次郎が明治二十五年(一八九二)に創業したのが 「しまや足袋」である。「つちやたび」と「しまや足袋」は恵まれたライバルとして成長した。
草履やわらじの不便さを補った履物として、縫付足袋、はだし足袋、ゴム底足袋などという広告を見た記憶がある。
この頃久留米では、木綿足袋とゴムの接着について、社運を賭けての競争が始められていた。 「つちやたび」がゴム底の地下足袋に目をつけたのは大正九年のことで、シンガーミシン会社の支配人が、アメリカ製のキャンバス・シューズの見本を持っていたことに始まる。
直ちに技術者が神戸のダンロップ会社に派遣された。足袋については抜群の破能者だが、残念なことにゴムに関しての知識は未熟であった。
日本で最初にゴム靴が作られのは明治四十一年(一九〇八)のことで、東京の三田土ゴム会社が作っている。 だがこれは試作に終った。
本格的に作り始められたのは大正八年(一九一九)の頃であり、神戸を中心とした関西方面だったのである。
一方「しまや足袋」の石橋徳次郎が東京の三越で、テニス用のズック靴を見つけたのが大正十一年(一九三一)だと伝えられている。
弟の正二郎と共に研究し、山の形のすべり止めもこの折りの考案だという。 |

地下足袋第一号
|
三井炭坑(大牟田)で試用の結果、大正十二年一月から「地下足袋」と名づけて売り出した。
別の名を「アサヒ足袋」ともいう。
木綿の足袋にゴムを接着させることは、容易ではなかった。
これを指導したのは第一次世界大戦で捕虜として久留米に収容されていたドイツ人の、パウルヒル・シュベルゲルである。
そして地下足袋は大正十二年に二百万、十三年に四百万、昭和三年には一千万、昭和十年は二千万足と、加速度的に需要を増加した。
しまや足袋は徳次郎の長男が大正七年(一九一八)に「日本ゴム」 を創設して、二代目徳次郎になって、弟の正二郎が、会社を設立したのは昭和六年(一九三一)である。 その名を「ブリヂストンタイヤ株式会社」という。
着想は早かったけれど、倉田家の「つちやたび」は「しまや足袋」に後れを取った。
大正十一年十二月に成功して翌年一月に、一足一円三十銭で売り出したが、難事が続出した。
しかし、昭和二年一月に久美愛地下足袋として生産を開始している。
久美愛というのは現在の農協のことで、久美愛はすなわち「組合」のことである。
昭和初年の頃は組合などという文字は卒直に使うことができなかった。つちやたびは、現在の「月星化成」である。
5 高良山・善導寺・大善寺 top
筑後国久留米は、高良山に始まると言って過言ではない。
『旧前風土記』には、景行天皇十二年(八二)の頃「天皇高良の行宮に駐留」とあり、十八年(八八)に「筑紫後国(しりのくに)」の名が日本書紀に見られる。
「筑後国」の名は、日本書紀によると持統天皇四年(六九〇)のことである。
久留目の名を見るのは更に遅く、応永二十五年(一四一八)のこと(三潴報恩寺畑地坪付)である。
高良山に高良玉垂宮が創建されたのは、履中天皇元年(四○○)と伝えられている。
文武天皇の大宝元年(七〇一)に大宝令が施行され、西海道が置かれて九州は筑前・筑後・肥前・肥後・豊前・豊後・日向の七国となった。
太宰府が完備したのは元明天皇の和銅元年(七〇八)と伝えられ、聖武天皇の天平十三年(七四一)の頃には、筑後に国分寺や尼寺が建立されている。
標高三一二メートルの頂上に近い高良神社は、弘化九年(八一八)に玉垂命(たまたれのみこと)という神号が贈られ、更に寛平六年(八九四)高良玉垂命は正一位を授けられている(『日本後記』)。
後醍蝴天皇の頃、天皇親政を主張したいわゆる「建武の中興」によって征西将軍・懐良(かねなが)親王が九州に下ってきたのは、南朝の延元三年(一三三八)であり、北朝の年号では光明天皇の暦応元年であった。
高良山は浮羽・朝倉・三井・三潴・八女の平野を一目に見下ろす要害の土地であり、その間を筑後川がうねり流れて有明海に注いでいる。
懐良親王を迎えて肥後の菊池氏、豊後の大友氏、薩摩の島津氏、太宰府の少弐氏、筑後の守護にも当っていた九州探題の一色氏などが、高良山をめぐっての戦いを繰返した。 |

高良大社拝殿
|
南・北の朝廷が一つになり、足利政権が全国を統一しだのは後小松天皇(北朝)の明徳三年(一三九二)である。
懐良親王の薨去は後亀山天皇の弘和三年(一三八三)八女郡矢部村においてであった。
昔は神仏混淆の時代があった。その名残りを現在に残しているのが京都・東山の清水寺である。
高良宮司の大祝家の三男隆慶が仏門に入り、社僧として高良山の北に連なる茶臼山に高隆寺を初め妙音寺や薬師寺を建てたのは、天武天皇の自鳳二年(六七四)の頃と伝えられる。
年代と共に高良山は勢力を伸ばして仏教の花開くころ、神領は一万町歩に近く、二十六寺三百六十坊というすさまじいまでの社寺に発展した。
九州で一大勢力を握った社寺に英彦山があり、俗説によると「三千八百坊」というけれど、昔から言われるように「三と八に実数なし」というのが正解であろう。
しかし、英彦山が大名にも匹敵する勢力を持ったのは事実である。
高良山も同様であった。
筑後の国分寺にとって代って平安中期ごろからは、座主の名をほしいままにして一千余人の寺僧を持つ豪族となり、薙刀を振りまわす叡山の僧に似た存在になっていた。
天正年間(一五七三〜九二)に、肥前の龍造寺と豊後の大友氏の間を行ったり来たりした四十四世座主の良寛や、最初の久留米城主・毛利秀包(ひでかね)を手こずらせて討たれた良寛の弟、四十五世の麟圭など、栄枯盛衰を自ら体験して生き抜いた人と言える。
『久留米年譜』によると、永正年間(一五〇四〜二一)に土豪が初めて「笹原城」を築く、と書かれている。
笹原城は後の「篠山(ささやま)城」である。天文年間(一五三二〜五五)に、荒れ果てた笹原城を御井の郡司が修築したという記事もある。
程なく久留米の一帯は、再び戦乱の巷になり果てる。
年表によると、
永禄七年(一五六四)
永禄十二年(一五六九)
元亀元年(一五七〇)
天正元年(一五七三)
天正六年(一五七八)
天正八年(一五八〇)
天正十二年(一五八四)
同年十月、 |
大友義鎮(宗麟)筑後を平定し、高良山に入り諸豪を引見す。
龍造寺征伐の記め義鎮高良山に出陣、吉見岳に陣す。和議。
大友軍高良山に出陣し龍造寺軍に攻められ、豊後に退く。
高良山座主・良寛は弟の麟圭をもって笹原城主とする。
龍造寺隆信は高良山に陣を取り、弟の麟圭が自ら座主となる。
大友方の兄・良寛と座主をめぐって争う。
隆信、良寛を降し筑後五郡を平定し、水ヶ江(佐賀)に帰る。
龍造寺隆信は島津との戦いで、島原において討死。
大友の部将戸次(べつぎ)道雪・高橋紹運など高良山に陣す。 |
ということになる。
肥前の豪雄、龍造寺隆信が島津の軍勢と戦い、武運つたなく島原で戦死を遂げたのは天正十二年三月であったが、翌年の春四月に、龍造寺政家は二万の大軍を引きつれ高良山を攻めた。
東久留米の野中に陣を敷き、迎えるは大友軍の戸次(後の立花)道雪・高橋紹運と、高良山の座主良寛が率いる衆徒など合わせて約一万人。
筒川(現在の石橋文化センター近く)や祇園原などで激戦が展開された。
九月、戸次道雪は陣中で病死し、十月、戦いに敗れた大友軍は良寛を伴って退山した。
天正十四年(一三八六)に島津義久の軍が高良山を攻め、火を放ち、いろんなことがあったけれど、翌十五年には島津征伐の豊臣秀吉が、春四月に三十五万余の軍勢をつれて高良山に入り、西方の吉見岳に陣を敷いた。
筑後十郡(生葉・竹野・山本・御并・三原・上妻・下妻・三潴・山門・三毛)が五人の諸侯に与えられたのはこの時からである。
天正十五年、毛利秀包(ひでかね)が久留米の城主に任命された。禄高は三万五千石。
その後、文禄・慶長の戦い(朝鮮出兵)で五万五平石の加増(一五九三)になったが、関が原の戦いに出陣(一六〇〇)して西軍に味方し、領地を没収された。
そして翌慶長六年に、赤間の関で死去している。三十五歳であった。
秀包の正室は大友宗麟の女であった。
だが、大友家の庇護を受ける高良山座主の良寛の弟、辯圭との間がうまく行かず、両者は筒川をはさんでの戦いを交えたりした。
そして天正十九年(一五九一)五月、秀包は和議にことよせて麟圭を城中に招いて惨殺した。
この折りに討たれた主従を弔う「八墓の石塔」が、玉椿神社のほとりに残っているが、いまはバーや喫茶店のかげに隠れ果てている。
供養の祭りは八月二十日ごろだが、ほとんど知る人もいない。
後年、田中吉政の頃に高良山の初代僧正を号した尊徳(四十六代座主)は、辯圭の子の秀虎丸であり、それまでは龍造寺家にかくまわれていたと伝えられている。
高良山(こうらさん)という信仰の山と神社は、水縄(みのう)山脈の西の端にある。
水縄山脈というのは筑後川の南側を川に沿って東西に連なっている山のことで、約二四キロの山の姿は、京都の東山連峰に似た美しい形を見せている。
標高二五〇メートルの高良神社社殿の後方から更に西の山麓にかけて、約一・六キロの間に、連なって並ぶ不思議な石がある。
古くからこの列石に対して「高良山神籠石(こうごいし)」と呼んでいる。
神籠石というのは小高い山地に、数キロにわたって、七〇センチほどの方形の切石が配列されたものの名称である。
その配列は、普通二〇〇メートルから四〇〇メートルの山頂を取囲み、谷を含めている。 |

神籠石
|
尾根を下るときは分水線の外側に列石を並べ、谷を渡るときには水門が設けられている。
形としては朝鮮式の山城と同じであるが、議論が分れた。つまり山城説と神城説である。
だがこのことも解決された。佐賀県の「おつけ山神籠石」と「帯隈山(おびくまやま)神籠石」の発掘調査の結果であった。
山城であることが証明された。だが、方形の石の外側の一角がL字型に削られていることなど、わからない点が多い。
神籠石は佐賀県に二ヵ所、山口県に一ヵ所、福岡県に六ヵ所発見されている。
しかも筑後に三ヵ所で、山門(やまと)郡瀬高町女山(ぞやま)と、筑後川北岸の朝倉郡杷木(はき)町からである。
久留米市東郊外の善導寺町に、善導寺という浄土宗の寺がある。
ここには浄土門の開祖である唐時代の高僧・善導大師の木像(重要文化財)や、わが国での浄土門第二の祖であり、この寺の創建者・大紹正宗国師の座像(重要文化財)などがある。
浄土宗の開祖・法然は善導の流れをくむ者であり法然の高弟が、浄土宗の鎮西本山・善導寺を建立した正宗(聖光上人・鎮西上人とあがめられた名僧)である。
建久二年(一一九一)つまり源頼朝が鎌倉に幕府を開く前年のことである。
このあたり、久留米市東方の山本町には永勝寺があり、天武天皇の白凰九年(六八〇)に建立と言い、また同じ山本町の曹洞宗の寺院・観興寺にも、天智天皇(六六二〜七一)の勅額を賜わったという伝説がある。
真疑は別としてもこの一帯の古い寺院には、貴重な文化財と、歴史の経過を知らずに眠り続ける何ものかが残されていることは、確かである。
山本町の手光寺には征西将軍・懐良(かねなが)親王の墓標がある。
千光寺は筑後草野の城主・草野永平が栄西(ようさい)禅師に開山させた名刹だという。
承元二年(一二〇八)ごろの創建である。栄西は宋国から帰朝後の建久六年(一ー九五)から十ヵ年の歳月をかけて、福岡市にわが国で最初の禅寺(臨済宗)聖福寺を開山した名僧である。
まだ栄西は佐賀県背振山に茶の種をまき、茶山を作った茶の開祖でもある。
語り伝えられ、更には記録もあるけれど、その年代は必ずしも一致していない。
それぞれの時点においての記述である。だが忘れてならないのは大事業を行わせたスポンサーである。その姓を草野氏という。
史書に草野氏は多く語られてはいない。年譜によると「片寛二年(一一六四)草野永経肥前より草野吉木に来り、竹之城による」とあり、続いて文治二年(一一八六)に「草野永平筑後国国司、押領使となる」と書かれている。
つまり、草野の一族が永経を主として肥前から筑後に来り、吉木のあたりに住みついた。
平清盛が太政大臣になる三年前である。近くの一帯に寺院を建て、更には古寺を復旧した。
安徳天皇の寿永四年に平家一門は壇ノ浦の戦いで滅び去り、平家の残党は九州へと逃れるが、草野氏は平家一族をかばうことなく召し捕えた。
その結果、源頼朝から認められて筑後の国司に任ぜられた、――というのが一つの推理である。
しかし、その後は数年で中原景良が領主となり、続いて武藤資頼、大友能廱、藤原基頼の名はあるけれど、草野氏が領主になった記述はない。
だが弘安四年(一二八一)草野永綱は元寇の役に出陣、その子経永敵船を襲う、という記事がある。
地位はなくても、草野の一帯にじっくりと根を下ろした実力者だったのであろう。
正平二年(一三四七)の筑後の守護は一色(いっしき)直氏である。
次いで少弐頼尚が後を継ぎ、草野武経が領主となるのは正平十三年(一三五八)、北朝の年号では延文三年である。
征夷将軍の懐良親王や五条頼元を奉じて肥後の菊池武光が、高良山や水縄山に陣を敷き、少弐頼尚や大友氏時を相手に激戦を交えているころであった。
菊池武光が肥後に後退するとともに、筑後の領主は草野武経から惟宗広憲(これむねひろのり)に交替した。
文中二年(一三七三)のことである。
久留米市草野町に、草野一族の居城・発心城を背にして専念寺がある。
大楠に囲まれた御堂は草野鎮永(家清)の頃の再建だという。
草野一族は久留米や浮羽郡の一帯に文化財と伝説を残して、天正十五年(一五八七)四月、三十五万余の軍勢を引き連れ九州征伐のため訪れた秀吉により、一族は自刃し、草野氏は断絶した。三万五千石、毛利秀包が久留米城主になるのである。
専念寺の北面の庭は「遠州の庭」と呼ばれている。茶人・小堀遠州は、黒田藩の高取焼を指導しただけでなく、久留米藩でもその名声を伝えている。
いま一つ、草野町には祇園神社がある。草野永平が建久八年(一一九七)に勧請したという。
本殿・拝殿・楼門が県指定の文化財になっている。
文化財はともかくとして、筑後の村や町には「お祇園さん」の数が多い。
京都のような本格的な祇園祭りではないが、田舎育ちの子供の心に、年に一度だけ、華やかな心の灯を残してくれる夏祭りであった。
その発進地が草野の祇園神社ではなかろうか。
祇園祭りがすんだ後「よど」という夜祭りが催された。“よど”は神社がない土地でも行われた。
つまり「夜渡り」なのであろう。祇園神社の御神体は下宮に下り、数日後に本宮に戻る。
「お下(くだ)り」と呼び「お上(のぼ)り」と称した。
京都八坂神社の祇園祭りは、七月十七日が神幸祭で二十四日の夜還幸となる。
盛大な祭りの行事ができなくて、一部の形式をまねして「夜渡(よど)の神事」だけが行われ、引き継がれていたのかも知れない。
久留米市山川町の王子若宮八幡宮に、福岡県の無形文化財に指定された「動乱蜂(どうらんばち)花火」がある。
九月十五日の夜、王子山頂で悪疫退散と五穀豊穣を祈って打ち上げられた古風な仕掛花火である。
久留米藩の砲術師古川安太夫が慶安(一六四八〜五二)の頃、村落の若者たちに伝授したと伝えられ、熊蜂の巣をつついたような爆音と火花が見る人の目をうばう。
そして、この青年たちの中から花火職人になって行く者もいるという。
筑後路は今でも花火の本場で、夏の夜など遠くに打ち上げられる花火の音を聞くことが多い。
火祭りは冬にも催される。久留米市筑邦町の玉垂神社境内で行われる[大善寺の鬼夜(おによ)]がそれである。
正月七日の鬼会(おにえ)であり、小さな松明(たいまつ)をかざし鉱褝の若者たちが社前の霰(あられ)川で身を清め、古式の行事の中で、鐘楼の前に用意された六本の大松明に点火する。
孟宗竹を芯にした大松明は、直径一メートル、長さ一二メートル余りのもので、豪壮な火祭りは夜半まで続けられる。
なお、この夜太宰府天満宮では、年中行事の「うそ替え」の神事があり、続いて八時ごろから、火祭りの「鬼すべ」が開始される。
うそ替えは参詣人各自が持っている木製の“うそ”と、まぎれ込んでいる社人が持つ金の“うそ”とを取替えようとするもの。
その後の「鬼すべ」は、鬼方(おにかた)とすべ方(かた)とに分れた氏子たちが、山積みの青松葉に火を放ち、大うちわで煙をあおぎ、鬼をいぶし出そうとする火攻めの攻防行事である。
6 篠山城と水天宮 top
久留米の篠山(ささやま)城は、天守閣のない多聞(たもん)造りの城で、本丸には二層と三層の櫓(やぐら)が六棟、寝殿造りの本殿を守っていたという。
城の防備には北と西側の城壁近くを流れる筑後川を利用して、
「……濠・堀・池又ハ本流ヨリ水ヲ引イテ、灌漑用水トヲ兼ネタル環流ヲ防禦ニ充(あ)テテイタ」と書かれている。
本丸跡の総面積は五千坪、つり橋を備えた立派な城であったというが、現在の二の丸跡はブリヂストンの用地となり、本丸御殿の跡地は久留米大学医学部となっている。
篠山城は有馬家累代の居城として明治維新を迎えているが、この城跡一帯は鷺の森と呼ばれる台地であった。 |

篠山城石垣
|
永正年間(一五〇四〜二一)に土地の豪族が笹原をひらいて城を築き「笹原城」と呼んだ。
その後、天文年間(一五三二〜五五)の始めに「廃亡した笹原城を御井(みい)の郡司某修築す」などと書かれているが、砦(とりで)のようなものだったのであろう。
筑後川べりの台地に砦が築かれはしても、久留米という土地は住みやすい場所ではなかった。
絶えず水の恐怖がつきまとうからである。現在の地名を見てもそのことがうかがい知られる。
篠山
瀬ノ下
繩手
荘島
日吉町 |
笹やぶが茂った岡であった。
筑後川の中に大さな岩盤が突き出て瀬を成していた。その下流が瀬の下であった。岩盤を除き、瀬ノ下に新川を掘って筑後川を現在の水流に変えたのは田中吉政で、慶長六年(一六〇一)である。
城下の町から瀬ノ下までは田圃続きで、いわゆる畷(なわて=ジュッタンボ)であった。
取替川に囲まれ仁砂洲の土地であった。
明治六年(一八七三)に日吉神社を移すまでは十軒屋敷と呼んだ。家の数から生まれた地名である。 |
笹原城が改築され久留米城と呼ばれるのは天正十五年(一五八七)からである。
豊臣秀吉から三万五千石を与えられて、毛利秀包(ひでかね)が二十歳の若さで城主の座についた。
だが、関が原の戦いで豊臣氏と運命を共にして、十四年の短い年月のうちに城を失った。
続いて筑後十郡、三十二万五平石の大名として田中吉政が領主となった。
慶長五年(一六○○)十一月(『筑後中興記』)である。
田中吉政の筑後入国は翌慶長六年の三月であるが、久留米城には十三歳の長男主膳を置き、自らは柳川城に五層の天守閣を築くなどして城の補強と拡張を図り、柳川を本城としたのである。
築城と治水で知られる田中吉政が本城としなかったことを見ても、当時の久留米の一端がうかがい知られるであろう。
吉政の嫡男主膳は慶長十一年十九歳で死去。吉政もまた慶長十四年二月、伏見の旅宿で客死した。
二男の忠政が後を継いだけれど、五年後の慶長十九年八月に忠政も二十三歳の若さで死没し、世継ぎがいないまま閥国(けっこく)となったのである。
丹波福知山で八万石、有馬豊氏が筑後二十一万千八百四十石の転封(てんぽう)を命ぜられたのは、元和六年(一六二〇)十二月八日であった。
豊氏が久留米に入城したのは翌元和七年三月十八日(太陽暦五月九日)である。
この年から城郭の規模を拡げ始めて、元和八年に久留米城を篠山城と改称した。
その後七年余りの間は城の大改築と城下町作りが続けられる。
元和七年『米府年表』によると「榎津(えのきづ)・城島・福島・黒木・赤司ノ五城ヲ毀(こぼ)チ、久留米城ノ修造二用フ」とあり、一方『筑後志』によれば豊氏は湘山和尚に命じて、梅林寺を創建させている。
梅林寺は旧領地の瑞厳寺を移したもので大竜寺と名づけたが、初代藩主豊氏の父則頼の分霊を葬ってから、法号の梅林院の名をとり梅林寺と改めた。
臨済宗妙心寺派の寺であり有馬家の菩提寺である。
筑後川にのぞむ梅林寺の外苑には、千五百株の梅が二月の空に咲き競ったりもする。
旧久留米藩主は次のとおりである。
初代 豊氏(とようじ)
二代 忠頼(ただより)
三代 頼利(よりとし)
四代 頼元(よりもと)
五代 頼旨(よりむね)
六代 則維(のりふさ)
七代 頼徸(よりゆき)
八代 頼貴(よりたか)
九代 頼徳(よりのり)
十代 頼永(よりとお)
十一代 頼咸(よりしげ)
十二代 頼匡(よりまさ)
十三代 頼萬(よりつむ)
十四代 頼寧(よりやす) |
治世二十三年、七十四歳で死去。父は則頼。父親即世の年から数えると治世は四十一年。母は細川夫人。
治世十四年、五十三歳で死去。父は豊氏、母は松平夫人。
治世十四年、十七歳で死去。父は忠頼、側室は磯部氏。
治世三十八年、五十二歳で死去。父は忠頼、側室は神保氏。
治世二年、二十二歳で死去。父は頼元、側室は小野氏。
治世二十四年、六十五歳で死去。父は赤松円心十四世の孫・石野則員、側室は小笠原氏。
治世五十五年、七十歳で死去。父は則維、側室は小林氏。
治世二十九年、六十七歳で死去。父は頼徃、側室は奥田氏。
治世三十三年、四十八歳で死去。父は頼端、側室は吉田氏。
治世三年、二十五歳で死去。父は頼徳、側室は田中氏(皆川氏)。
治世・明治四年七月廃藩まで二十六年、五十四歳で死去。父は頼徳、側室は立石氏。
五十八歳で大正七年死去父は頼咸、側室は浦辻氏。
六十四歳で昭和二年死去。父は頼咸、側室は金田氏。明治七年に頼匡は家督を継いだが、病のために明治十年三月弟の頼萬に譲った。
昭和二年に家督を継ぐ。 |
そして、戦前まで有馬家は伯爵であった。
有馬家歴代の藩主の中から特に選ばれて、旧篠山城本丸跡の篠山神社に、五柱の名君が神として祀られている。
初代の豊氏は、藩政の始祖として業績が評価された。
七代の頼行は、和算(数学)の天才として日本の数学史に残る業績によるものである。
十代の頼永については、知・行・徳ともに天下の名君としての業績、と書かれている。
だが十六歳で結婚して二十二歳で城主となり、治世は僅か三年間、二十五歳で死去した若者が名君とは考えられない。
多分に功労賞的な配慮があるのであろう。
十一代の頼成は、維新の活躍と郷土産業啓発の業績によってであり、十四代の頼寧は、農林大臣外多数の役職につき、常に自由と平和を愛し農政面における業績という理由による。初代の豊氏は武将であったであろう。
七代藩主の頼行は本物の学者であったと伝えられている。
そんな素地があったればこそ、約百年という年代をへだてた後に田中重久などという人物が誕生したのであろう。
東京で永代橋を渡って深川に入ると佐賀町である。九州では佐賀の隣りが久留米である。
そんなつもりで、東京の水天宮は永代の先の錦糸町のあたりと思っていた。ところがそうではなかった。
「東京・芝の水天宮は文政元年(一八一八)九代頼徳の命によって、その分霊を移したもの……」であった。
安産の神としての信仰が厚いという。大変な認識不足であった。
『久留米小史』によると「文政元年九月、江戸赤羽邸に水天宮を分祀す」とあり、『米府年表』では「十一月朔日(ついたち)とせり」と書かれている。
東京は別として、記憶に残る水天宮は久留米・瀬ノ下のお宮で、気どりのない遊び場所であった。
五月と八月にお祭りがあって、いろんな店が境内を埋めつくした。
そこでは騙(だま)されることなく、どのようにして少ない小遣銭を最大限に使うか、ということしか考えたことがなかった。
騙されるのは己れの不明のせいである。仁が二度と同じ諞しの手には乗らなかった。
そして言葉では言い表せない楽しいお祭りであった。
気楽な遊び場所ではあったが立派なお宮であった。 |

水天宮拝殿
|
事の次第は大正十二年(一九二三)からの治水工事で、筑後川の土砂をさらえ盛上げて境内を広くしたからだという。
樟(くす)の大樹に囲まれた社殿は荘厳であった。
神社のいわれは、安徳天皇(一一八〇〜八五)と生母の建礼門院(高倉天皇妃・清盛の女徳子、二位の尼(清盛の妻で徳子の母)と、更に天御中主神(あめのみなかぬしのみこと)が祀られている。
平家一門が西海で果てた折り、按察使局(あぜちのつぼね)であった伊勢が、鷺野原に祀っていたものを、四百六十余年後の慶安三年(一六五〇)に、二代藩主忠頼が瀬ノ下に移したものと伝えられる。
東京では安産の神というけれど、久留米瀬ノ下の水天宮は、水難除けであり、河童の神さまである。
九州で安産の神は「粟島(あわしま)さま」である。
文政十年(一八二七)に、対馬の宗家(そうけ)から海運守護のお礼を貰いに来たという話がある。
近くに住んでいる者の感覚ではマンガのようであった。
水天宮に殿さまがお札を貰いに来るなど思いもしなかった。水天宮はそれほど身近なお宮であった。
つまりは高良大社との相違でもあった。
久留米瀬ノ下は門戸(出入口)であった。
堺・博多・平戸・長崎・坊の津(鹿児島)がそうであったように、旅人は川をさかのぼって瀬ノ下に上陸した。
豊後の広瀬淡窓、筑前の亀井南冥、下総の伊能忠敬、肥後の中島広足、肥前の古賀穀堂、仙台の斎藤竹堂などである。
訪れたのは学者ばかりではない。そのため水天宮の門前町は旅宿やお茶屋(料理店)が軒を並べて繁昌した。
因縁とも言うべきであろうか、九州――特に筑後は平家一門との関係が深い。
平家が源氏との戦いに敗れて西へ落ちてきたのは、九州を最後の拠り所と考えていたからであろう。
しかし、平家は九州で善策だけを施したのではない。その結果、恨みを持つ者も少なくなかった。
九州・太宰府まで落ちのびた平家一門が、草野吉木の城主・草野永平の反撃を受け、再び関門の海を渡って寿永四年(一一八五)壇ノ浦の海で消滅する。
平家の落人が九州に住みついた。落人と袮する他国者も山奥に逃れた。
それらの人々を九州という土地は生きのびさせたのである。その理由は、平家の落人ということのためであった。
許せないことがあって反旗をひるがえしもしたけれど、最終的に九州は平家一族を受け入れる土地だったのである。
高良神社に重要文化財『紙本墨書(しほんぼくじゅ)・平家物語』十二巻がある。
覚一本(かくいちぽん)と伝えられるものの一種である。
平家物語は盲目の琵琶法師たちが、平家の盛衰を耳で覚えて口伝えにした物語である。
やはり、悲劇を伝承した文学で、「吾かくして敗れ記り、彼かく戦い勝者となり記り」という、負者が勝者をたたえたものである。
最初は三巻ぐらいというが、鎌倉中期には六巻本から十二巻本へと物語が成長した。
更にその末期には如一という煮が現れて、灌頂巻(かんちょうのまき)をつけた平家物語が出現した。
如一がつけ加えた平家物語を更に大成・確立したのが覚一である。
播磨国・書写山の僧であったが失明して琵琶法師となり、後には検校(けんぎょう)を授けられた。
平曲(へいきょく=平家物語)における覚一本は重要な位置を占めており、原本の所在は不明である。
転写本が六本あるが、その中でも特に注目されているのが、京都龍谷大学所蔵本と久留米高良神社所蔵本であると言われている。
柳川市沖ノ端(おきのはた)には、平家の落人・六騎がこの土地に住みつき漁師になったという伝説があり、六騎(柳川では“ろっきぅ”)の塚も残っているが、久留米の水天宮は、平家の悲劇に関して水に縁のある神社ということから、水難除けの神として信仰がある。
付随して河童の伝説がある。河童の伝説は全国的であり、九州にも数多く残されているが、有名なのが筑後川の河童一族である。
火野葦平の『河童曼陀羅』によると
「昔、インド・デカン高原の北方につらなり、ヒマラヤ山脈のふもとにひらけたタクラマカン砂漠を通過して、近東方面から河童の大軍が東方へ移住した。
水を求めての放浪であった。
かれらは蒙古から中国を経て、日本にねだり、美しい川の豊富な九州に住みついた。
その大頭目が筑後川の九千坊である」
とあり、更にまた
「壇の浦で亡びた平家一門のうち、男は平家蟹となり、女は河童となった。
その女河童たちは能登守教経(のとのかみのりつね)の夫人であった海御前(あまぼぜ)によって統率されている。
海御前は門司の大積村にある乙女岩に本拠をかまえ……」
とも書かれている。また、筑後川上流の田主丸と支流の巨勢(こせ)川一帯は河童なしでは夜の明けぬ町でもある。
河童と平家との結びつきが筑後川河童の特色でもあろうか。
水天宮と、そして河童という伝説上の動物とは、いわば悲劇(もしくは悲劇文学)の伝承者である。
そしていま一人、幕末維新期にあって、水戸学を学んだ久留米藩士(代々水天宮の神官)真木和泉守保臣もその一人であった。
天保十五年(一八四四)四月、父頼徳(よりのり)の死に会い、二十三歳で十代藩主になったのは頼永である。
頼永は水戸斉昭に深く私淑し、一方では鍋島直正・島津斉彬(なりあきら)・山内豊信など、いわゆる名君グループとの接触があった。
新藩主の頼永に期待をかけたのが天保学(久留米の水戸学派)グループであった。
だが、頼永は二年後の弘化三年(一八四六)七月、持病(尿血症)をこじらせ篠山城で死亡した。
後を継いで十一代藩主になったのが弟の頼咸(よりしげ、十九歳)である。
そして天保学グループは二派に分れて反目するようになった。
村上守太郎や野崎平八・佐田修平など内同志と、真木和泉・木村三郎ら外同志とによるものである。
村上一派の内同志が頼永の革新政治の補翼に力があったことは言うまでもない。 |

真木和泉の像
|
それだけに外同志の真木和泉たちは、頼永の死に会った後、十一代の顆成を廃してその弟富之丞(頼敦・後の松平直克)を藩主にしようとする陰謀を持つ者たちと考えた。
ところが嘉永三年(一八五〇)六月、江戸赤羽の藩邸で事件が起きた。
村上守太郎が隠していた短刀で同僚の馬淵貢を刺し、居合せた家老の有馬主膳なとがらその場で殺されたという事件である。
そして嘉永四年には内同志一党が処分された。
だが舞台は三耘して嘉永五年二月に外同志の関係者は、閉門謹慎を命ぜられ、更に真木和泉たちは無期禁獄にも等しい厳罰を受けることになり、天保学グループの外同志は完全に久留米の藩政から遠ざけられてしまった。
水田村(現在の筑後市)の実弟・大鳥居信臣の家に幽閉されること十一年、文久二年(一八六二)二月、脱藩の果て薩摩を経て京都に入ろうとしたが、伏見の寺田屋事件に遭って捕えられた。
文久三年八月、三条実美(さねとみ)ら七卿に従って長州(山口県)に下った真木和泉は、甲斐真翁と変名して忠勇軍の総管となり、益田・福原・国司の三国老や久坂義助(玄瑞)らと共に兵を引き連れて京都に入った。
念願を果そうとしたけれど、元治元年(一八六四)七月の禁門の変(蛉門(はまぐりごもん)の変)となって失敗に終り、同月二十一日に生存の同志十六人と一緒に自刃した。五十二歳であった。
122-61
真木保臣が和泉守に任ぜられ従五位下に叙せられたのは天保三年(一八三二)十月である。
明治二十四年四月に正四位を贈られたが、失脚の人であったことには変りはない。
明治四十五年(一九二一)に和泉守保臣の五十回忌を記念して、水天宮の境内に銅像が建てられたけれど、昭和十九年(一九四四)太平洋戦争のために金属回収の犠牲となって、台座だけ残されていたが、昭和四十四年に再建された。
彼もまた悲劇の人であった。
7 久留米四十八連隊 top
戦前の縁日や夜店・祭礼などでは、香具師(やし)の口上が馴染(なじみ)のものであり、風物詩の一つであった。
つまり「ガマの油売り」や「源水(げんすい)のコマまわし」そして「バナナの叩き売り」などである。
うろ覚えの記憶をたどり、口上を書くと次のとおりである。
「さあ始め、さあ始め、始めあったら終りあり。
尾張・名古屋は城でもつ。城の周りにや堀がある。堀の中には蓮がある。蓮の中には穴がある。男は穴ゆえ苦労する……」
という前説に始まって、その後は台湾バナナの身の上話となる。つまり
「青いうちからもぎ取られ、籠に詰められ船に乗せられて、着いたところが下関」という下(くだ)りの一節である。
そして、叩き売りの値段に入る。値段は高値から安値へと落して行く。
「………コンゴン(五十五)鳴るのは寺の鐘、四八(よんぱち)ゃ久留米の連隊で、いつも戦さにや勝ち通し、わたしのバナちゃん負け通し……」という口上が続く。
久留米に軍隊が設けられたのは明治三十年(一八九七)であり、歩兵第二十四旅団司令部と、四十八連隊の新設がその始めである。
場所は国分町であった。そして久留米は、たちまち「軍都」と呼ばれるようになった。年代を追うと次のとおりである。
明治三十年五月、久留米衛戍(えいじゅ)病院の創設
。戦時中の久留米陸軍病院であり、現在の国立病院である。場所は国分町であった。
同年の十月に第二十四旅団司令部が新設されているが、栄光の歩兵第四十八連隊が福岡二十四連隊から分隊して、久留米市国分の兵営に移駐したのは、明治三十年四月であった。
三十一年一月螢川町に憲兵屯所設置。三十五年に久留米憲兵分隊と改称。
四十年(一九〇七)十月、第十八師団が設置され(諏訪野町)同じ月に、工兵第十八大隊が御井町に駐屯した。
四十一年二月、騎兵第二十二連隊が習志野から来たけれど、大正十四年(一九二五)五月の第十二師団廃止に伴って、第十二師団が小倉から久留米に移り、それと同時に騎兵第十二連隊が小倉から移駐して、久留米の第二十二連隊は解隊した(国分町)。
同じ年の四十一年に野砲第二十四連隊が熊本から、独立山砲第三大隊が小倉からそれぞれ久留米の西町に移駐した。
独立山砲第三大隊は、のちに他の師管区へ転属になって、戦時中その兵舎跡は陸軍予備士官学校になった。
大正十四年(一九二五)五月に第一戦車隊が創設された。歩兵第四十八連隊応とのオンボロ兵舎を利用してであった。
大正八年(一九一九)には太刀洗に飛行第四連隊が付設された。
高射砲第四連隊が朝倉郡甘木町に新設されだのは昭和十二年(一九三七)である。
トコトンまで苦労させられて、かえりみられなかったのは、西町にあった輜重兵(しちょうへい)第十八大隊であった。
輜重兵をからかう軽口の歇があった。
輜重(しちょう)輸卒(ゆそつ)が 兵隊ならば
ちょうちょ(蝶) とんぼも鳥のうち
年代による相違もあるけれど、一般兵科の歩兵が一年十ヵ月で除隊になるとすれば、砲兵などの特科隊は二年間の歳月を必要とした。
特科隊は教育期間が長く、昇進が遅かった。その点て輜重兵は教育期間が短い。
三ヵ月で教育が終る。馬を動かすことができたら一人前である。
そして、昇進することなく、食事の程度は兵隊の中でも最低であった。
昭和六年{一九三四)九月に満州事変が勃発した。
久留米の第一戦車隊に動員令が下り、出発したのは十二月二十二日である。
戦火が南に飛んで上海事変が始まったのは翌七年の一月であり、日本海軍の陸戦隊と十九路軍とが衝突を繰返した。
久留米では、下元混成旅団が編成されて上海に派遣されることになった。
下元兵団は海軍の駆逐艦で呉淞(ううすん)に渡り、上海への進撃を計画したが、途中の廟行鎮(びょうこうちん)で十九路軍とぶつかり合って、久留米工兵第十八大隊(後の西部第五十二部隊)の名声を上げる戦いになったのである。
廟行鎮――という村落は、呉淞から上海へ通じる要衝の地であり、クリークが発達し、加えて陸路には鉄条網が張りめぐらされていた。
そこで鉄条網を破壊するために工兵大隊に命令が下ったのである。
松下大尉の工兵中隊から、大島少尉が指揮する二個班と、東島少尉指揮の二個班がこの作業に当った。
昭和七年二月二十二日の払暁、大島班は成功して大村連隊の突撃路を開いたけれど、東島班は失敗に終った。
作戦上のこともあればメンツの問題もある。
東島少尉は予備班に命令を下して強行突破を企てた。陸軍工兵一等兵の作江伊之助、北川烝(すすむ)、江丁武二の三人が任に当った。
北川一等兵は途中で傷ついたが、鉄条網にたどりついた瞬間に点火されていた竹製の破壊筒は爆発した。
三名の死により、福岡連隊は通路を得て攻略戦に成功した。
江丁・北川・作江の三人は二階級特進して伍長になった。
工兵第十八大隊が久留米を出発する朝、江下一等兵は、駅頭で見送りの小学生との間にドラマめいたことがあり、新聞各紙が竸って記事にした。
更には肉弾三勇士を讃える歌も作られた。
昭和八年十一月、久留米市中央公会堂前に「三勇士」の銅像が建てられたけれど、この銅像も今はない。
戦争によって作られたものが、戦争のこめに消え失せた。
久留米の国分寺がはっきりと書き出されているのは、聖武天皇の天平十三年(七四一)である。
金光明王護国之寺(国分寺)と法華滅罪(ほけめつざい)之寺(国分尼寺)である。
配置された僧侶の数は国分寺に二十名、尼寺には尼僧が十人いたはずだという。
この国分町に久留米陸軍病院があった。
正門にはいかめしく衛兵が立っていたけれど、一歩中へ入るとつつじが咲き、桜もきれいな庭があった。
旧病棟は赤煉瓦の建物で、その傍らにバラックの新病棟が二十二棟まで並んでいた。
大陸帰りの傷病兵を収容していたのである。
厳しいはずの軍律が、病院内ではきわめてゆるやかであった昭和十五年前半の頃――。
旧病棟に上海帰りの一等症患者がいた。
一等症というのは恩給を査定する時の病気の程度を示すもので、彼は男性の機能を失っていた。
軍医が手をつくしてもダメであり、美しい看護婦の努力も効果がなかった。
そこで一夜の外泊が許されて「さくら町」へと赴くことになった。
夕食後、同室の戦友たちに見送られて彼は営門を後にした。
無駄を承知で軍医は最後の望みを託し、見送る仲間こちら、しょんぼりと帰ってくる姿を予想しながら、励ましの声をかけていた。
ところが、結果は上乗であった。
「軍医殿、できました。朝方までに三発発射完了。人員・機材ともに異状ありません」
その晴れやかな声を聞いたのは起床ラッパの直後であった。程なく彼は退院して原隊に復帰した。
傷夷軍人として最高額の恩給を貰って故郷に帰れるはずの兵隊が、一夜の久留米「さくら町」があったばかりに、大きく方向を変えたのである。
兵隊と「さくら町」は切り離すことができなかっこけれど、戦後はさくら町の名を聞くことがない。
8 寺町と久留米つつじ top
京都や福岡の例を引くまでもなく、古い町には必ず「寺町通り」の名がある。
そして久留米の寺町にも十七のお寺が土塀を連れて眠ったように並んでいる。
寺町に眠る久留米の先人は、次の人たちである。
真教寺 藩の儒学者・樺島石梁。
妙正寺 久留米つつじの始祖・坂本元蔵。江戸新内の創始者・富士松紫朝。
西方寺 鳥の習性の研究家・川口孫治郎。
千栄寺 儒学者で、浄瑠璃「朝顔日記」の作者とも言われる広津藍渓。(広津和郎の父柳浪は、藍渓の曽孫)
善福寺 洋画家・古賀春江
遍照院 久留米で一生を閉じ記勤王の志士・高山彦九郎。
徳雲寺 久留米絣の始祖・井上伝女。
宗安寺 土木、治水の名奉行・丹羽頼母。
妙善寺 最初の洋行者・柘植(つげ)善吾。大石堰構築の上郡奉行・高村権内。
top
****************************************
|