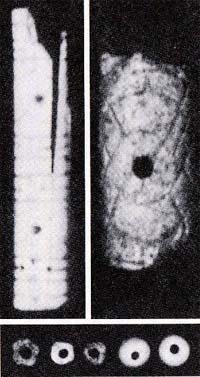|
****************************************
Index Ⅰ章 Ⅱ章(其一 其二 其三 其四) 付録 拡大地図
Ⅱ章 アイヌの交通路(其三)
二 西蝦夷地のアイヌ道を歩く
top
1 クマイシ番所を越えて 西蝦夷地への道
険阻な海岸
現在では、江差から国道二二九号線が多くのトンネルを有しながら小樽まで通じている。
難所の茂津多岬を越える道路は一九七六(昭和五十一)年十一月開通、茂津多トンネルは一九七四メートル、これで札幌まで近くなった。
西蝦夷地への入口にあたるこの地域は、早くから和人の往来があったものの、十九世紀後半になっても陸路はほとんどなく、交通は海路であったが岩礁地帯で難所が多かった。
ほっとする砂浜も所々にあり、潮の引くときにしか通れない海岸に代わる山道も所々にあったが、海岸に迫った険しい道は人通りが途絶えるとすぐに茨や笹に覆われた。
草にすがって滑りおりたり、清水が流れてぬかるんだり、崖崩れも多い。そのような交通路を、アイヌは役人の道案内に立ったが、自分たちのために利用したかどうかは疑問である。必要があったものだろうか。海路も利用しただろうが、アイヌの主要な交通路は、川を遖って別の川の上流に越えてゆきその川を下る、内陸の道であった。
堅雪の頃は山道ははかどる。東西の蝦夷地に分断された内浦湾側と日本海側を結ぶ東西の交通路が何本もあったことは、アイヌの歴史を見るうえで重要である。
元禄十三(一七〇〇)年『松前島郷帳』には「うすべち・ふとろ・せたない・はませたない・あふら・ちわし・しまこまき・夕まき・六條間・をたすつ」が記されている。
これらは点とし了の交昜地や寄港地であって、すべてが線で結ばれていたわけではない。
陸路でつなぐため所々に幕領期の山道開削があったが、「文化度」の道は松前藩復領後は「跡」になってしまっていた。
熊石村関内から太櫓(ふとろ)村良瑠石(たるいし)までの一二里(太田山道)と太櫓から寿都(すっつ)境までの二四里(狩場山道)は安政四年に開削されたが保全は容易でなかった。 |

図58 クマイシからイシカリへ
|
明治時代になっても、太櫓山道と称する天狗岳の険路、「蝦夷親知らず」の海岸、茂津多岬を含む前記の山道に難所は健在で、交通難と引き換えに絶景が提供されていた。
以下、熊石から北上していくが、交通路の記述は断らないかぎり松浦武四郎の日誌類に拠っている。
クマイシ(熊石)
クマイシはアイヌ語クマウシで、物干し竿がたくさんある所という意味である。
アイヌの口承文芸には、獲物が豊富である山中のコタンの様子をユククマタイ、カムイクマタイ(鹿肉干し棚、熊肉干し棚)が林立していると描写する。
ここではおもに魚を干していたのだろうか。
寛文九(一六六九)年には和人地のなかで南から相沼内(あいぬまない)、見市(けんにち)、熊石、関内にはアイヌと和人が混住していた。
相沼内にはアイヌ首長トヒシシがおり、シャクシャイン蜂起の際、西蝦夷地のアイヌを抑えるために藩の使者となった(『津軽一統志』)。
一〇〇年後には、見市に古くはイワンノシケという蝦夷で代々岩之助という百姓がいて、普段は和風の髪形であるが冬になると月代(さかやき)を剃らずにいて正月七日に蝦夷として領主にお目見えに行く者があった(『蝦夷草紙』)。
見市川に沿って遡り、八雲に出る国道二七七号線はその昔アイヌの道筋だったであろう。
平田内(ひらたない)川の奥から太櫓、瀬田内(せたない)へ、また遊楽部(ゆうらっぷ)へ越える道がある。
さしたる難所はないが道が細くて迷うから和人は越えられないという。
熊石から一〇丁ばかり行くと、セキナイにいたる。
ここから先は馬が通れない道しかなく、これより西蝦夷地のため番所がある。
セキナイのセキは関ではないが、松前藩の罪人の追放場所であった熊石の先のセキナイは、松前地に住む人々からは未知の蝦夷地というイメージがあったであろう。
松浦武四郎はクドウに向かう途中のヨリキ岬辺りで「この辺に到らば風土も大に人間地とは異なり、海外の趣をなすこと有る也」と書き残している。
寛文期のアイヌ首長は彦次郎であった。
ウスベチ(臼別)からは蝦夷地である。
臼別は臼別川流域が発祥の地名で、後に場所の名にも使われた。
場所の名はクドウともいう。運上屋の地の本名はテレケウシナイという。
クドウの名は近くのクントエト(エナオ岬)から来ていると思われる。
舟で行くと岬が目印になるからであろうか。
臼別川の水源から遊楽部川上に越えることができる。
帆越(ほごし)岬を越えると太田山(おおたさん)権現がある。
砥歌(とうた)川がオオクの由来だろうか。
アイヌは潮が引いているときは浜を通るが、潮が満ちているときは大難所だけれども天狗岳を越える。
フトロ(太櫓)
尾花岬からは太櫓場所になるが、運上屋のある所はキリキリという所で、場所のアイヌは文化年間にトシペツ川上のカンノボリ辺の住民を移した者だという。
太櫓川の渡し場に出る山越えの道がキリキリや北のラルイシからある。
太櫓川は屈曲蜿転、河口から川を三里遡ったと思っても陸に上ってみてみると半里ばかりしか行っていない。
最上流はセイヨウペツ(遊楽部川に合流)へ向背している。
アイヌは一日半で遊楽部岳に、二日で東海岸遊楽部に出ることができる。
セタナイ(瀬田内)
大河利別(としべつ)川の河口に出る。
この地域はセタナイと呼ばれたが、アイヌ語ではセタルペシナイが元の形だったようである。
デーアンジェリスの地図にセタナイとメナシをつなぐ東西の交通路として描かれている大河は利別川だと考えられるが、そのセタナイは川そのものでなく地域名になっていたとすると利別川=セタナイとはかぎらない。
『松前島郷帳』の「はませたない」は馬場川河口辺りと考えられている。
松浦武四郎がセタルヘシナイを馬場川と記録し、セタルナイ、セタナ、ポンセタナなどの旧字が馬場川にそってあったのは、誤り(『瀬棚町史』)とばかりはいえないかもしれない。
トシベツの意味は「縄川」で、そのわけは、川下は太櫓、瀬田内の入り組み領で、太櫓アイヌが瀬田内アイヌの漁場を段々と取ってゆき、利別川の支流真駒内川まで進出してきたので、その河口に縄を張って、もし太櫓アイヌが越境するときは瀬田内アイヌが償いを取ったからという。
河口から五、六里上流コケヤチ(和名)からは太櫓領で、上流サカイマップ(今金(いまかね)町住吉付近)からは山越内領であった。
ハンケサカイマップ(種(たね)川)にユウラップアイメ、少し上にフトロアイヌ、その上のヘンケサカイマッブ(北住吉)にユウラップアイヌが住んでいたが、乙に下げられ、ウロッケという者に境を守らせた。
浜の息子イメマカシはペンケサカイマップに居を移し、幕鎖期から畑で蕪(かぶら)を作っていて、松前復領期に畑作を禁じられていた時にも太櫓、瀬田内へ持っていって売ったので蕪親父とあだ名されていた。 |

図59 利別川
(美里河3砂金採掘跡)
|
妻が亡くなったので二丁ほど移って建てた家は三間×八間ほどで、フトロの山稼ぎの和人たちが手伝って建てた柾屋であった。 オシャマンペ、ユウラッブ、シラリカのアイヌはトシベツ川筋から浜へ移住させた者だという。
最上流はイナウ峠で分水嶺となり国縫(くんぬい)川上流へ越える。 この道は国道二三〇号線となった。
途中クロイフナイ(三股付近)にイヌマカシの小屋があり、そこをリヤコタンといって往来の者が一泊する。
ユウラップからはサクルベシベ、マクルベシベより往来、その道筋の跡はユウラップ川筋にあるというが、今の今金-八雲間の道道のルートである。
シラリカ川へ越えるときはイナウシ峠を越えた。利別川の上流には鉱石があり、砂金が採れて採掘跡が多数ある。
和人の鉱夫、杣夫(そまふ)が入り込んでいた状況がわかる(本書Ⅱ-一-1-(3)参照)。
イメマカシの丸木舟は幅一尺三~四寸、長さ二間、深さ五~六寸という小型なものであったが、一八八六(明治十九)年青江秀による『北海道巡回紀行』によると瀬棚から利別川を上るのにアイヌに舟を漕いでもらっているが、
「川舟は長二間許幅二尺余なり 其底は木を凹めて之を作り丸木舟の如し 舷は薄板を用る者にして務めて軽便を主とす」
というもので、一隻に二人が棹を取り「操ること甚だ巧なり 水浅れば細長なるを用い深れば扁短なるを用」いていた。
瀬田内のアイヌは冬は奥尻島に行ってオットセイ猟をしており、この地域のアイヌは他地方のアイヌと同様に海獣猟も巧みであった。
スツキに行く陸道はおおむね岩地で草鞋四足を切らす。狩場山を見ながらここにも稲穂岬(島牧村字原歌(はらうた)町)がある。
稲穂峠と同様に通行の際にイナウを捧げるので和風に稲穂と称するこの地名は各所にある。
チワセ(千走)川上流は利別川支流真駒内川に近い。 |

図60 三股
(利別川・ピリカベツ川・チュウシペツ川の合流点)
(美里河1・2砂金採掘跡)
|
シマコマキ-スッツ(寿都)-オタスツ
シマコマキの近くは寛文期に「毛嶋小巻(もうしまこまき)用ノマキチリ尻」が記録に見え、それぞれ河口と思われる。
首長チョツヘの名が見える。寛政初めにはアイヌ二〇〇人がいて栄えたという。
泊(とまり)川の上流、大平川の上流は利別川に近い。さらに行くと折(おり)川があるが上流は黒松内方面に近くなる。
オクシュマ(歌島)から堅雪の頃は二里ほどで弁慶岬を廻らずにスッツの矢追に抜ける山道がある。
海岸にはワシリ(断崖)がある。フシリを通行するときは、波間を考えて走り抜ける。
ここも「親知らず、子知らずの如し」。
弁慶岬を廻ると寿都湾に入るがその先はシュマテレケウシ。汐が引くのを待って、岩を跳ね越えるような難所であったが、これを岩崎と称してこの辺に漁場を開いた時に朱太(しゅぶと)川流域のアイヌを移住させたという。
寛文期のアイヌ首長は弥左衛門(やざえもん)という。
朱太川流域のアイヌは五〇〇人いたというが、朱太川は黒松内低地帯を流れ、ペッテからはウクスツ領、黒松内から上流はアブタ領である。
黒松内からやや下のオフイネでは歌棄(うたすつ)のアイヌが小屋を建て漁業をしていたが虻田(あぶた)アイヌに追い払われ、安政三(一八五六)年チャランケ(優れた演説を勝ちとする談判で、アイヌ社会の正当な解決法)で歌棄乙名(おとな)イトテンが礼文華(れぶんげ)小使カムイコチヤに負けた結果、下オフイネ(現在の緑橋付近)が境となった。
カムイコチヤはアイヌの伝承が絶えることに危機感を抱き、若い時から古老に故事を尋ね境に詳しかったという(『近世蝦夷人物誌』)。
翌年、寿都詰合(つめあい)、虻田詰合の立会いのもと、再びこの時チャランケになった。
イトテンは従弟である寿都脇乙名(わきおとな)ムニトクに、箱館の役人に内々たのんであるからムニトクが加担してくれれば勝てるという支配人の言葉を伝えて味方をたのんだが、ムニトクはアイヌとしての筋を通すと突っぱねた。
チャランケの席上、イトテンが上にあるウタサイの山は歌棄領だと述べた時、ムニトクはそれなら山をオフイネの下に持ち去れといったので、イトテンは返す言葉がなくなったという。
そこであとは役人の裁量になってしまった。
東に進むと潮路(うしょろ)川河口の歌棄になる。
英雄オタストウンクルの故郷オタスツ=ウクスツはあちらこちらにある地名である。
ポロベツで境となる。磯谷にかけては二八小屋が立ち並び、繁華な海岸であった。
大闘争の時代
康正二(一四五六)年、志濃里の鍛冶屋村で起きた事件に端を発し、翌年コシャマインに率いられたアイヌ軍が道南の館を次々と陥落させた(Ⅰ-三-2参照)。
コシャマインは「東部」の首長であるといい、彼が討たれてしまうとアイヌ軍は敗北するが、文明元(一四六九)年、同五年と蜂起は続発している。
どの地域の蜂起かはわからない。永正九(一五一二)年から十二年にかけては東部ショヤコウシ兄弟をリーダーに蜂起した。
大永五(一五二五)年には東西のアイヌが蜂起、享禄元(一五二八)年にも蜂起があり、翌年には西部のタナサカシが蜂起し、セタナイで戦った。
享禄四年にも蝦夷蜂起、天文五(一五三六)年にはタナサカシの女婿タリコナが蜂起した。
ここでの東部、西部とは渡島(おしま)半島内のことである。
アイヌは、和人が北海道に進出してきて以来、その関係を軸にして社会を変化させ、独特の文化を紡ぎだしていったのであり、歴史はアイヌ対和人の関係でのみ推移していったのではない。
和人の経済力や技術を利用してアイヌ民族内部も生産力を上げて首長層が成長していっただろう。
これらすべてのアイヌ蜂起に対する戦後処理は不明である。
このように次々と蜂起が起きているところをみると、一つの集団の闘争の決着は他の集団に影響を及ぼさなかった、あるいは当の集団にさえ蜂起の敗北が決定的な変化をもたらさなかったと思われる。
このような状況は、アイヌの共同体が川筋を地域的なまとまりとする親族で構成され、非常時には隣接する共同体のネットワークでより大きなまとまりがえられるものの、それぞれの集団の独自性が強かったということなのかもしれない。
直接蠣崎(かきざき)氏に関わった闘争についてはある程度記録されているが、ただ蜂起とのみ伝わったり、または闇に葬られてしまったアイヌの闘争があっただろう。
タリコナの蜂起後、一〇〇年以上の時がたって寛永二十(一六四二)年島小牧のヘナウケ(ヘンノウケ)が「叛」した。
天文二十(一五五一)年に知内(しりうち)のチコモクインを東夷の尹(いん、中国式の表現で長官のこと)に、セクナイのハシタインを西夷の尹に定めて、しばらくは状勢は落ち着いていた。
この処置は、ほとんど唯一の史料である『新羅之記録』によれば、和人の権力によって蝦夷地のアイヌ首長の権威が保証される、という体制である。
松前藩治下初めてのアイヌの蜂起は「叛」ととらえられ、松前藩は家臣を彼の地に派遣して征し、松前利広(としひろ)もまたセクナイヘ「発向」(討伐する意)した。
この時の蜂起の背景には、三年前の駒ヶ岳噴火の影響が考えられている。
島小牧に被害はなく、セクナイは最も降灰が激しかった。ヘナウケはこの機に乗じてセクナイヘ乗り込み、自己の勢力を拡張しようと図った、という解釈もある。
すでにみたように、利別川流域は広範囲で、セタナイのアイヌの活動範囲や勢力ということを考えるときには河口地域にのみ目を向けるわけにはいかない。
チャシ
戦争があったなら、拠るべき城か砦があったはずだ。チャシがそれである。
全道にチャシコツ(チャシ跡)という地名があり、今でも見てわかるチャシ跡には誰のチャシだとか、そこで展開されたことの伝承が残っている場合もある。
伝承があるがここだとわからないこともある。
壕(ほり)を備え柵(さく)をめぐらしたものもあるが、到底砦とは考えられないチャシも多い。
立地は、川・湖・海に面した崖の上、舌状(ぜつじょう)台地の先端、山頂部、独立丘などで、砦のような目的のほか見張り所や聖地であった場合もある。
山頂や独立丘のチャシは神聖な場所という伝承が伴うことが多く、古いタイプで、遺物・遺構から十四世紀以降に作られたと考えられている。
チャシの分布は東蝦夷地に偏っていて、十七世紀にはシャクシャインの戦いに使用されたチャシがあり、道東では十八世紀終り頃まで、チャシが使用された。
寛政元(一七八九)年のクナシリ・メナシの戦いにまつわって、クナシリの首長ツキノエの居城として記録にみられ、そのツキノエと戦うためにクシロのクサニシが拠ったチャシの記録が、実際に機能していたチャシの最後であった。
このような砦としてのチャシは、紛争が早い時期に発現した道南ではシャクシャイン戦争前に作られていた。
瀬田内チャシは瀬棚町字南(みなみ)川から北檜山(きたひやま)町字豊岡にかけての利別川河口に位置している。
発掘によって駒ヶ岳大噴火以前に壕が掘られていることがわかった。
しかし周囲にめぐらされているような状況は確認されていない。
火山灰の上層と下層から一七軒の建物が確認されている。 |

図61 瀬田内チャシ跡 |
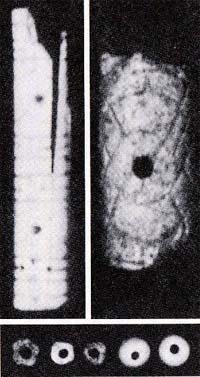
図62 針入れ(鳥管骨、左)・
キセル入れ(右)とガラス玉(下) |
国産陶磁器・外国産陶磁器・内耳(ないじ)鉄鍋・刀子(とうす)などの鉄製品、煙管(きせる)・古銭などの本州からの移入品と共に、キテや中柄、刺突具などのアイヌ自製の骨角製品その他多様な遺物が出土している。
セタナイが交易の拠点であったことは確かだし、時期的にヘナウケ蜂起と重なる。
寛文期にはセタナイに大将彦次郎の居城があったという。
このチャシがどのような役割を果たしたのだろうか。
また、島牧のチャランケチャシは島牧村字永豊(ながとよ)の泊川河口近くの左岸の砂丘にある独立丘にある。 |
山側には壕がある。
恵山期の遺物が出土し、アイヌ期の遺物は見つかっていないが、泊川河口にはコタンが営まれていたので(泊川河口遺跡)、そのコタンの人々にとってチャシがどのような意味をもっていたかが重要である。
チャランケチャシと呼ばれる所以は、アイヌ間の争いにおいてそこでチャランケが行われたという伝承があるからである。
同様な独立丘が数基あったというが現在ではチャシであったかどうかわからない。
島牧村にはアイヌの闘争があったと伝えられる永豊チャシ跡もある。
一つのチャシ跡が時期によってちがう利用のされ方をしていたとも考えられる。
家の敷地を整えたり舟着場を整備したりはしても、水路を引いたり大がかりな建造物を作ったりしなかったアイヌの人工的な構築物として注目される。
道内には五〇〇以上のチャシ跡があるが、チャシがどのような目的を持っていたにせよ、コタンを営む人々にとって必要なものであったはずで、チャシが営まれた時代のアイヌ社会の地域ごとの緊張感を示しているようにみえる。 |

図63 永豊チャシ跡
|
クロマツナイ(黒松内)越え
北海道の形をエイにたとえていえば尾の付け根、日本海側と内浦湾側を結ぶ狭い部分が黒松内低地帯と呼ばれる。
現在、道道一九号寿都黒松内線と国道五号線蕨垈(わらびたい)長万部間がかって黒松内越えと呼ばれた山道である。
「越え」るのは稲穂峠である。
この長万部川、朱太川に沿う交通路は西蝦夷地が鰊(にしん)漁で栄えると多くの出稼ぎ漁師が利用し、黒松内の花岡利右衛門経営の木賃宿に泊まった。
家は甚大で約二間四方の囲炉裏(いろり)があり、一〇〇人、二〇〇人が泊まれたらしい。
利右衛門は異説もあるが天保二(一八三一)年、アブタのアイヌ男女(エヒソ、ラムカクシ、シネハンコという男性の名が伝わる)を雇って橋を架け、谷地には木を横たえて道を整備したという。
それ以前、文化年間ごろにはアブタアイヌのオベフキがここに住んで漁業をしており、往来の者を木賃で泊めた。
その死後はハツカンネという者がいたという。
蝦夷地が再度幕領となると道路開削が急がれ、このルートは長万部から黒松内朱太川渡船場までは箱館の福次郎と千代田村の名主才太郎が開削を出願し、資金を勇払場所請負人山田文右衛門支配人士兵衛から受けた。
そして五年間、往来の者から一ヵ所三文で三八ヵ所分の一一四文の橋銭を取ることを許可された。
朱太川の渡船場は一三文の渡し賃をとっていた。新道開削の費用は官費ではなかったのだ。
渡船場から追分(寿都と歌棄への分岐点)は、歌棄・磯谷場所の請負人枡屋栄五郎とその父定右衛門が行い、箱館奉行が高札を立てて顕彰し通行人に知らしめ、彼らは一代苗字を許された。
これらの工事は安政三(一八五六)年中に着手、完成し、箱館奉行村垣淡路守が年末に通行した。
村垣は万延元(一八六〇)年日米通商条約批准書交換の遣米副使節となり、パナマ地峡の汽車にのった時、その周辺の山川地理がわが蝦夷の黒松内越えという新道によく似ていると航海日記に書いている。
松浦武四郎は開削されてもすぐに廃絶してしまう多くの道を見て
「此の間の山越えというは尋常の場所にてはなきが故に、その道よく案内せし老夷どもの居るうちに開き置きなばよろしがるべきものをや。
今、五、六年もせばここの間道案内の夷人もなくなりせば、西場所にして外冦(がいこう)これあり候とも何処より注進すべけんや。
海上の事は風無き時は如何致し候とも致し方なきものぞ」(『再航蝦夷日誌』)と警告した。
箱館奉行堀利煕(ほりとしひろ)は蝦夷地の道路開削を急務としたが、黒松内山道は急な事態に備えて箱館から唐太への交通の利便を意図していた。
瑕夷地が日本国土に組み込まれて、運輸上、防衛上、道路が整備されようとするときにこれらの道の通行人、すなわち国民に、アイヌは想定されていたのだろうか。
この地域のアイヌは文政五(一八二二)年に五九二人であったのが安政二(一八五五)年には三一四人に減少し、翌年からの疱瘡(ほうそう)流行によって、たとえば歌棄のアイヌは五四人から二〇人未満になった。
アイヌの人々は記録に十五世紀から闘争する姿をみせるものの、生活や文化のあり方を知ることはむずかしい。
しかし記録に残された交通路を見ると、東西の接触がかなりありえたことがわかる。
今後、利別川や朱太川流域をはじめ、諸所のアイヌの遺跡が明らかにされることを期待したい。
2 オカムイの岬 積丹(しゃこたん)の地
top
積丹半島
磯谷(いそや)から積丹半島を北上するルートには、雷電(らいでん)山道を越え岩内から古宇(ふるう)-積丹-古平(ふるびら)-余市-忍路(おしょろ)-高島への海岸を進むものと、岩内-稲穂峠-仁木(にき)をへて余市にいたる陸上の二つの道、磯谷-雷電海岸-古宇海岸-神威(かむい)岬-美国(びくに)海岸の積丹半島をめぐり余市・忍路をへて高島にいたる海上の道がある。
安政年間に積丹の道なき道を旅した、松浦武四郎の著作を案内に積丹半島をみていくことにする。
ノット(野津登)
磯谷(寿都(すっつ)町)から二キロほど進むと野津登坂。
ここは日本海へ突き出た小岬で海岸を廻る道はなく、坂道はそれほど高くもなく頂となる。
振返れば寿都の弁慶岬、島小牧(島牧村)の狩場山、向かいは雷電の山々、尻別川の上流けるかには後方羊蹄山(羊蹄山)の優美な姿が見られる。
ライデン(雷電)
野津登坂を下ると川端では萬吉という老人が渡し守をしており、尻別川や雷電山道の話を聞き、いよいよ雷電越えである。
「冬分雪路を越るに一日かゝるなり。其のほかは通ふものなし」(『再航蝦夷日誌』)といわれた雷電山を開削して山道を整備したのは、安政(一八五六)年イツナイ場所請負人の仙北屋仁左衛門とイソヤ場所請負人の桝屋栄五郎である。
この山道により陸上交通の閉ざされていた岩内-磯谷間に通行の手段が確保され、山道開削のおりに温泉(朝日温泉)が発見されている。
山道が通ったとはいえ西海岸の難所に変りなく、玉虫左太夫の『入北記』に
「これよりまた急な坂となり前の坂に比べると短いが危険は倍である。
前の人の足は私の頭の上にあり、後ろの人は私の足の下にいる、杖をつきあるいは蔦に頼って黙々と上る、実に恐ろしい様子である。
壮健を謗る者でさえ一言もなく、この山頂を稲穂峠といい俗に鼻つき峠ともいう」とみえる。
イワナイ(岩内)
雷電山道を下り海岸を五キロほど行くと岩内にいたる。
イワナイの語源ははっきりしない。
『西蝦夷日誌』に「イワナイ運上や、通行や、備米蔵(そなえこめぐら)、板蔵十七、雇や、漁や、其外立物多し」とあり、この頃岩内には本州からの出稼ぎ移住者が多く居住し、『再航蝦夷日誌』では「二八小屋多く七連(ななつら、娼妓)多しと聞り。……七連、按摩(あんま)、髪結床等有。其余また小間もの店も有る」と見え、官舎や商家が市街地を形成し、三味線の音も聞こえるにぎやかさであった。
この地が賑わうにはそれなりの理由があり、「この先フルウ場所は小場所にして二八小屋少なき故二七連もなし。又ヲカムイを越えると女は居らざるか故に」古宇(ふるう)・積丹へ向かう船は皆ここで遊んで行く。 |

図64 イワナイ(岩内)
|
その賑やかなこと筆状しがたしという猥雑な繁栄をみたのである。
和人の繁栄とは逆に、アイヌの人口は過酷な労役と疱瘡(ほうそう)の流行により激減している。
イワナイ運上屋から海辺を行けば積丹へ向かい、右に進めば内陸のヨイチ越えの路である。
稲穂峠
岩内から余市に向かうには船旅を選ぶことが多い、しかし神威岬が難所であることから陸上の道が求められていた。
文化六(一八〇九)年箱館奉行の命により一筋の道が確保され、安政三年にイワナイ・ヨイチ・オショロの場所請負人と漁民が分担して改修工事を行い通年の道が確保された。
イフナイを出て道を東にとれば、この地の馬主が馬を追い込んで放したことから付いた老古美(おいこみ、共和町)、越後弁之助の開墾場といわれる御手作場(おてさくば)を過ぎ、ヘンケシャマツケナイ(上流の横になっている川、共和町国富)という川端にでる。
ここから余市山道をそれ南に進むとサックルペシベ(夏越える道)、さらに進んで現倶知安峠(古くはエナオ峠)に達する。
その先はソウツケ(ソッキ、寝床。鮭の多くいるところ、の意に発する)の地となり、眼前には秀峰羊蹄山の雄姿がある。
道を余市山道に戻り、稲穂峠への登り道は『入北記』によれば、雷電山道と比べると楽で、その日は「笹小屋」と呼ばれる峠の宿泊所に入っている。
しかし、獰猛な熊が多く人馬に被害のでるおそれがあるので、空砲を撃って夜をすごしたとある。
翌日は山道の川を渡り、馬の通れない坂を上り下りして峠を越え、余市川上流のシカリペツ(曲がる川、仁木町然別)にでて余市運上屋まで川下りである。 |

図65 羊蹄山
|
シリフカコタン
イワナイヘツ(岩内川)を渡り砂浜の海岸を一〇キロほど進むとシリフカ(泊村堀株(ホリカップ))である。
堀株川筋は往古に千人もの人々が居住するアイヌの大集落があったと伝えられている。
寛文九(一六六九)年シャクシャイン蜂起の檄に応じてシリフカアイヌも蜂起し、商船を襲い水夫らを殺害したが、シャクシャインの死と共に戦いは終る。
しかし、シリフカのアイヌは「しりふかの狄共(てきども)逃候て出逢不申(であいもうさず)候」(『寛文拾年狄蜂起集書』)と抵抗の姿勢を崩してはいない。
大将カンニシコルによれば蜂起に呼応した本当の理由は、和人がアイヌの鮭漁の川に大網を入れて生業を奪っていること、干鮭買上げの不当な値引きと過酷な収奪によるアイヌの飢餓、「年寄狄」への毒殺陰謀の恐怖など、生活の基盤を奪う過酷な収奪にあり、昔はここにアイヌの家があったが今は何もない。
堀株1・2遺跡で四基のアイヌ墳墓が調査され、儀礼用太刀・漆塗製の膳・高皿・椀などが副葬されていた墳墓の作られた時代は、寛文九年の蜂起後に行われた刀狩的な刀剣など武器類の差出からみて蜂起平定直後の可能性は低い。
また、堀株神社遺跡では八歳の女子の墓、八歳と一〇歳の男子の合葬墓が調査され、寛永通宝(かんえいつうほう)が副葬されていたことから十七世紀以降、天保二(一八三一)年と安政二~四(一八五五~五七)年の疱瘡大流行との関係が考えられる。
茶津チャシ
堀株から岩石海岸の石を飛び跳ねてヒロカルウシに出る。この上の海岸段丘に擦文(さつもん)時代の集落、ヘロカルウス遺跡がある。
強い傾斜面に営まれ前面は日本海に向かい周りに生産的な環境はないので、千年の昔にどのような出来事があったのか不思議な遺跡である。
150()
岩岬を越え下ると「チャシナイ むかし此処ニ蝦夷大王の城有しと云伝よ」(『再航蝦夷日誌』)とみえる。
伝説や古い記録が現地の遺跡と一致して調査されることは少ないが、茶津(ちゃつ)チャシ(チャシは一般に砦と訳される)は一九八三年に茶津川左岸の日本海に突き出した丘陵上で確認された。
「丘陵先端付近のほぼ平坦な面を、幅一メートル、二メートルの二条の濠で区切っている、濠の深さは、約三十センチほどであり、濠間の距離は十五メートルを測る。
……チャシの主体部は、非常に狭い馬の背状を呈しているが、東側の崖面にかなり大きな崩落の跡が認められることから、構築当時は現在よりはるかに幅広であったことは想像に難くない」(豊原熙司「茶津チャシコツについて」『北海道チャシ学会会報 一四』)と報告され、チャシの歴史的背景については「泊村、茶津のチャシはシリフカの大将の居住地か、それに近く、南方から堀株付近に接近する船影を見張り、しかも陸からの攻防戦に備えるにもよい位置にあるように思われるがどうであろうか」元山道子「寛文十年西蝦夷の大将たち」『北海道チャシ学会会報 八』)との提起もある。
茅沼(かやぬま)炭鉱
暗礁の多い岩石海岸を渡り坂を上がり、岡を越えて進むとカヤノマ(カヤニオマイ、帆柱にする木のあるところの意に由来か)である。
安政三年、茅ノ澗(かやのま)村の鱈(たら)釣船の漁夫が山中で石炭を発見したことが茅沼炭鉱の始りで、箱館開港による外国船の燃料として注目され、万延元(一八六〇)年には箱館奉行による調査が行われている。
その後、再三試掘を行うが採算がとれず、慶応三(一八六七)年に幕吏蛯原庫太郎が英国人鉱山技師ガールの指導を得て坑口をつけ、石炭採掘の基礎を築いた。
また、茅沼川を遡り古平(ふるびら)に山越えの路があり、毎年堅雪の頃になると古平の支配人が越えてくるという。
海岸の岡を先へ進むとウスペツ、砂浜にはニシン漁の出稼人の小屋が多く立ち並んでいる。
また「夷家(えぞいえ)むかし四軒有りと。今はなし」(『廻浦日記』)ともみえ、アイヌコタンの消滅が知られる。
武四郎の記録には「夷家むかし有り、今はなし」との記述が随所にみられ、場所の開発と和人の進出によって地元アイヌはニシン漁場の労働力として酷使されしだいに姿を消していく様子がみえてくる。
フルウ場所
この先古平までの海岸線は後背の山裾が日本海に直接落ち込むため、小川が流入する場所以外に平地はなく「大岩大難所・大岩磯・大岩岬・岩壁伝・船澗・岩岬廻り」と記される難所が続き、トラセの岬を廻り岩石伝いに行くとフルウ川に達する。
フルウ(神恵内村)は意味のわからなくなった地名でもある。
フルウ運上屋「通行や、備米くら、板くら十一、大工小や、雇くら、舟くら」、「夷人小屋十八軒、人別七十五人」(『廻浦日記』)とある。
また、ここは神威岬に近く岬越えをするので皆櫓櫂(ろかい)の扱いが上手だともいう。
観音洞窟遺跡
運上屋近くに観音洞窟遺跡がある、擦文文化が主体で貝塚をともなっているため、骨角器が豊富に出土している。
鎌倉時代・室町時代の層から回転式銛先、さらに新しい良好な層から江戸時代後期・末期の遺物が一括して出土している。
狩猟用具と共に海獣や陸獣の動物遺体も出土し、狩猟漁労活動の性格が強い遺跡であることが確認され、縄文時代から絶えることなく人々の暮らしがあった。
フルウ運上屋からシャコタン運上屋まで三〇キロの海岸は今までにも増して困難なルートで、もはや道らしい道はなく旅とは呼べず探検であろう。
この間の危険な個所を拾ってみると、フイウシ「大岩の中を等通りて」、フレチシ「道いよいよ悪敷相成候」、ウェンチュツフ「滝に添うて草の根に足踏懸上る……木の根に取付てツ子まゝ……堅雪の上を鉞(まさかり)にて一欠づゝ欠ては其に足踏留めて下り」、ヲン子ナイ「赤砂崩れ来り如何にも辷りて危かり……下は峨々(がが)たる岩壁に白浪打当て」、エモエントマリ「裸に成(なり)海に飛入、上なる岩へ綱をかけて是(これ)をもちて越たり」と見える人外の地である。
シャコタン場所
「シャコタン場所(積丹町日司(ひづか))、運上や、板倉、漁小や、茅(かや)ぐら、弁天社、当所はクツタランにてシャコタンと云うは場所の惣名(そうみょう)なり」(『西蝦夷日誌』)とみえ、サク・コタン(夏の村)を意味する。
運上屋が置かれていたのは積丹川から一キロほど北に寄った日司でクッタラ・ウシ・イ(いたどり・群生する・ところ)に由来し(『北海道の地名』)、産物は鰊(にしん)・飽(あわび)・海鼠(なまこ)・かすべ・ホッケ・昆布などがあり、シャコタン岳では筆管や煙管に使用する斑模様のシャコタン竹を産し、五葉松の巨木が多いとも記される。
シャコタン運上屋をでてビクニまでの一三キロは陸道を行くが、安永七(一七七八)年にシャコタン場所請負人の岩田金蔵が山道開削をしており、フルウからの道とは違って周りを見る余裕がある。
樹木がないので神威岬がよく見え、平地だから開墾すれば畑地もできる。
ホロムイ(積丹町幌武意)の上に出ると美国・積丹の浜、さらに進んで高さを増すと石狩湾を越えて雄冬(おふゆ)岬(増毛町)と積丹の山々と神威岬が一望できる。
チャシナイ(城跡の沢)から浜に下りると出稼ぎの小屋が立ち並び、美国川を渡るとビクニ運上屋である。
ビクニからフルビラまでは浜道だが、近年は山道も開かれている。
フルビラはこの地一帯の名で「小湾をなして、其間船澗よろしく、漁業至極よろし」(『廻浦日記』)とあり、この時期、鰊が群来ており浜は大賑わいであった。
余市運上屋
フルビラからヨイチまで一五キロは「此処より石カリ迄は夷人ども多く山道浜道等有て歩行にて行ニよし」(『再航蝦夷日誌』)とあり、難所もあるだろうが「独木橋」もあり通行に支障はないようである。
次々と現れる入江には出稼ぎ小屋が立ち並び、規模の大きなところには番屋や稲荷社もあると記されるが、「夷人小屋」の少なさには驚かされる。
余市運上屋(余市町)は余市川河口の西にあり、「此処を下ヨイチ運上屋と云う。然れどもヨイチは此川の有る沢の名にして、当所はモエレが地名なるべし」(『西蝦夷日誌』)といい、シリパ岬と忍路の間に余市湾がありまさにモイレ(静か)である。 |

図66 旧下ヨイチ運上家
|
余市はこの地方の一大場所で、旧下ヨイチ運上屋は重要文化財に指定され、その規模は梁(はり)間八間、桁(けた)間二二間の一棟建てで、上座敷・表座敷二・物置部屋・帳場・番人稼方居間・船主居間・雑部屋などがあった。
「モエレ(人家続き五町八間)、此辺料理や、また浜千鳥といえる賤妓(せんぎ)等有て、三絃太鼓の音等もせり」(『西蝦夷日誌』)とみえ、安政年間の繁栄がうかがえる。
大川の遺跡
余市川周辺には遺跡が多く残され、余市川左岸段丘にある天内山遺跡は、発掘調査により土壙墓(どこうぼ)や貝塚が発見されている。
墓壙は擦文時代のもので大刀・刀子(とうす)・斧・鎌などの鉄製品が注目され、貝塚はアイヌ文化期で鉄鍋・キセル・マキリ・耳飾・ガラス玉・陶磁器などが出土し、クロアワビやニシンが多く含まれていた。
河口近くの左岸に入船遺跡、右岸に大川遺跡があり、入船遺跡は縄文時代から中世へと続き、近世では一七基のアイヌ墓が発見され、「墓壙認識の層位、キセルの型式学的所見、余市川河口の歴史的変遷などから考えると、十七~十八世紀の墓地であろう」とされ、副葬された秀品から余市コタンの豊かさが想像されるといい、貝塚・建物跡・石矢来(いしやらい)・石組炉などの遺構が発見されている。
大川遺跡は縄文~中世・近世にわたる一三〇〇基以上の墓壙や住居などの集落が重層して調査されている大遺跡である。
擦文期では大量の米が出土し、日本海をルートとする東北地方から北海道への交易路がみえはじめ、「夷」字が刻書された土器も出土しており共に注目される。
中世では壕で区画された居住空間が調査され、青磁や白磁、瀬戸・美濃の陶磁器と十五世紀前半の能登半島珠洲焼きの擂鉢(すりばち)が多数出土している。
この遺構について「雪解けの後、本州からやってきた船が着いて荷を揚げ、壕に囲われた家屋に住み着いていたのではないかと思う。
このことは、余市の住民、たぶんアイヌの人たちにとっての直接的な文化接触になったに相違ないが、あくまでも交易が主であり、アイヌの社会を変容させるにはいたらなかった」(『北の民族誌』)とみており、合葬された二基の火葬墓と銅鏡も発見されている。
近世では発掘区内に点在して一六基の墓壙(ぼこう)が調査され、副葬品には自製品はほとんど含まれておらず、アイヌ社会は多くの外来品によって成り立っていたことがわかる。
また、数百万点といわれる膨大な出土遺物は、どの時代をとっても秀品が多く、一度は訪れてみたい遺跡である。

図67 フゴッペ洞窟遺跡壁面彫刻 |

図68 小樽市忍路 |
フゴッペ(畚部)洞窟
余市川を渡りオクノシケ(砂浜の中央)の砂浜が終る所にフゴッペ洞窟があり、洞窟の岩壁に人物・獣・舟など二〇〇を超える彫刻が刻まれている。
現在はカプセル方式の保存施設によって護られ見学することができる、続縄文時代の神聖な場所とされる遺跡である。
これから先はまた絶壁の海岸が続き、オショロ運上屋に着く。
オショロ場所(小樽市忍路)は追分節にも歌われたニシン千石場所の風光明媚な深い入江で、「其辺り李花多く、満開の時は海面に映じて、掉入舟は水晶盤裏を渉るかと思わる」(『西蝦夷日誌』)とする安全な港である。
忍路に多くのアイヌが居住していたことは松浦武四郎の記録にもみえるが、忍路神社遺跡で十八世紀アイヌ期の貝塚が調査され、伝統的な海獣狩猟を行うと共に、網を使用した大規模な漁業活動を行い、ニシン以上にホッケやカレイの水揚げの多かったことが判明した。
ここから高島(小樽市)までは山道を行き、桃内(ももない、ヌモマナイ、果実ある沢)・塩谷(ショー・ヤ、岩・岸)をへて高島にいたる。
高島
高島は追分節にも歌われたこの地方の中心地であるが、地名は和名なのかアイヌ語なのかはっきりしないという。
和名の高い島、アイヌ語まじりのタカ・シュマ(鷹・岩)、トゥカラ・シュマ(海豹・岩)などの説があり、「高島といへども本名トカリシュマにして、訳(わけ)て水豹(あざらし)岩の義也。此処湾の中に水豹の多く寄集る岩有故に号しものなり」(『西蝦夷日誌』)とみえる。
ここに小樽水族館があり、海辺にあるトド飼育場では柵を乗り越えて外海のトドが入り込むこともあり、トゥカラ・シュマに肩入れしたくなる。

図69 大岩壁の雷電海岸 |

図70 カムイ岬 |
西蝦夷の難嶮
西蝦夷地を北上し余市・高島に向かうには船旅を選ぶことが多い。
黒松内(黒松内町)を越えて磯谷に着くと、そこから先は西蝦夷三険岬の一つ神威岬を廻る海上の道でもある。
磯谷を発するとまもなく、屏風のごとしといわれる大岩壁の雷電海岸が現れる。
ここには弁慶が刀を掛けたと伝えられる奇岩刀掛け岩がある。
岩内沖にさしかかるとイワオヌプリの赤禿た山容が望見され、格好の目印である。
岩内の野東川河口は小さな岬となっており、難破船の多いことからイナウ(木幣=もくへい)をささげ海の安全を祈ったエナオ岬の名が与えられている。
岩内湾を越えようとすれば堀株に接近する船影を見張る適地とされる茶津チャシがあり、茅沼には「烽火(とぶひ)有」、兜岬(泊村)「カムイシレハ、神崎の義、形兜に似たる」は海中に突出した大岩岬である。
険しい海岸が続き、陸上の交通路が整備されていない積丹半島では小さな入江ごとに船澗があり、中小の船が運搬の主役であり、船掛かりしているのが日常的な光景であった。
神恵内~積丹にかけては断崖絶壁の荒々しい海岸風景で、南から弁財澗・竜神岬・マッカ岬・川白(かわしら)岬・窓岩・西河原があり、「和人西院川原といふ。
舟を寄るに小石を積置けり」(『西蝦夷日誌』)とみえる。
カムイ(神威)岬
江差追分節に「忍路高島及びもないがせめて歌棄磯谷まで」とある。
通説は「忍路や高島の漁場に行っている懐かしい男を追っていきたいが、その手前のおかもい様(神威岬の大岩)が女人の通航を許さない。
せめてそこに近い歌棄、磯谷の漁場で働いて、帰りを待ちたい」という。
神威岬の女性通航禁止は「松前藩は、資源独占のために、極端な釧国制度を探り、奥地に和人が入らないように制限して居たので、この辺のアイヌの習慣を利用して、北地に女人が入り、従って開けて行くのを禁じたのであった」(山田秀三「北海道アイヌ地名閑談」『アイヌ語地名の輪郭』)と理解され、船舶航行の難所を利用した女人禁制はきわめて政策的なものであるが、北方警備の関係から蝦夷地が幕府の直轄地となり奥地開拓のため女人禁制が解かれ、女人通航が実現した。
「丙辰(へいしん、安政三年)の春迄はこれより奥は女を禁じ置しを、今期に入る様に成、浜千鳥と云賤妓、また引越の者等多く入込しが、当年は別て大漁なりと。是迄松前にて女を此奥え入ると漁が無と言伝へ有しも、全く荒誕(うそ)なりしこと明(あきらか)也」(『西蝦夷日誌』)と皮肉が書かれている。
だが船乗りたちはすぐに婦人を乗せた航行に理解を示したわけではなく、安政三年に箱館奉行所の梨本弥五郎が妻子を連れて宗谷に赴任する時、「この神威岩に差しかかると、舟子達が恐れて進もうとしなかったので、蝦夷開拓を妨げるものは、神に非ずと称して、岩に鉄砲を放ち、驚愕した舟子を叱咤して此処を通過した」『アイヌ語地名の輪郭』)とされ、迷信が消えさるには長い時間を必要とした。
この頃はニシンの主要漁場が北へ移動していた時代で、漁民もニシンを追って古平・余市への出稼ぎが増えており、江差追分も時代を反映する男女のドラマであろう。
安政二年にはニシン大網の使用を巡って江差から熊石の漁民が島小牧から積丹・古平の大網を切断してまわる「網切騒動」と呼ばれる事件も起きている。
神威岬をかわすと積丹半島のもう一つの突端、「廻りで外海になる。波浪愈(いよいよ)強し。岩ますます怪く、一撃せば忽(たちまち)魚腹に葬れんの地也」(『西蝦夷日誌』)とある積丹岬である。
しばらく進むと「その姿、あたかも人の如し」と言われる女郎子(じょろこ)岩があり、この先は岩壁と出稼ぎ漁民の小屋が立ち並ぶ小さな澗が交互に現れて美国・古平・余市へと続く。
3 イシカリ川筋と十三場所 top
石狩灯台
「喜びも悲しみも幾歳川」という映画をご存じだろうか。
実際に映画館でご覧になった記憶をお持ちの方は多くはないと思うが、木下恵介監督のこの映画は、名作としてビデオにもなっているというから、ビデオでなら、あるいは若い方でもご覧になった方もいらっしやるのではないかと思う。
一九五七(昭和三十二)年に封切られたこの映画は、若い灯台守の夫婦が、昭和初期から各地の灯台を転勤し、年月を重ねていくなかで経験する様々なできごとを描さながら、そこに舟の安全を守る責任、葛藤そして夫婦の愛を歌いあげたものといわれている。
この夫婦の最初の転勤先が北海道の石狩川河口にたつ灯台であった。
石狩灯台は、石狩川河口にある石狩港に出入りする船の目標のために建てられたもので、一八九二(明治二十五)年の開設であるから、とうに一〇〇歳を超えている。
実際、ロケもこの石狩灯台で行われているから、映画の中に見られる石狩灯台とその周辺は、一九五五年初頭ころの石狩川河口の様子を写し出していることになる。
現在灯台は無人化されているが、周辺はハマナスの丘公園として整備されていて、夏は北海道の花ハマナスの赤が青空に映えて美しい。「喜びも悲しみも幾歳月」主題歌の歌碑もある。
灯台は赤と白の横縞に塗り分けられているが、このように塗り分けられたのは、映画のロケの時からだという。
かっては白と黒のモノトーンであったというが、映画がカラー作品であったことから「写りをよくするため」、関係者の要求でこのように塗り替えられた。
灯台の案内板によれば、それまで国内の灯台は白もしくは白と黒に塗られていたが、石狩灯台の赤白が雪原ではよく目立つたということで、以後、降雪地にある灯台は赤と白に塗り替えられていったというエピソードがある。
この灯台を目印に、石狩川を遡ってみよう。
古代の「大河」
北海道を旅していると、よく、「北海道は歴史が浅い」という言葉を耳にする。
歴史という意味を、人間の歩みというようにとらえれば、決して北海道の歴史は浅くないのだが、それでも歴史に興味を持たれている方はよくご存じで、「文書に記録されている歴史」という意味では、北海道の歴史は新しいでしょうと切り返してこられる。
こうおっしゃる方の多くは、北海道が文書に登場するのは明治以降からと思っておられる方が圧倒的に多いようだ。
実は「えぞ」という言葉自体、久安六(一一五〇)年頃にはすでに和歌の中に登場していて、近世になると「北海道」のことが文書に記録される例は多いのである。
ところで、さらに遡ってその記録が古代史の範疇に入る『日本書紀』にも北海道のことが記録されている可能性があることが指摘されている。
驚かれるかもしれないが、斉明六(六六〇)年のことである。
この記事に、阿倍臣(おみ)比羅夫(ひらふ)は、「粛慎(みしはせ)国征討」のため、「船軍二〇〇隻を率いて陸奥の蝦夷(えみし)を同船」させて「大河のほとりに停泊し」たとある。
「蝦夷」や「粛慎」がどういう人々であったのかについては、議論のあるところであり、他の書物に譲るとして、今ここで注目したいのは「大河」という言葉である。
この大河がどこであったのかについてもまた、戦前から日本古代史や考古学の研究者の間で議論があり、この時、阿倍臣が北海道の地にまで足をのばしているとする研究者の中には、この大河を「石狩川」に比定する学者もいる。
『日本書紀』には詳しい記述はなく、また年代や記録の内容自体も検証が必要なので、断定することはできないとする、慎重な議論もある。
ところが、石狩川を中心とした広い範囲で、この記事の正統性を示唆するような考古学的発見があいついでいる。
石狩川からは距離的に離れるが、余市町の大川遺跡では、中世から近世にかけての、大陸産品を含む本州から持ち込まれたと考えられる陶器類やガラス玉などの考古学的遺物が発見されている。
また、同じく余市町のフゴッペ洞窟遺跡で発見された刀剣を復元研究したところ、古代律令国家で貴人が帯びていた太刀や刀子(とうす)と同じものであったという。
どちらも、北海道と古代国家との交流が古い時期からさかんであったことをうかがわせるに十分なものといえよう。
とすれば、ふるく『日本書紀』にあらわれた大河が、この石狩川であった可能性も、否定できないどころか、むしろ高いということもできそうである。
石狩川
古代に思いを馳せたところで、現代に戻って、手元にある地図帳を広げてみたい。
石狩川は、北海道の中央部に位置する石狩岳(標高一九六二メートル)に源を発し、周辺の山々から流れ出る河川を束ね、集まった豊かな水を日本海へと運ぶ、長さが二六八キロの河川で、信濃川、利根川に次ぐ日本第三位の長さを持つ。
河川は、北海道の穀倉地帯である石狩平野を蛇行しながら流れる。
近年は河川の改修や湖沼、湿地の埋立てがすすみ、旧河川の様子がわかりにくくなっているものの、まだ、所々にこの大河が大地に刻んだ痕跡である三日月湖を見つけることができる。
ところが、実際に石狩川の流れをながめつつ旅をしようとすると、簡単ではない。 |

図71 石狩川の三日月湖
|
たとえば札幌からJR列車函館本線に乗り旭川に向かうとしよう。
線路は石狩川とほぼ並行して走っているが、車窓からこの河川を眺めることができるのは、札幌の隣の市、江別駅をすぎてすぐ、左手に眺めることができるほかは、内陸部の滝川市をすぎて河川をまたぐまで、見ることができない。
札幌から旭川へは、国道一二号線が走っているが、これも江別市のはずれで左手にわずかにながめる程度である。
もっとも、札幌から北海道教育大学をへて石狩当別方面へと向かう札沼(学園都市)線に乗れば、下流において鉄橋でこの川を渡ることになる。
この河川が潤す石狩平野は、きわめて平坦で、河口から一〇〇キロほどの内陸部でも標高は三〇メートルほどであるという。
この低平さが河川の蛇行を生み、さらには頻繁な洪水を引起こすこととなる。
なかでも被害が大きかったのは、一八九八(明治三十一)年の洪水であり、「石狩原野大洪水」の名で呼ばれている。
また、比較的最近のものでは、一九七五(昭和五十)年の洪水が大きく、耕地二万九〇〇〇ヘクタール以上が浸水、浸水家屋は二万戸にも及んでいる。
石狩の語源
ところで石狩という名前は、河川名だけでなく、平野名、地方名、町名など、様々なところで見ることができる。
アイヌ語であろうとは、ほとんどの方が想像されるところだろうが、その意味するところとなると、正確にはわからないようだ。
アイヌ語地名研究の第一人者であった山田秀三は、一八九一(明治二十四)年の永田方正による『北海道蝦夷語地名解』の中にみられる三つの説をあげている。
(一)原名イシカラペツ。回流川の意。
(二)イシカラペツであり、美しく作りたる川。
(三)鳥尾にて箭羽(やばね)を作るところ。
この三つを紹介した上で、「石狩のような大地名になると、その地名の元来の発祥地が忘れられたので、従ってその語義も分からなくなるのが自然」であったし、「その音であっても、元来の形さえ見当がつかなくなる」という。
石狩川にかぎらず、多くのアイヌ語地名は、アイヌ語の音を、おそらく日本語話者が聴き、その微妙な音をカタカナさらには漢字に置き換えていったものである。
一〇〇年以上の時間をかけて、そうしたプロセスをへたものであるにもかかわらず、我々はその漢字のよみから、何とかアイヌ語としての意味を探るうとする。
北海道の地名の意味を探る試みは、楽しいが、かなり困難な試みでもあることを知っておくべきであろう。
江戸時代の石狩
さて近世になると北海道のことが文書記録にみられるようになると書いたが、その理由はおおまかにいうと、一つには渡島(おしま)半島松前に城を構えた松前藩が成立したこと、また、江戸時代を通して、蝦夷地周辺にロシアなどの外国船が現れ、それに対して幕府が神経を尖らせ、幕吏にさかんに調査を命じるようになったことによる。
前者には蝦夷地の産物の流通を請負った商人が残した膨大な記録類があり、そこにはその時々の、商人側とアイヌの人々との関係や松前藩との関係なども記録されている。
石狩川についても多くの記録があるが、ここでは探検家松浦武四郎が残した記録をもとに、その様子を眺めてみよう。
弘化二(一八四五)年以降、三度にわたって蝦夷地・樺太・千島を探検した武四郎は、『初航蝦夷日誌』『再航蝦夷日誌』『三航蝦夷日誌』の三つの記録を残している。
石狩場所へは弘化三年に訪れており、その様子を『再航蝦夷日誌』に記している。
この時期にはすでに場所請負が行われており、この地のアイヌの人々は場所を取り仕切る商人の元で、漁業に従事していたのであるが、このような場所が石狩川および支流を含めて一三あったとされ「石狩十三場所」と言いならわされている。
ただし、武四郎が記録したのはそのうち一二場所であり、その中には、石カリ、ワッカオイ、ハッシャフ、サッポロ、ツイシカリ、トウベツ、ユウバリなど、今日でも耳にする地名がみられる。
こうした拠点が、現在のどの場所にあったのかを比定することは、当時からみて今日では河川の流路もかわり、埋立てもすすみ、また市街地化もすすんだために、難しいようである。
武四郎が訪れたのは、秋味(鮭)漁のシーズンで、人々が漁を行っている様子が記録されている。
石狩十三場所の成立史については、『新札幌市史』(第一巻)にくわしいが、同書では、当時の石狩川とアイヌの人々の様子について、特に石狩川は流木がかなり多い川であったようで、毎年春先にはアイヌの人々に漁の準備のため、流木の撤去をさせていたが、その費用がかなりのものになっていたことを、紹介している。
さて、この石狩場所で、もっとも重要な産物は鮭であり、たとえば天明年間には一万二〇〇〇石ほどの漁獲量があったといわれる。
そのほか、鱒、平目、アブラコ、ホッケ、カスベなどがとれたとされ、めずらしいところではイトウそしてチョウザメなども産物としてあがっている。
ところで、蝦夷地での漁業といえば、アイヌ民族に伝わる「伝統的な」漁具を使っての漁をイメージされる方も多いのではないだろうか。
おそくとも十九世紀に入り、場所請負制(ばしょうけおいせい)下、資本力のある商人のもとでの漁場経営となると、和人の出稼ぎも多く、糸網を使った大規模な引き網漁となっていたという。
アイヌの人だけで行う漁場もあったが、そこでも行われていたのはシナ網をもちいた引き網漁であったという。
対雁(ツイシカリ)の歴史
ところで、石狩十三場所でツイシカリの名前をあげたからには、かってこの場所でおこったできごとについて、ふれないわけにはいかないだろう。
現在、対雁という漢字が当てられているこの地は、現在の江別市内にある。
ことのおこりは一八七五(明治八)年に締結された樺太・千島交換条約による。
十一月の公布に先立って、開拓使は同年十月、樺太からアイヌの人々一〇八戸、八四一人を北海道の宗谷へ移住させ、翌年六月、さらにこの対雁へ移住させたのである。
住み慣れた郷里を離れ、慣れない土地での生活を強いられることになった樺太アイヌの人々にとって、対雁への移住とそこでの生活がどれほど大変なことであったのか想像に難くないが、さらに追い打ちをかけるような、つらいできごとが樺太アイヌの人々を苦しめることになる。
一八八六(明治十九)年、函館に発生したコレラは、道内各地に蔓延、さらに悪いことには天然痘も流行り、これが対雁に暮らす樺太アイヌの人々をも不幸に陥れることになる。
亡くなった樺太アイヌの人々は約三〇〇人にものぼったという。
一九〇四年の日露戦争の結果、翌年、日本は北緯五〇度以南の樺太の割譲を受けることになる。
対雁へと移住させられた樺太アイヌの人々は、一九〇六年、樺太へ帰還することができたものの、当時の歴史の流れとはいえ、大国の都合で、慣れない土地への移住を強制され、さらには家族をも失うほどの悲しみと苦労を強いられた人々のことを、我々は忘れるべきではないであろう。
アイヌと鮭漁
アイヌにとって冬越しのための重要な食料源は鹿と鮭であったといわれる。
和人が蝦夷地に入り込む以前、アイヌの人々が自由に食料を捕り、交易していた時代は、おそらくこの二つが主要な食糧であったともいわれている。
そこで、鮭漁にまつわる地名を取り上げてみよう。
石狩川中流でも上の方、現在の深川市に一巳(イチャン)という地名がある。
「イチャン」という読みからして、多少なりともアイヌ語やアイヌ文化を勉強したものであれば、それがアイヌ語らしい響きをもつ言葉であることぐらいの察しはつく。
アイヌ語辞書をめくれば、それが鮭の産卵場所のことをさすのではないかということまで、たどりつくことはできよう。
さらに、深川の市街地あたりに、メムという地名が残っているという。
これはアイヌ語の単語でいえば湧き水のあるところという語がちょうどあてはまる。
実は、この組合わせは、鮭の生態学からみても、まことに都合がよい。
鮭が産卵のために生まれた川を上ることはよく知られているが、それでは、産卵するためには、どんな河川でも、どんな場所でもよいかというと、そうではなく、条件があるという。
その条件とは、河床が小砂利、小礫からなっており、そこに湧水があることであるという。
たとえば、札幌市を流れる石狩川の支流の豊平川に鮭を呼び戻す運動がおこって久しいが、戻ってきた鮭が産卵する場所の一つが、ちょうどJR函館本線の橋梁と河川が交わるあたりであるという。
このあたりは豊平川扇状地の末端部にあたるらしい。
扇状地地形ではその末端部で伏流水がわき出しているという地理学の知識を思いだせば、まさにJR橋梁付近の河川床は鮭の産卵に適しているということがわかる。
このような地名で呼ばれている以上、この地はアイヌの人々との間に鮭の産卵を通した深い関わりがあったとみるのが自然であろう。
まっさきに想像できるのは鮭漁の様子であるが、産卵という鮭の細かな動きに注意を払っていることから推測すれば、ここでの鮭漁は、鮭の行動をよく見極めたうえでの漁、たとえばマレクや引き鈎(かぎ)を使った漁が、考えられてよいのかもしれない。
そして、場所請負制下での漁であったとすれば、それは場所での仕事が終り、越冬に備えて自分たちの食料を確保するための、小規模な漁であったとも、考えられよう。
一口に鮭といっても、海でとれる鮭とある程度河川を遡上した鮭とでは、質が違うという。
前者は、河川の遡上、産卵という大仕事を控えているため、脂ののった状態、それに対し、後者は脂がおちた、いわゆる「ぽっちゃれ」状態である。
そして、冬越しのための天日干しや薫製には、脂がのった状態のものより、抜け落ちたものの方が、適しているという。
ある大学の授業で、「アイヌの人々はおなかに卵が入ったメスのサケは絶対に捕らない。
生まれてくる命を大切にしていたからであり、そうすることが、結果的に、将来の自分たちの生活を保証するものである。
それは、今日でいう資源の保護の考え方につながってくるものである」ということを聞いたことがある。
なるほど、「自然の中で、自然を大事にし、自然と共に暮らしてきた」といわれることが多いアイヌにとっては、大変都合がよい説明であるが、本当のところ、鮭漁に関しては、どうもそのようなことはなかったようである。
まず、アイヌの道具の中には、鮭の卵を潰して調理する木椀が実際に存在するし、それを使った料理もあることが知られている。
先ほどの言説を否定するにはこれだけで十分であろうが、私が実際に聞いた漁法も、紹介しておこう。
鮭はメスが産卵するそのそばにオスが寄り添い、産卵の瞬間、放精するが、実はこのカップルのまわりには、ナンバーツーをねらうやや力の劣るオスたちが隙をねらっている。
そこで、メスはとらずに、まずカップルになろうとするオスを銛で突いていく。
このようにして、何匹かのオスを捕ったあと、最後にメスのサケを捕る。
ある古老はこのような方法を教えてくれた。
メスを追いかけ、やっとチャンスがめぐってきたと思ったらグサリとやられるオスの性は悲しいものだが、鮭の習性を知り、動きをよく観察する目がなければできない漁法であるといえるのではないだろうか。
大河川である石狩川はまた、産業の発展にともなって、産炭地での洗炭用水や、パルプ、化学工業などの工業用水に利用されたり、また廃液が河川に流れ込むなど、汚濁が進んでいた。
一九七〇年代頃から始まったカムバック・サーモン運動は、石狩川支流で札幌市内を流れる豊平川に鮭を呼び戻そうというものであったが、こうした運動の成果もあって、段々と河川の清浄化がすすみ、七〇年代末からは、豊平川にも鮭の遡上がみられるようになった。
top
****************************************
|