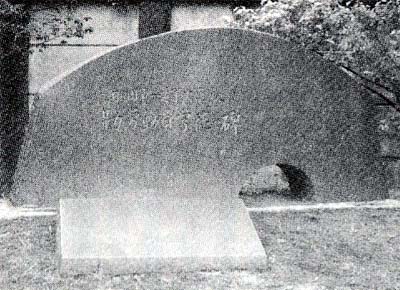|
****************************************
Index Ⅰ章 Ⅱ章(“上” “中” “下”) Ⅲ章 付録
Ⅱ章 陸前南部の歴史(“下”)
五 自力更生の実践 top
1 武士の農法・北海道移住
武士団の解体
戊辰戦争の敗戦で、仙台藩は六二万石から二八万石に減封された。
そして、仙台南部の宇田郡・伊具(いぐ)郡・亘理(わたり)郡・刈田郡・柴田郡は、南部藩の所領と決定された。
ところで、仙台藩に与えられた二八万石は表高(おもてだか)ではなく実高で、表高になおせば一八万石にすぎず、旧領の三分の一に満たない。
当時、仙台藩の家臣は直臣一万二〇〇〇人、陪臣二万三〇〇〇人であった。二八万石では、これら家臣団を養うことは不可能である。
そこで、思いきった家禄の削減を行った。明治二(一八六九)年の廩米(りんまい)基準によれば、一門一三〇俵、一家~太刀上五五俵、大番頭(一〇〇石以上)二五俵、同馬上以下一六俵、組士一二俵、凡下扶持人(ぼんげふちにん)八俵となっている。
福島県に接する伊具郡角田に要害を持つ石川氏は一門の筆頭であり、幕末に二万一三八〇石余を持ち、その家中は一三五二戸であり、わずか一三〇俵では家臣団を扶持できない。
仙台の南岩沼から浜海道に入った亘理に要害があった亘理伊達氏は幕末に二万四三五二石余を持つ一門であったが、これまた同様な状況におちいった。
さらに、奥羽街道沿いの刈田郡白石に居を構えていた片倉氏も一万八〇〇〇石余を有する一門であったが、いずれも家臣団の解体は眼前に迫っていた。
仙台藩は幕末まで知行制も維持し、給人の多くは知行地に居住地を持ち、家中を抱え、彼らは奉公人前という手作地を持っていた。
それをふまえ、藩では明治二(一八六九)年、弁事局に嘆願し、藩士・家中のうち農村に居住し、耕作している者に租税を負担させ、帰農させた。
また、知行地でも農民に耕作させている者、あるいは扶持米取の者は、今まで通りの居住地に住まわせ、養蚕そのほかの職業あるいは賃雇でもさせ、そのうち農業や商業を行わせたいとした。
弁事局では、仙台藩全域で、これを認めることにした。
この頃、さらに北海道移住も考えられていた。
扶持米受給者は城下仙台あるいはその周辺に居住していたが、版籍奉還の時点で、一九九二人の藩士が暇を出され、一八七五(明治八)年の調査では、家禄を受ける者は四七〇一人に減じている。
仙台南方五郡は仙台藩領から切離され南部領とされたから、旧支配者層のみならず、農民たちも動揺せざるをえなかった。
一八八九年一月、伊具・亘理・宇多三郡の農民代表者たちは、東京へ出て、明治政府に、従来通り仙台藩の支配下におかれるよう強く嘆願している。
士族の帰農
一八八九年までの給人、家中の帰農は組織だったものではなく、個人の自発に委ねられていた。
しかし、翌年になると、統一的・強制的な施策として行われるようになった。
同年六月、従来在郷住居の給主ならびに足軽、扶助米のない者の帰農が申しつけられた。
ただし、知行地を持つ給人であっても、手作地を持たない者、あるいは奉公人前がないか、わずかしか持たない者へは、囲取によって開拓地を分与することにした。
その実施は一ヵ所五〇〇〇坪を単位とし、囲取によって場所を定め、希望者にはさらに一ヵ所を追加し、一万坪を限度とした。
開拓地の申請者が多かったらしく、農民の入会地まで拡大されている。
家中の手作地・奉公人前や開発などして得た抱地の所有権は旧主人である給主にあったが、それも家中への分与も認める方針を打出した。
しかも給主の再生産基盤の確保と、農民の耕作権を侵さないという条件つきであった。
北海道移住をめざしていた片倉小十郎重役佐藤廓爾(かくじ)・伊達藤五郎重役田村顕允(あきざね)・石川源太重役泉奥太郎は、北海道移住までの間、奉公人前の地所について家中の自作を認めたいと、角田県へ嘆願書を提出した。
石川氏の場合角田県では一五歳未満、五〇歳以上の者に対し、向こう二年間にかぎり、田畑を貸付けることにした。
ただし武士身分で農業を行うことは不都合であるとし、脱刀を申しつけた。
しかも、奉公人前すべてが貸渡されるという期待をしたが、それは一部であり、脱刀という条件に不満であった。
貸付地は予定していた土地の三分の一であり、従来の給分五石以上の者には六石、二石以上五石未満の者へは四石、二石未満の者へは二石と定められた。
明治三(一八七〇)年、北海道移住を断念した石川氏は、家中の帰農願を角田県に再三行い、苦慮した角田県もやむなくこれを認めた。
ただし、一般農民になるので、廃姓・脱刀・主従関係の断絶という条件もつけられた。
家中=陪臣(ばいしん)層は主家の身分によって、帰農条件も異なっていたが、一八七五(明治八)年には、ほぼ三万戸の帰農者が創出され、村落の行政・産業・精神上の指導者として期待された。
大番士大槻安広は開拓分与地五〇〇〇坪のうち一〇〇〇坪を開拓し、その後旧知行地宮城六丁目、荒井両村で出畑を買得、山林なども購入して、一八八〇年頃には山林一四町、田畑六町余を持つ地主手作経営者となった。
また、角田石川氏の家中で稲置(いなおき)村の芦名(あしな)家は一八七七年の場合、山林を含めて、二町四反歩を所有しており、田の一部を小作に出している。
本藩・石川家臣団の移住
領地を大幅に削減された仙台本藩や館主が家臣団の帰農と共に、企図としたのは、北海道移住である。
仙台本藩が嘆願し与えられた北海道の分領地は、明治二(一八六九)年の千島の紗那(しゃな)郡、日高国沙流(さる)郡、翌年五月の千島の振別(ふれべつ)郡・蘂取(しべとろ)郡、明治四年六月の根室国目梨(めなし)郡・標津(しべつ)郡である。
日高の分領地は屯田基地としてであり、百数十人の卒族と、函館脱走兵七〇余名を移住させた。
ただ、本藩は移住開拓策に熱意を示さず、廃藩置県による本領地の解消によって、その歴史に幕を閉じた。
片倉氏・石川氏・亘理伊達氏の場合、南部藩領になるので深刻であり、特に最初に計画したのは、亘理伊達氏で、片倉・石川両氏もこれに同調した。
角田県では石川氏の陪臣の武装を解除し、すみやかに分領地室蘭に移住させようとしたところ、明治三年四月初旬頃、彼ら一〇〇〇余名の者が集合し、帰農の強訴を行った。
そして、移住した陪臣の多くは、帰農を希望しつつも、旧来からの恩義と上からの説諭により、それに従っただけで、多くは帰農を希望し、彼らの発言力が強く、積極的に移住開拓を行わんとする陪臣に影響を与えた。
館主石川源太は過日移住した四〇戸を除いた九四一戸の陪臣の帰農を認め、移住者は片倉・亘理伊達両家へ附属させ、分領地室蘭郡も両家へ分割させたいと内務省に嘆願した。
内務省もこれを認め、六月、石川氏の室蘭支配を罷免し、これを分割して、亘理伊達・片倉両家支配とした。
片倉・亘理家臣団の移住
片倉氏の場合、転封してくる南部藩の本拠地となるだけに、ただちに家臣団の新仙台藩領への移住と帰農が政府から諭達された。
そこで北海道開拓分領地の給与を出願し、明治二(一八六九)年九月に、胆振国幌別郡が与えられた。
翌年六月、移民二一戸が幌別に送り出され、翌五年三月に第二次の四五戸が移住した。
これは計画の一割にすぎない。その理由は、移住費用が自弁であり、その負担ができなかったからである。
ところが分領地給与と前後して、南部氏の盛岡復帰が認められ、白石を引払った。
そして、片倉氏の陪臣で帰農した者は苗字帯刀を禁止され、臣従関係を断つよう指示された。
これら帰農者の多くは、移住開拓に反対した。第三次の移住は明治四年十月の六〇四人で、彼らは前年に開拓使貫属(かんぞく)に編入され、石狩国札幌郡へ移住した。
この年、札幌本府の建設に伴うものである。
幌別移住の家臣団も貫属とされ、札幌への移住者と共に、最月寒川(もつきさむがわ)内に居を構え、一〇〇戸からなる白石村を設けたのである。
亘理伊達氏が北海道移住に最も熱心であった。
それは家老常盤(ときわ)新九郎(のちの田村顕允)が館主伊達邦成(くにしげ)にそれを進言したからである。
明治二年、分領地として、胆振国有珠(うす)郡が与えられ、翌年五月に室蘭郡の一部が、翌々年三月、虻田(あぶた)郡がそれぞれ加えられた。
開拓は紋別(もんべつ)を中心にして行われた。
明治三年までに、三五一戸が移住し、平均一町歩に近い土地が開墾された。
開拓史頭取のアメリカ人ホロン・ケプロンは、一八七四(明治七)年、地方視察を行ったが、この行中に紋別の開拓地を通過した時の印象として、この土地の人々は約二〇〇〇人で、耕作の方法はよく、作物もこの地方の気候条件に適し、その景況ははなはだよろしいと報じている。
一八八一年には、有珠郡への移住者は五七九戸となり、一戸平均三町弱もの開墾地を有するまでに至った。
その間、移民たちは物産の蕃殖(はんしょく)と販売を目的にした永年社(えいねんしゃ)を組織した。
この結社を中核にして、政府の保護を受けつつ、当地方の特産物として発展したのが麻苧(あさのお)の生産であり、甜菜(てんさい)の栽培による砂糖の生産である。
亘理伊達家臣団による開拓の成功の一つの理由は、このような自然的条件に恵まれていたからである。
移住を支えたもの
仙台藩諸氏の北海道への移住開拓は、土地や扶持(ふち)を取上げられた家臣団の生活を保障しなければならないという現実的な問題を解決する手段であった。
ただ、もう一つ重要なのは、亘理の田村顕允が主君邦成に移住開拓が国防のためであると建言し、邦成自ら烏合の民を募ったのではなく、譜代の家来が一致団結して移住するのであると強調したのは、脱刀帰農令に対する彼らなりの対応であって、武士身分の維持に固執していたのである。
明治四(一八七一)年三月、太政官は本藩に対し、邦成に帰農を説得すれば、政府が移住に扶持米を与えると伝えたが、彼はこれに応じなかった。
翌年九月、移民した亘理家臣団が民籍に編入された時、邦成が北海道へ移住したのは、刀剣を廃し民籍に入るのを恥じ、北門の警備にあたり、同時に開拓するのだと嘆いている。
以後も彼らは士族への復籍請願を繰り返し、一八七五年、政府より認められ、有珠の亘理伊達家ではただちに士族契約書を作成した。
このように武士たる誇りとその維持への執着が彼らの開拓精神の支えでもあった。
2 「南小泉村」と「わらじ村長」
top
真山青果
真山家は仙台藩大番組四〇石の藩士であった。
真山青果は一八七八(明治十一)年に仙台で生まれた。
父は寛。寛は教育者で、自由民権運動の進取社を興したことで有名である。
青果は寛の長男で、東二番丁小学校から東華(とうか)学校へ進み、同校廃校後、尋常中学校(のちの仙台一高)へ移った。 一八九七年、第二高等学校に合格し、同部改組後の医学専門学校に在籍したが、退学した。
その後地方の薬局生、代用教員などをへて、仙台河原町桑原医院の七郷村南小泉の代診医となった。 一九〇三年上京し新潮社に勤めた。と同時に小栗風葉門下となり、代作と共に小説家となった。
処女作『南小泉村』で、一躍脚光を浴び、自然主義作家として有名になった。
この小説『南小泉村』は、彼がこの地の代診医をしていたころの経験をもとにしたもので、明治末年の村の状況がなまなましく描写されている。
南小泉村に関する史料は皆無なので、明治末年の村の状況を真山の小説によってみることにする。 |

図65 真山青果
|
南小泉村
仙台の南北の隅から入って、愛宕山の裾を南東へ流れるのが広瀬川、埋木(うめき)と鮎(あゆ)で有名な川である。
その川下の誓願寺の渡場から東を指す枝川沿いに六郷村がある。
南小泉はまた枝分れの小川に沿った小村で、戸数は二〇〇戸ばかりである。
細長い家つづきの村で、大体は農家である。水車屋・駄菓子屋・提灯張が居るくらいで、ところてんさえ売る家がない。
ただ、石油・味噌・醤油・縫糸・煙草などの日用品は区長の家で取次ぎしている。
米は水車屋から買って食べるが、たいていは一升買をしている。
そのほかの買物などは、仙台の河原町で求めている。
この河原町は鉄道路線を西に踏切って行くと、一二、三町もない近くにあり、小学校の生徒の半分は仙台に、あとの半分は田を横切って東ヘー里ばかりの荒井という小村に行く。
そこに六郷村の役場も駐在所もある。大きな町にはそこから吐き出す芥川がある。
そして、近くの村々はその小川に沿っている。南小泉もその一つである。
百姓として独立の百姓ではなく、多くは都会のしたずみになって生活している。
その居まわりの旧畑が町から流れ出る湯のあか、染屋の紺汁・洗水・灰汁・塵埃(じんあい)に灌漑されているようなものだ。
田を耕作しているが、半分は菜園である。その日の生活費はそれでたてている。
それは主として女たちの役目で、束分(たばわ)けしておいた根もの・蔓ものを毎朝早く新河原町の青物屋に持ち込んで売る。
触商(ふれあきない)をするものは少ない。
棒手振(ぼてふ)を相手に一文、二文の儲けをさせているのだから、人気は自然に悪くなる。
妻女や娘でもみな人を喰った輩ばかりである。女だてらに負けじと罵り争う有様は見栄も外聞もない。
儲けの幾分かは各自が所持し、年寄りでも、子供でもただではいられない。茄子もぎとりとか、苗ひきとか、少ない賃銭を探して皆働く。
それがめいめいの小遣銭となる。だから、子供でも駄賃銭を貰わなければ、用を達してくれない。
小銭の有難味が骨の髄まで滲み込んでいる。
年寄どもは小銭袋を肌にしっかりと着けて、嫁子にも見せないで隠しておき、春秋の湯治や病気の時の薬代にする。
ときどき町から小間物売が廻ってきても、娘は娘、年寄は年寄で、ひそかに物隠に商人を呼び込んで、人にみられないように、そっと財布の紐を解く。
全く彼らの間に、銭の貴ばれるのが不思議なくらいだ。
親子の不和も、兄弟争いも大抵はその私得金から起る。
情誼や情愛といっても、銭だけは夫婦中でも滅多に油断なく、始終お互いの身銭を卑しく読んでいる。
農民の二重苦
この描写は真山の南小泉村での実体験をもとにしたもので、このような状況から彼はつぎのように述べる。
百姓ほどみじめなものはない。とりわけ奥羽の小百姓はそれがひどすぎる。
ぼろを着て、糧飯を食って、子供ばかりを生んでいる。
ちょうど、その壁土のように泥黒い、汚い、光もない生涯を送っている。
その顔立ちをみても、すぐに分かる。
家畜には家畜の匂いがあるように、百姓には百姓の紛れのない骨相がある。
賤しい顔立ちですぐ知れる。害虫を畏れ、自然の威圧におののかない日はない。
彼らの生涯は自然への降伏の生涯である。
一生を自然の前に跪ずくほかに、なお跪ずく地主がいる。
三人の主人に仕えている。
桝目を盗むとか、年の換納とかは常として、やれ雨だ風だ、浮塵(ふじん)だと、来る年も来る年も作柄に言い分をつけて、年貢をまけさせるのは、なかなか商人などの真似の及ぶところではない。
坪刈(つぼが)や毛見(けみ)をするといえば、その進路を用意して、経験のない地主の目を暗ます。
このような農民のあり方が、特に東北の農村では一般的であると真山はいうのである。
なお、南小泉村は一九二八(昭和三)年に一部が、一九四一年には、全域が仙台市の一地区となり、市民の住宅地となって、昔日の面影はない。
このような貧村の苦況を克服する努力をして、救済した人もいる。それが鎌田三之助である。
鎌田三之助
鎌田三之助は文久三(一八六三)年、寒村である志田郡の南端鹿島台村で茂庭氏の家臣の家に生まれた。
彼の祖父玄光、父三治ともに、品井沼の排水事業の生涯をささげた人である。
三之助は東京へ出て、はじめ軍人を志したが病気のため士官学校に入学できず、志を変えて政治家をめざし、明治法律学校(明治大学)に入学して法律を学んだ。
彼は福沢諭吉の「独立自尊」「自立自営」という言葉に啓発され、祖父の干拓と地方民の救助こそ自分の仕事だと考えるようになり、品井沼の干拓事業に心魂を打つことを決意し、帰郷する。
一八九四年、志田郡会議員、ついで宮城県会議員に立候補し、当選した。
彼は政治を志すというより、品井沼の干拓事業の完成に目標があった。
一九〇二年、旧自由党の流れをくむ立憲政友会衾が組織されたとき、彼はこれに入会した。
政友会が農村振興を一大綱領としていたからである。第七回の国会議員選挙の際、彼は立候補して当選し、同会議員となった。
翌年の総選挙でも当選した彼は桂内閣の軍備拡張、地租増徴に反対し、伊藤博文が妥協案を出したが、彼はこれにも反対し、同志とともに脱会し、河野広中、田口卯吉(うきち)などと共に同志研究会を組織した。
同年十二月十日、招集された第一九回議会で、鎌田は品井沼干拓事業はもとより、年ごとに疲弊してゆく全国の農村振興策について、その体験をもとに所論を陳述したが、議会は解散となった。
これにより、彼は、父祖の遺志を継ぎ、品井沼干拓事業の完成に全力を尽くすとを決意し、政界への野望を棄てた。
品井干拓事業
一九〇一年、高井沼の治水組合は改組して、水害予防組合が結成され、一九〇六年、品井沼の干拓の起工の段取りに入った。
工事費は五〇万円を要し、その借用にせまられ、鎌田は上京し、内務卿松方正義の仲介で日本勧業銀行から借用の許可を得た。
宮城県当局でも、重大な事業であったので、当時の県知事らも協力を惜しまなかった。
品井沼は志田・宮城・黒川の三郡にまたがり、鹿島台・大谷・粕川・大松沢・松島の五ヵ町村に囲まれていたので、これをまとめるのに鎌田は苦心した。
彼の努力がかない、品井沼の水をトンネル三条をもって松島湾に排水すれば組合地八〇〇余町から一三〇〇町の開墾地ができると予想した。
彼はまた、大陸移民合資会社を設立し、大陸移民により、貧民の救済に役立てようとした。
一九〇六年、彼は渡米しカリフォルニア移民を計画したが、排日感情が強いため、メキシコに目をつけ、メキシコ駐在公使の助力でメキシコ政府と交渉し、各地を調査してこの計画も、一応完了した。
ところが、品井沼干拓事業は、請負人と組合管理者との間で、干拓費用の増額をめぐって紛糾し、郡会も継続派と中止派に分かれ対立して、深刻な問題となっていた。
鎌田は東奔西走して中止派を説得し、辛くも工事続行となった。
村長としての三之助
一九〇九年、鎌田は村民の要望により鹿島台村村長となり、翌年の大水害があったが、これに屈せず、排水トンネルの完成にみるに至った。
当時の鹿島台村は県内第一の貧村であった。
さらに、木間塚・平渡・広長・深谷・大迫・船越の六ヵ村をあわせてできた新しい村であり、自治制により村政がしかれていたが、各有力者が反目し、地域間の対立にも根深いものがあったので、これを収拾するのは鎌田以外にはないというのが衆目の一致するところであった。
彼が当初めざしたのは、各地域にある学校の統合、神社の合祀、地域有財産の統一、負債整理である。
特に村の借金が一〇〇万以上になっているので、この借金を返済するためにはできるだけ倹約しなければならない。
また、村の田畑の七割は不在地主の土地である。それをどうしても返してもらわなければならない。
それにはやはり倹約が必要である。これ以来、彼は三十有余年、夏も冬もぶっ通して、破れれば繕い、汚れれば洗濯して、同じものを着用し、草鞋(わらじ)、脚絆(きゃはん)、腰に握飯(にぎりめし)姿で役場に出勤し、地域を順視する場合はもちろん、仙台や遠く東京へ出張する時も始終一貫してこれを通した。
そこから、「わらじ村長」といわれたのである。
鎌田家はこの地方では切っての豪農であったが三之助の時代には昔の面影はなくなっていた。
品井沼干拓などの公共事業に投資したりしたからである。
代議士時代、九〇〇石の小作米が入ったが、村長になってからは、貸しのある村民を集めて借用証文を返した。
また金にして九〇〇〇円、籾一〇〇石余、玄米五〇石があったが、これを村民に解放した。
一九一一年、多年の懸案であった品井沼も開墾されたので、これらの耕地を一々尋ね指導した。
当時鎌田家で自作していた土地は田が一町歩余、畑が一町五反余にすぎなくなっていた。
鎌田が村長就任時、七割余が不在地主のものであったが、農地改革時には、三割地主であり逆に七割が農民の土地となった。
これも鎌田の倹約を農民に奨励した結果である。
村の財政も、鎌田が村長就任時一〇〇万円あったが、日中戦争前には借金のすべても返済し、村長在任の晩年には、村全体の貯蓄が二〇〇万円にも達した。
一九三五年頃には、鹿島台村民個人の借金は一厘もなくなった。
こうして、村は健全性を取戻したのである。
以上の鎌田三之助の事跡の多くは同人の伝記に依拠した。
3 地域産業の試み top
蚕糸改良運動
宮城県の蚕糸業の奨励策は士族授産で始まる。
明治五(一八七二)年、仙台区百騎丁(ひゃっきちょう)に士族授産座繰(ざぐり)製糸場が設立され、営業を行ったが、ただちに廃業した。一八七六年、三陸商社が仙台市土樋に士族授産製糸器械場を設立したが、翌年に廃業した。
明治十年代、宮城県では養蚕製糸技術の改良をめざし、仙台区片平丁の勧業試験場と改称し、ここで蚕種・養蚕・製糸の技術伝習を行った。
この年、廃業した士族授産製糸場が再興され、仙台区北四番丁に共同製糸場が、北二番丁支倉(はせくら)通に共同揚返場が設立された。
翌年には士族授産場が設立されたが、いずれも失敗した。これが蚕糸改良運動の第一期である。
改良運動の第二期も士族授産からはじまり、士族興産組合が、一八八三年、無産士族を奨励し、三居沢などに桑園を設けた。
仙台外の郡部では、県北地方で改良運動がさかんになるが、県南地方でそれほど積極的でない。
第三期の改良運動は県の「蚕糸組合設置規定」の布達ではじまり、これが改定されて、蚕糸改良組合では、県北で直営の器機製糸場を建設し、製糸を集中して、一般組合員は養蚕だけに専念することになる。
県南地方では組合製糸を志向せず、小生産の生糸を共同揚返しするだけで、小生産の分解はあまり、進んではいない。
明治二十年代の蚕糸業
明治十年代の蚕糸改良運動で、宮城県の蚕糸生産高が増加する。
県南では、繭が伊具・刈田両郡で宮城県で上位を占め、特に伊具郡の生糸生産高は県内の第一位を占めている。
県の生糸生産高は一八八七(明治二十)年から急増するが、これは小生産者の家内工業より進んだ製糸工場があらわれたからである。
製糸工場は県北に多く、県南では一つである。
因みに、士族授産を目的とした製糸場として一八八七年に設立された仙台北二番丁の製糸伝習所が、一八八九年に士族興産製糸会となったが、一八九一年に廃業に追いこまれ、士族授産の製糸業が幕を閉じた。
県南唯一の製糸工場は、佐野理八が一八八五年、当時の伊具郡丸森村の東部金山本郷に設立した。
丸森は奥羽街道白石の南槻木(つきのき)から中村街道を通り、角田を南に下ったところにある。
この地方は阿武隈川沿いの道で福島の蚕糸業地帯信達(しんだつ)地方と結びついていたので、そこの商人資本の支配下で、蚕糸業が発達していた。
佐野は近江国神崎郡佐野村出身で、政商小野組のもとで、製糸事業を担当し、一八七四年、小野組が倒産した際、古川市兵衛と共に、東北地方の資産整理にあたった。
彼は福島の二本松製糸場の社長として生糸の生産を行っていたが、それを他人に譲り、蚕糸業のさかんな丸森に目をつけたものの、ゆえあって金山本郷に佐野製糸工場を設立したのである。
佐野製糸場は資本金三万八〇〇〇円、フランス製ケンネル式鉄製釜を備え、釜数一二〇を持つ北栄(ほくえい)館として出発した。
明治二十年代を通じ県内最大の器機製糸工場で、一八九三年には伊具郡の生糸生産高の二〇%を占め、アメリカに事務所を持つ佐野理八組を介して直輸出を行っていた。
この工場は明治後半から大正初年まで、順調に生産を行っている。
明治二十年代の県の養蚕・製糸戸数も増加し、特に伊具郡は佐野製糸場の発展もあり、繭と生糸の生産で県内第一位の地位を占めている。
ただ、座繰(ざぐり)製糸が器機(きき)製糸の生産をうわまわっている。
明治三十年代以降の蚕糸業
宮城県で器機製糸が座繰製糸を凌駕(りょうが)するのは一九〇二(明治三十五)年である。
この頃から、養蚕業と製糸業の分離が顕著になるが、県南地方では、座繰製糸を行う小生産者がそれほど減少していない。 このような状況下で一八九九年、白石に二〇〇釜を持つ刈田郡立模範製糸工場(白石製糸機業株式会社)が設立された。
最大の株主は米竹和藤治で、米竹組(山崎屋)と称し、幕末以来の豪商であり、維新後寄生地主になった。
明治二十年代、生糸商として活躍し、横浜に進出して、片倉製糸と競うほどの実力を持っていた。
この製糸工場の設立で、一九〇六年、刈田郡の生糸生産高が県内随一となった。
丸森の近村で西は福島県、北は白石に接する耕野村に、一九〇八年、耕野製糸場が設立された。
「女工」は白石製糸場で技術を習得したが、欠勤者も多く、技術も未熟な「女工」が多かった。
同工場では佐野製糸工場の残繭の賃繰などをし、また、「女工」を招いて技術の向上に努めたが、技術のすぐれた「女工」が集まらず、一九一三年に廃業した。
一九〇五年、巨大製糸資本片倉組が仙台に進出、片倉製糸工場を設立した。片倉組は県内各地特約養蚕組合をつくり、繭確保に努めた。
一九一一年、仙台が県内第一の生糸生産地となり、これにより白石製糸場などは片倉製糸に吸収されている。
土地集積と地主制の確立
明治初年の宮城県の小作地率は、一八七三(明治六)年で、一二・三%と推定される。
その後のインフレとデフレで、耕地の喪失と集積が激しくなり、一八八三年に二三・二%、一八八八年には、三〇%を越えている。
この間の小作地は一万四〇〇〇町歩も増加し、全耕地の一〇%以上が移動した。
幕末に質屋、木綿商で産をなし、明治初年には生糸の仲買(なかがい)として活躍、のちに白石商業銀行などの社長となった渡辺佐吉家の土地集積は以下の通りである。
明治初年の渡辺家は持地だけだった。
一八七三(明治六)年、一反七畝の土地を一七円で買い、一八七五年あたりまでに、二三反ばかり買入れた。
この年の七月に仁大町の某(なにがし)の持地一町七反の青田を四五〇円で購入した。収穫は籾で八七俵だった。
一八七九年までの間に、某に田地二三反、畑五反を抵当に貸金していたが、戻証文をやって、一二〇〇円で買切りにした。
この年の地価金は三八〇〇円で、小作米は一二四石となった。
一八七九年から八一年までの田畑を抵当にした貸金高は七五〇〇円であった。
八一年以降のデフレ期に、その流地で土地を自分のものにした。
一八八四年に、正金を足して元利を含め二七〇〇円の貸金があり、利子として七二石の米をとった。
流地が増加し、一八八九(明治二十二)年の地価金が一万二二〇〇円となり、この年、大地主会が県庁ではじまり、佐吉も常時これに出席したという。
一八八七年の宮城県の小作地率をみると、県北の単作地帯では三〇%を越えているが、県南の諸郡では三〇%未満である。
それ以降、土地の移動が進み、一八九七年の県南の諸郡でも小作地率がほぼ四〇%を越え、県北地帯と肩を並べるようになる。
一九〇二年と○五年の凶作で、土地の集中がさらに進み、蚕糸業地帯伊具郡では、一九一〇年の小作地率が五〇%を越した。
こうして、明治四〇年前後に宮城県の地主制は確立した。
一九二五(大正十四)年の一〇町以上の土地所有者をみると、五〇町未満の土地所有者が県南諸郡で九〇%を越え、県北にくらべてはるかに多い。
一〇〇町以上の地主については、県北の五郡の五五人に対し、県南では九人にすぎない。
仙台を含めた県南では一〇町から五〇町までの中小地主が多いのである。
そこで、その経営状況を高橋栄一郎家を例にとってみることにする。
小地主の経営
高橋家は白石の郊外旧大平(おおだいら)村森合の幕之内(まくのうち)家と呼ばれ、旧藩時代は片倉家の家中で、維新以降に帰農、一〇数町を持つ、この地方に多い地主兼自作である。
第一二代栄一郎は宮城師範学校尋常師範科を卒業、小学校長二校を勤め、刈田郡視学(しがく)となり、一九〇七年、退職して農業を営み、村の信用組合長となり、のちに村長となった。
一九〇八(明治四十一)年のこの家の「家政日記」によって、この年の経営状況をみると以下の通りである。
この家での農業経営は常時、年季奉公人数人をおき、家族人は労働に従事していない。
まず、一月一日、三人の「百姓」から小作米を受取っている。
同十三日、玄米四斗入三一俵を白石町新田で売却した。
また、四月八日、玄米二二俵、豆七斗を、白石町上西勇作へ売っている。
その前日、栄一郎は桑苗木買入のため白石町に行く。
同十二日、桑畑の仕事のため「雇人」を使用している。
同二十三日には、蚕種購入のため、某氏を訪問した。
同二十四日より、田植の準備が始まる。
五月に入ると蚕室の仕事となる。
五月一日、栄一郎は蚕種受取に福島の伏黒に出張した。
五月中旬、豆播として、「日雇」を使用。
五月後半、「蚕女」として四人を雇う。
六月初旬、桑葉を購入、さらに、桑畑などを買い、「桑摘人夫」数人を雇う。
六月十二日から十八日にかけて、余分の桑葉を白石などで売却している。
十七日、麦畑の刈方をする。
同月三十一日から田植の準備が本格的に行われ、同時に田植の「人夫雇」を依頼し、二十三・二十四・二十五日に田植を行った。
すべて「手伝」か「雇人」によっている。三十日には、「糸取女」二人を雇う。
また、二人の女に糸の賃引を行わせている。
この家では糸取釜六釜を持っており、すべて「工女」を雇って、糸を取らせているし、さらに賃引に出してもいるのである。
八月になると、秋蚕の掃立に追われる。
十一月になり、稲刈を行っているが、これにも「日雇」を使用している。
十二月十二日には、生糸を仲買人と思われるものに売却している。
十二月の暮には八人の小作人から、小作料を受けとっている。
このように栄一郎の家では、米・麦・豆・生糸の生産を行っているが、家族の者はいっさい労働をせず、すべて「常雇」か、あるいは「日雇」を使用している。
そして、大部分の土地は小作に出しているのである。 |
以上が一〇数町の自作兼地主の一年間の仕事の有様である。
六 草の根からの近代 top
1 職業人、表現者、運動家としての女性の登場
「産婆」の先がけ、山崎富子
近代は、女性たちにとって、新たな生き方を探り歩みはじめる時代となった。
「家」や地域のしがらみに呻吟(しんぎん=うめく)しながらも、時代の追風を受けて、どん欲に自らの生を切開いていった女性たちがいる。
陸前の風土に刻まれた女性たちの人生の軌跡をたどってみることにしよう。
一八八二(明治十五)年五月、牡鹿郡石巻村字墨廼江(すみのえ、石巻市住吉町)に、産科および眼科専門の医院「愛育舎」が開業した。
五月二十日付の『陸羽日々新聞』は、開業早々「診察を乞ふ者緒の如し」という愛育舎の繁盛ぶりを伝えている。
医師は山崎富子。宮城県内のみならず、東北地方において女医、そして「産婆」(さんば)としてパイオニア的な存在の女性である。 |

図66 山崎富子 |

図67 産婆免許状 |
富子は幕末の嘉永三(一八五〇)年、遠田郡小松村(田尻町)に医師大友慎庵(しんあん、のちに山下と改姓)の娘として生まれた。
父の没後、母の再婚により、継父の庄内藩の医師山崎信哉のもとで少女期を過ごし、一七歳になった慶応三(一八六七)年、縁あって石巻の湊村の一皇子(いちおうじ)宮の神官、日野志学(しがく)に嫁いだ。
神職の夫の仕事を支える一方、自宅で読書・算術・琴を教える私塾を開いていたが、富子の向学心はこれだけにおさまらなかった。
医者の家に生まれ育ち、兄の英順も上京して西洋医学を学んだのち、石巻村で山崎病院を開業しており、その兄から眼科の知識を学び、叔父の沼倉真庵から香川流の産論を学ぶうちに、富子自身が上京して本格的に医学を学びたいという気持ちを抱くようになる(『石巻の歴史』第2巻通史編(下の2))。
一八八〇年二月、石巻を発った富子は、東京の戸塚文海の塾で眼科を修め、さらに東京府病院内の産婆教授所に入学して産科学を修得した。
「産婆」の仕事は江戸時代まで、地域の中で出産介助の経験を積んだ、いわゆる「取上げ婆(ばば)」と呼ばれる年配の女性たちによって担われていたが、維新後の一八七四年八月、文部省の医制五七条が布達され、自由な営業に規制が加えられて国家免許を必要とする職業となった。
一八八一年には「産婆営業規則」が制定され、近代的な医学教育を受けて試験に合格した者だけが、「産婆」として登録されることになった。
富子が上京した時期は、まさに近代国家による産婆教育がスタートした時期にあたっている。
一八八一年六月、東京府病院を卒業した富子は、同年十一月内務省の第七九号産婆免許を取得、東北の女性としていち早く「産婆」の資格を手に入れることになる。
翌八二年三月、「眼科産科専門女医」として郷里に戻った富子は、他界していた兄の病院を引継いで、前述のように愛育舎を開業した。
特に力を注いだのは「産婆」の仕事であり、一八八九年には産前産後の心得などを記した「婦人心得草」を年賀に配っている。
出産の場は自宅であった時代に、富子は一八九一年、妊婦を入院出産させるための施設として、県内でいち早く愛育病院を開いている。
富子の功績は医者や「産婆」としての働きばかりではない。私財を投じて「産婆」の養成に努めたことこそ高く評価してよいだろう。
一八八五年一月、愛育舎の中に私立産婆講習所を設立し、自ら講師を務め、二年半後に最初の卒業生、鈴木清子、鈴木文子(ともに登米(とよま)村出身)、日野歌子(石巻村出身)の三名を送り出した。
三人はともに、内務省の産婆営業免許を取得して郷里にもどり、「産婆」として活躍することになる。
「産婆」を養成する講習所の設立は、宮城県下では一八八七年以降進んでいくが、富子による私立産婆講習所の開設は、そのさきがけをなしている。
一八八九年八月には「牡鹿郡産婆組合」を結成し、総代に就任した。「産婆」の組合組織として、全国的にみても早い設立である。
富子には大きな目標があった。郡内に一〇〇戸に一戸の割合で「産婆」を配置し、助産の古い習俗を一掃すること、そして「産婆」を医者の信用が得られる地位に高めたいという思いがあった(『奥羽日日新聞』一八九三年十一月十日)。
だがその志半ばにして、一九〇〇年九月六日、五〇歳の生涯を終えている。
明治末期から昭和初期にかけて、日本の家族はかってない多子化の時代を迎え、大家族を形成していく。
宮城県もこの時期、出生児数の増加と医療技術の進歩により、多産多死から多産少死の時代へと移行し、大家族の形成が進んだ。
山崎富子に続いた「産婆」たちの地域での奮闘が、そうした時代を根底から支えていたのである。
裁縫(さいほう)教育の推進者、
長谷理和(はせりわ)
宮城県の近代初頭の女子教育において、私塾での裁縫教育は、ミッションスクールのキリスト教主義教育と並び大きな位置を占めている。
前時代から婦徳の領域のひとつとされてきた裁縫は、近代に入り、女性がもつべき生活能力のひとつとされて、技能の鍛錬に関心が向かった。
実際、女性たちは裁縫の技術によって、家計補助の一役を担い、自立して生きる手段を獲得してもいる。
裁縫教育の普及・推進には多くの女性たちの努力と活躍があったが、その先駆者といえるのが、長谷理和である(中山栄子『宮城の女性』)。
理和は江戸時代後期の天保九(一八三八)年、仙台藩医志賀理節の娘として城下の大町三丁目に生まれている。
二二歳で藩士の長谷昌直に嫁いだが、一〇年後に夫が他界し、さらに維新後、家禄の返上により一家の生活が寡婦(かふ)の理和ひとりの肩にかかった。
そこで理和は、幼いころから母に習い、師匠にもついて修得していた裁縫の道で生きることを決め、明治三(一八七〇)年、仙台北一番丁に和裁を教える長谷塾を開業する(私立長谷柳絮学校編『私立長谷柳絮(りゅうじょ)学校百年小史』)。
一八八七(明治二十)年十一月、長谷塾は私立学校設立の認可を得て長谷柳絮学校と改称され、女子のための専門学校として新たなスタートを切った。
裁縫の指導を中心に、礼法や茶道・華道など、家庭を築く女子のために総合的な教養を授ける一方、文学博士大槻文彦や第二高等学校校長の三好愛吉ら、名士を招聘して修養講話の時間も設けられた。
なかでも長谷柳絮学校の名声を高めたのは、理和みずからが考案した長谷流の裁縫術であった。
生地を痛めないように、ヘラを使用せずに糸印をつけて作業するのが、長谷流の特徴のひとつである。
着物の急所である褄(つま)上げの仕上げの見事さも、高い評価を得ていた。
そうした和裁の技能を徹底して伝授することで、東北一の裁縫学校として評判を呼び、県内はもとより北は北海道、南は九州・四国からも入学者を集めた。
明治三十年代には三〇〇人を越える女子を抱える大規模な裁縫学校に発展している。
裁縫教育の指導者として、男性ではあるが、朴沢(ほうざわ)三代治にも触れておきたい。
一八七九(明治十二)年、仙台本荒町に裁縫塾の松操私塾(現在の朴沢学園明成高等学校)を開業し、一時期、師範学校で小学校の裁縫教員の育成にもあたっている。
裁縫教育における三代治の最大の功績は、従来までの個別指導による技術の伝達とは異なる模型を使った一斉教授の方法を考案したことにある。
集団を対象に基礎から応用へと系統的に学ばせる方法は、いわば裁縫教育に近代化をもたらすものとなった。
三代治が一八八〇年に考案した「裁縫教授用掛図」は、一八八二年仙台の出版業者から出版されて全国に出回った。一八八四年には同じく仙台の出版社から三代治編集の『小学中等科裁縫教授書』が刊行され、一八八六年文部省の師範学校用教科書の指定を受けて、裁縫用教科書として全国に普及していく。
松操私塾は一八八四年、私立学校設立の認可を得て松操学校と改称された。
「小物習はば朴沢に、長物習はば長谷につけ」と並び称されたように、松操学校と長谷柳絮学校は、裁縫学校の双璧として、ともに確かな技術を備えた卒業生を多数送り出した。
栗原郡若柳町で夫寿仙と共に裁縫塾の含翠私塾を開いた熊谷霜代、志田郡大柿村で一八八七(明治二〇)年裁縫私塾琢玉舎を開いた士族の妻、氏家徳代(うじえとくよ)などは、松操私塾の出身である。
新宿「中村屋」の女主人、相馬黒光(そうまこっこう)
東京新宿にパン屋「中村屋」を創業し、「中村屋サロン」と呼ばれた文化人・芸術家の後援活動でも知られた相馬黒光は、一八七六(明治九)年、仙台市木町末無(きまちつえなし、立町)の星家に生まれ、本名を良という。
地元仙台の宮城女学校、横浜のフェリス女学校、東京の明治女学校と三つの女学校に学んだのち、信州出身の相馬愛蔵(あいぞう)と結婚、一時は先の郷里信州穂高(ひたか)で暮らしていたが、夫婦で上京してパン屋「中村屋」を開業し、商売の成功を収めた。
ロシアの詩人エロシェンコやインドの独立運動家ラス・ビハリ・ボースの亡命を助けたことでも知られ、『黙移』(もくい)『広瀬川の畔』『穂高高原』の自伝三部作のほか、『明治初期の三女性』『アジアのめざめ』などの著作がある(『相馬愛蔵・黒光著作集』全五巻)。
明治生まれの地方出身女性として栄光の人生をたどったといってよい黒光であるが、不運な境遇に忍従することなく、自分の意志で生きることを求めていた仙台での少女時代がある。 |

図68 相馬黒光
|
生家の星家は仙台藩の評定奉行(ひょうじょうぶぎょう)も勤めた有数の武家であった。
だが維新後、没落の一途をたどる。
家の貧しさに加え、父や兄弟を次々に病魔が襲うという家族の不幸が重なり、六番目の子供であった黒光は、片平丁尋常小学校を卒業後、希望した高等小学校への進学をあきらめざるをえなかった。
三番目の兄圭三郎も小学校を卒業後、学業を断念して宮城県庁の給仕として働いており、女の子は一日も早く実生活に役立つ方向を選ばせたいとする母の意向により、裁縫学校に通うことになる。
だが、向学心旺盛な少女は母を説得して裁縫学校を中退し、東二番丁高等小学校に入学、その後宮城女学校(現在の宮城学院)への進学を果たした。
その宮城女学校を、上級生が起したいわゆる「ストライキ事件」に連座して一年足らずで退学、在学中に『女学雑誌』に出会ったことなどから、東京への遊学の思い募らせ、横浜のフェリス女学校をへて、かねてから憧れの明治女学校への転学を遂げた。
黒光は、家の窮乏や家族の不幸、さらに女であることによって、みずからの夢や志を思いとどめることはなかった。
これには叔母の豊寿(とよじゅ)の生き方が影響していたものと考えられる。
星家の二女に生まれた母の已之治(みよじ)は、姉の死亡により家の跡取りとなり、姉の婿養子であった喜四郎と結婚、不在がちの喜四郎に代わり、家を守り家族を支える生涯を強いられた。
一方、母の妹の豊寿は、星家に経済的な余裕があった時代に横浜のフェリス女学校の前身に学び、やがて妻子のあった医師佐々城本支と恋に落ち、恋愛を成就させた。
結婚後は矢島楫子(かじこ)と共に東京矯風会(きょうふうかい)の創立にかかわり、会の最初の書記を務め、禁酒・廃娼・男女同権を唱える社会改良運動に加わることになる。
植木枝盛(えもり)、徳富蘇峰(そほう)をはじめ、多くの政治家と交流をもち、さらに法律や政治外交問題を研究する婦人白標倶楽部を組織して活躍していた。
いわば新時代のインテリ女性の最先端を行く生き方を、叔母の豊寿が切り拓いてみせていたのである。
後年、フェリス女学校に進学し冬休みに一時帰郷したときのことを、「いつまでもこの廃屋に執着していては、家中残らず自滅するばかり、私一人でも早くこの没落のどん底から起き上らねばと、むしろ潔く故郷を後にして、まっすぐ横浜に戻りました」(『広瀬川の畔』)、「故郷は暗い。故郷は滅びていく、思いを東北に馳せることすら苦痛であった」(同)と回想している。
みずからを生きたいとする強い自我の芽生えた少女時代の黒光にとって、貧しく不幸が重なるばかりの家と故郷は、捨て去るべきものとして覚悟を迫っていたのである。
歌壇で活躍した原阿佐緒(あさお)と阿部静枝
近代は女性が自己を表現する自由を獲得した時代でもあった。
九条武子・柳原白蓮(びゃくれん)と共に中央文壇に三女流と並び称され、与謝野晶子に「才走った詩人、官能の鋭敏な詩人」と称賛された歌人、原(はら)阿佐緒は、一八八八(明治二十一)年黒川郡宮床村(大和町)に生まれている。
裕福な地主の家の一人娘は、クリスチャンで音楽愛好家の父幸松と、絵画を趣味にもつ母しげのもとで、幼少のころから日本画や習字、漢学の英才教育をほどこされて育った。
一九〇一年、開学四年目の仙台市立高等女学校(のちの県立高女、現在、宮城第一女子高等学校)に進学、病弱で孤独の中にあって、漢詩づくりに打込み、当時の第一人者、綿貫香雲から「女流の漢詩人出ず」と称されるまでに才能を開花させた。 |

図70 阿佐緒の生家
|
だが、肋膜炎のために女学校を三年で退学、郷里に戻り療養したのち、母の勧めで上京し、日本女子美術学校の日本画科に入学する。
英語教師の小原要逸との恋愛で子供が産まれたが、小原にはすでに妻子があり、離別を決めるしかなかった。
この最初の恋愛のつまずきが、阿佐緒を短歌に傾倒させる契機となる。
この涙つひにわが身を沈むべき海とならむを思ひぬはじめ
一九〇九年四月、『女子文壇』に投稿した右の一首が与謝野晶子の目にとまり、中央文壇でのデビューに結びついた。
同年「新詩社」に入会、一九一三(大正二)年には『青鞜』(せいとう)に歌を発表し、「アララギ」にも入会して斉藤茂吉や島木赤彦らの指導のもとに作品を発表していく。
中央歌壇で評価を獲得した阿佐緒は、宮城県の歌壇にも大きな影響を与えている。
一九一二年仙台の早坂掬紫が中心となり同人誌『シャルル』が創刊されると、若山牧水や斉藤茂吉らと共に賛助会員として名を連ねている。
一九二〇年にはアララギ派の歌人で物理学者の石原純が、仙台で文芸誌『玄上』を創刊、阿佐緒は同人二〇人の中でも石原と並ぶ中心的な存在となり、二人のもとには創作意欲に燃える若者が集まった。 |

図69 原 阿佐緒
|
この間、『河北新報』の「河北文壇」短歌欄には、宮床村在住の女性たちの投稿が目立っている。
阿佐緒の影響で郡部の村にも歌を詠む女性たちが育ち始めていた(宮城県・みやぎの女性史研究会編『みや子の女性史』)。
私生活では二七歳になった一九一四年、画家の庄司(しょうじ)勇と結婚し、次男が生まれたが五年後に破綻(はたん)、『玄上』の創刊をへて石原純と恋愛問題が生じた。
やがて阿佐緒の方から終止符を打つが、世間は「多くの異性を弄んだ妖婦」「毒婦」と阿佐緒ばかりを一方的に非難攻撃し、指導者の島木赤彦からも破門された。
そうした生活を背景に歌われた歌集『白木槿(しろむくげ)』『死をみつめて』『うす雲』は、郷里に暮らす老いた母と、母の手にゆだねた息子、そして宮床の愛しい自然に寄せる想いが写実的に歌い上げられている。
晩年は経済的に不遇の日々を過ごし、一九三四(昭和九)年、室戸(むろと)台風で書きためた歌稿の大半を失ってからは、創作意欲を失い、八二歳で亡くなるまでほとんど作品を発表していない。
不幸な結婚と恋愛、自己を押し通して生きることがままならないがゆえの苦悩と悲しみが、阿佐緒に女としての自我を自覚させ、短歌の表現に結実させたといえよう。
一方、阿佐緒の歌の風景を大きく占めていたのは、郷里の宮床村であった。
父のない子供を抱えて帰ったふるさとは、冷たい視線を浴びせて阿佐緒を深い孤独に追いやった。
老いた母に、家も田も売り払って東京に移ろうといい、嘆かせた日々もあったが、帰郷するたびに宮床村の豊かな自然に抱かれて、都会で傷ついた魂を癒されていた。
そして心底から、歌心を呼び起こされている。
原阿佐緒の生誕より十一年遅れて、一八九九(明治三十二)年、登米郡石森村(中田町)に阿部静枝が生まれている(『阿部静枝歌集』)。
眉凍る北辺に生まれ育ちたり冬を生き抜く草ともわれを
一九五〇(昭和二十五)年に出版された第二歌集『霜の道』に収められた右の一首に代表されるように、静枝の作風には意志的で理知的な響きがある。
結婚後、夫の影響で社会運動に身を投じた後の作品には、そうした生き方や思想が色濃く投影されている。
生家の二木家は、裕福な地主の家であった。五人兄弟の長女に生まれ育った静枝は、宮城県立高等女学校に進学し、東京女子高等師範学校(現在のお茶の水女子大学)に進む。この時代に短歌との出会いがあった。
卒業後、仙台の東華高等女学校(現在の宮城二女高)で教壇に立つ傍ら『玄土』に参加、石原純の指導を受けて腕を上げていく。
阿佐緒とは、ここでいっときの邂逅(かいごう=めぐり合い)を果たしている。
だが『玄土』は解散し、失恋の痛手も負った静枝は、職を辞して上京し、社会派の弁護士、阿部温知と結婚、それからの人生の歩みは原阿佐緒と対照的である。
社会民衆党の婦人部である社会民衆婦人同盟の役員となり、党の分裂により社会大衆党が誕生すると、一九四〇年の解散まで、党の婦人同盟の書記長・機関誌部長を務めた。
一九三八年に夫と死別した後も、社会活動は多忙をきわめ、戦後は社会党の所属で一九五一年から三期、豊島区議を務めている。
作家としての活動は社会運動へ傾倒した後もつづけられた。
自宅で短歌雑誌『ポトナム』の発行を引受け、短歌関係者と交流を深める一方、一九二六年、二八歳の時に、最初の歌集『秋草』を出版する。
その後労働総同盟の教育部講師を務め、新聞や雑誌に短歌をはじめ評論や随筆を発表し続けた。
戦後一九四八年から再び『ポトナム』で作歌活動を開始、翌四九年には女人短歌会を発足させて全国に支部をつくり、東北支部主催の短歌会にもしばしば講師として訪れている(『みやぎの女性史』)。
歌集に『冬季』『野道』など、評論随筆集として『女性教育』『愛と孤独』『寡婦哀楽』(かふあいらく)などがある。
労働運動家の生涯を貫いた山内(やまのうち)みな
近代の産業、なかでも繊維産業を根底から支えていたのは、東北出身の「女工」たちであった。
明治三十年代後半から四十年代にかけて、大凶作を背景に、貧しい小作農の娘たちが、前借金と引替えに関東方面の製糸・紡績工場に送り出されていった。
一日一二時間以上にもおよぶ工場労働と、監獄同様の寄宿舎生活に耐えきれずに保護を求めて逃げ帰ってきた少女たちの記事が、当時の地元新聞に散見される。
過酷な労働は少女たちの身体を蝕(むしば)み、ときに命をも奪っていた。
一九一〇(明治四三)年一月十八日付『河北新報』によると、一九〇八・〇九年の二年間に、宮城県から二〇〇〇人以上の女性たちが「女工」として県外に出ており、その一割にあたる二〇〇人以上が病気のために帰郷したことを伝えている。
一九〇〇年本吉郡歌津村字樋の口(歌津町)に生まれた山内みなは、一二歳で東京モスリン吾嬬工場の「女工」となった。
翌年工場のストライキに参加して以来、労働運動に身を投じていくことになるが、みなの生涯はそのまま近代日本の女性労働運動の歴史と重ね合わせることができる。
郷里の樋の口は、宮城県最北部の水平洋岸、伊里前(いさとまえ)湾から一〇キロほど内陸の山間部にある、戸数一〇戸ほどの小さな集落であった。
裕福な本家の娘たちは仙台の女学校へ進学していたが、分家のみなの家では尋常小学校に通うのが精一杯で、それも農家の娘が教育を受ければ家をつぶすと言い張る祖母を、母が無言で抵抗して卒業させてくれた(山内みな『山内みな自伝』)。
卒業後、離婚して実家に戻っていた叔母から上京して「女工」になることを誘われたが、父も母も、肺病になって帰り結婚できなくなることを心配して反対に回った。
「女工」になれば無事な体で帰ってこれなくなることが、当時はみなが住む本吉郡の山村にまで知れ渡っていたのである。
だが村に回ってきた募集人との間に前借金一〇円で三年三ヵ月働く契約が結ばれ、みなは「女工」として上京する。
入社後九ヵ月が過ぎた一九一四年六月、工場でストライキが起きた。
みなは全く状況を知らずにいたが、これを機に争議を支援した全国的な労働者組織、友愛会に入会し、二年後の一九一六年には友愛会婦人部の結成に参加、一九一九年一月二十六日の友愛会日本橋支部発会式で、婦入部を代表して演壇にのぼった。
「紡績女工」は一人前の労働者であるのに社会が同じ人間として扱わない、女労働者の団結こそ必要だという訴えを、『万(よろず)朝報』はじめ翌日の新聞は、日本最初の「女工の演説」として大きく取上げた。
演説は大きな反響を呼び、市川房枝(いちかわふさえ)・平塚らいてう・奥むめおら、名だたる女性運動家たちが、みなに会いに工場を訪ねている。
地元の『河北新報』も四目後の一月三十日、「壇上に気焔を吐く婦人労働代表者」という見出しで、写真入りで大きく掲載している。
同年七月二十一日には、工場内の「女工」三五〇余名を団結させ社長に男女臨時工の食堂の建設を要求したことなどが、「覚醒した女工 仙台出身の山内みな 社長を驚かす」と題して報じられている。
みなの奮闘ぶりはジャーナズムを賑わせ、活躍が郷里にも伝えられた。
同年八月、友愛会初の女性理事に選ばれたが、十一月に会社はみなを解雇した。
知己となっていた市川房技を頼り、市川らが婦人参政権運動の核として創立した新婦人協会の事務を手伝い、その後山川均・菊江夫妻の指導を受けながら、総同盟や婦人同盟の活動に加わる。
自立して生きるための道を探りながら、労働者の権利を求める運動を支え、さらに社会運動へと活動の場を広げていった。
十五年戦争末期の一九四五年八月、家族四人で暮らしていた大阪で空襲に遭い、郷里の歌津村に疎開して敗戦を迎える。
翌一九四六年四月、戦後初の衆議院議員総選挙で女性に初めて参政権が認められると、みなは宮城県から共産党で立候補した。
市川房枝が応援にかけつけ、党候補の中では最高の得票を集めたが、結果は落選であった。
この時期、働く女性が結束する組織づくりにも奔走し、宮城県婦人団体協議会を発足させるなど、宮城の働く女性たちの組織づくりにも大きく貢献している。
一九九〇年、八九歳で他界するまで、運動家としての生活を支えていたのは、戦時中に大阪で身につけた洋裁の技術であった。
2 「米騒動と社会運動 top
米騒動の勃発
一九一四(大正三)年の第一次世界大戦の開戦は、日本の経済を大きく揺るがし社会の構造矛盾を表出させた。
大戦景気で物価の騰貴(とうき)が進み、逆にインフレによって実質賃金が低下して、庶民の生活は困窮の度を増していった。
さらに一九一八年七月、ロシア革命に対抗して日本軍のシベリア出兵の方針が明らかになると、地主や大商人による投機的な米の買占め、売惜しみなどにより、たちまち米価が暴騰した。
同月、富山県魚津(うおづ)町の「女一揆」に端を発した米騒動は、またたくまに全国に波及し、有数の米作県であり前年は豊作であった宮城県にもその影響がおよぶことになる。
仙台市では白米一升の小売価格が二年前の一九一六(大正五)年頃は一六銭であったのが、この年七月には二七銭、八月十日には四二銭に上昇し、一日分の米さえ買うことができなくなくなった市民の間に不安が募った。
八月十三日と十四日、市内各所に十五日の集会場所を知らせるビラが貼出されると、十五日夕刻には西公園をはじめ青葉神社・停車場広場・宮城野原・伊勢堂山に群衆が集まり、このうち西公園に集まった群衆は、名掛丁(なかけちょう)方面に向かって行動を開始、大町・名掛丁・二日町・鉄砲町・八幡町などの米穀商人・酒造業者・高利貸など三七軒を襲撃し、一升二五銭での廉売(れんばい)や救済資金を強要した。
翌十六目、仙台警察署は禁足令を発したが、夕方には再び市内各所に市民が集り、解散命令を聞かずに米屋など三八軒を襲撃した。
前日に米の廉売を承諾しながら、売切れなどと称して相変わらず売惜しみが続いていたからである。
知事の指令で第二師団が出動し、十七日午前三時頃、騒動はようやく鎮静化した(中川正人「米騒動と民衆運動の展開」渡辺信夫編『宮城の研究』六)。
一夜明け九十七日は市内の要所が警察と軍隊によって警備され、さらに地域の消防組織や在郷軍人会なども動員されて、ものものしい警戒態勢が二十四日まで続いた。
仙台の米騒動は牡鹿郡石巻町、遠田郡涌谷町、登米郡柳津町、柴田郡大河原町などにも波及したが、一方、白石町や角田町などでは、地主や資産家側か機先を制したり危険を察知して、事前に米の廉売を行うことで騒動の発生を未然に防ぐことに成功している。
九月以降、県下の市町村は窮民対策を急務の施策としてゆき、天皇の下賜金や県費によって安い外米を買上げ、廉売を開始したほか(『大河原町史』)、大河原町・丸森町・白石町などでは地元の篤志家による寄付も行われて窮民対策が講じられている。
一九一八(大正七)年八月二十三日付『河北新報』が、「近時米騒動の如き、或る意味において明らかに国民思想の変動を物語るものである」と報じているように、一九一八年の仙台の米騒動は、県民の心に深く根づいてその後の社会の動向に大きな影響を与えることになる。
米騒動の参加者は、二千数百人とも、一万人とも伝えられている。
検挙者一二一人のうち六七人が起訴され、全員が有罪となったが、このうち四九人が控訴し、三六人が大審院まで上告して争った。
家内工業の職人や、町工場の「職工」「車夫」(しゃふ)「日雇」(ひやとい)、小売商人など、零細な労働者・商人たちが、生活難にもかかわらず、半数近くが大審院までの長い裁判闘争を続けたのである。
米騒動への参加を正当な行為と認識してこその行動であり、不法な取調べや事実誤認に対しても屈しない姿勢を貫いていた。
被告人の弁護士たちもまた、二〇人のうち三浦端(たん)・新妻胤嘉(たねよし)・土屋忠夫をはじめ半数以上が、米騒動後に続いた普選運動・借家人同盟運動などの新たな民衆運動に指導的な役割を果たしていくことになる。
労働争議、無産運動の高揚
米騒動の時代、工場では労働者の深刻な生活難を背景に、賃金値上げの要求やストライキなど、組織的な運動が多発した。
労働争議は宮城県で一九一八(大正七)年には五件、翌一九年には一四件が確認されている。
このうち一九一八年十月二十三日には名取郡長町村の東北板紙株式会社で、「職工」六〇余名が増給を求めて大年寺山に立籠もり、ストライキに突入、三人の委員を選んで交渉に入り、要求を実現させている。十二月には仙台市の小学校教員が市側に待遇改善を求めるなど、公務員の団結も進んだ(我孫子麟『宮城県の百年』)。
翌一九年七月、東京絹毛紡績会社仙台工場で、男女二二九人が賃上げを要求して立上がり、同年十二月には片倉組仙台製糸工場で「女子職工」一一〇〇余名が賃上げを求めている。
この時期、労働者としての自覚は男女を問わず高まり、要求実現に向けて結束が進んだ。
職人たちも横断的な闘いを繰広げていた。
一九一九年十一月には仙台畳業組合の職人による増給運動、一九二一年には「仙台銅鉄葉(ブリキ)職工同志会」および「石工組合職工」による賃下げ反対などの運動が起きている。
一九二五年、白石町内の製糸会社などの労働者七〇〇人が白石労働組合を結成し、仙台でも同年、印刷労働組合が結成されるなど、企業の枠を越えた地域の組合組織の結成が広がった。
一九二七年三月には、仙台印刷労働組合や全石巻労働組合など、五団体からなる宮城県無産者団体協議会が結成され、五月一日、協議会の主催により宮城県最初のメーデーが挙行された。
仙台市西公園広場に約六〇人が参集し、集会ののち、仙台停車場までデモ行進を行っている。
全国的な労働者組織友愛会の創立者、鈴木文治が栗原郡金成(かんなり)村の出身であったことも、県下の労働運動に大きな影響を与えていたといえる。
普選運動
労働争議をはじめ、全国的な民衆運動の高まりは、いわゆる大正デモクラシーの思想運動を背景に起っていた。 その旗手となったのが、古川町出身で民本(みんぽん)主義を提唱した吉野作造(よしのさくぞう)である。
吉野の唱える民本主義にもとづく、君臣同治(くんしんどうち)を実現する普選運動は、中央の運動に合わせて一九一九(大正八)年以降、県下に広がっていく。
同年二月、仙台に弁護士や憲政会会員を中心に普通選挙期成同盟が結成され、二ヵ月後に開かれた第二回要求大会では、普選の実施と共に、労働党の結成が呼びかけられた。 労働党は県内最初の労働者の政治結社となった。
翌二〇年以降、米騒動の検挙者を支えた弁護士や、学生たちがひろく市民と結束して、新たな政治結社や啓蒙運動の組織づくりが始まっていく(我孫子麟『宮城県の百年』)。 |

図71 吉野作造
|

図72 「婦人入場自由」と書かれた新聞広告(『河北新報』
大正11年8月28日付)
|
| 同年三月、東北帝国大学・二高・東北学院専門部の学生と仙台市内の官庁・企業の若干労働者が平民協会を設立、同年八月には普選活動をしていた若手弁護士を中心に、青年自由革新党が結成され、普通選挙のほか、婦人参政権、労働組合、八時間労働、司法省の廃止と裁判権の独立、陪審制度などの要求を掲げている。 |
これらの団体が開く大会や講演会に中央から多くの弁士が招かれているが、一九二〇年四月の平民協会の社会講演会では鈴木文治が労働組合の必要性を強く訴えている。
普選運動の高揚の中で、女性の政治参加を求める動きも活発化していった。
一九二二年四月、治安警察法第五条の改正により女性の政談集会への参加が許可されると、この年八月二十九日に仙台座で開かれた日本革新運動政談演説会が女性の入場を認めた。
翌二三年二月、東京で婦人参政同盟が結成され、三月十一日には同盟の会員によって、仙台座で仙台最初の女権拡張政談演説会が開催された。
奥むめお・上村露子・塚本仲子らが演壇に立ち、五〇〇人もの聴衆が集まったが、女性の参加者はわずかに二〇人から三〇人ほどであった。
一九二四年には婦選運動の大同団結組織として婦人参政権獲得同盟が結成され、のちに婦選獲得同盟と改称して地方遊説を開始、宮城県には一九三〇(昭和五)年六月二十日、市川房枝・金子しげりが来仙して講演会が開かれている。 仙台市の名士夫人らが中心となって女性参政権問題に取組んでいた、黎明(れいめい)婦人会がこの講演会を主催していた。
農民運動の高揚
農民運動もこの時期、組織的な活動が進み、闘争を激化させた。
伊具郡金山町では一九一二(大正一〇)年、四〇人の小作人が不作のために地主に小作料の二割減免を求めて争議を起こしており、町当局は、本田一割、干拓田二割の減免を提示し、地主側もこれに準じて減免を決定したことで、争議は終結した。
金山町にはこれを契機に小作会が結成されている。
翌二二年四月、日本農民組合(以下、日農と略す)が創立され、翌二三年四月には日農関東同盟の宮城県最初の支部として、桃生郡鹿又村(河岸町)に鹿又農民組合が結成された。
創立大会には前述した金成村出身の鈴木文治らが出席、組合員は二五〇人であった。
日農の指導の下で、各地に小作人組合などの農民組織の結成が進み、多様な運動が展開されていくが、鹿又(かのまた)村組合も凶作であったこの年は早速、地主に小作料の二割減を求める最初の争議を起こし、全面的ではないものの小作料減免を実現させる成果をあげている。
以後大正期には同郡大谷地村(現在の河南町)、宮城郡高砂村(仙台市)、同郡原町(仙台市)、多賀城村(多賀城市)、岩切村(仙台市)、七郷村(仙台市)など多数の支部が結成されていく(渡辺信夫他『宮城県の歴史』)。
原町村では一九二六年七月、キリンビール仙台工場の廃液により水稲被害を受けた農民二二人が、日農支部、労農党支部の支援をうけて被害者同盟を結成し、闘争に立上った。
翌二七年二月に日本農民組合宮城県連合会が結成され、原町支部に事務局がおかれると、闘争は本格化し、翌年六月に協定が成立、会社には沈殿池と排水路も完成させるなど、成果をあげた。
この反公害争議を通して原町支部の組合員は一四〇人もに増加し、労農党や仙台市内の労働組合との共闘が進んでいく。
このほか桃生郡大谷地支部、登米郡豊里支部などでも耕作権や小作契約をめぐり争議を起こし、組合側が勝利を収めている。
日本農民組合宮城県連合会の結成は、支部組織を拡大させ、一方、労働農民党宮城県支部連合会もこの時期、支部の結成を進めている。
七 戦時と戦後 top
1 東北振興運動と戦時体制
東北の救済
東北は、明治初期の大久保利通(としみち)による拠点開発政策が挫折して以降、食糧と資源の供給基地として位置づけられ、農業依存型の経済は凶作のたびに打撃を受け、住民は疲弊した。
東北救済の運動が始まるのは、一九一三(大正二)年のことで、東北は大凶作であった。
内務大臣原敬(はらたかし)が、東北の窮状打開のために渋沢栄一らの財界人とはかって、民間団体の東北振興会を組織し、救済対策に乗出した。
これは中央からの東北救済の運動で、その目標は、東北を振興して国の経済の進展を図ることであった。
以下、岩本由輝『東北開発120年』、安孫子麟『宮城県の百年』などによって、東北振興運動を概観してみる。
東北振興会
東北振興会は、義援金集めや啓蒙運動を行う一方、東北振興策確立のための基礎調査を実施した。
この調査報告は、一九一六年宮城県選出の衆議院議員村松亀(き)一郎らによって「東北振興に関する建議」として第三七回帝国議会に提出され、
①東北拓殖会社の設立、
②金融機関の改善、
③通信運輸機関の完成などを提言し、のちの東北振興政策に影響を与えた。
しかし、東北各県の動きは鈍く、東北振興会はやがて有名無実となって、一九二七(昭和二)年に解散した。
その直後、貴族院議員菅原通敬(みちたか、宮城県出身)らを中心とした新たな東北振興会が組織された。
この会は、政治的な東北振興運動を展開した点に特色があり、一九三二年から三年間、中央の実業家を中心とした東北産業視察団を編成して、東北各地の実情調査を実施した。
翌年には東北振興のための地租改正、金融施設整備など二八件の請願を帝国議会に提出し、採択された。
また、同年の東北振興問題座談会では「東北を特別行政区とし、政府の方針の下に拓殖経営を実行すべし」と提言した。
東北振興調査会
一九三四(昭和九)年十二月、内閣直属の諮問答申(しもんとうしん)機関として東北振興調査会を設置することを閣議で決定した。
東北振興問題が急進展したのは、この年の大凶作で疲弊のどん底に落ち込んだ東北の人々が、恒久的な東北振興対策の実施を、政府に迫ったからにほかならない。
たとえば八月、あいつぐ凶作と繭(まゆ)価暴落の慢性化の中で打撃を受けた仙南四郡(柴田・刈田・伊具・亘理)の町村長会が、飯米確保のために政府米払下げなどの応急対策樹立を決議し、政府や県への運動を開始した。
さらに全国農民組合の米貸せ運動の全県的な展開は、町村議会まで巻き込んで展開していった。
十月に、東北六県知事も、東北地方振興のための根本対策樹立に関する陳情書を政府に提出し、その中で「政府に於て東北地方振興調査会を設置しその根本対策を樹立すること」を強く要求した。
こうして設置された東北振興調査会の第一回総会は、翌年一月開催され、会長岡田啓介(けいすけ)首相の諮問第一号「東北地方の不振の真相究明と、災害を防除し、福祉を増進すべき具体的振興策について意見を求む」に関して、二月に、
①鉄道網の整備、
②冷害対策の早急な実施、
③東北振興策をめぐる各省庁間の統一保持を目的とした東北振興事務局の設置、
④生活改善に関する方策の急速な実行、
⑤農村における工業の発達を図るための緊急施策の五項目の応急対策をまとめ、答申した。
答申にもとづき、五月東北振興調査会の幹事業務や各省庁問の連絡調整を行う東北振興事務局が内閣の直属機関として設置された。
東北振興調査会は、八月に二四項目の東北振興策と「十二年度以降は長期的な総合計画を樹立し、それに基づいて恒久対策を展開すべきだ」とする答申をまとめ、九月には殖産興業の実施機関として東北興業株式会社(以下東北興業)、東北振興電力株式会社(以下東北振興電力)の二特殊会社を設立すべきであるとの答申をまとめた。
東北振興第一期総合計画
さらに、一九三六(昭和十一)年七月、東北振興調査会は、昭和十二年度から十六年度に至る五ヵ年間の東北振興第一期総合計画を策定した。
計画は東北振興を主唱しながらも、最終的な目標として国防を掲げているのが特徴で、東北救済にかわって「広義国防国家」建設のための東北開発という目的を重視するものであった。
一方、人的軍事力「強兵」の供給地帯として東北を捉える陸軍首脳部も、「陸海軍においては軍器制作関係の工場を東北に振り向けるように務める」という東北振興政策への積極的な提言を行っていた。
救済策を切捨てた東北振興政策は、一九三七年の日中全面戦争の開始と共に、国家総動員体制の中に東北経済を組込んでいく形で具体化され、後述する陸海軍の兵器製造工場の建設もこうした政策と深く結びついていた。
東北興業・東北振興電力の事業
東北振興調査会の答申の中で、特に実質的な効果を期待されたのは、一九三六(昭和十一)年に決定された東北興業と東北振興電力の設立であった。
東北興業は東北振興を目的とする起業や起業助成を行う会社で、投資によって設立された会社は、東北振興電力を別とすれば八三社におよんだ。
宮城県内では、刈田郡大平村(白石市)の種畜場、片倉製糸の仙台製糸所工場を買収した宮城県是共栄(ぜきょうえい)蚕糸、東北振興パルプ(石巻市)、東北船渠(せんきょ)鉄工(塩釜市)、東北振興皮革(仙台市)、東北振興ゴム(仙台市)などが設立された。
しかし、会社の設立は東北の要望によることなく、全面的に戦時経済体制下における軍事的性格を強め、もっぱら国策の必要上から進められた。
東北振興電力の事業は電源開発と発電で、一〇年間に水力発電所一四ヵ所、火力発電所一ヵ所を建設する計画で、宮城県内では白石川水系に、遠刈田(とおがった)発電所、曲竹(まがたけ)発電所がつくられた。
しかし、一九四〇年、電力の国家管理をめざす国策により、東北振興電力の反対にもかかわらず、翌年、日本発送電株式会社に吸収合併された。
船岡海軍火薬廠(しょう=軍の工場)
海軍省では、一九三二年頃から火薬廠(火薬・爆薬製造工場)増設の機運が高まり、準備、調査が始められた。 |

図73 曲竹発電所
|
一方、東北農村の疲弊は国家的重要課題となっており、差しせまった状況は新火薬廠を東北に設置する方針となり、一九三七年七月、柴田郡船岡村(柴田町)に建設することが決定した。
強制買収された建設用地約五三〇万平方メートル(五三〇町歩)は伊具郡北郷村(角田市)にもおよび、一九三八年には建設工事が始まった。
翌年八月、海軍火薬支廠として開庁し、一九四一年に第一海軍火薬廠と改称した。
山の斜面を利用した階段式工場で、東洋一の火薬・爆薬製造の総合火薬廠建設をめざしていた。
建設しながらの生産、生産しながらの建設であった。
火薬廠にかかわった人員は、軍関係は火薬廠長を含めて三五七人、応召入営者一九四人、工員(徴用工を含む)五七一七人、通年動員学徒一五五九人(男子七七九、女子七八〇)、勤労動員学徒一六八一人、女子挺身隊員六七一人その他で、総人員は一万三八二人であった。 |
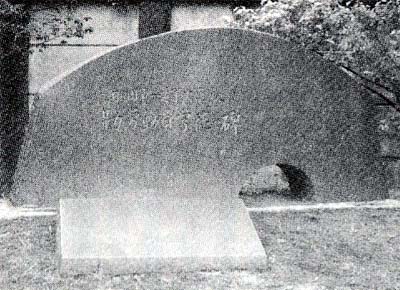
図74 船岡海軍火薬廠勤労動員学徒の碑
(現仙台大学構内)
|
しかし、熟練工は次々と応召し、労働力不足は質量ともに深刻化していた。
一九四四年四月、仙台工業専門学校・東北薬学専門学校の学生が通年動員されたのを始りとして、第二高等学校、近隣の白石・角田(かくだ)の中学校・高等女学校、大河原・岩沼(いわぬま)の高等女学校、岩手県の黒沢尻(くろさわじり)・大船渡(おおふなと)の高等女学校・専修校からも動員された。
また、翌年五月からは、近隣の国民学校高等科の生徒も入廠(にゅうしょう)させられた。
労働の苛酷さ、睡眠時間の不足、劣悪な食糧状態からくる疲労から、事故が多発し死亡する者もでた。
また、宮城刑務所の受刑者が建設工事に、朝鮮人徴用工が本土決戦にそなえての地下工場建設のトンネル掘りなどの難工事・突貫工事の重労働に従事していた。
一九六一年に海軍火薬廠跡地の払下げが実施されて以降、自衛隊をはじめ、仙台大学、船岡養護学校、角田ロケット開発センター、各種工場などの用地となっており、学徒として動員された人たちによって建てられた記念碑が旧海軍火薬廠正門付近(現仙台大学構内)にある。
なお、火薬廠の模型が柴田町の資料館思源閣に展示されている(『柴田町史』通史編2)。
原町(はらまち)苦竹(にがたけ)陸軍造兵廠(東京第一陸軍造兵廠仙台製造廠)
一九四一(昭和十六)年春、原町苦竹(現在のJR仙石線陸前原町駅の東側の広大な水田地帯)に陸軍造兵廠(陸軍兵器製造工場)の建設が始まった。
木造のノコギリ屋根の巨大な工場が幾棟も建ち、工場敷地はコンクリート製の塀で囲まれていた。
この造兵廠には工場が第一工場から第四工場まであり、二〇ミリと一二・七ミリの航空機関砲の弾丸をつくっていた。
十一時間拘束の二交替制の勤務体制であった。
従業員は、約一万人といわれているが、熟練工員は少なく、少年養成工と高等女学校・中学校から動員された学徙と女子挺身隊が大部分を占め、人手不足となっていた兵器生産の現場に通年で働いていた。
経験不足の素人が効率の悪い仕事をしており、不良品がところ構わずおいてあった。
敗戦間近になると、資材不足のために操業もできない状態で、工作機械を疎開させるために、もっぱら運搬作業に従事していた。
敗戦後の造兵廠跡地には、進駐してきた米軍のキャンプ、警察予備隊、保安隊がおかれ、一九六〇年以降は陸上自衛隊東北方面総監部(そうかんぶ)が設置され、現在に至っている(高砂敏夫『ふるさと仙台・原町』)。
多賀城(たがじょう)海軍工廠
一九四一(昭和十六)年十二月以降、海軍省は長期戦にそなえて海軍工廠(海軍兵器製造工場)の増設・拡張計画を急速に具体化していった。
翌年五月、横須賀(よこすか)海軍建設部は、係官を用地買収のために多賀城村(多賀城市)に派遣した。
多賀城村は全面積の半分以上が田や畑の農地で、人口七九〇〇人余の農村であった。
六月、買収対象の土地所有者を多賀城国民学校に参集させ、特高警察官で囲ませ、譲渡承諾の意思表示とみなすという万歳三唱を強制し、一ヵ月以内に移転することを指示した。
農地のほか、家屋や墓地にいたるまで買収された人も数多く、多賀城村八幡の沖区(八八戸)は、地区丸ごと買収の対象となり、地上から完全に消滅した。
買収用地面積は、四九六万一六〇〇平方メートル、村の全面積の約四分の一に達した。
七月に開始された海軍工廠の建設工事には、毎日数千人の労働力が必要とされ、村は、軍の指令のつど、「職工」や作業員を集め、協力を強いられた。
建物建設工事を請負ったのは、大林組・鹿島組などの軍の建設協力会のメンバーで、もっとも過酷な土木工事にあたっだのは海軍工廠(こうしょう)直属の勤労報国(ほうこく)隊や徴用工の形で連行された朝鮮人労働者、軍直属の土木工事を請負っていた菅原組の日本人と朝鮮人の労働者、宮城刑務所の受刑者であった。
軍事施設の突貫工事を請負っていた菅原組(本社、釧路市)は、労働条件のきわめて悪い工事現場で、労働者を監禁同様の状態で強制的に重労働に従事させて、多くの逃亡者・死亡者をだしている。
多賀城海軍工廠は、航空機用機銃、同弾薬包および爆弾(焼夷(しょうい)弾・親子爆弾・照明弾・吊光(ちょうこう)弾)製造の専門工場として、日本最後の最大の海軍工廠をめざして建設された。工廠で働いていた人員は、一般工員・徴用工員・動員学徒など、最盛期には約一万三〇〇〇人から一万六〇〇〇人といわれる。
危険な作業の中で爆発事故も発生し、多くの死傷者が出たが、軍秘扱いされ、真相は不明のままである(『多賀城市史』近世・近現代)。
最近、地域住民によって多賀城海軍工廠を考える実行委員会が組織され、松島町高城に現存する多賀城海軍工廠地下工場跡の調査・研究が始められた。
2 第二師団の兵士たち top
軍都仙台
仙台市は、敗戦後に陸軍が解体されるまで、第二師団司令部をはじめ多くの部隊がおかれ、まさに軍都であった。
軍都仙台の歴史は、明治四(一八七一)年に、明治政府が、北日本の治安・国土防衛上の軍事拠点として、東北鎮台をおいた時に始まった。
一八七五年には歩兵第四連隊がおかれ、仙台は、東北・北海道地域の戦略拠点の性格を強め、特に歩兵第四連隊はそのシンボル的存在となった。
一八八八(明治二十一)年に、仙台鎮台は第二師団と改称され、その後、第二師団の編成はめまぐるしく変るが、師団司令部と歩兵第四連隊は仙台を離れることはなかった。
郷土部隊
歩兵第四連隊に象徴される「郷土部隊」、この呼称は、地元紙『河北新報』などが、日露戦争以降、第二師団の地元部隊の奮戦ぶりを具体的に報道するなかで、地域住民に受容されていったといわれる。
また師団制が実施され、宮城県を本籍地とする兵士の大多数が第二師団、特に歩兵第四連隊に入隊したことは、県民に一体感を醸成するうえで無視できない役割を果たした。
県民は、「おらが連隊」とも呼んだが、その言葉の中には、兵営や戦場での夫・子・兄・弟の安否を気遣う思いも込められていたと考えられる。
第二師団の存在は、仙台の橋や道路など公共施設の整備をもたらし、さらに飲食店・みやげ店・旅館・劇場・遊郭などへの需要を生み出した。 |

図75 旧歩兵第四連隊兵舎の一部
(現仙台市歴史民俗資料館)
|
兵士は日曜日や祭日・休暇日に、当番勤務者をのぞいて外出が許可され、夕食前の点呼までに帰営すればよかった。 仙台の繁華街や公園、広瀬川にかかる大橋のたもとの茶屋などには、一般市民の姿に混じって学生と共に多くの軍服姿の兵士が見られた。
また第二師団は、歩兵第四連隊をはじめ各隊兵士の食糧・燃料・衣料・軍靴などのほか、騎兵隊・野戦砲兵隊・輜重隊(しちょうたい=輸送隊)で使役する軍馬用の飼料(大麦・稾(わら)・干し草)を地元商人から大量に買っている。
軍馬の購入も川内(かわうち)の追廻で行われ、軍の払下げの外套(がいとう、オーバー)・軍服などの古着や廃馬、各隊の下肥(しもひ)の汲取りと馬糞の入札競売などがあり、残飯の払下げを受ける業者もいた。
面会人や除隊兵士向けのみやげ品や記念品を売る菓子屋・漆器店・木盃(もくはい)製造販売店・旅館などが、大町一・二丁目と鉄砲町方面から駅前に向かって並んでいた。 このように、第二師団は、仙台の経済と深くかかわっていた。
戦争が始まると、応召者の送別会・見送り、戦勝祈願、凱旋(がいせん)時の歓迎慰労、戦勝祝賀会、戦病死者葬儀などが日常的に見られた。
県下の各停車場では、軍隊輸送車通過のたびに、昼夜の別なく茶・果子・弁当の提供、演奏などが行われ、動員された人々がうち振る日の丸や万歳の歓呼のなかを兵士は出兵した。
とくに日中戦争以降は、戦病死者の葬儀は、市町村葬として実施され、郷土の忠勇の範、国家のための死として抽象化された。
新聞は、郷土部隊の奮戦ぶりを詳細に伝え、戦病死者の名・戦歴・兵士が生前遺族に宛てた于紙の紹介など、出身兵士の人柄までを記事とし、地域住民の郷土部隊意識を高揚させた。
戦争と兵士
仙台に配置された軍隊の兵士が、はじめて出兵・参戦したのは一八七七(明治十)年三月、歩兵第四連隊第一・二大隊が西南戦争に動員され、熊本・鹿児島を転戦した時で、戦死者三一人、負傷者五五人であった。
海外への参戦の最初は、一八八四年、朝鮮ソウルの日本公使館の護衛として、歩兵第四連隊第一大隊第一中隊が派遣された時で、日本公使館に率いられて甲申事変(こうしんじへん)を起こし、戦死者は五人、負傷者六人であった。
日清戦争では、第二師団への動員令によって、一八九四(明治二十七)年十月、第一陣の第四旅団が青森を出発、集合地広島に向かい、続いて在仙部隊も騎兵第二連隊を先頭に、歩兵第四連隊などの歩兵、工兵・砲兵の各部隊が長町停車場(日清戦争へ出兵する兵士を送り出すための仮の停車場)を出発して行った。
農村は秋の稲刈りを迎える時期で、働き手や農耕馬を徴発されることは大変な痛手であった。
第二師団は、さらに徴用人夫として八八〇〇人(うち宮城県内二五二〇人)を従軍させた。
中国各地を転戦して、一年後に仙台に帰っているが、宮城県出身の将兵の犠牲は戦病死者三九〇人を数えた。
以下、戦争のなかの郷土部隊の兵土たちを『歩兵第四連隊史』と村山磐『戦争と歩兵第四連隊』で見てみよう。
日露戦争
日露戦争では、第二師団在仙部隊の先発隊である騎兵第二連隊が、一九〇四(明治三十七)年、開戦前に長町軍事鉄道停車場から出発した。
動員令が下った第二師団は、ただちに出戦準備にとりかかり、宮城野原練兵場での観兵式と師団長の訓示後、在仙部隊は広島へと出発した。
駅に向かう兵士の通り道には見送りの人垣がつづき、日の丸の小旗がうち振られ、仙台市内の児童生徒が整列し、「露西亜(ロシア)征伐の歌」を合唱して見送った。
日本の勝利により、一六ヵ月ぶりに第二師団の凱旋(がいせん)将兵を迎える地元の歓迎は、師団司令部の凱旋時に最高潮に達し、市内各家の軒下は、日の丸や旭日旗(きょくじつき)が飾られ、仙台停車場から川内の師団司令部までの道筋は、留守部隊・児童生徒・将兵の家族と一般市民でぎっしり埋まった。
しかし、戦いに疲れた兵士を迎えた郷土、宮城県下は大凶作に見舞われ、平年作の四分作から二分作、山沿いの刈田郡七ヶ宿・柴田郡・伊具郡などは収穫皆無に近かった。
犠牲も大きく日露戦争に倒れた第二師団将兵は二七四〇人で、宮城野原練兵場で招魂(しょうこん)大祭が行われた。
一九一〇年、日韓併合の日、ソウル市街を巡回警戒する日本憲兵隊の背後には、歩兵第四連隊第二大隊が臨戦態勢でにらみをきかせ、第一次世界大戦中に起きたロシア革命に対抗したシベリア出兵では、歩兵第四連隊が樺太・沿海州に派遣された。
また、一九一八(大正七)年仙台で米騷動が起こった時には、歩兵第四連隊や歩兵第二九連隊が鎮圧のために出動し、一九三六年、二・二六事件が起きた時には、歩兵第四連隊から混成一大隊が編成され、戒厳令下の東京に動員され、三ヵ月以上も駐屯した。
このように、第二師団の出兵は、それぞれの時代の政治や社会の動きを反映している。
「満州事変」
一九三一(昭和六)年九月、日本軍の中国東北部への侵略は、関東軍独立守備隊第二大隊と第二師団歩兵第二九連隊に発せられた北大営(ほくたいえい)と奉天城(ほうてんじょう)攻撃の関東軍命令によって始まった。
長春(ちょうしゅん)に駐屯していた第二師団歩兵第四連隊の出撃も速く、長春以南の主要地を占領した。
陸軍最強といわれた第二師団は、まさしく関東軍唯一の機動部隊・戦略部隊で、いわゆる「満州事変」は第二師団によって遂行され拡大していった。
「満州国」の成立後、二年ぶりに仙台に帰還・行進した凱旋道路の南町通は、師団長多門二郎(たもんじろう)の名をとって多門(たもん)通りと呼ばれることになった。
しかし、この時、蚕繭(さんけん)や農産物の価格の大暴落に加えて大凶作が東北地方を襲っており、欠食児童・娘身売り・一家心中が続出するといった惨憺(さんたん)たる生活を強いられていた農村に、多くの農民出身兵士は帰還したのである。
将兵の犠牲も大きく、戦死者三〇〇名、戦傷者約七〇〇名、凍傷(とうしょう)患者は約八〇〇名におよんだ。
アジア・太平洋戦争
一九三七(昭和十二)年七月、日中戦争が始まると、「満州国」北部の警備についていた第二師団に加えて、第二一師団が編成され、中国戦線に送りだされた。
第一三師団は、第二師団の留守部隊を母胎に特設されたもので、兵士には年配者が多く、宮城県人で編成された第一〇四連隊は盛んな見送りを受けながら仙台を出発した。
上海戦を皮切りに南京(ナンキン)、徐州(じょしゅう)などを転戦し、敗戦を中国で迎えた。
上海戦が拡大すると、第二師団主力の歩兵第四連隊諸隊の戦闘は激しくなり、一ヵ月の戦闘で二〇〇人以上の戦死者を出した。
第二師団は一九三九年、ノモンハン事件にも出動した。
一九四一年十二月、日本軍は真珠湾のアメリカ太平洋艦隊を攻撃し、戦場を太平洋に拡大していった。
第二師団は、前年「満州国」警備の任をとかれて仙台に帰還していたが、臨時編成の勇(いさむ)三〇一となり、歩兵第四連隊は勇(いさむ)第一三〇一部隊と呼ばれ、南方戦にそなえて、第一六軍に属し、フィリピン、ジャワ攻撃に加わることを決められた。
その後、第二師団は、第一六軍の基幹部隊となってジャワ島を占領後、ガダルカナル戦にのぞみ、多くの戦死者と餓死者を残し撤退した。
上陸将兵一万三一八人中の戦没者は七六七一人(七五%)、歩兵第四連隊では、上陸将兵二四五八人中の戦没者は一九〇六人(八〇%)であった。
このように、戦争が激化すると、第二師団の将兵は、たえず最激戦地に派遣され、大きな犠牲を強いられ、数多くの「英霊」(えいれい)が「無言の凱旋」の形で帰還した。
3 地域構造の変化と住民の生活防衛
top
高度経済成長の陰り
宮城県では、高度経済成長の始まった一九五五(昭和三十)年に五二・七三%を占めていた農林水産業を中心とする第一次産業の就業人口は、一九九五(平成七)年には八・二%にまで減少した。
さらに、一九七〇年度から実施された減反、すなわち米の生産調整と、政府管轄米以外の自主流通米の誕生、すなわち米販売の市場競争は、農業県としての宮城県のあり方を大きく変えていった。
米の減産目標は全国で一五〇万トン、宮城県には四万三〇〇〇トンが割当てられた。
こうした減反政策と市場競争によって、特に宮城県では、山間部と沿海部の米の生産はしだいに減少し、過疎化の遠因ともなった。 また、高度成長に伴う産業構造の変化は、特に仙台圈への人口の流入と、山間部と沿海部からの人口流出を激化した。
一九七〇年の県内の人口動態を見ると、転入超過は、仙台圏の九市町村と石巻圈の二市町だけで、ほかの六三市町村はすべて転出超過であった。
宮城県における過密・過化の様相は、一九七〇年以降も進行し現在に至っている。
高度経済成長期の産業構造の変化にともない、産業経済の発展と生活のあいだのギャップがしだいに広がり、「生命と暮らしを脅かす」課題が発生した。
次に述べる角田市農業協同組合とみやぎ生活協同組合との産消(さんしょう)直結運動や、柴田郡川崎町の産業廃棄物(はいきぶつ)処分場問題の住民運動は、全国的な注目を集め、このような課題への先駆的な取組みとして評価された。
角田市農協とみやぎ生協の産直(さんちょく)運動
一九七〇(昭和四十五)年四月、宮城県南部にある角田市農業協同組合(以下角里市農協)とみやぎ生活協同組合(以下みやぎ生協)の前進である宮城県民生活協同組合・宮城県学校生活協同組合との産地直送の取組みがスタートした。
当初は豚肉と鶏卵(けいらん)のみの取引きであったが、その後、野菜・梨・梅干し・苺(いちご)と増えて、生産者と消費者が協力しあい、かつ学習しながら産直品を育てていくという、宮城の産消直結運動(以下、産直運動)の原型がここに形づくられた。
宮城では、産直運動がスタートしたときから、農協と生協の「協同組合間協同」を原則としており、
①産直品の生産をとおして地域経済が自立すること、
②生産物の価値がきちんと評価されること、
③地域内で食糧を自給すること、
④地域の環境を守っていくこと、
⑤消費者の望む物がいつでも手に入る体制であることなどのプランの実現をめざしてきた。
そのために、組織的なつながりを産直の中心におくこととし、農協・生協の代表者で構成する産消提携推進協議会を設置し、その基本的な約束ごとは「産消提携に関する基本協定書」で明らかにされている。
一九八五年、みやぎ生協と仙南広域営農団地(角田市農協を含む仙南の七つの農協で組織)の間で、初めて基本協定書が締結された。
以後、協定書をもとに様々な産直組織が生まれ、現在みやぎ生協は三五の農協・団体と協定書を締結している(みやぎ生活協同組合編『みやぎの産直収穫祭り』)。
こうした取組みのなかから、農協とみやぎ生協は、これぞ産直品といえる多くの優れた農・畜産物を共同開発して、育てていった。
黒豚(産直ふるさと豚(ポーク))・コープ九〇日の鶏・桜卵(さくらたまご)・平飼(ひらか)い卵・完熟トマト「桃太郎」・朝摘みイチゴ・手づくり梅干し・産直ふるさと米・宮城小粒納豆示粒大豆)などはその代表的なものである。
また、一九八四年には、生産者代表と農協・生協実務者で有機農薬プロジェクトと自家配合飼料プロジェクトを結成し、一九八六年にパラコート使用の全面禁止、翌年には産直品使用農薬基準を発表し、二〇種類の禁止農薬を決めた。
また、角田市農協は、農薬の空中散布は「地域を農薬で包んでしまう」という考えから、一九九一(平成三)年に、農協単位としては東北で初めてこれを廃止した。
川崎町の産業廃棄物処分場
一九九三年二月、突如として柴田郡川崎町本砂金(もといさご)地区に産業廃棄物(はいきぶつ)処分場(以下産廃処分場)を建設するという問題が持上がった。
建設予定地は、仙台市のすぐ南に位置する本砂金地区と隣接する川崎町川内(かわうち)地区のほぼ中央部の山林一五ヘクタールで、土地所有者はすべて仙台市の住民であった。
産業廃棄物処理業者は、川崎町住民、特に本砂金地区や川内地区の住民に産廃処分場建設の事前説明をすることなしに建設に着手しようとした。
産廃処分場建設には都道府県の認可が必要であるが、業者が土地所有者との事前協議書を県に提出する前に、本砂金地区と川内地区の住民に察知され、産廃処分場反対の大きな激しい住民運動が起きた。
計画された産廃処分場は素堀りの穴同然の簡単なもので、有害物質が流出する可能性がある当時最も多いタイプであった。
住民は、当時裁判闘争によって画期的な結果を勝ちとった伊具郡丸森町耕野地区の住民による産業廃棄物最終処分場の営業差し止め仮処分申請運動に学びながら、幾度となくミニ学習会を開催し、産廃処分場建設が地域住民に対してどのような弊害をもたらすかを確認しあい、一万人規模の署名活動を展開した。
住民の反対理由は、
①予定地には、仙台市南部の水ガメである釜房(かまふさ)ダムにそそぐ太郎川の水源があること、
②さらに本砂金地区と川内地区の農業用水に利用している沢水が流れていること、
③先祖から受継いだ自然環境を子供たちに無傷のままで手渡したいという地域住民の願いがあること、
④産廃処分場が建設されれば、森林を破壊して生態系や保水にも影響があること、などであった。
住民運動が高揚するにつれ、川崎町当局、町議会も産廃処分場に反対の意志を示し、住民の要求と一致して取組むという全国的にみても珍しい産廃処分場反対運動が展開した。
マスコミもこうした運動を大きく報道し、反対運動はさらに大きな広がりを見せ、仙台市長・仙台市議会・宮城県知事・宮城県議会へ陳情・請願を行った。
一九九四年六月、仙台市議会と川崎町議会は、住民の産廃処分場反対請願を可決、反対署名も一万人以上集まった。
翌年三月には、宮城県議会が、仙台市議会や川崎町議会と同様に反対請願を可決し、産廃処理業者は産廃処分場建設を断念した(大村泉・平林一隆『産廃処分場と地域環境――宮城県川崎町・丸森町地域住民の証言を通して――』)。
宮城県内では、産廃処分場問題は今なお後を絶たない。最近では、高濃度の硫化水素が発生し、汚水流出・悪臭などが問題化している柴田郡村田町沼辺(ぬまべ)の竹の内産廃処分場(一九九〇~九一年、県の許可を受けて操業)で、許可容量を大幅に上回る量の産業廃棄物が埋められていたことが判明し、県の監督責任と住民の生活を守るための具体的な対応策が問われている。
top
****************************************
|