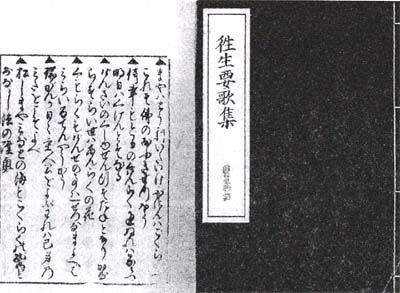|
****************************************
Index Ⅰ章 Ⅱ章(“上” “中” “下”) Ⅲ章 付録
Ⅲ章 地域としての陸前南部
一 地域文化の発見 top
1 仙台藩の学問と文化風土
雲居(うんご)和尚の往生要歌
雲居希膺(きよう、伝一五八二〜一六五九)が説き著したとされる『往生要歌』(おうじょうおうか)と、その上巻にあたるといわれる『医世(いせ)物語』という書物がある。
渡辺喜勝氏は民衆教化に尽くした功績について詳細に論じられているが(「瑞巌の医王−雲居和尚と民衆教化−」渡辺信夫編『宮城の研究』七)、仙台藩初期の統治思想や文化風土を語る上で興味深い史料である。
特に近世初めには、むしろ儒学以上に、仏教はきわめて大きな役割を果たしたと考えられるからである。
雲居は、江戸時代初期に活躍した臨済宗の名僧として全国に知られていた人物で、仙台藩主伊達政宗・忠宗父子の再三の招請によって、寛永十三(一六三六)年に松島瑞巌寺の住職となり、中興の祖といわれる事績を残している。
雲居は、臨済宗の有力寺院である京都の名刹妙心寺で、同士とはからって念仏禅を唱導し、大衆の教化に努める運動を起こした。
百八首とされる和歌によって、見やすく聞きやすく生きるべき道を説いたのである。
そのため「道歌」(どうか)とも称される和歌が、南無阿弥陀仏の念仏と組合わされて詠唱されることから、雲居念仏、あるいは往生要歌とも呼ばれていた。
この書の版木は瑞巌寺にも残されているが、延宝九(一六八一)年には、おそらく京都にあったと思われる書林から啓蒙的な仏教書として出版されていた。
ごく一部であるが例をあげて、この禅僧が創始したとされる極楽浄土を希求する念仏道歌の特徴をみることにしよう。 |

図77 雲居希膺
|
世を遁(のが)れ修行の道は別になし 智者愚者共に座禅念仏
貴賤智愚僧俗男女別なれば 菩提(ぼだい)の修行も 分(ぶん)に応ぜよ
医世 医国 医民の薬方(やくほう)別になし 慈悲仁政を本草とせよ
儒釈道 三つの教の言(こと)の葉(は)は 何れも苦(にが)き薬なりけり
道はただ三教一致と聞くぞかし 何れになりとも入れや人々
人として仏陀神明しらざるは 是(これ)きりしたんか さては禽獣(きんじゅう) |
在家信仰にふさわしい簡便な座禅念仏を推奨し、政治を行う側と行われる側の倫理・道徳や信仰のありかたを軸として、それぞれの身分に応じた社会秩序意識の普及や、儒学・仏教・神道の三教を一体とする教学を日本の教学としてキリシタンを排斥するなど、幕藩体制社会の安定に役立つ思想内容をそなえていたことがわかる。
往生要歌が藩主政宗夫人の陽徳院(ようとくいん、愛姫・田村氏)の要請に応じてつくられ、進上されたと伝えられ、夫人が侍女らと共に念仏会を催しこれを詠唱したと伝えられるのも、往生要歌が時代に適合した教化内容を盛りこんでいたからであろう。
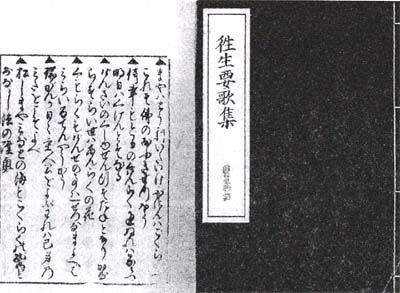
図78 『往生要歌』(瑞巌寺刊) |

図79 松島念仏踊(『奥川名所図会』より) |
六斎念仏踊り
往生要歌の中に「松嶋や 湊の海も極楽の池水と同じ 法(のり)の陸奥(みちおく)」という一首がある。
松島は、極楽浄土を現世に映し出す聖地だったのである。特に見仏(けんぶつ)上人以来の修行の地として雲居も座禅を組んだ雄島(おしま)は、十四世紀半ばの僧宗久(そうきゅう)の紀行文『都の苞(つと)』に、人々が死者の遺骨や出家する際に切った毛髪などをおさめる霊地として記録され、十八世紀末の藩内の地誌『封内(ほうない)風土記』にも同様に記されている。
納骨塔や板碑、岩壁に穿(うが)たれた洞窟の修行場跡が今にその歴史を伝えている。
これと関連して注目されるのが民衆に伝承された雲居念仏と念仏踊りの関係である。
藩校養賢堂(ようけんどう)で和学を講じた保田光則(やすだみつのり)の『新撰陸奥風土記』には、盂蘭盆(うらぼん)の頃、幾群れかの老若男女が雲居国師の百八つの歌を詠じながら鉦(しょう)・小太鼓を鳴らし踊ってきて、道すがら施しを受けてきた米銭を雄島に納め、「親族不離の亡霊に供養」していた、と記されている。
このように幕末に至るまで、民間信仰の六斎念仏と往生要歌とが一体のものになっていたことが知られる。
安永七(一七七八)年の自序のある篤学者相原友直(ともなお)の『松島巡覧記』によると、この六斎念仏は、元々は月に六日ある六斎日に僧俗が集まって念仏を唱え精進する念仏講が結成されていたもので、寛文二(一六六二)年に念仏講で往生要歌を唱詠していた有志の者が不昧堂(ふまいどう)という道場を建てたところ、松島だけでなく「遠郷他邦」(『奥州名所図会』)から伝え聞いて来る者が多かったという。
盂蘭盆の海上に流される無数の灯籠流しの行事とあわせて往生要歌は広く庶民に知られ、今につづいているとも述べている。
おそらくは中世からつづいて浄土信仰に基礎をおく念仏講や念仏踊りが行われていたところに民衆教化の一環として往生要歌が注入され、雲居念仏と称されるようになったのであろう。
ただし、往生要歌は堅苦しい道歌ばかりではなかった。江戸時代の希有(けう)の旅行者であった菅江真澄(すがえますみ)も雲居念仏を耳にし、「書写寺(しょしゃでら)の僕の衣の虱(しらみ)とる昔の御僧今ぞ恋しき」というユーモラスな一首を書き留めているが、それはまさしく往生要歌のなかの一首である。
書写寺が播磨国(兵庫県)書写山円教寺のこととすれば、『義経記』の弁慶の荒法師ぶりを伝える話として地域の民衆には馴染みのあった所である。
源平争乱などの歴史上の挿話を引用した類例はほかにもあり、往生要歌はこうした楽しみを加えながら、寺僧の説話を通して近世社会に適合する徳育を推し進めたのであろう。
藩校養賢堂と医学館
元文元(一七三六)年、仙台藩は初めて儒学の殿堂としての学問所を設置したが、小規模なものであったため、宝暦十(一七六〇)年、移転・拡充が図られ、医学講師もおかれた。
安永元(一七七二)年に養賢堂(ようけんどう)と称するようになり、同九年には学頭の職がおかれるようになるが、本格的な学制改革が図られたのは文化六(一八〇九)年のことである。
この翌年には、江戸の芝の藩邸にも学問所として順造館(じゅんぞうかん)が設けられた。
学制改革の中心になった大槻平泉(おおつきへいせん)は、江戸の昌平黌(しょうへいこう)に学んだほかに、長崎に遊学し蘭学を修めていた人物で、師の大学頭林述斎(はやしじゅっさい)や幕府若年寄で蝦夷地警衛のため派遣された体験のある堀田正敦(まさあつ、堅田(かただ)藩主・仙台藩伊達氏出身)の意見を聴き、学田一万二〇〇〇石を財源として設定し、学舎の拡充、医学館の独立、養賢堂での印刷・出版事業、人材選抜「見分」制度、儒役世襲制の廃止、ロシア・オランダ語和解(翻訳)方部屋の設置などを着実に実現していった。 |

図80 大槻平泉像
|
平泉は学頭として文武の総合学舎を建設したが、この学制改革の前年に、蝦夷地でロシア船の来航やロシア人による幕府船の焼討ち事件などが発生したため、仙台藩は会津藩と共に蝦夷地警備を命じられ出兵し、これに従った藩医高屋養庵の手記によれば相当数の罹病者を出したばかりであり、北方問題への関心が強まっていた。
朱子学を堅守していた藩学に蘭学・医学が加わり、その比重が増していく仙台藩の特色が明確になるのは、この頃からである。文政四(一八二一)年には蘭学方が新設され、相談役として蘭学界の泰斗(たいと=権威者)であり出身地の仙台藩医であった大槻玄沢の長子玄幹(げんかん)が参与している。
ロシア語を含む蘭学の充実に重きをおくようになっていたのである。
医学館は文化十四(一八一七)年に完成し、初代講師(俗に学頭とも呼んだ)に渡辺道可(どうか)が任じられ、施薬所を設けて恵まれない人々に医療を施し、臨床実習を行った。
薬園もつくられ、調合した薬を市中の薬屋を通して売っていた。文政五年には医学館に蘭科が設置された。
助教として就任した佐々木中沢は一関出身で大槻玄沢の門下であり、鶴岡(山形県)出身で、のちに幕府天文方に転じて蛮社の獄にかかわり自殺した小関(こせき)三栄(のち三英)も助教となっている。
工藤平助と林子平(はやししへい)
仙台藩の北方問題への関心は、藩と関係のあった知識人の影響によるところも大きかったと考えられる。
『赤蝦夷(あかえぞ、ロシア人)風説考』の著者として知られる工藤平助は、紀州藩医の家に生まれ、仙台藩医工藤丈庵(じょうあん)の養子となって江戸に住み、青木昆陽(こんよう)や『解体新書』の翻訳に参加した前野良沢(りょうたく)、桂川甫周(ほしゅう)のような蘭学の先覚者と親交を結んでいた開明的な知識人であった。
彼らから得た知識や松前人士との接触による情報などによって書かれた『赤蝦夷風説考』は、天明三(一七八三)年に幕府老中の田沼意次(たぬまおきつぐ)に差し出されたもので、ロシアの蝦夷地進出を警告し、蝦夷地開発の必要や、ロシアとの交易の利を説き、田沼の政策に大きな影響を与えたといわれている。
その工藤平助か序文を寄せている『海国兵談』を書いた林子平(しへい)は幕臣の家に生まれたが、父が牢人(浪人)となって禄を離れた。
しかし、姉なほが六代藩主宗村の側室となった縁から兄嘉膳(かぜん)が仙台藩士に登用され、「厄介」の身分として仙台に住むようになった。 |

図81 林子平
|
子平は幾度となく江戸や長崎を訪れ、工藤平助とも知己となり、子平が天明五(一七八五)年に刊行した『三国通覧図説』に序文を書いている桂川甫周や、大槻玄沢などの蘭学者との交流をもった。
寛政三(一七九一)年、『海国兵談』が版行されると、幕府は子平を江戸に召喚し、北町奉行小田切土佐守直年(なおとし)を掛役として二著の内容について尋問を行い、ロシアの南侵や、これに触発される蒙古(もうこ)系民族による日本侵略の危険性に対する警告、弱体な江戸湾警備の指摘、地図・地理の誤りなどの諸点を糾問して、「奇怪」な「異説」を世に広めるものと断じた。
幕府老中松平定信の政権下、子平は、版木没収のうえ仙台での蟄居処分を受け、寛政五年、失意のうちに病死した。
しかし、幕末に至って対外危機意識が深まるにつれ、ロシアのシベリア開発や蝦夷地進出をいちはやく日本の対外的脅威と感知し、軍備の必要について警鐘を鳴らした子平は、先覚者として復権され喧伝されることになる。
只野真葛(ただのまくず)の『独考』
歌文集や随想・紀行文・評論に才能を発揮した女性只野真葛(一七六三〜一八二五)の父は『赤蝦夷風説考』の著者工藤平助、母も仙台藩医桑原隆朝の娘であった。
名はあや子、綾子・文子とも書いた。
華やかな家庭環境の中で育った知的に早熟な少女は、一六歳で七代仙台藩主伊達重村夫人年子(近衛氏)に仕え、さらに藩主の娘詮子(あきこ)の嫁ぎ先である彦根藩井伊家に移り、二六歳まで屋敷奉公をつづけた。
父の得意の時代は田沼意次(おきつぐ)の失脚と共に終り、彼女は失意のうちに三六歳のとき仙台藩士只野伊賀行義(いがつらよし)の後妻として嫁ぎ、仙台城下の屋敷に住むようになった。
一二〇〇石を領して中新田(加美町)に居館を構え永代着座の家格を持つ家である。
真葛が五〇歳当時に書いた自伝風の代表作『むかしばなし』は、いわゆる田沼時代の闊達な都市江戸の空気の明暗と、女性の立場から見た家父長制下のイエ(家)制度のゆがみをよく伝えている。
しかし、もっとも注目されるのは真葛が五五歳の時に書き、『南総里見八犬伝』の作者滝沢馬琴に出版の世話を依頼しようとした『独考』(ひとりかんがえ)であろう。
現在では草稿の全文は残っていないが、それでも十分に独創的な思索の跡を知ることができるし、結局は出版の世話を断った馬琴がこれを旧道徳の常識的な立場から批判した『独考論』を書いているので、これによってその一端を補うことができる(鈴木よね子校訂『只野真葛集』)。
その一例をあげれば、真葛は当時の社会を人間の本性にもとづく金銀争奪の競争社会と見ていた。
土地争奪に明け暮れてきた武士はそれを覚ることができず、中国からの借り物である儒教に縛られて、変化する時代の「天地のひょうし(拍子)」に乗り遅れ、金銀を争う町人や年貢を少なくしようとする農民の活力に押されている。
そのため、彼らに鉄製の「法の網」をかぶせようとしているが、やがてそれも錆(さび)果てて破れるだろうという。
また、男女の差は肉体には存在するが、「才知」の能力に差は無いと具体的な例をあげながら断言する。
真葛が歴史に対する鋭敏な感覚を持ち、商品生産社会の発展や資本主義原理の芽生えを的確に捉えていたことや、女性として、性差別に対する疑念と真正面から取組んで考え進めていたことを示している。
真葛は仙台城近くの屋敷で六三歳の生を終るまで、真摯な思索を続けていたのである。
地域文化のなかの養賢堂
幕末の養賢堂では門戸を広げる努力も行われた。
漢学・国学(皇学)・書学・算法・習礼・兵学・蘭学・洋学・剣槍術・柔術などの諸学科に分かれ、定員のない寄宿生のほかに一〇〇〇人以上の通学生がいたといわれるが、嘉永四年には大身武士の子弟が入学できる小学校(振徳館)を別に開校し、さらに安政四(一八五七)年には養賢堂内に日講所を設置して凡下(ぼんげ)扶持人・百姓・町人に門戸を開くなど、社会情勢の変化を反映した動きをみせている。
天保六(一八三五)年頃、養賢堂の蔵書は一一一七部、一万七一八三冊のほか地図一軸物類三四〇点ほどを数えたという。
明治維新時、養賢堂は薩摩・長州藩を中心とする奥羽鎮撫軍の宿営や仙台県時代の県庁などになり、蔵書も散逸したといわれているが、一八八一(明治十四)年、宮城書籍館に移管された蔵書の中に、オランダ語を主としてロシア・イギリス・フランス・ドイツ語の出版書二七〇冊ほどが含まれていたという。 また、医学館の構内には、文政十二(一八二九)年、青柳(あおやぎ)文蔵が寄贈した二万冊余の蔵書があり、青柳館文庫と称され、一般に公開されていた。
青柳は磐井(いわい)郡松川村の出身で江戸で医学を学んだ人物である。
儒者で『無刑録』(むけいろく)を著した芦東山(あしとうざん)や、蘭学に巨大な足跡を残した大槻一族のような学究に代表される地域の文化人もまた藩校を支える力になり、特に地方知行によって各地に居住する藩士や、その家臣たちが開設した庶民教育のための寺子屋や私塾は、この地域では大きな割合を占めており、そこで使用される養賢堂版を頂点とする仙台城下出版の各種の教科書は、地域民衆の文化の源になっていた。 |
 |

図82 大槻玄沢 |

図83 大槻磐渓 |

図84 玉虫左太夫 |
蘭学から洋学へ
嘉永三(一八五〇)年に父平泉の跡を継いで養賢堂学頭となった大槻習斎(しゅうさい)は、蘭学方を蘭学局とし、洋学科を設置した。開国後、習斎は大船建造を建言して大砲・軍艦製造御用係となり、学頭につぐ指南役であった小野寺鳳谷(ほうこく)が主任となって、洋船建造技術を学んだ気仙沼の舟大工太七らを用い、寒風沢(さぶさわ、塩竈市)で西洋式軍艦開成丸を建造したほか、大砲・小銃の鋳造を行っている。
このように、学問の府であった養賢堂は、軍制改革を支える技術の府としての機能を備えだしていたが、財政難から十分な展開はみられずに終っている。
医学館講師で蘭学局の総裁を兼ねた医師出身の小野寺丹元は長崎でシーボルトに学び、ついでロシア語を学んだ。
開国後の蝦夷地警備や、安政六(一八五九)年、蝦夷地の一部を領土として与えられたことによる経営問題など、開港場箱館を控えた蝦夷地との関係の深まりが、ロシア語への関心を強めたのであろう。
慶応元(一八六五)年に養賢堂学頭になった大槻磐渓(ばんけい)は、ロシアとの和親と交易開国論を唱えていた。
磐渓の父大槻玄沢は、石巻廻船若宮丸の乗員で寒風沢出身の水主(かこ)であった津太夫らが、寛政五(一七九三)年にアリューシャン列島の一島に漂着してロシア本土を横断し、文化元(一八〇四)年、ロシア使節レザノフに同行して帰国した体験を聴取した記録『環海異聞』(かんかいいぶん)を著している。
その次男が磐渓である。
このような事情もあってか、磐渓が嘉永六(一八五三)年に幕府に提出した『献芹微衷』(けんきんびちゅう)は、ロシアを世界第一等の強国でヨーロッパ州の盟主である「王侯貴人」の国であるとして、警戒すべき「姦商猾賈」(かんしょうかっか)のイギリスと対比している。
ロシアに対する好意的な評価は工藤平助に通ずるものがあり、イギリスに対する認識は、玄沢がイギリス船フェートン号の長崎港侵入事件ころに書いた『捕影(ほえい)問答』に通ずるものがある。
磐渓が養賢堂学頭になったとき、副役にあたる指南役統取に任じられたのは玉虫左太夫(さだゆう)であった。
左太夫は、万延元(一八六〇)年に日米修好通商条約批准のために派遣された遣米使節団に従者として加わってアメリカに渡り、有名な『航米日録』を書いている。その帰朝後、左太夫が学監に任じられていた江戸の順造館に学ぶ藩士らが、横浜のアメリカ人の宣教師で医師のジェームス・ヘボン、宣教師のサミュエル・ブラウンやジェームス・バラーなどについて英語を学ぶようになり、慶応三年にはのち日銀総裁となる富田鉄之助のほか、蔵相・首相となる高橋和喜次(わきじ、是清)ら二名のアメリカ留学生も派遣された。
左太夫は、挙国一致による富国強兵を説き、機械工業の導入や自由貿易の振興、対等外交を保障するための洋式軍事力の強化などについて論じた遺稿の中で、「人心一和(いちわ)」による国民の合意を形成して漸進的な社会経済の変革を進め、それを基礎にして政治の変革に至る道を日本の近代化の理想として描いている。
しかし、現実に勝利したのは、軍事的国家統合を急ぐ薩長勢力であり、政治的変革を優先し、その国家指導の下に急激な社会的変革を推進する道であった。
左太夫は、戊辰戦争の際に奥羽越列藩同盟の議事応接頭取に任じられ、その責任を問われて牢前切腹を命じられ、満四六歳の生を終えた。
2 仙台城下の出版業と民芸 top
仙台城下の出版
城下町仙台を通る奥州街道と深くかかわって成立した地域の文化の例として、東北地方の城下町の中でも多くの書肆(しょし、本屋)が集住してさかんな出版活動を展開していた、国分町における出版の様子と、仙台の産物の中でも、街道沿いの堤町を中心とする一帯で生産されていた堤(つつみ)人形を紹介する。
江戸時代には幕府の文教政策や、経済的な時代風潮を反映して、江戸・京都・大坂の三都を中心に活発な出版活動が開始された。
この三都に名古屋を加えた四大都市の書肆(しょし)の出版数は、全国の出版物の九九%を占めていたといわれるほど、出版活動は大都市に集中している。
これに対する地方都市における出版活動の動向をみると、書肆が一〇人以上活動している地域は、仙台・金沢・広島・和歌山・長崎・津・松坂・伊勢山田・高野山・水戸の一〇ヵ所であり、また、一〇点以上の出版物を刊行しているのを確認できた書肆は二二人であった(大和博幸「地方書肆の基礎的考察」朝倉治彦・大和博幸編『近世地方出版の研究』)。
その二二人の中に、伊勢屋半右衛門・本屋治右衛門・柳川屋庄兵衛などの仙台の書肆も含まれている。
特に伊勢屋半右衛門は一〇〇点に近い出版数をもって、その二二人の中で最多の出版数を誇っている。
彼らはいずれも国分町で出版業を営んでいた。
国分町は奥州街道と城下の主要幹線大町が交わる札の辻(別名芭蕉の辻)の北に位置し、伝馬を担当する町の一つであった。
街道を通じて様々な情報がもたらされる国分町に、最新の情報を手に入れたい版元である書肆が集中するのは必然的なことであったと思われる。
仙台における出版物として、国分町の西村治郎兵衛から明暦元(一六五五)年に刊行された『古文真宝後集(魁本大字諸儒箋解古文真宝)』が確認され、また書肆の出現は、延宝六(一六七八)年十二月八日付の記録によって知ることができるが、本格的な出版活動が行なわれるようになるのは、やはり、明和期(一七六四〜七二)以降のことである。
国分町を中心に、相沢屋甚二郎・池田屋源蔵・伊勢屋半右衛門・伊勢屋安右衛門・菅原屋安兵衛・高橋屋忠吉・西村治右衛門・宮城屋新左衛門・柳川屋庄兵衛・加志和屋正六・山田屋庄兵衛などが出版物を刊行している。
伊勢屋半右衛門は屋号を裳華房(しょうかぼう)・墨雲堂(ぼくうんどう)と称し、伊勢半と呼ばれ親しまれていた。
「嘉永辛亥年(嘉永四年〈一八五一〉)仙台高名見立競(みたてくらべ)」(『亘理伊達家文書』)にも「書林ハ伊勢半」と記されているように、仙台を代表する最大手の書肆であり、近年の調査では、その出版数は三三九点におよぶことが報告されている(渡邊慎也「仙臺書林・伊勢屋半右衛門の出版実態」 『日本出版史料』七)。 |

図85 『古文真宝後集(魁本大字諸儒箋解古文真宝)』巻頭・巻末
|
正徳元(一七一一)年刊行の『万日記尽』を最古とするが、明和期以降江戸時代を通じて出版を行い、明治時代まで活動している。
最盛期は文化期から天保期である。享和元(一八〇一)年時点では、小間物仲間に加入し(「仲間諸留写帳」 東北大学附属図書館所蔵『小谷文書』)、さらに、江戸の本屋である須原屋茂兵衛が発売した「家伝順気散」、木谷藤兵衛から売り出されていた「中橋実母散」という二種の婦人用薬も扱っていた。
西村治右衛門は本屋治右衛門と名乗り、屋号を流輝軒(りゅうきけん)といった。
享保五(一七二〇)年の『初遊松島参遊富山(とみやま)』の出版を嚆矢(こうし)とし、安永期から安政期を主たる活動期間とするが、最盛期は文化・文政期である。
文化九年正月、御書物方(ごしょもつがた)御用達であった六代栄水は養賢堂の蔵板頒回所に指名され、翌十年には国分町の仮検断を勤めている。
伊勢屋安右衛門は静雲堂(せいうんどう)と称し、伊勢安と呼ばれた。確認されている出版物はあまり多くはないが、最も古いものは文化四(一八〇七)年刊の『新板百人一首』である。万延元(一八六〇)年時点で、薬種仲間に加入し、合薬・絵具・筆・墨などの直仕入(じきしいれ)に携わっていたことが知られている(「仲間印形帳」東北大学附属図書館所蔵『小谷文書』)。
菅原屋安兵衛は静嘉堂と称し、寛政十一 二七九九)年に『錦耕商売往来』を刊行している。
菅原屋安兵衛発行の引札には書物が棚に並べられた店先が描かれ、「山本山」などの茶類を商っている様子も見てとれる。
目録上では五〇〇点以上の出版数を確認できる仙台の出版内容は、藩校や寺子屋などの当時の学校教育に密接にかかわる教科書や、大部ではない書籍、文学書などが大勢を占めている。
これが仙台における出版活動の基本的性格であった。
この基本的性格の形成には、仙台藩の藩校である養賢堂の出版方針・計画が大きく影響をおよぽしている。
文化七年に養賢堂の学頭に就任し、大規模な学制改革に着手した大槻平泉(おおつきへいせん)は、江戸昌平坂学問所の林大学頭述斎(じゅつさい)にどのような方針で改革にのぞむべきかを尋ねた。
出版について、林述斎は「手遠きものは他国から買入れ、素読などに使用される基本的な教科書を安価に手に入れることができるよう出版し、仙台藩の人々の著述で世間に有用なものを開板すべきである」と平泉に進言した。
この述斎の意見によって、養賢堂では「手近き素読等の書」である教科書類の出版が行われることになったのである。
西村治右衛門は文化九年に養賢堂蔵板の頒行所に指定され、伊勢屋半右衛門や伊勢屋安右衛門・菅原屋安兵衛なども加わって、養賢堂版といわれる出版物が刊行されていった。
養賢堂のこの方針は、仙台の書肆の出版姿勢ともなっていった。
寺子屋などで使用される教科書類や求めやすい文学書などの出版が大勢を占めることになったのである。
基本的な教科書類を主に出版するという方針であった仙台の出版は、その内容に多様性や娯楽性を伴うことができなかった。
たとえば仙台における出版物で、錦絵のような娯楽性の高い多色摺の絵画資料は見出せない。
例外的に仙台東照宮の祭礼に出された山鉾もしくは山車ともいう渡物を描いて出版した「渡物図」があげられるが、大概は墨の一色摺であり、多色摺が制作されるようになるのは明治時代になってからのことである。
城下の民芸
江戸時代の仙台藩の実体をうかがえる資料として「仙台領高名競 角力見立(すもうみたて)」と「嘉永辛亥年仙台高名見立競」の二つの番付がある。
前者は文政十二(一八二九)年に一騎(いっき)が製作したもので、相撲番付に見立てて仙台の著名なものを整理したものである。
一九四〇(昭和十五)年に仙台昔話会から復刻されたものによると、「松島」「金華山」を筆頭に、仙台藩内の様々なことがらが格付けされている。
凡例には「上段は古今とも天下に名高きもの、二段は日本にかくれなきもの、三段は諸国にあらはれたる者、四段五段は江戸又は近国にもきこへたる者」を示し、著名人であっても文政十二年の段階で生存している人は載せなかったと記されている。
そこには仙台城下の産物として、二段目に萩軸や浮き張り煙管(きせる)・仙台平(ひら)・象眼(ぞうがん)が、五段目に「荒町の団扇(うちわ)」や「通町の土人形」が取上げられている。
後者は番付という資料名が付されてはいるか、「大社ハ一ノ宮、高山ハ蔵王嶽、霊山ハ金華山、大寺ハ瑞巌寺と正法寺、御祈祷所(ごきとうしょ)ハ龍宝寺、名所ハ松島、古跡ハ中尊寺と壺ノ碑、大川ハ北上川と阿武隈川云々」ではじまる一文で、作者不詳ながら嘉永四年(一八五一)時点での仙台藩内の高名なものが二四〇項目あげられている。
仙台関係の産物としては、「張子雛(はりこびな)ハ六番丁」とか「土人形ハ八番丁」「はね兎と甘酒ハ比丘尼坂」「筆ハ又七」「名産ハ金鼠ニ紙布晴好平」「草履(ぞうり)ハ二十人町」「てう灯ハ小田原」「団扇(うちわ)ハ荒町」「浮張ハ山屋敷」「摺鉢(すりばち)ハ堤」「織物師ハ小松弥右衛門」「紙たばこ入ハ十九軒」「笊(ざる)ハ土樋士」などが紹介されている。
これらに「通町の土人形」とか「土人形ハ八番丁」と紹介されているのが、現在は「堤人形」と呼ばれている土人形のことである。
通町も北八番丁も堤町に近接することから、堤町周辺一帯で作られた人形の総称として、堤人形と呼ばれるようになったのである。
原型から採った二枚の型を用いて素焼の人形を作り、彩色するというのが堤人形の基本的な作り方である。
良質の粘土や下塗りの胡粉(ごふん)、赤色の彩色に使用する植物染料の蘇芳(すおう)などを必要とするが、窯(かま)は比較的簡便な構造のもので間に合う。
堤町は仙台城下の北の端、仙台を南北に貫く奥州街道に沿って割り出された町で、名称は町の南側の広大な堤に由来する。
少なくとも寛文九(一六六九)年までには成立していたとされ、城下の警衛のため足軽が配されていた。
足軽たちは弓隊に属しており、明治三(一八七〇)年の記録では三番卒十四番組と同十七番組に編成されていたことが知られる。
付近一帯は良質の粘土を産することから、足軽たちは副業として堤焼や瓦・堤人形を製作するようになった。
前述した記録にも、芳賀養吉(はがようきち)や松根勝三郎・庄司乾馬(けんば)・針生(はりう)祐蔵など窯業で活躍した人々の名前を見出すことができる。
堤焼の創始は、仙台藩四代藩主伊達綱村(つなむら)が元禄年間(一六八八〜一七〇四)に江戸から陶工の上村万右衛門(〜一七一五)を招いて、奥州街道の東側の杉山台において陶器を焼かせたことによるとされている。
綱村は元禄十(一六九七)年二月に頻繁に杉山台を訪れ、元禄十二年正月二十一日には仙台焼の灰器を用いた茶会を催している。
また、五代藩主吉村は宝永元(一七〇四)年に、叔父の稲葉正通に仙台焼灼碌(ほうろく)底取二組を贈っており、元禄期の杉山台における窯業の開始を推測することができる。
その後、杉山台の粘土の枯渇に伴い、生産の中心は奥州街道沿いの堤町をはさんで東方の杉山台から西方の北十番丁・同八番丁・通町の一帯へ移動する。
「通町の土人形」とか「土人形ハ八番丁」と記されるのは、そのような活動の場の移動を推測させる。
堤人形は天神の像を作り始めたのが最初といわれている。
しだいに年中行事にかかわる雛人形や恵比寿・大黒像が作られるようになり、さらに、芝居に関するものなども加わり、多様な内容になった。
文化・文政期には著名な人形産地として他地方に影響を与えるほどになっている。
現存する最古の型は寛延元(一七四八)年銘の「政岡」(まさおか)と称される人形の型で、堤人形の工人として高く評価されている初代庄司勇七の作品である。
政岡は、演劇「伊達騒動もの」に登場する女性である。
事件そのものは江戸時代前期に起きた仙台藩内の政争で、この事件に取材した演劇は事件から四〇年余が経過した正徳三(一七一三)年に、江戸市村座で「泰平女(たいへいおんな)今川」としてはじめて上演された。
その後、この種の歌舞伎や浄瑠璃が演目を変えて、頻繁に上演され、現在行われているような伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)のような物語・登場人物などに整理されていく。
政岡の型が制作された寛延元年十一月一日には、江戸市村座において、一変形である「放下僧(ほうかぞう)弓勢鉢木(ゆんぜいはちのき)」が上演されていた。
この公演にヒントを得て現在称するところの政岡の人形が作られた可能性も考えられる。
寛政四年六月銘の「谷風・小野川」の型は、二代庄子勇七が制作したものである。
この人形は仙台出身の名横綱の二代目谷風梶之助(一七五〇〜九五)と宿敵小野川との対戦の様子を人形にしたものである。 |

図86 堤人形 政岡
|
谷風は第四代横綱で、安永六(一七七七)年の春場所から四年間にわたって不敗の快記録六三連勝を樹立するなどの活躍を見せた。
谷風の活躍によって相撲の人気は高まり、谷風を描いた様々な錦絵も出版されていた。
そして寛政三年六月には江戸で将軍徳川家斉(いえなり)の上覧相撲が催され、小野川に勝利した谷風の名声はさらに高まり、この堤人形「谷風・小野川」が作られた。
堤町周辺の人々は政岡や谷風についての情報をどのようにして得ていたのであろうか。
奥州街道沿いに住む堤町の人々には、街道を往来する人々から雑多な情報がもたらされたであろう。
また、初代庄司勇七の孫庄子勇吉は五二年の出仕期間に、参勤交代の供を二回命じられているように、参勤の機会に江戸の町の実態を肌で感じることがあったかも知れない。
いずれにせよ、堤町にもたらされた最新の情報をもとに、人形は制作されたのである。
ところで、最新の情報をもとに堤人形が作られたとして、人形を購入する側はその情報を理解していたのであろうか。
仙台の場合、城下の六ヵ所の神社(三月三日木下白山神社、四月八日榴ヶ岡(つつじがおか)釈迦堂、六月一日荒町毘沙門天、六月二十五日榴ヶ岡天満宮、八月十五日大崎八幡神社、九月十七日東照宮)の祭礼の場合にかぎり、晴天一〇日間の相撲や芝居や見世物の興行が許されていた。
芝居だけでも仙台城下では少なくとも年間六〇日間の興行が行われていることになる。
東照宮の祭礼の場合、豪華な渡物(わたしもの)が練り歩く城下を代表する祭であり、毎年行われていたわけではないが、江戸時代中期の事例をみると、東照宮の別当寺である仙岳院では毎年神事が行われており、角力(すもう)や腰に人形を付けて演じる操(あやつり)芝居の興行は祭礼の有無にかかわらず行われていたらしい(水野沙織「宝暦年間の興行事情――宮町での角力・操芝居――」『市史せんだい』一三)。
このことからも仙台地方においても最新の演劇情報を受容する素地が確立していたことが想像できる。
最新の情報を盛り込んで制作された堤人形は街道を通って販売され、購入され、広がっていった。
その様子は、堤人形などが高く評価され、収集家がこぞって収集を始めた昭和初期に、それらがどの地域から収集することができたかという記録によって知ることができる。
一九三二年頃から東北地方の人形を収集した大阪出身の本出(ほんで)保治郎の記録によると、実際に収集にあたった本出の代理人は、人形を探出した箇所を記録した地図を一九三八年に本出に提出した。
その地図「尾花沢」(おばなざわ)には「赤線は歩いたところ 赤太点三春張子 紫泥人形類(堤その他)」、地図「黒沢尻」(くろさわじり)には「鬼柳町 旧南部領以北花巻人形 相去町 旧仙台頷以南 堤人形」と書込みされていた。
この書込みは尾花沢(山形県尾花沢市)地区では三春人形と堤人形などが収集できたこと、黒沢尻(岩手県北上市)地区では、旧盛岡藩領では花巻人形が、旧仙台藩領では堤人形が収集できたことを示している。
これらから堤人形の販路および分布範囲は仙台藩領とその周辺となることがうかがえる。
なお、尾花沢地区における三春人形の収集は特殊な例であり、何らかの事情が働いた結果のことと思われる。
ここで取上げた仙台の出版物と堤人形は全く異質のものである。
しかし、ともに街道を介してもたらされる情報と深いかかわりを持っているという点で共通性はある。
本来の場所から動かすことが容易なこれらの資料ではあるが、逆に江戸時代における収蔵状況を確認することによって、さらに情報とのかかわりの深さが確固たるものになるだろう。
今後の所在調査に期待したい。
3 民衆的語り物とその民俗的基盤
top
飛来する白鳥
奥州刈田(かった)・柴田(しばた)両郡の人々にとって、この地に飛来し飛翔する白鳥は、白鳥明神の化身であった。
柳田国男によれば、「白鳥の奇瑞(きずい)といふことは、両所(刈田郡・柴田郡)の信仰の最も主要なる部分であった。
つい近頃になるまで此地方一帯に、非常に白鳥を崇敬して其飛翔を見ても拜をなし、追うたり捕へたりせぬは勿論、たまたま誤って其肉を食べた者と合火(あいび)しても、忽(たちま)ち大熱を発し又は口中が腫れ痛むとさへ畏れて居たのも、全く神が時あって此鳥の形を仮りて、去来したまふことありと信じて居た結果と思はれる」と述べている(『伝説』)。
こうした白鳥信仰が古くからあったことは、伊達政宗が息子の忠宗に宛てた一六二五(寛永二)年の書状に、白鳥を鉄砲で撃つことは刈田郡「白石計(ばか)りは無用に候」と記していたことから明らかである。
藩主ですら、地域民衆の白鳥信仰への配慮を余儀なくされたのである。
白鳥伝説
刈田・柴田両郡の蔵王山麓には白鳥明神を祀る多くの白鳥社が分布し、白鳥明神の由来説話である白鳥伝説が広く流布していた。
たとえば『奥羽観蹟(かんせき)聞老志』(享保四〈一七一九〉年序)には、白鳥社の一つである柴田郡平村の大高宮(大鷹宮)の祭神の由来を説いた縁起が紹介されている。
それは次のようなものであった。
遠い都から橘豊日尊(たちばなのとよひのみこと、以下、用明天皇と記す)が訪れ、当地の玉倚姫(たまよりひめ)を娶った。
ある晩、玉倚姫は、白鳥の姿を借りて飛来した男神が彼女の心の中に入る夢を見て懐妊した。
一年後に若君が誕生すると、用明天皇は愛する妻子をおいて帰京した。
都に呼び寄せるという約束があっかにもかかわらず、三年の間音信がなく、玉倚姫は悲嘆に暮れて衰弱した。
|

図87 白鳥宮
(本山明神社、白石市福岡深谷)
|
それを哀れんだ乳母(うば)は、夫婦の再会を願って、男神の生まれ変りである若君を川へ投げ捨てた。
すると、若君は白鳥の姿となって飛び去った。
しかし、玉倚姫は用明天皇との再会という切なる想いを遂げられずに最期(さいご)を迎え、乳母も亡くなった。
その後、玉倚姫の墓陵に白鳥が再来し泣きやまなかったので、不審に思った村人がこのことを都へ報告した。
用明天皇の哀惜(あいせき)の念が伝えられると、玉倚姫の霊は和(なご)んで白鳥(一説に白鷹)と化し、墓陵から飛上った。
用明天皇はそこに白鷹社を建て、玉倚姫の霊を神として祀った。これがのちに大鷹宮と呼ばれるようになったというのである。
この縁起は大高宮(犬鷹宮)の祭神を、遠来の用明天皇との愛に苦悩して亡くなり、白鳥(一説に白鷹)と化した女性の霊とする説話であった。
中世社会では「夫婦の愛の深さと、それゆえに主人公の受ける苦難と、その苦難のゆえに神になれる資格を得たことの三つを中心的主題」としたいくつもの縁起が生まれ、民衆に広く受容されたという(齊藤利男「中世における正統イデオロギーと民衆的認識の世界」)。
従って、この白鳥明神の由来説話は中世的なものであるといってよい。
白鳥伝説の広がり
柴田郡には若君(御子神=みこがみ)を祀る村田白鳥神社や、乳母(うば、姥神)を祀る足立村の乳母祠もあった。
白鳥と化した用明天皇の妻だけでなく、白鳥の姿となって飛翔した若君(御子神)も白鳥明神として信仰の対象となっていたのであり、柴田郡では白鳥を「『和子(わこ)さま』という『殿の若子(わくご)』を思わせるような親愛な呼び方」をすることもあった(谷川健一 『神・人間・動物』)。
さらに、こうした白鳥伝説が刈田郡でも語られていた。刈田郡宮村の松川のほとりにあった刈田宮の祭神の由来について、『奥羽観蹟聞老志』には、「郷党相伝よ、此の神すなわち用明帝の后妃(こうひ)、薨(こう)じて白鳥と化す、土人祠(ほこら)を建て之を祀る、水早疾疫必ず祈りて験(げん)有り」と記されている。
このように水の女神である刈田宮の祭神を、やはり愛に苦悩して亡くなり、白鳥と化した用明天皇の妻とする説話が語られていたのである。
ただし、刈田宮を建てたのは用明天皇ではなく、村人であったという。
また、刈田郡には若君(御子神)を祀る深谷村の本山明神社や長袋村の「児宮社跡」(安永六〈一七七七〉年の『風土記御用書出』)もあり、若君を投げ捨てたと伝えられる児捨(こすて)川もあった。
これらのことから「結婚と別離」「愛と受難」を主題とする白鳥明神の縁起、すなわち母子神の由来説話が刈田・柴田両郡に広く流布し、人口(ひとのくち)に膾炙(かいしゃ=話される)していたことがわかる。
中世の秋祭りと白鳥伝説
では、こうした白鳥伝説はどのようにして生み出されたのであろうか。
その民俗的基盤の一つというべき中世末期における刈田宮の秋祭りについてみてみよう(鯨井千佐登『境界紀行』)。
この祭りは天正年間(一五七三〜九二)の末に廃止されてしまったが、近世初頭に至るまで、地域民衆は毎年刈田宮へ産着(うぶぎ)を奉納しつづけた。
それは刈田宮の女神が古くは毎年出産を繰返す母神だったからである。その祭りは、具体的には次のようなものであった。
刈田宮の近くの「市屋敷」に住んでいた市という巫女(みこ)が、「内方(うちかた)屋敷」(「内方」は妻を意味する)で身を清めたのち、刈田宮の女神に成り代わって、九月八日から九日にかけての深夜に刈田宮を訪れた男神との神婚を演じた。
九日には神輿(みこし)を刈田宮から祭場となる河原(松川と白石川の合流地点)へ渡し、「内方屋敷」で用意した神饌(しんせん)や流鏑馬(やぶさめ)を奉献することによって、御子神の誕生を祝い、これを祭場から送り出した。
渡り鳥の白鳥が飛来しだのに、ちょうどこの祭りがとり行われていたころである。
つまり、女神が水辺で出産し、誕生した御子神が白鳥の姿を借りて飛翔すると信じられていたのである。
このように、中世末期における刈田宮の秋祭りの内容は、
①男神の来訪、
②女神(巫女)との結婚、
③御子神(男神の生まれ変わり)の水辺での誕生、
④水辺での神送り、
⑤白鳥の姿をした御子神の飛翔というものであった。
もちろん、こうした神婚を演じ御子神の誕生を祝う祭りは古くは普遍的なもので、刈田宮に限らなかったであろう。
これに対して白鳥伝説では、
①男神の来訪、
②玉倚姫(たまよりひめ)との結婚、
③若君(御子神)の誕生、
④若君(御子神)の川への投棄、
⑤白鳥の姿をした御子神の飛翔などが語られていた。
このように、白鳥伝説のモチーフの一つと祭りの内容は完全に一致する。従って、白鳥伝説は刈田宮などの中世の秋祭りをふまえてつくられたといってよい。
また、訪れる男神を用明天皇に、女神(巫女)をその妻に見立てれば、白鳥伝説の骨格はできあがる。
つまり、白鳥伝説における用明天皇と玉倚姫の「結婚と別離」は、男神と玉倚姫の結婚や若君の川への投棄(子捨て)と同様に、秋祭りにおける神婚と神送りが投影されたものであった。
では、なぜ男神を用明天皇に見立てたのであろうか。柳田国男はこの点について、それは「他でも無い。人界に在って最優れたる王子、廐戸(うまやど)皇子の御父であった為」と述べている。
柳田がいうように、用明天皇が神々しい若君の「この世」における父として最もふさわしかったからであろう。
巫女の巫祖祭文
白鳥伝説のなかの用明天皇の妻は、刈田宮などの秋祭りの重要な担い手であった巫女自身でもあり、巫女の遠祖とでもいうべき存在であった。
こうした巫女が、刈田宮や大高宮の祭神を巫女の遠祖とする白鳥伝説、つまり巫祖祭文を語りはじめ、それが刈田宮や大高宮の縁起として定着したのである。
なお、白鳥社の祭神説の中には、白鳥明神を前九年の合戦に従った安倍一族の白鳥八郎とするものもあった(平川新『伝説のなかの神』)。
この祭神説は白鳥信仰に白鳥八郎の御霊(ごりょう)信仰が結びついた結果、生まれたものであろう。
人口(ひとのくち)に膾炙(かいしゃ=話される)した白鳥伝説は、もとは祭神を巫女の遠祖とする巫祖祭文であったと考えられ、目の不自由な巫女は一度つぶして作り替えた声、シャマン特有の喉声(しゃがれ声)でこれを語ったのである。
御産会の神事と舞台の舞
神婚を演じ御子神の誕生を祝う中世の秋祭りは広くみられたが、近世になってもそれに類する神事が少なからずみられた。
『奥羽観蹟聞老志』によると、名取郡の岩沼の人々にとっては、狐が神の化身であった。
この稲荷神を祀った岩沼の稲荷社(竹駒神社)では、大晦日の頃にあたる立春前夜、つまり節分の夜から社殿の背後にある岩穴の「御室」(「宝窟」)において「御産会の神事」がとり行われた。それは次のようなものであった(『竹駒寺年中行事抜書』)。
寛保二(一七四二)年の事例であるが、まず枕二つを「御室口」へ献納した。
二つであり、これを「安産の御枕」といったから、「御産会の神事」が男女二神の結婚と御子神の誕生を意味していたことは間違いない。
しかしその重要な担い手は、もはや巫女ではなく、精進潔斎(しょうじんけっさい)を済ませた「年男」(としおとこ)であった。
節分の夜から七日間、岩沼では歌舞音曲など一切の鳴物(なりもの)が禁止され、ちょうど一週間後の早暁(そうぎょう)に御子神が誕生したのである。
岩沼の人々は「御室」に大きな白狐の姿を借りた女神がおり、「御産会の神事」によって誕生した御子神も狐の姿をしていると考えていた。
狐が人里に現れたのは冬で、それは白鳥の場合と同様であり、どちらも神の化身であった。
刈田郡「白石ニハ白鳥ノ宮有テ白鳥ヲ恐レ尊フコト、此土ノ狐ニ同ジ」(『仙台聞見録』天保十一〈一八四〇〉年成)といわれており、稲荷信仰と白鳥信仰との間に本質的な違いはなかった。
このような年の変り目や九月という稲の収穫期の祭の中で誕生した御子神、つまり神威を更新した男神は、元来は稲の精霊=穀霊であるとされ、そうした穀霊の霊威の更新やその増殖によって土地の稔りが保証されると信じられていた。
また、御子神が白鳥や狐などの冬の動物の姿を借りるとされていたのも、元来は稲の種子が倉に保存されている間は、穀霊が種子から容易に遊離し、白鳥や狐などの姿を借りて人前に現れると信じられていたからであった。
従って、九月九日の刈田宮の秋祭りは単なる稲の収穫祭などではなく、男神の神威の更新をはかり、翌年の稲の豊穣(ほうじょう)を祈願するものであった。
そのほか、名取郡熊野堂村の熊野神社における九月の祭りでは、古い歴史をもった「舞台の舞」が演じられた。
それは開闢(かいびゃく)の舞からはじまり、龍王の舞、二柱(ふたばしら)の舞、稚児(ちご)の舞、太平楽と続くものである。
これらのなかの二柱の舞は、「尉と姥との仮面を被(かず)き舞ふ」、「をとこ女のふるまひなどする、をかしきわざをす」といわれており(『奥州名所図会』)、水上の舞台の上で神婚が演じられた。
二柱の舞、稚児の舞、太平楽と続くところからも、神婚→御子神の誕生→豊かな未来というように受取られていたことが推察される。 |

図88 二柱の舞
(『奥州名所図会』
|
笠島の道祖神と実方伝説
名取郡笠島村の道祖神も女神で、特に子授けや安産、縁結びの神として知られ、慶長年間(一五九六〜一六一五)に廃止されてしまった九月の祭りでは神婚儀礼がとり行われていたようである。
また、小正月の祭りや個人祈願の際には、訪れる男神の象徴としての男根の模型が奉献された。
これは男女二神の結婚によって豊かな未来が約束されるという観念にもとづくもので、神婚を意味していた。
ところで、白鳥伝説は巫女が語り始めたものであったが、笠島の道祖神の由来やその神威、さらに左近衛中将藤原実方(さねかた)の雀(すずめ)への転生などを説く実方伝説もそうであったかもしれない。

図89 道祖神社 |

図90 実方中将の墓 |
『源平盛衰記』(巻の七)には、大略次のような伝説が記されており、それは名取の里にも古くから流布していた。
笠島の道祖神(どうそしん)は京都の出雲路の道祖神の娘で、親の意思に反して商人と結婚したため、勘当されて奥州に追われてきたのを、名取の里人が崇敬して祀り始めた。
これに男根の模型を供えれば、どのような願いごともかなえてくれる。
そうした霊験あらたかな女神であるにもかかわらず、陸奥守の実方中将は里人の忠告を聞かずに、社前を馬上で通行したため、神罰にあたって馬もろとも死んでしまった。
そして、亡くなった実方の霊は雀と化したというのである。
京都の出雲路の一帯は北畠(きたばたけ)と称し、中世には唱門師(しょうもんじ)の居住地として有名であった。
この唱門師の配下にあって、出雲路の道祖神と深く結びついた巫女がいたらしい。
実方伝説では、出雲路の道祖神の娘が親の意思に反して商人と結婚したため、勘当されて奥州に追われてきたなどと擬人化されて語られていたが、それは巫女が自身の姿を重ねて、この伝説を語り歩いていたからではなかろうか。
もしそうであれば、そうした伝説が『源平盛衰記』に採録されたということになろう。
伝説の機能
名取の里に流布していた近世前期の実方伝説では、より具体的に出雲路の道祖神の娘が当地で亡くなったと語られていた。
白鳥伝説の主人公も、愛に苦悩して亡くなった女性であった。
地域民衆はこうした伝説を聞くたびに、彼女たちに同情し、生前に受けた苦難にかえて彼らの心願をかなえる女神であると了解したことであろう。
しかも実方伝説では、不敬をはたらいた実方中将を馬もろとも殺したとされていた。
つまり、笠島の道祖神は国守という権威的存在に神罰を下すほどの霊験あらたかな女神だったのである。
このように「結婚と別離」や「愛と受難」、また荒々しさを語るこれらの伝説は、神々の神威を保証していたのである。
塩竈明神の縁起
中世後期の奥州では、奥州一宮の塩竈社に祀られた塩竈大明神を花園少将とする独自の縁起が広く受容されていた。
この縁起の主題も「結婚と別離」「愛と受難」にあった。
すなわち、花園少将とその妻さわらび姫の愛の物語であり、二人の別離、さわらび姫の苦難、夫婦の再会、子の文殊王の流浪、文殊王を想う両親の愛情など、全く民衆的といってもよい話ばかりであった(齊藤利男・前掲論文)。
おそらく、この縁起も歩き巫女たちによって語り広げられたものであろう(入間田宣夫「塩釜大明神の御本地」)。
祭文から御国浄瑠璃へ
この塩釜大明神の本地譚(ほんじたん)は、近世になると目の不自由な座頭(ざとう)によって語られるようになった。
その点は、坂上田村麻呂(さかのうえたむまろ)伝説の場合も同様であった。
近世社会では、巫女は修験者や座頭と夫婦であることが多く、妻の語り物から夫のそれに移行したともいえよう。
中世の馬牧には巫覡(ふげき)の徒が多く集まり、廐祓(うまやはら)いや口寄せなどを生業とする巫女の門付け芸のなかから、巫祖祭文を原型とする多彩な語り物が生まれたといい、白鳥伝説が生み出された中世の刈田郡にも馬牧が点在していた。
本項ではこの白鳥伝説を事例として、中世の秋祭りと巫祖祭文との密接な関係についてのべたが、「田村」などの語り物や社寺縁起、その原型をなした巫祖祭文などの物語構造を巫女の成巫儀礼から説明する福田晃氏の有力な学説がある。
本項でのべた諸伝説についても、そうした視点からの再検討が求められるかもしれない。
ところで、異賊・悪鬼退治を主題とする坂上田村麻呂伝説でも、主人公の田村麻呂と伊勢国鈴鹿山(すずかやま)に住む天女鈴鹿御前との行逢(いきあ)いと結婚、鈴鹿御前の援助による田村麻呂の活躍などが、重要なモチーフをなしていた(斉藤利男二剛掲論文)。
つまり、田村麻呂は鈴鹿御前の愛に包まれ、その庇護(ひご)のもとに手柄を立ててゆくのである。
また、田村麻呂伝説において注目すべきは、対立んじする天皇に鈴鹿御前が次のような言葉を発していることである。
「いかに天王、さても汝(なんじ)、日本にて神の司、十善とや、我は天竺(てんじく)は梵天(ぼんてん)の生まれにて、大千世界の司に有し我なれば、此国の帝王など物の数とも思はれじ」(『三代田村』)。
このように田村麻呂伝説では、
①夫婦愛が重要なモチーフをなし、
②女神が公的な権威や価値を超越する存在として語られていた。
前者は本項でみてきたどの縁起とも一致し、後者は笠島の道祖神の場合と一致する。
これらの点に関連して想起されるのは、刈田宮の白鳥明神や笠島の道祖神などのもとの姿が、天皇や親という権威的存在に翻弄された不遇な女性だったことである。
このように、どの伝説も世俗的な権威の対極に位置する社会的弱者の側から構想されたものであった。
こうした田村麻呂伝説の語り手は古くは巫女、近世になれば座頭であった。座頭の語り物は御国浄瑠璃と呼ばれ、その声は巫女が口寄せをしたり、祭文を語ったりする時の喉声(しゃがれ声)の影響を受けていた。
つまり、平曲・謡曲の声明系の含み声としゃがれ声との中間音で語ったのであり、この点にも民衆的語り物の伝統の継承を見て取ることができよう。
4 伝説と神々の変貌 top
白鳥明神の変貌
元禄・享保年間(一六八八〜一七三六)になると、ヤマトタケルが東征の帰路亡くなり白鳥と化したという記紀神話をふまえて、刈田・柴田両郡の白鳥社では新たな縁起が作成され、祭神がヤマトタケルとその生まれ変わりにおき換えられた。
たとえば、仙台竜宝寺の梅国実政(ばいこくさねまさ)が享保元(一七一六)年に撰述した刈田宮の縁起では、祭神の由来が次のように説明されている。
すなわち、ヤマトタケルが当地を訪れ、一人の女性の歓待を受けたのち帰京するが、その途次亡くなって白鳥となる。一方、この女性の産んだ子は村人によって川に投げ捨てられ、父と同様に白鳥となって飛び去る。その後、祟りがあったので、若君は村人の手で神として祀られたが、ヤマトタケルも仲哀(ちゅうあい)天皇や坂上田村麻呂らの尽力で合祀されるようになったというのである。
この縁起では、地方妻の「愛と受難」のことなど一顧だにされなかった。こうした白鳥伝説の改作と祭神の軍神への改変は、国家の正史(せいし)である記紀といった公的な権威をもつ文献にもたれかかったものであり、「白鳥卜化シ玉ヘルハ日本武尊ノ神霊也、殊ニ武尊ハ東夷征伐シ玉ヒシ事アレハ、武尊ヲ祀リタリトイハヽ信スヘシ」(『江都道中記略』元禄十〈一六九七〉年成)という「歴史の知識」への対応であった。
笠島の道祖神の変貌
同様にして、笠島の道祖神も記紀神話にみえるサルタヒコにおき換えられた。
仙台藩の儒者佐久間洞巌(どうがん)は、熊本藩士井沢蟠竜(ばんんりゅう)の『広益俗説弁』(こうえきぞくせつべん、正徳五〈一七一五〉年刊)の指摘を受けて『笠島道祖神記』(享保来年成)を著し、実方伝説を否定した。
彼は出雲路の道祖神の娘と商人の結婚が正史などの公的な権威をもつ文献にみえないことから、笠島の道祖神は出雲路の道祖神の娘であるはずがなく、もし俗説の通り親の意思に反して商人と結ばれたとすれば、法的にも道徳的にも容認できない「淫奔(いんぼん)の罪」を犯した「淫祠」(いんし)になってしまうと述べている。
また、実方中将の死も偶然の事故にすぎず、もし俗説の通りなら、死という根源的な脅威をおよぼす「邪神」になってしまうとも述べている。
このように佐久間洞巌は古くからの伝説を否定し、その上で当時出雲路の道祖神がサルタヒコとされていたことなどを根拠にして、笠島の道祖神もサルタヒコを祀ったものであると断定した。
この縁起が広く流布し、のちには私撰の地誌によって、東征の旅路にあるヤマトタケルが勧請したサルクヒコ、あるいは大和政権による蝦夷征討に協力して、ヤマトタケルを嚮導(きょうどう)したサルタヒコなどという新たな性格まで付与されるようになった。
塩竈明神の変貌
さらに、塩竈社に祀られた塩竈大明神を花園少将とする奥州独自の縁起も否定され、元禄六(一六九六)年、藩主伊達綱村は塩竈社に祀られた祭神をタケミカヅチ、フツヌシという軍神と岐神(ふなどのかみ)の三神とする縁起を正式に採用した。
これまた、記紀という国家の正史に依拠したものであった。
以上のような祭神の改変は、大局的にいえば、地誌や藩史の編纂、領内の名所・旧跡整備などと共に、中央の貴顕の文化に連なることで、「僻地陸奥国の仙台領が決して卑俗非文化の地でないことを立証」(平重道「『封内風土記』解説」)しようとする仙台藩の文化政策に規定されたものであった。
すなわち、国家の正史や中央の文化のもつ権威や価値を自明なものとみなし、それを優先させる発想によって、「結婚と別離」「愛と受難」を主題とする土着の伝説が否定され、神々は国家の権威を体現する男神に改変されたのである。
故将堂(こじょうどう)伝説の変容
つぎに故将堂伝説についてもみてみたい。
『奥羽観蹟聞老志』(享保四〈一七一九〉年序)によれば、刈田郡斎川(さいかわ)村の故将堂に祀られた甲胄(かっちゅう)姿の二体の木像を、地域民衆は田村麻呂と鈴鹿御前としていたという。
この田村麻呂と鈴鹿御前は、夫婦愛を重要なモチーフとする御国浄瑠璃を語った座頭と巫女の夫婦が投影されたものであったかもしれない。
もっとも、元禄年間(一六八八〜一七〇四)の道中記(旅日記)によれば、二体の木像は佐藤庄司(しょうじ)の二子、継信(つぐのぶ)と忠信(ただのぶ)の妻たちであったという。
源義経の平家討伐に従軍した夫の甲胄を妻が着用して舅の前に現れた話は、中世以来の語り物である『尼公(にこう)物語』にみえるが、世上に流布していたこの話にもとづき、十七世紀後半以降の藩による名所・旧跡整備の過程で、甲胄姿の二体の木像を経信・忠信の妻たちとする祭神説が喧伝されるようになったのかもしれない。
『奥羽観蹟聞老志』はこの祭神説を採用している。
『封内名蹟志』(寛保元〈一七四一〉年序)も同様であったが、この地誌は嫁たちが夫の甲胄を着用して、二人の息子の帰国を待ちわびる舅姑を慰めたとしている。
これに対して御国浄瑠璃の『尼公物語』では、臨終の間際にある佐藤庄司への妻(姑)の思いやりの方に重点があり、嫁たちは姑の指示に従って甲胄を着用したにすぎない。
つまり『尼公物語』では、御国浄瑠璃の『三代田村』などの場合と同様に、夫婦愛が重要なモチーフをなしていたのである。
このように近世中期になると、田村麻呂と鈴鹿御前の伝説に代えて、もっぱら佐藤庄司の物語、それも御国浄瑠璃の原型から離れ、舅姑に孝行を尽くした嫁たちの話によって、二体の甲胄像の由来が説明されるようになった。
いわば伝説からの夫婦愛のモチーフの欠落であるが、伝説はさらに変容してゆく。
天明六(一七八六)年に故将堂を訪れた京都の医師橘(たちばな)南渓が、『東遊記』の中で紹介した伝説は、嫁が亡き夫の甲胄を着用し、二人の息子の死を悲しんで沈んでいる姑を慰めたというものである。
このように伝説が舅姑両者への孝行から、姑への孝行を称揚する話に変容しているのである。
のちの『新撰陸奥風土記』(安政七〈一八六〇〉年序)では、「郷人伝えて曰わく、二女の木像佐藤次信志信の婦なり、共に舅姑に孝順なり、姑老いて次信兄弟の帰るを待ち侘びて、まさに死なんとしける時、両婦甲冑を着て、次信忠信今帰り侍りといいて、其の心を慰めけるを木像にうつして祀りけるなりという」とされており、ここでは継信・忠信兄弟の無事な帰りを待つ嫁と姑といった設定である。 |

図91 甲胄堂
|
要するに、故将堂の二体の由来を説明する伝説から夫婦愛の要素が除かれ、嫁たちの孝行の物語へ、それも姑に対する孝行の物語によって、二体の由来が説明されるようになったのである(日下龍生「白石市斎川甲胄堂再建と甲胄堂伝説の変容」)。
嫁と姑の関係
舅姑に対する嫁の孝行は儒教道徳の根幹をなし、近世社会における公的な規範であった。
しかしそれにしても、特に姑に対する嫁の孝行が称揚され喧伝され始めたのは何故であろうか。
嫁と姑は家族内では役割継承の関係にあったから、その間に葛藤が生じやすかった。
しかも、老親の扶養介護における嫁の役割への期待も大きかった(柳谷慶子「近世家族における扶養と介護」)。
しかし、嫁の負担が過重にならず、夫婦関係と親子関係が両立している時代は、嫁姑関係は必ずしも深刻なものとならなかった。
ところが、十八世紀後半になると、宝暦飢饉や天明飢饉などをきっかけとする農村荒廃によって、老親の病気や貧困という問題が切実さを増し、看病・介護・扶養などの負担が嫁に重くのしかかるようになった。
また、夫は夫婦関係よりも親子関係を優先させざるをえなくなった。
十八世紀後半の事例であるが、「先年両度娶(めと)り申し候妻も母の心に合い申さざる事これ有り、離縁致し候間、亦以て娶り候ても却って母の苦労に相成るべきも計り難し」と述べて、結婚せずに母に孝首を尽くした息子が藩から表彰されている(『封内忠孝等之者書上』五)。
このように、公的には夫婦関係よりも親子関係(擬制的親子関係)を支える徳目が重視されていたのである。
その結果、特に嫁と姑との間に深刻な葛藤が生じるようになったのであるが、だからこそ、姑に対する嫁の孝行が称揚され喧伝され始めたのである。
故将堂伝説の機能
幕府や藩は老親の看病や介護・扶養などを家族の私的な問題であるとして、公的扶助を恒常的には行わなかった(柳谷慶子、前掲論文)。
故将堂の二体の由来説話である嫁たちの姑への孝行の物語は、嫁のよりいっそうの献身を引き出し、幕府や藩による公的扶助の欠如と嫁への押付けを免罪する機能を果たしたといってよい。
御国浄瑠璃の田村麻呂伝説や『尼公物語』から大きく乖離(かいり)した故将堂伝説は、為政者や知的エリートら社会的支配層によって喧伝された。
『奥羽観蹟聞老志』をはじめとする地誌の類や『東遊記』などの道中記の類は民間社会に大きな影響を及ぼした。
もちろん、新しい伝説を口にする社会的支配層の声は、祭文の喉声(しゃがれ声)やその影響を受けた御国浄瑠璃の伝統的・民衆的な声などではなかった。
こうして白鳥明神から故将堂の二神にいたるどの祭神も、国家の秩序や制度を奥州にもたらし、それを聖化する神々、あるいは儒教の家族道徳に従順な神々に改変された。
つまり、公的な権威を体現する神々への変貌を余儀なくされたのである。
総力戦の下支え
『東遊記』の記事が国定教科書に掲載され、継信・志信の妻たちを祀る甲胄堂(故将堂)が再建されたのは昭和十年代であった。
姑への孝養を尽くした妻たちの姿は、嫁と姑が手を携えて銃後(じゅうご)を守り、兵士となった夫や息子の戦功を信じ、夫亡きあとも家を守る女性たちのあるべき姿となった(日下龍生・前掲論文)。
そして兵士が命を捧げるべきものは、変貌を余儀なくされた地域の神々により、まさしく聖化された国家にほかならなかった。
5 民衆的伝統の継承と発展 top
白鳥伝説と実方伝説
元禄・享保年間(一六八八〜一七三六)に新たな縁起が作成されても、白鳥伝説は消失しなかった。
刈田郡では、用明天皇の来訪譚がヤマトタケルのそれに代わり、刈田宮の祭神がヤマトタケルとその息子に改変されはしたものの、そうした祭神の由来譚(ゆらいたん)としての性格を薄めながら、地域民衆の間では「結婚と別離」「愛と受難」を主題とする地方妻の悲恋物語として語り継がれた。
柴田郡では用明天皇の来訪譚がそのまま残り、やはり祭神の由来譚としての性格を薄めながら語り継がれた。
また、実方伝説も消えてしまうことはなかった。
『嚢塵埃捨録』(のうじんあいしゃろく、文化八〈一八一一年序)には、「当社は女神なりとて心願あれば、陰茎を作りて捧物とするは甚非礼なり、斯妄説を世伝するに因て、児婦の族専是を説聴せり」とある。
実方伝説を「妄説」とし、男根の模型の奉納を非礼としているのであるが、その一方で、実方伝説は女性と子供たちによって語り継がれており、男根の模型の奉納という素朴な習俗も失われてはいなかった。
つまり、女性と子供たちは公的な権威から相対的に自由な伝統的世界を保持していたのである。
このように、民俗的なものがすべて抑圧しつくされたわけではなく、古くからの伝説が確実に生きていた。
それは塩竈(しおがま)大明神の本地譚の場合も同様で、御国浄瑠璃の一曲として、座頭(ざとう)によって語り継がれた。
御国浄瑠璃
御国浄瑠璃は近世民衆の娯楽として愛好された。
座頭は「村方修行と称して村々を廻」り、村役人宅に宿泊したが、廻村の手引きは村の子供たちが担当していたようである。
特に馬頭観音の祭日や月待ち、日待ち(庚申講=こうしんこう)などには座敷へ必ず招かれ、追福作善(ついふくさぜん)のためにも御国浄瑠塙を語ることが多かった。
座頭が来村すると近在から聴きにくる人もおり、たとえば享保年間(一七一六〜三六)、伊具郡毛萱(けがや)村の平七は「隣里、瞽(こ)を延(まね)くこと」があると、「俗曲を喜ぶ」老父に「随行し、保護して往(い)」くのが常であったという(『仙台孝義録』)。
座頭は「四天王剛強つくし、或いは弁慶・義経、田村三代記など、本数多く覚えたるを上手」とし、「追善などには何の本地(ほんじ)、何物語など云ひて、愁歎という物を語」ったという(『奥州名所図会』)。
神仏の本地譚は中世の伝統をひいたもので、座頭は嘆くように語ったのである。こうした曲の中には、名取郡川上村に居住したと伝えられる桑島長者の愛娘幾世(いくよ)姫と小佐治の悲恋物語など、地方的特色をもつものもあった。
『田村三代記』では、六段目の悪玉と子熊の母子名乗りの段が最も好まれた。田村麻呂と契った九門長者の水仕(みずし)女悪玉と九門長者に養育された子の千熊に対する同情が民衆的受容基盤となっていた。民衆が好んだのは、男女や親子の自然の情愛を主題とするものであり、また怪異譚であった。
こうした座頭は民間宗教者としての性格も備え、嘉永六(一八五三)年六月八日頃から、一人の座頭が名取川の栗木(くりき)の淵で七日間にわたって食を絶ち、雨乞いの祈祷をとり行っている(『大旱雑記』)。
元禄四(一六九一)年に招聘されて仙台藩領内の座頭を統括した検校(けんぎょう)矢口城泉(じょうせん)も、和泉(いずみ)国岸和田にいた頃、三弦(さんげん)をひいて雨乞いをし、雨が降ったので、雨検校と呼ばれたという。
他界に通じ、聖なるものとかかわる座頭の性格は、稀薄になりながらもまだ残存していたのである。
だから、神仏の本地譚などを語り、聴衆の涙を誘うこともできたのである。
座頭を旅宿へ招く旅人も少なくなかった。松尾芭蕉はもとより、文人中山高陽の『奥游目録』の明和九(一七七二)年六月二十日条にも、「瞽(こ)あり、仙台上るり(御国浄瑠璃)を能くす、旅舎に呼びて一曲を弄す、古朴(こぼく)聞くべし」とある。
仙台城下の旅宿でのことで、その語りは「古朴」と受取られていた。
幕末の志士吉田松陰も嘉永五(一八五二)年三月二十三日の晩と翌日に、七ヶ宿街道の下戸沢宿の宿屋へ座頭を招き、忠臣蔵を聞いて涙を流している。
御国浄瑠璃からデロレン祭文(さいもん)へ
明治に入ると御国浄瑠璃の語り手はきわめて少なくなり、陸前南部では赤井沢龍之一(りゅうのいち)らを残すのみとなった。
龍之一は幕末の嘉永年間(一八四八〜五四)に名取郡熊野堂村に生まれ、七歳で失明したのち、長町の赤井沢秀奥一に学んで、師匠の家を継いでいる。
毎年三月から九月頃まで秋保(あきう)温泉において、按摩(あんま)と御国浄瑠璃を語ることを生業としていた。
こうした御国浄瑠璃に代わって、人気を博するようになっだのは、デロレン祭文という遊芸化した祭文である。
その前身は説経節の苅萱(かるかや)や小栗判官などを語り歩いた修験者の説経祭文であった。
デロレン祭文は近世後期に関東宇都宮あたりから仙台藩領に伝わり、修験者の配下の祭文語りが語ったらしい。
明治期の宮城県内には祭文語りの組合があって、春秋二回の寄合いや、貝の吹合わせという催しも行われた。
彼らは錫杖(しゃくじょう)を改造した金錠(きんじょう)を右手で振り、左手にもった薄手のほら貝を口にあてて「デレレン、デレレン」と口三味線を発し、講談的な部分では両手の人差指と中指の間に挟んだ二本のツケ(経木)で机をたたきながら、喉声(しゃがれ声)で語った。
陸前南部は祭文語りの本場で、伊具郡を発祥地とする桜元(さくらもと)一家と一刀斎(いっとうさい)一家が古格を保ち、浪花節(なにわぶし)化しない宮城県の祭文を代表していた。
関東においてデロレン祭文の金錠と貝が捨て去られ、浪花節と同化してしまった大正以降も、人気は衰えなかった。
桜元元祖の初代から四代目までの桜元観龍(かんりゅう)は伊具郡桜村の出身であったが、五代目は柴田郡大河原町の人で、昭和十年代に活躍した六代目は名取郡岩沼町の人であった。
五代目観龍の弟子の名取郡館腰村の桜元義平(本名斎藤常治)は半農で、単独もしくは刈田郡宮村の桜元義清(本業渡世)らと共に、名取郡の海岸地方はもとより、七ヶ浜方面からも招請を受けて巡業した。
さらに一九三五(昭和十)年〜三九年にかけて、毎年JOHK(仙台放送局)の昼の放送に出演し、「観音丹次(たんじ)」「義士貞女よしの」などを熱演した。
名取郡館腰村の桜元義喜や同郡玉浦村の桜元義之もいたが、一九三九年当時はすでに廃業していた(藤原勉「祭文・浪花節の研究」)。
このように、祭文は説経祭文やデロレン祭文などの民衆の心に響く芸能・娯楽として発展し、新しい話がいくつも生み出された。
明治以降の陸前南部には、さらに祭文松坂を語る女性たちもいた。
こうした語り物の主題は伝統的・民衆的なもので、その主人公の多くは公的な権威の対極にあった。
地域民衆の間では中世以来の民衆的な伝統が確実に継承され、発展していたのであり、特に喉声(しゃがれ声)の伝統は、のちには演歌という大衆音楽に継承されてゆくのである。
二 陸前南部の歴史と日本史 top
1 南と北の境界
語り物のなかの多賀国府
幸若舞(こうわかまい)に「信田」(しだ)という曲がある。
平将門の嫡流、信田小太郎を主人公とする貴種流離譚(きしゅりゅうりたん)である。
信田小太郎は小山行重のために所領を取上げられ、四国・西国・北陸の港々を売られて行き、陸奥国外の浜(津軽半島の陸奥湾側の沿岸)で塩焼きの奴隷の境涯に落ちていたが、塩路庄司(しおじのしょうじ)に見出されてその養子になり、多賀国府において国守に見参し、系図を提出して、平将門の子孫、相馬の実子であることが認められる。
そして国守の仲介で奥州五十四郡の主となり、小山を攻め滅ぼして復讐を遂げる、という物語である。
説経「さんせう太夫」とよく似ている点でも知られている物語である。
「さんせう太夫」の方は、岩城判官正氏の実子の厨子王丸(ずしおうまる)が日本海沿いを売られ売られて、丹後国由良(ゆら)の長者の山椒(さんしょう)太夫のもとで塩焼きの奴隷になり、姉の安寿(あんじゅ)の犠牲によって、そこを逃れて、天王寺(大阪市、四天王寺)において梅津院に見出され、乞丐人(こつがいにん)の境涯から輝くばかりの貴公子に生まれ変わり、「玉造の系図」によって奥州五十四郡を回復し、山椒太夫に復讐を遂げる、という筋書きである。
塩焼きの奴隷といい、系図の役割といい、奥州五十四郡の回復といい、両者の類似は明らかである。
しかしここでは特に奴隷、乞丐の境涯からの甦りの場が、「信田」では外の浜と多賀国府、「さんせう太夫」では摂津(せっつ)国の天王寺とされている点に注目したい。
西方極楽浄土の入口とされていた天王寺が、死と再生の境界的な場として、中世後期の多くの人に受入れられていたことについては、岩崎武夫氏の考察がある(『さんせう太夫考』)。
多賀国府もまたそのような場として意識されていたのではないだろうか。
多賀国府を同じように位置づける物語が、奥浄瑠璃の一つ「塩釜大明神の御本地」にもある。
むかし垂仁(すいにん)天皇の孫に花園の少将という人がいて、内大臣の娘のさわらび姫と人もうらやむ恋愛関係にあった。
ところがそれをうらやみ、横恋慕した桃園(ももぞの)中将の讒言(ざんげん)によって、花園少将は陸奥国に流される。
幸福の絶頂から一転して流人の境涯になるという悲劇が訪れるのであるが、流された先の多賀国府では五十四郡の大名・小名にかしずかれて、「みちのく殿」と称せられ、都に劣らぬ華やかなくらしが再現する。
一方、さわらび姫も都を出て、艱難辛苦(かんなんしんく)の末に多賀国府で花園少将に再会し、二人の間には文殊王という若君が生まれる。
文殊王は羽黒詣での山伏に連れ去られるが、都で外祖父の内大臣に見出され、名乗りを遂げて、天皇に拝謁し、花園中納言と名乗ることになる。
父の花園少将は赦免されて、「奥州大国」を賜り、桃園中将は硫黄が島に流される。
その後、老齢におよんだ花園少将は再び陸奥国へ下り、塩釜大明神となってあらわれた(人間田宣夫「塩釜大明神の御本地」『中世陸奥国府の研究』)。
ここでは多賀国府は流刑の場であると共に富貴・幸福の場でもあるという、両義的なところとしてあらわれる。
そこはまた人が神になるところでもあった。多賀国府が境界的な場として受取られていたことは明らかであるといってよいであろう。
多賀国府以東のはて、みちのくの国府であって、他の国々の国府とは異なり、直接、異域に接触している。
現実にも境界的な場であった。
都の人にとっては、そこはどんづまりのさいはての地であると共に、興趣(きょうしゅ)にあふれた憧れの地でもあったのである。
繰返す人の来住
境界的な場であるこの地域は、そこを訪れる人が多く、その中にはこの地に定着する人も少なくなかった。
時代の変わり目には特にそれが多い。
この地域の住民は幾重にも層をなして、過去の移住の記憶を伝えていたのである。
古代においては、陸奥国府である多賀城への国司の下向があったことはいうまでもないが、人の移住という点では関東式土器といわれる土器の出土に見られるように、関東地方からの人の移住が多かった。
十一世紀になると、受領の郎等として下向した武士の土着がみられるようになる。
前九年合戦の緒戦において源頼義に斬られた伊具(いぐ)十郎平永衡(たいらのながひら)はそのような人であり、奥州藤原氏の祖の亘理権大夫(わたりごんのだいふ)藤原経清(つねきよ)も同じような経歴の人であったと考えられる。
彼らは伊具・亘理といったこの地域の郡を土着の拠り所とし、武者の世である中世を切り拓いていった。
鎌倉時代には関東御家人の東北移住といわれる歴史事実が、陸奥国の各地でみられるが、この地域でも長江(ながえ)・国分(こくぶ)・留守(るす)・亘理(わたり)などの一族の移住があった。繰返す関東からの移住である。
さらに十四世紀の南北朝内乱の中では、多賀国府の地に室町幕府の奥州管領府がおかれ、奥州管領の吉良(きら)・畠山・斯波(しば)氏に従ってこの地に来往した人々がおり、その痕跡は今もこの地域に居住している人々の名字として記憶されている。
たとえば仙台市を含む旧宮城郡内に今も多く居住している桜井を名字とする人は、もと三河国碧海(へきかい)郡の出身で、奥州管領の吉良貞家に従って来住した一族であった可能性が高い。
また岩沼市に多い長田(おさだ)姓や仙台市などに多い二宮(にのみや)姓も、同じ頃に奥州管領の斯波氏の家臣として来住したものと考えられる。
そして十七世紀の近世初頭には伊達氏の家臣が伊達・信夫(しのぶ)・長井(ながい)の地から、大挙して移住している。
近代においても、仙台は東北の中心都市として多くの外来の人々を受入れてきた。
前述した語り物のなかの多賀国府は、こうした南あるいは西からの人々の来住をうながす、場の磁力を象徴する存在だった。
文化の受容と地域の個性
人の移住に伴って、この地域には外来の文化が何度にもわたって移し植えられてきた。
そのようなことの結果として、この地域の文化は重層性を特徴とすることになった。
この地域の県民性の一つとして、閉鎖的でとっつきにくいことと、都会的でもあることが指摘されているのも、その表われの一つということができる(武光誠『県民性の日本地図』)。
だがそれはこの地域の文化が個性のうすいものであることを意味するわけではない。
板碑文化の受容を例として、この地域ならではの文化の個性を考えてみたい。
板碑は追善(ついぜん)あるいは逆修(ぎゃくしゅう)を目的として立てられた石造の供養塔の一種で、鎌倉時代のはじめに関東で発祥して全国に広がり、中世を通じて造られつづけたものである。
宮城県には約五〇〇〇基の板碑があることが確認されているが、それは埼玉県の二万基、東京都の八〇〇〇基につぐものである。
仙台市域には五〇〇基をこえる板碑が現存する。この地域は全国的にみてもまれに見る密度の濃い板碑の分布域なのである。
それが関東の板碑文化の影響のもとに造られたものであることは疑いないが、できあがった板碑文化は、関東のそれとはかなり違ったものになっている。
その一つは板碑に見られる信仰の内容である。板碑の多くは梵字(ぼんじ)で主尊(種子=しゅし)を彫り、その下に造立の年月日と造立趣旨(願文)を彫る。
関東ではその種子の八〇%が阿弥陀如来(あみだにょらい)をあらわすキリークであるといわれる。
阿弥陀浄土の信仰が広く関東の人々の心をとらえていたことが明らかであるが、これは法然や親鷺のいわゆる専修念仏の信仰ではなく、天台浄土教の信仰を表すものである。
ところが東北地方では、大日如来をあらわすバン(金剛界大日)やア(胎蔵界大日)の方が多く、仙台市の板碑でいうと、バレー一七基、アー○六基、キリーク九一基という数になる。
大日如来は真言密教の教主であるが、この場合は天台宗の信仰で、天台宗では大日如来は顕教(けんぎょう)の釈迦如来と同体であると説く。
つまり関東の板碑もこの地域の板碑も天台宗の信仰を表明している点は同じなのであるが、関東では末法の世にふさわしいといわれる阿弥陀浄土の信仰が主流になっているのに対し、この地域ではそれ以前の保守的な天台宗の信仰、言い方を替えると天台宗の本来の信仰に対する執着が強かったということになる。
また板碑の造立の趣旨を記した願文は、簡単な文章で、年月日の左右に一行ずつに振り分けて記されるのが普通であり、関東でもこの地域でもそうなのであるが、この地域の板碑の中には、何行にもわたる長文の願文を有し、年月日はその最後の行に記しているものが見られる(願文がそれほど長くない場合にも)。
これは願文が本来、口頭で読み上げられる(諷誦=ふうじゅ)べきものであったことを示しているのであるが(年月日は最後に読む)、このような形の願文は関東では初発期の板碑にしか見られない。
つまり関東では、間もなく願文は形式化し、口頭で読まれるものであることが無視され、図案化して、年月日の左右に振分けに記されるようになるのであるが、この地域ではその段階になっても、願文の本来の形に執着し、それを復活しようとする人々がいたのである。
以上のようなことは、この地域の人々の保守性あるいは原則主義的な性向(一種のかたくなさ)を表わしているといってよいように思う。
この地域の文化は、くりかえす南から西からの人々の来住によって、大きな影響を受け、東北地方の他の地域とは異なった都市的なものに育て上げられてきたのであるが、それは地域の保守性や原則主義によって変更を加えられ、独特の風貌(ふうぼう)を帯びたものになっていったのである。
2 地域と国家 top
城下を支える商品生産
仙台藩の治世下でこの地域が担った役割のひとつは、城下町の士民の生活を支える米・蔬菜(そさい)類・流木(ながしぎ)の制度もある山村の薪炭(しんたん)類・海や川の魚貝類・和紙その他の多様な手工業製品の生産にたずさわることであった。
それらの産物は生産者自身によって、また、宿駅の町場に多い在方商人の手を通して、日常的に城下に搬送された。
陸前南部は北部にくらべて畑作地が多いこともあって、特有の名産品を生み出している村々もあった。
大量な商品生産の展開を招来することは少なかったが、村々や城下職人の家内手工業生産と結びついて紙子・紙布や仙台平などにみられるような精巧な技術を育てていたことも知られる。
北上川やその支流域にひろがる陸前北部の村々は、藩の手で治水と河川改修による新田開発が大規模にすすめられて水稲単作地帯として発展し、藩財政を支える買米専売制度が実施されていた。
年貢以外の米も藩が買上げて江戸に廻し売却して利益をあげる制度であるが、陸前南部では通常、買米専売制度は行われなかった。
開発も早く比較的安定した環境にある陸前南部地域の産米については、藩が領国支配政策上、城下をはじめ領内消費用にあてることを考慮したためであろう。
他領とのつながり
流通政策の面でも陸前南部と北部には違いがあった。
陸前北部には有力な移出入港の石巻があったにもかかわらず、江戸から輸入される他領の商品はいったん城下仙台に運ばれ、藩に仲役(取引税)を支払って仙台の問屋から買ってくる制度になっていた。
陸前南部のうち南方の諸郡では、時によって禁止されたこともあるが、一般には知行主である有力家臣の出願に応じ信達地域(福島県信夫・伊達郡)などからの直接移入取引をみとめていた。
その背景にあるのは、南方諸郡の村々では養蚕業がさかんで、生産される生糸が信達地域の市場に売出され、米の移出も行われるなど、両地域の村や町場の商人の関係が深かったことである。
その品質の良さが評価されていた紅花は、村山地域(山形県)の市場に移出された。
京都西陣織の染料などに使用され、京都の紅花問屋と直接の商取引関係も行われている。
村山地域からも煙草・水油のような生産品や上方下りの衣料などが流入し、最上衆と呼ばれる奉公人も城下の店や村の農家で働くようになっていたし、街道沿いの村では婚姻関係も増加してきていた。
染料として生産される藍も信達地域や盛岡藩領に移出された。
近世後期になると、陸前南部地域の社会では藩境を越えた諸関係が進展していたのである。
維新期の陸前南部
慶応四(一八六八)年の戊辰戦争にさいして奥羽越列藩同盟の盟主となり戦い敗れた仙台藩は、徳川氏・会津藩征討について真っ向から疑義を表明し、その可否について諸侯の衆議公論にもとづく公明正大な決定を行うよう主張していた。
この「東方の大藩」の六二万石はいったん上知され、二八万石の新封となる。陸前南部地域も二分されて南方の刈田・伊具・亘理・宇多郡は一時は盛岡藩の転封地となり、ついで白石(のち角田)県となって廃藩置県後に仙台(のち宮城)県に合した。
新県下では旧藩の帰農家中をふくむ世直し一揆・騒擾が続発した。
この地域でも転封にともなう家臣団の解体が急速に進められ、村では人馬負担などをめぐる一揆・騒擾(そうじょう)が発生している。
新仙台藩に対しても明治二(一八六九)年四月、藩内人事の内紛や藩士の一部が箱館で抵抗を続ける旧幕府軍に脱走・参加するという事件が生じ、再度政府の鎮撫(ちんぷ)軍が派遣され、切腹処分をふくむ藩内首脳部の粛正(しゅくせい)が行われた。
藩政への衝撃は大きく、以後新首脳部の施政は政府の評価を高めることになる。
この傾向はその後も続く。その好例として地租改正がある。
政府が地租改正の大事業を始めた時、まず西の旧長州藩の山口県から着手し、東北からは磐前県のほか宮城県を選んでいる。
宮城県は着手の順としては三番目のグループに属したが、事業の完成順では全国二位で、先行した山口県に迫る好成績であり、しかも土地丈量など本格的な方法を採用した初の事例であったとされている(有尾敬重・福島正夫解題『本邦地租の沿革』)。
「東北地方の模範」となるように指示されたともいうが、全国の試行事例になったこの事業の経緯は、当時の政治的な状況と無関係ではないのであろう。
東北地域の中で仙台は急速に中央官庁の出先機関が集まる都市になり、国家統治の分核の役割を担っていく。
「第二都市」論
その早い例で重要な意味をもっかのは軍事機関である。廃藩置県にさいして仙台城二の丸跡に東北鎮台(はじめ石巻に東山道鎮台)が設置された。
一八七三(明治六)年には仙台鎮台と改められ、第二軍管として東北を統轄する軍事機関となった。
翌年には榴岡(つつじがおか)に歩兵営が建てられ歩兵第四連隊が設置される。
仙台鎮台は、一八八八(明治二十一)年に第二師団となった。
明治四十一年版の『仙臺市史』によると、仙台城二の丸付近には第二師団司令部などのほか、歩兵・騎兵・砲兵・工兵・輜重(しちょう)兵の各隊の兵営や兵器支廠と練兵場、衛戍(えいじゅ)監獄などがあり、榴岡には歩兵第四連隊区司令部・歩兵営、第三旅団司令部、陸軍地方幼年学校がたち、これに隣接する広大な宮城野練兵場が広がる。
市の南北に追廻・台原の両射撃場、市内に点在する衛戍病院、憲兵隊本部と憲兵屯所や陸軍作業場などがあり、在営兵員数万人は、市の経済状況にも種々の影響力を持ち、「軍都」の呼称に値する実態を備えていた。
また、一八七四(明治七)年設立の官立外国語学校(宮城英学校)は三年ほどで廃校になったが、伝統のある仙台藩校の医学館の建物を使ったものであった。
以後、仙台にはキリスト教系や実業系の私立中等教育学校もさかんに開校されていく。
一八八六(明治十九)年には旧制第二高等中学校(一八九四年、第二高等学校と改称)が設立されて、高等教育の「学都」への歩を進め、一九〇七(明治四十)年には東京、京都につぐ東北帝国大学の設置が決まった(一九一一年発足)。
軍都や学都の呼称をもった仙台は、また、かつてしばしば「第二都市」と称されることがあった。
資本主義社会の中で近代工業の発展に取残された東北の中にあって、突出して国家機関の支庁が集中的に設置され、その結果として大企業の支店や支社も多い仙台は、第一師団や第一高等学校、そして国家機関の中枢をなす本庁、大企業の本店や本社が林立する首都東京のもとにある東日本地域の第二都市という評価を受けてもきたのである。
新たな地域の形成
一九三〇年代に展開された東北振興運動は戦時経済体制下の兵器生産拡充に結びつき、陸前南部地域には、国家政策により船岡海軍火薬廠、仙台原町苦竹(にがたけ)の東京第一陸軍造兵廠仙台製造廠、多賀城海軍工廠などの建設が行われた。
仙台は一九四五(昭和二十)年七月十日零時すぎからの米軍機による空襲のため市中心部を焼失し、確認死者数一〇六四人、未確認死者数三三五人の犠牲者を出している(仙台「市民の手でつくる戦災の記録」の会編『仙台はフェニックス』)。
戦後復興のなかから出発した仙塩(仙台・塩竈)特定地域総合開発計画、東北開発三法、仙台湾地区の新産業都市指定、白石・角田・大河原・村田・柴田の二市三町の低開発地域工業開発促進法指定、これらに続く農村地域工業導入促進法、工業再配置促進法によって、特に仙台港の開港や一町村一工場あるいは一町村二工場を目的として推進された工場誘致が行われ、地域の風景は激しい変貌を遂げた。
このような日本列島改造を呼号した高度経済成長期が終ると、環境問題と共に地域の生活をみつめなおす動きが強まった。
現在、人口一〇〇万人超の政令指定都市となった仙台市民と陸前南部地域の農業経営者のあいだは産直運動で結ばれ、近代の行政区画に隔てられがちであった県境の意識も明らかに変化の兆しを見せている。
たとえば仙台・山形両市のツィン都市計画や山形県村山・仙台両地域二八町村が参加する「やまがた・仙台交流連携促進会議」は、これからの自治体のありかたとして、新しい時代の動きに応じる自治体同士の横の連携の必要性を謳っている。
現実に進んでいる地域交流の動きが行政を後押ししているのである。
このような動向が、現在、各地域に広がりつつある認識であることは間違いない。
かっての歴史を地域が共有できる文化的体験としてみれば、「第二都市」の時代とは異なった状況が生まれているのであり、それを地域の歴史の復権とみることもできるのである。
top
****************************************
|