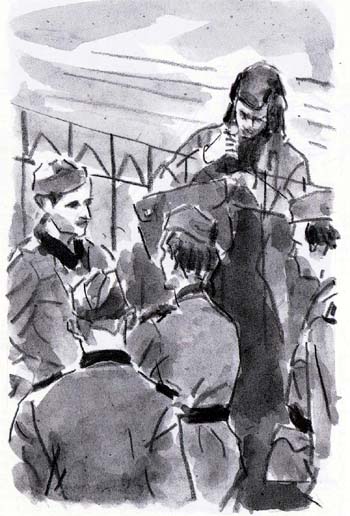|
****************************************
Index 一章 二章(その一 その二 その三) 三章
第二章 ミュンヘンに「白バラ」を追跡(その二)
10 「白バラ」 一号は六月に出る
top
ゾフィーとハンスが、このアパートに住んだのは、碑文の一九四二年六月からではなく、大学の冬学期開始の一二月からではないかと思います。
というのは、ミュンヘンの郊外都市ウルムに実家のある二人は、それまでに戦争による動員義務を果たさなければならなかったからです。
日本にも学徒勤労動員令で、戦争末期には学生はもちろんのこと、学童だった私も鉄工場へ狩り出されました。
それとよく似ています。
一九四〇年に高校を終えたゾフィーは、大学入学試験はすんだものの、そのままスンナリ進学できるわけではなかったのです。
戦時勤労動員があって、ようやくミュンヘン大学の生物学と哲学学生として、ミュンヘンに来たのは、四二年五月の始め頃。
ある未亡人宅に下宿し、それから短期間ですが武器工場に動員されました。
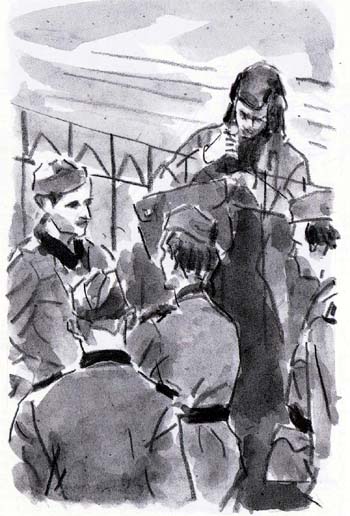 |
 |
兄のハンスは、同じ大学の医学生でありながら国防軍の兵士で、ミュンヘン学生中隊に所属していました。
同年七月にロシア戦線に出動、実習任務を終えて、無事に戻ってきたのは十一月に入ってから。
ですからハンスに関していえば、前線行きで三ヵ月余の国内空白期間かありました。
抵抗運動の「白バラ」ビラは、一号から四号までが、その空白期前の六月から七月までに発行されています。
原稿を書いたのはハンスとシュモレルで、部数は各一〇〇枚ほど。これにはゾフィーは関与していないとみるのが、正しいようです。
物理的にも不可能だからです。
ビラの印刷作業は、建築家アイケマイヤーのアトリエの地下室で行われ、ここはその前から、グループの読書会などによく使われていました。
シュモレルほか、ブローブストに、グラーフなどの学友が、それぞれの意見を交えながら、心を合わせて抵抗の火種をかきたてていったのです。
文字通りの地下非合法組織に、ゾフィーとフーバー教役が参加するようになったのは、兄妹が同じアパートに住んだ一二月以降のことです。
さて、その「白バラ」の内容ですが、ビラ一号は、次のような書出しから始まっています。
以下の引用一部分は『白バラ抵抗運動の記録』未来社)より。
無責任な暗い衝動に身をゆだねた支配者の 徒党(ととう)に、抵抗することもせずに、「統治」を許することほど、文化民族にとってふさわしからぬことはない。
今日、誠実なドイツ人はすべて、 みずからの政府を恥じているのが実状ではないだろうか?
そして、ひとたび我々の目からベールが落ちて、一切の尺度を無限に越える残忍きわまる犯罪が白日のもとにさらされる時、我々と我々の子孫の上に落ちかかるであろう汚名のはなはだしさを、我々の誰に予感できよう?
11 「自由! 自由!」と top
タイプ印刷ですが、タイプライターと原紙、ならびに謄写版(とうしゃばん)は、いくらか小遣いに恵まれたシュモレルが入手したとされます。
手刷りで発行されたビラの送付先は、大学の友人たちが主で、あとは電話帳なとから適当に抜き出したアドレスが少々。
もちろん差出人の住所・氏名は伏せてです。
書き出しを読んだだけでもわかることですが、ビラのいわんとすることは理解できるものの、何とも生硬な文体です。
もう少し平明で具休的な記述にならなかったのかという気にしないではないけれど、ナチスによる「残忍きわまる犯罪」を強調して、その「統治」を許すことはできない、と訴えています。
「人間が有し人間をあらゆる生物の上に位せしめる最高もの、すなわち自由意志を放棄」してはならぬの、強烈なメッセージです。
一号ビラは、ゲーテの詩を引いて、次のように締めくくられています。
いま私は雄々しき人々に会う。
彼らは夜に集まって、
沈黙し、眠ることがない。
そして自由という美しい言葉が
ささやかれ、口ごもられて、
ついには思いもよらぬ新しいかたちをとり、
我々は神殿によりそって、
再び感激して叫ぶに至る。
自由! 自由! と。 |
「自由」という「美しい言葉」を希求する私と彼らは沈黙を拒否し、夜に集まっても眠ることなしに、ついには「われわれ」となる。
そして「自由! 自由!」と叫ぶに至るとは、自由こそが人間の命ともいいたげです。
その自由を奪う権力に対して、沈黙はあり得ないというのです。次はビラ二号の一節です。
いまや我々は終末に直面している。
今こそ、おたがいに再発見し合い、人から人へと啓蒙し、常に思いをこらして休まず、最後の一人にまで、この組織に抗して戦うことがどうしても必要であることを確信させることが大切である。
こういう決起の波が全国をひたし、「気配が空中にただよい」、多数の人々が来たり加わるならば、最後の力強い努力によって、この組織をくつがえすことができる。 |
12 ハンスは軽率だったか top
この組織とは、もちろんヒトラーの独裁政権のナチスのこと。
そのナチスが「終末」にあるとは、あくまでも彼らの主観でして、客観性を欠いた認識です。
ナチス・ドイツは「終末」どころか、その敗北は二年以上も先のこと。
手作りビラ「白バラ」を何回か発送したぐらいで、「決起の波」が全国をひたすはずもなく、ヒトラーの統治が「くつがえる」ものではなかったのです。
ビラ一号から四号までは、合計しても四〇〇枚ほどでしかない。
捨てられたり没収されたりした分を引いたら、一体何人の手に渡り、どれだけの人の心を勣かしたことでしょうか。
効果のほどを考えれば、骨折り損の何とやらで、それに伴うあまりの危険度に、たいていの人はたじろぎ、身を引くにちがいない。
映画に出てくるゾフィーの恋人フリッツじゃないけれど、「ナチスに反対するなんて損だよ」が、当時の一般的な潮流だったといえそうです。
にもかかわらず、抵抗グループの先頭に立って火中へ飛びこんでいったハンスは、いささか軽率ではなかったか。
兄妹のアパートを訪ねた後で、喫茶店の片隅でコーヒーカップを手にしながら、そのことが話題になりました。 |

|
K青年いわく。
「惜しいことをしましたね。ビラも四号までで終えていたら…と思っちゃいますにね。
ハンスの、高揚した気持はわからないじゃないけれど、グループのリーダーとしては、ちょっと分別が足りなかったのかな、と」
「そうね。ゲシュタポも、ビラ四号までは、全く犯人の目星がついていなかったのが、確からしい。バックになんの組織もなかったせいですよ」
「ですから、そこまでだったら、ゾフィーもハンスも、仲間たちも処刑されることはなかったわけで、今もミュンヘンのどこかに生きていたかもしれません」
「それはそうかもしれないけれど、だとすると、我々がいま、ゾフィーの青春を追いかけていく理由も必要もなくなるわけだ。
なぜならゾフィーとハンスの名前さえ、歴史に残ることはないはずです。
若気の何とやらというけれど、自分の信じた道を、一途(いちず)に進むのが青春なのかもしれませんね。
もちろん誰にでもできるごとじゃないけれど、そういう若者もいなくちゃいけないんだと思う」
「ええ」
と、彼は苦笑してうなずき自分の生き方に重ね合わせてか、「耳に痛いです。それにしては、ちょっと残念でした」
「え? 何が?」
「さっきのアパートですよ。あの記念板てす」
「鳩の糞だらけの…」
「ええ、真実は糞にまみれで、モップですぐにでも消せるのに、それができていないという現実です。
通行人も、ああ、そんなものもあるんだなくらいで、白バラに関心を持つ者はめったにいないってことです」
「……」
「もっとも、ぼくもその一人でしたが。先生からの手紙を受けとるまでは」
「うーん」
と、唸らざるを得ません。
残念ということでは同感で、ズバリいえば私も失望でした。
でも、それは、ある程度まで予測できたことで、映画「白バラは死なず」のラストのテロップが、まざまざと脳裹によみがえってくる。
「白バラ」グループの死刑判決は、現在も有効だとするショッキングな、あの字幕です。
それとアパートの慘(さん)たる記念碑とは、決して無関係ではないといえそうです。
日本と違って、草の根をわけててもナチスの残党を探し出し、戦争責任を追求し続けるのがドイツだ、とばかり思っていました。
しかし、それは理想であって、東ドイツはともかく、西ドイツの場合はいまだにショル兄妹らは、国家反逆罪のままということなのでしょうか。
死刑もやむなしということなのか。実際はどうなっているのでしょうか。
 |
 |
13 姉のエリーザベトさん宅ヘ top
ミュンヘンを後にして、私たちを乗せた特急列車は走り続けていました。目的地はシュッツットガルトです。
といっても、私には未知なる町でして、K青年から最初にきいた地名が、舌でもかみそうで、すぐにはなじめませんでした。
「ドイツ西南部のバーデン・ヴュルテンベルク州の州都ですよ。
ショル兄妹の実家ウルムもわりと近くて、南ドイツではミュンヘンと並ぶ古くて歴史的な町ですが、今はむしろ産業都市といった感じですね。
ペンツなど、西独の自動車工業の中心地でもあります」
彼は、そんなふうに説明してくれましたが、車に関心のない私は、実はベンツなどどうでもいいことでした。
それよりも、その古い歴史の町でのインタビューがうまくいくか、どうか。今回の取材のヤマ場にきた、といっていいでしょう。
私たちが訪ねていくシュッツットガルトには、ゾフィーの姉であるエリーザベト・ショルさんと、そのご夫君であるフリッツ・ハルトナーゲル氏が住んでいるのです。
お姉さんは、さらにもう一人いて、『白バラは散らず』の著者、インゲ・ショル女史が長女で、エリーザベトさんは次女になります。
ショル兄妹は五人ですが、その内訳は次の通り。
インゲ、 一九一七年生まれ。
ハンス、 一九一八年生まれ。
エリーザベト、一九二〇年生まれ。
ゾフィー、 一九二一年生まれ。
ヴェルナー、 一九二二年生まれ。
ハンスとエリーザベトの間は二年あいていよすが、あとは年子です。
このうちハンスとゾフィーが処刑された後、弟のヴェルナーも東部戦線で戦死。
両親はすでに他界して、今も生存しているのは、ゾフィーの二人の姉しかおりません。
日本語版訳者の内垣先生から、著者のインゲさんを紹介してもらいましたが、彼女は体調がすぐれず、代わりに妹をということで、アドレスを教えてもらいました。
しかし、K青年がシュッツットガルトのお宅に電話をしたところ、あまり好意的でない口調だったとか。
「姉がそういうならお会いはしますけれど、私たちは私たちですからね。写真などはいっさいお断わりですよ」
と、最初から、釘をさされてしまったのです。
「ですから、どうやら招かれざる客ってわけです。要するに、そっとしておいてってことでしょうねえ。
しかもフリッツ氏は、元かどうかはわかりませんが、民族裁判所の判事だそうです。
ショル兄妹で注目されたくはないし、社会的な場に出るのも、遠慮したいってことでしょうね」
「うーん、そりゃきびしいなあ」
「先生、最悪の場合は、玄関払いもありと覚悟してください」
「ま、とにかく当って砕けろ、でいくとしましょう」
社会的に注目されるのは困る、そっとしておいてという心情は、私にも何となく理解できます。
長女のインゲ女史は、戦後まもなく弟妹たちのことを一冊にまとめ、自分から積極的に訴えて出たこともあって、ショル兄妹に関する対外的な役割を担わざるを得なかったのです。
しかし、エリーザベトさんの立場と事情は、やや異ります。
最愛の兄と妹を断頭台で殺され、連帯責任を問われて自分も獄につながれた立場は共通だとしても、その後の彼女は、フリッツ氏と結ばれているのです。
フリッツ氏はゾフィーが十代からの意中の青年で、映画でも「恋人」で登場し、「いずれ結婚しようと考えていた」と、ゾフィー自身が尋問で語っています。
ゾフィー亡きあとその姉との結婚は、横すべりといっては失礼ですが、決して晴れがましいはずがなく、夫妻の心のどこかに何らかのひずみとして残っているのではないか。と思うのは取越苦労でしょうか。
しかし、今となってはショル兄妹の生存者は貴重な存在でして、この先のチャンスが二度とあろうはずはなく、一期一会(いちごいちえ)なら、何とかしてゾフィーについての証言を得たいのです。
いや、証言などという、固苦しいことはいわない。ほんのひとことの思い出でいい。
ひとことがだめなら、一目だけでも会えればいいのです。
ミュンヘンから目的地までは、特急列車で二時間余。駅前からタクシーで一四、五分ばかり走って、閑静な住宅街の一隅に、私たちの訪ねる家がありました。
うらやましいほどの樹木に被われたお宅で、門をくぐっていった先に、どっしりと落ちついた木製扉の玄関が。
K青年がチャイムを押す指先を見つめながら、私の胸はいやがうえにもときめきました。
14 眼光の鋭いフリッツ氏 top
ドアが開き、その人エリーザベトさんが現われました。
写真でみるゾフィーと、よく似ている!
想像していたよりは長身で、栗毛色の髪の下の顔はやや小づくりですが、目もとは知的で、その頬はいくらかやわらいでいます。
ビッテビッテという声に、私は、はっと胸をなでおろしました。
それはプリーズと同意語のはずです。
玄関を入ったとたんの、応接間に通されました。
土足で入るのは、日本人の感覚ではどうもなじめません。
特にそのことを感じたのは、室内の学術的な落ち着いた雰囲気もさることながら、先にフリッツ氏が、そこで私たちを待っていたからです。
ドイツ人としてはそう大柄ではないけれど、元軍人のせいか、肩幅のがっしりとした体躯で風格があります。
氏はやあやあといった感じでの握手となりましたが、ソファーに座って顔を見合わせれば、職業柄かさすがに眼光鋭い人でした。
先に調べておいたのですが、エリーザベトさんは六三歳(この時)。フリッツ氏は三歳上のはず。
とすると、あるいは判事職は定年で退職しているのかもしれません。 |

|
「あのう、奥さまは、写真の妹さんと、とても似ていらっしやるのでは…」
緊張気味の私は、開口一番、正直にそういいました。
テーブルのカップに、湯気の立つコーヒーを注ぎながら、彼女は微笑して、
「みなからそういわれました。昔はよく間違えられたものです」
「ま、自然な成りゆきでね。私どもも、トシをとりましたよ」
と、フリッツ氏は、ふくみがちの声でうなずきました。
自然な成りゆきで、ゾフィーの姉と一緒になったということか。それとも積み重ねられた歳月のほうに、その言葉はかかっていたのか。
戦中はもちろんのこと、戦後も物心両面からなる辛酸に落ちこんでいたショル家を、フリッツ青年が懸命に支えてきたであろうことは、容易に察せられます。しかし、そこから後、話はなかなか本論には入れませんでした。
「今日は、あなた方を迎えるにふさわしいさわやかな日和(ひより)ですが、西ドイツをふくむ∃ーロッパの動きは、いつもこんな具合にはいきません。平和が常に脅かされているのが現実でして、残念なことです」
フリッツ氏は、コーヒーを味わいながら、窓ガラスに映る木洩れ日(こもれび)に目をやりつつ、やみくもに平和問題から切り出しました。
いま西ドイツには、市民の側から平和をの動きが新しく起こりつつある、といいます。
それは一九七九年にNATO(北大西洋条約機構)の決定により、加盟国にアメリカの中距離ミサイルの配備が計画され、それがいよいよこの一二月にも着工されるとあって、緊迫した状況になってきたということ。
ここからほど近い米軍基地ムードラングンにも、核ミサイルが配備される。ために数日後に、市長を始めとする市民たちの坐りこみ反対運動が始まるが、自分もそこに参加するつもりだといい、こうした平和運動では、遠く離れた日本の動きはどうか。アジア最大の米軍基地があると聞いているが。…
判事という要職にあった氏から、まさか、そんな問題で問いかけられようとは予想外で、いささかあわてました。
きけば夫妻は、五〇年代の終わり頃から、NATO軍と西独国防軍の核武装計画許さずの市民運動にかかわってきたのだ、といいます。
非核三原則を一応は国是(こくぜ)としている日本と違って、核兵器にオブラートはかかっていません。
しかし、日本では弁護士は別として、判事、検事といった人たちの平和運動など耳にしたことはなく、大いにとまどいました。
「それが、ドイツの暗い夜に、手を取り合って抵抗の灯をともしたあの人たちへの、ささやかなつぐないかと思えるからです」
しみじみとした語調でいうのに、隣席の夫人もうなずいて、
「あの人たちは、なによりも平和と自由を願って、そのために…でしだから」
と、つぶやくようにつけたしました。
15 過去からの声なき声を top
私はメモをとりながら、目の前に、火花が飛び散るような気がしました。
生残ったゾフィーの姉に、一目でも会えれば…くらいのつもりでやってきた私は、決して軽い気持ではなかったものの、夫妻の心の底ふかく燃え続けている思いには、想像力が及びませんでした。
過去からの声なき声を重ねて生きる夫妻の姿勢はきびしく、そう簡単にいい返事をしなかったのもうなずけるのです。
「立場はちがいますが、もの書きとして、ほんの少し、私もできることをしてきました。
今回もそうでして、いつまでも心に残る人たちを日本に紹介したい…と」
ふと思いついて、背広の襟につけていたバッチをはずして、差し上げました。
PEACE-1982 に、ピカソの鳩をあしらった去年の反核・軍縮バッチは、常時つけているわけではありません。
たまたま往路の飛行機で隣合わせの席の、婦人団体平和ツアーの人からの、プレゼントでした。
小さな一個のバッチは、夫妻の気持をいくらかやわらげたようにも思われました。
おたがいに初対面で、相手は私どもについてのなんの予備知識もなく、しかもK青年の語学力の限界もあって、かゆいところに手の届かぬもどかしさがあったけれど、一個のピースバッチは、言葉よりも先に、平和の意志の伝達に多少は役立ったかのようです。
「あれから…」
と、私はメモを片手に、夫妻の顔に目を向けました。
「ちょうど四〇年の歳月が過ぎたわけですが、あの人たちのことを振返ってみて、いかがですか」
[そう、一九四三年でした。今年で四〇年になる…]
フリッツ氏はあごを引いて、感慨深けに目を細めました。
「生きていれば、ほとんど同じくらいの年齢のはずですが、まるで昨日の出来事のよう。何か悪い夢でも見た後のような気がしています」
「……」
「私は、ゾフィーがまだ女学生の頃から親しくしていましたので、家族の一人のようなものでした。
騎士道精神に憧(あこが)れてとでもいったらいいか、早くから国防軍にいた私に、彼女はよく手紙を書いてくれました。
それも授業中に、先生に見つからぬように、こっそりと」
「ひとくちにいって、ゾフィーは、どんな娘さんでしたか」
私の用意した質問は、そう多くはない。ただポイントに迫りたくて、たたみこむように尋ねました。
「そうね、ちびで、きかんぼうで、お茶目な、普通の女の子です。
ですから、彼女を英雄視するのに私は賛成できません。
ゾフィーは、鉄のような思想や意志の持主じゃなくて、今もそのへんの街角をスキップしている少女の一人ですよ」
「でも、その普通の少女が、普通でないことをしたわけですね」
「ええ」
と、やや間があいて、控えめに同意したのは、エリーザベトさんのほうでした。
「あの人たちは、ただ個人の権利と、自由を求めたにすぎないのです。
私もあなたも、みんなが人間として、人間らしく生きたいという願いからだと思いますけれど」
「それは、いつの時代でも、誰もが願っていることですが…」
「その願いこめて、自分の意志を貫ぬいた、ということでしょうか」
「しかし、それもね…」
と、フリッツ氏が、ようやく言葉をついで、 「あの暗い時代ですから、心が千々(ちぢ)に乱れるばかりに悩み迷いながらの結果だった、というか。
ゾフィーは、本当に悩んでいましたよ、誰よりも」
一九三七年になると、日独伊防共協定が調印されます。
これで、ショル兄妹が憎悪してやまなかったナチス・ドイツと、私たちとは無関係でなくなります。
日本人の一人として、ゾフィーやハンスが、生命をかけて抵抗したファシズムと同盟した責任の一端を、感じないわけにはいかない。
日独伊防共協定はその名の通り、社会主義のソ連を敵対視した軍事同盟で、日本とアメリカ・イギリスなどの対立はこれで決定的なものとなり、東西にまたがるファシズム三ヵ国のトリオから、戦争の火種が、全世界にばらまかれるごとになるのです。
ヒトラーが、全ヨーロッパのユダヤ人絶滅を予言したのは一九三九年。
未曾有の国家的な民族差別と虐待の一方で、凶器を通り魔のように振りかざしたナチス・ドイツ軍は、三月、プラハに進撃、九月はポーランドへ。
イギリスとフランスはただちに参戦し、ここに第二次世界大戦の悲劇の幕が切って落とされたのでした。
17 「発砲してくれるな」と top
「ゾフィーの悩みは…」
フリッツ氏は、当時を回想してか、低くくぐもった声になりました。
「今にして、彼女の心中が手にとるようにわかります。
家内の意見に私も同感でして、ゾフィーは誰よりも人間的だったのだろう、ということ。
理不尽なものや不条理に対して、目をつむることができなかったのですよ」
「……」
「自分をそれだけ尊重できたからこそ、人の命をもいとおしむことができたのではないのかな。たとえば…」
と氏は続けて、それがよほど印象的ごったのか、一九三九年九月のある日に、自分あてに届いたというゾフィーの手紙の内容を語ってくれました。
――戦争が始まって、これから先に敵味方を問わず、人間が人間によって生命を奪われることに納得できない。
祖国のためというけれど、人間があってこその祖国ではないのですか――と。
「しかし、当時のあなたは軍人。祖国を守ること、上部からの命令を第一義(だいいちぎ)にしなければならなかったわけですね」と私。
「ええ、それ自体がたいそうな矛盾でして、私にはとてもつらいことでした。
だってゾフィーは、決して発砲してくれるな、というんですからね。
しかし、撃たなければ撃たれることだってあります。それが戦場というものです」
「それで、あなたは…」
私は、ためらいを捨てて聞く。ここまで踏みこんでしまったからには、もう引くに引けないのです。
「立場の違いはあきらかですが、私の身を思ってくれる気持だけは、ひしひしと痛いように迫ってきました。要するにゾフィーは、敵を殺傷することなく、無事に生きて帰ってきてくれ、ということですよ。今なお忘れずに覚えています」
四〇年余もさかのばって、はるかな青春を振返る氏の髪に白いものが揺れ、彫りの深い横顔に苦渋の陰影がよぎりました。
これまでの人生を回想しつつ、彼らの犠牲を二度と繰返すまじの、決意のほどがうかがえます。
「妹は、とても、やきしい心を持っていたのです」
それまで黙っていたエリーザベトさんか、静かな口調で切出しました。
「発砲するな、といわれたのは兄のハンスも、その友人たちもそうでした。
前線へ出発するボーイフレンドの皆さんから、あの子は、発砲はしないの約束を取りつけて歩いたんです」
「そうだったんですか。殺すな殺されるなってことですね」
「今でこそなんでもないことのようだが、当時としては、大変な勇気のいることでした」
と、フリッツ氏。
「撃たなければ、きっと、神が守ってくれると、あの子は信じていましたから」
そういう夫人の声はかぼそく、ややうるみがちです。
「おかげで、私も奇跡的に生きて帰れました。
スターリングラードの激戦地から。撃たれなかったかわりに、ひどい凍傷の負傷兵になってね。
天国の彼女が守っていてくれたのかもしれません。ええ、たぶんそうですよ」
と、フリッツ氏は微苦笑し、ハンカチを手にしたエリーザベトさんは、はるかな遠い日の妹を偲んでか、その目は途中から伏せたままでした。
 |
 |
18 時きたり、君を欲せば top
当時としては大変な勇気のいることだった、というフリッツ氏の言葉が、帰途の車中でも、私の頭のなかに残りつづけて、重々しく響いていました。
その通りだと思います。「当時」に学童として、子供なりの戦争体験を持つ私の立場でいえば、ゾフィーの青春は、狂おしい勢いの逆流をさかのぼろうとした一匹の、小さなメダカのようにも思えます。
「発砲するな」
という訴えは、もうそれだけで、戦争をする国の方針への明白な反逆行為であり、利敵行為です。
当時、日本で、それらしい声がちらとでも官憲に洩れたらどうなるか。
「非国民」以上の「不忠者」か「国賊」「アカ」扱いで、とうてい無事ではすまされなかったはず。
いや、召集されていく父や兄たちを見送る家族は、「発砲するな」とは口にしませんでした。
国民のばとんどは「撃ちてし止まむ」で「一億火の玉」でしたが、ごく一部にこっそりと、小声で耳うちした人はいました。
戦争がどうなろうとも、「あなた(おまえ)だけは死ぬんじゃないよ」と。
敵は「鬼畜」でしかなく、同じ人間として思いやる気持などはなかった、といえましょう。
もしも、ゾフィーのような発言を、繰返したとしたら…。考えただけでも、戦慄(せんりつ)を覚えます。
しかし、フリッツ氏の言葉ではないけれど、ハンスもゾフィーも、「鉄のような思想や意志の持主」ではなくて、どうどうと押し寄せる逆流に、懸命にもがきあがきつつも、悩み迷うメダカだったのです。
そのメダカが、ついに意を決してきびすを返し、彼らの愛唱歌の一節を、自らの行動の規範にして大胆な行動に転じたのには、それなりの理由があります。
時きたり 君を欲せば
敢然として 立ちあがれ、
けむりまく 炎のさなか
最後のたきぎ 君をなげうて。
(『白バラは散らず』未来社より)
|
top
****************************************
|