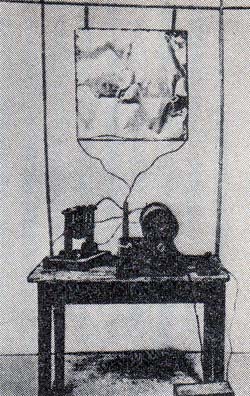|
****************************************
HOME 概要 ワット スチブンソン エジソン マルコーニ ライト兄弟
Ⅳ グリエルモ・マルコーニ(1874~1937)――無線電信
1 父母と生い立ち top
グリエルモ・マルコーニは一八七四年四月二十五日、イタリアのボローニャで生まれた。
ボローニャはその一世紀ほど前にガルバーニ(一七三七~九八)が動物電気を発見して近代電気学の幕を開いたところである。
父ジュゼッペ・マルコーニは裕福な実業家で、ボローニャの町に住居を構えるほか、田舎にも上地をもっていた。
母はジュゼッペ・マルコーニの二度目の妻で、アイルランド人だった。
アンナ・ジェームソンといい、有名なアイルランドのウィスキー醸造家アンドルー・ジェームソンの娘だった。
母方の親戚には、第一次世界大戦でイギリス軍総司令官になったヘイグ卿がいる。
アンナ・ジェームソンは音楽の勉強をしにボローニャへ行き、そこで未来の夫に会って、一八六四年に結婚した。
彼女の最初の息子アルフォンソは一八六五年に生まれ、二番目の息子グリエルモはその九年後に生まれた。
マルコーニ一は比較的年配の両親から生まれた未っ子だった。
親は二人ともなかなか才能ある人だったが、気質はまるで違っていた。
父は抜け目ない成功した実業家だった。
商売のこまごましたことまでよく覚えていて、きびしく、しつこく始末をつけるのが自慢だった。
生活態度はどちらかというと冷たく、無口で読書を好んだ。
母は空想的な性格で、冷静で、決断力に富んでいた。
グリエルモは父より母に似ていた。
母と同じに髪は褐色でウェーブしており、目は青かった。
二人の間には想像力をもって理解しあう、深い結びっきがあった。
兄のアルフォンソは態度も品行もすぐれ、誰からも愛される少年だった。
両親にとって模範的な子供だった。
しかしグリエルモはそうでなかった。
たぶん多少は、非の打ちようもない行儀のよい兄に対する反感もあったのだろう。
彼はいたずらで、強情で、一人ぼっちのことか多かった。
六、七歳のころは、頭のよい子だと思われた――といっても、並はずれた人物になるとはだれも思わなかったが。
だいたいは両親ともうまくいっていた。
父は愛情は深かったが厳格で、実行型の人の常として少年は規律に従うべきだと信じていた。
母は彼の心中を本能的に洞察し、ガミガミ叱る必要があるとは夢にも思わなかった。
マルコーニはほんとの母親っ子だった。 |

マルコーニ(22歳)
|
母は彼の特異な集中力を最初に認めた人であり、彼の能力がすくすく育つよういつも気をくばっていた。
マルコーニも、母から一番激励を受けたと語っている。
父は彼の成果が世に認められるまでは乗気でなかった。
マルコーニは少年時代の大部分を、ポンテッキオの父の領地にあるグリフォーネ別邸ですごした。
これは丘の中腹にある三階建の大邸宅で、たくさんの部屋のほか、科学文献をおさめた立派な図書室もあった。
まわりは何エーカーもある庭園でかこまれていた。
グリエルモは内気だったが、臆病ではなかった。
他の少年だちと乱暴な遊びをするのは好きでなく、一人で木にのぼったり、馬に乗ったりするのを好んだ。
釣りと海がものすごく好きになった。九歳のときもうリボルノ湾でヨット操縦をおぼえた。
晩年になって彼は、もしも貧乏な家に生まれていたら、たぶん発明家にならずに船乗りになっただろうといっている。
マルコーニは母から教わって完璧な英語を身につけたが、反面彼のイタリア語には英語風のアクセントがまじり、これは一生消えなかった。
彼はいつも母と英語で話したので、父の領地で働く人たちは二人が自分たちのことをどういっているのか、さっぱりわからず、気に病むのが常だった。
子供のころ彼は英語風のアクセントを自分で気にして、そのため近所のイタリア少年たちとのつきあいを避けるようになり、孤独癖を強めたのかもしれないと考えられている。
読書は好きだったが両親は彼に正規の学校教育は受けさせなかった。
その地の小学校の校長を家庭教師に雇って、家で勉強させた。
母のからだが弱いので、冬になると家族たちはポローニヤのきびしい寒さを避けてフイレンツェかリボルノに移ったが、マルコーニの教育を中断させないためそこでも別の家庭教師が雇われた。
マルコーニが電気に興味をもっているのに気づくと、母はリボルノ工科大学のロレザ教授を雇って家で教えさせた。
彼はリボルノ工科大学でいくつかの講義をきいたが、特に物理化学に興味をもった。
マルコーニはグリフォーネ別邸の三階の一部屋に、粗末な実験室をつくった。
そこは以前父がその地の百姓から買い入れたまゆを、製糸業者に売るまで一時貯えておくのに使った部屋だった。
彼は一次電池やサーモパイル(熱電対列)を手に入れて、熱を直接電気に変換する実験を行なった。
蒸気機関の蒸気を能率よく使う方法も実験したし、化学にも深い興味を示した。
2 無線電信のアイディアが浮かぶ top
数年間彼はアマチュアとして科学や電気の研究をつづけた。
やがて、二十回目の誕生日ごろになって、ハインリヒ・ヘルツ(一八五七~一八九四)の夭折(ようせい)という悲しいできごとが突如として彼の注意を引きつけた。
一八九四年の春、異母兄のルイギとビエラ・アルプスにいたとき、ふとあるイタリアの電気雑誌を開いたところ、その年の一月一日に死んだヘルツの業績の記事がのっていたのである。
マルコーニは何年も前からヘルツの研究を知ってはいたのだが、格別注意をはらったことはなかった。
しかしその記事を読んでいる間に、ふいに無線電信のアイディアが浮かんできた。
アルプスのホテルのベッドの中で、どうしたらそれを実現できるかを空想しながら、眠れぬ数時間をすごした。
時々松の木の香りが鼻をつき、真夜中に誰かが歩きまわると板がキューキューきしった。
彼以後になって、無線の最初のアイディアを思いだすといつもこの匂いと音が浮かんでくるといっている。
ヘルツは高周波発電機を使って二つの金属球の間隙に火花をとばせて電波を送りだし、狭いすきまをあけた金属環にそれを受けた。
環の中に振動電流が発生し、そのためすきまに火花がとび、これによって電波を検出できた。
マルコーニのアイディアはこうだった。
電波の発信を時々中断し、電波の連続時間を長くまた短く区切ることができたなら、受信環のすきまにとぶ火花もまた長時間、短時間に切れてあらわれるだろう。
短時間あらわれる火花はモールス符号の「トン」に、長時間つづく火花はモールス符号の「ツー」に対応させることができるだろう。
はじめてこのアイディアが浮かんだとき、彼はそれを実際にやってみようなどとはまるきり考えなかった。
あまりにも簡単明瞭な、だれでも考えつくことと思われたからだ。
彼はたくさんの有能な人たちが電波の実験に従事していることを知っていたから、誰かがとっくにやってみたにちがいないと思った。
彼はすぐにもこの実験に成功したという発表が出るものと予想し、それをやる方法についてあれこれ空想をめぐらしながらその夏をすごした。
こうして何ヵ月かじっと待ったが、そんな発表はとうとう出なかったので、秋になって、自分で実験してみようと決意をかためてグリフォーネ別邸へ帰った、
母は三階の二つの大部屋をあけて彼に使わせてくれた。
マルコーニは朝早くおき、夜おそくまで仕事をつづけた。
部屋には鍵をかけ、父には何をしているか話さなかった。
こうして家族と顔を合わせることもめったになくなったので、父はたまには息子の顔もみたいものだとぼやくことが多かった。
グリエルモは人から悪口をいわれるとひどく気に病み、冷笑されたり共感されなかったりすると意気消沈してしまうのだった。
釣りが好きになったのもたぶん、他人と顔を合わせず、口をきかないですみ、一人きりで考えることができたせいだろう。彼は釣師としてはたいして上達しなかった。
寒さはきびしかったか、母はその冬はグリエルモとともにグリフォーネ別邸にとどまった。
母は時おり彼の部屋にやってきて、仕事の進みぶりを見た。女中が食事を盆にのせて一緒にくることもあった。
彼はよく仕事に夢中になって食事の時刻を忘れたからだ。
実験をはじめたのは一八九四年十二月だったが、早々に驚くべき成果があがった。
それは彼には、まだ誰も達成していない新しいものと思われた。
やがてある晩のこと、真夜中に自分の部屋をかけて下りて、母をゆりおこし、最初の成功を見てもらうという段になった。
三十フィートの距離をへだてて電波でベルをならすことに成功したのだった。
父はべつに感動しなかった。
ベルをならす方法はいくらでもあるじやないか、といった。
その年の末には、マルコーニは電波を使ってはじめて離れたところに電文を送り、それを受信し記録することができた。
一八九五年の春になると彼は別邸の庭で実験をはじめた。
父は栗の木の見事な並木道をもつ美しい庭園を、少しでもけがすことをきらった。
あちこちに柱を立てたり、地面に穴を掘ったりすることには強く反対した。
そこでグリエルモは、できるだけ父にみつからないよう、おもに早朝か夜おそくに仕事をした。
こういう異常な時刻は彼のロマンチックな空想に強くアピールし、彼の戸外での最初の実験は、新しく掘りかえした土の匂いや、輝く朝露と結びついて思いだされるようになった。
彼は兄たちや、領地で働く人たちの息子を動員して、実験の手伝いをさせた。
彼らは装置をあちこちに動かしたり、観測に協力したりした。
マルコーニは孤独癖があったが、それでも人を指導する力にすぐれていた。
金持の地主の息子として、もともと領地の人たちに命令を下すことになれていたが、そればかりでなく、生まれつき自分の意志を他人に強いる能力をそなえていたことは疑いない。
3 電波の発見 top
以上が、マルコーニか一八九五年ごろに達した状態だった。
ここで、当時科学者たちの電波研究がどのくらい進んでいたかをながめる必要がある。
電波の存在がまだ夢にも考えられなかったかなり昔から、電波がひきおこす効果はすでに感づかれていた。
最も早く記録された例としては、一七八〇年にアダムズが、ライデンびんを放電させた瞬間に、導体間の狭いすきまに火花がとんだと書きとめている。
ガルバーニも一七九一年にマルコーニの生地ボローニャで、同様な観察を発表している。
一八四二年にジョゼフ・ヘンリー(一七九七~一八七八)は、磁気検出器を使って遠方の稲妻の発生を記録していたとき、ライデンびんの火花放電が実験室から三十フィートも下にある地下室に設けたその検出器に影響を及ぼすことに気づいた。
もう一つの注目すべき例は、印刷電信機や炭素マイクロホンを発明した音楽家のD・E・ヒューズ(一八三一~一九〇〇)が、一八七九年に、金属の粒をゆるくつめた管が遠方の火花に感じることを発見したことだった。
一八八〇年にヒューズは当時王立協会会長だったスポッティスウッドやG・G・ストークス(一八一九~一九〇三)、ハクスレーの前でこの現象を実験してみせた。
ストークスはそれは誘導によっておこるもので、伝導によるのではないといい、「その結果全体を頭から鼻であしらった。」
ヒューズは彼らが二時間半自分と一緒にすごしたあと、「いとも冷たく去っていった」と書きとめている。
ヒューズは電話の受話器をつないでグレート・ポートランド通りまでもち出したが、火花放電の影響は五百メートル離れてもまだカチカチときこえた。
こういうわけで、一八八〇年にストークスは事実上電波の実験的発見をおし殺してしまったのだった。
エジソン、エリュー・トムソンその他の人たちも、たぶん電波からおこったらしい火花を観察したことがあった。
電波という概念をはじめてのべたのはマイケル・ファラデー(一七九一~一八六七)である。
彼は一八三二年に王立協会に、当分開いてはならぬという条件つきで一通の封書をあずけた。
一九三七年になってそれを開封することにきまり、ときの王立協会会長ウィリアム・ブラッグがそれを読んだ。
その中でファラデーは、電磁気の作用は何かの振動の形をとって空間を伝わるとしか考えられないとのべていた。
一八四六年にファラデーは王立研究所で行なった講演でこの考えをもっと詳しく説いている。
一八六五年にジェームズ・クラーク・マクスウェル(一八三一~一八七九)は、ファラデーの電磁気学上の実験的諸発見を数学的に記述すると、それから電気的作用が波によって光の速度で伝搬されるという結論が導き出されることを明らかにした。
電波の存在がそのあと二十二年間も実験的に証明されずにいたということは、むしろ不思議である。
若い研究者ハインリヒ・ヘルツは、先生のヘルムホルツから電波をみつける仕事をやってみよとすすめられ、一八八七年になって見事に成功した。
彼は波長のわかっている電波をつくりだし、それを使って電波が反射、屈折、干渉などの現象を示すことを実証し、それらが可視光の場合とぴったり似ていることを明らかにした。
ヘルツの発見は学者たちの興味を強くひきおこした。
多くの国の物理学者が彼の実験を繰返した。
ヘルツのねらい、そしてまた他の物理学者たちのねらいは、自然の基本的研究の一分野として、この新しい範囲の波の知識を拡大することにあった。
ヘルツは特にこの精神にもえていた。
それは彼が、もとは技術者として生活をはじめたのに、基礎研究が好きになって科学に転向した人だったからだ。
4 無線電信の先駆者たち top
ヘルツの研究を最も早くからうけついだ人の中に、ボローニャのA・リギ(一八五〇~一九二〇)教授とイギリスのオリバー・ロッジ(一八五一~一九四○)教授がいる。
リギの家はグリフォーネ別邸のそばにあり、グリエルモ・マルコーニは彼と知合いだった。
マルコーニはリギと化学や力学について議論したことがあったが、電波のことをはじめて学んだのは彼からではなかった。
マルコーニは、リギの電波の講義は、ききたいとは思っていたけれども、一度も出席したことはないといっている。
マルコーニが無線のアイディアをはじめてリギに話したとき、リギはそれは実用にはなるまいど考えた。
リギは放電がとぶ金属球のすきまを、空気でなくワセリンでみたすことを考えだし、それによって火花を強め、したがって火花が生みだす電波の強さを増した。
マルコーニは自分の送信機の通信距離を増すためにリギの装置を利用した。
コヒーラーの使用をイギリスへ導入したのはロッジだった。
放電が粉末に影響を及ぼすことは早くも一八五〇年にギタールが気づいていた。
彼は、日光に照らされておどりまわっているほこりの粒子が、近くで起電機を動かして放電をおこすと、互いにくっついてしまうのを観察した。
ほかにも多くの人が同様な効果に気づいたが、一八九一年になってフランスのエドワール・ブランリー(一八四四~一九四〇)は、管の中に入れた金属のやすり屑が、近くで放電がおこると互いにくっついて(コヒーア)しまうことを明らかにした。
くっついたやすり屑は、管を叩くと元どおりバラバラに離すことができた。
ロッジはこの「コヒーラー」を電波の検出に応用し、一八九四年には、コヒーラーが一度電波を受けたあと、それを自動的にたたいてやすり屑をバラバラにし、次の信号を受けられるようにする機械装置を考案した。
一八九五年四月、A・S・ポポフ教授(一八五九~一九〇五)はセント・ペテルスブルク物理化学会に、高い垂直のアンテナとアースを使って遠方の雷の放電を受信したと報告した。
やってきた電波がアンテナの中に電気振動をつくりだし、それが揺れ戻し装置をもったコヒーラーによって検出された。
一八九五年十二月にポポフは、十分強力な電波発信器を考案できたなら、自分の受信器は無線信号を受けるのに利用できるかもしれないと予言した。
彼は自分の実験の解説を『エレクトリチェストボ』一八九六年七月号に発表した。
一八九二年にウィリアム・クルックス(一八三二~一九一九)は『フォートナイトリー・レビュー』(隔週評論)誌に注目すべき論説を発表した。
それは無線電信の可能性を論じたもので、新しい電波に関するロッジの一講演をきいたあとで書いたものだった。
クルックスはこう論をすすめる。
電波は波長数千マイルから数フィートまで、ほとんど無限の範囲をもっている。
驚くべき新世界が展開されつつあり、これが「情報を伝達する可能性を含んでいないと考えること」は困難である。
それは「針金なしの電信という、人々の頭を混乱させるようなものが可能であることを明らかにした。」
電波の束を望みの方向に集束させることが可能であり、モールス符号にした電文をある通信手から別の通信手へ送信することができる。
二人の友人は各々の裝置を互いに「同調」させることができ、受信器がある特定範囲の波長に対してだけ働いて、他の波長には耳をかさないように設計することができる。
クルックスはねじをまわすだけで装置が特定の波長だけ受信するよう調整されるようになるだろうと考えた。
これによって「十分な秘密保持」ができるだろうし、暗号を使えばいっそう高めることができる。
こういったことはすべて「単なる浮世離れした哲学者の夢」ではない。
これを日常生活に持ち込む手段は十分みつけられる見込みがあり、大変合理的で、「ヨーロッパのあらゆる首都で活発に遂行されつつある」研究の線にのっていることは明白だから、それらが「冥想の領域からぬけ出て冷厳な事実の領域にはいった」という声明がいずれ出ると期待される。
一八九四年九月にオクスフォードで開かれたイギリス科学振興協会の会合で、ロッジは無線を使ってモールス符号を送れることを実証した。
電信技術者ミュアヘッドの示唆に基づいて、ロッジは一八〇フィートの距離をへだて、二つの石壁を通してトン・ツーの信号を送った。
受信にはケルビンのデッドビート鏡検流計を使い、光線を尺度の上で、ツーのときは長く、トンのときは短く振れさせた。
自動モールス印字機もテーブルの上に用意していたが、それを回路につなぐ気はなかった。
ロッジはこの証明実験の解説を公表しなかった。
二年前にクルックスが自分の研究に刺激されて上記の論説を書いたというのに、ロッジはまだ自分の実験が意味するものを見てとることができなかったのだ。
一九二三年になってロッジは、自分が無線の開発を取上げなかったのは、教育の仕事に忙殺されて暇がなかったか、または、特に航海や戦争で「並はずれた重要性をもっていることを感じとるだけの先見の明」がなかったからだといっている。
また『自叙伝』の中でこうも書いている。
ロッジがコヒーラーを使って電波を検出できることを実証すると、偉大なレーリー卿はこういった。
「そうだ、これできみは前進できる。そこにきみのライフワークがあるぞ!」
しかしロッジはその道を行かなかった。
彼は教育に従事していたので、「今では無線電信へ発展したその序曲をみすごしてしまったのだった。」
一八九四年に、ニュージーランドの若い研究学生が独力で磁気検波器を再発見し、一八九五年はじめに六〇フィートの距離で電波の伝達に成功した。
この青年はアーネスト・ラザフォード(一八七一~一九三七)だった。
ラザフォードは一八九五年にイギリスにわたり、ケンブリッジ大学にはいったが、なお自分の検波器を改良し、伝達距離を半マイルにのばした。
先生のJ・J・トムソン(一八五六~一九四〇)はロンドン市に、ラザフォードの電波研究を推進するため商業的援助をあたえることはできないかと問い合わせたが、回答は無線通信になんらかの実際的用途があるとは思われない、というのだった。
ラザフォード自身は、自分の磁気検波器はコヒーラーより感度が低いという意見をもっていた。
こうしたいろいろの理由から、彼はぷっつり電波を棄て、トムソンの電子の発見を手伝うほうに移る。
彼はひたすらこの道を追い、ついに原子核にまで到達することになった。
六年後にマルコーニはラザフォードの磁気検波器を改良し、ついにコヒーラーを全廃してこれにかえた。
技術的将来性についての彼の意見はラザフォードのそれと全く反対で、二人の天才のちがいをものの見事に示す一つの例である。
マルコーニは以後十年間にわたり、磁気検波器を自分のシステムの標準装置とした。
5 マルコーニ、独力で無線電信を開発 top
グリフォーネ別邸の庭園で孤独のうちにすごしたマルコーニの青春時代は、ヘルツの発見につづく数年間にわき動いた純粋研究の流れの全く圏外にあった。
彼はある意味ではニュージーランドのラザフォードよりさらに孤立していた。
アカデミックな組織体に属していなかったし、問題を一緒に議論できる仲間もいなかったのだから。
新しい波、電波に対するマルコーニの態度は、職業科学者のそれとはまるで違っていた。
科学者たちも、電波が通信に使えるかもしれないと知ってはいたが、それは彼らの主要な関心事ではなかった。
彼らは電波をこれまで知られなかった自然現象の広大な一領域と考え、大いそぎでそれを踏査しようと熱をあげていた。
マルコーニははじめから、実用的な考え方しかもっていなかった。
この新しい波はどうやれば電信に利用できるだろう?
彼が電波に関心をもったのは、それ自体のためでなく、ある目的のための手段としてだった。
世に出てから、死ぬまで、いつも彼の関心はただ一つ、実用的な無線通信、特に情報通信のシステムを開発することにあった。
彼はいつも、事業、戦争、政治等の情報を伝達できるモールス式無線電信は、無線電話より重要だと感じていた。
彼にとっては、音の放送はけっして無線電信ほど根本的に重要ではなかった。
マルコーニは科学者というより発明家であって、彼の発明はまず第一に他人の科学的発見を利用することからはじまった。
彼は独力で研究したから、自分の目標、つまり実用的な無線電信システムの発明だけに精神を集中した。
これを実現するためには二つのことが特に必要だった。一つは、大きい距離で通信できること、もう一つは、装備が簡単で、信頼でき、しろうとでも扱えることだった。
科学者の実験室に備えつけられた装置をながめたとき、彼は自分の観点からすればおびただしい欠陥があるのがすぐにわかった。
こうして実験室の装備に重大な限界があって、自分のシステムにはそのまま利用できないことを知ったので、彼はさっそくそういう欠陥を除去する改良を発明するようになった。
まずはじめに、空気中でなくワセリンの中で火花放電させるリギの強力型発振器を採用して、通信距離を大きくした。
次に一対の放電用金属球の一方を、鉛直に高く張った針金つまりアンテナにつなぎ、もう一方を地面にアースするという方法で、通信距離をさらにずっと長くした。
アンテナとアースは発振器の電気容量をずっと大きくし、それによって電波発射能力を大幅に増加した。
発信機の力を大きくする一方、受信機の感度も増した。マルコーニはコヒーラーを大幅に改良し、これに鋭敏な電信用継電器をつないでモールス印字機を作動させた。
装置を室内から庭園へもち出したとき、彼ははっきりと気づいていなかったが、それを保護された実験室内の環境から出して、天候きびしい戸外の条件へさらしたのだった。
屋外での実験は直ちに彼に、克服しなければならない距離を改めて意識させ、また天候に耐える丈夫な装置が必要なことをはっきり認識させた。
おかげで彼は、特に丈夫な装置を考案するよう心がけるようになり、それらは後に少し手を加えれば海上の船舶でも使うことができた。
受信機を庭園へもち出してからまもなく、彼は途中に丘が立ちはだかっていても信号か受信できることを発見した。
この経験から彼は、無線電波は地表上のどんな障害物ものりこえられると、断固として信じこむようになった。 |
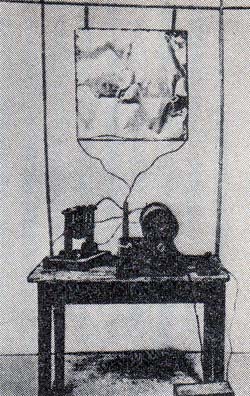
マルコーニの最初の発信機
|
マルコーニはグリフォーネ別邸で一人コツコツ研究しながら、一八九五年の末までに以上すべての改良、発見をやってのけた。
正規の科学や技術の教育を受けていなかったので、数学の知識は乏しく、製図も特にうまくなく、いわば一夜漬けの技術者にすぎなかった。
世界の最もすぐれた物理学者たちが八年も前からよってたかって電波を研究していたのだが、実用的な無線電信の発明者は彼らの隊列の中から現れはしなかった。
二十歳の若いイタリアのアマチュアは、大物理学者たち全部に追いつき、追いこしたのだった。
このことはマルコーニの独創性と偉大さをくっきりと物語っている。
クルックスがいったとおり、ヨーロッパの全首都の科学者たちが電波を研究していたのだが、マルコーニは「一八九四年に電磁波を使って空間を通して電文を送り、記録した」と主張することができた。
彼はこういっている。
自分が使ったアイディアは既知のものであり、装置は先輩のものを改良しただけであり、ただ、自分自身の観察から生まれた少数の発展を組み入れたにすぎない。
しかし「これら新しい要素を導入したことこそ、私の長距離通信が成功する基礎になったといっても、いいすぎではなかろう。」
マルコーニの意見によれば、労力と時間の消費を最小限度にとどめながら成果をあげることは、科学の本分であって、「結果こそが、ある人の業績の価値を判断する基準とみなされる。」
6 イギリスへわたる top
マルコーニの母は夫に説いて、息子の実験費として一千リラを出させた。
成果がはっきりしてきたころには、父もあたたかい支持をあたえた。
他方、母は非凡な息子とその研究について、アイルランドの親戚たちにあてで長い手紙を書いた。
親戚たちは商業上、社会上で重要な地位をしめていた。
母の努力のおかげで、イギリスの政治、産業界でマルコーニの実験に対する関心が高まった。
戦争のときに、海上無線電信が重要なはたらきをするだろうことは、イギリス海軍の専門家たちが早くからさとっており、一八九一年以来H・ジャクソン大佐がその秘密研究をすすめていた。
一八九五年にはジャクソンは、マルコーニと無関係に、無線を使って数百メートルの距離でモールス符号を受信していた。
この実験はもちろん公表されなかったが、無線の可能性を強く認識する人々がそこにはいた。
ジャクソンは第一次世界大戦で海軍長官になり、大戦の将来を決定した海戦、ユトランド沖海戦では海軍の最高責任者だった。
ドイツ艦隊が港を出たらしいという推測は、ドイツの海軍無線信号がやってくる方向を観測して得られた。
母の活躍の結果として、マルコーニは母につれられて一八九六年二月にロンドンへわたった。
親戚のジェームソン・デービスは、後にイギリスにマルコーニ会社を創立した人だが、マルコーニが装置をテストできるよう、ウェストボーン・パークの中の静かな下宿屋を世話してくれた。
母と子はたくさんのケース、バッグ、ふくろをもって到着した。
マルコーニはすぐにウィリアム・プリース(一八三四~一九一三)と接触するようになった。
プリースは郵政省の技師長で、大変有能で思いやり深い人物だった。
プリースはロンドンの中央郵便局の屋上にマルコーニの送信機を設置するようとりはからってくれた。
それから数百メートル離れたテームズ川の堤防上に設置された受信機へ、モールス符号を送ることかできた。
マルコーニは最初の特許を一八九六年六月に申請した。
それは高いアンテナとアースにつないだコヒーラーを備えた受信機の使用を含んでいた。
これは世界最初の無線の特許だった。
プリースは、政府の指令を受けて、郵政省の技術陣の総力をあげてマルコーニか自分の装置とアイディアをテストするのを援助した。
無線信号の送受は、ブリストル海峡をへだてたペナースとウェストン・スーパー・メアの間で行なわれた。
ついで距離九マイルにおよぶ送受信がサリスベリー平原で、陸海軍の高級将校の面前で実演された。
マルコーニは直径約二フィートの反射器を使って、波長約五十センチという短い電波を受信機の方向へ集束させた。
この極超短波を使って二マイルの送受信をやってのけた。
この反射器は「チーズ」とよばれたが、第二次世界大戦がおこってから、同様な装置がマイクロ波レーダーの走査用に、特に潜水艦の潜望鏡をみつけるために、再登場することになった。
プリースは新しい無線について、大変熱心な講演をいく度も行なった。
そのうち何度かはマルコーニも出席して質問に答えた。
聴衆は二十二歳のイタリアの発明家の若々しい姿にびっくりした。
彼はいつもスマートな服を着こなし、低いやわらかな声で完璧な英語を話し、大変慎み深い態度はイタリア人というよりずっとイギリス人ら仕組みえた。だれもが、それと知らされるまでは、彼をイギリス人だと思った。
マルコーニは月並な会話は好まず、証明実験をするほうがずっと好きだった。
大勢の中にまじっておしゃべりするよりも、彼ら同志しゃべらせて自分はポツンとしているのが常だった。
金持ちの家に育ったうえ、生来ひかえ目だったせいで、彼は金持ちや権力者にとり入らなければならないとは感じなかった。
彼ははじめから当然自分もそういう階級の一人だと思い、無線電信を自己の財産とみなしていた。
冷静な用心深い態度は、彼の気質のせいばかりではなかった。
彼ははじめから無線を独占することをめざしていた。
自分の特許、世界最初の無線の特許につづいて、考えられるかぎり改良を考案し、それらを可能なかぎり特許にとって、自分の無線のまわりに難攻不落の防御体勢をきずき上げるよう努めた。
そのための一つの戦術は、しゃべるときによくよく注意をして、権力をめぐる産業戦争で敵にあげ足をとられそうな無思慮な言葉をもらさないことだった。
彼の全生涯、全経歴はいわば自分の発明を説明する一種の趣意書になっていた。
彼の若々しい光輝は、老熟した科学者たちをバックにしてきわめて人目をひいたので、すぐに一般の人々の同情を集めた。
しかし彼の振舞いや態度のせいで人々の共感はすぐに消散してしまうた。
大衆は彼に好意をよせ讃美したものの、社交界では彼はあまり成功しなかった。
とはいっても、次から次へと特許をとり、特許権を行使して競争者をおさえつけ、自分のシステムを実用的なものに改良して商業や戦争の道具に仕上げる、という方向で自分の基本的な位置を確立する一方で、マルコーニは自己宣伝にも大いに注意を払った。
彼はひっきりなしに王族に招かれたし、学会でもチヤホヤされた。
インタービューや共同記者会見もちょいちょいやった。
もっとも、新聞記者たちの前で彼ぐらいしゃちこばっている有名人は少なかったけれども。
7 最初の無線会社ができる top
特に母の強力な縁故関係のおかげで、マルコーニは自分の発明を発展させ実用化するための財政援助をみつけるのにさして苦労しなかった。
世界最初の無線会社、「無線電信信号会社」が一八九七年に、ジェームソン・デービスを専務取締役として設立された。
取締役陣は異例の有名人ぞろいで、十万ポンドの資本の大部分は少数の富裕な投資家たちが引受けた。
この会社はマルコーニの特許の大部分を買いとり、それに対してマルコーニに一万五千ポンドを支払い、また株式の六十パーセントをあたえた。
会社の名は一九〇〇年に「マルコーニ無線電信会社」とかえられた。
マルコーニははじめて自分の発明に対してかなりの額の金をもらったわけだが、そのとき彼が真先にしたことの一つは、自転車を買うことだった。
それは高価な型ではなく、彼の実用上の必要に一番合った型だった。
マルコーニはまだ若かったが、可能なかぎりの最良の助言や助力を得ようとつとめた。
まだ二十年代半ばというのに、ケルビン卿(一八二四~一九〇七)に技術顧問をたのむほどの心臓をもっていた。
ケルビンはそのとき七十歳をこえ、過去三十年にわたってイギリスの物理学界を牛耳ってきたのだった。
一八九七年、二十五歳のとき、有名な電気技術者J・A・フレミング(一八四九~一九四五)を雇った。
フレミングは後に二極真空管を発明した人だが、そのとき五十歳だった。
こういった大家のほかに非常にすぐれた若い人たちも雇った。
たとえば後に短波ビームを使う無線通信を開発したC・S・フランクリンがいる。 |

1898年ごろのマルコーニと送信機(右)、受信機(左)
|
これらの人々は、物理学者または技術者としてはマルコーニよりはるかにすぐれていたが、他方無線の発明の分野では、それと同じ程度に、マルコーニのほうがはるかに彼らをしのいでいた。
一九〇〇年には彼はすでに十七人の科学スタッフをかかえていた。
彼がそういう人たちのサービスをコントロールする人間的な強さをもっていたことはたしかである。
彼は各自の分野では自分よりはるかに能力のすぐれた人々を雇うことを恐れなかったし、個人的な人気にたよることなく彼らを支配することができた。
スタッフが七百人にふえたころには、そのうち彼に話しかけるほど十分彼を知っている人はたぶん半ダースをこえなかったろう。
彼の関心は無線電信というただ一つのアイディアに集中され、ほかのことはすべてそれに従属させられた。
彼は何日もつづいて毎日十六時間働くことがあり、緊急に必要な実用的改良を解決するためには、三十時間もぶっつづけに仕事するときもあった。
きまりきった日常業務や管理は好きではなかったか、それらの主要原理を見ぬく鋭い感覚をもっていた。
万事にひかえ目な態度を保ったが、そのくせ世間一般の動向はもちまえの洞察力でちゃんと見てとっていた。
マルコーニははじめから、自分のシステムがいつかは現存する電信や海底ケーブルのシステムと商業的に競争することになるだろうと確信していた。
彼はケルビン卿(海底電線の敷設に大きな技術的寄与をした人である)が自分の会社の無線局で世界最初の無線電報を送る(一八九八年六月三日。ワイド島とボーンマスの間)人になるよう仕組んだ。
ケルビンは、たぶん何も気づかなかっただろうが、最初の電報を送る相手にジョージ・ストークスを選んだ。
それは二人が大の親友だったからだが、皮肉にもストークスは数年前にヒューズの実験に立ち会い、その冷たい態度でヒューズの意気を沮喪させた人だった。
一八九八年の夏、マルコーニは『ダブリン・エクスプレス』紙の依頼で、キングズタウン・ヨット・レガッタのレースの進行を自分のヨットから無線で報告した。
ジェームズ・ゴードン・ベネットは彼をアメリカに招き、自分の『ニューヨーク・ヘラルド』紙のためアメリカ・カップ・ヨット・レースの進行を報道させた。
またビクトリア女王の依頼で、ワイド島沖に碇泊する王室のヨット「オズボーン」号と、ワイド島にある女王の別邸オズボーン・ハウスとの間に、無線連絡設備を設立した。
プリンス・オブ・ウェールズ(皇太子、後のエドワード七世)がこのヨット上でひざを怪我し、船上で治療につとめており、女王は病状をたえず知りたがって、マルコーニに無線開設を依頼したのだった。
十六日間に百五十回もの電報が無線でとりかわされた。
マルコーニは、専門家でない一般大衆が一番びっくりしたのは、動いている船から無線で通信が送れることだったらしいと評している。
これからの実演は、何よりもまず、海上で無線電信がちゃんと実用できることを大衆にわからせ、注目をひく目的で行なわれた。
マルコーニはひっきりなしに新聞にニュース・ストーリーを供給するよう努力をはらった。
8 無線の独占をめざす top
一方で彼は装置の改良と独占の拡大につとめた。
一八九七年にオリバー・ロッジか、電波の送信機と受信機を同調させる基本的方法を特許にとっていた。
マルコーニはこの同調の原理を実際の無線電信の送信機と発信機に応用して実用的な装置に仕上げ、この革新の特許を一九〇〇年に出願した。
これが有名な特許七七七七号(四つの七とよばれる)である。
ロッジは特許権侵害でマルコーニを訴えたが、マルコーニは十一年にわたってイギリスの裁判所でなんとかこれを守り通した。
しかし一九一一年になってモールトン卿が、ロッジの特許を勝ちと判決した。
そこでマルコーニ会社はロッジの特許をロッジ・ミュアヘッド・シンジケートから買いとった。
この会社はロッジの特許を利用するため、一九〇一年に五万ポンドの資本で設立された。
しかしシンジケートは、イギリスで有効な商業的免許をついに獲得することができず、金銭的に成功していなかった。
シンジケートは特許をマルコーニ会社に売ったあと解散したので、オリバー・ロッジは会社からかなりの金を受けとった。
強固な支配政策の一環として、マルコーニは一九〇〇年に、無線装置を使用者に売らず、賃貸しするだけときめた。
一九〇四年ごろにフレミングが最初のラジオ真空管つまり二極管を発明したとき、フレミングはそれを販売するために製造することを許可してくれるよう、マルコーニにたのんだ。
しかしマルコーニはこう答えた。
二極管は長距離無線に大いに役立つ受信機になりそうだから、「できればこれら実験の独占権を我々の手におさえておきたいと思う。」
フレミングの契約条件によって、彼の無線の発明はマルコーニ会社の財産になってしまった。
だから彼は自分の二極管をどんなふうに使用するかを自分で決定することはできなかった。
マルコーニの考えはこうだった。
自分が独占をめざすのは、無線の完成に必要な研究と開発にあてるための収入を確保したいからである。
私は無線の完成を、自分自身か、または自分の指揮下にやってのける決意なのだ。
こういう初期の時代にあっては、マルコーニは悲しげな鋭い目と、ひきしまったうすい唇をもち、服装がいささか端正すぎる青年とみられた。
髪にはていねいにブラシをかけ、一日に二回ひげをそることも多かった。
戸外では普通毛皮のコートを着た。
時間をきっちり守るのが自慢で、会見の時刻に遅れた人は、玄関払いをくわせるか、会ってもひどく冷たくあしらった。
彼の態度は、流行はずれの服を着て、心を宙に迷わせている世間離れした教授たちと完全に対照的だった。
マルコーニはエドワード(七世)時代の上流社会で活躍したのだが、たとえオスカー・ワイルドの世界に入れられても場ちがいとは感じなかったろう。
彼は同僚の大多数とはほとんどつき合わず、自分自身の研究室にやってこられるのを嫌った。
気むずかしい性格だったが、いつも自制して外に示さなかった。
ごく少数の、直接の助手グループとはよく協力した。
だから、気分にむらのない人のようにみえた。
しかし愚か者には我慢がならなかった。
9 電波が大西洋を横断 top
無線システムが、有線電信や海底ケーブルに対抗できるために根本的に必要な条件は、送信距離を増すこと、特に大西洋をこえて通信することだった。
ヨーロッパ大陸とアメリカ大陸をつなぐ無線通信には、大きな潜在的市場があった。
この条件を達成する努力が、さっそく、極度の烈しさでおしすすめられた。
海上一七〇マイルの距離で使える信頼できる無線システムが確立したとき、マルコーニは、電波がこれだけ海面の曲がりをのりこえられるからには、二つの大陸の間に横たわる大西洋という巨大な盛り上がりを電波が乗りこえるかどうか、あえてためしてみる裏づけが十分あると感じた。
彼は通信距離を一七〇マイルからいっぺんに二千マイル以上にのばすことを試みようと決意した。
それはハッと息をのむような決定であり、ついでおこった成功は、発明の歴史の上で最も大きな業績の一つだった。
マルコーニがこの冒険をやってみようと決意したときは、まだたった二十六歳だった。
彼はコーンウォールのポルジューに強力な送信所を、またニューファウンドランドのゴッド岬には受信所を建てるよう命じた。
マルコーニはフレミングに、在来のどの送信機よりも一けた強力な送信機を設計するようたのんだ。
フレミングは電灯の電力供給用に、高電圧の電気機械を設計した経験があった。
フレミングはこのための出力は約二十五馬力必要だろうと推測し、このみつもりに従って送信機を設計した。
送信所と受信所ができあがると、マルコーニは一九〇一年十一月にゴッド岬に向かって出発した。
カナダの冬の天候がはげしいので、受信所はうんと高いマストを立てることはできなかった。
そこで、シグナル湾の岸でタコを四百フィートの高さに上げ、それから長いアンテナをつり下げた。
すべての受信設備が最高感度に調整されると、マルコーニと助手のG・S・ケンプ、P・W・バジェットは、あらかじめ打ち合わせたポルジューからの信号に耳をすましはじめた。
信号はアルファベットのSで、これはモールス符号ではトンを三つ並べたものである。
信号はポルジューから毎日午後三時から六時まで、ぶっつづけに発信された。(時差の関係で、ニューファウンドランドには午前十一時半から牛後二時半までの間にとどくはずだった。)
波長をはかる計器がまだ発明されていなかったので、ポルジューの電波の正確な波長はわかっていなかった。
それで、シグナル湾に設けた同調装置を動かしてその波をひろい上げなければならなかった。
マルコーニの耳は、長年にわたってかすかな音をききとる訓練をつんでいたので、まもなくモールス符号のSの三つのトンをききとることができた「一九〇一年十二月十二日」。
彼は自分の観測を念のためケンプにもたしかめさせたが、バジェットは少し耳が遠いので、きくことができなかった。
マルコーニはポルジューの電波を昼間きくことに成功した。
彼はまだ、長い波は夜間のほうがずっとよく伝わることに気づいていなかった。
もしもシグナル湾とポルジューが両方とも夜のときに電波を送受したなら、トントントンの音はずっと大きくきこえたにちがいない。
10 電離層の発見 top
マルコーニが成功したことを発表すると、すさまじいセンセーションがまきおこった。
新聞は、彼が前もって根回ししておいたので、この一見魔法のような成果を熱狂的にたたえ祝った。
フレミングはマルコーニの発表を『ザ・タイムズ』紙で読んだが、この仕事に自分が果した役割が一言もふれられていないのにはびっくりした。
科学界、技術界は警戒と懐疑をもってこれを迎えた。
理論物理学者たちは、電波は大洋表面にそって進むほど大きく曲がることはありえないといった。
エジソンは、人はとかくまぎれこんだ効果をきくと、それを打ち合わせた信号と思い違えるものだといった。
レーリー卿は、電波が回折によって大西洋をわたることはありえないといい、マルコーニの観測が確実だったかどうかに疑問を投じた。
一口にいえば、事実上、科学界、技術界をあげてマルコーニの敵にまわった。
理論家たちは問題全体を精力的に再検討し、レーリー、ポアンカレ、J・W・ニコルソン、A・E・H・ラブ、マーチ、リブジンスキー、G・M・ワトソンらが、それが回折によって起こる可能性はないことを決定的に証明した。
回折とは、波がふちをまわって影の部分にいくらかはいりこむ現象である。
ついでオリツァー・ヘビサイドとA・E・ケネリーが、電波が曲がったのは太陽光線のはたらきで上層大気に電離が生じたせいではないかと示唆した。
電離がおこると上空の空気は導体になるので、電波を反射したり屈折したりすることかできる。
後の研究はこの考え方が正しいことを確証した。
通信距離をのばして大陸間無線通信システムの基礎をつくろうと努めるうちに、マルコーニは地球物理学上の一大発見をなしとげたのだった。
ほとんど全世界の懐疑の目のなかで行なわれた彼のすばらしい実験は、上層大気中にこれまで知られなかった全く新しい現象分野が存在することを暴露した。
明らかにそこでは今まで夢想もされなかったたくさんのことが起こっており、その本質を見きわめようと、長年にわたる探究が開始された。
この電離層はひどく複雑な性質をもっていることがすぐに明らかになった。
それの研究は二様の観点からすすめられた。
マルコーニが電離層を研究したのは、無線電信をどうすれば改良できるかの手がかりをつかむためだったが、他方で地球物理学者たちは、地球のこの未知の新領域がどんなものであるかを明らかにするために、電波を使って探索をすすめた。
11 技術的困難を乗りきる top
大西洋横断通信の成功で、当然のことだが彼は全時代を通じて最大の発明家兼科学者の一人とみなされることになった。
しかしその反面、彼の名声を高めたその現象自体が、商業的には彼をほとんど破滅させるにいたった。
電離層は思いもよらず微妙で気まぐれなものとわかった。
それは時によっては電波を曲げて大西洋のかなたに届かせたが、時によってはそれをやらないのだった。
それは研究の対象としてはすばらしい新現象だったが、商業情報をのせた電波にとってはどうにもあてのできない伝搬手段だった。
時には電波がしだいに弱まって全く消えてしまうこともあるし、時には空電がまじってめちゃめちゃにかき乱され、まるきり聞き取れなくなることもあった。
時にはちゃんと働くが、うまく働かないことも多いというのでは、無線通信システムは、高度に信頼性のある海底電線とはとうてい太刀打ちできなかった。
海底電線は嵐にこわされることもなければ、予知できない妨害を受けることもなかったのだから。
マルコーニは一九〇一年に大西洋をこえて無線信号を送ることに成功したものの、商業的な大陸間無線システムが確立されるのはやっと一九〇八年のことであって、なお七年にわたるはげしい努力が必要だった。
マルコーニ会社の財政状態はひどく困難になった。
一九〇一年のあの大実験には、四万ポンドもの費用がかかった。
それは彼に大きな名声をもたらしたが、一文の収入もなかった。
商業面では彼の会社は船舶用マルコーニ無線システム一本槍ですすまざるをえなかった。
無線が航海の安全にきわめて重要な役目をもつことは明白であり、イギリスの大きい船の多くは、適当な賃金と賃貸料を払ってマルコー二会社の通信手と装置をのせ、そのサービスを受けた。
その一方、マルコーニは海上で多くの時間をすごし、無線電波の観測を行なった。
それは大陸間通信の問題点を解決し、海底電線と競争して勝てるような手段をみつけるためだった。
一九〇二年になってはじめて彼は、長い電波が昼間より夜のほうかよく伝わることに気がついた。
汽船フィラデルフィア号での観測は、距離五百マイルまでは昼の信号と夜の信号ではちがいはないが、七百マイルをこすと昼の信号は弱まるのに、夜なら同じ信号が二千マイル以上も遠くまで聞えることを明らかにした。
これらの観測から、電波は二つの道を通って伝わることが認識された。
一つは地球表面にそってすすむが、もう一つは一度上空にのぼってから電離層に反射されて地面にもどる。
一九〇五年にマルコーニはアンテナの指向性を発見した。
つまり、地表に平行に張った水平アンテナは、自由端と反対の方向に一番強く電波を出すことを見出した。
彼は船の位置をみつけるのにこの性質を利用し、この方法で十六マイル遠くの船の位置を非常に正確につきとめた。
この指向性アンテナの理論はあくる年になってやっとフレミングがうちたて、その性質を説明した。
マルコーニは洞察と実験だけでそれを発見したのだった。
彼は自然に強制してその秘密をもらさせる力をもっていた。
ある可能性に感づくと、並はずれた意志と執念をもってとことんまでそれを追いつめた。
長距離通信は、連続波送信機を使うとずっとうまくいった。
というのは、連続波だと共鳴効果によって笛の鳴るような音を作り出すことができ、たとえ空電による妨害がまじっても、通信手はこれなら、火花発信機からのカチカチいう音よりも、ずっと楽に聞き分けることができたからだ。
マルコーニはもともと火花発信機からスタートしたので、連続波の特許は他のシンジケートがもっていた。
彼は「時間円板」システムとよばれる機械的方法を開発して、この非常に困難な事態を打開した。
この方法を使うと半連続的な電波を作り出すことができた。
それは莫大な労力をついやして手に入れた成果で、技術的には大きな成功だった。
時間円板システムを使ってマルコーニは、一九〇八年にはじめて制限なしの大西洋横断商業無線電信サービスを開始することができた。
この機械は音がひどくやかましくて、発信局の通信手たちにうるさがられた。
彼らはまもなくこれに、「岩石粉砕機(ロック・クラッシャー)」というあだなをつけた。
12
結婚とノーベル賞、アイザックス事業に加わる top
マルコーニは一九〇九年にノーベル物理学賞を受けた。
彼の業績は十分それに相当したといえよう。
彼はノーベル賞受賞講演で、低出力の船舶無線信号が時には一二〇〇マイル遠くできこえたという自分の観察をのべた。
北と南、東と西で送受信にちがいがあるのも観測していた。
日の出や日の入の近くでは短い波は長い波よりも大西洋をよくこえた。
これらは、無線の科学と大気の物理学の両方に貢献する重要な新観察だった。
マルコーニは一九〇五年に最初の結婚をした。
妻はインチキン卿の娘、ベアトリス・オブライエンだった。
三人の子が生まれたものの、この結婚は最後まで続かず、一九二七年に解消された。
個人的な感情は別として、マルコーニがオブライエン家と姻戚になったことは、彼の会社に非常に重要な影響を及ぼした。
マルコーニ会社は一八九七年に創立されたが、一九一〇年までは無配当だった。
マルコーニは専務取締役として事業と技術の両面で経営の責任を負い、鉄の意志をもって商売上の敵とたたかうとともに、無線開発のための技術的諸問題――それは予想よりもずっと複雑で困難なことが判明した――に取組んだ。
このたたかいのなかで、彼がいたるところで困難にぶつかったことは驚くにあたらない。
彼はほとんど誰とも衝突するようになった。
はじめてイギリスにわたったころあれほど力になってくれたウィリアム・プリースとさえ、仲たがいするにいたった。
ブリースは一九〇七年に下院の特別委員会でこうのべている。
私はマルコーニ会社こそ、自分がこれまで関係をもった会社のなかで一番経営の悪い会社だと考えるようになった。
その性格は、誰とでも喧嘩をするという事実のなかに、はっきり示されている、と。
マルコーニは何よりも技術面に関心をもった。
一九二一年になって、長距離無線通信を開発するための「長年にわたるはげしい労働と実験」に、彼の会社は三十六万ポンドを使い、二百人の技術者を雇ったとのべている。
マルコーニ個人は金持ちで、自分の会社の繁栄を当てにしていなかった。
一九一〇年に、会社が現金を使いぼたしたとき、彼は会社に一万二千ポンドを貸し、当座の支払いにあてさせた。
イギリス海軍にとって、またイギリス帝国の安全という面から、無線電信ははかりしれぬ戦略的重要性をもっていたから、それを一手に引受けるマルコーニ会社がむざむざ見殺しにされるようなことは考えられなかったが、しかし商業上では、経営のやり方を変更しないかぎり、たぶんけっして成功しないだろうことも、はっきりしてきた。
マルコーニは、事業面の重荷を彼にかわって引受けられる人をさがしはじめた。
一九〇九年に義兄のD・オブライエンは彼にゴドフリー・アイザックスを紹介した。
オブライエンはアイザザックスの事業処理の手腕に感銘を受けていたのだ。
まもなく、とりあえず六ヵ月の試用期間で、アイザックスはマルコーニと並んで会社の専務取締役になることにきまった。
ゴドフリー・アイザックスは一九一〇年一月からこの地位についた。
13 イギリス帝国無線連結計画 top
その一九一〇年の三月、会社の技術者の一人が、会社は、イギリス全領土を無線局でつなぐ帝国連鎖システムを建設する契約を、政府から獲得すべきだと提案し、アイザックスの注意をひいた。
そのころ、ドイツのテレフンケン・システムは、世界全体にまたがる無線局連鎖を確立しようと、着々努力をすすめていた。 ドイツでもロッジやマルコーニと同じころ無線の研究がはじまり、G・F・ブラウン(一八五〇~一九一八。ブラウン管の発明者。一九〇九年マルコーニとともにノーベル物理学賞)の発明をジーメンス・ハルスケ会社が実用化し、他方A・スラビー(一八四九~一九一三)とG・フォン・アルコ(一八六九~一九四○)の研究をもとにAEG社が無線設備の製造をはじめた。
両社の間に特許争いがおこったが、ドイツ皇帝ウィルヘルム二世が仲裁にはいり、一九〇三年に両社は協同してテレフンケン会社という新会社を作った。
テレフンケンはドイツ政府の後援で、ドイツ海軍に無電設備を備えつけ、アフリカや南太平洋のドイツ植民地に無電局を建設した。
テレフンケンの装置は質がすぐれており、またマルコーニが賃貸しかしなかったのに対して、売り渡しもしたので、その勢力は大きく伸長した。
第一次大戦にいたるまで、テレフンケンとマルコーニは世界無電界の覇権をめぐってはげしい競争をつづけた。
マルコーニ会社は三月に植民省にあてて手紙を出し、イギリス帝国全域に無線局を建設する二十年間の特許をあたえてほしいと申し出た。
十一月までは何の回答もえられなかったが、この月になって、提案はジョージ五世の戴冠式のさい、開かれる帝国会議で検討されるだろうという知らせが会社にあった。`
同じ一九一〇年三月に、ゴドフリー・アイザックスの兄ルフス・アイザックスが、下院の平議員から抜擢されて法務次官になった。十月に彼は法務大臣になった。
一九一一年六月に帝国防衛委員会の分科委員会は、政府所有となるべき六つの無線局の建設を直ちに着手するよう、そのためマルコーニ会社と契約の交渉をはじめるべきだという提案を承認した。
無線局建設に関する政府委員会の勧告は、郵政長官ハーバード・サミュエルにまわされ、実行に移されることになった。
長々と交渉を重ねたあと、郵政省と会社は合意に達し、会社は一九一二年二月に契約申入れをし、郵政省は同年三月七日に暫定的にそれを文書で受入れた。
ゴドフリー・アイザックスはその数日前に、そういう契約が結ばれるだろうということを事のついでに兄のルフスに知らせた。
14 アメリカ・マルコーニ会社の増資 top
一九一二年三月九日に、マルコーニとゴドフリー・アイザックスは、アメリカ・マルコーニ会社の難状を打開するためニューヨークに向けて出発した。
二人は三月十六日に到着し、『ニューヨーク・タイムズ』が主催した盛大な大衆宴会で歓迎された。
この新聞は前もってルフス・アイザックスから短い電報を受取っており、その中には「どうかマルコーニと私の弟がすばらしい企業を見事に発展させたことを祝ってやってください」という文言が含まれていた。
この電報は、他のたくさんの同様な通信と一緒に、宴会の席上で読み上げられた。
一九一〇年には、アメリカ・マルコーニ会社(一八九九年創立)の赤字はつもりつもって四四万五一〇ニドルに達していた。
この赤字は一九一一年と一二年で穴埋めされたが、一九一二年の春にはまだ株価は額面を割っていた。
この会社は以前から、アメリカのユナイテッド無線会社と訴訟で争っていた。
ユナイテッド無線会社(三極真空管の発明者リー・ド・フォレスト(一八七三~一九六一)が一九〇一年に作ったアメリカ・ド・フォレスト無線電信会社の後身)は、アメリカの無線事業の大部分を独占していたのだが、一九一二年についに破産してしまった。
そこでゴドフリー・アイザックスは、アメリカ・マルコーニ会社の資本をもう数百万ドルふやしてユナイテッド無線会社の資産を買入れ、いっそう事業を発展させるべきだと提案した。
アメリカ・マルコーニ会社の重役たちは、マルコーニとゴドフリー・アイザックスが、イギリスのマルコーニ会社を代表して財政的責任を引受ければよし、さもないかぎり、増資には同意しないといった。
マルコーニは、アイザックスが個人でアメリカ・マルコーニ会社の新株を五十万株引受けるという条件で、やっとこれを受入れた。
アイザックスは株の大部分をさまざまな金融代理人に分けた。
一九一二年四月九日、ゴドフリー・アイザックスは兄弟のルフスとハリーと一緒に食事をし、二人にのこった株の一部を引受けないかといった。
彼はルフスに、イギリス・マルコーニ会社とアメリカ・マルコーニ会社との関係は、イギリス政府がイギリスの会社と契約を結んだとしても、アメリカの会社はそれから何の利益も得られないようなものだと保証した。
ルフスはよくよく考えたあげく、株を引受けることを断った。
しかし彼が去ったあと、ハリー・アイザックスは五万株引受けるといった。
15 タイタニック号の遭難と株価の急騰
top
四月九日から数日たつと、アメリカ・マルコーニ会社の株は上がりはじめた。
イギリス・マルコーニ会社の株はめざましく上がり、十五シリングから、四月十六日にはほとんど十ポンドすれすれになった。
一九一二年四月十四日、世界最大の汽船タイタニック号が処女航海の途上で沈没し、全世界が大きなショックを受けた。
この船は構造が特殊なので絶対沈むことはないと考えられており、船長はそれを信じて氷の海原をフルスピードで走らせていた。
船は真夜中直前に氷山に衝突し、三時間たたないうちに沈没した。
乗客と乗組員は乗れるかぎり救命艇に乗り、二人のマルコーニ無線通信手がひっきりなしに無線救助信号を送り出した。
二人の通信手は最後まで職場にとどまり、船とともに沈んだ。
無線信号のおかげで、近くにいた船は全速力で遭難現場にかけつけた。
生残った七一二人が救われたが、一五一七人が死んだ。
マルコーニ無線は、生残った者たちを救助するうえに大きな役割をはたしただけでなく、全世界に事件の一部始終を時々刻々に知らせつづけた。
遭難現場のすぐ近くにいた一隻の船は、無電設備をもっていなかったため、信号を全くきかなかったことがわかった。
もしもこの船が無線をもっていたなら、もっと多くの人が助かっただろうことは疑いない。
今や世界の世論は、すべての外洋航行船に無線装備を義務として強制するよう要求した。
当然この要求は、マルコーニ会社の株価をいっそうおしあげる刺激となった。
16 マルコーニ・スキヤンダルのはじまり
top
一九一二年四月十七日の夜、ハリー・アイザックスは兄ルフスを訪れ、自分が引受けたアメリカ・マルコーニ会社の株をいくらか分担してくれと、強くいいはった。
ルフスはついに一株二ポンドで一万株引受けることを承知した。
その四月十七日の夜おそく、ルフスは当時大蔵大臣だったロイドジョージと、そのときダウニング街の大蔵大臣官邸に住んでいたマスタ・オブ・エリバンク(マスターは子爵または男爵の長男の称号)――当時大蔵省官吏選考長官で与党の院内総務だった――に、自分が獲得した株の一部を引受けないかとすすめた。
二人とも株を買うと答えた。ルフスは、すぐ払うことは考えなくてよい、株はまだ現実には存在しないのだからといった。
新株の発行は、四月十八日に、アメリカ・マルコーニ会社の株主たちから承認された。
その日の晩にロンドン市場でのその値段は一株三ポンドに上がり、あくる日には三ポンドと四ポンドの間を動揺した。
一九一一年七月に約百万ポンドの価格だった株が、一九一二年には約四百万ポンドに上がった。
ルフス・アイザックスとロイドジョージは、株を自分の名で買っていたので、大臣たちがマルコーニ会社に投資しているという事実がすぐにシティーに広まった。
それをきいた人たちの大部分は、大臣たちはイギリス・マルコーニ会社の株に投資しているのだと考えた。
このうわさがいっそう株価上昇をあおったことは疑いない。
ルフスは自分の抹のうち七千株をこの四月十九日に、一株約三ポンドで売った。
そのあとの売買で、一九一三年三月までに結局二二〇〇ポンドの損をした。
イギリス・マルコーニ会社の無線局連鎖の契約をめぐる折衝は、一九二一年前半にすすめられていた。
そのころから、契約がうまく結ばれるか否かに、大臣たちが金銭上の利害関係をもっているといううわさがシティーやクラブで広まった。
法務大臣が弟のゴドフリーにそそのかされて、郵政省長官サミュエルに影響力を及ぼしてその契約を強引に成立させ、法務大臣、大蔵大臣、郵政長官が内部情報に基づいてマルコーニの株を安いうちに買い、そのあとブームの絶頂で売って、莫大な財産をつくったというのだった。
サミュエルがこのうわさを耳にしたのは六月ごろだった。
ルフスは彼に、アメリカ・マルコーニ会社の株を売買したことを語った。
サミュエルはこの情報はたいして重要でないと思ったが、それでも首相のアスキスに報告した。
アスキスの見解は違っていた。
「我々の同僚が、これほどばかげたことをしでかすとは、考えられないことだ」と彼はいった。
一方その間に契約の署名もすみ、いよいよ議会に提出されて追認か拒否かを待つことになった。
議会は事務がひどく繁忙だったので、八月七日、つまり夏季休会前の最終日まで、マルコーニ契約を討議するひまがなかった。
郵政長官サミュエルは、契約に反対する人々を納得させることができなかったので、この件の討議を秋までのばすことに意見が一致した。
一部の不満な人々は、夏の休暇の間に一切がご破算になってしまうことを期待して秋まで延期されたのだと言いはった。
サミュエルはあくる八月八日に、ヨークシャー行きの列車に乗るためキングズ・クロス駅へ行った。
彼は駅の新聞雑誌販売店で、『アイ・ウィットネス』(目撃者)という三流週刊誌をみかけた。
それはG・K・チェスタートン(一八七四~一九三六。作家、評論家)の弟セシル・チェスタートンが編集する雑誌だった。
それに「マルコーニ・スキャンダル」と題する記事がのっていた。
ゴドフリー・アイザックスとサミュエルがひそかに共謀して、「イギリス国民をして上記サミュエルの手を経て莫大な金をマルコーニ会社にあたえさせ、上記アイザックスの利益をはかった」というのが内容だった。
サミュエルはすぐさまルフスに手紙を送り、その記事はあんまりくだらないので対抗処置をとる気にはなれないとのべた。
そのすぐあとルフスは首相に手紙を送って事情を説明した。
アスキスは、「その下品な三文記事を注意深く読んだが、私ももちろん貴下がそんなものを気にする必要はないと考える」と答えた。
『アイ・ウィットネス』は相手にされなかったので、前の記事にひきつづき、金融ジャーナリストW・R・ローソンの手になる、マルコーニ会社に関する長いシリーズを連載しはじめた。
九月になると、マックスが『ナショナル・レビュー』(国民評論)誌でローソンの記事を引用しながら、「大臣たちは未曾有の大規模な、公私混同による不当利得の記録をつきつけられながら、彼らの個人的利害関係に関する疑惑が世上に流布しているのにまるきり驚こうともしない」と評した。
17 特別委員会が設置される top
マルコーニ契約が再び下院の議場にのぼったのは一九一二年十月十一日のことだった。
サミュエルは、マルコーニ会社、マルコーニ氏、郵政長官の間で結ばれた契約に関する諸事情を調査するため、特別委員会を任命すべしという動議を出した。
討論の中でジョージ・ランズベリーは、「政府を代表して契約を結ぶにあたっては、直接、間接を問わず、それに利害関係のありそうな人が、当事者となるべきではない」といった。
この言葉はルフス・アイザックスのことをいっているように思われたので、ルフスは直ちに立ち上がって、自分は契約の締結に何ら影響力を行使したことはないし、イギリス・マルコーニ会社の株を取引したこともないといった。
しかし彼は、アメリカ・マルコーニ会社の株を売買したことはいわなかった。
ロイドジョージは、いわゆるうわさとはどんなことなのか教えてくれと要求した。
「委員会に付託する前になぜ政府がフランクな討議を欲するかといえば、その理由は、議会の背後で汚れた唇から唇へと伝えられたこういううわさ、このいまわしいうわさを、我々はここへ持ち出したいと思うからである。」
しかしロイドジョージも、自分がアメリカ・マルコーニ会社の株を取引したことをいわなかった。
設置された特別委員会は十五名の委員から成り、うち七人が自由党員、六人が保守党員、二人がアイルランド民族党員だった。
委員会の調査は六ヵ月以上つづいた。
閣僚、官僚、金融家、技術者、ジャーナリスト、株式仲買人らか詳しい審問を受けた。
二万九一七六の質問が発せられ、議事録は四つ折版二段組で二千ページ近くに達した。
暴露された情報のなかには度胆をぬくようなものもあったが、犯罪をにおわせるものは一つもなかった。
一九一三年二月にルフス・アイザックスとサミュエルは『ル・マタン』紙を相手どって訴訟をおこした。
『ル・マタン』は、契約の交渉がすすんでいる間に二人がイギリス・マルコーニ会社の株を操作したと書いたのだった。
二人は有名な保守党の法律家エドワード・カーソンとF・E・スミスを弁護士に雇ってたたかい、『ル・マタン』は記事を完全に取り消した。
だがルフスは、その機会をとらえて、自分とロイドジョージがアメリカ・マルコーニ会社の株を買ったことをのべた。
この情報は大きな政治的センセーションをまきおこした。
契約に反対する新聞雑誌界はこぞってこの問題に論点を集中し、特別委員会の活動に対する関心が急に高まった。
ルフスとロイドジョージは委員会に喚問された。
大衆は大臣ともあろうものが、私的な金融活動で初歩的な判断の間違いをおかしたらしいときいて、びっくりした。
二人は、比較的少額の投資――二人ともそれで損をした――によって、政府と自分の経歴の両方を大変な危機におとし入れたのだった。
ロイドジョージの友人たちは、彼は株式取引では子供同然だったのだと弁解したが、彼に敵意をもつ批評家たちは、彼は現職の大蔵大臣ではないかと反論し、国家の財政がそんなにも不適格な人物の手中にあることはきわめて不幸だと評した。
ルフスのほうは、当時最大の金融法律家だったから、いくら何でもそういう問題で子供同然だったというわけにはいかなかった。
18 政治的攻防へ発展 top
だが月日がたつにつれて、委員会の活動はいよいよ政治的になった。
対立する自由党の委員と保守党の委員は、調査をすすめることよりも、互いに相手側を攻撃するほうに熱中するようになった。
実際彼らは、委員会が設立された目的をそっちのけにして、党派闘争に役立つ新しい爆薬をみつけるほうに夢中になっているようにみえることが多かった。
保守党は、この大臣の軽率な行動を手がかりに、政府を総辞職に追いこめる可能性があるとみてとった。
審問が進行している間に、その折の株式取引で「こっぴどい目にあって」破産したある株式仲買人の帳簿が管財官の手にはいった。
この株式仲買人は、マスター・オブ・エリバンクのためマルコーニ株の操作をやっていたことがわかった。
委員会がその帳簿をしらべてみると、自由党の資金責任者だったエリバンクが、党にかわって自分の名で資金の一部をマルコーニに投資していたことがはっきりした。
委員会はエリバンク自身には手が出せなかった。
というのは、彼はすでに院内総務の地位を退き、委員会が設置されてから二ヵ月ほど後に、重要な個人事業で南アメリカヘいってしまっていたからだ。
ルフス・アイザックスとロイドジョージは、本人と妻の銀行通帳を、調査のため委員会へ提出するよう要請された。
マルコーニは自分の会社のために、その契約から手を引くと申し出た。
彼は委員会にあてて、自分の経歴と会社を説明した長文の手紙をよせ、こうのべた。
会社がそのブームのさなかにあった間、自分は一株たりとも売り買いしなかった。
自分も自分の会社も、株価の変動には全く何の責任もない。
変動はすべて「自然的需給関係」によっておこったのである。
彼は終わりに、何の底意もなしにイギリス政府と契約したことに対して自分がひどい非難を加えられていることに、憤慨の意を表明せずにはいられなかった。
彼は自分の会社の内情、特にゴドフリー・アイザックスがアメリカで行なった事業――それを彼はすべて承認し支持した――について委員会が尋問したことに腹を立てていた。
彼は、自分の会社がイギリス政府の諸省のために――それは「実は国民全体」のためである――こうも長年にわたって行なってきたサービスが、もうちょっと高く評価されると期待したのに、そうならなかったのは残念に思うとのべた。
こういった言明に対し、質問が出されたのに答えて、マルコーニはこうつけ加えた。
私は、自分の名をくっつけたありとあらゆるバカさわぎがわき立っているのに、本当に腹を立てている。
「外へ出てみれば、いたるところに『マルコーニ・スキャンダル』『マルコーニ式』『マルコーニ流』『マルコーニ事件』等々と書いたプラカードが目につくだろう。
私は自分の名が党争のスローガンにされ、私が少しでもそれに関係があるとは誰一人いっていないありとあらゆる中傷的非難を吊り下げるかけ釘にされていることに、きわめて強い不快を感じるといわざるをえない。」
19 委員会の結論は白 top
委員会は一九一三年六月に、最終報告を出した。
それは、八対六の多数決で、大臣たちに対する嫌疑は「絶対に事実無根で、それを公表した責を負うべき人々は、それを正しいと信じる理由をもっていなかった」と結論した。
ロバート・セシル卿は、大蔵大臣は「任務にそぐわない重大な不行跡をおかした」と非難する草案を提出したが、しりぞけられた。
この委員会報告が下院で討議されたとき、ルフスは「あの株を買ったのは間違いだったと、まじめな厳粛な顔をして」のべた。
ロイドジョージはたくみな演説を行ない、反対党には何ら弱身をみせずに議会に対し陳謝することに成功した。
彼は、「もしも事実全体をあの十月十一日の議会ですっかり明らかにしていたら、こんなことにはならなかったろうに」と率直に認めた。
彼はその次の委員会で説明しようと思っていたのだが、事件が急展開して「それが判断のあやまちだった」ことを明らかにしてしまった。
おしまいに彼は、自分が何か破廉恥なことをおかしたとは思っていないとのべた。
「私の行動は無思慮で、不注意で、間違っていたかもしれませんが、私は悪意なく正々堂々と正直に行動したのです。」
首相は、大臣たちに悪意はなかったが、行動は十分慎重ではなかったと思うとのべた。
最後に議会は、厳密に各党の路線に従って投票した後、大臣たちの遺憾の表明を受入れ、不誠実に行動したというかどは無罪とし、贈収賄という非難は完全に虚偽であることが証明されたので却下すると議決した。
その数ヵ月後、ルフスは高等法院長に出世した。彼は後にインド総督になった。
マルコーニ事件は彼に非常な苦痛をのこし、以後彼は二度とこのことを口にしなかった。
アスキスの伝記の著者はこう記録している。
アスキスは「死ぬまでこれを、自分が公的生活の間に処理しなければならなかった私的事件のうち、最も困難で最も苦しかったものと考えていた。」
この事件で、マルコーニの契約の追認は一年遅れた。
その結果、第一次世界大戦が一九一四年にはじまったとき、イギリス帝国全土を結ぶ無線局連鎖はできあかっていなかった。
この年の終わりに、政府は契約をとり消したので、マルコーニ会社は六十万ポンドの損害をこうむった。
しかしゴドフリー・アイザックスがイギリスとアメリカの事業経営を引受けてからは、二社とも以前よりずっと繁栄していた。
アメリカ・マルコーニ会社は、一九一一~一二年までは巨大な赤字を累積するだけだったが、一九一三年には二一万一二四六ドルの純益を生みだした。
この財政的・政治的危機の時期にマルコーニが示した粘り強さは、無線の技術開発に示した粘り強さにほとんど劣らないめざましいものだった。
彼の性格はきわめて頑固で、そのため人々に愛されることは少なかったが、同時に並はずれた勇気をもっていた。
初期のころに非常に有能な人々が彼の仲間に加わり、以来水火も辞せず彼のもとにふみとどまったのは、特に彼のこの勇気にひきつけられたからだった。
究極には技術的・商業的に成功するという彼の確信は、度かさなる体験によって裏打ちされて、彼の魅力に乏しい性格をおおいかくすほど偉大なものになっていたのだ。
20 短波通信の開発 top
第一次世界大戦の軍事的必要から、短波に対する関心が復活した。
一九一六年にマルコーニは、C・S・フランクリンにこの問題を再調査するよう依頼した。
一九〇四年に二百メートル以下の波長帯は、アマチュアの遊び用にあたえられた。
長距離通信にはもっと長い波しか使えないと考えられたからだった。
ところがアマチュアたちは、時には二千マイルも遠くの小さな発信局が出した信号をききとることができるのを発見した。
一九一七年までに、フランクリンは、波長三メートルから十五メートルの電波を反射するための、針金で作った鏡を考案し、一馬力以下の短波送信機を使ってロンドンとバーミンガムの間で通信を送ることができた。
大戦後、マルコーニは自分のヨット「エレットラ」号を使ってフランクリンの研究に協力した。
この優美な船は、長さが二二〇フィートあり、以前はオーストリアの王子のものだった。
マルコーニはこの船を一九一九年に買い入れ、手を加えて、浮かぶ住居兼実験室とした。
マルコーニは各大洋を巡航したが、この浮かぶ実験室は無線通信で彼が次に実現した大進歩にはかりしれないほど役立った。
フランクリンは短波の研究をつづけ、電波を送るうとする方向に直角にたくさんの送信用アンテナを並べることにより、ずっと強力なビームを作りだした。
彼はそれのうしろに針金を並べたものをもう一つおいて、反射器の役をさせた。
針金の間の距離が反射される電波の波長に比べて小さければ、針金の格子はまるで連続した鏡面のように電波を反射する。
アンテナ中の電気振動は真空管を使って作りだした。
真空管はそのころには強力な発振器に成長していた。
(三極真空管は一九〇六年にド・フォレストが発明したが、数年間は二極管と同じく検波にしか使われなかった。
一九二一年になって、ド・フォレスが増幅作用を発見し、一三年にアームストロング、ド・フォレストらが発振作用を発見して、はじめて三極管はその本来の機能を発揮することになった。)
この送信システムを使って波長十五メートルから九十メートルの強力な短波ビームをつくり、地表から十度ないし十五度以上へ向けて射ち出した。
ビームは電離層に屈折されて地表にもどり、遠距離の受信局にとどいた。
マルコーニはエレットラ号上で観測し、ビームの到達距離と集束の鋭さをテストした。
おしまいに、一九二四年になって、ポルジューからたった十二馬力を使って発射された波長三十二メートルの電波が、南アメリカとオーストラリアではっきりと受信された。
マルコーニ会社はとうとう、海底ケーブルに立派に太刀打ちできる通信システムをつくりだしたのだった。
会社はイギリス政府に、イギリス帝国全土を短波ビームでつなぐ無線局システムを建設するよう提案した。
提案は受入れられた。
短波局の連鎖はすぐさま成功をおさめ、長波局の連鎖よりはるかに少ない費用ですんだ。
こんなわけで、連鎖システムの建設が十六年も遅れたため、その長期間のおあずけからさまざまないら立ちや緊張、事業上、政治上の摩擦が生じはしたものの、結果からみればこの遅れは一見不幸のようで実は幸運だったことがわかった。
そのおかげでマルコーニ会社は、いずれは価値を失って資産から削除しなければならなかったにちがいない長波局に、大変な資本投下をしないですんだのだった。
短波システムの成功はイギリス政府に、無線会社と海底電線会社との統合を促進させる結果になった。
それでマルコーニ会社は、三十一年にわたる独立活動のあと、一九二八年にケーブル・エンド・ワイヤレス会社の一部となった。
この会社は後に国有化された。
21 ファシストとの関係 top
短波の開発でマルコーニが示した想像力と粘り強さは、全く驚くべきものだった。
グリフォーネ別邸ではじめて行なった実験も、短波ビームを使ったものだった。
一九〇五年に王立研究所で行なった講演で彼は、何かの方法でイギリスから出した電波をオーストラリアに集束できるだろう、この方法で信号を送るにはごくわずかのエネルギーしか必要でないだろうから、サービスの費用はそれだけ少なくてすむだろう、と予想している。
マルコーニは想像力を働かせて、電波について将来どの程度のことか発見されるだろうか、電波は今後どんなことをするだろうか、またどんなことをしないだろうかと、いつも注意をめぐらせていた。
一九二一年に彼は「空間のどこかからくるらしい」電波が引き起していると思われる効果に、真剣な関心を表明した。
一九三二年にジャンスキーが本当にそういう電波が外部空間からやってくることを明らかにし、マルコーニの目の鋭さを完全に実証した。
かくて、「電波天文学」という輝かしい新科学の土台がおかれたのだった。
同じ講演の中でマルコーニは次の戦争(つまり第二次世界大戦)では、電波を使ってたとえば無線操縦兵器といった「ゾッとするようなもの」が作りだされるだろうと予測している。
しかしそういうものが開発されれば、「それとたたかい、妨害する手段がすぐに発見されるだろう」といっている。
航空機を迎えうつためのレーダーや、飛行爆弾を破壊するための近接爆発信管の急激な発展は、彼の驚くべき先見の明を裏づけするものだった。
晩年になって彼はまたも未来に目をそそいだ。つまり、波長数センチというごく短い電波がもつ可能性を探究することに熱中した。彼の予見はまたもや実証された。というのは、レーダーの最大の勝利は、こういうごく短い電波の応用から勝ち取れたのだから。
マルコーニの前歴、環境、気質から考えれば、彼が一九二三年という早い時期からイタリアのファシスト党を支持したことはたぶん驚くにあたらない。
一九二七年に彼はアメリカの新聞通信員に、ムッソリーニの「大胆不敵な政治的・財政的政策がイタリアを一変させた」と語った。
最初の結婚が法王の特別免除によって解消されたあと、マルコーニは若くて美しい女伯爵マリア・クリスチナ・ベッチスカリと再婚した。
彼女もイタリアのファシストの肩をもち、ファシストが出現したおかげではじめて「イタリア五百万の婦人労働者」が「男性と絶対的に平等に――つまり同一労働、同一賃金に」なったとのべた。
マルコーニは一九三〇年にファシスト大評議会の議員に任命され、イタリア科学アカデミー総裁にもなった。
彼は二十いくつの爵位や勲位をあたえられ、また二十いくつの名誉学位をさずけられた。
ノーベル賞のほかにも二十以上の賞やメダルをさずけられた。
22 マルコーニのえらさ top
マルコーニは一九三七年七月二十日に死んだ。この日は偶然にも、彼の有名な無線電信が創立されてから満四十年目の記念日だった。
彼は一生涯人気者にはなれなかったが、史上最大の発明家の一人だった。
はじめのうちは独力で、実用上根本的に重要な新しい装置を考案した。
そのあと彼はだんだんと、無線研究技術者のチームをひきいる指導者にかわった。
指導者は、独力の発明家とは全く異なる資質を必要とするが、彼はこの分野でもあいかわらず同様に大きな成功をおさめた。
彼の会社とともに歩んだ四十年間全部を通して、彼の見通しのきく想像力、科学者の保守主義と対照的な鋭い予見、ひっきりなしにおこる事業上、政治上の混乱にたじろがない粘り強さ、衰えぬ研究への熱情、大胆な新しいアイディアといったものが、同僚たちを支配し、無線の発展に卓越した地位をしめることになった。
マルコーニは強迫観念型の発明家で、ただ一つの関心が彼のすべてを圧倒した――それが無線だった。
個々の部門では、彼にまさる人がなかったわけではない。
たとえば、彼が生んだ単一の発明のなかで、フレミングの二極管を三極管に変えて現代の多種多様な真空管を生みだす土台をつくった、あのリー・ド・フォレストのグリッドに並ぶほど輝かしいものは一つもない。
真空管こそは近代のラジオ放送、テレビ放送、その他さまざまなものを可能にしたのだった。
しかしリー・ド・フォレストは狂人型の発明家だった。彼はだれとも協力できなかったし、何か一つのものに固執することもできなかった。
彼はある分野で一つの輝かしいアイディアを生んだ後、すぐさま全く別の分野の同じくらい輝かしいアイディアへととび移った。
彼の発明を実用化するために創立された会社はみな失敗した。
マルコーニの最大のえらさは、彼が無線開発の全領域を支配したことにみられる。
全体としての彼の業績は、この分野では類を絶するものである。
彼はすばらしい成功をおさめたが、ひきかえにある種の人間的な面で大きな犠牲を払わなければならなかった。
たぶん彼が生きた時代にあっては、そうでなくては成功は不可能だったのだろう。
参考文献 top
ガーリン・E・ダンロップ『マルコーニ――人とその無線』マクミラン社、1937年。
B・L・ジャコット、D・M・B・コリアー『マルコーニ――空間の支配者』ハッチンソン社、1935年。
R・N・ビビアン『無線30年』ジョージ・ラウトレッジ社、一九三三年。
W・R・マクローリン、R・ジョイス・ハーマン『電波産業における発明と革新』マクミラン社、1949年。(山崎俊雄・大河内正陽訳『電子工業史』白揚社、1962年)
レディング候『ルフス・アイザックス』ハッチンソン社、1942年。
サミュエル伯『思い出』クレセット・プレス社、一九四五年。
『マルコーニ無線電信会社の契約に関する特別委員会報告』政府刊行文言、1912~13年。
J・A・フレミング『G・マルコーニと電波通信の発展』王立芸術協会雑誌、第八六巻(1937年)所収。
top
**************************************** |