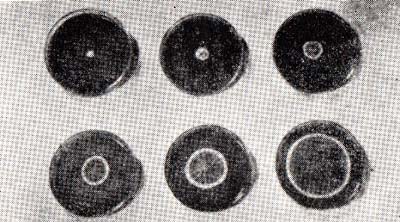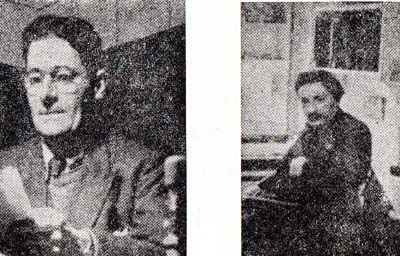|
****************************************
Index 中世まで ルネッサンス 近世 大戦後 特別読物
Ⅳ 大戦後の医学
十章 病原菌をとかす謎の物質 《ぺニシリン》 フレミング
top
1 ペニシリン発表に反応なし
ロンドンのフレット街のはずれ、パデイントン鉄道の終点は、汽車の警笛や騒音でやかましい。 くすんだ赤レンガの広大な聖メリー病院学校は、その中で、どっしりとかわらぬ姿でおちついている。
学校の中にはいってみよう。
「ライト・フレミング微生物研究所」という表札にかざられた研究所がある。
この表札にある偉大なペニシリン発見者の名前を知らない人はあるまい。
もっとも、もう忘れてしまった人もいるかもしれないが。
一九二九年フレミングの口から、ペニシリンが初めて紹介されたときの学者たちの反響は、氷のようなものだった。
その日、ロンドンの医学研究クラブの医者たちのまえには、灰色の髪、青みをおびた灰色の目、そして灰色の蝶ネククイと、すべてが灰色ずくめの小柄の紳士がだった。
聖メリー病院の細菌学教授、アレクサンダー・フレミングという紹介がすむと、彼はしずかな口調で、自分が発見し名前をつけたペニシリンの話を始めた。 |

ペニシリンを発見した
フレミング(1881~1955)
|
発表がおわったフレミングは、質問や意見がだされるのを期待するように、伏目がちに待った。
だが、賛成の意見はおろか、反対の意見も、質問さえもでない。
医者たちは、ペニシリンにひとかけらの興味も感じないらしかった。
内心の失望をかくして、しずかに席にかえったフレミングは、ひそかに思うのだった。
「いつの日にか、ペニシリンはかならず人類の光明となるにちがいない。」
フレミングという姓は、スコットランドではありふれている。
アレクサンダー・フレミングは、スコットランドのダーペル近くの農場で生まれた。
海抜八〇〇フィートの高原のまん中に、ちょうど荒海のなかの小島のような石づくりの低い頑丈な家がある。
この家で一八八一年、パスツールがタンソ病のワクチンを完成した記念すべき年に、フレミングは八人兄弟の七番めとして生まれた。
彼をとりまく自然は、たちまち少年をとりこにした。
生まれつき物わかりのよい、記憶力のすぐれたこの子供は、あ机野をかけめぐっているうちに自然の法則を学び、するどい観察力と、スコット・ランド人特有の粘り強さを身につけた。
次々と上級の学校にすすんだフレミングは、十三歳のとき、兄の住むロンドンにやってきた。
鮎の泳ぐ小川や兎の穴倉や小鳥の巣から、乗合馬車や蒸気の地下鉄の騒音でいっぱいの都会にうつるのは、全くめまぐるしい変化だった。
ロンドンの工芸学校を卒業したフレミングは、ある船会社の事務員として勤めはじめた。
彼はこの職業がすきではなかったが、自分にあたえられた仕事は忠実にはたし、不平はこぼさなかった。
しかしやがてこの退屈な勤めから解放されるときがきた。
フレミングが二十歳のとき、ちょっとした遺産がころがりこんできたのだ。
兄のすすめで医学の勉強を始める決心をしたフレミングは、軍隊時代にウォーター・ボロの試合をしたことのある、聖メリー病院付属の医学校をえらぶことにした。
こうしてなにげなくえらんだ医学の道は、彼の天性の才能とぴったり一致した。
あらゆる種類の賞、生理学、薬学、衛生学などほとんどの学科の首席はフレミングにきまっていた。
フレミングの記憶力はすばらしく、彼が夜中まで灯りをともして勉強したり、夢中になって本にしがみついたりしているのをみた者はいなかった。
彼は学校の射撃チームの選手てあったし、ウォーター・ポロや水泳もやり、素人芝居までした。
こうしてすばらしい成績で学校を卒業したフレミングが、つぎの働き場所としてえらんだのが、有名な細菌学者アームロス・ライトの君臨する「予防接種研究室」だった。
2 「予防接種研究室」 top
チフスのワクチンを作り出して、有名になっていたライトは、病気にたいする免疫はどんな仕組で行われるかを研究していた。
古ぼけた建物のなかの、狭い二つの部屋にたてこもった助手たちは、天才的な師のライトを中心に、科学にささげた情熱でむすびあっていた。
雄弁で皮肉なライトをかこむ賑やかなグループの中にはいっても、フレミングはあいかわらず、用心ぶかい無口な青年だった。
ライトは、免疫の本能としてメチニコフのとなえる食菌作用の正しさを信じていた。
そして食菌作用を研究しているうちに、この作用はメチニコフが考えていたよりもっと複雑で、食菌細胞と細菌が出会っただけでは不充分で、食菌細胞が細菌を食べてしまう前に、オプソニンという物質が体の中にできることを発見した。
オプソニンというおいしいバターをぬられた細胞だけが、食菌細胞に食べられるのだった。
フレミングは食菌作用を研究してしるうちに、人間が自分の体の中にもっている天然の武器、つまり食菌細胞オプソニンなどを使って、自然に細菌と戦う姿に強い感銘をうけた。
こうしてライトのもとで、ワクチンの勉強をつづけながら、彼は伝染病と戦う手段の探究にのりだした。
こののち一生のあいだ、彼の研究の目標は、当時の人類のもっとも恐ろしいわざわいと思われていた伝染病の病原菌を、どうしたら殺せるかということだった。
一九〇九年は医学の歴史のうえで注目すべき年だった。
この年、エールリッヒは秦佐八郎と協力して「魔法の弾丸」サルバルサンをつくりあげた。
運命の気まぐれによって、この世界最初の化学療法剤は、イギリスでは、フレミッグが最初に使うことになった。
それまでのゆっくりしたワクチン療法をみなれていたフレミングは、おどろくほどの短時間で病原菌を殺すサルバルサンの偉力に目をみはった。
それから五年後、第一次世界大戦が始った。
フレミングはフランスにわたり、野戦病院の研究室で働くことになった。
毎日病室を横ぎるたびに目にうつる負傷兵のようすは、彼の心を苦しめた。
骨をくだかれ、筋肉をひきさかれ、血管をきられた兵士たちが毎日運び込まれる。
傷口はふさがれ出血は止まっても、わずかな時間のあいだに、顔色は灰色にかわり、脈が衰えて死んでゆく。
ガス壊疽(えそ)だ。
軍医たちは傷口にやたらに石炭酸やオキシフルをつめこんで包帯するのだったが、ききめはなかった。
戦場の泥にまみれた傷口から、容赦なくガス壊疽菌は入り込んだ。
いったん発病したら最後だった。ガス壊疽を喰いとめる決定的な力をもつ薬はなかった。
(ガス壊疽というのは、土の中にいるガス壊痕菌という菌が傷口から入り込んで、体の一部をくさらせる病気である。
くさる部分にガスが発生してふくれあがり、毒素のために心臓がよわって死ぬ。)
フレミングは小さな木造の納屋にこもって、ガス壊疽(えそ)と敗血症の研究に専念したが、彼らの必死の努力もむなしく、負傷兵たちをガス壊疽から守ることはできなかった。
苦しみながら次々と死のとりこになり、彼の救いの手を待ちのぞむ人々のよこで、フレミングはサルバルサンがスピロヘータを殺すように、ガス壊疽や敗血症の病原菌を殺す薬、しかも人間には毒でない薬をみつけたいと心から願った。
戦争は終った。フレミングはふたたびロンドンの研究室に戻った。
3 鼻汁の殺菌力 top
その頃フレミングは、やっかいな鼻かぜをひいていた。
ある晩、棚や机の上にうずたかく積みあげられた、培養皿(丸い平たいガラスの容器で、なかの寒天の表面に細菌が植えてある)を一つ一つ注意深く調べていた。
同じ部屋の若いアリスンは、とっくに捨ててしまってもいいような古い培養皿をゴタゴタと取っておくフレミングのくせを、おかしく思いながら自分の仕事をつづけていた。
ある日のこと培養皿を明りにすかして調べていたフレミングは、ぬっと一枚の培養皿をアリスンの前にさしだした。
「潔癖屋さん、私のがらくたの中に、こんなおもしろいものがあったよ。」
びっくりしてアリスンがのぞきこむと、寒天の表面には黄色い大きい細菌のかたまりが生(は)えていた。
そして奇妙なことには 細菌のかたまりの中に、菌がとけてガラスのように透明な場所があるのだった。
なんのことやらわからないで首をかしげているアリスンに向かって、フレミングはいった。
「これは私の風邪の鼻汁を植えたものだよ。
この黄色い細菌はどこかからとんできて、寒天の上で増えたのだろうが、見たまえ、この透明なところは 鼻汁のために細菌がとかされてしまっている。
私はこれはとてもおもしろい発見だと思う。
一緒に鼻汁の中の細菌をとかす物質を探し出掃除ゃないか。」
これは全く偶然の発見だった。
偶然ということ、それはでたらめに石を役げたらうまくあだったというようなものではない。
偶然の発見にも実はルールがあるのだ。
さて翌日から二人は「鼻汁の殺菌力」という奇妙な研究にとりかかった。
まずためしに試験管に、細菌でにごった液体を入れて、鼻汁を一滴たらしてみた。
にごった液体はみるみるすんでしまった。
鼻汁のかわりに人間の爪、唾液、毛、涙をいれると、どれも液を透明にする力をもっていた。
人間の体の組織には、黄色い細菌をたちまちとかしてしまう働きのある何かが、ふくまれているらしかった。
「やあ、今日はすみませんが、あなたの涙をいただけませんか。」
この頃フレミングの部屋をおとずれた客は、誰彼をとわず涙をしぼりとられた。
レモンの皮を目にあて、むりにすい取られた涙は、病院の新聞の漫画のたねになった。
フレミングは涙の中にある殺菌力のある物質に菌をとかすという意味でリゾチームと名づけた。
リゾチームは人間の体からばかりでなく、花からも、根からも、卵からもとれた。
細菌のたくさんいる空気や土の中にいる動物や植物が、細菌におかされずにすんでいるのは、リゾチームが守っているからだということがわかった。 |

人の眼から涙をとるフレミング
|
「もしかしたら、リゾチームは伝染病の病原菌を殺してくれるかもしれない。」
はじめフレミングはそう思った。
しかし残念なことに、リゾチームは恐ろしい伝染病の病原菌には歯がたたなかったが、人間の体には害がなくて、細菌だけを殺す薬をもとめていたフレミングは、リゾチームに大きな期待をかけて研究をつづけた。
フレミングのこの期待は、当時の医者からからはまるきり無視されてしまったが、現在では微生物学者、工業家、医者たちにとって、リゾチームは重要なものとなっている。
4 カビが菌をとかす top
一九二八年の夏、フレミングは四十七歳になっていた。
リゾチーム発見から六年がすぎ、大学教授フレミング博士のしずかな研究の日々がながれていった。
その年の夏はすずしくて湿気があり、カビにとっては都合のよい気候だった。
あいかわらず薄暗く、やたらに培養皿が積まれている実験室で、フレミングはブドウ状球菌(敗血症やうみを持つ病気のもとになる病原菌)を培養した培養皿を調べる仕事に忙しがっていた。
ブドウ状球菌についての本を書くための実験だった。
そのとき友人のプライスがこの部屋にたずねできた。
「あいいかわらず汚いな。」
「ハッハッハ、ぼくにとっては宝箱さ。」 |
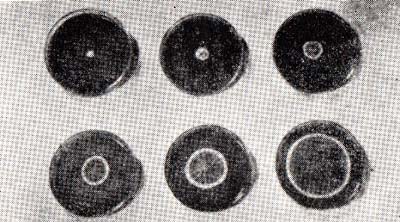
ペニシリンを作るカビ
|
フレミングはプライスを相手に冗談をいいながら、それでも仕事の手はやすめず、培養皿のふたをとっては、寒天の上のブドウ状球菌のようすを調べていた。
寒天のうちのいくつかにはカビが生(は)えていた。
何度もふたをとっているうちには風でとばされてきたカビの胞子が寒天について、そこで成長してしまう。
いつものことである。だが、突然彼はだまりこみ、真剣な顔になった。
「これはかわっている。」
いつもとちがってこの培養皿では、カビのまわりのブドウ状球菌がとけている。
半透明の黄色いかたまりを作っているブドウ状球閑のひろがりの中で、そこだけが透明な露(つゆ)の粒になっていた。
プライスが、「リゾチームの発見のときもこんなでしたわ。」と話しかけたが、フレミングは返事もせずに、立ちあがっていた。
彼は白金の小さな環でそのカビをすくいとると、培養用の肉汁を入れた試験管にそれを移し入れた。
数日後、カビはもっとふえ、実験に使えるようになった。
フレミングは、カビが細菌をとかして殺してしまう力を試してみた。
まず培養皿の中心にカビを植え付け、そのまわりに放射状に、いろいろな病原菌を植えてみた。
この培養皿をあたためて培養してみると、カビに関係なく生えている菌があったが、ブドウ状球菌、連鎖状球菌、ジフテリア菌などは、カビのだす物質をきらって、カビからずっとはなれたところに生えているだけだった。
「このカビはすごい力をもっているぞ。
リゾチームとちがって、病原菌を殺したり、生えなくさせる働きを持っているらしい。」
5 フレミングをつぐフローリーとチェイン top
一九三七年、オックスフォード大学ではフローリー教授とチェイン博士の手でリゾチームについての研究が完成された。
ペニシリンが発見されてからこの年までにいくつかの出来事が起こった。
一九三五年、ドイツのイー・ゲー・ファルベン会社のゲルハルト・ドマークが、あらゆる種類の化膿菌によくきくプロントジルとよぶ薬を発表した。
エールリッヒのサルバルサンにつぐ、化学療法の「魔法の弾丸」として、人々にむかえられた。
アメリカのロックフェラー研究所ではルネ・デュボス博士がのちに抗生物質の華々しい研究を生みだすもとになった重要な研究を着々とすすめていた。
そして一九三九年第二次世界大戦が始った。
新しい薬、フレミングの夢をみたすような薬が生まれる気運は熟していた。 |
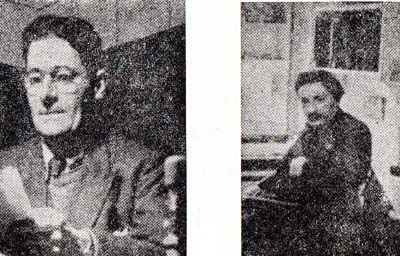
フローリー(1898~ ) チェイン(1905~ )
|
ハワード・フローリー博士はオーストラリア人で、生理学と病理学を学んでいた。
彼はフレミングの発見したリゾチームの不思議な力に強くひかれ、若い生化学者チェイン博士と一緒にリゾチームを取り出して結晶にすることに成功した。
チェインはこの研究をすすめながら、リゾチームに似た作用をもつ物質をさがし、それがどんなふうに研究されているかを調べて参考にしていた。
やがて彼はペニシリンにぶつかった。
ペニシリンの病原菌を殺す力のすばらしさが印象的だった。
化学的な性質が不安定であって、結晶にして取り出すことがむずかしいという問題も、かえって化学者チェインの征服慾をかきたてたのかもしれない。
フローリーとチェインは、ペニシリンのほかに二つの問題に興味をもっていた。
さてどれから先に手をつけようか?
二人は議論しながら帰り道をたどっていた。
そして二人がちょうど公園の入口の大きなエルムの木の下にさしかかったとき、二人はペニシリンを始めることにきめたのだった。
チェインは、その頃カビについては何一つ知らなかった。
まずカビの扱い方になれなければならない。
気まぐれなカビは中々思うようにペニシリンを作り出してくれなかった。
チェイソはみるみるうちにこわれてゆくペニシリンを何とかつかまえようと、自分の知識を総動員した。
そして当時に血液などの保存のためさかんに使われるようになった「凍結乾燥」をペニシリンに応用してみようと思いついた。
「凍結乾燥の原理」は簡単なもので、ペニシリンを凍らせて、真空状態にするだけでよい。
ペニシリンのまわりの水分は、まわりを真空にされると、個体から直接気体の状態にうつってしまって飛び去り、あとにはペニシリンの粉末だけが具合よく残される。
こうなるとチェインは一刻もはやく動物に試してみたかった。
その結果は、フレミングのときと同じに、中毒症状は何もあらわれなかった。
凍結乾燥という新方法のために、フレミング以来の難問は見事に解決された。
フローリーとチェインのコンビには、新しくヒートリーがくわわって、ペニシリンの研究にはいっそう拍車がかけられた。
ペニシリンをなるべく純粋な形で、量を多く取り出す研究、鼠を使っての病気の治療の研究がすすめられた。
鼠の治療の効果はおどろくほどあがった。
病気の鼠がバタバタたおれてゆくなかで、ペニシリンを注射した鼠ばかりが元気に走り回っているのだった。
フローリーたちのこの報告をよんだフレミングの驚きと喜びはどんなだっただろう。
彼はさっそくオックスフォードにでかけ、たがいに喜びの言葉を交しあった。
つぎは人間の病気の治療にとりかからなければならない。
そのためにもたくさんのペニシリンを作らなければならない。
何とかして薬品会社の工場で作ってもらえないだろうかというフローリーたちの思惑は、見事にはずれた。
戦争中の工場は、手のかかる割の合わない仕事をおいそれと引受けてはくれなかった。
フローリーたちは、ドイツ軍の空襲をうけながら、たとえドイツ軍が侵入してきても、ペニシリンを守りきろうと、上衣の裏や内ポケットに、ペニシリンを作る菌をしみこませて、万一の場合にそなえた。
6 アメリカで工業化 top
フローリーは、ペニシリン工業の研究を、アメリカに頼むことにした。
そして彼が紹介されたのは、中西部の平原の町ペオリアの研究所だった。
ここは平原にゆたかにみのるトウモロコシのあく汁「コーン・スティープ・リカー」の利用法を研究していた。
コーン・スティープ・リカーはその地方にあまるほどたまり、処置に困っていた。
そしてペニシリンを作る菌とよく似た菌をこの液体にはやして、ある薬品を作っていた。
コーン・スティープ・リカーは、ペニシリンを作るカビを育てるには絶好の栄養物だった。
こうして最初の問題が解決され、研究の前途は明るくなった。
つぎの進歩はビンの中で作っていたカビを、タンクの中でかきまぜながら、きれいな空気をふきこんで育てることに成功したことだった。
数千本のビンを取り扱う苦労はなくなり、一つの大きなタンクで安い費用で作ることができるようになると、もっとペニシリンをたくさん作り出すカビをさがすことが、残された問題になった。
全世界にちらばるアメリカ軍からも土が送られてきたが役にたたなった。
研究室の若い娘さんは毎日市場へいって、なんでもカビの生えたものを買ってくるようにいわれていた。
ある日「カビだらけのメアリー」とよばれていたこの娘さんがもってきた、くさいメロンを調べると、このメロンのカビは、すばらしいカビだということがわかった。
いま全世界に利用されているのは、このカビの子孫である。
ペニシリンの生産は着々とすすみ、フレミングは賞賛と感謝のあらしにまきこまれた。
フレミング、フローリー、チェインはノーベル賞を贈られ、世界中の人々がその功績をたたえた。
十一章 もう結核で死ぬことはない 《ストレプトマイシン》 ワックスマン
top
1 日本に来たワックスマン
一九五二年十二月十六日、師走の冷たい風がふきまくる東京・羽田空港は、夜ふけだというのに人波でうずまっていた。
爆音がとだえた滑走路の機体から、何人かの客かおりたつと、その中の地味な風采の老夫妻のまわりに、たちまち人が群がりより、カメラマンのフラッシュが集った。
白いペストとおそれられた結核の治療薬ストレプトマイシンの発見者、ワックスマン博士夫妻が日本をおとずれたのである。
ワッグスマンは、ノーベル医学賞をスウェーデンの首都ストックホルムで受賞しての帰り道であった。
それからの数日のあいだ、日本の各地に足をのばした博士夫妻は、多くの人々から感謝の言葉と、手厚いもてなしをうけた。
それは、不治の病とされて大変おそれられていた結核と戦う有力な武器が、初めてワックスマンによってあたえられたからである。
ワックスマンが自分の生まれた国ソビエトを訪問していたときのことである。
モスクワの「子供の病院」では、いま朝食の最中だった。
九つのかわいいニーノチカも、ベッドにすわったまま朝食を食べている。 |

ストレプトマイシンを発見した
ワックスマン(1888~ )
|
彼女のまわりをとりまく医者とワックスマンは、驚きと喜びのまじったようすで、彼女をみまもっていた。
ニーノチカは九週間まえにとっくに死んでいたはずだった。
恐ろしい結核菌が、小さなニーノチカの脳を犯したのだ。
やがてニーノチカはワックスマンのために英語で詩を暗誦してみせた。
ワックスマンの胸は感動にふるえた。
毎年この病気で四百人もの子供が入院するのだが、いままで生残った子供も退院できた子供もいなかった。
だがニーノチカは治ったのだ。ストレプトマイシンが、この奇跡をもってきたのだ。
ストレプトマイシンのおかげて、いまではこの病気にかかった子供のうち二人に一人は治っている。
ワックスマンは、微生物にささげた自分の生涯と、その研究から生まれたストレプトマイシンの威力に誇りを感じずにはいられなかった。
しかしここまでの道のりは長く、地味な苦労の多いものであった。
2 いじめられた少年時代 top
はてしないウクライナロシアのステップ、夏は麦の畑が見渡すかぎりのゆたかな大海原をつくり、冬は雪が大地をおおう、広い平野にあるもの寂しいノーバヤプリルカの町には、ユダヤ人がたくさん住んでいた。
ロシア革命の三十年ほど前の一八八八年に、ワックスマンはユダヤ人の中でもわりあい裕福な家の一人息子として生まれた。
ウクライナの黒土の香りとナイチングールの歌は、彼をかしこい意志の強い少年に育てあげた。
しかしユダヤ人だというだけで、満足に教育をうけることがでさなかったワッグスマンは、ツァー(皇帝)の治めるみじめたロシアにみきりをつけ、二十歳のとき従姉をたよってアメリカに移住した。
ニューヨークに近い、ラトガースという田舎のカレッジで三年間をすごしたワックスマンは、いよいよ卒業の年をむかえ、卒業論文の研究を始めた。
彼のえらんだ題目は、「土の中の細菌を探し出して、それを種類別にわけること」だった。
3 土の中を掃除する放射菌 top
彼は一年後、来る日も来る日も、畑のそこここに人が入れるほどの穴を掘りつづけ、深いところ浅いところ黒い上に赤い土と、ちがった土の標本を集めた。
この標本を水にとかして、うわずみを培養基(寒天に栄養分をとかして固めたもので、この上に細菌を繁殖させて調べる)の寒天の上にながし、二日か一週間もすると、寒天の上に小さな粒々がたくさんできた。
この粒は、土の中の細菌が培養基の中の栄養分を食べてふえ、目にみえるかたまりになったものだ。
ワックスマンはこうして毎日、粒々の数を数えているうちに、みなれない形と色をした粒が時々できてくることに気が付いた。
先生もこれがどんな種類の細菌かくわしくはしらないという。
たずねまわったすえ、やっとこれが放線菌という菌で、まだよく性質のわかっていないものだということがわかった。
私たちの足元の土は、不思議な働きをもっている。
人や動物が病気にかかると体の中でふえた病原菌は、排泄物や死骸と一緒に土の中にドンドン棄てられてゆく。
もしこの病原菌が、そのまま土の中で生きつづけたり、ドンドン繁殖したりすれば、土の中は恐ろしい病原菌の巣になってしまって、うっかり庭いじりなどしたら、たちまち病気に取付かれてしまうはずである。
ところが調べてみると、土の中には人や動物の病気のもとになる細菌は、ごくごく少しいるだけなのだ。
土の中には働き者の掃除屋さんがいて、まぎれこんでくる病原菌をドンドン退治してしまうのだ。
この働きものが放線菌だった。
ワックスマッがはじめて興味をひかれた頃、放線菌のすばらしい働きは何も知られていなかった。
しかし姿をみせたばかりの放線菌は、日一日とワックスマンの心をとらえていった。
こうして彼の一生の大半を、この放線菌に捧げることになった。
4 弟子デュボスに教えられる top
一九三八年、放線菌を友としたワックスマンの研究生活も、もう三十年以上にもなった。
土壌細菌学(土の中の細菌の働きを研究する学問)の部門では、彼は一流の学者として知られていた。
ある日のこと、彼はニューヨークのロックフェラー研究所の一室をたずねた。
ワックスマンを出迎えたのは、かっての弟子、ルネ・デュボス博士である。
デュボスは、ワックスマノのもとをはなれてから、肺炎をひきおこす肺炎菌を殺すことのできる細菌を、土の中からみつける研究をつづけていた。
ずっと以前、偉大な科学者パスツールは、こんな予言をしている。
「有害な細菌と戦うために、無害な細菌を利用するときが、きっとやってくる。」
デュボスの研究は、この言葉を受継いだものだった。
彼は、まず土が持っている病原菌を殺す力を試してみようと思った。
そこで壷に土をつめて、その上から、恐ろしい病原菌がウヨウヨしている水をそそぎこんだ。
つぎの日も、つぎの日も、毎日、毎日、病原菌の水をそそぎつづけた。こうして半年がすぎた。
もう土の中は、この悪い菌でいっぱいになっただろうか?
前から土の中にいた良い菌も、こんなにたくさんの悪い菌には、まけてしまったにちがいない。
デュボスは、壷のなかの土を永にとかして顕微鏡でのでいてみた。
みえたのは棒のようなかっこうの菌だけだった。
これは病原菌ではない。何ということだろう。あんなにたくさんいれた病原菌が一つもいはしない。
つぎにデュボスは、病原菌がたくさんはいって白くにごっている水の中に、壷の土をひとかけらいれてみた。
するとこの水は、たちまち透明にすみきってしまった。
水を白くにごらしていた細菌の大部隊は、たちまちのうちに土に殺されてしまったのだ。
顕微鏡でみえた棒の形の菌は、まるでスーパーマンのようにこの細菌も退治してしまったのだった。
これはブレビス菌といって、土の中にはいつでもたくさんいる菌だ。
デュボスは、この菌をたくさんふやして、培養液のなかからタイロスライシンという薬を取り出した。
タイロスライシンを肺炎にかかった鼠に注射すると、鼠のなかの肺炎菌はたちまち死んでしまった。
しかし残念なことに、この薬は肺炎菌を殺すばかりでなく、しばらくするうちに鼠まで死なせてしまった。
これではとても人間にはつかえない。
ワックスマンは、デュボスの研究をきいて、目がさめたような気持ちだった。
研究室を出ながら、彼は弟子としっかり握手をかわした。
「デュボス君、今日は実にすばらしい日だった。
きみの立派な研究をみせてもらい、きみと議論するたびに、私は新しい考え方を学びとる。
おかげて私のすすむべき方向がはっきりつかめたような気がするよ。」
興奮した声で別れをつげたワックスマンの頭には、彼がいままで手がけてきた土の中の細菌を使って、人間の病気のもとになる悪い細菌を退治する方法が、しっかりできあがっていた。
「デュボスの研究からは、人間に直接役立つものはできなかった。
しかし、病原菌を殺す力を持った細菌を探し出して、その細菌のはきだすもののなかから、病気を治す薬を作るという考え方は、実に新鮮な魅力を持っている。
パスツールの《細菌を使って細菌を殺す》という予言は、この研究法で実現することになるだろう。
私がいままで二十年のあいだ手がけてきた放線菌やカビの勉強と知識に、この方法をむすびつければ、かならずすばらしい薬が手にはいることだろう。」
ラトガース大学に帰ったワックスマンは、さっそく助手たちと新しい研究にとりかかった。
5 アクチノマイシン top
手なれた放線菌がまず材料にえらばれた。
この菌が作り出したものは真赤な物質で、アクチノマイシンと名づけられた。
この頃、オックスフォード大学のフローリーとチェインは、ペニシリンの絆粋な結晶を手に入れようと研究を始めたところだった。
アクチノマイシンは人間につかうには毒性が強すぎたが、大製薬会社のメルク社が興味を持った。
そしてその後、ワックスマンの研究にはメルク社という後樞がつくようにだった。
アクチノマイシンにつづいて、ワックスマンたちは、あらゆる種類の放線菌が作る抗生物質をくまなく取り出して、その中から役に立つ薬を探し出すごとにきめた。
彼は、フレミングのペニシリンのことも知っていた。
しかしカビは、ペニシリウム・ノタートウム以外には、あまり望めそうになかった。
放線菌なら……、それにペニシリンがきかない病原菌心まだまだ多く残っている。
ワックスマンは、コッホ以来、大細菌学者がとりくみ、どうしても攻撃できなかった結核菌を取上げた。
いろいろな種類の放線菌がいる土を別々にとり、それに結核菌をまく。
しばらくして結核菌を調べる。結核菌がぐんとへっていれば、そこにいる放線菌は有望である。
それを培養基に培養して、結核菌を殺すかどうか調べる。
一方の培養基のうち千個ぐらい残る。
その千種の放線菌を液体培養基で大量にふやし、抗生物質をだすかどうか調べる。
そのうち百個ばかり有望なのが残る。
百個のうち、有効な物質を取り出すことのできるものは十個ぐらいである。
その十種の物質を動物に注射して毒性を調べる。
大勢の人手、多額の費用をかけて、長い月日の苦労ののち、三年たった一九四四年になって、たった一種の物質がこの厳重なテストにパスした。
一万のうちから探し出した一つの特効薬、それは結核菌の繁殖をおさえ、しかも動物や人体への害はなかった。
ついに結核を地球から追放する最初の薬がみつかったのである。
その物質を作り出す放線菌が、ストレプトミセス・ダリセウスだ。
ワックスマンは、その特効薬にストレプトマイシンという名前をつけた。
6 ストレプトマイシン top
この放線菌がみつかったときのことをちょっとお話しておこう。
しばらくまえ、大学の近くの農事試験場に、お百姓さんが一羽の鶏をつれてきた。
「獣医さん、ちょっとこいつを診察してください。どうも風邪をひきこんだらしいんで。」
「ドレドレかしてごらん。みたところ、別に悪いところもなさそうだな。
しかし、伝染病にかかっているといけないから、いちおう調べてみよう。」
獣医さんは、鶏ののどの奥の粘液をとって、寒天の培養基の上にぬりつけた。
この培養を受持った女の助手はしばらく前までワックスマンの助手として働いていた人だった。
三、四日たつと彼女は、培養基の上に、伝染病の病原菌ではなく、ワックスマンの部屋でみなれた放線菌らしいものがはえていることに気がついた。
彼女は新しい研究のために放線菌を集めていたワックスマンにこの菌を届けた。
確かにこれは放線菌だった。
しかもこの菌は、大腸菌やブドウ状球菌のほかに、結核菌を殺すものを作り出すらしいのだ。
一万の培養物からえらばれただった一つの薬、ストレプトマイシンは、この薬が作ったものだった。
たとえ試験管の中であっても、結核菌がうちまかされたというニュースは、世界中にものすごい反響をまきおこした。
そしてこの希望は裏切られなかった。
こんにちでは、結核は、昔ほど恐ろしい病気ではなくなっている。
7 菌を菌で殺す top
フレミングとちがって、ワックスマンは化学工場と密接な関係をもって研究していた。
それでストレプトマイシンは、発見されるとすぐに工場生産にうつされた。
結核は治らないものとあきらめていた、世界中の療養所の医者たちは、そのききめのすばらしさに目をみはっておどろいた。
大勢の患者の目に、ワックスマンはまるで救いの主のようにうつった。
特に結核性脳膜炎にやられた子供たちのためには、いちだんとその力を現した。
これまでこの病気にかかって、かろうじて助かったという人が、人類史上でたったの五十人だといわれていたからだ。
療養所を視察したワックスマンの首に、そのようにして助かった子供たちが、花輪をまきつけた。
彼が大歓迎されたのは、当然のことである。
ストレプトマイシンの発見のもたらしたものは、これだけではなかった。
世界の科学者の目は、いっせいに土の中の宝庫、放線菌にそそがれた。
放線菌は全く多種多様である。どんな抗生物質が生まれるか、だれにも予想できなかった。
それにその研究方法は、ワックスマンが部厚い本に書いてくれたし、世界中を講演して説明してまわってくれたのである。
はたして、その後十年たらずのあいだに、いろいろな種類の細菌を殺すいろいろな新抗生物質が、各国の研究所から大学から、続々と発見されていった。
そして現在でもこの研究は、医学の最も先端をゆくものとして期待され、おしすすめられている。
いまでは、ビールスやハンセン氏病菌のような特殊な細菌をのでいて、ほとんどすべての病原菌が、この抗生物質の攻撃をうけている。
昔、伝染病の恐怖のまえに、祈ることと死ぬことしかできなかった人類は、いまや科学の武器を手に、伝染病にたいする総攻撃を展開する準備が(社会制度の不備による抜け穴さえなければ)完全にできあがったというわけである。
パスツール以来、約百年間のできごとであった。
十二章 人工的に「癌」をつくる 《癌細胞》 山極勝三郎
top
1 銀行に勤めるのは嫌だ!
勝三郎少年は、奇宿舎の押入の中で、息を殺して外の気配をうかがっていた。
校長先生はすこし腹をたてたようなあらい足音をひびかせて帰ってゆく。
「なんだか申し訳ないような気がするな。
でもしかたがない。銀行の帳簿をつける仕事なんてどうしてもやりたくないんだ。」
押入からはい出た勝三郎は、大きくのびをして窓にこしかけた。
はるかに遠い烏帽子岳から、まぢかにせまる太郎山まで、山々は白い雪におおわれ、千曲川を流れる水の色はにぶい冬の光をたたえている。
勝三郎少年は、文久三年、長野県上田市に生まれた。
時は幕末、世の中は明治の改革を目前にして騒然としていた。 |

兎の耳にタールをぬって癌の実験をする山極勝三郎と市川厚一
|
六歳のとき、徳川幕府はたおれ、上田藩につとめていた勝三郎の家はたちまち、貧しくなってしまった。
小学校をすばらしい成績で卒業した勝三郎の将来を心配した校長先生は、その頃できた銀行の帳簿係として彼を推薦した。
しかし肝心の勝三郎のほうは、学校で勉強した世界のようすが頭にいっぱいで、何とかして世界に名を知られるような人間になりたいと思いこんでいた。
狭い上田で帳簿づけをする気にはとてもなれないので、今日も押入に隠れて、枚長先生の勧めをやりすごしたのだった。
2 医学がやりたい top
十七歳になった年、勝三郎は東京の山極家の養子となり、医学を学ぶことになった。
時に一八七九年、ドイツではコッホがコツコツと自分の研究にとりかかっていたころだ。
この頃のドイツは、資本家が力をのばしはじめ、すばらしい勢いで国のたて直しをいそいでいた。
新しい産業がドンドンおこり、学問の発展の速度もめざましかった。
特に人間の体の仕組を研究する生理学や病理学の研究がすすんだ。
なかでもウィルヒョウと、その師であるミューラーは、当時の最新の学説であった細胞(シュライデンとシュワンが発見した)説を取入れて、謎の病気であった癌について、たくさんの研究をかさねた。
そして癌は細胞の働きが狂ってできる病気なのだと説明した。
癌の本体をつきとめ、狂った細胞がふえるのを喰いとめるための研究は、この時から始ったといっていい。
勝三郎の大学生活は経済的には恵まれたものではなかった。
しかしそのために成績がさがることはなく、在学中首席をとおした。
そして大学を卒業した勝三郎をまっていたのはあいかわらずの貧しさだった。 |

人工的にガンをつくった
山極勝三郎(1863~1903)
|
家族も友人も勝三郎に、すぐに病人を診て代金を手に入れる医者になってほしいとたのんだ。
だが勝三郎ののぞみは病理学(病気の体を調べて、人間の体の組織や細胞が病気のためにどんなにかわったかを調べ、病気の原因と対策を考える学問)を研究することだった。
だからコッホの作ったツベルクリンの研究のために、ドイツ留学を勧められたときも、ツベルクリンの研究が終ったあとで、ウィルヒョウのところで病理学の研究をすることが約束になっていた。
3 癌に取組む top
ウィルヒョウの研究室で、望みどおり病理学の勉強をし、ウィルヒョウの考え方を受継いだ勝三郎は、明治二十八年に東京大学の教授に任命され、病理学の教育と研究に専念することになった。
胃癌、乳癌、白血病(白血球がへったり、こわれた白血球がやたらにふえて、体の抵抗力がなくなって死ぬ病気)などは悪性腫瘍または癌とよばれている。
癌は細菌が外から入り込んで起こす伝染病とちがって、我々の体を作っている普通の細胞か、何かの原因で急に無秩序にふえだしてできるものである。
癌は数子年前の昔から人間の命をうばっていた。
四千年前のエジプトの若い王さまのミイラをレントゲンで調べたら、癌だったとわかった。
古代インドの詩人も、ギリシアの名医ヒポクラテスも、癌について書き残している。
4 癌の原因は何か top
しかし、細胞か発見され、それが癌とむすびつけて考えられるまで、癌の正体はつきとめられなかった。
癌をなおす方法は、外側の目でみられる癌をきりとることしがなかった。
たくさんの病気の組織を顕微鏡の下において、細胞のようすをくわしく調べる勝三郎の毎日がつづいた。
結核におかされた体をいたわりながら、規則正しい研究生活をつづけているうちに、勝三郎の興味はしだいに癌の研究にしぼられていった。
ウィルヒョウが癌の正体をつきとめたあと、体のなかの悪いもが癌のもとだとか、生まれつきだとかいう説は見捨ててられた。
そして癌がなにゆえおこるかについて、二つの説が対立していた。
一つは、コーンハイム説で、
「皮膚や骨を作る細胞の一つがほかの組織に迷いこんで、長いあいだ隠れているうちに癌のもとになる、というのだ。
もう一つは、ウィルヒョウの説で、
「何かの刺激がふつうの細胞に長いあいだ繰返してくわわるとそこに癌ができる。」というのだ。
両方の説にしたがう人々は、それぞれ実験を繰返し、自分たちの正しさを証明しようとしていた。
勝三郎はこれまでに人間の胃癌をたくさん取り扱っていた。
胃癌のようすを顕微鏡でみるとき、かならず気がつくのは、まわりに刺激でかわいたと思われる部分があることだった。
癌ができるのはここからだという確信は、だんだん強くなった。
十八世紀ごろのエギリスでは、煙突掃除は七、八歳の子供がやっていた。
ロンドンの医者パーシバル・ポッ卜は、煙突掃除人についてこんな論文を書いている。
「煙突掃除人だけがかかる死病に、ススイボという病がある。
小さい子供の時から煙突のなかにはいらされて、皮膚をすりむいたり、やけどをしたりしながらススを落とすうちに、このやまいにおかされて死ぬのである。
これは長いあいだススのなかのタールに刺激されるからだと思われる。」
ポットのこの研究はだれにも注意されず、長いあいだ全く忘れられていた。
しかし癌の研究がだんだん盛んになると、よく取上げられるようになり、刺激説を証明する実験に、タールが使われるようになった。
ところが、それまでタールを動物にぬって、その刺激で癌をつくろうとした学者はだれも成功しなかった。
イボのようなものができたりはしたが、こんなものはタールをぬるのをやめるとすぐひっこんでなかってしまって、癌のように、ドンドンひろがる悪性の腫物にはならなかった。
しかし勝三郎には確信があった。
「癌細胞がはじめから体の中にあるはずがない。
あとからどこかから入って、それが刺激して癌細胞ができるのだ。
それではなぜいままで実験した学者たちはみな失敗したのだろうか?
いや失敗ときめつけるのははやすぎる。
人間にできる癌は、子供の時からうけた刺激がつもりつもって、大人になって癌細胞ができると思われる。
たかが半年ぐらいの刺激で簡単に癌細胞ができると思うほうが間違いなのだ。」
「よし、かならず私の手で癌を作ってみせるぞ。」
さて、勝三郎から問題をだされた学生たちや助手は半信半疑だった。
いままで外国で実験してできなかった癌が、日本人だけでつくれるのだろうか?
それに人間の死体ばかりいじっていた我々が、生きた動物を扱うなんて……
嫌々ながら鼠の耳をピンセットでひっかいたり、こすったり、焼きごてをあてたりして刺激の実験をしてい人に学生たちも、鼠にかまれたりして、みんなにげごしになり、だれも真剣にやらうとしなくなってしまった。
5 市川厚一(あついち)との協力 top
そこで勝三郎は若いまじめな市川厚一を助手にむかえ、本腰を入れて研究にとりかかった。
実験動物には兎をつかうことにした。
兎の耳は長く大きくて、変化のようすを観察するのに便利だし、兎の耳に天然に癌ができるということにきいたことがないから、刺激をあたえて人工的に癌をつくるには都合がよかった。
刺激剤には、キシロール、クレオソート、タールなどがえらばれた。
ピンセットでこすったり、ひっかいたりする実験もつづけた。
いくつかの刺激剤のうち、一番やくにたちそうなのはやはりタールだった。
一回ぬっただけでも皮膚がただれてきた。刺激剤はこうしてタール一つにきめられた。
兎六十匹を買い入れ、毎日兎の耳にタールをぬるという根気のいる実験が始った。
市川助手はとうとう教室にとまりこみ、自炊をしながら兎の世話をつづけた。
二人ともタールにかぶれて顔や手がただれてきた。
しかし兎は別の病気にかかり、バタバタと死んでいった。
実験を初めてから半年たった九月には、兎はたった二匹になってしまっていた。
しかしうれしいことに、この二匹の耳に粟粒から米粒ぐらいのイボができてきた。
6 先生、やっと癌が! top
「先生、やっとイボができてきました。」
「うん、のぞみがでできたな。この二匹はよっぽど大事に育てなければならんで。」
二人は勇気百倍した。
「ここまでは外国の学者がやったことと同じだ。このイボが本物の癌にかわる日がきたときこそ、我々の勝利の日だ。」
勝三郎の自信はゆるがなかった。
しかし、あくる年の三月の学会で発表されたこの研究には、白い目がむけられた。
「このイボは癌とは関係ないものだし、こんな研究はなんにも役にたっはずがない。」という声が多かった。
そして体の弱い勝三郎は、また病気がぶりかえし、床についてしまった。
この年(大正四年)の夏、市川厚一はいつものように兎の耳を調べているうちに、はっと目をみはった。
顕微鏡の下にみえるこの細胞、これは明らかに癌細胞だ。
イボが癌にかわったものだ。彼はこの細胞の標本をていねいにしあげ、大切にしまいこんだ。
「さてこの見本を先生におみせしようか?
すばらしいニュースはお聞かせしたいが、病後の先生乍興奮させてはからだに悪いし……。」
市川助手はまよった。
二、三日して、実験室をみまわりにきた勝三郎は、いつものように兎のようすをたずねた。
癌になり始めたものがあると答えながら、市川助手は標本を勝三郎に手渡した。
きづかわしげな市川助手の目のまえで、勝三郎は顕微鏡をじっとのぞきこんだ。
そして、「市川、できたな」とさけぶと、
「成功! 成功!」と部屋のなかを歩きまわりはじめた。
うれしさで、どうしていいかわからないほどだったのだ。
二人は手をとりあって喜んだ。俳句のすきな勝三郎はこの感激をすぐに句に作りかえた。
癌できつ 意気昂然と 二歩三歩
うさぎ耳 見せつ鼻高々と 市川氏
九月に癌ができたことを報告しても、学者たちはまだ疑っていた。
あれは本当の癌ではないだろうという人がいた。
それほど癌を人工的に作るのはむずかしい、と思われていたのだ。
しかし、やがて確かに癌であるという証拠がいくつもあらわれ、年とともにこの研究のすばらしさが認められるようになった。
この一、二年前、デンマークのフィビガーが、鼠の胃に人工的に癌を作ったと報告していた。
このほうがすこし華やかだったためにノーベル賞はフィビガーにあたえられたが、その後、フィビガーたちの研究は間違っていたらしいとわかり、いまでは山極、市川の実験が世界で最初の人工癌だと認められている。
こうして日本の癌研究は、世界にさきがけて、すばらしい勝利をおさめた。
山極たちにつづいて、何人もの日本の学者がすぐれた研究を発表している。
しかし癌の研究は非常にむずかしくて、癌の原因についてもまだよくわかってしないが、近い将来にきっと癌の正体がつきとめられ、癌の予防ができるようになるであろう。
top
**************************************** |