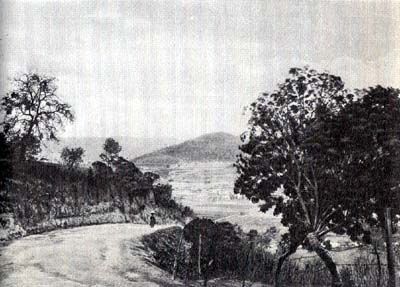|
****************************************
Home 概要 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
Ⅱ 二人の探検家
4 謎の都ヘ
ジョン・ロイド・スティーヴンズが、友だちのフレデリック・キャザウッドと二人で、ニューヨーク港を船出しだのは、一八三九年の十月三日水曜日の午前七時であった。
イギリス帆船マリー・アン号は、港を出ると進路を南にとって、フロリダ半島ぞいに、大西洋をしずかにすべっていった。
行き先は中央アメリカのイギリス植民地の首都で、エジプトのアレキサンドリア港に似ているといわれる、美しい港の町ベリーズ。
スティーヴンズは上甲板で日影をみつけると、そこに椅子を用意させて幾冊もの本をはこび、そのひとつをひろげて読みふけっていた。
彼は、三十四歳であった。
五年前までの彼は、ニューヨーク市に法律事務所をもった、ちょっとした若手の政治家だった。
ところが、五年前の一八三四年の秋、彼は、少年時代からあこがれでいたエジプトへの旅にでた。
二年間に、エジプトの古代遺跡や、アラビヤの砂漠や、イスラエルのエルサレム地方も、探検旅行をして歩いた。
そして一旦ニューヨークへかえって、二年間の探検記を本に書いて出版すると、すぐにその年の暮れにギリシア地方へ旅行した。
有名なスパルタや、コリント地峡や、アテネなどをみるうちに、新たな歴史の興味にかりたてられて、トルコへ向かい、そこからポーランド、ロシアなどに旅をして、一八三八年再び、ニューヨークにかえってきた。
このときの旅行記は、古代の遺跡や古代史をさぐっただけではなく、その折々の各国のなまなましい政治や外交、市民生活の実情をくわえたもので、スティーヴンズの政治家としての目が、するどく光ったものである。
ときのアメリカ合衆国大統領マルチン・ヴァン・ビューレンは、二つの探検旅行記を読んで、さっそくスティーヴンズを、ホワイトハウス(大統領官邸)にまねいた。
「あの有名なアラモの戦いの後、テキサス州がメキシコから独立して(一八三五~三六年)わが合衆国に合併したことは、あなたもご存知だろう。
いまのところ、合衆国とメキシコとの外交関係はよろしいが、困るのは友好条約を結んでいる中央アメリカ連合である。 最近あそこはまるで、“ひょうたんなます”のようにのらりくらりである。
ひとつ、あなたの古代史研究をかねて、中央アメリカの内情を、どういう情勢であるか、視察してくれないか。」 |
という話である。
スティーヴンズは、すぐに承知した。
というのは、地中海の文化遺跡や、トルコやロシアを旅行するうちに、自分の住むアメリカ大陸には、古い文化遺跡は本当になかったのだろうかと、くりかえし疑問に思っていた矢先であったからだ。
大統領は、さっそくスティーヴンズを合衆国外交官特別使節に任命し、中央アメリカの指導者に自由に会えるように、いろいろな手続きをとってくれた。そして、
「同行者は、君のほうの探検に、大切な者がいいだろう。
なるべく君の前の旅行のように、自由にふるまってくれたまえ。」
そういった大統領の親切な言葉から、彼は古代史研究の友人であり、すぐれた画家でもあるキャザウッドをえらんで、船出したわけであった。
「猛烈に暑いねえ。」
キャザウッドは、やせた首すじに、したたりおちる汗をぬぐいながら、甲板をよこぎってきた。
スティーヴンズは本から目をあげた。
「今朝は、華氏八十度(27度C)だったが、今はおそらく百度をこえているだろうね。」
「中央アメリカは、中東地方より暑いかねえ、ジョン。」
「どうかな?その答えにおあつらえむきとはいかないけれど、メキシコ湾沿岸に住むインディオの国をうたった詩が、ここにある。読んでみようかね。」
そういうと、ページをくりなおしたスティーヴンズは、低く節をつけて読みはじめた。
オルメックのゴムの国
ここに住む人々は ゆたかなり
彼らのふるさと 彼らの国は
食物の国 花ばなのさく国
富める国 ゆたかなる国
そこはココアが
黄色くゆたかな「トウモロコシ」が
ゴムの木とともに おいそだつ
そこは心の花が
様々な草花とともに おいそだつ
そこには緑の宝石が
美しい月の光の玉が
様々な玉とともに あらわれでる
そこにはまた
金と銀があらわれ光る
美しくやさしい如人だらけ
刺繍(ししゅう)の名手
おりもの仕事にもすばらしく
そのうえ 礼儀をわきまえる人々
男たちはいさましく つね日ごろ
弓と光る斧(おの)をもってはたらく
それらの人々はゆたかなり
しかしぜいたくではなかりき…… |
スティーヴンズは、読み終わって、にこりとした。
キャザウッドは、夢みるように、じいっと、青い海原をみつめている。
「これはね、十年前に発見された本だ。
スペイン軍の征服後、すぐにやってきた宣教師のサハンという人が、インディオの古い歴史を調べて書いたものなんだ。」
「どのあたりになるだろう、そのゴムの国は?」
「メキシコ湾に近いタバスコ地方だそうだ。いずれ馬かロバの背に乗ってたずねるつもりだよ。
きっと、古代のほろんだ民族の、すばらしい遺跡があるに違いない。
こちらの本は、ドイツの軍人ワルデック伯爵が、ごく最近にチャバス地方の奥地を探検して、マヤ族の都らしいパレンケというところを、調査したものだ。
伯爵は六十六歳で密林の中へわけ入ったらしいねえ。」
「ほう。そんな老人を夢中にさせるような、大変な遺跡が密林の中にあるんだねえ。」
|

インディオの女性

ユカタン半島の民族衣装を着たインディオ(左)
|
開かれたページには絵そのものは下手(へた)だが、原始林の中に壊れた中世風の城のような図が描かれている。
説明文には、このように樹木にくわれて森の中に沈んでいる城や宮殿が、この地方にいくつもある、と書いてある。
キャザウッドは食い入るるようにみいって、大きなため息をついている。
「これらの文化遺跡を残した民族は、『旧約聖書』で行方しれずになったと記されているイスラエルの十支族の子孫だと、考えているようだよ。
また、それに違いないと主張しているのが、この新しい本を書いたキングスボロウという人なんだが、ヨーロッパの考古学者からは一笑にふしているのだ。彼らは頭から新大陸に古代文明はない、とね。」
「いや、僕はこの本を信じるね。信じているからこそ、エジプトやギリシアのような、腕がふるえる遺跡に、うまくいきあたるように、と出発以来、毎晩、金星に祈っているのだ。」
二人は、それから地図をとりだした。
ベリしス市に×をつけ、イサベル湖とグアテマラ市に大きな○じるしをつけた。
○じるしのところは注意、つまり、遺跡探検の必要なところである。
「グアテマラで太平洋岸にでて、沿岸ぞいに一気にコスタリカまで行こう。
コスタリカからは内陸を通って、ニカラグアやホンジュラスをみて歩き、もう一度、グアテマラのこの港へつく計画だ。
それからまた遺跡の多いチャバス地方を調査しつつ、メキシコ湾へでる。」
「メキシコ湾から、まっすぐ帰る?」
「いや、ユカタン半島のメリダ市による。あのあたりは、マヤの古い遺跡が埋もれているというからね。」
二人は、そんな計画をねっていった。
帆は風を一杯はらんで、カリブの海をすべるように進んでいった。
5 インディオの国で top
十月二十九日、マリー・アン号は、無数の美しい珊瑚礁に囲まれたベリーズの港についた。
おりから、この地方特有のスコールが襲って、一瞬、港も船もその向こうの町もみえなくなった。
「大歓迎だ。こりゃ幸先がいいですよ。」
船長は二人をふりかえって笑うと、町の方を指さしてみせた。
と、町の上には大きな虹が雨足の去った後に半円を描いている。
「なるほど、いいことがありそうだね。」
キャザウッドはうなずきながらいった。
ランチがおろされ、乗客たちは、上陸をはじめる。棧橋には、歓迎の人が鈴なりになっている。
そのうしろには、材木の山がいくつもみえるのは、この地方特産のロッグウッドという染料をとる材木と、家具用のマホガユー材の山らしい。
スティーヴンズは、出迎えの領事と一緒に、まっすぐ政府官庁にいき、ベリーズ市総督のマクドナルド大佐や、イギリス植民地の高官たちに会って、大統領からのメッセージを渡した。
夕方には総督官邸で華やかな、すばらしい歓迎パーティが開かれた。船長がいったように旅の幸先はいいらしい。
翌日、総督から、探検旅行に必要な野外キャンプ用のハンモックや雨外套などが、二人にプレゼントされた。
それに召使い兼通訳をやる若者も紹介された。
若者は、ハイチ島のサン・ドミンゴ生れのフランス系スペイン人で、すこしは英語も理解するし、インディオの言葉もわかるという重宝な青年であった。
名前は、ホセ・オーガスチン。ただひとつの難点は、グアテマラ市までの約束であるが、ホセはさっそく船に荷物をつみこんだり、こまねずみのようにはたらきはしめた。
グアテマラの入口、リビングストン行きの小汽船は、スティーヴンズとキャザウッド、ホセ、それにローマ法皇庁からやってきていた若い司祭さんの四人を乗せて、ベリトスの棧橋を離れ、星条旗をなびかせた舳先(へさき)を外海へ向けた。
そのとき、港の十三門の砲台がそれぞれ、一発ずつの礼砲をひびかせはじめた。
棧橋には、挙手の礼をする背の高い総督をはじめ高官たち、それに黒人、インディオたちまでが黒山のように見送っている。 と港の船たちまでがいっせいに、霧笛を鳴らす。
「大変な名誉礼をうけるねえ、ジョン。」
「うん、我々の壮途を祝すだけでなく、祖国への礼儀を示されているのだ。大佐は、国旗に対して挙手されているのだ。」
スティーヴンズは、甲板に直立不動で答礼しながら、感激の声でいった。
港を出る時、マリー・アン号とすれちがった。
船長は、長い古いマスケット銃を空に向けて、一発ぶっぱなしてから叫んだ。
「幸運を祈りますよォ! お二人さーン!」
希望を一杯のせた小汽船は、緑の樹林のせまったイギリス領ホンジュラスの海岸線に沿って、一路南下をつづけた。
海は太陽にきらめいて、まさに夢の国への旅のようであった。
パンタ・コーダの港につくと、暑い白い浜辺を、裸足のインディオたちが、むらがるように駆け寄ってきて膝まづく。
司祭さんがやってくることを知っていたらしい。
司祭は、さっそく浜辺で祝福と洗礼をはじめた。
ホセは臨時のお供になって、燭台をささげ、スティーヴンズたちは、司祭の壮重なラテン語の教えをフランス語に通訳し、それをホセがまたインディオ語や、スペイン語になおすのだった。
あるインディオの母親は、小さな赤ん坊の洗礼名を、この立派な人の名前にしてほしい、とスティーヴンズを指さした。
それでその子は「ジョワン」になった。
コーダの町のゴシック式教会は、地震のためにくずれる一歩手前のよう傾いていたが、たくさん集った人々は、久しぶりに訪れた司祭さんのミサに、ほとんどが涙を流して喜んでいた。
「町の商人も黒人もインディオも、神の教えに感動していたね。
特にインディオはひかえ目で礼儀正しいようだね、ジョン。
それにあなたたちは何というインディオか、ときいた時は、誇り高かったねえ。」
「全くだ。胸を指さして、マヤム! ていったときの誇(ほこ)らしさ!」
スティーヴンズは、名づけ子の親たちからの贈物の、バナナやマンゴーやトウモロコシの篭をみながら、何度もうなずいた。
彼はその昔、コロンブスの一行の船が、はじめてこの近くの海上へきたとき、一群のカヌーがこぎ集まってきて、乗り手の小ぎれいでさっぱりとした白服の原住民たちが、礼儀正しい挨拶をして、友好のしるしに篭一杯の果物を差し出した話を思いだしていた。 |

浜辺で司祭を出迎えるインディオたち
|
そのとき「君たちはどこの国の人か」とコロンブスがきくと、胸をたたいて誇り高く「マヤム」といった、という。
それが文明社会が始めて接触したマヤ族の人たちで、以来この地方の住民を「マヤ」とよぶようになった、という十五世紀の話である。それと同じであった。
違うのは、いささか貧しく、白人に支配されているからか、表情が暗い。
そのため、白人より熱心なキリスト教徒で、未来の天国での幸せを願っている、という点てある。
つぎに訪れたのは、グアテマラの北の玄関口に接するリビングストンであった。
上陸するとコーダの町と同じく、カトリックの信者たちがむらがり集った。
司祭さんはミサに洗礼に大忙しだった。
スティーヴンズたちは、これから始まる内陸への旅の準備に大わらわ、食料を買い集めたり、町の役人の世話で、ロバとインディオのロバ追い人夫、道案内人を雇い入れたりした。
町では、グアテマラ内乱の話でもちきりだった。
「いま、グアテマラ市へはいるのは困難です。」
イギリス人とフランス人の商人たちは、口をそろえて、危険な旅だ、と忠告して、
「なにしろ、あそこのインディオどもは、外国人を目のかたきにしているそうです。
それで我々もうかつに、商売にでかけられないのです。
イサバルヘ行けば、もっとくわしいことがわかりますが、用心、用心ですよ。」
「御忠告ありがとう。私は合衆国大使として、あの国へ行かねばならんのです。
外交官にまでは、乱暴しないでしょう。
それにマヤインディオは、元々おとなしく、礼儀正しい民族です。用心はしますが……。」
スティーヴンズは、きっぱりそういった。
「雲行きがあやしいね、だが、ぼくらには、幸運がついてまわるさ。ねえ、ジョン。」
キャザウッドは、ロバの背の荷物を点検しながら、大夫たちの不安を吹きとばすように笑ってみせた。
三頭の荷駄用のロバの背には、三人の食糧とその道具、野営用のハンモックや、外交官服その他の衣類を入れたトランク二つ、それから大きなコンパス、六分儀、クロノメーターなどの観測用機材がつんである。
もちろん、キャザウッドのスケッチなどの画材道具もそのなかにあって、すべて防水シートがかけてある。
これから先は、ほとんど山国である。山の天気はいつ変わるかも知れない。
だから機材のなかで一番大切なのは、山岳用の高度も測れる気圧計である。
これだけはすでに、頑丈なひもで、スティーヴンズの肩から斜めにさげられていた。
それから左右の腰には大型ナイフと拳銃で武装をしていた。キャザウッドもホセも同じである。
案内人兼人夫頭と三人のロバ追いのインディオは、マチェーテという大幅の刀をベルトにはさみ、一丁ずつ銃をもたせたが、スティーヴンズは厳重に注意をした。
「どんなことが起きようともだ。私の命令以外、絶対に発砲してはならんぞ。いいか、絶対引金をひいちゃならんぞ。」
こうして一行が出発の準備を終わったころ、この町に一応とどまる司祭(しさい)さんが、イサバルの神父宛に紹介の手紙を書いてくれ、
「あなた方の無事と幸運を祈りまして」とミサをあげてくれた。
ごきげんになった一行七人は、まず国境の税関へ向かった。
グアテマラ側の国境税関は、まだ子供の土民兵が七、八人、背丈より長いような旧式銃を手に見張りをしていた。
隊長はイギリス側か手をふって送っているのをみたためか、実に簡単に通行証をくれた。
「ミサのおかげで、ますます幸運のようだ。」
というキャザウッドに、四人のインディオたちは安心したように白い歯をみせた。
行手はシュロ、ココナツ、マホガユーの森だった。そこをぬけると、川沿いの登りの山道であった。
ときおり、鳥たちが音をたてて飛び立ち、ほえザルが梢の木の葉をゆすって移動する。
気味の悪い声で、最初は、スティーヴンズも思わず首をすくめた。
山道はくだったと思うと、また登りである。
人夫たちは、古代の人たちと同じに額(ひたい)からかつぐ荷を実にかるがると背負い、とっとっと登っていく。
ロバに乗っている方が、なれないせいもあって、大変である。
まずホセが真先にふり落され、ついでキャザウッドがころがり落ちた。
「ロバでの山登りが、こんな苦労だとわかっていれば、今度の旅は断わるのだったぞ、全く、この畜生め!」
「フレディ、ロバにあたったってしかたないよ。要はバランスよく乗りこなすんだよ。」
といい終わらぬうちに、今度はスティーヴンズが、すべり落ちる。
だが半日もすると、三人ともどうにかバランスをとることができるようになった。
その昼過ぎ、小暗い、ゴツゴツした道を、苦労して登りきると、きゅうにあたりに光がたちのぼるように明るくなった。
「湖ですだ、イサバルの。」
先頭の人夫頭は指さしながらいった。
そこからみえる湖面は、マヤの国のヒスイのように青く、キラキラと光っている。
三方は、波うつような山々がせまり、じいっとみていると、壮大な湖水からは、何か、遠い時代のもの音がきこえてきそうである。
町はすぐ眼下に、よりそうようにあった。 |

ロバから振り落とされるスティーヴンズ
|
6 危難あいつぐ top
|

グアテマラの町
|
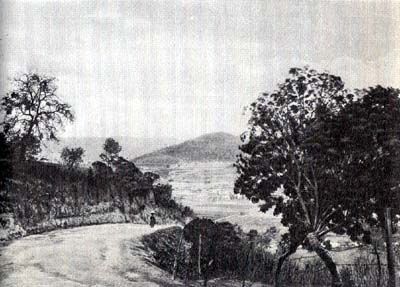
美しい山道
|
「ここからは、真のインディオの国です。
あの向こうの高原の峡谷のあたりから、古くからのインディオの村や、壊れた廃墟がたくさんあります。」
イサバルの年老いた神父は、樹木のおいしげる高原を指さして教えてくれる。
「しかし、一番、興味ぶかいのは、コパンです。
そこには、いつの時代なのかわからないほど古い、マヤの都のひとつらしい廃墟があるそうです。
今はすっかり原始林の中に埋もれているそうですが……。」
「いつの時代か、わからないほどの古い都ですって?」
スティーヴンズは、興奮してききかえしたほどだった。
「ですが、そこへの旅はお気をつけなさい。
いま、グアテマラでは、中央政府のモラサン将軍に反対するインディオたちが、一杯いますからね。
インディオたちと土地の者は、カレーラという将軍にひきいられて、グアテマラの独立を勝ち取ろうと、必死ですから。」
中央アメリカの統領モラサン将軍と、グアテマラ独立軍のカレーラ将軍との戦いのことは、スティーヴンズもよく聞き知っていた。
彼は、二人の将軍に会って、アメリカ大統領のメッセージを渡さなければならない任務もある。
「神父さん、両軍の衝突は、そのコパンの近くでもありそうですか……。」
「いや、今のところ、首都グアテマラ市を中心にしたところでしょう。
ですから、首都へまっすぐ入られるのも考えものです。
と申しますのは、カレーラ将軍側のものは、外国人はみな政府軍を応援しているという噂を信じて、外国の方に敵意を抱いている者も多いのです。
それに戦争の最中だと、もっと危険です。どの道を行かれますにも、どうかよくお気をつけてください。
もっとも、あなた方のような立派なお方には、乱暴はしないと思いますが……。」
老神父は、にこっと片目をつぶってみせた。
「ご忠告、よくわかりました。充分に注意します。首都へは、状勢をみてはいるようにいたします。」
スティーヴンズはそうこたえると、さっそくコパンヘの山旅の凖備にとりかかった。
コパンの位置は、神父が教えてくれたところによると、グアテマラとホンジュラスの国境にあるらしい。
イサバルから直線に計ると、およそ、六十キロの道のりである。
その地方は、山また山の高原がつづき、ふかい淵のような谷が、東から西へはしっている。
しかも、原始林が峡谷や山すそをびっしりとおおっているのだ。
「その登りくだりを計算にいれると、コパンヘの道のりは、およそ三倍とふんでいなきゃだめだね。」
地図をみながら、スティーヴンズは、そうつぶやいた。
キャザウッドのほうは、神父や町の人の意見をききながら山道を書き、大峡谷地帯の略図と方角を丹念につくっていた。
ホセは食糧の用意だった。
そうして、いっさいの準備がととのうと、彼らはイサバルから出発した。
湖辺からふいに数万羽の白鳥が、とび立った。なんだか、幸先はいいようだった。
先頭は人夫頭、つづいてスティーヴンズ、そのうしろが荷駄用の三頭のロバ追い二人で、そのうしろにホセ、しんがりが暑がりのキャザウッドともう一人ロバ追いで一列になって進むのだ。
山道は、ぬかっていた。雨期だったら、おそらく、山越えはできない道だ。
一ヵ月ほど前まで、このあたりは豪雨のたたきつける雨期が半年もつづいていたということだった。
「わりあい、高原はすずしいねえ。」
キャザウッドは、ニコニコしていた。ロバの乗り方もだいぶ馴れてきたようだった。
「ただ、この道が石でできていたら、ロバがとっとっと行くので、すばらしいんだけどね。」
「キャザの旦那さま、おっこちないでくださいよ。右手の谷は深いそうですよ。」
「ホセ。君こそ、ほら、ぬかるみに落ちるぞ。」
二人は大声で前後に、軽口をとばしている。
ぬかった道は、くらい原始林の間の道をぬけでると、かたい山道にかわった。
ひとつの山をこえると、なだらかな高原が眼下に広がり、それは、すばらしい花の国のような眺めである。
草花の、赤や黄、白の群落のはてに、樹海が波うつように広がっている。
「本と森と、花の谷の国。」
イサバルの老インディオがいったとおりだ。
「ゴムの国より、美しいぞ。」
キャザウッドが、望遠鏡をのでいていう。
高度気圧計で山の高さをはかっていたスティーヴンズも、そばにいたロバ追いの若者タマラに、
「大切にもっていってくれ。」と気圧計をもたせると、キャザウッドと並んで双眼鏡をのぞきこんだ。
「全くだ! 美しい国土だなあ……。」
二人はのぞきこんだまま、ため息をつく。
それからホセの用意で、気分のいい、食事がはじまった。
乾パンと煮豆とコーヒーだけだが、あまい空気と美しい光景で、ゆたかな宴会のようであった。
が、一人ロバ追いのタマラだけ、食事もせずに大事に気圧計を両手でかかえている。スティーヴンズは笑って、
「私がしていたように、首から斜めにかけて、食事をしなさい。その大事な器械は、これから君にもってもらうからね」
タマラは、ぱっと目をかがやかせた。そしていかにも満足そうに、うなずいた。
一時間後、一行は再び出発した。美しかった高原をぬけると、また山道である。
タマラは、スティーヴンズの横を、全く得意満面で、ロバをひいていく。
左の腰にマチューテを斜めにさし、右腰にかねの水筒をさげ、そのちょっと上に、ぴかぴかの気圧計が歩くごとにゆれる。
水筒とぶつかったら危ないな、とスティーヴンズは思ったが、若者のうれしそうな得意な歩きぶりに、頭をふった。
それがいけなかった。
仲間のはやし言葉に、大見栄をきるように振り返ったタマラは、とたんに、ずるっと足をすべらせて勢いよくはいつくばった。
あっ、という間もなく、金属の壊れる音がしたようだった。
事実、気圧計と水筒が当たりあってガラスが壊れたのだ。そして、水銀が流れだしてしまった。
「ああ、なんていうことだ。タマラー 一番大事な器械を!」
ロバから飛びおりたスティーヴンズは、青くなった。キャザウッドは、どなりつけた。
そして地団駄をふんだ。
これから先を思うと、気圧を測れないし、山の高さも測れなくなったのだから、二人があわてるのもむりはなかった。
人夫たちはみんなオロオロして肩をよせあっていた。タマラはふるえて、泣きだしてしまった。
スティーヴンズはやがて、
「いや、私も君にあずけたのが悪かった。いくらくやんでも元通りにはならん。
さあ、気分をなおして、出発だ。タマラ、もう転ぶんじやないぞ。ホセ、力を貸してやれ。」
「そういえばそうだ、さあ、元気に行こう。」
キャザウッドも笑顔をもどして、明るく人夫たちに声をかけた。
タマラは、ホセに肩をたたかれるたびに、しゃくりあげながら、みんなについてくる。
やがて、木々の間に、巨大な石の教会らしいのがみえてきた。
それは、天井がおち、半分崩れかけたカトリックの教会であった。
あたりは廃村になったインディオの村だった。
一行はここで、野営キャンプを張った。
朝、日の出前に起きたスティーヴンズは、ハンモックから出るとキャンプをみまわってみた。
と、タマラの姿がない。彼は叱り過ぎたことを後悔した。叱られて、夜の間に、いたたまれずに逃げだしたらしい。
朝食のコーヒーができても、みんなムッツリとだまりこんでいた。
「フレディ、ちょっとひどかったようだね。」
「いやジョン、君はすぐ、やさしくしたさ。」
「でもねえ、はじめカッとしたからねえ。」
「ぼくだってさ。あの器械は補充がないし……。」
と、二人がしめっぽく話していたとき、ふいにロバ追いたちが、ざわめいた。
タマラが息をきらし、篭をかかえで走ってきたのだ。
彼は夜中、走って、鶏の卵をどこかのインディオ村から買ってきたのだった。
「旦那さま、卵あったらといった。悪いことしたおわびに卵を買ってきた。」
「さすが、義理がたい、インディオだ。マヤの子孫は、礼儀正しい。
えらいぞ、タマラ。」
キャザウッドは、タマラを抱きしめて、相好をくずした。
スティーヴンズも、目をうるませて、うなずきをくりかえした。
ほがらかになった一行は、足どりもかるく山道を登りはしめた。
雨降って地がかたまる、の格言のような光景だった。
フつん、インディオの国はすばらしい。」
キャザウッドは犬声でいった。ホセが、それをみんなに通訳したときだった。
ふいにぐらぐらっと、地震がおこった。
原始林からは、鳥や猿のさけびと、木々のぶつかりあう音がわく。
みんなは、平気でロバをおさえているが、キャザウッドのあわてようったらなかった。
地震はまた、二度、三度と地面をゆさぶった。今度は、前より小さかった。
「いやな予感がするよ。さっきはほめすぎたかな? それとも、神々の返事かな。」
キャザウッドは、しがみついていた木からはなれると、ほこりをはらいながら、顔をしかめてみせた。
スティーヴンズは、
「火山の多いグアテマラには、地震はつきものさ。
海抜二千メートルの高地でも、波のようにゆれる、と書物に書いてあったよ。」
と、いったとき、一瞬、あたりが暗くなった。
そして、叩きつけるような雨が襲ってきた。
熱帯の豪雨(スコール)は、半時間ほどで去ったが、山道はまるで川の流れのようになっていた。
太陽が出ると、それがもうもうたる蒸気に変わって、たえがたいほど、むし暑い。
そのむし暑さのなかを、一行は絶壁のそそりたつ大峡谷地帯を苦労してくだって、広い河に出た。
このモタグワ河は、川幅もひろく流れも急で、ロバをカヌーに乗せてわたすのは、なかなかに困難であった。
全部がわたりきるのに、数時間もかかり、みんな泥まみれであった。
日が暮れかかった土堤のむこうには、広場を中心にしたスペイン風の町グアランの、これまた地震で崩れかけた大教会がみえる。 |

昨日の失敗で、姿を消していたタマラが
卵を持って戻ってきた。

地震におそわれて木にしがみつくスティーヴンズ
|
一行は、水浴で泥をおとし、服装もこざっぱりとしてから、町の広場へはいっていった。
広場の中心の噴水のまわりには、白い服のインディオたちが、一人の黒い僧服の司祭をかこんで、口々にわめきたてていたが、スティーヴンズたちをみると、急にしずかになり、とがめるような眼つきになった。
「イサバルからの旅のお方だ。心配ない。」
司祭がそういうまで、彼らインディオたちは、敵意をあからさまにみせていた。
イサバルの老神父の手紙がなかったら、どうなったかわからないほどの、空気だった。
「みんなは、サルバドルからモラサン将軍がのりこんでくるというので、気が立っているのです。
北からも政府軍がくるというし……。」
司祭は、町長や町の主だった人たちを紹介したあと、そう説明しながら、一行の宿の世話までしてくれた。
「できるだけ早く、コパンヘ急がれた方がよろしいですよ。戦争にまきこまれないために。」
スティーヴンズたちは、この親切な忠告をいれて、夜が明けるとすぐに町を出た。
top
**************************************** |