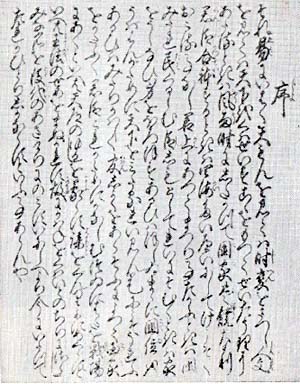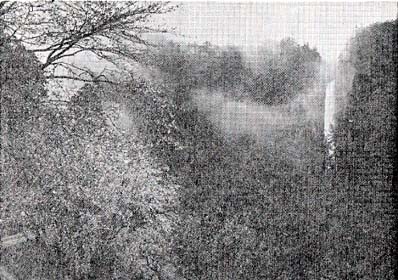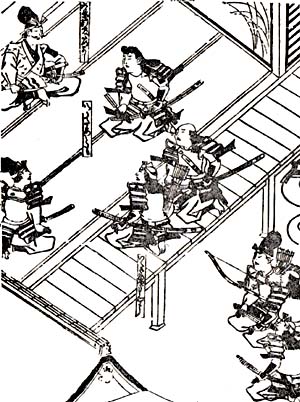|
****************************************
Index 保元(巻上 巻中 巻下) 平治(巻上 巻中 巻下)
保元物語 巻上
1 いとぐち top
鳥羽天皇は堀河天皇の第一皇子としてお生れになり、五歳の時、父帝(ちちみかど)がおなくなりになりましたので、その後をうけて第七十四代の天皇の御位(みくらい)におつきになりました。
御在位十六年の間、御祖父白河法皇のお力添え(院政)により大平無事の政治をお布(し)きになり、国民の生活は大いにうるおいました。
御年二十一歳で、御位を第一皇子崇徳(すとく)天皇に譲って、上皇におなりになりましたが、二十七歳の時、白河法皇がおなくなりになりましたので、かわって院政をおとりになることになりました。
忠義の臣下に対しては厚く恩賞をお与えにたり、また罪を犯した臣下に対してもやさしい態度でお許しになりましたので、国民はみなひとしく上皇の御慈愛に感服して仕事に励み、毎日毎日平和と幸福に満ち足りた生活を送ることができました。
さて、崇徳天皇の御代も十七年ほど続きましたころ、鳥羽上皇と美福門院(びふくもんいん)という女御(おきさき)との間に体仁(なりひと)親王がお生れになりました。
上皇にとっては第五皇子、崇徳天皇にとっては異母弟にあたられます。
上皇はこの皇子をとりわけ深くおかわいがりになり、さっそく生後まだ三か月というのにもう皇太子にお立てになりました。
そのあくる年に、天皇には第一皇子重仁(しげひと)親王がお生れになりましたけれども、どうすることもできません。
第一皇子があってもその皇子には将来の天皇の地位が保証されていないわけですから、天皇の御心中はどれほど残念であったでしょう。 |
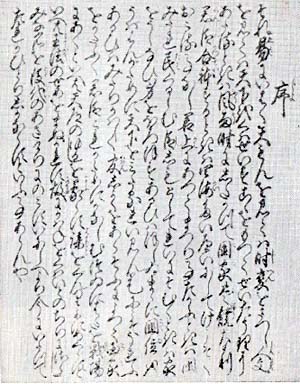
保元物語 版本巻頭
|
そういう天皇の無念さを、ちっとはげしくかき立てる事件がおこりました。
それは皇太子体仁(なりひと)親王がお年三歳の時のことでした。
法皇――この年に上皇は仏門にお入りになりましたので法皇と申します――は、天皇に迫ってむりやりに御位を譲れとおっしゃったのです。
権力のある法皇のお言葉ですがらそむくわけには参りません。悲しみと憤りの涙をおさえて天皇は退位し、上皇におなりになりました。
こうして、体仁親王はわずか三歳という幼いお年で御即位になりましたが、この方を近衛(このえ)天皇と申しあげます。
鳥羽法皇と崇徳上皇とは本当の父と子という間柄(あいだがら)なのですけれども、近衛天皇をめぐるおかしな空気がしこりとなって、お二人の仲に冷たく重くよどむことになりました。
それでもいつしか十四年の年月は流れました。
近衛天皇は、か年十七歳です。まだまだ前途には長い春秋に富んでいらっしゃるのに、どうしたことか、ほんのしばらくの間の御病気でおなくなりになりました。
御父法皇、母君美福門院のお嘆きの深さは申すまで奄ありません。
ところで、第七十七代の天皇の御位(みくらい)はどなたがおつぎになるでしょうか。
これが、さし迫った現実の問題です。崇徳上皇としては、がっての不平不満が今度こそ自然な形で解決できるという期待をお持ちになりました。
それは、御自身がもう一度返り咲くことはできないにしても、第一皇子重仁(しげひと)親王がきっと天皇におなりになるに違いないと、内心ひそかに楽しみにしておいでになったのです。
世間の人々もみな、当然そうなることと信じていました。
ところが、意外にも法皇の第四皇子で、雅仁(まさひと)親王と申す方の御即位ということにきまりました。
後白河天皇と申すことになりますが、この方は今まであまり目立たず、ぱっとしない存在でしたので、世間では目をまるくして驚きました。
なぜ、こんな結果になったかと言いますと、そこにはつぎのような事情がかくされていたのです。
、そういう方の皇子に皇位がまわってはくやしい、何とか邪魔をしなくてはならない――と、こういうふうに美福門院がお考えになりまして、法皇に対してしきりに雅仁(まさひと)親王をおすすめになりました。
法皇も、これに動かされて雅仁親王を立て、とうとう重仁親上を無視しておしまいになったのです。
さあ、こうなると崇徳上皇はたまりません。
十四年もの長い間の隠忍自重(いんにんじちょう)がようやく報いられて、胸の重苦しさが今度こそ軽くなるだろうと信じきっておいでになったのに、これではまるでトビに油揚をさらわれたようたものです。お怒りの炎がまた一段とはげしく燃えさかったのは、無理もありません。
さて、一番深く愛しておられた近衛天皇に先立たれておしまいになった鳥羽法皇は、その年の冬、はるばると紀州路(和歌山県)にお出かけになりました。
熊野権現(くまのごんげん)に御参詣(ごさんけい)になるためです。
熊野本宮の本殿の前で、この世のみならず来世までもの幸福を一心こめてお祈りになっていますと、本殿の中に童子(どうじ)の姿がぼうっと見えて、ひらひらと手を何べんも裏返して見せるようです。
不思議なこともあればあるものだ、どういう意味なのか、一つ神さまのお告げをうかがってみようとお思いになりました。 |
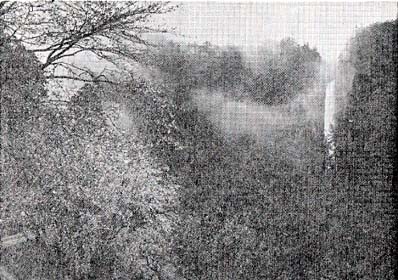
熊野、那智の原始林。右は那智の滝
|
そこで熊野三山の中で最もすぐれた巫(みこ)をお呼びになり、“神おろし”ということをおさせになりました。
けれどもなかなか神さまは下りません。
朝から始めて昼になってもまだ下りませんので、山伏八十余人が加わって大般若経(だいはんにゃきょう)を一せいに読みあげて祈願をこらし、玉石一心不乱になってお祈りをささけますと、どうにか効験(こうけん)があらわれました。
巫(みこ)がやっと神がかりの状態にはいって、いろいろ人間離れの動作を見せ始めました。
そして、法皇の方を向いて、右の手を高くあげてひらひらと何べんも裏返す形を見せます。
法皇ははっとして、これは先ほど本殿の前で見た夢想の姿そっくりだ、今こそ神さまのお告げを聞こうと、お思いになりました。
そして、さっそくおすわりになっていた席をすべりおりて、右手を合わせ、
「神さまのお告げを伺いたいと思ったのは、そのことです。いったい、どういう意味ですか。」
とおたずねになりますと、
「明年の秋のころに、法皇はかならずおなくなりになるであろう。
そののち、国内はちょうどこんなふうに手をびっくり返したような大混乱がかかるであろう。」
というお告げです。思いもよらない大変なお告げなので、法皇は申すに及ばず、お供の人々もみな涙を流して、
「それでは、どうすれば法皇はもっと長生きなさることができますか。」とたずねますと、
「寿命の長さは前世からきよっているから、とうにもしようがない。」と答えて、神さまは天に上っておしまいになりました。
こんなお告げを親しくお聞きになった法皇のお心細さは、どれほどであったことでしょう。
いつまでも長生きして何回でも熊野権現に参詣することを、ずっと楽しみにしておいでになりましたが、はからずも今日の参詣が最後になるのだとお思いになると、今はもうほかに何のお望みもなく、ただ安楽に極楽往生できるようにというお祈りをおささげになるばかりでした。
さて、明けの年は四月に年号が改まって保元(ほうげん)と呼びます。
このころから法皇の御健康は、とかくすぐれなくなりました。
世間では、近衛天皇をおなくしになったお悲しみの積もり積もったせいかとおうわさ申していましたけれども、法皇御自身は熊野権現のお告げがいよいよ本当に現われたことと信じて、ありかたいやらさびしいやら複雑なお気持でした。
そして、病気平癒(へいゆ)のための加持祈祷(かじきとう)といった類のことはいっさいおさせになりません。
ただひたすら、極楽往生のお祈りをこめた勤行(ごんぎょう)ばかりさせておいでになります。
七月二日、法皇はとうとうおなくなりになりました。
七月(今の九月ごろ)になったばかりとはいうものの、とにかく秋の季節ですから、熊野権現のお告げはぴたりと的中したわけです。
お年はまだ五十四歳でした。
普通ならもっと長生さして、いつまでも御政治をおとり遊ばされるはずの御年輩です。
生ある者はかならず死ぬという人生のはかなさは、常日ごろだれでも感じているのですから別に驚くことはなさそうですが、今、法皇のお身の上にまざまざとこれを見ては、お側近くお仕えする人々はもちろん、世間の人もみな、今さらのように悲しみの淵に沈むのでした。
中でも美福門院のお嘆きの深さは、何とも申しあげようもありません。
お元気でいらっしゃったころの法皇の御面影は、まぶたに焼きついて離れることなく、昔恋しさの涙にかきくれてばかりおいでになりました。
2 上皇のお心 top
このように世間が上下をあげて法皇をおいたみ申しあげている折から、崇徳上皇はいったいこの情勢に対してどういう態度をおとりになるであろうか。
一旗おあげになるのではあるまいかという不安の念が人々の胸中に広がりました。
というのは、法皇がまだ御病気中のころに、すでに上皇は御謀反をお企てになっているらしいといううわさも立ち、ただうわさだけでなく、証拠として軍兵が東からも西からもあいついでどんどん京都をさして集まるし、馬や車に積みあげた武器が、次々に市内に運びこまれるなど、疑わしい点がたくさんありました。
上皇方の武士は東三条(とうさんじょう)殿に立てこもり、夜は相談をねり、昼間は山の上や高い木の技にのぼって、天皇の御所高松殿のようすをうかがい見るという気配も見えます。
そこで、七月三日、天皇は源義朝(みなもとのよしとも)に命じて東三条殿の留守居役藤原光貞(ふじわらみつさだ)と武士二人を召し捕らせ、事情をお調べになりました。これが法皇がおなくなりになった日の明くる日のできごとですから、よほど情勢はさし迫っていたちのと見なければたりません。
第三者の目にも、こんないろいろな兆候となってはっきりとわかるほど、上皇御自身のお気持ははげしい怒りの炎に燃えさかっていました。
“昔から、天皇の御位を譲り受けるのは、かならずしも長子には限らないけれども、すぐれた人物であり、また母君の家がらが立派な人でなければならないことになっている。
それなのに、近衛天皇が瞼の皇后さまのお気に入りの皇子だというたたそれだけの理由でむりやりに皇位を奪われたことを、自分は大そう残念に思ってすごしてきた。
ところで、近衛天皇がおなくなりになったからには、当然の順序としてわが皇子重仁親王こそ皇位におつきになるのが当然なのに、意外にもまた第四皇子(後白河天皇)にだしぬかれてしまったことは、くやしくてならない。”と、こんなふうに思いつめておいでになりました。
そしておさえ余ったお心の端を、「いったい、どうしたらいいのか。」と側近(そっきん)の者にもらして、御相談をおかけになるのでした。
3 頼長(よりなが)の野心
top
このころ、藤原頼長という人がかりました。
頼長の邸は京都の南方の宇治にありましたし、その地位が左大臣でしたので、世間では頼長のことを宇治の左大臣と呼んでいました。
人物は一点の非の打ち所もないほどりっぱで、学問は和漢共に通じて人一倍すぐれていました。
儀式や礼法についての知識も豊富で、藤原家だけでなく、他家に伝わる文書の内容もよく理解していて生辞引のようです。
それに文章の才能にも恵まれ、あらゆる方面の研究が深く、いずれは朝廷で心重要な地位、たとえば摂政(せっしょう)や関白(かんぱく)の地位にもつくことのできるはずのすばらしい素質を備えていました。
頼長は、当時指折りの大学者藤原通憲(みちのり、信西)の弟子となって、もっぱら中国の学問研究にはげみ、その成果を政治の上にはっきりと反映させました。 |

藤原頼長像
|
儒教(じゅきょう)の主張である仁(じん)・義(ぎ)・礼(れい)・智(ち)・信(しん)をやかましく言い、功労ある者には賞を与え、罰すべき者は罰し、てきぱきと仕事をさばいて厳正な政治をおこないましだから、世間の人は「悪左(あくさ)大臣」(おそるべき左大臣という意味)または「悪左府」(あくさふ)ともよびました。
こんな呼び名を聞くと、どんなにきびしい頑固な人間かと思われますが、本当は気立が大そうきちょうめんで、いくら身分のいやしい舎人(とねり)とか牛飼でも罰せられたときに、筋の通った釈明をすれば、ていねいに耳を傾けて聞くだけの度量を持ち、もし無実の罪であることがはっきりすれば、あっさり取消しました。
また、宮中の公の儀式や会合の席上で、役人が頼長からとがめられたときに、間違っていない理由を弁明をし、それが頼長に納得がいけば、その場ですなおに折れてわび状を書いて与えましました。
こういう性格の人物ですから、世間一般も敬服し、父からも兄以上にかわいがられました。
父は知足院(ちそくいん)禅閤殿下(ぜんごうでんか)と呼ばれる藤原忠実(ただざね)で、兄は法性寺殿と呼ばれる藤原忠通(ただみち)です。
この忠道は当時関白で氏長者でしたが、温厚などちらかといえば、政治家には不向きのタイプで和歌や漢詩を作ることがうまく、また書道の方面にもすぐれた才能を示しました。
こういう性格は頼長から、
「詩や歌を作るなんていうことは、閑(ひま)つぶしの趣味さ。朝廷にとっては何の足しにもならないよ。
字がうまいといったって、そりゃいっときの楽しみさ。国事に精出す者は、そんなものにかまっちゃおられない。」
と、あっさり片づけられるにすぎません。
こんなに性格のへだたっている兄と弟ですし、それに父が弟の方をひいきにするものですから、おのずから仲は悪くならざるをえません。
このことから、ひいては権勢をめぐる争いにまで発展していきました。 |

藤原忠通像
|
さて、忠実は、頼長を氏長者(うじちょうじゃ)にし、続いて内覧の宣旨(せんじ)をも受けさせました。
氏長者というのは、その氏の中で最高の官位を有する人がつく地位で、摂政・関白たる人がなるのが当然です。
また、内覧の宣旨というのは、天皇に奏上する文書を、まず閲覧する役で、関白たる人がこの役につくのが通例です。
したがって、氏長者も内覧の宣旨も忠通の役であるべきはずなのに、忠実は頼長かわいさの余り、こんな異例の人事を行いました。
世間の人気、この点を鋭くついて非難しましたけれども、無理か通れば道理が引っこむのたとえそのままに、
「左大臣だって、将来あるいは関白になられるかもしれない。
とすればすこしばかり早く実際の仕事をくりあげたのだと思えばいい。」
と、あきらめのいい口実を作ってみなの者も目をつぶりましたので、一応この人事は実現しました。
納まらないのは忠通です。もともと関白とは名ばかりで、天下の政務にたずさわることもありませんでしたが、あまりにもふみつけられた今度の件については、さすがに腹にすえかねて。
「近衛天皇が御即位になって、世間はすっきりしたはずだ。
とすれば、私の関白の辞任をお認めくださるか、それとも内覧の宣旨・氏長者という役目を関白たる私におつけくださるか、二つに一つ、いずれにしても天皇におきめいただきたい。」
と、しきりに申し、不平不満をぶちまけました。
さて、忠通は関白ですから、当然天皇の御所に出仕します。すると頼長は、兄が天皇方なら自分は自分の道を行くとbあかりに、上皇の御所に出仕します。
こうして、藤原家内部では兄弟の間の溝がだんだん深くなっていくころ、皇室内部においても法皇・天皇と上皇との御仲たがいは次第にその険しさの度を加えていきました。
そういう時に訪れたのが、法皇の崩御(ほうぎょ)という事件です。
目はしの利く頼長が、どうしてこの好機を見のがしましょう。
“今の天皇が御位についていらっしやる限り、兄が関白でいるわけだから、その兄をさし越えて自分か摂政の地位につくことはできない。
たまたま法皇がおなくなりになったこの際、クーデター(非常手段)をおこして上皇の第一皇子重仁親王を天皇にいただき、兄を隠退させて、自分の思う通りの政治をやってみたいものだ。”
と、こんなよからぬ考えをおこしました。
そして、上皇の御機嫌をとる態度に出ました。上皇も、御自分の立場にとり入ってくる頼長をたのもしい人物だとお思いになりましたから、おのずからそこには、お話の調子もはずんで参ります。
ある夜、上皇は頼長に向かってとうとう本音をお明かしになりました。
「いったい、昔の例を考えてみるに、天智(てんじ)天皇を初め幾代もの天皇が、長子の系統で御位におつきになっていらっしやる。
私も、たまたま亡き法皇の長子に生れたので、一たん天皇の御位につくことができた。
近衛天皇がおなくなりになった後は、自分がもう一度天皇になってもかまわないと思ったが、それができないにしても、長子の重仁(しげひと)親王こそ候補者にはいるのが当然だと思っていた。
それなのに、全然文武の道に秀でてもいない雅仁(まさひと)親王に御位を奪われてしまったことは、くやしくてならない。
けれども父法皇がお元気のうちは、何ともしようがなく、むざむざと月日を送ってきたが、今は法皇もおなくなりになったんだから、私が天下を奪うことに何の遠慮がいろうか。
きっと神の思召しにもかない、世間の期待にもそむかかないと思われるがどうだ。」と、おっしゃったのです。
頼長は“しめたっ。これで自分も摂政(せっしょう)になれることほ間違いない。”とこおどりするばかりによろこびまして、
「お考えは道理千万に存じます。おっしゃる通りでございます。」と、おすすめしました。
こうお心がきまりますと、今までお住みにたっていらっしゃる御所鳥羽離宮の田中殿を引きあげる準備をお始めになりました。
人々も、はっきりとはわからないものの、「どうもひとさわぎおこりそうだ。」と薄気味悪く思い、家財道具をあちらこちらに疎開させるやら、家屋敷の戸じまりを厳重にするやら、武器を集めるやら、京都の町全体に、あわただしい空気がみなぎって参ります。
これを見て、心ある者はまゆをひそめてこんなふうに嘆きました。
「これはどうしたことなのか。
たとえ上皇がクーデターをお起しになったとしても、法皇がおかくれになってからまだ七日しか経っていたいじゃないか。
それなのに、こんな不穏なことをなさるなんて、神さまもけっしてお許しにはならないであろうし、平民の我々が考えたって、どうも納得がいかない。
近頃世間は何の波風もなく平和に治まっていたのに、寝耳に水といったぐあいにこんな騒ぎがおこるなんて……”
4 戦雲動く top
さて天皇方では、このような情勢に対処して京都市中の秩序をとりもどすために、武士をお召しになりました。
お召しに応じて、源義朝(よしとも)・義康(よしやす)・季実(すえざね)、平基盛(もともり)・維繁(これしげ)・実俊(さねとし)・資経(すけつね)ら源平両家の将兵がたくさんに高松殿に参上しました。
高松殿では南庭において少納言入道藤原信西を通じて、天皇のお言葉が達せられました。
それは去る二日、法皇がおなくなりになって以来、武装した将兵があちらからもこちらからも続々と京都に入り込んでくるのは、とんでもない不穏の行動である。
そういう連中はひとり残らず召し捕って宮中に連れてこい、という意味の御命令です。
義朝以下は庭上に平伏して、うやうやしくこの御命令をお受けします。
続いて、警備の部署についてのこまかな御指示があり、それに従って各自の配備がきまりました。
まず、義朝・義康の部隊は高松殿において天皇をお守りします。季実は淀口(摂津方面からの入口)、基盛は宇治路(奈良・宇治方面からの入口)、維繁は粟田口(東近江方面からの入口)、実俊は久久目路(くぐめじ、山科方面)、資経は大江山(丹波方面からの入口)といったぐあいに、京都周辺の重要な関門を固めることになりました。
一方、大納言藤原伊通(これみち)以下の諸公卿もその夜参内しまして、会議を開きましたところ、謀反を企てた一味は全部召し捕って島流しの刑に処せよという天皇の御命令が下りました。
明ければ六日、義朝以下の将兵はそれぞれ配備の部署につきます。宇治路の部署に向かって出発した平基盛は、百騎余りの部下を指揮して法性寺(京都市東山区東福寺の付近にあった寺院)近くの一の橋あたりまで下ってきました。
すると前方から乗馬の武士十騎ほどに徒歩の兵士二十余名合計三十余名の部隊が軍装も物々しくこちらに向かってやってくるではありませんか。
そこで、基盛は部下の者に、
「あなた方は、どちらの国から来てどこに向かうのか。」とたずねさせますと、相手は、
「いや、すぐ近国の者です。近頃京都の市中が不穏だと耳にしましたので、くわしい事情をお聞きしようと思い、入京するのです。」と答えます。
これを聞いて、基盛はみすがら進み出て、
「法皇がおなくなりになったのち、武士どもが続々京都にはいってくるということが天皇のお耳に達したので、警備せよという御命令が出て、今我々は部署に向かうところなのだ。
あなた方がもし天皇方にお味方するのなら、われわれと行動を共にするがいい。
さもなけりや、お通し申すことはできない。
私は桓武天皇十代の御末、刑部卿忠盛の孫、安芸守清盛の次男、安芸判官(あきのほうがん)基盛(もともり)という者で、当年とって十七歳だ。」
と名のりをあげます。
これに応じて、先方からは部隊長らしい男が進み出て、
「こちらは大した者でもないけれども、人並に系図がないわけではない。
清和天皇九代の御末、六孫王(経基)七代の末孫、摂津守頼光の弟、大和守頼親の四代の後胤、中務丞(なかつかさのじょう)頼治の孫、下野権守(しもつけごんのかみ)親弘(ちかひろ)の子で宇野七郎源親治という者だ。
大和の国(奈良県)宇智郡に長く住んでいて、武勇の点ではまだ恥をかいたことはない。
左大臣頼長殿のお召しを受けたので上皇方にお味方するのだ。いくら天皇の御命令だからとて、あっさり天皇のお味方にはなれないよ。
そもそも忠節を守って二君にはお仕えしないというのが、われわれ源氏のおきてだからね。
と、堂々と言いきってそのまま行き過ぎようとしますので、基盛はすぐさま百余騎の部下にぐるりをとりかこませて攻めかかります。
これに対して親治は多勢に無勢とはいえ、もとより覚悟の上ですから、少しもさおかずあわてず、応戦に出ます。
追いつ追われつ互角の戦いです。二時間ほどたつ中に親治の方では十余名、基盛の方に八騎の戦死者を出し、負傷者は無数といった形勢です。
やがて親治は平氏の二人を射落し、敵のたじろぐすきをねらってわあっというかけ声もろとも乗馬の十騎が一かたまりとなって包囲網を破ってかけ抜けようとしました。
この勢いにのまれた基盛の部隊は、こりゃかなわぬと思ったのでしょう、さっといっせいに退却しました。
これより先、この合戦の知らせはいち早く天皇方の本拠高松殿に届きましたので、増援の兵士が続々やってきて、その勢力は一千余に達しました。
基盛は勇気をふるいおこして小高い所にかけ上って一同に向かい、
「敵はそこにいるだけの小人数で、後続の部隊は一人もいない。
幸い味方は多人数だから、体当りでぶつかってみんな生け捕りにして天皇のお目にかけよ。
首はかくな。生け捕りだぞ。」と命令を下しました。
この声に励まされて、五、六人から七、八人もが一かたまりになって相手の一人に組み討ちをしかけますので、さすがの親治(ちかはる)もかないません。
さきほどの広言もどこへやら、自害することもできずにおめおめと生け捕りにされてしまい、そのほかおもだった部下たちも捕虜となりました。
基盛は鎧の袖に射立てられた矢を抜くこともせず、血を浴びて真赤になったそのままの姿で、親治以下の捕寤を護送して高松殿に引き返し、天皇に戦況を御報告申しあげるや、再びくびすをめぐらして定めの宇治路へと向かいました。
この功績に対してその夜臨時の除目(じもく、官吏任命の儀式)が行われ、基盛は面目をほどこしました。
5 頼長の陰謀発覚 top
そのころ頼長の行勵についてへんなうわさが立ちました。
それは頼長が東三条殿に一人の僧侶を篭らせて秘密の行事を行わせ、天皇に呪いをおかけ申しているというのです。
捨てておけないので、天皇は義朝に対して、その僧侶を捕えてくるようにお命じになりました。
さっそく義朝が東三条殿に出向きますと、どの門もみなぴたりとしめきってあって、いくら「あけろ」とどなってもあけてくれません。
やむをえず小さな門をたたきこわして中にはいり、あちらこちら搜しまわります。
と、広い邸内の片ほとりで何やら秘法を行っている僧侶がいますので、“しめたっ”とこおどりして近づいてみますと、相模阿闍梨(さがみのあじゃり)勝尊です。
義朝は、「天皇の御命令だぞ。こい。」と、どなりますが、勝尊は義朝には目もくれず、だまったままです。
部下の者が近づいて勝尊の両手を引っぱろうとしますと、ひじをうんと曲げて少しものばさず、引っぱりようがありません。
まるで仁王様を相手にしているようです。じれったくなった義朝が、
「おとなしくつれ出そうと思ったが、これじゃだめだ。やむをえないから、ふんじばってしまえ。」
と言うや否や、部下の兵士はばらばらっと大ぜいかけよって取り押さえ、がんじがらめにしばりあげて、高松殿につれていきました。
高松殿では、すぐに取調べが始まりましたが、勝尊は、
「はい。たしかに私は秘法を行っていました。
が、それはほかでもございません、
関白様(忠通)と左大臣様(頼長)兄弟お二人の仲がまるく納まりますようにとお祈りしていただけです。
呪いなんどとは、とんでもない濡衣です。」と、白ばくれて答えます。
けれども、一緒に取りあげられた証拠の書類をつきつけられては、いくら口先でうまくごまかしたつもりでも、どうにもかくしきれません。
うわさの通り頼長に頼まれて天皇に呪いをおかけするための秘法を行っていたことが明らかになりました。
証拠の書類というのは、頼長から勝尊にあてた七月二日付の手紙で、その中にはっきりとそのことが書いてあったのです。
また別のうわさもきこえてきました。
それは、頼長が平馬助忠正(へいまのすけただまさ)とか多田蔵人頼憲(ただのくろうどよりのり)とかいった一かどの武将を味方に引き入れようと、しきりにさそっているらしいというのです。
そこで念のため忠正や頼憲に呼び出しをかけてみますと、はたして宿所にはいません。近頃はずっと宇治の頼長の邸(やしき)に詰めているという話です。
こういう事実から判断して、頼長が何か不穏な陰諜を企てていることは、もはや疑う余地はありません。
そこで関白忠通以下の公卿にお召しがあり、臨時の会議が開かれまして、頼長に対する処分が議題となりました。
結局、来る十一日に島流しにするという結論が出ました。
6 上皇、白河殿へ top
さてその日はちょうど亡き法皇の初七日にあたりますので、鳥羽離宮内の田中殿で御法要が行われました。
ところが、同じ御殿にお住まいになっていらっしやるのに、どうしたことか上皇は御法要の座においでになりません。
人々が変だなと感じていた折も折、京都の方に移りたいと仰せになりますので、左京大夫教長(のりなが、京都左京地区を取締る役所の長官)はあわてて、
「法皇がおなくなりになってから、まだ御四十九日もたちませんのに、京都にお移りになるということは、世間が変なふうにおとりするにきまっています。
それにまた、神仏もきっとおとがめになりますから、御遠慮あそばしては……。」
とおいさめ申しあげますが、上皇は少しもお聞き入れになる気配がありません。
困りはてた教長が、上皇の母君の兄、徳大寺内大臣実能に相談しますと、実能は教長の考えに全面的に賛成しました。
「いや、かねがね左大臣が上皇に御謀反をおすすめしているといううわさは、私も耳にしていたがまさかと思っていた。
もし、本当だとすれば、むだなお考えと申さればならない。
何といったって天皇の御運は大したもので、人間の思慮のおよぶ所ではなく、全く神さまの思召(おぼしめ)しによることである。
わが国はちっぽけな島国だけれども、神国だから、八百万(よろず)の神々が皇室をお守りになっている。
だから神さまの思召し次第で天皇の御位が弟の宮や甥の皇子にかわっていくことは、昔たっていくらも例がある。
上皇も運を天に任せてじっとしておいでになるのが一番いいのだが、それがおできにならないなら、いっそ御出家なさってさっぱりしたお気持で静かに余生をお送りになるのがおきれいだと私は思う。
とりわけ法皇の御四十九日のさなかで、まだ初七日が過ぎるか過ぎないかのいま、わざわざ京都にお移りになることは、どうも合点がいかない。
あなたは、もう一度上皇の御機嫌のいい時を見はからっておいさめ申しあげなさい。」とありのままに卒直な意見を述べました。
これに力を得た教長は、さっそくまた上皇の所に参りまして、実能(さねよし)の意見に添えてあらゆる言葉を尽くして御進言申しあげましたが、上皇はなかなか御承知になりません。
「そりゃ、話の筋はその通りだ。
げれども、私がこの御殿にいると、危害を加えられそうだということも耳にしているので、その難を避けるために引きあげようと思うだけで、ほかに何の目的もありゃしないよ。」と、つっぱねておしまいになりました。
そして、とうとう七月九日の夜もふけたころ、教長(のりなが)以下をお供につれて田中殿から白河殿にお移りになりました。
7 為義(ためよし)、白河殿へ
top
そのころ六条判官源為義といって、源氏の本家を代表する武将がありました。
あの有名な八幡太郎義家の孫にあたりますが、事情があってその養子となっていました。
このような名門の武将を味方につけるとつけないとでは、士気の点でも勢力の点でもプラスマイナスの大きなわかれ目になります。
そこで、天皇方でも上皇方でも何とかして為義を味方に引き入れようと一生懸命です。
両方から引っぱりだこになりました。
ところが本人の為義は、どういうつもりなのか、一向に態度を明らかにしません。
それでも上皇方の度重なるさそいにやっと折れて、お味方するという意思表示はしましたものの、やはりじっと自分の宿所に腰をすえたまま動こうとしません。
しびれを切らした上皇方からは、教長が使者となって六条堀河にある宿所に出かけ、膝詰談判をしました。
このことは、かえって為義の心を硬化させ、もうお味方できないとまで言わせてしまいました。
為義は、こう言ったのです。 |

八幡太郎義家(前賢故実より)
|
「私は、義家の養子として源氏の代表となって皇室をお守りすべき身分の者ですから、上皇が頼もしい奴だとお思いになるのは無理もございません。が、私は、本当の所、合戦らしい合戦をした経験がまだないのです。
名ばかりの合戦なら、十四歳の年、叔父義綱を近江の国の甲賀山中に攻めたとき、叔父の子供はみな自害するし、その家来たちは散り散りばらばらに逃げてしまったために、義綱ひとりが出家して、降参したのを捕えたことがありますし、また十八歳の年、奈良の興福寺の僧兵が皇室に対する不満を情らすために大挙して京都に押しかけて参りましたときに、たった十七騎という小人数でしたが数万騎の僧兵を追い散らしたこともあります。
けれども、こんなものは合戦の数にはいりません。
そののちは、何か大きな事件がおこりましても、いつも若い者どもをやって取りしずめさせましたから、私の手柄にはなりません。 こんなわけで、私自身は合戦についてはずぶの素人ですし、それにもう七十に近い老人にもなりましたので、何のお役にも立ちません。
先日来、天皇方からもたびたびお召しがございましたが、病気だと申しておことわり申しあげました。
とにかく今度の合戦の総大将の役をお引受けしたくない理由は、まだほかにもございます。
と申しますのは、さかごろも氏神の石清水(いわしみず)八幡宮にお龍りして願をかけておりましたところ、妙なお告げをいただきましたし、それに気味の悪い夢を見たりなどしたものですから、どうしてもおことわり申しとう存じます。
何しろ、源氏には御承知の通り「月数」(つきかず)を初め八領(はちりょう)の鎧が家宝として代々伝わっておりますが、その鎧の八領が八領ともみな旋風(せんぷう)に吹き飛ばされて散り散りになってしまうという縁起の悪い、いやな夢なのです。 どうか今度の合戦の総大将は、だれかほかの者にお命じになってください。」 |
――こんなふうに言葉を尽くして辞退いたしますと、教長は、
「夢などというものは、はかないものですよ。
般若経という尊いお経の中にも、はかないもののたとえとしてはっきり言いてあるじゃありませんか。
それに夢見が悪いから引寵るなんて武士らしくもなく臆病ですよ。
白河殿に帰って上皇に御報告申しあげるのにも、それじゃ困ります。
どうしてお召しに応じられないことがあるものですか。」 |
と食いさがりますので、為義は、
「それでは、だれか私の代りの者を御推薦申しあげましょう。
私の子供の中では義朝が一番の適任者です。義朝は東国育ちでございまして、合戦については場なれしていますし、部下もいくさしょうずの強兵揃いという男ですが、残念ながら天皇方に参っております。
この義朝を除いては他の子ともに部下も少なく大将の器でもございません。
ただ一人、八男の為朝だけは、腕っぷしは人一倍強く、弓も人並以上でございます。
若いころ、ちと乱暴が過ぎましたので、九州の方へ追い払ってありましたが、近頃京都に帰ってきております。
どうか、この為朝をお召しになりまして、作戦や何かについての意見をお聞きください。」
と、どこまでも逃げよう、逃げようとしますが、教長はなお心ねばり強く、
「そういうことも、あなた自身が白河殿においでになって上皇に直接申しあげなさるのが本筋ではありませんか。
家に腰をおちつけたままで、上皇のお言葉に御返事申しあげるなどということは、どうでしょうか、失礼千万と存じますよ。」 |
と、為義の痛い所を突きます。
こう言われては、もう為義も動かないではいられません。
やっと頼賢(よりかた)以下六人の子供を引きつれて白河殿に参入しました。
上皇のおよろこびは大したものでした。
すぐに荘園(領地)をお与えになるやら、判官代(院の御所に仕える判官)をお命じになるやら、その上鵜丸(うのまる)という太刀まで賜わるやら、為義にとっては名誉この上もないはどの御信頼ぶりでした。
こういうおもてなしに感激する為義の心のなかには、それとは別に源氏の運命をこの一戦にかけるのだという悲壮な気持がわきあふれてくるのをどうすることもできませんでした。
さて、ここで両軍の顔ぶれ比べてみましょう。
上皇方には左大臣藤原頼長を初めとして、教長(のりなが)、成雅(なりまさ)、成隆(なりたか)、頼輔(よりすけ)、泰成(やすなり)、盛憲(もりのり)、経憲(つねのり)、平正弘父子、平忠正父子、源為義父子ら総勢一千余騎。
天皇方には関白頷原忠通(ただみち)以下実能(さねよし)、公教(きみのり)、光頼(みつより)、源師仲(もろなか)、信西(しんぜい)、源義朝(よしとも)、義康(よしやす)、頼政(よりまさ)、季実(すえざね)、平清盛(きよもり)父子ら合計二千余騎。
この二つの大きな勢力がいずれも京都市内に本拠をかまえて、天下分け目の決戦に臨もうと水ももらさぬ作戦をねっています。
8 為朝(ためとも)の武勇
top
山河殿では軍の勢ぞろいがすみますと、それぞれの出入口に将兵を配置することになりました。
このとき、源為義一家は大坎御門面(おおいみかどおもて)の西門を守備するよう命ぜられましたが、為義の八男為朝(ためとも)は、自信たっぷりと広言を吐いて、ただひとり賀茂川に面した西河原面(にしかわらおもて)の門を引き受けました。
その言葉がなかなかふるっています。
「われは親にも連れまし、兄にも具すまじ。
高名不覚も紛れぬ様に、ただ一人如何にも強がらん方へさしむけたまへ。
たとい千騎もあれ万騎もあれ一方は射払はんずなり。」 |
私は父や兄と一緒ではいやです。
手柄を立てるにしても、恥をかくにしても、その責任がはっきりするよう、どこか強敵の寄せて来そうな場所にただひとり向けてください。
そうしたら、たとえ一千騎来ようが一万騎押し寄せようが、私の引き受けた場所の敵はきれいに追い払ってみせるつもりです。
自分の腕によはどの覚えのない限り、こういう思いきったひきうけ方はできないはずですが、為朝には胸に満ち溢れる自信が脈うっていました。
この人物は、源為朝という呼び方よりも鎮西八郎(ちんぜいはちろう)為朝という名の方がぴったりくるでしょう。
あの弓の名人為朝は、この人なのです。鎮西というのは九州地方のことをいい、為朝はかつて九州地方に追いやられていたことがあるのでこういう呼び名を用います。
八郎というのは八番目の男子という意味です。
彼の体格は人並すぐれ、性格は勝気で強弓をらくに使いこなし、矢を続けざまに早く射ることのできる名手でした。
弓を押す左手の肘が弦をひく右手に比べて四寸(約十二センチ)も長かったのですから、だれよりも長い矢を射ることができたのも当然でしょう。
幼年時代から遠慮ということを知らぬ気性で、兄を兄とも思わず、自由奔放な、手に負えぬ腕白小僧でした。
そこで父為義は、こんな子供をいつまでも手許に置いておくことはよろしくないと考え、親子の縁を切って九州に追放したのです。
そのころ為朝はわずか十三歳でした。
九州に追っ払われた為朝は、追っ払われてしょげるどころか、かえって自由の天地に羽をのばし、天皇からいただきもしない自分勝手な九州総追捕使という肩書をふりまわして、九州征服の企てをおこしました。 |

鎮西八郎為朝(前賢故実より)
|
これに対して、菊地・原田を初め数十か所の豪族は所々に城を築いてそれに対抗する手段を講じました。
為朝の気勢はますますあおられます。阿曽三郎忠国を案内者として、十三歳の三月末から十五歳の十月までの間に大きな合戦を二十数回、城を攻め落すこと数十か所という目ざましい奮戦ぶりです。
作戦射画、戦闘方法が実に巧みで結局三年間に九州全土をうち従えてしまったのです。
最初にふりまわした九州総追捕使という肩書を、単なる空念仏に終らせず自分の力で実績を作りあげたからえらいものです。
けれども、そのためにはかなり無理な戦法で押し通しましだから、当然そのむくいを受けなければならなくなりました。
それは、いじめぬかれた土地の人々を代表して、香椎宮(かしいのみや)の神官たちが京都に上り、朝廷にその横暴ぶりを訴えて為朝を処分していただきたいとお願いしたのです。
そこで、為朝を召しとるようにという天皇の御命令が出てしまいました。
ところが、このような御命令が出ても、為朝はいっこうに平気なものです。
このままでは朝廷の威信に傷がつくというわけで、父為義を免職にするという処置がとられました。
さあ、事ここに及んではさすがの為朝も閉口してしまいました。子供として、自分の身代りに父親が処罰されたと聞いてはだまっておられません。
為朝は、とうとう兜をぬいで、おとなしく朝廷の処罰に服しようと決心し、大いそぎで京都に帰りました。
こうして一たんは遠い九州まで追放した子供が父親の身を案して孝行の志を見せてくれれば、親たる者の心のほどけるのは当然でしょう。
為義もよろこんで勘当を解きました。ところが、今度の合戦です。
為義はさっそく一味として加えることになったのです。
さて、堂々と武装に身を固めた若武者為朝が味方に加わったことは、上皇方の勇気を百倍にも千倍にも奮いたたしました。
このホープが、かつて九州一円を思う存分に打ち従えた戦略戦術を基礎として、目の前にせまった合戦の作戦計画について考えを述べました。
それは、夜襲・焼討ちという作戦です。
「為朝久しく鎮西に居住仕って、九国の者共従へ候について、大小の合戦数を知らず。中にも折角の合戦二十余箇度なり。
あるひは敵に囲まれて強陣を破り、あるひは城を攻めて敵を亡ぼすにも、みな利を得ること夜討に如くこと侍らず。
然ればただいま高松殿に押寄せ、三方に火を懸け、一方にて支へ候はんに、火を遁(のが)れん者は矢を免(まぬが)るべからず。
矢を恐れん者は、火を遁るべがらす。
主上(しゅじょう)の御方(みかた)心にくくも覚え候はず。但し兄にて候義朝などこそ駆け出でんずらめ。
それら真中指して射落し候ひなん。まして清盛などがへろへろ矢、何程のことか候ふべき。
鎧の袖にて払ひ、蹴ちらして捨てなん。
行幸(ぎょうこう)他所へならば、御免(おんゆる)されを蒙(こうむ)って、お供の者、少人射んずる程ならば、定めて駕輿丁(かよちょう)も御輿(みこし)も捨てて逃げ去り候はんずらん。
その時為朝参り向かひ、行幸をこの御所へなし奉り、君を御位につけ参らせんこと、掌を返すごとくに候ふべし。
主上を迎へ参ら壮んこと、為朝矢二つ三つ放たんするばかりにて、いまだ天の明けざらん前に、勝負を決せん条、何の疑ひか候ふべき。 |
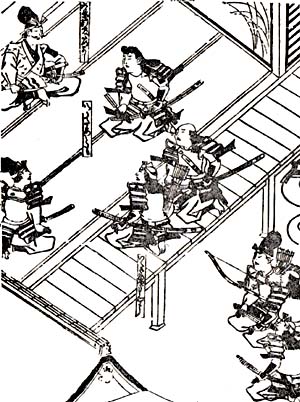
為義と為朝、軍議を練る(版本のさし絵より)
|
|
「私は長い間、九州に住んでいまして、あの辺一帯を征服いたしましたが、征服するについては大ふさまざまの合戦をいたしております。
中でも真剣な気持で戦ったことが二十ぺん余りございます。
その経験から申しますと、勝つためには夜襲が一番有利でございます。
ですから、今すぐ高松殿に攻め寄せて、三方から火をかけ、一方で待ちぶせしますれば、敵をみな殺しにすることができます。
と申しますのは、火を避けて逃げ出す者があればそれはこちらの思う壺、矢で殺すだけですし、がりに矢を恐れて後もどりして逃げこめば、火に焼かれて死んでしまうという寸法です。
敵方の兵力など少しも強いとは思われません。ただ、私の兄義朝は、勇敢な男ですからあるいは囲みを破って逃げ出すかもしれませんが、それも私がぴたりとねらいをつけて射落してしまいましょう。
義朝でさえこれですから、ましてあの清盛なんかのひょろひょろ矢など、てんで問題にたりません。
鎧の袖で軽くはたき落とすばかりです。
天皇がもしお逃げ出しになるようでしたら、恐れ多いことですが、お供の連中をねらって矢の二、三本も射かけましょう。
そうすれば御輿かきもきっとびっくりして御輿を放り出して逃げてしまいましょう。
そのすきに御輿をこの白河殿にかつぎこんで、御位を上皇にお譲りいただいてはいかがでございましょうか。
じつに簡単な話でございます。
わずか二、三本の矢で天皇をここにお迎えできるわけでして、夜もまだ明けないうちにあっさり勝負がつくにきまっております。」
と雄弁にまくし立てます。すると頼長は、
「為朝の今の意見は、とんでもない暴論だ。
まだ年も若いからかもしれないが、そもそも夜襲などということは、お前ども武士だけの間の十騎か二十騎程度の小競合(こぜりあい)の場合の話だ。
いやしくも天皇と上皇との御仲で、御位を奪いあいなさるうという今度の合戦にあたり、源氏も平氏も二派に分かれて総がかりで正々堂々の勝負をしようというのに、そんな小細工はもっての外だ。
それに今夜はまだ味方の兵力も不足している。
もうすぐ奈良の興福寺の僧兵どもが、吉野十津川の猛者連をつれて千余騎ではせ参ずるのだ。
今夜は宇治泊りで、明朝早くここに着くはず。
この部隊の着くのを待って陣容をととのえてから、合戦を始めることにしたい。」
と、自分勝手な判断をくだし、為朝の意見は全然問題にもしません。
為朝は内心不服でたまりませんが、しかし、左大臣の裁定ですからその場はおとなしく引きさがりはしたものの、納まらない胸の不満を部下の者にそっとこんなふうにあらすのでした。
「この広い世界のどこを捜(さが)したって、政治と戦争とが一緒になるなんてこともあるものか。
餅は餅屋のたとえの通り、合戦については万事武士にまかせておくのがいいのに、畑違いの大臣が自分の手にきめるなんて、どうかと思う。
兄貴義朝はなかなかのいくさ上手だから、きっと機先を制して今夜夜討ちをかけてくるに違いない。
あすまでじっとしていてくれれば、こっちには奈良からの僧兵が加わってくれようけれど、今すぐ押し寄せてきて風上に火をつけでもしたら、もうだめだ。
敵がそれで元気づいたら、味方は一たまりもあるまい。
それを思うだけでも、くやしくてたまらない。」
9 天皇方の勢ぞろえ top
さて、話はかわってこちらは天皇方です。
今までの手狭な高松殿から広々とした東三条殿に本拠を移して着々と開戦の場合に備えます。
まず、関白忠通以下の公卿が擺まって天皇の御前で作戦についての会議が開かれました。
会議の席には武士の代表として源義朝が呼び出され、少納言入道信西を通じて合戦の方法についておたずねがありました。義朝は、
「いくさの方法もいろいろございますが、あっという間に敵を打ち従え、勝利をつかむには夜襲にまさるものぱございません。
聞くところによれば奈良の僧兵が吉野・十津川の連中をつれて、明朝京都入りするそうでございます。
敵の兵力が大きくならないうちに、先手を打って押し寄せましょう。
皇居の守備は清盛にでもお命じになってください。 |

僧兵(一遍上人絵伝部分)
|
攻撃の方は私自身お引受けしまして、一挙に勝負をつけましょう。」と自信たっぷりのお答えをいたします。
この言葉を聞いた信西(しんぜい)は、関白忠通(ただみち)の内諾か得まして、
「そりゃ名案だ。詩だ、歌だ、音楽だといった方面は公卿のお得意だけれども、それだってまだまだわからない点が多い。 まして畑違いの武芸といった方面については、さっぱり見当がつかない。
だから、いくさについては万事おまえの一存に任(まか)せよう。
諺にも『先んずる時は人を制す。後にする時は人に制せらる』(こちらから積極的壮行動に出れば、相手を圧倒することができる。
その反対にぐずぐずしていれば、相手に圧倒されてしまう)とある通り、敵の出鼻をくじいて今夜こちらから打って出ようという考えは賢明だ。
が、それなら清盛を皇居の守備に残す必要もない。
武士の者総がかりで出かけよ。
天皇の御威光を軽んじ申す敵が、どうして天罰を受けずにすむものか。
一刻も早くそういう連中を討ちたいらげて、天皇のお怒りをおしずめ申すならば、おまえが常日ごろ望んでいる昇殿(殿上人の身分に任せられること)のお許しの出ることも間違いないぞ。」
と励ましますと、義朝は、
「私は戦場に出かけるのに、生きて帰るうなどとは夢にも思っていません。
ごほうびをいただくなら、たった今、この場でいただいて、冥途のみやげにいたしとう存じます。」
と言い放つや、武装のまま、つかつかと殿上の間にのぼっていきました。
あわてたのは信西です。
自分がよけいなことを言ったばかりに大変なことになった、とうろたえて、
「義朝、何をする。」
と、しかりつけましたが、天皇は、かえって生一本な義朝の気性をおもしろくお思いになり、何のおとがめもありませんでした。
時を移さず、天皇方の部隊は出撃の準備をととのえ、はやる心をおししずめおししずめして京三条殿を出発しました。
すでに、月は西の山に沈んで夜明けにはまだ間のあるほの暗さなのに、その上あたり一面は秋霧が濃く立ちこめて、目ざす白河殿の方角はさっぱりつかめません。
折しも濃霧の底をぼおっと染めてあがるかがり火の赤さ――あれこそ敵の陣営だと勇みおどって進んでいきました。
ころは保元元年七月十一日午前四時のころ。その兵力は義朝勢が三百余騎、清盛勢が六百余騎、頼政勢が二百余騎、そのほか合わせて千七百余騎という大がかりなものでした。
top
****************************************
|