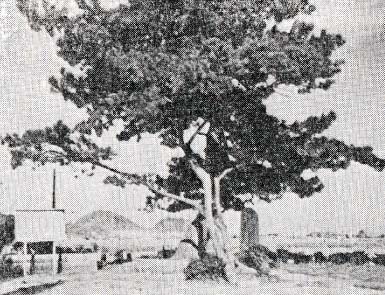|
****************************************
Index 保元(巻上 巻中 巻下) 平治(巻上 巻中 巻下)
平治物語 巻下
1 義平の死 top
ところで、美濃の国青墓の宿から飛騨路をさして落ちていった悪源太義平の運命はどうなったでしょうか。
飛騨にはいって軍兵を募りますと、たちどころにたくさんの兵士が集まりましたが、やがて義朝が尾張の国の野間であえなく最期を遂げたという情報が伝わってきます。
もともと烏合の衆の悲しさ、とたんに離れ去ってしまい、また元の一人にもどってしまいました。
義平も一たんは自殺して父の跡を追おうとしましたけれども、いやいや同じ死ぬなら、親のあだの清盛父子の中のだれでもいい、せめて一人なりとも討ち取ってからにしようと思い直しました。
そして都に引き返し、あけくれ六波羅のようすをうかがっていました。
と、ちょうど折よく義平の家来の志内六郎景澄(かげずみ)にめぐり合いました。
「景澄じゃないか。どうだ、まさか昔の恩顧(おんこ)を忘れてはいないだろうな。」と言いますと、
「どうして忘れるものですか。
けれども私は役立たずの人間でして、源氏の一味とはだれも知りませんので、敵をだますのは簡単です。
とにかく生きながらえるのが何よりも第一だと思いまして、手づるをたどってうまうまと平家の下役人になりすましています。
今ここで、図らずも、あなたさまにお目にかかれて本当によかったと思います。
いったい、これから先どうしようというお考えですか。」
「にくい親のあだをただの一人でもいいから討ち取りたいのだ。力をかしてくれ。」
「はい。承知いたしました。何なりとお命じになってください。」
「じゃ、こうしよう。わしがおまえの家来に化けるから、おまえは何食わぬ顔で主人ぶっているんだぞ。いいね。」
――こんな会話が二人の間にかわされました。
そして明くる日からは、景澄の出勤する後にいやしい身ごしらえにやつした義平がちょこちょことついていくことになりました。
太刀を持ったり、履物を持ったり、またある日は雨具の蓑笠(みのかさ)の類をささげていくかっこうは、見るからに忠実そうな下僕(げぼく)ぶりです。
こんな苦心を重ねて敵の本拠六波羅の邸の内に自由に出入する機会をつかみましたげれども、残念ながら目ざす敵に手出しをする折はなかなか訪れず、むなしく日は過ぎていきます。
二人はもともとにわか仕込みのにせ主従です。
景澄(かげずみ)がいくらふんぞりかえって横柄(おうへい)そうに振舞っても十分にこなしきることはできませんし、言葉使いにしても柄(がら)についていません。
一方、義平は育ちが育ちですから、いくら家来を装ってみても、態度は堂々として落ちつきがあり、目の色も鋭く、きつく、曲者らしさは隠すことができません。
景澄(かげずみ)の宿所のあるじは、
「こりゃ変だぞ。主人と家来とまるであべこべじやないか。
きっと何か人にはばかるわけがあるにちがいない。」――
こうにらんだものですから、二人の行動に疑惑の目を光らせるようになりました。
怪しいといえば、宿所でする食事のことも納得がいきません。
というのは、食事のころになるといつもきまって部屋をピタリとしめきり、人目を避けるようにしてコソコソと食事をすませる気配があるのです。
そこである日、あるじは二人の部屋の障子の隙間からそっと中のようすをのでいて見ますと、景澄が家来用の食膳につき、家来が主人用の食事をしているではありませんか。
あるじは思わず、あっと声をあげそうになりましたが、危く声を殺して、
「やっぱりそうだったのか。にせの主従たったわい。
くさいとにらんだのはまさしく図星だったぞ。だが、いったい二人の正体は何なのだろう。」
と、いろいろ考えめぐらしました。
“景澄という人物は以前は源氏の郎等たったそうだから、この家来というふれこみの人物はだれか源氏の名のある者にちがいない。
ひょっとすると悪源太義平じゃあるまいか。
義平が六波雜に近づく窮余の策として景澄の家来に化けているのかもしれない。
そうだとすれば、こりゃ放っておけないぞ。
もしほかの方面からわかってきたら、宿のあるじとしては重大な罪に問われるにきまっている。
とにかく届け出なければなるまい。”――
こう思ったあるじは、さっそくこのことを六波羅に訴(うつた)えて出ました。
驚いたのは平家です。お膝元に屈強の残党が潜んでいようとは夢のようなはなしです。
すぐさま、取る物も取りあえず難波次郎経遠(つねとお)が三百余騎を引き連れてかけつけ、宿所をぐるりととりかこみました。そして。
「鎌倉悪源太義平はいるか。難波次郎経遠が迎えにきたぞ。出てこい。」と大声でさけびますと、中から義平は、
「おう、たしかに悪源太義平はここにいるぞ。かかってこい。腕前のほどを見せてやるぞ。」
と「石切」の名刀をふりかざしておどり出るや、たらどころに先頭の敵兵四、五人を切り伏せたかと思うと、ひらりと屋根に飛びあがり、そのまま屋根から屋根へと伝わって夕やみの中に姿をくらましてしまいました。
時に正月十八日の午後六時ごろでした。
危く急場をのがれた義平は、大原、静原(しずはら)、芹生(せりふ)、梅津、桂、伏見と、都のほとりのあちらこちらを転々として、昼はじっと身をひそめ、夜になるといつも六波羅近くまで足をのばして、すきをうかがいましたが、なかなか折はおとずれません。
そこで、しばらく骨休めしようと思い近江の国(滋賀県)の石山寺の近くに住む知人の所をたずねていくことにしました。
途中、逢坂山の山中で、ごろりと横になってほんの一眠りするつもりのはずが、ぐうぐう高いびきをかいて前後不覚に眠りこけてしまいました。
偶然そこを通りかかったのが経遠(つねとお)の弟難波三郎経房(つねふさ)です。
経房は折から五十騎の部下を連れて石山寺に参詣した帰り道だったのです。
「こんな所にねているのは何者だ。名のれ。」とゆり動かしますと、がばとはね起き、
「源義平だ。さあこい。」と名のるやいなや、散々に切りまわるのでした。
頃合を見すまして経房が引き放った矢は、義平の小腕にみごとに命中しました。
こうなっては、さすがの義平も思うように刀が使えません。 |

義平の昼寝(前賢故実より)
|
多勢を頼む敵兵はなだれのように義平の上に折り重なって、とうとう手を取り足をつかみ髻を引張りして、生捕りにしてしまいました。
時に正月二十五日のことでした。
六波羅に引き立てられた義平は、縁にすわらせられました。こんな取扱いがどうして我慢なりましょう。
「義平ほどの武将に対してこんな扱いってひどいじゃないか。いくら敵だからといってもあんまりだぞ。」
と、どなります。平家方では苦笑いして侍の間に移し、そこで清盛みずから親しく尋問することにしました。
「おい義平。そなたは強いはずじゃなかったか。
この間三条烏丸の隠れ家では三百騎余りもの厳重な囲みをさえ破って逃げ出しておきながら、今度関山じゃたった五十騎余りの軍勢に手もなく召し捕られるとは、いったいどうしたのか。」
「運が尽きたのさ。中国の項羽(こうう)は百万騎の部隊をひきいていても、漢の高祖(こうそ)につかまったそうだ。
人間だれだって運の尽きた時はこんなものだよ。
このわしを生かしておいては平家のためによくないぞ。さっさと切れ。」
と、きっぱり言い切って、あとはもう何と言われてもだまったきりです。
そこですぐさま難波三郎経房(つねふさ)の手で死刑が執行されることになりました。
場所は六条河原です。白昼のこととて河原は黒山のような人だかりです。
死に臨み、堂々と言いました。
「いくら敵だからといって、この義平ほどの勇士を白昼都の真中の賀茂河原で切るとは無念至極である。
さる保元の乱に際して、たくさんの者が処刑されたが、その処刑もなるべく人目に立たないよう昼は西山、東山の片ほとり、たまたま河原で切るとしても夜になってからだった。
武士たる者の身の上は、あすの運命はわからないものだ。
今日は他人のこととして平気でいても、あすはわが身の上に及ぶかも知れないぞ。その辺覚悟しておくがいい。
いったい、平家のやつは上も下もみんな情の冷たいわからず屋ぞろいだ。
去年清盛を初め平家一族が熊野詣でをした折、こちらからどんどん進撃して討ち取ろうとわしが言ったのに、都におびき寄せて一挙にみな殺しにするのだと、あの臆病者の信頼(のぶより)が反対したために失敗した。
それで今日こんな恥さらしの目にあうことになったのはくやしい。
あの時、何が何でも紀州の湯浅か藤代のあたりまで押し寄せるか、安部野で待ち伏せるかして、一兵も余さず討ち果たすことができたのに……。」
「何を今さらぐちをこぼすのか。観念しろ。」と経房がたしなめます。
「なるほど、その通りだ。わしにとってはぐちにちがいない。
さて、おまえはこのわしという勇士の首を切るほどの身分の男か。
見た所そうじゃなさそうだが、とにかく名誉なお役目だ。
みごとに切れよ。切りそこなったら、おまえの頬っぺたにかみつくぞ。」
「何をはかなことを言うか。わしのこの手で切り落す首が、どうして頬っぺたにかみつくことができるものか。」
「いや、今すぐかみつこうというのではない。
むこう百日の中にきっと雷となってけ殺してやるというのだ。」
と、こんな押問答のあと、義平はにゅっと首を高くつき出します。経房が太刀を抜いて背後にまわりますと、くるりと首をまわして、
「みごとに切れよ。」とにらみつけた目つきの鋭さは、とても尋常の人間とは思われませんでした。
こうして義平は、意地と熱との固まりにも似た純情勇取な二十年の生涯を武道つたなく閉じてしまいました。
2 頼朝、捕虜となる top
さて、話かわって頼朝です。寒さきびしい風雪の中で、みなにはぐれ、たったひとりぼっちになった心細さのあまり。
「政家はおらぬか。金王丸はどうした。」
と幼い声を張りあげて呼びますが、答えるものとては、ただごうごうと鳴るふぶきの物すごいうなり音ばかりです。
夜もすがら雪の難所をふみまよいましたが、夜明け方には小平(こひら)という山寺のふもとの村に出てしまいました。
父一行の目ざした青墓とは全然別の方角です。ここで、頼朝は、とある小屋を見つけて近づきますと、中からこんなことをいう男の声がきこえます。
「きっとこの山中にも源氏の落武者どもが隠れているにちがいない。
何しろこの大雪では身動きもでぎかねるだろうな。
たとえ一人でもいいからつかまえて六波羅に差し出したら、ごほうびがもらえるにちがいない。どれ、一つ捜しに出かけてみようか。」
頼朝は、こりゃ大変と、大急ぎでそこを走りぬけました。
あまり走って疲れたので村はずれの木の蔭で一息入れていますと、たまたまそこを通りかかる尼さんがありました。
尼さんは親切な人で、寒さにふるえている頼朝をいじらしく思い、自分の家に連れていって、ゆっくり休ませてくれました。
その親切に甘えた頼朝は、とうとう正月中はそこに厄介になってしまいました。
やがて雪も消えるころになりましたので、頼朝は厚く御礼を言って、またあてどもないさすらいの旅に出ます。
人目をはばかる身ですから、道もないような所をたどりたどり歩いていきますと、ある谷川のほとりにさしかかりました。
ここで一人の鵜飼(うかい)の人にいきあいましたところ、この人も情深い人でして、こう言ってくれます。
「どうやら人目をはばかる訳があるようだね。正直に言ってごらん。私がどこへでも送り届けてあげよう。」
「じつは青墓という所へ行きたいんだよ。」
「それじゃ、そんな姿では見つかってしまうよ。身なりを変えなくちゃ……」と言って、女の着物をきせ、名刀「髪切」(ひげきり)は菅(すげ)に包んで自分で持ち、ちょうど男の人が女の人を連れていくといったかっこうで、どんどん歩き出しました。
お蔭で、だれにも見とがめられることかく青墓に着くことができました。すぐ大炊(おおい)の邸を訪ねて、
「頼朝だよ。」と名のりますと、延寿(えんじゅ)は大そうよろこびまして、娘夜叉御前(やしゃごぜん)の部屋に住まわせて手厚いもてなしをしてくれましたが、頼朝は落着く暇もなく、東国に向けて出発するのでし
た。
宿場を出はずれて、さびしい野原の道のあたりにさしかかりますと、前方から大きな部隊がやってきます。
こりゃ困った、とあわてて道の側(そば)の草むらにもぐりこんだのですが、時すでに遅く、相手に感づかれて、引きずり出されてしまいました。
相手の大将というのは平頼盛の家来で弥兵衛(やひょうえ)宗清(むねきよ)といい、たまたま尾張の国から京都に行く途中だったのです。
宗清が疑いながらこの少年を捕えて顔を見ますと、まごう方なく頼朝ではありませんか。
思わぬ所で思わぬ拾い物した宗清のよろこびようは大したものでした。
さっそく引き連れてそのまま京都への行軍を続けます。
道はやがて青墓の宿場町に入ります。皮肉にも宗清は大炊の邸に泊ることになりました。
かねてから耳にしている節があるので、宗清は何気ないふりで庭に出てあたりを見まわしていますと、一か所土の香も新しい墓めいた場所があります。
卒塔婆(そとば)さえ立ててあるではありませんか。
さては……と思い、すぐ掘り返させてみますと、首と胴体とをつき合わせた死骸が出てきました。
主人の大炊を呼びつけて問いただしますと、何と、これが頼朝の兄朝長(ともなが)の死骸とのこと。
こうして宗清は、またもや偶然の拾い物を手に入れたわけで、朝長の首と、生け捕りの頼朝とを、今度の旅行の何よりの土産(みやげ)物としてよろこび勇んで上京しました。
朝長の首は、すぐ獄門にさらされましたが、頼朝の身柄は一時宗清(むねきよ)に預けられることにきまりました。
3 池禅尼(いけのぜんに)の慈愛
top
やがて、頼朝も処刑されるといううわさが立ちました。
「どうです。死にたくはないでしょう。」
「うん。前の保元の乱の特にはたくさんの叔父や親類の者をなくし、今度の合戦でも父や兄や弟もみんな死んじやったから、いっそお坊さんになって死んだ人々の冥福を祈ってあげたいんだよ。
だから、死にたくはないさ。」
「私の主人頼盛(よりもり)殿の母池禅尼という方は、清盛公には継母にあたられますが、清盛公は大切に扱っていらっしやるので、この方におすがりして命ごいなさったら、あるいは助けていただけるかもしれませんよ。
もともと大変慈悲深い方でして、先日も私がお側に参った時、『お前のところに頼朝がいるそうだが、どんな人間か』
とおたずねになりました。
そこで私は、『年のわりにおとなびています。それに姿が家盛殿(禅尼の亡き実子)にとてもよく似ています』
とお答えしましたら、本当になつかしそうなご様子でしたよ。」
「命ごいしてもらうといって、だれが池禅尼に取りなしてくれるかしら。」
「そういうお気持でしたら、私がお願いしてみましょう。
望み通りにいくかどうかは受け合いかねますがね。」
――こんな会話が宗清と頼朝との間にかわされました。
さっそく宗清は池禅尼(いけのぜんに)の所にいき、訳を話しますと、禅尼もついほろりとなって、
「私が慈悲深いということを、いったいだれが頼朝の耳に入れたのかしら。 いやそんなことはともかく主人の忠盛が生きていたころは、たくさんの者の命ごいをしてあげたが、今となってはうまくいくかどうか受け合いかねるよ。
|

池禅尼(版本のさし絵より)
|
それにしても、頼朝が亡き家盛にとても似ていると聞くと、ふびんでたまらない。
あの家盛さえ生きているなら、たとえ火の中水の中に飛び込んででもあいたい。
もし、あの世であえるというのなら、今すぐ死んであの世にいきたいとさえ思うんだよ。
そんないとしいかが子に生き写しの頼朝が切られるなんて……。
いつ頼朝の首を切ることにきまったのかね。」
「十三日だと聞いております。」
「そう。うまくいくかどうかわからないけれど、一応すぐ頼んであげよう。」
こう言って禅尼は、すぐに重盛を通じて清盛にこのことを伝えさせました。
けれども、清盛は言下にはねつけました。
何しろ、頼朝は、年こそ幼けれ、義朝の血をひく一人であり、それに兄弟の中でも特にすぐれていると見こまれていたのですから、余人ならいざ知らず、この者だけはもし生かしておいては、平家のためによろしくないと思われたのも、むりからぬことです。
重盛は帰って禅尼に知らせますと、
「やっぱり、そうだったの。昔の方がよほどよかった。
夫忠盛が生きているなら、私の頼みもこんなにあっさりけられることはあるまいに……。
源氏一門はもうほとんど死に絶えているんだから、あんな幼い頼朝ひとりぐらい助けておいたところで、大した心配があるものですか。
私は前世で頼朝に助けられた因縁でもあるのかしらないが、頼朝の身の上を聞いてからというものは、とてもふびんに思えてならないんだよ。
何とか命ごいできないものかしら。
あなたを悪くいうわけではないが、事の成る成らぬは、一つにはお使いの者の言い方にもよるというから、もういっぺん取りなしてくれませんか。
それでもだめだったら、私も死んでしまおう。
頼朝の面影が家盛にそっくりだというので、いつも家盛のことばかり悲しく思い出されて、胸も重苦しく、物もろくろくのどを通らない有様。
こんなではどうせ私の寿命も長くはありますまい。
もし、こんな私の命でも助けてやろうとお思いなら、まず頼朝の命を助けてやってください。」
と、涙をほろほろと落します。
情深い点では劣らぬ重盛は、ついもらい泣きしますが、一方では困った問題を押しつけられたと弱りました。
が、ようやく心をきめて、今一度清盛に頼んでみることにしました。
前にこりていますので、頼盛とふたりで清盛の前に出て改めて嘆願しました。
さすがの清盛も弱り果てました。
そこで、結局十三日の処刑は一まずのばすということにしてその場はつくろいましたが、死罪を取り止めるという点については、まだはっきりした返事をしません。
さて頼朝ですが、十三日という日がきても何の沙汰もありませんので、これこそ源氏の氏神八幡大菩薩の御加護であるとありかたく思い、ますます信仰を深めるのでした。
そして、せっかく寿命がのびたのだから、念仏を唱え読経もして、亡き父の後生安楽を弔おうと卒塔婆(そとば)を作り、それに経文も書いて、ねんごろに供養しました。
このことが禅尼の耳にはいりますと、いよいよふびんがつのり、あれやこれや手を変え品を変えて清盛に命ごいしましたので、清盛も、とうとう折れて、死一等を減じ伊豆の国(静岡県)蛭が小島(ひるがこじま)に「島流し」するという刑にきめました。
頼朝が死刑をまぬがれ流罪にきまったと聞いてだれよりも一番に喜んだのは池禅尼です。 |
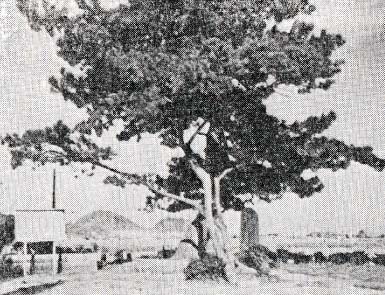
蛭が小島
|
すぐ宗清に対し頼朝を連れてくるようにということばがありました。
二人は今までまだ一度も顔を合わせていなかったのです。頼朝を初めて見た禅尼はしんみりとした気持で、
「本当に宗清のいった通り家盛そっくりの姿をしているね。
どこか都のほとりに住まわせておいて、家盛の身代りに、好きな時にはいつでも側に呼び寄せてみたい気がする。
それを、ぱるばると伊豆の国まで流すのはほんとにたまらないよ。
おまえを家盛だと思って、春や秋にぱ季節の着物を送り届けよう。
おまえも母だと思って、もし私が死んだら十分に弔っておくれ。
伊豆という国は、シカがたくさん住んでいる所で、いつもいつもシカ狩だ、何だ、彼だといって荒っぽい催しが多いが、うっかり誘いこまれてはいけないよ。
もしそんなことをして、流され人のくせに勝手な振舞をずるけしがらん奴だ、などと六波羅に訴えられてごらん。
それこそ今度は命ごいしたってもう追っつかないんだからね。」
「どうしてそんなわがままな振舞などするものですか。私は髪もきれいに剃り落して僧侶になり、心しずかに父の後生安楽を祈りたい気持でいっぱいなんです。」
「そりゃ感心な心がけだね。じゃ、早く旅立ちの支度をしなさい。」
と、まるで実の母のような情のあふれた禅尼のことばに、頼朝はただもう感激の涙にくれるばかりでした。
三月十一日の暁(あかつき)早く、頼朝は邸を出発しました。
頼朝が流されると聞き、延暦寺や三井寺の僧兵どもが大津の浜べに並んで見物しようとひしめいていました。
護衛の者に守られて街道を下っていく頼朝の心は、いつの日にか必ずや源氏の勢力を東国で盛り返し、堂々とこの湖畔の同じ道を京都に討入りするようなさっそうたる自分の姿を夢に描いているのでした。
その心の中が、おのずから表情にも現われていたらしく、見物の僧兵どもは、
「頼朝という男は、まだ子供なのにずば抜けてどっしりした体格を持ち、犯し難い気品も備えているなあ。
ああいう人間を、いくら田舎だからといっても伊豆の国に流しておいたら、どんなに大それた野心をおこすかもしれない。
まるでトラの子をひろびろとした野原に放してやるようなものだ。恐ろしいことさ。」
と、口々にうわさするのでした。
4 常盤(ときわ)の都落ち
top
これより先、六波羅当局では、義朝の男の子三人の消息は判明しました。
すなわち、義平は処刑ずみ、朝長は死亡、頼朝は生げ捕りにして監禁中というわけです。
ところが、義朝にはまだこのほかに男の子が三人あるはずだということで、探索の手がまわりました。
これを聞いたその母常盤(ときわ)は、
「私は義朝さまにお別れしてから、悲しくつらくてならなかったのだけれど、これら三人の男の子が義朝さまの忘れ形見だということをせめてもの楽しみに今日まで過ごしてきた。
それなのに、もしここで敵の手に奪われでもしたら、この私は片時も生きてはいられないだろう。
だからといって、身を寄せてかくまってもらえるようなたしかな親類もないし、赤の他人のだれが物ずきに親子四人をかくまってくれようか。
ああ、どうしたらいいんだろう。」
と泣き悲しみます。しかし、いくら泣いたとていい知恵も出ません。
そこで思いあまって、日ごろ信心している観音さまにおすがりしたら……と清水寺(きよみずでら)に参りました。
八つになる今若(いまわか)を前に歩かせ、六つの乙若(おとわか)の手を引き、まだ二つにしかならない牛若(うしわか)はふところにだいて、こっそりと家を立ち出るのでしたが、お供の者一人もなく、母子四人とぼとぼと夕やみにまぎれいく姿は、世にも哀れな図でした。
常盤は、夜もすがら観音さまの前にすわってお祈りを捧げ、わが身に代えても三人の子供の命ばかりはお助けくださいと熱心にお願いします。
やがてその夜も明けました。清水寺は、清盛の本拠六波羅のすぐ近くですから、長逗留(ながとうりゅう)はできません。 |

清水寺
|
お坊さんによくよくあとの祈願を頼みこんで、まだほの暗いうちに出かけます。
春とはいえ、寒さはなお去りやらず、雪はしんしんと降りつもります。
そんな夜明けの道を今若、乙若の二人ははだしのまま歩いていきます。
「寒いよう、お母さん。つめたいよう。」
と泣かれると、常盤は自分の着物をぬいで子供たちに着せかけてやり、自分が風上の方に立って冷たい風にあたらないようにかばってやります。
着ている着物を解いてはだを包んでやりながら常盤は言って聞かせます。
「ここをもう少し歩いていくと、棟門(むねもん)の立っている邸があるよ。
そこが敵清盛の邸なのだから、静かにおし。
声を出して泣いたりなんかすれば、捕まって殺されてしまうんだからね。
死ぬのがいやなら、泣くのはおやめ。」
言われて今若が、弟乙若に向かって
「泣かずにこらえようね。」と励ますいじらしさは、何ともけなげな限りでした。
せっかく包んだ足もすり切れて、血は赤く道を染め、雪と共に涙もほおに凍りつくつらさをしのぎしのぎして、ようやく京都の町を出はずれ、伏見に住む叔母の家にころがり込みました。
ところがどうでしょう。頼る叔母は居留守を使って、泊らせまいという魂胆です。
その昔、まだ義朝の羽振りのよかったころには、奥方様、奥方様とあがめ奉り、ちやほやしてくれたのに、今や朝敵の妻であり、その子てあるから、うっかり世話はすまい、もしかかわり合って六波羅に知れておとがめを受けでもしたら大変だと思ったのです。
本当に血も涙もない仕打ちです。
そうとは知らぬ常盤は、やさしいおばさんにすがってしばしの骨休めをしたいと思う一念から、今に帰るだろう、もう会えるだろうと帰りを待ち暮しますが、むろん帰ってこようはずもありません。
それに、叔母から言い含められている家の者は、だれひとりやさしくいたわってもくれません。
常盤はやむなく涙ながらにしおしおと雪の夕やみに歩き出しました。
日はとっぷり暮れてしまいました。見わたす限り一面の銀世界。道は次第に人里を遠ざかり、寒さはいよいよつのってきます。
一休みしようにも木蔭とてありません。それでもやっと一軒の小屋を見つけました。
近寄って今夜の宿を貸してほしいと頼みますと、中から主人が顔を出し、うさん臭そうにじろじろとながめまわしたあげく、こんなにくまれ口を利きます。
「今どき、こんな夜おそく小さい子供を連れてまようなんて、きっと朝敵のだれかの身内の者にちがいあるまい。
そんな者に宿を貸すなんて真平(まっぴら)ごめんだ。」
すげなく断わられて、とりつく島もなく、さりとてこの夜ふけの雪の中にさまよい出る勇気もありません。
しばし泣きむせんでいますと、見かねた主人の妻が、
「私どもは、どうせこんないやしい身分の者ですから、朝敵の方に同情したってまさか六波羅から叱られるなんてことはありますまい。 女は女同士ってことがあります。何、かまいやしませんよ。おはいんなさい。」
こう言って、こころよく迎え入れてくれました。
そして、あかあかと火を燃やして部屋を暖め、熱い食べ物をこしらえて、ありったけの着物を出して着せるなど、さまざまにいたわってくれますので、ようやく元気が出てきました。
その夜も明けました。常盤はねんごろに礼を述べて出かけようとします。
前夜きついことを言って門前払いをくわせようとした主人も、妻のやさしい心づかいに打たれたのでしょう。
常盤母子にすっかり同情する気持になってしまいました。主人は、いとけない子供たちがふびんでならず、
「もう一日だけ、お子さまたちに休ませてあげなさい。」と親切に申します。
ついほだされてその日も、あくる日も泊ってしまいました。
三日間厄介になると、母子そろってみながすっかり元気を取り戻しましたので、とうとう出かけることにきめました。
主人は馬の用意をして常盤を乗せ、子供たちは召使いの背に負わせて、木津(きづ)という所まで送っていきました。
こうしてあわれな母子四人の一行は大和の国(奈良県)の宇多郡(うだぐん)竜門村(りゅうもんむら)に住む叔父の所にたどりつき、ここに当分の間身を寄せることになりました。
5 常盤、都に帰る top
ここまで遠く逃げのびて、ほっと息つく瑕もなく、常盤の耳にはいやな都のうわさがきこえて来ました。
それは母が清盛の部下のため捕えられて、自分たち母子の居所を白状しろと毎日毎日ひどい目にあわされているというのです。
自分ゆえに六十の坂を越えた母親がつらい思いをたえ忍んでくれるのだと思うと矢もたてもたまりません。
どうせ今若たち三人は朝敵の子なんだから、いずれは木の根草の根を分けてでも捜し出されて殺されるに違いない。
おそかれ早かれそうなるのだったら、一日も早く自首して出て、罪もない母上の苦しみを除いてあげよう――こう決心して、京都に引返して参りました。
京都にもどるや、まずお仕えしている九条女院(近衛天皇の中宮)の所に暇ごいに出向きます。
「近ごろ姿を見せなかったが、どうしたのかね。」という九条女院のおたずねに答えて、
「実は大和の国の叔父の所に隠れていました。清盛公が今若たちをきびしくお捜しになっていますので、しばらくでも私の側にかくまっておくことができようかと思ったんです。
ところが、そのために母親が六波羅に召されてひどい目にあわされていると聞きましたので、もどって参りました。
どうか、私ども四人をすぐ六波羅に送って、母親を許してやってください。」
と申し出ますと、みなの者は
「普通ならば、もうすでに年老いた母親を犠牲にしてでも、行末春秋に富む幼い子供を何とかして助けたいと思うのが人情なのに、逆に子供は犠牲にして母親を助けようという心ざしは本当にめずらしい。
神さま、仏さまもきっと感心だとお感じになるに違いない。」
とふびんに思い、女院みずからいろいろのお召物を賜わり、子供たちにもそれぞれ立派な装束(しょうぞく)を着せて、きれいな車に乗せて出で立たせるのでした。
晴れの衣裳を着飾った四人は、これが御所の見訥めだと思うと、名ごり惜しさに涙はとめどなく出て参ります。
やがて車は六波羅に近づきますが、一歩ごとに死所に近寄る思いは、まさしく「屠所の羊」(としょのひつじ)のたとえそのままでした。
いよいよ六波羅に着きましたので、伊勢守景綱を通じて清盛に自首して出た心境を申し出ました。
「母は本より科(とが)なき身にて候へば、御免(おんゆる)し候べし。子供の命を助け給はんとも申し候はず。
一樹(いちじゅ)の下に住み、同じ流れを渡るも、この世一つの事ならず。
高きも卑(いや)しきも、親の子を思う習い、皆さこそ候へ。わらわこの子供を失いては、かいなき命、片時(へんじ)も堪(た)へてあるべしとも覚え候はねば、まづわらはを失わせ給いて後、子供をばともかくも御計(おんはか)らい候わば、この世の御情(おんなさけ)、後の世までの御利益、これに過ぎたるおんこと候はじ。
ながらえて夜昼嘆き悲しまんことも、罪深く覚え侍(はべ)る。」 |
「私の母親には、もともと何の罪もございませんから、どうかお許しくださいませ。
子供の命までお助けくださいなどと欲ばったことは申しません。
たまたまこの世で親と子の縁を結ぶのも実は前世からの深い因縁によるものでございまして、親が子を愛する気持には、身分が高かろうと低かろうと、何の違いもありません。
それで、もしこれらの子供を失いましたら、生きて何の楽しみもない私は、もはや少しの間だって生きてはいられそうにありませんから、いっそのこと、この私を真先に殺してください。
そして、そのあとで子供をどうにでも処分してくださいますならば、これにまさるうれしさはございますまい。
かりに私がお助けいただきましても、死んだ子のことばかり明け暮れ嘆き悲しんでいましては、かえって罪業(ざいごう)が重くなるかと存じます。」
常盤は、こういう間も泣きじゃくりながら、ことばはとぎれがちです。
見るに見かねた乙若は六つという幼さにも似あわず、
「お母さん、しっかりなさいよ。泣いてなんかいないで、はっきり申しあげるんですよ。」
とけなげな調子で母をたしなめますと、常盤はいよいよ涙にむせぶばかりでした。
これには、さすが気強そうに見えた清盛も、やはり人間です、にじみ出る涙をそっとふいて、さりげないようすをむりに作っています。
清盛でさえこんなですから、側にいる将兵もみなもらい泣きし、座にいたたまらずにこそこそと席をはずす者もたくさんありました。
ところで、常盤は、年二十三。天性の美貌に恵まれている上に、幼い時から九条院に宮仕えに出て人の応待にはよくなれていますし、物言いもはっきりしていました。
ただ、このごろの苦悩にやつれがにじみ出てはいますが、かえってそのうちしおれているようすがひときわの美を加えるのでした。
それも道理、九条院の父伊通(これみち)卿が絶世の美人を女院付の女房にしようと思って、千人もの数多い美人の中から選びに選びぬいた内裏一番の女性だったのです。
こんな常盤が泣きくずれるのですから、清盛もほろりとせずにぱいられません。
さてまず常盤の母をゆるすことにしました。ついで周囲の者の反対を押し切って、今若たち三人の義朝の遺児も、死罪どころか流罪にさえしないという、まことに寛大な処分ときまりました。
先に頼朝が危いところを殺されずにすんだのは、池禅尼の慈悲にあふれる愛情の勝利でありましたが、今また常盤の熱意がその母親とその子とを救い出すことができました。
「一念岩をも徹(とお)す」というたとえがありますが、その通り人間が命がけでまっしぐらにぶっつかる時、どこにも「不可能」という壁はありえませんでした。
6 源氏、再び興る top
こののち、常盤は六波羅に住みついて清盛に仕えることとなりました。
今若は醍醐寺で出家しましたが、なかなかの暴れん坊で、全済(ぜんさい)という号があるのに悪禅師とあだ名されるほどでした。
乙若も八条宮――後白河天皇の皇子――にお仕えする僧官となって円済と名のり、また末弟牛若は鞍馬寺にはいって遮那王(しゃなおう)と呼ばれることになりました。
かように母子四人は別れ別れの人生の道を歩むことになったわけですが、この遮那王こと牛若が源義経その人なのです。
遮那王は、兄二人があっさり出家したことを大変残念に思い、師匠がいくら出家しなさいと勧めても聞き入れずに、将来いつか平家を滅ぼして亡き父の仇討ちをなし遂げたいと固く決意していました。
そして、その日のために日夜学問に励み武芸を練り、とても人間わざとは思われないほどの修練を身につけました。
十六年の春、鞍馬寺信者の金商人吉次(きちじ)という男と知り合い、さらにこの吉次の連れ深栖重頼(ふかすのしげより)という武士にも近づきになることができました。
吉次は奥州の出身、重頼は下総(しもうさ、千葉県)の住人で、いずれも東国です。
しかも重頼は源氏の出であることがわかったので、遮那王は自分もまた義朝の遺児であることをはっきり打明けました。
そして一まず重頼の生国下総へ、ついで古次の出身地奥州に連れて下ってくれと頼みこみました。
三月三日の朝早く鞍馬山を抜け出して東国へのはるかな旅路に出で立つことになりました。
途中、都からそれほど遠くない近江の国(滋賀県)鏡の宿で、自分で勝手に元服して、源九郎(げんくろう)義経(よしつね)と名のりました。
街道をまっすぐ下って予定の通り重頼の生国下総に着き、ここに一年ほど身を寄せていましたが、武勇は人一倍すぐれていて、土地の人々の手を焼いている山賊強盗の類(たぐい)なんか平気でひっとらえるほどの剛胆ぶりです。
こんなことでは、六波羅にいつかはうわさが伝わるだろう、何とか考えなくては……というわけで、さらに遠く奥州に下ることにしました。
まず、伊豆にいる兄頼朝の所に出向いてあいさつし、その紹介で上野の国(群鳥県)に住む一人の尼をたずねることになりました。
この尼は、その昔、義朝と縁のあった女性なのです。
義経はここで、この尼の子佐藤三郎嗣信(つぐのぶ)、四郎忠信(ただのぶ)両人を家来につけてもらって、吉次(きちじ)の居所を訪れ、とうとう平泉(ひらいずみ)に着きました。
藤原秀衡(ひでひら)は大歓迎です。
何しろ、当時秀衡は奥州随一の勢力家でしたから、ここに身を寄せた義経は大船に乗ったように安全なものでした。
話かわって伊豆の頼朝です。
頼朝は配所に暮すこと二十一年。
治承(じしょう)四年(一一八〇)六月十七日に文覚上人(もんがくしょうにん)の勧めによって後白河上皇の院宣(いんぜん、上皇のお言葉)をいただき、和泉判官(いずみのほうがん)兼高(かねたか)を門出の血祭に討ち取って平家追討の旗印を高く掲げました。
東国はもともと源氏の本拠です。
それに二十年余にわたる長い間に、頼朝が植えつけた源氏再興の機運は関八州の隅々にまで行き渡っています。
ですから、またたく間に源氏の勢力は強大なものになりました。
急を聞いて京都から全済(ぜんせい、昔の今若)円済(えんさい、昔の乙若)が味方に馳せ参じますし、平泉からは義経が強兵百騎ばかりを打ち連れて上ってきました。
頼朝は、すでに十万騎の大軍をもって相模の国大庭野(おおばの)に陣を布いていましたが、ここに二十年の歳月を越えて義朝の遺児たちの劇的な対面が行われることになりました。
終始一貫復仇(ふっきゅう)の悲願を燃やし続けてきた兄弟の感動の深さはどれほどであったでしょうか。 |

源頼朝像
|
いよいよ源氏の進撃です。太平洋の潮風に幾十幾百旒(りゅう)の白旗を吹きなびかせて、箱根の険(けん)を越え、富士川の難所をわたり、一路都へ都へと攻め上るさっそうたる陣容がまぶたにうかぶではありませんか。
苦しみの果てに訪れたこのよろこびこそ何ものにも代えがたい男子の本懐(ほんかい)であったに違いありません。
top
****************************************
|