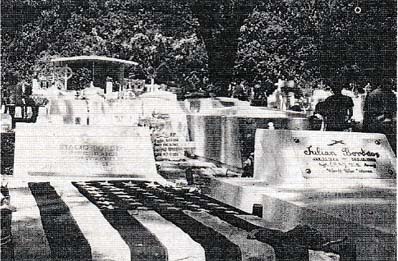|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章
一章 フィリピンへ
1 バタアンデー
一九七〇年四月九月
一を聞いて十を知る方法
輸入代替型から輸出指向型へ
「死の行進」
ある新聞記事から
2 保税加工区へ
KMとの出会い
ベトナム戦争とフィリピン
立ち退き
補完的生産 |
3 フィリピンでの出会い
ブイック・クレメンテ
レナト・コンスタンティーノ
民族的自覚
4 南池袋の部屋で
スリチャイ・フングーオ |
1 バタアン・デー top
一九七〇年四月九日
一九七〇年四月九日に、私はいくつか、視界が広がってくるような「基本的な体験」をしました。
基本的な体験というのは、待っていればワッと出てくるというようなものではないのでしょうけれども、偶然に起こってくるものです。
それはフィリピンのバタアン州における保税(輸出)加工区(1)についてでした。
(1)保税(輸出)加工区 区域内の工場の原料輸入、製品輸出を非課税とすることで外資導入をうながすために、途上国に設けられた工業団地、外貨獲得、技術移転、周辺産業の育成、雇用の剔出などで工業化の推進が期待されたが.安い労働力を求める先進工業国の下請け構造に組み込まれ、途上国どうしの競合も生じ、ねらい通りの効果を生んでいないケースが多い。
近年では、「輸出加工区」という呼称が使われている。
そのことは、『アジアを知るために』(筑摩晝履 一九八一年)にかなり細かいケーススタディーを書いています。
その最初のところでアジアを知る勉強法というようなことを述べています。
そこには、一つのところに目をとめると全体がわかってくるという、一種の典型(モデル)としての事例があります。 |

図1 フィリピン、ルソン島中央部
|
そして、それをずっと見つめていくと、世の中の仕組み、今日の言い方で言えば日本と東南アジアの経済のかかわり方とか工業化とか、あるいは最近のNICS、NIESというふうなものが生まれてくる過程がわかってくる。
一九七〇年の時点て、どういう勉強法があり得るか、単純に言えば、いまもたいして変わっていないと思います。
日本の新聞を読んでいればよくわかるとか、大学に来れば東南アジアのことがよくわかるとか、そういうシステムは、日本のなかにまだありません。
いまのほうがいくらか市民運動的な部分か広がり、いろいろなプリントその他が出ていますので、わかってくる部分がありますが、当時はそれもなかった。
当時は、たとえば東南アジア専門の本屋というのはありませんでした。
「一を聞いて十を知る方法」
『アジアを知るために』のなかで私は、アジアを知る認識法として「一を聞いて十を知る法」――典型を見ているとだんだんわかってくる、というふうなことをつぎのように書いています。
よく「アジアはどろどろして複雑で、全体をおさえるような共通項はない」といわれる。
それは確かにその通りだが、東南アジアと日本ないしアメリカとの関係のあり方には、かなりの共通項が見られる。
だからその一点を押さえて、深く追及すると、視界はみるみるうちに拡がって、日本と東南アジアの関係の全体が見えてくるようなことが起こる。
もちろん最初に押さえる一点が重要で、これは全体を象徴するような典型としての可能性を含んでいなければならない。
何か典型としての価値をもっているかは最初はわからない。
だからこそ、平常の一般的学習と経験によるカンが必要である。
これは重要だと思って調べてみても、いっこうに視界がはれてこない場合だって起こるのである。
先にあげたバタアン半島のマリベレスに出かけたのは、ここがそうした典型としての価値をもっていると思ったからだ。
東南アジア各国に保税加工区作りが盛んだが、それは台湾の高雄と韓国の馬山を先陣として、ほとんど同時期に始まっている。
それはなぜか。マリベレス保税加工区は、投資奨励法、輸出奨励法と連動して働くようになっている。
ASEAN(2)五か国の投資奨励法は、タイを別格として、いっせいにスタートしている。
それはなぜか。この時期はベトナム戦争が最高潮に達し走時期だが、それとこれとは関係があるのか、ないのか。
マリベレス保税加工区の進出企業のうち最大手はフォードの車体工場であるが、これはマルコス政府(3)の進歩的自動車生産計画(4)に組みこまれ、同時に、ASEANの相互補完生産計画とも連動している。
(2)ASEAN東南アジア諸国連合(Assosiation of South-East Asian Nation)。一九六七年にインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの五か国によって設立された地域協力機構。現在は、上記五か国に、ブルネイ、ベトナムが加わっている。
(3)マルコス(Ferdinand E. Marcos(1917−89)フィリビン共和国第六代大統領。一九六五年就任、六九年再選ののち、憲法では三選が禁じられていたにもかかわらず。
戒厳令下の七四年、「新憲法」を発効させ、独裁体制を完成したが、長期政権、政治の腐敗、経済の悪化などから国民の不満が募り、八六年、軍部も離反して国外脱出にいたった。
マルコス政権の重要政策であった外資導入による工業化政策の具体化の一つが、保税(輸出)加工区設置であった。
(4)進歩的自動車生産計画 その後、「漸進的自動車国産化計画(PCMP)」という訳があてられるようになった。
とすると他の東南アジア各国の自動車生産計画はどうなっているのか。
また、日本の自動車産業は、こうした地域全体の計画の中でどう動こうとしているのか。
マリベレスは「死の行進」(後述)の原点だったが、その米比連合軍降伏の日、四月九日は、フィリピンでは「バタアン・デー」という国民的記念日である。
なぜ侵略者に降伏した日が国民的記念日になるのか。
同じような日としてシンガポール陥落の日の二月一五日があるが、それとこれとはどうちがうのか。
また日本の敗戦記念日八月一五日とは歴史の意味づけの仕方が似ているのかどうか。
記念日としては、フィリピン独立記念日の六月一二日があるが、それはどういう日なのか。
六月一二日を独立記念日と定めるのは「当時」先代大統領のマカパガル(5)の時代、一九六二年だが、それまでは七月四日が独立記念日だった。
22-16
なぜ独立記念日をわざわざ変えたのか。一体マカパガルは何を考えたのか。
七月四日といえば、アメリカの独立記念日だが、なぜアメリカとフィリピンは同じ独立記念日をもっているのか。
(5)マカパガル(Diosdado Macapagal,1210-) 1961年から65年までフィリピン共和国第五代大統領。彼の進めた経済自由化政策はフィリピン国内のアメリカ企業を利することに主眼があり、フィリピンの民族系資本は打撃を受け、国民の生活もインフレで苦しくなっていった。 |
このように、一つのことを集中して見ていくと問題はどんどん広がって見えてきて、疑問符の矢をあちこちに投げることができます。
輸入代替型から輸出指向型ヘ
マリベレスというのはバタアン半島の突端にある村で、現在そこに大きな工業団地ができています。
これがいま続いている工業化の流れの、一番初期の大きな受入れ母体です。
今日も続いている第三世界の工業化というのは、戦略によりおおよそ二つの時期にわかれます。
最初は、自分の国のなかを市場にして工業化をしようという戦略、これは「輸入代替型」の工業化と言われています。
フィリピンは一番典型的な例です。
フィリピンが輸入していたのは電球や、もっと基本的なものではマッチです。
そういうものは国外でたくさんつくられています。それを何とかして国内で自力でつくるようにしようというのが輸入代替型です。
それは一九六〇年代に始まりますが、六〇年代の半ば過ぎにはあちこちで破綻します。
なぜかというと、二つ理由があります。
一つは、他の国でマスプロでたくさんつくっているものを買ってきたほうが、ずっと安いからです。
たとえばフィリピンの中ですと、当時の人口が三〇〇〇万ぐらいですから、非常に市場の規模が小さい。
私が自動車のことを調べ始めた一九七〇年代には、フィリピンの自動車のマーケットの規模は二万合ぐらいでした。
ですから二万台のマーケットに向かって自動車つくるのと、あの当時、日本の国内市場は五〇〇万台か七〇〇万台だと思いますけれども、それでつくったものとでは規模が違います。
日本のほうがずっと安くできる。
それから、何かをつくろうとすると、資本財、つまり工場の機械を入れなければいけない。
結局、国外から買ってくるわけですから、代金は払わなければいけません。
そのためには、かなり売って利益をあげなくてはならない。
しかし、三〇〇〇万の人口のところに対して売っていたのでは十分な利益があがらないということで、失敗するわけです。
国によって違いますけれども、一九六〇年代後半になって出てくるのが「輸出指向型」です。
これが、いまも続いている型なのです。
はっきり言えば、三〇〇〇万のフィリピンのマーケットに対して何かをつくって売るということではなくて、フィリピンでつくったものを輸出する。
日本と同じ形ですけれども、その受入れ母体といいますか、工業団地として、先ほど述べたマリベレスの保税加工区ができてきます。
|

「死の行進」の出発点(マリペレス、1975年、以下筆者撮影)
|

マリベレスの村(一九七三年)
|
「死の行進」
バタアン半島は日本軍が攻め入ったときの、最初の激戦地でした。
「死の行進」の出発地点になったので、マリベレスの保税加工区の目の前の小さな公園には、銃剣の上にヘルメッ卜をのせた記念碑があります(左図)。
数万の兵士がそこから――そこだけではないのですが――北へ向かってマニラ湾の奥まで歩かされました。
日本軍は一九四二年一月二日に、首都マニラに無血入城したのですが、マッカーサー(6)が指揮していた米比連合軍は全部、バタアン半島一帯に籠城している。
すぐ追いかけてそこへ入っていき、一月のごく初めから四月九日までに、バタアン半島にいた兵土たちを降伏させます。
その時、山の中からどんどん人が出てきますが、日本軍は、これを運ぶ手段がありません。
日本軍も精いっぱい戦っているわけですから。それで、歩かせたのです。
フィリピンにあるアメリカの基地(7)には、二つ大きなものがあって、一つはクラーク基地でもう一つがスーピック基地です。
(6) マッカーサー(Douglas Mac-Arthur,188o-1964) 太平洋戦争開戦時の駐比アメリカ極東軍司令官。のちに、西南太平洋連合国軍総司令官となり、日本の降伏後は連合国軍最高司令官として日本占領の最高責仔者に任ぜられた。フィリピン戦線では、バタアンの敗戦でいったん退却したものの、レイテ島に再上陸し連合国軍を勝利に導いた。
(7)アメリカの基地 フィリピン独立(注10参照)の翌一九四七年。アメリカ軍の援助を約した「軍事援助協定」とセッ卜で調印された「軍事基地協定」は、フィリピン国内二三の基地を米軍が九九年間使用(のちに一九九一年までとするよう改正)できるとし、さらに五一年には「相互防衛条約」も結ばれ、アメリカの防共戦略の重要な一環を担わされることになった。
その後、国際情勢の変化でしだいに縮小傾向にあったが、九一年の協定期限切れの前年にフィリピン上院は期限延長拒否を決議し、撤廃が実現した。
スーピックは極東艦隊、第七艦隊の基地で、クラークは空軍基地です。
そのクラークの先に捕虜収容所が設営されていたので、収容所へ向かう鉄道の始点までの約一〇〇キロを歩かせた。日本軍も歩きました。
一月から四月まで三か月間の激しい戦闘のあとですから、歩いている間にマラリヤとか赤痢でバタバタと倒れて死んでいく。これが「死の行進」です。
「死の行進」について、私たち日本人は、戦争中ですから海外との連絡は絶たれているので知りませんでしたが、連合軍はそれを日本の残虐行為として世界中に宣伝していました。
南京の虐殺とか、最後にはフィリピンで絞首刑になる山下奉文がマレー半島からシンガポールを占領したときにシンガポールで起こした華人の虐殺、これらは明らかに日本軍による、自覚的な虐殺行為です。
だけれども「死の行進」というのは少し違った。やむなく歩かせて、それで死なせたということです。
ある新聞記事から
私が一九七〇年「四月九日」をなぜ記憶しているかというと、つぎのようなことがあったからです。
その月、マニラで「アジアは一つ」国際会議というジャーナリストの会議が開かれました。
私は新聞記者ではありませんが、日本の代表団の一員として出席しました。
アジアは一つではないにもかかわらず、「アジアは一つ」という名前で会議が開かれたのです。
日本の新聞記者は、日本の大企業と同じように、どちらかというと西洋に向いていてアジアを蔑視していますから、マニラで開かれる新聞記者の国際会議というものにはあまり関心を示さない。
私はしかたなく、朝日、毎日、読売各紙の主だった方々を訪ねて、ぜひ代表団を出そうではありませんかという話をしました。 |

「アジアは一つ」国際会議(一九七〇年)
|
結局出すことになって、私はフリージャーナリストとして、その一員にもぐり込みました。
いまは東京とマニラとか、東京とバンコックとかを、往復の飛行機がいっぱい飛んでいて、ほとんど満員です。
一九七〇年ごろは、ヨーロッパから出た飛行機が南回りで東京へ来ていました。
当時、ヨーロッパまで行くには、アラスカ経由の北回りで行ったほうがずっと速く、南回りはガラガラに空いていました。
それが混むようになったのは、七〇年代の終わりぐらいです。
アジアに日本の経済が入っていくようになってから混むようになり、アジア各国と東京間の往復便がたくさん飛ぶようになった。
私は日本の代表団の一員として、マニラ経由で飛んできたスカンジナビア航空に乗りました。
座席に着くと、その後マルコス大統領の戒厳令(8)で潰されてしまう『マニラ・クロニクル』と『マニラ・タイムズ』の二紙が配られた。
(8)戒厳令 マルコス大統領(当時)は、国内の治安回復を名目に一九七二年九月二一日、戒厳令を発布した。これにより農地改革や外資導入などがある程度押し進められたが、真のねらいはライバル政治家の追い落としと権力の保持にあったとみられている。
あとチョコレートをもらいました。
ガラガラの機内でチョコレートをかじりながら、その二紙を読んだら、大きな紙面の四分の一ぐらいに、「バタアン・デー」という記事がある。
私は大正一五(一九二六)年の生まれで戦中派ですから、戦争中の記憶がかなりあるほうです。
ですからバタアンというのはわかりましたが、バタアン・デーというのはわがらなかった。
新聞を読んでみますと、それはそこで戦っていた米比連合軍が降伏した日なのです。
それは。こういう記事です。
「かつてアメリカとフィリピンとが協力して日本の軍国主義と戦った。
そこが現在、いまやフィリピンの工業化の最先端の基地に生まれかわろうとしている」
つまりマリベレスに大きな工業団地がつくられようとしていることが書かれていた。
それで私はハッと思いました。
|

“バタアン・デー”のポスター(1973年)
|

バタアン保税(輸出)加工区用地からの出口(一九七三年)
|
私は「バタアン」という言葉は憶えていたけれども、“タアン・デー”ということはわからなかった。
侵略した国家に属している私のほうは忘れ、侵略されたほうは覚えている。そういう忘れる構造と覚えている構造がある。
それで、バタアン半島に行かなければいけない、行ってみたいへという気が起こってきました。
そういう意味で、日本とフィリピンとの関係、特にバタアンでは米比連合軍と日本とが戦っていますから、日本とアメリカとフィリピンという三国の関係ぺ頭のなかに入ってきます。
ちょうどこの時期が、先ほど述べた、輸入代替型の工業化から輸出指向型の工業化へ転換するという時期にあたっています。
最初にマリベレスを訪問したのは一九七二年八月の末です。この時期もはっきり覚えています。
一九七二年というのは、フィリピンでは非常に雨が多かった年で、マニラの大半は洪水でした。
水が引くのを待って、マリベレスの保税加工区へ行きました。
2 保税加工区へ top
KMとの出会い
友人を通じて、一人案内を頼みました。
その年の九月二一日にマルコス大統領が戒厳令を発布しますが、当時は、市民運動をふくめてフィリピンでは非常に革命的な運動が高まっていた時期です。
カバタアン・マカバヤン(KM)といっていたフィリピン共産党(9)系の青年組織があって、名前を訳すと「愛国青年同盟」です。
(9)フィリピン共産党 フィリピンの共産党は、はじめアメリカの支配下にあった一九三〇年、国際共産主義運動の流れのなかで労働者と農民の勢力を基盤に生まれたが、五七年に非合法化され低迷した。
しかし、アメリカのベトナム戦争介入にとも なう反米闘争の盛り上がりのなかで、六八年、毛沢東思想にもとづく武装路線を打ち出して、再建された。そのときの指導者が、アマド・ゲレロ(ホセ・マリア・シソン)である。
これは全国に拠点を持っており、その学生活動家の一人が案内をしてくれることになった。
それでどこへ行ったかというと、最初はクラーク基地のあるアンヘレス市です。マニラからバスで行きます。
そこでは、KMのメンバーが洪水につかった村々に対してお米を配るというような活動をやっている。
その事務所では、たまたま五、六人がゲームをやっていました。
モノポリーというゲームです。「モノポリー」は独占という意味です。
これは一種の双六みたいなゲームで、サイコロを使って自分の札を動かしていって、自分か最初に止まった場所をお金を出して賈います。
買うと、そこに権利が生じて、あとがらそこに入った人は地代を払わなければいけない。
そこにホテルを建てると、そのホテル代も払わなければいけないということで、やがて誰か破産します。
そういうきわめて資本主義的なゲームを、共産党シンパとおぼしき若い人たちがやっている。
そのすぐ隣の部屋では村人に対して革命論についての講習会が開かれていました。
アマド・ゲレロの『フィリピン社会と革命』(邦訳、北沢正雄訳、亜紀書房、一九七七年)という本が使われていました。
毛沢東思想にもとずいて書かれた革命論なのです。
そこで案内役がかわり、またバスに乗って同じ道をしばらく下っていく。
マニラヘの道とわかれて南西に下ってリマイといういまは石油基地がある町で、また案内役が交代する。
それで最後にマリベレスに入るわけです。
この郷土主義の問題は、東南アジアのことを考えるとき、大変重要なことです。
つまり、いっぺんには目的地に行きつけません。
ここの人はここと連絡があって、ここの人がここまでついてきて、ここでまた案内人がかわるというふうに、地方ごとに生きている。
ベトナム戦争とフィリピン
土砂降りの雨で、途中バスが通れないようなところもあって小舟に乗り換えたりしながら、マリベレスヘたどり着きました。
そうしたら保税加工区の工事が、わずかながら始まっていた。
バタアン半島は山間部から急斜面になっていて、二又に海になるわけですが、その斜面を掘り崩している。
土砂降りの雨のなかですから、工事は止まっているのです。
大きなパワーショベルや機材が丘の斜面に置きっぱなしになっている。
そのパワーショベルなどは、フィリピン政府軍工兵隊のものです。
日本でもベトナム戦争中に外務大臣は、「日本はベトナム戦争について中立ではない。
はっきり言えばアメリカの側についている」というふうに言いました。
日本は平和憲法がありますから出兵はしませんが、出兵した国もあります。
韓国もそうですし、ニュージーランドもそうですし、フィリピンも名目的に工兵隊を送った。
ただ、フィリビンのなかでは当時、ナショナリスタ党とリサフル党という二つの政党が対立し、一方にかなりナショナリズムの空気がありました。
そして、フィリピンがベトナム人民の解放の闘争に対して軍隊を送るとはなにごとか、という批判が非常に高まって、工兵隊を引き上げます。
その工兵隊により保税加工区がつくられていたのです。
工業団地の予定地には、まだ村がありました。
植民地時代(10)、アメリカは、バタアン半島のかなり広い地域を長年軍事基地用地として――ミリタリー・リザーブだと言っていました――全部自分で持っていました。
(10)アメリカの植民地時代 一八九八年、スペインによる三三四年間の植民地支配が終わったものの、新たな支配者としてアメリカが現われ、形式的とはいえフィリピンが独立を果たすのは四八年後の一九四六年のことである。
この間も、「独立」後も、アメリカに対する抵抗運動。反対運動が各地で起こったが、アメリカは一方で「民主主義」を標榜しながら、一方で軍事力を背景にした強硬な態度をとり続けた。
第二次世界大戦が終わると、戦略が変わります。
つまり、かつての植民地をアメリカの手で直接守る必要はほとんどなくなってくる。
それから戦略体制も、スペインとアメリカとが戦争をしてフィリピンがアメリカのものになるというようへ植民地宗主国どうしの植民地分割というふうなことはない。
かわりに、社会主義対資本主義の国という状況になってきた。ですからバタアン半島は、アメリカにとっては要らない土地になってしまう。
それでもしばらく持っていて、六〇年代になってょうやく返します。
この地域一帯はアメリカが持っていた海軍基地としてかなり重要なところで、マリベレスの沖合のコレヒドール島には完全なトンネルの要塞が築かれていました。
立ち退き
マリベレスには、アメリカがもう要らないと言っている、アメリカ海軍の軍艦修理工場があった。
小さな町工場ぐらいの鉄工所です。
この町工場に働く人が、あちこちから移ってきて村ができた。 だからそこは、マリベレスの工場で働く人の村と、元々住んでいた人の漁村とが隣あわせになっていました。
そして漁村のほうが取られてしまって、保税加工区の工業団地になろうとしていました。
鉄工所で働いている移民のほうの村の村長さんの家で雨宿りをしたら、「ここもいずれは取られるんだ」、つまり、立ち退かなければいけない、と言うのです。
その時私は、三里塚(11)の話をしました。
成田で農民の土地が取られようとしている。
(11)三里塚 一九六六年、住民に何の相談もなく、新東京国際(成田)空港建設予定地は千葉県成田市三里塚地区とその周辺地域とする、と閣議で決定された.この決定と、その後の政府の対応に納得できなかった農民は、長期にわたる激しい反対運動を展開して、政府の強権的で非民主的な施策の不当性を訴え続けた。
|

立ち退きを迫られた村の子どもたち(1973年)
|
成田も実はよそから入ってきた移民――移民というのは変ですけれども――が土地を開拓して農村をつくり始めた。
それがいまや飛行場になって、立ち退きを迫られているという話です。
それから約三週間して九月二一日に、「マーシャル・ロー」、つまり戒厳令が発布されます。
私はKMの人とつきあっていたので、少し危ないと思い、一年間ぐらいフィリピンに足を入れるのを遠慮して、結局七四年から再び出かけ、何回も訪ねて滞在もするようになりました。
補完的生産
この保税加工区の一番大きな入居者はフォードでした(その後、撤退)。
先ほど輸入代替型から輸出指向型にというふうに述べましたべその転換が始まっていました。
自動車にかんして、それまでフィリピンでは一一社ぐらいありましたが、一社の年間の生産台数は二〇〇〇台くらいの規模でした。
二〇〇〇台というと一二か月で割ってみても非常にわずかな数です。
これはとてもマスプロ(大量生産)には合わないので、もう少し集約化しよう、ということで、「漸進的自動車国産化計画」というのが一九七二年の終わりごろ始まって、五社に統一される。
その時に出てきたのが「補完的生産」という形です。この言葉はいまはあまり使われませんが、現在も実質的には行われています。
補完的生産というのは、フィリピンで一台の車を末端の部品から全部をつくるということではなくて、フィリピンでシャーシをつくればエンジンは台湾でつくるという形で、補いあうことです。
フォードはフィリピンで車体をつくって、エンジンは韓国と台湾でつくる。それで全体をまとめて一つの車にする。
つまり、フォードは年間で七万台ぐらいの車体をつくりましたけれども、そのうちフィリピン国内にまわるのはせいぜい数千台です。
六万何千台はニュージーランド、オーストラリアを経て、はるばるロンドンなどに輸出される。
エンジンは台湾で七万台分つくって、台湾の国内の分だけ差し引いた分が輸出される。
そういうのが補完的自動車生産です。
3 フィリピンでの出会い top
ヴィック・クレメンテ
一九七〇年四月というのには、もう一つ意味があります。
私は日本の新聞記者代表団の一員として行っていましたから、いまでも最高級になっているホテルに泊まっていました。
そこで、KMの議長に会いました。
議長に私のほうから会いたいと申し込んだ理由は、一つだけでした。一九六五年にアメリカの北爆が始まってすぐにベトナム反戦運動が日本で起こります。
そのなかで六七年に「イントレピッドの四人」(12)といわれたアメリカの脱走兵が日本に現れます。
(12)イントレピッドの四人 一九六七年一〇月、北爆に参加したアメリカの航空母艦イントレピッド号の乗組員であった四人の米兵が脱走して「べ平連」に支援を求めてきた。
この四人を無事スウェーデンへ送り込んだ「べ平連」は、「イントレビッド四人の会」「ジャテック(反戦脱走米兵援助日本技術委員会)」を組織して、四人に続くその後の脱走米兵への支援体勢を整えた。
全く偶然ですが、べ平連に保護を求めて来たので、私たちはそれを匿(かくま)って、最終的にはヨーロッパヘ逃がします。
日本の内部にあるアメリカの基地とフィリピンにあるアメリカの基地とは、基本的にかわりはありません。
アメリカ軍である以上、必ずアメリカ軍事文化というものを共有している。
だから、日本の基地で米軍の脱走兵が出るのだったら、フィリピンにおけるアメリカの基地だって脱走兵が出るはずで、そういう可能性はないのか。
それに対する支援の体制は組めないのか。ということで、KMの議長であったヴィック・クレメンテという男に会った。
かれも忙しくて、私も忙しいから、別にひと目を避けるということではありませんが、真夜中に私のホテルへ友たちと二、三人で来て、一緒に酒を飲みながら話をしました。
彼の答えが面白かったのです。
「フィリピンは、充分にアメリカに痛めつげられていて、アメリカに対する憎しみが非常に強いから、いかに脱走兵といえども、アメリカの兵士を助ける気はない」
ただしあとになって実感として感じたのですが、どうもそういうふうにはフィリピン人一般がアメリカに対して憎しみをもっているとは考えられない。
というのは、四月九日のバタアン・デーではいまでもお祭りが行われます。
お祭りでは仮装行列も行われ、フィリピンをアメリカの一州にしたいというような人も参加しています。
また、フィリピンで日本のお盆に当たる日は十一月一日です。
これはフィリピン群島全部に蝋燭(ろうそく)の煙が漂うというくらいの日で、みんな一週間ぐらい前から行って一生懸命お墓を磨いて、当日にはお墓のまわりで御馳走を食べるという大切な日です。
その十一月一日に私はマリベレスにいたことがあります。
漁村のすぐ裏の山手に墓地があり、いくつかのお墓は一九四二年四月九日までに戦死した人たちのもので、遺族がそこへ行っています。
そして、お墓をおおうように星条旗がかけてある。
まだ米比連合軍ということについての、ある種の思い入れがあるのでしょう。
フィリピンの人が全体としてアメリカ人に対して憎しみをもっているというヴィックの考え方は、きわめてイデオロギー的な、観念的な観察であるというふうに後になって思いました。 |
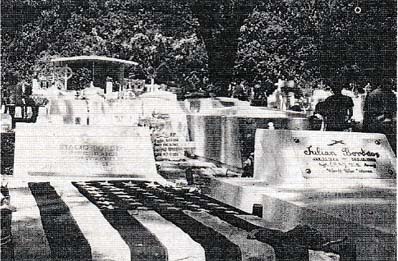
「お墓をおおうように星条旗が……」(マリベレス、一九七三年十一月)
|
とにかく、フィリピン群島のなかでアメリカ軍の脱走兵を支援するような運動を組織できないかという私の申し入れに対しては、ノーと言った。
つぎに彼は、私に対して申し入れを二つしました。
一つは、アマド・ゲレロの著作を日本で印刷できないか、というものでした。
日本で印刷してフィリピンに送ってもらいたいというのに対して、私はノーと言った。
つまり、印刷するのは簡単だけれども私たちはオープンな市民運動ですから、当時のフィリピンでおおっぴらには刊行が認められていなかった著作を、日本で印刷してフィリピンに運ぶというようなことはできません。
もう一つは、フィリピンヘ日本から武器を送れたいか、というものです。これはますますノーです。
私たちは平和運動をやっているのであって、武器を送る運動をやっているのではありませんので。
ですから互い違いになってしまいました。
レナト・コンスタンティーノ
それが一九七〇年の四月一二日です。夜中でしたけれども、飯が食いたいというので、外へ行きました。
その時、彼にきいたのです。フィリピンのいまの若い人たちが、詩人でも作家でも誰でもいいが、一番尊敬して読んでいる著者は誰だ、と。
彼はテーブルの上にあったナプキンに、レナト・コンスタンティーノという名前を書いてくれた。
それで私は、レナト・コンスタンティーノの著作をそのあと一生懸命読み始めました。
その当時はレナト・コンスタンティーノとつきあいはありませんでしたが、それから二、三年して親しくつきあうようになりました。
レナト・コンスタンティーノからは非常に大きな影響を受けました。
レナト・コッスタンティーノの翻訳は全部で六冊出ています。二冊は論文集で『フィリピン・ナショナリズム論」(上下、井村文化事業社)、それから『フィリピン民衆の歴史』(全四巻、同上)です。
民族的自覚
私が強く影響を受けたのは、『フィリピン・ナショナリズム論』の下巻に入っている「民族的自覚の問題」という論文です。
そこでは、こういうことが書かれています。
フィリピン人であるという民族的自覚――彼はネーションフッド(nationhood)という言葉をつかっていますが――は未完成の発展的概念である、というものです。
この文章から二つの示唆を私は受けることになります。
一つは、私たちのネーションフッド、私たちの日本人としての自覚というのは一体どういうものなのかということ。
私たちは、自分たちが日本人であるということについての自覚をあまり強く意識しません。
意識しないというより、あまりにも自明であって、それが発展的概念であるとはとうてい考えられない。
発展的概念というのは、これから変えられる、変わっていくということで、そういうふうには私たちは考えない。
そういう意味では、フィリピンと日本とはずいぶん違う。
主観的に言えば、日本人であるということを変えられるとすれば、これほど素晴らしいことはないなと、私は思いました。
いまのは日本の私たち自身についての考えですが、もう一つは、東南でジアの諸国民というのは、民族的自覚が、国民という形でのまとまりとしては「未完の状態」である、ということです。
未完の状態ということを、私は蔑(さげすみ)として、あるいは遅れているという意味で述べているのではありません。
そういった強力な国家を形成しなくても暮らしていけるような社会がこの地球の上にはある。
それならそれでいいではないか、と思っています。
ここで言っているようなことは、かなりの国においてあてはまることです。
たまたま残念なことに――残念なことにというのは私の考え方ですが――植民地にされた社会が独立解放の結果、国家の位置を獲得したことに対して、やや極端な見方ですが、国家にされてしまったというふうに見ることができます。
つまり、欧米列強による植民地的分割や支配が国家の名において行われたために、植民地もまた国家にならざるを得なかった。
こういう、ある意味から言ったら歴史的な逆説があるわけですが、逆説への対応というものは、国家の位置を獲得した側――独立したフィリピンとかインドネシア――では、充分に自覚的に準備がされていなかったと考えられます。
その結果として、第三世界の諸国家では、しばしば分離独立運動が起こる。フィリピンにおけるモロ民族解放戦線もそうです。
ミンダナオでは一九七二年から七六年まで内戦(13)があった。
(13)ミンダナオでは一九七二年から七六年まで内戦 一九六〇年代の急激なクリスチャン・フィリピーノ(三章注6参照)の流入にともない、ミンダナオ島では宗教対立を背景に経済的、政治的利害がからみ、殺傷事件をともなう衝突が頻発していた。
七二年末、ミンダナオ、スルーの分離独立を主張してヌール・ミスワリらがMNLF(モロ民族解放戦線)を結成して、ミンダナオ島南部から西部は内戦状態に突入した。七六年、トリポリ協定で一時的な休戦状態となったが、最終的な解決にはいたっていない(鶴見良行「フィリピンの難民Iミンダナオの内戦を中心として」、国連大学・劍価大学アジア研究所共編『難民問題の学際的研究』御茶の水書房、一九八六年。参照)。
「モロ」は、もともとスペイン人がイスラム教徒に対して用いた呼称であるが、今日では、フィリピンのイスラム教徒の総称として使われている。
インドネシアでもあちこちに分離独立運動が現在でも蠢(うごめ)いていて、それが強権的な法律でおさえられています。
それからまた、こうした分離独立運動をおさえて工業化を進めるために、「開発独裁」というシステムが出てくる。
開発独裁というのは。工業化の開発を進めていくためには独裁が必要なんだという形で独裁が進むことをいう。
これは私たちの周辺にたくさんあります。現在の中国だって開発独裁的な形と言えます。
つまり、国家をつくったとき、あるいは、「国家」という資格を引き受けたときに生じる問題に、独立した側が充分に対応していなかった、考えていなかったということに思い至るわけです。
レナト・コンスタンティーノがフィリピンのネーションフッドは未完の状態と言ったのは、このような問題まで含めて考えていたのです。
こうして、私は東南アジアのことを考え始め、東南アジアと日本との関係を考え始め、東南アジアにおけるいま述べたような工業化の問題を、ずっと観察し続けることになります。
ですから、一九七〇年の「四月九日」というのは、私にとっては、自分の目を開かせてくれるような基本的な体験という気がするわけです。
もちろんその前に、私は一九六五年にベトナムで銃殺された兵士を眼前にしていますが、一九七〇年四月の私の体験からも、いろいろな脈絡で、思考が流れ出てきたのです。
4 南池袋の部屋で スリチャイ・ワングーオ top
タノーム独裁政権に嫌気がさしていた私は日本の文部省奨学生試験を受け、一九七一年に日本の土を踏んだ。
戦後日本社会の変化というありきたりなテーマで正式に東大の研究生になったときは、一九七三年になっていた。
その開タイでは日貨排斥運動が盛り上がり、私はタイ人として日本人に意見を求めたが、それに応えてくれる人は教官、学生ともほんのわずかだったことに驚いたのを憶えている。
その一捩りの学生や韓国人研究生らとグループを作り、論議に明け暮れるようになった。
やがて日本とアジアの政治状況を民衆側の視点で知らせる英文雑誌『AMPO』の存在を知って、バックナンバーを読みたくなり、当時は赤坂にあった発行元のアジア太平洋資料センターをたずねた。
鶴見良行さんに最初に会ったのは、そこだったと思う。掘削に水爆を使う可能性のあったタイのクラ地峡運河計画のことを『AMPO』に大変詳しく書いているケン・オハラという人物がいたのだが、それが彼のペンネームであることを知った。
鶴見さんの足で集めたアジアの知識には舌を巻くものがあり、彼が呼びかけていたアジア勉強会に参加していた同世代の若者たちとも親しくなった。
南池袋の彼の自宅での集いにも、ときどき顔を出した。
狭い迷路のような部屋で、アジアへの日本の経済進出などが話されたと記憶している。
鶴見さんはどうやって情報を得たらよいかの方法については、いっさい語らなかった。
しかし、日本人はアジアのことをもっともっと知るべきだということだけをさかんに強調した。
がれ自身が独立を指向する人間だったので、その群れの中心に立とうとすることもなかった。
誰もが自由に発言していたあの部屋の雰囲気は、タイ珸でいうサバーイ(心地よい)そのものだったと思う。
そのうちに、彼らを具体的に頼らざるを得ない事態が起きた。
一九七三年一〇月四日、タイの学生革命である。タイ人留学生が集まって死者の追悼デモをしようということになった。
だが、どうやってデモの許可を申請すればいいのかなどが、外国人の私たちにはわからない。
それを教えてくれたのが、鶴見さんと南池袋に集っていた若者たちだった。
一九七五年ころから、私はディン・ナードーン(田の盛り土)というペンネームで『AMPO』にタイの農民運動指導者虐殺事件などの記事を書くようになった。
しかし、体を動かすよりは本を読んで考えているほうが好きなところは変わらなかった。
そんなおり鶴見さんが、「できるだけ自分の目で見たほうがいい」と、私にあるスタディ・ツアーヘの参加を勧めた。
宇井純氏らが企画したそのディスカバー・ポリューテッド・ジャパン・ツアーに参加して、私は目から鱗(うろこ)が落ちた思いだった。
長年の環境汚染に対して日本政府が何の対策も打ってこなかった足尾銅山の惨状をこの目で見てから、それまで自分の中にまだほんのりと残っていた日本的な近代化へのあこがれを再考せざるを得なくなったからである。 |
top
**************************************** |