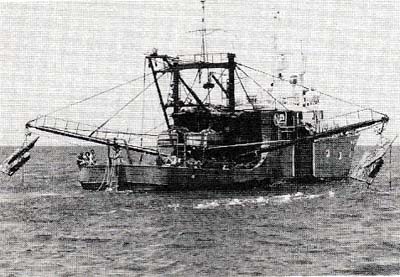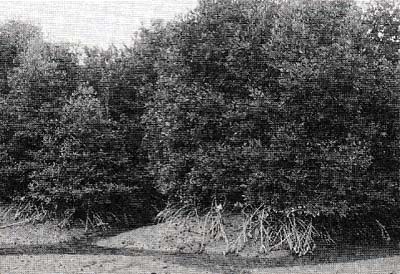|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章
三章 バナナとマングローブ
1 “アジア塾” top
|

バナナ農園。労働者の仕事の場であり、生活の場である(一九七八年)
高度消費社会
『バナナと日本人』(岩波書店、一九八二年)は、一九七〇年から八〇年代にかけての仕事です。
それから二年ぐらいおいて、『マングローブの沼地で』(朝日新聞社、一九八四年)を書いています。
七〇年代の末から八〇年代にかけての、時代の気分、時代の特徴が、どんなものだったかというと、高度経済成長を終えて、いちおうの安定期に入って、石油ショックもなんとか乗り越えた、というものでした。 |

袋をかけられたバナナ(ダバオ近郊、1978年12月)
|
当時、「機関車論」――アメリカと西ドイツと日本が世界経済を引っぱっていかなければいけないというような議論――があり、そういう形で、なんとか乗り越えたのです。 そして西ドイツと並んで、日本は世界経済のなかで非常に大きな重みを占めるようになってきていました。
同時に、経済安定期に入って、市民運動のほう丸ある種の停滞期に入ってきました。
「高度経済成長」から「高度消費社会」へ、です。
私が、その頃何を考えたかというと、日本経済は、なりゆきに任せて無自覚に東南アジアにのめり込んでいっているけれども、それに対する批判的な研究は、既存の体制のなかからはうまく出てきていない、ということでした。
既存の学制というのは、学校とか書物とかのことです。
この学校に入れば、東南アジアのことがわかる、というものがないわけです。
それから、この本を読めば東南アジアのことがわかるというふうな本丸その当時はなかったし、たぶん、いまもないと思います。
アジアを学ぶ
そういうなかで私は、なんとかして市民的な学習の組織をつくらなければいけないと考えていました。
私はこの時期、一九七〇年代の末から八〇年代のはじめに、三つの試みをしています。
ただし、その三つの方法を、どうやって選んだかというのは、あとからわかってくることであって、三つの方法をきちんと、これとこれとこれをやらなければいけないという形で選んだわけではないのです。
その時の日本経済と同じで、なりゆきにまかせて選んだということがあります。
その一つは、“アジア塾”(アジア勉強会)というものを自分で運営してみるということです。
その時、その時で名前は違うのですけれども、いちおう“アジア塾”と呼んでおきます。それぞれ一年半ないし二年回のものを三回やっていました。
ですから、合計すると五年ないし六年、私は“アジア塾”をやっているわけです。
そのなかでわかったことがいくつかあります。
私は“アジア塾”のむかで、自前の研究者というものを育てたかった。
ところが、やってみると、アジアについての一般的な教養を与えることはできたものの、それだけに終わってしまって、自前の研究者を育てるということでは失敗しています。
しかし、私の持っている気分――や全局級な言い方をすると志です――が、“アジア塾”に参加した生徒に伝わり、三回で六〇人ぐらいですけれども、その五分の一ぐらいとは、今日でもつきあいは続いています。
少なくとも私が目指した調杳・研究者という形では残っていませんが、なんらかの形で、アジアにかかかる市民運動的な意味での戦線に残っていると考えていいだろうと思います。
これが一つの試みです。
“アジア塾”で、とくに三回目のときにそうだったのですが、欧米の大学の大学院ぐらいのレベルで教えることができないかと思いました。
つまり、毎週宿題を出して、この本と、この本とを読んできて、それを報告せよ、ということを考えたのです。
そうしたら運営している仲間に、そんなことをしたら一人も出てこないだろうと言われまして、そういうものかなと思ってあきらめました。
アジアについて勉強する既存のシステムがないということは、日本について、ある程度言えることなのです。
欧米のほうは、もう少し、そういうシステムを持っています。
ただし、欧米のほうが先に進んでいるという意味ではありません。
欧米は植民地主義の歴史が非常に長いので、そのなかから、ある種の遺産として、東南アジア通史というようなものが、きちんとできています。
日本には、そういうものはありません。少なくとも、いい本として私が推薦できるようなものは、ほとんどない。
もう一つ、アジアのことでむつかしいのは、アジアというものを一つの実体として考えるのには無理があることです。
インドと中国と東南アジアと東北アジア、それから日本列島、沿海州、つまりシベリアがあります。
イスラム圈も太平洋圈もアジアと考える立場もあります。 |

ダバオの漁港で水揚げされるマグロ(一九七八年)
|
政治的な掛け声としては、アジア・アフリカ連帯というような形がありますけれども、アジアというものを一つの実体として考えることは、学問上は無理です。
2 バナナの調査 top
“感情移入”
この時期の私の第二の試みは、バナナの調査です。
前に、“感情移入”と“地理”という話をしましたけれども、バナナの問題は“感情移入”に、きわめて沿った形で問題を立てています。
非常に平易な“感情移入”の回路に沿って事例研究、ケーススタディをしようという試みです。
私はそれまでに、バタアン半島の保税加工区や、水爆によるクラ運河計画に絡んで、一人だけで調査をやって、それぞれ書物を書いてきました。
私は、その頃から自分のことを学者としてよりも、むしろリポーターとして、つまり、学問の持っている一種のルール、実証性とか、そういうのは一応おさえた上で、普通の方に読んでもらえるように、普通の方に伝えるために私は仕事をしていくのだということを、ますます考えるようになってきました。
ですから、普通の人に伝えるためには、どうしたらいいかということが問題になってきます。
そこで考えたことの一つは、一九三〇年代(1)との対比なのです。
一九三〇年代の日本人は大陸に対して、どんどん軍国主義的に膨張していきます。
そうすると、戦争ということにかかわりなく生きていられた日本人というのは、当時の日本にはいませんでした。
お父さん、お兄さん、亭主が戦場で兵士として戦っているかどうかは別として、だれもが戦争にかかわっていたと思うのです。
それと全く似たような状況が、今日の日本にあります。
それは一九七〇年代に始まりますが、アジアにかかわりなく生きていられる人というのはいません。
塾で教えている先生でも、子供が持ってくる月謝の幾分かは、アジアで稼いでいるという形になっています。
お金というのは巡り巡る。
いまの日本の貿易の三分の一はアジア(2)ですから、アジアとかかわりなく私たちは暮らしていけません。
(1)一九三〇年代 「一五年戦争」ともいわれる中国大陸への日本の侵略は、一九三一年の日本軍による鉄道爆破事件を口実にして開始された。 翌年には傀儡国家としての「満州国」を建国させ、中国東北部の鉄、石炭などの豊富な資源を獲得し、三七年には盧溝橋事件をきっかけに中国との全面戦争を引き起こしていく。
中国大陸侵略行為とそれによって得た厖大な権益は、当時の日本人の暮らしに直接、間接につながっており、現在の日本と近隣のアジアの経済的関係を想起させるものがある。
(2)日本の貿易の三分の一はアジア この講演がおこなわれた一九八九年の日本の貿易総額は輸出約二七五二億ドル、輸入約ニー○八億ドルで、アジア全域に対しては輸出約九〇四億ド大輸入約八七三億ドルとなっている。
私は関係ないよ、と言えないはずです。そういう意味から、アジアにかかわっている普通の人に、私の考えている、私が調べてわかったことを伝えていきたかったのです。
日本と東南アジアとが実体的にかかわりがあるということと言えば、“感情移入”の回路が潜在的にはっきりと準備されていったということになります。
まさに、潜在的であるということが問題なのであって、それをどのように掘り起こして、自覚化していくか、ということを考えておかなければなりません。
共同研究
そのような意図はあったのですが、実際にバナナの調査を姶めたのは、たまたまダバオのバナナ・ブランデーションで働いているフィリピン農民が、きわめて悲惨な状態に陥っているということを耳にしたからです。
そこで、フィリピンの仲間と共同研究の態勢を組みました。
共同研究の態勢と、研究費をどうやって捻出したかということについて、少し触れてみたいと思います。
私のパートナーになったのは、ランドルフ・ダビッドという人で、フィリピン大学の第三世界研究所の所長(当時)です。
そして東京のアジア太平洋資料センター(PARC)(3)の私と、第三世界研究所の彼との間に研究態勢が組まれました。
第三世界研究所の場合には、はっきりした研究所ですが、私の場合には、その当時、私の周りに三人ぐらい、バナナ研究を手伝ってくれた人がいました。
ここで、先ほど言った“アジア塾”の問題が出てくるのですけれども、私の周りでバナナ研究の調査を手伝ってくれた三人は、すべて“アジア塾”第三期の卒業生です。
彼らはダバオを訪れたり、横浜港や大阪港へ出かけて、乙仲(おつなか)(4)と呼ばれる荷揚げ業者を取材したりしています。 そういう意味から言えば、“アジア塾”の試みと実際の調査とは、つながっていました。
(3)アジア太平洋資料センター(PARC=Pacific Asia Resources Center) 一九七三年に創設された市民団体で、アジア・太平洋・第三世界の民衆運動の情報収集や調査研究、連帯運動などを目的にしている。
六九年に、ベトナム反戦運動にかかわっていた市民。研究者が英文雑誌『AMPO』を発刊、PARC創設のき。かけになった。鶴見良行は創設メンバーの一人だった。現在も続く『AMPO』に加え、月刊誌『オルタ』の発行、自由学校の運営など多彩な活動をおこなっ‘ている。
(4)乙仲 輸出入業務で荷主。船会社に代わって貨物の受け渡しを行う業者。輸入貨物でははしけ運送と沿岸荷役、輸出貨物では荷主から貨物を受け取り、海上運送業者に引き渡すまで、いっさいの運送荷役を行う。通関業務の代行を併せて行うものが多い。
調査費
つぎに調査費の問題です。調査費については、その当時の時代と政治の動きを反映する面白い問題が浮かび上がってきます。
全体の割り振り、労働の分担としては、フィリピン班がダバオにおける生産の現場についての調査を担う、私たち日本のグループが、日本における流通の調査をする、ということです。
これは、きわめて当たり前の分担です。
マニラからダバオまでは夜間のムーンライトという飛行機を使っても、二時間ぐらいかかります。
ダバオはフィリピンの一番南ですから、どうしてもお金がかかるわけです。
船はありますけれども、船ですと三日四晩ぐらい。さらに、現地に調査拠点をつくらなければなりません。
お金の負担は、圧倒的にフィリピン側にかかってきます。
日本のグループは私をふくめて四人ですが、みな東京に住んでいます。
バナナの流通を調べるには交通費ぐらいしかかかりませんから、たいしたお金は要りません。
日本のグループはダバオまで足を運びましだから、そういう費用はかかりましたけれども、それ以外は自前でできると踏んでいました。
ただしフィリピン側はお金が要るわけです。
国連機関のアジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)は一次産品調査というのをやっていました。
一次産品というのは、バナナとかコーヒーとか砂糖とかゴムとかです。
そこで、そういう一次産品の調査プロジェクトのなかに組み入れてもらいました。
そして、八〇〇〇ドルのお金を調達したのですが、それをすべてフィリピン側で使ってもらうことにしました。
私は調査期間中、三度ほどダバオに足を運んで、ダバオで暮らしていますが、その費用はほとんど自前で稼ぎ出しました。
そういうことを言うのは、私は立派であるとかという形で、自慢するためではないのです。
私たちは、他の国に比べて、いま非常に高所得になっているからです。
高所得てある私たちの所得のなかには、アジアで稼いでいるものが、ずいぶんあるのです。
したがって、私たちが自前でやるのは当然です。
ただ、そのことが、少なくともアカデミズムの社会では十分理解されていないような気がするのです。
民衆の間では、すでに行われています。
工事現場などで働きながら、一年に二か月ぐらい東南アジアへ行ったりする人を、たくさん知っています。
さて、ESCAPの本拠地はバンコクにあります。
一次産品調査の主任監督官をしていたのはインドネシアの方なのですが、私が英語で書きましたバタアン半島の保税加工区調査の報告を読んでいて、それを高く評価していたので、すぐに話はまとまって、八〇〇〇ドルのお金をくれました。
そこで非常に面白いことがわかりました。
日本政府はESCAPの一次産品調査について同情的ではないので、資金をぜんぜん出していなかったのです。
したがって、私の調査能力は認めるけれども、日本グループについてはお金を出せないとのこと。
私は、「それでけっこうです、全部フィリピン・グループに渡してください」と言って、フィリピン・グループに差し上げました。
つまり、日本政府は一次産品調査に警戒的、批判的であった。そしてお金を出していないから、私のところにお金がこないわけです。
私は日本側のグループのためにお金をつくろうとしたのではないから、かまいませんが、なぜ日本政府が一次産品調査にお金を出していないのか。
私は植民地主義を、前期植民地主義と後期植民地主義にわけるのですが、後期植民地主義、つまりブランテーション(5)などをつくった時代に、一番お金を儲けた、世界市場につなげて利潤を上げた産品は、コーヒー、砂糖、ゴム、コプラなどです。
(5)プランテーション ヨーロッパ列強および日本は、アジア、アフリカ、ラテンアメリカで、タバコ、サトウキビ、ゴム、コーヒーなど単一作物の大規模企業農園を形成した。 こうしたブランテーションは、広大な土地を占有し、低賃金労働力を使い、本国などへの輸出商品を生産した。
この農業形態は、植民地の解放後も多くの地域で継続している。
それがいまでも、植民地経済の状態と同じような形で残っています。その問題についての調査なのです。
そういう産品で、一番利潤を上げていたのは、もちろん欧米の植民地主義の国家です。
それに対して日本政府は、ある種の遠慮があるわけです。
分析の視点
もう一つ考えたことがあります。
それは、バナナの本を書いているときに問題になってきたことで、分析の視点ということです。
私たちがバナナ研究で出した報告書は二種類あります。
一つは英語で書かれた、ESCAPに対する報告書です。もう一つは、私か書いた『バナナと日本人』です。
ESCAPの報告書では、私は流通を分担していますから、その分を英語で書きました。
これは一次産品の調査の一環ですから、当然、今日のブランデーション生産におけるバナナだけに焦点を当てています。
ところが、この視点に立ちますと、問題が非常に単純化されてしまいます。
一方に、非常に強くて悪玉のアメリカ系の多国籍企業。
アメリカ系以外で参入しているのは、日本の企業一社。
いずれも流通部門をになう企業です。
他方に、非常に弱々しくて、被害者になっているフィリピン農民。そういう図式になっているわけです。
こうした見方に、私は批判的でした。今日の経済の什組みは、善玉・悪玉論だけで切れるような単純なものではないわけです。
現在のバナナ・プランテーションだけに焦点を当てて、借金奴隷、債務奴隷になっているような農園労働者の苦しみだけを描き出しますと、歴史的な背景が見えなくなってしまうのです。
彼らは北方からやってきたクリスチャン・フィリピーノ(6)です。
(6)クリスチャン・フィリピーノ フィリピンの宗教人口は、カトリックが八五%と、圧倒的に優勢であるが、ミンダナオ島では、二〇世紀初頭までムスリム(イスラム教徒)が植民地支配を排除していた。
これに対し、アメリカ植民地時代から今日まで、とくに一九六〇年代のマルコス政権下、ルソン島やビサヤ諸島などの(ミンダナオ島から見れば北方の)土地を持たない農民(ほとんどはクリスチャン)を入植させることで、ミンダナオ全域を支配下におくことが、一貫したマニラ政府の政策であった。このため、いまなお先住民やムスリムと入植者との衝突は後を絶だない。
「ここは、北方パナイ島のイロンゴ族開拓民が拓いた村である。ドンが生まれるはるか以前に父親たちがここへ移ってきた。
故郷で食べられなくなった貧農民の流出である。だが今日では教会や学校も建設され綺麗に整っている。
クリスチャン開拓民は、ムスリムの土地でそれだけ豊かになったのである。
役場の前には、フィリピンではどこでも見かけるリサール像があった。
一九世紀末の啓蒙思想家ホセ・リサールは、対スペイン独立戦争直前に殺された。それで国民的英雄となった。
だがそれもスペインに服従しなかったムスリムには、あまりかかわりのない話にちがいない。
クリスチャン・フィリピーノのコタバト流入は、一九二〇年代に始まり、戦後に急激に増加した。セブ島やイロコス州の出身者も多い。
イロコス州はルソン島の北西、マルコス大統領の故郷だ。」(『マングローブの沼地で』)
|

ミンダナオ島の中心都市
ダバオ市バスターミナル付近(一九七八年)
北方というのは、大地主が支配している土地で、そこからやってきたのは、土地なし農民です。
経済用語でいう言葉がないので非常に具合が悪いのですが“ルンペン農民”です。 地主からすれば彼らは厄介者ですから、追い出そうとする。
みんな国内移民としてミンダナオなどへ入ってきています。 その人たちが、現在はダバオの小さな自営農家、もしくはその労働者として、バナナ農園で働いているわけです。 |

図3 ミンダナオ島とその周辺
|
しかし彼らがやってきた当時、そこには当然、先住民族であるマノボとかパゴダという積霊信仰の人たちがいました。
そういう人たちを追い出しているのです。
それ以前、戦前期には、一九〇六年ぐらいから、日本人が入って、ダバオで麻農園(7)を開きました。
(7)麻農園 マニラ麻(アバカ)は、ロープの原料として一九世紀半ば以降のフィリピンの重要な輸出作物のひとつであった。
これをミンダナオ島ダバオ周辺で大規模に栽培を始めたのが。二〇世紀になってこの地に入植してきた日本人であった。
日本人入植者は一九三〇年代には匹刀五〇〇〇人から二万人を数え、日本人農園の生産量はフィリピンの全生産量の四分の一をこえたといわれている。
現在、問題となっているダバオの日比混血児の多くは、これら入植日本人の子どもたちである。
|

バナナ農園労働者が利用するサリサリ・ストア(日用雑貨店)
|

バナナ農園労働者の住居
|
麻農園を開いた日本の移民の六割ぐらいが沖縄からです。
貧しいがゆえに、土地なきがゆえに追い出されてきた人たちが、そこに入って加害者になっています。
それが現在では、さらにまた被害者になってくる。そういう関係が見えます。
そういう歴史の重層的な、パラドクシカルな関係というものは、現在のドールとか、デルモントとか、チキータとか、バナンボとかだけに光を当ててしまうと見えてこない。
繰り返し繰り返し、歴史は変わっていっています。
フィリピン側が出してきたリポートというのは、現在だけに焦点を当てており、しかも彼らの立場は、かなりマルクス主義に近いので、そういうところが出てきません。
ESCAPの場合は一次産品調査ですから、私の英語のリポートでは、それだけに焦点を合わせましたけれども、『バナナと日本人』の場合には、そこら辺は全部書き直してしまったわけです。
現在存在するバナナ農園を、フィリピン史のなかに置き直してみる。
あるいは、ミンダナオ史のなかに置き直してみるというふうにしたのです。
この種の、善玉・悪玉論という視点は、現在もフィリピンの左翼の運動の一部に見られます。
非常に単純に、アメリカの多国籍企業を悪者とし、自分たちは被害者であるというふうな、単純な割り切り方をしているこの見方は、フィリピンの左翼において、かなり強く見られる思想的な弱点だと私は考えています。
記述のスタイル
つぎに、『バナナと日本人』を書いた、記述のスタイルの工夫について。
私たち日本人は、自分であるうと、子供であろうと、亭主であるうと、すべて、どっぷりとアジアに浸かっています。
ですから、私は自分のわかったことを、アジアに直接行っている方とか、アジアを勉強しているプロに読んでいただくことは、あまり念頭にない。
もっと、普通の方に知っていただきたいわけです。
先述したように、“感情移入”の回路が、潜在的に準備されている。
それが潜在化しているのではだめで、それを掘り起こして、自覚化していく。
そのためには、普通の方に読んでもらうということが、大きな眼目になっているのです。
だからなるべくやさしい文章で晝くようにしています。
そのうえ、最終原稿の段階で外部の方に加わってもらって、一字一句、表現を点検しました。
この作業は深夜まで続いたのですが、それが二晩ほどありました。
こういうふうな、私の文章を読んで批判してくれる人のことを、読んでくれる人という意味て私は「リーダー」と呼んでいます。
これは、文章が独りよがりになることを防いで、客観化するために非常に有効な作業だと私は考えています。
“失敗”
しかし、失敗というほどではないのですけれども、こういうふうに読んでくださったらいいのにな、という思いが残った問題もあります。
その一つは、バナナ・プランテーションで働いているフィリピン労働者への同情のあまり、バナナを食べなくなった人々が現われてきたことです。
この問題は非常に厄介です。ある意味から言ったら、深刻な問題です。
出版社の地下の会議室で夜明けまで点検したときに、こんな批判が起こったのです。
バナナの問題について、こういうことがわかってきたら、鶴見さんは、もっとはっきりと、それについてどうしたらいいかという解決案を書くべきだという議論です。
私は二つの理由から、それに反対しました。一時間ぐらい議論しました。
その一つの理由は、『バナナと日本人』という、現物に即しながら、しかも、それを民衆に伝えるというタイプのアプローチは、いまある学問、大学にしても、そこの中からら生まれてきていないからです。
現在でも、ほとんど生まれていません。
とすれば、私がそれをつくったということだけで、ある種の運動的な効果になっている。生まれていないということに対しての、私の現状批判になっているわけです。
もう一つ、こちらのほうがもっと重要ですけれども、私がそのことについて解決策を出すとすれば、批評運動ではなくて、実体的な運動にかかかることになります。
「お前たちは、これをやるべきだ」と言うことになります。
私はそういうふうに上に立って、人に指令を与えるような形の運動は、あまり好きではありません。
はっきり言えば、私が提供した情報によって、それはこうすべきだということは、読者のなかから生まれてこなければいけない。
私は指令を出す立場には立ちたくないのです。
私は、いまの学問の体制のなかから生まれてこないような情報を、提供しているわけです。
それを受け止めてもらわなければ困ります。
バナナを食べろとか、食べるなとか、そういうことを命令する立場には立ちたくありません。
私は自分の運動というものを、そういうふうには思っていません。
それは、ある種の民主主義の問題なのです。
そのことについては、“早とちりの良心主義”、つまり、良心が独りよがりになるということもあることを、十分に考えてほしいという気がするわけです。
ただし、あとで述べるエビについては、私たちは食べないほうがいいというふうに書くべきだという結論に、ほぼ達しているのです。
それは、環境破壊、資源枯渇が、あまりにもひどすぎるからです(四章1参照)。
だれかが搾取されているから、それに対して同情して、食べないほうがいいということではなくて、世界を荒らしているという状況を少しでも止めるためには、エビはそろそろやめたほうがいいだろうと書こうと、考えています。
付随的に申し上げますと、私はエビは食べますし、バナナも食べます。それは、単純に言うと、こういうことです。
私たちは調査マンとして、義理でもものにつきあわなければいけません。
バナナとつきあった以上は、バナナをいじらなければいけないし、エビとつきあった以上は、トロール船にも乗らなければいけないし、食べなければいけないし、市場にも行かなければいけないのです。
私は机の上だけで、ものを書くという姿勢に反対です。徹底的に歩いて、現場に触れて、それで書く。
その意味では調査マンは、そのものにつきあった以上は、エビだろうと、ナマコだろうと、マングローブだろうと、つきあうというのが、調査マンとしての職務上の義理です。
ですから、私はバナナもエビも食べるし、いまでも市場で買ってきます。
このあいだも京都の錦で買ってきました。そのエビは真っ赤なのです。
錦の魚屋さんに、このエビはなんていうのかと聞いたら、アシアカだと言っていました。どこの産だと聞いたら、「オスト」だと。メキシコは「メキ」で、「オスト」というのはオーストラリアなのだそうです。 |
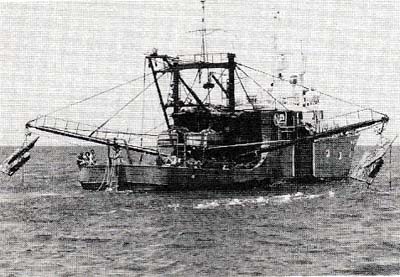
エビトロール漁船(一九八八年)
|
「オスト」のアシアカエビというのは、グレートバリア・リーフの東海岸から来たのだと思います。
そういうエビ(8)が日本に入って、高級エビとして売られているわけです。
そういうことを知るためにも、我々は目にし、触り、いじり、食べてみなければいけないわけです。
(8)エビ エビは1961年に輸入30万2975トン、金額にして3387億円で、輸入食料の卜ップである。
インドネシアからの輸入がもっとも多く、6万3666トン。ついで、タイが4万9345トン、インドが4万4113トンと続く。
インドネシアやタイからのエビの多くは、養殖エビ(ブラックタイガー)である。 なお、オーストーラリアからは6140トン。メキシコからの輸入量は近年少なく、1994年にはわずか859トンだった。
3 マングローブ top
|
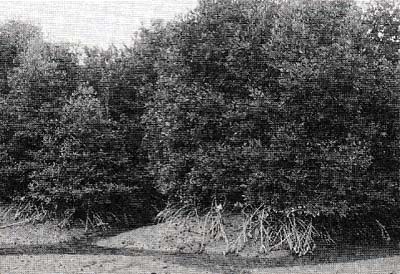
大地を造成するマングローブ(南部タイ、1991年)
第三の試みとして書いた『マングローブの沼地で』の最初の舞台は、バナナ・プランテーションのあるミンダナオです。
先述したようなフィリピン研究者の公式主義への不満から、私はミンダナオをずいぶん歩きまわり、古い資料を読み漁りました。
ですから、この仕事は、書いた順序からいうと『バナナと日本人』につづく形になっています。
しかし『バナナと日本人』が、“感情移入”をまるまる受け入れる形になっていることへの自己嫌悪が無意識に働いているせいか、“感情移入”を禁欲して、私の言う“地理”に近い書物になっています。
これは、『朝日ジャーナル』に連載したものを書物にしたのですが、その題名はずいぷんと考えあぐねて、四ツ谷駅でふっと思いついたのです。
マングローブという植物群の名を。
日本人にとっていくらかなじみがあって、しかもなじみのあまりないキーワードは何か。そんなことを考えていました。 |

土手に植えられたマングローブ。子どもたちの向こう側が海である
(インドネシア、1987年)
|
抵抗者の舞台
『マングローブの沼地で』については、二つ意識がありました。
私はそれまで、東南アジアで出てきている、いろいろな一揆、反乱者、抵抗者の歴史をケーススタディとして調べていました。
この問題について東南アジア全域について書かれた本というのは、非常に古いものですけれども、ホブズボーム(9)という人が書いた本があるだけです。
(9)エリック・ホブズボーム(Eric J. Hobsbawm, 1917-)イギリスの歴史家。青木保編訳『反抗の原初形態』(中央公論社)の邦訳がある。
そういうものを調べていますと、反乱者たちが働いた舞台というのは、必ずしも水田耕作地帯ではありません。
そこで日本の「百姓一揆」について読んでみたのですが、日本では「百姓一揆」というと、全部農民一揆です。
「百姓」というのは百の姓で、そこには漁民もふくまれているのです。
漁民一揆というのは日本の史料のなかでは出てきません。
日本列島の一揆については、そこに農中心主義があることを実感してしまいました。
ところが東南アジアを見ますと、一揆や反乱が起きたのは、かなり海岸べりの、マングローブの沼地です。
日本の日本史理解も、日本の東南アジア理解も、ヨーロッパの東南アジア理解も、定着農耕地(10)をそれらの舞台として考えていますが、そうではない舞台もあるわけです。
(10)定着農耕 (11)に触れられている「焼き畑」のような移動耕作に対して、一か所で繰り返しおこなう農耕。
これは、家畜飼育などによる肥料の登場で進展したが、現在では化学肥料、農楽の貢献が大きい。
一方、統治者にとっての管理、課税という点でも都合のいいシステムであった。
マングローブの沼地というのは、日本では沖縄しかありませんが、そこは、海でもなく、陸でもない。
海が陸に入ってきて、陸が海にせり出してくるという、緩衝地帯なのです。
エコロジーでは「転移帯」と言います。
日本列島では海岸線が一本で切れます。せいぜい白砂青松の白浜だけです。
東南アジアでは海岸の幅が非常に広いのです。私たちの目には、ここは非常に住みにくいところです。
そういうところでも歴史の展開があった。
定着農耕的な、大地を中心とした歴史観で東南アジアを理解している、世界を理解しているというのは、間違いではないか。
もっと違う生態系で、人々は活き活きと暮らしていたのではないか。
日本史の舞台に戻しますと、この一〇年ぐらい、日本史をコメ史だけで書くのでは困るという言い方がたくさん出てきています。
大地の生産系だけで言うと、イモもあったし、コメをあくまで拒否してイモだけ食べていた人たちがいたはずではないか。
あるいは、焼き畑(11)の民があり、漁民がある。そういう日本の生産史を全部、目に入れて考えるような歴史の理解の仕方というのが出てきました。
(11)焼き畑 森林や雑草を焼いて耕作をおこない、一〜二年で地力が落ちると、回復するまで他の場所で耕作をする農耕。
労働生産性、土地生産性の点で必ずしも定着農耕に劣るわけではないが、単位面積当たりの収穫量が少ないため広い耕作地が必要となるので、しだいに減少している。東南アジア各地では今も見られるが、森林伐採や森林開発との競合でさらに減少に拍車がかかっている。
鶴見は君主や王への「忠誠の選択」を可能にした「移動分散型社会」の生産形態の一つとして焼き畑に着目していた。
「逃げ出すとは、文字通り他所の土地へ移住することだ。同じような条件の土地はいくらでもあった。
焼き畑にしろ漁業にしろ、移動は生業(なりわい)の一部である。農民の田畑は、先祖代々、営々として血と汗を注ぎこんできたというようなものではない。領主を気に入らなければ民衆はいとも容易に腰をあげて移っていった」(『マングローブの沼地で』)
それとつなげるように、これまである東南アジアについての歴史観というものを引っくり返すような形で、『マングローブの沼地で』を書いたわけです。
そういう意味では、日本史にかかわります。しかし、これは“感情移入”が非常にしにくいのです。
マングローブの沼地そのものを、多くの方はご存じないでしょう。
白い砂浜にココヤシが立っているというのは、熱帯のイメージとして定着しているでしょう。
しかし、東南アジア海岸は、マングローブの沼地が大部分なのです。そういうことがわからない。
逆に言えば、わかりやすいということが“感情移入”の回路になっているから、“感情移入”がしにくいということを、私は提起しているのです。
作者の意図
もう一つの意識は、作者の意図にかかわる点です。
たぶん、他の作者についても同じような問題意識があるのだと思いますが、書いて知らせた内容に主眼があるのではなく、なぜそれを書いたのかという、作者の背後に潜む問題意識が主眼であるような作品があります。
こういうふうに作品として書かれたものには、その背後にかくされた著者の意図が、表面に出ていないようなものがあります。
こうした作品は、文学においても見うけられます。
たとえば、司馬遼太郎著『韃靼(だったん)疾風録』(上・下、中央公論社、一九八七年)では、日本、朝鮮、中国の国家主義への批判を読みとることができます。
私が『マングローブの沼地で』を書いた意図を、もう一度ごくおおまかにいうと、これは日本史に対する批判、近代西洋から発したアジア学についての批判なのです。
それが、「マングローブの沼地」というキーワードにあらわれています。
4 YUKI ランドルフ・ダビッド
top
鶴見良行さんは、まず何より心、いまの日本人の生活のあり方への批評家なのだ、と、私は常に考えてきた。
彼が東南アジアを研究する民族誌学者になったのも、このことによっていると私は推測している。
彼は東南アジアの人々、地理、歴史、文化、そして政治経済を非常に独自な視座からとらえようとしていた。
つまり、日本が「発展」していくなかで東南アジアはどのように形成されていったのか、そして東南アジアの人々の生活が、どのように日本人の生活様式に従わさせられているのかを理解するために。
東南アジアを歩いた鶴見さんの仕事は、彼の本の読者、とくに若い日本人たちが自分たちの生活のあり方に批判的な見方をするうえでの鏡のような役割を果たしていると、彼自身が位置づけていたようだ。
バナナ、ナマコ、ヤシ、輸出加工区、そのどれを調査している時にも、鶴見さんは一貫した方法論と理論を維持した。
彼が分析している商品やシステムについての細かい描写の裏には、日本資本の行動とその当面の犠牲者である日本の消費者に対する思慮深い攻撃が込められていた。
私は彼の学生となる幸運には恵まれなかった。
しかし私たちは共同研究者として、ミンダナオでバナナの調査をおこなった。
私自身の知性の成長過程において、鶴見さんがこんな強い影響を与えたのを、私は後年になるまで気づかなかった。
彼は私が知った最初の日本人研究者であり、私は、彼が友人であることをいつも誇りにしていた。
私が出会った何人かの日本の学者たちが、彼を一匹オオカミのジャーナリストにすぎないと見なしていることを知ったときでも、私の考えは変わらなかった。
彼は念には念をいれて、データをチェックするタイプだった。
必要な記事や論文についてはコピーを送ってもらえるよう、世界中の友人に頼んでいた。
彼は多くの古い文献を各地の図書館に探し求めた。
その多くは歴史書であり、いくつかはフィリピンの例のように、邦訳した。
彼はたぶん、東南アジアにかんする本の最良の個人コレクションを持っているにちがいない。
それだけでなく、彼は執筆もした。彼の晝いたものは、いつも明瞭で面白かった。
多くの学術的な論文にありかちな、ドライで知ったかぶりのところがなかった。
学者でも素人でも、同じように彼の本を理解できた。
彼は、いつも、調査対象地の住民たちを心から愛し、しばしば、彼らに料理をつくってごちそうした。
だからこそ、彼らは“YUKI”を親戚のように歓迎した。彼の文章がいつも感動的なのは、このためである。
彼は、偉大な旅人であった。どこででも何でも食べた。
病気になることや、今夜の宿がみつからないことの心配もしなかった。
数年前、何かの理由で、マレーシア政府が、彼の入国を認めないことがあった。
彼はシンガポールにもどり、食堂でコーヒーを飲みつつ、ノートを書きながら過ごしていた。
私は偶然にそこで彼に会い、一緒にジャカルタとバリヘの旅行にいかないかと誘った。
計画にはなかった旅に来て、彼は多数の新しい友人と出会った。
これが、その後、インドネシアの辺境にある島々を調べることにつながっていったのである。
(フィリピン大学教授、原文英語) |
top
**************************************** |