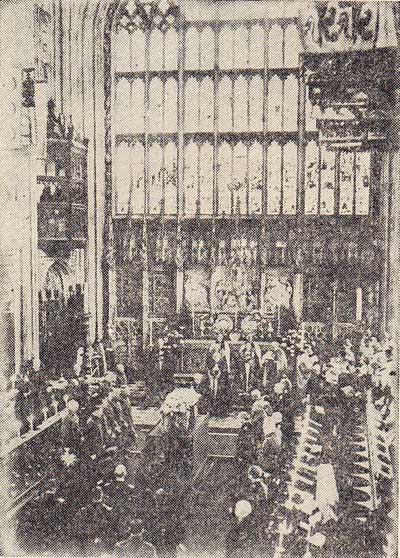|
****************************************
Home ヒトラー 暗殺事件 ナチ武装親衛隊 ムソリーニ スターリン ソビエトの悲劇 ジューコフ
ソビエトの悲劇――トハチェフスキー元帥粛清事件の真相
(ビクトル・アレクサンドロフ著/高橋 正訳 昭和38年刊 抜粋)
写真集
訳者まえがき
著者まえがき
第一部 スターリンの陰謀
第二部 暗躍するナチスのスパイ
第三部 ソ連軍の悲劇
|
●第二次大戦前夜のソビエトでは、スターリンの猜疑心の犠牲となって、革命の元勲たちが次々と処刑される悲劇的な粛清の嵐が吹きまくった。
そして一九五三年、スターリンは栄光に包まれながら死んだ。
●トハチェフスキー事件とは、スターリンとヒトラーの謀略によって一九三七年、赤軍の至宝、ソ連国防次官兼参謀総長トハチェフスキー元帥をはじめ、多数の将星たちが、祖国背信のかどで処刑された事件である。
これに端を発して三万人に及ぶ将校が粛清され、その結果、独ソ戦初期のソ連軍大敗北の原因となった。
●その規模や影響において、ゾルゲ事件をはるかに凌ぐ今世紀最大の国際的大謀略であり、これは単にソビエトのみならず、全世界の悲劇的な運命につながるものであった。
●著者は、この粛清事件の真相解明に、ドレフュス事件(注)のゾラにもまさる情熱をかけ、本書は、その克明な調査に基ずいて書かれた真実の書である。
(注)1871年の普仏戦争に敗けたフランスが経済不況に陥っていた時、フランスの反ユダヤ組織が参謀本部のユダヤ人のドレフェス大尉をドイツのスパイだとでっちあげた事件で、フランス国防省は敗戦の責任逃れのためこれを支持しドレフェスは無期懲役の刑を受けた。
これを作家エミール・ゾラがドレフェスが無罪であることを証明したので、フランスではドイツのような反ユダヤのナチスが起こらないですんだ。 |
 |
著者 ビクトル・アレクサンドロフ(左の写真)
著者は、一九一〇年ソビエトのレニングラードの弁護士の家に生まれ、十代でロシア革命に会い、家族に連れられてパリに亡命した。
パリのソルボンヌ大学とベルリンのフンボルト大学に学び、世界旅行二度。その後各国で特派員生活を送り、戦後も、欧米各紙に健筆を振っている。「ニキタ・フルシチョフ」「クレムリンの謎」「クレムリン千年史」など十数冊の著書があり、米、英、仏、西独、日本など各国で出版されている。
訳者 高橋 正
1933年 東京生まれ、1956年早稲田大学政経学部卒
訳書:「シベリア横断四万キロ」「毛沢東と私は乞食だった」「中国とその影」
現職:東京新聞外報部員 |
写真集 top

近代赤軍の父とうたわれた
ミハイル・トハチェフスキー元帥 |

何やら親しげに話し合うスターリンとウォロシーロフ
写真は粛軍開始直前のもので、国防相ウォロシーロフの変節によって
トハチェフスキーは、このメーデーで公衆の前に姿をみせたのを最後に、
エジョフの秘密警察の手で銃殺され、やがてブリュッヘル、
エゴロフ両元帥も同じ運命に見舞われることになった。 |

1937年赤の広場でメーデー行進を観閲するクレムリンと赤軍の首脳たち。
上段前列左端がスターリン、一人おいて小男の秘密警察長官エジョフ。
その隣りにミコヤン、モロトフ、カリーニンらの顔もみえる。
下段は左から、ありし日のトハチェフキー、ブリュッヘル、ウォロシーロフ、
エゴロフ、ブジョッヌイの赤軍五元帥。 |

モスクワ川に影を落とすクレムリン宮の全景。かつて
スターリンは、ここクレムリン宮の奥深くに君臨した。 |

世界制覇の野望に燃え、戦わずして赤軍首脳部を
潰滅させる陰謀を企んだヒドラ一・ドイツ総統。 |

ヒトラーを恐れ、トハチェフスキーの名声をねたんでいた
スターリン(右)は、モロトフ(左)と語らって
反独派トハチェフスキーを粛清しヒトラーと手を結ぼうとした |

旧友スターリンに
死の抗議をした
オルジョニキーゼ |

大陰謀とは知らずに、
一役買わされた
チェコ大統領ベネシュ |

旧敵スターリンに
利用されたラディック |

『食人鬼』といわれた
秘密警察長官エジョフ |

エジョフに粛清された
前秘密警察長官
ヤーゴダ |

粛清裁判の立役者
ウィシンスキー
検事総長 |

1953年スターリンの葬儀。栄光に包まれて死んだスターリンも、やがて激しい
スターリン批判のなかで、遺体はレーニン廟からも移される運命となった。

フルシチョフのスターリン批判をきっかけに名誉回復され、
再び近代ソ連軍建軍の父と仰がれるミハイル・トハチェフスキー元帥。
これは、1936年スターリンの軍事使節として、フランス軍
首脳とパリで会談し、フランス陸軍省を退出するところ。 |
訳者まえがき top
一九六一年秋のソ連共産党第二十二回大会で、フルシチョフはモロトフら「反党グループ」事件に関連して、スターリン批判を再燃させた。
その口調の激しさもさることながら、万場の聴衆をひとしく仰天させたのは次の発言であった。
「最近、ある外国紙に載った情報によると、ソ連侵略をもくろんでいたヒトラーは、ナチス情報機関に命じて、赤軍の至宝トハチェフスキー元帥、ヤキール大将らが、実はドイツ参謀本部のスパイであるという偽の証拠を捏造させ、それを故意にチェコのベネシュ大統領に洩した。
ベネシュは恐らく善意から、でっちあげとも知らずこれをスターリンに手渡したという。
ヤキール、トハチェフスキーらは逮捕され、銃殺された」 |
フルシチョフが、引用したこの外国紙の報道こそ、実は本書ビクトル・アレクサンドロフ著「トハチェフスキー事件」の初稿だったのである。
一九三七年のソ連国防次官兼参謀総長卜ハチェフスキー元帥粛清の真相究明に、ドレフュス事件のゾラにも劣らぬ情熱を注いで来た著者は、十年の努力の成果を、六〇年春、まずイタリアの新聞ジオルナーレ・ディタリア紙上に発表した。
その夏のベニス映画祭の折、著者をみつけたソ連大使館の一等書記官は「大変興味深く拝見しました」と、問わず語りに話しかけて来たという。
二十二回党大会の直前、フルシチョフの女婿アジュベイ・イズペスチア編集長と作家のエレンブルグがローマに立ち寄ったが、同紙の記事をフルシチョフに伝えたのは、恐らくこの二人であろうと思われる。
それはさておき、西側ではトハチェフスキー事件の真相は、すでにある程度知られていた。
フルシチョフの言明通り、ソ連侵略をねらうヒトラーは赤軍を弱体化させるため、例の偽造文書をベネシュを通じてスターリンの手もとに流すことに成功したが、トハチェフスキーの声望を妬(ねた)んでいたスターリンは、対独政策をめぐる対立も手伝って、渡りに舟と元帥を粛清してしまったというのである。
この事件をきっかけに、赤軍内部の大粛清が断行され、ために赤軍は潰滅状態に陥り、独ソ戦初期に、あのような惨たんたる敗北を喫することになるのであるが、当時は、専門家の間にさえ事件の真相を知らず、トハチェフスキーら赤軍首脳が、実際に反スターリンのトロツキス卜やナチス・ドイツと関係していたと信ずる者が多かったほどである。
ところで、フルシチョフの引用や西側の観測は必らずしも十分とは云えない。
アレクサンドロフが本書の中で明らかにしているところによると、スターリンはナチスの偽造文書にだまされるどころか、自分の秘密警察(NKVD)に命じて、ナチスの情報機関(SD)やゲシュタポと協力させ、進んで陰謀でっちあげに一役買ったのだという。
この陰謀を最初に思いついたのは、当時ナチスの情報機関で働いていたロシア人の二コライ大佐で、偽の文書はSD長官ハイドリヒが、前科者を使ってドイツ参謀本部の書庫から強奪して来た資料をもとに、ベルリンで作成された。
これをソ連側に仲立ちしたのは、パリにある亡命ロシア軍人団体ROVSの陰の実力者スコブリン将軍で、妻は帝制時代モスクワのナイトクラブで名花とうたわれたプレビツカヤ、彼女は金のためにNKVDのスパイとなっていた。
この信じられないような事件の経緯を、最初に著者に教えたのは、パリに住む古い革命家で無政府主義者のビクトル・セルジュであった。
一九四六年連合軍の従軍記者としてベルリンに滞在していた著者は、かつてプレビツカヤのマネージャーをしていた男のアパートで、トハチェフスキー元帥の処刑後、スコブリンからこの男に宛てた手紙を発見した。
その手紙には「神に感謝する。悪魔は亡びた」と書かれていた。
このスコブリンこそトハチェフスキー事件の鍵を握る人物で、妻プレビツカヤの関係からNKVDと関係を結ぶ反面、「聖なるロシアを共産主義の魔手から解放する」ためナチスを利用しようとした二重スパイだったのである。
著者はパリにあるロシアの老革命家ウラジミル・ブルツェフの家で、この二重スパイの正体をあばこうとする別の白系ロシア人団体RISの記録を発見し、この間の事情はいよいよ明らかになった。
そして最後に数年前、ナチス側の資料をドイツ参謀本部外国軍三課の課長をしていたカール・シュバルケ将軍から入手することができたのである。
アレクサンドロフの労作はソ連はもとより、欧米全体に一大センセーションを巻き起し、各国の新聞、雑誌、放送などが争って著者とのインタビューや、労作の内容を紹介した。
著者のもとには英、仏、西独など各国から出版の申入れが殺倒したが、その後の資料をもとに加筆してまずフランスで出版されたのが、ロベール・ラフォン社「現代史叢書」の一冊として出た トハチェフスキー事件」(Victor Alexandrov : L'AFFAIRE
TOUKHATCHEVSKY. Collection《L'History Que Nous Vivons》Robert Laffont. 1962)で、本書はこれをテキストに訳出したものである。
本書はスリルとサスペンスに充ちた一編のスパイ小説の体裁をとっているが、第二次世界大戦の前夜、モスクワ、ベルリン、パリ、ロンドンはじめ欧州全土を舞台に、スターリン、ウォロシーロフ、ヤーゴダ、エジョフ、ラデック、トハチェフスキー、スコブリン、ベネシュ、ハイドリヒ、ヒムラー、ヒトラー、はじめ欧米各国の政治家、外交官、将軍、秘密警察員、亡命者、ジャーナリストらの登場人物が繰りひろげる世紀の大陰謀は、事実は小説よりも奇なりのたとえ通り、読者を圧倒せずにはおかない。
しかも、ロシアに生まれ、パリとベルリンに学び、東はイスタンブールから西はバルセロナまで、記者として欧州を隅なく歩いているアレクサンドロフほど、この国際的大陰謀を描くに打ってつけの人物はなく、彼が集めた豊富な資料や情報といい、偏見のない叙述といい、本書は歴史的真実究明の書として、立派にその使命を果している。
トハチェフスキー事件は、その規獏や影響において、ゾルゲ事件を遙かに凌ぐ国際的謀略であるが、ここにこの「二十世紀のドレフュス事件」究明の書を訳出することができたのは、ひとえに弘文堂田村勝夫氏のご好意と激励によるものであり、編集部生田栄子さんのご協力ともども、深く感謝する次第である。
なお、地名人名等の表記は新聞の慣例に従った。
一九六三年七月五日 高橋 正
筆者まえがき top
一九五六年二月、ソ連共産党第二十回大会の席上、フルシチョフ首相兼党第一書記が、かの有名な秘密報告でスターリンの罪を暴露した時、彼は次のような注目すべき発言を行なった。
「一九三七年から四一年にかけ、幾多の軍首脳や大物政治家が、スターリンの猜疑心の犠牲となり、よこしまな中傷をもとに処刑されたことは、特に第二次大戦初期に極めて重大な結果をもたらした。
その期間中、軍幹部の一部に向けられた弾圧は、事実上、下は中隊長、大隊長クラスから、上は最高首脳部に至るまでを揺がす結果になった。
幾多の高級将校たちが収容所々刑務所に送られ、軍はもはや彼らの消息をきくことすらできなかった」
この時、フルシチョフは別に名前を挙げなかった。
これから一年半経った一九五七年八月二十三日、コムソモルスカヤ・プラウダ(青年共産同盟機関紙)はまるで何事もなかったかのように、トハチェフスキー、ブリュッヘル両元帥ならびにプトナ将軍を称賛するような記事を載せた。
その後間もなく、ソ連大百科辞典第五十巻は、スターリンに暗殺されたほとんどすべての将軍だもの名を載せ、これを大かれ少なかれ好意的に扱った。
中でも、トハチェフスキー元帥のことには四ヵ所でふれていた。
一九五八年二月二十三日、クズネツォフ将軍は「パキソスキー・ラボーチー」(バター労働者)紙上で「ソビエトの優れた戦略家」として、ウボレビッチ、ヤキール両将軍ならびにエゴロフ元帥の名を挙げた。
同じ一九五八年に出た大百科辞典第五十一巻(補遺)には、トハチェフスキーの経歴と写真が載った。
そして、赤軍建軍四十周年に当り、「歴史の諸問題」誌は、ソ連参謀本部の監修のもとに、研究結果を発表、トハチェフスキー元帥の名誉をそれとなく回復した。
この論文は、トハチェフスキーを「赤軍とその戦略理論の真の組織者であり創設者である」と賛えていた。
本書の目的は唯一つ、いわゆる「トハチェフスキー事件」と呼ばれるものの真相を究明し、微力ながら、劇的な歴史が作り出したさまざまな出来事の異常なからみ合いを解きほぐし、併せて、偉大な愛国家であった元帥の霊を葬うことにある。
本書の信懣(しんぴょう)性については、これを問題にするものもあろうと思うので、私は信ずるに足る証言や文書に基づく事実だけを述べるよう心がけた。
登場人物の会話については、実在の記録をもとにし、その時の彼らの心境と、当然考えられる状況に見合ったものとするようできる限り努力を払った。
読者の眼には勝手な想像の産物としか思われないようなエピソードにしても、確実な筋から引き出したものである。
たとえば、読者は私がトハチェフスキー逮捕の模様に通暁しており、元帥と縛吏の将校とが交わした言葉まで書き留めていることに驚きの念を抱かれるかもしれない。
しかしながら、この将校は、一九三七年ソフィアのソ連大使館にNKVD(内務人民委員部)の代表として派遺され、この話を任地の上司ラスコルニコフ大使に洗いざらい語っているのだ。
そして後日、ラスコルニコフ大使が職務を投げうってパリに亡命した時、私はラスコルニコフからこの話をじきじきに聞いたのである。
私に言わしむれば、本書に述べられた諸々の事実は、いずれも厳選された筋から出たものであり、本書にこうしたエピソードを盛り込んだのは、これによって事実を誤魔化すためではなく、逆に本書をできるだけ生き生きとした、わかり易いものにするためだったのである。
私はロシア人であり、政治に興味を持っているので、三十年来トハチェフスキーに目をつけて来た。
しかし、私が特にトハチェフスキーの生涯に興味を惹(ひ)かれるようになったのは、一九三三年(トハチェスキー失脚四年前)、ふとした出来事にぶつかったのがきっかけであった。
当時、私はアテネで幾つかの外国紙の特派員として働いていた。
それは私がオフィスで「バルカン諸国はどこへ行く」という連載ものの記事を書き上げた日のことであった。
表(おもて)の騒ぎが聞くともなしに私の耳に響いてきた。
例によって、ラバの背にメロンを積んだ行商人と道を急ぐ車の運転手の派手ないさかいだな、そう思いながら、私は眼の前に山積みされた書類の調べを続けた。
トルコとギリシャの友好に関するイスメット・イノニュの演説、ドイツ副領事の手紙等々。
その時、ドアをノックする音が聞えて、外から声がかかった。
クドルファーだ。私はびっくりした。
クドルファーは明るい背広に派手なネクタイをつけ、髪は短く刈り上げ、鉄十字を彫り込んだ手杖を持ち襟には[労働戦線]の襟章を光らせていた。
かってのちり紙屋、いまの駐ギリシャ公使館ナチス代表クドルファーは親しげに話しかげて来た。
ク「私の手紙、届きましたか?」私が答える間もなく、彼は旅役者そこのけの気取り方で、押しかぶせるように云った。
ク「あなたは私共にはなくてはならない方だ。ワイマール共和国のために働いて下さった時のように、新しいドイツのためにも働いて下さい。わが党(ナチス)は必ずやそのご恩に報いますよ。わが党の大物、ローゼンベルクのことを考えて下さい。彼もロシア出身です!」
私「何のお話です、クドルファーさん?」私はぶすりと答えた。
ク「あなたなら、私共のためにして下されると思うんですか、よろしかったらお話し致しましょう」
私「どうぞ」
ク「アテネに、ルーキンという白系ロシア人でウラングリ戦友会の会員がいると思うんですが、昔、ソ連の国防次官ミハイル・トハチェフスキーの戦友たったとかいう」ルーキンの名をきいて、私は面をあげた。
私「あなた方がトハチェフスキーに何の用があるんです?彼が第三帝国をどう思っているか、私よりあなた方のほうがずっとよくご存知じゃないですか!」
クドルファーは煙草に火をつけ、脚を組み直して云った。
ク「どうも、あまり単純なのは困りますな。あなたのおっしゃる彼の考えというのは、どの考えです?彼が公式の席で述べたことですか? 愚かな百姓(ムジーク)どもの最高会議(ソビエト)でしゃべったことですか?それとも彼の本当の考えですかな?」
私「トハチェフスキーは共産党に忠実だと思いますがね。しかし、まあ先きをどうぞ」私は用心して答えた。
ク「ほう、あなたにも興味がおありのようですね。これは嬉しい。わが公使館はあなたが祖国ロシアをこの上なく愛しておられるのをよく存じておりますし、私も祖国に忠実な人々を常に尊敬しております。かりにその人々の利害が私共の利害と相反するような場合でもね。しかしまあ、本題に戻りましょう。あなたもご承知の事情で、フォン・シュライヒャー将軍が急死してから……」
私「つまり、あなた方SS(ナチス親衛隊)がベルリンのアパートで彼を暗殺してからというわけで」クドルファーは咳払いしながら、私をさえぎった。
ク「どうお考えになっても結構です。どのみち、もはや昔話ですからね。肝心なのは、彼の死後その住居で大量の記録文書や書簡の類が発見されたことです。この書類はプリンツ・アルプレヒト・シュトラッセのわが本部や、ミュンヘンのブラウンハウス(ゲシュタポ本部)で綿密に調査しました。書簡の多くは総統(ヒトラー)が政権を担当される以前にドイツに来ていたソ連の将官だちからのもので、その中にトハチェフスキーのもあったのです」
私「で、その手紙には何か書いてあったというでんす?」
クドルファーはソファに深々と腰掛け直し、頬杖(ほおづえ)をつきながら云った。
ク「この手紙が本物だとすれば、元帥が本心からドイツを憎んでいるとは到底考えられません。彼は完全な“親独派“だと断言してもいい。おわかりですか? しかし、問題はこの書簡類が本物かどうかです。そこでですが、そのルーキンという男はウラングリ将軍のもとに寝返りを打つまで長いことトハチェフスキーのとり巻きだったというじゃないですか。とすればルーキンはトハチェフスキーの筆跡を見分けられるわけだ」
私はさえぎった。
私「それなら、ご自分でルーキンをお探しになったらいいじゃないですか? 私にどうしろとおっしゃるのです?」
ク「そこです。ルーキンはロシア語のほか片言のギリシャ語しかしりませんからか。それにあなたの親しくしておられるチェコの連中は、ルーキンが元帥の手紙は本物だと証言したらその内容に無関心ではいられないでしょう。確かあなたはチェコの新聞“フラーヘル・プレッセ”にも寄稿しておられる筈でしたね。そこで、ひとつあなたに“チェコの民主主義と自由の恩人”にして“偉大な汎スラブ古義の守護者”トハチェフスキーが、実はベネシュ一派が考えるような人物ではさらさらないというセンセーショナルな記事を書いて貰いたいのですが」
私「つまり、私にお宅の大使館の情報をチェコの新聞で宣伝しろとおっしゃるわけですね?」
ク「いや、ちょっと面白いもくろみをお話してしみただけですよ」
私「出て行って下さい!」と私は言下に云った。
これが利いた。クドルファーは弁解もせず、ドアの方へ歩いて行った。
ク「後悔なさいますよ」彼は捨てぜりふを残して立ち去った。 |
彼が私のオフィスのドアを、次いで玄関のドアを、さらに通りに面したくぐり戸を荒々しく閉めて行く物音がきこえた。
私はしばらく部屋の中央に突っ立っていたが、やがてソファの上に、クドルファーが「フォルキッシャー・ベオバハター」紙を置き忘れて行っだのに気がついた。
私はそれをまとめて、窓から外になげ捨てた。紙は突風に吹かれて舞い上った。
向うの山のうしろに、日が沈みかけていた。
クドルファーの訪問に私は戸惑った。ナチスはトハチェフスキーのことで何を企んでいるのだろう?
彼らが、トハチェフスキーはドイツの肩を持っているという噂を流したがっているのは何故だろう?
そしてまた、彼らがこの噂を特にチェコのベネシュ大統領の耳に入れたがっているのはなぜだろう?
その日以来、私はトハチェフスキーの運命について、特に注意してみるようになった。
私は彼のことを調べるために、彼に関係のある記録をできるだけ集めるよう心がけ、戦前バルカン諸国やドイツ、フランスなどに仕事で出かけた機会を利用して、トハチェフスキーに関する情報を持っていそうな人々を片っ端からインタビューするようにした。
私にはトハチェフスキーが親独感情を持っているとは到底信じられなかった。
私に最初の情報を与えてくれたのは、ベネシュの情報機関員としてジュネーブに来ていたウォルガーニンとネマノフ、これにブルガリア駐在ソ連大使をつとめたことのあるラスコルニコフであった。
最初にダリレビッチの策動とダンチヒでのラデックと二コライ大佐の密談を教えてくれたのはネマノフである。
今にして思えば、この密会こそある意味でトハチェフスキー劇の前奏曲となったといえよう。
シェルシュ・ミディの刑務所からベネシュの取巻きをたぶらかし続けたアレクセェフ、スコブリン将軍の古い戦友たち、ダリュー街の酒場でたまたま出会った人たち、プレビツカヤ夫人の幼友達など、いずれも私の調査に協力してくれた。
私は第二次大戦中も追究の手を緩めなかった。
アメリカに亡命中、私はたまたま、これも卜ハチェフスキー事件に深い関心を抱いていた文筆家のビクトル・セルジュがメキシコ・シティの「クエツァレス」社に送った手記の一部を手に入れた。
一九四五年、私は、従軍記者として欧州に舞い戻り、偶然のきっかけからウラジミル・ブルツェフのもとにあった書類を手に入れることができた。
ブルツェフは革命以前、有名なアゼフが実はツァーリの秘密警察の「挑発分子」であることを暴いた人物である。
ブルツェフと彼が発行していた新聞「共同の利益」は、白軍の将軍スコブリンの活動について何物にもまさる情報を提供してくれた。
もっとも、ブルツェフは注意を怠らなかったにもかかわらず、背後でいろいろな関係を結び、大きなパトロンを持っていたスコブリンの正体を最後まで見分けることができなかった。
しかし、ブルツェフの述べているところは、一九三八年十二月セーヌ県のアシズ裁判所で行なわれたプレビツカヤ・スコブリン裁判の時、明らかにされた事実と大部分一致している。
一九四六年従軍記者としてドイツに行った時、私はまたしても偶然の機会にダンチヒの密談の証人に出合った。
一方、私かポーランド筋から集めた情報の信憑性については、一九四六年夏ポーランド外務省情報局長ビクトル・グロン将軍がこれを保証してくれた。
最後に、私かRIS(「ロシア史的委員会」という白系ロシア人の団体で、本部は戦前パリのサン・ラザール街百番地にあった)の記録にあたってみたところでは、トハチェフスキーの有罪を証拠だてる文書を、ゲシュタポが偽造したのは、スコブリン将軍の差し金であって、スコブリン将軍は確かにゲシュタポとNKVDの二重スパイだったようだ。
その点については、SS(ナチス親衛隊)のシェレンベルク少将が、その回想録の中で述べているSD(親衛隊保安部隊)長官ラインハルト・ハイドリヒとの対話の内容から明らかである。
そこでハイドリヒは彼に自分が「偽の証拠」を捏造した理由と方法とを打ち明け、スコブリンがこれにどのような役割を果したかを話してきかせている。
ハイドリヒによると、この秘密を知っていたのはヒトラーとヒムラーと、ヘスとローゼンベルクだけだったということだ。
トハチェフスキー処刑の報をきいたヒトラーは、次のような歴史的な名文句を残している。
「我々はこれでツ連を少なくとも十年間中立化することができた。この十年の間に、全世界はわが手中に帰するであろう。その時こそ我々ぱ、スターリンとボリシェビズムに決算をつけてやろう。最後に笑うものが笑うのだ!」
このほかに、重要な証言をきかしてくれたドイツ人、か二人いる。一人は、OKW・T3(ドイツ参謀本部外国軍三課)の課長だったカール・シュパルケ将軍、彼は戦犯としてNKVDのルビヤンカに投獄され、一九五一年までトハチェフスキー事件について徹底的に取調べを受けた。
いま一人は、SD隊員だったナウトック中佐で、彼は私に「ナウトック、戦争に火をつけた男」という彼のことを書いた本を贈呈してくれ、彼がいかにトハチェフスキーをおとしめる「証拠」のでっちあげに手を貸したかを教えてくれた。
トハチェフスキー元帥の心理描写については、私は数多くの記録や証言をもとに、これを復元した。
たとえば、一九一六年インゴルシュタットの捕虜仲問だったレミ・ルールの本や、ド・ゴワ・ド・メゼイラック将軍の話は、十月革命前後の若い近衛士官トハチェフスキーの面影を蘇えらせるのに大いに役立った。
エフゲニー・ルーキン、アレクサンドル・バルミン、ラスコルニコフ、クリビッキー将軍、元ドイツ共産党軍事局長エリッヒ・ウォレンブルク、ジュヌビェーブ・タブイ、リディア・ノール(ザゴルスカヤのペンネーム)らの話から、さらに私は内戦時代から栄光の絶頂にあった頃までさかのぼってトハチェフスキーの面影を追求した。
そして、入手したすべての記録ならびに聞き込んだ諸々の証言から、私は「トハチェフスキーは無実だ」という確信をいよいよ深めるに至ったのである。
第二次大戦を目前にして赤軍を瓦解させた陰謀の謎を解き明かすのに四苦八苦しながら、私は「ドレフュス事件はさぞ大変だったことだろうな」と思わずにはいられなかった。
しかし、このトハチェフスキー事件はその重要性と結果において、とてもドレフュス事件の比ではなかった。
ドレフュス事件の場合はいんちき裁判で人種的な憎しみを充したに過ぎないが、トハチェフスキー事件の場合は、いんちき裁判のために第二次大戦の警鐘がかき消され、その結果、ロシア人千七百万を含む四千万の人間が犠牲となったのである。
モスクワ郊外ホデイソスコニの野原にある死刑囚の共同墓地に投げ捨てられたトハチェフスキーの遺体は、まさにこの第二次大戦の最初の犠牲者だったのだ。
トハチェフスキー元帥の悲劇は、スペイン内乱とともにこの世界的悲劇のほんの序幕にすぎなかったのである。
上述のような記録の援けをかりて、私は一九五九年、トハチェフスキー事件に関する本を書きあげた。
しかし、その後二年間というもの、この本を出版してくれようという出版社はついぞ見当らなかった。
いずれも「こんな話はありそうもないし、あまりに奇想天外過ぎる」という答えだった。
「あなたの本のように、この事件でウォロシーロフ元帥があんな役割を果したとは信じられない」とも云われた。
一九六〇年になって唯一つ、ローマの新聞「ジオルナーレ・ディタリア」だけが私の原稿を連載してくれた。
私の書いたことが「ありそうもないこと」でも「奇想天外」なことでもなく、逆に恐ろしく真実に近いことを世間が認めるようになったのは、ようやくソ連共産党第二十二回大会以降のことである。
ウォロシーロフ元帥はもはや国家元首(最高会議幹部会議長)ではなく、一介の「反党分子」であり、ひどいと云われた私のウォロシーロフに対する見方は、彼の旧友たちの云っていることよりずっと生ぬるかったことが明らかになった。
この事件が、モスクワで何千というソビエト代表や、全世界の友党代表を前に公然と述べられたのは、一九六一年十月二十七日のことである。
この日の党大会の席上、フルシチョフ第一書記のスポークスマンを買って出たアレクサンドル・シェレピン(NKVDの後身、国家保安委員会議長)は、次のように述べた。
〈ヤキール将軍処刑の日(トハチェフスキーその他エジョフの牢獄に捕われていた将軍たちの処刑と同日)、正確には一九三七年六月十目、悲運の将軍はウォロシーロフに手紙を書き、家族のものは無関係だから助けて欲しいと願い出た。
それに対しウォロシーロフ元帥はこう返事を書いた。「不誠実な人間の誠意を信ずるわけには行かない」と。
この死刑囚は同日スターリンにも手紙を送り、自分はあくまで誠実であり、党と共産主義とスターリンに対する信頼は少しも揺がないと訴えている。
ところが、この手紙の余白に次のような注釈が書き込まれているのだ。
「スターリン――ヤキールは下司で裏切者だ」 「ウォロシーロフ――全くだ」 「モロトフ――スターリンに全く同感」 「カガノビッチ――売国奴だ、豚だ」 「判決は?――死刑」〉 |
党中央委員会活動報告と共産主義建設計画をめぐる討議の結語演説で、フルシチョフは次のように述べた。
〈諸君はさきに同志シェレピンの報告をきかれた。
彼はいろいろと語ったが、もちろん、これまでに明らかにされたことすべてをしゃべったわけではない。
かにも何千という無実の人が殺されたが、それぞれのケースを語り出したら切りがない。
軍人もまた多数殺された。
この席では、すでに罪なくして斃れた多くの党指導者や政治家のことが、痛恨の念をこめて語られた。
トハチェフスキー、ヤキール、ウボレビッチ、コルク、エゴロフ、エイデマンその他の傑出した軍人も弾圧の犠牲者として斃れた。
彼ら、特にトハチェフスキー、ヤキール、ウボレビッチは有能な傑出した軍人だった。
彼らに続いてブリュッヘルその他の優れた軍首脳がこの弾圧の犠牲になった。
外国の新聞に、奇妙な報道がのったことがある。
それによると、ヒトラーはわが国に対する攻撃の準備を行なう一方、その情報機関を通じて、同志ヤキール、トハチェフスキーその他がドイツ参謀本部の手先だという偽造文書を流したが、この「極秘文書」がチェコ大統領ベネシュの入手するところとなり、ベネシュは明らかに善意から、これをスターリンに送ったというのだ。
ヤキール、トハチェフスキーその他の同志は逮捕され、まもなく銃殺された。
かくして、赤軍の傑出した司令官や政治工作員の多くが粛清された。ここに出席している代議員のなかにも――迷惑をかけたくないので名は云わないが――長年監獄に閉じ込められていた同志がいる。
彼らは特別の手口で、自分たちがドイツ、イギリスあるいはその他の国のスパイだったことを無理に「納得」させられてしまったのである。
なかには進んで「自白」したものもいる。
彼らは自分たちのスパイ容疑、が晴れてからも、いぜん自分たちはスパイだと云い張った。
早く拷問から免れて死なせてもらうためには、偽りの自白を貫いたほうがよいと考えたからである。
これがすなわち個人崇拝の意味するものである!
個人崇拝時代の誤ったやり方を復活しようとしたモロトフその他の連中の行動が何を意味するかと云えば、すなわちこれである。
反党グループは党をそこへ逆戻りさせようとした。
だからこそ、反党グループに対する闘争はかくも熾烈に、かくも仮借なく行なわれたのである。
反党グループに対するかかる闘争の意味は、いまやすべてのものに理解されている。
私は同志ヤキールをよく知っていた。
トハチェフスキーも知っているにはいたが、ヤキールほどではなかった。
今年、アルマ・アタで或る会議に出席した時、カザクスタンで働いているヤキールの息子が私に会いに来た。
彼は私に父ヤキールのことを尋ねた。しかし私が彼に何を話すことができようか?
我々が中央委幹部会でこの事件を調査し、トハチェフスキーもヤキールもウボレビッチも、誰一人として党と国家に対して何一つ罪を犯していないことを知った時、我々はモロトフ、カガノビッチ、ウォロシーロフの三人に尋ねた。
「君たちはこの人々の名誉を回復することに賛成か?」
「賛成だ」彼らは答えた。
「しかし、この人々を処刑したのはほかならぬ君たちなのだ。君たちが誠意ある行動をとったのは、その時なのか、それとも今なのか?」
彼らはこの質問には答えなかった。今後も答えはしないだろう。
諸君はさきに、彼らがスターリンにあてた手紙のなかでどんなことを云ったかという話をきかれた。
あんなことを云っていた連中が、いまさら何を云うことができようか?
大会演説で、同志シェレピンは赤軍内部のこれら最良の共産党代表たちがいかに粛清されたかを諸君に話した。
彼は同志ヤキールがスターリンに宛てた手紙を引用し、手紙に披瀝された彼の決意を読み上げた。
その時でさえ、ヤキールはスターリンを心から信じていたのだ。
ここで、ヤキールが処刑の時「党万歳! スターリン万歳!」と叫んだ事実をつけ加えてもいい。
彼は心から党とスターリンを信頼していたので、この不法行為が故意に行なわれたものであるとはとても信じられなかった。
彼は敵の手先が内務人民委員部に潜り込んだと信じていたのである。
ヤキールが最後の瞬間まで毅然としていたことを聞いたスターリンは、彼を口汚く罵った。
ここで、セルゴ・オルジョニキーゼのことを思い出してみよう。私は彼の葬儀に参列した。
私は彼が急死したという人の噂を本当だと思っていた。心臓が悪いことを知っていたからである。
しかし、本当は自殺だったことをたまたま知ったのは、ずっと後の、それも戦後のことだった。
セルゴの兄弟も逮捕の上、銃殺された。
同志オルジョニキーゼはスターリンの竹馬の友であり、党内で高い地位を占めていたにもかかわらず、もはやスターリンに協力することはできないと考えたのだ。
オルジョニキーゼはレーニンの知遇を得、彼から高く買われていた。
しかし、オルジョニキーゼがもはやまともに仕事ができないような事態が生じた。
彼はスターリンと事を構えたくなかったし、さりとてスターリンの権力乱用の責任を引き受けたくなかったので、自殺を決意したのである。
幾多無実の人々がこのようにして死んで行ったのである〉 |
周知の通り、この結語演説でフルシチョフ第一書記は、その「外国筋」が一体何者であるかは明らかにしなかった。
しかし、私の知る限りでは、当時、この件に関するまとまった文献で公表されているものと云えば、一九六〇年「ジオルナーレ・ディタリア」に掲載された拙稿をおいてほかになかった。
そしてローマのソ連大使館がこれに目をとめたことは疑いない。
一方、二十二回党大会の始まる半月ほど前、ソ連の著名な作家イリヤ・エレンブルグとフルシチョフの女婿で「イズペスチア」(政府機関紙)編集長のアレクセイ・アジュベイが、ローマで開催された東西関係に関する集会に出席したが、その際、この二人が「ジオルナーレ・ディタリア」に載ったトハチェフスキー事件に関する筆者の調査に目をとめたことも疑いない。
以上のようなわけで、私は、二十二回党大会でフルシチョフから提案され、万場一致で決議採択された「スターリン主義の犠牲者だものための記念碑」の建立に、ささやかながら一役買ったと考えている。
私は心からの平和主義者であり、米ソ間の和解以外、第三次世界大戦を回避する道はないと信じているものであるが故に、読者諸氏が本書を挑発の書と受け取られることなく、ある種の政治的手口に対する告発の書として受けとられることを願ってやまない。
歴史的な一大挑発行為ともいうべき事件の内容を明らかにしようとした私の目的は唯一つ、エジョフであれ、ヒムラーであれ、マッカーシーであれ、誤れるナショナリズムに目の眩んだ連中の政治組織が用いたマキアベリ流の手口の極限を、私と同世代のものに思い起させ、若い世代の人々に伝えることにあった。
第三帝国の崩壊、スターリンの死、ソ連の自由化とそれに続く科学技術面の驚異的発展を経て、我々は今や、あらゆる哲学的、社会的、道徳的観念の再検討を望み得る時代にさしかかっている。
「科学技術上の可能性が無限となれば、暴力はもはや進歩の手段、方法とはなり得ない」レーニンはH・G・ウェルズよりも早くこう云っている。
本書を執筆中、私の脳裡からは、ドレフュスを弁護したエミール・ゾラの面影が片時も消え去らなかった。
彼のひそみにならって、私もまた「何ものもこれを妨げ得ない真実の歩み」の前途に灯をともすべく努力したつもりである。
パリにて ビクトル・アレクサンドロフ
第一部 スターリンの陰謀
top
1 ヒトラーを叩け
2 「猿」ラデックの役割
3 毒殺魔登場す
4 クロンシュタットの亡霊
5 ダンチヒの密談
6 激怒するスターリン
7 最後の舞踏会
8 食人鬼エジョフ
9 葬送行進曲
10 パリの夜
1939年、世界をあっといわせた独ソ不可侵協定成り、晴れやかに握手を交わすスターリンとリッベントロップ独外相。
この瞬間のために、スターリンは赤軍の至宝トハチェフスキー元帥粛清の大陰謀を企み、続いて一大粛軍を断行したが、それがやがて、独ソ開戦初期にソ連の惨たんたる敗北を招くことになった。 |
 |
5 激怒するスターリン top
国防最高会議の秘密会は、ウォズビジェンカ通りにある、ウォロシーロフ元帥の事務所の広間で行なわれる習わしだった。
壁にはレーニンとマルクス、エンゲルスの肖像がかかっているだけだった。
部屋の中央に緑色のクロスをかけた長方形のテーブルが置いてあり、そのまわりに、最高国防委員十五人分の椅子が並べてあった。
部屋の左隅、ドアに近い方には別に十余りの椅子が置いてあり、これは政府や党政治局のお歴々など招待客用のものだった。
ルイ十八世風のウォロシーロフ元帥の椅子はクレムリン宮から持って来たもので、ひときわ異彩を放っていたが、床のベージュの絨毯はすり切れて、花や鳥の模様も消えかかっていた。
その日、最高国防会議議長(ウォロシーロフ)はやや遅れてやって来た。
きつい仕事や口やかましい妻エカチェリーナから逃れて自由になれるのは午後のほんの一時だけだったが、彼はその間国防人民委員部(国防省)に働いている若い美人秘書アンナ・イワノブナにうつつをぬかしていたのである。
アンナは黒髪の、すらりとした美人で、国防省で働いている婦人たちの聞でもひときわ目立つ存在だった。
その日、二人の密会はいつもより少々長引いた。
というのは、国防省の舞踏会用にアンナが新調したドレスに、元帥はすっかり魅せられてしまったからである。
彼女の瞳のように青い布地で、彼女のように清純な、しかもコケティッシュなドレスだった。
元帥はそれに見とれて、つい時間が経つのを忘れてしまった……。
彼は遅れて来たいいわけに、罪もない運転手を叱りつけてみせた。
エゴロフ元帥が口火を切り、簡単な報告を始めると、まもなく電話が鴾った。ウォロシーロフ(タリム)は受話器をとった。
タ「はあ……。会議は始まっております……。いえ、トハチェフスキーはまだ来ておりません。彼は最後にしゃべることになっているものですから……」
受話器からがらがら声が洩れた。ウォロシーロフの顔が曇った。
彼は頬を掻きながら、いかにも気遣わしげに云った。
タ「わかりました……。 エゴロフとブジョンヌイとブリュッヘルをつれてうかがいます……。 いえ、チモシェンコはウボレビッチといっしょにスモレンスクに出かけました」
彼は受話器を置きながら云った。
タ「今日の会議は延期する」
ウォロシーロフはブリュッヘル、ブジョンヌイ、エゴロフ三人の元帥を引き連れて、最近国防省が特別にアメリカから買い入れたリンカーンに乗り、クレムリンに向っだ。
スターリンはクレムリンの執務室に彼らを迎え入れた。秘書のポスクレブイシェフも一緒だった。
彼はポスクレブイシェフに速記の用意を命ずると、激しくまくし立て始めた。
ス「国防人民委員部はいつからソ連国内の独立国家になったんだ!? いったい誰が君たちに政治局の命令もないのに外交問題に口ばしを入れる許可を与えた!? 誰がトハチェフスキーに、ワルシャワやプラハやブカレストやパリの駐在武官を通じて、そんな探りを入れさせる許可を与えた!? どうして、在外公館が国防人民委員第一代理(国防第一次官)に報告書を送ってよこさなければならないんだ!? え、タリム(ウォロシーロフ)、君は自分のひざもとで何かおこっているのかも知らないのか!?」
タ「このあいだの政治局の会議で、トハチェフスキーの活動のことは、前もって君に云っておいたじゃないか!?君はあの時、別に反対しなかった筈だが……」
ウォロシーロフは抗弁した。
ス「私はそんなことは認めなかった」
「認めたも同然しゃないか、ヨシフ・ウィサリオノビッチー!」
ス「私の信頼を裏切りたいのか、タリム。それとも、君も陰謀団の一味か!?」
スターリンは立ち上って云った。
ス「第四号作戦の一環として、政治局でちゃんと話したじゃないか! あれは……」
タ「覚えてないね……。ああ、そうか! あのおかしな構想か、ポーランドとチェコがヒトラーと戦争を始めたら、これを援助し、最後には我々も介入するという……」
ス「なにがおかしいんだ? ピルスズキー(当時のポーランド大統領)はチェコのベネシュ(当時の首相兼外相、のちの大統領)とそのことでとっくりと話し合っているんだ」
タ「ああ、だが、それはいつのことだ? 一九三三年だろう。その頃はヒトラーはまだいなかった。その後、正確には一九三四年二月ポーランドはドイツと不可侵条約を結んだのを忘れたのか!?」
エ「一月ですよ、同志スターリン」 エゴロフが口を添えた。
ス「いや、絶対二月だよ、エゴロフ君」 エゴロフは困惑して黙ってしまった。
ウォロシーロフは、また説明し始めたが、スターリンはもはや聞いていなかった。
いらただしそうに紙挟みを開くと、何かの書類を取り出し、エゴロフ元帥の方に向き直って云った。
ス「失礼、同志エゴロフ。 リプスキー(当時のポーランド外相)とフォン・ノイラート(当時の独外相)がベルリンで問題の条約を結んだのは一月二十六日だった。 しかし、日付けは大した問題じゃない。 問題なのは、わが参謀本部の同志たちが愚かにもいまだにドイツ・ポーランド戦の可能性を信じていることだ。 いったい、ポーランド人が我々のために喜んで火中の栗を拾うほど馬鹿だと思うかね?」 誰も答えなかった。
スターリンはパイプをふかし、一息入れると、前より冷静になって話を続けた。
ス「たしかに、私は彼が戦略の立案ということだけだったら反対はしない。あらゆる場合に備えるのが当然だからね」
タ「だから、それだけの話だよ、ヨンフ・ウィサリオノビッチ」ウォロシーロフは口をはさんだ。
ス「まてよ、タリム。しかし、私はこの種の計画をことのほか重視するのは好まんよ。 殊にああ公然とやられたんではね。 あれでは、ドイツ側も対抗上計画を立てるだろうし、お互いにそれからそれへと対抗処置をとり、結局は軍事衝突を引きおこすことになるからね。 その場合、ポーランドが、我々の背後にまわって、いきなり匕首(あいくち)を突きつけてくることだって大いに考えられる。 私はピルスズキーがワルシャワでフランス大使のパナフューと会談した時のことを思い出す。 あの時、ピルスズキーは『ポーランドは二人の盗賊ロシアとドイツの間にはりつけにされたキリストみたいなものだ』と云ったそうじゃないか。彼が一番嫌っているのは我々なんだ」
タ「しかし、それはビルスズキーにとって、ヒトラーが権力を固める前にドイツを叩こうとベネシュ(注)にもちかけることまでやめにしなけりゃならない理由にはならない。 ためらったのはむしろベネシュの方なんだ」ウォロシーロフは答えた。
(注=エドワルド・ペネシュ(一八八四〜一九四八):マサリクとともにチェコ独立の父といわれたチェコ政治家。プラハ大学教授から転じて第二次大戦前外相、首相を歴任、一九三五年大統領となる。大戦中ロンドンに亡命、戦後連立政権の首班となり、四八年共産政権樹立で退陣。ドイツに対抗するため仏ソと手を結ぶ政策をとった)
スターリンはいらいらしながら云った。
ス「これは君には解しかねることなんだよ、タリム。しかし、ここでは君がまだ駐在武官たちの打診の結果を政治局に報告してないっていうことを指摘しておくだけにしよう……」
タ「だから次の月間報告でそれをやろうと思っていたところだよ」
ス「いや、それには及ばない。同志ヤーゴダがINO(内務人民委員部外国課)の報告を提出してくれたからね。私は君より詳しい。事態は深刻だよ。卜ハチェフスキーは外務人民委員部(外務省)の許可はおろか、これに通告もせずに、外交にかかわる各種の話し合いを強行している」
タ「しかし、リトビノフ(外相)には報らせてあるし、彼も了解している」
ス「確かかい、タリム?」
タ「もちろんだとも。リトビノフの手紙もちゃんと持っている」
ス「そうか。じゃあ、その手紙を私によこしたまえ。必要になると思うから………。私が背後で企まれている陰謀の息の根をとめようと決意する日にね。いいかね、陰謀を根こそぎにする日にだよ。対外打診をやっているのはトハチェフスキーやリトビノフの徒でも、党と国家に対してその責件を負わなけりゃならないのは私なんだからね。彼らには出過ぎたことだ!」
悪い方の手で、スターリンは話は打ち切りだという仕草をした。
将軍たちは敬礼し戸口の方へ去って行った。スターリンはウォロシーロフを引き留めた。
ス「ちょっと待てよ、タリム。君にもう一言だけ云っておきたいことがある」二人は座り直した。その間に秘書のポスクレブイシェフは姿を消した。
スターリンは外国の要人やジャーナリストの間でも有名な、例の穏やかな眼差しに返って云った。
ス「タリム、私は君が好きだし、君を困らせる気はなかったんだよ。ただ、今のことが、その無秩序ぶりが、たるみが気に障ったんでね。軍部を甘やかしちゃいけないっていうことは君も十分知っているだろう。君がちょっとでも甘い態度をみせれば、それでおしまいだ」
タ「そりゃ、君の考え違いだよ。トハチェフスキーは悪い奴じゃない。彼は知識はあるし、才能はあるし、それに善人だ。僕の云うことを信じてくれないか」
ス「神学校をやめてからもう三十年にもなるが、あの時以来、私には信ずるか信じないかは問題じゃなくなっている。馬鹿者は許しておけないんだよ」
タ「じゃ、彼にそう注意しておこう」 その時電話が鳴った。スターリンは受話器をとりあげた。
ス「ふむ、ふむ、イギリス国王が死んだと? 儀典課に私が弔電に目を通したいと云っていると伝えてくれ」
スターリンは受話器を置くと、ウォロシーロフの方をみながら云った。
ス「イギリス国王が死んだとさ」
タ「彼のためにはかえって仕合せだったんじゃないかな。少なくとも革命に会わずにすんだからね」
ス「しかし、あと継ぎが革命に会うだろうさ。それはそうと、さしあたって、誰かを葬式に行かせなけりゃならない」
タ「それなら、リトビノフが打ってつけだ」
ス「いや、彼じゃ十分じゃない。それに、私はユダヤ人をやりたくはないしね」
タ「じゃ、モロトフはどうだ?」
ス「いや、彼じゃもったいない。英国王の葬式など大したことじゃないからね」
タ「じゃ、アンドレエフなら……」
ス「あれは田舎者で、礼儀作法を知らない。やっこさんを王族や貴族の間に出せると思うかい?」
タ「じゃ、誰にする?」
ス「そうだな……。いる、いる。タリム、正真正銘の貴族で、しかもソ連の高官になっている男、礼儀作法を心得ていて、フォークの使い方もうまい男ならどうだい? わからないか? じゃ云おう。トハチェフスキーだよ。彼をロンドンにやったらどうだろう? 打ってつけじゃないか」
ウォロシーロフは答えなかった。なんと云ったらよいのかわからなかったのだ。
彼はずっと若い頃からスターリンを知っていた。そしていつも感心させられてきた。
しかし、これまでただの一度も本当に彼の気心をつかんだことはなかった。
その後、ロンドンに送るソ連代表団の構成について政治局で話合いが行なわれた時、スターリンは最初の心積りを変えて、リトビノフを主席代表に、卜ハチェフスキーを次席に任命した。
第二部 暗躍するナチスのスパイ
top
1 ナチスの犬
2 ヤーゴダの悪あがき
3 われらのミーシャ
4 二重スパイ・スコプリン将軍
5 どちらが裏切者か
6 口説かれたハイドリヒ
7 総統官邸のクリスマス・イブ
8 政治局での対決
9 セーヌ河岸の追跡
10 人の生命にかえても
11 アメリカ大使の報告
12 でっちあげられた「証拠」
13 二十万マルクの取引き
1936年ロンドンのウエストミンスター寺院で行なわれた英
国王ジョージ五世の葬儀。
トハチェフスキーは、ソ連代表団副団長としてこれに参加したが、同寺院に鳴り渡った弔鋒は、彼の政冶牛命の終りを告げる弔鐘であり、同時に全世堺に第二次大戦の間近いことを告げる不吉な警鐘だったのである。 |
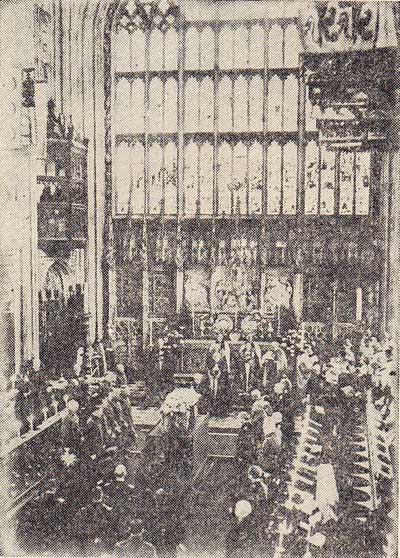 |
7 総統官邸のクリスマス・イブ top
歴史には有名なデッチあげの例がいくつも残っている。
ナポレオンがロシア侵入に先立ち捏造した、ピョートル大帝の「偽の遺言」もそうだし、一八七○年、ビスマルクが手を入れて発表したために普仏戦争が起こった「エムスの公文書」もそうである。
二十世紀ともなると、世論と議会と新聞とを一度にごまかすことは不可能なので、もはや「国書偽造」の時代は終りを告げかに思われた。
しかし、ヒトラーの全体主義国家や、スターリンの警察国家の誕生で、この手口は再び脚光を浴びるようになった。
かくして、発案者スミフリンの教唆を受けたハイドリヒはトハチェフスキー元帥に対する「中傷」だけでは足りない、もっと大がかりな手段を使って、トハチェフスキーの有罪を実証する文書を捏造しなければならぬと腹を決めたのである。
SD長官ハイドリヒの取り巻き、内相ヒムラーの部下、ゲシュタポ(秘密警察)、アルフレート・ローゼンペルクが創設したAPPARAT(特殊機関)などのうち、この捏造計画を報らされたのは、シェレンペルク、プリンツ・ワルデック・ピルモント、総統官房長ボルマン、総統本部長シュピツイなど極く僅かのものだけだった。
しかし、事を始める前に、ハイドリヒとヒムラーは、ヒトラーならびに副総統のヘスから許可をとりつける必要があった。一九三六年末という問題の時期に、ヒトラーとその取り巻き連中が何をしていたかを知るためには、ここで誰かひとり証人に立ってもらう必要があろう。
米第七軍「調査隊」とともにドイツ戦線に従軍したフランス軍大尉アルベール・ゾレルは一九三三年から四五年までヒトラーの秘書室に働いていた女性速記者を一九四五年に尋問した。
大尉はその際、この女性が次のように述べたことを明らかにしている(注)。
(注=ソレル大尉によるヒトラーの婦人秘書尋問の模様は一九四五年から四六年にかけスイスの新聞に度々報道されたが、なかでも「ウォヘンツァイツング」は次のように書いている。
「ハイドリヒがこの計画をヒトラーとヒムラーに提示したのは、一九三六年のクリスマス・イブのことだった。
彼はトハチェフスキーとドイツ軍の共謀を実証する証拠をスターリンに送れば、トハチェフスキーを消すことができると二人を口説いた」。
ドイツ軍最高司令部外国軍三課の課長だったシュバルケ将軍は、のちにこの事実を実証する記事を書いている。)
〈総統は宗教上の祝祭がお嫌いでした。
お祭が近づくと、総統はまるで、何百万人という人々が、このお祭や休みを楽しむくせに、ナチ党の祝祭の方は迷惑かっているとでも考えているように、不機嫌になられるのでした。
総統は特に、ドイツでは古い昔からの伝統となっているクリスマスが大嫌いでした。
私たち秘書室のものが、クリスマスーツリーを飾るのは大目にみてくれましたが、ツリーに灯りをつけることは絶対許されませんでした。
そして、クリスマスの間、いつも全然無関係の会合をやることにしておりました。
そのようなわけで、総統はよくミュンヘンの奇術協会会長を招いて手品をやらせました。
私たちもよくその準備を手伝わされましたが、総統はこの老奇術師を「世界的に知られており、ドイツの栄光のために貢献した人」と袮して、尊敬していたようです。
けれども、一度だけこの催しをとりやめたことがあります。
あれは確か一九三六年のクリスマス・イブのことでした。真夜中頃例の奇術師がやってくるというので、私たちは皆大広間で待っておりました。
そこへ思いがげなく総統とヘス副総統が入って来られました。
二人は話に夢中になっており、私たちがいるのも気づかないようでした。
私は総統のすぐ近くにおりましたが、その口からスターリンの名が何回も飛び出して来だのを覚えております。
総統は副総統にこんなことも云っておられました。
「私はスターリンに対しては個人的な恨みは一つもない……。あれは危険な野獣だが大胆な奴だよ!」
それから、総統は私たちのいるのに気づき、こう申されました。
「みんな、好きな処へ行って、クリスマスのお祝いをしなさい。私は今夜は忙しいから」
私たちは部屋を出ましたが、入れ違いにヒムラーやハイドリヒが入って来るのをみてびっくりしました。
クリスマス・イブに、これだけお歴々が勢揃いするなんてみたこともなかったからです〉 |
この秘書は見なかったが、そのあとでローゼンベルクもかけつけ、クリスマス・イブのその夜、まさにトハチェフスキーの運命と、戦争か平和かを決する劇的な会議がそこで開かれたのである。
ハイドリヒはこの席でヒトラーを口説き、例のスコブリンの奸計を実行する許しを得た。
トハチェフスキーとドイツ国防軍の関係を証明する記録を捏造し、この「証拠」をクリスマス・プレセントとしてエリコフとスターリンに贈り、彼らにトハチェフスキーとその同僚たちを粛清する口実を与える!
ローゼンベルクはヒムラーとハイドリヒのこのもくろみにすぐ賛成した。
しかし、ヒトラーに一番信任のあるヘスはなかなか承知しなかった。
そこでハイドリヒは「トハチェフスキー・グループの粛清はすぐ赤軍首脳部全体の粛清に発展し、その結果、赤軍の軍事力はゼロに等しくなる。
そうなれば、ソ連と協定を結ぶ必要はないし、秘密交渉を即座に中止して、まずソ連を叩くことができる」とヘスの説得につとめた。
ハイドリヒは、自説を裏付けるためにこんなことも云った。
| 〈トハチェフスキーを叩いておかなければ、反独感情に凝り固まった彼は、我々の再軍備が完了しないうちに、わが第三帝国に対する予防戦争を仕掛けて来る恐れが多分にある……(注1)〉 |
ハイドリヒはこの会議を極秘にしておくようヒトラーに上奏した(注2)。
ハイドリヒの率いるSDやシェレッペルクの率いるゲシュタポのうち、この会議のことをきかされたのは、トハチェフスキーの有罪を実証する「証拠」を捏造し、モスクワに送り込むためにスコブリンと連絡をとらなければならないベーレンス(SD次長)、ヘットルなど極く少数の当事者だけであった(注3)。
偽文書作成を指揮する特別の委員会『3H委員会』(ヘス、ヒムラー、ハイドリヒ)の設置が決まったのもその夜のことであった(注4)。
(注1=ライトリンガー著『ハイドリヒとナチ親衛隊』参照)
(注2=この会議は極秘に付されたため、ドイツ国防軍首脳にも全然知られなかった。当時国防軍首脳に近かったカール・シュパルケ将軍はこう書いている。
「一九三六年秋のトロツキスト裁判の時、トハチェフスキー元帥の名が出てすぐ消えたのに驚いてモスクワ駐在武官のケストリング将軍に問い合せたところ、将軍は『トハチェフスキーの件だって?彼は安泰だよ。落ち着いて、つまらぬ妄想はやめたまえ』と答えて来た」
なお、クリスマス・イプの会議にはゲーリングとフォン・ノイラートは出席しなかった)
(注3=戦後一九四六年ヘットルは「秘密戦線」という本を書き、その中で偽文書作成の件につき述べている。一方、ベーレンズはセルビアのSS長官として戦後ユーゴスラビア側に逮捕され、戦犯としてベオグラードで処刑されたが裁判の際トハチェフスキー元帥を失脚させるための偽文書作成につき、一切を目白した。この供述書はモスクワのベリアのもとに転送され、いまでもソ連の国家保安委員会の書庫に収められている筈である)
(注4=ドイツ国防軍最高司令部外両軍三課の課長だうたシュパルケ将軍はこの点につき次のように書いている。
「一九三七年夏、参謀本部の高官の一人が私に『トハチェフスキー事件についてきかせて欲しい、ハイドリヒがトハチェフスキー失脚の筋書をつくったという話だが』とたずねてきた。彼は赤軍首脳部を解体させたのは自分だと、ハイドリヒが話したということを、SSの連中からきいたのである」)
ヒトラーはこの計画を全面的に承認すると、3H委員会の活動を特に重視し、ハイドリヒに、三人が考え出した段階について自分の承認を求めたい時には、いつでもやって来てよろしいという許可を与えた。
一方、国防軍情報部長カナリス提督はこの計画を全然報らされなかった。
ハイドリヒはカナリスがイギリスの情報機関と関係があるとにらんでいたからである。
しかし、ベーレンスとしては偽文書を捏造するのに、どうしてもその土台となる本物をいくらか手に入れておく必要があった。
しかも、その本物は国防軍最高司令部の「外国軍三課」(赤軍担当)と、国防軍情報部に蔵ってある。
したがって、ベーレンスとしては、たんとかカナリスを出し抜かなければならなかった。
その方法は?
一九三七年一月始め、カナリス提督は副総統ヘスから、かつてのドイツ国防軍と赤軍との関係を示す文書をそっくりハイドリヒに提供するようにとの極秘の書簡を受取った。
これらの文書の中にはかつての独ソ秘密軍事協定により交換将校としてドイツに来ていたソ連将校の名簿、彼らのドイツ国防軍内での活動記録、彼ら自筆の報告書などが含まれていた(注)。
(注=この点に関するベーレンスのベオグラードでの自白はピーター・クライスト著『ヒトラーとスターリンの間』の次の文章とほぼ符合する。
「当時、国防軍の首脳部ではバイトリヒがカナリスに旧独ソ秘密軍事委員会のメンバーだったソ連将校たちのサインの見本を提供しろと要求したという噂がもっぱらであった。トハチェフスキーとその同僚たちがこの委員会のメンバーだったことは言うまでもない」)
ヘスの書簡は、特にトハチェフスキー元帥に関する記録をできるだけ早く、遅くも一九三七年二月一日までに提出するよう指定してあった。
事実トハチェフスキーはナチスが政権を握る前、ソ連将校団の一員として度々ドイツに来ていた。
なかでも、一九二三年、彼はピアタコフの率いる六人の「特別」グループの一員として、ドイツ革命が成功した場合、ドイツ「赤衛軍」の指揮をとる目的でドイツに来たことがある。
この一団はその時、ウンター・デン・リンデン七番のソ連大使館に陣取っていた。
一九二三年十一月末、ドイツ革命が失敗に終ったことが明らかになると、ピアタコフは五人の軍人を引き連れてベルリンを離れた。
しかし、トハチェフスキーだけはベルリンに残り、クレスチンスキー大使のもとで、赤軍最高司令部の「連絡将校」として独ソ秘密軍事協定の下準備をすることになった。
しかし、クレスチンスキーとそりが合わず、結局二ヵ月後に自ら求めて帰国した。
トハチェフスキーは、前後五回ドイツにやって来た。そのうち二度は、「独ソ委員会」の一員として、一九二二年から二五年に至る赤軍と「陰のドイツ国防軍」との秘密協定の実施を監督するため、一度はこの秘密協定に従って実際にドイツ軍に加わって指導に当るためであった。
そのほか、一九二六年から三二年にかけても二度ドイツを訪れた。
こうした滞在中に、彼が種々の記録を残して行ったことはもちろんである。
そして、自筆の手紙、報告書、領収書、その他もろもろの書類がカナリスの書庫に収められることになった。
ハイドリヒが、何とか不審の念を抱かせずに、カナリスから手に入れたいと思ったのは、まさにこの書類だったのである。
カナリスは洞察力もあり、怪しいと思わないほど未経験でもなかったが、まさか、ハイドリヒが文書偽造を画策しているとは思わなかった。
ハイドリヒのこのマキアベリズムは、第一次大戦中逆情報活動で輝かしい功績を残したカナリスにも、あまりに常軌を逸しているので、さすがに想像がつかなかったのである。
カナリスは、ゲシュタポが軍の高官、恐らくシュライヒャー・グループのだれかの身許をもう少し洗う必要に迫られているのだろうと想像した(注)。
(注=一九三四年反ナチ陰謀という理由でシュライヒャー前首相が暗殺された時、SS黒シャツ隊とゲシュタポは同将軍のもとにあった文書や記録の一部を掠奪して行った)
そこでいい加減な口実をつくって、ヘスの要求する記録の提供を引き延し、できるだけハイドリヒの陰謀を邪魔してやろうと決心した。
ヒトラーの官房長マルチン・ボルマンが動き出しだのは、これからである。
彼は「3H委員会」のボスにおさまり、カナリス提督が提供を拒んでいる例の記録をものにする計画を立案した。
第三部 ソ連軍の悲劇
top
1 妻への疑惑
2 きみはナポレオンの器じゃない
3 猫なで声の夜の電話
4 ウォロシーロフの変節
5 昨日の英雄も今日は廃物
6 死の独房の中で
8 幻の女スパイ
9 証人たちの末路
10 世界の悲劇
第二次大戦前、世界最強を誇ったソ建軍の首脳部を固める五人の元帥。
左から、トハチェフスキー、ブジョンヌイ、ウォロシーロフ、ブリュッヘル、エゴロフ。
スターリンの粛軍と国防相ウォロシーロフの変節のため、このうちまずトハチェフスキーが粛清され、続いてブリュッヘルとエゴロフも姿を消し、中軸を失ったソ連軍は戦わずして潰滅状態に陥った。 |
 |
5 昨日の英雄も今日は廃物 top
エジョフがスターリンに「証拠物件」を手渡してから二日後の一九三七年五月二十日トハチェフスキー元帥はモスクワ駅頭からボルガ軍管区司令官として新しい任地に向かおうとしていた。従者は副官のミロノフ大隊長ひとりだった(注)。
(注=ミロノフ大隊長は、トハチェフスキー逮捕後極東に配転された。さらにレニングラード軍管区に転任させられたが、一九三九年、フィンランドとの戦争中捕虜になり釈放後、フィンランドを去って南米に移住した)
国防省の同僚たちは誰ひとり見送りに来なかった。
トハチェフスキー左遷の噂は野火のようにモスクワ市中にひろまっていた。
五月十七日、党中央委員会と政府が軍管区司令部にかわる「三人委員会」を設けるという布告を出した時、すでに世間ではこの布告を「トハチェフスキー政令」と呼んでいた。
この布告が元帥とその同僚目当てに出されたものであることは、火をみるより明らがだったからである。
トハチェフスキーは、巻添えになるのを恐れて駅へ見送りにやって来なかった人々を、別に恨む気にはならなかった。
はっきり知っているわけではないが、彼らがもはや自分たちの思い通り動きまわれる身柄でないことは、凡そ察しがついた。
しかし、一九二〇年の対ポーランド戦中第十六軍の有能な将校で、ワルシャワの戦闘の時負傷した駅長のマルコフだけは勇敢にも彼を見送ってくれた。
マルコフはトハチェフスキーを急行列車に連結された専用客車のところまで見送り、しばらく雑談した。
この厚意に感激した元帥は駅長に、パジャマを忘れたから妻に電話してくれないかと頼んだ。
その落着きぶりにマルコフはすっかり驚いてしまった。
列車はやや遅れて出発した。発車間際に「鉄道公安官が三名」元帥の専用車に乗込んで来たが、「道中の安全を確保する」という名目で、ボルガ軍管区司令官専用車に同席する許可書を持っていたことは云うまでもない。
トハチェフスキーはちょっと意外な顔をしたが、別に気にするでもなく、彼らに車内の一室を与えた。
その夜の夜景は美しかった。まさにロシアの春の夜だった。一週間あまり雨も降らなかった。
満天の星が劇場の天井の灯のように輝いていた。元帥は寝る前に一仕事することに決めた。
ボルガ地方の住民による「予備軍」の動員計画を詳しく研究しておきたいと思ったのである。
この予備軍は敵がソ連領深く侵入して来た場合、活用することがである。
(因みにこの予備軍は一九四一年十月から十一月にかけて動員され、モスクワ防衛戦に勝利をもたらした)
トハチェフスキーはオカ、ボルガ、カマ三河にまたがる地域に住むほとんど無尽蔵の人的資源を活用するこの計画の推進者であった。
彼が新しい任務をやすやすとむしろ喜んで引き受けたのは、すでに一九三二年から唱えていたこの計画を現地で磨きあげることができると思ったからである。
朝になった。元帥は起上って車室のカーテンをあけてみた。外は晴れていたが寒かった。
列車は深い森の中に停っていた。人影も建物もない、貨車が木材の積み降ろしをやる貨物駅の前だった。
白樺や樅(もみ)や樫(かし)の丸太が線路の際まで伝み重ねてあった。あたりは物音一つしなかった。
元帥は車室の壁を叩いた。副官の返事はなかった。廊下に出て洗面所の方へ行ってみた。誰もいなかった。
客車は緑の沙漠のような深い森の中に置き去りにされているようだった。
しかし、それは見かけだけで、実はNKVDの制服に身を固めた連中が、参謀長の肩書を持つ将校の指揮のもと、車の出入口という出入口を見張っていた。
彼らは内務人民委員代理フリノフスキーの命令を受けていたのである。
トハチェフスキーが出入口に姿をみせるや例の将校は下から敬礼し、客車に上ってきて元帥に姿がみえなくなった副官の車室に来るよう伝えた。
ト「ミロノフ大隊長はどうした? 君は誰だね」
トハチェフスキーは尋ねた。
その将校は再び敬礼して答えた。
将「ミロノフ大隊長は途中で下車しました。自分はNKVDのもので、閣下の保護を命じられておる者です」
ト「ここはどこだね?」
将「〈山賊〉という停車場です。閣下の客車はNKVD次官の命令で列車から切り離されました。自分はどのくらい車をここに止めておくのか存じません。いずれにしても、四日分の食糧は用意してありますから」
ト「私は逮捕されているのかね?」
将「そのような命令は受けておりません。しかし、閣下が車を離れることは許されません。これは正式の命令です」
トハチェフスキーは肩をすくめた。
ト「それでは結局、逮捕されているということではないか。国防相は事前に通告を受けたのかね?」
将「その点は何も存じません。自分は上司から閣下を車内に足留めしておくよう命ぜられたのです。ほかのことは自分の知ったことではありません」
ト「武器は持っていてもいいのかね?」
将「いえ、閣下を武装解除するよう命令されております。車室を捜査して、武器ならびに文書を一切押収せよとの命令も受けております」
ト「しかし、私にはウォロシーロフ同志の正式の命令を受けずに、国防省の秘密書類を君に渡す権利はないよ」
将校はポケットから紙切れを取出した。
将「同志エジョフの署名入りの令書です。同志スターリンの特別秘書の認証も得ております。これでも不足ですか?」
ト「私は共産党員だよ、同志参謀長」
元帥は所持していた二丁の拳銃と、四枚の秘密書類を渡した。
将「ありがとうございます、同志閣下。無理を云わなければならないのは何とも心苦しいことです。自分もポーランド戦線に出征し、当時は閣下の部下でしたから」
トハチェフスキーはしげしげと相手を見た。三十五、六の男だった。相手は心得たように、
将「ブレスト・リトフスクでポーランド軍と戦った時、自分は十九でした。自分はワルシャワ近郊のジョゼフォンで偵察任務中負傷致しました……」
将校が引き下ってから、元帥は自室にひとりこもっていた。事態はもはや明々白々だった。しかし、最後まで彼には自分が逮捕されるなどとは信じられなかった。
午後、元帥はさきほどの将校を食事に招いて雑談した。驚くことばかりだった。
夢想家の将校はぶっきらぼうにこう答えた。
将「現代は革命の時代であります。昨日の英雄も今日は廃物になる。これが歴史の弁証法というものです、同志閣下」
(元帥の出発を見送ったものに、マルコフ駅長のほか、一九一八年来元帥の運転手をつとめてきたイワン・フョードロビッチ・クドリアフツェフがいる)
9 世界の悲劇 top
トハチェフスキー元帥はじめ、赤軍の将星たちが粛清されてから十一年、長らくモスクワに駐在し、この事件に通じているといわれたニューヨーク・タイムズ紙のウォルター・デュランティは、一九四一年に出したその著書の中で、この事件をこんなふうに解説している。今になってみれば、とんでもない見当違いなのだが……。
〈トハチスエフスキー元帥はじめ赤軍首脳部の一部将軍たちは、スターリンの軍に対する干渉に我慢できなかった。
両者の争いは激しくなるばかりで、遂に数ヵ月後、トハチェフスキーは武力行動に訴えてこれに決着をつけようと決意するに至った。
ラッパロ条約の結ばれた一九二二年からヒトラーの抬頭に至る十年間、ソ連軍とドイツ軍との関係は極めて親密だった。
二〇年代の終り頃、ドイツ国防軍参謀総長フォン・ハンマーシュタイン将軍がキエフ方面で赤軍演習の指揮をとったことがあるほどだ。
そんな関係で、トハチェフスキー元帥、ガマルニク大将らは、スターリン打倒のクーデターないしは「宮廷革命」実行の際には支持してくれるようハンマーシュタイン将軍に依頼した。トハチェフスキー元帥らはクレムリンの親衛隊と士官学校の生徒たちを使ってクーデターを決行しようとした。
大体、彼らは一般将兵や国民を軽視しており、だ。
からこそドイツに支持を求めたり、その代償にウクライナやコーカサス北部の経済的、政治的権益を与えようなどと云い出すことができたのである。
これに対し、クレムリン側は迅速かつ精力的な手を打った。一九三七年六月始めトハチェフスキーほか七人の将軍たちが逮捕され、これまでの粛清裁判では数週間否数ヵ月にわたる大がかりな予審、が行なわれたのに、彼らの裁判は僅か三日ですんでしまった。
ガマルニク大将は逮捕の前夜自殺した。ほかの粛清裁判同様、この裁判もソ連最高裁判所軍事法廷で行なわれたが、二つだけ大きな違いがあった。ひとつはこの裁判がほかと違って非公開だったこと、もう一つはいつもの三人の判事のほか、赤軍の高級将校八人か判事として加わったことである。
この裁判には各地から有力な軍人が百名以上も出席して一役買った。被告たちはいずれも罪を認め、死刑を宣告された。処刑は判決後四十八時間以内に行なわれた。
ソ連の秘密警察はトハチェフスキーがチェコの情報機関の仲介でプラハとベルリンに行った時ドイツ軍参謀総長との間に交した話の内容を、キャッチしたようだ。
プラハでトハチェフスキーはヒトラーがチェコに侵入した場合の対策を打ち合わせるためにベネシェ大統領(当時外相)や軍司令官シロビ将軍らと会見したが、この会談には書記を置かず、従って記録も全然とらなかった。
ところが、トハチェフスキーがペルリンに行ってから、ベルリンのチェコ情報機関が、トハチェフスキー・ベネシュ・シロビ会談の内容がドイツ軍首脳部に筒抜けになっているという情報をプラハに伝えて来たのである。
ベネシュはその内容があまりに正確だったので、これはてっきりトハチェフスキーが情報をドイツ側にもらしたものに違いないと考えた。
ペネシュが卜ハチェフスキーとクレムリンのいざこざに一役買ったというのはちょっと信じ難いことのようだが、卜ハチェフスキーがプラハ秘密会談の内容をドイツにもらしたというので頭にきた彼はチェコ情報機関がキャッチした情報をすぐさまモスクワに伝達したのである。
このためベルリンからロンドンに行ってジョージ六世の戴冠式に出席することになっていたトハチェフスキーは急抛モスクワに呼び戻され、モスクワ到着と同時に逮捕されたのである〉 |
新聞記者のデュランテイばかりではない。アイザック・ドイッチャーのような歴史家までがSDとNKVDがなれ合いで仕組んだこの芝居を額面通りに受け取っているのは驚くほかない。彼はその著「スターリン」のなかでこんなふうに書いている。
〈トハチェフスキーの陰謀とその失敗をめぐる正確な事情は明らかでない。しかし、スターリン筋以外のあらゆる見方をつき合わせてみると、いずれも次の点では一致している。
すなわち、将軍たちは実際にクーデターを計画していた。
そして、それはまったく彼ら自身の発意によるもの、しかも彼ら自身のまったく個人的な理由によるものであって、外国勢力との関係は皆無である。
このクーデターの主舞台はあくまでクレムリン内に置かれる手筈になっていた。
一種の宮廷革命によってスターリンを暗殺することがねらいだったのである。
もちろん、NKVD本部の攻撃というクレムリン外での軍事行動も計画されていたが………。
そしてこの陰謀の中心にトハチェフスキーがいたのだ〉 |
スターリンは胸をなでおろすことができた。彼のねらいは図に当った。
政治家も外交官も新聞記者も彼の思惑通りの反応を示し、自分がヒトラーと手を結ぶのに一番邪魔になる赤軍の反ヒトラー派の将軍たちを難なく片づけることができたのである。
こうして束の間ながら、独ソ協調の時代が始まった。一九三九年八月独ソ不可侵条約が結ばれ、翌九月ヒトラーがポーランドを攻撃するや、スターリンはポーランドの残り半分を占領した。
同十月三十一目、当時首相をしていたモロトフはソ連最高会議の席上
「我々とドイツとの関係は根本から改善されている。我々は常に強力なドイツの存在は欧州の平和安定に欠くべがらざる条件であると考えてきた」
と語っている。
とにかく、トハチェフスキーらの処刑からヒトラーのソ連侵入まで、スターリンは一時的なものとは知りながら独ソ協定に安住していたのである。
しかし、ここでは自己流の判断はやめて、現代の最も権威のある証人フルシチョフ・ソ連首相がソ連共産党第二十回大会で行なった発言に耳を傾けることにしよう。
スターリンという一個人の手に集中された権力は大祖国戦争(第二次大戦)中、重大な結果を招くことになった。
戦前、我々の新聞や政治教育機関は口をひらけば
「もし敵が神聖なソ連の大地を犯すようなことがあれば、敵の一太刀に対してわが方は三太刀報いる。我々は大した損失もなく勝利を収め、敵の領土内で相手を撃滅する」
などと空威張りしていた。
しかし、こうした大言壮語には少しも現実の裏づけがなく、もとよりこれで国境の安全が保障されるわけでもなかった。
戦時中から戦後にかけて、スターリンはソ連が緒戦であのような悲劇を味わったのは「不意討ち」の結果だと主張した。
しかし、この点に関する戦前の事実をつぶさに調べる時、ヒトラーはソ連に対し戦争を仕掛けることしか念頭になかったこと、そのため強大な機械化部隊をソ連国境方面に集結させていたことは紛れもない。
チャーチルも駐ソ大使クリップスを介してスターリンに、ドイツは軍事力の再編をやっているが、これはソ連を攻撃するためだと警告していた。
ところがスターリンはこれに一顧も与えなかったばかりか、ドイツを挑発するといげないからといって、この種の情報を本気にしないように命令しさえしたのである。
こうしたとびきりの警告があったのに、彼は祖国を防衛し、侵略を阻止するのに必要な準備さえ行なわせなかったのである。
ナチの軍隊が現実にソ連領に侵入し、軍事行動を開始しているのに、それでもなおモスクワはこれに発砲するなと命じていたのである。
なぜか。事実の示すところによれば、スターリンは戦争はまだ始まっていない。
それはドイツ軍中の軍紀違反の連中が仕組んだ挑発行為に過ぎず、もしこちらが反撃すればドイツ軍に宣戦の口実を与えることになると考えていたからである。
その後のことも明らかになっている。ヒトラー軍のソ連侵入の前夜、あるドイツ人がドイツ軍は六月二十二日午前三時にソ連に攻撃を開始せよとの命令を受けたという報らせを持って越境してきた。
この情報はすぐさまスターリンに伝えられたが、彼はこれも黙殺した。
この呑気な態度、紛れもない事実の軽視はどのような結果を招いたか。
その結果は開戦後数日、否数時間の間にわが方は国境地帯で飛行機、大砲、その他軍需品などを大量に失うことになったのである。
多くの精鋭を失い、隊伍は支離滅裂になってしまったのである。
敵がソ連領深く侵入するのを阻止できなかったのもそのためである。
この最後の情報をもたらしたドイツ人というのはウィルヘルム・コルピクという古くからの共産党員で、彼の所属する部隊に攻撃命令、が伝わった時、ソ連に脱出してきたのだが、スターリンは彼の決死の情報に耳をかさなかったばかりか、「脱走兵、デマゴーグ」の罪で即座に銃殺させてしまった。
しかし、もしかりにこの最後の警告をスターリンがききいれていたところで、もはやすべては手遅れだったろう。
スターリンがトハチェフスキーのヒトラーに対する予防戦計画を拒否し、トハチェフスキーらを銃殺した時、すでにソ連国民はドイツの侵略で塗炭の苦しみをなめる運命におかれていたのである。
ヒトラーの侵略にソ連は多大の犠牲を払った。戦争で死んだソ連国民の数は千八百万、そのほか全世界で三千三百万の老若男子が命を落とした。
このような悲劇のあとで、誰が一人の男の悲劇などをごてごて話していられようか。
しかし、トハチェフスキー元帥の短い生涯とその死は、まさに一国の、一世代の、否全世界の悲劇につながっていたのだ。
top
**************************************** |