|
****************************************
Index 序章 一章 二章 三章 四章 五章
Ⅴ すべてが語り尽くされる頃
1 死のさまざまな影
1.1 むなしい願い
1.2 エリノアとフランクリン
1.3 秘められた女性
1.4 ロンメル、自決を選ぶ
1.5 エバとアドルフ
1.6 ベネツィア宮の情事
1.7 湖畔の暗い午後
1.8 墓標なき墓場 |
2 米英ソ大同盟の最後の歩み
2.1 ベルリン攻略
2.2 ヨーロッパ勝利の日
2.3 幻滅
2.4 原爆誕生
2.5 広島、長崎、さらに……
2.6 終戦という敗戦
2.7 マッカーサー、厚木に着く |
|

戦争終結を報じる「朝日新聞」昭和20年8月15日
大詔(おおみことのり=天皇のお言葉)渙発(かんぱつ=発布)さる
|
1 死のさまざまな影 top
1.1 むなしい願い
大戦当時まで孤立主義を続けてきたアメリカは、ヨーロッパの実情と距離を保っており、イデオロギーのうえではともかく、直接の現実的利害関係ではソ連とまだ対立していなかった。
そしてルーズベルトは米英ソ三国の友好関係を今後の世界平和の条件としており、とくに国際連合を成立ざせるため、ソ連の協力を必要としていた。
しかも大統領は個人的にもスターリンに親近感を抱くとともに、自信過剰とみえるほど、この独裁者を左右し得ると思い、さらに国際機構によってソ連の動向を制御できると考えた。
しかしヤルタ会談後、ポーランド問題など、ソ連の東欧政策は米英の期待を裏切るようにみえた。
これに不満なルーズベルトはスターリンとの話し合いに望みをかけていた。大統領は自分の努力によって解決できると思い、そのためにはモスクワに行って、スターリンと会見してもよいと考えていたようである。
それが永遠に実現しないことになろうとは知らずに――。
ルースベルトは一九四四年一一月四選され、アメリカ史上、最長の任期を務める大統領であったが、大戦中、彼は病める身であり、それは動脈硬化症が昂進したものとみられる。
大統領はすでに集中力を欠き、睡眠時間も長くなり、やがて煙草に点火するときに手もとが狂ったり、話を聞きながら居眠りしたりするようになった。
そしてヤルタではチャーチルはじめ、大統領の健康を気遣う者は少なくなかった。
疲労の影が濃く、血の気がない顔色で、衰えが目立つ場合もあった。
チャーチルの侍医モランはルーズベルトの脳動脈の硬化に気づき、数ヵ月の生命とさえ判断していた。
ヤルタから帰ったのち、大統領の健康はやや回復したが、それにしても参謀総長ジョージ・マーシャル元帥――チャーチルが「勝利の真の組織者」と呼んだマーシャルが、事実上の執務に当たる状態であった。
そしてルーズベルトのスターリンに対する不満は、しだいに強くなってきたとみえる。
一九四五年四月六日付、チャーチルあての通信のなかに「我々は恐れているという誤った印象を、誰にも与えてはならない」とあり、四月一一日付(大統領の死の直前)のものにはチャーチルに同調しつつ、ポーランド問題で強い路線を保とうとする気持ちが察せられる。
スターリンは確かに大統領を重んじていたが、ソ連の国益にかけて果たして譲り得たであろうか。
親ソ的なルーズベルトが健在であったとしても、米ソ関係の悪化は避けられなかったであろう。
とすれば、「自由の戦士」ルーズベルトが反共政策に転じざるを得ない情勢の進展を前にして、死はまた人を救ったのであろうか。
いや、米ソ対立が生じたとしても、この大政治家は彼の後継者よりも巧妙な対応を示して、戦後の「冷戦」の展開に違った様相を与え、あるいはその深刻化を防ぎ得たであろうか。
一九四五年四月のフランクリン・ルーズベルトの死を想うたびに、たとえば一九二四年一月のウラジミール・レーニンのそれのように、歴史における個人、その生死が左右するところを問わざるを得ない。
1.2
エリノアとフランクリン
一九四五年四月一二日の昼頃、ルーズベルトのなじみの保養地ウォーム・スプリッグズでは、明るい陽光がさんさんと降り注いでいた。
この地の邸宅で、三月末から静養中の大統領は自分の肖像画のために、いま、女流画家エリザペス・シューマトフのカンバスの前に腰をおろしている。
冗談をとばしながら絵筆が進むままに任せていた彼は、午後一時一五分頃、急に低くうめいて手を頭に当てた。彼は激しい頭痛を感じている様子であったが、すぐに気を失って倒れた。
ベッドに運ばれてから一度も意識を回復しなかった大統領の死は、午後三時三五分、医師によって告げられた。
このときルーズベルトは保養がてら、近づくサンフランシスコ会議の開会演説の草稿を作る予定であった。
そして彼はその会議のあと、夫人同伴でイギリスを訪問するつもりで、彼女に衣服の新調をすすめていた。
戦時中、渡英は危いと自重を促す側近に、大統領はヨーロッパでは五月の末までに戦争は終わるだろうと言った……。
ルーズベルトが倒れたとき、その傍に一人の女性がいた。
しかし夫人エリノアではなかった。
「おそろしく頭が痛い」――この最後のつぶやきが聞きとれたか、どうか、ともかく彼の最期を見つめていたのはその女性であった。
そして彼女はただちに屋敷を去り、死者の枕頭(ちんとう)には無論、葬儀にも姿は見られなかった。
一九〇五年、ときの大統領セオドア・ルーズベルトのめい、エリノアと結婚したフランクリン・デラノ・ルーズベルトはおそらくは一九一六年、妻の秘書ルーシー・マーサーを愛するに至った。
彼は当時、三〇歳代の半ばに近く、ハンサムでレディー・キラーの海軍次官補であった。
小児麻痺の発病は一九一二年である。
エリノア夫人が二人の仲を知ったのは一九一八年秋、何気なく夫あての手紙類を整理していた折という。
気丈な妻は離婚か、さもなくばルーシーと別れることを条件に、形だけの結婚生活を送ることを迫った。
家名を重んじ、経済上の実権を握る母の反対、政治生命への配慮、子供たちに対する愛情などは、ルーズベルトに離婚を許さなかった。
ここに「あるアメリカの悲劇」が始まった。
情事が発覚してから夫の死に及ぶまで、ルーズベルト夫妻の幸福そうな結婚生活は世間体だけのもので、おそらくは通常の夫婦生活はついに営まれなかった。
裹切られた妻の意志が固かったからである。
それは理想的夫妻の演技であったが、夫はそういう妻を敬(うやまう)ことこそすれ、愛することはむつかしかった。
1.3 秘められた女性
一九二○年、ルーシー・マーサーはかなり年上の富豪、男やもめのビンスロップ・ラザファードと結婚した。
一子をもうけ、貞淑な妻とみえた。
ルーズベルトとの関係も終わったようであった。
しかし一九四一年、太平洋戦争が始まった前後の頃から、たまたま二人の交際が始まり、再び愛はひそかに語られるに至った。
まもなくラザファードは病死し、二人の密会は繁くなった。
男は六〇歳を、女は五〇歳をこえている。 |

最後の未完の肖像図――この絵のモデルに
なっているとき、ルーズベルトは亡くなった。

エリノア夫人とくつろぐルーズベルト
|
ルーシー・マーサー・ラザファードは大統領が好む女らしさを一身に備え、気品高く、いつも暖かい微笑みをもって彼を迎えた。愛人と会うことを除いては何の欲もないような風情も、男をひきつけた。
大統領のみならず、誰しもが心ひかれる女性であったらしい。
だからこそ周囲の人びとが二人の逢う瀬に力を貸したのであろう。
彼らの関係は公にはされなかった。
とくにエリノア夫人には秘密であった。
密会の時と所は巧みに設けられ、社会・教育事業などで多忙なエリノア夫人、「ファースト・レディー」の典型であった夫人が対外的に活動したり、国外に出るような折には、ルーシーはホワイト・ハウスにも姿を現した。
ここで二人が昼食を共にするとき、すべてのドアに見張りがつき、大統領への電話の取次ぎも控えられた。
ルーシーが何かで遠くに離れているときには、度々の電話が彼女の声を求めた。
一九四五年一月二〇日、ルーズベルトの第四期大統領就任式の日は思いなしか、暗いムードに包まれていた。
それは曇って冷たい天候の故ばかりではあるまい。
ルーシーは列席者としてではなく、秘密警察に守られつつ、ある場所で自動車の中から、老い、やつれた愛人の姿を見た。ルーシーがエリザベス・シューマトフを伴ってウォーム・スプリングズに来たのは、大統領よりも遅れて、四月九日のことであった。ルーズベルトは最愛の女性と、はからずも生涯の最後の四日ほどを過ごし得たのである。
ワシントンにいたエリノア夫人が、急を聞いて駆けつけたのは深夜であった。
このエリノア夫人は夫の死後、その最期の場にもルーシーがいたことを含めて、仔細を知って恨み、憤った。
これに対する故大統領の愛娘アナ――ホワイト・ハウスの秘密の会食に相伴したこともあるアナの言葉には、感慨がこもっていた。
「だってお母さま、お父さまはとても淋しかったのよ」。
1.4 ロンメル、自決を選ぶ
おそらく世界中の限りない人々が、大統領の死を悼んだことであろう。
チャーチルは議会における追悼演説で、「最大の自由の戦士が永遠に去った」ことを嘆いた。
外国関係のニュースを軽視するソ連の新聞も、この死去の報道と死者の肖像を第一面に掲げた。
スターリンも深い弔意を表したが、彼らしく、大統領が毒殺されたのではないかと疑った。
日本政府も哀悼の念を示した。
しかしルーズベルトの死に希望を見出した人物もいた。ヒトラーである。
一八世紀半ばすぎ、プロシアとオーストリアがいわゆる七年戦争を戦った。
そしてプロシア王フリードリヒ二世が窮地に立ったとき、オーストリアに味方していたロシアの女帝エリザベータが急死し、後継者ピョートル三世は戦いよりも和を選び、プロシアは全面的敗北より救われた。
ヒトラーはこの故事にならった一種の「奇跡」を、ルーズベルトの死に期待したのであるが、無論、それは起こるべくもなかった。
ヒトラーにとって起死回生を信じたいような事件が、すでにほかにも生じていた。
一九四四年七月二〇日の反ヒトラー陰謀の失敗で、このとき九死を得たことは、彼に自らの運命に対する自信を与えたのである。
ヒトラーの冒険主義に亡国の危惧を抱くドイツ軍将校たちは、戦前、戦中、たびたび陰謀を計画しながら、いずれも不発にとどまった。
しかし「七月の陰謀」は別であった。
すでに米英連合軍はノルマンディーに上陸し、ドイツは東西から挟撃される情勢となっていた。
その日、東プロシア、ラステンブルクの総司令部のある建物で、ヒトラーを囲んで会議が開かれた。
陰謀派の一士官は暗殺をめざして、午後一二時半すぎ、時限辯弾を入れた書類用のかばんを机の下に置いた。
総統のすぐ近くであった。
しかしその士官が人目を忍んで戸外に逃れた直後、他の将校が邪魔になるので、このかばんの位置を変えた。
何気ないこの行為が総統の命を救った。
一二時五〇分頃、爆発が起こり、同席の二〇数名に若干の死者、重傷者が出たが、ヒトラーは軽傷を負っただけであった。
彼の暗殺を契機に、新政府を成立させようという陰謀派の計画は挫折してしまった。
復讐が野獣のように残酷に行われたことは言うまでもない。
あのロンメル元帥もこの事件に関連して落命した。
彼は事件に直接関係していなかったうえに、ヒトラーに対して批判的ではあったものの、忠誠を守っていた。
ところが元帥の名が利用され、取調べ中に一、二の陰謀派将校からもれてしまった。
彼が国民的英雄であるだけに、ヒトラーはこれを恐れて、その死を求めた。
一九四四年一〇月一四日、ロンメルは逮捕か、自決かを迫られて毒を仰いだ。
それが妻子を安泰ならしめる道であった。公式発表は負傷に起因した死亡である。
総統は未亡人に仰々しい弔電をうち、国葬を命じ、大きな花輪を贈り、軍の長老ゲルト・フォン・ルントシュテット元帥は事の真相を知ってか、知らずか、「彼の心は総統と共にあった」云々という追悼の辞を述べた……。
東部戦線を離れたヒトラーは一九四五年一月中頃から、形勢が一段と悪化した新しい年の日々を、ベルリンの総統官邸、地下五〇フィートの防空壕で過ごしていた。
ドイツ軍最高司令官としての焦土抗戦という彼の信念は、揺らぐべくもなかった。
一月三〇日、政権獲得後、一二周年目のラジオ放送、最後となった放送で、彼は自分のことを「いつもただ一つ、殴ることしか知らなかった男」と語った。
二月、ヒトラーは党最高首脳マルティン・ボルマンに、いわゆる『ヒトラー・ボルマン文書』を口述した。
彼はそのなかで「余はヨーロッパ最後の希望であった」と豪語しつつ、反共・反ユダヤ主義などの持論を固執し、あるいはドイツの野望を妨げたイギリスの抗戦、チャーチルの抵抗を憎悪している。
イスラム圈を味方につけ得なかったことを悔やんでいる文章も、印象に残る。
しかし一面、この記録には数々の失敗に対する愚痴っぼさが目立ち、口述者の追いつめられた心情を察知させるものがある。
ヒトラーの愛人エバ・ブラウンがミュンヘンから禁を犯して、総統のもとに身を寄せたのは三月中頃のことのようである。
それはヒトラーの身を案じつつ、愛情と共に忠誠からの、おそらくは死を覚悟しての行為であった。
彼はエバがどうしても防空壕に留まると言ったとき、落涙(らくるい)したという。
三月十九日、この同じ人物はいわゆる「ネロ指令」を発し、敵に利用される恐れがある産業、輸送施設などの破壊を命じてはばがらなかった。
1.5 エバとアドルフ
一九四三年以来、戦況が不利になるにつれてヒトラーの孤立が目立つた。
かつては敗戦の実情を報告する将軍たちに、最後の勝利を確信させて退去させた総統の雄弁も色あせ、軍や将軍への罵倒のみが募った。
その健康も害され、白髪も多くなった。
彼はしばしば理由もなく怒り、意味不明のことを口走り、手をふるわせ、足をひきずった。
しかも一説によれば、彼は侍医テオドール・モレルを過信し、薬の乱用でかえって体をむしばんだ。
ヒトラーに提出される書類は「総統用」タイプライターで、とくに大きく打たれていたが、それでも度が強い老眼鏡――それをかけた写真は珍しいが――に頼ることが多かった。
その輝かしかった眼も昔日の魅力を失ってしまった。
その一方では、ヒトラーとエバの仲はますます濃(こ)まやかとなった。
いつ頃の言葉であろうか、「私にはたった二人の友人しか残っていない。エバとブロンディ(愛犬)だけだ」。
エバ・ブラウンは一九二一年ミュンヘンに教師を父として生まれ、三人姉妹の次女、陽気で明朗、人生を愛し楽しむ娘に成長していった。
この平凡な娘がヒトラーと知り合うに至ったのは、一九二九年頃、彼女が有名な写真家ハインリヒ・ホフマンの事務員に雇われ、そしてホフマンがナチスとその党首に関係が深い写真家であったためである。
初め、この「大人物」の党首も彼女の関心をひかず、ちょびひげの滑稽な男に見えただけであった。
一九三一年九月、ヒトラー夫人、いとこのアングラ(ゲリ)・ラウバルが謎の自殺をとげた。
その後三二年から、ヒトラーとエバとの情事が始まったといわれる。
しかしすでにエバから彼に送られていた手紙が、ゲリ自殺の一因という臆測もあるようだ。
ともかく三三年、ヒトラー首相が誕生する頃にはエバの地位は明らかであり、彼女はいまでは「ちょびひげの滑稽な男」を愛し、尊敬するようになっていった。
この男は他にも一、二のロマンスの花を咲かせたが、結局、エバを離さなかった。
ただし彼女はその陰の地位を悲しみ、狂言ともみられる自殺未遂を演じたりしたが、これをおりにヒトラーは真剣になった。
ヒトラーは自らの政治的運命は妻帯を許さないと信じ、私の妻はドイツだと言ったという。
しかし一人の妻を持つことは、多くの女性の支持を失うことでもあろう。
そういう読みがあったのかもしれない。
ベルリンで、ミュンヘンで、そしてベルヒテスガーデンの山荘ベルグホフで、彼の周辺にエバの姿が見うけられた。
とくに「ペルグホフのホステス」としての彼女は、一部の人々の間では親しい存在となった。しかし一般の国民は彼女について全く関知しなかった。
エバ・ブラウンは運動好きで、水泳、体操、スキー、山登りなどが得意であり、また歌やダンスも巧みだった。
美しい衣装が好きな彼女はまたベスト・ドレッサーでもあり、総統の写真の専売権をホフマンと共有していたので、小遣いにはこと欠かなかった。 |

ヒトラーの愛人エバ
誰もが去った総統官邸防空壕で、死ぬ直前に結婚式をあげた。
|
彼女は政治には関心がなく、したがってヒトラーに対する公的な影響はあまり考えられないが、案外、独裁者の気持ちを左右した面もあったらしい。
総統は愛人の身を案じ、常時、飛行機の利用を許さず、また彼女が乗る自動車を時速六〇キロ以上のスピードで走らせることを禁じた。
たまたまエバがいるミュンヘンが空襲をうけたような際には、彼は安否を気遣って、「繿のなかのライオン」のように部屋を歩きまわった。
しかし数えきれない人命が彼のために悲惨な最期を遂げているときに、その彼とエバが「語り、笑い、食い、飲み、そして愛しあって」いたのである。
1.6 ベネチア宮の情事
一九四五年四月、ベルリンに迫るソ連軍の砲声を聞きながら、総統官邸の防空壕における二人の生活は、思い出のアルバムをめくったり、昔話に花を咲かせたりしつつ、静かに送られた。
ヒトラーを愛するためにだけ生きてきて、いまや覚悟を決めた女性の一途な姿は、周囲の人びとの感動を誘った。
ルーズベルトの訃報が伝わったのは、こういう雰囲気のなかである。
逆境が一転するかもしれないという希望が絶望と変じた後にも、エバだけは楽天的に振舞っていた。
しかし悲劇もあった。
エバの義弟、親衛隊の将校ヘルマン・フェーゲラインが裏切りを問われて、四月二八日、官邸の庭で銃殺されたが、彼女はなす術もなかった。
これより先に、四月二〇日、総統は五六回目の誕生日を迎えた。
反響するのは祝砲ではなく、ソ連軍のベルリン砲撃の音であった。
二七日から二八日、砲撃は最高潮に達した。
そしてムソリーニの悲惨な最期の報が防空壕に届いたとすれば、二九日の午後であった。
すべての人々に見棄てられたムソリーニのもとへ自ら進んでおもむき、ヒトラーにおけるエバ・ブラウンのように、最後の運命を共にしたのはクラレッタ(クララ)・ペタッチである。クラレッタはエバと同じく一九一二年の生まれ、ローマの医者――教皇の侍医を務めた――の娘で、当時のイタリアの多くの女性のように、ムソリーニの熱烈な崇拝者となった。
そして彼女が二〇歳となってまもない時、全く偶然にムソリーニと出会った。
彼はいわば一目惚れで、女に接近した。
一九一〇年以来、ムソリーニには妻ラケーレがいた。
しかし強引な女あさりでは人後に落ちない彼が、得意の絶頂にあった一九三六年頃からクラレッタに心を奪われたのは、彼女のむしろ平凡な愛らしさ、素直さによるのかもしれない。
ムソリーニは居所のベネツィア宮に、クラレッタのための一室を設けるありざま、ただし彼の情事は誰が相手でも、公邸で行われたらしい。
そして彼女を利用してムソリーニに近づき、私利を得たその一家の「ペタッチ・スキャンダル」は国民の反感を募らせ、したがって彼の名を傷つけた。
彼が没落し、北イタリアにヒトラー傀儡政権をたてた頃にも、ラケーレ、クラレッタとの二重生活が営まれ、妻の嫉妬は逆境の夫をさらに悩ませた。 |

ムソリーニの愛人クラレッタ
ゲリラに追われているムソリーニを追いかけ、二人一緒に処刑された。
|
1.7 湖畔の暗い午後
一九四四年七月二〇日、あの暗殺未遂事件の日、実はヒトラーはムソリーニの来訪をうけ、会見することになっていた。
駅頭に出迎えた総統は顔色が悪く、右手に包帯をして、別人のようであった。
そして彼は訪客をまだ煙が残っている建物の焼け跡に案内した。
196
ヒトラーは何時間か前、自分の命が失われるところであった場所を示し、死を免れたいま、現在の危機を乗りこえて幸福な結末に達成し得ることを確信すると、怖じ気づいている相手を元気づけた。
このときがファシストたちの最後の会見となった。
激励されたムソリーニは吉兆を信じて帰国したが、一九四四年後半から四五年にかけて、連合軍はイタリア半島で着々と進撃を続けた。
そして三月からイタリアのドイツ軍は連合軍と和平交渉に入り、四五年五月二日、完全な降伏となった。
この間、ムソリーニのサロ共和国は揺れ動き、反ファシズム抵抗運動も高まるうちに、統領自身の逃避行が始まった。
スイスへの亡命を果たせなかったムソリーニは一九四五年四月二七日、北方に退却するドイツ軍自動車部隊に身を潜めた。
午後三時頃、コモ湖畔のドンゴでパルチザンはドイツ軍を停止させ、検査を始めた。
ドイツ兵の外套を着たムソリーニは車中で背を丸め、帽子をまぶかにかぶって顔を隠し、眠ったふりをしたが、ついに発覚した。
連行されるムソリーニは、彼を探しているクラレッタに会うことができた。
同じくパルチザンに捕われていた彼女は、愛人の消息を聞き、これと行を共にしたいと哀願して許されたわけである。
出会った時、二人は短い会話を交わしただけであった。
――「なぜ、私の後を追ってきたのかね?」「だって、ただそうしたかったの……」。
四月二八日早朝から、パルチザンの見張りのもとに、二人はある農家の二階の大きなベッドで、午前一一時頃まで最後の時を過ごした。
午後四時頃、彼らは車に乗せられ、運転手によれば、男は青ざめていたが、女はとても落着いていた。
そして「死刑」はある別荘のひっそりとした門のあたりで行われた。
四時二〇分であった。
パルチザンは、連合軍が求めているイタリア・ファシズムの元凶を、自分たちの手によってこそ倒さねばならなかった。
二人がどのようにして殺されたかについては、何人かの証言が細かい点ではくい違っている。
二人は少しの間隔をおいて、低い壁の前に立たされた。
発砲されようとするとき、ムソリーニは身動きもせず、無感動であったとも、見苦しく震えていたともいう。
男をかばおうとしてか、抵抗したのは女であり、銃弾はまずクラレッタを倒したとも、逆に、女は狂乱状態のうちに男のあとを追って倒れたともいう。
二人の遺体はミラノに運ばれ、並んで、ロレート広場の鉄骨に逆さ吊りにされた。
さすがにあるパルチザン(女性?)――これにも異論がある――が見かねたのか、クラレッタの顔にかぶさったスカートを束ね、その細く美しい脚がさらされるだけにとどめた。
広場を埋めて惨死体に罵声を浴びせる民衆は、かつて同じ人物に歓声を浴びせた民衆であった。
1.8
墓標なき墓場
盟友の非業(ひごう)の死を知った頃、ヒトラーは側近の医師に、毒を飲んでからピストルを使用できるか、否かを確かめ、自らの死の用意に取りかかった。毒薬の効果をためすため、愛犬ブロンディにこれを与えることも命じた。
用意といえば、彼は一九四五年四月二八日深更から二九日早暁にかけて、最後の祝宴を催していた。
砲声がこだまするなかで、二八日真夜中、宣伝相ヨーゼフ・ゲッベルスたちの立会いのもとにエバとアドルフの簡略な結婚式が行われ、それに続いてささやかな宴が張られたのである。
結婚証明書の日付は二九日になっている。
エバにとって多年の願いの成就、愛の至福の成就であった。
署名の折、彼女はエバ、それからブラウンと書き始めたが、すぐ大文字のBを消し、「エバ・ヒトラー、原姓ブラウン」と改めた。
まことに四八時間にも満たない花嫁であった。
一場の茶番ともみえるが、本人たちは真剣である。
四月三〇日の昼食は午後二時をまわっていた。
ヒトラーはいつものように肉を食べず、エバは飲物のほか、ほとんど何も口にしなかった。 |

官邸前のヒトラー最後の姿
|
三時すぎ、総統は防空壕で生活を共にした人々に別れの挨拶をした。
ゲッベルスやボルマンのようなナチス首脳から、将校たち、医師、秘書、料理人――菜食主義のヒトラーには菜食専門の者がいた――召使、運転手等々、五〇名ばかりが同席していた。
ヒトラーはなぜか、悲しい響きをこめるためか、「アウフ・ビーダーゼーエン」ではなく、「グッド・バイ」という言葉を使った。エバの顔は青白かったが、取り乱してはいなかった。
衣装は花婿の気に入りのものである。
三時三〇分頃であろうか、二人が入った部屋から一発の銃声がひびいた。
服毒のうえ、ピストルで右のこめかみを射ったヒトラーは血にまみれてソファーに倒れ、傍に毒を仰いだエバが息絶えていた。
横に落ちている薄いピンクのスカーフが印象的であった。
二人の死体は最後の遺言に従い、すぐに庭に運ばれ、ガソリンをかけて焼かれた。
この個人的遺言には、自分と同じ運命をたどろうとする女性と結婚すること、降伏などの屈辱を免れるために自殺を選ぶことも記されている。
ヒトラーの遺骸を発見し、持ち去ったのはソ連軍とされている。
しかし五月末、スターリンは訪ソ中のアメリカの特使たちに、ヒトラーは生きて隠れているのではないか、あるいは潜水艦で日本に逃れたのではないか、とかなり真面目に語っており、この独裁者はいまひとりの独裁者の死に疑惑を抱いていたようである。
ともかくヒトラーの自殺がソ連で初めて公認されたのは、スターリンの死(一九五三年)後のことであったとみえる。
その総統亡き総統官邸を、危険を冒して次々と去って行く人々のなかで、ゲッベルスは妻、六人の子供たちともども自殺した。
彼と共にヒトラーから後事を委ねられていたボルマンは、防空壕を脱した後、全く消息を絶ち、南米などにおける潜伏説も流れたが、一九七三年に至って脱出直後のベルリン内における死が認められた。
ヒトラーはいま一通の政治的遺言で、米英側とひそかに和平交渉をしたナチス首脳ヘルマン・ゲーリングとハインリヒ・ヒムラーを除名して、その憤りのほどを示した。
しかしこのヒトラーの死去の直後、信任厚いゲッベルスとボルマンもソ連軍と交渉し、むなしいとみて自殺を、あるいは挫折した逃亡を選んだのである。
それらはすべて、彼アドルフ・ヒトラーが一千年の繁栄を信じた「第三帝国」――神聖ローマ帝国、ドイツ帝国に続くべき第三帝国の滅亡の惨めな余話にすぎなかった。
五月一日夜、まだドイツ軍の支配下にあったハンブルク放送は「重大発表」と予告した後、まずブルックナーなどの荘重な調べを流しながらヒトラーの死を伝えた。
それから提督カール・デーニッツは自らが総統の遺言によって、その後継者となったことを語った。
同時に彼はヒトラーの死の実状をまだ知らなかったが、それがどうあろうと、彩られた結末を告げねばならなかった――総統は共産主義とのたたかいに命を捧げ、英雄の死を遂げたと。
「神々のたそがれ」――彼が愛したワグナーの楽劇から取られたこの言葉が、ヒトラー最後の日々の表現に当てられている。
ヒトラーはドイツを滅ぼし、ヨーロッパを荒廃させ、第一次世界大戦以来の米ソ台頭を決定づけた。
彼は未曾有の破壊の後に、そのめざしたところとは全然、逆の結果をもたらした。
ヒトラーの死が放送された一夜が明け、翌五月二日、それはソ連軍がついにベルリンを占領した日である。
この日のためにヨーロッパ戦争最終段階が展開していたのであり、これをよそにして、総統は官邸地下防空壕でほとんど結末を待つのみの生活を送っていたのである。
舞台は一九四五年春に返る……。
2 米英ソ大同盟の最後の歩み top
2.1
ベルリン攻略
一九四五年四月一二日、上院にいたアメリカ合衆国副大統領ハリー・トルーマンが急遽、呼ばれてホワイト・ハウスに着いたのは午後五時半頃であった。
二階の一室で、エリノア・ルーズベルト夫人は副大統領の肩に手をおいて、夫の訃報を告げた。
彼はしばらく無言のまま立ちすくんだ。
午後七時頃、大統領就任の儀式が即席に行われた。
この年一月に就任、副大統領として日が浅かったトルーマンが記者会見で、いままでどういう人にも課せられたことがない重大任務が与えられた。
私のため祈ってください、という意味のことを語っているのは、当時の心境をまざまざと伝えるものであろう。
成行き上、彼はルーズベルト外交路線をひきつぐこととなるが、ロシア嫌いのトルーマンが親ソ的な前大統領の後任となったことは、米ソ関係の前途に関して、どうであったか。アメリカの大統領交替の一九四五年春、戦いは最後の段階に達した。
この年に入って、米英空軍によるドイツ爆撃は一段と激化していた。
ベルリンは無論のこと、ドイツ諸都市が対象となったが、とくに二月中頃、ドレスデンは荒廃に帰し、何万という市民が死亡した。 |

ルーズベルトの逝去で急遽、
大統領になったトルーマン。
|
それはユダヤ人に対するものに劣らず、一つの「大虐殺(ホロコースト)」であった。
一方、ヒトラーが最後の望みを託した新兵器“ロケット”は、「空飛ぶ爆弾」としてロンドン市民などを苦しめたが、戦局を変えることはできなかった。
もはや軍事的勝利を時間の問題とみたチャーチルは、ドイツの死命を制すべきベルリン攻略に関してルーズベルトに、連合軍総司令官アイゼンハワーに、これをソ連軍に委ねることなく、米英軍をもってすることを要望した。
しかし三月末、ベルリンを目標に含めない米英軍の進撃作戦をスターリンに通告し、その諒解を得ていたアイゼンハワーは、この主旨を変更しなかった。
しかもソ連は米英を疑い、ベルリン占領をひそかに急いだ。
ドイツ軍の主力と戦ったソ連軍としては、ベルリンこそ、必ず自らの手によって占領しなければならない都市であった。
チャーチルが同じく重視するプラハの解放もソ連軍に委ねられた。
ルーズベルトの一つの失敗は、副大統領を外交政策から遠ざけていたことであった。
そのうえ彼が急死したため、このトルーマンは種々の事情に通じていなかった。
また事実上、ルーズベルトの代役を務めていたあのマーシャル元帥は、軍事中心に情勢を判断した。
この軍人はいかに早く、いかに損害少なく戦争を終わらせるかに、当然ながら専念し、チャーチルの政略を重んじなかった。
そして米英連合軍の主導性がアメリカ軍にあることは、チャーチルの指導力の弱さを意味せざるを得なかった。
それにしても、この場合、米英軍の動向如何によっては、ソ連軍との衝突を招く恐れがあったのではあるまいか。
一九四五年五月二日、ソ連軍の兵士たちはベルリン国会議事堂に赤旗をひるがえした。
この軍を指揮したゲオルギー・ジューコフ元帥はレニングラード、モスクワ、スターリングラードなどの防衛戦で輝かしい戦功を収め、大戦期のソ連軍を代表する軍人である。
彼はスターリンと対等に議論できる人物であった。
気さくで社交的なジューコフはアイゼンハワーとも親密となったが、スターリンはこれに渋い顔をしていた。
ベルリン陥落より先、ソ連が疑惑と不信を抱いたのは、ドイツから米英に対して単独講和の動きが生じたことである。
たとえば四五年二月から三月、不明な点が多いが、イタリア方面のドイツ将校がスイスで米英側と交渉するという事件があった。
ドイツの米英ソ大同盟離間策と見なされるこの種の工作は、その後ヒムラーやゲーリングによって企てられ、またベルリン陷落後の最終の局面においても、ヒトラー自殺後のつかの間の後継者デーニッツは西部戦線でまず降伏しようとした。
スターリンはドイツと米英とが和平し、反ソ十字軍が行われることを恐れねばならなかった。
資本主義諸国と共産主義国の不自然な同盟は、共通の強敵ドイツの存在によってこそ成立しているのであり、そのドイツが敗北してゆくなかで大同盟は解体するであろう。
いまや米英は逆にドイツと結んでソ連と対抗すべきであろうとは、ヒトラー自身の最後の希望でもあった。
一九四五年四月二五日午後、ベルリンの南約七五マイル、エルベ川に面したトルガウにおいて米ソ両軍は会遇し、それから夜陰に及んでウオッカ、ウイスキーによる乾杯、アコーディオンの演奏による歌、踊りなどが続いた。この交歓の場面こそ、軍人、兵士の姿を借りた米ソの人民が、ファシストたちの野心をうち砕いた光景であろう。
それはまたヨーロッパに代わって、米ソの時代の到来を暗示する光景であったかもしれない。
そして戦後、米ソの対立によってこの「エルベの会遇」は無視され、いや、隠蔽さえされ、トルガウの戦士たちがモスクワで再会したのは、一九五五年五月、冷戦がようやく雪どけを迎え始めた頃であった。 |

米ソ両軍が会遇したエルベ
両軍が仲良くできたのはこの時だけであった。
|
2.2 ヨーロッパ勝利の日
一九四五年五月七日午前二時半すぎ、北仏ランスのアイゼンハワー司令部で、ドイツ軍の代表は降伏文書に調印した。
これにはソ連代表も出席していたが、スターリンはさらにベルリンにおける調印を求めた。
八日から九日にかけての夜半、そのジューコフ司令部でドイツ軍は改めて降伏の手続きをとった。
西欧側の文献は前者を重んじ、ソ連側の文献は後者を重んじている。
枢軸側のルーマニア、フィンランド、ブルガリ一ア、ハンガリー、いずれもすでに休戦していた。
ところでベルリンにおける調印前に、伏せておかれたドイツ無条件降伏の件がもれたため、米英当局も黙しておれなくなった。
そこでトルーマンとチャーチルとは五月八日を「V・Eデー」、つまり「ヨーロッパ勝利の日」と布告した。
フランス共産党紙『ユマニテ』は、スターリンとルーズベルトの写真を大きく上段に、トルーマン、ド・ゴール、チャーチルのそれらを下段に掲載して、勝利を報じた。
ウィンストン・チャーチル夫人クレメンタインはド・ゴールの人柄を尊敬し、戦時中、異郷で孤独だったイボンヌ夫人のよき友人であった。
また戦時中、クレメンインは赤十字社のロシア援助に関係し、募金活動にも参加していた。
彼女は一九四五年四月、ソ連に招かれ、各地で大歓迎を受けたが、ヤルタを訪れたときには、夫が宿泊した館の同じ部屋で眠った。
旅行中のショッキングなニュースはムソリーニ、ヒトラーの相次ぐ死であり、うれしいニュースはV・Eデーであったなどとは、娘メアリー・ソームズが記すところである。
五月八日、クレメンタインは夫に祝電を発した――
「今日という最高の日、私か考えることはあなたと同じ、あなたあってこその今日、この日」。
五月一一日、ロシアを去るに当たって、彼女はスターリンに手厚いもてなしに対する感謝の書状を送った。
翌日、本国の飛行場には、喜びに溢れたチャーチルの出迎えの姿が見られた。(『クレメンタイン・チャーチル』より)
しかもなお、この勝利者の念頭を離れないことがあった。
一九四五年五月一二日付、チャーチルからトルーマン大統領あての電報には、「鉄のカーテンが彼らの戦線に降されています」と、彼の造語ではないが、戦後、有名になった「鉄のカーテン」という言葉が使用されている。
彼らとは無論、ロシア人のことである。
チャーチルは依然として政略を重んじ、ドイツ軍を撃破したソ連勢力がヨーロッパに拡大することを恐れ、アメリカがこれに対処することを求めた。
この頃、チャーチルがソ連を悪罵するさまは、ヒトラーやゲッペスルたちを想起させるものがあった。
しかしトルーマンらアメリカ側はポーランド問題などで対ソ不信感を強めつつも、依然として今後の国際協調を考慮して、ソ連との協力を重んじた。
少なくともアメリカはさしあたり対日戦参加や、国際連合成立(四月から六月、国連憲章作成のためサンフランシスコ会議開催)において、ソ連の協力を期待する立場にあった。
のちにチャーチルはルーズベルトの死後、機会があったにもかかわらず、トルーマンに会いに行かなかったことを悔いている。
2.3 幻滅
思えばイギリスがソ連と結んでドイツに相対抗した当時、英帝国の死活に関する敵はドイツであり、ナチズムを倒すためには、チャーチルは悪魔とも結びかねないと言われるありさまであった。
そのナチズムを倒し得る条件は英ソの、さらに米英ソの同盟であり、ひとたび形成され、動き出し、そして見事に勝利を得つつあるこの同盟を、その戦争が終わってしまわぬうちに破るような行為に出ることは、言うべくして至難の業であろう。
ましてアメリカにとって、ソ連ないし共産主義の脅威はなお直接的ではなかった。
これは当時において、イギリスとの大きな差であった。
戦争を通じて、従来も今も、協力を要している国を、しかもまだ戦争中、急にないがしろになし得るものではあるまい。
チャーチルの動きには、無理と知っての無理強い、無きにしもあらず、との感もする。
それにしてもソ連はまさに機を逃さず、東ヨーロッパに安全保障地域の確保を求めた。
とくにポーランド、チェコスロバキア、ハンガリー、ルーマニアなど、国境を接するに至った国々が、今後、反ソ行動の場となったり、あるいはソ連侵略の経路となることに危惧を抱いた。
現に二度、ソビエト政権はポーランド方面から攻撃されたのである。
そして東欧に対ソ友好国を設けるために、ソ連はこれら諸国の共産党系、親ソ勢力を支持し、伸張させねばならなかった。
すでにポーランドに対してはヤルタの取決めが米英が期待したようには運ばれず、ルーマニアの場合には内政干渉も辞せられず、チェコスロバキアの共産党支配は強まり、ヤルタの「解放されたヨーロッパに関する宣言」などは無視されたようであった。
一九四五年四月、トルーマン大統領はポーランド問題などをめぐって、訪米中のソ連外相モロトフと激論を交わした。
ソ連が要求しているアメリカからの借款も実現しなかった。
この対ソ関係調整のために五月から六月、独ソ開戦の頃、故ルーズベルトの特使を務めたハリー・ホプキンズが再びモスクワに派遣された。
スターリンはこの病身の使者、アメリカの対ソ援助に尽くしたホプキンズに、さすがに協力的であった。
そしてポーランドで新たに組織された挙国一致臨時政府の閣僚には、親ソ派が多くなったが、妥協も行われ、七月初め、米英はポーランド新政権を承認した。
しかしヤルタで約された可及的速やかな自由総選挙は延期された。
ソ連にとって、ポーランドは最も重要な安全保障地域である。
選挙の結果、自国に友好的な政府成立の可能性がなければ、スターリンとしては面子にかけても、これを実施できなかったであろう。
第二次世界大戦の発端はポーランド問題であった。
「冷戦」の発端もポーランド問題となった。
一九四六年一月末、ホプキンズは故大統領の後を追った。
ポーランドの総選挙はそれから約一年後、四七年一月のことであった。
こうして東ヨーロッパにおいて、西部国境に安全保障地帯を拡げたいというスターリンの勢力拡大政策は、着々と実現されていった。
米英がその軍事力で解放したイタリアやフランスに対して強い関心を抱くとき、ソ連がその軍事力で解放した東ヨーロッパ諸地域――それはたとえば英仏におけるオランダ、ベルギーに匹敵しよう――に対して強い関心を抱くことは、少なくともスターリンの論理からすれば当然であるかもしれない。
まして米英はソ連が切望した第二戦線を遅らせ、ソ連こそが多大の犠牲のもとにヒトラーを倒したという自負が、スターリンの念頭にあったとすれば……。
ソ連は東欧諸国を押さえたのみならず、戦争を通じて西方に広い領土を併合し、東では南カラフトと千島列島を得た。ソ連一国がこの大戦で領土を目立って拡大した。
反共主義者にたち戻ったチャーチルは、後年、第二次世界大戦を経て、ヨーロッパの半ばは一人の独裁者を他の独裁者と取り替えたにすぎないようにみえた……と書いている。
しかもチャーチルの失意は、いまや、その足元からも生じたのである。
2.4 原爆誕生
当時のイギリス下院議員は実に一九三五年に選出されたままであり、一九四五年七月、総選挙が行われることとなった。一般の国民は月初めに投票したが、各地の軍隊の票が集まってくるのを待って、開票は二六日に延期された。
この間、チャーチルは保守党の勝利を信じつつ、七月中頃、ベルリン近郊のポツダム会談におもむいた。
ヨーロッパにおける戦後の諸問題と、最終段階に至った対日戦について議する必要があったのである。
ポツダムはソ連占領地帯にあり、ベルリンに近いという点で、スターリンの意にかなった。心臓病のため、なるべく空路を避けるスターリンは旧ロシア帝室用客車を交えた列車を利用し、また身辺の危険を考えて最短距離のポーランドを通らず、北方を迂回した。
ベルリンではあの総統官邸で、「私は地下に降りて、彼と夫人が自殺した部屋を見た。 |
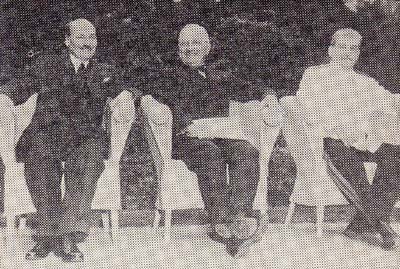
ポツダム会議――左からアトリー、トルーマン、スターリン
イギリスはチャーチル首相とアトリー労働党党首が出席したが、半月後の総選挙の結果、チャーチルの自由党が敗北し、アトリー首相になる。
|
それから我々は上にあがって、彼の死体を焼いた場所を示された」と、チャーチルはまだ生々しい一件について記している。エバの部屋には花のない花瓶が残っていた。
トルーマンはベルリンの荒廃を見た後、「人間が背伸びをしすぎると、あんなことになる」とだけ回顧録に書いている。
ポツダム会談は「ポツダム宣言」の名において日本人に親しい。
ただしこれは米英によって取りまとめられ、会談に出席していない中国側に照会されて成立したものであり、ソ連は事後の承諾であった。
しかしポツダム会談自体は米英の二人にスターリンを加えて、大戦中、三国首脳の三度目で最後の会談であった。
その最初の日の一九四五年七月一七日午後、チャーチルはアメリカ側から一枚の紙片を渡されたが、それには「赤ん坊たちは満足に生まれた」と書いてあった。
これは原子爆弾の実験に成功したことを意味していた。
ルーズベルト大統領が原爆の共同開発をイギリスに提唱したのは、あの「真珠湾」の約二ヵ月前、一九四一年一〇月であり、その厳秘とされた進行のなかでも、彼はチャーチルだけとは協議していた。
ルーズベルトは原爆がもつ外交上の価値を考えていたらしい。
原爆開発についてソ連に知らせて、原子力国際管理に関する三国協力という提案もあったが、両首脳はこれを退けて、米英の独占を続けた。
そしていま、原子爆弾を使用すべきか否かについては、一瞬の議論の余地もなかった。
これは米英関係者のまったく一致した意見であり、その使用は敵味方の無用な生命の浪費を救って、戦争を早く終わらせて世界に平和を与えるものだと、チャーチルは結論している。
さらに彼はこれでアメリカはソ連参戦を必要としなくなったと判断し、また少しのちに、もしドイツや日本がこの新兵器を発明していたならば、我々に対して使用していたであろうとも言った。
ある側近によれば、チャーチルは原爆実験の成功を子供のように喜び、それを単独に所有して、欲するところへどしどし投下することを、あるいはロシアの工業や人口の中心地帯を一掃することを考えていた。
トルーマンからこの新兵器について知らされたスターリンは、なぜか、ほとんど関心を示さず、それは結構なこと、日本人に対して有効に使用してほしいと言っただけであった。
しかしその夜、スターリンはモロトフ外相にこの件を語り、同時にソ連における研究促進を考えたのであろうか、故国の科学者たちに打電を命じた。
トルーマンはポツダムでチャーチルに、スターリンに初めて接したが、その回顧録には、スターリンの身長は一メートル六五センチくらい、写真を取るとき、踏み台の上に立ち、チャーチルも同じことをした、二人とも自分より背が低かったのだ……というような文章も見受けられる。
スターリンの皮肉なユーモアが会談中に目立った、とも書いているが、ロシア人たちの頑固、強情に閉口したらしい。
チャーチルについては、おしゃべりで人間的触れ合いを重んずるこの人物の操縦法を、ルーズベルト未亡人があらかじめトルーマンに伝授していた。
会談はドイツを民主化、非軍国主義化、非ナチ化すべき戦後処理や、講和条約のための五大国(米英仏ソ中)外相会議の設立、ポーランドの西部国境、賠償や戦犯問題などを議題として八月二日まで続いた。
会談中の七月二五日午後、そのチャーチルは開票を気づかって本国に帰った。
結果は三九三対二一二の議席数で労働党の勝利であった。
彼自身は当選したが、ただちに首相の地位を退き、ポツダムでも労働党党首、新首相クレメント・アトリーがイギリス代表となった。
アトリーは会談当初から同行しており、前首相とは対照的にビジネスライクで、議事の処理などに長じていた。
しかし会談自体は火が消えたようになった。
チャーチルはアトリーから出席を求められたが、応じなかった。
政権の交替は、個人的感情に溺れぬ英国民の政治上の聡明さを示した。
彼らは判断した、チャーチルは偉大な「戦争の人」であるとしても、戦後の国家再建については労働党の政策が信頼するにたると。
しかしチャーチルは当然のことながら強い不満を感じ、それ以上に落胆した。
ルーズベルトのように、病気でまたは飛行機事故によって、死んだ方がましだとか、もうべッドから起きる理由も失せた、栄光の日々は終わったなどと嘆いた。
まさに偽わらざる心境であろう。
しかし一九四五年七月二六日付の国民へのメッセージは、日本に対する任務の未了を遺憾としつつ、在任中、国民から与えられた支持に淡々と感謝している。
2.5 広島、長崎、さらに……
ルーズベルト、ムソリーニ、ヒドラーと他界し、チャーチルも退場した。
大戦初期から彼らに伍し、いま一人だけ残ったスターリンにはまだ大きな宿題があった。
ヤルタ会談でアメリカの要請に対し、対独戦終了後二ヵ月ないし三ヵ月で対日戦に参戦することを約したスターリンにとって、七月がその機でなかったとすれば、八月であろう。
実はソ連はヤルタで約された中華民国との条約を結んだ後、対日戦に参加する意向であった。
しかしその中ソ友好同盟条約が成立した八月一四日には、すでにソ連は参戦し、またポツダム宣言にも加わっていた。
しかも大戦最後の段階において、日本が米英との和平の仲介を求めようとしたのは、ほかならないソ連に対してであった。
その日本では敗色濃厚のうちに、一九四四年七月、東条内閣は総辞職、小磯国昭(陸軍大将)内閣が成立し、戦争終結の好機とも見えた。
しかしそれも空しく見送られ、四四年一〇月から四五年二月までに、アメリカ軍はレイテ沖海戦を経て、フィリピンを奪回、一方、米空軍の日本本土爆撃も始まった。
三月、硫黄島の守備隊全滅、四月、戦火は沖縄に移り、六月、全島は焦土と化して日本軍の抵抗は終わった。
東京、大阪をはじめ、無差別都市爆撃も一段と激化してきた。
すでに一九四五(昭和二〇)年四月、鈴木貫太郎(海軍大将)内閣が小磯内閣と交替していた。
五月七日、ドイツは降伏した。
敗戦はもはや必至であり、「本土決戦」が叫ばれる反面では、和平工作が試みられ、五月中頃、対ソ交渉が決定された。
これはソ連の参戦を押さえつつ、米英に対する和平仲介を求めるためである。
七月、ポツダム会談に先立って和平工作を進められるように、特使として近衛文麿が派遣されることとなり、ソ連側へ申し入れが行われた。
しかし一九四四年一一月、スターリンはある演説でドイツと並べて、初めて日本を侵略国とみなしていた。
そして四五年四月、ソ連は日ソ中立条約の廃棄――ただし一年後発効――を日本に通告し、参戦の態勢を整えつつあった。
したがって日本の折衝に対して、ソ連は特使の訪ソ目的が不明脯であるとして応じなかった。
なお日ソ中立条約廃棄について、アメリカ側は満足の意を表している。
スターリンはポツダム会談の席上、トルーマンにソ連に対する日本の調停依頼と拒否について意向を求めたうえ、参戦上の名分めいたものを得ていたのだから、まことに日本外交の甘さが伺われよう。 |

近衛文麿
|
そして米・ソ首脳との会談をいずれも拒否された近衛は、戦後、戦犯に指名され、逮捕直前に毒を仰いだのである。
一九四五年七月二六日、米英中三国は、日本に戦争終結最後の機会を与えるべきポツダム宣言を発表した。
それは軍国・侵略主義の除去、その完了までの連合国の日本占領、日本領土の範囲、軍の完全武装解除、戦犯の処罰、言論・思想の自由と基本的人権の尊重、日本経済と産業の維持の保証、再軍備産業の禁止、日本国国民の自由意思による政府の樹立などの条件をあげつつ、日本軍の無条件降伏を要求するものであった。
七月二八日、軍部の圧力に屈した鈴木首相はこの宣言を「黙殺し、あくまでも戦争完遂をめざす」と発表した。
首相は「黙殺」に、「ノー・コメント」の意味を持たせたかったと言われるが、外国では日本政府が拒否したものと受け取った。和平を求めての日本の対ソ交渉を知る米英は、むしろ驚かされた。
原爆投下はこの「黙殺」後のことである。
しかしソ連がまだポツダム宣言に加わっていないだけに、日本政府はなおも対ソ交渉に期待をつないでいた……。
トルーマン大統領が広島への原爆投下の第一報に接したのは、大西洋を渡る艦上で、八月二日に終わったポツダム会談から帰国の途次のことであった。
原子爆弾投下の目標としでは広島、小倉、新潟、京都などが決まったが、「美術の宝庫」京都が削除されて、代わりに長崎が取り上げられたという。
八月六日、広島が、九日、天候の状態で小倉を避けて長崎が、それぞれ目標となった。
その間の八月八日夜、モスクワでモロトフ外相はようやく佐藤大使を招いた。
しかしそれは日本が待望していた知らせではなく、ソ連の対日宣戦の通告であった。
独ソ開戦の直後、日本が廃棄するばかりであった日ソ中立条約は、ここにソ連によって現実に廃棄され、満州に進出するその軍の前に関東軍は敗走した。日本の傀儡国家、満州国も解体した。
そして軍人以上に犠牲となったのは、開拓農業移民たちであった。
2.6 終戦という敗戦
原爆投下の背後には、まず「真珠湾」などに対する復讐の意図があったと察せられる。
この点、原爆は早くから、人種差別を伴って、日本に対する使用が決められていたという。
さらにアメリカは対日戦を早期に終わらせて人的被害を減ずることを望み、いまとなっては参戦してくるソ連の勢力拡大をできるだけ押さえ、併せて新兵器の威力を示そうとしたものであろう。
ソ連参戦以前に日本を降伏させる意図があったとも推測されるが、それは成功しなかった。
実はソ連は対日参戦について、米英中の公式要請が欲しかったのである。
しかしいまやソ連の方でも参戦を急ぎ、中国との条約成立後という予定よりも早め、同時に条約自体の成立をも急いだと思われる。
そして広島の翌日、帰国直後のスターリンはクレムリン宮にソ連有数の原子物理学者数名を招き、費用を惜しまないから、できるだけ早くアメリカに追いつくことを命じた。
なおソ連が初めて原爆を所有したのは一九四九年である。
原爆投下とソ連参戦は日本にとって決定的であった。
もはや降伏以外にはなかったのであるが、実はこのとき日本の支配者層にとって従来から唯一つの、しかし最大の関心事があった。
それは国民を無益な戦禍から救うということではなく、いわゆる「国体護持」、すなわち天皇制維持にほかならなかった。
すでに一九四五年二月、近衛文麿は早期和平を説く『上奏文』のなかでヨーロッパ、中国などにおける共産勢力の進出に言及しつつ、述べている。
「……国体護持ノ建前ヨリ最モ憂ウルベキハ敗戦ヨリモ、敗戦ニ伴ウテ起ルコトアルベキ共産革命ニ御座候」。
また米内光政海相は五月、「我々として皇室の擁護が出来さえすれば良い。
本土だけになっても我慢しなければならぬのではないか」ともらした。
一九四五年八月九-一〇日の御前会議において、
「天皇ノ国家統治ノ大権ヲ変更スルノ要求ヲ包含シ居ラサルコトノ了解ノ下ニ」
日本政府がポツダム官言を受諾するという外相(東郷茂徳)案に対し、なお軍部に戦争継続、本土決戦を望む声が強かった。
「八月九日(木)晴……十一時五十分より翌二時二十分迄、御文庫付属室にて御前会議開催せられ、聖断により外務大臣案たる皇室、天皇統治大権の確認のみを条件とし、ポツダム宣言受諾の旨決定す」(『木戸幸一日記』)。
席上、「唯国体ノ護持ハ皇室ノ御安泰「国民全部戦死シテモ之ヲ守ラザル可カラズ」というような発言もあったが、天皇制がいかに日本人を狂信的、非人間的にしていたか、ということの一端も伺われよう。
御前会議、八月一〇日の決定に基づく日本の申し入れに対して、アメリカから届いた連合国(米英ソ中)側回答の真意が、前記の了解事項を暗に認めるものと察知されたとき、一四日の御前会議において再び天皇の聖断によって、ポツダム宣言受諾の詔書発布が決定した。
席上、なおも国体護持に不安を抱き、戦争継続を推す意見があった。
「……朕ハ帝国政府ヲシテ米英支蘇四国ニ対シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ……」。
この「終戦の詔書」の日付は八月一四日である。
そして一五日正午、天皇自身の録音ラジオ放送が突然、国民に降伏を告げた。
以来、天皇の開戦や戦争遂行への関与は、その降伏時の聖断や平和主義をもって巧妙に覆われることとなった。
しかしこの和平にしても、何ヵ月も、何ヵ月も前に行われるべきであった降伏が、その間の国民の甚大な被害の累積ののちに、ようやく実現したのである。
そこではアジア諸民族に対する責任などは、全く考慮されることもなかった。
こうして日本支配者層は国内の社会混乱によってではなく、むしろ、これを避け得て、原爆投下とソ連参戦によって敗戦を迎えた。
この二つの事実を米内海相は「言葉は不適当と思うが……或る意味では天佑だ」と評した。
2.7 マッカーサー、厚木に着く
ギャラップ社がこの年六月初めに行った世論調査によれば、アメリカ人被調査者の約七〇パーセントが、天皇を戦争犯罪人として何らかの処罰を与えることを望んでおり、「処刑せよ」が三三パーセントを占めている。
八月一〇日の日本側申し入れについて、ギャラップ社が緊急に行った世論調査では、日本側の条件を認めることに反対の答えが二対一の割合で多かった(荒井信一『原爆投下への道』より)。
したがってアメリカからの回答文に、天皇および天皇制の存続を許す意味の条項が作られるためには、政府内での意見の応酬を要した。イギリス側の同意も求められた。
そしてアメリカ首脳部の間に、天皇存続論を強めたのは、米英とソ連との関係の冷却下のなかで、日本の安定化が求められたからであろう。
チャーチルも天皇制の効果を考え、天皇の戦争責任を英連邦中、最も強く問うオーストラリア政府に反対したという(藤村信『ヤルタ――戦後史の起点』より)。
のちの東京裁判に際しても、アメリカは政治上の判断から天皇を訴追しなかった。日本をめぐる米ソの対立は早くも示された。
アメリカは北海道の北部を望むソ連の要求を拒否して、日本の単独占領を実施し、一方、アメリカはソ連領となる千島列島の一部に、恒久的航空基地を要求して拒否されている。
八月一六日から二五日までの間のやり取りである。
これより先、中国にもいち早く日本降伏の報が伝わった。
「一九三七年から戦われた日中戦争で中国人の死者は低めに見つもって一干万……虐殺と飢餓と農村の荒廃、数千万難民の群、失業、インフレが渦まくなかの勝利であった。中国人はこれをもって“惨勝”と形容した」(中村・桐山編『アジア一九四五年』より)。
八月三〇日午後二時すぎ、日本占領の連合国最高司令官、元帥ダグラス・マッカーサーはカーキー色の軍服、上着をつけず、黒眼鏡、右手にパイプ、静かな足取りで厚木飛行場に降り立った。
フィリピンからオーストラリアに逃れ、それからの反攻であった――
「メルボルンから東京まで長い道のりだった。
長い、そして困難な道程だった。しかしこれですべては終わったようだ……」。
丸腰、こういうスタイルで、武装解除前の敵地に降り立った元帥のさまを、「戦争中の司令官が行った最も傑出した振舞」と、チャーチルは評した。 |

厚木に降り立つマッカーサー
|
一九四五年九月二日、その日は九月初めにしては涼しく、曇ってはいたが、東京湾に風はなく波も静かであった。
午前九時すぎ、湾上のアメリカ戦艦ミズーリ号上で、政府代表の外相重光葵(しげみつ・あおい)、大本営代表の参謀総長梅津美治郎(うめづ・よしじろう)とマッカーサーおよび連合九ヵ国代表との間で、降伏文書の調印が行われた。
アメリカ、中国、イギリス、ソ連、オーストラリア、カナダ、オランダ、ニュージーランドと並んで、フランスが対独抗戦の雄ルクレール将軍を臨席させた。
日本軍の真珠湾攻撃の翌日、当時のド・ゴール派の自由フランス運動側は日本と戦争状態に入ったことを宣言していたのである。
調印の大役を、和平派であった重光は天皇の親任を示す名誉として引き受け、抗戦派であった梅津は強制されれば切腹すると怒っていたが、説得されてようやく承知した。 |
 ミミズリー号艦上の日本全権――先頭は、重光葵と梅津美治郎 ミミズリー号艦上の日本全権――先頭は、重光葵と梅津美治郎
ミズリー号は戦勝記念艦として、今は真珠湾内で展示されている。
|
九月二日、降伏文書と共に布告された米軍の日本軍に対する「一般命令第一号」のなかに、朝鮮に関して北緯三八度という便宜的な、しかし宿命的な文字が初めて見うけられる。
その以北に在る日本軍はソ連軍に降伏すべし、という条項である。無論、以南はアメリカ軍の勢力範囲となった。
アメリカ合衆国大統領トルーマンはこの九月二日をV・Jデー、すなわち「対日戦勝利の日」と宣言し、続けて神の加護が我々をこの勝利の日に導き給うたが、さらに神々の加護によって、我々自身のために、全世界のために、これから平和と繁栄を達成しようではないかと、その演説を結んだ。
同じ日、ソ連邦首相スターリンは日露戦争、対ソ軍事干渉、張鼓峰(ちょうこほう)・ノモンハン事件と、日本からの攻撃を概観しつつ、ついに日本が敗北したことを国民に告げ、また南カラフト、千島列島がソ連に移ることを明言した。
ここに太平洋戦争を含めての第二次世界大戦は終わり、ここに満州事変以来の対中国「一五年戦争」は終わり、そしてここに神聖不可侵の天皇の国、「神国」大日本帝国は終わった。
「終わり」から新しき日々が始まり、「戦前」は「戦後」によみがえってはならない。
top
**************************************** |








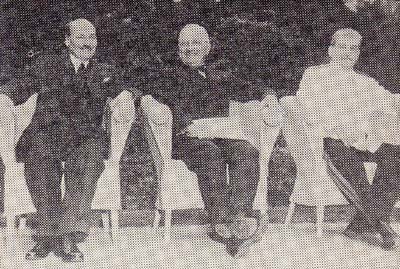


 ミミズリー号艦上の日本全権――先頭は、重光葵と梅津美治郎
ミミズリー号艦上の日本全権――先頭は、重光葵と梅津美治郎