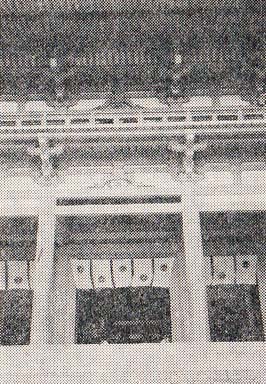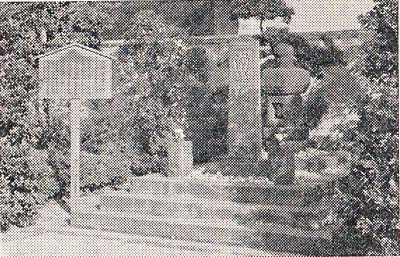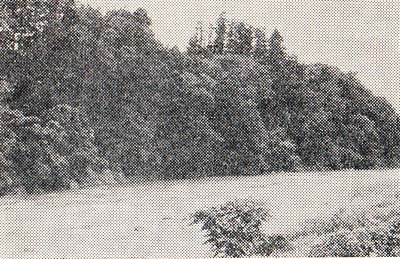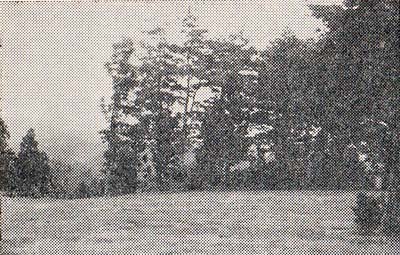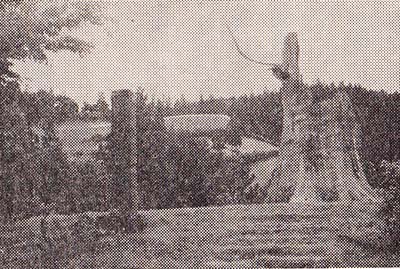|
****************************************
Home Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章
一章
古代の争乱
概要
九州の日向に天降った神々の子孫、神日本磐余彦命(かむやまといわれひこのみこと)は更によりよき土地を求めて東に進み、大和に攻め入った。
しかし大和の豪族の長(おさ)、長髄彦(ながすねひこ)の抵抗にあって敗退し、大きく迂回して南方から再度大和に進入した。
そして長髄彦の大軍を磐余(いわれ)の地に破り、磐余彦命は橿原(かしはら)神宮に即位して初代天皇神武と諡(おくりな)された。
これが「記・紀」の伝える神武帝東征の神話である。
「記・紀」にはその後、四道将軍の派遣や日本武尊の遠征、神功(じんこう)皇后の新羅(しらぎ)征伐などの物語を伝えているが、これは大和朝廷がしだいにその版図をひろげて行った過程をものがたっているのであろう。
日本に仏教が伝来したのは西暦五五二年のことだが、この扱いをめぐって大和朝廷の二豪族、蘇我(そが)・物部(もののべ)氏の争いが起こった。
この争いは排仏派の物部氏が滅んで幕を閉じたが、これを機に蘇我氏の勢いはようやく高まり、ときには天皇家の勢威をしのぐまでになった。
これを憂えた中大兄(なかのおおえ)皇子(おうじ)、藤原鎌足(かまたり)はひそかに蘇我氏の討滅を策し、皇極(こうぎょく)天皇三年(六四四)大極殿で蘇我入鹿(そがのいるか)を一瞬のうちに屠(ほおむ)った。
そして天皇家の絶対王権の確立を宣言し、初めて年号をたて、大化(たいか)と称した。
そこでこのクーデターを大化の改新というのである。
中大兄皇子が近江の大津宮に即位した(天智天気)のはそれより二十年後のことだが、在位わずか四年で崩じた。
つぎに立ったのは天智天皇の子、弘文天皇である。
そのころ吉野にはさきに天智天皇に追われた大海人皇子がおり、天智天皇の死を契機に、吉野と近江の間に戦雲がたれこめた。
六七二年六月、吉野の兵は進んで近江に迫り、敗れた弘文天皇は自ら縊(くび)れ死んだ。
この年は壬申(みずのえさる)の年だったのでこれを壬申(じんしん)の乱というのである。
その後、都は平城(奈良)から平安(京都)に遷って、天慶二年(九三九)坂東の荒野に突如として平将門(たいらのまさかど)の乱が起こった。
将門は地方に下って土着し、いわゆる武士となった皇族の後裔である。
この乱は初めは同族の争いにすぎなかったか、や
がて将門が関(かん)八州を制覇するに及んで「坂東の新皇」と称し、平安の朝野を震駭(しんがい=恐怖におののく)させたのであった。
しかし、ほどなく将門が討たれてこの乱は終わった。
このころ、奥羽には蝦夷(えみし)が蟠居して、一応は朝廷に帰服していたか、永承六年(一〇五一)蝦夷の長、安倍一族が叛いたため、朝廷は源頼義(みなもとのよりよし)を鎮守府将軍として派遣した。
このときの戦いが前九年の役である。
頼義が前後十二年かかって鎮定した戦乱は、前九年の役に功のあった清原氏の内訌(ないこう、内輪もめ)をきっかけに応徳三年(一〇八六)に再び火を噴いた。
頼義の子八幡太郎義家は金沢柵に武衡(たけひら)を攻めて滅し、乱を平定した。
これが後三年の役である。
こうした合戦を経て、武士の勢力はしだいに強まっていった。
その代表的な勢力として台頭するのが源氏(げんじ)と平氏(へいし)である。
かくて世は源平二氏対立の時代に突入する。
1 神武帝の東征 top
大和は日本の歴史のふるさとである。
耳成(みみなし)・香久(かぐ)・畝傍(うねび)の大和三山にかこまれ、森と丘と古墳の散在する平地に日本の古代王朝がうまれ、そして栄えた。
この平野を東で区切るのが北から南へ生駒(いこま)山、暗(くらがり)峠、十三峠、高安山、信貴山(しぎさん)とつづく生駒山脈である。
最北端の生駒山は東の大阪からは峻しくみえるが、西の奈良のほうはなだらかな傾斜で大和平野に裾野をとけこませている。
この裾野一帯が『古事記』『日本書紀』のつたえる神武帝東征の古戦場だ。
高天ヶ原(たかまがはら)から日向(ひゅうが)の高千穂の峰に天降りした神々の子孫、神日本(かむやまと)磐余彦命(いわれひこのみこと)は、
「何地(いずこ)に坐(ま)さば、平らけく天の下の政(まつりごと)を聞こしめさむ。
なほ東(ひむがし)に行かん」
といって、日向の海岸から東征の軍を起こし、瀬戸内海を東にすすんで難波(なにわ=大阪)に上陸した。
そして生駒山の険を越えて一気に大和へ乱入しようとしたのである。
これを孔舎衡坂(くさかのさか)で迎え撃ったのが、大和の豪族長髄彦(ながすねひこ)であった。
孔舎衡(くさか)は、のちに
「押照る難波を過ぎてうちなびく、草香乃(くさかの)山を夕暮れに吾が越え来れば……」
と『万葉集』にうたわれているが、おそらく生駒山西麓、東大阪市日下(くさか)町のあたりをさしているのであろう。
生駒山を血て染めての激戦が展開されたが、磐余彦命の軍勢は強大な長髄彦の軍勢に悩まされ、乱戦のうちに命(みこと)の兄五瀬命(いつせのみこと)が流れ矢にあたって重傷を負うという苦戦ぶりであった。
このとき磐余彦命は、自軍が東に向かって戦っていることに気づいた。
「われは日の御子(みこ)である。それがどうして日に向かって勝つことができよう」
そこで磐余彦命は兵を転じて紀伊半島をまわり、熊野から吉野に出で、東から大和に攻め入ろうとした。
途中、紀の国の男の水門で五瀬命の傷を洗ったといい、和歌山市小野町に水門神社がある。
ここで五瀬命は没し、竃山(かきやま=和歌山市和田)に葬られた。
山深い熊野路に行き悩む磐余彦命の軍勢を道案内したのは八腿烏(やたからす)という一羽の烏だったという。
烏は熊野信仰と関係が深く、牛玉宝印の神札の文字は烏をあしらって書かれている。
八腿烏の案内で吉野川の上流に出た一行は、それより川沿いに下り、宇陀(うだ、奈良県宇陀市)に到着した。
ここには八咫烏を祀る神社がある。
この地の豪族の兄弟、兄(え)宇迦斯(うかし)、弟(おと)宇迦斯を討ち平らげ、ついで忍坂(おさか=奈良県桜井市忍坂)で土雲(つちぐも=土民)の八十建(やそたける)を滅ぼし、長髄彦の本拠に迫った。
かくて生駒山を退いてから二か月後、磐余彦命の軍勢は再び磐余の地で長髄彦と対決することになった。 |

磐余の古戦場 奈良県桜井市南方
|
出陣にあたって磐余彦命は次のような歌をうたった。
みつみつし 久米の子等が 粟生(あわふ)には
韮(かみら)一茎(ひともと) そねが茎(もと) そね芽繋ぎで 撃ちてし止(や)まむ |
元気のいい久米の人々のつくる粟畑に、くさい韮(にら)が一本まじっている。
その根と芽とを一つにして撃ってしまおう、というのである。
最後の「撃ちてし止まむ」は太平洋戦争のとき全国民のスローガンに使われたものだ。
磐余はいまの奈良県桜井町の東南方で、『日本書紀』には、旧名を片居(かたい)、あるいは片立(かたたち)といったが、
磐余彦命が進撃したとき大軍がこの地に密集して満(いわ)めた。
そこで磐余と呼ぶようになった、とある。
いま文珠院(ぶんちゅいん)という寺のある山が、当時の磐余山だといわれている。
このあたりは路傍や森かげに古墳や塚が多く見られ、神話の舞台にふさわしい雰囲気をただよわせている。
両軍はこの地で激突し、混戦は数日におよんだが、形勢は不明であった。
このとき一天俄かにかき曇って、氷雨が降りがした。
そして金の鵄(とび)が飛び来たって磐余彦命の弓にとまり、稲妻のような閃光を放った。
この強烈な光に長髄彦の軍兵の目がくらみ、ついに敗退した。
これは『日本書紀』にある有名な金鵄(きんし)の話である。
それよりこの地を記念して、鵄の邑(とびのむら)というようになった。
近鉄奈良線の富雄駅から富雄川沿いに北方三キロのところに鵄邑(とびむら)の地名が残っている。
ここが金鵄発祥の地だといわれ、林の中に記念碑が立っている。
しかし磐余の鳥見山の北麓にも外山(とび)というところがあって、同じように金鵄発祥の伝説地になっている。
こうして長髄彦を討ち滅ぼして大和を平定した磐余彦命は、畝傍山のふもと、白檮原宮(かしはらのみや)に即位し、神武天皇と諡(おくりな)された。
時に辛酉(しんゆう)の年正月一日であったという。
明治政府はこの元日を太陰暦から太陽暦に換算し、二月十一日という日を算出して、紀元節としたのである。
白檮原宮の址といわれる畝傍山の東南麓に、橿原神宮が創建されたのに明治二十三年になってからだが、いまも日本建国のふるさととして訪れる人々が多い。
2 蘇我・物部氏の争い
top
北に大和三山、東に飛鳥川、南に仏頭山を望む景勝の明日香(あすか)村に聖徳太子誕生地、橘(たちばな)寺がある。
かってこのあたりには橘がしげり、それが寺名となったといわれるが、太子がこの地に生まれたのは敏達(びだつ)天皇三年(五七四)のことであった。
聖徳太子といえば「十七条憲法」の制定をはじめ法隆寺の創建、遣隋使派遣など、すぐれた政治家、文化人としてのイメージが濃い。
しかし、仏教の伝来をめぐって蘇我・物部氏の争いが起こったとき、蘇我氏に加担した太子は命を賭して奮戦し、武人としての才能もみせているのである。
このころ、大和朝廷はほぼ全国的な統一国家に成長していたが、天皇家をめぐる豪族には蘇我氏と物部氏が並び立って、権勢争いがつづいていた。
それが仏教の伝来を機に、崇仏、排仏をめぐって火 物を噴いたのであった。
『日本書紀』によると、欽明(きんめい)天皇十三年(五五二)に百済(くだら)の聖明王が仏像、仏典を献じたという。
天皇はこれを信ずべきか否かを群臣にたずねたところ、蘇我稲目は
「西方の諸国で信奉しているものを、どうして我が国だけが信奉しないでいられましょうか」
と答えたが、物部尾興(おこし)らは
「天皇は古来の天神地祗を祭るべきであって、蕃神などを信奉されるとあらば、神々の怒りを招くことは必定でありましょう」と反対した。
こうして朝廷での信奉は一応とりやめとなったが、このことがあって蘇我・物部の確執はますます激しくなっていった。
その後、蘇我氏は馬子(うまこ)、物部氏は守屋(もりや)の代になったが、敏達(びたつ)天皇十四年の春、馬子が奇病にとりつかれた。
卜者(占者)にみてもらうと、父稲目のときに淀川へ捨てた仏像の祟りだという。
そこで早速敏達天皇にこのことを言上し、蕃神信奉の許可を得た。
ところが、このころから疫病が流行しはじめ、人々の苦しむこと、ひとかたならぬものがあった。
ここぞとばかり物部守屋ら排仏派は「これは蘇我氏がいまわしき蕃神を信奉するからだ」と非難の火の手をあげた。
そこで敏達天皇もやむなく仏法禁制にふみきった。
守屋らはただちに馬子の建てた仏殿に押し寄せ、仏像ともども焼き捨てたばかりか、尼をとらえて衆人環視の中で尻に鞭打ちの刑を加えた。
ところが疫病はますますひろがり、ついには敏達天皇と守屋にまで伝染した。
すると人々は逆に、これは蕃神を焼いた報いにちがいない、といい出した。
そこで馬子はふたたび仏法信奉を嘆願し、病に苦しむ敏達天皇はこれを許した。
しかし秋にはいって敏達天皇はついに病没し、用明(ようめい)天皇が立った。
聖徳太子はこの用明天皇を父とし、敏達天皇三年(五七四)に生まれている。
用明天皇の母は蘇我稲目(いなめ)の女(むすめ)である。馬子からみると甥にあたるわけだ。
朝廷内で崇仏派の蘇我氏が勢力を強めてくるのは当然であった。
果たして、用明天皇は即位とともに群臣を集め、仏法を信奉したいといいだした。
守屋は反対したが、群臣は馬子に雷同して押しきられてしまった。
身辺の危険さえ感じた守屋は、急ぎ河内渋川の跡部の別邸に引きあげ、兵を集めはじめた。
跡部はいまの大阪府中河内郡竜華村のあたりである。
世情騒然としている間に、用明天皇は在位わずか二年で朋じ、次の天皇の擁立をめぐっで馬子と守屋のあいだに争いが起こった。
守屋は敏達天皇の弟穴徳部(あなほべ)皇子を淮したが、馬子は妹と欽明天皇のあいだに生まれた泊瀬部(はつせべ)皇子を擁立し、いちはやく穴穂部皇子を殺してしまった。
こうして蘇我・物部の対立はついに火を噴いた。
蘇我一族はこの機に乗じて物部一族を誅滅しようと大軍をさし向けてきたのである。
これを知った守屋は一族を集結して、稲城(いなぎ)をきずいて防備を固めた。
稲城というのは刈った稲を、横木にかけて柵のように並べ敵の矢を防ぐという、原始的な防壁のことである。
この稲城址というのが衣摺稲城(東大阪市衣摺)、渋川稲城(八尾市跡部)、その他河内に数か所あり、どれが真かは不明だが、代表的なのは八尾市南木ノ本の光蓮寺で、境内に稲城址の碑が立てられ、住職も代々稲城の姓を名乗っている。
やがて蘇我一族がこの稲城へ押し寄せてきた。
廐戸(うまやど)皇子(のちの聖徳太子)も蘇我氏との縁でその陣営に加わっている。
守屋はみずから榎の樹の上にのぼって寄手に矢を雨のように射かけ、蘇我の大軍を三度まで敗退させた。
このとき太子は乱戦のうちに守屋の兵に包囲され身辺に危機が迫った。
すると一本の椋(むく)の大樹が二つに裂け、太子がその中に身をひそめると再び裂け目を閉じた。
守屋軍は太子をくまなく探しもとめたが、ついにあきらめて引きあげたと「勝軍寺略縁起」にある。
九死に一生を得た太子は、白膠(ぬりで)の木で四天王の像を刻み、
「諸天の冥助によって勝利を得れば、四天王寺を建立して恩を無窮に報じよう」
と祈願し、馬子もまた寺塔を建立することを誓って猛攻に転じた。
その甲斐あって、述見赤檮(とみのいちい)の放った鏑矢(かぶらや)は榎(えのき)の樹上の守屋を射落した。
主将を討たれた物部軍は潰滅し、ついに物部氏は滅び去ったのである。
戦後、太子はこのときの誓願を果たすため、難波に四天王寺を建立した。
これが現在の大阪市にある四天王寺である。馬子も法興寺(飛鳥寺)を建立している。
また太子は危急を救った椋の本の傍らに一寺を建立したが、いま八尾市太子堂の勝軍寺とよばれるのがそれである。
境内に守屋の首を洗ったという守屋池や、守屋の墓があり、聖徳太子古戦場の碑が立っている。
南方に守屋の胸をつらぬいた矢を埋めた鏑矢塚という丘があったといわれるが、いまはもう押し寄せる宅地化の波に洗われて消えうせている。
物部氏の滅んだ翌八月、蘇我氏の推す泊瀬部(はつせべ)皇子が即位した。崇峻(すしゅん)天皇である。
こうして蘇我一族の全盛時代がはじまった。 |

勝軍寺 大阪府八尾市太子堂
|
3 大化の改新 top
崇峻(すしゅん)天皇は蘇我馬子(そがのうまこ)に擁立された天皇だが、物部氏を倒したあとの蘇我氏の専横には内心不満だった。
そこで崇峻五年(五九二)に猪を献上する者があったとき、ふと
「この猪の頭を切るように、いやな男の首をはねてやりたいものだ」ともらした。
これが馬子の耳にはいると、馬子はただちに崇峻天皇を暗殺してしまった。いわゆる馬子の大逆事件である。
崇峻天皇のつぎに、皇位はわが国初の女帝推古(すいこ)天皇から舒明(じょめい)天皇、再び女帝の皇極(こうぎょく)天皇へとうけつがれた。
この間に蘇我氏も馬子から蝦夷(えみし)、入鹿(いるか)と代がかわっていたが、これら一連の皇位の授受は、すべて蘇我氏の意のままに動かされていたのである。
皇極元年(六四二)の夏、大旱魃(かんばつ)が見舞った。
そこで天皇が雨乞いをしたところ、蝦夷もまた雨乞いを行なった。
雨乞いの祈祷は天皇のみが持つ霊術とされていた。
それを蝦夷があえて行なったということは、天皇にたいする公然たる挑戦である。
さらにこの年、蝦夷と入鹿はあらかじめ自分らの墓を築いたが、このときには朝廷や皇族の部民(領民)を勝手に使役し、しかも陵(りょう)と称した。
陵というのは皇族の墓にかぎって用いる称号である。
翌皇極二年、入鹿は聖徳太子の遺児山背大兄(やましろのおおえ)皇子を斑鳩(いかるが)宮に襲ってこれを白刃させた。 入鹿は皇極天皇のつぎに蘇我氏の血をひく古人大兄(ふるひとおおえ)皇子を立てようとしている。
そのためには朝野に徳望のあつい山背大兄皇子は邪魔な存在だった。
さらに翌皇極三年、入鹿は飛鳥の中心にある甘橿(あまかし)岡に一族の館を築いた。
甘橿岡は高市郡豊浦にある小さな丘だが、裾に飛鳥川をめぐらし、当時としては要害だったことが想像できる。
岡の頂きにのぼると、皇極天皇の皇居、板蓋(いたぶき)宮址は眼下にある。
不敬きわまりないことだが、入鹿としては天皇家と同等の地位についたつもりだったのかもしれない。
のちに大化の改新を断行した中大兄皇子が
「これより君に二政なく、臣は朝を二にするなかれ」と宣言しているところをみると、あるいはこのころ、朝廷が二つ存在する状態だったとも考えられる。
しかし馬子の気づかぬところで、着々と打倒蘇我の計画が進められていた。
その中心人物は中臣連(なかのおみのむらじ)鎌子(かまこ)、のちの藤原鎌足(かまたり)である。
鎌足は皇極天皇の子、中大兄皇子こそ盟主と仰ぐべき人と見込むと、法興寺での蹴毬(けまり)の会にまぎれて中大兄皇子に近づき、その知遇を得た。
意気投合した二人は、さらに同志をつのり、蘇我氏の一族である蘇我倉山田石川麻呂、佐伯子麻呂、海犬養(あまのいぬかい)勝麻呂、葛城稚(かつらぎのわか)犬養網田(あみた)の加盟をえた。
そして皇極四年、一切の準備を完了した一味は、決行の日を六月十二日と決定した。
この日は三韓から進貢の使者が到着するので、入鹿も参内する。
そこで石川麻呂が上表文を読み上げるのを合図に入鹿を斬り倒すという計画であった。
かくて待望の六月十二日がやってきた。
今日が最期の日とも知らず、入鹿は板蓋(いたぶき)宮に参内した。
皇極天皇の皇居、板蓋宮がどこにあったかについては二説あり、甘橿岡の北にある板蓋神社の地とも、東南の立神塚付近ともいう。
いずれも甘橿岡から見おろせる位置にある。
昭和三十四年に立神塚付近の発掘が行なわれたが、大規模な飛鳥時代の宮殿の遺跡が掘り起こされ、おそらくはこれが板蓋宮址だろうとされている。
入鹿は帯剣していない。鎌足が宮中の道化師にいいふくめて、巧みに剣を外させたのだ。
中大兄皇子は宮中の十二の門をすべて閉鎖させた。邪魔のはいるのを恐れたのである。
そしてみずからは長槍をとり、鎌足は弓に矢をつがえ、刺客の佐伯子麻呂、稚犬養綱田は剣をにぎって物蔭にひそんで時の到るのを待った。
大極殿では石川麻呂が上表文を朗読しはじめた。
しかし佐伯子麻呂らは臆して斬りこむことができない。
上表文はしだいに終わり近くなって、石川麻呂は気が気ではなく、声もふるえてきた。
その様子を怪しんで入鹿が「なぜそのように震えるのか」と問うた。
「天皇の御前で、あまりにも恐れ多くて……」と石川麻呂がうろたえるのに、もはや猶予はならぬとみた中大兄皇子はみずから先頭にたって斬りこんだ。
つづいて躍りかかった刺客のためにたちまち入鹿は切り刻まれて息絶えた。 |

入鹿の首塚
|
目前での惨事に驚愕した皇極天皇が「これはいったい何事であるか」と中大兄(なかのおおえ)皇子に問うた。
これに答えた中大兄皇子は、
「入鹿は皇位をうかがう反逆の臣であります。よってこれを誅したのであります」と奏上した。
かくて大極殿のクーデターは成功した。しかし甘橿岡には入鹿の父、蝦夷が健在である。
これを倒さなければ真の成功とはいえない。
そこで中大兄は飛鳥川をへだてて甘橿岡に対する法興寺にたてこもり、兵を集めた。
この変事を伝え聞いた皇族、豪族はことごとく中大兄のもとに馳せ参じた。
一方、蝦夷のもとにも一族が参集して決戦の気構えをみせた。
しかし中大兄が使者を送って帰順をすすめると、蝦夷の軍は動揺して武装を解き、四散してしまった。
翌十三日、中大兄皇子の軍は甘橿岡に攻め寄せたが、守るべき兵もなく、蝦夷は館に火を放って自刃した。
館にはかって馬子が聖徳太子と共同で編纂した『天皇記』『国記』をはじめ重宝珍宝があったがこれらもすべて灰となった。
ただ『国記』だけは辛うじて焼出をまぬがれたという。
こうしておよそ百年間、大和朝廷最大の豪族として権勢を誇った蘇我氏は滅び去った。
いま、法興寺西方の田圃の中に入鹿の首塚と伝えられる五輪塔が甘橿岡を背に、千有余年の風雨に哂されて黙然とたたずんでいる。
蘇我氏滅亡後、皇極天皇は退位して軽(かるの)皇子(徳孝、皇極天皇の弟)が即位し、中大兄皇子は皇太子に立った。
かくて六月十九日、天皇、上皇、皇太子は群臣を大槻(おおつき)の木の下に集め、天皇家の絶対的地位確立の宣言を行ない、初めて年号を立て、大化元年とした。
世にこれを大化の改新という。
中大兄皇子は非情の皇子であった。改新ののちも、彼は次々と政敵を倒して行った。
たとえ皇族といえども容赦しなかったのである。
異母兄の古人皇子、改新に功のあった蘇我倉山田石川麻呂、孝徳天皇の子有馬皇子らがその犠牲者となった。
クーデターで政権をにぎった中大兄皇子は、いつかはまた自分もクーデターで倒されるかもしれないという脅(おび)えにとりつかれていたのであろうか。
4 壬申の乱 top
大化の改新(六四五)で蘇找一族を倒し、朝廷の権威を確立した中大兄皇子が滋賀の大津宮に即位したのは二十二年後(六六八)のことであった。
天智天皇である。
大津市北郊の琵琶湖畔に近江神宮があるが、この付近が大津宮址だといわれている。
前面にさざ波たつ琵琶湖をのぞみ、背に比叡の山なみを負った景勝の地である。
この皇居は僅か五年で廃都になってしまったが、いまでもこのあたりから当時の建物の礎石平瓦などが発掘されている。
大化の改新の直後、天智天皇はみずからは皇位につかず、母皇極天皇の弟、孝徳(こうとく)天皇を立てた。
そして孝徳天皇が崩ずると母皇を重祚(ちょうそ、二回天皇になる)させた。
これが斉明(さいめい)天皇で、わが国の重祚の初めである。
斉明天皇の死後、天智天皇はなおも即位せず、称制(しょうせい)して七年におよんだ。
皇太子のまま天皇の政(まつりごと)を行なうことを称制というのである。
この間、天智天皇はしきりに朝廷の権力増強につとめた。
大がかりな土木工事や、朝鮮半島への外征などは、そのあらわれだった。
しかし土木工事は人心の離反があって成功せず、外征もまた白村江(はくすきのえ)で大敗を喫してしまった。
天智天皇の即位はその後に行なわれたのである。
しかし天智天皇の治世が安泰というわけにはいかなかった。
たび重なる失政に不満をいだいた豪族たちが、大海人(おおあまと)皇子に心を寄せはじめていたのだ。 |
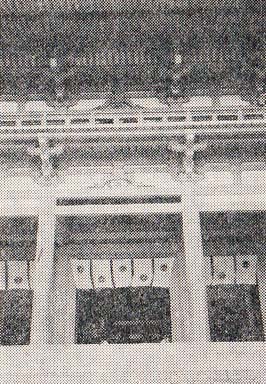
近江神宮社殿
大津宮地に建てられ、祭神は天智天皇
|
大海人皇子は天智天皇の実弟で、皇太子でこそなかったが、人々は当然のように次の天皇はこの人、とみていた。
しかし、天智天皇には大友皇子という実子がある。
「博学多通、文武の材あり」とたたえられるほどの秀才だったが、残念なことに生母が伊賀の小豪族の娘で出身が賤しい。
そこで天智天皇は大海人皇子の手前もあって、皇太子にも立てづらく、即位して四年(六七一)太政大臣に任命した。
天智天皇としては、わが子の大友皇子に皇位をゆずりたい。
そのためには、大海人皇子は邪魔な存在であった。
二人のあいだにすきま風が吹きぬけるようになったのも当然というべきだろう。
そのうえ、二人のあいだには恋あらそいがあった。
大海人皇子の恋人であり、十市皇女という子まである額田王(ぬかだのおおきみ)を奪って、天智天皇は自分の後宮に入れてしまった。
その後の話だが、天智天皇が群臣をひきつれて近江の蒲生野(がもうの、滋賀県蒲生郡八幡町)に狩りに出かけたことがある。 このとき大海人皇子は額田玉へのたちきれぬ想いを、袖をふって伝えた。
| あかねさす紫野行き標(しめ)野行き 野守は見ずや君が袖ふる |
『万葉集』にあるこの歌は、額田王が「そんなことをなさると野守(天智)にみつかるではありませんか」と、やさしくたしなめたものである。これにたいして大海人皇子も、
| 紫のにほへる妹(いも)を憎くあらば 人妻ゆえにわれ恋ひめやも |
と詠んでこたえた。分けへだてられた二人の激しい愛のぽとばしりが聞こえるような歌だ。
恋人を奪われ、いままた皇位から遠ざけられようとしている大海人皇子の忿懣(ふんまん)は、大津宮での酒宴の最中に爆発した。
酔いに激発した大海人皇子は、いきなり長槍を座敷に突き立てたのである。
天智天皇は怒って大海人皇子を殺そうとしたが、鎌足が間にはいって事なきをえたのであった。
即位四年(六七一)天智天皇は病に倒れ、重態に陥った。
そこで、大海人皇子を枕頭に呼び、譲位のことを相談した。
もしこのとき大海人皇子がこれを受けたら、おそらく殺されていたかもしれない。
しかし大海人皇子は、「じぶんはその器ではない」と固辞し、吉野にはいって法師になりたいと願った。
天智天皇がこれを許すと、大海人皇子は早々に吉野へ向かった。
このとき、ある者が大友皇子に、「大海人を吉野にやるのは、虎に羽をつけて放つようなものだ」といった。
大友皇子はもっともだと思い、軍を整えて呼びもどしに行くようなふりをして、殺してしまおうと決心したという。
『宇治拾遺』にある話である。
大海人皇子が吉野に向かったのは十月十九日、すでに吉野の山々には雪や氷雨が降っていた。
み吉野の 耳我(みみが)の嶺に 時なくぞ 雪は降りける 間(ま)なくぞ 雨は零(ふ)りける
その雪の 時なきがごと その雨の 間なきがごと 隈(くま)もおちず 思(も)ひつつぞ来しその山道を |
『万葉集』にあるこの歌は、のちに大海人皇子が吉野への山路をたどったときのことを回顧して詠んだものである。
暗澹(あんたん)とした大海人皇子の心中がしのばれる。
吉野の宮滝には大海人皇子が離宮を置いた「宮滝遺跡」の碑が草に埋れて寂しく立つが、ここでの大海人皇子の明け暮れもまた暗く佗(わ)びしいものであったろう。
大海人皇子がこの宮滝に落ちついたころ、大津宮では十二月三日天智天皇が崩じ、大友皇子が即位した。
弘文天皇である。
ところが翌年六月、大津の情勢ただならぬものがあるという情報が吉野の大海人皇子のもとにとどいた。
近江朝廷では、美濃、尾張の国司に先帝の陵をつくるからと称して人数を集めさせた。
しかし武器をもたせよという命令もいっしょに出ているというのである。
さらに、近江から大和まで物見を立て、吉野に食糧を運ぶのも阻(はば)んでいるというしらせもはいった。
そこへ弘文天皇の妃になっている大海人皇子の娘、十市皇女から、ひそかに焼き鮒の腹につめた密書が送られてきて、近江方の陰謀が明らかになった。
ここに至って、手をつかねていれば死滅するのみだと、ついに大海人皇子も立ちあがった。
六月二十二日、大海人皇子は美濃にある料地の兵に出陣を命じ、二十四日には妃、皇子らをともなって吉野を出立、伊賀、伊勢を経てみちみち馳せ参じる豪族を糾合し、美濃にはいった。
吉野方の司令官は大海人皇子の子、高市皇子(たけちのみこ)である。
一方、大和方面では近江方から寝返った大伴馬久田(まくだ)、吹負(ふけい)兄弟が古京の岡本宮を陥れて大和一円を制圧してしまった。
大海人皇子起つの報に接して近江方は驚愕した。
大海人皇子の軍にはしるものもあり、山野にかくれるものも続出して、戦わずして潰滅状態になった。
そこでただちに諸国に援軍を募ったが、使者はいずれも吉野方にとらえられ、あるいは追い返されてしまった。
七月二日、大海人皇子は全軍に近江進攻を命じた。
同志討ちをさけ、吉野方の将士はすべて上衣に赤い色をつけた。
その大軍が進撃する有様は、まるで枯野を焼く火のようだった。
出陣した高市皇子の勇姿を柿本人麻呂は、
「大御身(おおみみ)に 太刀取り帯(お)ばし 大御手に弓取りもたし みいくさを率(あとも)ゐたまひ
ととのふる 鼓の音は 雷の 声と聞くまで 吹き響(とよむ)る 小角(くだ)の音も
敵(あだ)見たる 虎が吼(ほ)ゆると 諸人(もろびと)の おびゆるまでに……」 |
とうたっている。
迎え撃つ近江方は山部王(やまべのきみ)、蘇我臣果安(そがのおみはやたす)、巨勢人(こせびと)らが数万の兵を率いて進発したが、内輪もめがあって山部王は殺され、果安は自殺するという有様で、戦う前からすでに敗色は明らかだった。
二十二日、大海人皇子の軍は瀬田に迫った。
瀬田には宇治川の上流、瀬田川にかかる橋があって、唐橋、長橋、臥竜橋などとも呼ばれている。
この橋は古くから京都防衛の重要拠点であった。橋の上に立つと、南に石山、北に比良、比叡の山なみがつらなり、ことに夕映えは近江八景のひとつとして美しい。
近江方は勢田橋の中央の板をはずし、かわりに長い板をおいて、吉野方の軍勢がその上を渡ったら綱を引いて落とすという仕掛けをつくって待ち受けた。
しかし吉野方の豪将大分稚(おおわけおみ)が二領の鎧を重ねて身につけ、全身針ねずみのように矢を浴びながら馳せ渡って綱を切った。
このため、仕掛けは役に立たず、吉野方はわれ先きにと対岸に押し渡った。
近江方の将智尊は「退く者は断る」といって味方の潰走をくい止めようとしたが、ついに支えきれず、全軍敗走にうつった。 |

瀬田の唐橋 近江朝廷の重要な防衛拠点であった
|
このとき勢田に出陣していた弘文天皇も敗残の兵にまじって逃れたが、ついに追いつめられて山前(やまざき、大津市三井寺前)で縊(くび)れ死んだ。
在位することわずか八か月、年二十五歳であった。
この年は壬申(みずのえさる)の年だったので、これを壬申(じんしん)の乱というのである。
近江方に圧勝した大海人皇子は敵将を斬刑、あるいは流刑に処し、大和に凱旋した。
そして岡本宮の南に飛鳥の浄御原宮(きよみはらのみや)をつくり、翌年(六七三)二月、即位した。
天武天皇である。
5 平将門の乱 top
利根川の流れがまだ東京湾に注いでいたころ、常陸(ひたち)の南部、下総(しもうさ)のあたりは
「馬に乗った人の弓の先までかくれてしまう」と『更級日記』に書いてあるほど、丈の高い葦の生いしげる沼沢地だった。
天慶二年(九三九)、筑波おろしの吹きすさぶこの茫々たる広野から関東の新皇と称して朝野を震駭させた異端児が出現した。平将門(まさかど)である。
時代は平安朝にはいって百五十年近くを経、藤原忠平を頂点とする藤原一門が安逸をむさぼっていたころであった。
この将門は桓武天皇の後裔である。桓武天皇の曽孫高望王のとき、平(たいら)という姓を賜って臣籍に下り、常陸大掾(だいじょう)上総介(かずさのすけ)として東国に赴いた。
皇族が臣籍に下り、地方官として中央を離れるといった例は平安時代を通じて数多くみられる。
そのうちには土着して武力をたくわえ、土豪になる者もある。
いわゆる武士がこうして発生するわけだ。
平氏(へいし)がそれであり、清和天皇から出た源氏(げんじ)もまた同じである。
坂東(ばんどう)に下った高望王に六人の子があって、それぞれ土豪と結んで勢力をもった。
将門はその三番めの良持の三男である。
年少のころ、立身を夢みて京に上った。
比叡山の頂上で藤原純友(すみとも)と京の町をみおろし、天下簒奪(さんだつ)の野望を語り合ったというのはこのころのことだが、もちろんフィクションである。
田舎育ちの将門などが都で立身できるはずもなく、やがて帰郷して土地の実力者だろうと考えた。
このころの将門の根拠地は茨城県の守谷(もりや)にあって、その館址という丘の上に「平将門城址」の碑が松の巨木に寄り添うようにたたずむ。
野心家であり青年客気な将門の言動は、当然のように周囲との軋轢(あつれき)を生ずるようになった。
まず、伯父の下総介(しもうさのすけ)良兼と反目した。ことの起こりは境界争いである。
すでに父のない将門をあなどって、伯父たちがその領地をかすめとろうとしたのだ。
さらに将門は良兼の反対をおしきって、その娘を妻にしている。
ところが、この娘にはかねてから常陸大掾(ひたちのだいじょう)源護(みなもとのまもる)のむすこ扶(たすく)が想いをかけていた。
それを将門にとられたので、怨みをいだいた扶は弟らと語らって将門に戦いを挑んだ。
将門の伯父国香も扶に助勢した。承平五年(九三五)のことである。
しかし、結果は将門の大勝利におわり、国香や扶らは討死した。
すててはおけぬと国香の弟良正が起ちあがったが、これもあっけなく敗れてしまった。
国香の長子貞盛は都で左馬允(さばじょう)になっていたが、父の死を知ると急ぎ東国へ帰った。
しかし将門の勢いに恐れをなして、手をつかねて傍観するばかりだった。
一方、良正は兄の良兼に助けを求め、翌六年、兄弟で数千の兵を率いて下野(しもつけ)に向かった。
良盛も良兼に励まされて、この軍に加わった。
しかし、迎え撃った将門は寡兵ながらもよく戦い、ついに良兼の軍を潰走させた。
そこへ京都から護と将門の双方に召喚命令がとどいた。
さきにわが子を討たれた源護が朝廷に対し将門弾劾の訴えを送っていたのだ。
将門はただちに上京して事情を陳弁し、無罪となるばかりか、剛勇の士と名をあげて関東へ帰ってきた。
良兼、良正、貞盛らは面白くないこと、もちろんである。
そこで将門が帰る早々、ふたたび戦いを挑んだ。承平八年八月のことである。
このたびは将門の大敗たった。
良兼らは高望王と将門の父良持の像を陣頭に立てて押し寄せてきた。
これには将門も弓を引けない。
さらに将門は脚気(かっけ)を病んでいたため陣頭指揮ができず、さんざんに打ち破られてしまったという。
このとき将門は葦のしげみにかくれて逃れたが、妻子は捕えられて上総(かずさ)に連れ去られた。
将門の無念さ思うべきである。
復警の鬼と化した将門は十月になって再起し、筑波山麓の良兼の館を襲った。
こんどは良兼が命からがら逃げ出す番であった。
こんな騒動をくり返しているところへ、朝廷から「将門を追捕せよ」との官符が関東へ下った。
十二月、良兼は将門の従者の手引きで、八十騎をもって将門の本拠、石井の館を襲った。
石井はいまの茨城県猿島郡岩井町である。
しかし、いも早く知らせる者があり、将門はたった十人の兵でこれを迎え撃ち、三十余人を殺して撃退した。
これによって関東における将門の武名はますます高まった。
そこで翌天慶元年(九三八)貞盛は京都に走って将門暴逆を訴えようとした。
将門はこれを信濃の千曲川(ちくまがわ)のほとりまで追ったが、貞盛はかろうじて逃れ、将門追討の官符を手に入れて帰った。
とはいっても、やはり将門に敵すべくもないので常陸の北部にかくれ、機会をうかがっていた。
このころ、武蔵国に権守(ごんのかみ)として桓武帝五世の孫興世王(おきよのおう)が下向してきた。
源経基が介(すけ=ナンバー2)としてそれに従っていた。のちに清和源氏の祖となる男だ。
この興世王が足立郡司の武蔵武芝という者と争いを起こした。
将門がその仲介にはいり、武蔵の国府(東京都府中市)で和解の盃をかわすことになった。
ところが、行きちがいがあって、武芝の兵が経基の営所をとり囲んだ。
経基はおどろいて京都に逃げ帰り、興世王や将門が謀反を起こしたと訴えた。
これにたいし将門は、近国の国司の解文(げぶみ、上申書)を集めて、無実を陳弁し、ようやく嫌疑をはらしている。
将門の運命が狂いはじめるのはこれからだ。
このころ、武蔵守として百済貞連(くだらのただつら)が着任したが、興世王はこれと気が合わず、将軍を頼ってきた。
そこへまた常陸の住人で悪名高い藤原玄明(はるあき)という者も駈けこんできた。
玄明は常陸の官物を強奪し諸税も納めないので、常陸介藤原維幾(これちか)の追捕をうけ、行きがけの駄賃に行方(なめかた)、河内(かわち)両軍の不動倉から穀物を奪って逃げてきたのである。
親分肌の将門がこれをかばうと、維幾は強硬に引き渡しを求めてきた。
もちろん将門は拒絶する。交渉がくり返されるうちに、双方とも感情的になり、ついに将門は千余人の兵を率いて常陸に押し寄せ、国府を囲んだ。
三千余人の兵を失って維幾は降伏し、印鑰(いんやく=かぎ)を献上した。
これまで将門が戦ってきた相手は一門の者で、いわば私闘だった。
しかし、このたびは常陸国府を襲ったのだ。これはもう叛逆である。
『将門記』によると、このとき興世王がいった。
「一国を討っても朝廷の責めは軽くはない。どうそのことなら関八州を討ち平らげて、様子をみたらいかがであろうか」
将門はたちまちその気になった。
「わたしも天皇の後裔だ。関八州を手はじめに、京都まで手に入れてやろう」
翌年、将門はこの計画にもとづいて行動にうつった。
数千の兵を率いてまず下野の国府に向かうと、国司らは戦わずして降り、印鑰(いんやく)を捧げた。
つぎは上野(こおずけ)国に向かったが、ここも同様だった。
ところがこのとき、一人の巫女が上野国府にあらわれ、神託を絶叫した。
「朕が位を平将門に授け奉らん。この位記(辞令)は右大臣正二位菅原朝臣道真の霊であるぞ。
すべからく三十二相の音楽をもって迎え奉るべし」
将門は感激して巫女の前にひざまづき、たったいまから「新皇」を称することを誓った。
時に天慶二年十二月十五日であった。
これより将門は武蔵(むさし)、相摸(さがみ)へと兵を動かし、あたるべからざる勢いで坂東の主にのしあがった。
この報が京都にとどくと朝廷はふるえあがった。
『将門記』には「京官大驚し、宮中騷動す」とある。
同じころ、西では伊予(いよ、愛媛県)の日振島(ひぶりじま)に根拠をおく藤原純友(すみとも)が瀬戸内海を荒らしまわっており、朝廷は東西の反乱軍が呼応して京を襲うのではないかと不安に陥った。
天皇は朝敵調伏の祈願のため、八百万の神々の位を一階あげるという措置をとり、廷臣らもまた必死に神仏に念じるという有様だった。
しかし、将門の衰運は急速に近づいていた。
さきに官符を手に入れて坂東に帰っていた平貞盛は、ひそかに八方奔走し、下野(しもつけ)国押領使(おうりょうし=警察官)の藤原秀郷(ひでさと)と手を結ぶことに成功した。
俵藤太の異名をもつ秀郷は藤原北家の末流だが、罪を得て配流(はいる)され、のち許されて下野国の押領使になった者だ。
お枷(とぎ)草子『俵藤太物語』では、この藤太が三上山の大百足(むかで)を退治した英雄で、将門を退治するために関東へ下向したということになっている。
貞盛が秀郷と同盟したという情報を得た将門は、天慶三年二月一日、下野へ軍を進めた。
しかし歴戦の雄秀郷のため、先峰が散々に打ち破られ、将門が陣頭に立って敗勢を挽回しようと奮戦したのもむなしく、ついに退却した。
同月十三日、秀郷らは大挙して将門の本拠下総に攻め入り、将門の館とその周辺の民家を焼き打ちした。
手兵わずか四百の将門は猿島の北山に退いていたが、翌十四日の午後三時ごろ、猛然と反撃に出た。
その日は南からの強風が吹き荒れていた。
『将門記』には「暴風枝を鳴らし、地籟(ちらい=響き)塊(つちくれ)を運ぶ」とある。
将門はその風を背にして貞盛の陣に襲いかかったのである。
将門の鬼神さながらの戦いぶりに、さすがの秀郷、貞盛らの同盟軍も浮き足立った。
しかしこのとき、突如として風向きがかわった。将門が風下にまわったのである。
チャンス到来とばかり秀郷らは陣を立て直して激烈な戦いとなった。
将門はみずから駿馬をとばして奮戦したが、流れ矢にあたってどっと落馬した。
それが坂東の新皇の最期だった。
将門最期の地、岩井町上岩井にはいま国王神社が荒れはてて残り、近くには将門首洗いの池などもある。
このあたり、春さきには土煙をまきあげて烈風が吹きあれ、人々を悩ましている。
付近は一面の畑になって古戦場の面影はないが、この風ばかりはむかしと変わらない。
時の権力に敢然と挑戦した将門の像は民衆の心に深く焼きついて、いつまでも消えなかった。
朝廷に反逆した大悪人ともいうべきであるのに、かえって崇拝されてきたのである。
いまも関東の各地に将門の墓、将門塚と称するものがたくさんある。
東京の中心、大手町のビルの谷間に右将門首塚というものがあり、これは将門の一味が、ひそかに京から首を持ち帰って埋めたものだといわれる。
また、千代田区外神田にある神田明神も、将門を祀ったものだ。
将門の死につづいて、翌天慶四年、西国の純友も敗死し、さしもの大乱もおさまった。
承平にはじまり天慶に終ったこの大乱を、世に承平天慶(しょうへいてんぎょう)の乱というのである。 |
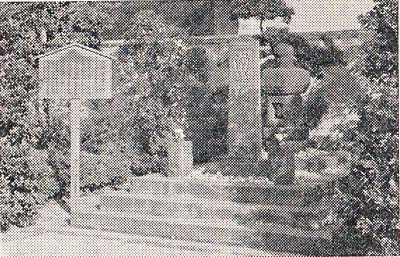
平将門の首塚 東京大手町のビル街にある。
|
6 前九年の役 top
平安のむかし、みちのくは文字通り「道の奥」であった。
京からへだたること数百里、そこは蝦夷(えみし=異民族)
* の跳梁する、さいはての異域であった。
* 蝦夷 “えぞ”と読めば江戸時代の北海道である。その頃は蝦夷地防御のため松前藩があるだけで、本土の人間はわずかだったが、明治に入って本土から多数の人間が移住した。これは東日本の諸藩の武士が失業して渡って行った者がおおい。
坂上田村麻呂を中心とした経略が成功し、陸奥(むつ)国府が多賀城に、鎮守府が胆沢(いざわ、現岩手県奥州(おうしゅう)市水沢)城におかれているとはいえ、やはりそこは荒ぶる蝦夷の国であった。
農民化した蝦夷は俘囚(ふしゅう)といって国府の支配下にあったが、夷俘(いふ)とよけれ狩猟を業とする蝦夷がいまだに蟠居(ばんきょ)していた。
永承年間、陸奥の俘囚の長である安倍頼良が朝廷に叛いた。
租税も払わず、力役もつとめない。
陸奥(むつ)国守の藤原登任(なりとう)が出羽の秋田城介(じょうのすけ=城主)平重成とともにこれを攻めたが、鬼切部の戦に、かえって大敗を喫してしまった。
そこで朝廷は源頼義を陸奥守兼鎮守府将軍に任命して、頼時を討たせることにした。
永承六年(一〇五一)のことである。
源頼義は清和天皇の後胤、源家の嫡流で当時相摸守であった。
生まれつき武略に長じ、勇猛人にすぐれてよく士を愛した。
そのため、門客、つねに室に満ちていたという。
頼義は長子の義家をはじめ精強無比の坂東武士団を率いて陸奥へ赴いたが、折りから大赦令が発せられ、罪をゆるされた頼良(よりよし)は頼義(よりよし)に帰順してしまった。
そして名前の音が将軍と同じなのはおそれ多いとして、頼時(よりとき)とあらためた。
天喜二年(一〇五四)頼義は任期が終わりに近づいたので帰京することになり、多賀の国府から胆沢(いざわ、現岩手県奥羽市水沢)の鎮守府にはいった。 |

源頼義・義家父子 前方中央が義家後方中央が頼義
〈前九年合戦絵巻〉
|
ここに十数日滞在している間に、一つの事件が起こった。
部下の藤原光貞の官営を何者ともしれぬ一隊が襲ってその人馬を殺傷し、風のように逃げ去ったのである。
そこで光貞を呼んで、誰がやったか心あたりはないかと問うたところ、
「それは頼時の長男貞任(さだとう)にうたがいなし」という。
先年、貞任が光貞の妹を妻に申し受けたいといったことがあった。
しかし光貞は俘囚(ふしゅう=とりこ)の長などに妹はやれぬと断った。
それを恨みに思っての仕業に相違ないというのである。
頼義はそれを理のあることとみなし、貞任を罰しようとした。これを聞いて頼時は怒った。
「およそこの世に人が生をうけているのは、妻子があるからだ。愚者とはいえ、貞任は自分にとっては子である。
いかなる理由があるとはいえ、子は見捨てられぬ。頼義が攻めてきたら防ぎ戦うまでである」
かくて頼時は一族あげて抗戦の覚悟をきめ、衣川の柵にこもった。
頼義の軍勢は大挙して衣川に迫ったが、その中に頼時の婿藤原経清、平永衡(ながひら)が従っていた。
この永衡が銀の兜をしているのを見て、頼義に讒言(ざんげん=悪口)するものがあった。
「なんといっても彼は頼時の婿である。表面は服属しているが、内心はどうであろうか。
あるいは内応の約束ができているのかもしれない。
目立つ銀の兜をつけているのも、いざ合戦のとき頼時の兵に射られないために違いない」
頼義はそれを信じ、永衡を斬った。すると経清が不安になった。
「前車のくつがえるのを見て後車の戒めとなすという言葉がある。次は自分の番だ。近くその日がやってくるだろう」と経清は頼時の陣へ逃走してしまった。 |
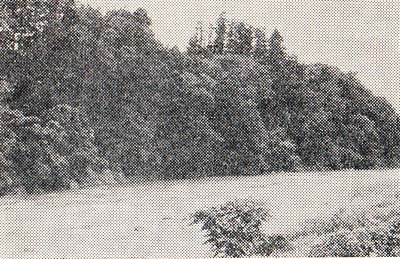
衣川の柵址 岩手県西磐井郡平泉町
|
こんなこともあって、攻撃が思うにまかせない間、朝廷は頼義の任期が終ったので新たに陸奥の国司を任命した。
しかし、新国司が現地の形勢に恐れをなして辞退したので、頼義が重任することになった。
天喜五年、頼義は現在の青森県のあたりのアイヌの長である安倍富忠を誘って頼時の背後を襲わせた。
激戦は二日に及び、頼時は流れ矢にあたって傷つき、鳥海の柵に帰って死んだ。
しかし、その子貞任らはなおも抗戦をつづけた。
頼義は朝廷にたいして援軍と兵糧の補充を申し送ったが、さっぱり反応がない。
そこで頼義は独断で河崎柵に貞任方の金為行を襲った。
しかし貞任は大軍をもって逆襲し、黄海(きのみ)に戦った。
ときに十一月の初旬、陸奥の地は風雪がはげしく、さすがの坂東武者も凍えと飢えに苦しんだ。
反対に雪になれた貞任の軍勢はさんざんに頼義軍を打ち破り、頼義の命さえもあやうくなった。
このとき、頼義の長子、若冠十七歳の義家は大鏃(やじり)の矢で敵を狙い撃ちにして百発百中、鬼神をもしのぐその勇猛さに敵がたじろぐ間に重囲をきりぬけて助かった。
八幡太郎の勇名がとどろきわたるのはこの時からである。
義家は石清水(いわしみず)八幡の社頭で元服し、それで八幡太郎といったという。
この戦いは頼義の生涯で最大の苦戦であり、多くの勇上が命をすてた。
貞任らの勢いはますますあがり、頼義は苦境に立たされた。
康平六年(一〇六二)頼義の任期がきれたので、朝廷では高階経重を後任として赴任させた。
しかし人々は頼義を慕って新国司に従わない。やむなく経重はそのまま京都へ引き返した。
こうなると頼義としては、是が非でも貞任らを討たねばならなくなった。
人々の信頼にこたえるためには、それ以外に道はない。
そこで頼義は出羽の国の俘囚の長、清原光頼、武則兄弟に珍宝を贈って協力をもとめ、援軍一万余を得て、まず貞任の弟宗任がこもる小松の柵(一ノ関市萩荘上黒沢)を攻め、宗任を敗走させた。
ところが、たまたま雨が降りはじめて数日つづき、頼義の陣では糧食が欠乏しはじめた。
宗任はこの機に乗じて頼義軍の糧道を断とうと、しきりに輜重(しちょう、食糧)隊を襲った。
そこで頼義は一千の兵を防戦に向け、三千の兵を付近の稲刈りにまわし、食糧を確保させた。
しかしこのために本営が手薄になった。
これを探知した貞任は精兵八千をもって頼義の陣を襲ったが、かえって敗北を喫し、衣川の柵に走った。
衣川の柵は中尊寺で名高い平泉にあった。
北上川の支流、衣川沿いの柵址は欝蒼たる森になって、かっての要害ぶりをしのぶすべもない。
勢いに乗じて頼義は衣川に迫ったが、降雨で水量の増した衣川の流れが天然の濠になって寄せ手の進撃を阻(はば)んでいる。
このとき清原武則の郎党に久清という者があって、ひそかに柵中にしのびこみ、火を放った。
これを合図に寄せ手は筏を組んで川を渡り、どっと柵中になだれこんだ。
貞任はあわてて柵をすて、逃れようとした。
これを義家が追いつめ、「衣のたてはほころびにけり」と詠(よ)んだところ、貞任はふりむいて、「年を経し糸の乱れの苦しさに」と前の句をつけた。
義家はそれに感じ入り、つがえていた矢を外して貞任を見逃したという。
頼義はさらに進んで白鳥の柵を抜き、ついで鳥海の柵を陥した。
しかし貞任は最後の拠点、厨川(くりやがわ)の柵に拠ってなおも抗戦の構えをみせた。
厨川の柵は北上川西岸の崖の上(盛岡市大新町天昌寺)に築かれていたが、その要害ぶりは『陸奥話記』によると、川と柵の間に空濠が掘られ、底に刀を逆さに植え、地上には鉄菱をまきちらして敵を防ぐようにつくられていたという。
しかし現在、それらの跡はすべて消え失せ、ただ、奥羽街道のかたからに厨川柵址を示す小さな石柱が立つばかりで、古代奥羽(おうう)の覇者の遺跡というにはあまりにも寂しい。
頼義は総力をあげて攻撃したが、城中からは大弓や石で応戦し、柵に近づいた敵には熱湯をかげろという戦法で、びくともしない。
攻めあぐねて兵を引くと、櫓の上で美女を舞わし、寄せ手をあなどる有様である。
|

厨川の柵址 盛岡市大津町天昌寺
|
そこで頼義は付近の民家をこわしてその屋根の萱を柵の前に積み、氏神の石清水八幡に祈って火をつけた。
すると、たちまち大風が起こって柵中に飛び火し、大混乱におちいった。
貞任は柵を出て決戦をこころみたが、ついに負傷して捕われ、大楯にのせられて頼義の前に引き出されたが、一言もはなさず息をひきとった。
身長六尺有余、腰囲七尺四寸、容貌魁偉(かいい)、皮膚肥白だったという。
白人であったらしい。アイヌは白人 * である。年三十四。
* アイヌ 当時の東日本には、多数のアイヌがいたらしい。
貞任の弟たちのうち、重任は斬られ、宗任、家任、則任は降参した。貞任の子千世童子も斬られた。
城中で泣きさわいでいた美女数十人も捕えられ、頼義の部下に分け与えられた。
こうして厨川の柵は落ちた。康平五年九月十七日のことであった。
戦端が開かれてから十二年を経たわけである。
いまは前九年の役というが、これは後年になって誤りつたえられたものである。
康平六年二月、頼義は貞任、重任、経清らの首を京都に送った。
朝廷はその功を賞し、頼義を正四位下伊予守、義家を従五位下出羽守、清原武則を従五位下鎮守府将軍に任じた。
7 後三年の役 top
永保半年(一〇八三)九月、源頼義の子、八幡太郎義家は、陸奥守(むつのかみ)に任じられ、鎮守府将軍も兼ねて陸奥へ下った。
このころ、出羽国では清原家に内訌(ないこう、内輪もめ)が生じていた。
清原家の当主は、前九年の役に功のあった武則の孫真衡(さねひら)であった。
真衡には子がなかったので、成衡を養子として常陸の多気権守宗基の女(むすめ)とめあわせた。
このとき一族の吉彦季武(きびこのすえたけ)という者が祝いに来て、黄金をつんだ盤をささけて庭にひざまづいた。
ところが真衡は客と碁をうっていて、季武のことを忘れていた。
季武は老人である。しだいに疲れて苦しくなってきた。そして腹を立てた。
「じぶんは真衡とは同族である。ただ果報の優劣によって主従となっているにすぎない」
そう考えると重いものを捧げてひざまづいているのがばからしくなり、やにわに盤をなげ出して郷里へ帰ってしまった。
真衡のほうも怒り、ただちに兵を率いて季武を討とうと出羽へ向かった。
すると季武は一族の清衡と家衡(真衡の異母弟)に、「真衡ごときに臣従するのを無念と思わぬか」とけしかけた。
二人はただちに季武に応じ、真衡の留守をついた。
しかし、報せをうけた真衡が急ぎ引き返すと、家衡、清衡も兵を引いて対峙した。
義家が赴任してきたのはこのころである。
真衡の妻はしきりに義家の機嫌をとりむすんだ。そこで義家は真衡を援け、清衡、家衡と戦った。
戦況は義家に有利だったが、真衡が病のため頓死してしまった。
そこで清衡・家衡は義家に降り、義家は清原家の上に君臨することになった。
ところが、こんどは清衡と家衡のあいだが不和になった。先に手を出しだのに家衡である。
刺客を放って清衡を暗殺しようとしたが、失敗すると清衡の館を襲って妻子を殺した。
清衡は命からがら逃げ出し、義家の助けをもとめた。
応徳三年(一〇八六)義家は沼柵(秋田県平鹿郡沼館町)に家衡を攻めた。
攻防は数か月におよんだが、柵は容易に落ちない。
やがて冬が訪れるとともに出羽の山河は吹雪につつまれ、義家の軍は寒気と飢えに苦しみはじめた。
軍馬を食い、互いに抱き合って暖をとり、義家みずから凍死寸前の兵士を抱きあたためて蘇生させたほどだという。
やむなく義家は囲みをといて国府へ引きあげた。
義家の弟、新羅三郎義光は兵衛尉として京都にいたが、兄が苦戦していろとの噂を聞くと矢も楯もたまらず奥州に下った。
弟と対面した義家は涙を浮かべ、「お前の顔を見ると故入道(父頼義)の生まれかわりのような気がする。お前の助けがあれば、もはや賊は討ち平らげたも同然である」と喜んだ。
一方、家衡の陣には新たに叔父武衡が加わり、両者は沼柵をすてて金沢柵に移っていた。
寛治元年(一〇八七)九月、義家はふたたび大軍を発してこれを囲んだ。
金沢柵は現在の秋田県横手市金沢公園にあって、いま城址には義家が戦勝を祝って兜を埋めたという兜八幡社と石清水八幡を勧請した八幡神社がある。
本丸跡は東西約四〇間、南北約六〇間の台地で、両側は深い谷にのぞむ要害の地だ。
本丸の南方に斥候(ものみ)山という丘があり、ここにのぼれば寒々とした北国の空の下に横手平野がひらけて、その果ては、はるか出羽の山波につらなる。
金沢柵を囲んだ義家麾下数万騎の大軍は雲霞(うんか)のように野山にみちあふれた。
その時、雁(がん)の群が一列になって空を飛んで行くのが見えた。
突然、その列が乱れ、四方に飛び散った。 |
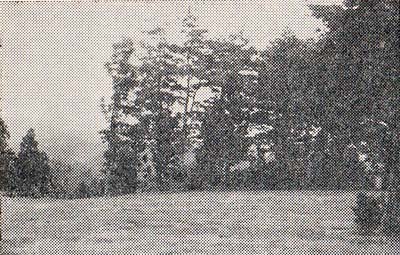
金沢の柵本丸址 横手市金沢公園
|
義家はそれを望み見てあやしみ、兵たちに介して付近の草むらを探索させた。
果たしてそこには敵の伏兵がひそんでいた。義家の兵はたちまちこれを押し包んで射殺してしまった。
義家のこの彗眼にはいわくがある。
先年、義家が宇治殿で前九年の役の物語りなどしたとき、大江匡崕という者があって、
「義家はなかなかの器量の武士だが、惜しむらくは合戦の道理を知らぬ」とひとりごちた。
郎党がこれを聞きつけて義家に告げたところ、義家は怒らず、かえって匡房の門を叩きその教えを乞うた。、
その折、講義をうけた兵書の一つに「兵野に伏すときは、雁の列破る」とあった。
この知識が敵の伏兵を見破ったというのである。
かくて金沢の柵はまったく義家軍に包囲されたが、その構えは堅固で、なかなか手が出せない。
このとき家衡の郎党に藤原千任という者があり、櫓の上に立って義家をののしった。
「過ぐる年、汝の父頼義は故清原将軍武則の助けをかりて貞任、宗任を討つことができたのではなかったか。
それにもかかわらず、いま重恩を忘れて弓を引くとはなんたる不義不道。かならずや天道の責めを蒙るであろう」
義家は激怒してただちに攻撃を開始した。
義家麾下(きか)の勇士たちは力をつくして戦ったが、柵中からも遠いものは矢で射、近いものは石弓を放って応戦し、寄せ手の死傷者は数知れずという有様だった。
寄せ手に相摸の国の住人鎌倉権五郎景正という者があった。 年わずか十六歳だったが、臆せず命のかぎり戦っていた。 激戦のさなか、矢が右の目にあたり、首のうしろまで射抜かれるという深傷を負った。
景正は気丈にもその矢を折って射返し、敵をしとめた。
それから後陣へもどると同国の三浦平太郎為次がおどろいて、景正を仰向けにねかせ、足で景正の顔をおさえて矢を抜こうとした。
ところが景正が下から刀で突き刺そうとしたので為次が「なにをする」と叫んだ。 すると景正は答えて、「弓矢にあたって死ぬるは武士たるものの本懐である。
しかし、生きながら顔を土足で踏まれるのは末代までもの恥辱だ」といった。 聞いて為次は非礼を詫び、膝をかがめて顔をおさえ、矢を抜いた。
これを見聞くもの、感嘆しないものはなかった。
いまも古戦場の一隅に鎌倉権五郎景正の功名塚というのが残っている。 |
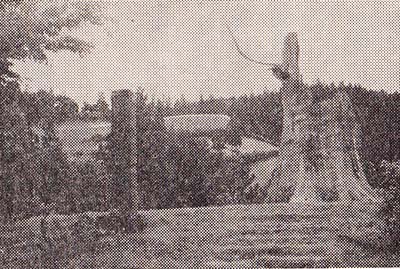
権五郎景政の功名塚
|
戦端が開かれてから、はや数日を経たが、柵は落ちる気配もない。
そこで義家は毎日「剛臆の座」を設けて督戦した。
その日勇敢に戦った者を「剛の座」に、働きのなかった者を[臆の座]につかせるのである。
だれしも「臆の座」につくまいと必死に戦うのだが、戦況は思うにまかせない。
やがて冬も近づこうとしている。寄せ手の胸中に去来するのは、昨年沼の柵を囲んだときの悪夢である。
このとき吉彦季武が義家に献策した。
「城の備えは固く、味方は戦いに飽いている。
この上は無益な戦いをやめ、ただ包囲して糧食が尽きるのを待つべきでありましょう」
義家はこの策をいれ、退いて包囲をきびしくした。案の定、柵の中では糧食が尽きてきた。
そこで武衡は義光に降参のことを申し送った。義光はこれを義家に語ったが、義家は許さなかった。
すると武衡は、義光に城中へ来てくれと懇願した。その供をして柵から出すというのである。
義光が単身柵中へおもむこうとするのを義家は、
「昔から今日まで、大将副将が敵陣に行くなどということは聞いたためしがない。もし敵方の俘虜になったら、それこそ恥を末代にさらすことになろう」といって許さなかった。
秋が過ぎ、冬になった。城中は飢餓に苦しんだ。
そこで、せめて女子供だけでも柵から出そうということになり、木戸が開かれた。
女子供が続々と群れをなして出て来るのを見た季武が、「これらの女や子供の頸(くび)を斬るべきである」という。
義家がその理由をたずねると、
「この女子供たちが斬られるのを見たら、恐れてもう柵からはだれも出なくなるでありましょう。
そうすれば、城中の糧食はそれだけ早く尽きるはずです」
義家はこれを聞いて、なるほどとうなずき、敵の眼前でことごとく斬った。
このため、城を出る者がなくなって、城中はますます窮迫した。
十一月十五日の早暁、城中から火の手があがった。たまりかねた城兵が脱走しはじめたのである。
火炎地獄の城中に乱入した義家の兵は殺戮(さつりく)をほしいままにした。
武衡は池の中にひそんでいるところを発見されて捕われ、斬られた。
千任も捕われ、木の枝につるされた。
足下に武衡の首が置かれ、足をちぢめなければ主君の頭を踏むことになる。
時がたって千任は力つき、主の首を踏んだ。
これを見て義家は、「二年の愁眉が今日ようやく開いた」といった。
家衡は一旦は柵を逃れたが県(あがたの)次任という者に討たれ、首は義家のもとに送られた。
かくて三年のあいだ出羽の天地をゆるがした戦いも終わりを告げた。
『奥州後三年記』には、「城中の美女ども、つわもの争い取って陣のうちへ率いて来る。
男の首は鉾(ほこ、槍に似た武具)にさされて先に行く。妻は涙を流してしりに行く」とある。
戦いのつねとはいいながら、まことに悲惨な光景である。
戦後、義家は朝廷に鎮定の顛末(てんまつ)を報じ、追討の官符を賜らんことを願い出た。
しかし朝廷はこれを私闘とみなして顧みなかった。
そこで義家は、私財を投じて部下の功を賞したのである。
坂東武者の義家を徳とすること、限りがなかった。
top
**************************************** |