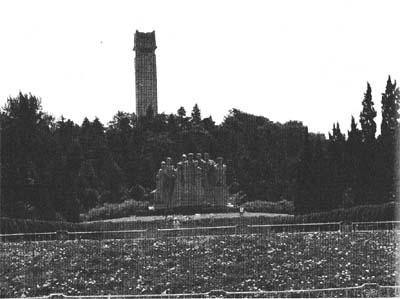|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章
二章 南京からの手紙
|

長江(揚子江)にかけられた南京大橋
|

天秤をあやつり荷物を運ぶ女性

道路はトロリーバス、自転車が行きかう
|
上海から南京へ、特別快速「火車」(ホアツアー)で約三百キロを、全くのノンストップ四時間
* で走りました。
* この頃から中国での新幹線網の建設がはじまり、今は上海〜南京間は一時間三十五分で走る(ネットより)
「火車」って、中国語で汽車、列車のことで、駅は「火車站」(ホアツアーズア)、そして「汽車」はなんと自動車なのです。
ついでに書けば「机」は機械のことだそうで「飛机」(フェイジイ)で飛行機になり、「司机」(スーチー)はドライバーだとか。
「飯店」(はんてん)はホテルで「飯館」(はんかん)がレストランと、わかりそうでいてわからなく大いに面くらってしまいます。
火の車と書いて、どうして列車になるのか。
がっての蒸気機関車は石炭をくべて、釜を真っ赤にして走ったから、その名残りかもしれませんが、なんだか、尻に火がついたような感じでたどりついた南京の町でした。
ついにきた、戦禍の目的地へ!
日本人にとっては、加害の町でもあります。
夏は最高四十度近くにもなるという南京は、かっと照りつける直射光にさらされていましたが、市内に入ると、それはどの炎暑を感じません。
というのは、通り路がみな木陰で、緑したたるようなトンネルになっているからです。
通りの両側はうっそうたるプラタナス、ポプラ、楊柳(やなぎ)などの巨木で、中心部のバス車線から、その左右の自転車専用路、そして歩道まで、緑がびっしりと街路全体を覆いつくしているのが、南京の初印象でした。
この緑のおかげで、気温も確実に三、四度は低くなっているとか。
確かに気のせいばかりでなく、ごみごみとした国際都市、上海とくらべ、町全体がどことなくおっとりとしたたたずまい。
「これらの街路樹は、解放後まもなく政府が植樹したものですけど、秋になると一苦労です。
わかりますか、落葉のかたづけですね」
という通訳さんの説明に、さもあろうと私はうなずき、ほっと息を抜きました。
かって、悪名高い日本軍の蛮行で放火され、焼きつくされたはずの町に、街路樹だけが無事に生きのびたとは思えなかったからです。
それにしても、戦禍の町というにはほど遠いイメージ、さわやかなグリーンの町並に目がなごみましたが、すべてはこれからです。
車で行くと、町のあちこちに天をつくばかりの城壁が残っていて、素人目にもわかったのは、ああ、ここは要塞の町なんだ、ということ。
南京城と呼ばれた所以です。地図を広げてみました。
市の西北に長江(揚子江)が流れ、東の紫金山(しきんざん)、南の丘陵雨花台(うかだい)、西には清涼山(せいりょうざん)をのぞみ、これは外敵をよせつけぬ天然の地型です。
その南京は北の都・北京に対して、文字通り南の都として古くから栄え、紀元前五百年ほど前の戦国時代に、はやくも城の原型といえるものが建てられたとか。
それが発展して、一大城廓都市となっだのは明(みん)の時代、今から千三百年ほど前のことで、南京城は外まわり三十五キロにおよび、十三の大門をもつ威容となったと通訳さんの話。
レンガ造りの城壁の一部はいまも残っていますが、高さ十五〜二十メートルにも達するという。
そして、この町は、激動の歴史の舞台となり、いずれも短期間ではあったけれど、何度か中国の首都になりました。
一九一二年には「中国革命の父」と呼ばれた孫文(そんぶん)による中華民国臨時政府がおかれ、それから十八年後(1930)には蒋介石(しょうかいせき)による国民政府の樹立。
そして一九三七年には、日本軍による南京大虐殺の悲劇の場となり、人民解放軍によって、解放されたのは一九四九年のこと。
次に生活文化の面で、南京と日本とのかかわりは、どうか。
かって中国から日本にきて、南京にちなんだものを、通訳さんが次々と上げてくれました。
それらはかならずしも南京産とはいえないのに、南京に首都があった関係でつけられた名称のように思えます。
たとえば、南京豆、南京米、南京袋、南京錠、南京木綿、南京虫、手品の南京玉すだれ。
「ああ、南京虫も、中国からきたのですか。
戦中戦後にかけてシラミと一緒に僕もずいぶんひどい目に会いましたが、いつ頃どうやって海を渡ってきたんでしょうね」
「さあ、それはわかりません」
「まさか、海を泳いできたわけじやないでしょうから、もしかして、南京で悪いことをした日本軍が持ち帰ったのでは……」
通訳さんは笑いましたが、あるいは、そんなこともありうるかもしれません。
日本兵が南京虫を土産にするはずはないから、兵士の肌にしがみついてきたとすれば、相当な抵抗精神があったというべきでしょうか。
いや、これは冗談。
|

南京市の住宅街は細い路地にそって並んでいる
|

庶民的な街角風景

南京城からみる泰淮河にかかる橋
|
南京ばかりとかぎったことではありませんが、中国の町で、私たちがまっ先に目を見張るのは、朝から夜まで路上に途切れることのない自転車の大群です。
ほんの少しだけ、路上風景に目を移すとしましょうか。
自転車はレジャー用品ではありません。実用品です。ですから決して軽快な感じではなく、頑丈そのもの、車輪も大きくて二十八インチとか。
しかもサドルをいっぱいに持ち上げて、短足の日本人にはとてもペダルに足が届きそうにないのです。信号はあってないようなもの、ものすごいスピードで突っこんできます。
そこ退けそこ退け自転車が通るで、たとえ交差点といえども、青信号を一人で渡るのにはかなりの勇気がいります。
少しハラを決めないことには、いつまで待っていても、通りを渡れません。
いま南京市の人口は二百二十万人、自転車の数は百二十万台といいますから、人々の半分以上が専用の自転車を持っていることになりましょうか。
南京には、市内電車も地下鉄もありませんから、人々の交通手段はバスで、そのバスがいつも超満員となれば自転車にたよらざるをえず、自転車がいわば人々の足であり、マイカーなのです。
それはわからないではないけれど、歩行者が小さくなっていなければならないのは妙な話で、もう一つ、理解に苦しむのは、どの自転車も例外なくライトなし。
夜なんか、街灯のない闇のなかを、照明なしの自転車がゲリラの大群のようにやってくるのは、ぶっそうでなりません。
「ライトをつけると、明りに目がくらんで、交通事故が増えますからね」
通訳さんのもっともらしい説明ですが、それでニコリともしないところをみれば、ご本人も納得しているらしい。
慣れというのはおそろしいもの。本音は、おそらく省エネにちがいないのですが。……
それにしても、緑のアケ−ドを散策して飽きることがないのは、いまや私たちの日常から遠ざかってしまった生活感から溢れる活力といったものでしょうか。
通りは単に自転車の大群ばかりでなく、リヤカーに大荷物をつけてけんめいにペダルをこぐ人もいれば、うしろに二人がけの座席に両輪をつけ、前のほうは普通の自転車の、これは人力タクシーといったらいいか。
たまに田舎からきたらしい馬車も、一昔前、日本にあったオート三輪から、サイドカー式のバイク、荷物いっぱいの改造乳母車と、既製品ではなくて、ほとんど持主の個性もあらわなオリジナルです。
ひどい暑さにもめげず、みな汗水流して、それら愛着のマイカーに満足そうです。
バスは、かなりの年季ものの骨董品の二両がジャバラでつながっていて、頑具のがらがら蛇みたいにやってくるが、どうやってあんなに奥まで人が入ったかと思うばかりに、缶詰並みに超満員です。
乗降口にいる車掌からキップを買うにも買う手がのびず、バス代金はたいてい乗客たちの手渡しリレーになるとか。
それは、通訳さんから聞いたお話で、私は興味があったものの、ついに一度もバスに乗らずじまいでした。
乗ってみたいのはやまやまですが、バス代を渡せずに、無賃乗車とやられてはかないませんし、それに日本人に向けるであろう一般の視線。……
気にならないといったらウソになります。
さて、気の重い戦争関係の取材を明日にひかえた一日、私はツアーできた知人たちのバスに乗せてもらいました。
南京の特徴を知ることも大事で、冷房のよくきいたバスに便乗できるのなら願ってもないチャンスというべきでしょうね。
なんといっても、南京の最高の見どころはといえば、中国革命の先駆者、孫文(そんぶん)こと孫中山が眠る中山陵(ちゅうざんりょう)でしょうか。
「革命いまだ成らず」のひとことを残して、一九二五年に病死した孫文の墓は、紫金山の中腹にあって、花崗岩の石段を登りつめたところ。
石段は、なんと三百九十二段。炎天下の登りはつらく、それでもなんとか祭堂にまでたどりつき、大理石の臥像(がぞう)のついた柩(ひつぎ)をカメラに収めました。
ところが、帰途に石段の途中まで、追いかけてくる男あり、罰金を払えとのこと。どうやら撮影禁止だったようです。
なお罰金は五角(十八円)で、ちゃんと領収書をくれました。それにしても十八円の罰金とは……。 |

「中国革命の父」孫文がねむる中山陵と孫文と夫人の宋慶齡
|
|

上海→南京→北京と通訳で同行してくれた沈さんと著者
|

1968年、8年の歳月をかけて完成した長江大橋
|
次は市の北西、雄大な長江の流れをひとまたぎにする長江大橋です。
一九六八年に約八年もの歳月をかけて完成した南京市ご自慢のもので、全長六千七百メートルもの二層橋。
上段は自動車道で、両側に歩道があり、下段は鉄道用複線になっています。
ご自慢の理由は、ソ連の技術者たちが中ソ分裂のために引き上げてしまったあと、中国人の独力で完成させたところにあるらしい。
「自力更生」の結晶をごらんくださいという次第でしょうか。
そして、中華門。市の南にあって、かっては聚宝(じゅほう)門と呼ばれ、明の時代の南京城南門になります。
門の前の流れは泰准河(たいわいこう)で、外部からの人はみな橋を渡って門をくぐることになる。
要するに、南京城への交通の要衝にあったといえましょう。
こんにちに残された中華門は南北、東西、ともに百二十メートルに及び、高さは約二十メートル。
城壁の上には城楼がそびえ、壁面には緑のつたがびっしりと這い、眼下の町並が一望のもとに見放せます。
眺望は申し分ないものの、夏の日射しは相当なもので、たちまち汗みどろになりました。
さらに玄武湖公園へ。南京駅前の通りをへだてた南側にある湖です。
五つの島があって、市民の憩の場となっているらしい。
島といってもかなりの面積で、屋外劇場や音楽堂、プールもあります。
どの島にも環湖路を経て車で自由に入ることができますが、さざ波の立つ湖面はいかにも水々しく、涼風が猛暑をやわらめてくれるせいか、目のやり場に困るほど若いカップルばかり。
島の一つである菱洲島にはミニ動物園があって、日本でもおなじみのパンダがいます。
中国ではそう珍しい動物ではないのか、見物人はちらほら程度。
上野動物園で見るのとちがって、薄汚れてきたならしいパンダにがっかりしましたが、あるいはそれが野性の姿に近いのかもしれません。
パンダ見学のあと、玄武湖を後に市内へ。
外人向けのお土産専門店「友誼(ゆうぎ)商店」に寄って、いろいろな品物を物色する大たちに見習い、ちょっぴり買いこんでバスに乗りましたら、さすがに疲れました。
冷房がきいていて、気持ちよかっだこともあります。ついうとうととして、自転車と人の雑踏にバスが渋滞したところで、目をさました。
その時、私は、かすかな胸騒ぎを感じました。
バスのガラス窓ごしに何気なく見だのは、街角のモニュメントですが、なにか私と関係ありそうな。
いや、そっちのほうが先に目のなかに飛びこんできた、といっていいのかもしれません。
「あの、ちょっと、ここでおろしてくれませんか……」
歩道から何段か石段を上ったところに、幼児の遊び場ほどの小空聞かあって、通りすがりの人を包みこむような楕円型のモニュメント。
そこに私は、「日本軍」という文字をちらと見かけたような気がしたのでした。
|

南京市北極閣の街並にあるモニュメント
バスを降りて、石段を上ってみると、やはり思った通りです。 白い花崗岩の上部に、黒い大理石が横一列にはめこんであって、私でも読める漢字の配列は「侵華日軍南京大屠殺北極閣付近遇難同胞紀念碑」としるされ、その下に「南京市人民政府 一九八五年八月」と刻まれています。
そして献花がどっさり。 |
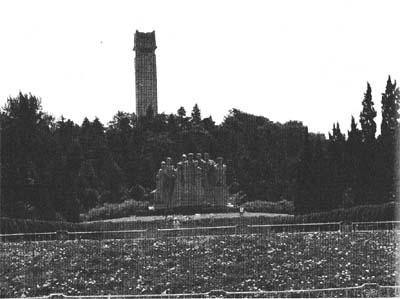
雨花台に立つ殉難者の群像碑(上=全体図、下=アップ)

|
戦後四十年目に南京市によって建設された慰霊碑で、「日軍」だけで日本軍とあらわすのでしょう。
「このあたりが、北極閣というんですか?」
と、通訳さんにたずねますと、
「ええ、そうです。この付近だけで、二千人からの同胞が殺されました。一九三七年十二月に……日本軍に……」
「この付近といいますと、どのへんまで含まれるのですか」
「いま私たちの車がきた通りを北京東路といいますが、東へ二キロばかり行ったところに太平門があり、その先に富貴山かあります。 そのあたりまで、至るところ死体だらけだった、ときいています」
「同じようなモニュメントは、まだほかにもあるのですか」
「ええ、ここが、その一つです」
日本軍がしでかしたことを同じ日本人に語るせいか、通訳さんは言葉すくなめでしたが、しかし必要なことだけはきちんと語ります。
それが、中国人の、あるいは通訳としての義務と考えているのかもしれません。
たった一日の観光でも、私は、くるべきところにきてしまったらしい。……
中国旅行ブームとはいっても、日本からわざわざ南京にやってくる観光客はそう多くないはずですが、こんなときには一体どうしたらよいのだろう。
なんといったらよいのだろう。
中国側は日本からの観光客には、戦争のセの字も見せないように配慮していると聞きます。
ですから、たまたま目に入ったとしても、見て見ぬふりをする人が大半ではないのでしょうか。
しかし、それではたとえ観光であったにしても、マナーに欠けます。もちろん、おたがいの友好にもなりません。
なぜかというなら、こちらに関心があろうとながるうと、相手方はちゃんと過去の歴史をおぼえているからです。
現にモニュメントを前にしての私の質問に、戦後生まれの若い通訳さんは、メモひとつ見ることなく、その周辺の被害状況を説明してくれる。ということは、なんでもちゃんと知っているのです。
知っていても、必要でなければしゃべらないだけのことなのです。
人をなぐった側はその事実を忘れても、なぐられた方の痛みはいつまでも消えることがないのでしょう。
それにしても私は、碑文のなかの「屠殺」(とさつ)の二文字に、すくなからぬ衝撃を受けました。
もしかして、中国には「虐殺」という用語はなく、同意語が「屠殺」なのかもしれないけれど、しかし、屠殺といえばすぐ屠殺所が思いうかび、それは家畜などの獣類を、肉や皮の必要から殺すところのはず。
日本語では、人間が対象ではないのです。
してみると、南京では、日本軍によって、人々が家畜なみに殺されたということなのでしょうか。
残念ながら、そう考えざるをえません。
かつて南京へと攻めのぼった日本軍のなかには、全員がそうだなどとはいいませんが、中国軍を全く人間と見なしていなかったのではないか、と思えるふしがあります。
たとえば、今度の旅で読みつづけてきた石川達三の小説『生きている兵隊』(新潮文庫)の一節に、次のような描写が目につきます。
やがて発煙筒は穴の中に投げこまれた。
両側の入口からむくむくと煙が出てきた。
笠原は兵を押しのけて軽機の台尻をかかえこみ、ぴたりと畦(あぜ)の泥に寝そべった。
暫くすると、青服に着ふくれた支那軍の正規兵がひとり煙の中からとび出して、頭を両手でかかえて走り出した。
方角も何もあったものではない。ただ真一文字に走り出したのであった。
だだだだ……と彼の機銃は大地を慄(ふる)わせて鳴った。
「一匹!」と笠原は怒鳴った。
次に二人つづいて同じようにとび出した。
「二匹、三匹!」
再び機銃は菱形の炎を吐いて鳴った。
――そうして彼はついに十一匹まで数えると立ち上って歩きだした。 |
『生きている兵隊』は、日本軍が南京を陥落させたあと一ヵ月もしないうちに、現地を直接に取材して書かれた氏の代表作のひとつですが、あまりにもなまなましく「戦争の実態」を描き過ぎてか、掲載誌の『中央公論』は発売と同時の一九三八年二月に発禁処分となりました。
当局にとっては、日本軍の信頼をいちじるしく傷つけるものと解釈したのでしょうが、それだけに真実に近い実態を伝えていたとも考えられるのです。
敵味方が対峙(たいじ)する戦場での戦闘員同士の殺し合いは、戦争そのものの宿命ともいえますが、しかし、その敵兵を「一匹」「二匹」と数えて殺していく兵士の異様な神経は、作者にいわせれば、一人の敵兵を殺すことは一匹の鮒を殺すと同じで」「殺戮(さつりく)は全く彼の感情を動かすことなしに行われた」のだという。
感情を動かすことなしにとありますが、人間にとっていかなる状況下でも決して動かぬ感情なるものがあるのだろうか。
だとすると、それはもはや感情とはいえないのではないか。……
感情なしの人間は存在しない以上、彼らはもはや人間ではなかったのかもしれない。
そんな機械じかけの兵士たちによって行われた無差別の殺戮が、あるいは屠殺といえるものだったのかもしれないのです。
彼らは真暗な家の中へふみこんで行った。
砲弾に破られた窓から射しこむ星明りの底に泣き咽(むせ)ぶ女の姿は夕方のままに踞(うずくま)っていた。
平尾は彼女の襟首を掴んで引きずった。
女は母親の死体を抱いて放さなかった。
一人の兵が彼女の手を捻じあげて母親の死体を引きはなし、そのままずるずると下半身を床に引きずりながら、彼らは女を表の戸口の外まで持って来た。
「えい、えい、えいッ!」
まるで気が狂ったような甲高い叫びをあげながら平尾は銃剣をもって女の胸のあたりを三たび突き貫いた。
他の兵も各々短剣をもって頭といわず腹といわず突きまくった。
ほとんど十秒と女は生きてはなかった。
彼女は平たい一枚の布団のようになってくたくたと暗い土の上に横たわり、興奮した兵のほてった顔に生々しい血の臭いがむっと温かく流れてきた。 |
『生きている兵隊』は小説ですから、もちろん虚構の世界ですが、なんともやりきれぬページをめくるうち、南京大虐殺ならぬ大屠殺は、まるで嵐の前ぶれの黒雲のような戦慄(せんりつ)をともなって、私の前にみるみる迫ってくるのでした。
ああ、もう、ここから身を引くことはできないようです。
top
**************************************** |