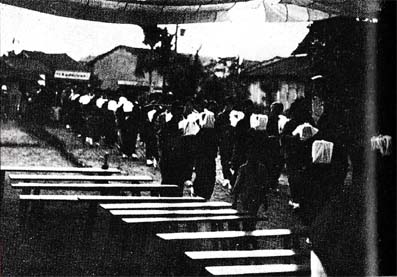|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章
二章 霧社(むしゃ)事件についての手紙
|

霧社の町並(上)と案内図(下)

|

霧社(現仁愛郷)事件の現場
|
1 台湾は「鬼が島」と top
純ちゃんへ。
一回目のファックス通信は、届きましたか。
あなたにとっては、きっと初めて知る事柄がいろいろ出てきたと思うけど、内容はいかがでしたか。
いやいや、ちょっと無理だったのでは……と、長い手紙を送信し終えたあとに、ふっと気がつきました。
かっての日本の植民地支配といえば朝鮮を、侵略といえば中国と、とっさに思いつく人も、台湾については戸惑う面が少なくありません。
いわんや霧社事件の霧社がどのあたりにあるのかさえ、実は私だって知らなかったのですから。つい先頃までは――。
やはり、いささかの説明が必要なようです。
そこで、引き続きこの手紙では、現地に入る前に、私の思い出やら日本と台湾との関係、さらに霧社事件のあらましをメモすることにします。
*
私の少年時代はあの戦時中でしたが、いま振り返ってみれば、人権尊重などクスリにしたくてもないような時代でした。
当時の軍国主義教育は、極端な他民族蔑視思想を軸にして、「国民即戦士ノ覚悟」の敵愾心をあおっていったのだと思います。
台湾に「生蕃」がいるとは、いつの頃だったか教室で耳にしたのですが、黒板に「蕃」の文字を大きく書いた先生は、すぐ横に「蛮」と添えました。
文明からはほど遠い「野蛮人」ということでしょうか。
「台湾はわが国の領土だが、昔は鬼が島だったんだ。
チフスにコレラ、ペストにマラリヤと恐ろしい病原菌がうじゃうじゃしていて、おまけに山には生蕃だ。
別名は首狩り族といってな、うかうかしていれば、バンコロに首を取られてしまう。
だから皇軍は桃太郎と同じだ。
キビ団子のかわりに日の丸を掲げて鬼退治をし、命がけで守ってきている。
これすべて東洋平和のためにだ」
桃から生まれた桃太郎が、日の丸の鉢巻きをしめて、犬、猿、キジをお供に攻めていった鬼が島は、どこの島なのかは知らないけれど、台湾もそうだというのは驚きで、それと「生蕃」(せいばん)の二文字がなにやら不気味な存在として、強く印象づけられたのでした。
当時、支那=中国人の蔑称に「チャンコロ」、朝鮮人「半島人」のほかに、「バンコロ」がいたというのは初耳でしたが、まもなくして日本が南で激戦を交えている敵主力の 米英は、「鬼畜」(きちく)とされていったのです。
その頃は、町で青い目の外人などめったにお目にかかれませんでしたから、皇軍が必死でたたかっている敵は、本当に鬼か牛みたいなもので、頭に二本の角でも生えているかのように思ったものです。
日本は桜エビみたいな小さな国なのに、こんなに多くの鬼やケモノたちを相手にしては、たとえ挑太郎といえどもラクじやないと思ったけれど、もちろん口にすることは禁物だと、子供なからにわかっていました。
しかし、考えてみれば、台湾は「外地」とはいえ、地図の上に赤く塗られた日本の領土なのです。
その山地にいる人たちといえども、「一視同仁」(いっしどうじん)なら、共に敵とたたかう同胞ではないのか?
しかも、戦時下の私たちの生活は、その「外地」によって支えられている面がかなりありました。
最近調べてわかったことですが、たとえばコメです。あのきびしい食糧難の日々に、海を渡ってきた「外米」のうち、もっとも多かったのはベトナム米でした。
それが引き金となって生じたベトナム大飢饉は別の本に書きましたが、実は台湾米もかなりの量になっています。
農林省資料によれば、一九四〇年の杣人米のうち、台湾米は二三%、四三年は一八%、四四年は一九%です。
“なにがなんでもカボチャを作れ”という標語が町中に張り出された頃まで、私たちが台湾米に助けられて生き抜いたのは、紛れもない事実なのです。
それを「鬼が島」だなんて、間違っても言えた義理ではなかったはずです。
|

霧社遠景
|
2 台湾出兵から七〇年戦争 top
さて、その台湾に日本が出兵したのは、一八七四(明治七)年のことでした。
日本の近代史は約一二〇年ですから、それをそっくりそのまま引くと、日本の侵略の発端と経過が浮き彫りになってきます。
すなわち一八七〇年代までさかのぼるわけですが、この頃の歴史的な大きな節目は、なんといっても明治維新です。
「富国強兵」策を前面に打ち出した天皇制明治政府は、たまたま台湾で起きたある事件を口実に、南方への前進基地を確保すべく、最初の対外軍事行動を起こしたのでした。
一八七一年のこと、沖縄漁民が折からの暴風雨で台湾東部に漂着したところ、外敵がやってきたとかんちがいした先住民族に殺害されたのが、事の起こりです。
日本は報復を大義名分にして、台湾出兵を閣議決定、大軍を台湾に上陸させて、半年余にわたり暴れまわりました。
これが一八七四年の、いわゆる「台湾征討」です。
兵を引くについては、台湾を支配していた清国(中国)から、五〇万両(テール)という賠償金をせしめた上に、帝国の皇威を広く内外にアピールすることができたのでした。
日本の外征の第一弾だったといえましょう。
|

現地駐在の日本人巡査(中央)を歓迎する高地住民。
「台湾征討」(1874年)以後、帰順した島民に「日の丸」が与えられた
次いで、その台湾を清国から切り離してわが手に収めた上、二億両(テール)もの賠償金と、数々の特権を得たのが、一八九四〜九五年の日清戦争でした。
二億両とは、当時の金額にして三億円ですが、日本の国家予算の四年分にも相当する大金だったといいますから、政府も心ひそかに戦争はもうかる、とほくそ笑んだことでしょう。
しかも、そればかりではない。日清戦争の勝利は朝鮮への支配権を確保し、台湾をステップにして南方進出への確かな足がかりにもなったのです。
台湾出兵に端を発した日本の対外軍事行動は、それからさらに勢いを増していきます。
外征の第三彈ともいうべき日露戦争は一九〇四〜五年のことでしたが、これで日本はさらに南樺太を手に入れました。 |

台湾南部に居住するパイワン族の子供たち(1938年)

中央山地の中部より北に居住するタイヤル族。
顔に剌青することが特色の一つだった(1932年)
|
続いて一九一〇年には韓国を併合植民地化し、やがて中国東北部から東南アジアへと戦火を拡大していったわけですから、近代日本の戦争は一九四五年まで、台湾出兵からなら連続して約七〇年、日清戦争からなら五〇年という見方も成り立つはずです。
ちょっと、話が先へ行きすぎました。
再び元に戻しますが、日本が台湾を支配する総本陣は、台湾総督府の設置です。
さっそく第一代総督に海軍大将・樺山資紀(かばやますけのり)が任命されたものの、さてその統治はとなると容易ではありません。
ごく短期間でしたが、台湾官民は台湾民主国を作って抵抗、これをなんとか治めたものの、さらに手強い相手ともいうべき先住民族によるゲリラ活動が、至るところに待ち受けていました。
彼らは、もともと中国大陸からやってきた漢系移民に圧迫された上に、今度は日本を相手にして、二重の苦難を強いられたわけですから、黙っていられなかったのでしょう。
南部台湾守備隊指令官として遠征した乃木希典(のぎまれすけ)も、このゲリラにはさんざん手を焼いたらしい。
しかし、なんといっても最初の植民地であり南方の前線基地ともなれば、台湾の平定こそは絶対の条件で、引くことも身をかわすこともできなかったのです。
平定は、武力による弾圧でした。
各地で連鎖的に発生するゲリラ活動に対し、「匪徒(ひと)刑罰令」を制定した日本軍は、「反乱者」を次々と殺害し、その家屋を焼き払いました。 |

霧社蜂起事件 きっかけは現地人の有力者と日本人巡査のトラブルから、一挙にそれまでの憤懣に火がついた。派遣された日本軍鎮圧隊
|
陸軍中将・児玉源太郎(こだまげんたろう)が台湾総督となった一八九八年から一九〇二年までの五年間に、殺された人々の数は、日本側統計でも次の通りです。
一八九八年に三一〇〇人、九九年に八三四人、一九〇〇年に一三五〇人、○一年に一九九〇人、○二年に四六七六人で、計一万一九五〇人とは、なんとおぞましくもすさまじい殺戮でしょうか。
日本の統治が軌道に乗るまでの八年間ならば、三万二〇〇〇人が「反乱者」として殺され、その数は実に当時の台湾人口の一%を上回ってしまうのです。
3 少数先住民族のこと top
ところで、日本統治のアキレスけんとなった先住民族について、少し触れなければなりません。
当初は清国がつけた「生蕃」(せいばん)もしくは「蕃人」(ばんじん)という蔑称(べっしょう)を日本もそのまま使っていましたが、しばらく後になってから「高砂族」(たかさごぞく)と改めました。
(現在では、山地原住民、高山族、山地同胞ともいう)
しかし、その「高砂族」も居住地によって複雑に種族系統がちがい、アミ、タイヤル、パイワン、ブヌン、プユマ、ルカイ、ツオウ、サイシャッ卜、ヤミの九種族に分かれるとされています。
彼らは、はるかな昔、南のマレー、ポリネシア方面から台湾にたどりついたといわれてますので、原住民族というよりも、先住民族の呼称が正しいのかもしれません。
古くは平野部で狩猟と漁業で生活していたものが、そのうち漢民族住民に生活圏を侵食されて高地へと追われ、彼らなりの対抗手段として、「出草」(しゅっそう=首狩り)が習慣化したものと思われます。
男子は「出草」で、首級を取ってきてはじめて一人前とされたのでした。
生きていくためには、なによりも闘争力が必要とされたのでしょう。
|

霧社蜂起事件の鎮圧には4000人からの警官隊を含めた軍隊が出動した(1930年)
|
日本総督府は、当初は平野部の統治で手いっぱいでしたが、十年あまりが経過した頃に、いよいよ山岳地平定の施策「理蕃(りばん)事業」に乗り出しました。
平定部隊は続々と山岳地に向かい、武力にものをいわせて、隘勇(あいゆう)線と称する守備範囲を拡大していきましたが、これに対し、もっとも激しい抵抗を示しだのは「高砂族」のなかでも、特に険しい山地のタイヤル、ブヌン族でした。
後に抗日蜂起の大事件が発生した中部山岳地の霧社(むしゃ)は、そのタイヤル族です。
わけても勇猛果敢で知られ、みずからをセーダッカと称して、十一集落で成り立っていました。
その一つ、ホーゴー社で一九一一年に、後の霧社事件に結びつくと思われる凄惨な事件が発生、総督府による資料に記録されています。
それは、日本官憲に家族八人を家ごと焼き殺されたという少年の話で、私は思わず、
「あ、これだ!」 と、息を呑みました。
先の観光旅行中に、ガイドのKさんが雑談まじりに話してくれたのを思い出したからです。
「そんなことをすりや、いつかはやられるってわけだ」
という言葉を、私は半信半疑で聞いていたのですが、やはり事実だったのです。
ピホ・ワリスというのが、少年の名でした。
「同人は父ワリス・ローバオが、明治四四年本島人脳丁を殺戮したる廉(かど)に依り、逮捕せられんとして自宅に逃げ込み、屋内より弓矢、蕃刀(ばんとう)を以て抵抗長時間に亘(わた)りしため、已(や)むを得ず外部より火を放ち一家八人を焼殺するに至れるが、当時彼ピホ・ワリスは未だ十一、二歳にして夏季の暑熱を避くるため一家族中彼のみが(付近の櫓(やぐら)造り鶏小屋に就寝(しゅうしんし)居たるため)此の災厄から免れたるものなり」
台湾総督府警務局による「霧社事件誌」からですが、これはもちろん加害者側の一方的な記録です。
少年がその惨劇を見ていたかどうかは不明ですが、殺された被害者には語る術がありません。
屋内から弓矢、蕃刀で抵抗したというのも、真疑のほどはわからないのです。
記述で確かなのは、一家八人を焼殺したということ。仮小屋みたいな住居で、八人もが焼け死んだとは信じがたく、日本側は家族一同を封じ込んでから退路を断ち、放火したのではないでしょうか。
この事件により、少年ピホ・ワリスの「日本官憲に対する怨恨(えんこん)は深刻なるものがあり」としていますが、当然のことだ、と言いたくもなります。
そんな恐ろしい怨恨を、少年の心に植えつけた者こそ、責められなければならないはずです。
|

男たちの戦果の生首を提げて踊る女たち。
武勇をたたえる習慣として行われていた白酒の宴
4 ムチのほかアメも用意して top
この事件から約二〇年が経過して、ピホ・ワリスは三一歳。同じ集落の従兄(いとこ)が日本警察霧社分室で取り調べ中死亡(おそらく殺された)のを根持つ同僚ビホ・サッポとともに、いつの日か報復の機会をねらっていたと、総督府資料は分析しています。
それにマヘボ社の頭目、というよりも霧社一帯に勢力を持つ実力者モーナ・ルダオが共鳴し、謀議をたび重ねて大事件を引き起すに至ったのだ、と。 |

霧社事件の指導者モーナ・ルダオ(中央、タイヤル族セーダッカの総頭目)とマヘボ社勢力者(右)とブカサン社頭目
|
モーナ・ルダオは当時四八歳、一九〇センチ近くの長身で、若い頃から戦術に腕を鳴らした武将として知られ、性格的にも多くの人をひきつける豪快さと、人間的な魅力があったとされています。
しかし、責任ある地位にあって、若者たちの痛憤に背を向けられなかったのでしょう。
また、警察官と結婚した妹が捨てられて戻ってきたことも、胸の底深く疼(うず)いていたはずです。
しかし、ホーゴー社での焼殺事件から二〇年のあいたに、日本の「理蕃事業」は山岳地の平定まで含めて、表向きは大いに成果を上げたかのように見えました。
武力による威圧だけでは民心は離れていくと知った総督府は、ムチのほかアメも用意して一方で脅しつつ、一方で山地に遅れていた保健医療整備から農業指導まで、ぬかりなく手を伸ばしていったのです。
さらに学校教育と無縁だった子供たちに寺子屋式の「蕃童(ばんどう)教育所」を設置し、警官が教師もかねて、国語=日本語を教えるようになりました。 |

徹底した討伐で事件は終結した。山奥で行動中の軍隊への食糧の運搬
|
|

事件が終わり、降伏した現地民代表と新任郡守の記念撮影
|

投降した現地民に対しては恵与品を分配した
|
それまで習慣化されていた民族間の「出草」や、集落間の抗争も禁止、また銃器も押収。
それ自体は悪いことでもなかったかもしれないが、彼らの生活の糧となるはずの狩猟はいちじるしく制限され、勇猛果敢でその名を知られたタイヤル・セーダッカ族も、まるで牙を抜かれた狼のようになっていきました。
要するに武装解除で、抵抗の根を断つのが目的だったのです。
各集落に作られた警察駐在所は、天皇制軍国主義と総督府の出先機関でした。
その権力は大変なもので、集落の隅々にまでにらみをきかせ、賃金のうわまえをはねるはおろか、物資の交易まで支配したのです。
ありとあらゆる品物の購入は、警察協会の経営する販売所からでなければできない仕組み。
その締めつけには、懐柔策として民族同士を起用しました。
巡査や警手(助手)など、行政や統治の末端職につかせたりしたのです。
さらにまた積極的に奨励されたのが、現地巡査と、山地頭目や勢力者の娘との結婚です。
といっても、大抵の場合、正常な婚姻関係ではなく、いわゆる現地妻の例がすくなくなかったのですが……。
日本の警察官のなかには、もちろん良心的な方もいたはずですが、平地での失点や素行の悪い者が避地へ回されるのが一般例で、八の字ひげを生やして権力を振り回すばかりか、女性関係も乱れた者がいました。
警察官と結婚したテワス・ルダオ(モーナ・ルダオの妹)が後に捨てられた一人なら、パーラン社頭目の娘イワリー・ローバオも、そうでした。
ホーゴー社の娘オビン・ノーカンも。
ほかに巡査の手引きで、内地の遊廓に売られた娘など、目に余る行為がたび重なりました。
娘たちがもて遊ばれている、という印象は、結婚の対象を奪われた山地の若者たちには、耐えがたかったにちがいない。
セーダッカ族のしきたりでは、妹の仇を兄が討つのは、男子の使命とされていました。 |

蜂起の頭目モーナ・ルダオの妹テワス・ルダオは、
日本の巡査と結婚した。
彼は花蓮港に転勤になって、まもなく失踪。
テワスは失意のうちに故郷に帰り再婚した
|
ほかにも、怒りと恨みの不満はまだまだ……。
駐在所の建築や道路の補修などなどの強制出役です。
特に霧社小学校寄宿舎の新築工事による木材の運搬は、急峻な坂道をかついでいかねばならず、農作業を後回しにしての重労働です。
にもかかわらず、賃金は約束とちがって、減らされたり遅れたりで、数々の怨念が積み重なれば、ある日突然に爆発したとしても、決して不思議ではなかったかもしれません。
5 一九三〇年一〇月二七日朝 top
さわやかな秋晴れの霧社で、日本の植民地統治上「未曾有の不祥事」が発生したのは、一九三〇年一〇月二七日のことでした。
その朝早く、霧社先住民族六集落の怒れる男たち約三〇〇人が、マヘボ社の頭目モーナ・ルダオの指揮のもとに、総決起。これが、いわゆる霧社蜂起事件です。
彼らはまず周辺集落の駐在所を次々と襲撃し、電話線を切って連絡網を断ち切り、大量の武器や弾薬を奪って、中心部の霧社へとなだれ込みました。
蜂起側の目標は、霧社公学校です。その日は秋季合同大連合運動会で、年に一度の大祭典でした。
周辺地区の日本人子弟だけの小学校をはじめ八ヵ所の「蕃童教育所」の子供たちに、保護者と警察職員など、およそ三五○名の参加で、そのうち日本人は約二〇〇名ほど。
能高郡守(のうこうぐんしゅ)小笠原敬太郎臨席のもと、はなばなしく開催されようとしていました。
午前八時。日の丸の掲揚とともに、「君が代」のオルガン伴奏がはしまったとたん、蜂起側の一斉襲撃が開始されました。
山地では、日の九の旗は赤い丸が天皇で、白地は大和民族と教えられていました。
「君が代」は、もちろん天皇をたたえる歌です。
偶然とはいえ、大日本帝国に対する一大反逆といえるかもしれません。
彼らは日本人だけを目の敵にして、女性、子供の区別なく一三四人を殺害、運動場から教室も宿舎も、またたくまに血みどろの大修羅場になりました。
誤殺された中国人が二人だけだったことでも、蜂起側の日本人皆殺しの意図は明らかです。
しかし、女性や子供にはなんの責任もなく、そんな弱者まで巻き添えにしたのは許せないという批判があります。
ガイドのKさんも口にしたものですが、よく資料を調べていくと、当初は女性と子供は対象外だったはずが、決議に参加していなかった一人がいちはやく警察官夫人を殺害、それから歯止めを欠いてしまったのが事実のようです。
運動場から逃げた日本側の総責任者、ふ笠原長官はやっと眉渓川の小橋までたどりついたところで、先回りしたピホーワリスに二刀のもとで馘首されました。
彼は、家族たち八人の怨みを晴らしたのかもしれません。
事件はすぐに総督府の知るところとなりましたが、「理蕃事業」がもっとも成功したとされていた模範地区で起きたことと、大規模な蜂起やその犠牲の大きさに、総督府と政府が受けた衝撃は、計り知れないものがありました。
まさに、日本の植民地統治への一大鉄槌だったのです。
蜂起の根が深いことに気づいた日本側は、そうした民族運動が他地区に、いや、ほかの植民地に波及するのを恐れて、徹底的な鎮圧作戦に乗り出しました。
山岳地帯にひそんだ反乱軍に対して、軍隊、警官など四〇〇〇人余りを動員し、機関銃や山砲、さらには飛行機まで使っての総攻撃です。
飛行機からは、当時すでに禁じられていた毒ガスまで使用されたといわれています。
「その毒ガスも、はじめは催涙ガスを使ったのだが、これでは手ぬるい、というのでホスゲン、ルイサイトなど(中略)、ほかに緑弾というのを打ちこんでいる」
霧社事件を分析した歴史家、山辺健太郎氏は『現代史資料21、台湾』の解説にそうしるしています。
「飛行機の爆撃が去って、山間に静けさが甦った時、我々は異様な臭いをかいだ。
と同時に、猛烈な吐き気がして、目がつぶれて、やたらと涙が出てきた。
水を求めてさまよう者、血を吐き倒れる者、苫しさで胸をひっかく者など、次々と出た。
……もうもうとたちこめる毒ガスが、我々の目を、鼻を、口を、そして喉を冒(おか)した。
岩窟(がんくつ)のあちこちに避難していた我々の仲間は、悲痛な叫び声をあげて、次々と死んでいった。
その顔は醜くゆがみ、肌はただれ、悪臭を放った」(アウイヘッパハ『証言・霧社事件』より)
このような記録を読むと、催涙ガスのほか、やはりびらん性ガスも使用されたのかもしれません。
|

事件の日本人犠牲者の遺骨が一ヵ月後に日本に送還された。
到着を待つ遺族
|
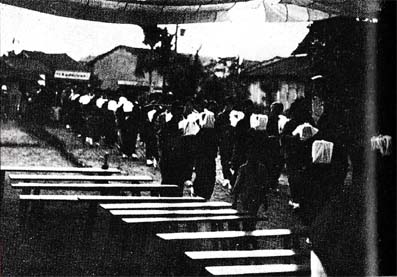
日本に到着した遺骨の長い列
|
6 モーナ・ルダオの最後 top
討伐隊が、ついに国際法で禁じられている毒ガス使用にまで踏みきったのは、山岳地帯にたてこもった蜂起側の抵抗が非常に強く、とうてい一筋縄ではいかなかったからといえましょう。
しかし、なんといっても多勢に無勢です。
さらに蜂起側が竹槍、鎌、鍬、弓矢、刀にせいぜい猟銃どまりの武器だったのに対し、日本軍は、蜂起側集落と仲が悪く討伐隊についた「味方蕃」も含めて、ありとあらゆる近代兵器を投入し応援部隊も補給も完全でした。
蜂起側かやがて食糧と銃弾が尽きれば、どうなるかは目に見えています。
しかし、モーナ・ルダオを中心にした彼らは、これ以上の屈辱には耐えられなかったのでしょう。
たとえ生死を賭けてでも守らなけれはからないもの――それが民族の自由であり、尊厳だったのではないでしょうか。
さらに言えば、日本当局が、彼らをそこまで追い詰めてしまったのです。
激烈な戦闘は、二ヵ月余も続き、蜂起側の死者は六五〇名近くになりました。
この数は、霧社公学校の運動会を襲撃した実動部隊の倍以上ですが、家族たちが行動を共にしたからです。
死者のうち半数は、首吊りなどで自決し、降伏するよりも死を選んだのでした。
駐在所の乙種巡査と警手の任にあった花岡一郎(ダッキス・ノービン)と花岡二郎(ダッキス・ナウイ)もまた、日本軍にはつかすに遺書を残して自決しました。
日本が手塩にかけてきた二人でしたが、ついに最後まで同胞を裹切らなかったのです。
そして、主謀者のモーナ・ルダオは? 彼はどんな運命をたどったか。
モーナは最後に妻と、四人の妹、二人の嫁に姪、孫などを連れてマヘボ社奥の自分の耕作小屋へ行き、一同に縊死(いし=首吊り自殺)をすすめました。
お前たちは先に行って祖先と会うようにせよ、自分は誰もいない谷間の断崖で、敵に見つからない場所を探して死ぬから、と告げたという。
しかし、一族の集団自決はそう簡単にはいきませんでした。
「十四名は縊死したるも、妻バタンワリス外三名は其の縊死の様を見て恐怖し、夫に銃殺せられるよう申出たるを以て、モーナルダオは之を実行し、尚(なお)敵に首を刎(はね)らるるを慮(おもんばか)り小屋に火を放ち岩窟に帰りたりと」
(『霧社事件の顛末(てんまつ)』台湾総督府より)
鬼気迫るような情景が、まざまざと目に浮かんでくるようです。
家族一同の最期を見届けた彼は、たったひとりで樹海に入り、人跡未踏の洞窟で自決(その白骨体が発見されたのは、四年も過ぎてからでした)。
これで、霧社蜂起事件は幕を閉じたかのように見えました。
ところが、そうではなかったのです。
翌一九三一年、収容所に送り込まれた蜂起側の生き残りに、日本官憲の手引きによる「味方蕃」が襲いかかり、一五歳以上の男たちなど二一六名が殺される大惨事が引き起こされました。
第二霧社事件といいます。かくして六社一二〇〇名余の蜂起側一族は、婦女子を主にわずか三〇〇名ばかりになってしまったのでした。
では、モーナ・ルダオの腹心となって、マヘボ山中で抵抗し続けたあのピホ・ワリスはどうなったか。
小笠原長官を仕止めて往年の怨みを晴らした彼は、その後日本側に逮捕されました。
同志たち三二人とともに坤里(ほり)警察所に連れ去られたあとの消息は不明で、二度と再び戻ってくることはなかったのです。
ピホ・ワリスばかりでなく、誰一人として帰らなかったのは、何を意味するのでしょうか。
日本官憲が、いかに復讐の鬼と化していたかを、語り尽しています。
霧社事件のあと、台湾総督ほか関係者は責任をとって辞任し、日本の「理蕃政策」もまた改められました。
先住民族の呼称も「生蕃」から「高砂族」へと変えられました。
それ自体はいままでの政策よりも前進したかのように見えましたが、実は本格的な皇民化運動の幕開けで、やがて彼らを皇軍兵士「高砂義勇隊」にしたてあげ、戦場へ動員する路線が確立していったのです。
top
**************************************** |