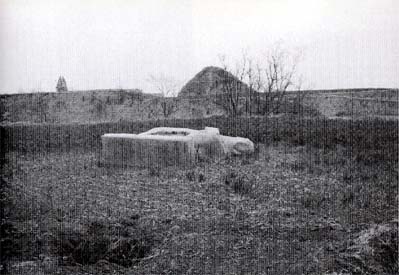|
��������������������������������������������������������������������������������
Index ��b�@��b�@�O�b�@�l�b�@�ܘb�@�Z�b
|
�Z�b�@���j�����l�X
�@1 ��˂����ΐl�A�Ώb���� top
�@���㔪�N�O���A�����̌Ós�A�����̖k��Z�Z�L���ɂ���O�����Ƃ����_���n�т������˂��B
�@�͐��̖k�ł���B����̍c��˂������˂�̂��ړI�ł������B
�@���ȑO�ɂ͒�˂͓y����ł��������A�������̎���ɂȂ�ƁA�R�Ȃǂ̎��R�̒n�`�𗘗p���āA�������悤�ɂȂ�B |

�u4�l�g�v�Ǖ����j���q�������̗x��i�k���E�V�d�����j
|
|

��˂̂��鑺
|
�@���V���@�i�����Ă�Ԃ����j�Ƃ��̕v�̍��@�̍�����A�����i�����傤�j����\�I�Ȃ��̂ł���B
�@���������̒�˂ł��y����̂��̂��l���A���̂����O��O�����ɂ���B
�@�ǂ���������ł��邽�ߌ��J����Ă��Ȃ��B
�@�ē����Ă��ꂽ�̂́A蟐��ȍl�Ì������̌������Œ������i���傤������j����ł���B
�@������͌��������@���������̐ӔC�҂ŁA�����J��Ղ̗\�������̂��߂ɎO�����ɍs���Ƃ����̂œ��s�����Ă�������B
�@�����̂�����͈ܓx����̂������ł͑����B�O�����͈�ʂ̔����ŗ͔Z���A�Ƃ���ǂ���ɉԐ���̓���ǂ����i������ǂ�A�t�炵������ł������B
�@�w�Z���璋�H���Ƃ�ɉƂɋA��q���������������J�̋����́A���̓��{�ł͂��͂⎨�ɂ��邱�Ƃ͂܂�ł��낤�B
�@�O��̒�˂͔����̒��ɐ��S���[�g���̋����������Ă����Ă����B
�@�ǂ���y�\���^�̕�ŁA���u�̐��܂ŏ����̗����܂�A���u���������낤���ĕۑ�����Ă����B
�@��ԓ��ɂ́A�������̑n�n�ҍ��c�A�����i�肦��A�ܘZ�܁`�Z�O�܁j�̕�A�����i�����傤�j���������B
�@�����͕�e�͂̂���l���Ől�ނ��W�߂��@��|���A������s�Ƃ��ē��������͂��߂��B
�@����c��̕�Ȃ̂ŁA�s��ȕ�����҂���������ꂽ�B
�@������Z���[�g���͂ǂ̏����Ȃ��̂ł������B
�@�����͋㐢�I�O���̈�O��c��A�h�@�i�݈ʔ���l�`��Z�j�̏��ˁA���͌h�@�ٕ̈��ɂ������ܑ㕐�@�i�݈ʔ��l�Z�`�l�Z�j�̒[�˂ł��邪�A���ꂪ���A�W�A�ɌN�Ղ����������̍c��̕悩�Ƌ^����悤�ȏ��Ԃ�̂��킢����ł������B
�@����̌`���͂ǂ�������ł���B
�@������܂肵�����u���͂�Ŗ���i���j������A����ɂ����ꂽ���`�����炭�����Ă̗ˉ��̋��ł��낤�B
�@�y�̑͐ςɂ���Ă��肩���m����ɂ����Ȃ���荂��������ׂĔ����Ɖ����Ă���B
�@���u�̓�����k�ɂ��ꂼ��Ύ��q�������̂悤�ɂ����Ă������A���܂͂��̎O���̈�قǂ����낤���Č��^���Ƃǂ߂Ă���ɂ����Ȃ��B
�@����̐��ʂ͓�̖�荂ŁA�������炳��ɓ�ɎQ���i�i�n���j�����тĂ����B
�@�����ɂ�����Q����[�ɂ͓��{�̒����̂悤�ɉؕ\�i���Ђ傤�j�\�\�̐Β��������A�����Ă͓��̗����ɕ����E�����̐Α��A�Ώb�Ȃǂ����R�ƕ���ł����B
|
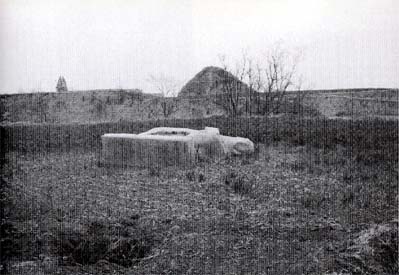
�������Δn�A�c��̕悪������Ɍ�����

�_�Ƃ̒�ɂ��낪��Ό�
�@���������͉����̖ʉe�͂قƂ�ǎ�����A��Z�̗]��̐ΐl�����̂������ɒ������Ă����ق��́A�ؕ\�������n�ʂɓ|��A���邢�͔��Δ��ɖ��܂�Ȃ���U�����Ă����B
�@���������c�Ȕj��̂��Ƃ��߂����A���^���Âׂ���̂͏��Ȃ��B
�@������������̂́A�_�Ƃ̒���ɐ̌Ղ��������܂��Ă������Ƃł������B |

������Ύ��q

��̂Ȃ��ΐl�������̒��ɂ��낤���ė����Ă���
|
�@����͒����̐������x�ɔ��B��������ł��邪�A�̌Ղ͒������B
�@���Ȃ菝��ł��邪��i�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�@�������_�Ƃ̐l�͗R����m�炸����Ȃ�̋��Ǝv���Ă����Ƃ����B
�@�悭���ׂĂ݂�ƁA�Ղ͂�����̂��������A��˂̈͂��ɂ����̑傫�Ȕj�Ђ��g���Ă���A�֏��̘e�ɂ��ؕ\�̎c����������ɓ]�����Ă����B
�@�ΐl�̂������͎����Ă����B
�@�������Ĕ���̂����A���̕������Ƃ������ƂŁA���������ɖR�����_���̐����ł͂��̗��v�͋��z�Ƃ����Ă悢�B
�@���̎�̕������r�炵�͌��₾�Ȃ��B���ɏ��˂ł͈��㎵�N�Ɏ���������������ł������B
�@�܌��̐[��A���˂̎Q���ɕ���ł����ΐl�Z�̂̂����l�̂̎藎�Ƃ��ꎝ������ꂽ�B
�@����Ɏc���ꂽ�n���}�[�Ƃ����˂��肪����ƂȂ��ċ߂��̔_����l���ߕ߂��ꂽ�B
�@�ނ�̘b�ł́A�ܑ̖ڂ̎��낤�Ƃ����Ƃ���A�Ƃ����Ƃǂ낫�A�V�̓{�肩�ƕ|���Ȃ��ē����o�����Ƃ����B
�@�����̍����͍L���ɏZ�ލ������i�����Ƃ����傤�j�ŁA���˂Ă���u蝐����i�������傤�j�ɂ͑����̕���������B
�@�����o���J�l�ɂȂ�v�Ƃ����Ă����̂����Ă����Ƃ����B
�@���ݏo�����Γ��͈�̎l�����i�����̃��[�g�Ŗ�ܖ��~�j�Ŕ������������ł���B
�@��Ƃƍ������̍ٔ��́A���N���A��Ȃ��̐ΐl�����ԏ��˂̑O�ɊJ�݂��ꂽ�Վ��@��ōs��ꂽ�B
�@���J�ٔ��̌��ʁA�e�E�Y�̔������ł��B���Y�͎l�̂̐ΐl�̒����ōs��ꂽ�B
�@���̂悤�ȕ擐�l�̐S�Ȃ����Ƃɂ���ׂ�ƁA��Z�Z�Z�N�̕���ɑς��������Ă����̓��������̎p�͂ЂƂ����A���Ȃ��Ɏv�����B
�@�����̓��O�ɂ��[�˂��r�炳��Ă����B
�@��˂̑O�ŏe�E���s��ꂽ���Ƃ́u�j��O��̂Ȃ��Y��v��]���ꂽ���A�ٔ��ɂ����Y�ɂ��������߂̗v�f�������B
�@����������͈�ʂł͓��ǂ�����������̑����Ɏ���Ă��Ă��鎖�������̂ł��낤�B
�@������łȂ��������̔j����[���ł���B
�@2 �����̕ی�ƌ��J top
�@�������̍c��˂̂��������Ƃ��傫�����̂͐������琼�A��Z�L���قǂ͂Ȃꂽ�R�\�\���R�i��傤����j�𗘗p���Ă���ꂽ�����i�����傤�j�ł���B
�@���x��Z�l�����[�g���̖k�̒��������̂܂ܕ�ɂȂ��Ă���B
�@�����j��B��̏���ł��鑥�V���@�i�����Ă�Ԃ����A�����ł͕����V�j�Ƃ��̕v�A��O��c��A���@���܂���������ł���B
�@���ӂɍc�q�ȂLjꑰ��d�b�ȂNj߂����l���܂��Ɣ������i�������ځj���ꎵ��������B
|

�i����̕�i�����j
|

�i����̕�A���@���ꂽ��(1977�N�j
|
�@���@�̑����𑒂����i�����i����������������j�̕������{�ł��悭�m���Ă���B
�@�����i�c��̖��j�͗��z�ɉł����Z��N�A�ꎵ�Ŏ��B
�@���̒��v�i���イ�����j������Ⴂ���̎�������Ɏv���A�ܔN��ɕ�𗌗z����ڂ����̂��Ƃ����B
�@��̒��̕����ł͓�Y�Ŏ����ƂɂȂ��Ă��邪�A���@�̒��b�i���傤����j�̈��������������Ƃ���@�̓{��������A���𖽂���ꂽ�̂��Ƃ������Ă���B
�@��̒n��͍�����l���[�g���̓y�\���^�ň��Z�Z�N�����N�Ԕ��@���s��ꂽ�B
�@�����͒n���ɉ���g���l���i����������ǂ��j�A�O�掺�A��掺�i���������j����Ȃ�A�O���̕ǂɊ����̌Q����`�����������lj悪����B
�@���{�̍����ˌÕ������@���ꂽ�Ƃ��A���̕lj�̗D��ȏ������̃��[�c�Ƃ��Ęb��ɂȂ����B
�@��\���N�O�Ɏ����K�ꂽ�Ƃ��ɂ͖����J�Ŏ������������Ă��Ȃ������B
�@�W�̐l����̒n���g���l���̓����̓싞���i�Ȃ傤�j�������ē���Ă��ꂽ���A�����͑A���ƑO�掺�̕lj�͂��̂܂ܕۑ�����A�V��ɂ͓��@�҂̂��������܂Ŏc���Ă����B
�@��D�_�͂�����������ċM�����ȂNj��ɂȂ肻���ȕ����i��D�����B
�@���@���̉��ɂ́A��D�_�̎g�������@�����⍜���U�����Ă����Ƃ����B
�@�����炭�l�����߂����ēD�_���m���������������̂��낤�B
�@�A���̗����ɂ͏����ȋ�Ԃ����������i�����j����A�����ɂ͏ĕ��̉ƁA��˂Ȃǂ�A�j���E�����E�����̘��i�悤�A�D�l�`�j�����R�Ƃ�����A�����ɂ����P�N�̂͂Ȃ₩�ȓ�����Â��Ă����B
�@���I�ȕ������肪��ʂɍ��܂ꂽ�傫�ȐΊ��̈��u���Ă��錺���i���j�̓V��ɕ`���ꂽ�����Ɩ��V�̐��́A���҂��܂�F���ςƂ̊֘A�Ř_�c���Ă�ł����B
�@���������N�O�ɖ��Z�N�Ԃ�ōĖK�����Ƃ��ɂ́A�������邵�����܂����ɋ������B
�@���͂͒뉀�̂悤�ɐ�������A�H����V���b�s���O�̂��߂̌���������������ł����B
�@��̓����ɂ����h�Ȕ�������Ă����B
�@�lj�͕ۑ��̂��߂ɔ�������ċ�ܔN�ɐV�݂��ꂽ蝐��ȗ��j�����قɈڂ���A���I�Ȗ͎ʂɑウ���Ă����B
�@����͕������ی�̂��߂̕ۑ��[�u�Ƃ��Ă�ނ����Ȃ������̂��낤�B
�@�ߎS�������̂͌����ł������B
�@���炭���܂���Ԃɖ������ɐl����ꂽ���߂ł��낤�B
�@�ǂɂ��V��ɂ��J�r�������F�߂�ꂽ�B
�@�l�Ԃ̓f�����ɂ͔��ʂ̎��C���܂܂�Ă���B
�@�吨�̐l�����������ƂŁA�����̋�C�������i�������j�ƂȂ��ʂ̃J�r���������̂ł���B
�@�������ۑ��̐��Ƃ̘b���ƁA�lj�ɐJ�r����������ƁA���B��������̕ۑ��Z�p�ł����ꂾ���͂ǂ����悤���Ȃ��Ƃ������Ƃł������B
�@�V��ɂ����ꂽ�������C�}�i�����������j�͖{���ł��邪�A���͂�J�r�̐N�H�ɔC����ȊO�ɂ͂Ȃ��悤�Ɏv�����B
�@�����ƈ������Ƃɂ́A�����̓V��ɗ��\�Ȏ��ő傫�������̖��O�̗��������������B
�@�M�d�Ȋw�p�����A�������Ƃ��čőP�̏�Ԃ��ێ����Ȃ���ۑ����邱�ƂƁA�l�ނ��邢�͖����̋M�d�ȏ䉻��Y�Ƃ��đ�O�Ɍ��J���邱�ƂƂ́A�w���i�ɂ�͂��͂�j�I�ȉۑ�ł���B
�@�Ƃ��ɍ��̒����ɂƂ��ẮA���̉����͂���߂Đ[���Ȗ��ƂȂ��Ă���B
�@���Z�N��ȍ~�̉��v�E�J���ɂƂ��Ȃ��H�Ɖ��Ǝs�ꌴ���̓����́A�������ی��������������ȉۑ�Ƃ����B
�@���k���͂��߈�Ղ̑����n��̑����͔��W�̒x�ꂽ�Ƃ���ł���A���ꂾ���Ɏs��o�ς̐Z���͌����ւ̊��]�i���ڂ��j���������Ă�B
�@�����葁���������Ƃ��ď��˂̏ꍇ�̂悤�ȓ��@�̑����͔����������B
�@���̑傫�ȉQ�̂Ȃ��Œ����̗��j�w�ҁA�l�Êw�҂͗l�X�ȋꓬ��]�V�Ȃ�����Ă���B
�@���̒����̍l�Êw�́A��˂��͂��߂Ƃ����^��̔��@��}�����Ă���B
�@����ł��J���̓r���ł̋��R�̔��������������ƂȂ�A�܂���Q���L���Ȃ����߂̉��}�[�u�Ƃ��ē��@���ꂽ��ً̋}���@���s������������B
�@�R���ȋȑ��i���傭�悭�j�ɂ͎������i�O��ꁛ�����`�O��ܘZ�j�̏���A����̕悪���邪�A���̏���̕�̂����ł͂����Ƃ���^�ł������B
�@�����N�����ɂ͂��̂����̂ЂƂ��_�C�i�}�C�g�Ŕ��j���ꂽ�B
�@�S���ň�Z�̂�����l�̌Êy���i�ҏ����ւ傤�j�����ݏo����A���`�ɖ��A�o���ꂽ�B
�@�����킢��C�̔����ق�������͂����Ĕ����߂������A��Z�̌Êy��ɂ͖���������A�S�����Ȃ���ƈ�̕��͂ƂȂ����B
�@����͐W�̓a�l�������ɖ������Ă����Ȃ����푈�̋L�^�ł���A������̕ҔN�����肷��ۂ̑�ꋉ�̎����ł������Ƃ����B
�@���̓��@�������@�ɖk����w�ƏȂ̍l�Ì��������ً}���@���s���A�S���̑�^��@�����B
�@�O�L�̕ҏ��̂ق��A���I�Ȑ��킪�����o�y�������A��������ؗ�ȑ������{�������p�I�ɂ����l�̍������̂ł������B

�u�ё���㎖��������؍��N�v�̐�`��
(1977�N�A��a�������j
�@3 �����X��������l�Êw�� top
�@����������钆���̍l�Êw�҂̂��������͂��܂�m���Ă��Ȃ��B
�@�����͂��߂Ē����ɍs�����̂́A��O�N�Ԃɂ킽�蒆��������������������v�����I��������㎵���N�ł������B
�@��������v�����Ɏw�������ɂ������ёv�l�A�]��̃_���[�v�\�\������u�l�l�g�v���ߕ߂���A���v���I��������ł������B |

�k���E�V�d�u4�l�g�v�Ǖ��̐�`��(1977�N�j |
�@�V����L��Ő���ɏj���鍑�c�߂ւ̏��҂Ƃ������ڂʼn�X���{�̊w�҂��Ă�ł��ꂽ�̂́A�����̃A�J�f�~�[�ł��钆���Љ�Ȋw�@�ł������B
�@���v���I�����̂ň��N�Ԃ�ɓV����L��ɉԉ��オ��܂���Ƃ������҂̌��t�ǂ���ɁA���̔N�̍��c�߂͑����̉�������܂����ĉ₩�ɏj��ꂽ�B
�@�V�d�i�Ă�j����a���i���킦��j�Ȃǂ̖����ɂ͐l�X���W�܂�A���̉�����j�������Ă����B
�@���������Ă�ł��ꂽ�Љ�Ȋw�@�͓����Ɨ���������ł������B
�@�������錤���҂͈��Z�Z�l�Ƃ�����g�D�ŁA���j�W�ł͗��j�������A�ߑ�j�������A�l�Êw�������Ȃǂ��������B
�@���������v�̏��Ղ͂܂����X���������B
�@���v���ɏ����̑����͉����Ƃ������ƂŔ_���ɍs�����ꂽ�B
�@�����Ƃ����̂͊����������̊v���v�z��b���邽�߂ɉ����g�D��_���ɍs�����Ƃł���B
�@�Ƃ��Ɋw�ҁA�����҂̂悤�Ȓm���l�́A���m�̃u���W���A�v�z�ɐ��܂��Ă���̂ŁA�J���̌���ɉ������A�J���ɏ]�������Ďv�z��b���Ȃ������Ƃ�����|�ł������B
�@���m�̊w�p�v�z�́A�m�z�i�悤�ǁj�N�w�i�z�͓z��̓z�j�Ƃ��Ĕr���̑ΏۂƂ��ꂽ�B
�@��㎵��N�Ɏ��������k���ɌĂі߂��Ă����܂ŁA��匤���͔��N�ԃX�g�b�v���A�O������Y��܂����Ƃ��钷�V���j�Ƃ�������̂���ۂɎc���Ă���B
�@�K�₵���k����w�ł��A�u�l�l�g�v�͌����ȗ��̋���̐��ʂ����u�m�����傫����Α傫���قǍ߈��v���Ƌ����A��������͓����̓���ɉ������Ƃ����Ă����B
�@�Ƃ��ɕ��Ȍn�̊w��ɂ��ẮA�Љ���w�Z�Ƃ���u�J���w�v�i�������������j�Ƃ������j����w���ɍZ�O�ł̊����������i���傤�ꂢ�j���A�w�͒ቺ�ɔ��Ԃ��������̂��Ƃ����̂���w�W�҂̐����ł������B
�@�Љ�Ȋw�@��K�₵���Ƃ��A����V�N�w�҂͌����Ɏx�����Ȃ��猺�ւ܂ʼn�X���}���A�����čĂъO���̌����҂ɉ��Ƃ͎v��Ȃ������Ɨ܂Ȃ���Ɋ��S�i�����j��������B
�@�v�z�ʂ̈��������łȂ��A������̍������[���ł������B

�����X��ՋL�O�فB�k�����l�̃��v���J
�@�����Ŕ_���ɍs�����ꂽ�Ƃ��A�����҂̑����͂����k���ɂ͋A��Ȃ����낤�Ƃ������ƂŁA�Z������ƂɕԔ[���Ă������B
�@���̌�A�������̎w���Ŗk���ɖ߂��悤�ɂȂ������A�Z�ނƂ��낪�Ȃ������B
�@
��ނ������������̏��ɂɕz�c���������݉Ƒ�����݂ŕ�炵�Ă���悤�ȏ��������B |

�����X�̎R����
|
�@���̂Ƃ��Ñ�j�w�҂Ƃ��ėL�������B�i���j����Ɉē�����Ď����X�ɍs�����B
�@�����X�͖k���̓쐼��܁Z�L���ɂ���ΊD��̋u�ŁA�������甭�@���ꂽ���ΐl�ނ��A�k�����l�i�V�i���g���v�X�E�y�L�l���V�X�j�ł���B
�@�k�����l�i�����ł͉��l�j����炵�Ă����͖̂�܁Z���N�O�Ɛ��肳��A���łɓ������g���Ă������Ƃ��m���Ă���B
�@�l�ނ̋N�����l�����ꋉ�̏d�v�����ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
�@�����������N�ɔ��@���ꂽ�قڊ��S�ȓ������͂��ߋM�d�ȉ��Ύ����́A�����푈���̈��l��N�ɓV���i�Ă�j�̕u���ɉ^�ꂽ�܂܍s���s���ƂȂ����B
�@���{���A���邢�̓A�����J�������Ă������Ƃ�����������A���݂ł��s���͂킩��Ȃ��B
�@���B�i�����j����͂̂��ɎЉ�Ȋw�@�l�Ì��������ƂȂ鉷���Ȋw�҂ł��������A�����X�i���l���j��ՂɌ����������Ԃ̂Ȃ��Œ����̗��j�Ƃ������Ă������т������̈�[��b���Ă��ꂽ�B
�@���B����̘b�̂ЂƂ͕��v���̏o�����ł������B
�@������́A�]���炵�������V���@�̓`�L�������Ƃ��܂�ꂽ�B
�@�]�͗��p�i���т�j�Ƃ������O�Ŋ�����C�̏��D�Ŗё̉��Ԗڂ��̔z��҂ɂȂ����l�ł���B
�@���@�����@�̔z��҂���c��ɂȂ��������ŁA�����悭�C���̋�����l�ł��̓_�͍]�Ɏ��Ă����B
�@�]�������j��B��̏���ł��鑥�V���@�̓`�L���������悤�Ƃ����̂́A�ޏ����g���ё̌�p�҂Ƃ��āu�l�l�g�v�𗦂��A����̂悤�ɑS�����ɌN�Ղ��悤�Ƃ����]�����������炩������Ȃ������B
�@�u�l�l�g�v�̍ߏ��\�������̂͂������L�����y�[���̂Ȃ��ŁA�]�������ЂƂ�̑��V���@�ɂȂ肽���ƍ��������Ƃ��A�悭�}���ق��畐�@�̖{����o�������A����͖�S�̏؋����Ƃ������b���܂��Ƃ��₩�ɓ`����ꂽ�B
�@�]�̕��@�ɑ���X�|�͂����Ƃ܂��߂Ȃ��̂������悤�ɂ��v���邪�A���̓_�肷��\�͎͂��ɂ͂Ȃ��B
�@������ɂ��Ă����B����͍]�̗U�������ۂ����B
�@���͉��x�����Ă������f��܂����ƁA���B����͋����Ă������B
�@���v���̒m���l�̂����ꂽ�����Ȋ����l����A���B���]�̈˗���f�����̂͑�ςȂ��Ƃł������B
�@���B���ǂ�ȕ������ɂ��Ă͌����ł������Ă������A�����炭�����̏d�����o�������̂ł͂Ȃ����B
�@���B����̂����ЂƂ̘b���[���ł������B
�@���O���N���������A�k���i�����͖k���j�x�O���b�a���i�낱�����傤�j�ł̕��͏Փˎ��������������ɓ����푈���͂��܂����B
�@�������͖k���̏Z���ƕ���������邽�߂������킸�ɖk���𖾂��n�����̂ŁA�����͂��߂ɑ��������{�R���k���ɓ��邵���B
�@���B����̘b�ł́A���̒���ɌR���Ɏ���ē��{�̐l�ފw�҂̈�s�������X�ɂ���Ă����B
�@�ނ�͐V�����̔��@���߂����ĂЂƌ��ԁA���l���̎��ӂ��@�����B
�@�u�����������o�Ȃ������̂ŁA�ނ�͂�����߂ċA��܂����v�A���B����͂��������ăJ���J�������B
�@���{�̐l�ފw�҂������Ƃ��A��l�̍l�Êw�҂��u�肵�Ďc�����B
�@�ނ�͘J���҂ɐg������Ē��Ԃ͓��{�l�̖��߂ɂ����������@��Ƃɂ����������A��ɂȂ�ƓK���ɖ��ߖ߂����B
�@���{�l����Ԃ�ŋA�����w��ɂ́A���O�̕����钆���l�Êw�҂̌����̒�R���������B
�@���̌�A�헐�̂Ȃ��ň��N�ԁA�����X�̔��@�̓X�g�b�v�����B
�@���l��N�A�v���ɂ���Ē��ؐl�����a�����������A�����X��Ղ��V���{�ɐڎ����ꂽ�B
�@���̂Ƃ��������{������J�M��������̂͛��B����ł������B
�@���O�N�ɂ͔��@�Z���^�[������ꔭ�@���ĊJ���ꂽ�B
�@���Z�Z�N�ɂ́A���{�̐l�ފw�҂������ł��Ȃ������k�����l�̓����̔j�Ђ����l���̏�����Ŕ������ꂽ�B
�@4 �J���Ǝ�������j top
�@����Z�N��́A���{�ł͌o�ς���������u����ꂽ��Z�N�v�ł��������A�����ł͌o�ϔ��W���}���ɂ�����
�Ƃ��ɏ�C�Ȃlj��C���̓s�s�ł́u��N����Z�N�v�̊����������B
�@�������}���Ȍo�ϔ��W�ɂƂ��Ȃ��J���̋��s�ɂ���Ē����̍l�Êw�҂͐V��������ɒ��ʂ���悤�ɂȂ����B
|

�k���Љ�Ȋw�@���j���������ւŌ���(1977�N�j
�@���̑��h���钆���̍l�Êw�҂̂ЂƂ���k���̗��j�����ق̑O�ْ����̒��i��@�����傤�j����������B
�@�ނ͕����ǂ��蒆���l�Êw��̗��_�I�w���҂ŁA�Ƃ�������m�̉Ȋw�ƌ�����ꂪ���̍l�Êw���A���m�ɐl�Ԃ̉Ȋw�Ƃ��Ĉʒu�Â���ƂƂ��ɁA�F����̂Ƃ��Ă̌����҂̎�̐��ƌ����̌���I�Ӌ`���������Ă��邱�ƂȂNJw�Ԃׂ��_�������B
�@�����Ȃǂ��琄�@����ƃA�����J��t�����X�̍ŐV�̗��_�Ɖ^���̐��ʂ������Ȃ���A�Ǝ��̍l�Êw���_��听�����B
�@�����炭���̂��Ƃ����v���Ɂu�m�z�N�w�v�̎�����Ƃ��Ĕނ��U���̖�ʂɗ��������̂ł͂Ȃ����B
�@���ْ��͖��ނ̈����ƂŁA�����E��Ƀ^�o�R���͂���ł��邪�A�w����{�����Ă���B
�@������v���̂Ƃ��ɔ��Q����A��x���E��}���������ł���B
�@��x�ڂ͎��s�A��x�ڂ͊m���Ɏ��ʂ��Ƃ�����č����d�������B�w��{����������A���͂Ƃ�Ƃ߂������ł���B |

�k�����j�����ّO�ł̋L�O�B�e
�i�O��A�E����M���ˁA�Ζ؉딎�A���̒��A�M�ҁj

���̒��ْ��i�E�j�ƕM�ҁi���j
|
�@���͂��̎�����邽�тɕ��v�ƁA����ɑ����}���ȎЉ�ϓ��̂Ȃ��ŁA�w��I�ǐS���т����߉ʊ��ɐ���Ă��钆���̒m���l�̋ꓬ�ƁA����ƑΏƓI�ȓ��{�̒m���l�̈��y���v�킴������Ȃ������B
�@����Z�N�O���A���j�����قْ̊����Ŗ��̒��ْ��ɂ��ڂɂ��������Ƃ��A����ɐ[���Șb�������������B
�@���������̊J���v���̂Ȃ��ōő�̂��̂��O���_���̌��v��ł������B
�@�O���͎l��A�Ζk�̏ȋ��ɂ���勬�J�ŁA�S�����Z�L���A���]�i�g�q�]�j�ő�̓�Ƃ��ꂽ�B
�@���]�̗��ꂪ�ΊD��w���т��Ƃ���ł͗��݂�����A�앝����Z�Z���[�g���ɖ����Ȃ��n�_������A�Ƃ���ɂ��܁Z�Z���[�g����������f�R��ǂ����܂��Ă���B
�@�܂�����w�̂Ƃ���ł́A�J�͍L�������[���A�q�s�͊댯�ł���B
�@�O���̌i�ς͌Â����璍�ڂ���A�O�����ォ��̔����ȂǑ����̕�����Y������B
�@�����Ƀ_�������s��Ȍv��������v���̎w���ҁA�S�������������̂́A���ꔪ�N�ł���B
�@���̌�A���Z�N�߂��_�c����Ă������A������^�����_�@�ƂȂ��āA�����N�̑S���l����\�ґ���i���{�̍���ɂ�����j�̓_�����݂����c�����B
�@�㎵�N�H�ɂ̓_�����ݒn�_�Œ��]�̖{���������~�߂��A��Z�Z��N�̊������߂����ă_���{�̂̍H���������߂��Ă���B
�@�_���͊�������ƒ����ʂ͎O��O���g���A�_���̒����͖�Z�Z���L���ŁA�d�c�s�܂ŒB����B
�@���d�ʂ͈ꔪ��Z�L�����b�g�ɒB���A�N�Ԍ܁Z�Z�Z���g���̐ΒY�̐ߖ�ɂȂ�Ƃ����B
�@�܂����ʂ����ώl�܃��[�g���㏸���āA�ꖜ�g�����̑D���d�c�܂ōq�s�\�ƂȂ�A�^���̒��߂�ؖk�n���ɋ�������q�쐅�k���r�v������s�ł���B
�@�߂��ߋ��̗�ł͓����푈�̂Ƃ��A���{�R�͎O���̛ӂɂ���܂���Ē�������s���ڂ����d�c�ɂǂ����Ă��U�ߏオ�邱�Ƃ��ł����A���̂����ɑ�K�͂ȋ�P�ɂ���ċ��������悤�Ƃ����B
�@���̂��Ƃ����ӂ��߁A�܂����O���_���̌��݂́A������Ӗ��Œ����̍��^�����������ƃv���W�F�N�g�ł���B
�@���̒��ْ��̘b�́A�_�����݂ɂ���Đ��v���镶����Y�ɂ��Ăł������B
�@�O���ł͖{�H���ɐ旧���Ē��]�̕����H�����͂��܂������A����ƕ��s���Ĉ�ՂȂǂً̋}�������s��ꂽ�B
�@���ْ����ӔC�҂ɂȂ�S������O�Z�̌����@�ւ��Q��������K�͂Ȓ����ł������B
�@�����҂����͂��łɗ����ނ����_�Ƃɔ��܂�A�e�H�ɑς��Ȃ��璋�錓�s�Œ����������Ȃ����B
�@���̌��ʁA��Z�N���܂łɈ���̈�Ղ����v���邱�Ƃ������炩�ɂȂ����B
�@���̂����ɂ͑����̎��l�����ɂ�����₢�����̐ΌA���@�Ȃǂ��܂܂�邪�A���i��j�ْ����Ƃ��ɗJ�����Ă����̂́A�b�l�i����j�����̖��ł������B
�@�l��Ȃ͔엀�i�Ђ悭�j�Ȕb�i�j�A冁i���傭�j�����̒n�Ƃ��Ĕ��W���A���j����ɓ���B�b�͏d�c�𒆐S�Ƃ���l��ȓ����A冂͐��s�𒆐S�ɐ����ɐ��͂����B
�@�������k���̐`���쉺����ƁA�퍑���㖖�ɂ͔b�A冂Ƃ��ɐ`�ɐ������ꂽ�B
�@�ŋߔ�������b�����������O�����i���������j��Ղ́A�O�Z�Z�Z�N����l���Z�Z�N�O��冂̕����ɑ������̂ƍl�����Ă���B
�@�ڂ���яo�������̉��ʂ≩���̉��ʂȂǓ��F����╨����������o�y���āA���͕����ƈقȂ镶���̃��[�c�Ƃ��Ē��ڂ��ꂽ�B
�@���]����ɂ͟u�A���Ȃlj��͌��̌Ñ㍑�ƂƂ͕ʌ̍��Ƃ����݂����\�����w�E����Ă���B
�@�������b�̕����͂��̏d�v���ɂ�������炸���܂蕪�����Ă��Ȃ��B
�@�b�̕����̉𖾂́A���������̃��[�c�������炩�ɂ��邽�߂ɏd�v�������߂Ă���B
�@�O���n��ɂ͘Z�Z�Z�����L���ɂ���ԌÑ�̈�Ղ�����A�Ƃ��ɔ��Z�Z��ȏ�̕悪�_�����݂ɂ�萅�v���邪�A�����͂����Ă̔b�l�����̒��S�n�ł������B
�@��l�Z�Z�Z�N�O�Ȃ�����Z�Z�Z�N�O�̕����ŁA�O��Z�܁Z�N����u�i���j��łڂ������̕����̐땺�i������j�����b�̈ꑰ�ł������B
�@冂͔_�k���ł��������A���͋��J���A���v����n��ɂ͎Љ�w�҂��u�y�Ƒ��v�i�ǂ������j�ƌĂԏ��������̑��������܂܂�Ă���B�u�y�Ƒ��v�͔b�l�̌����i���������j����ƍl������̂ŁA��Ղ����łȂ������̑��̐��v�ɂ���Ă����炭�b�l�̌����͌���I�ɕs�\�ɂȂ�ł��낤�Ƃ����̂��A���ْ��̈ӌ��ł������B
�@���ْ��́A������M�d�ȕ�����Y�̕ی���ĎO���{�ɑi�����B
�@�l�X�ȋ@��ɑi��������Ԃ����̂Ŗ��̒��̖��O�͑S���ɒm��킽�����B
�@�m��Ȃ��l�Ɖ���Ė��h��n���Ɓu�����A���Ȃ�����̖��̒����c�v�Ƃ�����n���ł������Ƃ����B
�@�㎵�N�ɂ͒������j�����ق͐��v����_���̕�����Y�̎��Ԃ��Љ����ʓW���J���ĕۑ��̕K�v���𐢘_�ɑi�����i�Ζ؉딎�u������Ñ㋙�J���E�b�l�����v�w�����V���x�@���㎵�N�Z���l���t�j�B
�@��ɐG�ꂽ�ً}���������i��j�ْ��̓��������Ŏ��������B
�@�������i�ʂ̕ۑ��[�u���u�����Ȃ��܂܂Ƀ_�����݂͋��s���ꂽ�悤�Ɏv�����B
�@�ْ��͐��{�Ɏ��\���o�������A����͎��̍l���ł͐E��q���Ă̍R�c�ł������悤�Ɏv�����B
�@���j�����ق̖ʂ��Ă���V����L��͈����N�A�����Z�Z�N�L�O�j�T���@��ɉ��C����Ėʖڂ���V���A���v�J����搉̂���l�X�̌Q��ŎG���i�����Ƃ��j���Ă������A���͂�ْ����ɖ��ْ��̎p�����邱�Ƃ͂Ȃ��B
top
�������������������������������������������������������������������������������� |