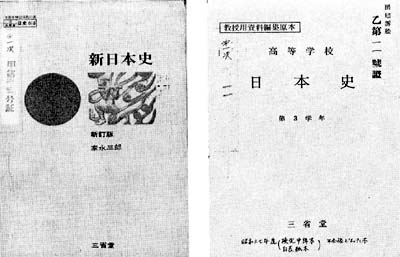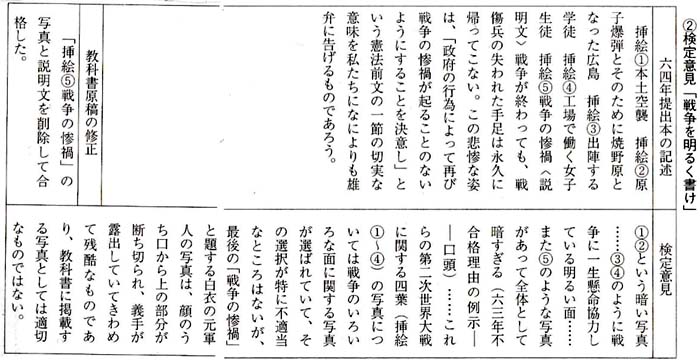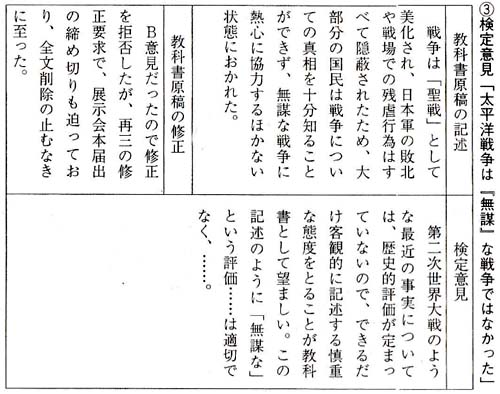|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章
|
四章 教科書裁判
|

|
1 家水裁判、勝利の炎 top
|

石垣島では島のすみずみに50本の立看板が立てられた
(1970年7月)
|

家永三郎氏
|
一九七〇年七月一七日、夕暮れの迫った大田浜(沖縄県石垣島)では、子供たちがキャンプファイヤーを始めていた。
まだ十分明るい珊瑚礁の海は、コバルト・ブルーに輝いていた。遠くむこうの潮干帯の端に、リーフがさざ波となって白く細い線を描いている。
大浜中学の二年生約一六○名が、それぞれいくつものキャンプファイヤーを囲んで砂浜に尻を下ろし、その中の男子生徒の一人が、
「祝! 家永教科書裁判勝利判決」
と白布に黒ぐろと書いた幟(のぼり)を立てている。その傍らに学年主任の社会科教師黒島精耕が立っている。
彼は沖縄県教職員会(後の沖縄県教職員組合)八重山支部の青年部長であった。
歴教協の会員でもあり、沖縄県の祖国復帰運動や家永教科書裁判支援運動を熱心に進めている一人であった。
彼は、みんなを見回しながら、静かにしかし大きな声でいった。
「君たちも今日のテレビニュースで知っていると思うが、教科書裁判で杉本判決が出て、先生たちが応援している家永側が勝ったのです。
家永先生が書いた教科書の文章を文部大臣が検定で書き直させたのは、憲法と教育基本法に違反するから取消せという内容です」
すると、幟を持っていたクラス委員の子が、、
「だから、今夜は『教科書裁判勝利』のファイヤーに切り換える」
と大声で叫んだ。
八重山教科書裁判支援会では、杉本判決の出た十七日の午後、市民に呼びかけ市立文化会館で「教科書裁判勝利」の集会を開いた。
そして翌日、白塗りのブリキに「教科書裁判判決勝利」と書いた立看板を五〇枚作り、石垣島全島に立てたのであった。
その三年後の一九七三年、原告の家永三郎が八重山歴教協・教科書裁判支援八重山地区連に招かれて石垣高を訪れた際、三年を越えて毅然と立ちつづけるこの立看板を見てひどく感動したことが、その時同道した私の目に焼き付いている。
|

|
2 違憲・違法の検定を裁く top
高校教科書『新日本史』(三省堂)の著者家永三郎は、自分の教科書に対して行われた一九六三・六四年度の検定が「憲法・教育基本法をふみにじり、国民の意識から平和主義・民主主義の精神を摘みとろうとするもの」であるから、検定とその制度を憲法(表現・学問・教育等の自由の保障)、教育基本法(教育行政の教育介入禁止)に違反するとして一九六五年六月十二日、国家賠償法にもとづき、国を相手どって東京地裁に提訴した。
これが家水教科書裁判二次訴訟である。
家永は、「戦時中、戦争を賛美しなかったことには誇りをもつが、戦争を阻止できなかったことを懺悔(ざんげ)する。
今日戦争の芽生えがあれば、それは絶対につぶさねばならない。
裁判の勝敗だけが問題なのではない。
広く国民の中に教科書検定の事実を広げ、問題を白日(はくじつ)の下に曝(さら)け出し、検定制度の違憲・違法性を明らかにしていくことだ」と述べ、また法廷で「私は……戦争に抵抗できなかった罪の万分の一でも償いたいという心構えから、あえてこうした訴訟に踏切ったしだいであります」
と証言している。
家水教科書裁判には一次・二次・三次訴訟があるが(「家永教科書裁判の経過概要」「年表 教育・教科書問題・教科書裁判」参照)、いずれも原告・被告ともに同じである。
一・二次訴訟はすでに終結し、一九九七年五月現在、最高裁で審理中の三次訴訟上告審を残すのみとなっている。
この訴訟は教育と教科書をテーマに、憲法と教育基本法、平和と民主主義を守る闘いであり、戦争体験世代の戦争責任・戦後責任を問う裁判でもある。
そして提訴当時の六〇年代、国際的に高まっていた「戦争犯罪に関する国際裁判」(注1)(「ベトナムでのアメリカの戦争犯罪を裁く国際法廷」など)の精神に通じ、国内的には朝日訴訟(朝日茂が憲法二五条違反を告発)などの憲法裁判とその軌を一にするものであった。
(注1)イギリスの哲学者バートランド・ラッセルの呼びかけで、フランスの作家サルトルを裁判長に第一回裁判が一九六七年五月ストックホルムで開かれ、全員一致でアメリカの「ベトナム侵略」と「人道に対する犯罪」に有罪の判決を出した。
ラッセルが運動を進める中で主張した「黙っていることは共犯者になることだ」の言葉は、世界の平和を願う人々の心をとらえた。
これらは「民衆」が「権力」を裁こうとするところに大きな意義があり、憲法裁判・教育裁判としてその中心に位置したことはいうまでもない。
またこの訴訟提起は、検定の検閲化が進むなかで活路を見出すべく苦難の道を歩んでいた教科書運動に、勇気と励ましと展望を与え、この運動を民主的な教育運動とかかわらせつつ、より広範な国民運動に発展させる貴重な契機となった。
しかも六〇年代のこの時期は、新たな日米安保条約と高度経済成長優先を二本の支柱とする教育が強引に進められていたのである。
家永教科書裁判は、こうした歴史的背景を考えると、訴訟提起自体がすでに大きな歴史的意義をもっていたということができよう。
提訴三ヵ月余で早くも全国組織「教科書検定訴訟を支援する全国連絡会」(以下教科書裁判全国連)が、団体や個人によって結成されたのであった。
|
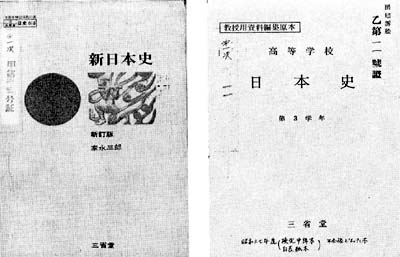
右=昭和37年度不合格となった「日本史」白表紙本
左=『新日本史 改訂版』(1965年3月15日発行)

昭和55年度新規検定申請原稿本(白表紙本)
|

杉本判決を伝える教科書裁判ニュース
(1970年8月15日、教科書検定訴訟を支援する全国連絡会発行)
|
3 憲法・教育基本法の原則に立った杉本判決
top
家水教科書裁判は教育・教科書問題への関心を国民のなかへ広めたが、それを飛躍的に拡大したのは、この裁判の最初の判決――(一九七〇年七月十七日の二次訴訟一審)杉本判決(注2)であった。
(注2) 杉本判決の国民の教育権および検定にかかわる個所の概要は次のようなものであった。
――「未来に可能性を持つ子供が、生れながら持っている生存権的基本権としての学習権を保障するために教育を行う責務を担うものは国民全体であり、この責務は、いわゆる国家の教育権に対する概念として国民の教育の自由(国民の教育権)であると呼ばれる」
「国家は国民の教育責務の遂行を助ける責任を持っており、国家に与えられた権能は教育を育成するための諸条件を整備することであって、国家が教育内容に介入することは基本的に許されない。」
として、目民の教育権を確定し国家の教育権を否定した。
教育内容については、一般の政治のように政党政治を背景とした多数決によって決定されてはならない。
また、父母国民の付託を受けて教育に当たる教師は、その学問研究の成果を子供たちに理解させ、子供にものを知る力、考える力、創造する力を身に付けさせるものであるから、教師にとって学問の自由の保障を欠くことができないと同時に、教師に教育の自由と教授(授業) の自由が尊重されなければならない」とする。
従って「国が一方的に教科書の使用を義務づけたり、教科書の採択に当たって教師の関与を制限したり、学習指導要領の細目にわたって法的拘束力があるものとして現場教師に強制したりすることも、教育の自由を侵すことになる」のである。
さらに、「検定の運用を誤って審査が教科書の思想内容に及ぶときは違憲となる。
思想内容の審査とは、政治思想の審査はもちろん、広く精神活動の成果に対する審査をいう。
従って学問研究の成果としての学問的見解や学説に対する蜜査も当然含まれる。
具体的に歴史教科書でいえば、史観や歴史事象の評価などに対する審査はもとより、年代などについても歴史学上の評価に関わるときは、これに対する審査は違憲となる」と判断した。――
|

杉本判決検討会(1970年7月18日、肩書は当時のもの)。
左から徳武敏夫、大江志乃夫(東京教育大学助教授・歴史学)、
阿部知二(作家・教科書検定訴訟を支援する全国連絡会代表委員)、
渡辺良夫(弁護士)、五十嵐顕(東京大学教授・教育学)
|

杉本判決を伝える当時の新聞
|
この判決は、子供の生存権的基本権としての学習権を軸に目民の教育権を確定して国家の教育権を否定し、国民が民主的な教育と教科書の創造、憲法と教育基本法、平和と民主主義擁護の闘いのなかで勝ち取った貴重な勝利であった。
自民党政府が対米従属の「軍事同盟」と「高度成長」にみあう国家主義・能力主義思想にもとづく差別・選別の教育を進めているなかで、杉本判決に示された「国民の教育権」思想が広く国民にとらえられるようになったのである。
それまで必ずしも自覚的でなかった教師・父母たちの「国民の教育権」思想が、杉本判決を契機に自覚を強め始めたことにほかならない。
4 最終段階を迎えた家永教科書裁判 top
|

沖縄県では訴訟開始後まもなく支援運動を始め大集会を開いた。
「講演と民族芸能の集い」会場の石垣市登野城小学校で講演する家永氏(1973年12月)
|

「第三次訴訟最高裁勝利」の集会で報告する筆者
|
一九九三年三月十六日、最高裁第三小法廷(可部恒雄裁判長)は六五年六月の提訴以来二十八年にわたる家永教科書裁判・一次訴訟で上告棄却(ききゃく)の判決を下した。
教科書検定の憲法判断をすべき最初の最高裁判決であるから、当然大法廷に回付して審議すべきであったが、口頭弁論も開かず、判決の言い渡し期日を原告にさえ事前に知らせず、突然の小法廷判決でとどめてしまった。
司法の独立を放棄して文部行政を追認したかに思われるこの判決は、本来「憲法の番人」であるべき裁判所が「政府の番人」になり果てたとしかいいようがあるまい。
原告家永三郎は判決直後の記者会見で「最高裁はここまで堕落(だらく)したか」と述べたが、その言はまさに正鵠(せいこく)を得たものといえよう。
これに先だつ一九八九年十月三日、家永教科書裁判・三次訴訟一審判決(東京地裁・加藤裁判長)があった。
三次訴訟は八〇年代の検定、しかもアジア太平洋戦争記述を中心に、戦争・天皇・民衆など重要な歴史認識にかかわる記述への検定処分に絞って告発した国家賠償請求訴訟である。
これは、一九八二年に文部省の教科書検定が国際間題にまで発展した後の検定に対する最初の判決であるだけに、国家が教育内容にどこまで介入できるか、あの侵略戦争に対して裁判所がどのような見解を示すかなど、国内外注視の中での判決であった。
しかし加藤判決は、教科書検定制度については「合憲・合法」とし、個別個所では告訴八件中「早莽隊」(そうもうたい)相楽(さはら)総三と年貢半減令」への検定意見にのみ「違法」があったとするにとどまった。
これにつづく一九九三年十月二十日の控訴審判決(東京高裁第五民事部、川上正俊裁判長)は、一審の「草莽隊」に「南京大虐殺」「南京戦における婦女暴行」を加えた三件記述への検定意見に「看過しがたい過誤」があり「違法」であるとした。
この判決は、三件というわずかな前進ではあるが、この年三月の「文部省検定は無謬(むびゅう)である」という最高裁判決後最初のものとして原告側か勝ちとった貴重な勝利であり、展望をもってねばり強くたたかえば必ず道は開けることを教えた。
国内外の教科書訴訟支援運動・教科書運動などによる検定批判の世論の高まり、最近の従軍慰安婦問題など日本の侵略・加害を問う国内・国際世論の反映でもあろう。
しかし、この教科書裁判は教科書検定とその制度の違憲・違法性を告発し、教育・学問・表現などの自由を保障させることが本旨である。
従ってこの判決がたんに三件の裁量権逸脱による違法という判断にとどまり、最高裁判決に追随して検定制度と検定処分を合憲としたことは、不当判決というよりほかはない。
さらに、「南京における日本軍の婦女暴行」の事実を認め、その記述への検定意見は「誤り」と認めながら、「華北などにおける貞操侵害行為が、特に記述すべきほどに特徴的な事実であるといえない」から、その記述への検定意見は「誤りではない」という納得しがたい論理でこれらを「合法」としている。
また八〇年代初頭、国際問題化した不当検定の典型である日本の「侵略」を「武力進出」に書き替えさせたことについて、「自国の行為について否定的価値を下すような重要な事項については、できる限り価値評価を伴う記述を避けて客観的記述」によるべきで、これに関する検定意見は「誤りではない」としているが、これで真実に裏づけられた歴史教科書が書けるであろうか。
七三一部隊についての記述は、検定当時(一九八三年)、すでに十分な資料の存在を家永側は一・二審で繰返し論証したにもかかわらず、「教科書に書くことは時期尚早」という一審判決をそのまま追認している。(注3)
(注3) 最高裁第三小法廷(大野裁判長)は、一九九七年八月原審に「七三一部隊」を加えて四件違法とした。
|

[教科書裁判の勝利をめざす中央集会]で報告する筆者(1993年)
沖縄戦で、検定は「軍官民一体の共生共死」の「殉国美談」として描く「集団自決」の記載を強制した。
だが、沖縄戦における「集団自決」は、一審の沖縄出張尋問のさいの安仁屋政昭・金城重明、二審での石原昌家らの証言で日本語本来の「自決」(みずから決断して自分の生命を断つこと――『広辞苑』)に当たるものではなく(「自決」者の中にいた多くの乳幼児がどうして自決できようか)、その人たちの死は皇軍(天皇の軍隊)の強制誘導による肉親どうしの悲惨な殺し合い、集団死であったことが明らかにされている。
しかし判決は「集団自決」の挿入強制の検定意見を「合法」とした。 |

第三次訴訟の判決を伝える当時の新聞
|
またこの判決の教科書観は、教師の介在を無視して「子供は判断能力がない」から「中立・公正」「正確・安定」な知識を上から与えることが必要で、教科書は「主たる教材」として使用が強制・義務化され、子供の側には選択の自由がないというものである。
先に述べた杉本判決にみる教育観・教科書観・子供観とは雲泥の差があり、今日国際通念になっている「子供の権利条約」からもほど遠い。
|

非戦闘員の悲惨な集団死(1945年6月21日、沖縄本島南部)
|
5 文部省の歪んだ歴史認識と現代認識 top
高嶋伸欣(当時筑波大付属高校教諭、現疏球大学教授)は自分の学問研究と授業実践の成果を教科書に取入れて、一九九四年度用高校公民科現代社会の教科書『新現代社会』(一橋出版)の一部を執筆して不合格となった。
そこで高嶋は九三年六月十一日、国家賠償請求訴訟を横浜地裁に提起した。(注4)
(注4) 横浜地裁(慶田裁判長)は、一九九八年四月二件違法の判決を言い渡した。
訴訟の主な争点は、
(1)昭和天皇死去の際のマスコミの異常な番組の問題を取上げること、及び天皇に「死去」を使うことは不適切、というもの。
(2)近代日本がアジアの諸国民に犠牲を強いたという歴史的事実の認識や評価が、日本人とアジア人の間で大きな落差があるが、その理由を考えさせるために書いた本文中の「脱亜入欧」の脚注に、福沢諭吉の「脱亜論」(一八八五年三月一六日付『時事新報』社説)を引用したところ、教科「現代社会」の教科書には「不適切」というもの。
(3)一九九一年の「自衛隊の掃海艇派遣問題」を取上げ、その脚注に「……東南アジア諸国からは、派遣を決定する以前に意見を聞いてほしかったとする声があいついで出された」と書いたところが、文部省は「掃海艇派遣について東南アジア諸国の意見を聞くなど低姿勢に過ぎ、不適切」というもの。
(4)政府などによる情報コントロールがいかに危険なものであるかについて、湾岸戦争の際の「多国籍軍」が行ったマスコミ利用の世論操作の脚注に「朝日新聞」と「文芸春秋」を使ったところ、資料が新聞や雑誌では駄目だというもの。
現代社会(公民科)でも、天皇・天皇制にかかわる記述、自衛隊・PKOなど政府の重要政策にかかわる記述に対しては、検定がことさら厳しい。
6 家永教科書にはどのような検定が行われたか
top
①『古事記』『日本書紀』の真の編纂意図は何か
〈六三年度不合格本原稿記述〉『古事記』も『日本書紀』も「神代」の物語から始まっているが、「神代」の物語はもちろんのこと、神武天皇以後の最初の天皇数代の間の記事に至るまで、すべて皇室が日本を統一してのちに、皇室が日本を統治するいわれを正当化するために作り出した物語である。
『古事記』『日本書紀』はこのような政治上の必要から作られた物語や、民間で語り伝えられた神話・伝統や、歴史の記録なとがら成り立っているので、そのまま全部を歴史とみることはできない。
〈不合格理由〉この記述は、全体として『古事記』および『日本書紀』の記述をそのまま歴史とみることはできないということのみ強調していて、これらの書物が現在少ないわが国の古代の文献の一つとして有する重要な価値については全くふれていない。
〈六四年度提出本原稿記述〉『古事記』も『日本書紀』も「神代」の物語から始まっている。“「神代」の物語はもちろんのこと、神武天皇以後の最初の天皇数代の間の記事に至るまで、すべて皇室が日本を統一してのちに 皇室が日本を統治するいわれを正当化するために構想された物語であるが”、その中には民間で語り伝えられた神話・伝説なども織りこまれており、古代の思想・芸術などを今日に伝える貴重な史料である。
〈修正意見〉傍線部分は断定にすぎ、不正確であるから削除せよ。
〈合格本記述〉『古事記』や『日本書紀』の中には諸豪族や民衆の間で語り伝えられた神話・伝説なども織りこまれており、古代の思想・芸術などを今日に伝える史料として貴重なものである。 |
『新日本史』は別のところで「『古事記』『日本書紀』などにはこうした口承文芸のいくつかが取入れられている」と書いてあるにもかかわらず、不合格理由に「……貴重な価値についてはまったく触れていない」とあるのは不当である。
不合格理由を参考にして修正した六四年度提出本と「修正意見」ならびに合格本を比べてみると、文部省のねらいは、初めから記紀の編纂意図の削除にあり、「記紀の内容に高い評価を認める教育をし、新たな皇国史観を育成する基盤たらしめるところにあると思われる」(『原告準備書面』)のである。
文部省は挿絵①居⑤、ことに⑤を削除させたかったのであろう。
口頭指示にあった「全体として暗すぎる」は漠然としていたため、法廷に提出した準備書面では「顔のうち……きわめて残酷」「健康・安全教育上不適切」と、常識では考えられないような理由を、まことしやかに掲げた。なぜならば、「顔のうち……」はレイアウトの都合上トリミングしたものであり、傷夷軍人の義手が露出しているのは当たり前である。
|

64年提出本の記述
|

64年提出本の記述
|
top
**************************************** |